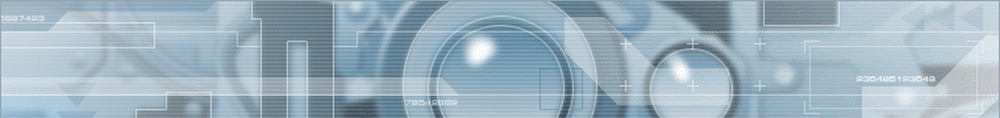2. 八年前からの助け舟
小学生の頃書いた絵日記が、祖父母宅から出てくる。
ページを捲っていると、身に覚えの無い内容を発見する。
---------------------------------
一冊の日記帳が原因で、僕は危うく死にかけた。
それは、夏休みの中頃の話だ。
高校一年生にもなって祖父母の家に預けられていた僕は、その日は珍しく七時半という早い時間に目を覚ましたので、祖母の朝食作りを手伝っていた。僕が料理の基本玉子焼きを作ると、祖母は「上手い上手い、晴ちゃんは将来料理人かねえ」と手を叩く。相変わらず大袈裟な人だと思いつつ、結構満更でもなく、僕は得意気に皿に玉子焼きを移し、皿を食卓に運んだ。
朝食を終え、さて今日は真面目に宿題でもするかと伸びをしていると、「ちょっと、晴ちゃん」と祖母が僕に手招きした。背中に何か隠し持っているようだったので、お金なら嬉しいなという失礼なことを思いながら、祖母に近付く。
「これね、晴ちゃんがずっと前に、この家に置いていった絵日記なんだけど」
「絵日記?」
祖母は言うなり、一冊のノートを僕に見せた。モンシロチョウが花に止まった姿が表紙の、緑色のノートだ。大きく「にっきちょう」と書いてある辺り、それは日記帳に違いは無い。しかし、そんなものを祖父母にプレゼントした覚えとなると、全く無い。だが表紙には大きく、汚い字で「須藤はるひこ」と書いてある。
「そのときは私たちも気付かなかったんだけどねえ、ちょっと前に、部屋の掃除をしていたら見つかって」
祖母が申し訳なさそうに言うその言葉を聞いて、僕の頭の中に、ある光景が思い出された。それは確か、小学三年生の、夏休み明け。提出するはずの絵日記を失くして、半泣きでおろおろする僕。あの時は先生に素直に謝って事なきを得たが、そうか、この家に置いていっていたのか。
「ああ、思い出した。随分と懐かしいものだね」
「ごめんねえ、早く気付かなくて。あの後晴ちゃん困ったでしょう」
両手を合わせて謝る祖母。
「いいよ、もう過ぎたことだし」
そう言って、もう一度絵日記に目をやる。良く見ると、表紙の部分が随分と色褪せていて、角のところも破けている。一体どんな場所に保存されていたのだろう。
「それでね、昨日、失礼だけど読んでみたのよ。そしたら面白くて面白くて。晴ちゃんも読んでみない?」
口に手を当てて、祖母は微笑んだ。その『面白い』というのは果たしてどの意味での面白いなのか気になったが、小学三年の頃の日記に恥ずかしさを覚えるほど、僕は繊細な人間ではない。むしろ、周囲の人間と一緒に、過去の自分を笑うタイプの人間だ。あまり昔のことに拘らないのが、僕の長所であり、短所でもある。
僕は日記帳を受け取ると、祖母に促されて表紙を捲った。
一ページ目には、胴体と顔の大きさが不釣合いな人間が、両手両足を開いて、「X」の形になっている様子が書いてあった。文章を見るに、どうやらこれは、夏休み初日ということではしゃいで、万歳をしている僕らしい。当時はまだ色の塗り方すら知らなかったらしく、いかにもクレヨンで適当にぐりぐりと塗りましたという形跡が、その人物には見られた。どこの戦闘民族だ、これは。
二ページ目を開く。これは一目で分かった、ラジオ体操をしている人たちの姿だ。大小様々な人間(通常の二分の一の身長の人もいた)が、全員屈伸運動をしている。全員が全員こっちを向いて笑っていたので、なんだか不気味だった。『早起きは辛い!』と平仮名で書いてある。今だってそうさ。
横で微笑む祖母に合わせて苦笑いしながら、三ページ目。カブトムシを必死に模写しようとしたらしいが、どう見ても象にしか見えない黒い物体がページ一杯に書いてある。これは記憶力の無い僕も、すぐに思い出すことが出来た。確か初めてカブトムシを捕まえた日のことだ。祖父の協力を得て、腐ったバナナに料理酒を混ぜ、ストッキングに塗ってクヌギの木に設置し、翌朝祖父と共にそこへ向かうと、ストッキングに足を絡ませ動けなくなっているカブトムシがいた。このときばかりは、祖父を尊敬したものだ。夏休み明け、周囲に祖父の知識を、あたかも自分の知識のようにして自慢しまわった記憶がある。祖母は僕の日記の絵を見て、「晴ちゃんは昔から絵が上手かったのよねえ」と頷いていた。
四ページ目には犬か猫か分からないような黒い生物が僕と向かい合っている奇妙な図があり、数ページ後には僕が仁王立ちをして大粒の涙を流している絵があり、そして十ページ目。
ここが問題だった。
そのページには、規則正しく灰色の長方形が並んでいた。しばらく真面目に考えて、僕はその灰色の物体が、墓石であることに気付いた。後ろに書いてある卒塔婆が、何よりの証拠だ。となると、この周囲に飛び回っている火の玉は、人魂ということになるのだろう。そしてその墓石の中心には、絵本に出てきそうな典型的幽霊が書いてあった。端の方に、一つだけ不釣合いな小さく丸い墓石がある。意味が分からない。
そして、文章。
『怖い怖い幽霊に出会った。けれども僕だけには、その正体がすぐにわかった』
益々意味が分からない。
本当にこんなものを、僕が書いたのか?
僕は祖母の顔を見る。祖母は、相変わらずにこにこと微笑んだままだ。
「これ、どういう意味かな?」
文章部分を指差して、祖母に聞いてみる。
「さあねえ。怖い夢でも見たんじゃない?」
笑顔で流された。まあ、元から大した答えは期待していない。
僕が顎に手を当てて、この文章の意味を理解しようとした。怖い幽霊。けれども、正体はすぐわかる。しかも、自分にだけ。一体何のことだろうか。悪戯好きの祖父が幽霊のふりをして僕を驚かしたという可能性も否定できないが、仮にそんな事件があったら、僕の脳に深く刻まれるはずである。覚えていないということは、十中八九、大した事のない出来事だ。しかし、絵からして、僕がお墓に行ったことは確かなのだ。この頃の僕が想像力だけで墓石を書いたら、そこに卒塔婆なんて存在するわけが無い。
腕を組んでうなっていると、玄関が開いて、「ただいま」と祖父の声が聞こえた。朝市に行ってきたらしく、両脇にスイカを抱えたまま居間に入った祖父は、「暑い暑い」と言いながら扇風機のスイッチを入れる。台が黄ばんだ、首を回すたびにぎいぎいと軋む扇風機の前で、胸元に風を送り込む祖父に、祖母は先程の日記を見せて、ついでに僕が疑問に思っていることも伝えてくれた。
その話を聞いた祖父は、しばらく考え込んだ後に、何故か急に正座して、神妙な顔つきで僕に言った。
「そりゃあもしかしたら……『くねくね』に出会ったのかもな」
「くねくね?」
僕が訝しげに聞き返すと、祖父は人指し指を立てて、神妙な顔つきで話し始めた。
「ここらみたいに、田んぼが多い田舎に現れる化け物のことだ。夏、水辺で多く目撃されるんだがな。暖かい風が吹いたと思うと、突然風が止む。それが、くねくねが現れる前兆だ。辺りを見回すと、水辺に案山子のようなものが見つかる。しかしそいつは風も吹いていないのに、くねくねと踊るんだ。好奇心に駆られ、そいつを双眼鏡を使ったりして、見ようとしたが最後。見た本人もくねくねになって、狂ったように笑いながら踊り出す。俺が奴を見たのは、まだ子供のときで」
「じいちゃんって、子供の頃は都会に住んでたんだよね」
すかさず僕が口を挟むと、祖父は舌打ちした。
「……可愛げの無い孫だな、相変わらず」
「そちらこそ虚言癖は健在なようで」
僕がそう返すと、祖父は大声で笑い出した。隣で黙って話を聞いていた祖母も、相好を崩す。この人は昔からこうだ。突発的にその場で考えた嘘をついては、僕をからかって楽しんでいる。流石にこの歳になると慣れて、今のように軽く流すことが出来るが、昔はお盆の時期なんかは『この歳になると幽霊が見えるんだ』などと大ぼらを吹き、墓参りの最中にも『墓で転ぶと死ぬぞ』『ああ、振り返っても死ぬな』と平気で嘘をつき、その度僕は酷く恐怖したのだった。
「じいちゃんの言葉は八割が嘘だって分かってるからね。で、実際この日記には心当たりは無いの?」
「心当たりも何も、お前が書いた日記だろうが」
全くその通りでございます。
再度日記帳に目を落とし、絵の中心にいる幽霊を見た。随分と愛くるしい幽霊で、まるでハロウィンで使われるカボチャみたいな顔をしていて、今にも「トリックオアトリート!」と言い出しそうだ。きっとこの幽霊の方は、僕の想像で書いたのだろう。とってつけたような存在である、
「あれ? 何を見てるの?」
祖父の笑い声が聞こえたのか、麻里まで居間に入ってきた。そうして、僕の手元を見るなり、「絵日記? もしかして、晴彦の?」と両目を見開いて、嬉しそうな顔をして僕から日記帳を奪い取った。
麻里は現在も付き合いがある、僕の唯一の幼馴染だ。田舎に住んでいた僕らは、互いの親の仲が良かったため、よく一緒になって遊んでいた。今回の夏休み、偶然祖父母の家に預けられていた僕は、麻里と再会した。そうしてなぜか今麻里は、まるで家族のようにこの家に泊まっている。昔から麻里と仲の良かった祖父から誘ったのだ。昔から兄弟のように接していた僕たちは、一緒の家に寝泊りしていても、大して互いを意識しない。というか、気付けば既に一緒にいた相手を、意識しろという方が無理な話だ。殆ど僕らは兄妹なのだ。そう、あくまで僕が兄である。
「へえ、八年前の日記か。なんかロマンチックだね」
祖父の隣で日記帳をぺらぺらと捲りながら、肩より少し上まで伸びた少し癖のある黒髪を押さえる麻里は、とても懐かしそうにしていた。彼女はこういう類の話が大好きで、ノスタルジアだとかいうのに妙に関心を持っていて、ついでに児童文学をこよなく愛している。つまるところ、ロマンチストなのだ、彼女は。
「内容はロマンチックとは程遠いがな」
苦笑した後で、僕は「そういえば」と麻里に十ページ目のことを説明した。笑い話のつもりだったのだが、麻里はその話に妙に食いつき、「ミステリーだね。それは面白い」と再度絵日記を熟読し始めた。どうにかして、八年前の僕の真意を汲み取るつもりらしい。ページを捲って「伏線は無いかな」と無茶な注文を言う麻里は、時折僕に質問をした。
「『僕だけには正体が分かった』だってさ。生意気だね、こいつ」
「文句を言うなら八年前の俺に言ってくれ」
「この黒い生物は何?」
「カブトムシか犬か猫。もしくは俺」絵も見ずに答える。
「……単に晴彦の記憶力が無いだけじゃないの? 本当はお墓なんて行ってないんじゃ?」
卒塔婆の件について説明すると、麻里は先程の僕のように両腕を組んで、うなりだした。そのまま三回ほど器用に前転した麻里は、ふと、何かを思いついたのか、両手で膝をたたいた。
「そういえば、この辺りにお墓があったね」
確かに、ここから四、五キロほど離れた場所に、荒れ果てたお墓がある。昔はよく、夏休みの学校の行事で肝試しをする際、あそこを利用したものだ。
「あの肝試しで見た幽霊ってことはないの?」
「ないな。あの肝試しでは、お化け役はいなかったし」
僕の数学年前の生徒が低学年を泣かせたことが原因で、以来お化け役というのは配備されなくなったのだ。
「ああ、でもこの墓に行ったという点は、間違っていないかもしれない。墓に行ったのは事実だからな」
「妙なことだけ覚えてるんだね」
「全てを忘れるよりましだろう」
しばらく無為な議論を交わした後、麻里は唐突に「お墓に行ってみよう!」と右手を勢い良く挙げた。僕が冷めた目でそれを見ていると、麻里は慌ててその手を下げて、「いや、ほら、だって暇じゃん。このままじゃ真相も分からないし。そういうきっかけで、案外思い出したりするものだよ」と呟いた。暇か、実に羨ましいことだ。僕はまだ、課題の半分も終わっていないというのに。
隣で祖母が、時計を指差して「出掛けるなら、午前の方がいいよ。昼間は暑くなるからね」と言う。話の流れが読めていないらしい。
口を尖らせて、僕は言った。
「具体的に、墓に行って何をするんだよ」
「城阪晴彦が何を見たのか、その真相に迫る。二時間スペシャル」
「どこのテレビ番組だ。大体、昼間から姿を現す幽霊なんているのか?」
「馬鹿だね、もし本当に出たら困るから昼なんだよ」
理屈の通っていない屁理屈を言い、麻里は「それじゃあ、昼ご飯までには帰ってきますので」と僕を引っ張り出した。祖父母がそれを見送りながら、大笑いする。僕自身、こういう状況は満更でもないのだが、それにしても、この炎天下の中を計十キロ近くも歩く羽目になるのかと思うと、少しげんなりした。大体こいつは、本当に真相を確かめようとはしていない。単純に散歩がしたいだけだろう。女子高生はウォーキングが大好きだ。
玄関を出るなり、途端熱気が襲ってきて、アブラゼミの鳴き声が降り注ぐ。なぜ冷房の付いていない祖父母の家と外でこれほど気温差があるのか不思議だ。もしかしたらあの家には、年寄りならではの人生経験を生かした工夫があるのかもしれない。目を細めながら、少しずつ太陽に目を慣らす。
外に出ると、麻里はどこから持ってきたのか、田舎臭い麦藁帽子を被った。それから虫除けスプレーを取り出して、数回振ると、肌の出ている部分に吹き付けた。そして、僕の顔面に向けて噴射した。舌がぴりぴりとして、何だか苦い。
「これで顔を刺される心配は無いね」
そう言う麻里からスプレーを奪い、同じことを仕返してやった。麻里は「これ案外きついな」と、けへけへ咳き込む。当たり前だ。
「ところで、その田舎臭い麦藁帽子は」
頭を指差して指摘すると、麻里は両手を帽子の唾に当てて、少し傾けた。
「別に街を歩くわけじゃないしね。あと、なんだか懐かしいなあって」
麻里も、僕が肩の出る服を着ているのを見て、「大胆ですねえ」と指摘してきた。中途半端に日焼けするのが嫌なのだと説明すると、「ああ、なるほど」と納得していた。
そうして僕らは歩き出す。お墓のある場所まで、大体一時間はかかる。最初のうちは相変わらず絵日記について議論していたが、それにも飽きると、今度は僕が祖父から聞いた「くねくね」の話をしてやった。麻里は「昼にも幽霊はいるのは反則だ」と訳の分からない反論をした。流石ロマンチスト、幽霊の存在も未だに信じているらしい。
話題も尽きると、ひたすら歩いた。汗がだらだらと出てきて、首元を伝う。服にしみこんだ汗で、いちいち肌に服がまとわりつく。単調で耳障りなアブラセミの鳴き声が、さらに暑さに拍車をかける。こんなに暑いと動物もだれるらしく、道路上に猫が体を伸ばして、死んでいるかのように寝ていた。麻里が近寄っても、面倒そうに麻里のことを見るだけで、逃げる様子は無かった。調子に乗った麻里は猫を撫でようと手を出したが、その瞬間ものすごい素早さで、猫は彼女の右手を引っ掻いた。
「あいたたた。畜生、触ってみたかったのに。肉球」
慌てて引っ掻かれた部分を左手で押さえる麻里の横に立って、僕は彼女にアドバイスした。
「猫の爪の届く範囲で、急な動作をするからそうなるんだよ。そりゃあ猫だって警戒するさ。もう少しこちらが何をするか分かるように、ゆっくり撫でてやるんだ。嫌われてからでは遅いけど」
そういった後で、自分でもあれ? と思った。麻里も同じ感想を持ったらしい、僕に尋ねてくる。
「晴彦って猫飼ったことあるっけ?」
「いや、一度もないな」
「じゃあ何でそんなことを知ってるのさ?」
「何でだろうな。俺にも分からない」
「相変わらず記憶力が無いなあ」
しばらく自分でも考え込んだ。きっと、何かの本で読んだことがあったのだろうという結論で落ち着いた。もう、これ以上僕の人生に謎を増やしたくない。
歩いている途中、セミの抜け殻を拾った。気味悪がられると思ったら、麻里はそれを見て、手にとって「懐かしいね」と喜んだ。そういえば昔は、よくこれを大量に服に引っ掛けて、「蝉のなる木!」などと言って遊んだことを思い出して、笑ってしまった。
次第に僕らは、「冷麺が食べたい」「私は水羊羹が」「クーラーの効いた店で休みたい」「雨降らないかな」と、あまりの暑さに自分の願望のみを口にするようになり始めた。祖父がセミを揚げて食べていたという話をしたりして、必死に暑さを忘れようとしていると、丁度良く目の前にセミが現れて、「食べるか?」と麻里が笑った。
それから疲れが出てきて冗談も言えなくなり、互いに「暑い」「暑い」としか喋らなくなってきて、さらに十分ほど経った頃。
ようやく、お墓が見えてきた。段々と道路が砂利道になり始め、独特の雰囲気が漂ってくる。無闇に日当たりが良いところが、却って不気味だ。昼間だというのに、やたらお墓周辺は静かで、蝉の声が妙に遠くに感じる。田んぼに囲まれているというのもあるのだろうが、まるでそこだけ現実世界から切り離された、別の場所のように思えた。
お墓に入る。嫌な感じの静けさに、僕は身震いした。そういえば、今はお盆の時期だということを、今更になって思い出した。この時期は墓参りの人がいてもおかしくないと思ったが、そこには僕ら以外誰もいなかった。しかし誰かが少し前にお墓参りに来ていたらしく、線香の香りが漂ってくる。
腰の下ろせそうな場所を探すが、どこも墓石ばかりで、座ったりしたらバチが当たりそうだった。随分と小さいベンチを見つけて、そこに二人で腰を下ろす。幸いそこには屋根があって、日陰になっていたため、お墓の雰囲気とも相まって結構涼しくなれた。屋根の柱のところどころには、持ち主のいないクモの巣が張ってある。
「ところで、何をしにきたんだっけ?」
額の汗を拭いながらそう言うと、麻里は急に立ち上がって、すたすた歩き始めた。
どこに向かっているのか、彼女の視線の先を追うと、なにやら小屋があるようだった。小屋と言っても、完全木造、茶色一色のひどく古ぼけた廃屋だ。一体何に使われていたのだろう。窓は安っぽい素材で出来ており、少し力を入れて殴れば割れそうである。麻里はその窓から、中の様子を窺った。人が中にいたらどうするつもりなのか。
「どんな感じ?」
「誰もいないみたい。それに、ひどく痛んでる」
僕もベンチから立ち上がり、中を覗いてみた。中も外壁と同じく、全くの茶色一色で、おまけに床には天井や壁が剥げ落ちた箇所が沢山落ちており、今にも抜け落ちそうな天井からは黄色いスポンジがはみ出て、そこから水滴が垂れていた。放置されて、何年経つのだろうか。
好奇心で、中に入ってみようと入り口の方に回ると、そこには一台の車が停まっていた。しかしこちらも人がいた形跡はなく、ガラスが全て割れていて、車内に散らばっている。ガラスの他にも、壊れかけた家具や、用途の分からない金属部品などが、散らばっていた。
「不気味だな」
僕はそう漏らした。
「ミステリーだね。ちょっと晴彦、入ってみて」
「あいよ」
まあこういうのは男の役目だろう。僕は反論せず、小屋の中へ足を踏み入れた。
窓の外から見たのと同じで、痛んでいる以外は特に変わった様子も無い。強いて言うなら、妙に湿っぽい。一歩歩くごとに床板が軋む。危険そうだったので、僕は適当に中を見回した後、すぐに小屋の外に出た。
「何も無かったぞ……」
そう言いかけたところで、僕は目を疑った。
麻里の姿が、見当たらなかった。
「麻里?」
慌てて辺りを見回すが、どこにもいない。
小屋に入っていたのは、ほんの数秒のはず。その間に、どこかに隠れたのだろうか。しかし、彼女はその手の悪戯をして楽しむようなタイプの人間ではないことは、僕が良く知っている。
ベンチで休んでいるのかと思ったが、そこにも麻里はいない。墓石の裏など、辺りを探し回ったが、やはり彼女の姿は見えなかった。僕は一度ベンチに腰を下ろして、考えた。もしかしたら、この炎天下が我慢できず、先に帰ってしまったのだろうか。それとも――
僕の脳内に、ある光景が浮かぶ。麻里がお盆が絵里の幽霊に連れて行かれ、墓の下に引きずりこまれる様子。いや、違う。ここの墓は田んぼに囲まれている。今朝祖父に聞いた、「くねくね」かもしれない。狂ったように笑いながらくねくねと踊る麻里を想像して、これはこれで面白いと考えた。
などとふざけている間に、ふと妙なことを発見した。先程まであったはずの、屋根の柱のクモの巣が、一切無くなっている。巣を作ったクモが、回収したのだろうか? 実際そういうクモがいると、本で読んだことがある。しかし、それにしては妙だ。この短時間で、ここ一面のクモの巣全てが、タイミングよく回収されるものなのか? それに、そんなにクモがいるのなら、一匹くらい僕の目に入ってもおかしくない。
考えてみれば、先程まで遠くからとはいえ響いていたセミの声も、今では止んでいた。それどころか、小鳥の声も聞こえず、耳を澄ましたところで、聞こえるのは自分の呼吸音だけ。
耳を澄ませてみる。
静寂。
辺りを見回す。麻里といいクモの巣といいセミといい、ここには、生き物がいるという証拠が、全て無くなっているように見えた。まるでこの短時間で、僕以外の生物が消えてしまったようだ。
「麻里?」
もう一度、叫ぶ。その声は辺りに反響して、吸い込まれるようにして消えていった。途端、猛烈に寂しくなり、酷い孤独感に襲われた。その気持ちは、小学生の頃大きなデパートで迷子になった、あのときの気持ちと良く似ていた。
とにかく麻里を探さなくては。僕は立ち上がって、歩き始めた。まずは、もと来た道を戻ろう。彼女は既に帰っているかもしれない。それに、何かここにいるのは危険な気がする。
踵を返し、僕は駆け足で来た道を戻った。しかし来た道という割には、その道はまるで初めて通る場所のようで、僕は無性に不安になった。いや、一本道で道を間違えるわけが無いのだ。単に、行きと帰りでは左右が違うため、別の道に見えるのだろう。よくあることだ。そう自分に言い聞かせ、何とか平静を保つ。
寂しさを紛らわすため、わざと砂利を蹴飛ばして、物音を立てて歩いた。砂利道が終わると、道路に出る。しかし道路にも車どころかミミズの死体一つ見えず、ただ日の光が反射して、きらきらと輝いていた。
心細くて、とにかく誰かに会いたくて、僕は終いには全力疾走した。
麻里が猫に引っ掻かれた場所まで来た。しかしそこにすら、生物は存在しなかった。一体何があったのか。もしかして、自分の頭がおかしくなったのか? そう思ったが、五感はきちんと働いている。痛覚も聴覚も健在だ。
疲労と不安で、思わずアスファルトに座り込んでしまった。「くねくね」でも何でもいいから、とにかく何か、存在してくれ。そう思って溜息をつく。「誰かいませんか」と叫んでみるが、勿論返事は無い。
全ての行為が無駄だと分かると、立ち上がって、再度歩き出した。
そうして三十分ほどして、何とか、家までたどり着いた。
しかし僕は、内心不安で仕方が無かった。ここまで来るまでに、結局人一人として見ていないからだ。もしこれで家の中に誰もいなかったら、僕はどうすればいいのだろうか。
暫時、ドアの前で迷った挙句、僕は思い切って家に入った。大声で「ただいま」と叫び、居間に入った。
数分して、僕は家を出た。
数時間前、麻里と虫除けスプレーをかけあった場所に立ち尽くして、何も考えずに呆けていた。人間は無人島に放り込まれると、すぐに気が狂うという話を思い出しながら、あれもあながち嘘ではないなと思った。
三十分ほど経っただろうか。
ふと、あるものの存在に気付いた。
それは大きな看板だった。白い板に赤いペンキで一言、『帰り道は振り返ってはいけません』と書いてある。字は至って普通の明朝体で、おどろおどろしいところもない。なのに僕は、その看板を見て、妙な危機感を感じた。
勿論さっきまでは、こんなもの存在しなかった。既に不可思議な現象なら幾度も起きているが、目の前で起こった変化はこれが初めてである。信じ難いが、この看板は僕を意識してそこに現れたとしか思えない。
僕に何かを伝えようとしている者がいる。直感的に、そう思った。
看板の言葉をもう一度読みかえす。『帰り道は振り返ってはいけません』。帰り道とは、何のことか。家に帰るまでというのなら、既に僕は辺りを見回す際、何度も振り返っている。この行動に何かまずい点でもあったのか。
そしてルールを破ったら、どんな代償が待っているのか。
分からないこと、だらけだった。理解できないことが多すぎて、途方に暮れた。
そうしてどれくらいか、座り込んで考えていた。
不意に――物音が聞こえた。
後ろの方で、誰かが走ってくる音がしたのだ。
振り向いたが、残念ながらそれは麻里ではなく、しかし何故か彼女は、僕に向かって手を振っていた。黒髪で高身長の、二十歳くらいの女性だった。
僕に追いつくと、彼女は息を切らしながら、「やっと追いついた」と両手を膝についた。人に会えたのは嬉しいが、知り合いでないのは確かだし、なのに彼女は僕のことを知っているらしく、随分と不気味感じられる。それに怖い話では、こういうときに出てくる人物が黒幕だったりするものだ。咄嗟に身構え、僕はさり気なく距離をとって、「あのう、失礼ですがどちら様で?」と訊ねた。
「晴彦さん、ですよね?」
僕の質問には答えず、女は顔を上げて言った。その顔を見て、僕は少し驚いた。
目が、真っ黒だったのだ。いや、日本人なら目が黒いのは当然なのだが、彼女の場合瞳が大きかったし、まつ毛も長くて、妙に黒く感じたのだ。加えて背中までの黒髪に、黒いワンピース、黒い靴。
物語の中に出てきそうな、黒尽くめの、美人な女の人だった。
「サチと言います。覚えていますか? あなたが幼い頃、一度お会いしたのですが……」
彼女は笑顔でそう言ったが、生憎僕はそんな名前の人を知らない。忘れっぽい僕ではあるが、流石に一度見た人の顔を忘れるほどではない。増してや、こんな特徴的な顔を。正直に首を降ると、サチと名乗る女の人は「そうですか」と俯いて、少しだけ悲しそうにした。それから、すぐに顔を上げて、「助けに来ました」とこれまた意味不明なことを言った。
状況が掴めない僕は、それでもこの女性が自分の味方だと分かると、安心して溜息をついた。それから、放っておけばまた意味不明なことを喋りだしそうな彼女に向けて、先に質問をした。
「その前に聞きたいんですが……」
僕は常識外れは承知で、今まであったことを全て話した。知り合いとはぐれたこと、生物の気配が全くしないこと、一時間ほど前から彼女以外には誰とも会っていないこと。それは口に出してみると随分と荒唐無稽な話で、焦っていた分僕の話も支離滅裂だったのだが、彼女はそれを至極真面目に聞いていた。少しも不思議そうではない。
一通りのことを説明し終えると、気が楽になった。
彼女は今度はこちらの番とでも言うように、ゆっくりと口を開いた。
「これから言うことを、冗談半分に聞いてください。どうせ信じられませんので」
くすりと笑ったかと思うと、突如真剣な目つきになり、続けた。
「結論から言うと、あなたは今、死にかけています。裏側の世界に、迷い込んでしまっています。おそらく、あの廃屋が原因でしょう。詳しい説明は省きますが、あの小屋は今、こちらとそちらを繋ぐ、いわゆる冥界の扉となっています。あなたはそれに足を踏み入れて、こちらの世界に迷い込んでしまったのです」
随分と典型的な話だ。そう頭では思っていても、なぜか今は信じてしまう。むしろ彼女が言う言葉の一つ一つに、納得してしまう。現在の状況を肯定するならば、それしか通る理屈はないからだ。
「帰る方法は――いいですか、一つしかありません。これからあなたは、再度あの小屋に向かいます。それは、あなたにとって『帰る』ことになるんです。けれどもいいですか、一度帰ると決めたら、その後は一度も振り向いてはいけません。仮に振り向いてしまった場合、あなたはこちら側の住人になることが決定されます」
先程の看板を思い出す。帰り道というのは、そういうことだったのかと納得した。つまり僕は、今まで必死に帰ろうとしていたが、逆に目的地からは遠ざかっていたわけだ。
そして、振り返ってはいけないというのは、考えてみればどこかで聞いたことのあるような、話だった。そう、確か過去に祖父が、僕を怖がらせようとした際にした話だ。正確には、こんな話だった。この世とあの世の間には、振り向いは行けない場所があり、もしそこを無事突破できたら、生き返られる。しかしあの世の住人は、多彩な手段でその人を振り向かせようとするから、大抵の場合はそのまま死んでしまう。強い意思を持っていないと、生き返るのは困難だ。まあお前見たいな臆病者には不可能だろうがな、ははは。そう祖父は言っていた。
理屈でこの話を納得するのは難しい。しかし、既に理屈では証明不可能な現象が、目の前で起きているのだ。そう、仮に僕が今いるのは、夢の世界としよう。そして彼女は、夢の世界の住人だ。そうすれば、全ての事柄を受け入れることが出来る。
僕は顔を上げて、答えた。
「話は、信じます。現にそうでないと説明できないような現象が起きていますしね。しかし、ところであなた――サチさんは、誰なんですか? 僕との明確な繋がりを教えてください」
サチは首を振り、「そこまでは教えられません」と残念そうに言った後、くるりと後ろを向いた。僕の方を見ないまま、再度真剣な声で、言った。
「これから、私についてきてください。いいですか、私の横を歩くんですよ。決して後ろから何をされても、何を話しかけられても、無視に徹してください。これから私が振り向けといったとしても、無視してください。大丈夫です。すぐに、元の場所に帰れますから」
僕も回れ右をして、サチの隣に行き、帰ることを決め、そうして二人で歩き始めたのだった。
*
祖父の言うとおり、僕らが歩いている中、様々な妨害があった。
まず、彼女に言われるとおり歩き始めた瞬間、背中に違和感を感じた。背後に、誰かがいるのが気配で分かった。そいつはぴったりと僕の一歩後ろをついてきて、歩くスピードを上げても一向に離れない。一度立ち止まってみたが、やはり背後でそいつも立ち止まっているようで、余計不気味だった。なぜ何もしてこない? そんな疑問が、僕を振り返らせようとする。
「一体こいつはなんなんですか?」
僕がサチに問うと、彼女は「知りたいですか?」と意味深なことを言った。僕が頷くと、「私にもよくわかりません」と拍子抜けな答えが返ってきた。彼女が言うに、僕らが想像する「幽霊」と現在僕らを妨害している「彼ら」は、似ているようで別物なそうだ。それじゃあサチ自身はどうなんだ? そう疑問に思ったが、仮に質問して彼女が幽霊だった場合、少し怖いので、やめておいた。
さっきまでは閑静としていた道は、今では騒がしくなっていた。何も無い空間からセミの鳴き声が響き、同じ様に目の前を見えない何かが飛び去っていく。目を閉じて耳を塞いでみても、音は聞こえっ放しで、むしろ目を閉じた分そこに実際に何者かが存在するように感じ、僕は慌てて瞼を開いた。
まるで、悪夢そのものだ。
時間を増すごとに、音は種類を増していった。
例えばそれは、笑い声だった。辺りから楽しそうな声が、僕に向けて発せられていた。それはバラエティ番組で流れそうな、男女混ざった明るい笑い声なのだが、このような場で聞くと、妙に恐ろしかった。
お母さん、お母さんと僕の数メートル先で泣きじゃくる者もいた。目には見えないが、声のする辺りからして、大体身長百センチ程度だろうか。呂律の回らない状態でお母さん、お母さんと段々声の調子を上げて叫ぶ。さり気なく隣でサチが、「水子でしょうね」と呟いた。過去に同級生で子を作ってしまい、中絶したという話を思い出して、何となくやりきれなくなった。
もし一人だったら、間違いなく僕はどこかで振り向いていただろう。しかし隣にサチという存在がいるのは心強く、僕に強い安心感をもたらした。彼女は時折僕を慰め、時には僕にアドバイスした。これはこうだから気にしてはいけない、こうすればどうにか耐えられる、こうだから絶対に振り向くな。彼女の一言一言には力があり、確実に僕の励ましとなっていた。
守護霊、という奴だろうか。途中、僕はそんなことを考えた。祖父から聞いた話、誰にでも守護霊というものはついているものらしく、それは最も親しい者であったり、親族の誰かであったりするらしい。その守護霊の徳が高ければ高いほど、生き長らえる可能性が伸びるそうだ。頼りになる守護霊で、本当に良かった。
「砂利道が見えてきたら、一気に走ります」
サチは前方を指差して、そう言った。
「何も考えずに突っ走ってください。とにかく、小屋に入ることだけを考えてください」
墓のある場所は危険なんです。そう言うと、彼女はまた黙り込んだ。本当ならお喋りでもして気を紛らわしたかったのだが、気が少しでも緩めば、ちょっとしたきっかけで振り向いてしまいそうな気がした。だから僕らは、黙って歩き続けた。
背後から、「駄目だよ」と耳元に囁かれた。僕は驚いて少し腰を浮かせたが、それでも決して振り返りはせず、歩き続けた。先程の声の主が、「あああああああ!」と泣き喚いているのが聞こえた。
ここまで来るともう、相手はこちらの気を引くことしか考えていない。とにかく意味不明な発言や行動を繰り返して、こちらを混乱させてくる。「ねえ、どっちがいい? どっちがいい?」と嬉しそうに話しかけてくる中年男性の裏声と思われる声。ひたすら息を荒くして、僕の真横についてくる奴。「振り向いちゃ駄目!」と連呼する女の声。
僕は殆ど何も考えずに、足を速めた。脇の下を、冷や汗が次から次へと伝っていく。
「助けて、助けてよ」
足元で、口々にそう囁く声。
「うるさい!」と僕が叫ぶと、周辺から一斉に笑い声が響いた。
思わず、僕は駆け出していた。
必死だったせいか、思ったよりも早くアスファルトの道を抜け、そうして、砂利が見えた。
あともう少しで、小屋に辿り着く。
そのときだった。
背後で、獣のような絶叫が聞こえた。人がガソリンをかけられて焼かれたら、丁度こんな声を出す。聞いたことも無いのに、なぜかそう思った。聞いている側が発狂しそうなその声に、僕は思わず振り向きそうになってしまった。首が四十五度ほど回ったところで、何とか寸止めしたが――
視界の隅に映った「何か」に、僕は目を向けずにはいられなかった。
それが何だったのか、果たしてそれを見た僕がどんな感想を持ったのか、全く覚えていない。
とにかく、走っていた。気付けばサチに促され、全力疾走していた。
「振り向いては駄目です、走ってください!」
必死に叫ぶサチの声が、次第に遠ざかっていく。僕は直感した。自分を襲おうとしている何かを、サチが食い止めてくれている。
サチ? どこかで聞いたことのある名前だ。
いや、当たり前だろう。たったさっきまで、僕の隣にいた女性のことだ。
違う。そうじゃない。僕はもっと前から、彼女の存在を知っていた。
息を切らしてひたすら足を動かす中、脳内に、ある言葉が浮かんだ。
『飼ってあげられなくてごめん』
飼う? 何のことだ? 動物のことか?
……猫。
そうだ。黒猫だ。
それをきっかけに、段々と記憶が、連鎖するように蘇ってきた。
――サチは、捨て猫だったんだ。
日記の四ページ目に、黒い生物と僕が遊んでいる姿があった。
確かあの日、僕は捨て猫と出会ったんだ。
首輪を付けていて、とても人間に慣れている、賢いメス猫だった。随分と弱っていて、僕はその猫のために、牛乳を家から持って行ったんだ。最初は僕を警戒して、引っ掻いてきた彼女だったが、しばらくすると、僕の与えたものを受け取った。美味しそうに牛乳を舐める猫に、僕は愛着を持ち、翌日も猫に会いに行った。彼女は後ろ足を怪我していたらしく、いつも一定の場所でじっと座っていたから、その次の日も、その次の日も、僕は猫に会いに行った。初めの内は食料さえも受け取らない彼女だったが、しばらくすると僕が撫でても、嬉しそうに目を細めるようになっていた。その時、僕は猫の撫で方を覚えたんだ。僕はいつか家族に言って、この黒猫を飼ってあげようと思っていた。
しかし猫は、死んでしまったんだ。元々衰弱していて、寿命も切れかけていたんだろう。僕はその黒猫のために、お墓を作ってあげた。ただそこら辺に埋めるのでは可哀想だと思って、わざわざ人間と同じ様な場所に、丁寧に埋めたんだ。そうして辺りから一番大きい石を持ってきて、上に乗せた。
確かあのときの猫の首輪に書いてあった名前は、サチだった。
そうか。お前だったんだな。
今まで気付けなくて、ごめん。
ありがとう。
背後に響くサチの叫び声。僕は小屋の中に入ると、再度出口に飛び込んだ。
景色が反転して、世界が逆転して、サチの声が遠くに聞こえた。ニャー、ニャーと耳元で猫の鳴き声が聞こえ、笑い声が響き、突然背後の気配が消えたかと思うと、くるくると世界が回転した。
そうして僕は、どこか遠くへ飛ばされたのだ。
*
気付くと、目の前に砂利があって、目を瞑った瞬間思いきり砂利にヘッドスライディングする羽目になった。数メートル砂利の上を腹で擦り、痛みでうめいていると、聞き覚えのある声が、頭上から聞こえてきた。
顔を上げると、驚き半分、笑い半分と言った感じの麻里が、僕を見下ろしていた。
「脅かさないでよ。死体でもあったの?」
立ち上がり、小屋の入り口を見るが、何かが追ってくる様子は無い。辺りにはアブラゼミの鳴き声が響き、小鳥の囀りが聞こえる。ベンチの屋根の柱を見ると、ちゃんとクモの巣が張っていた。
ようやく、戻って来れたのだ。
僕は安堵の溜息をつき、服の汚れを払った。
確認の意味で、麻里の顔をもう一度見る。やはり本物の麻里だ。嬉しさの余り思わず握手を求めてしまい、凄い勢いで不審がられた。
それから、「数時間も、よく待ってたな」と言うと、眉をひそめられた。
「さっきから何を言っているの? 暑さで頭をやられた?」
どうやら、僕には数時間の出来事に感じたが、彼女の体感時間ではほんの短い間の出来事だったらしい。いや、もしかしたらこちらでは一秒も過ぎていなかったのかもしれない。多分あちらは、時間という概念が存在しないか、こちらと基準がずれているのだ。彼女からしてみれば、僕は小屋に入った瞬間、大慌てで飛び出てきて、数メートルヘッドスライディングしているのだろう。驚くのも無理は無い。
何から言おうか迷ったが、どうせ今までのことを話しても信じてもらえないだろうと思い、僕は麻里にその小屋に入らないように言いつけた後、サチを埋めた、お墓のところに行った。
僕が八年前に置いた墓石は、綺麗に真っ二つに割れていた。
じんわりときて、少しだけ涙腺が緩んだので、慌てて数回瞬きをして、それから空を仰いだ。
――日記を書いた、あの日のことを思い出す。
『怖い怖い幽霊に出会った。けれども僕だけには、その正体がすぐにわかった』
サチを埋めた翌日、もしかしたらサチが生き返っているのではないかと、僕はお墓に再度足を向けた。なぜそんなことを考えたかは未だに良く分からないが、その予想はあながち外れていなかった。そこで、僕は黒尽くめの女性と出会ったのだ。目が合った瞬間、僕には彼女が、幽霊だということがわかった。そして、サチだということも。子供というのは、そういうことに敏感なのだ。
僕は彼女に謝った。ちゃんとしたご飯をあげられなくてごめん。飼ってあげられなくてごめん。
サチはあまり深いことは語らず、ただ、いつか僕が彼女にしたように、僕の頭をゆっくりと撫でてくれた。
「謝ることは無いです。むしろ、こちらが謝りたいくらい。本当に本当に、感謝しています。私はあなたを忘れませんが、あなたは私のことを、忘れてください」
目を細めてそう言って、サチは姿を消した。しばらくして、僕は綺麗さっぱりそのことを忘れてしまった。
何故そうも簡単に、あのような衝撃的な出来事を忘れることが出来たのか。最初は不思議でならなかったが、今思うと、何となく納得が出来る。おそらく今日あった出来事も、数年もすれば僕の記憶からは消し飛ぶのだろう。何かきっかけが、ない限り。
後ろから追いかけてきた麻里に向かって、僕は言った。
「どうして俺が日記の内容を思い出せなかったか、ようやく分かった気がした」
その言葉に、麻里は不思議そうな顔をして首を傾げた。
そう。
悲しいことは、忘れるようにしていたんだ。無意識のうちに。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
-
-

- 気になる売れ筋おもちゃ・ホビー・ゲ…
- LEGO ‐ Star Wars ‐ | レゴブロック…
- (2025-11-15 21:55:46)
-
-
-

- 鉄道
- 【2025/10/30】江ノ島電鉄線 1101‐1…
- (2025-11-22 14:15:52)
-
© Rakuten Group, Inc.