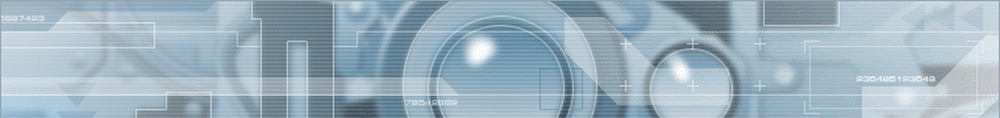4. 雨のせらせら
「まるで君の部屋だね」
美春がそう言って笑う。棚にあるテノールリコーダーを手にとって、「でかい」と驚いている。
最近まともにクラシックギターの練習をした記憶が無かったので、今日こそは、本腰を入れて練習に挑むことにしていた。この日は今野も来ていなく、部室には僕一人だった。少々寂しいが、集中できると考えれば、別に文句は無い。オープンにしたチューニングをレギュラーに戻していると、控えめなノックの音が聞こえた。ここにわざわざノックをして入ってくる人間も珍しい。待っていても入ってこないので「どうぞ」と冗談交じりに答えると、ドアが開いて美春が「やあ」と入ってきた。辺りを見回して、「ええ、君しかいないの?」と驚いた様子でドアを閉める。驚いたのはこちらもだ。一度、座席表か何かで見たことがあったが、彼女は確か部活動無所属で、ああそうか、暇なのか。
「教育実習生と仲の良い、小菅くん」
中腰で変な呼び方をしてくる。
「なんですか」
「その教育実習生は今、忙しいみたい」
「教育実習生なんだから、当然だろうね」
「でも私は、忙しくないんだ」
だからなんですかと言いたくなるのを堪え、適当な返事をする。「そうなんだ」
「君は忙しい?」
「そうでもない」
一応、真剣に練習に取り組もうとしていたところなのだけれど。
美春はアップライトの鍵盤を手馴れた動作で叩き、ラの音が鳴らない事に対して不満を覚えたようで、その鍵盤を連打する。ジャズのようなフレーズだったが、何を弾こうとしたのだろう。
「なんか弾いてみて」と美春が振り向き様に言った。
「悪いけれど、弾かない」
「どうして」
「今日は弾かない日だから」
「なんだそれ」
「それに、あまり人前で弾くものじゃないんだ」
「ふうん。普通は自分から弾きたがるのに」
アップライトを見捨て、半回転してこちらに戻ってきてから、「じゃあ、私も弾かない」と言った。よく意味の分からないことをいう女だ。黄色いスポンジがはみ出た丸椅子に座ってくるくる回りながら、「本当に弾かないの?」と訊いて来る。
「練習くらいはするかも」
「しなよ」
「するか」
ようやくレギュラーチューニングに戻ったギターを左太腿に乗せて、手癖のようなフレーズを幾つか弾き流した。美春は僕の左右の指の動きを真剣な眼で追い、僕が三四個のフレーズを弾き終えると、「やるね」と手を叩いた。褒められて悪い気はしない。「ありがとう」と返しておく。
「よくそんなに複雑に指を動かせるね」
感心したように僕の手を見詰める。
「練習しているから」
「手の大きさ、どれくらいあるの?」
これくらい、と手を開いて指をぴんと伸ばして見せた。すると美春も同じように手を開いて、それを僕の掌に重ねた。何回かずらして位置を合わせた後、重なった手を見つめ、「なんだ。特別手が大きいわけじゃないんだ」とからかうように言った。
心持強めに美春の手を掴むと、「痛い痛い」とあまり痛くなさそうにわめいた。手を離すと、彼女は掴まれた方の手を押さえ、「今ので、だいぶ縮んだ」と俯いた。
「縮んだ?」
「うん。握られすぎて、縮んだ」
「じゃあ、引っ張ったら伸びるな」
「かもしれない」
美春が中指を引っ張っている姿を眺めながら、運指練習を機械的にこなす。美春もすぐに飽きて、壊れたアップライトでハノンを弾き始める。どちらも曲は弾かないというのが変だ。
「小菅くんは、どう思う?」
「教育実習生のこと?」
「うん。クラスではあんまり評判がよくないみたい」
「無愛想だからね」
「小菅くんと同じく」
「そうそう」
「うそうそ」
「僕はあの人のこと、あまり嫌いじゃないよ。教え方は結構上手」
「やっぱり雰囲気の問題かな」
「ちょっと怖いかもしれないね」
「私も最初は怖いと思ったけれど――」
しばらく指と口を切り離して、二人で早雨についての印象を語り合った。やはり美春は彼のことを気に入っているらしく、早雨に関するエピソードを幾つか聞かせてくれた。その中には平生の彼からは想像できないような話もあり、同時に美春が想像以上に彼と親しくしていることも伝わってきた。
そうやって練習した結果、どういうわけか、これまでに無いほど練習に集中できた。珍しい来客の前だと、見栄が出てきて綺麗な練習がしたくなるのかもしれない。曲を弾かない、と断言したのも理由にあると思う。何より美春と喋ると、会話が滑らかに進み、楽しいのは否定の仕様が無い。異性と気が合い、会話が純粋に弾むという経験は、今迄あまり無かった。
「教育実習生の人を一緒に迎えにいってみない?」と美春が指を止めて言った。
「まあ、構わないけれども」
構わないけれども、僕を連れて行ってどうするつもりなのだろう。
美春は「ありがとう」と言い丸椅子から降りて、僕に手招きしてドアに向かった。ギターをスタンドに立て掛け、後を追う。
昇降口を出たところで、二人で適当な間隔を取って呆然と突っ立っていると、すぐに早雨は姿を現した。美春は彼の生態系を正確に把握しているらしい。
「さつさん」
美春は早雨の元へ駆け寄っていった。なんだ、さつさんって。いや、早雨のことなんだろうけれど。ついて行くか行かないか迷っていると、美春が再度僕に手招きした。恐る恐るついていく。
「あれ、小菅じゃないか」
早雨が僕を見て、唯一瀬良さんとの接点となり得る僕を見て、教室では浮かべないような種類の表情を浮かべる。
「どうして小菅まで?」
「流れです」
「私が連れてきたんです」と美春が口を挟む。
「そうか有難う。美春はすごい」
早雨が腰を低くして真正面から美春を褒める。美春は照れくさそうに「どういたしまして」と早雨と握手する。
判然としないが、会話を聞く限り、早雨が僕と話したいという意思を持っていたということになるのだろう。そこで美春が気を利かせて、僕を連れてきた。
感情のベクトルを向ける方向に悩んでいると、今度は僕の顔を早雨が覗き込んできた。
「美春と仲が良いのかい?」
思わず一歩後退りそうになる。どうなのだろう。自分でも分からない。向こうがどう思っているかが分からない。
返事に窮していると、早雨は勝手に話し始めてくれた。
「最近悩み事があってさ」
「はあ」
「自分の年齢の二倍くらいの人間と親しくなるには、どうすればいいんだろうか」
「さあ」
つくづくこの人間はどういう性格をしているのか分からない。言動だけ見ると、至って普通の、気さくな人物なのだが。
「先日、瀬良さんの話をしたじゃないか」
「しましたね」
「それで、実を言うと、ははは」
突然笑い出す。自分でこれから言おうとしていることが可笑しいらしい。大体察しは付いているが、「実を言うと?」と先を促す。
「まあ、歩きながら話そう」
僕の肩を押し、隣に並んで歩き出す。美春がきょとんとした表情でその後ろを付いてくる。
「俺はね、小菅。瀬良さんと、もう一度だけ、話をしてみたいんだ」
もう一度だけ、というところが強調される言い方をした。無遠慮に大きい体と比べて、願望は控えめだ。
「どうすれば話せるか、一緒に考えてくれないかな?」
五歳以上年上の人間に、この手の相談をされるというのも妙な気分だ。僕がまばたきしているのを見て、早雨は「いや、普段はこんなに図々しくないんだよ。ただ今回は、切羽詰っているから」と取り繕う。「切羽詰っている?」と僕は聞き返す。
「実習が終わったら、また実家に戻るんだ。友人にはそう約束して泊めてもらわせている。好機があるとしたら今のうちだけなんだ。出来るなら、近隣の住民として、瀬良さんと関わってみたい」
近くのアパートでも借りればいいだろうと思ったが、早雨は貧乏なので、そういうわけにも行かないのかもしれない。
さりげなく振り返る。一歩後ろを来る美春の表情が固い。微笑んでいるけれど、固い。皆それぞれ一緒にいたい相手とは一緒にいられないのだろう。苦笑いしたくなる。
「関わってみたい、というと?」
「世間話とか、してみたい」
「そんなんでいいんですか」
「ゆくゆくは、冗談とかも言い合ってみたい」
物凄い寡欲ぶりだ。
「もう名前を読んでもらえたら幸せかもしれない」
「さつさん。さつさん」
「なんだい美春」
「ちょっと気持ち悪いですよ」
「そうかもしれないなあ」
気持ち悪いといいながら笑う美春と、気持ち悪いといわれて笑う早雨。あれ、気持ち悪いってどういう意味だったっけ。最近定義が曖昧になってきた。
ああ。もしかしたら早雨は、瀬良さんのことを既婚者と考えているのだろうか。いや、考えてみればあの年で独身なのは珍しい方だ。瀬良さんを一目で未婚者だと見抜ける人間はそうそういない。控えめになるのも無理は無いのかもしれない。早雨は「一度だけ話してみたい」とは言っているが、本心はで懇意になりたいに決まっている。瀬良さんが独身ということを知れば、男女としての関係も持ちたいと願うだろう。
試しに考えてみる。瀬良さんと赤の他人で、顔が怖くて、体が大きくて、控え目で、奥手な彼が、瀬良さんと仲良くなる方法。いや、仲良くならなくてもいいのか。一度話せれば十分みたいな言い方をしていた。
「困ればいいんじゃないでしょうか」と思いついたことを言ってみる。
「というと?」
「子供染みた単純な方法ですが、瀬良さんの傍で、いかにも困って見せればいいんです。そうすれば十中八九助けてもらえます。そういう人なんです」
早雨は僕の言葉に、しきりに頷く。自分が一度助けてもらって経験があるから尚更だろう。当時のことを思い出しているらしく、目が少し潤んでいる。
「そうすれば一度互いに顔も見ていますし、あとはもう、流れです」
「さすが、頼りになる」
僕の背中をばしばし叩く。これくらいで褒められてもこっちが困る。
「ただひとつ、覚えて置いてください」
「なんだい」
「瀬良さんと話そうとする上で一番難しいのは、瀬良さんと会うことです。付き合いの長い僕ですら、見つけろと言われても中々見つけられるものじゃありません。どこに住んでいるかも分かりません」
「家の場所が、わからない?」
「訊く度に変わっているんです。要するに隠しているんです」
「どうして隠す必要があるんだろう」
「瀬良さんは秘密が多い方が格好いいと未だに信じているんですよ。会えるかどうかは、流れ次第です」
「流れ、か」
ふっとからかうような目つきになる。
「小菅は、流れという言葉が好きみたいだね」
「流されているのを自覚しているからです。選べるのは、右か左かくらいです」
「難しいことを言うんだね」
「難しいことを言いたいんです」
駐輪場につく。早雨の置き場は僕らと離れているので、一時的に僕と美春の二人になった。そこでようやく美春が口を開いた。
「瀬良さんって? 小菅くんの知り合い?」
当然の疑問だ。僕は自分達の関係をなんと呼べば的確に表せるかを考えて、しかし我が意を得るような回答は思い浮かばなかったので、「うん。知り合い」と無難に答えた。
「どういう人?」
「良い年の重ね方をするとああなる代表」
「え、年寄りなの?」
「五十歳くらいかな。見た目はもっと若いけれど」
「五十歳って、さつさんの二倍以上じゃん」
ぎこちなかった声にいつもの調子が戻ってくる。自分にも希望はあるとでも思ったのだろうか。
「瀬良さん、ね」
「そう。瀬良さん」
「ケセラセラ」
「人物像もそんな感じだよ」
「なるようになるさ」
「流されるだけだね」
早雨がペダルを漕いでくる。美春がケセラセラ、と呼びかける。早雨が首を傾げる。
「どれだけ年上好きなんですか」
にやついた美春を見て、早雨が僕に「なんで教えちゃうんだ」という視線を送る。
「まあ確かに、もう少し若かったら、とは思う」
苦笑いをする。もう少し若かったら、どうなのだろう。今より近づきやすかったのかもしれない。
数日後、駅の広場で「3Dで視力を良くする本」と睨めっこする瀬良さんを見つけた僕は、このような問いかけをしてみた。
「瀬良さんは、若返れたらどうしますか?」
やはり本を素早くしまった瀬良さんは口を尖らせ、「年寄りで悪かったな」と意地悪い笑いを浮かべる。こうも僕が頻繁に瀬良さんと遭遇するのは、行動様式が二人で似通っているからだろう。
「いや、違うんです。遊びです。他意はありません。僕もこういう想像は頻繁にします」
「じゃあ、模範解答をどうぞ」
「五歳児に戻れたら僕はピアノを始めて、ついでに同じクラスにいた、当時は目立たなかった麻里ちゃんと仲良くなっておきます」
「へえ。その遊びは楽しい?」
「一時的に」
彼女は「そうだな」と腕組みをした。姿勢は悪いが、手足が長いので、腕組みがさまになる。口元にうっすらとある皺が僅かに歪んでいる。
「若返ったら、また年をとる」
「そうですね」
全くその通りだ。
「二十歳くらいに若返れたら、ちゃんと、結婚すると思う」
「今だって出来ますよ」
「嬉しいことを言う」
「三四回は出来そうです」
「多ければいいってわけじゃない」
「しないよりましですよ」
「耳が痛いね」
彼女は一呼吸置いて、「私は」と続けた。
「大人気ないんだ。いい年こいて、ロマンチストなのさ」
僕が釈然としないのを見て、こう付け加えた。
「羽の生えた白い馬に乗った王子が迎えに来るのを待っているんだ」
「理想が高いと言う意味ですか?」
「そういうこと」
「子供じゃないんですから」
「うるさいどうせ賞味期限切れだ」
「賞味期限って意外と当てになりませんよ」
「当てにしないのは貧乏人だけだ」
「確かに」
早雨辺りはあまりそういうのを気にしていなさそうだ。食品も、人も。
「でも貧乏人にも良い人はいます」
「まあ、そうだね」
やけに物分りがいい瀬良さんはあっさり譲る。こういうところが清々しい。
「カボチャの馬車が来て魔法をかけてくれれば、一件落着なんですがね」と僕は独り言のように言った。
早雨もそれを望んでいる。もう少し、若かったら。
ふと今更のように気付いたが、早雨がここにきてから、既に三週間が過ぎている。あと一週で彼はここを去るのだ。それを考慮すると、彼が急く気持ちも分からないでもない。
そんな時期になっても、早雨は相変わらずクラスに馴染めずにいた。一人べたべたと張り付いている美春を除けば、彼に進んで話しかける人間などいない。まともに話したことがあるのは僕と美春だけ、という可能性も少なくない。かと言って、一般の人なら諦めそうな位置関係にある瀬良さんに対してはそこそこ積極的である。興味の無い人間にはとことん興味が無いのだろう。親友はいるけれど友人がいない種類の人間だ。両極端しか選択しない、もしくは出来ない。
僕だって本来ならば、彼と関わりあうようなことは無かった筈だ。偶然、今目前にいる瀬良さんと知り合いだったために、早雨は僕に接近した。接近することにより、僕は早雨が見た目にそぐわず人畜無害な人間だと知った。早雨が僕に接近したから、美春も僕に近づいた。近づくことでようやく僕は、美春という人間が想像していたよりずっと親しみの持てる相手だと知った。
例えば僕が瀬良さんと話している現場を早雨が目撃しなかったら、早雨は僕に話しかけるようなことはせず、一人で悩んでいただろう。僕は早雨のことを無愛想な人間だと決めつけ、美春は僕のことをクラスメイトの一人としてしか扱わなかっただろう。
こんな風にして、これまで僕は、幾つもの良き出会いを潰していった可能性はいくらでもある。考えても仕方の無い話だが、早雨や美春のように付き合ってみれば印象が変わる相手が何人もいたらと思うと、悔しくなる。気の会う人間全てと知り合うのは不可能だし、知り合った人間全ての性格を全面から把握することも不可能だ。いやひょっとしたら、たった一人の人間でさえ、全面から捉えるのは無理なのかもしれない。それは考えてみると、結構勿体無くて、寂しい話だった。
太陽と雲が重なり、僕らを照らしていた陽光が遮られる。近頃、世間が梅雨を意識し始めた。もうすぐ雨の季節になる。湿った空気の到来と共に、早雨はいなくなる。
4.
何をしたわけでもないのに、指の調子が格段に良くなった。各指がほぼ独立している。一音一音を大事にする余裕が出てきて、単純な曲を弾いても今迄と違う。一体自分に何があったのだろうと思う。
終いには僕の演奏を聴いた今野が、簡単に褒めてくれた。あの今野が、褒めてくれた。口を開くだけでも珍しいというのに、
「特に芸術的な腕前は、ある日突然変わるものなんだよな」
などと突然説明し始めるものだから、開いた口が塞がらなかった。
「絵も音楽もそうなんだけれど、ちょっとした大きなきっかけで、随分変わるんだ。心境、心掛け、環境の変化一つで、数年間伸び悩んでいたものが、いきなり急成長することがある。現在のお前みたいに」
「へえ。よく分からないけれど、ありがとう」
僕の返事に軽い失望を覚えた様子だった。またいつもの調子で、地道にトレモロ練習を始めた。僕が真似をして後を追うと、構わずテンポを上げてくる。あっという間に僕は追いつけなくなった。何が急成長だ。
ドアが二度、軽い音を立てる。振り向く間も無く美春が「やあ」と顔を出し、今野を見て、「あれ?」と素っ頓狂な顔を上げる。
「部員が二人もいる!」
「本当は全部で四人いる」と答えたのは今野の方だった。
「知らなかった」
「美春か。どうした?」とようやく僕も反応する。先程から今野が予想と少し違った行動を取る。
「今日もさつさんは忙しいみたい」
「今日は僕も忙しい」
「今日も私は忙しくない」
今野が「急に忙しくなった」と言って立ち上がろうとする。引っ張って無理矢理座らせる。
「死ぬほど忙しいってわけじゃないよ、僕らは」
「そうなんだ。じゃあ、二人に面白い話をしてあげようか。さつさんに纏わる」
僕は今野の顔を窺う。今野が別にいいよ、という風に瞳を動かす。
「してくれ」
「え、迷惑じゃないの?」
「じゃないみたい」
「そう。じゃあ、話そう」
さつさんというのは教育実習生のことだ、と僕は今野に説明する。それくらい分かる、と彼はあっさり流す。
「私は、さつさんが実習生として学校に来る以前に、彼と知り合っているんだ」
ああ、それで。
ようやく、長い間抱えていた疑問が解けた。だから何の抵抗も無く、あの癖の強い教育実習生を受け入れられたのだ。
「と言っても、顔見知り程度かな。会ったのは一度きりだし。中学生の頃の話で、当時私は塾に通っていてね。電車で通っていたんだけれど、帰りの電車がすごい眠いんだよね。いつも慌てて降りて、たまに乗り過ごして。中ニのときだったな。その日も慌てて降りて、一安心して、そこで車内に荷物を置き忘れたのに気付いて、――同時に背後から話しかけられたの」
早雨に、か。
「なんて話しかけられたと思う?」
見当も付かない、と僕は答える。今野も同意する。
「お嬢さん、忘れ物ですよ。って」
「お嬢さん?」
「そう。お嬢さん。無愛想な声で。振り向いたら、あの顔」
横目に今野を見る。口元に力が入っている。おかしいのを堪えているのだろう。身振り手振りが大袈裟な美春を見ていると、今野でも愉快になるのだ。
「びっくりしたよ。男の人にお嬢さんなんて呼ばれたの、初めてだったし」
美春は幸せそうに思い出し笑いをする。
「しかもさつさん、私を追いかけてきたせいで、電車に戻り損ねちゃって。極めつけに、自分の荷物は車内に置き忘れているの」
「見た目に反して意外とぬけているんだよね、あの人」
「なんか申し訳ないから、一緒に駅員さんに相談して、次の電車を待って、見送って」
数年後、学校で再会。
遠い目をして、思い出を確認するように話す美春を見て、以前早雨が瀬良さんのことを話していた場面を思い出した。この二人は矢張り似ているのかもしれない。
話が尽きた後で、美春が「ところでさ、今日は弾く日?」と思い出したように言った。そういえば以前、今日は弾かない日などと言って誤魔化した気がする。「弾く日だよ。彼が」と言って今野を指差すと、「自分で弾けよ」と舌打ちされた。仕方無しに右脇に抱えていたガットギターを構えなおし、何を弾こうか考え、小難しくなく一番耳障りのいい曲を選んだ。僕がイントロのハーモニクスを爪弾き始めると、またクラシック以外の曲か、と今野が意地悪い笑みを浮かべた。僕が指先に集中している間は、美春も話しかけてこなかった。
「今の、何ていう曲?」
演奏が終わると、美春が拍手をしながらそう聞いてきた。弾き損ねた回数でも宣告されると思っていたが、今野も手を何回か叩いてくれた。
「アンジェリーナ、という曲だよ」
アンジェリーナ、アンジェリーナと美春が繰り返す。自分の名前を呼ばれているような気分になる。
その後、今野にも無理強いし、アルハンブラの思い出などの非人間業を披露させ(こちらの方が美春には受けが良かったようにも見えた)、更に美春にもピアノを弾いてもらった。以前弾いたジャジィなフレーズは、どうやらビル・エバンスの曲らしい。こちらは今野がやけに感心していた。
時間は瞬く間に過ぎる。今野が腰を上げ、「じゃあ」と珍しく挨拶をして、一足先に退室した。僕も帰り支度をしていると、美春が「ねえ、アンジェリーナ」と呼びかけてくる。「なんだいお嬢さん」とふざけ返すと、「今日もさつさんを迎えに行こう」と誘ってきた。校舎を出ると既に日は沈んでいて、教室が所々強い光を放っている。中でも一際明るい職員室の中で、教師達がせわしなく働いている。
今日の早雨には何があったのか、この季節にどうやったらそんなに汗をかけるのかといった状態で、前髪が額に張り付いて悲惨なことになっていた。どうしたのかと訊ねると、緊張による汗だと言う。何がそれほど彼に冷や汗をかかせたのだろう。
「しかし、本当に長いですよね、さつさんの髪」と美春が見上げて言う。本当だよ、と早雨が前髪をかきわける。その様子を見て美春は、「そうだ、いいことを思いつきました。私が美容師になればいいんです」などと突拍子も無いことを言い出す。
「週一でカットしてあげます」
「そしたら助かるね。俺の印象ももう少し、明るくなる」
「さつさんは眉が出るくらいの方が似合います」
「俺もそう思うんだけれど、すぐ伸びるからさ」
「だから週一で切るんです」
冗談なのか本気なのか分からないようなことを真顔で活き活きと喋る。今日は僕が一歩後ろをついて歩く。
「そういえば、小菅。困ったことがある」
すぐにこちらに意識を移す。美春の口がすぼむ。
早雨の言う、困ったこと。それはいくら計画を練ろうが、積極的になろうが、、解決しようの無い問題。
肝心の瀬良さんが見つからない、ということだった。
話を聞いた僕は、それでも、黙っていても二人はそのうち出会えるだろうと高をくくっていた。しかし早雨の猶予期間が残り四日ともなると、流石に焦燥の感が出てきた。逃げた猫でも探すように「瀬良さーん」と彼女のいそうな場所を捜索しても、全く見当たらない。旅行でもしているのだろうか。彼女の行く先は見当が付けにくい。
瀬良さんは、美春に勝らず劣らず自由人だ。奔放に生きていて、一つの場所にとどまること知らない。ふいとどこかに出かけては、土産を持って帰ってくる。なにも知らないこちらが、これはなんだと訊ねると、良くぞ聞いてくれたとばかりに土産話を披露する。また、自由人なのに加え、謎多き人でもある。一例を挙げると、僕は彼女の職業を未だに知らない。下手な友人より余程長く付き合っている相手なのに、下の名前を知らない。住居を構えている場所も分からない。知っているのは瀬良という苗字くらいなものだ。
残り二日、日曜日の午後。早雨が教育実習生として過ごす、最後の日曜日だ。
傘入れからを自分のを抜き出し、楽器店に足を運ぶ。CDショップの二階にある、比較的こじんまりとしたそこに、早雨はいた。隙間無く並んだフォークギターを眺めて、虚ろな目をしていた。と思ったら出し抜けに気合の籠った顔になる。声をかけると、いつもの表情に戻る。
「実は、あれから定期的にここに足を運んでいるんだ」
早雨が自嘲的に笑う。僕が言った、瀬良さんとここで出会ったという話を鵜呑みにして、いや、藁にすがるような思いで、やってきているのだろう。奥手だが健気な人間だ。
「それで、瀬良さんはきましたか?」
「いや。残念ながら、一度も」
でしょうね、と肯く。僕も、もし若返ったら、という話をしたのが最後になる。
「瀬良さんは、一体どこにいるんだろうなあ」
早雨が嘆息する。こんなことならもう少し早く行動に出ればよかった、そう思っているに違いない。彼の目には、もうなりふり構わないぞ、といった狂気染みた覚悟すら浮かんでいた。僕も、一度協力するのを決めた以上、彼を瀬良さんと一目でも合わせなければ申し訳が立たない。二人で焦る。
「おそらく、ここ最近、雨で冷え込んでいるのが原因じゃないでしょうか。瀬良さんは、暖かくないと外出しないんです」
「寒がりなのか」
「前にも言ったように、いざ探すとなると見つけるのが難しい人間なんですよ。半年くらい会わないことだってありました」
こんなことなら、以前会った際、「あなたと話したがっている人がいる」とでも伝えて置けばよかったのだろうか。しかし、その頃の早雨はそれを望んでいなかった。
「どうしてここにきて雨が続くんだろう」と早雨は自分の苗字半分を恨んで嘆息した。「縁が無いのかな、俺には」
問いかけには答えず、「晴れるといいですね」と僕は言う。
「晴れてもらわないと困る」
店を出る。傘を開くと、互いの距離が少し開く。結局瀬良さんと会うには、彼女同様ふらふら歩いて行き当たりで偶然を待つしかない。
彼女が好みそうな場所を探して歩く。イコール、僕が好む場所でもある。森林公園、本屋、紅茶専門店、屋台。片端から早歩きで早雨と回る。一つ巡るたびに「いない」と早雨が肩を落とす。
川沿いを歩く。いつもはジャージ姿でランニングする人が目立つここも、この天気では人通りが少ない。川も大分濁っており、いつもは陽気な川辺もこれでは台無しだ。ここに瀬良さんが来るわけがない。道を外れて次の目的地へ向かう。
段々と雨が小降りになってきて、擦れ違う人々に傘を閉じて歩く者が増え始めた。早雨も水気を払い、傘を丁寧に巻き始める。僕もそれに倣う。
ふと、思った。今のうちに、しっかり話をしておくべきなのかもしれない。彼とまともに話す機会は、意外と少なかった。
次第に僕の口数が増えてくる。思いついたことを、吟味しないで次々と口にして会話を紡ぎだす。殆ど場を持たせるためだけに用いられるようなことも話す。
「――そういえば、早雨さんは、教師になるんですよね」
「こうしてきたからには、そのつもりだよ」
「どうして教師に?」
「流れだね」
「流れで教師にならないでくださいよ」
「いや、流されっぱなしでもない、時々ちょっとは泳いだ」
「ときに、恋人はいるんですか?」
「いないよ。小菅は?」
「僕ですか」
「そうだよ」
「妻が八人と愛人が十二人います」
「やるね」
ここまで聞いて、自分は今更何を聞いているのだろう、という疑念が出てきた。こんなことは教育実習生として高校にきたときに最初にする話でしかない。しかし、では、別れをすぐそこに控えた他人と話しておくべきこととは何なのだろう。陳腐な内容ばかりが頭を行き交う。もしかしたらそんなもの、最初から無いのかもしれない。
それに気付いてからは無駄なことは口にしなくなった。背の高い女性の姿を探しながら、とりとめの無いことを幾つか考えた。
早雨が去ったら、美春もまた休みがちになるのだろうか。この一ヶ月、美春が皆勤しているのは言うまでも無く早雨がいたからだ。音楽室へ頻繁に訪れていたのも、早雨を迎えに行くまでの暇つぶしだ。しきりに僕に話しかけてきたのは、早雨が僕に接近したからだ。これがなくなることで、美春は一気に僕から離れていくだろう。仮にそうでなくとも、今までほど都合のいい関係ではなくなる。早雨、さつさんと言っていれば一緒にいる理由も簡単に創作できたが、これからはそうもいかないのだ。
それくらいの理由で悲観的に考えるのは、僕も案外消極的な人間である証拠だ。しかし人との関係というのは、意思の力でどうこうできる問題ではない。それはまさしく、早雨がいくら積極的になろうが、瀬良さんには届かないように。
彼らのことを思い浮かべたとき、脳裏によぎるものがあった。そうだ。あった。手遅れになる前に、早雨と話しておきたいこと。
駅の傍の広場で立ち止まる。真ん中の窪みに水の溜まった座椅子が、時折雲の間から差し込む光で煌く。数人の小学生が走り回っていて、中には真っ青な長靴を履いた子もいる。殊更に水溜りに踏み込んで、飛散する水に周囲の子が逃げ回る。「元気だな」と頬に飛んできた水を手で拭いながら早雨が笑う。
「長靴ですね」
「ああ。俺も小学生に戻ったら、まずあれを履いてみたい」
小学生に戻ったら。そんなフレーズをどこかで聞いたことがある気がして、僕は記憶の引き出しを乱雑に開けていく。
「そういえば、似たような話を、瀬良さんとしたことがあります」
「長靴のこと?」
「いえ。もし若返ることが出来たら、という話です」
「いいなあ。瀬良さんは、なんて言っていた?」
やはり彼女に関連する話になると途端に口数が増える。
「僕は五歳児に戻れたらピアノを始めて、ついでに同じクラスにいた、当時は目立たなかった麻里ちゃんと仲良くなっておくんです」
「瀬良さんは?」
「結婚したいそうです」
「していないのか?」
「していないんです」
「意外だなあ」
「相手は白い馬に乗っていないと駄目なそうです」
「じゃあ俺は駄目か」
「でも説得したら、貧乏人でも良くなったみたいでした」
「でかした」
この辺りで本題に切り込む。
「早雨さんは、瀬良さんと会えたら、最初に何を話したいですか?」
早雨の表情を窺う。
「小菅の話をするよ」
即答された。既に自分でも色々と思索していたのだろう。しないわけがない。しかし、
「どうしてまた、僕の話を?」
「瀬良さんに、こう言うんだ。『私は小菅君と親しい間柄なんですよ。それで、彼と話しているうちに貴女の話が出てきて、会ってみたいと思ったんです』と。そんなストーリーの話を」
「実はこそこそ隠れて観察していたくせに」
「そうなんだけれどね」
「他には?」
「『それと以前はお世話になりました。あなたが彼の言う瀬良さんだとは思いも寄りませんでした』。まずはここまで伝えたい」
「そういえば、前に瀬良さんに助けてもらったって言っていましたけれど、具体的に何を?」
「教えない」
そう言った彼の表情は、得意気だった。これだけは自分一人の思い出、とでも言うような微笑だった。これだけ見て暗いとか怖いと言った印象を受ける人はいないはずだ。そういう顔も出来るんだな、とここにきて初めて感心する。
聞きたいことは聞いた。後は待つだけだ。次はどこへ向かおう。正直、彼女の行くような場所はこれ以上思いつかない。休憩がてら、自販機でコーヒーを買い、ベンチに座ってしばし考える。早雨は心ここにあらずと言った様子で、遠くを見詰めている。
小学生の騒ぐ声が聞こえる。見ると、野良犬を前にしてはしゃいでいるようだった。犬は周囲を囲む者とは対照的にすました態度を取り、警戒心の無い目で彼らを眺めている。
「見てください、あの犬」と僕はそれを指差す。
「見ているよ。野良犬かな? 珍しいね」
「あ、ほらほら。始まった。見て見て」と小学生の一人が一際大きな声を出す。
野良犬は、僕と瀬良さんが始めて出会ったときにしたように、両足を上げる。早雨が「なにをしているんだ、あれは」と僕に訊ねるのより早く、犬は筆舌に尽くしがたい方法で用を足し始める。小学生の歓声があがる。早雨も「おお」と感心する。そのとき僕は既に、彼らとは別のことに注意を奪われていた。
また平然と歩いて広場を出ていく犬を、小学生が追いかけていく。早雨はそれを見送ると、僕に何か言おうとして首を捻った。しかし僕と目が合うより早く、彼の眼球は僕の隣にいた人物を捉えた。
先の犬より更に凄いものを見た、という顔で早雨は口をぱくぱくさせた。
「ね、今の犬、見ました?」
瀬良さんが僕ではなく、早雨に向かって言う。しどろもどろになりながら、早雨が「見ました」と頷く。
5.
梅雨は続いていた。青と黒の絵の具を水で溶いたような天気。降りそうで降らない。家を出た後で、しまった、やはり傘を持つべきだったと後悔する。数分ペダルをこいでから、やはりUターンすることにした。空模様が段々怪しくなってきたからだ。時間的にも、一応余裕はある。
見計らったかのようなタイミングで踏切が行く手を阻む。いつもこうだ、とブレーキをかけると、見慣れたショートカットの頭がすぐ傍に来ていることに気付く。
「お嬢さん」と声をかけると、美春は凄い勢いで首を捻ってこちらを見た。しばらく何か言いたげに口を開け、それから僕の自転車を見て、「あ、今日は時代遅れだね」と言った。
「いや。古き良きだよ」
「言っていることが前と違うよ」
「考え方も流れるんだ」
「節操の無い男だね」
「融通が利く男なんだ」
「うん。あるいは、私の方が古い人間なのかもしれない」
「時代遅れの人間は嫌いじゃないよ」
「ありがとう」
時代遅れ、という自分の発した言葉で、ふと教育実習生の顔が頭に浮かぶ。
早雨が学校を去る日、美春は一度は学校にきたものの、すぐに保健室の方へ引っ込んでしまった。形だけの寄せ書きを渡し,簡単な別れの挨拶をクラスの代表がして、早雨の教育実習は終わった。最後まで教室は彼の居場所にはならなかった。そのことが悔やまれる。殆どの生徒の中で、彼に関する記憶はどうでも良いものとして扱われるだろう。そしてすぐに薄れていく。美春はあの光景を見るのが嫌で、教室から逃げたのかもしれない。それは別れを惜しむ感傷的な感情というよりは、傍目にも辛い状況の者から目を背ける哀れみの感情から来た行動だ。日常親しくしていた相手がそういう目に遭うのを見るのは特に避けたい。
僕は初めから彼とは割り切って付き合っていたので、からかうくらいの軽い心持ちで最後も接した。生徒からどう思われようと瀬良さんと繋がりを持てたから満足していると思ったら、どうやらほどほどに沈んでいる様子だった。最終的には僕が慰める形となった。人の考えていることは最後までわからない。美春が今、どんな心境なのかも現にわからない。
「乗っていく?」
荷台を指差して言うと、美春は目を丸くして、「乗らないよ」と語尾を高くして両手を振った。
「何を言っているんだよ」
「さあ。何を言っているんだろう」
電車が通り過ぎる。轟音が止んだあとで、踏み切りを渡りながら「間に合うの?」と訊ねる。
「今日も間に合いそうにありません」
美春が携帯電話を開いて、時刻を読み上げる。
「僕も間に合いそうにないよ」
ペダルから足を降ろしてだらだら地面を蹴って、歩くのと変わらぬペースで自転車を進ませる。
「いや、小菅くんは間に合うよ」
「でも、自転車が重いから」
「乗りなよ」
「君が乗りなよ」
「なんでだよ」
答えずそのままゆっくり進む。美春が困ったように笑う。
下り坂の手前まで来たところで、荷台が重くなる。重心が固定されたのを確認すると、僕はペダルを漕ぎ出し、後は流れに任せて一気に坂道を下る。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- GUNの世界
- 絶版MGC Kimber CUSTOM COMPACT HW …
- (2025-11-22 14:42:35)
-
-
-

- 戦闘機の写真を撮るのが好き!
- 三沢基地航空祭2025.09.21
- (2025-11-22 06:30:06)
-
© Rakuten Group, Inc.