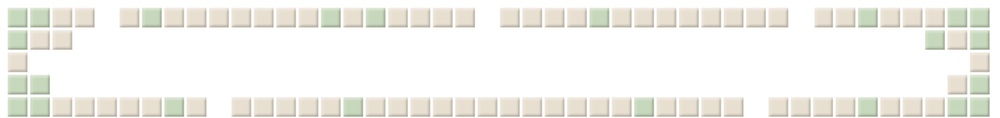#1-7 邂逅(fin)
#1
僕は玄関のポストを開けた。求人や広告を引っ張り出して、ひとつひとつ、確認した。
そして溜息をついて、田舎の夕焼け色の空を仰いだ。
吐く息は白く、その白い息は虚空の空へと消えていく。コートのポケットに手を突っ込んで、僕はアパートの階段を一段ずつ登って行った。部屋へ入って鞄をほり投げ一台のパソコンを立ち上げる。
起動したパソコンに、文字を綴っていく。一文字一文字を丁寧に、とても奇麗に、僕は懸命に入力していく。そうやって、僕の今日は終わるのだ。
「高橋。今からさ、駅前のバーガー寄ってかねぇ?腹減った」
「ゴメン、僕、今日も忙しいから」
そういって僕は友達に謝って教室を後にした。
家に着くと、僕は玄関のポストを開ける。漁るように中身を見てから、また溜息をついた。
「もう、本当に来ないのかな…」
僕はもう一度溜息をついて部屋に入った。そうして昨日と同じようにパソコンをひらき、文字を綴った。
もう、僕には、こうすることしかできないんだ。そう思っていた。
じわじわと流れる時間が僕を焦らせ、また心細くしていった。
#2
それは僕の初恋だったのかもしれない。
「あの、貴方は誰ですか?もしかして、以前、お会いしましたか?」
あの時、彼女はそう訊ねてきた。高校の通用門を抜けて、右に真っ直ぐいった処にある、ある教会の裏。そこには、只、一つのベンチと何もない、麦畑が広がっている。
そこは、僕のお気に入りだった。
体が弱く、休みがちで、固定した友人がいない僕は、いつも一人でここに来て、本を読むのが楽しみだった。
どんな不安を抱えて、心細くなったときでも、僕はいつもこの場所に足を運んだ。
不思議に人が全然通らない、この場所で、僕は誰にも邪魔されず、読書することで、自分が物語の中に溶け込むような、そんな感覚になるのが大好きだった。すべてを忘れて、ただその世界と一体化するのは気持ちがよかった。
でも、そんな僕の場所には、先客がいた。
「あの、貴方は誰ですか?もしかして、以前、お会いしましたか?」
彼女が顔をのぞき込むように僕を見た。
「い、いや、初見だよ」
「―――よかった」
何がよかったのだろうか、僕は考えた。
そして、僕は彼女の事を考えていた。すごく清楚な感じの彼女に見とれてしまっていた。
彼女は一体誰なのだろうか。
いつもここに来るのだろうか。でも僕は彼女と初めて会った。そっと彼女を横目で見る。可愛らしいワンピースを着ていた。
「秋穂 夕(あきほ ゆう)と言います」
彼女は僕に向きなおって優しい笑みで名乗った。僕は、そんな彼女に釘付けだった。
よく考えれば、僕と夕は似た者同士だったのかも知れない。
体が弱くて、休みがちで、文化系で本が大好きだった。そんなところがお互いに似ていて、だから、繋がったのかもしれない。
あれから、僕らはよく教会の裏で夕と会い、喋ったり、本を読んだり、そんな風に僕と夕は過ごしていった。
あの時、初めて一緒にいたい人を見つけたんだと思う。僕は、毎日が、とても楽しいって初めて思った。
―――あの日の数分の邂逅に、僕は感謝した。
#3
僕には才能があると思いたかった。
人とは違う何かを持っていて、それで世界の人たちに貢献できて、僕は世界中の人から尊敬される人間になる。そんな空想的なことを、考えていた。
高校三年の夏、僕は現実を見た。
特別な何かなんて自分にはなくて、ただ、自分がぼんやりとしか見えなくて、僕は夢から覚めた。普通に大学に行って、卒業して就職して、普通に恋愛して結婚して家庭ができて、いつの間にか老人になって退職して、年金をもらい、静かに暮し、そして静かに死ぬ。それが現実で、今の僕の未来へと敷かれたレールで、僕はその上を拒むことなく歩き続ける。
そういう現実を、目の前の進路希望調査は語っていた気がして、そのたった一枚の紙の存在が、大きくて重くて、あの時の空想的な夢は、やはり空想的だってことを僕に示しつけていた。
その日の帰り、僕は教会裏に行った。こんな気持ちになったときは、その場所で本を読むことで忘れていた。でもその日、そこにある、只、一つのベンチには一人の少女が座っていた。
「あの、貴方は誰ですか?もしかして、以前、お会いしましたか?」
彼女が顔をのぞき込むように僕を見た。
「い、いや、初見だよ」
「―――よかった」
彼女は麦畑を見渡した。つられて僕も麦畑をみてしまう。何もない麦畑が、今の僕みたいで、すこし切なくなった。
「秋穂 夕と言います」
そういって見せた彼女の笑みは僕の心を貫いた。けれども、これ以上、僕はここにいてはいけない気がした。それは、理屈をなくして訴えかけてくる僕の何かだった。
「あ、それじゃ、僕はこれで…」
「あ、まだ名前、聞いてません」
「高橋 光(たかはし こう)」
「さよならです。高橋さん」
そうやって僕らは邂逅した。
#4
その日も僕は、教会の裏に足を運んだ。
もしかしたら、昨日の女の子に会えるかも知れない。そんな期待をしていた。
―――秋穂、夕。
名前を胸中で呟くたびに、何とも言えない感覚がした。
それが僕にとって二度目の恋であることは、自分でもわかっていた。
たとえ、一目ぼれで、昨日初めて会って、昨日の女の子が僕のことを何とも思っていなくても、それは仕方のないことだった。
けれど、その反面、僕はもう恋なんてしないと、誓っていたはずだった。
だから、この恋は不覚だった。してはいけないものだった。
恋なんて報われるはずがないのだから。
○○○
高校一年の時、初恋をした。
一般からしたら、遅いのかもしれない。もしかしたら、それよりずっと前に、初恋なんてしているのかもしれない。
けれど、この時、初めて"恋"という感情に芽生えたんだと思う。
その時の僕は、まだ、本ばかり読む物静かな感じでも、友達がいなかった訳でもなかった。
安定した仲間と、それなりのノリをもった、普通の高校生だった。
――そんなとき、僕は初恋をした。
その時も一目ぼれだった。近くの有名な神社の娘だった。
小柄の、かわいらしい少女だ。
彼女を追いかけるように、同じ文芸部に入った。廃部になりかけの文芸部には三年生一人しか部員はいなく、その優一の部長も、受験があるらしく、ろくに顔を出さなかった。
文芸部に入ろうと思ったモノ好きは居る訳もなく、毎日、僕と彼女は放課後、部室で本を読みふけっていた。
ある日、僕は彼女に想いを伝えた。そして、あまりにもあっさりと、僕たちは彼氏彼女になった。
「海って、世界中と繋がっているんだよね。うらやましい。私も、そうやってたくさんの人と繋がって、必要とされる人間になりたい。」
彼女はいつもこういった。
僕は、それを軽い意味として、ただ相槌を打った。そうして、彼女を抱きしめた。
小柄で細い彼女は、力いっぱい抱きしめると壊れてしまいそうだった。ウサギや猫を抱いてあげる感じで、僕はそっと彼女を包みこんだ。僕はその時、彼女にキスをしようと思った。
体を離して、彼女に向きなおった。僕の顔が、彼女に近づいていく。
「ダメ…」
彼女が呟いた。僕は慌てて顔を離して距離をとった。
赤面しながら、その場をお互いに誤魔化した。
夏休みから、彼女は僕を避けるようになった。
僕は戸惑った。
「どうして、僕を避けてるの?」
僕は彼女に迫った。けれど、彼女は首を横に振って僕から逃げるのだった。
取り残された僕は、泣きそうになった。けれど、意地で歯をくいしばって泣かなかった。
まずは彼女が僕を避けている理由を訊こう、と前向きに考えた。
夏休みの中盤、僕は再び、彼女に迫った。
「別に、避けてなんか、ない」
彼女はそう言ったが、眼は僕を向いていなかった。
「嘘だ……」
「嘘じゃ、ないわ」
「じゃぁ、どうして僕から逃げるんだ?言いたくはないけど、いい雰囲気になったとき、いつも誤魔化すのはどうして?」
「それは……」
夕日が二人を照らした。
遠くから見ていたら、こんな話をしていなければ、かなり幻想的で、最高の光景だったのだろう。そうならなかったのが、残念で、悔しかった。
「私、もうこれ以上、高橋君とは付き合えない…」
静かな声でそう切り出した声は僕の頭の中を何度も駆け巡った。
「ど、どうしてだよ…。僕が、嫌いになったのか…?」
頭を強く打った感覚に襲われ、目眩がした。
急すぎる別れ話に、度惑いとショックを隠せなかった。僕は口を半開きにしたまま、理解に苦しんだ。
彼女は首を振って、今でも好きよ、と言った。そして、俯いた。
「―――私には、許嫁が、いるから…」
世界が歪んだ。
許嫁?今時、そんなもんが残っているのか?
有名の神社の娘だからか?いくらなんでも、許嫁は、ないだろ…?
許嫁という本の世界でしか見たことがない言葉に僕は唇をかんだ。少し、血の味がする。
「家のしきたりだから。分家の方から選んで、結婚するの。昔から、そうしてきたから」
そういった、彼女は少し、泣いていた風に見えた。逆光で分からなかったけれど、僕の勘違いかもしれないけれど、眼に、涙を浮かべていたように見えた。
僕は『しきたり』を呪った。呪って呪って呪って呪って呪って呪って、恨んだ。
高校生の僕には、その『しきたり』という言葉が、大きすぎた。
どうすることも、できない。
そんな僕の非力さに、今度は自分を呪った。
―――彼女といたい。
―――けれど、許されない。
彼女と付き合ってから、手は握ったが、キスは一度もなかった。
いつも彼女が、その場を制して、ブレーキをかけた。
そうやって僕との距離に一線を引いていたのかも知れない。
僕一人だけが、心踊っていたのかもしれない。彼女は、はじめから分かっていて僕との交際を受け入れたとしたら、彼女は苦しんでいたのかもしれない。
『好き』という気持ちと『しきたり』という呪縛の中で彼女は苦しんだはずだった。
どちらかを選ぶかは、決まっていた。
「だったら…、だったらどうして僕と、付き合ったり、したの?」
「反抗して、みたかった。親に。いつも私は親の言うとおり勉強して、進学して、しきたりを守ってきた。けど、そうしてるうちに自分が虚しくなって、一度でいいから、親に、反抗したかった…」
そう語った彼女を僕は直視できなかった。
拳を強く握った。怒りと、苦しさで体が震えていた。爆発してしまいそうだった。
それをギリギリのところで抑えているのは、彼女の前だからという、ちょっとした意地だった。
「やっぱり、僕のことは、別に…」
「それは、違う…。初めは、誰でもよかったけど、けど、今は、高橋君にしてよかったと思ってる。私は高橋君が好き。それは変わらない。けど…」
数秒間の沈黙が流れた。
とても長く感じられた。立っているのに精いっぱいな僕にとって、その時間の沈黙は僕には重かった。
「これ以上、すすんだら、もう、戻れなくなる…から。私は、これでも、水島家の一人娘だから…」
最後にそう残して、彼女は僕の前から去った。
僕の初恋も終止符が打たれた。僕は、恋は、辛いと知ってしまった。
数日は立ち直れなかった。
彼女の顔を見るのも怖かった。見たら、自分が壊れてしまいそうで、必死に 布団の中で彼女の存在を消そうと努力した。
彼女―――水島は確実な一歩を踏み出したんだ。僕と別れることで、水島の名を守ったのだ。多分、勇気のいることだっただろう。けれども、彼女はちゃんと勇気を出した。
彼女の勇気を犠牲にしてはいけない、そう思った。
―――僕は、恋という感情を捨てて、彼女に笑顔を向けることができる人間になろうと、努力した。
―――僕は、もう恋はしないと、誓った。
#5
世界はどこまでも灰色だった。
外気は錆びた鉄の匂いがして、息苦しい。
外套はチカチカ光って、僕を照らす。入ってくる光さえも、やはり、灰色だった。
キーボードをたたく手をやめ、窓から外を見た。
灰色な世界にやはり終わりなんてなく、僕はため息交じりに一息ついた。
○○○
「や、やぁ…」
僕は彼女に声をかけた。彼女は僕を物珍しそうな眼で数秒見つめたのち、こんにちは、とだけ答えた。
「高橋、さん、ですか?」
「え?」
「昨日も、ここでお会いしましたよね」
麦が揺れていた。多分、風がすこし、吹いたのだと思う。
僕はそんな麦を見ながら、そうだね、と答えた。
彼女も麦を見て、しばらく、カラスが鳴くのを聞きながら、ただ揺れる麦を、僕たちは見ていた。それは、傍からみたら、おかしな光景だったと思う。
ただ、一通りの少ないこの場所で、僕らを見て不思議がる人なんて、居なかった。
「私、名乗りましたか?」
不意に彼女がそんなことを訊いた。なぜ、そんなことを訊いたのか、大しては気には留めなかったけれど、それでも僕はただ、不思議に思った。
あの日、初めて僕らが邂逅した日、僕よりも先に、彼女は笑顔で名乗ったはずだ。
そんな光景を僕は忘れることができないだろう。それが、彼女の、秋穂夕の当り前の名乗り方だったとしても、僕には印象的だったのだ。
人間、忘れることだってあるだろう。
けれど、昨日の今日で自分が名乗った相手を忘れるものだろうか?それとも、ただ単に、彼女にとって僕はとても小さな、それこそ商店街ですれ違う見知らぬおばさん程度の気にも留めない小さな存在だったのだろうか?
そうでないことを僕は願いたい。
「ここには、よく、来るの?」
「はい。この場所って素敵ですよね。私、好きです」
そう言って彼女は微笑んだ。
僕はそんな彼女に見とれてしまう。つい、口元がにやけてしまいそうで気を入れなおす。
夕焼け空もだんだん橙色から薄い紫色に変わりつつあった。僕の感じる時間の感覚とは全然違う速さで時間は進んでいたようだった。
「家、この辺りなのかな?」
「え?」
「いや、家。ここから近いのかと思って…」
彼女は黙りこんだ。しまった、地雷踏んだかな?なんて僕は考えてしまう。僕は身構えた。
「家は、かなり遠いです…」
「そう…。じゃぁ、暗くなるし、送ろうか?」
「そうじゃないくて、その、家は、ここから歩いて行けない距離、と言いますか…」
「え?」
今度は僕が黙り込む番だった。どういうことか、わからなかった。
家がここからかなり遠い。けれども、彼女はよくここに来る。いや、実際、邂逅から二日しか経っていないし、彼女にも何か抒情があるのだろう、そう思った。
「明日も、ここへ来る?」
僕は尋ねてみた。何も考えないことにしよう。そう思った。進路希望調査という紙一枚で現実を知って、世の中と自分とを考えて、これからのことを考えて、他に考えることは山ほどあった。
「はい」
だから、せめて、ここにいる間だけは何も考えないでいようと思った。
わがままかも知れない。
でも、それでもいいと僕は思ったのだ。
「じゃぁ、また、明日ね」
「え、あ、はい。また、明日」
片手をあげた僕に彼女は満面の笑みで答えてくれた喜びを、僕は噛みしめながら、僕は踵を返した。
#6
私にとって、今日も世界は灰色でした。
雲間からかすかな光が差し込んだと思ったら、その光はすぐに別の雲に覆われて消えてしまいます。
重い体を引きずりながら、私は、またこの場所にやってきました。
どうしてでしょうか?
どうして私はこの場所に来るのでしょうか?
あの日から、私の時間は止まったはずなのに、私は何を期待しているのでしょうか?
○○○
私には、記憶が、ありません。
どうして記憶がないのかもわかりません。
私の記憶を支えているのは、あの日から今日までの、日記帳。
私の記憶は24時間で、すべて消えてしまう。
昨日のことも一昨日のことも、一年前のことも十年前のことも、私にはあって存在しない時間なのです。
もうひとつ。
私は17歳で、死にます。
それは変えることができないことだそうです。
原因不明の病気で、この世界で何人もの研究者がその実態を研究しているのですが、未だにその実態は分かっていなくて、ただ、わかっているのは、その病気にかかった人は、だんだん記憶をなくして、そして十七歳の誕生日を迎えた瞬間に死ぬ、ということ。
かつての私の兄がそうでした。
兄は、中学生に上がったころから記憶障害が起き、母を忘れ、父を忘れ、友を忘れ、先生を忘れ、そしてあれだけ可愛がってくれていた私をも忘れて、十七歳の誕生日に、死にました。
16歳の私には、もうその症状が出ているんでしょう。
いずれは全てを忘れるのでしょう。
自分の名も、文字も、言葉でさえも……。
○○○
「やぁ。」
少年――高橋さんが私に声をかけてきた。
「こんにちは。」
私は笑顔で返した。
また会えた、そんなうれしさがこみ上げた。
私は恋をしているのかなぁ、そう思うと笑ってしまいます。
だって、私には、もう希望なんてないのだから。
好きになったら、きっと、不幸だから。
#7
今でも時々、僕は思いだす。
僕たちがまだ、普通に付き合っていた頃のことを、だ。
夕といるだけで、何もかもが幸せのように思えて仕方がなかった。
普通に話して、買い物して、手をつないで、笑いあって、お互いの眼を見て、キスをして。
そんな、"当たり前のこと"を僕たちは何よりも大切にしていた。
○○○
「大丈夫、だから」
夕は最後にこう言った。
夕が僕を覚えていた最後の日、夕は僕に向かって、そういったのだ。
彼女は怖がっていたに違いない。
頭の中のものを端から順にブラックボックスのようなもので覆われて、失っていく、そんな一瞬一瞬が、すごく怖かったに違いない。
僕にはわからないけど、夕の苦しさを分かち合いたかって、一緒に泣いてあげたかったけど、僕は無力で、才能なんかなくて、ただ、見ていることしかできなくて、そんな自分が嫌になって何度も何度も何度も手首にカッターの刃を押し当てて。
夕の苦しみを物理的に味わってみたくて、痛くて、でもそれが嬉しくて…。
○○○
最後、何も覚えていない夕は、あやふやな日本語で僕に言った。
「海って、世界中と繋がっているんだよね。うらやましい。私も、そうやってたくさんの人と繋がって、必要とされる人間になりたい。」
僕の頭に水島のことが蘇った瞬間だった。彼女が言ったことの意味深さを僕はその時痛感した。
泣いて、泣いて、泣きじゃくって。
水島の時も、夕の時も、僕はいったい、何なんだ!
高校生なのにみっともないなんて微塵も感じずに、ただ、夕の前で、涙を流した。
その時からだ。
世界が灰色に見えたのは。
僕が、物語を綴るようになったのは。
○○○
夕の病状がひどくなり、夕は遠くの病院へと言ってしまった。
最後に僕は夕の付き添いの方にお願いをした。
「もし、夕が元気になったとき、僕に教えてください!ただ一言、僕に教えてください!僕、いつまでも、待ってますから!」
病室で叫んだ。
涙を、流しながら。
付き添いの方は、真剣な顔で頷いてくれた。
だから、僕は待つんだ。
一通の報告を。
―――これが、僕たちの邂逅の結末。
―――僕たちが、邂逅した証。
(finish...)
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
-
-

- 鉄道
- 【2025/10/30】小田急江ノ島線 3275…
- (2025-11-21 04:22:19)
-
-
-

- どんな写真を撮ってるの??(*^-^*)
- 秋の東京散歩5(北とぴあから隅田川…
- (2025-11-21 06:48:51)
-
© Rakuten Group, Inc.