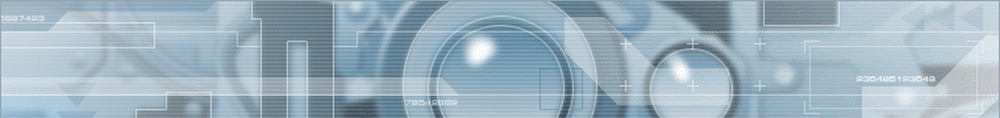第4話
魔導戦騎 リッタールベリア第4話『怒りに燃える 蒼 い炎』
―1―
「うー、いたぁー・・・・・・」
「打ち身で済んだだけマシだろ?」
「そうだけどさぁ・・・・・・リッタールベリアは?」
「外傷は酷いが、内部はそこまででも無いな。回復までそうはかからないだろ」
「そっか」
燐の負傷は魔導機の損傷に比べ軽く、腕や足に包帯は巻いているものの、数か所の軽傷だけで済んでいた。
それも、魔導機操縦時に纏う鎧の恩恵である。
二人は今、次の街へと向かう馬車の中にいた。
「・・・・・・馬車?」
「どうした?今更」
「いや、私の知ってる馬と違うなぁ、と思って・・・・・・」
「そうなのか?」
「うん、まず、私の知ってる馬に角は生えて無い」
「・・・・弱そうだな」
「まぁ、戦わないからね」
燐が疑問を持った客車を引いている動物、馬と呼ばれているが、燐の思う馬とは少々違いがあり、両耳の横から二本の角が生えていた。牛や鹿と馬を足して2で割ったような印象である。
「鹿馬・・・・馬・・・・鹿・・・・・・」
「・・・・お前、しょうもない事考えてるだろ」
「え?!い、いや、ベツニナニモ?」
「・・・・ぜって―考えてたな」
馬車に揺られる事数時間、ようやく目的の街『コルテーゼ』に着いた。
レンガ造りの大きな建物が並ぶ比較的大きな街である。
「おー、随分とにぎやかな所だねぇ」
「ここらじゃ一番活気のある街だからな」
「ほぉーほほーぅ」
「落ちつきねぇな、お前・・・・・・」
きょろきょろ、と燐は辺りをせわしなく見渡すが、実質見えているのは賑やかさだけで、人の流れは全くと言って良いほど見えていなかった。
「お?あっちの方に良い感じのお店が―――おおっ?!」
「あっ・・・・・・」
前を見ていなかった燐は、角から出て来た人影とぶつかってしまった。
「ご、ごめん!!大丈夫?」
「あ、うん、平気・・・・そっちは?」
ぶつかった人影は燐と背も年齢もさほど変わらないくらいの少女だった。
肩より長い髪をひとくくりにして左から前に流している。
見た目の年齢より少し大人びたような、美少女、と言う言葉が似合うような少女である。
「私は全然」
「そう、こっちこそごめん」
「いや、悪いのは私だし・・・・」
「そうそう、前を全く見て無かったこいつが悪いんだよ、な?」
「その通りなんだけど、あんたに言われると納得いかない・・・・」
「なんでだよ!!」
「えー、だってー」
「・・・・・・・・ふふっ」
「ほら、紅男のせいで笑われたー」
「俺のせいか?!」
「ごめん、仲が良さそうだったからつい・・・・」
「そういえば君、名前は・・・・」
「ライカー?」
燐が少女に名前を聞こうとしたのとほぼ同時に、名前を呼ぶ声が聞こえた。声の主はこちらに近づいてくるようで、おそらく、この少女に向けられたものだろう。
その声に、少女が答える。
「イリス」
「時間になっても来ないから心配したよ・・・・」
「ごめん、急いでたらちょっとこの人達とぶつかっちゃって」
「あー・・・・ごめんなさい」
「いや、別にそんな謝ってもらう程の事じゃ・・・・」
「そうだよ、私も不注意だったんだし・・・・」
「そう?じゃぁ、おあいこって事で!」
「切り替え早いな・・・・」
「あははー」
「二人は、ここの人?」
「いや、俺達は旅の途中・・・・みたいなもんだな。」
「そっちは?」
「私達もそんな感じ」
「そうか、じゃあ道案内は望めないか・・・・・・」
「ごめんね、えっと・・・・」
「あっ・・・・私はライカ。こっちは精霊の」
「イリスだ」
「私は燐。んで、こっちは紅男」
「雑な紹介すんじゃねぇ!!ヴェニティリオ・ブレンネアだ」
「ライカは急ぎの旅?」
「? そこまで急ぎ、って言うわけではないけど・・・・」
「じゃあさ、一緒にこの街回らない?」
「私は別に構わないけど・・・・・・ね、イリス?」
「あぁ」
「おい、リン!!俺達の方は・・・・・・」
「まぁまぁ、情報収集も兼ねて旅先での交流を、ね?」
「ったく・・・・・・」
こうして、燐とライカ、ヴェニットとイリスの知らない街探検は始まった。
―2―
「ほら、ライカ。あっちのお店行ってみない?」
「・・・・さっきアイス食べたよね?」
「えー?じゃあ、あっち?」
「うーん・・・・あっち?」
燐とライカの二人は数分程で打ち解け、街を歩き回って既にかれこれ数時間が経過していた。
二人の少し後を精霊二人がついていた。
「悪い、なんか無理矢理付き合わせてしまったようで」
「別に構わねぇよ。リンも久々に同年代と絡めて楽しいんだろ」
「それはライカにも言えるかもしれないな」
「・・・・ま、たまには悪かねぇな、こういうのも」
「・・・・そうだな」
「? 紅男ー?イリス?何してんの?」
「・・・・置いてっちゃうよ?」
「あぁ、すまない。今行く」
「へいへい」
「気の無い返事だなぁ・・・・ん?」
「・・・・ボール?」
燐の足元にボールが転がって来た。
燐が周りを見回していると、広場の方から小さな女の子が走ってくる。
「これ、君の?」
「うん。ありがとう、お姉ちゃん!!」
「はっはっは、良いって事よ」
「一人で遊んでたの?」
「んーん、友達と一緒ー。ほら、あそこ」
女の子が指さした方に視線を移すと、小さな影があった。
その友達であろう精霊が燐達に近づいてくる。
「アーリィー?ボールはー?」
「あ、ネロ。このお姉ちゃん達が拾ってくれたんだよ」
「二人は、契約してるの?」
「んー、まだー」
「精霊と契約するには人間が10才にならないと契約出来ねぇんだよ」
「へー」
「へぇって・・・・リン、知らなかったの?」
「あ、あははー」
「でも、ずっと一緒だもんねー?」
「ねー?」
「じゃあ、私達と一緒だ。ね、イリス?」
「あぁ、私達ももう十年以上の付き合いだからな」
「そうなんだ・・・・二人で遊んでたの?」
「うん!」
「よし、じゃあお姉ちゃんが一緒に遊んであげよう!!」
「ホント?!」
「よし、行くぞー」
「「おー」」
「ほら、ライカも」
「え?えぇっ?!」
「あいつ・・・・完璧に目的忘れてるだろ・・・・」
「目的?そういえばお前達は・・・・」
「ほーらっ、紅男とイリスも!!」
「だぁーっ!!周りの都合全く考えないだろお前!!」
「おい・・・・まぁ、いいか・・・・」
ヴェニットとイリスも若干苦笑を浮かべながら彼女等との遊びに加わった。
燐、ヴェニット、ライカ、イリス、アーリィ、ネロ、総勢6人で広場の一角で、ボール遊びに限らず、色々な遊びを繰り広げた。
―3―
「ふぃー、久々に良く遊んだー!!」
「私も・・・久しぶり・・・・・・」
「楽しかったー、ありがと、お姉ちゃん達!!」
「紅男とイリスも、ありがとー」
「ベニ・・・・あ、あぁ。礼には及ばねぇよ」
「ヴェニティリオ、笑顔が引きつってるぞ」
「うっせ」
出合ってから数時間、遊び倒した彼女等は疲弊したように座り込んでいた。
気付けば既に陽も落ちかけており、空がオレンジ色に染まりかけていた。
「あ・・・・そろそろ帰らなきゃ・・・・」
「あ、じゃあ家まで送っていくよ?」
「お前、そろそろ・・・・」
「まぁまぁ・・・・ほら、行こ?ライカ達は?」
「私達も一緒に・・・・良いよね?イリス」
「あぁ」
「・・・・・・まぁ、今日くらいは良いか」
「なんだかんだ、お前も甘いな、ヴェニティリオ」
「なっ・・・・ンな事無ぇよ・・・・」
「どうだかな?」
「・・・・・・フン」
6人は連れ立ってアーリィの家に向かって歩いていた。
夕焼けに染まるレンガの道を進みながら、燐はある物に気付いた。
「・・・・ネロ、その首から下げてるの、どうしたの?」
「そういや、最初は着けて無かったな」
ネロの首から小さな黒い石の付いたネックレスがかかっていた。
幼い印象のある彼女には少々不釣り合いであるように見えるが、本人はとてもうれしそうである。
「これ?えへへー、アーリィからさっき貰ったの!!」
「へぇ・・・・綺麗だね。宝石?」
「んー、分かんない。さっきね、貰ったの」
「・・・・・・貰った?」
「うん、『友達の精霊にあげれば喜ぶよ』って」
その一言に、イリスが怪訝な顔をした。疑問をそのまま、アーリィに問う。
「・・・・・・誰に?」
「んー・・・・秘密!!」
「秘密って・・・・・・」
イリスの様子を見て、燐も少なからず不安を抱き始めた。
「おじちゃんとの約束なんだもん。秘密だって。」
「・・・・・・おじちゃん?」
「あっ・・・・・・」
「アーリィ、そいつはどんな・・・・」
「う・・・・ぁっ・・・・」
「!? ネロ?!どうしたの?!」
「イリス、これは・・・・・・」
「あぁ・・・・ネロ、そのネックレスを外すせ!!」
「え?!何?!どう言う事?!」
「まさか・・・・・・」
「ネロ?!ネロ?!どうしたの?!苦しいの?!」
「あっ・・・・うぅ・・・・ぐ・・・・ん・・・・」
ネロの着けているネックレスから黒い光が発せられ、彼女の苦しみ方がどんどん酷くなっていく。
「が・・・・ぁ・・・・あ・・・・あぁぁぁぁぁぁぁッ!!」
「まずい・・・・・リン、アーリィ、離れるぞ、早く!!」
「う、うん!!・・・・アーリィ、行くよ!!」
「やぁっ!!ネロが・・・・ネロがっ・・・・」
「アーリィ、いい加減にしろ!!ネロはもう・・・・」
「いやぁぁぁぁぁぁっ!!ネロッ・・・・・・ネロぉぉぉぉぉぉっ!!」
「が・・・・ア・・・・A・・・・ぐァァァァァァァァァァァッ!!」
黒い光が大きくなるにつれ、ネロの身体が膨張し、巨大化してゆく。
それは加速度的に変化が大きくなり、原形を失うのに時間はかからなかった。
「ネロ・・・・ネロぉ・・・・・・」
「そんな・・・・こんなことって・・・・・・」
かつてネロだったモノは既に30m程にまで巨大化し、その身を黒い鎧で覆っていた。
その手と脚には朱い爪、その口には朱い牙。紛れもない、魔獣の、それである。
<ガゥァァァァァァァァァァァッ!!>
そこに、ネロの面影は無く、破壊の狂獣としての姿だった。
その脚で大地を砕き、その爪でレンガを切り裂く。
「あのネックレスについてた石が・・・・黒晶だったんだ・・・・」
「えっ・・・・・・」
「ン・・・・のバカッ!!」
「わたしの・・・・せいなの・・・・・・?」
「え?あっ・・・・・・」
「わたしが・・・・あのネックレス・・・・ネロに・・・・あげた・・・・から・・・・」
「いや、それは・・・・・・」
「アーリィ、その話は後だ。まずはここから逃げる。リンも、良いな?」
「・・・・いや、ライカ達だけで逃げて」
「・・・・・・え?」
「ここは、私が何とかする。だから、その間に」
「リン・・・・何言って・・・・・・」
「良いから早く!!紅男、行くよ!!」
「あぁ!!さっさと逃げろよ?お前達!!」
「「炎騎召喚!!」」
「・・・・・・ッ?!」
燐とヴェニットはライカ達の前で召喚の陣を発動させる。
ライカ達がアーリィを連れて逃げながら後ろを振り返ると、そこには火柱が立ちあがっていた。
そして、その中から真紅の巨体が姿を現す。
「炎の魔導機、リッタールベリア・・・・見参・・・・・・ッ!!」
―4―
『クソッ・・・・・こんな近くにいながら・・・・・・』
「・・・・ネロ・・・・・・」
かつてネロだった魔獣と対峙しながら、魔導機の中で二人が愚痴る。
自分達の不甲斐なさを噛みしめながら、その憤りの行き場を探すように。
しかし、その時間を十分にくれるような相手ではない。目の前にいるのは紛れもなく、魔獣である。
<ガァゥ・・・・ゥグォァァァァァァァァッ!!>
「うわぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ?!」
『畜生・・・・こいつ・・・・今までの魔獣より・・・・』
「強い・・・・・・」
<ガゥォォォォォォォォッ!!>
「っ・・・・ぁあああああっ?!」
魔獣から振り下ろされる太い腕と鋭い爪を受け、リッタールベリアに傷が生まれる
左腕に大きな損傷が生まれ、胸部装甲にヒビが入る。
にもかかわらず、燐は魔獣への反撃を躊躇っていた。
『リン、お前・・・・何してやがる!!』
「だって・・・・あれは・・・・ネロなんだよ?!それを・・・・」
『違う!!あれは魔獣だ!!』
「違わないよ!!だって、さっきまで一緒に遊んで、一緒に笑って・・・・」
『それでも!!』
「・・・・・・紅男・・・・?」
燐の想いを諭すようにヴェニットは叫ぶ。その声は僅かに震え、悔しさが滲み出ていた。それを噛み殺し、ヴェニットは続ける。燐と、自分に、言い聞かせるように。
『それでも・・・・あれはもう・・・・魔獣なんだ・・・・・・ッ!!』
「紅男・・・・・・・」
『もしこのままあいつが暴れ続けて、アーリィを傷つけたとして・・・・そんな事になったらあいつはきっと悲しむだろ・・・・そうじゃなくても、何人もの被害を出したらきっと自分のせいだって、余計にアーリィが苦しむ・・・・そんな事、あいつは望んじゃいねぇ・・・・』
「・・・・・・ごめん」
『・・・・・・なに謝ってんだ?俺達のやる事・・・・分かってんだろ?』
「・・・・・・・・うん、やろう。ネロの為にも・・・・・・」
膝をついたリッタールベリアは立ちあがり、その手に剣を構える。
魔導機の瞳に既に迷いの影は、無い。
『左腕の損傷もほっとけるレベルじゃねぇな・・・・そんなに時間はかけられねぇぞ』
「また無茶を言ってくれるね・・・・」
『誰のせいだと思ってんだ?』
「ごめん!!」
『良いから、さっさと決着つけるぞ!!』
「応ッ!!」
剣に炎を纏わせてリッタールベリアは魔獣に向かって走り出す。
―5―
「ハァ・・・・ハァ・・・・・・紅男、左腕は・・・・」
『自分で動かしてりゃ分かるだろ?』
「・・・・やっぱり、完全に動かないか・・・・・・」
魔獣と対峙し、攻防を続けて数十分が経ち、魔獣へのダメージもさることながら、リッタールベリアへのダメージも相当な物になっていた。
魔獣の鎧は肩や胸の装甲を砕かれ、左足からは紫色の血液が流れている。
リッタールベリアは左腕は動かない状態まで破壊され、脚部の装甲にも大きなヒビが入っていた。
「どうする・・・・?片腕だけで・・・・やれるかな・・・・・・」
『やんなきゃなんねぇンだろ?腕が無けりゃ・・・・』
「どんな手段を使ってでも・・・・・・ねッ!!」
魔獣の脚元から炎の鎖が伸びて魔獣の四肢を絡め取る。
暴れるもその炎は断たれる事無く動きを抑え、体表を焼いて行く。
鎧が砕けた部分が焼かれ、魔獣は苦悶の叫びを挙げる。
<グゥゥゥゥゥォォオォォォォ・・・・・・>
『駆けろ炎龍、紅蓮の炎で焼き尽くせッ!!』
剣を横に一閃すると、纏っていた炎が魔獣に向かって飛んで行く。
炎の龍は魔獣を包み、焼き焦がす。
魔獣が怯んだその隙を逃さず、薙いだ剣を魔獣に突き刺す――
「よし、これで・・・・・・」
「ふむ、なかなかやるな、リン」
「?!」
直前に、突然呼ばれた名前に、燐は戸惑い、動きを止めてしまう。
リッタールベリアの瞳が周りを見回すと、声の主はすぐに見つかった。
街の時計台の上に、白い影。
『やっぱりテメェの仕業か・・・・・・アクナイト・グリラシオォォォッ!!』
「いやぁ、この間は失礼した。まさか君が魔導機の装主になっているなんて夢にも思わなかったのでね」
「・・・・・・は?」
「黒晶を渡した少女と精霊を観察していたら君達がその魔導機を呼び出す所を見かけてね、驚いたよ。まさか君が、異界の住人である君が魔導機を呼び出せるなんてね」
「・・・・やっぱりあんたがアーリィに・・・・・・」
「無礼を詫びよう。君が装主だったと知っていたらこの間のような仕打ちはしなかったよ。どうだい?私の研究に協力してくれないか?」
「・・・・・・研究?」
「あぁ、異界の住人である君が精霊と契約出来るなんて、そんな特殊なケース、研究せずにはいられないだろう?」
「・・・・・・オーケイ、よーく分かった・・・・・・」
「ご理解いただけたようでなによりだ、リン」
「あんたが、どうしようもないクソ野郎だって事がね!!」
『そうやってネロの事も実験動物程度にしか見て無かったってワケだ!!』
「いやぁ、彼女は実に良い実験結果を出してくれたよ。『人との繋がり』の強さが『魔獣の強さ』に影響を与える、と言う研究の一例を、ね」
「―――――ッ」
『テメェの都合で・・・・他人の気持ちを弄びやがって・・・・・・』
「あんたとは・・・・どうあったって分かり合う気は―――無いッ!!」
「そうか、それは残念だ・・・・・・・・貴重な研究材料を失うのは非常に心苦しいが・・・・・・」
そう言いながら、アクナイトは白衣のポケットから箱を取り出し、その中から黒く艶めく水晶をとりだし、魔獣に向かって投げた。
「ではもう一つ、実験をしてこの場を去るとしよう・・・・・・」
『?! リベライト晶石を・・・・魔獣に・・・・・・?!』
「一体何を・・・・・・・・?!」
<グ・・・・ヲ、ヲヲヲヲヲォォォォォッ!?>
投げられたリベライト晶石が魔獣の身体に取り込まれるや否や、一際大きな魔獣の咆哮が轟いた。
魔獣は叫びながらその身体を変化させてゆく。
体表から黒い水晶が生え、黒い鎧の一部が結晶化する。刺々しい印象のあった魔獣が、より禍々しい姿へと変貌してゆく。
「魔獣は精霊の魔力許容量を越えた姿、ならば、そこにさらなる魔力を加えてやれば・・・・」
「魔獣の・・・・・・」
『強化・・・・だと・・・・・・』
「強化された魔獣、か。ふむ、その名前、頂こう。仮に強化魔獣とでも名付けようか。いや、未だに前例の無い実験だったのでね、成功して良かったよ」
『アクナイト・・・・テメェ・・・・・・』
「さて、そのボロボロの魔導機で一体どこまで出来るかな・・・・・・?」
<GAGUAAAAAAAAAA!!>
「くぅっ?!」
強化された魔獣の爪がリッタールベリアを襲う。
その一撃は先程までの魔獣のそれとは比べ物になら無いほどの力だった。
手に持っていた剣は砕け、胸部の装甲が大きく抉られた。
『クソッ・・・・・・こいつで・・・・・・ッ!!』
<GUOAAAAAAAAAA!!>
先程魔獣を捉えた炎の鎖を、今度はいともたやすく千切り消す。
「?! 一瞬で?!」
「ふむ、実に良い実験結果が得られそうだ。感謝するよ、リン。あぁ、あと・・・・・・」
アクナイトは口元に笑みを浮かべながらその言葉の続きを告げた。
「彼女に石を渡してくれた、あの少女にも、ね。ハハハッ」
愉快そうに、本当に愉快そうに笑うアクナイトの声。
その笑い声を聞いた燐は完全に―――
「・・・・・・っざっけんな・・・・・・」
「・・・・ん?」
「っざっけんなって言ってんだよ!!このクソ野郎!!」
キレた。
「アーリィは、アーリィは本当にネロの事を大事に思ってて、ネロも同じくらい、アーリィの事を大事に思ってて・・・・・・」
燐は感情の爆発を抑える事もせず、沸き出てくる言葉をそのままぶつけた。
「本当にお互いを大好きで、喜んでくれると思ったから、あんたの言葉を素直に信じて・・・・ネロにプレゼントして・・・・・・」
「その結果がこの状況だ。実に滑稽で愉快じゃないか」
「煩いッ!!あんたのせいで・・・・あんた一人の為に、二人の幸せ壊して・・・・街中の幸せを崩して・・・・その業を、あんなちっちゃい子に背負わせるなんて・・・・」
「だったら、どうすると言うんだね?」
「あんたは、絶ッッッッッッッ対に許さない!!」
『リン・・・・・・?!これは・・・・・・』
燐が想いを全て吐きだした瞬間、リッタールベリアの身体が炎に包まれた。
今までの紅蓮の炎では無い。紅い炎よりなお熱く燃える、蒼い、炎。
「なんだ?これは・・・・・」
アクナイトも予測していなかった事態に、その場に立ち尽くす。
「なに・・・・これ・・・・・・」
『魔力供給量増加・・・・・・回路異常無し・・・・左腕部機能回復?!どう言う事だ?!』
「脚部損傷修復完了・・・・胸部・右腕装甲修復・・・・リッタールベリアが・・・・治っていく・・・・?」
『こんなシステム知らねぇぞ・・・・俺は・・・・・・』
戸惑う燐達に関係なく、魔導機のシステムは次々に復旧していく。
そして、各部の復旧はさらに進み、強化へと移ってゆく。
全ての工程が終わった瞬間、リッタールベリアの右腕が蒼い炎を振り払う。
そこに立つのは、蒼い、巨人。
紅を基調としていた騎士は、今はその身に蒼い鎧を纏っている。
『システムオールグリーン、全パラメータ通常時を遥かに上回ってる・・・・リン、これなら・・・・』
「うん・・・・行けるッ!!」
リッタールベリアが左腕を左に薙ぐと、強化魔獣の足元に蒼い陣が発生した。
その陣から蒼い炎の鎖が伸び、先程のように引きちぎられる事無く、強化魔獣の四肢を捉えた。
「はぁぁぁぁぁぁぁぁっ!!」
リッタールベリアは飛びあがり、両手で剣を上段に構える。
その剣は蒼い炎を纏い、その火力は勢いを増して行った。
「これで・・・・・・」『終わらせるッ!!』
白銀の剣は魔獣を断ち斬り、その身を蒼い炎で焼き尽くした。
<GUAOOOOooooo・・・・・・>
魔獣はその身を焼かれながら、黒い霧となって霧散した。
「・・・・・・・・ネロ・・・・・・」
『・・・・・・・・・・』
燐とヴェニットが眠らせたネロの事を想っていると、おもむろに拍手が聞こえて来た。
その主は見ずとも分かった。
「いやぁ、素晴らしい。素晴らしいよ、リン。やはり、君は研究材料として欲しいよ」
「アクナイト・・・・・・」
「だが、残念ながら今日は引きあげさせてもらうよ。それじゃあ、また会おうじゃないか」
『なっ・・・・待て!!』
ヴェニットの制止も空しく、アクナイトは時計台から飛び降り、その姿を消した。
『クソッ・・・・・・あの野郎・・・・・・』
「・・・・・・いいよ、別に。・・・・・・今は、戻ろ?アーリィ達の所に」
『・・・・・・あぁ』
燐とヴェニットはリッタールベリアから降り、ライカやアーリィの元へと向かった。
―7―
「ネロぉ・・・・ネロぉ・・・・・・ごめん・・・・っ・・・・ごめんね・・・・・・っ」
「・・・・・・・・アーリィ・・・・」
燐達が戻った頃、アーリィはまだ泣きじゃくっていた。たびたび嗚咽を漏らしながらネロへの謝罪の言葉を口にしていた。
戻って来た燐に、ライカが静かに声をかけた。
「リン・・・・装主だったんだね・・・・・・」
「あ、うん・・・・別に隠してた訳じゃなかったんだけど・・・・」
「あ、いや、良いんだけど・・・・・・」
「・・・・くっそ・・・・あの男、次に会ったときには絶対にぶっ飛ばしてやる・・・・・・」
「・・・・・・私が早く気付いていれば・・・・」
「イリスのせいじゃないよ。私にもっと力があれば・・・・・・」
「・・・・俺達に力があったとしても、魔獣になっちまったら元には戻せねェんだ・・・・」
「・・・・・・わたしが・・・・ネロを・・・・あんなふうに・・・・・・ごめん・・・・ごめんね・・・・・・」
「アーリィのせいじゃないって!!アーリィはこれっぽっちも悪くない!!」
「・・・・で・・でもぉ・・・・・・」
「そんなにずっと泣いてたら、ネロだって心配しちゃうよ?」
「・・・・・・・・・・」
子供相手にちょっと卑怯かとも思ったが、アーリィは泣きやもうと頑張っていた。
その姿を見て燐は、アーリィに優しく声をかける。
「・・・・今日はさ、お家に帰ろ?」
「・・・・・・うん」
「ライカ達は・・・・どうする?」
「あ・・・・私達は・・・・」
「・・・・・・すまないが、私達はこれで失礼するよ。」
「あ、宿探すなら一緒に・・・・」
「いや、私達はこのまま街を出るよ。急ぎの用事が出来たのでね」
「・・・・・・そっか、じゃあここでお別れだね」
「そう・・・・だね・・・・」
「・・・・それじゃ、元気でね、ライカ」
「・・・・・・うん、リンも。元気で」
「イリス、お前もな」
「あぁ、お前達の旅が安全な物になるよう、祈っているよ」
「ほら、アーリィも」
「・・・・・・ライカおねえちゃん・・・・イリスおねえちゃん・・・・じゃあね・・・・」
「・・・・うん、じゃあね。」
「それじゃあ、失礼するよ」
そう言って、ライカとイリスは燐達に背を向けて街の出口へと歩いて行った。
その後ろ姿を見送って、燐はアーリィと一緒に彼女の家へと歩みを進めた。
「・・・・・・ねぇ、紅男」
「・・・・・・・・なんだ?」
「魔獣って・・・・精霊、なんだね・・・・・・」
「・・・・何言ってんだ、今更・・・・・・」
アーリィに聞こえないように、そう、呟いた。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-
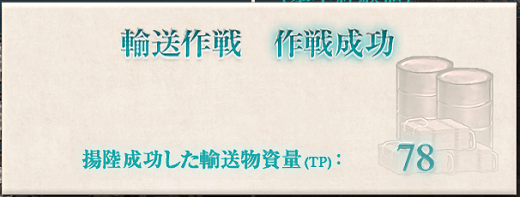
- ゲーム日記
- 基本無料ゲーム「艦隊これくしょん」…
- (2025-11-21 08:59:30)
-
-
-

- 妖怪ウォッチのグッズいろいろ
- 今日もよろしくお願いします。
- (2023-08-09 06:50:06)
-
-
-

- 寺社仏閣巡りましょ♪
- 11月12日のお出かけ その1 飛木稲…
- (2025-11-14 23:40:04)
-
© Rakuten Group, Inc.