神無月
【10月:神無月】

旧暦の名称~神無月(かんなづき、かみなしづき)
日本中の神様が出
雲に集まり、諸国に神様がいなくなるため「神の無い月」から来ている。
逆に神様が集まる出雲では「神有月、神在月(かみありづき)」と言います。
《主な行事》
* 1日:衣替え~
 中国にならい平安時代の宮中で定着した習慣です。「衣更え」「更衣:こうい」とも言います。
中国にならい平安時代の宮中で定着した習慣です。「衣更え」「更衣:こうい」とも言います。
宮中では、旧暦4月1日に冬装束から夏装束に、10月1日に夏装束から冬装束に、調度品も含め改めました。
実際には端午(5月5日)、重陽(9月9日)の節句に行い、季節の節目のお祓(はら)いの意味でもありました。
江戸時代からは、4月1日からは冬の綿入れから袷(あわせ)に、端午の節句(5月5日)からは単
(ひとえ)に着替た「五月更衣」、9月1日からは再び袷を着る「後の更衣」、重陽の節句(9月9
日)からは綿入れを着ると、幕府により衣替えが決められていました。
*「単」は裏地のない着物のことで、帷子(かたびら)ともいいます。
*「袷」は裏地のある着物のことです。
*「綿入れ」は裏地と表地の間に薄く綿を入れて仕立てた着物のことです。
現在制服などは、6月1日と10月1日に衣替えを行うところが多い。
*8日(頃):寒露(かんろ)~
二十四節気の第17。九月節 太陽視黄経 195 度。
『暦便覧』では「陰寒の気に合つて露結び凝らんとすれば也」とある。
本格的な秋になり、冷気が強まり露が凍り始める頃。
*十三夜(栗名月)~

十五夜同様に、古くから旧暦9月13日を「十三夜」といい、「十五夜」と同様に月見をする風習があります。
十五夜に対して十三夜は「後の月(あとのつき、のちのつき)」とも言います。
新暦では10月の半ばから11月の初め頃になります。
十五夜の月見は中国から伝わりましたが、十三夜は日本独特の風習で、食べごろの豆や栗をお供えするので、十五夜
の芋名月に対し「豆名月」、「栗名月」とも言われます。
十五夜の月見をして十三夜の月見をしないのは「片月見」と言い、縁起が悪いとされています。
*第二月曜日:体育の日~
 「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」国民の祝日です。
「スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう」国民の祝日です。
元々は10月の第1土曜日を「スポーツの日」としていましたが、1964年(昭和39年)に開催された東京オリ
ンピックがにちなみ、開会式が行われた10月10日を記念して1966年に国民の祝日「体育の日」となりまし
た。
観測史上10月10日は晴れの確立が高いため、オリンピックの開会式の日に選ばれたと言われています。
2000年(平成12年)からは10月の第2月曜日に移行されました。
*23日頃: 霜降(そうこう)~
二十四節気の第18。九月中。 太陽黄経が210度
『暦便覧』では「露が陰気に結ばれて霜となりて降るゆゑ也」とある。
露が冷えた大気により、霜となりに降りて来る頃。
*31日:ハロウィン ~
 11月1日はキリスト教のすべての聖人を祝う祭日の「万聖節」(日本のお盆のようなもの)で
11月1日はキリスト教のすべての聖人を祝う祭日の「万聖節」(日本のお盆のようなもの)で
す。
ハロウィンはその万聖節の前夜祭です。
アメリカなど外国では、おばけなどの仮装をした子どもたちが、
"Trick or Treat!"(お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうよ!!)と言って、
近所の家を回る習慣があります。
家によっては、あらかじめ小分けにしたお菓子を用意しておき、子供達から"Trick or
Treat!"
と言われたら "Happy Hallween!" と言ってお菓子を渡すそうです。
また、ハロウィンは、古代ケルト民族の先祖の霊を迎える儀式に起源があると言われ、古代ケル
ト暦の10月31日は大晦日にあたり、ご先祖様の霊が帰ってくる日とされていました。
ハロウィンのシンボルのカボチャでできた提灯「ジャック・オ・ランタン」は、先祖の霊が迷わ
ずに帰るための目印と言われます。
-
-
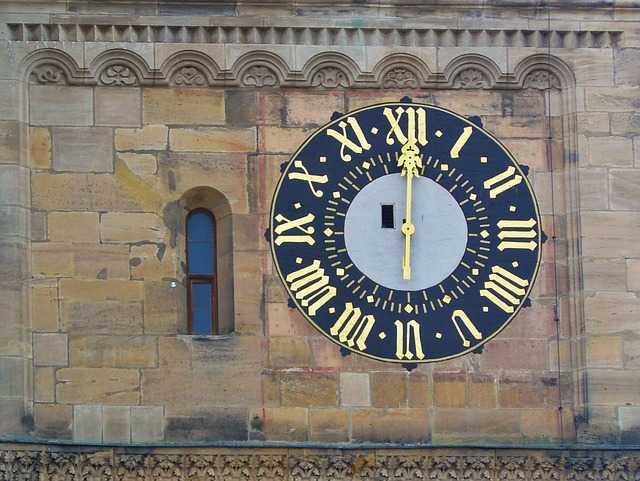
- 風水について
- フライングスター(玄空飛星派)風水…
- (2025-11-10 18:05:38)
-
-
-

- 運気をアップするには?
- マスクパワーガードの出番です!東京…
- (2025-11-18 23:38:54)
-
-
-

- 私なりのインテリア/節約/収納術
- 今年仲間入りしたクリスマス雑貨☆
- (2025-11-19 10:25:02)
-


