2011年04月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-
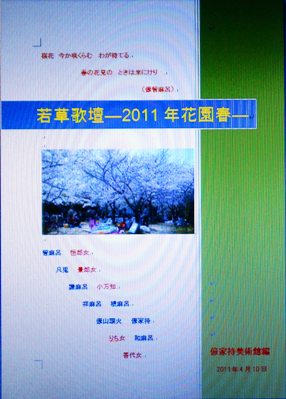
若草歌壇2011花園篇公開ほか
その1.若草歌集 4月10日の若草読書会のお花見の際の歌を編集した若草歌集第8巻、「若草歌壇2011年花園春篇」が、昨日、河内温泉大学図書館にて公開に供されました。興味を持たれた方は下記をクリックして覗いてみて下さい。 河内温泉大学図書館 若草歌壇2011年花園春篇(偐家持美術館編)その2.青雲会でも震災支援募金を実施 先日4月27日に大学の法学部同窓会(青雲会)の幹事会があって出席して来た。大震災後初めての幹事会で、我が同窓会も義援金募集を行おうということになり、この7月開催の総会の案内状を5月末から6月初旬に発送するに合せて、これに同封して、義援金を会員に呼び掛けることと決まった。既に多くの方が個人として義援金に応じて居られると思われるが、こういうものはいくら重なってもよかろうと、青雲会としてもこれを行うべく、会員に対し義援金の拠出を募ることとなった次第。その3.青雲塾万葉ウオーク下見 また、青雲会で行っている青雲塾の次回テーマが「万葉を歩くシリーズ第2回」と決まり、6月5日(日)に西大寺から薬師寺への西ノ京の歴史の道を歩くこととなった。案内役兼講師を仰せつかったので、歩程を調べるため、28日午後からコースを歩いて来た。大池(勝間田池)まで回って6~7km位だろうか。自転車では何度も走っているが、久し振りに歩いてみた。と言っても帰路は自転車で走りたいので、自転車を押してウオーキング予定コースを歩くという妙なウオーキング・スタイルとなった。 事情の知らない人は自転車がパンクして押して歩いているのかと、気の毒そうな視線を注いでいたかも知れませんな(笑)。 予定コースは以下の通り。 午前10時半近鉄西大寺駅集合→西大寺・孝謙天皇万葉歌碑→ 菅原天満宮天神堀→菅原天満宮→喜光寺・石川郎女万葉歌碑 →垂仁天皇陵→唐招提寺→薬師寺→大池(勝間田池)→薬師寺 八幡宮→近鉄西ノ京駅前午後3時解散 かなりゆっくり目の行程計画である。これはご高齢の方にも配慮したことと寺院の参拝・見学の時間を十分に取ったことによるものだが、それでももう少し早い時間に解散となるかも知れない。けん家持はトレンクル持参にし、解散後に、銀輪散歩をもうひとっ走りしようかと考えているのであるが・・。 道中下見で撮った写真を2~3掲載して本日の日記とします。(菅原道真が産湯を使ったとの伝承のある池「菅原天満宮天神堀」)(本堂が大仏殿のモデルとなった喜光寺)(薬師寺の撮影ポイントの大池)(薬師寺八幡宮へは踏み切を渡って行く。)(薬師寺八幡宮)<参考>過去の日記で似たようなコースを銀輪散歩しているのは ないかと探すと下記が見つかりました。これなども参考 にレジメを作成することとしますかな(笑)。 西大寺駅から矢田寺経由富雄駅まで (2010.3.5.) 西大寺駅から矢田寺経由富雄駅まで(その2)(2010.3.6.)
2011.04.30
コメント(0)
-

第78回智麻呂絵画展
第78回智麻呂絵画展 智麻呂絵画展の開催であります。大型連休初日を飾る力作の数々をじっくり、ゆっくり、ご覧になり、コックリなども結構。どうぞ、ごゆるりおくつろぎ下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(アセビ) これは、先のお花見の日に小万知さんがお持ち下さったアセビです。可愛い三輪車の花車です。アセビは馬酔木と書きますから、馬に引かせず三輪車で参ろうという趣向ですな。 万葉では「あせび」ではなく「あしび」です。あしびの万葉歌の代表はやはりこれですかな。磯の上に 生(お)ふる馬酔木(あしび)を 手折(たを)らめど 見すべき君が ありと言はなくに (大伯皇女 巻2-166) 弟の大津皇子の死を悲傷しての姉、大伯皇女(大来皇女とも書く)の絶唱である。大切な人を失った人の心に沁みて来る歌であるだろう。小生の高校時代の国語の女先生(おばあちゃん先生と呼ばれていらっしゃいましたが)は涙を流しながらこの歌や有間皇子の歌などを授業の時に朗唱されました。そのことが懐かしく思い出される。思えばそれが小生と万葉との出会いであったのですな。彼女の授業の他の部分は全て記憶の彼方に消えてしまっているが、万葉の授業だけは今も鮮明に覚えている。(鮎) これはお菓子の鮎。以前にも同じ題材の絵がこの絵画展に登場していますが、智麻呂邸訪問の際の偐家持の手土産に時々なってくれる「鮎」であります。 万葉にも鮎を詠う歌が結構ある。20首位はあるだろうか。万葉では「年魚」と表記したりもする。ここでは大伴家持の歌を掲載しておく。年のはに 鮎し走らば 辟田川(さきたがは) 鵜(う)八頭(やつ)潜(かづ)けて 川瀬たづねむ (大伴家持 巻19-4158) 上の歌に出て来る辟田川については、富山県氷見街道筋の、泉川説、阿尾川上流説、雨晴海岸に注ぐ、紅葉川説、加古川説、小矢部川支流の子撫川説と諸説あって、一定しない。(けんちゃんの兜) これは、第73回智麻呂絵画展で紹介しましたが、智麻呂さんに手作りバレンタインチョコをくれた小学生、あのSちゃんの弟の「けんちゃん」のために描かれた兜です。3月3日にはSちゃんにお雛様の絵をプレゼントされましたので、弟のけんちゃんには5月5日に兜の絵、という訳です。けんちゃんも今年から小学1年生。お姉ちゃんと一緒に朝、智麻呂さんに「おはようございます。」とご挨拶して前の道を登校して行きます(笑)。(野芥子) 野芥子は、智麻呂さんはその葉の形状に興味が引かれたようでありました。ためつすがめつ葉を眺めて居られました。(雛芥子・ 雛罌粟) 力拔山兮氣蓋世 (力は山を抜き、気は世を覆う) 時不利兮騅不逝 (時利あらずして騅逝かず) 騅不逝兮可奈何 (騅逝かざるを如何せん) 虞兮虞兮奈若何 (虞や虞や汝を如何せん) 上は、「垓下の戦い」に於いて楚の項羽が漢の劉邦の大軍に包囲され進退極まったかと思われた時に詠んだ歌。脱出を図ろうとする項羽の足手まといになってはと、妃の虞妃は自刃する。その彼女の墓に咲いた花がこの花。よって人はこの花を虞美人草と呼んだ。 小生は、この話を未だ知らなかった高校時代に読んだ夏目漱石の小説「虞美人草」から、長らく何故か紫の花をずっとイメージしていたので、それと知った時には失望とまでには行かないが、期待外れと言うか、予想外と言うか、意外な、道端でよく目にする朱色の花が虞美人草であったことに驚いたものでありました。美人と言うより可愛い花である。項羽は美人系よりもカワイイ系が好みであったのか(笑)。(牡丹桜) 八重桜。山桜に対して里桜とも呼ぶらしいが、花の形姿から牡丹桜ともいう。ソメイヨシノが散った後に数日遅れて咲く。奈良や京都の貴族はこの花を愛したようだが、兼好さんは桜は一重に限ると言って居られますな。小生もどちらかと言えばこの点については兼好さんに同感である。友人の凡鬼さんは八重も一重もいいと申されていましたな(笑)。では、百人一首から、いにしへの 奈良の都の 八重桜 今日九重に 匂ひぬるかな (伊勢大輔)(藤の花) 桜が散って、藤の花が咲き、その藤の花も散り始めている。季節の移ろいの何と早きことか。藤波の 影なす海の 底清み しづく石をも 珠とそ吾が見る (大伴家持 巻19-4199)妹が家に 伊久里(いくり)の森の 藤の花 今来(こ)む春も 常如此(かく)し見む (高安王 巻17-3952) 伊久里の森についても、栃波市井栗谷説、新潟県三条市井栗説、奈良市説と諸説あるが、これも一定しない。大和説伊久里の森は当ブログで紹介済みですが、富山の井栗も新潟の井栗も訪ねなくてはいけませんな。(スノーフレーク、鈴蘭水仙) この花も智麻呂さんお好みの花の一つ。何度かこの絵画展にも登場している。(和菓子の蛙、ひよこ、ネズミ、兎) これも、偐家持の手土産。和菓子を買っていたら、店先を通りかかった若い女性たちが「カワイイ~!」と歓声。見ると動物をかたどったお饅頭。これも追加で一箱いただく。これだけを単独で買う「勇気?」は偐家持にはありませんな。8個入りと4個入りがありましたが、絵の題材なら4個入りで十分ではないかと(笑)。<追記・注>「スノーフレーク、鈴蘭水仙」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月6日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.29
コメント(14)
-

偐万葉・童子森の母篇(その5)
偐万葉・童子森の母篇(その5) 和歌の数は少ないのだが、パロディ詩、替え歌などのお遊びも混じって字数が嵩みましたので、偐万葉に繰り上げ掲載です(笑)。 <参考>過去の偐万葉・童子森の母篇はコチラからどうぞ。 童子森の母さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が童子桜郎女に贈りて詠める歌6首及び詩1編、替え歌1曲 併せて童子桜郎女が作れる歌3首 童子桜郎女の贈り来れる歌 腕組みて いらぬお世話と 思ふわれ 誰ぞ知らぬが かなしき人よ蕗の薹(たう) ひとつ萌ゆらし 津軽にも 春来(く)と聞けば われもうれしも なすことも なかり花見の 席取りは 野良と仲良く なるのほかなく 童子桜郎女の返せる歌サクラ木の 下ではじまる 宴待ち 猫とたはむる 人にてありき桃(もも)桜(さくら) いづれと知らね 魯桃桜(ロトウザクラ) 春の津軽の 路頭に咲ける (梅吉) 「津軽猫旅情の歌」 作 猫崎藤村 津軽なる岩木の麓 猫二匹終始まどろむ 緑なす敷物の上 若草にしかずよしとす しろがねのソファーの窓辺 日に照りて白猫光る あたたかき部屋にしあれば 野に満つる香(かほり)も知らず 浅くのみ猫は眠りて 髭の色ともにぞ白し 野良の群ふたりは知らず ぬくぬくと部屋にぞありぬ 暮行けばお岩木見えず 腹哀しクーと鳴るゆゑ 母御前(ははごぜ)にいざりぞ寄りて 庭ちかき縁側にのぼり 削り節削れる喰ひて 猫枕しばし慰む <参考> 小諸なる古城のほとり 雲白く遊子(ゆうし)悲しむ 緑なすはこべは萌えず 若草も籍(し)くによしなし しろがねの衾(ふすま)の岡辺(をかべ) 日に溶けて淡雪流る あたゝかき光はあれど 野に満つる香(かをり)も知らず 浅くのみ春は霞みて 麦の色わずかに青し 旅人の群はいくつか 畠中の道を急ぎぬ 暮行けば浅間も見えず 歌哀し佐久の草笛 千曲川いざよう波の 岸近き宿にのぼりつ 濁(にご)り酒濁れる飲みて 草枕しばし慰む 「軽海峡猫景色」 歌:猫川ゆすり 作詞・作曲:野良たかり 飢えの腹の夜食抜きで やっと来たけど 大盛りめしは 店の中 店の中の人の群れは 誰もドけちで 自分のだけを 食っている 私もひらり 隣の椅子に乗り こごえそうな顔で見つめ 鳴いてみました にゃあ~あ 津軽海峡 猫景色 ごらんあれは野良の猫よ きたならしいわと 見知らぬ人が 指を指す 泥で濁る足の先を ふいてみたけど かすかに汚れ 落ちるだけ さようなことより 私は腹ペコで 腹の虫が今もゆする グーっとばかりに にゃあ~あ 津軽海峡 猫景色 そんなことよりも 私にエサをくれ 腹の虫が餓えてわめく エサをくれよと にゃあ~あ 津軽海峡 野良景色 <参考>曲 上野発の夜行列車 おりた時から 青森駅は 雪の中 北へ帰る人の群れは 誰も無口で 海鳴りだけを きいている 私もひとり 連絡船に乗り こごえそうな鴎見つめ 泣いていました ああ 津軽海峡 冬景色 ごらんあれが竜飛岬 北のはずれと 見知らぬ人が 指をさす 息でくもる窓のガラス ふいてみたけど はるかにかすみ 見えるだけ さよならあなた 私は帰ります 風の音が胸をゆする 泣けとばかりに ああ 津軽海峡 冬景色 さよならあなた 私は帰ります 風の音が胸をゆする 泣けとばかりに ああ 津軽海峡 冬景色 童子桜郎女の贈り来れる歌堅香子(かたかご)を 摘みて振り向き 笑み浮かめ これも恐ろし もののけ童子 (姥桜の家持) 偐家持の返せる歌2首片栗の 花はな摘みそ 散るまでは 餡かけ恋(こほ)し ときにはあれど (餡掛時次郎)かたかごの 花にし今も あるやらむ 津軽の妹の 花笑みぞこれ (応援家持)ムスカリは 青き土筆に あるやらん つぼみ夢見の ときにしあれば (蒸蟹持(ムスカニもち)) (注)掲載の写真は全て童子森の母さんのブログからの転載です。
2011.04.28
コメント(7)
-

銀輪花遍路(その8)
桜も散り、大阪は心そはそはすることもない時期となりました。代って青葉の美しい晩春から初夏への景色へと移りつつあるようです。さくら花 ちりぬる風の なごりには 水なき空に 浪ぞたちける (紀貫之 古今集89) 貫之は上のように詠いましたが、ヤカモチは、さくら花 ちりぬるあとの なごりとて 野に咲く花の 遍路に立たむ (偐家持)という訳で、懲りずに銀輪花遍路であります(笑)。 先ずは、ライラック。ブログ友のビッグジョンさんこと歩麻呂殿も先日この花をブログに掲載されていましたが、同氏の母上のお好きな花とのこと。 (ライラック)<参考>ライラック ライラック ライラックは英語風の呼び名。フランス風にはリラ。リラと呼ぶとちょっと気障な感じになるが和歌や俳句にするなら促音を含むライラックよりもリラの方が馴染みますかな。和名はムラサキハシドイ(紫丁香花)。和名の方も和歌や俳句には使えそうもない文字数と語感ですな。初恋は うすきむらさき リラの花 冷たき雨に 濡れてある道 (札幌麻呂)(ハルジオン) ハルジオンは「春紫苑」と書く。よく似た花にヒメジョオン(姫女苑)があるが、両者の区別などは、下の<参考>をクリックすると見分け方が解説されていますので、どうぞ(笑)。<参考>ハルジオン ハルジオン シオン ヒメジョオン 我妹子も かくやありしか 春紫苑 蕾に見ゆる はにかみの色 (偐家持) 次はマツバウンラン(松葉海蘭)。 この花も河原や土手などに群生しているのを最近はよく見かけるが、群れ咲いているとなかなかに美しい。そこはかとなく美しいのでありますな。 (マツバウンラン)<参考>マツバウンラン 行く春の なごりとどめよ 吹く風の まにまにぞ咲く 松葉海蘭 (偐家持) (名前不詳) 上の花はよく見かけるような気もするのだが、名前は分らない。 <以下4月29日追記> 小万知さんのコメントから、この花はアメリカフウロと判明しました。 <参考>アメリカフウロ<追記:2022.5.28.>掲載写真10枚中9枚が横倒しの歪んだ画像になっていましたので修正しました。(参考:過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.)
2011.04.26
コメント(4)
-

越後・会津銀輪散歩余録・かたくりと雪割草
(承前) 前回の日記では、信濃川畔の林の中にて目にしたカタクリと雪割草の花をご紹介しましたが、今回はその写真をまとめて掲載です。 先ずカタクリです。 カタクリは万葉にただ1首のみあるが、それだけでもう万葉の花として十分過ぎるほどの存在感を示しているのは、その万葉歌が名歌であるというだけでなく、この花の可憐な美しさによるものであろう。物部(もののふ)の 八十少女(やそをとめ)らが 汲(く)みまがふ 寺井の上の 堅香子(かたかご)の花 (大伴家持 巻19-4143) この歌は大伴家持が天平勝宝2年(750年)3月2日に越中の国で詠んだもの。うら若い少女たちがたくさんやって来て水を汲んでゆく寺の泉の畔に咲いているかたかごの美しい花。さんざめく少女たちの姿とこの可憐な花とがダブルイメージとなって、春の到来の喜びが伝わって来る、いい歌である。 では本家の家持殿にならって偐家持も「かたかごの歌」を作ってみましょう。上の二つ寄り添い咲いている花を愛でて、ひとり咲く 花もよけれど かたかごの 花はふたりし 咲くこそよけれ(偐家持) もののふの 八十やその少女をとめも 好き好きに 咲きてこそよき かたかごの花 (偐家持) 我妹子わぎもこの 花にしあれり かたかごの 春とまたもや 越後に逢へる (偐家持) カタクリの咲いている一角から少し離れた処には雪割草が咲きこぼれてありました。早春を彩る可憐な花の代表とも言うべきカタクリと雪割草をふたつながら同時に目にするという幸運。何ともラッキーな、そして贅沢な銀輪散歩となりました。 雪割草というのは、言わば「愛称」であって、ミスミソウ、スハマソウ、オオミスミソウ、ケスハマソウなどの総称とのこと。 地方によっては、イチリンソウ、ニリンソウ、ショウジョウバカマ、アズマイチゲ、ハシリドコロを雪割草とか雪割花と呼ぶらしい。 園芸上は、愛好家によって交配が重ねられ様々な交配種が生まれているようで、花姿は多種多様。花音痴のヤカモチにはもう何が何だか分らぬ状況にある。 雪割草は万葉には登場しない。スミレを愛した赤人ならこの花のためには一夜と言わず、二夜、三夜、野に連泊するも厭わなかったことでしょう。大伴家持も越中国守ではなく越後国守となっていたら雪割草の歌も作ったに違いないと思うのですが、赤人も家持も越後とは縁がなかったようにて残念なことでありました。 この花は葉が特長的である。可憐な花姿に似合わず、葉はぼってりとして何か野暮ったいものがある。きっと厳しい雪国の冬を耐えるための力とタフさがその葉の形姿に秘められているのであろう。 八重に咲く花もあるようだ。 雪割草には「かたかごの花」のような鮮烈な個性はないが、楚々と咲くその姿には見る人を飽きさせないものがある。両者のデザインについて、かたかごが岡本太郎であるなら雪割草は・・なんぞと思ってみたりのヤカモチでありました。 「手に取るなやはり野に置け蓮華草」という句があるが、雪割草も然りでありますな。 雪割草の花言葉は「はにかみや」だそうな。目立つことに臆病なように見えるこの花の在り様を言い得たものと言うべきだが、それが却って人気を呼びこの花を目立つ存在にしたのだと思うと面白い。はにかみと辛抱強さが 裏と表についているそんな花にと 生まれたからは 厳しい冬の 雪にも耐えて春さり来れば 微笑み咲ける花は越後の 花は越後の 雪割草 (雑木林雪子)春告げの 越後の花は 雪割草 人みな笑みて 生きよと咲ける (偐家持) いかにとや 越後の春に 恋ひ来れば われに笑みぬる 雪割りの花 (偐家持) <参考>前編 越後・会津銀輪散歩 越後・会津銀輪散歩(その2)<追記・注>「カタクリ」の写真4枚と「雪割草」の写真4枚が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月6日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.25
コメント(8)
-

越後・会津銀輪散歩(その2)
(承前) 急遽予定変更の会津行き。新潟から会津まで快速あがので2時間40分かかる。新津から磐越西線に入り、トロトロと阿賀野川沿いを列車は走る。津川の麒麟山温泉は以前来たことがある。山峡に入ると雪が未だ消え残っている。早春の風景である。山々は雪を戴いてもいる。 阿賀野川沿いの自転車道を走る予定が鉄道の旅になってしまった会津行き。前の記事と前後しますが、今日の日記は会津への道中の景色から始めることといたしましょう。 運転席の隣から眺めた車窓の景色をしばしお楽しみ下さい。(線路脇には未だ雪が消え残っている。)(左に見える川が阿賀野川)(青く霞む遠山には未だ雪が消え残っている。)会津への 消残(けのこ)る雪の 山青み いつしかわれも 旅人の顔 (偐家持)遠山の 雪もかなしけ その先に なゐに泣く人 ありとし思へば (偐家持) 帰途は高速バスにしたが、バスの方が運賃が安い上に所要時間が1時間50分程度と鉄道よりも随分速い。但し、山中を突っ切る高速道路はトンネルも多く、味気ない。眺めを楽しむなら、やはり鉄道がお薦めだ。 さて、何やら季節を早春に巻き戻してしまったような景色になりましたので、新潟の花風景をご覧いただきましょう。こちらは桜が満開、チューリップも咲き匂っていた。岸辺の自転車道も走っていると心がおのずときめくのである。(信濃川やすらぎ堤の桜)難波にて 送りし桜 越後にし 咲きてありけり われ待つらしも (偐家持)(桜花の下にはチューリップも) 満開の桜を見上げるようにチューリップたちが群れ咲いている。信濃川のこの岸辺は「やすらぎ堤」と名付けられているらしい。新潟市民の憩いとやすらぎの場となっているのだろう。そこここに散策する人、ベンチに休む人、花の下でお弁当を広げる人、そして、小生同様に銀輪散歩する人が行き交う。童女(わらはめ)の ごと咲(ゑ)み群れて チューリップ 越後は春の 今盛りなり (偐家持) チューリップたちはみなあどけない笑みをくれる。もし花たちが声を持ったとしたら、チューリップたちはさぞやかましいことだろうと思ったりもするヤカモチでありました。 銀輪を停めて、土手に目を寄せると土筆も生えているのでありました。いづくにか 去れるを惜(を)しと 恋ひ来れば 春は越後に 待ちてありけり (偐家持)(土手には土筆も) 信濃川沿いの林の中に何気なく立ち寄ってみると、かたくりと雪割草が沢山咲いていました。これは思わぬ収穫。写真を撮りまくりました(笑)。 全てはページを改めてまた別にご紹介することとし、ここではそれぞれ1枚だけ掲載して置きます。(かたくり)(雪割草) そして信濃川の夕照。(信濃川夕照) 夕照はやはり慈愛の色にて、何でもない橋梁をもやさしく美しい色に染めて行く。(信濃川夕照 2) <参考>前篇 越後・会津銀輪散歩 続編 越後・会津銀輪散歩余録・かたくりと雪割草<追記・注>「桜花の下にはチューリップも」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月6日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.24
コメント(6)
-

越後・会津銀輪散歩
昨日思い起って新潟経由会津若松まで行って来ました。ひろろさんがブログでご紹介されていたチャリティ美術展を拝見してまいりました。と言っても銀輪散歩のついでのようなものではあったのですが・・。2008年5月に阿賀野川沿いの自転車道を途中まで走ったので、その先を走ってみようか、それとも三条市にあるというもう一つの万葉の「伊久里の森」と言われる井栗を訪ねようか、などと考え新潟行きを計画していたのであるが、ひろろさんのブログ記事を見て急遽予定を変更、会津行きとなった次第。 会場では、ひろろさんの絵は何処に、とそれらしきものを探しましたが、何とブログでご紹介されていたあの猫の絵でありました。ちょっと色が異なるのでひょっとすると色違いの別の絵かも知れませぬが・・。買い求めようとするも既に売約済みの赤丸のシールが貼られていて買えませんでした。仕方がないので、気持だけを義捐金箱に入れてお暇いたしました。 会津は間もなく桜が満開になろうかという時期にて、若松城こと鶴ヶ城は桜の花越しに優雅な佇まいを見せてくれていました。会津はかなり以前に自転車で走り回ったことでもあり、今回は到着から新潟への帰りのバスまでの4時間半程の滞在時間で、美術展を拝見し、サイクリングもして、という思い付き遠征でありましたので、鶴ヶ城周辺と駅前の間をブラブラ散歩する程度で済ませました。ちょっと勿体ない会津散歩となりました。(会津若松駅 白虎隊の像。後方には「赤べこ」も居ました。) 新潟からは磐越西線で会津に入りましたが、帰途はバスが速いというので、高速バスで新潟に戻りました。 駅前でトレンクルを組み立て、観光案内所で、会場の文化センターの場所を教えて戴いて、昼食を済ませた後、出発。会場までは20分程度。(文化センター) ひろろさんの絵。ブログ読者ならすぐにそれと分かる絵でありました(笑)。(ひろろさんの絵) 会場の文化センターは鶴ヶ城の三の丸跡の直ぐ近く。桜が五分咲き程度にて、何やら大阪で見送った春景色を巻き戻して見ているような気分。(若松城の堀端の桜) やはり、この季節、鶴ヶ城は見て置かなくてはなるまい。天守閣の方へと自転車を走らせる。天守近くは自転車乗り入れ禁止となっているので、いつものように、肩に担いで行く。 予想通り、美しい城の姿である。何か女性的な美しさと言うべきか。この城は桜の花が特に似合うようだ。桜の衣を纏った鶴姫様のおな~り~でありまする。(若松城<鶴ヶ城>)難波では 散りにし桜 会津いま 鶴姫飾る 衣となれり (偐家持)(同上) この城はこの角度が一番美しいと知ったかぶりのヤカモチであります。(同上) もう4~5日後なら、もっと桜が艶やか、華やかになって、鶴ヶ城も更に映えたことでしょうな。こと程左様に、旅人にとって桜の盛りと遭遇するのは、そう簡単なことではないのでありまする。(山鹿素行生誕地の碑) 城を出て西に行くと山鹿素行生誕地の碑があった。隣には直江兼続屋敷跡の標識も立っていた。<参考>山鹿素行、直江兼続(同上) 碑は東郷平八郎の揮毫です。 国道を北に行くと蒲生氏郷の墓所がある。 <参考>蒲生氏郷(蒲生氏郷墓所)(同上) 墓の隣には氏郷の辞世の歌碑と幕末の会津藩主松平容保の歌碑が立っていました。容保の歌は、その後の会津藩の運命を思うと、もの思うほかなきと言うべきか。限りあれば 吹かねど花は 散るものを 心みじかき 春の山風 (蒲生氏郷) 百とせを 三たびかさねし 若松の さとは幾千代 栄えゆくらん (松平容保) (左:蒲生氏郷歌碑 右:松平容保歌碑)<参考:松平容保> 駅前へ戻って来たらバスの発車時刻まで未だ1時間近くある。さりとて何処かへ立ち回るには不案内な土地では少し中途半端な時間。かくて近くの「大町白虎公園」という小さな公園で時間潰しをする。バス待ちの 時間潰しの 公園に われ待ちわびて 花とたはむる (花川啄木) さすが白虎隊の名にし負う公園。野良猫はいない。ヤカモチは仕方なく花とたわむれて居りました(笑)。(芝桜)(タンポポ)(ホトケノザ)<注>正しくはヒメオドリコソウでした。 またもホトケノザ。二つ並べて横から見ると連獅子を想起させる。顔ならぬ ホトケノザもや 二度三度 過ぎてぞあらば 獅子ともならむ (偐家持)(オオイヌノフグリ) オオイヌノフグリが可憐に咲いている。ハコベも立ち混じっている。蟻の目になりて見れば、オオイヌノフグリのジャングルである。しかし、このようなジャングルなら道に迷うてみるのも風流と言うものである。(同上)(同上) そして、またもやムスカリ。名前を知った所為か、最近よくこの花も目につく。大阪も会津も野や公園に咲く花は似たり寄ったりということのようです。(ムスカリ) 本日はここまで。新潟から会津への磐越西線の車窓風景や信濃川沿いの花景色は次回といたしまする。<参考>続編 越後・会津銀輪散歩(その2) 同 越後・会津銀輪散歩余録・かたくりと雪割草<追記・注>「同上(山鹿素行生誕地碑)」「蒲生氏郷歌碑」「松平容保歌碑」「同上(オオイヌノフグリ下段2枚)」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月6日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.23
コメント(4)
-

銀輪花遍路(その7)
少しブログ更新怠っていましたので、今日は頑張って更新いたします。この間、誰かさんのように昏倒していた訳ではありません。元気にいたして居ります。何といってテーマの無い時は「銀輪花遍路」(「花逍遥」を使うこともありますが、木の花桜さんが「花逍遥というタイトルは知的な感じがする」というようなことを仰っていましたので、「知的な」内容にはなりそうもありませぬゆゑ、「花遍路」)であります(笑)。 以下、銀輪散歩にて目にした花たちであります。(ハナニラ)<参考:ハナニラ> 小生とこの花の出会いは2008年4月16日(同日の日記「星の花?」参照)でありますが、以来、この花は春から初夏への時期の銀輪散歩では道の辺の花として、すっかり馴染みになりました。 初対面のこの花に贈った歌は、春の野の 片辺に咲ける 星の花 我に笑ましし 妻とやいはむでありましたが、まだこの花からは色良い返事を貰って居りませぬなあ(笑)。(ナズナ)<参考:ナズナ> ちょっと写真がまずいのでナズナか何だか分らない。ナズナは、天が世を捨て暮らしている人のために生じさせたもの(貝原益軒)らしいが、それはペンペン草になる前の春の七草であるまでのこと、こう大きくなっては世捨て人も歯が立たない。(オランダ耳菜草)<参考:オランダ耳菜草> これも道端でハコベなんかと一緒によく見かける雑草であるが、ミミナグサというちゃんとした名があるのだ。(アミガサユリ)<参考:アミガサユリ> この花は、下を向いて咲くので花の内側を撮ろうとすると地面に寝転ばなくてはならない。花弁の内側は美しい網目模様になっている。時々の 花は咲けども 何すれそ 母とふ花の 咲き出来(でこ)ずけむ (丈部真麿(はせべのままろ) 巻20-4323) 万葉集の上の防人の歌に登場する「母とふ花」の「ハハ」は、このアミガサユリのことだという説がある。これをビッグジョンさんのコメントへの返事を打っていてふと思い出しましたので、追記して置きます。(白いノジスミレ?)<参考:すみれの図鑑> スミレも色々と品種があって小生などにはその区別がつき兼ねるのであるが、タチツボスミレは葉が丸みのある形なのに対し、ノジスミレは葉が細長い形をしている。これは先日、恒郎女様から教えていただ俄か知識である。しかし、この程度の知識ではスミレの品種の区別には全然歯が立たないのである。(野芥子)<参考:野芥子> この花は我々が子供の頃は「毒タンポポ」などという穏やかならぬ名で呼んでいたが、野芥子という可愛らしい名があったのだ。こいつの大きいのが鬼野芥子ですかな。<追記>上の写真の花はノゲシ(野芥子)ではなくノボロギク(野襤褸菊)です。この頃の草花に関する筆者の知識は現在よりずっと貧困で、このようなミスを犯したようです。謹んで訂正します。(2020年4月17日)(鳩) これは、ハナではありません。ハトです。けん家持もこの程度の区別は自信を持って出来るのであります。 花ばかり続きましたので、ちょっと気分転換して戴きました。(福寿草)<参考:福寿草> これは人参ではありません。福寿草が成長するとこうなるのですな。こうなるともう「福福寿草」ですな。一瞬、何の花かと思ったものでした。(ヒヤシンス?)<参考:ヒヤシンス> これもちょっと自信ありませぬがヒヤシンスだろうと思います。なかなかいい風情で、ヒヤシンスをちょっと見直しました。ごちゃごちゃとたわわに咲き過ぎるというのが、小生のヒヤシンスに対する消極的評価の原因なのですが、これは派手過ぎず、大盛り過ぎず、適度なる花の付き方です。(ムスカリ)<参考:ムスカリ>(ホトケノザ)<参考:ホトケノザ>(注)実はヒメオドリコソウでありました。 ホトケノザもこれだけ群生すると壮観である。人は死ぬと皆ホトケ様になると言う。そんなに仏様が多くなって大丈夫かな、と心配したが、これだけホトケノザが空席であるのだから、当分は大丈夫のようだ(笑)。指定席を買い求める必要はないのである、自由席でも大丈夫だ。 ところで、春の七草の一つにホトケノザがあるが、それはこの花ではなく、コオニタビラコ(小鬼田平子)という別の花のことだそうな。これを摘んで食べたりなさいませんように。あの世でのホトケの席がなくなってしまいますぞ(笑)。(同上)みほとけの いづくおはすや ほとけのざ わが座もここの いづれかならむ (偐家持) <追記・注>「ナズナ」「ヒヤシンス」「ホトケノザ(実はヒメオドリコソウ)」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月6日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.21
コメント(10)
-

第77回智麻呂絵画展
第77回智麻呂絵画展 智麻呂絵画展第77回を開催いたします。どうぞ皆さまお気軽にお立ち寄り下さり、しばしくつろいで行かれませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(プリマベーラ) 偐山頭火氏がお持ちになった花たち。 個々の花の名は別として、まとめて「プリマべーラ(Primavera・春)」と名付けることとしました。 勿論、ボッティチェリの名画「La Primavera」を意識して名付けましたが、これと対抗するなんぞという大それた気持はさらさらございません(笑)。しかし、この絵で「春」と「愛」を感じて戴ければ幸いであります。今こそは ひとみな愛に 結ばれて ともにぞ咲かな 日の本の春 (偐家持)(桜) これは若草読書会のお花見の前に描かれた桜の絵です。桜花 今か咲くらむ わが待てる 春の花見の ときは来にけり (偐智麻呂)(木蓮)悲しめる 人に添はなと 火明(ほあ)かりを ともし咲きぬる 木蓮の花 (偐家持)(春の小箱とケーキ) 春の小箱とケーキはヤカモチの手土産。 何でも絵にしてしまう智麻呂画伯でありますな。 そう言えば、先日の「たこ焼きパーティ」で小万知さんであったか、「いかな智麻呂様でもたこ焼きだけは描いてから食べるという訳にはいかない。」と仰っていましたが、たこ焼きは例外ですな。たこ焼きは熱いうちに食べてしまわなくてはなりませんから写生している暇がない(笑)。たこ焼きを くへたこ焼きは 熱きうち かくして絵には ならぬたこ焼き (大伴蛸焼)(セイヨウカラシナ) これは恩智川や花園公園の遊水地の土手などに自生している「菜の花」であります。先日のお花見の帰途に3~4本摘んで来たものです。摘みて喰(く)ふ 人もなかりき 春されば 西洋芥子菜(せいやうからしな) 花盛りなり (芥川虎之介)(タンポポ) 4月10日のお花見の席の傍らに咲いていたタンポポです。 種の一つ一つを最も効率よく風で散らそうとすると相互に支えあってこういう美しい秩序のある形になるのですな。僕らの社会もかくあれやです。 お花見の始まる前に智麻呂さんが熱心にスケッチされていました。描き終える頃には春風が綿帽子を半分ばかり散らしてしまっていましたが。美しき 秩序の形 神なせる わざにしあれり たんぽぽの絮(わた) (偐家持)(蕨) 蕨は小万知さんがお持ち下さったもの。もう一つ馬酔木の花もありましたが、これは、昨日現在制作中にて、次回の出展となりますな。10日のお花見の日に絵の題材が一挙に舞い込みましたので、智麻呂画伯も大忙しですな(笑)。摘み摘みて 野の上の蕨 我妹子が 持ちや来たれる 春にしあらむ (偐家持)(水仙)(チューリップ) 水仙とチューリップは凡鬼・景郎女様ご夫妻がお花見の日にお持ち下さったもの。黄の花も 真白き花も よき水仙 咲ける湖畔の 木陰し思はゆ (偐家持)チューリップ 空の果てまで 咲く道は 妹とし行きし 越の道なり (偐家持)「絵筆から生まれる花々は大したものではなくても、すくなくともそれらを描くことは、われわれが自然の花々とまじわって生きることなのだから、それはたのしいなぐさみで、とりわけ、花を模写するために、いっそう近づいて花をながめるとき、その美しさにはあきることがない。」(プルースト「失われた時を求めて」) <追記・注>「ケーキ」及び「タンポポ」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月7日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.17
コメント(16)
-

西洋芥子菜とその後の菫
この時期になると恩智川の河川敷は一面菜の花で黄色く染まる。先日お花見をした花園中央公園は恩智川沿いにあるのだが、お花見からの帰りに、川べりで、この花の眺めも楽しみました。公園の土手にも沢山生えていたので3~4本摘んで、智麻呂さんの絵の題材にとお花見の帰りに智麻呂邸へと持ち帰りました。 桜はあらかた散ってしまって、地面が花ビラでピンク色になって、その名残りをとどめている。代って八重桜が咲き出し、ここ何日かが見頃のようです。 さて、こちらの恩智川べりの「菜の花」は桜よりも花の時期が長いようで、先日10日に眺めたのと同じ状態で咲き匂っていました。(恩智川の菜の花) この「菜の花」、正しくは「セイヨウカラシナ(西洋芥子菜)」という名の花である。食用として我が国に入って来たそうだが、今は野生化して、河川敷や土手などに群生して、春を彩ってくれている。 <参考>セイヨウカラシナ恩智川 土手の桜は 散りぬれど みぎは盛りと 菜の花咲ける (偐家持) 今日、銀輪散歩のついでに智麻呂氏宅に立ち寄ってまいりましたが、先日摘んだこの花が未だお部屋で咲いていました。この花の絵も1枚完成して居りました。 この花は花粉を散らすようで、花を挿した花瓶の置かれているテーブルの上に黄色い粉沫が盛んにこぼれ、恒郎女さんを悩ませているようです。そんな訳で、かなり萎れかかってもいるので、花をもう捨てることにしましょう、と提案したら、智麻呂氏から大層お叱りを受けた、とか。笑いながら話して居られました(笑)。 そう言えば、上の写真でも川面に黄色い粉のようなものが浮かんで流れているようにも見えます。これは川面に花が映っているのか、こぼれた花粉が浮かび流れているのか、さてどちらなんでしょう。 本日、新作の絵画数点ゲット、7日と10日にゲットした5点と合せて10点となりましたので、明日には智麻呂絵画展を開催することにいたします。智麻呂絵画ファンの皆さま、明日までお待ち下さい。 さて、智麻呂邸で目にしたもう一つの発見。 第74回智麻呂絵画展でご紹介申し上げた「明日香のスミレ」でありますが、種を付けて居りました。スミレの種なんぞ目にするのは初めてでありましたので、写真に撮らせていただきました。ちょっとピントが甘くなってしまいましたが・・。 <参考>第74回智麻呂絵画展(明日香のスミレも種を付けました。)
2011.04.16
コメント(2)
-
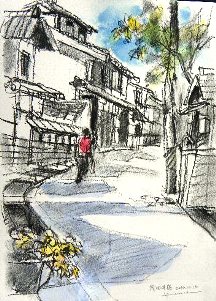
偐万葉・ひろろ篇(その7)
偐万葉・ひろろ篇(その7) 本日、会津のひろろさんからコメントを頂戴しました。今回の大震災ではひろろさんご自身にはさしたる被害もなかったようですが、岩手などにご在住のご親戚の方を津波で亡くされるなど、悲しく辛い思いをされたようです。 こういう時に偐万葉というのがいいのかどうか疑問なきにし非ずですが、いささかなりとも、ひろろさんのお心の慰めにでもなれば、と思い、ひろろ篇(その7)をアップすることとしました。歌は最後の1首を除き全て大震災以前のものです。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌19首古(いにしへ)の 日もやかくしか 旅籠町(はたごまち) 行く人ひとり 午後の曲道(まがりぢ) スケッチを する人描(ゑが)く スケッチを 見つつ払はむ ピラカンサの枝 (枝打実在証明) 絵を覗く 人を描(ゑが)ける 絵を覗く われは見る人 見られつる人 (実在不明家持)いてふちる 塔のかげにも 祈りあり ばんげのあきの ふけゆくならむ (注)ばんげ=会津坂下(ばんげ)町 鉄を打て 火と燃ゆ熱き 鉄を打て そこし生(あ)れます やさしさぞある (鉄火家持)安達太良に もみぢ葉散れる 土湯越え はや磐梯に 日も傾きぬ (智恵郎女)あをによし 奈良の大路(おほぢ)は 行きよきに 迂回せよとや 電車の走る (禁忌日本鉄道)風吹かば 吹かれぞ行かむ 雨降らば 濡れにし行かむ 雲も我が友 (雨風の雲持)百重(ももへ)つく ポインセチアの くれなゐの 葉も大輪の 花と咲く朝 (小春日の朝麻呂) うらうらの 春日(はるひ)の窓辺 寄る猫に 淡き色にぞ 花もや咲ける (大伴猫持)初春の 含(ふふ)める梅や こっちゃんの 飽かず作れる 砂の饅頭 (遊砂童女(うさのわらはめ))大雪の ことは知らじな わがふたり ゆらりみなもの ゆれる春なり(偐舟持(にせふなもち)) 熱き茶に 頬ゆるみゆく 囲炉裏端 見やれば間なく 雪なほ降れる (お蔵の郎女) 朝寒を 開きて今し 立たすらむ いさりの船の 見らくしよしも (冬浜郎女(ふゆはまのいらつめ))ほととぎす 鳴き行く方は 磐梯の 山にしあれり 雲立ちなびく (会津家持)我妹子(わぎもこ)の 待ち恋ふらむか 磐梯の 絵は早や夏の 雲しぞ立てる (春飛佐助)雪融けの なづめる道も 朝なれば 濡れにし靴も 春を言ふらし (長靴家持) (注)なづむ=滞る、行き悩む。 雪解けは 道たづたづし にゃんとせむ 雨は降るにゃん 吾(あ)は困るにゃん (会津猫麻呂) (注)たづたづし=心もとない、たどたどしい。枝垂(しだ)るるも さにあらざるも 桜みな 悲しみ越えて 青空に咲け(注)掲載の絵画・写真は全てひろろさんのブログからの転載です。
2011.04.14
コメント(10)
-

囲碁相変わらず不調
本日は梅田スカイビルでの囲碁の例会の日。前々回はMTBで行ったが、前回同様、今回もトレンクルで出掛けました。朝10時5分自宅を出発。先週の水曜日(6日)も、大阪城の桜はほぼ満開で花見の人で賑っていたが、今日は更に花は華やかさを益している感じで、やはり花見の人がをちこちにブルーシートを広げていました。(大阪城の枝垂れ桜) いつもの昼食場所の喫茶店「アポロ・カフェ」でランチと珈琲。12時10分、少し早いが昼食も済んだので、スカイビルの囲碁の部屋へ。小生の目論見では、折りたたんだトレンクルを部屋に置いて、他のメンバーが来るまでの間に阪急梅田にある紀伊国屋書店に行くべしであったのだが、すでに青○氏が来られていて、早速一局を、ということになった。仕方がないので、お相手をする。優勢に進んでいたが、終盤で逆転され負け。対局中に竹○氏、福○氏、平○氏も来られ、小生含めて本日の出席者は5名。 続いて、平○氏と対戦し、これも負け。気分転換に席を外し、紀伊国屋書店に行って買い物を済ませて来る。帰って来て福○氏と2局対戦するが、1勝1敗で、都合1勝3敗と今日も駄目でありました(笑)。 囲碁はこの処さっぱりなので、梅田スカイビルの空中庭園でも宣伝して置くことにします(笑)。下をクリックして、空中庭園の360度展望をお楽しみ下さい。昼間と夜景の両方がありますので、夜昼を選択してご覧下さい。 空中庭園からの展望 梅田スカイビル
2011.04.13
コメント(8)
-

偐万葉・木の花桜篇(その12)
偐万葉・木の花桜篇(その12) 本日は偐万葉シリーズ第100弾、木の花桜篇(その12)であります。 <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇はコチラからどうぞ。 木の花桜さんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持が木花桜姫に贈りて詠める歌19首 並びに木花桜姫の返せる歌5首じんちゃうげ いづくさくらむ はるのよの まどべのかぜは そよりとふきぬはくもくれん しろきほのほと さきもゆる はるのあさひの またるこのごろ紫の 濃き色に咲く 春花の ビオラも目覚む 啓蟄の朝 (吉備虫麻呂) 木花桜姫の返せる歌夕ぐれの 小雨に濡るる 花ありて いたくな降りそ 散らまくの惜し ナナホシも 今は節電 桜子の 庭歩き行く 飛ばずありける (七星点灯麻呂)店頭の 品消えゆくを をこなりと 見つつ七星 身ひとつ行ける (七星店頭麻呂) (注)をこ=おろかなこと、ばかげたこと、馬鹿。桜子の 祈りそ届く みちのくの 人にし桜 ほどなく咲かめ (桜郎女) いまだ見ぬ 実を見が欲しと 山茱萸(さんしゅゆ)の 黄金(こがね)の花に 秋恋ふわれは (偐家待(げんやかまち))チューリップの 花も仏の 好むとや 間(あひだ)掻き分け 咲くホトケノザ 木花桜姫の返せる歌野に咲ける 花を手折りて み仏に 蓮座つくりて 供へまつらむ 木花桜姫の追和せる歌花園の 夕べの雲の 惑ひをり 帰らぬ人の 風の音聞こゆ 上は偐家持の次の歌に追和せるにてあり。 かなしみを とどむすべなみ みかんいろ したるゆふひに ねのみしなかゆアネモネは 咲けど北風 ヒヤシンス 星のハナニラ 空クロッカス (四面楚花)智麻呂の 家にもありし ハナニラは ダビデの星に 似たる花かも (花韮星麻呂) またや来(こ)む 交野(かたの)が原の さくら見に 咲ける盛りも 散りぬるのちも (偐俊成)(元歌)またや見む 交野(かたの)の御野(みの)の さくら狩 花の雪散る 春のあけぼの (藤原俊成)みぢのぐの なゐを泣くらし 春さへも 吉備のはだれの 庭にぞ落(ふ)れば (注)はだれ=まだら雪春や春 吉備にし泣くは よかれども 吾妻(あづま)から先 笑みし忘るな 木花桜姫の返せる歌なゐよりは かたみの袖を 求めつつ 今日降る雪を あはれはかなみ (注)なゐ=地震 不安満つ 世をば知りてか 黄水仙(きすいせん) 角に移りて 避難路確保 (四方見麻呂(よものみまろ)) 木花桜姫の贈り来れる歌若人に 負けじと駆ける 鶴見野の 胸のときめき 恋にはあらねど (息切れのフォスター) 偐家持の返せる歌老いたるも 老いぼれはせぬ 言(こと)立(だ)てて 千歳(ちとせ)過ぎたる 走りや見せむ (ネタ切れの無謀家持) (注)言立て=口に出して言うこと。揚言、誓言横顔を 見せてアネモネ 流し眼の もっとお寄りと 君の言ふまで (裕次郎) 桜花 咲きてひとみな あらたなる 旅に立つらむ 今日をよき日に桃園に まぎれて一木(いちぼく) 咲く梨花(りか)の しるくもわれは 恋ひつつあらむ (冠ただす麻呂) 追ひ払ふ 人もしなくば 野良たちも なつき来たりて にゃあとや言はむ (野良にゃ~麻呂)(注)掲載の写真は全て木の花桜さんのブログからの転載です。
2011.04.12
コメント(4)
-

花は~花は河内の朝桜・若草読書会お花見
東日本大震災から今日で1カ月。 思えば1カ月前のこの日午後2時46分、突如その悪夢は我々を襲った。 もう1カ月、まだ1カ月。遅々として進まぬ災害復旧。被災地の辛い日々は続いている。そして打ち続く余震。今日も震度6弱の強い余震があった。 この1カ月我々は色んなことを考えさせられ、感じさせられた。大津波の前に我々は如何に無力であったかを思い知らされたし、原子力発電に依拠していることの危うさも思い知らされた。安全神話という言葉通りに、それは人間が作った神話・伝説に過ぎなかった。或る想定に基づく一定条件を前提として、安全であると言うものに過ぎなかった。普通こういうのは「仮説」と言うのだが、色んな局面で我々はこのような「仮説」を絶対のものであるかのようにして安心しているに過ぎないということがあるのでしょうな。 散る桜 のこる桜も 散る桜、であります。 さて、若草読書会お花見の続編であります。 前回は猫と戯れて居りましたが、今回は「朝日に匂ふ山桜花」ならぬ「朝日に匂ふ河内桜」であります。 お花見の場所取り担当ヤカモチが場所を確保したのは朝5時半になるかならぬ頃、未だ日の出前でありました。花見の花園中央公園は生駒山の西麓にて、東に山があるので日の出が遅い。(花見場所のシートに寝そべって見上げるとこんな眺め)(生駒山の山の端は赤く染まり日の出を待っている。)(花園中央公園の桜) 朝鴉が鳴いて、桜の花も静かに目覚めゆくかのよう。(同上)(これはソメイヨシノではなくオオシマザクラですかな。)(午前6時18分、山の端に日が昇る。)朝(あさ)烏(がらす) 鳴き行くほかに 音もなく 桜の咲きて 日は射し始(そ)めぬ (偐家持) 日が昇ると桜花たちは一斉に輝き、われに笑みをくれる。(朝日に匂う桜花)はなびらの うすきくれなゐ やはらかに 朝日昇り来(く) 生駒山の端(は) (偐家持)(朝日受け花も目覚めぬ・・)(夜桜は妖艶、朝日桜はすがすがしく、ただひたすらに美しい。) 朝日に匂ふ桜花の美しさを堪能する。 この花を見よ。この花を見よ。この花こそ、朝日に匂ふ桜花なり。 場所取り当番のお陰でこのように美しい花を見ることができたことは感謝すべきことであります。 そしてこの後に野良猫たちとの出会い(前回記事参照)があったのでした。 朝日は桜花だけでなく、全てのものを均しく照らす。それに応えて輝くか否かはそのもの次第なのだ。 樫の新芽も輝いている。(これは白樫だろうか。新芽が朝日に輝いている。) クヌギの青葉もさみどりに輝き、桜の花との対比が美しい。(クヌギの青葉) クヌギたちも今は花の盛りなのだが、これに目を向ける人はいない。今回はヤカモチもクヌギのあの房状の花は写真に撮らなかった。 桜を尻目にクヌギの花見をして他から危ない人と気味悪がられるのも一興かも(笑)。しかし、若草の友人諸賢には即却下されることでしょうな。 そんなことを思っていると携帯電話が鳴った。東京のリチ女さんからだ。今回は欠席なので、智麻呂氏ほか皆さまに宜しくお伝え下さいとのこと。 それから約2時間経過して10時15分偐山頭火氏がMTBで到着。やがて智麻呂ご夫妻、東京からの祥麻呂氏が到着。続いて凡鬼・景郎女ご夫妻が到着。その後直ぐに謙麻呂氏到着。最後に、小万知さんと槇麻呂氏が到着し、出席予定者全員揃い、お花見の開始と相成りました。 ヤカモチは5時間以上も花見を堪能した後なので、花見の宴に入ると、景郎女さんがご用意下さったヤカモチ弁当をひたすらぱくついていたのでありました(笑)。話題はやはり地震・津波、大震災のこと、原発事故のこと、被災地・被災者のことが中心で「雅な」とは参りませなんだ。(タンポポ) 智麻呂さんがスケッチされていたタンポポ。偶然小生が場所取りの間に写真に撮っていました。 お花見終了後、花園公園を散策。海棠やモクレンの花も愛でた後ブラブラ歩いて智麻呂邸まで帰る。智麻呂邸では続編・二次会のたこ焼きパーティ。作った和歌のある人はそれを提出して戴く。やはり震災関連の歌が多い。これは追って若草歌集としてまとめ、河内温泉大学図書館で公開することといたします。(花園中央公園桜広場のお花見風景。我々グループは奥の方です。)(前編)われ待ちわびて猫とたはむる・若草読書会お花見<追記・注>「タンポポ」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月7日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.11
コメント(6)
-

われ待ちわびて猫とたはむる・若草読書会お花見
本日は若草読書会のお花見。 一昨年から始めたお花見会であるが、場所取りは諸般事情により、けん家持の担当となっている。場所取りもなかなか競争が激しく、朝早くに行かないと希望する場所が確保できる保証がない。前夜から木の間にテープや紐を差し渡して場所を取ってしまうグループもある。 小生としては前夜からテープなどで場所を確保するのは、何やらアンフェアな気がして、あくまで早朝に人間が行ってシートをその場に敷いて誰かが番をするというのが正道であるという、妙なこだわりがあるので、早起きをして出掛けることにしている。 今年も朝5時に起床。MTBで現地に5時25分到着。シートを広げ、場所を確保してから、そこでパンと珈琲で朝食をとる。集合時間の11時までの5時間半そこで留守番をするのである(実際には、誰かが少し早く来てくれるので一人で居る時間はもう少し短い。今回も偐山頭火氏がMTBで10時15分に来てくれたので、一人で居た時間は4時間50分であった。<笑>)。 それでも、5時間近く、一定の場所に一人なすこともなく拘束されるというのは、かなり忍耐の要る苦行である。従って、桜を写真に撮ったり、携帯に思い付いた和歌を打ち込んだり、お茶やコーヒーを呑んだり、周辺を徘徊したり、同じように場所取りに来た人に話しかけたり、果ては、そのシートを敷くお手伝いをしたり、と何かをして気分を紛わせようとするのであるが、今回は何故か野良猫君たちに気に入られて、彼らと長らく遊んで貰ったのであった。(シート敷き終えて場所取り完了。) もっとも、上の写真は6時34分撮影であるから、場所確保から1時間余経過したもので、そろそろ退屈して、あれこれ写真を撮り始めた中の1枚である。 生駒の山の端から朝日が射し始めると桜たちが生き生きと輝きを放ち、景色が一気に「匂う」が如くになる。盛んに「朝日に匂う桜花」を写真に撮っていると、足元に何やらやさしく触れて来るものがある。 見ると猫である。花園中央公園をねぐらとする野良猫集団の一つだろう。数匹が小生の回りに集っている。その中で白黒の猫の毛の色の感じが津軽ご在住のブログ友・童子森の母さん宅の猫である「クー君」に少し似ているのである。それでこの猫の名を「偐クー」とすることにした。この偐クーが特に人懐っこいのであった。 「クー」というのは若草の小万知さん宅のワンちゃんの名(こちらは、正確には「クウ」だ。)でもあるのだが、ここは、猫なので津軽のクーなのである(笑)。(シートに坐ると傍にすり寄って来る「偐クー君」)(「偐クー君」の傍を離れない「寅さん」)(「クロ兵衛」と「偐クー」。自転車の影から「寅さん」が見ている。)(偐クーが見る方へ寅さんも必ず目を向ける。) そのうちに偐クー君は小生の脚の間にちょこんと入ってしまう。 「お前、ちょっと慣れ慣れし過ぎないか?寅さんがヤキモチ焼いてるぞ。」(心配顔の「寅さん」・・男は辛いよ。)(寅さん「どうするかなあ・・。」と思案顔。)(マイペース。知らぬ顔の「クロ兵衛」)(やっぱり気になる「寅さん」)(そろそろと近付いて来る「寅さん」)(寅さん「クー、俺はそろそろ行くぜ。」)花園の 桜の下の 場所取りに われ待ちわびて 猫とたはむる (猫川啄木)なすことも なかり花見の 席取りは 野良と仲良く なるのほかなく (大野良猫持) この話を聞いた偐山頭火氏の言いによると、けん家持の生活スタイルが野良たちと共通するものがあるからではないか、とのこと。 お花見レポートなのに、桜が登場しない? そうですな。それは次回にご紹介することとして、ここでひとまず休憩といたします。(続編)花は~、花は河内の朝桜・若草読書会お花見
2011.04.10
コメント(16)
-

東日本大震災関連歌
東北地方太平洋沖地震発生から明後日で1か月になる。この間にブログ友のブログへのコメントや当ブログ掲載歌として作った歌で震災に関連する歌が多くある。重複するがここに纏めて置くこととします。 <2011.3.13.>おほなゐの うばひしいのち みちのくの ひとしおもへば こころぞいたき (注)なゐ=地震おほつなみ うちたほしゆく いへいへの ひとつひとつに ありししあはせちのかみの いかなおもひか きまぐれか などてねこそぎ うばひてゆけるあくしんの つかひなるかや おほつなみ たはたもいへも いましのみゆくひとびとは いづちきえにし あとかたも なくなりにける まちのかなしきいまはもや がれきのやまと なるまちを ゆくひとかなし つまこよぶこゑちちははも つまこもうばひ なにごとも なきかをのうみ そこしうらめしみのひとつ あればよしとし おもへかし なきてののちは まけずあゆまなよりそひて ともにぞいきむ みちのくの ひとにしわれも なすべきなさめ <2011.3.14.>うらうらに 春日(はるひ)は照れど みちのくの ことし思へば 胸ぞふたげる <2011.3.17.>あは雪の ほどろに降り来(く) 避難所に 身を寄す人の いかにかあらむみちのくの 野にこそ咲けや つぼすみれ 寒き朝風 雪さへ降れどレヴィアタン 海ゆ来たりて 町潰(つひ)え 怨嗟と祈りの 空に雪舞ふ福島の レヴィアタンなり な目覚めそ 今し闘ふ 人ぞ雄々しき今ひとつ レヴィアタンあり 円買ひの 貪欲なれる 獣(けもの)にしあり (注)レヴィアタン(リヴァイアサン)=旧約聖書(ヨブ記など)に出て来る怪物青葉なる 杜の都は 我妹子の 若き日の街 いざ立ためやもみちのくの ひとにしとどく わぎもこの やさしきおもひ うみしへだつもつぼみても 朝にはまたも オキザリス こりずや咲かむ ひともかくあれ <2011.3.18.>ナナホシも 今は節電 桜子の 庭歩き行く 飛ばずありける (七星点灯麻呂)店頭の 品消えゆくを をこなりと 見つつ七星 身ひとつ行ける (七星店頭麻呂)青柳の 糸染めかくる 春風を 包み届けむ みちのくの地へ <2011.3.19.>ユキヤナギ 咲きぬるなへに 春風の やはらにそより かの地にも吹けみちのくに きみしうゑけむ うめのきの めぶきてはるは いまそこしあり <2011.3.20.>おだやかな 日々うばはれし ひとびとの ありうらうらの はるひもかなし言の葉の 雨もやさしみ 寄り添はな 人の心の みな美しき桜子の 祈りそ届く みちのくの 人にし桜 ほどなく咲かめ (桜郎女) <2011.3.21.>凪ぎて今 青き海には 木綿(ゆふ)の花 泣けと咲くらむ 帰らぬ人の白たへの 花は我妹の 祈りにて 悲しき人に 添ひてやもがもGAMBATTE うみのかなたゆ とものこゑ さはにしあれり なゐにな負けそしくしくに 糸引く雨の 音なきは 道行く人の 涙なるらし <2011.4.22.>夕風の 寒けく吹けば() 白木蓮 地震(なゐ)に失(う)せにし 御魂(たま)かとぞ見ゆ我背子は 今は深山(みやま)の 土佐水木(とさみづき) 咲ける山道(やまぢ)の いづちや行かむ妹と見し 去年(こぞ)の春野の 猫柳 芽吹く今年は ひとりかも見む寄り添ひて あるらむものを 木瓜の花 誰し散らして 離さうべきやかなしみを とどむすべなみ みかんいろ したるゆふひに ねのみしなかゆ今はただ 心おきなく 泣かれよと 蜜柑の色の 夕日の言へる <2011.3.25.>みちのくの 人にぞ添はな 月明かり 世界の人と われも灯(ひ)消さむ福寿草 今し咲きたり みちのくの 春の楊(やなぎ)も あすは萌ゆらむ我妹子(わぎもこ)は いづちゆかめや 春の雪の 摘みにしなづな 野辺にそ咲けるつねならば 吾(あ)に摘むなづな いちしるく 野辺にそ咲ける きみしまさねば吾子(あこ)がため グレープフルーツ 剥(む)く指に キッと力(ちから)を 明日(あす)へと込めむ悲しめる 人にし添へや 野辺こそは 土筆(つくし)ぞ萌える 春にしあれば <2011.3.27.>みぢのぐの なゐを泣くらし 春さへも 吉備のはだれの 庭にぞ落(ふ)れば春や春 吉備にし泣くは よかれども 吾妻(あづま)から先 笑みし忘るな <2011.3.30.>流されし ひとのみたまの かへり来て 槻のほつ枝に 芽吹くにあらば (祈家持)不安満つ 世をば知りてか 黄水仙 角に移りて 避難路確保 (四方見麻呂)タイにては 助けたいとや 象もまた 我らにくれる 力のあれる (象潟夫人)いのちある ものみな生きよ われらみな ともにし今を 地球にあれば (Same Boat) <2011.4.1.>来(こ)し道は 青き野にあり いちしるく 何そ津波の 流さうべしや (偐山魁夷) <2011.4.4.>基督の 花にしあるか 道の辺に 咲きてハナニラ われに憩へと (韮麻呂) <2011.4.7.>なぬなぬと ナノも読むらし 被災犬 救はれ安堵の 春の知らせは (ナノ麻呂) <2011.4.8.>火の玉の 上に生(お)ひたる 葦黴の もろきにわれら 生きるとぞ知るされば今 腰ひきからげ をのこらの ごとに身をなし 神の声聴かななゐの神 何をしなすや 春たけて 咲かすも神ぞ 行かめ花遍路 計54首(今日の花園公園の桜)
2011.04.09
コメント(6)
-

銀輪花遍路(その6)・海棠
銀輪花逍遥は昨日で一段落と申し上げましたので、本日は「銀輪花遍路」といたします(笑)。花園中央公園に咲くカイドウの花をブログに掲載したくなったからであります。 とは言え、花逍遥は一段落と宣言したばかりなので困ったな、と思っていたら、「銀輪花遍路」というのがありました。「花遍路」と「花逍遥」、どう使い分けているのかと検討してみましたが、さしたる違いもこれなく、命名したヤカモチ自身が区別できない有様です(笑)。これに「花散歩」「花暦」も加えるといよいよ混沌でありますな。火の玉の 上に生ひたる 葦黴の もろきにわれら 生きるとぞ知る (偐家持)されば今 腰ひきからげ をのこらの ごとに身をなし 神の声聴かな (偐家持)なゐの神 何をしなすや 春たけて 咲かすも神ぞ 行かめ花遍路 (偐家持) 昨夜また大きな余震がありましたが、ヤカモチはめげずと言うか、懲りずと言うか、花遍路であります。 かくして行かむ、銀輪花遍路(その6)・海棠、であります。(モクレン 1) これは花園中央公園のモクレンです。 木がまだ小振りですが、花は一人前に咲いています。ハクモクレンはヤカモチの好きな花であるがモクレンは必ずしもそうではない。しかし、このモクレンは色がやや淡く、ヤカモチの好みに合致していました。 モクレンとハクモクレンの交雑種であるサラサモクレンという品種かも知れない。<参考>モクレン(木蓮)(モクレン 2) さて、カイドウです。 花園中央公園の北端の一角に数本のカイドウの木があるのだが、今日見ると2本を除き、枝が切り払われていた。公園の管理者が剪定したものか、誰か心ない人が花枝を摘み取ったのか、定かではありませぬが、花が見当たらない。うち1本は下枝の一つが根元から折れて股裂きのような痛々しい姿。 まあ2本だけは花を一杯に付けて事なきを得ているので、ひとまず安堵いたしました。(カイドウ 1)(カイドウ 2) 日の光に透かして見るカイドウの花はひと際美しい。桜に負けてはいないのである。<参考>カイドウ(海棠)(カイドウ 3) 足許に目をやると、カラスノエンドウが同じピンクの花を付けて、「われをもな忘れそ」と言っているようなので、撮ってあげることにいたしました。<参考>カラスノエンドウ(烏野豌豆)(カラスノエンドウ 1) カラスノエンドウは「カラス・ノエンドウ(烏・野豌豆)」なのですな。小生は長らく「カラス・ノ・エンドウ(烏の豌豆)」だと思っていました(笑)。(カラスノエンドウ 2) よく似た色合いの花が続きましたのでお色直しとします。恩智川沿いの道にあるクチナシの木々の新芽です。花にはあらねど照る日に輝いて花のようにも見える。<参考>クチナシ(梔子)(クチナシの新芽 1)(クチナシの新芽 2) 次はクスノキの花です。新芽の中心部に花の蕾が顔を覗かせている。5月から6月には小さな白い花が房状に咲くのであるが、遠目には余り花らしくない。 クスノキは防虫成分を含む木だから、花を咲かせても虫は寄り付かないだろう。してみれば、派手な花は不必要。申し訳程度に花もどきを付けて「お茶を濁している」のですかな。 いずれ咲きましたらまた写真に撮ってみることといたしましょう。<参考>クスノキ(楠)(クスノキの新芽) この新芽が開くと、若葉の中心に花の卵が準備されている。何か虫の羽化を連想させる。(クスノキの花の蕾) 調べてみると、クスノキの花、既に紹介していました。 参照=銀輪花暦(2009年5月26日)<追記・注>「カラスノエンドウ1」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月7日これを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.08
コメント(6)
-

銀輪花逍遥(その8)・大阪城の桜
昨日6日は囲碁の例会で梅田までトレンクルで出掛けましたが、途中大阪城公園の桜を少しばかり楽しんでまいりました。かくて銀輪花逍遥であります。 4日の深北緑地と星田妙見の桜、5日の石川畔の桜に続く桜銀輪花逍遥の第3弾、大阪城の桜です。3日連続の銀輪花逍遥もこれで一段落とします。世の中に 絶えて桜の なかりせば 春の心は のどけからまし (在原業平 古今和歌集53)ではありませぬが、ヤカモチも桜を追いかけてこの3日間心せわしいことでありました。これで銀輪散歩コースの桜は北・南・西を一応網羅したので、ひとまず一段落という訳です。 大阪城の桜は今まさに満開。多くの花見客の姿が見られました。それにしても、桜とお城・お堀は何故かよく似合う。(大阪城の桜 1)もののふの 夢見のあとや 花越しに 城は見るべき ものにしあらむ (偐家持)(大阪城の桜 2)(大阪城の桜 3)咲くもよし 散るもよかりき 桜花 ひともかくしぞ 生きめといふや (偐家持)(大阪城の桜 4) ここにアップしたのは朝11時半頃の写真ですが、帰路の5時頃にも花見の人が多く居ました。これは夜桜を楽しもうという人たちが集まって来ているのでしょうな。(大阪城の桜 5)(大阪城の桜 6)桜花 今し盛りと 咲くなれば 寄りてたぐひて 見せむ妹がも (偐家持)(大阪城の桜 7) さて、以下は囲碁を終えての帰途のこととなります。 いつもの道から少し外れて走っていたら、以前に立ち寄ったことのある仲村神社の前に出た。ここでしばし煙草休憩。(仲村神社・鳥居) 上の鳥居の写真と下の本殿の写真は、この日撮ったものではなく、去年の6月9日撮影のものです。ブログ未掲載なので、ここで利用することとします。(仲村神社・本殿) 仲村神社は、延長5年(927)創始にて、延喜式巻9の神名帳に「河内の国、若江郡、中村神社」と、その名が見える古い神社である。 祭神は己己都牟須(こことむす)比(びの)命(みこと)(興台産霊命とも書く。)である。中村連氏の氏神として奉祭されたのがこの神社の始まりという。己己都牟須比命は天兒屋根命(あめのこやねのみこと)の親であるから、天兒屋根命を祭神とする枚岡神社や春日大社とは親戚みたいなものですな。天兒屋根命を祖とする藤原氏、中臣氏と同じく、中村連氏も天兒屋根命から分れた氏族である。(菱沢池・・これは昨日撮影です。) この神社は、「疱瘡(ほうそう)を病める者祈願すれば験(しるし)あり」とされ、正徳4年(1416)には、蜂須賀候家臣の陶山(すやま)与一左衛門長之、水谷平右衛門勝政より疱瘡全快の謝恩として鳥居が贈られているとのこと。 伝承では祈願をするに当たっては、先ず大和川(菱江川)で斎戒沐浴し、川瀬の祓いを行う。次に社殿軒下の雨だれの砂を頂き、これを袋に入れて腰に下げてお守りとする、とのこと。 大和川の付け替え後は境内の菱沢池で祓いを受けたそうだが、そのような風習も大正時代には姿を消したとのこと。 菱沢池は今も境内にあるが、空池で水がない。水神さんは何処に潜んでおられるのやら。
2011.04.07
コメント(6)
-

銀輪花逍遥(その7)・石川の桜
昨日5日は花園中央公園から南へ、石川畔の桜並木や「いかに」と銀輪花逍遥してまいりました。 花園中央公園桜広場の桜はまだこれからです。既にお花見をされている方も散見されますが、ちょっと寂しい雰囲気。この土日がピークかな。場所取りが大変かも。昨年は4日に、満開の花の下、ここでお花見をしているから、今年は満開が数日遅くなっているようだ。昨年の日記を見ると朝5時半に到着して場所取りをしたようなので、今年もそれ位に行くことと致しましょう。 <参考>若草読書会2010年お花見(2010年4月5日)(4月5日現在の花園の桜)(花見客もチラホラ) ラグビー場の方に回ると、こちらの方が開花が進んでいる。(花園ラグビー場前の桜) ラグビー場を出て、近鉄東花園駅前の踏み切りを渡り、恩智川沿いのいつもの道に入る。一路南へ。池島弥生橋を渡った処で橋の写真を1枚。(池島弥生橋全景) この橋の向こう側に遊水池公園が広がっている。左に見える水面が恩智川。恩智川が増水するとこの斜面から右側の遊水池に水が流れ込み下流への影響を緩和する仕組みになっている。花園中央公園の一部もこの遊水池公園であり、深北緑地も同様である。 恩智川沿いの道から大和川に出て、橋を渡ると石川沿いの自転車道に入る。ここまで来ると自転車族が沢山走っている。この石川沿いにも桜並木があって花見の人で賑うが、木によってはかなり咲き進んでいるのもあるが全体的には盛りまではもう少し日数を必要とするようだ。(石川畔の桜 1)(石川畔の桜 2)(石川畔の桜 3)(石川畔の桜 4) ここは花の盛りには桜のトンネルのようになるのだが、まだチラホラである。今日今日と 待ちし桜も 石川の 風の寒きや のちに咲くらし (夜寒娘子(よさむのをとめ)) (元歌) 今日今日と わが待つ君は 石川の 貝に交(まじ)りて ありといはずやも (依羅娘子(よさみのをとめ) 万葉集巻2-224)(石川畔の桜 5) 上は土手の桜ではなく、川沿いの民家の庭の桜である。こちらはもう満開で見事に咲き匂っている。(石川畔から二上山を望む。) ここは「延羽の湯」という温泉で、前庭に足湯があるので立ち寄ったが、先客が多数居て満員。諦める。時計を見ると午後4時。自宅を出たのが午後2時と遅かったので、早くもこんな時間。銀輪花逍遥もここまでとし、引き返すことに。来た道をなぞるようにとって返し、花園ラグビー場前広場に着いたのが5時半。しばらく公園内を散策。芽吹いた欅の葉が夕日に照らされて、もみじのように輝いていました。(花園ラグビー場前広場の欅) 前日の星田妙見の桜に続いての石川畔の桜、二日続きの銀輪花逍遥でありました。 <参考>銀輪花逍遥(その6)・星田妙見の桜(2011年4月5日) 今日6日は囲碁の例会にて、梅田スカイビルまで、MTBではなくトレンクルで行って来ました。途中大阪城の桜を愛でて参りましたが、それは明日のアップといたします。 囲碁は青○氏、竹○氏、福○氏、村○氏、荒○氏、平○氏と小生の7名出席。小生の成績は、村○氏と竹○氏に負け、福○氏に勝ち1勝2敗。まだ負け癖が治りませんな(笑)。
2011.04.06
コメント(2)
-

銀輪花逍遥(その6)・星田妙見の桜
昨日4日はMTBで星田妙見宮まで桜目当ての銀輪花逍遥をしてまいりました。今日は、反対方向の南へ走り、石川の桜でもと思っています。 星田妙見宮へ走るのは昨年の12月23日以来のことである。<参考>星田妙見宮万葉歌碑序幕式 今回は少し遠回りになるが深北緑地の桜も見て行くことにする。(深北緑地外周の桜)(同上。レンギョウとユキヤナギが裾を彩る。) 深北緑地から少し北へ行った辺りで外環状道路にお別れし左折、東に向かう。偶々通りがかった四条畷コミュニティセンターの前の歌壇に、このような被災地応援の看板が。(復興がんばれ、の看板。中野町福祉委員会の名が見える。) 府道20号線に出て北へ。JR星田駅の少し先で右に入る。500m程行くと左手に星田公園がある。新宮山八幡跡との標識があったので立ち寄ってみる。(星田公園・新宮山八幡跡) 小高い丘で正面は階段であるが左右にスロープがあるので、右のスロープを自転車で上る。レンギョウとユキヤナギが美しい。(星田公園スロープ道から) 頂上は公園になっていて、新宮山八幡宮の痕跡か鉄製の鳥居がある。その裏の広場では子供たちが遊んでいて、ボーイスカウトのキャンプ場もある。(新宮山八幡跡) 星田公園一帯の丘陵地は新宮山と呼ばれ、山頂には明治の頃まで新宮山八幡宮があったそうな。新宮山と呼ばれる由縁は、天暦3年(949)当時三宅山と呼ばれていたこの地一帯を石清水八幡宮に寄進し、八幡宮の分霊を勧請して祀ったことから、石清水八幡を本宮、こちらを新宮と呼んだことにある。新宮山八幡宮は室町時代には隆盛を極め、文安2年(1445)には六小社を有する大社と宮寺の愛染律院及び六支院が山頂に立ち並んでいたとのこと。その後衰退し、新宮山八幡宮は明治5年(1872)に廃され、星田神社に合祀され、その後愛染律院も廃された。(旗掛け松跡の碑) 慶長20年(1615)の大坂夏の陣にこの地に本陣を置いた徳川家康が軍旗を懸けさせたと伝えられる「旗掛け松」が山上にあったとのことだが、今、碑の傍らにある松はまだ小さくて、その面影を伝えるよすがとは成り得ていない(笑)。100年経ったらまた来てみるか。 更に500m程行き広い舗装道路に出ると道の辺の土手がユキヤナギの花盛り。これはもう大雪ですな。(道の辺のユキヤナギ) ユキヤナギの道を左へ300m程下ると妙見川沿いの道に入る辻がある。そこから、川沿いに500m程上って行くと星田妙見宮である。この川沿いが桜並木となっていて、花見客目当ての屋台の店も数店出ていて(金魚すくいまであった。)、華やいだ雰囲気にさせる。(妙見川沿いの桜。右の舗装道をMTBで上って行きました。)(星田妙見宮。鳥居の左に万葉歌碑が見える。)(妙見川沿いの桜 2)(妙見川沿いの桜 3)またや見む 交野の御野の さくら狩 花の雪散る 春のあけぼの (藤原俊成) この地、交野は水無瀬離宮からも近く、平安貴族たちの狩り場でもあったのでしょうが、桜の名所でもあったのでしょう。しかし、ソメイヨシノは江戸時代に作られた交配種、鎌倉・平安時代には存在しない。 俊成も定家も貫之もそして勿論万葉時代の家持もソメイヨシノは知らない。彼らの眺めた桜風景は現代の桜風景とはかなり違ったものであったでしょうな。まあ、吉野の山桜とか八重桜を想像した方がいいのかも(笑)。 ソメイヨシノばかりでは、という訳で少し下流に並んでいた寒緋桜もご紹介して置きましょう。(妙見川沿いの桜 4) 帰途、妙見川沿いに「小松寺」の案内表示板が目に付いたので立ち寄ってみましたが、新しい建物過ぎて、ヤカモチの好みには合いませぬ。(小松寺) 以上までで下書き保存の状態にして置いたようで、公開措置をせぬまま、銀輪散歩に出掛けてしまったようです。本日5日は南へ走り、石川沿いの桜並木を見て来ましたが、これは明日のアップといたしましょう。<追記・注>「旗掛け松跡の碑」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月7日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.05
コメント(2)
-

第76回智麻呂絵画展
第76回智麻呂絵画展 本日は第76回智麻呂絵画展とします。 もう2~3点作品を仕入れてからと思っていましたが、前回の続きの絵もありますので、作品が6点とやや少ないのですが、開催といたします。(ハナニラ) 上のハナニラと下の野菊のような花は、デイサービスの施設の職員のTさんがお届け下さったものです。前回の絵画展でご紹介の土筆、ムスカリ、ヒメリュウキンカと一緒にお持ち下さったものであります。 ハナニラ(花韮)はユリ科の多年生草本。原産地は南米。別名ベツレヘムの星。葉にはネギやニラに似た匂いがあり、ハナニラと呼ばれる由縁であるが、花には甘い芳香がある。最近は道端でよく見かけるようになった。基督の 花にしあるか 道の辺に 咲きてハナニラ われに憩へと (韮麻呂)(名前不詳) (4月5日追記。この花の名前はノースポールであると、 木の花桜さんからご教授いただきました。) 野菊のようなこの花。名前は不明です。 菊は中国から入って来たものであるが、ヨメナやノジギクなど在来の野菊はそれ以前から日本にあったとされる。万葉歌に登場する「百代草」がそういった野菊(ノジギク)のことであるとされる。もっとも百代草はツユクサ、ヨモギなどとする異説もあるのだが。 死者の国を黄泉の国と言うが、これは黄色の花が咲く泉の水は生命を復活させる水で、ヨミの国は不死の国であり、そこにはその泉があるとされるからである。これはペルシャ起源の神話であるが、これが中国に伝わって菊水伝説となって、日本にも伝わった。菊が葬式の花となったのも死者の甦りを願う気持が根底にあったということでしょう。本来、菊は永遠の命を願い、寿を言祝ぐ花であったのですな。父母(ちちはは)が 殿(との)の後方(しりへ)の 百代草(ももよくさ) 百代( )いでませ わが来るまでは (生玉部足國(いくたまべのたりくに) 巻20-4326) (父母の住む建物の後方に生えている百代草のように百歳まで も元気にいて下さい。私が帰って来るまでは。) 元気に長生きするためには、しっかり食べなくてはなりませんな。 と言う訳で、鮭の燻製などはいかがでしょうか。(燻製) これは偐山頭火さんのお手製の燻製。下が現物の写真ですが、偐家持が撮影した時には、ご覧のようにチーズが1個減っていました。恒郎女様曰く「わたしではありません。」どうやら、智麻呂氏が絵を描き終えた処で一つ食されたようであります(笑)。(燻製写真)(菜の花) 上の菜の花と下のミモザは小万知写真集からのものです。 下のミモザについては、恒郎女様は「バナナチップスみたいでしょ。」と仰っていましたが、確かにそのようにも見える(笑)。(ミモザ)ミモザの絵 何をし思(も)ふや 我妹子(わぎもこ)は バナナのチップに あるやと尋(と)へる (偐智麻呂) 下の絵は深北緑地の寒桜です。当ブログの3月18日の記事でご紹介した寒桜ですが、その掲載写真をベースに絵にされたものです。(寒桜)わが行きを 散らずあり待て 桜花 相見てのちは 散りぬともよし (花園智麻呂) <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~
2011.04.04
コメント(6)
-

墓参と桜散歩
本日は朝から墓参。4月2日は亡くなった娘の誕生日である。命日も月こそ違え2日である。死んだ子の年を数えても意味の無いことであるが、生きていれば35歳になる。 墓参りをしていると、鶯がホーホケキョと美しく鳴いて、春の日が穏やかに射しているのでありました。西の方、大阪市内はぼんやりと春霞の中である。(墓地の楠) 墓地の一番高い場所にある楠の大木。枝打ち払われて、何かオブジェのようでもある。 墓参の後は、うらうらの春日の中、山裾の道を散策。見やればおちこちに桜が咲き始め、足元の野道にはハコベ、イヌノフグリ、タンポポ、ホトケノザ、カラスノエンドウなどが咲いている。 歩いていると暑くなり、上着を脱いで腰に巻き、シャツの袖を肘あたりまで捲り上げて、丁度いい位の春の陽気である。 枚岡梅林までやって来ると、梅はあらかた散ってしまったが、それに代って桜が満開とはゆかぬが五分咲き位で、華やいだ雰囲気を醸していた。(枚岡梅林の桜)(同上)(同上)鶯の 鳴き来や野辺の 桜花 今し咲けるを 見む人もがな (偐家持) 梅林で桜を愛でては「梅」に申し訳ないが、梅林なのに桜があるのだから仕方がない(笑)。梅林からたつみ橋を渡ると枚岡神社の境内に入る。<参考>枚岡梅林(2009年2月21日) 枚岡神社(2008年7月12日) 枚岡神社秋郷祭(2008年10月14日) 枚岡神社秋郷祭2009(2009年10月16日)(枚岡神社本殿)(枚岡神社拝殿)(同上・吊り灯籠) 枚岡神社から枚岡公園へと続くハイキングコースの道の傍らに小さな池がある。最近これの改修工事が行われていたが、やっと終わったようで、以前の荒れ放題の池がこじんまりと整備されてしまった。この池にまつわる話など知らなかったが整備・改修工事で案内説明板も設置され、その記載から今日初めてそれを知りました。(姥ヶ池) 以下は案内説明板記載内容を転写。 この池は昔から「姥が池」と呼ばれていました。それは今をさかのぼること約600年前の出来事「悲しい老婆の身投げ伝説」に由来しています。 その伝説とは、枚岡神社の御神燈の油が毎夜なくなり、火が次から次へと消えていました。妖怪変化の仕業と不気味がられていましたが、その正体をつきとめると、生活に困っていた老婆がこの油を盗んでは売っていたのでした。そのわけを知り、気の毒に思って老婆を釈放してやりました。しかし、人の噂が広まっていたたまれなくなり、老婆は池に身を投げてしまいました。村人は明神の罰が当たったとして誰も同情しませんでした。その後、雨の晩になると池の付近に青白い炎が現れ、村人を悩ましたと伝えられています。 この物語は、井原西鶴の短編話など多くの俳諧、戯曲に「姥が池の姥が火」として登場しています。また、「和漢三才図会」「河内名所鑑」などにも記載されています。 平成23年3月 東大阪市<参考>姥ヶ火・Wikipedia 姥が火・井原西鶴『西鶴諸国ばなし』巻五「身を捨て油壺」より(枚岡公園への桜並木の坂道)(同上) 枚岡公園内の桜も五分から七分咲き、間もなく満開ですな。 レンギョウも今を盛りと黄色い花を咲かせていましたが、そんな中でちょとそれとは違う小さな花を付けたこのような花も。 東石切公園まで歩き、引き返すこととしました。(東石切公園から山を望む。右の峰が元枚岡神社のある神津嶽) 二つ見える峰のうち、右側の峰が神津嶽である。麓にある枚岡神社は始めはこの峰の上にあったとのこと。今も山頂の森の中に小さな祠があり、枚岡神社創始の地の碑がある。孝徳天皇の時代というから、大化の改新の後に山上から麓に遷座したことになる。(神津嶽アップで)<追記・注>「墓地の楠」及び「同上・吊り灯籠」の写真が横倒しの歪んだ画像になっていたので、2020年11月7日これらを復元修正しました。●過去記事の写真が歪んでいたりすること 2020.10.12.
2011.04.02
コメント(8)
-

春や春
一気に春めいて来ました。 今日から4月。 桜も咲き始めました。 けん家持の銀輪散歩の基地ともなっている花園中央公園も木によってはかなり咲いている桜も見られます。(花園中央公園の桜)(同上) 若草読書会では、この10日にこの公園でお花見をする予定になっている。昨年もここでお花見をした。今年は東日本大震災のこともあり、自粛するかという意見もあったが、予定通り行うこととなった。 場所取りはけん家持の担当となっているので、本日はその下見も兼ねて、同公園の桜広場に様子見に立ち寄りました。桜広場の方の桜はまだチラホラで遠目からは花は感じられない(写真下)。丁度10日が見頃になるのかも知れません。今年は被災地の方々に心を寄せてのお花見といたします。(昨年のお花見の場所の桜はやっと開花し始めたばかりです。)春雨に 争ひかねて わが屋前(やど)の 桜の花は 咲き始(そ)めにけり (巻10-1869)(春の雨にあらがいかねて、わが家の桜の花も咲き始めたことだ。)桜花 今そ盛りと 人は云へど われはさぶしも 君としあらねば (大伴池主 巻18-4074)(桜の花は今が盛りだと人は言うけれど、私は寂しい。あなたと一緒で はないので。) 上の大伴池主の歌は大伴家持に贈った歌である。この時、池主は越前国掾であった。隣国同士ということでもあった所為か、越中国守の家持とは盛んに歌を交わしている。 池主は大伴祖父麻呂または大伴牛養の庶子かと言われている。両者は大伴吹負の子であり、吹負は大伴安麻呂(家持の祖父)の父長徳の弟に当るから、家持から見れば、池主は、曾祖父の弟の孫ということになる。 池主は橘奈良麻呂の変で逮捕され、獄死している。 757年の奈良麻呂の変は、橘諸兄の死後、その息子の奈良麻呂が、藤原仲麻呂の専横に不満を持つ分子を集めて、仲麻呂を暗殺し、孝謙天皇を廃し、塩焼王、道祖王、安宿王、黄文王の中から天皇を推戴しようとしたクーデター計画である。 密告により露顕し、443名が処罰される。この事件により、反仲麻呂派は一掃され、仲麻呂が政権第一の座に就く道を開くことになる。 では偐家持も1首。わが花見 十日後(のち)なり 桜姫 あわてず遅れず その日にぞ咲け (偐家持) 公園の別の場所では海棠が蕾を膨らませていました。(花園公園の海棠)(同上)桜花 咲き始(そ)めたれば 海棠(かいだう)も 負けじと蕾 ふくらませたる (偐家持) ついでに、わが家の馬酔木も今を盛りと咲いてもあれば。(わが庭の馬酔木)(同上)磯の上に 生(お)ふる馬酔木(あしび)を 手(た)折(を)らめど 見すべき君が ありと言はなくに (大伯皇女(おほくのひめみこ) 巻2-166) 上の歌は弟の大津皇子が謀反の罪で処刑された後、斎王をしていた伊勢から大和に帰って来て、その死を悲傷み姉の大伯(大来とも書く)皇女が作った歌の一つである。 上の歌とは関係なく、偐家持も1首。妹に恋ふ 花にしあれり わが宿の 馬酔木の花は 今盛りなり (偐家持)
2011.04.01
コメント(4)
全23件 (23件中 1-23件目)
1










