2013年06月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

直越えのこの道にして・南生駒まで(続)
<承前> 昨日の記事は芭蕉の句で終りましたが、その句「菊の香にくらがり登る節句かな」はひょっとすると下のような棚田の風景を眺めながら、道の辺や畔に咲く菊の花を見つつの句であったかも知れません。 この棚田風景は犬養万葉歌碑から少し坂を下った処での写真です。(峠の棚田) 芭蕉は元禄7年(1694年)9月9日、重陽の節句の日に奈良から暗峠越えで大坂に入りますが、彼はこの後、病に臥し亡くなりますから、この暗越えが言わば最後の旅となるという次第。 この時に奈良で作っている彼の句で菊を詠んだものに、下記の句があります。 菊の香や な良には 古き仏達 (笈日記・杉風宛書簡) 菊の香や ならは幾代の 男ぶり (杉風宛書簡) 菊に出て な良と難波は 宵月夜 (笈日記) 梅が「花の兄」と呼ばれるのに対し、菊は一年の最後に咲く花という意味で「花の弟」とも呼ばれる。 しかし、今は未だ6月。兄は去り、弟は未だ姿を現さず、道の辺に見掛けたるは、古代中国四大美女の一人、西施ならぬ合歓の花でありました。(合歓) 合歓の花は万葉にも登場するが、芭蕉の次の一句は有名。象潟や 雨に西施が ねぶの花 (奥の細道)(同上)吾妹子が 形見の合歓木は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも (大伴家持 万葉集巻8-1463) 美女・西施は生きたまま皮袋に入れられて長江に遺棄されるというむごい最後を迎えているが、合歓の花も柄の付いたまま、未だ凋みもしない花が地面に落ちているのをよく見掛ける。鳥がついばむのか、風や雨で花の柄が折れるのか。 花は何やらなまめかしいものを感じさせるが、実の方は、マメ科の木にてもあれば、何ともむさくるしく実用的とでも形容するしかない形姿である。大伴家持さんに申し上げたきことは、実になってもどうかという花もありますよ、ということですかな(笑)。(藤尾町阿弥陀如来立像) ラッキーガーデンへの分岐道から少し下った処に石仏がある。(同上)(同上説明板) 坂を下り切ると龍田川、そして近鉄南生駒駅である。振り返ると越えて来た生駒山が遠くに見えている。防人歌を真似て詠むなら、龍田川 うち出でて見れば 神さぶる 生駒高嶺に 雲ぞたなびく (偐家持)でありますかな。(龍田川と生駒山)(同上)(近鉄生駒線・南生駒駅)(南生駒駅南側の踏切。道は国道308号線である。) 暗峠奈良街道(国道308号線)は、大阪側の登り口から矢田丘陵を越えるまでは、概ねこのような、対向車とのすれ違いにも支障をきたす細い道であり、国道という名に誤魔化されてはいけないのである。 この踏切の一つ北側の踏切を渡った処にある造り酒屋・菊司醸造さんの前に阿波野青畝の句碑がありました。この酒屋さん(駒井家)と青畝とは親戚だと副碑に記載されている。句碑は昭和59年9月9日建立とある。ここでも重陽の節句(菊の節句)でありますな。(阿波野青畝句碑)和を以って 貴ぶために 菊の酒 (青畝)(矢田丘陵) 大阪側から奈良へ行くには、生駒山を越えて、更に矢田丘陵を越えなくてはならない。しかし、この日のヤカモチは不調・注意散漫、大瀬中学の先の南生駒変電所の前で左折して矢田丘陵に向かわなければならないのに、何か他のことを考えてもいたか、既に矢田丘陵を越えたような錯覚があって、そのまま直進して坂を下ってしまいました。気が付けば萩の台の団地の中。何のことはない、折角上った坂であったのに、再び龍田川のレベルまで下りて来てしまったという次第。再度下って来た道を引き返し国道308号線の処まで戻り矢田丘陵へと向かったのであるが、時刻を見ると既に3時45分。これでは、奈良まで行って引き返していると、暗峠まで戻って来る頃には「くらがり」になっているやも知れぬ。という訳で、奈良は次の機会にと諦めて引返すことにした次第。(紫陽花) 行きにはパスした大瀬中学の校門前の万葉歌碑を見て行くことにする。 これも犬養先生揮毫の歌碑である。 歌はまたしても前ページで取り上げた秦間満の歌でありました。(大瀬中学校前の犬養万葉歌碑。背後の山は生駒山。)由布佐礼婆 比具良之伎奈久 伊故麻山 古延弖曽安我久流 伊毛我目乎保里夕されば ひぐらし来鳴く 生駒山 越えてぞ吾が来る 妹が目を欲り (秦間満 万葉集巻15-3589)(同上) 復路は、往路と逆。奈良側からが上りとなり、大阪側が下りとなる。 奈良側の上りでも漕ぐのを諦めて途中から押して上っていると、後からMTBの青年が自転車に乗ったままやって来た。「頑張るねえ。」と声を掛けると笑顔で「まあ、歩いているのと変らない速度ですけどね。」と彼。確かに小生が少し早足で上ると彼の方が後ろになるという具合だから、これはもう自転車乗りの「意地」で乗っている、というようなものだが、その意地を通せる処が素晴らしい(笑)。 そんな彼に携帯電話の着信。彼が通話している間に小生はどんどん先へ。 途中にプラムが熟れ始めている木や小さな実をつけているザクロの木などを写真に撮りながら進む。 暗峠の喫茶店「友遊由」にてコーヒーブレイクしようとしたら、漸く彼が追い付いて来た。彼はそのまま峠の方へ。大阪へと帰って行ったのでしょう。 小生も20分ばかり喫茶店で時間を過ごした後、峠から一気に大阪側への下り坂を駆け下りました。(プラム)(ザクロ)(紫陽花) 締め括りの花は、やはりこの時期は紫陽花ですかな。 上のプラム、ザクロ、アジサイは全て暗峠への奈良側の上り坂で見掛けたもの。ではこれにて直越えの道銀輪散歩完結です。今回もお付き合い下さり有難うございました。
2013.06.30
コメント(6)
-

直越えのこの道にして・南生駒まで
長らくブログの更新を怠っていましたが(と言っても5日間サボっただけですが)、本日は近隣銀輪散歩のテーマでアップすることとします。 久し振りに、山に向かい、くらがり峠を越えて南生駒までの往復の行程。矢田丘陵を越えて奈良までの心算でしたが、途中で左折すべき処を直進してしまい、萩の台の方に下ってしまったので、意気消沈、奈良を諦めて引き返すこととしました。往路も復路も急峻な坂道を上ることとなる山越えの道にて、距離の割にはハードなコース(勿論、急坂は押して上るしかないのでありますが・・)。 このコースは2010年9月16日などに走ったコースと途中までは一緒なので、重複する写真などは省略しました。それぞれの散歩の記事を併せご参照戴くと分かり易いかと存じます。 <参考> 1.暗峠を越えて 2010.9.16. 2.暗峠を越えて(余録) 2010.9.17. 3.暗(くらがり)峠 2009.1.29. 辿る道は国道308号線(暗峠奈良街道)である。枚岡神社の北側から枚岡公園南入口・椋ヶ根橋、豊浦橋などを経て暗峠へと急坂の道を行く。 くらがり峠越えのこの道は平城京と難波・河内を結ぶ最短の道にて、万葉人は「直越えの道」と呼んだ道である。直超(ただこえ)の この道にして おし照るや 難波(なには)の海と 名づけけらしも (神社忌寸老麻呂(かむこそのいみきおゆまろ) 万葉集巻6-977) 先ず、遣新羅使人、秦間満の万葉歌碑と芭蕉の句碑にご挨拶して行くこととする。これらの碑のことは、上記<参考>の「3.暗(くらがり)峠」にも掲載されていますので、ご参照下さい。(歴史の道の碑) この碑の裏面に秦間満の下記歌が記されている。夕されば ひぐらし来鳴く 伊故麻山 越えてぞ吾が来る 妹が目を欲り (万葉集巻15-3589) はしまろ氏は難波津から新羅へと出掛ける前に、大和に居る妻か恋人に逢うために、夕方この道を上って行ったのですな。 小生もそういう状況なら、この急坂も何のそのであるが、そんな女性がこの山の向こうで待ってくれているのでもなければ、ただ、はあはあと息喘がせての苦しいだけの急登である(笑)。 ひぐらしは勿論鳴いていない。その季節ではない。代りにホトトギスが鳴いていました。この方が家持的でよろしい(笑)。(歌碑) そして、すぐ近くに芭蕉の句碑もある。 芭蕉さんは、奈良側から大阪へとこの道を下って来たのですな。(芭蕉句碑) 菊の香に くらがり登る 節句かな 奈良県側からやって来たのなら、この位置では「くらがり登る」ではなく「くらがり下る」でありますから、この句は奈良県側の上り坂の何処かで作ったものと考えるべきでしょうな。 漕いで上るのを諦めて、自転車を押して歩きながら後を振りかえると、男性がMTBを押して上って来るのが目に入った。 彼は、加納地区に在住で、暗峠を奈良側へ少し下った処に住む友人を訪ねるのだと言う。前後になったり、並んだりしながら、峠まで一緒に行く。 語らう内に、彼も小生も同じ年齢であることが分かり、親近感が増す。仕事を止めて未だ2年とのこと。小生は丸7年、8年目に入っているから、隠退生活では、小生の方が5年先輩になる。 仕事を卒業した際に息子さんが自転車(MTB)をプレゼントしてくれたのだそうな。ウォーク歴は古いが自転車は未だ2年そこそこで、大阪城公園や鶴見緑地など銀輪散歩しているが、それ程遠方へは行っていない、とのことであったので、「先輩」として、あれこれのサイクリング・コースをご紹介しながらの「山登り」でありました。(弘法の水と笠塔婆)(同上)(笠塔婆)(同上説明板) 昔、未だ母が若かった頃、近所の奥さん達と一緒に毎朝早起きして、ここまで水を汲みに来ていました。水が美味しいということもあったのでしょうが、彼女の健康法の一つでもあったのでしょう。 しかし、この水も今は飲料には適さなくなってしまったようで、汲みに来る人もいない。 暗峠に到着。ここで、同行のMTB君と別れ、南生駒へと、今度は急坂を一気に下って行く。爽快であるが、ブレーキ掛け続けないとスピードが出過ぎてしまって、少し危険。(峠にある喫茶店「友遊由」から見る南生駒方面) この喫茶店はこれまで何回か利用しているが、この写真は帰途に立ち寄って撮ったものです。帰途、此処まで帰って来た時はもう午後5時半になっていたので、店仕舞をされている処でしたが、声を掛けると、ホットコーヒーはもう無理だがアイスコーヒーならOKだと仰るので、暫し休憩させて戴いたもの。本当は苦いホットコーヒーが飲みたい気分であったのですが・・。(犬養万葉歌碑) そして、犬養万葉歌碑です。 この碑も紹介済みですが再掲載して置きます。 この写真も帰途に撮ったものです。 <参考> 犬養万葉歌碑を訪ねて山越え 2009.8.21.難波津(なにはと)を 漕ぎ出て見れば 神(かむ)さぶる 生駒高嶺に 雲そたなびく (大田部三成(おほたべのみなり) 万葉集巻20-4380)(同上)(くらがり峠碑) 犬養万葉歌碑の近くにある碑ですが、芭蕉に因んだもののよう。大阪側の登り口にあった「菊の香にくらがり登る節句かな」の句碑は此処にあるのが相応しいという気がしますが、こちらには句が刻まれてはいません。 文字数制限一杯です。続きは明日とします。(つづく)
2013.06.29
コメント(6)
-

第121回智麻呂絵画展
第121回智麻呂絵画展 本日は第121回智麻呂絵画展であります。 どうぞ皆さまごゆるりと智麻呂絵画をお楽しみ下さいませ。 今回の作品9点で、これまでに当展覧会に出展・掲載の智麻呂絵画は1070点となりました。<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずはこの季節に相応しい花。クチナシです。 智麻呂邸の前の小さな公園にもこの花が咲いていて、甘くやさしい香を放っています。雨に濡れたる様の清げなるがふたつみつ咲きたるもいとをかし・・でありますが、絵を見ると一つ多い四つが咲いていました。「よつばかり咲きたるもいとをかし」であります(笑)。(クチナシ) みみなし山(耳成山)も、しりなし川(尻無川)も、銀輪散歩したけれど、くちなしの山も川も「まだふみもみず」であります。耳成山の麓には昔、口無しの井戸や目隠し川があったという伝承があるそうだが詳しいことは知らない。 クチナシという名はその果実に由来し、クチナシの実は熟しても割れないため「口無し」と呼ばれたという説があるが、この実を乾燥させて黄色の食品着色料としても利用する(栗きんとん、沢庵など)。静岡県熱川では、赤飯ならぬ黄飯、くちなしの実から出る黄色で米を炊いた、くちなしご飯というものがあるそうな。そう言えば蜜柑ジュースで炊き込んだ蜜柑飯という黄色いご飯もありましたですな。 次はグミの実。先の若草読書会の集りで、小万知さんが自宅庭に生っているのを摘んでお持ち下さったものです。(グミ) グミは子供の頃のご馳走。懐かしい味ですが、これは食べてはならない。智麻呂さんの画材なのである。(パイナップル) パイナップルはどなたがお持ち下さったのかヤカモチ館長の記憶が怪しくなっていますが、これを食べようとする奴は居るまい(笑)。小さい鑑賞用のパイナップルであります。これも面白い絵になりましたね。 次のブーゲンビリアも若草読書会にお持ち下さったものですが、お持ち下さったのは香代女さんです。(ブーゲンビリア) ブーゲンビリアという名は、この花をブラジルで発見したフランスの探検家ブーガンヴィルに由来するとのこと。上の絵でも分かる通り、ピンクの花とも見えるのは包葉という葉で、実際の花はこの葉に取り囲まれるようにして、その中央に小さく咲くのである。(黄色い果物) これは、ヤカモチ館長が持参した枇杷の実と果物たち。 これは食べてもいい(笑)。 長い年月の内に何となくメンバーの行動がそれぞれが一定のパターンに習慣化するようで、小生の場合は、果物を持参するというのがいつの頃よりか「役回り」(笑)のようになっていますな。 この日は美しく箱詰めされた枇杷に心惹かれるものがあって、すっかり馴染みになったいつもの果物店でこれを買い求め、余りのお金で果物の盛り合わせを買ったのでありますが、こちらの方は何が入っていたのか覚えていない。恒郎女さんが小生が持って来たものだと仰っているから、そうなんでしょう。描かれている黄色い面々は、枇杷と夏蜜柑と真桑瓜ですかな。(大阪城の絵ハガキ) これは、和郎女さんから智麻呂ご夫妻に届いた「変形絵ハガキ」記載の大阪城のイラストを見て写生されたものだそうです。 智麻呂さんは車椅子生活なので、室内で花などの絵を描かれることが多く、建物や風景を戸外で写生するということは、なかなかその機会に恵まれないという状況もあって、このようなテーマの絵は珍しいのであります。そんなこともあってか、絵ハガキや写真などで、心に止まるものがあると、花の絵の合間にそれらを絵にされることもあるようです。この大阪城と下の錦織公園はそのような形で生まれた絵であります。(錦織公園) 小万知写真集の写真から、絵にされたものでありますが、この景色は智麻呂氏も実際に少なくとも二度は現地に行ってご覧になっているので、そのような記憶をも重ね合わせて絵にされたものであるのでしょう。(トレニア・コンコロル) これも小万知写真集からの絵です。 花の名が分からなかったので、小万知さんにメールでお尋ねした処、「トレニア・コンカラー」(又はトレニア・コンコロル)だとご教示下さいました。 これも上のブーゲンビリアと同様、人名に由来するもので、こちらは、スウェーデンのトレーンという人物の名に由来するとのことである。 下は、その花名ご教示のメールに添付されていた、小万知さん撮影の「今日のトレニア」であります。サイズを小さくして写真掲載して居りますが、他の写真同様、クリックすると大きいサイズでご覧になれます。すみれみたいな花でありますな。(トレニア・コンコロル<小万知氏撮影>)(ザクロ) これはザクロの花なんでしょうか。ちょっと感じが違うのですが、智麻呂さんが通って居られるデイサービス施設で、同じく其処に通って居られる方のお一人が智麻呂氏への画材としてお持ち下さったもので、その方が「ザクロの花」だと仰っていたようです。 開花が進むとザクロの花もこんな風に見えるのかも知れませんが、小生は当初「カクテル」という名の薔薇の花かと思ってしまいました。しかし、葉の付き方、形状がカクテルのそれのようではありませんので、きっと開花の進んだザクロであるのでしょう(笑)。ウバザクロなどと言うと何処かからブーイングが起こりそうですから、館長は「クチナシ」でいます(笑)。
2013.06.23
コメント(11)
-

青雲会幹事会
本日は大学の同窓会・青雲会の幹事会。来月の青雲会総会を控えての直前の幹事会ということで、小雨の中、出席して参りました。「青雲のたなびく日すら小雨そぼ降る」は新潟の弥彦山であるが、大阪の青雲開かるるこの日も「小雨そぼ降る」でありました(笑)。 幹事を引き受けて十数年になるが、小生が同窓会の役員に引っ張り込んだに等しい同期の黒◎君が今は事務局長をやってくれているので、小生も幹事を辞めることが出来ぬまま今日に至っているという次第。 青雲会交流センターは裁判所の近くにある。青雲会囲碁の会場として、既に何度か当ブログでは紹介済みである。午後6時半からであったが、最寄駅の地下鉄御堂筋線淀屋橋に着いたのは5時20分頃。喫茶店で時間を潰してから行く心算でいたので、予定通りの行動。 地下鉄の駅から地上に出て御堂筋を北へ。土佐堀川に架かる淀屋橋を渡り、大阪市役所の前を過ぎて堂島川に架かる大江橋に差し掛かった処で、前を目がご不自由と見られる男性が白い杖をコツコツ言わせながら、心もとない足取りで歩いて居られるのが目に止まる。丁度退社時間にもかかっていて人の流れは駅へと向かっている。歩道を走って来る自転車もあったりで、その流れと逆行する形で進むのは見ていて何やら危なっかしい感じ。 ちょっと放って置けない気がして、声を掛ける。 「どちらまでいらっしゃいますか?」 「アメリカ領事館の先までです。」 小生は橋を渡って直ぐに右に入った処にある喫茶店に入るべしであったのだが、領事館は直進して少し先まで行かなければならない。しかし、時間にも余裕があり、領事館はそう遠くもないので、 「わたしもその方向に参りますから、ご案内しましょうか?」 「助かります。」 ということで、彼に小生の左腕を取らせ、誘導することとする。 男性は目が不自由になって10年余になるらしいが、全く見えないのではなく、ぼんやりとは見えているらしい。しかし、薄暮の時間帯は、今日はおまけに雨が降っていることもあって、一番見えにくいとのこと。 目的地はと聞くと、蕎麦屋で「なにわ翁」という店だと言う。アメリカ領事館の先の老松通りを右に行った処にあると聞いて、やって来たのだと言う。 「もう治らない病気で、完全に失明するのも時間の問題。少しでも見えている間に行きたい処には行ってみようと思って・・。」と男性。 御堂筋の歩道には点字ブロックがあるが、老松通りはそんなものは無い。目の御不自由な方には歩き辛い道である。そんな道を歩きながら、店の場所も、しかとは分らぬのに、一人で出掛けて来るなんて無茶なのでは、と思ったりもしたが、彼にとっては、目が不自由というのは日常。であれば、それをものともせず出掛けるということをしなければ、日常生活は成り立たない。彼にとってはこれも訓練みたいなものであるのかもしれない。であるならば、小生の親切は「余計なお世話」ということにもなるか、などと思いながら、彼と歩く。 御堂筋と違って老松通りは歩道も狭く、車道と歩道の境目に高さ1m位の金属柱が数m置きに立っていて、彼と並んで歩くのは危なっかしい。小生の背中のザックを持って貰って縦に並んで歩くことにするが、その金属柱に彼が体をぶつけたりしないように気を配らなくてはならない。向かいから来る人にも注意しなくてはならない。なかなかに誘導も大変である。目の不自由な方が安心して歩けるような構造にはなっていないことを、痛切に感じる。日頃はそんなことを考えもしないのであるが、こうして行動を共にすれば、直ぐにそれが体感される。 時には、車椅子を押したりすることも、白い杖を手に、いささか心もとない動きをされている方を見掛けたら声をお掛けして介添えしてみることも、そのようなハンディをお持ちの方の目線で、ものを見る、ものを感じる、ということが出来ることとなるので、いいことだと思う。(なにわ翁) 漸くに、「なにわ翁」と看板表示のある蕎麦屋さんに着く。思ったよりも距離があったので、途中でその在り処を尋ねたりしたものであった。 「はい、着きましたよ。」 「有難うございました。」 彼は店の中に消えて行きました。 彼と別れて時計を見ると5時45分。予定していた馴染みの喫茶店まで引き返し、珈琲。30分足らず休憩してから交流センターに向かう。定刻の少し前にて丁度よい時間。 今年から青雲会会長も三◎氏から野◎氏に引き継がれ、今年の総会は新会長にとって最初の総会。その野◎新会長が議長となって、役員、幹事20名ほどの出席で、幹事会の議事はテキパキと進められ、終了。二次会の懇親会は、大阪駅前第一ビルの地下にある「但馬」という店の一室にて開催。(酒宴 但馬 梅田店)(同上) 写真がピントのずれたものになっていますが、酔っていた訳ではありません。手早くパチリと撮ったらこんな風に写っていたという次第。腕もカメラも悪いのでありました。 副会長の松◎氏が何くれとお世話役をされていましたから、彼の馴染みと言うかお知り合いのお店のよう。 懇親会は大いに盛り上がり、楽しく賑やかなことでありました。中締めは9時を過ぎていました。散会後、大先輩の三◎幹事長が珈琲を、と仰るので同期の黒◎君と小生とがお付き合いすることに。10時を過ぎた処で帰途に。帰宅は11時を20分ほど回っていました。梅雨本番 但馬の梅田 青雲の 集ひのこの日 こさめそぼ降る (偐家持) (本歌) 伊夜彦 おのれ神さび 青雲の 棚引く日すら 小雨そほ降る (万葉集巻16-3883)
2013.06.21
コメント(8)
-

偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その6)
偐万葉・ふぁみキャンパー篇(その6) ようやく梅雨らしいお天気。雨が続いています。銀輪散歩も暫しお休みということで、本日は偐万葉シリーズ第177弾、ふぁみキャンパー篇(その6)と致します。なお、ふぁみり~キャンパー氏は偐万葉に於いては、偐家持の勝手命名にて「越後湯麻呂(えちごのゆまろ)」とお呼びすることと致しております。 <参考>過去の偐万葉・ふぁみキャンパー篇はコチラからどうぞ。 ふぁみり~キャンパー氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が越後湯麻呂に贈りて詠める歌15首柏崎 道はた遠み 赤坂の 山の桜も まだふみを見ず (柏崎・赤坂山公園)猫舌に あらね犬なる われもまた 花よりたこ焼 冷めたるがよし (偐光君) (湯麻呂殿の愛犬、光の君)みやびなる われにしあれど 歌詠まず むやみみやびを 言はぬがみやび (言ワン麻呂)風さそふ 花もよかれど われはまた 団子もよかり 酒なほよかり (偐ふぁみ麻呂) (三条八幡の桜)難波には あるやこの歌碑 コリアンの 街の入口 立つやこの歌碑 (偐王仁) (本歌)難波津に 咲くやこの花 冬籠り 今は春べと 咲くやこの花 (古今和歌集仮名序)さゆり花 いまだ咲かねど ゆり家にて 背子食べぬるか お好み焼きを (司馬喰太郎) (ゆり家のお好み焼き) (注)ゆり家=東大阪市、近鉄小阪駅前にあるお好み焼き屋 替え歌「宍道湖舟唄」 歌:出雲亜紀 お酒はぬるめの 燗もダメ 肴はしじみの 汁でいい しじみは小振りの 方がいい あさりはもとより 好きじゃない しみじみ飲んで しみじみと 残した底の 貝殻が 手元にポロリと こぼれたら 思い出すのさ 宍道湖を ♪ 桐一花(いっか) 咲きて近づく 夏を知る (筆蕪蕉) (元句) 桐一葉(ひとは) 落ちて天下の 秋を知る (片桐且元)安了の 杜にし咲ける 白藤の 花はまた来む 春にかも見む (本歌) 妹が家に 伊久里(いくり)の杜の 藤の花 今来こむ春も 常かくし見む (高安王 万葉集巻17-3952) (八王寺の白藤・安了寺境内)安兵衛は 寝返らざるに 腹立つは 戊辰(つちのえたつ)の 新発田の寝返り (偐継之助)寝返りに 新発田と言ふな 訳あれば あひつはあひつ 庄内ことよ (偐周平) (蒼柴神社・悠久山公園)いかと読む 凧はいかなる 凧なるや 糸切り合へる 三条の空 (偐凧持) (三条凧合戦)姫さゆり 見らくし人の きみひとり ありてやうれし 雪峰の庭 (百合郎女) (本歌)夏の野の 繁みに咲ける 姫百合の 知らえぬ恋は 苦しきものぞ (大伴坂上郎女 万葉集巻8-1500)三条の 人の心は いかなるを 知らにと咲ける 姫小百合花 (四条の人)三条の 花にしあるは くやしかも ここだも咲きぬ 姫さゆり花 (九条の人加茂) (ヒメサユリ)吊舟草(つりふねさう) 樹(こ)の下隠(したがく)り 咲く花の 秋葉の山の みちは恋(こほ)しも (秋葉神社) 雲の海に 浮かみ青める 佐渡の島 (筆蕪蕉) (元句)雲の峰 幾つ崩れて 月の山 (芭蕉) (弥彦山頂から見る佐渡)あをによし 奈良の都に わが背子の ありとし聞けば うれしくもあるか<注>掲載の写真は全てふぁみり~キャンパー氏のブログからの転載 であります。
2013.06.20
コメント(4)
-

同期の紫陽花
本日は、5月31日の日記でも書きましたが(参考:夕々の会)、大学同期の原◎君、広◎君、深◎君、西◎君、水◎君らとの会食でありました。 阪急石橋駅東口改札前で夕方5時の待ち合わせ。小生は4時10分頃に石橋駅到着。早過ぎて当然誰の姿もない。で、駅前の喫茶店に入って本などを読みながら時間潰し。煙草も吸えるので(笑)。(阪急宝塚線石橋駅)(同上・駅前の喫茶店から) 喫茶店は2階にあり、駅改札前の様子がよく見える。この喫茶店は母校に同窓会関連の所用でやって来た折などに何度か立ち寄っている喫茶店である。ここで30分ほど過ごして4時45分に駅前に行くが、誰もまだ来ない。駅ホームの方にばかり気を取られていたが、振り返ると原◎君、深◎君、西◎君、水◎君らの顔。彼らは3時に待ち合わせて母校のキャンパスを散歩して来たらしい。やがて広◎君もやって来た。 水◎君経由で参加すると言って来ていた谷◎君が定刻の5時を過ぎても顔を見せないので、暫く待つが、数分ばかり過ぎた処で、原◎君が予約して置いてくれた店へと移動する。何かアクシデントでもあったかと気にもなったが、電話連絡も付かず、日時を間違ったか、忘れてしまっているのだろうと、諦めることとした次第。 原◎君が手配してくれた店、「かさ家」は駅前の通りの最初の路地を左に入って直ぐの処にあり、徒歩1~2分でもあれば、連絡が入れば直ぐに迎えに行けるということもあって、そのようにしたのでありますが、結局彼は現れませんでした。忘れたか日を間違っているのかも、ですが、来月13日は同窓会総会でもあれば、彼も顔を見せるでしょうから、その時にでも事の次第を尋ねてみることと致しましよう。(かさ家) 8時過ぎに解散。広◎、原◎両君とは駅前で別れ、反対方向の電車に乗る深◎君とはホームで別れ、水◎君、西◎君と小生の3人は梅田行きの電車に。豊中駅で水◎君は下車、十三駅で西◎君は神戸線に乗り換え、小生のみ梅田まで。どうやら小生が一番遠いかも、でしたが、それでも9時半には帰宅でありました。 なお、同期の集りなので、タイトルは「同期の桜」とでもすべきなのでしょうが、予科練でもあるまいに、であり、季節的にも合わないので、「同期の紫陽花」として置きました。その心は、あぢさゐの 八重咲くごとく 八つ代にも いませわがどち 継ぎてぞ相見む (偐家持)(本歌) あぢさゐの 八重咲くごとく 八つ代にを いませわが背子 見つつ偲はむ (橘諸兄 万葉集巻20-4448)であります。<注>今回、5月31日の日記「夕々の会」の記事で、会解散後に喫茶店に立ち寄った中に広◎君の名が抜けていることに気付きました。まあ、遡って訂正する程のことでもありませんので、ここで訂正して置くこととします。
2013.06.18
コメント(10)
-

能登半島・白川郷便り
先日、友人の岬麻呂氏から旅の便りとEメール写真が届いた。(岬麻呂旅便り145) 過日のメールでは、能登を旅行すること、雨晴海岸や高岡市万葉歴史館などにも立ち寄るかも知れない、というようなことであったので、実の処、如何なる旅便りが来るのか、ひそかに楽しみにしていたのだが、雨晴海岸からの立山連峰は雲に遮られて見られず、万葉歴史館は休館日で入場できず・・と残念な報告でありました。 まあ、立山連峰はお天気の所為ですから、これは致し方ないとして、万葉歴史館については休館日などを調べずに行くという辺りはヤカモチ風、さすが小生の友人だけのことはある、と思ったものでありました(笑)。もっとも、岬麻呂氏にとっては、万葉歴史館は小生向けのついでの立ち寄り先にてメインのものではなかったのであれば、さもありなむ、であります。 小生のような銀輪散歩ではなく、レンタカーでの移動でありますから、行動範囲は頗る広範囲。能登半島の先っぽから内陸は県境を越えて白川郷までというものであったようです。同じ「先っぽ」でも、小生は大阪中之島の東西の先っぽですから、これは勝負になりません。 で、折角ご送付戴いた写真なので、ここでそれをご紹介することと致します。(高岡市万葉歴史館) 高岡市万葉歴史館は何回か訪問しているが、小生もこの処はご無沙汰である。調べてみると2007年10月以来だから、7年半以上もご無沙汰していることになる。当ブログにも写真では登場していないようなので、図らずも岬麻呂氏の写真にて初登場ということになる。<参考>高岡市万葉歴史館(同上・前庭の万葉歌碑) 万葉歴史館の前庭にあるのが大伴家持の「二上山之賦」の歌碑。小生が諳んじているいくつかの万葉長歌の一つで、好きな歌の一つでもある。 二上山之賦射(い)水(みず)川 い行き廻(めぐ)れる 玉くしげ 二上(ふたがみ)山は 春花の さける盛に秋の葉の にほへる時に 出で立ちて ふりさけ見れば 神(かむ)からやそこば貴(たふと)き 山からや 見がほしからむ 皇神(すめがみ)の 裾廻(すそみ)の山の渋渓(しぶたに)の 崎の荒磯(ありそ)に 朝なぎに 寄する白波 夕なぎに 満ち来る潮の いや増しに 絶ゆること無く 古(いにしへ)ゆ 今の現(をつつ)に 斯(か)くしこそ見る人ごとに 懸けて偲(しの)はめ (万葉集巻17-3985) 大伴家持は天平18年(746年)6月21日に越中国守になり、天平勝宝3年(751年)7月17日少納言に昇進、同8月5日京へと旅立つまでの5年余を越中で過ごしている。お隣の越前では半年ごとに国守が代わっているのであるから、家持は国守としても有能でよくその職分を果たしたのであったのだろう。(雨晴海岸) 岬麻呂氏は雨晴海岸から立山連峰の雄姿を眺める、というのが旅の目的の一つでもあったようですが、「雲だにも心あらなむ隠さふべしや」で、立山は雲の中。見ること叶わねば、駅前の看板絵の撮影で「懸けて偲はめ」ということであったようです。 雨晴海岸は雨でも晴でもなく「曇り海岸」であったのでしょうか。 雨晴海岸の方は小生、去年6月に訪ねていますな。 <参考>高岡銀輪散歩(その6)(白川郷) そして、白川郷の写真も。今回の旅の写真は上のものだと思うが、秋と冬の写真も添えられてありました。以前の旅のものでしょう。冬の白川郷も是非訪ねて下さい、とありましたが、銀輪家持には白銀の白川郷はちと厳しいですかな。(同上・秋)(同上・冬) 調べてみたら、白川郷を銀輪散歩したのは2009年10月のことでありました。ブログに掲載するタイミングを逸して、未掲載となっていますので、その折の写真なども、岬麻呂さんに便乗して二三掲載して置きます。 兵庫県宝塚市からという自転車旅行の女性二人組に出会ったことを覚えている。 さて、以下はヤカモチ撮影の写真。携帯電話での撮影ですが。(白川郷。上の写真と同じ場所からのものですな。)(屋根の葺き替え工事中のお家もありました。)(明善寺)(白川八幡神社)(鳩谷八幡神社)(長瀬家)(神田家)(和田家)(嘉念坊善俊道場遺跡)(トチの実) (庄川)
2013.06.16
コメント(8)
-

野田藤そして中之島尖端
<承前> 今日は先日(12日)の銀輪散歩の続きと昨日(14日)の銀輪散歩の合作記事であります。 昨日の記事で野田恵美須神社の境内にあった「野田藤」の鉢植えの写真をご紹介いたしましたが、今日はその「野田藤」についての話から始めることとします。(恵美須神社前の道標) 表通りから一歩中に入ると、古い道標や民家の佇まいが昔の町並の雰囲気を偲ばせる玉川4丁目界隈であります。(玉川4丁目付近の民家) この辺りは、昔は淀川の河口部にて、難波八十島と呼ばれていた海辺の地域。漁業が盛んであったことが恵比須神社があることでも偲ばせるが、その海辺の砂州に根付いた藤が松の木などに絡まって繁茂していたようで、野田藤として有名になる。「吉野の桜、野田の藤、高尾の紅葉」と並び称されたという。 いつの頃よりかこの地域は藤原氏の所領となったよう。春日神社が置かれたのも、そういうことであったのですな。鎌倉時代初期の太政大臣西園寺公経が宝剣を奉納したりなどとこの地の春日神社は広大な敷地を備えて隆盛を誇ったようであるが、今は、町角の片隅の小さな祠として「春日神社」「白藤大神」「影藤大神」を残すのみ。 西園寺公経と言えば、百人一首の96番目の歌「花さそふ嵐の庭の雪ならでふりゆくものはわが身なりけり」の歌が思い起こされるが、この人の「野田藤」の歌に次のようなのがある。難波かた 野田の細江を 見渡せば 藤波かかる 花のうきはし(春日神社・野田の藤跡) 玉川コミュニティセンターと新なにわ筋(阪神高速道神戸線)を挟んで向かい側に影藤社、白藤社があり、白藤社から一歩奥に入った処に春日神社と表示の小さな祠があり、其処に「野田の藤跡」と刻された碑が建っている。 戦前まではこの地の春日神社境内に藤の古木が残っていたそうだが、太平洋戦争の空襲で焼失。市街化の進展もあって野田藤は絶滅に瀕していたという。これに危機感を持った人々を中心に野田藤を守護・復活させようとの取組が始まり、野田藤を福島区の花に指定すると共に、行政や地元の方々のご努力によって、野田藤はこの地域各所で着実に甦りつつあるという。あちらこちらに藤棚や藤の鉢植えが見られるのは、そういう地元の皆さんによる「野田藤」再生への取り組みであるのですな。尊い営みであります。 因みに、野田の藤を「ノダフジ」と命名したのは、植物学者として有名な、あの牧野富太郎博士だそうです。(野田の藤跡碑)(戦前の春日神社) 上の説明にある「エスポワール藤」の角の藤棚が下の写真です。(野田藤再生の地道な努力)(白藤大神・白藤社) 堂島川の一番川下の橋が船津橋、その一つ上流、新なにわ筋が通る処に架かっているのが上船津橋、その一つ上のあみだ池筋が通る処の橋が堂島大橋。 その堂島大橋北詰にあるのが下福島公園。この公園の一角に藤庵の庭が再現されている。(藤庵の庭) 藤庵というのは、この地にあった藤家の屋敷のことで、文禄3年(1594年)に秀吉がこの地の藤見物を兼ねて茶会を開いた場所ということであるが、詳しいことは下記の「のだふじの会」のホームページをご参照下さい。 <参考>のだふじの会ホームページ 同上・野田藤の歴史 同上・豊臣秀吉のフジ見物(同上) ここまでは12日の銀輪散歩の写真による記事でした。 以下は、14日の銀輪散歩の写真によるもの。 船津橋まで来たのだから、中之島の頭かお尻かは存じませんが、その先っぽを見て置こうと(笑)。(中之島西側尖端・船津橋側から) これが島の最西端。 上は北側から見たもの。下は南側から見たもの。(同上・端建蔵橋側から)(安治川右岸から中之島尖端を見る。) 奥に見える白い高層ビルは中之島センタービル(NCB)。 小生が未だ若かった頃、このビルに長らく職場があったので、この付近は懐かしい。しかし、中之島の先端(末端)をそれと意識して覗き見るなんてことはありませなんだ(笑)。 因みに、中之島センタービルを我々は中之島尖端ビルと呼んでいたような気もする。 で、最西端を見たからには最東端も見て置こうと、猛暑の中、土佐堀通りを東へとひた走る。(中之島東側尖端・天神橋上から) 最東端の方がスマートですな。 どうやら、中之島は上流に向かって進もうとしている風に見える。 見上げると伊丹空港に着陸しようとしている飛行機。(伊丹空港への着陸体制にある飛行機) 話は戻りますが、中之島の西端の湊橋(新なにわ筋が土佐堀川に架かる橋)の南詰にこんな碑がありました。 副碑を見ると2年前の建立。ブロ友のテラケン氏は宮本輝の大ファン。副碑の氏名に同氏の名があったら面白いと思うが本名を知らないのだから話にならない(笑)。(小説「泥の河」舞台の地碑)(同上・副碑) もう字数制限です。以下は淀屋橋近くでのもの。 趣旨は碑文をお読み下さい。(淀屋の屋敷跡)(淀屋の碑)(同上・碑文)(大坂市長・林市蔵の像)(同上・碑文) -完-
2013.06.15
コメント(2)
-

玉川界隈
<承前> 12日の安治川銀輪散歩、安治川から六軒家川水門へ、の続きですから、今日の記事も12日のことであります。 大阪中央卸売市場の前の道を北に行くと大阪環状線野田駅と地下鉄千日前線玉川駅である。戦国時代にはこの辺りには野田城があったと言われている。織田信長と対立抗争を繰り広げた三好三人衆軍が築城したものである。 織田軍に攻められ苦境にあった野田城の三好三人衆軍であったが、元亀元年(1570年)9月12日、石山本願寺第11世門主・顕如が門徒衆に檄を飛ばし、三好側に立って参戦することを表明、14日には本願寺軍が信長軍に攻撃を仕掛けた。これによって、戦況が一変し、信長は軍を撤退させる。以後、石山合戦と呼ばれる石山本願寺と信長との抗争の幕明けとなった事件である。しかし、それも束の間のことにて、結局は信長の再度の攻撃によって天正4年(1576年)に落城する。信長の手に落ちた野田城は、その後の信長による石山本願寺攻略の重要拠点となっている。 その野田城がこの付近にあったというのである。玉川4丁目交差点付近と極楽寺という寺の門前とに野田城跡の碑が建てられているので、それを見て行くこととする。 <参考>石山合戦・Wikipedia 野田城・福島城の戦い(地下鉄玉川駅付近。後は大阪環状線。) (野田城跡碑・地下鉄玉川2番出口前) (野田城跡碑・極楽寺前)(極楽寺)(同上・本堂)(二十一人討死墓) 極楽寺境内には「二十一人討死墓」がある。実はこの写真は本日(14日)に撮影のものである。12日に撮り忘れたので、本日再度MTBで出掛けて来ました。しかし、今日は寺の門が閉まっていて境内に入れない。 裏の勝手口というか、ご住職さんのお住まいの玄関口というか、そちらに回って、呼び鈴を押して、事情をお話すると、寺のお譲さんか若奥さんと思しき若い女性の方が出て来て下さって、どうぞとご案内戴き、撮影することができました。 墓碑が真新しいので、お尋ねすると、以前のが古くなったので、最近に作り替えたのだと仰る。以前の古い碑は鐘楼の後ろに置いてあると教えて下さったので、それも撮影させて戴いた。(古い墓碑) この野田21人衆の話は、上の野田城での合戦よりも少し古い話になる。 天文2年(1533年)8月9日野田村に布教に訪れた本願寺第10世門主証如上人は、近江の佐々木(六角)定頼の手勢に襲われるのであるが、野田村の門徒衆が証如上人を守護して戦い、証如上人を小船で泉州方面へと脱出させる。この時の戦いで野田の門徒衆21人が戦死する。極楽寺は21人衆墓所に建てられた道場が始まりという。本願寺が東西に分裂した際には野田衆は東本願寺に属し、延宝4年(1674年)に極楽寺という現寺号を称するようになったとのこと。享保2年(1717年)から御坊同様の扱いを受け、野田御坊とも呼ばれる。(証如上人御旧跡と刻まれた灯籠・極楽寺前) 極楽寺から北へ100m程の処にある玉川コミュニティセンターの庭には二十一人討死碑がある。(二十一人討死碑)(同上) こちらの碑は1940年建立であるから、それほど古くもないのであるが、裏面は半分剥離していて、判読不能である。(同上・裏面) 近くに円満寺という寺があり、この寺の門前にも証如上人御由緒と刻まれた灯籠が建っている。 こちらの寺も21人衆の菩提を弔うために建てられた寺で、証如上人より教圓という名を与えられた久左衛門という人物が建てた寺と書いてあるものと、西本願寺派の門徒により享保2年(1717年)に建てられたと書いてあるものもありで、その真偽のほどは小生知る由もない。何れにせよ、こちらは西本願寺派の寺であるが、先程の極楽寺から見て北東の位置にある。 東本願寺の極楽寺が西寄りに、西本願寺の円満寺が東寄りにある、というのも面白いし、寺号も極楽に円満であるから「対立・分裂」とは縁遠い感じで面白いですな。(円満寺)(同上)(証如上人旧跡碑など)(野田村21人討死御由緒)(野田御書・拡大) 円満寺の西側に恵美須神社があったので立ち寄る。(恵美須神社)(同上)(同上)(野田藤再生計画) 境内の奥に野田藤の再生のための鉢植えが並んでいました。 野田藤については、ページ改めることとします。 どうやら制限文字数のようです。(つづく)
2013.06.14
コメント(3)
-

安治川から六軒家川水門へ
<承前> 昨日(12日)の安治川銀輪散歩の続きです。 安治川水門・弁天埠頭から安治川トンネルまで引き返します。安治川隧道(安治川トンネル)は安治川の川底のトンネル。階段またはエレベーターで川底の地下トンネルに降りて対岸に渡れるようになっている。歩行者と自転車専用のトンネルである。 このトンネルを利用するのは、2006年12月23日に友人の偐山頭火さんと渡船廻り銀輪散歩をして以来だから6年半ぶりのこととなる。(安治川トンネル・南側出入り口) 上の写真は、左岸(南側)のエレベーター乗降口。 下の写真は、そのエレベーターで地下に降りて、私達左岸側の者が地下通路に出た後、右岸側からやって来た人達がエレベーターに乗り込んでいる処。結構利用者があります。(同上・地階) 地下通路は冷んやりして気持ちがいい。エレベーターでご一緒になったおばあちゃんと「ここは涼しくていいですね。」などと話ながら歩く。「この辺も随分変りましたね。」とおばあちゃん。「そうですね。」と言ったものの、ヤカモチにはどう変ったのかは勿論分からない。 まあ、行きずりの会話というものは、これでいいのである。話の流れに合せることが第一。でないと事情や訳を説明しなければならなくなり、話の流れを阻害してしまう野暮になる(笑)。(地下通路) 地下通路を歩いていて思い出したのが新潟の海底トンネル。いつ其処(底の洒落ではありません)を走ったかと調べてみたら、2009年9月のことでありました。 <参考>佐渡銀輪行余聞 2009.9.24. 新潟のそれは、車も走る海底トンネルで、長さ、規模の大きさは比べるべくもないのだが、ヒンヤリした空気の感覚でその日の記憶が甦りました。あそこは自転車で走り抜けましたから、此処のように自転車を押して歩かなくてもよいことになっていたのですな。(同上・北側出入口)(同上) 安治川右岸に渡り、川沿いに下流へと走る。1km弱で道は行き止まりとなり、右に曲がると六軒家川に架かる春日出橋。(春日出橋) 橋から六軒家川上流を見ると、ユニバーサルシティ駅に行くJRゆめ咲線(桜島線)の鉄橋が見えている。(春日出橋から六軒家川上流を望む。) 六軒家川は安治川の北側を流れている川で、春日出橋の直ぐ下にある六軒家川水門の先で安治川に合流する。 春日出橋を渡り、六軒家川が合流した安治川右岸を下流へと凡そ2.5km走るとユニバーサルスタジオ・ジャパン(USJ)であるが、今回は其処まで足を延ばしている余裕は無さそうである。(六軒家川水門) 安治川右岸の道に戻り、上流へと引き返す。大阪環状線の鉄橋付近で南方向を見やると高層マンション。何やらキングコングの映画を思い出させる眺めでもある(笑)。(大阪環状線安治川鉄橋付近)(安治川トンネル付近) 上の写真の、安治川トンネルの上に架かる鉄橋は阪神電車と近鉄が相互乗り入れしている阪神西大阪線が通っている。左に行くと西九条、千島、伝法などを経て尼崎へと続き、右に行くと近鉄難波に繋がっている。 安治川トンネルから1kmほど上流に行くと中央卸売市場である。(大坂市中央卸売市場・市場棟)(大阪市中央卸売市場入口) 市場の表に回ってみると上の写真のような眺め。何処から撮影したかと言うと船津橋の北詰。同じ場所でカメラを橋の方に向けると下の写真のような眺め。 船津橋は堂島川に架かる中之島の先っぽに渡る橋。 写真右奥のアーチは端建蔵橋(はたてくらはし)でこれは土佐堀川に架かっている。つまり、土佐堀川と堂島川がこの両橋の繋がった地点で合流しているのであり、合流と同時に南へと流れる木津川と南西へと流れる安治川に分流する。このような場合、何処からが、堂島川、土佐堀川、木津川、安治川なのか、考え出すと頭が混乱するのであるが、船津橋を含み船津橋から上流が堂島川。橋を含まず橋から下流が安治川ということですかな。 その区分に従えば、中央卸売市場は安治川の「最上流」の右岸にあることになる。(船津橋) さて、この後、地下鉄玉川駅近くを少々散策するのですが、それは次回のこととし、本日はここまでとします。(つづく)
2013.06.13
コメント(8)
-

安治川銀輪散歩
本日は囲碁例会。台風がそれたお陰で青空。MTBで銀輪散歩をと朝8時過ぎに家を出る。 今回の目的地は安治川水門。尻無川水門、木津川水門は先日廻ったので、これでアーチ型三水門走破ということになります。 その前に、囲碁例会のことを記して置きます。本日は福◎氏と平◎氏と小生の3名だけの出席。暑さの所為か皆さんご欠席。で、小生は銀輪疲れで集中力を欠いたか、ポカが多くて福◎氏にも平◎氏にも大きく負けて0勝2敗。これで、今年に入ってからの成績は9勝18敗。不調が続く(笑)。 さて、銀輪散歩の方です。前2回は千日前通りから大正橋というコースでしたが、安治川は少し北になるので、中央大通りから本町通りに入り、木津川橋を渡って、直進、安治川に出て、左岸を下流へと向かう、というコースを取りました。 上町筋、谷町筋、松屋町筋、堺筋、御堂筋を越えて、ひたすら西へ。(信濃橋交差点) 四ツ橋筋を越え、なにわ筋、あみだ池筋を越えて新なにわ筋へ。(靭本町3丁目交差点) 新なにわ筋も越えて、直進。木津川を渡る。木津川橋である。(木津川橋の碑)(木津川橋) 木津川橋から上流を見ると、正面に昭和橋。この橋の向こうは土佐堀川で、中之島がそこでオシマイ。中之島の北側を流れている堂島川と合流すると共に、コチラ側・木津川(南へと流れる)とアチラ側・安治川(南西へと流れる)とに分流する。(木津川橋から昭和橋を望む。) 写真正面の高層ビルは、左二つはマンション。右の白いビルが中之島センタービル。関西電力や関経連などが入っている。 木津川橋を渡り、直進すると、直ぐに安治川(左岸)にぶつかる。川沿いに下流へと走る。 程なく、大きな石碑のある三叉路に出る。国津橋である。 河村瑞賢の碑と古川跡の碑が建っている。 詳細は、下の説明板や碑文をお読み戴くとして、要するに、安治川は河村瑞賢によって江戸時代に開削された新川であったのですな。 (河村瑞賢紀功碑) (同・裏面)(同副碑・碑文全訳)(同上・説明板)(古川跡碑)(同上・碑文) 河村瑞賢の碑から500mほど下流に安治川トンネル(安治川隧道)がある。安治川水門を見た後、引き返して来てこのトンネルを使って対岸に渡るので、今は省略。更に600mほど行くと大阪環状線の鉄橋がある。 (大阪環状線・安治川鉄橋・上流側から)(同上・下流側から)(安治川・上流を望む。)(同上・下流を望む。) 安治川の堤防に近づき、下流を覗き見ると水門のアーチが国道43号線・安治川大橋の向こうに見えていた。水門まで、あと600m位である。 その安治川大橋の下から見た水門が下の写真である。(安治川水門)(同上) 安治川水門のアーチの色は赤。尻無川水門のそれが青で、木津川水門のが緑。色を変えているのは川を遡上する船が川を間違えないようにするための工夫でしょうな。(同上)(同上) (木津川水門) (尻無川水門)<参考>「青雲会囲碁・木津川水門など銀輪散歩」 「囲碁例会・大正橋から尻無川銀輪散歩」 水門からさらに先へ、弁天埠頭港緑地公園で少し休憩してから、引き返すこととしました。 途中やり過ごした安治川トンネルを潜って、対岸に出て、ついでに六軒屋川の水門も見て置こうという次第。こちらはアーチ型ではなく普通のスタイルの水門です。(弁天埠頭・関西汽船乗り場) しかし、本日はここまで、続きは明日とします。(つづく)
2013.06.12
コメント(4)
-

土佐稲荷神社
<承前> 昨日の「青雲会囲碁・木津川水門など銀輪散歩」の続きです。 新なにわ筋の下には地下鉄千日前線が走っている。長堀通りと交差する手前が西長堀駅。交差点を左折、西へ。直ぐの処に土佐稲荷神社がある。境内の南側・西側は土佐公園になっている。 MTBで走りながら、昼食の店を探していたのだが、なかなか見つからない。それで、見掛けたお弁当屋さんで「お弁当」を購入。この土佐公園で「お弁当タイム」にしようと考えた次第。木陰の石に腰掛けて、「優雅な」昼食であります(笑)。 折角なので、土佐稲荷神社にご挨拶して行く。(土佐稲荷神社) 下の神社略記にある通り、大阪城築城の際に運ばれて来た石の中に霊験只ならぬものがあり、これをこの地に置いて祀ったのが、この神社の起源であるらしい。航海安全の神として広く信仰を集めたよう。 その後、土佐藩の蔵屋敷がこの地に置かれ、伏見稲荷から分霊を受けて祀るようになったことから土佐稲荷神社と呼ばれるようになる。 三菱の創業者岩崎弥太郎はこの地で事業を起こし、この土佐稲荷を篤く敬い、事業繁栄の守護神とした、とされる。(土佐稲荷神社略記) <参考> 土佐稲荷神社ホームページ 土佐稲荷というと、随分の昔に堺事件のことを書いた本で登場したのが記憶にある。書棚のあちこちを探してみたが、その本は見当たらない。何処かの奥に入ってしまっているのであろう。 堺事件というのは、慶応4年(1868年)2月15日夕刻、堺港から無許可上陸したフランス水兵とこれを阻止しようとした土佐藩士との間に生じた刃傷事件。水兵11名が死傷。 フランス側は賠償と関係した土佐藩士20名の切腹を要求。新政府はこれを呑み、土佐藩士20名の切腹を命じる。 土佐藩邸に蟄居謹慎させられていた関与の藩士は29名であったが、20名という命令であったので、彼らはこの土佐稲荷神社の前で籤を引いて切腹する者20名を決めたという。 切腹は堺市堺区材木町東4丁にある妙国寺にて日仏立会人の面前で行われたが、フランス側立会人がその凄絶な様に堪え切れず、12人目の切腹が行われる前にその中止を求めた、という。 <参考> 妙国寺・Wikipedia(拝殿)(本殿)(東側は道路を挟んでマンション)(西側も道路を挟んでマンション)(神馬) お稲荷さんの使いは狐であるのに、何故か境内には馬です。 廃藩置県で、土佐藩邸の土地建物は岩崎家の所有地となり、岩崎弥太郎はその一画に居を構えたよう。周囲は今はマンションが林立している。そのような地の一つに「岩崎家旧邸跡」の碑が建てられていたようだが、今は土佐稲荷神社の境内地に移設されている。(岩崎家旧邸跡碑)(同上副碑)(兵庫谷源次郎歌碑) 「千代までも くちぬ命と この石を まつる願いは 神もまもらん」と刻まれた歌碑にて、作者で歌碑建立者は兵庫谷源次郎という人物。その曾孫なる人物による副碑によって、その由来などが知れるのであるが、ご両名共にここにて初めてお目にかかるお名前にてあれば、ふむふむ、であります。(同上副碑) 拝殿の西側、奥には其角の句碑がある。 こちらは、芭蕉の門弟の一人。どなたもご存じのお名前ですな。 裏面を見ると嘉永4年3月建立とある。 <参考> 宝井其角・Wikipedia(其角句碑)明星や 桜定めぬ 山かつら 江戸時代から土佐稲荷は桜の名所として親しまれていたらしい。 現在も桜の木が沢山あって、花見が楽しまれているよう。 しかし、近頃のお花見衆はマナーがよくないのか、土佐公園内の随所に「火気・宴会禁止」の立て札が立っている。どうやら筵を延べて飲食しながらの宴会スタイルのお花見は此処では禁止されているようである。(句碑裏面)(同上) ひとしきり土佐神社境内を歩き回った後、新なにわ筋からなにわ筋に移り、靭公園を横切って四ツ橋筋に出て、暫く北に走った後、御堂筋に移り、淀屋橋、大江橋を渡り、裁判所の前の庭に駐輪。囲碁例会の会場となっている青雲会交流センターへ。 丁度入口前で藤◎氏と出会い、一緒に会場へ。こんなことで、小生の最初の対局相手は藤◎氏となった次第。会場の部屋に入ると既に数名の方が来て居られてそれぞれに対局が始まっていました。
2013.06.09
コメント(10)
-

青雲会囲碁・木津川水門など銀輪散歩
本日は大学の同窓会・青雲会の囲碁サークル例会の日。3月以来、久々に参加することとしました。盛会にて10余名の出席。 先ず藤◎氏とお手合わせ。この方には2連敗しているが今回もしてやられて、黒星スタート。次に黒◎氏、五◎氏に勝ち、宮◎氏とは2局して1勝1敗、最後に田◎氏と打って、これは勝ち、ということで今日の成績は4勝2敗でありました。 この囲碁の会は中之島の近く、裁判所の裏手にあるビルの一室を会場に毎月1回行っている。開始は午後1時頃。 ということで、この日も囲碁の前に銀輪散歩をと、朝9時15分にMTB(マウンテンバイク)で家を出る。 行く先は、木津川水門と決めていました。今月5日に尻無川水門に銀輪散歩したので、その続編ということになります。大正橋までは、5日とほぼ同じコースを走りました。 その前に少しエピソードを。 下の写真の自販機に関すること。先日5日に、この自販機で飲み物を買おうと500円硬貨を投入した処、釣銭切れの表示。返却ボタンを押すも反応せず。お金が返って来ない。こういう経験は何度かあるので、早速自販機に表示の連絡先へ電話を入れ、経緯を説明。住所・氏名・電話番号を告げて、後日の返金を求める。 で、昨日、この自販機所有の会社からお金が送られて来ました。500円と電話代50円で550円が返金されて来ました。携帯による電話代は50円もしていないと思うし、電話代を請求した覚えもないのに、であります。 これまで、何度か、このような形で返金して戴いたことがありますが、電話代まで付加されて返金下さったのは、初めてである。 中には、こちらが告げた住所・氏名などの記録メモを紛失したのか、返金して来ない処もあったりしたのに、とても良心的というか、よき心遣いである。 ということで、この自販機で今日も飲み物を買い求めた次第である。こういうことは、金額どうこうではなく気持ちが大切なのでありますな。(布施商店街の自販機) さて、今日は大正橋を渡らず、その手前で木津川沿いに左岸の道を下流(つまり南方向)へと走る。 海抜0mまたはマイナスの地域にて、川は高い堤防が築かれているので、道からは川は見えない。大浪橋の処で、道から階段を上って橋のたもとまで行って、川の様子を眺めてみた。(大浪橋) 大正橋から木津川水門までは1.5km程なのだが、川が右にカーブしているようで、水門の姿は未だ見えない。(大浪橋の上から木津川下流を望む。) やがて、前方に、巨大アーチが見えて来た。(木津川水門) 尻無川水門はアーチ部分もブルーであったが、ここの水門はアーチ部分が緑色で、青と緑の「二色刷り」でありますな(笑)。なかなかの迫力。 ブログ上で少し交流のあるcementman氏がこの水門と同型の安治川水門がある付近のご出身とかで、昨日(7日)の記事に掲載の尻無川水門の写真をご覧になって、「懐かしい」と楽天プロフィールの方にコメントを下さったのですが、今日は安治川水門に回る時間的余裕がありません。次回には此処にも行ってみようかと思っています。(同上・真横から見ると、こんな具合。) 水門から少し下流に渡船場がある。落合上渡船場である。これを利用して対岸に渡り、右岸沿いに大正橋へと戻ることにする。(落合上渡船場) 渡船乗り場から水門がよく見える。道路と同じ扱いにて、乗船料などは不要。自転車もそのまま持ちこみOKである。(同上・対岸に船。こちらへ渡る人を乗せているところ。)(渡船時刻表)(乗船注意事項)(渡し船がやって来ます。)(接岸です。) 船がやって来ました。5~6人の人が降り、我々が乗船する番。こちらから、対岸に渡るのは、小生の他には3名の自転車の女性と1名の若い男性。小生も自転車であるから、5名全員が自転車でありました。男性は、サラリーマン風、自転車でお得意様回りの営業、銀行マンだろうか。船を待つ間もパソコンを開いて何やら作業をしていました。(渡し船の上から見る木津川水門) 3分程度の「船旅」であります。 下船して、今度は反対側。右岸を上流へと走る。大阪環状線大正駅の手前で木津川に架かる鉄橋の下を潜る。丁度、電車が通過したので撮影する。(木津川に架かる大阪環状線の鉄橋) ついでに、大正駅にもご挨拶です。(環状線・大正駅) 大正駅から大正橋を東へ渡り、一つ目の広い通りを左(北)へ行く。新なにわ筋である。 大阪の道は南北に走る道を「筋」と呼び、東西に走る道を「通り」と呼ぶ。ニューヨークのAvenue、Streetの使い分けと同様ですな。小生は「千日前通り」から「新なにわ筋」に入った、という訳である。 直ぐに橋を渡る。汐見橋である。道頓堀川を渡る。 地図によると、汐見橋から下流は、西道頓堀川と何故か名前が変るようですな。(西道頓堀川・汐見橋の上から下流を望む。)(新なにわ筋) 新なにわ筋には、このような自転車専用道があるので、とても走りよい。全ての道もかくありたきものであります。 この後、西長堀で土佐稲荷神社に立ち寄ってから、中之島方面へと向かうのですが・・本日はここまでとします。(つづく) <参考> 「囲碁例会・大正橋から尻無川銀輪散歩」 2013.6.5. 「尻無川水門・花逍遥」 2013.6.7.
2013.06.08
コメント(8)
-

尻無川水門・花逍遥
一昨日の尻無川銀輪散歩の記事で、字数制限の関係で割愛した写真を此処に掲載して置きます。 <参考>囲碁例会・尻無川銀輪散歩 2013.6.5. 先ずは、尻無川防潮水門です。 台風による高潮対策として設置されたアーチ型防潮水門である。アーチが上流側に倒れて川を塞ぐ方式の水門である。船舶の航行が多いので、その航行を妨げないために採られた方式とのことで、同様の水門が安治川(安治川大橋の西100m位の処)と木津川(大正橋の下流1.5km位の処)にもある。 <参考>安治川水門・Wikipedia 大阪の水門を廻って居られる方が居られます。そのお方の ページ「大阪の水門」はコチラからご覧になれます。(尻無川防潮水門) この水門設置工事には悲しい話がある。 1969年11月25日午後7時40分、大水門中央橋脚工事中にケーソンの上部がさく裂、水面下20数mで土砂などの搬出に当っていた11名の作業員の頭上に落下、その下敷きになって全員がお亡くなりになられる、という悲しい事故があった。 その慰霊碑が水門脇に建てられている。(尻無川水門工事事故殉職者慰霊碑) 川底に眠る尊き11の御霊に合掌であります。(同上碑文) さて、話は変って、下はハクサンボクの実。これは、尻無川銀輪散歩の後の囲碁例会の休憩中に散策した、梅田スカイビルの里山で撮影したもの。今年の春、花が固い蕾であった時に写真に撮っていて、花が咲いたらそれも写真にと思っていたのでしたが、うっかり時日を徒過しているうちに、花は全て散り、実になってしまっていたのでありました。(ハクサンボクの実) このハクサンボクの花の蕾の写真は下記の日記ページに掲載されています。 <参考>「さようなら、アポロ・カフェ」 2013.3.13. そして、昨日の散歩で見掛けた白いタチアオイの花です。 夏の日差しへと変って行く季節の、道の辺に咲くこの花が小生は好きである。それは、きっと銀輪散歩の爽快な記憶と観念連合して記憶されている花でもあるからでしょう。先日の墓参で見掛けたタチアオイはピンクと赤であったが、この日、花園公園で見掛けたのは白いタチアオイでした。やはり白い花が一等いい。 <参考> 「墓参・花散歩など」 2013.6.1. (タチアオイ・立葵) <参考>タチアオイ・Wikipedia もっと近くに寄ってみましょう。 タチアオイは別名ホーリーホック(Hollyhock)。この花は12世紀頃に十字軍によってシリアからヨーロッパにもたらされたものであることから、「聖地の花」という意味も込められての名前だそうな。 聖地の花、と呼ぶなら、やはり白い花がそれに相応しい。(同上) タチアオイの近くに咲いていた花はスケトシア。 このような名前をヤカモチが知っている訳もなく、種を明かせば、花の傍らに花名の書いたものがあったのであります。 瑠璃菊という別名もあるようだが、こちらの別名なら覚えられそうではあります(笑)。(スケトシア) <参考> スケトシア(瑠璃菊)(同上)(同上)(同上)
2013.06.07
コメント(4)
-
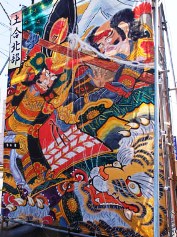
偐万葉・英坊篇(その21)
偐万葉・英坊篇(その21) 本日は、偐万葉シリーズ第176弾。英坊篇・その21であります。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌16首 並びに英麻呂が作れる歌11首百年(ももとせ)を 余り三十年(みそとせ) 言祝(ことほ)ぐと 大門(だいもん)大凧 空駆けるらし(大門凧祭)わが背子に 見せばやとてか はまぐりも 気を吐き海に 塔を建つらし (蜃家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首感激に 身体こころも うち震へ 撮りしカメラの 首尾をば信じ (英麻呂)(魚津海岸の蜃気楼)われはもや 蜃気楼見たり みなひとの 見がてにすとふ 蜃気楼見たり (高岡鎌足) (本歌)われはもや 安見兒得たり 皆人の 得かてにすとふ 安見兒得たり (藤原鎌足 万葉集巻2-95) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首松江城 城歌なくて 可哀そう 船頭唄う 他所の城歌 (英麻呂)来し人は 乗れとや松江 城の堀 めぐる舟人 歌うたひつつ (偐家持)ほととぎす 来鳴きとよもせ わが丘に にほへをとめは 咲き始(そ)めにけり(高岡つつじ公園) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 柏原に 似た風景に 気もゆるみ (英麻呂) つつじの丘に しばしまどろむ (偐家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首万葉と 藩政の面影 あるこの地 しかと伝へて 誇りの町に 偐家持が返せる歌1首古(いにしへ)の 香(かほり)ゆかしき 高岡は つぎて見まくの 欲しき町なりせんかくも ならねばいしの だいせうで かみとほとけの さかひきめにし (越の八一)(寺と神社の境界の石組) 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首行きたけど 路銀のなくは 叶はずで 地図をひがなし 眺め居るわれ (英麻呂)富士京都 国の津々浦々 あるなれど 帯に足らずて 襷に余る (英麻呂)草枕 旅の路銀は 神まかせ まづ立つ若き 日の旅もがな (偐家持)それぞれの 富士も京都も さにてよし 帯も襷も せぬわれなれば (偐家持)雄神川(をかみがは) 大門河原(だいもんかはら)に もののふの 八十(やそ)凧どもの 空に群れ舞ふ (注) 雄神川=庄川の古名。万葉時代の呼称。 英麻呂が贈り来れる歌2首都富士 京よりのぞみ 偲うには 見下ろし湖の 波の静けさ都富士 下りて訪ねし 詩仙堂 時はもみぢて 今はさつきか 偐家持が追和せる歌1首都富士 知る人ぞなき 叡山を 下れば雄琴 近江富士見ゆ (注) 都富士=比叡山のこと。京都側から眺める比叡山をこう呼ぶ。 英麻呂が贈り来れる1首瓜と芋 薩摩に入りて 名が付きし 隼人薩摩の 渡来の実かな 偐家持が返せる歌1首いもが名は 薩摩にあれど 背子がうり その名隼人と いふ訳(わき)知らず 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首笠深く 被りのわりに 顔目立ち 前に下がりし ものはなんダベ (英麻呂)季語もなく ただ目立ちたく 徒に 歌もどき詠む 我ぞ悲しき (英麻呂)笠につく 布は何とも 知らねども 目元涼しき 祭の若衆 (偐家持)思ひ陳(の)ぶ ことが歌にて あるなれば もとより季語は 要らぬものなり (偐家持) 名月に あらね敦賀の 英遊行 (筆蕪蕉) (元句) 月清し 遊行の持てる 砂の上 (松尾芭蕉 「奥の細道」)(気比神社芭蕉像と句碑)家にあれば 椀に盛る飯(いひ)も みやびとて 野辺に手作り 竹筒に盛る (やってみ麻呂) (本歌)家にあれば 笥(け)に盛る飯(いひ)を 草枕 旅にしあれば 椎(しひ)の葉に盛る (有間皇子 万葉集巻2-142)(竹に盛る) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首ならび咲く 淡い紫陽花 いじらしい 母の日の花 ならぬものかよ (英麻呂)母の日は カーネーションと ひとは言へ われあぢさゐの 花とや言はむ (偐家持)(注)掲載の写真は全て英坊3氏のブログからの転載です。
2013.06.06
コメント(4)
-

囲碁例会・大正橋から尻無川銀輪散歩
本日は囲碁例会。出席者は青◎氏、竹◎氏、福◎氏と小生の4名だけ。第1局の青◎氏には勝ったものの、第2局の竹◎氏、第3局の福◎氏には負けて、1勝2敗。本日も今ひとつでありました。ちょっと強引過ぎる打ち方になっていて、自ら墓穴を掘っているような具合。まだまだ、人間が出来ていないということのようであります(笑)。 さて、いつもより少し早やめに家を出て、MTB(マウンテンバイク)で、回り道の銀輪散歩をして参りました。 いつもの中央大通りのコースをとらず、近鉄奈良線に沿ってその南側の道を西へ。鶴橋駅の手前で千日前通りに移り、これをひたすら西へ。上本町・難波・湊町・桜川を経て大正橋を渡り、尻無川沿いに、その河口付近まで銀輪散歩してから、会場の梅田スカイビルへと向かいました。(大正橋) 大川(旧淀川)は、中之島によって二つの流れに分れ、島の北側が堂島川、南側が土佐堀川と呼ばれる。両川は中之島の西端で合流し、南へと流れる木津川と西へと流れる安治川に分れる。 木津川は大正橋の手前で道頓堀川と合流し、そのまま南へと流れる木津川と西へと流れる尻無川とに分流する。(大正橋の上から木津川上流方向を見る。) 写真奥には大阪ドーム球場の屋根が見える。左手に見える橋は尻無川に架かる岩松橋。(大正橋西詰めの橋の説明碑) この説明碑によると、大正橋の南側の欄干は五線譜のデザインでベートーベンの第九の音符になっているとのこと(写真下)。(大正橋・南側<下流側>欄干) 大正橋の東詰めには、江戸時代に建立された、大阪での大津波の様子が記録された石碑がある。詳細は下の写真をクリックしてお読み下さい。(大地震両川口津波記)(同上)(大地震両川口津波記石碑<西面>)(同上・東面) (同上・南面) (同上・北面) この石碑のことを記した瓦版も安政2年に出版されていて、それには次のような歌が記されているとのこと。先達之 人は知しきそ 末の世に くちぬかたみを 残す石ふミ(大正橋西詰め交差点・北方向)(岩松橋)(尻無川・下流方向) 写真奥に見える鉄橋は大阪環状線のもの。左に行くと大正駅。右に行くと弁天町駅である。(尻無川右岸遊歩道)(同上) 遊歩道を行くと、タンクの間から大阪ドーム球場が見える。ドームにもご挨拶だけして行くこととする。(大阪ドーム球場) ドーム球場から、環状線沿いに左へ、岩崎橋を渡って直ぐの処で環状線のガード下を潜って反対側に出ると、尻無川左岸にちょっとお洒落と言うか変った雰囲気の店が並んでいる。(尻無川左岸の一風変わったレストラン・カフェ)(同上)(同上)(同上)(尻無川と球場と船と大阪環状線の電車) なおも川沿いに下流へと走る。救急車やパトカーが追い抜いて行った。やがて前方に黒い煙が見え、ゴムの焼けるような臭い。火災?(前方で火災?) 建物火災ではなく、廃棄物置き場での出火のよう。(消火活動の消防士さんたち。廃品置き場でのボヤでした。)(尻無川水門)(甚兵衛渡船場) 大阪のベイサイド、河口付近には何箇所か渡船乗り場がある。以前、友人の偐山頭火氏と銀輪渡船めぐりをしたことがある。 ここもその時に来たのかどうか記憶が判然としない。(尻無川河口付近。この先は人工島です。) 尻無川の終点。あてもない銀輪散歩。道が尽きたら引き返すだけです。時間もよし。梅田スカイビルへと向かう。
2013.06.05
コメント(4)
-

第120回智麻呂絵画展
第120回智麻呂絵画展 本日はお待ち兼ね智麻呂絵画展であります。 今回は第120回展、多数のご来場お待ち申し上げます。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(紫陽花) これは、母の日に上のお譲様から恒郎女様に贈られて来た花。 橘諸兄が宴会で詠んだ歌に、あぢさゐの 八重咲く如く やつ代にを いませわが背子 見つつしのはむ (万葉集巻20-4448)というのがあるが、これは宴会の主人を幾重にも咲く紫陽花の花の華やかさになぞらえて、「やつ代にいませ」と、その長寿を祈念した歌であろう。お譲様も母上・恒郎女様がいつまでも紫陽花の花のようにあでやかに美しく元気にいらして下さいますように・・との思いを、この花に込められたのであるのでしょう。それを歌にすれば、下のようになりますかね。紫陽花(あぢさゐ)の 八重咲く如く やつ代にも いませ母御前(ははごぜ) 見つつ祈らむ (橘諸姉) この紫陽花は恒郎女様その人でもあるということになります。それゆゑでもあるか、智麻呂氏の上の絵では花の部分がまばら過ぎると、恒郎女様はクレームをお付けになって居られました。 絵は一部分を描写されたものであるのですが、たしかに花がうち重なって豪華な雰囲気を醸している部分を避けて、まばらな部分を描写されていたのでありました。智麻呂氏としては、うち重なった花びらが醸す華やかさよりも、花が点々とあるそこはかとなき佇まいこそが魅力的と感じられたのでしょうが、これは「女心を知らぬワザ」でありますな(笑)。(紫陽花2) かくて、その後に花の重なる絵を別の紫陽花で描かれたのが上の絵でありますが、別の紫陽花では、花が重なっていても、いくら華やかに描いても「駄目」なのであります(笑)。あの紫陽花でなければ。(サワちゃんからの玉葱と豌豆) 上は智麻呂さんのご近所のご友人、サワちゃんケンちゃん姉弟からのお土産の玉葱と豌豆です。ヤカモチ館長も最近は物忘れ病、地名は忘れてしまいましたが、姉弟のお父様だったかお母様だったかのご実家に里帰りされた際に、そのご実家で栽培の玉葱と豌豆をお土産に持ち帰られたとのこと。そのお裾分けとして智麻呂邸にお届け下さったものなのであります。(ムラサキツユクサ)むらさきの つゆくさにもが 置く露の 恋は消(け)ぬとも 継ぎて咲くなれ (偐紫田舎源氏蛍) 以下の花の絵は小万知花写真集から絵にされたものでありますが、花の名がよくは分かりませんので、絵のタイトルも適当に付けて置きました。 名も知れぬゆゑ、コメントも付けにくい、ということで、適当に歌を作って添えて置くこととします。(浅き夢見し) 本名:ワスレナグサ八千種(やちぐさ)の 花は咲けども 常ならぬ 浅きひと夜の 夢にしあれる (いろはの郎女)(コマチモシラズ) 本名:リュウココリネ この花の名は?と、先日の若草読書会で小万知さんに尋ねてみましたが、何とも分からぬ球根を植えて置いたら咲いたもので、小万知さんもご存じではないという。で、ヤカモチが命名したのが「コマチモシラズ」です。花の名は いかにととへど むらさきの 小万知も知らぬ コマチモシラズ (偐家持)(咲きぬれば) 本名:ブラキカムブラスコ これはキク科の植物。菊は万葉には登場しない。万葉の「ももよぐさ(百代草)」が菊だとも言われているが、異説もあり定かではない。 菊は平安期以後に中国からわが国に入って来たものと思われる。従って、菊という漢字には「キク」という音読みしかなく、訓読みがないのである。きくううと つちにまみれて さにはべに われたちくらす ひとなとひそね (会津八一) 菊と来ると会津八一の上の歌を思い出すのであるが、これにかこつけて1首追和すれば、きくかくと へやにこもりて ふでひとつ われたちくらす ひとなとひそね (若草智一) 次のドクダミの花は写真からではなく、散歩の途次に見掛けられたものを描かれたのかも知れません。しかし、この花を摘んで部屋に持ちこむというのは、かなり勇気のいること。花姿の清純さと香りが合致していない。神様の手抜きですな。(ドクダミ)道の辺の 白き火(ほ)明かり わが行ける 先にし咲ける ドクダミの花 (偐家持)(出雲蕎麦) 上は、ヤカモチの出雲銀輪散歩のお土産の蕎麦。と言っても蕎麦の包装ラベルの絵を写されたものであります。大遷宮 神も家移(やうつ)り 蕎麦打つや われも喰(くら)はな 出雲思(しの)ひて (偐家持) そう言えば、先日の大学の同期会・夕々の会で一緒した深◎君が出雲は松江の出身。黄泉比良坂の近くがご実家だと言って居られました。彼が実家に帰ったついでに黄泉比良坂を訪ねたのが5月11日で、小生が訪ねたのが5月9日、僅か二日違いという偶然を二人して面白がったことでありました。 では、これにて閉館。 今日もご来場、ご覧下さり、有難うございました。
2013.06.04
コメント(8)
-

若草読書会・押し絵教室
本日は若草読書会の例会の日。 この処、若草読書会は本を読まない読書会が続いて居りますが、今回もその例でありまして、和郎女さんの指導でメンバーが押し絵制作に挑戦であります。 「押し絵と旅する男」は江戸川乱歩の小説。偐山頭火さんは「押し絵を強制する男」にて、和郎女さんには講師と指導を無理強いし、我々メンバーには和郎女さんの指導の下で押し絵を制作せよと強制、素直で紳士淑女のメンバー各位は、この「押し絵を強制する男」の企画に眉をひそめつつも(笑)、異議は唱えず、唯々諾々と従ったのでありました(笑)。 ヤカモチとしては、もう一度やりたいかと言われれば答は「ノー」でありますが、それでも、やり始めると真剣そのもの、黙々と煙草も我慢し、取り組んだのでありました。同様に、他の皆さんも真面目にコツコツと制作に励まれました。小生はと言えば、和郎女さんの懇切な説明と適切な指導によって、何とかやり遂げることができたのでありました。 以下に各自の作品をご紹介申し上げます。先ず、一番問題視されていたヤカモチの作品です。(偐家持作「釣り」) 下絵デザインは出来ていて、それに合せて型紙を切り出し、布切れで包み、ボンドで接着して行くだけ。 偐山頭火さんも同じテーマの作品でした。上と下で相違する処は何カ所あるでしょうか。そういうクイズを出すために二人が示し合わせたものではありませんが、よく見ると相違する処が何カ所かあります。と言うか、沢山あります。(偐山頭火作「釣り」) 祥麻呂さんはふくろうのタペストリーに挑戦されました。作品によって手間ヒマの具合が異なりますから単純比較はできませぬが、祥麻呂さんが完成一番乗りでした。手先が意外にも器用な祥麻呂さんでありました。(祥麻呂の「ふくろう」) 凡鬼さんも同じく「ふくろう」に挑戦されました。野菜作りはお手の物の若草の藤沢周平こと凡鬼さんも「ふくろう」には「苦労する」と仰っていましたが、味のある作品となりました。(凡鬼昨「ふくろう」) 小万知さんと恒郎女さんは、女性らしく「赤トンボと少女」です。(小万知作「赤とんぼ」) 光の加減で写真の色合いに差異が生じましたが、現物は同じ色合いであります。 「夕焼け小焼け~の赤とんぼ~♪」ということで、上の小万知さんのが「夕焼けの赤とんぼ」、下の恒郎女さんのが「小焼けの赤とんぼ」ということにして置きましょうか。 それぞれに、見事な出来栄えでありました。(恒郎女作「赤とんぼ」) 参加者は上の6名と指導の和郎女さんに智麻呂さん、謙麻呂さん、香代女さんで計10名でありました。謙麻呂さんと香代女さんは定刻より遅れての参加で押し絵には挑戦せずでありました。智麻呂さんは左手1本なれば参加は無理。謙麻呂さんと智麻呂さんのお二人は、我々の悪戦苦闘を見学しつつ歓談しておられました。香代女さんは制作がほぼ終わった頃に来られましたので、参加は無理であったという次第。 常連の槇麻呂、和麻呂、りち女、景郎女各氏は仕事その他の関係で今回は欠席でありました。 次回は、8月休会とし、9月に彦根一泊の小旅行ということになります。<参考>若草読書会関連記事はコチラからどうぞ。
2013.06.02
コメント(7)
-

墓参・花散歩など
本日は午前中は墓参と花散歩。午後は智麻呂邸を訪問し、新作絵画を6点仕入れてまいりました。先に2点の作品を戴いているので合計8点。そろそろ智麻呂絵画展開催しなくてはなりませんが、もう暫くお待ち下さい。 明日は若草読書会ですから、その報告記事の方が先になりそうです。 墓への坂道の途中に寺がある。毎回その門前を通って墓へと向かう。門前に掲げてあった今日の言葉は「いくら落ちこんでもここには少し光がさしてくる」というものでありました。いくら落ち込んでも少しの光、希望があれば、人は立ち直れるし、生きて行ける。その少しの光に目を向け、そのことに気付けるかどうかが大事なのですね。落ち込むと暗い穴の方にばかり目が行き、背後から差し込んでいる光の方に目を向けなくなってしまいがちですが、ちょっと振り向いてみることが大事、ちょっと振り向かせてあげることが大事、ということなんでしょうね。(6月墓参の時の言葉) 先月5月初めの墓参の時の言葉は「太陽は夜が明けるのを待って昇るのではない」というのでありました。太陽が昇るから夜が明ける。人も夜が明けるのを漫然と待っていてはいけないのですな。自らの夜は自ら立ち上がって歩き出すことによって夜が明け、朝を己に引き寄せることが出来る。 まあ、短い言葉ですから、色々に解釈できる。人によっては違った解釈、感想を持つことでもあるでしょう。一義的な言葉よりも多義的な言葉の方が魅力的で深いと感じるのは、受け手側に解釈の或る部分を委ねているという処にその秘密がありそうです。論理的な言葉ではなく、比喩や心情に訴える言葉というものは、短く、言い尽くさず、いささかの曖昧性がある、と言うか、境界線がぼやけて裾野が広いように見えていなくてはならない。それでいて、本質、核心となる部分だけは鮮明・的確に言い得ていなくてはならない。なかなかに難しいものでありますな。 言葉遊びの「いい加減ヤカモチ」も、たまにはそんな言葉を吐いてみたいものであります(笑)(5月墓参の時の言葉) 墓参の道は花散歩の道でもある。 夏に向かって梅雨時に咲く花と言えば、紫陽花は別格としてクチナシやタチアオイもその代表的な花ですね。今日はクチナシの「ハナなし」でありますが、タチアオイを見掛けました。下から順に花が咲き、てっぺんの花が咲くと「梅雨明け」だと言われているというのを何処かで読んだか聞いたかした記憶がある。(タチアオイ)梨(なし)棗(なつめ) 黍(きみ)に粟(あは)嗣(つ)ぎ 延(は)ふ田葛(くず)の 後(のち)も逢はむと 葵(あふひ)花咲く (万葉集巻18-3834) <ナシ、ナツメ、キビに続いてアワが実り、つるをのばすクズのように、 これからも逢いましょうとアオイの花が咲きます。> 葵は「あふひ」と訓むので「逢ふ日」と掛けて使われる。会津が「あひづ」で「逢ひつ」と掛けて使われるのと同様ですな。 これを両方使って歌を作ると、 葵(あふひ)咲く 日は逢ふ日なり 恋ひ恋ひて 待ちにし君に 会津(あひづ)に逢ひつ (偐郎女)になりますかな(笑)。 (同上) 次はランタナみたいな花。「ランタナミタイダナ」ということにして置きます。(ランタナみたいダナ) そしてアジサイも咲き始めました。(紫陽花)言(こと)問はぬ 木すら紫陽花(あぢさゐ) 諸弟(もろと)らが 練(ねり)の村戸(むらと)に あざむかえけり (大伴家持 万葉集巻4-773) <言葉をいわぬ木でも花が変化する紫陽花があるように、諸弟らの練 達の占(ムラト)にだまされてしまったよ。>(バラ) 五月のバラも六月に入って、少しくたびれてきましたかな。吾妹子が 立ちて窓辺に 笑みたるは 五月の薔薇の 花の咲く朝 (偐家持)(ヒメジョオン) 蕾が上を向いているから、これは、ハルジオンではなくヒメジョオンです。 そしてドクダミの花も咲き群れています。姫女苑 どくだみの花 奥津城に 咲き群れてをり 水無月の朝 (偐家持) (ドクダミ) そしてチガヤが風に揺れている。(チガヤ)銀色の その穂いとほし 風がまま われも茅(ちがや)の ごとや生きなむ (偐家持) そして、ノビル(野蒜)です。万葉に1首歌があります。(ノビル)醤(ひしほ)酢(す)に 蒜(ひる)搗(つ)き合てて 鯛願ふ われにな見えそ 水葱(なぎ)の羹(あつもの) (長意吉麻呂(ながのおきまろ) 万葉集巻16-3829) <醤と酢に蒜をまぜ合わせて鯛を食べたいと思っているのに、水葱の 羹なんぞ俺に見せるな。>(同上) 名の知れぬ草が風に靡いている姿もいい。名が知れればもっとお近づきになれるのでしょうが(笑)。(名前不詳の草)
2013.06.01
コメント(6)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- 【楽天】長男の一目惚れ!小学生の冬…
- (2025-11-14 12:16:50)
-
-
-

- 気になるニュース&話題(Infoseekニ…
- クマ対策の最新の情報‼️⚠️
- (2025-11-14 13:09:27)
-








