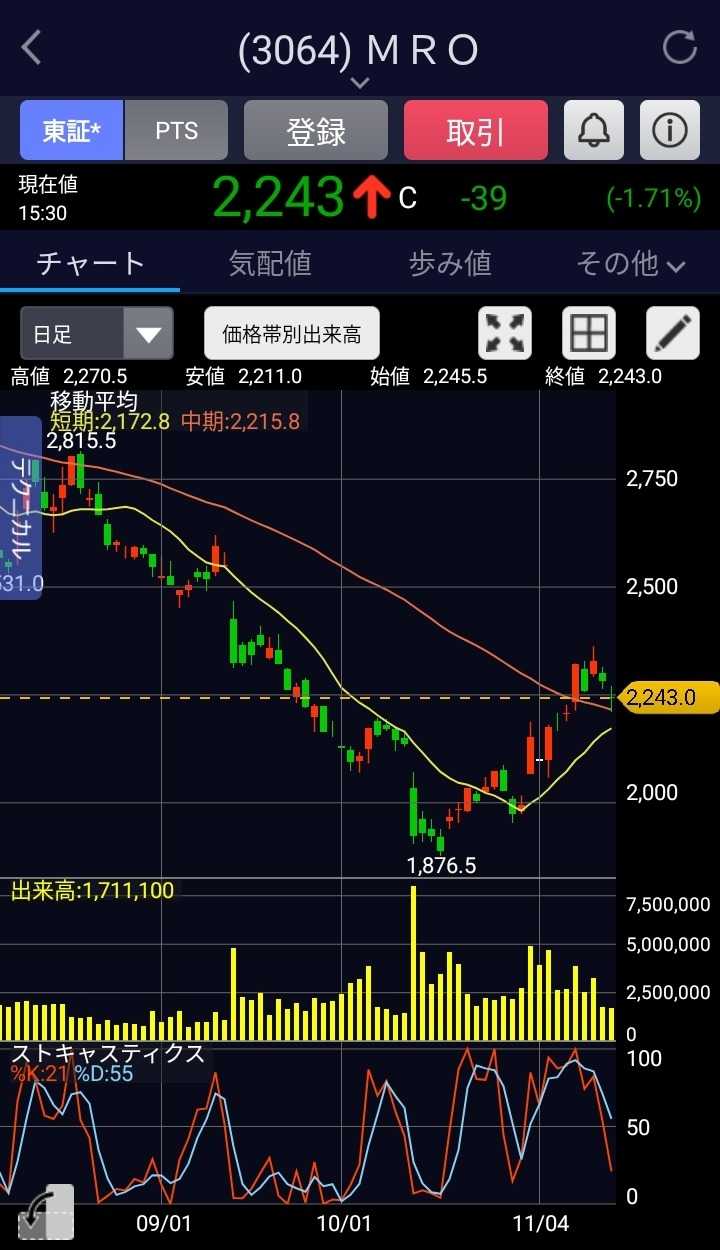2013年10月の記事
全22件 (22件中 1-22件目)
1
-

吉備路自転車散歩・総社宮から鬼ノ城へ
<承前> JR吉備線東総社駅は、総社駅から国道180号に出て、これを東に走ると道路沿いにある。駅から東へ100m位の処にあるのが総社宮。総社市の市名はこの総社宮に由来する。 <参考>総社市観光ガイド・総社宮 総社・wikipedia 総社とは、その地域の神社の祭神を集めて祀った神社で、全国あちこちにある。赴任した国司の最初の仕事が国中の神社を参拝するということであったことから、誰か横着な国司が、国府の近くにこれらの神社の神様をひとまとめにして祀れば国中を巡回する必要もない、と思い付いたのであろう。 遥任と言って都に居たまま任国に赴かない国司も居たのだから、これ位は許されるそうじゃ。(総社宮)(同上・説明板)(同上)(同上) 総社宮を出てその南の辻で左折、県道272号を北へと行く。 JR吉備線を渡った処で道は斜め右(北東)に進むがやがて大きく左にカーブして北へと進む。(鬼ノ城への道・奥手前の丘を越えた辺りで突き当りを右に行く。) この道の突き当たりを右折、東に向かい、岡山自動車道の高架を潜って700mほど行った交差点で左に入る。ゆるやかな坂道を上って行くと砂川公園である。 上の写真の正面奥にポッコリ見えている山が鬼ノ城山だろう。(鬼ノ城への道・砂川公園) 砂川公園は鬼ノ城の方などから流れて来る川に沿ってあるいい雰囲気の公園である。キャンプ場などもある。バーベキューを楽しんでいるグループや川遊びをしているのか楽しそうな声を上げている子供たちの姿も。 公園管理事務所の前で小休止していると、事務所の人が出て来られてトレンクルに興味を示される。どうぞ、と少し乗って戴く。慣れない所為で少し危なっかしい走りぶりでしたが(笑)。鬼ノ城までの所要時間をお尋ねすると、1時間はかからないだろうとのこと。ビジターセンターまでずっと舗装された道であるとも。(同上) 公園が切れた辺りから段々と坂道が険しくなって来る。それでも堪えて喘ぎつつ漕いで行くが、それを嘲笑うように前方に更にも厳しい急坂が見えて来る。そんな景色を見てしまっては意気阻喪、ギブアップ。押して上る。(鬼ノ城への道・赤坂池) 山の中の池。下の砂川公園の川へと流れている水系なのだろう。 水面に映る景色が美しい、このクヌギは美しく色づいているではないか、などと自分への口実を設けて、ひと休みしつつの道中でありました。 漕いだり、押して歩いたり、休憩したりを繰り返しながら、少しづつ高みへと上って行く。所々で道が狭いので車も対向車待ちをしなければならないようで、トレンクルもその巻き添えで対向車待ちをしたり・・この感じは、わが地元の暗峠への道に似ている。ただ、道の舗装状況はコチラの方がまさっている。(鬼ノ城への道) 道脇には点々とお地蔵さんがある。第○番と番号が付してあるが何番まであるのかが分からないので目的地までどれ位の距離なのかを知る役には立たない。砂川公園の辺りだったか、「鬼ノ城まで3000m」という表示板があったのだが、その表示板が500m間隔で設置されていて、それが残り距離を教えてくれる。(鬼ノ城への道・新山集落の稲田) かなり上った処の山中に小さな集落。新山集落である。何軒かの家がある。この風情も暗峠に似ている。くがね咲く 吉備の鬼(き)ノ山 峠道 黄金(くがね)色なり 稲穂も柿も (偐家持)(鬼ノ城への道・新山集落の柿畑)(鬼ノ城への道・新山集落の先) しかし、この先まだ急坂の上りがあって、漸くにして鬼ノ城ビジターセンターに到着です。 ここから先は自転車も入れない。ビジターセンターの前に駐輪して、徒歩にて鬼ノ城に向かう。ビジターセンターの方のお話では1周約1時間とのこと。うらうらの 秋の日差しも やさしみと 来ればなかなか 温羅の城跡 (偐家持)(鬼ノ城遠望)<参考>鬼ノ城・Wikipedia 鬼ノ城ホームページ 鬼ノ城については上の「鬼ノ城ホームページ」をクリックしてご覧戴くともうそれで十分であり、小生の下手な写真をご覧戴く必要はさらさらないということになりますが、それではブログになりませんので、次回は鬼ノ城をグルリ1周の写真を掲載させて戴きます(笑)。 その前に、鬼ノ城の温羅伝説のお話を知って置いて戴くのがよろしかろうと、吉備津神社のホームページにあった絵本仕立のものをご紹介して置きます。 <参考>キビツヒコの温羅退治(吉備津神社ホームページより) ということで、本日はここまでとします。(つづく)
2013.10.31
コメント(0)
-

吉備路自転車散歩・円通寺へ
<承前> 2日目の27日は円通寺と鬼ノ城を訪ねることとしました。 朝8時35分総社駅発の電車で倉敷乗り換えで新倉敷駅へ。9時5分到着。駅前からトレンクルで円通寺に向かう。円通寺行きは突如思い付いたもので、前夜にパソコンで検索した地図によって凡その道筋と方向を頭に入れての走行。途中少し道に迷う場面もあり、少し遠回りの道になってしまいましたが、無事に円通寺に辿り着けました。 円通寺は若き良寛が修行した寺である。(総社駅ホーム) 総社から新倉敷に行くには倉敷で乗り換えとなる。 倉敷~西阿知~新倉敷。2駅目である。(倉敷駅) 西阿知駅を出て直ぐに大きな川を渡る。高梁川である。(高梁川・下流方向) 新倉敷到着。 在来線側の出口には良寛さんの像がありました。(新倉敷駅前の良寛像) 円通寺は新倉敷からは南西5~6kmの距離にある。(新倉敷駅と円通寺の位置関係) 円通寺は玉島港を望む小高い丘の上にある。トレンクルで上り切るには厳し過ぎる急坂にて途中から押して行く。国民宿舎良寛荘がある高みから更に上った処にある。(円通寺公園、国民宿舎「良寛荘」付近) 良寛荘から真っ直ぐに上って行くと、そこは円通寺の裏口。またしても裏口からの入場である(笑)。そこは展望休憩所のある、円通寺境内で最も高い場所でありました。 本堂へは道を下って行くこととなる。(円通寺・本堂と良寛像)<参考>円通寺ホームページ(円通寺・本堂)(円通寺・白雲閣) (円通寺・説明板) (良寛堂説明板)(良寛堂)(良寛像)<参考>良寛・Wikipedia 此処の良寛さんの像は通常見慣れているそれと違って青年僧の姿である。20代から30代に掛けての若い時代に此の寺で修行したのでもあれば、此処での良寛像はこのような姿でなくてはならないということになる。 本堂から下って行くと庭園の一角に山頭火の句碑がありました。(山頭火句碑)昭和11年に円通寺を訪れた山頭火が詠んだ句だそうな。岩のよろしさも良寛さまの思ひ出 (種田山頭火)思はぬに ここにも居たか 山頭火 岩根踏みつつ 円通寺の朝 (偐家持)(同上・説明板) 裏から入って表から出て行く。 細い凸凹の急坂は自転車に乗っては下れない処もありました。(参道脇の碑)(円通寺のある丘) 銀輪万葉であるから。良寛はさて置き、万葉歌も紹介しなくてはなりませんですな。ぬばたまの 夜は明けぬらし 多麻(たま)の浦に 求食(あさり)する鶴(たづ) 鳴き渡るなり (遣新羅使人 万葉集巻15-3598) 「多麻の浦」は、異説もあるが、一般には玉島の海浜であろうと言われている。 上の写真を撮影した川べりから背後一帯の地名が玉島阿賀崎であるから、万葉の頃は、この川の辺りも海であったのだろう。してみれば、小生は多麻の浦に立って、円通寺のある丘を眺めているということになる。 遣新羅使人一行は、おそらくこの辺りの入り江に仮停泊し、一夜を過ごしたのでしょう。明け方に鶴の鳴き声を枕辺に聞き、夜が明けたのだろうと思いやっている歌である。そう言えば、総社市には鶴の飼育センターがあるし、後楽園でも丹頂鶴が飼育されている。(新倉敷駅ホーム) 新倉敷駅に帰って来ました。駅前で昼食を済ませ、電車で東総社へ向かう。東総社から鬼ノ城へ自転車で走ろうという算段である。 再び、高梁川を渡る。今度は上流方向を撮影。(高梁川・上流方向) 倉敷で山陽本線から伯備線に乗り換える。伯備線は高梁川に沿うようにして北上している。清音駅の手前辺りで車窓から西を見ると高梁川の対岸に二上山のような山が目に入りました。 吉備路自転車道では「三輪山」を発見致しましたが、此処では吉備の「二上山」を発見であります(笑)。(吉備にもあった二上山?)高梁の 川沿い来れば 玉くしげ 吉備にも二上 あるはうれしも (偐家持) 鬼ノ城に一番近い駅は東総社駅と見て、切符は東総社まで買ったが、新倉敷からだと倉敷で伯備線乗り換え、総社で吉備線乗り換えとなり、総社駅に着いてみると東総社への電車は1時間に1本、待ち時間を見ると自転車で走った方が東総社に早く着ける。総社駅で下車。(JR吉備線・東総社駅) 東総社駅前に到着しましたが、本日はここまでです。(つづく)
2013.10.30
コメント(4)
-

吉備路自転車散歩・吉備津彦神社から備中高松へ
<承前> 吉備津彦神社は吉備津神社から「吉備の中山」を北東に2kmほど回り込んだ位置にある。どちらも吉備津彦を祭神とする神社。 吉備津彦神社は備前国一の宮。吉備津神社は備中国一の宮。もう一つ備後国一の宮の吉備津神社は、ずっと西、広島県福山市にある。 <参考>吉備津彦神社・Wikipedia 吉備津神社(福山市)・Wikipedia(吉備津彦神社・神門)(同・安政の大石灯籠)(同・拝殿)(拝殿から奥の本殿まで社殿が4つ並んでいる。)(同・本殿)(同上説明板) 崇神天皇10年に四道将軍の一人として山陽道に派遣され、吉備氏の祖となったとされる吉備津彦であるが、詳しくは下記参考をご覧下さい。 <参考>吉備津彦命・Wikipedia 彼は281歳まで生き、死後中山の三町に葬られたと伝えられる。仲山の山頂に在る中山茶臼山古墳がその墓だとされる。今回は山頂を訪ねなかったので、次回にということになりますかな(笑)。(これは何?) 予想したよりもあちらこちらで時間を食ったようで、日暮れ前には総社駅前に戻るというのは無理な雲行きとなって参りました。 吉備津彦神社を出て、吉備津神社へと自転車道を引き返す。吉備津神社の参道まで戻り、参道を北へ、国道180号に出る。(吉備津神社の参道松並木・国道180号から) 国道180号を備中高松駅目指して走る。前方に大きな鳥居が見えて来る。最上稲荷の大鳥居である。吉備病院の前で、JR吉備線の踏み切りを渡り脇道に入る。ほどなく小さな芝生の公園に出る。(JR吉備線・岡山方面)(同上・総社方面) 高松城水攻めの築堤跡が公園の一角に残っている。 吉備津彦の古代から秀吉の近世まで一気に1200年程を走ったことになりますかな(笑)。 <参考>備中高松城の戦い・Wikipedia(蛙ヶ鼻築堤跡)(高松城水攻め築堤説明板)(道標) 高松城跡公園に向かう。最上稲荷の大鳥居の向こうの空は既に夕色。(最上稲荷大鳥居)(備中高松城跡公園)(同上)(同上)(同上・説明板)(史蹟・舟橋)(同上説明板) 国道180号に戻り、暗くなる前に行ける処まで行こうと足守の方向に走り始めたが、足守川の手前の辻から先が歩道のない道となっている上、ライトを点灯した車がひっきりなしに走っている状態。 これでは自転車で走行するのは危険と判断。足守駅から電車でと思うものの、地図がないので、駅までの距離や正確な位置が分からない。ということで、備中高松駅まで引き返すこととする。 後で調べると足守駅が少し近い距離でしたが、知らぬ道を行って迷うこともあり得ることを考えれば、引き返したのが正解でしょう。 備中高松駅前に着いた頃はすっかり暗くなっていました。(備中高松駅) これにて初日26日の銀輪散歩終了です。(つづく)
2013.10.29
コメント(4)
-

吉備路自転車散歩・吉備津神社から吉備津彦神社へ
<承前> 足守川を渡り、川沿いに左岸の道を下って行くと、明治天皇惣爪御野立所と刻された石碑のある小さな緑地に出る。 明治43年(1910年)11月に陸軍の大演習がこの付近で行われ、明治天皇がこれを統監した場所が此処だという碑である。背後の小高い処には「龍蹤表彰之碑」というのもある。皇帝は「龍」に喩えられるから、これも同じ趣旨の碑であり、こちらの碑の方が古いものなのであろう。 (明治天皇惣爪御野立所の碑) (龍蹤表彰之碑) 銀輪万葉としては、これらの碑よりも、この近くにある惣爪塔跡の方を見て置くべきであったのだが、下調べが杜撰でこれを見落としました。 奈良時代にあった大寺の塔の跡と見られているらしい。「岡山県の国指定文化財」というサイトの「惣爪塔跡」というページに掲載されている写真(下掲)によると、直ぐ近くで、首を廻らせば目にすることが出来たのに、まことに迂闊なことでした。(明治天皇御野立所の碑から惣爪塔跡を見る。ウェブサイト「岡山県の国指定文化財」から転載。) 足守川にお別れし、東へと走る。前方の山が所謂「吉備の中山」であるのだろう。吉備津神社の社殿が遠目にも見えて来る。 自転車道を外れて集落の中の路地を走る。やがて鳥居のある辻に出る。吉備津神社である。どうやら、吉備津神社の裏口のよう。此処でもヤカモチは裏から入ることとなりました(笑)。(吉備津神社鳥居) <参考>吉備津神社・Wikipedia(吉備津神社・西側入口)<参考>吉備津神社公式サイト(本殿へと向かう長い長い回廊) 長い回廊が西から東へと続いている。奥に本殿があるよう。前方に高校生の一団が賑やかな声を上げている。行ってみると、皆、袴姿の凛々しい出で立ち。弓道の試合か何かのよう。 吉備津彦は薀羅と弓矢で戦うのであってみれば、この神社で弓道の試合なり奉納があるというのも似つかわしいことと言うべきか。(弓道場) 暫し、弓を射る姿を拝見させて戴く。高校生達の群れをやり過ごして更に奥へ。(尚も続く回廊はやがてゆるやかな上り坂となる。) 漸くにして本殿・拝殿のある場所に着く。本・拝殿は東を向いている。西から入って来たので、本・拝殿の背後からやって来たことになる。(本殿・拝殿) 正面の門に回って、正面から拝殿へと入り直す(笑)。まあ、そんなことは頓着しないヤカモチなのであれば、これは神門を写真に撮るための行為に過ぎなかったのでありますが・・。(正面の神門から拝殿を見上げる。)(神門) 自転車は裏口に停めてあるので、回廊を西へと引き返す。 裏から外に出て、東へと回る。中程にも入口があったが、これは、高校生達が居た弓道場のある辺りの回廊へと繋がっているのであろう。(中央の入口) 東側の正面入り口の方に回るとそこが正面の参道となっていて松並木が北へと延びている。 吉備路自転車道はこの参道の横から脇へ入って東方向に続いている。それを辿ると、鼻ぐり塚というのがあった。(鼻ぐり塚) 立ち寄ってみたが、何やら勝手に入ってはいけないようなので、奥には入らずに引き返しました。帰宅後ネットで調べてみると、無人の受付で参拝料を払えば、入ることが出来たようだ。 参拝者以外立ち入り禁止、のようなニュアンスの表示であったので、遠慮したのでしたが、中は下記の<参考>にある通りで、牛の鼻輪(鼻ぐり)を供養している処のようです。 <参考>鼻ぐり塚・福田海本部(同上)(藤原成親遺跡碑)<参考>藤原成親・Wikipedia 鼻ぐり塚の入口前に、藤原成親遺跡碑なるものが建てられていた。 成親と言えば、平重盛の妻・経子の兄。平家打倒の陰謀・鹿ヶ谷事件で西光、俊寛らと共に捕縛された御仁。重盛が父・清盛に助命嘆願してくれたお陰で、備前国配流の処分となるのだが、結局はこの地で殺されることとなる。(細谷川歌碑) 鼻ぐり塚の少し先に、歌碑がありました。古今集の歌です。まかねふく 吉備の中山 帯にせる 細谷川の 音のさやけさ (古今集巻20-1082)<黄金を産出する吉備の国の中山が、帯のようにめぐらせている細谷川の水音の澄みわたって清らかなことよ。> この細い川が細谷川と言うのだろうか。吉備津神社付近の川の名とする固有名詞説と「細い谷川」という意味の普通名詞とする説もあるのであってみれば、此処であってもいいことにはなる。 <参考>吉備の中山(吉備津彦神社への道)(吉備津彦神社駐車場にある桃太郎像) 吉備津彦神社に到着です。先ず迎えてくれたのは桃太郎。しかし、もう字数制限のようです。続きは明日に。(つづく)
2013.10.28
コメント(0)
-

吉備路自転車散歩・備中国分寺から吉備津神社へ
<承前> 国分寺の前にはコスモスなどの花が群れ咲いていました。 これは観光客への「お・も・て・な・し」という奴ですかな(笑)。(秋の花と備中国分寺)(同上) コスモスとルドベキアのお花畑。遠景の塔とよく似合う。コスモスの 花越しもよし 大空に 吉備のみ寺の 塔は立ちける (偐家持) 国分寺を出て東へ。直ぐに大きな古墳が左手に見えて来る。こうもり塚古墳である。(こうもり塚古墳) <参考>こうもり塚古墳・Wikipedia こうもり塚古墳の東隣が備中国分尼寺跡である。こちらは、建物はなく文字通り「跡」である。復元であれ建物が存在すると却って想像力が制限されてしまってよろしくない。何もないのは寂しいが、石碑だの礎石だの偲ぶよすがが少しばかりあるのが一等いい。(備中国分尼寺跡)(同説明板)森深く 道しづもりて みほとけの 慈愛もかくや 尼寺の跡 (偐家持) (同・中門跡)(同・説明板)(同・金堂跡 何故かこの写真モノクロ調になりました。)(同・説明板)(同・伽藍配置図) 国分尼寺跡から北東に1.5km程行くと造山古墳という巨大古墳がある。先に見た作山古墳よりも大きい。全国第4位の大きさと言うから仁徳陵、応神陵、履中陵に次ぐ大きさである。古代吉備の国力が大和のそれに劣らぬ強力なものであったことが分かるというものである。 どちらも「つくりやま古墳」であるが、地元では両者を区別するため、作山古墳は「さくざん古墳」、造山古墳は「ぞうざん古墳」と呼んでいるそうな。 万葉時代では吉備真備(下道真備)が先ず思い浮かぶ吉備氏の人であるが、万葉歌人では、志貴皇子の葬送をドラマチックに詠い上げた笠金村やその娘という説もあり、大伴家持との歌のやりとりで有名な笠女郎などが思い浮かぶ。笠氏も亦吉備氏の流れなのである。高円の 野辺の秋萩 いたづらに 咲きか散るらむ 見る人無しに (笠金村 万葉集巻2-231)皆人を 寝よとの鐘は 打つなれど 君をし思へば 寝(い)ねかてぬかも (笠女郎 万葉集巻4-607)(造山古墳) <参考>造山古墳・Wikipedia(同上・陪塚) 作山古墳には巨大古墳に付き物の陪塚がないが、造山古墳には上のような陪塚が6基もある。(造山古墳の北側にある牧場・若駒牧場) 造山古墳の北側には観光牧場があって、引退した競走馬やポニーなどが飼われている。乗馬体験などもさせてくれるようだ。 柵の外側を白いポニーがポックリ、ポックリと気ままなお散歩を楽しんでいました。(造山古墳・北東側から後円部を望む)(吉備路自転車道・岡山市北区新庄上地区付近) 造山古墳を後に東へ。高速道路の高架を潜ると足守川である。 足守川の上流に足守という地がある。適塾開設者の緒方洪庵は足守藩の下級武士の家に生まれたのであるから、この川の上流の出身である。ヤカモチの母校は緒方洪庵とは深い関係があるのだが、足守まで「足」を延ばす余裕は今回はありませぬ(笑)。下流に走る。(足守川)(足守川、津寺付近の橋の上から上流を望む。左奥に加茂小学校。)(同・下流方向。)(吉備路自転車道・足守川畔、津寺付近)(吉備路自転車道案内図、津寺地区黒住1号排水機場近くの緑地内) 県道270号線に出た処で自転車道は橋を渡り、右岸から左岸の道となるのだが、県道の向かいに鯉喰神社というのがあるので立ち寄って行く。 桃太郎伝説や温羅伝説に因む神社である。(鯉喰神社)<参考>鯉喰神社(同・説明板)(道標)(足守川左岸、倉敷市域をかすめて通り過ぎる。) 鯉喰神社も倉敷市になるが、自転車道はここで倉敷市に入り、明治天皇惣爪御野立所碑の処で再び岡山市となり、吉備津神社へと続く。今日の記事はここまでとします。(つづく)
2013.10.27
コメント(6)
-

吉備路自転車散歩・総社駅前から備中国分寺まで
26~28日と吉備路を自転車散歩して参りました。 初日26日は吉備路自転車道を走る。起点は総社駅前。終点の吉備津彦神社で折り返し、帰途は途中で自転車道から国道に移り、備中高松城跡に立ち寄り、総社へ帰還というコース。(JR総社駅) JR総社駅前を折りたたみ自転車「トレンクル」で出発。 既に昼近くになっていたので、通りかかったラーメン屋さんで昼食。 ブロ友のふぁみり~キャンパーさんなら、ここでラーメンについての蘊蓄が披露されるのだろうが、小生には何と言って申し上げることもありませぬ(笑)。 ネットで吉備路自転車道というものを知り、やって来ましたが、サインが不十分で分かり辛い所もある自転車道です。当初は岡山駅から総社に向かって走る心算でしたが、自転車道は備前一宮駅前・吉備津彦神社付近から総社駅前までということで、先に総社まで行き岡山方向に走る方が道が分かり良いかと、急遽変更しました。しかし、出発して最初の右折のサインの位置が既にして不適切で、間違って一つ手前の交差点を右折してしまいました。 よく見ると400m先とか何とか小さく表示されていたのですが、交差点の少し手前にあったので、その交差点を右折するものと早合点した次第。もう一つ先の交差点を右折するのなら、右折標識はこの交差点を渡った地点とその先の交差点の手前との間に設置すべきものでしょう。 お陰で少し道に迷ってしまいました。しかし、何とか総社運動公園の前に出ることが出来て、漸く自転車道のサインを発見。 (きびじアリーナ前) (総社運動公園からやよい広場へ) 運動公園を過ぎると長閑な田園風景が広がり、田中の自転車道を快適に走る。やよい広場という小さな緑地に高床式倉庫が復元されてありました。(やよい広場の高床倉庫)(同上説明板) やよい広場から南を望むと三輪山が・・。 地図などで推測すれば、これは福山城跡のある福山という山かと思われます。 <参考>福山城(備中国)・Wikipedia(吉備の三輪山?)三輪山を 見つつも行かな 道の隈 大和のみかは 吉備の三輪山 (偐家持) 吉備路自転車道は、やよい広場から東へ500m行くと右折して南へと向かう。1km余で作山古墳の西側に出る。(作山古墳)(同上説明板) <参考>作山古墳・Wikipedia 陵募に指定されていないので立ち入りは自由。トレンクルを担いで、墳丘に上ってみる。クヌギの大木が多く生えていて、落ちた実が地面を黒くしている。(墳丘上にはクヌギの実が一杯に落ちて・・)(墳丘上からの眺め。) 方向は定かではないが、多分これは南か南東の方向を眺めているのだろうと思います。 吉備路自転車道は作山古墳の西側を南下し、県道270号に出る手前で左折、東へと延びて備中国分寺へと至る。 前方後円墳の前方部分から墳丘上に登り、後円部から下る。真っ直ぐに行くと国道429号に出る。自転車道が何処にあるのか分からない。国道を南へ下ってみると、果たしてありました。(作山古墳・東側の国道429号からの眺め。)(吉備路自転車道・塔見の茶屋付近) 自転車道に入って前方を見ると国分寺の五重塔が目に入る。この辺りが吉備路自転車道としては一番眺めの良い場所のようだ。 さもあるか、「塔見の茶屋」という喫茶店が県道270号沿いにあり、五重塔の方向に広い窓が設けてあって、塔を眺めながらお茶を飲んだり食事をしたり出来るようです。店には入らなかったので、詳しいことは分からずです。何も窓越しに眺めなくてもいいのだから入る必要はない(笑)。(塔見の茶屋)(国分寺が近付いて来ました。) 国分寺到着です。(備中国分寺)(備中国分寺山門)(同・五重塔)(同・本堂)(同・大師堂)(同・勅使門)(同・客殿)(同・鐘楼)(同・伽藍配置図) <参考>備中国分寺・Wikipedia銀輪の 刈り穂の道や 秋の風 吉備のみ寺に 恋ひて我が来し (偐家持) 本日はここまで。続きは明日とします。 (つづく)
2013.10.26
コメント(6)
-

第129回智麻呂絵画展
第129回智麻呂絵画展 本日は第129回智麻呂絵画展であります。 多数のご来場お待ち申し上げて居ります(笑)。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(柘榴)<参考>柘榴が登場する智麻呂絵画展は次の通り。 実:第6、12、67、88、89、90、110、121回展 花:第121回展 これは、智麻呂さんが通って居られるデイサービス施設のAさんが画材にとお持ち下さったものだそうです。 ザクロも智麻呂さんがお気に入りのモチーフのようです。過去にもいい絵を描かれています。(薔薇)<参考>バラの登場する智麻呂絵画展は次の通り。 第3、34、108、123回展 こちらは、もう一つのデイサービスの施設、福寿苑に咲いていたバラを写生されたものです。咲く薔薇も 実なる柘榴も うれしきは それみな人の こころなりけり (偐智麻呂) 次の彼岸花以下4点の絵は先般の若草読書会彦根旅行の折に偐家持が撮った写真から絵にされたものであります。(彼岸花)<参考>彼岸花が登場する智麻呂絵画展は次の通り。 第16、45、65、88、107、128回展(琵琶湖畔のコスモス)<参考>コスモスの登場する智麻呂絵画展は次の通り。 第10、17、35、46、65、89、128回展(琵琶湖畔のセンニンソウ<仙人草>とツマグロヒョウモン)<参考>センニンソウは第108回展にも登場している。仙人も 蝶と戯れたる 秋の道 (筆蕪蕉) ブログ友の一人、るるらさんは智麻呂絵画のファンで、この智麻呂絵画展をこまめにご覧戴いているようでもありますが、彼女は智麻呂さんのことを、敬愛の念を込めて「智麻呂仙人」とも呼ばれています。彼女に言わせれば、仙人草は智麻呂さんに相応しい花ということになるのかも知れませんですね(笑)。 もっとも、この絵は恒郎女さんに言わせると、蝶のツマグロヒョウモンの翅の模様などがちゃんと描かれていない「手抜き」で、未完成であるということでありましたが、画伯ご自身は「これでいいのだ。」とのことで、出展と相成りました。しかし、ひょっとすると、更に手を加えられるかも知れませんので、そのような場合には、再掲載させて戴きます(笑)。ツマグロの つまはいまだと 妻言へど われは仙人 気が向くままよ (智麻呂仙人) (彦根城の彼岸花) 次の「鳥取砂丘のラッキョウ」は先頃の偐山頭火さんの鳥取旅行のお土産です。(鳥取砂丘のラッキョウ)<参考>鳥取砂丘のラッキョウは第90回展にも登場しています。辣韮を 噛めばチリチリ 秋時雨 (筆蕪蕉)辣韮の 花咲きたるか 秋時雨 (筆蕪蕉) 第90回展にも「鳥取砂丘のラッキョウ」の絵がありますが、それは偐家持の旅の土産。この時はラッキョウの花が咲き始めている季節でもありましたので、智麻呂さんは、ラッキョウの花の絵も描いて居られます。<参考>「鳥取銀輪散歩・多鯰ヶ池ほか」 2011.10.31.(梨と蜜柑)<参考>ナシが登場しているのは、第20、43、68、106回展です。 ミカンは何度も登場していますが、次の通りです。 第24、30、51、54、67、69、72、74.92、94、97、110、 112、116、117回展。 上のナシも偐山頭火さんの鳥取土産。ミカンの方は恒郎女さんが買って来られたものです。(ビッグジョンさんの白い彼岸花) この白彼岸花は、ブログ友のビッグジョンさんのブログにアップされていた写真を絵にされたものです。 かなり以前のことになりますが、智麻呂さんが彼岸花を描きたいと仰っていたので、ビッグジョンさんのブログ写真を印刷してお届けしたことがありました。それがこのような素敵な絵になったという次第。 因みに、この白彼岸花の写真が掲載されているビッグジョンさんのブログ記事は下記です。 <参考>歩人のたわごと「紅白のヒガンバナ」 2013.9.23.
2013.10.25
コメント(18)
-

チサの実のさはにぞなれる
雨降れば いたもすべなみ ちさの実の ことなど陳べむ 秋の一日 (偐家持) 台風接近と秋雨前線下、銀輪散歩もお休みでありますので、先日に花園中央公園で見掛けた、エゴノキの実に因んだ記事でも・・という次第。(エゴノキの実) エゴノキの花は可憐な花です。万葉集では「ちさ(知佐)」の花として登場している。 花は、2008.5.6.の記事に掲載しています。そこでは、チサの万葉歌全文を掲載していますが、今回は、口語訳も付けて、再掲載して置くこととします。(同上) この歌は、天平感宝元年(749年)5月15日に、越中守大伴家持が、遊女の左夫流子に夢中になり妻子を顧みなくなっている部下の書記官である少昨に説教した歌である。真面目な説教と言うより、宴会の場での戯れ歌で、若い少昨が宴会で遊女の左夫流子にモテているのを見て、それを揶揄した歌のような気もするが・・。事実はどうあれ、万葉集に掲載されてしまった少昨こそいい迷惑(笑)。 今なら、名誉棄損、プライバシー侵害、パワハラなどの法的問題も生じかねないかと思われますな。 そういうこととは別に、記載された前文から古代の離婚事由なども覗われて面白い。史生尾張少昨(をくひ)に教へ諭す歌1首併せ短歌七出(しちしゅつ)の例に云はく但し一條を犯せらば、即ち出すべし。七出無くてたやすく棄つる者は、徒(づ)一年半。三不去(ふきょ)に云はく、七出を犯せりとも、棄つるべからず。違ふ者は杖(つゑ)一百。唯(ただ)し、奸(かん)を犯せると悪疾はあるとは棄つること得(う)。<七出の例(コメント欄脚注1参照)に云うには、その一条でも犯したら離別してよい。七出に該当しないのに安易に棄てる者は徒刑1年半である。三不去(同注2参照)に該当する場合は七出を犯した場合でも離別できない。違反した者は杖百の刑である。但し、この場合でも姦通した者と悪疾者は離別してもよい。>両妻の例に云はく、妻ありてまた娶る者は、徒一年。女家(ぢょか)は、杖一百にして離(はな)て。詔書に云はく、義夫節婦を愍(めぐ)み賜ふ。<両妻の例に云うには、妻があるのに娶る者は、徒刑1年。女性は杖百に処して離別せよとのこと。また、詔書に云うには、義夫節婦をいつくしめ、と>謹みて案ふるに、先の件(くだり)の数條は、法(のり)を建つる基(もとゐ)、道を化(をし)ふる源なり。然れば則ち、義夫の道は、情(こころ)、別(べち)無きに存(あ)り、一家財を同じくす。豈(あに)旧きを忘れ新(あらた)しきを愛づる志(こころざし)あらめや。所以に、数行の歌を綴り作(な)して、旧きを棄つる惑ひを悔いしむ。その詞(ことば)に曰く<謹んで思うに、先述の数条は立法の基本となるものであり、道を教える根源である。してみれば義夫たるの道は、情があって、差別しないこと、一家で財産を共有することである。どうして、古い妻を忘れて新しい女性を愛するというようなことがあってよいものか。よって、数行の歌を作って古い妻を捨てるという過ちを悔い改めさせようとするものである。その歌は次の通り。>大己貴(おほなむち) 少彦名(すくなひこな)の 神代より 言ひ継ぎけらく 父母を 見れば尊く 妻子(めこ)見れば 愛(かな)しくめぐし うつせみの 世の理(ことはり)と かくさまに 言ひけるものを 世の人の 立つる言立て ちさの花 咲ける盛りに はしきよし その妻の子と 朝夕(あさよひ)に 笑みみ笑まずも うち嘆き 語りけまくは とこしへに かくしもあらめや 天地(あめつち)の 神言寄せて 春花の 盛りもあらむと 待たしけむ 時の盛りぞ 放(さか)りゐて 嘆かす妹が いつしかも 使(つかひ)の来(こ)むと 待たすらむ 心不楽(さぶ)しく 南風(みなみ)吹き 雪消(ゆきげ)まさりて 射水川 流る水沫の よるべなみ 左夫流その子に 紐の緒の いつがり合ひて にほ鳥の 二人並びゐ 奈呉の海の 沖を深めて 惑(さど)はせる 君が心の 術(すべ)もすべなさ (万葉集巻18-4106)<オホナムチやスクナヒコナの神がおられた神代の昔から言い継いで来たことは、「父母を見れば尊く、妻や子供を見れば愛しく可愛い。これが世の道理である」。このように言い継いで来たのに、世間の人が口にする決まり文句だが、チサの花の真っ盛りのようにいとしい妻と朝夕、時に微笑み、時に嘆きつつ語らったことは、「いつまでもこんな風に貧しくはあるまい。天地の神様が助けて下さって、春花のように栄える時も来るだろう」ということ。その待っていた盛りの時が今ではないか。遠く離れ居て嘆いておいでの妻は、いつになったら使いが来るのやらと待って居られることだろう。その心を寂しくさせて、南風が吹いて雪解け水が増す射水川に流れる水沫のように寄るベなく、寂しがるそのサブル子に、紐の緒のように親しみ合い、カイツブリのように二人並び居て、奈呉の海の沖のようにも心深く迷ってしまっている貴方の心は、何ともどうしようもないことよ。>反歌3首あをによし 奈良にある妹が 高々に 待つらむ心 しかにはあらじか (同4107)<奈良の都に居る妻が、今か今かと貴方を待っているであろう心は、まさにその通りではありませんか。>里人の 見る目はづかし 左夫流子(さぶるこ)に 惑(さど)はす君が 宮出後姿(みやでしりぶり) (同4108)<里人の見る目も恥ずかしい。左夫流子にうつつを抜かしている貴方の出勤するうしろ姿であることよ。>紅(くれなゐ)は うつろふものぞ 橡(つるばみ)の なれにし衣に なほしかめやも (同4109)<(紅色は色褪せるもの。クヌギの実(ドングリ)で染めた薄墨色の着なれた衣には及ばぬものです。>右は、五月十五日、守(かみ)大伴宿禰家持作れり
2013.10.24
コメント(3)
-

打上川治水緑地公園など
昨日(21日)の銀輪散歩は北方面に向かいました。 朝8時半にMTBで家を出て、旧東高野街道を北へ。途中から国道170号(外環状道路)に出て、JR野崎駅付近で外環状に別れ、JR線(学研都市線)に沿って走り、JR四条畷駅の先で、国道旧170号に入る。旧170号線は東中野交差点で終り。そのまま直進すると府道20号(枚方富田林泉佐野線)となるが、この道を北上。府道20号はJR忍ヶ丘駅前でJR線に沿ってその東側を走る道とJR線を渡ってその西側を走る道とに分かれるが共に府道20号なのでややこしい。東側の道を行く。両20号はJR東寝屋川駅の先で再び合流する。 その合流点の交差点で左折して西行きの道に入り、JR線を渡ると府営寝屋川公園である。ちょっと立ち寄ってみる。結構広い。深北緑地を少し小さくしたような公園である。(寝屋川公園) 暫し公園内を散策したる後、再び府道20号に戻り、北へ。JR星田駅の手前の大谷橋交差点で左折、府道154号・私市太秦線に入り、これをを西へ。第二京阪道路の下を潜り、寝屋交差点で左折、府道18号(枚方交野寝屋川線)に入る。(第二京阪道路・府道154号私市太秦線との交差点) (寝屋交差点) この辺り一帯が、寝屋川、寝屋川市の名の起源をなす寝屋という土地である。何故、「寝屋」というかと言うと、藤原実高という長者の別荘が此の地にあり、東高野街道を行く旅人に無料でこれを宿に提供したからだそうな。そして、この藤原実高は御伽草子「鉢かづき姫」の主人公、初瀬姫の父親でもあるということで、寝屋川と鉢かづき姫とが繋がる。以前、こちら方面を銀輪散歩した際に「鉢かづき姫」の像が道脇にありましたが、その意味がやっと理解できた次第。(参照:「銀輪散歩・JR忍ヶ丘駅の先まで」2010.7.4.) また、継母にいじめられて家を追い出された姫を助けた公卿、山蔭三位中将というのは、藤原山蔭のことで、彼は京都の吉田神社、茨木市の総持寺を開創した人物。 というような具合に、話が芋づる式に広がって行くのが銀輪散歩というものの楽しさでもあります(笑)。ということで、寝屋ついでにこんな歌も思い出されますかな。夜もすがら ものおもふころは あけやらで ねやのひまさへ つれなかりけり (俊恵法師 千載集765 小倉百人一首85) さて、府道18号を南西に進むと左手に打上川治水緑地という公園がある。この公園も以前立ち寄ったことがある。この時はどの道を走っているという意識もなく走っていたので、その後、この公園が何処にあったのか、その位置が曖昧になっていましたが、今回その位置をしっかりと把握できましたので、今後は上の寝屋川公園と併せて、北方面への銀輪散歩の立ち寄り休憩地として利用できそうです。 <参考>「七夕」 2008.7.7.(打上川治水緑地)(同上)(同上) まだ、紅葉には早いのが大阪周辺の状況ですが、そんな中でいくつかの木が色付き始めていました。 「花は盛りを、月は隈なきを・・」ではありませぬが、「もみぢ」も「盛り」よりは、わずかに色付き始めた様、「もみぢそめける」様こそ趣も深きものにて・・と気取ってもみますかな(笑)。(同上)(同上)もみぢ始(そ)む さまこそよけれ わが苑は 疾(と)くや来ませと 色づくならし (偐家持)(同上) 打上川治水緑地から西へ400m位で国道170号(外環状道路)に出る。これを左折、南へ400m位行くと秦八丁交差点。ここで府道21号(八尾枚方線)に入る。外環を行くと深北緑地を経て花園中央公園であるが、今回は、一つ西側の道を南下することとする。 JR住道駅前に立ち寄り、其処で昼食を済ませてから帰宅することに。住道駅付近で寝屋川と恩智川が合流している。恩智川沿いを上流へ。 加納緑地で携帯に電話着信のあったことに気付く。友人の西◎氏からであった。折り返しの電話をするが、大した用ではありませなんだ。 帰宅すると12時半。住道駅~自宅は自転車で30分程度のよう、案外に近い。約4時間の銀輪散歩でありました。
2013.10.22
コメント(6)
-

銀輪万葉・マンホール
銀輪散歩の傍らマンホールの蓋を撮った写真が結構溜まっています。 この辺でそれらをまとめてアップして置くこととします。 先ず、地元、東大阪市のマンホールから。1.東大阪市 枚岡梅林に因んだ「梅」と花園ラグビー場に因んだ「ラグビー」の2種類があるようです。下のようなのもありますが、これは古いタイプのものかも知れません。2.大阪市 次は西隣の大阪市のもの。大阪城がデザインされています。3.八尾市 南隣の八尾市のもの。河内木綿がテーマのようです。4.柏原市 柏原市は葡萄栽培が盛ん。葡萄がデザインされています。5.藤井寺市 2種類ありましたが、右のものは道明寺天満宮の梅に因んで「梅」をデザインしたものでしょうね。 6.羽曳野市 これは抽象的過ぎて如何なるもののデザインであるかは不明。7.大東市 次は北隣の大東市です。「野崎詣りは屋形船で参ろ♪」の歌でもお馴染み、お染・久松所縁の野崎観音は大東市にある。右のものは、それをデザインしたものですな。 野崎駅前通りのそれは彩色されていて美しい。8.四条畷市 四条畷神社は楠木正行を祀っている。従って、右のそれはクスノキをデザインしているのでしょう。 9.交野市 星田妙見宮の脇を流れる妙見川沿いは古来からの桜の名所。従って、桜があしらわれていますが、裾にある花は何の花でしょう。 10.寝屋川市 桜とバラかクチナシの花。どういう意味が込められているのか、小生には解けませんですな。 下のようなのもありましたが、これは古いものでしょう。現在の同市の市章はネで矢を表し、ネ矢、それと両サイドの半円弧で川を意味し「ネ矢川」即ち「寝屋川」という駄洒落のようなもので、上にある通り。下のネに丸は昔の市章であるのでしょう。11.門真市 門真市の市の花はサツキということで、サツキがデザインされていますが、何故、市の花がサツキであるのかは存じ上げませぬ。 12.その他 近隣の市のものを掲載しましたが、遠方の町のものも、少しばかり、ありますので、ついでに掲載して置きます。 マンホールを写真に撮り始めたのは最近ですが、こうして眺めてみるとこれはこれで面白いものです。これからも折々に撮影してみることとします。(大阪府管理の流域下水のマンホール)(京都市のマンホール)(彦根市のマンホール)(山形県鶴岡市のマンホール) 鶴と大宝館(大正天皇即位を記念して建てられた建物で現在は郷土人物資料展示施設となっている)と桜が描かれている。(山形県由良温泉のマンホール) これも鶴岡市のものであるが、日本海側由良温泉のある由良地区のもの。(秋田県にかほ市のマンホール) これは旧象潟町の上浜地区、国道7号線にあったもの。手前の山は鳥海山か。鳥と海と山とで鳥海山を示しているのであろう。<追記> 偐山頭火氏から下記の写真がメールで送られて来ましたので、参考までに追加させて戴きます。同氏のブログで既に掲載されている写真かも知れませんが。 <参考>偐山頭火氏のブログはコチラからどうぞ。 (山口県湯田温泉のマンホール)<再追記>写真を整理していたらこんなのも見つかりました。ひろろさんへの返事コメントで、裏磐梯旅行ではマンホールの写真は撮っていないと申し上げましたが、撮っていたようであります(笑)。(猪苗代町のマンホール)猪苗代町の「町の花」は鷺草であるのだろう。
2013.10.21
コメント(8)
-

銀輪散歩・白鳥神社、誉田八幡、道明寺天満宮
昨日(18日)は恩智川沿いを南に走り、八尾市、柏原市、藤井寺市、羽曳野市と銀輪散歩して参りました。 何処に行くという目的もなく、気儘にと言うか、適当にと言うか、地図も持たず出鱈目に道を走りましたので、もう一度同じ道を走れと言われても、無理かも知れません。 大和川に出て、新大和橋を渡り石川沿いの道に入って直ぐに斜め右に入る道があり、そこを行くと国府八幡神社に突き当たる。神社の後が応神天皇の皇后である仲津媛の御陵である。そこを左折すると広い道(府道12号・堺大和高田線)に出る。それを右折し西へ。近鉄南大阪線の土師ノ里駅の前で左折、国道170号旧道を南へ。そこから先をどう走ったのか思い出せない。途中から路地に入ってジグザグに廻っているうちに方向も怪しくなってしまったからである。 途中、路地の奥でザクロを写真に撮りましたが、そこは近鉄南大阪線の古市駅のスグ裏でした。そして白鳥神社の前に出た。(上を向いてなっている柘榴) 柘榴は下を向いてなっているものですが、この柘榴は何故か上を向いています。隣の柘榴は横を向いている。まあ、どちらを向こうと柘榴の勝手ですから、文句はないのですが、何だか妙な気分です。(近鉄南大阪線・古市駅) 古市駅は近鉄南大阪線から長野線に乗り換えの駅でもある。近鉄長野線は古市駅から富田林、河内長野へとつながっている。 初めてこの駅で乗り換えた時、「長野」行きという表示の電車に妙な感じがしたものだが、大阪府にも長野(河内長野)があったことに気付き腑に落ちた次第。(白鳥神社)(同上) 白鳥神社は、偐山頭火さんとの銀輪散歩で4年前に訪れているので、その記事と下の説明板をご参照戴くこととし、コメントは省略です。 <参考>「藤井寺界隈」2009.11.22.(同上・説明板)(東高野街道<旧道>に面してある白鳥神社の一の鳥居) この鳥居を撮影している時にポツリと雨が落ちて来た。空を見上げると雨雲らしきものも見える。結局雨は降らなかったのであるが、引き返すこととしました。 東高野街道を北へと走る。(東高野街道の道標)(同上・古い道標) 道は誉田八幡宮の前を通るので立ち寄ることに。ここも、上掲・参考の「藤井寺界隈」をご参照下さい。(誉田八幡宮・拝殿)(同上・本殿)(同上・南大門) 今回初めて気付いたのがこれ。古戦場址碑。(誉田林合戦址碑)(同上副碑・説明板) 南北朝の頃から大阪夏の陣までしばしばこの辺りは戦場となったのですな。千早赤坂の方から流れて来る石川と大和から流れて来る大和川との合流点であり、古代の国道1号線とも言える竹内街道が通っていることなども考え合せると、それも納得されるというものである。 神社の北側は巨大な応神天皇陵古墳であるが立ち寄らず行く。 (注)応神天皇陵は「古市古墳群めぐり」2009.7.31.の記事参照 更に北へと走ると道明寺である。神仏分離で道明寺と道明寺天満宮に分れているが元々は一つのもの。今回は東側の道明寺天満宮にのみ立ち寄る。(道明寺天満宮・拝殿)(同上・本殿<裏の梅林から>)(小林一茶の句碑) 境内に小林一茶の句碑があった。これも今回初めて気付いたもの。特徴のある字は榊莫山揮毫によるもの。青梅や 餓鬼大将が 肌ぬいで (一茶) これは、寛政7年(1795年)西国行脚の途中に道明寺に立ち寄った一茶が詠んだ句。一茶がこの時に詠んだもう一つの句がこれ。暁や 鳥なき里の ほととぎす (一茶) 道明寺には菅原道真の叔母の覚寿尼が住んでいた。大宰府に左遷されて西国へと向かう途上、道真は道明寺を訪れ、叔母との別れを惜しむ。 別れに際して道真は「鳴けばこそ 別れも憂けれ 鶏の音の なからん里の 暁もがな」と詠んで旅立つ。以来、道明寺では鶏を飼わない習わしとなっているそうな。 一茶の上の句の「鳥なき里」はこの故事を踏まえたものである。(修羅<復元>) 境内には復元した修羅も展示されている。修羅は古代の運搬具であるが、詳しいことは下の説明板をご参照下さい。(修羅説明板) もう一つ境内に珍しいものがありました。楷の木。(楷の木) 説明板によると、孔子廟の前に弟子の子貢が植えた木の末裔のようである。 <参考>子貢・Wikipedia カイノキ・Wikipedia 楷の木の歴史(同上説明板) 道明寺の商店街を抜けると道明寺駅である。(近鉄・道明寺駅) 駅前で右折。踏切を渡って東に行くと玉手橋付近の石川畔に出る。石川自転車道に入って北へ。新大和橋を渡って恩智川沿いの道に戻り、来た道を帰る。花園中央公園に着いた頃は5時少し前。公園を暫し銀輪散歩したる後、家路に。(黄昏迫る花園中央公園と生駒山)
2013.10.19
コメント(6)
-

偐万葉・雑詠篇(その6)
偐万葉・雑詠篇(その6) 本日は、シリーズ第185弾、偐万葉・雑詠篇(その6)と致します。 「近現代の高岡」さんとは2010年6月からのブログ交流ですが、最近は同氏のブログ更新が途絶えています。アメキヨさん、マダムゴージャスさんは、それぞれアメキヨ篇、マダムゴージャス篇を編んでいましたが、長らく歌の書き込みも途絶えて・・。というようなことで、この後、歌の書き込みも多くは望めないと見込まれるお三方について、ひとまず、これまでの歌を一括して掲載することと致しました。 <参考>過去の偐万葉・雑詠篇はコチラからどうぞ。1.偐家持が「近現代の高岡」氏に贈りて詠める歌11首仏の子 なれど人の子 我もまた 忘るることあり 写真なかりき (高岡仏子)行き廻る 射水(いみづ)の川を 帯にせる 越の二上(ふたがみ) 見れども飽かず (注)射水の川=小矢部川のこと。万葉集では射水川と呼称。 (射水川こと小矢部川)名をしのみ 残し桜の 馬場通り 永久(とは)と言ひしも 夢のはかなき河内より 越の金屋に つながれる 鋳物の道も あるとやならむ (河内鋳麻呂(かふちのいまろ))(注)金屋=高岡市金屋町。高岡城築城の時、2代藩主前田利長は、 河内国丹南郡狭山郷日置庄の勅許鋳物師の流れを汲む 鋳物師七人衆を栃波郡西部金屋から城下に呼び寄せて 住まわせた。これが金屋町の始まりとされる。 (金屋町)我が里に 春花咲けり 越中の 伏木の里に 咲かまくはのち (偐武天皇)(本歌)わが里に 大雪ふれり 大原の 古(ふ)りにし里に ふらまくは後(のち) (天武天皇 巻2-103)八千種(やちぐさ)の 菓子もうつろふ 時々の 人の好みを 吾はうつさな (菓子麻呂)(注)上の歌は偐万葉掲載に当り一部修正しました。(本歌)八千種(やちぐさ)の 花はうつろふ 常磐なる 松の小枝(さえだ)を 吾(われ)は結ばな (大伴家持 巻20-4501) (反魂旦)としながに おくありませば おほをとめ いづくともとむ やかもちならむ (注)おほをとめ=坂上大嬢(さかのうへのおほをとめ、又は、おほいらつめ)。 大伴家持の正妻である。大伴坂上郎女と大伴宿奈 麻呂との間の娘。 (永姫ちゃん)和田川の 流れ清みか 恋ひ行けば 風の音ばかり 増山の城 (注)和田川=庄川支流の川。上流に増山城址がある。 (増山城)利長は 菓子で十番 陣中も 最中(もなか)夢中で 尚武にならぬ (前歯虫歯か)最中(もなか)攻め 五番あたりで 匙投げむ 前歯利長 虫歯なりけり (利長十番勝負) (注)1.利長十番勝負=高岡市の菓子舗が販売している最中(菓子) の商品名 2.上の歌は、偐万葉掲載に当り、第4句を一部修正しました。 (利長十番勝負)もののふの 八十伴(やそとも)の男(を)の 踏み平(な)らし 詣(まう)で来(こ)し神 尾山ぞこれに (尾山神社) (注)掲載の写真は「近現代の高岡」さんのブログからの転載です。 同氏のブログはコチラです。2.偐家持がアメキヨの郎女に贈りて詠める歌6首初夏(はつなつ)の 緑は光る 朝風に 今日も花咲く この道行かな (朝の散歩)新緑の 風もさやかに 吹くならむ ひとりし山に 恋ひてわれ来(こ)しさみどりの 風に吹かれて 風がまま 権現山の 朝の道行く (浅川峠への道)はやみとせ ブログの庭に 鳴く蝉の 声も繁けく なりにけるかも (偐蝉丸)豊の年 明けるとならし よきことの よしときざしも 妹にし立てばよしあしは 見るひと次第 よしあしを これときめぬも よしと言ふべし (よしのあしまろ) (注)掲載の写真はアメキヨさんのブログからの転載です。 アメキヨさんのブログはコチラです。 過去の偐万葉・アメキヨ篇(その1)(その2)はコチラからどうぞ。3.偐家持が宝郎女に贈りて詠める歌3首 並びに宝郎女が作れる歌1首ムンバイへ 発つらむ人の 草枕 旅の幸(さ)きけと あやめは咲きぬ入梅と 言へるも雨の 降らざるは 妹ムンバイに 発つを待つらし 宝郎女が作れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首置き去りの 吾子住む国を 覆う雲 地震(なゐ)よ襲うな 母帰るまで敷島の 大和の国も 残る子も 幸(さ)きくぞ待たむ 母帰るまで (注)マダムゴージャスさんのブログはコチラです。 過去の偐万葉・マダムゴージャス篇(その1)(その2)はコチラか らどうぞ。
2013.10.18
コメント(6)
-

若草歌壇・2013年彦根旅行編公開
偐山頭火さんからメールあり。 若草歌壇・2013年彦根旅行編が河内温泉大学図書館に収納され公開に付されたとのこと。 先の9月24・25日の若草読書会小旅行の際の持ち寄りの歌や俳句などを纏めたものであります。 まあ、若草の仲間うちの「遊び」「楽しみ」としてやっているものにてありますが、ご興味を持たれたお方は、下記写真の下のタイトルをクリックして戴くとご覧になれます。(「若草歌壇・平成25年(2013年)彦根旅行編」)<参考>若草読書会彦根旅行(1)許六と李由 (2)芹川 (3)楽々園、玄宮園 (4)彦根城 (5)中山道銀輪膝栗毛 (6)竹生島 (7)湖上にて河内温泉大学図書館はコチラからどうぞ。偐山頭火さんのブログはコチラからどうぞ。
2013.10.17
コメント(10)
-

白と青と黒はあるが赤はない。
白と青と黒はあるが赤はない。それは何か。 東西南北の四神は東・青龍(青)、西・白虎(白)、南・朱雀(赤)、北・玄武(黒)と4色で、季節の色もこれを当てて、青春・朱夏・白秋・玄冬となる。土俵の房の色もこの4色。 白と青と黒はあるが赤はないもの、それは鷺であります。 赤サギというのがありますが、これは詐欺師の「サギ」であって、鷺ではない。結婚詐欺専門の詐欺師は「赤サギ」と呼ぶそうな。 さて、本日の銀輪散歩で見掛けたのは、詐欺師ではなく、鷺。 白鷺と青鷺でありました。 銀輪散歩の定番コースの恩智川沿いの道にて見掛けました。(白鷺)(青鷺) それで、鷺の出て来る万葉歌はないかと探してみましたら、ありました。「鷺」という言葉が含まれる歌が1首、そして「鷺」そのものを詠んだ歌が1首あります。勿論、「詐欺師」を詠んだ歌なんぞはありませぬ(笑)。白鳥(しらとり)の 鷺坂(さぎさか)山の 松かげに 宿りて行かな 夜もふけ行くを (万葉集巻9-1687)(白鳥の鷺。その鷺の名を持つ鷺坂山の松の木陰に泊って行くことにしよう。夜も更けて行くことだ。)(注)白鳥の=鷺坂山の枕詞。 鷺坂山=京都府城陽市久世にある久世神社の丘陵のこととされる。 久世神社は、祭神が日本武尊であることから白鳥の宮とも 呼ばれている。日本武尊が死後、白鳥となって此処に飛来 したという伝説があるらしい。 白鷺の木を啄ひて飛ぶを詠む歌池神(いけがみ)の 力士舞(りきしまひ)かも 白鷺の 桙(ほこ)啄(く)ひ持ちて 飛び渡るらむ (万葉集巻16-3831)(池神の力士舞として、白鷺が桙をくわえて飛び渡っているのだろうか。)(注) 池神=地名説、寺名説などがあるが、所在は不明。また、 池の神様のこととする説もある。 力士舞=伎楽の一つで、仏法を守護する金剛力士が桙を持って、 美女を追っかけている怪物の崑崙を打ち据える舞。伎楽 は、推古20年(612年)百済の味摩之という人が来朝し て伝えたもの。彼を桜井に住まわせて少年達に舞を習わ せた。その場所が土舞台として今に伝えられている。 <参考> 土舞台は「磐余銀輪散歩(1)」2012.10.10.で紹介して います。(白鷺) 白鷺は、大サギ、中サギ、小サギと分類されるようだが、単独で見る段には小生には区別がつきません。(同上) 恩智川の鷺から、ここまで話を広げては「詐欺」みたいなものですが、詐欺罪には該当しない(笑)。刑法でいう詐欺罪は単に騙すことだけでは成立しない。金品を騙し取る意図がなくてはならないのでありますな。(青鷺)(同上)
2013.10.16
コメント(6)
-
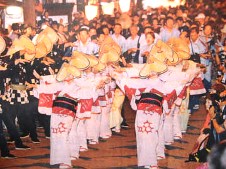
偐万葉・英坊篇(その24)
偐万葉・英坊篇(その24) 本日は、シリーズ第184弾、偐万葉・英坊篇(その24)と致します。 <参考>過去の偐万葉・英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌12首併せ俳句 並びに英麻呂が作れる歌11首併せ俳句 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首大国の 尊の担く 袋には 蒲の穂先が 出番待ちかなおほなむち ドクターGの はじめなり 蒲の穂敷きて 寝よとの見立て (因幡白兎病院) (注) おほなむち=おおなむぢ・大穴牟遅。大国主命のこと。 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首上臈の ような姿の 艶やかを 誰が呼びしか 女郎蜘蛛だと秋されば 花女郎花(をみなへし) 虫もまた 女郎蜘蛛なり その訳(わき)知らず蜘蛛糸を 撚(よっ)った長丈(ロング)の ドレスだど 着る人見る人 知るや知らずや絹糸は しるくと知るも 蜘蛛糸は 不知哉(いさや)と言ふの ほかなかるべし風の盆 過ぎたる後(のち)の 名残り風 吹かれ行かなむ 銀輪われは 英麻呂が贈り来れる歌2首に答へて詠める歌1首向日葵の 面満面の 力みには 自分は自分 もろにあらはすおわら町 暮れのぼんぼり 仄あかり 輪連れ手おどり 哀愁無限ひまはりも ややうつむける 風の盆 泣きに来よとか 胡弓の流る (風の盆) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる下2句 ぼたん君 店の百合みて 立ち歩み (英麻呂) ボタ餅なるに 焼き餅焼くか (偐家持) (注)萩の季節のあんこ餅は、おはぎ(お萩)であるのに対し、牡丹の 季節のそれはボタ餅(牡丹餅)と呼ばれる。 百合の花 生けて眺めて 牡丹(ボタン)と座り (英麻呂) 山か高砂 乙女か笹か (偐家持) (注)山は山百合、高砂は高砂百合、乙女は乙女百合(姫小百合)、 笹は笹百合のこと カマキリの 鎌に抓(つま)まれ 男(断)末魔 (英麻呂) 後悔するも 後(ゆり)の祭ぞ (偐家持) (注)「後」は、万葉の頃は「ゆり」とも訓じた。 いがぐりも 雨に濡れつつ 善徳寺 (筆蕪蕉) 菊の香と 城端歩く 節句かな (筆蕪蕉) <元句> 菊の香にくらがり登る節句かな (芭蕉) (栗) (城端・蔵回廊) 英麻呂が作れる上3句に偐家持が付けたる下2句による歌2首 勝ち取りに 行く頬に吹く 秋の風 (英麻呂) 負けたらあかんで 東京と碁に (天童ごうち) 止まりしも 名は知らねどの 涼し虫 (英麻呂) みどりも深き 秋のとばくち (偐虫持)江戸へ行く 道をきく馬鹿 示す馬鹿 あっちと言ふの ほかなからなむ (江戸家菊八) (江戸への道標) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首越の山 二上麓で 案ずるは 怒涛彼方の 大和二上玉くしげ 二上山は 大和越 ふたつながらに 神からの山 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌1首三輪山の 登拝の苦の 汗の態 足の笑いと 共の思い出三輪山の 頂に懸るな たれ雲よ 人は見たしに 隠しまからぬみは山に しかと登らな くもなくも 転びなせそや こしの旅人 (注) みは山に=「三輪山に」と「身は山に」を掛けている。 くもなくも=「雲なくも」と「苦もなくも」を掛けている。 こしの旅人=「来しの旅人」と「越の旅人」を掛けている。 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持の返せる歌2首愚痴を聞き ガマの穂の身は ストレスで 丈の伸びより 寸に太りし若草の 殿に鎮座の 安椅子の 肘の手握り 人型合わせガマの穂の ガマンももはや これまでか 愚痴のあれこれ 弱りもぞする (痩せ我慢の太りガマ)若草の 主(あるじ)が身にも 合はせれど 車つかぬ身 ここだ悲しき (車椅子に嫉妬の安楽椅子) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首夕照に 映える雲斑(まだら) 美しき 色のたとえぞ なくて哀しきい群れ行く 千々の雲見ゆ 夕ぐれは 秋こそまされ 人ぞ恋(こほ)しきはくさんに たてやまつるぎ みなよけど ふたかみの名の なきぞかなしき 「実」よりも 「虚」がまさりける 坊の柿 (筆蕪蕉) (柿・貼り絵)<注>掲載の写真・絵画は全て英坊氏のブログからの転載です。
2013.10.14
コメント(6)
-

囲碁例会・北海道紅葉便り、そして会津みやげ
昨日は囲碁例会の日でありましたが、天気予報は台風通過の名残りの雨が降るとの予想でもあったので、自転車は取り止め、電車で梅田に向かいました。しかし、実際には雨は降らず、これなら銀輪散歩も可能であったのにと悔しがることしきり(笑)。 雨の予報もあってか、出席者は青◎氏、福◎氏と小生の3人だけ。 先ず、福◎氏と対戦。概ね優勢のうちに寄せとなり、後は駄目を詰めるだけとなり、無造作に詰めていると、下辺黒地に取り込んでいた2目を、駄目を詰める前に上げてしまわなければならない形になっていることを見落としていて、その指摘を福◎氏から受けることに。駄目詰めをしてから上げてもいいと勘違いしていたので、本当は大逆転で負けとなっている処でしたが、お情けで、そのアドバイスを相手から頂戴するという、お情けの勝利となりました。 続く青◎氏との対戦は、黒模様を消しに行った白石が二つに分断されながらも青◎氏の手順のミスもあって両方とも活きてしまい、中盤までの劣勢を逆転しての勝利。本日は2戦2勝となり、これで今年の通算成績は18勝28敗となりました。6月から8月までの11連敗の所為で、今年の勝率5割確保は絶望的ですが、少しでも「借金」を返済して置きたいものと(笑)。 ということで、囲碁例会に伴う銀輪散歩の話題が今回はありませんので、先日、と言っても10日ほど前のことになりますが、友人の岬麻呂氏から届いた「北海道紅葉便り」の写真をご紹介して置くことと致します。(黒岳五合目付近・中央手前は竜胆の花) 関西では紅葉は未だ先ですが、北海道はもうすっかり紅葉していますね。 木花咲耶姫は南から北へ旅をされますが、竜田姫は北からお越しになられるのでありますな。 知床半島では、今年は紅葉せぬままに枯れ葉となってしまうという異変が生じていると聞きますが、十勝地方はそういうことではないようですね。いやはや、それにしても見事な紅葉です。(銀泉台・赤岳南東斜面)(旭岳ロープウェイ)(十勝岳温泉・陵雲閣の露天風呂からの眺望)(富良野鳥沼公園)(富良野・風のガーデン) 風のガーデンは前回の旅便りでもその写真がありましたので、2度目の登場となります。 <参考>「友あり、紫陽花・タオル・旅便り来たる」 2013.8.2.(ファーム富田から眺める十勝連山)(美瑛・四季彩の丘) そして、本日は、「第128回智麻呂展」の記事を印刷に打ち出して(と言っても、そのまま印刷しては先頃のレイアウト変更でサイド欄が拡大したアオリを受けて字が随分と小さくなってしまいます。それで、日記本文をコピーして別用紙に貼り付け、写真や文字配置などレイアウトの編集をする、という手間が必要になったのですが・・)、智麻呂邸にお持ちしました。第1回展からずっと印刷したものをクリアファイルに入れて、表紙も作り、「智麻呂美術全集」にしているのでありますが、これが現在第21巻目に入って居ります(笑)。 お伺いすると、智麻呂さんはデイサービスから未だお戻りではなく、小生も他に用が出来てしまったので、智麻呂さんお帰りを待たず、第128回展の分をファイルに収納する作業だけ行って、早々においとましたのでありましたが、奥様の恒郎女さんは先頃の会津旅行からお帰りになったばかりにて、そのお土産まで頂戴してしまいました(下掲)。 (会津旅行のお土産・柏屋薄皮小饅頭) 小生は智麻呂さんのように、これを絵に画いてお礼状にするなどという高度な技術は持ち合わせませんので、デジカメに撮って、ブログに掲載して、そのお礼とさせて戴きます。 嘉永5年(1852年)奥州街道の郡山宿に薄皮茶屋として生まれたのがこの菓子舗の由来だそうですが、智麻呂絵画展の場合に倣いまして、どうぞ皆さまもお一つお召し上がり下さいませ(笑)。
2013.10.10
コメント(8)
-

偐万葉・ひろろ篇(その14)
偐万葉・ひろろ篇(その14) 本日は、偐万葉シリーズ第183弾、ひろろ篇(その14)であります。 <参考> 過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌17首 並びにひろろの郎女が作れる歌3首一の戸の 川にし春は 来(きた)れるか わが泣く涙 干(ひ)なくはあれど (一ノ戸川)山都(やまと)には 田植えのときの 近づけり 母とふ人の 今は居なくに (山都町)高々の 橋は変らず 今日(けふ)もあり 母とたぐひて 見し日恋(こほ)しも (一ノ戸川橋梁)みなぎらふ 田ごとの鏡 光る風 山都の春の 見らくしよしも (注)みなぎらふ=漲(みなぎ)らふ。水が満ち溢れている。 「みなぎる」の未然形「みなぎら」に反復継続 の助動詞「ふ」がついたもの。 (「春」)穂高には 星の光の 降る音の するとふ言ひし ひとのありけり (「穂高」)朝霧の たち流れゆく 梓川 鳥鳴き行きて 目覚むるならしかみかうち かぜもさやさや わぎもこは みそひともじの ゑをかくらむか (にせやかもち) (上高地風もさやさや我妹子は三十一文字の絵を描くらむか)はつなつの やまはうれしも もくだうも わがあしうらを おしかへしくる (にせやかもち) (初夏の山は嬉しも木道も我が足裏を押し返し来る) 上2首はひろろの郎女が作れる下記の歌3首に追和せるものなり。ひんやりと 峰より降るは 青い風 皮膚より入(い)りて 肺に届きつ緑陰の 木道きしむ 登山靴 カラマツ林 雲湧きかかる朝靄の ベールまといて 西穂高 水面(みなも)の投影(かげ)に 水鳥の二羽 (大正池) (「初夏」)森黒く 水面(みなも)の夕照 阿寒湖は 今日のひと日に ゑみくれるらし (阿寒湖夕照)ロンドンは 山の彼方に 朱(あけ)に染む 雲に君をし 思ひつつぞ居り (エマの郎女)恋ひ恋ひて わが待つ君に 逢へる日の いつとや待たむ 会津この地に(エマの郎女) (「彼方へ」) ふるさとや キウイに偲ぶ 盂蘭盆会 (筆蕪蕉) (元句) 旧里(ふるさと)や 臍の緒に泣く 年の暮 (芭蕉)盂蘭盆会(うらぼんえ) 庭にし立てば 父母(ちちはは)の 植えしキウイの ここだも生(な)れる恋ひ来れば ここぞと鳴きぬ 油蝉 夏の七日を 惜しむとあらし (キウイ) (「夏の川」)みちのくの ドガにしなけど をどりこを ゑがきぬ今日の ひはひろろのひ (ひろのいらつめ) (「lesson」)かはきたる すなのごとにも さらさらと じざいのこころ うしなふべしや (にせやかもち)すくふての ゆびすりぬけて こぼるるは かはきてすなも いのちうるらし (にせやかもち) (「砂浜」)雨の日は 雨をしめでむ 晴れの日は 白き家にて ランチもよしも (「雨の日」) (レストラン)(注)掲載の写真、絵画は全てひろろさんのブログからの転載です。
2013.10.08
コメント(12)
-

第128回智麻呂絵画展
第128回智麻呂絵画展 智麻呂絵画展の開催であります。今回は7作品と点数はやや少なめでありますが、コスモスやヒガンバナや栗の実など秋らしい題材の絵が揃いました。どうぞごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~(アケビ) まず、アケビの絵から。ともまろが 花瓶にあけび さし添へて 描(ゑが)けば暮るる 若草の里 (偐家持) (本歌) ますらをが 爪木(つまき)にあけび さし添へて 暮るれば帰る 大原の里 (寂然<藤原頼業> 山家集1215) (注)爪木=「つまぎ」、折り取った薪のこと。 デイサービスで通って居られる施設のどなたかが智麻呂さんのためにお持ち下さったものだそうです。下の「茶の実」も「栗」も同様です。 皆さんが温かく智麻呂さんの絵を応援し、支えて下さっているのであり、まことに有難いことであります。(茶の実)それ光琳 二つ茶の実は 家紋にて 十(とを)にしなれば 智麻呂絵画 (偐家持) (注) 光琳二つ茶の実=茶の実家紋の一種である。(コスモス) このコスモスは小万知写真集から絵にされたもの。 何やらおめでたい紅白のコスモスであります(笑)。(白い彼岸花) この彼岸花は、デイサービスの施設「福寿苑」に咲いていたものだそうです。 下記の「長崎物語」の歌詞を待つまでもなく、彼岸花はやはり「赤い花」でなくてはならないのであるが、白い花も悪くはない。 赤い花なら 曼珠沙華 阿蘭陀屋敷に 雨が降る 濡れて泣いてる じゃがたらお春 未練な出船の あゝ鐘が鳴る ララ鐘が鳴る ついでに、もう一つ彼岸花の歌をリンクして置くこととしましょう。 ♪♪山口百恵「曼珠沙華」 次は秋の絵の定番。栗の絵です。(栗の実) 栗の実の絵は智麻呂さんのお得意な絵の一つ。 そのことをご存じででもあったか、旅のお土産にとデイサービス施設のどなたかがお持ち下さったそうな。 ♪♪安田章子「里の秋」(安福寺)<参考>「安福寺から錦織公園まで」2009.11.1. これは大阪柏原市の玉手山丘陵の一角にある安福寺の絵。 小生も何度か銀輪散歩で訪問している寺であるが、これは、偐山頭火さんが銀輪散歩の傍ら撮影されたもので、その写真を持って智麻呂邸にやって来て、これを描いたらどうか、と提案されたよう。花の智麻呂、時々「虫麻呂」にてありますれば、風景画はまれにしかお描きにならない。 そういう智麻呂さんに対して、偐山頭火さんはもっと風景画を描かせたいと思われたのやも知れませんですな。 それで、という訳でもないでしょうが、シルクロードの風景画・・まで登場と思いきや・・・、(平山郁夫画伯の「月下シルクロードを行く」の模写) これは、上のキャプションを読むまでもなく、それとお気付きになった方も多いかと存じますが、平山郁夫画伯の絵「月下シルクロードを行く」の模写であります。 先日(9月24・25日)の若草読書会の彦根旅行の2日目は、智麻呂・恒郎女ご夫妻は、偐山頭火さんの車で佐川美術館に行かれました。その折に買い求められた絵ハガキの一つが、平山画伯のこの絵であったという次第。絵ハガキから智麻呂絵画にされましたが、智麻呂さんにとっては、絵を模写しているという意識ではなく、これも一つの風景と見て、写生されたに過ぎないものでありますから、これも亦、智麻呂絵画と言うべきなのであります。 では、これにて第128回智麻呂絵画展はお開きと致します。本日もご来場、ご覧下さり、有難うございました。
2013.10.07
コメント(14)
-

朱雀・醍醐天皇陵へ
<承前> 醍醐寺西大門まで戻り、駐輪してあったトレンクルに乗車。北へ。 旧奈良街道の一つ山側の道を北上していることになる。 奈良街道は追分で終点。そこで西(左)からの東海道に繋がり、東(右)に行くと逢坂の関を越える、所謂大関越えで近江の国へと至るのであるが、今日はそのような大遠征をする心算はない。 醍醐寺を出て二つ目の辻の先、右手にあるのが朱雀天皇陵。(朱雀天皇醍醐陵) 朱雀天皇(諱は寛明(ゆたあきら))は第61代天皇(在位930年~946年)。醍醐天皇の第11皇子。 935年・936年の平将門の乱・藤原純友の乱(承平天慶の乱)の時の天皇である。子供がいなかったので、早々と同母弟の成明(なりあきら)親王(村上天皇)に譲位している。(同上) 遠近(をちこち)の 風とぞ今は なりなまし かひなきものは 我が身なりけり (朱雀天皇 新続古今集巻16-1559)(同上)<参考>朱雀天皇・Wikipedia 朱雀天皇の父親である醍醐天皇の御陵は更に300mほど北に行った処にある。御陵の前のバス停の名も「醍醐天皇陵」である。(醍醐天皇後山科陵) 醍醐天皇(在位897年~930年)は第60代天皇。第59代宇多天皇の第一皇子。父親の宇多天皇が親王から臣籍降下して源定省(さだみ)と名乗っていた頃に生まれたのが源維城(これざね)(のちの醍醐天皇)。光孝天皇が後継者を指名しないまま重態に陥ったため、藤原基経らの策動により、源定省は皇族に復帰し皇太子となる。光孝崩御後に即位して天皇となる。これに伴い、その子の源維城も敦仁(あつひと)に改名し、皇族に列せられることとなり、宇多天皇即位により皇太子となる。やがて宇多から譲位を受け醍醐天皇となるという、まあ、ちょっと変った経歴をたどる天皇である。 宇多天皇と言えば、菅原道真など非藤原系の有能な人材を登用して、藤原北家嫡流への権力集中をけん制しようとした天皇であるが、早々と位を譲った息子の醍醐天皇と対立するようになる。その結果、宇多の信任の厚かった道真も醍醐から疎まれるようになり、藤原時平の讒言により道真が太宰府に左遷されることとなるのはどなたもご存じの有名なお話であります。(同上)<参考>醍醐天皇・Wikipediaはかなくも 明けにけるかな 朝露の おきてののちぞ 消えまさりける (醍醐天皇 新古今集巻12-1171)(同上) 醍醐天皇陵で予定の目的地は全てクリア。帰途に。(奈良街道<府道35号>から醍醐山を望む。) JR奈良線の六地蔵駅まで戻るが、JR奈良線で奈良駅まで行ったのでは近鉄線への連絡が不便となる。ならばと、近鉄京都線の桃山御陵前駅まで走ることとする。 桃山御陵前駅到着。そこでトレンクルをたたみ、急行で西大寺へ。西大寺で近鉄奈良線に乗り換え、石切駅下車。石切駅から再びトレンクルで自宅まで走る。 途中立ち寄った東石切公園では桐の大木が沢山の実を付けていました。公園から西の空を見やるとかすかに赤くなり始めている。それではと、枚岡梅林に回り、高みの道を辿って自宅へ。夕焼の写真を今回の記事の締め括りに使おうという魂胆もあっての遠回り作戦でありました(笑)。(桐の実・東石切公園にて)(大阪平野夕景・枚岡梅林から)(同上・自宅付近から) これにて、「友人とランチのち銀輪散歩」の巻、全3巻完結であります。ご覧下さり有難うございました。<完>
2013.10.06
コメント(2)
-

醍醐寺へ
<承前> 石田の杜から奈良街道(府道35号線)に出て、北へと向かう。 途中、合場川で旧奈良街道と分岐する。旧道を行く。醍醐寺は旧道沿いにある。分岐から醍醐寺総門前までは1km余。その中間位に善願寺という寺があった。光明皇后の発願、行基によって創建された寺というから、醍醐寺よりも古く、万葉時代からある由緒ある寺なのでありました。(善願寺) (善願寺説明板) (腹帯地蔵) 石田の杜も醍醐寺も気にはしつつも今まで小生は訪れたことがなかったのでありました。 醍醐寺と言うと、秀吉の「醍醐の花見」で広く知られる寺であるが、何故かこれまで行く機会がないままでありました。今回、同期の桜と会ったからの洒落ではありませぬが、ヤカモチも「醍醐の花見」ならぬ「醍醐の秋風」に吹かれてもみむ、と思い立った次第。 醍醐寺は真言宗醍醐派の総本山にて、貞観16年(874年)、弘法大師の孫弟子に当る理源大師・聖宝の創建にかかる寺である。 醍醐山(笠取山)に登った聖宝の前に白髪の老人が現れるが、これがこの地の神、横尾明神。この神から山を譲り受けた聖宝が観音像を刻み山上に祀ったのが醍醐寺の始まりと伝えられる。 山上の伽藍を上醍醐、山下のそれを下醍醐と呼ぶそうだが、今回は時間の都合上、下醍醐だけの拝観であります。はい、醍醐寺前に到着しました。(醍醐寺・総門)(唐門<国宝>) この門の向こうは三宝院。三宝院は醍醐寺第14世座主勝覚によって永久3年(1115年)に創建されたもの。現在の三宝院はこの唐門なども含め、慶長3年(1598年)に秀吉によって再建されたもの。(西大門・豊臣秀頼による再建とのこと。) 三宝院はやり過ごし、奥へ進むと西大門。この門前にトレンクルを駐輪して、醍醐寺境内に入場。ここから先が有料です。 (左・吽形、右・阿形の仁王像)(西大門を入ると緑のトンネルである。) この先で、左に行くと金堂、右に行くと清瀧宮、五重塔。先ず左から廻る。(金堂<国宝>) このお堂も秀吉の命による再建で、秀頼の時代、慶長5年(1600年)の完成とのこと。醍醐寺の中心をなす建物にて、この堂に安置されている薬師如来坐像が醍醐寺のご本尊である。(不動堂) 金堂の東隣にあるのは不動堂。5体の明王像が安置されている。前庭が護摩道場になっている。(真如三昧耶堂) 不動堂の東隣が真如三昧耶堂。(清瀧宮本殿<重文>) 右側エリアにあるのは清瀧宮本殿と拝殿。その奥に五重の塔がある。(五重塔) 左右エリアの間の道を奥へと行くと祖師堂である。 堂内には弘法大師と理源大師の像が祀られている。(祖師堂)(旧伝法学院<修行道場>) 祖師堂の東隣(奥)が旧伝宝院建物。若き修行僧たちはここで修行に励んだのでもあろう。(観音堂への門) 旧伝法院から更に奥へ。小さな門を潜ると、観音堂と鐘楼のある、下醍醐の一番奥のエリアとなる。(鐘楼)(観音堂) 西国三十三観音霊場の11番札所である山上の上醍醐准胝堂の遙拝所として建てられたもので、准胝観音菩薩が祀られている。(弁天堂) この池の畔の休憩所「寿庵」の先に出口があって、其処から山上の上醍醐への道が続いているのであるが、今回は此処までとし、上醍醐は次回の訪問まで取って置くこととします。これもヤカモチ流です。 と言う訳で、秀吉さんの醍醐の花見跡もまたの機会に繰越しであります。花どきに あらねもみぢも 早ければ 下の醍醐で すませけるかな (偐家持) この後、朱雀、醍醐両天皇陵を廻りますが、それは明日の日記に、ということとして、今日はここまで、です。(つづく)
2013.10.05
コメント(4)
-

友人とランチのち銀輪散歩・石田の杜
本日は、大学同期の楽老君と道◎君と京都駅烏丸口で待ち合わせ、ランチでデートでありました(笑)。 横浜在住の楽老君の兄上が大津にいらして、その兄上宅に所用あってこちらまでやって来たついでに昼飯でも一緒に喰おうという同君の誘いで、京都在住の道◎君と小生がそれに乗ったという次第。 楽老君とは今年4月23日以来の再会。道◎君とは5月31日以来。ブログのお陰でそういうことが分かるので便利。 京都駅到着が10時20分。待ち合わせ場所には待ち合わせの11時よりも30分も早い10時半に到着。小生が一番乗り。やがて楽老君が現れ、続いて道◎君到着。駅ビルの屋上庭園から京都市街を眺めた後、8階の食堂街へ。11時を少し過ぎた位なので、どの店も空いている。楽老君が「ここがよかろう。」という「おばんざい京百菜」という店に入る。(JR京都駅烏丸中央口) <参考>京都駅・Wikipedia 京都駅は梅田スカイビルを設計した原広司氏の設計なので、両者は何となく似た雰囲気を持っている。(京都駅ビル大階段上から2階自由通路を望む。) 1時間余のランチタイム。12時半に両君と別れ、小生は銀輪散歩に。実は折りたたみ自転車トレンクルを持ってやって来ていたのでありました。 当初は、京都駅から自転車で走るつもりでいましたが、時間が読めないこともあって、気が変り、JR奈良線で伏見区、宇治川近くの六地蔵駅まで電車で行くこととする。 目的地は、石田の杜(天穂日命神社)、醍醐寺、朱雀天皇陵、醍醐天皇陵である。(石田の杜・天穂日命神社東側正面参道) 石碑に「万葉遺跡」とあるように、「石田の杜」は万葉集に登場する古い神社なのである。現在は、天穂日命神社というのが正式な名称となっているが、古くは石田神社、田中神社などとも呼ばれたらしい。 地下鉄東西線が山科から南へと延びて来る通り(府道)に面して神社はある。地下鉄石田駅から南西100m位の位置にある。 (南側脇入口) (天穂日命神社説明板) 六地蔵側から北東方向に府道を上って行くと、道の左手に先ず目に入るのが、脇から入る路地の入口に建てられた小さい石碑「石田の杜」である。うっかりしていると見落としてしまうような位置と大きさであるが、これを見落としても大丈夫。更に5~60mばかり行くと正面参道の入り口に建てられている大きい「石田の杜」の碑に出くわす。これを見落とす奴は居るまい。 うっかりヤカモチも今回は小さい方の碑でそれと気付き、細い通路を入って行きました。鳥居の前で広い正面の参道に出る。(天穂日命神社)(藤原宇合歌碑) 正面鳥居脇に歌碑が2基建てられている。藤原宇合の歌碑と順徳天皇の歌碑である。宇合の歌碑の歌は、万葉集巻9に宇合の歌3首として掲載されているうちの1首である。山科の 石田の小野の ははそ原 見つつか君が 山路越ゆらむ (藤原宇合 万葉集巻9-1730) (注)ははそ=柞。ブナ科のコナラの木のこと。 この歌の次に掲載されているのが下記の歌。山科の 石田(いはた)の杜に 幣(ぬさ)置かば けだし我妹(わぎも)に 直(ただ)に逢はむかも (同上 同巻9-1731)( 上の1730番の歌は「君が山路越ゆらむ」とあるように、「君」とは男性を指して言う言葉であるから、女性の作った歌と考えるのが普通。女性が旅行く夫か恋人のことを思って詠んでいる歌である。宇合の作ではなく、宇合の妻か恋人が詠んだものが間違って宇合作として掲載された可能性がある。まあ、宇合が洒落っ気のある御仁にて、1731番の歌を詠むついでに、相聞歌風に仕立てた方が面白かろうと、女性側の歌まで作ってしまった、という可能性もなくはないですが。(順徳院歌碑) 石田の杜は奈良街道の西250m位の位置にある。 今は住宅などが建て込み、間に地下鉄が走る府道が通っていて、奈良街道とのつながりを感じにくくしているが、古代にあっては奈良から山背を経て近江へと向かうため奈良街道を通る旅人にとっては、逢坂山を越えて行くに当って、先ず旅の無事を祈願する場所であり、奈良街道にとって大切な場所でもあったのだろう。 そんなこともあって、万葉の頃から歌枕となっていたのであり、後世の人もそのような場所として逢坂山と並んで石田の杜を歌枕にして行く。順徳さんもその一人である。ひぐらしの 涙やよそに 余るらん 秋と石田の 森の下風 (順徳院) この歌がいつどのような状況下で詠まれたものか知らないが、順徳院と言えば、父後鳥羽院の「承久の変」に連座して佐渡に流されたお方。佐渡にある真野御陵はこの方のお墓。佐渡へと流される旅の途中で詠んだ歌だとすれば、その趣も一層深いものとなるが・・。(天穂日命神社・本殿)(本殿から鳥居方向の眺め) 往時は、もっと広大で深い森であったのだろうと思われるが、市街の中にこのように樹林が残っているのは嬉しいことである。(境内奥から東方向を望む。)山背(やましろ)の 石田(いはた)の杜に 心鈍(おそ)く 手向(たむけ)したれや 妹(いも)に逢ひがたき (柿本人麻呂歌集 万葉集巻12-2856) (注)こちらの「石田の杜」は八幡市にある式内社石田神社だという説 もあるようです。(本殿向かいの社殿)(神社の東側、日野通りと奈良街道を結ぶ路地にある灯籠と碑。 灯籠には「田中社」とある。合祀されていた田中明神は明治41 年に木幡の許波多神社に遷座されたそうな。) さて、これより醍醐寺に向かいます。(山科川。新小石橋の上から上流を見る。) その前に山科川にご挨拶して行く。正面の手前の低い山が北端山。その右後ろの山が高塚山、その奥が音羽山であろう。音羽山の左奥には逢坂の関があり、近江・琵琶湖へと繋がっているのである。 どうやら、文字数制限のようです。続きは明日です。(つづく)
2013.10.04
コメント(3)
-

囲碁例会・空は秋にしあれど
今日は囲碁例会の日。MTBで梅田まで。 出掛けるのが遅めだったので、梅田スカイビルに着いたのは12時45分前後。花野に新しく出来たカフェテラスでパスタのランチ。 昼食を済ませて会場に入ると、既に福◎氏と荒◎氏が来て居られて対局が始まっていました。青◎氏も来て居られたので、小生は青◎氏とお手合わせ戴く。中盤で思い違いをして白石7つを取られてしまい、下辺の白地がかなり凹んでしまいましたが、前半で稼いだ地のお陰で勝利。 次に、荒◎氏と対局。上辺の黒模様を消しに行った石が黒の薄みをうまくついて生きることができた上、、先手が回って来たので、黒の手抜きの石を攻めてこれを殺し、勝負あったで、これも勝利。 続く福◎氏との対局は序盤で勘違いの悪手を打ってしまい、左辺に大きな白地を形成される羽目となり、20目近い大差で負け。2勝1敗。 最後に、竹◎氏と青◎氏との対局を途中から見学して、本日は終了。本日の出席者は小生を含めて5名と少なめでした。これで、今年のこれまでの成績は16勝28敗。11連敗が響き、今年の負け越しはこれで確定のようです。 帰途は、花園ラグビー場、花園中央公園に立ち寄ったのみで、銀輪散歩でご紹介すべきものが何といってありません。で、今日の夕刻の空をでもご覧戴くことと致しましょう。 その前に、ここ暫くは見掛けなかったのですが、今日またしても芝生広場で黒い大型犬をリードから放し、ボールを投げて取って来させるという遊びをしている男性が居ました。この人は常習者ですが、近くにドッグランが設置されているのに、そこで遊ばせずに、この芝生広場を使う。すぐ傍に「犬をリードから放して散歩させないで下さい。」という公園管理者の看板があるというのに、何を考えているのやら。 さて、空はすっかり秋のそれであり、吹く風も涼しく心地良いのであるが、自転車でスピードを上げて漕ぐとまだまだ暑く、汗びっしょりになる。銀輪散歩に適した涼しさになるのは、もう少し先のようですな。(花園公園夕照) 右側の建物は花園ラグビー場のメイングラウンドの建物。 空は秋のそれ。雲が夕日に輝いて美しい。さびしさに 宿をたちいでて ながむれば いづこもおなじ 秋の夕ぐれ (良暹法師 後拾遺集333 小倉百人一首70) 振り返ると生駒山。人麻呂風には「かへり見すれば」となるのであろうが、人麻呂は東の空から西の空をかへり見たのであれば、ヤカモチの「かへり見」は反対、西の空から東の空へ、であるから、歌にはならないですかな。西空の 雲のあけにし 染む見えて かへり見すれど 月は出で来ぬ (偐家持) 人麻呂曰く「ヤカモチさん。場所が違うのはいいとしても、 かへり見する季節も、時刻も、方向も間違っ ていますよ。」 ヤカモチ「ムムムムム・・・」(生駒山夕景) 話は変わって、絵の話。 囲碁サークルのメンバーでは、青◎氏と福◎氏とは絵もお描きになられる。 福◎氏の絵は以前(下記<参考>参照)にもご紹介したが、今日、新作の絵画を持ち込まれていました。近く開催される展覧会に出品されるらしい。 で、撮影させて戴きました。展覧会よりも一足早い公開となります。 「アッカンベー」をしているみたいな、舌を少し出したお猿さんの表情がいいですね。 <参考>福◎氏の絵画を掲載している記事は下記です。 「SS会・2013年夏の陣 2013.8.5.」(「ここまでおいで」 福◎氏画)
2013.10.02
コメント(9)
全22件 (22件中 1-22件目)
1