2014年02月の記事
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-

もう一つの弓削神社そして物部守屋の墓
(承前) 前回の記事でJR志紀駅の東側にある弓削神社の写真を掲載しましたが、駅の西側にあるもう一つの弓削神社は、これまでブログには取り上げていないことが分かりましたので、本日再度JR志紀駅目指して銀輪散歩して参りました。 午後1時過ぎに家を出て、弓削神社に到着したのが1時50分。今回は恩智川沿いを走り、八尾翠翔高校の前で西に入り、近鉄線を渡り、曙川東小学校の前で玉串川沿いを上流(南)へ、長瀬川との分流地点で右折、長瀬川沿いを北西に進む、というコースでやって来ましたが、このルートだと自宅から志紀駅まで45分を要するのみ。思ったよりも近い。(西の弓削神社) 東の弓削神社は無人であるが、こちらは宮司さんも居て、社務所もある。 境内は何やら工事中で、写真撮影にはちょっと不向きな状況であるが、致し方なきことにて候。(同上・拝殿) 弓削氏は物部氏の配下の氏族。物部氏と同じくニギハヤヒ、ウマシマジを祖とする。蘇我馬子との権力闘争に敗れた物部守屋は母親が弓削氏の出自であったことから、物部弓削連守屋とも名乗ったとされる。 蘇我物部戦争に敗れた物部氏は弓削氏や石上氏などを名乗るが、守屋の子孫は弓削氏を名乗ったようだ。 天武天皇の皇子に弓削皇子という方が居られる。弓削氏との関連などは知らぬが、同母兄の長皇子と共に万葉集に歌を残している。中でも有名なのは、晩年の額田王との間に交わした次の歌でしょう。 吉野宮に幸しし時、弓削皇子、額田王に贈り与へませる歌1首いにしへに 恋ふる鳥かも ゆづる葉の 御井の上より 鳴きわたり行く (万葉集巻2-111) 額田王、和へ奉れる歌1首いにしへに 恋ふらむ鳥は ほととぎす けだしや鳴きし 吾が思へるごと (万葉集巻2-112) 小生は紀皇女に贈った歌4首の方が好きであるが、その内の1首を下に記して置きましょう。夕さらば 潮満ち来(き)なむ 住吉(すみのえ)の 浅香(あさか)の浦に 玉藻刈りてな (弓削皇子 万葉集2-121)(同上・本殿) (神社の由来などの碑。クリックすると拡大写真で見ることが出来ます。) 弓削氏が歴史の上で最も権勢を持ったのは、称徳天皇の時代でしょうか。この時期には天皇はこの地に行宮(由義宮)を設置している。 志紀駅北方1.5kmほどの処にある由義神社には由義宮跡地の碑が建てられているが、それが何処にあったのかは定かではない。 <参考>関連記事 由義神社は次の記事に出ています。 近隣散歩・八尾空港まで 2011.10.4.(東西の弓削神社位置図 JR線に平行している川が長瀬川。) 上の地図で、志紀駅の北東にある河内大社と記載されているのが、東の弓削神社、駅の南西に弓削会館とある字のスグ上部(北側)にあるのが西の弓削神社である。 (若林南山句碑) 弓削神社境内に上のような句碑がありました。若林南山。存じ上げない名であったが、「河内野創刊以来編集長兼発行人」という記載に反応しました。 一昨日立ち寄った喫茶店「ナナ(nana)」で、店の方が「万葉関係の記事がある。」として見せて下さったのが「河内野」という俳誌であったように記憶していたからである。 こういう偶然もあるのですな(笑)。 さて、弓削神社を後にし長瀬川沿いの道に出て、北西方向(下流方向)に走る。JR八尾駅の南西、太子堂交差点のすぐ西側、道路脇にある物部守屋の墓を訪ねるためである。 東西の弓削神社を訪ねたら、守屋殿のお墓にもご挨拶申し上げるのが筋目というものでありましょう(笑)。(長瀬川沿いの道) 一昨日の記事へのコメントで、3年前に長瀬川沿いを歩いた、とブロ友のビッグジョンさんが仰って居られましたが、この道を歩かれたのでありますな。 上の写真はJR八尾駅の手前800m位の処にある安中公園の前辺りから八尾駅方向を写したものです。自転車は小生の愛車MTBです。(JR八尾駅) JR八尾駅の前を通るのも何度目かになるが、写真はブログに掲載していなかったようなので、掲載して置きます。 物部守屋の墓は、八尾駅の西側の踏み切りを渡って、南西へ1km弱行った処にあります。(物部守屋の墓) 守屋の墓の直ぐ西に大聖勝軍寺・太子堂がある。聖徳太子開基の寺院である。蘇我氏の一員である聖徳太子はこの地の椋の木によって守られ、その結果、守屋を打ち破ることが出来たとされているのであるから、守屋さんも何とも落ち着かない場所に眠らされていることになりますな。聖徳太子さんは、敵味方の区別なくその霊を祀ったというのではあるが・・。無念を呑んだ守屋さんとしては微妙(笑)。むくの木の なほし恨めし 守屋われ などてやむくろ ここにし埋めし (物部無理屋) この後、その大聖勝軍寺に回りますが、 それはページを改めてのことと致します。(つづく)
2014.02.28
コメント(2)
-

弓削の川原の埋もれ木の・・そして新生ナナ
本日は南方向へ銀輪散歩。 PM2.5濃度が基準値を超えているとして、大阪府から「外出は差し控えて下さい。」という注意報が出ていたが、1296歳のヤカモチ、今更健康を気遣っても50歩100歩。有害物質が空気中に飛散しているとしても、それが身体に影響を及ぼす前に死んでしまう筈だから、こんなことで外出を差し控えるのは本末転倒。いざいざ行かん、でありました(笑)。 一昨日、布施駅前の万葉歌碑を取り上げた際に、八王子神社(常世岐姫神社)のことに言及したが、調べてみるとこの神社は当ブログには取り上げていないことが分かりました。 ということで、先ず八王子神社に向かい、其処から足を延ばして、JR志紀駅前の万葉歌碑に立ち寄る・・との目論見にて、午後からMTBで出掛けました。(道の辺の紅梅、服部川駅付近にて) もう、梅の花の盛りの季節。 見つつぞ行かな生駒山の辺、である。(近鉄恩智駅、JR志紀駅周辺地図) 上の地図の中央を南北に走っているのが近鉄大阪線。その右(東)側に平行している川が恩智川である。その更に東側のオレンジ色の道が国道170号旧道である。今日は往路はこの旧道を北(上)から走ってやって参りました。右上隅に緑色の一角があるが、そこが恩智城跡公園である。そこから下(南)の位置に「神宮寺」という文字が記載されているが、その少し南西の位置にあるのが八王子神社である(この地図では表示されていない。)。(八王子神社)(同上)(同上) 小さな神社である。常世(常世岐)氏のことや赤染氏との関連など、この神社の由来については、下の説明碑をご参照下さい。(八王子神社説明碑) 八王子神社からJR志紀駅に向かう。 志紀駅東側のロータリーの真ん中に立派な万葉歌碑がある。 この歌も以前取り上げた気がするが、歌碑は初お目見えです。(JR関西本線志紀駅前の万葉歌碑)真鉋(まがな)持ち 弓削(ゆげ)の川原の 埋れ木の あらはるましじき ことにあらなくに (万葉集巻7-1385)<ま鉋を持って弓を削る、その弓削ではないが、弓削の川原の埋もれ木が 何れは現れるように、われわれの仲もやがては人に知られてしまうこと でしょう。> (注)真鉋持ち=弓削にかかる枕詞。 弓削の川原=現在の長瀬川の川原。 埋もれ木=樹木が水底や土中に埋もれて炭化したもの。 秘密の交際の比喩として使われる。 ましじ=「~ましじ」は、~ないに違いない、~ないだろう。 (同上) (同上・裏面)(JR志紀駅・東口) 万葉歌碑は、東口の階段(写真左)を上った処にある。 東口は駅裏。表の西口に回ってみる。(同上・西口)(志紀駅由来の碑) 志紀駅の北東側にある弓削神社にもついでに立ち寄る。 此処は2011年5月17日の銀輪散歩でも立ち寄って居り、同18日の日記に写真を掲載し、いささかの説明をしているので、コメントは省略し、写真のみ掲載して置きます。 <参考>銀輪近隣散歩・弓削神社 2014.5.18.(弓削神社)(同上)(同上・説明碑) 帰途は恩智川に出て、恩智川沿いのいつもの道を走る。 この川沿いに小生がよく珈琲タイムに立ち寄る喫茶店がある。 上の地図で言うと、恩智駅の右(東)側にある銀行の地図記号の直ぐ下(南)辺りにある。 最近は閉まっていることが多く、長らく立ち寄っていなかったが、今日は開いていました。 店に入ってみると、何やら雰囲気が違う。先客は2~3組。奥に店の方と思しき3名の女性。取り敢えず奥のカウンター席へ。珈琲を注文。いつもの女主人の顔はない。3人の女性の顔に見覚えはない。「店の経営者、変りました?」と尋ねると「はい、この2月から変りました。店の名前は引き継がせて戴いています。」との返事。それで、納得。 珈琲を戴きながら店の方とお喋り。前を自転車でよく走っているので、以前から何度もこの店は利用させて戴いていることなどの話から、自転車の話、万葉の話へ、果てはブログの話にまで広がる。遂には、店で企画している集りで万葉の話などして貰えないかというお願いまでされる羽目に。まあ、返事は曖昧にして置きましたが(笑)。(カフェ・ド・ナナ) 旧のナナのこともブログに書いたことがあるという話をしたら、新しいナナのこともブログで宣伝して下さいと頼まれました。 ということで、一応、宣伝して置きます(笑)。 もし、お近くに来られることがございましたら、是非、皆さまもお立ち寄り下さいませ。何れ劣らぬ美女3人が出迎えて下さり、美味しい珈琲を入れて下さいます。定価で。春立ちて 生(あ)れましにける あらたしき ナナにしあれり こぞりぞ来ませ (七麻呂)(同上) まあ、ヤカモチは以前から贔屓にしていましたから、経営者が変っても「ナナ」に違いはあるものか、です。コチラ方面に銀輪散歩の折には、従来通り、時々は利用させて戴く所存です(笑)。銀輪は 二輪にあれど 七車(ななぐるま) つなぎ継ぎてぞ 往(ゆ)き来(く)かよはな (七伴家持)(同上)<参考>旧の喫茶ナナが登場するブログ記事 2011.3. 4. 恩智川沿いの道 2010.3.20. 恩智川銀輪散歩
2014.02.26
コメント(9)
-

第137回智麻呂絵画展
第137回智麻呂絵画展 本日は今年に入って4回目の智麻呂絵画展となります。 どうぞ、ごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは、ど~んと「苺」から。 全員整列!!(いちご) この苺は、ヤカモチが2月1日の読書会にお持ちした苺です。 前回の絵画展の苺の絵をご記憶の方は、「あれは読書会で、デザートとして、皆で食べてしまい、残ったのは4個だけの筈」とお思いでしょう。 確かに、前回の絵画展の苺の絵は4個で、その説明文にも「これは皆が食べた後の残り」というような主旨のことを記したかと思います。然るに今回その全部が揃った絵が描かれている。智麻呂さんが想像して描かれたのか? これには、種も仕掛けもあるのでした。実は、お持ちして箱を開けた際に、恒郎女さんからヤカモチに、写真に撮って置くようにご下命があったのでした。恒郎女さんもヤカモチもそのことは忘れていたのですが、4個の苺の絵を見て、ヤカモチは思い出したのでありました。 それで、その写真を後日に印刷してお届けした次第。すると、こような見事な絵になったのでありました。とても丁寧に描かれていて、色ツヤといい、形状といい、如何にも「い・ち・ご」です。相当のお時間を掛けてコツコツと描いて居られたようで、恒郎女さんは「この苺の絵ではしっかりと遊ばせて戴きました。」と笑って居られましたが、智麻呂さんは、黙々とたっぷり時間を掛けて仕上げられたようで、まさに力作だと思います(笑)。(バレンタイン・チョコ from みずき&さき) もう、バレンタインは、随分以前のことになってしまいましたが、これは智麻呂さんの可愛いお友だちの、みずきちゃん・さきちゃん姉妹からのチョコです。 先日の読書会の折には、智麻呂邸の前の道でヤカモチもこの姉妹と遭遇。何となくみずきちゃんとさきちゃんではないかと感じつつ、「こんにちわ」と言葉を掛けたのですが、可愛い声で「こんにちわ」と返事をしてくれました。 智麻呂邸の門扉を開けながら、離れた処にいる二人の方に目をやると、「さき~」と大きい方の女の子が小さい方の子を呼んでいる処でありました。「やっぱり・・」と思いながら智麻呂邸の玄関へ(笑)。(バレンタイン・クッキー from さわちゃん) これは、もう一方のお友達、さわちゃんからのものです。手作りのクッキーですな。 さわちゃんとケンちゃんの姉弟。こちらは、ずっと年長で、ケンちゃんは未だ小学生かも知れませんが、さわちゃんはもう高校生かも知れません。ヤカモチはお二人には未だお目文字叶って居りませぬ(笑)。(さくら餅) このさくら餅もさわちゃんからのもの。或いは、さわちゃん・ケンちゃん姉弟からの、いや、姉弟のお母上からのものかも知れません。勿論、これは手作りではなく、絵に添えられている文字やマークでお分かりの通り、鶴屋吉信のさくら餅です。 以下の3点の花の絵は当ブログ掲載の写真から絵にされたものです。ヤカモチが入院中の暇を持て余して、病院の庭に咲いているのを撮影して、ブログにアップしたものでありましたが、智麻呂さんの目を引いたようで、このような絵になったという次第。 ブログ掲載写真も併せて並べさせて戴きました。(紅白の山茶花) 写真と絵で微妙に上下関係などが異なっていますが、絵は絵、写真は写真であります(笑)。 <参考>「梅の花咲きてぞ春は」2014.2.9.(白梅)「梅の匂ひにぞ、古(いにしへ)の事も立(たち)かへり恋しう思ひ出(いで)らるる・・」 (吉田兼好 徒然草・第19段) 「さまざまの事おもひ出す桜哉」と詠んだのは芭蕉であるが、兼好さんは、梅を見て同様の思いを抱かれたのであります。まあ、梅でも、桜でも、薔薇でも、菫でも、山茶花でも、花というものは、それぞれに人に色々なことを思わせるものでありますから、古人も我々も、その点では何も変るところなし、であります。<参考>「梅の花咲きてぞ春は」2014.2.9.梅が香に 昔を問へば 春の月 答へぬ影ぞ 袖にうつれる (藤原家隆 新古今集45)ひとはいさ 心もしらず ふるさとは 花ぞ昔の 香ににほひける (紀貫之 古今集42)あこくその 心は知らず 梅が香を 袖にうつしつ 来にけりわれは (偐家持) (注) あこくそ=紀貫之の幼名(梅の花今しも咲ける・・)<参考>「本日退院しました。」2014.2.12. 今回は出展作品7点と少なめとなりましたが、最後までご覧下さり、有難うございました。
2014.02.25
コメント(10)
-

河内女の手染めの・・
偐万葉が続き過ぎるのも如何なものかと思われますので、本日は銀輪での近隣散歩を記事にします。 一応「万葉」なので、近鉄布施駅前の万葉歌碑からご紹介です。(近鉄・布施駅) 近鉄布施駅は2階部分が近鉄大阪線で3階部分が近鉄奈良線のホームになっている。この駅で奈良に向かう奈良線と八木・桜井・名古屋・伊勢方面に向かう大阪線とが分かれる。小生の通った高校は大阪線の八尾駅が最寄り駅であったので、高校時代は奈良線でこの駅まで出て、ここで大阪線に乗り換えて八尾に向かうのが通学のコースであった。その頃は未だ高架にはなっていなかったかと思うが記憶がハッキリしない。少なくとも八尾駅は高架ではなかった。 さて、万葉歌碑です。 駅南側のバスターミナルの西側歩道上にそれはある。 正確に言うと、それは万葉歌碑ではなく、「大和・伊勢ゆかりの地 布施」の碑の裏面に万葉歌が刻まれているというものに過ぎない。 (万葉歌碑)河内女(かふちめ)の 手染(てぞめ)の糸を 繰り反(かへ)し 片糸にあれど 絶えむと思へや (万葉集巻7-1316)(河内の国の女が手染めの糸を糸車にかけて何度も繰り返す、そんな風にして作った糸だから、片糸であっても、切れることはない。そのように私達の仲も絶えることはないと思います。) (注) 片糸=通常は2本の糸を撚り合せるのに対して1本で撚りをか けた糸のこと。片恋の比喩として使われている。 思へや=「思ふ」の反語。絶えてしまうと思うでしょうか、いやそん なことはありません、という意味である。 河内は古来「河内木綿」が栽培され、撚糸業が盛んであった。 先月12日に訪ねた恩智神社の一の鳥居から700mほど南に行った処に八王子神社というのがある。この神社の正式な名は常世岐姫神社で、常世氏の氏神を祀る神社である。常世氏はもとは赤染氏と称していた。続日本紀(天平19年8月23日条)に、「正六位上赤染広足、赤染高麻呂ら九人に、常世連の姓を賜ふ。」とある。赤染氏というのは、大陸から渡来し、染色を業としていた氏族であり、河内国大県郡がその本拠地であった。 そんなことで、万葉の頃には既に、河内の手染めの糸の質の高さについての認識が一般に広くあったことを、この歌は示している。 そう言えば、八尾市のマンホールの蓋のデザインは、女性が糸車で木綿糸を繰っている図柄でした。 (銀輪万葉・マンホール 2013.10.21.)(同上) さて、勝手に「万葉歌碑」と呼んだこのモニュメントは、大和や伊勢とのつながりを示す布施という土地のことを紹介した碑というのが、その本来の性格でありますから、その碑文の本文を下に転記して置きます。「東大阪市は古代、生駒山麓まで入り込んでいた海を通じて、大陸文化が渡来した処です。布施は、旅人のため駅路に置かれた昔の布施屋に由来するらしく、南北朝時代には足代荘、江戸時代中頃には布施之庄と呼ばれました。大和川の付け替え(宝永元年)までは、その本流の長瀬川を中心に、水運交易の拠点となり、大和、伊勢に通じる近くの十三街道、奈良街道はかって伊勢詣で賑いました。」 布施駅から近鉄奈良線沿いに東に走ると、次の駅が「永和駅」である。高校時代に最も親しくしていた同級生で、同じ大学の同じ学部(法学部)を志望していたこともあって、高3の夏休みに一緒に受験勉強をした、梶◎君の自宅のあったのは、この駅の近く。 次の「小阪駅」は、高校時代から通い始めたキリスト教会の最寄り駅。智麻呂氏やその他の若草読書会の方々と出会ったのは、この教会に於いてである。 また、高1の時に同じクラスとなった鴻◎君は、陸上部で棒高跳びをやっていたが、何故か彼とはよく一緒に帰ったものであった。彼の最寄り駅はこの駅であったので、此処で別れるというのがお決まりであった。 卒業以来、全然会っていなくて、何年か前に同窓会で再会した折に、クラブ活動も共通でなく、志望校も彼は理系、小生は文系で異なる、何か趣味が一緒という共通点もなかったよう、だのに、よく一緒に帰ったのは何故だろう、と彼に話したら、彼も同じ感想を持っていて、二人とも「?」「?」で、笑い合ったものでした。(近鉄・小阪駅前、お好み焼き「ゆり家」) 突如、お好み焼き屋「ゆり家」です。 新潟のブロ友であるふぁみり~キャンパーさんが車で九州に出張された際に、帰途、大阪に立ち寄られ、この店でお好み焼きを食べた、というようなことをブログ(13年4月30日記事)に書いて居られました。道すがら、たまたま店の前を通りましたので、写真に撮らせて戴きましたが、まあ、それだけのことです(笑)。(近鉄・八戸ノ里駅) 小阪の次の駅が八戸ノ里駅。司馬遼太郎記念館は、この駅か小阪駅から徒歩10分余である。 司馬遼太郎氏の命日・2月12日はもう過ぎてしまったが、この日はご存じの通り「菜の花忌」と呼ばれる。 八戸ノ里駅から少し東に行った処を通っている中央環状道路の歩道には、菜の花が沢山咲いていました。(中央環状道路の歩道に菜の花が咲いて・・)菜の花忌 過ぎてその花 今日見たり (筆蕪蕉) では、本日はこれにて・・。
2014.02.24
コメント(11)
-

偐万葉・閑人篇(その1)
偐万葉・閑人篇(その1) 本日も偐万葉です。 偐万葉シリーズも遂に第200弾となりました。 今回は初登場、ふろう閑人氏であります。 昨年12月18日に、ビッグジョン氏のブログから同氏のブログ(同12月17日の記事)に初めて訪問させて戴き、コメントを残したことから、交流が始まりました。同氏も亦、小生と似たスタイルで折りたたみ自転車で旅をなさったり、クロスバイクで銀輪散歩をなさって居られます。 例によって、偐万葉ではハンドルネームとは別に偐万葉用の名を名乗って戴く習わし、「京閑麻呂(みやこのひままろ)」と呼ばせて戴くことと致します(笑)。 <参考>ふろう閑人氏のブログはコチラ。 偐家持が閑麻呂に贈りて詠める歌18首きみが名は つとに知りきも 銀輪の どちとし知るは 今日にしあれり金胎(こんたい)の 寺も然(しか)なり 鷲峰(じゅぶ)の山 あすかのそらゆ いつしか行かむ (注)あすかのそらゆ=「あすかのそら」は、閑麻呂氏のブロ友さんの お名前。「明日香の空から」の意。 (道路標識)みちの草 尾花が下(もと)の 思ひ草 今日しも知りぬ 君はも我も (注)尾花=信楽にある料理店「みちくさ料理尾花」のこと。 思ひ草=ナンバンギセル (本歌)道の辺の 尾花が下の 思ひ草 今さらになぞ 物か思はむ (万葉集巻10-2270) (みちくさ料理「尾花」)こだはりせむとや さだめけむ もてなしせんとや まもりけん あねのかうぢの まちみれば わがみさへこそ なごまるれ(後人微笑)(本歌)あそびをせむとや うまれけむ たはぶれせんとや むまれけん あそぶこどもの こゑきけば わがみさへこそ ゆるがるれ(梁塵秘抄) (姉小路界隈地区建築協定区域)をりふしに ふしみは行けど 稲荷山 人出を多み 初(はつ)はなさざり (伏見稲荷)七福の 福を求むる 心には 神も仏も 隔てなからむ (泉涌寺山門)風吹けば 四条大橋 ひれ酒の 匂ひ起こして 客寄せるらむ (菅原酒真(すがはらのさけざね)) (四条大橋の料理屋)ひま加へ わが名は今し あらためぬ 知りてひとみな ひまな忘れそ (閑家持)ためしにて キタに出でにけり このたびは 日頃ミナミの われにしにあれど (南家持)酒呑みは かくにしあるか 青竹を かっぽと切りて 八本並べ (竹林の八酒人) (かっぽ酒)絵の餅を 絵画モードに 撮りて見む 食えぬ餅でも 遊べるならし (偐家餅) (絵画モードの写真)右目したる のちの世界と くらぶれば 昔はものを 見ざるなりけり (術後の敦忠) (本歌) あひみての のちの心に くらぶれば むかしはものを おもはざりけり (藤原敦忠 拾遺集710 小倉百人一首42)我はもや 車馬にしもなき 娑婆世界 帰りて何の 益やあるらむ別世界 なれるとも見ゆ この目にて 憂しと見し世も いましばし見むやきうちは みやこべにもあり いしのふみ まことつたふと ここにしたてる (東山馬麻呂) (京都空襲の碑)時は今 花は香炉に うち薫じ 塩サバかしは いぶしています (閑原閑也) (注)第5句は偐万葉掲載に当り、中原中也の雰囲気を出すため「いぶ してもぞみむ」を「いぶしています」に修正しました。 (元詩) 時こそ今は花は香炉に打薫じ、 そこはかとないけはひです。 しほだる花や水の音や、 家路をいそぐ人々や。 いかに泰子、いまこそは しずかに一緒に、をりましょう。(以下略) (中原中也 「時こそ今は・・・」<山羊の歌>) (塩サバとカシワの燻製)桜木の 燻しの香をば まとひつつ いざとり召せと 鯖さそふらし (庭辺燻人)よき色に 焼けて香もよし 味もよし 鯖燻鳥燻 楽しきろかも (庭辺燻人)<注>掲載の写真は全てふろう閑人氏のブログからの転載です。
2014.02.23
コメント(10)
-

偐万葉・ウ―テイス篇(その2)
偐万葉・ウーテイス篇(その2) この処は銀輪散歩もサボりがち。近隣散歩で誤魔化して居りますれば、新しきネタもこれなくあり、本日も偐万葉シリーズと致しまする。 ということで、本日は、シリーズ第199弾・ウーテイス篇(その2)と致します。 <参考>過去の偐万葉・ウーテイス篇はコチラ。 ウーテイス氏のブログはコチラ。 偐家持がウテ麻呂に贈りて詠める歌17首 並びにウテ麻呂が詠める歌2首西へ西へ 行けばやがては 東なり 卵が先か にはとり先か (コロンダスの卵) (注)上の歌は偐万葉掲載に当り第5句を一部修正しました。今更に 絵筆握れど ままならず こころはあれど 絵にならじかも歌詠みは 曖昧両義を 本分と すればすまじき 理路のふみかな ウテ麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が返せる歌2首庭に来て 我が家のマンゴー 盗むのは ガロと言う名の リスの仲間か (ウテ麻呂)リスなれば スリもゆるさむ マンゴーを 欲しと吾家(わぎへ)に 来(こ)れるガロかも遠島を 申し受けたる わが侘び家 日々天国の 冬も雪なし (ウー爺)雪月花 雪しなければ 花月にて お笑ひ寄席の 名とやなるらむ蟹食(く)ふに 海老もしかなり 始末よく 食らはばゴミも デルスウザーラまじ (ゴッタガヤ)(注)デルスウザーラ=黒沢明監督の日ソ合作映画「デルスウザーラ」に登場する人物の名前。ロシアのシベリア探検隊のガイドを務めた先住民ゴリド族の猟師である。 ゴッタガヤ=ブッダガヤとは無関係である(笑)。寝ろとかも 言はれてネロは 詩を練ろと 寝ずは人みな 暴君と呼べり野葡萄も 薬と知れば 野放図に 延(は)ふるその様 よしとぞ見ゆる昔こそ 大(だい)大阪と 呼ばれけめ 今都構想の あがきなどすれ (本歌)昔こそ 難波(なには)田舎と 言はれけめ 今は京(みやこ)引き 都びにけり (藤原宇合 万葉集巻3-312)大大阪 いづち行かめや うつ手無み 州だの都だの 容れ物論議 (本歌)愛(かな)し妹を いづち行かめと 山菅(やますげ)の 背向(そがひ)に宿(ね)しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577)わが客は 湯女(ゆな)にはあらじ 湯麻呂とふ 越後ゆ来たる をのこなりけり切られては われな切りそと 棘つけて 枝なりませる ブーゲンビリア (棘麻呂)まつ身にも 迎へのなくば 竹の花 未(いま)だ咲かざり 梅咲くばかり (偐松竹梅)また来むと いひて素通り せし君の またはまずなし 来むとは待たじ (偐の又三郎)見ても見ぬ 人あるなれば 見えぬもの 見しとし言へる 人もあるなり (見麻呂)いつの世も にせは尽きざり しかありて 千年万年 われもまた生く憂しと見し よも明けぬれば うまなりて うまくもなけど も~そっと生きむ (牛野馬麻呂)生きる意味 もとよりなけど 死ねもせず 用無き身をば 恥さらしつつ (万年生太郎)(光芒)<注>関連写真がありませんので、手持ちの写真を適当に貼り付けました。上の本文記事とは直接の関係はありません。
2014.02.22
コメント(6)
-

亀がダウン鴨
愛用のコンパクト・デジカメがダウンしました。バッテリーの寿命が来たようで、十分に充電している筈なのに、1~2枚撮影すると、ピピピーと音がして「電池の残量がありません。」という文字が画面に表示され、暗転・シャットダウンしてしまいます。 かなり前からたまにこのような事が起こっていたのですが、バッテリーをいったん外して入れ直すと元に復していました。ところが、3日前から突如、「レンズを初期化しています。」という表示が出て、ピントが合わなくなる、などの現象が生ずるようになった他、頻繁に「電池残量がありません。」という表示も出るようになって、撮影しようとするとシャットダウンしてしまうという次第。 もう6~7年も使っていますから、バッテリーのみならずカメラも寿命なんでしょう。同じ機種のものは今は販売されていないらしい。同じメーカーのカメラの方がパソコンへの取り込みや編集のための再設定の必要もなく便宜だろうと、電気店で探しましたが、このメーカーの機種入れ替えの時期に当たっているとかで、3月末頃にならないとコンパクトカメラの新機種は入荷しないとのこと。止むなく同じメーカーの一眼レフ・カメラを購入することにしました。 主人たる小生が眼のレンズを入れ替えたので、カメラの方もそれに合せて「入れ替えてよ」と横着を言い出したようであります。是非に及ばずですな。 ブログ写真を撮るだけなので、余計な機能などは不要。軽量・コンパクトなのが一番なのですが、ないものは仕方がない。なるべく小さめの嵩張らないものなら一眼レフ機種でもよかろうと、取り敢えず購入致しました。 (春はまだ光のみなり冬木立) この写真は、一昨々日(18日)に花園中央公園で撮影したもの。何という木かは知らないのだが、枝が複雑に枝別れして、まるで毛細血管のような様相を呈しているのが面白い。 「乱れて今朝はものをこそ思へ」という歌が思い浮かんだりもしましたが、寝乱れた黒髪はかくにしもあるか・・であります。しかし、ちと乱れ過ぎですかな(笑)。 この日は冷たい風が吹き、冬の寒さでありました。手袋をしていても銀輪のハンドルを握る手がジンジンと痛くなるようでもありました。されば木々たちも未だ冬眠。咲き出した梅も、トムソーヤではなく、寒そうや。そらそうや、と閑人ヤカモチ。木立らは 春立ちぬれど 吹く風の まだ冬なりと い寐てやあらむ (偐家持) どうやら、木立は朝から夕方までずっと、ただ寝乱れ眠りを貪っていただけにて、ものは思っても居らなかったようでありました。されば、寒くもありて、色気も何もあったものではないと言うべきか(笑)。 そして、花園ラグビー場の上の空には雲の峰が・・。その峰の向こうに輝いて見えるは西方浄土のそれやらん・・ランボーでもなくば、どれひとつ念仏でもあげることとしようか、でありました。(雲) 上の3枚は従来のカメラで撮ったもの。下の2枚は新しいカメラで昨日(20日)試し撮りしてみたもの。新しいカメラの操作、撮影の仕方やメニューなどの詳細は未だよく理解できていませんので、追々に慣れて行くしかありません。(花園中央公園北出入り口付近)(花園中央公園・北出入り口付近から南方向を望む。) 花園中央公園の水際には葦が群生している。鴨や鳰や鷺が見られることもあるのだが、この日は姿無し。寒き夕べと葦原と来れば、浮かぶのはこの歌。葦辺ゆく 鴨の羽交(はがひ)に 霜ふりて 寒き夕(ゆふべ)は 大和し思ほゆ (志貴皇子 万葉集巻1-64) この歌は、慶雲3年(706年)、文武天皇の難波宮行幸に従駕した、志貴皇子が大和のことを思って詠んだ歌である。大和にのこして来た妻のことなども思われての歌であろう。道綱のおっかさんの歌「なげきつつひとりぬる夜のあくるまは・・」なんぞよりは、ずっと清澄で美しい、気品のある歌である(笑)。 高円山の麓にある白毫寺は志貴皇子の別荘のあった場所であるが、この寺は、高校生であった頃に訪ねて以来、何度となく訪ねている小生お気に入りの寺の一つでもある。 デジ亀の話で始まったブログ記事が鴨の歌で終るということで、何とも脈絡も、取りとめも無い記事となりましたが、お赦しいただくこととして、今日はこれにて。 今月に入ってからは一日の休みもなく、毎日、記事の更新が続いています。先月31日から始まり、これで22日連続更新。多分自己新記録ではないでしょうか。我ながら「あっぱれ」でありますが、銀輪からは「われをこそ22日連続で乗るべきにて、喝。」と言われそうです(笑)。
2014.02.21
コメント(6)
-

偐万葉・ふらの篇(その2)
偐万葉・ふらの篇(その2) 本日は、雪深き富良野の森から、シリーズ第198弾、偐万葉・ふらの篇(その2)をお届け致します。 <参考>過去の偐万葉・ふらの篇はコチラ。 furano‐craft氏のブログはコチラ。 同氏開設の木力工房・富良野麓郷庵(富麓庵)のHPはコチラ。 偐家持がふら麻呂に贈りて詠める歌19首併せ俳句4句 並びにふら麻呂が詠める歌1首併せ俳句1句恋ひ恋ひて 遠くしあれば ふるさとは 去りにし女(をみな)の 笑みにも似たる (注) 敢えて「やさしき母の笑みも似たる」にしないのが偐万葉なので ある(笑)。斧の色も さまにしなるや 一閃の 形におのが 斧と知るらし (斧の小町) (薪割り) ふら麻呂が贈り来れる上3句に偐家持が付けたる下2句の歌1首北新地 歌の世界と 思ひけり (ふら麻呂) わが身は北の 大地にあれば (偐家持) ふら麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首銀輪を 遠くの冷地で まちわびて その日のために 努力おしまん (ふら麻呂)深草の 少将がごと 家持は 百夜は待たじ 斧にも死なじ (斧家持)麓郷の 森に雪ふみ わがなせし おのが斧(をの)これ つばらにも見よ (斧麻呂) (注) つばらに=詳しく、詳細に。斧ひとつ 突き立て春を 吾(あ)は待たむ 雪しんしんと 降り重(し)く森に (斧麻呂)麓郷の 厳しき冬も 斧一閃 打ちおろしてぞ われ此処に生く (斧麻呂)斧の柄の 色もしるべと われ置かむ 道の隈廻に それとこそ知れ (斧の小町)森の色は 同じと見ゆれ いたづらに 道に迷へる ひともやあらむ (森野小町) (本歌)花の色は うつりにけりな いたづらに わが身世にふる ながめせしまに (小野小町 古今集113 小倉百人一首9) (斧のオブジェ)三十頭 春さり来れば 揃ふとふ 富良野の春を 今かと待たむ (修正歌)三十頭 春さり来れば 揃ふとふ 富良野の鹿の 出(い)で来(く)を待たむ 中原中也風に、来るわ来るわ 鹿のオブジェが 出て来るわ 富良野の森に 春芽吹く頃 (鹿原鹿也) 山部赤人風に、春の森 鹿を見むとて 来(こ)しわれぞ 森なつかしみ ひと夜寝にける (森辺菫人) (本歌)春の野に すみれ摘みにと 来(こ)しわれぞ 野をなつかしみ ひと夜寝にける (山部赤人 万葉集巻8-1424) (鹿のオブジェ)麓郷(ろくがう)の 雪踏み平(なら)し 蝦夷鹿も 今かも春と 出でにし来(きた)る (鹿麻呂)麓郷の 森はわれこそ 案内(あない)せむ しかとなすなり しかにしあれば (鹿麻呂)このたびは 角(つの)もめでたき 牡鹿なり 春張り切れと 足踏み張れる (角麻呂)わが背子は 蝦夷鹿見せつ 麓郷の 森の芽吹きを いつぞ示すや (高市鹿人) (本歌) 我妹子(わぎもこ)に 猪名野(いなの)は見せつ 名次山(なすぎやま) 角(つの)の松原 いつか示さむ (高市黒人 万葉集巻3-279) (鹿のオブジェ)降りしけば 道たづたづし 富麓庵(ふろくあん) 雪やむ待ちて 行かせわが背子 (大雪女(おほゆきめ)) (本歌)夕やみは 道たづたづし 月待ちて 行かせ吾背子 その間にも見む (豊前国の娘子 大宅女(おほやかめ) 万葉集巻4-709)わが思ふ かたちもとめて 今日もかも 富良野の森と 語らひ行かむ (偐富良持)きみが思ふ かたちは良けど 大雪の 富良野にしあり 身をこそいとへわがなせし うたをよしとす ひとひとり ありてうれしき きさらぎのころ (にせやかもち) 春なれど リスもスリ寄る 寒さかな (松尾栗鼠) 蝦夷リスと メシなどしたき 雪の日は (松尾栗飯) 蝦夷リスも わが友とせむ 雪降れば (松尾桃栗) (リスの食堂)<脚注>掲載の写真はfurano‐craft氏のブログからの転載です。
2014.02.20
コメント(8)
-

南奔北走・岬麻呂旅便り
東奔西走と言うのはあるが、わが友人、岬麻呂氏は南奔北走ですな。 先日(1月23日)、同氏の北海道旅便りをご紹介したばかりだが、今回は沖縄(慶良間列島)からの旅便り。これを「南奔北走」または「北奔南走」と言わずして何ぞや、であります。まあ、妄奔迷走しているヤカモチには縁の無き旅スタイルでありますかな。 白内障手術での入院とその後の自重生活で銀輪もままならねば、ブログネタにも不自由しているだろうとのお心遣いにてもあるか(笑)。 小生、退院後の初検診で今朝病院に行って参りましたが、全て順調とのことで、本日より普通通りに生活してよろしい、との有難きお言葉を戴きました。病院から帰宅するや否や、先ずなしたる事は、お風呂に飛び込み、頭を心ゆくまで洗ったことでありました。よくないことや悪行からは足を洗い、顔を洗って出直す、というものでありますが、ことヤカモチの場合は「頭を洗って」出直すのであります。 さて、それは余談。岬麻呂氏の旅便りです。 例によって、送られて来た、紙焼き写真をデジカメで撮って、ブログでご紹介というものでありますが、沖縄や南西諸島についての地理感も知識もないヤカモチには、慶良間列島が何処の辺りにあるのかさえ、よくは分かりませぬ。 ただ青々とした海の景に見惚れているばかりなのであります。(高良家住宅・国指定重要文化財)(アカ大橋からの展望) アカ大橋から望むアヲき海であります。いづかたゆ 神は来ますや あをき海の さやけき波の 音にしきかな (偐家持)(アカ大橋からアカ港を望む。)(ゲルマ橋からの展望)(ニシバマビーチ・北方向の眺め)寄せ来る波の絶ゆるなく、満ち来る潮のいや益しに・・でありますかな。(ニシバマビーチ・北西方向の眺め)ニシバマの 浜辺を一人 行く人の 影遠のきぬ 寄する波の音(と) (偐家持)(古座間味ビーチ・北東方向の眺め)(古座間味ビーチ・北東方向の眺め) (古座間味ビーチ・南東方向の眺め)(ガヒ島・後方は座間味島) 上の写真は「航空写真の複写」と注記されていましたから、岬麻呂さんの撮影ではなく、どなたかが撮影の航空写真を写真に撮られたのでありますな。してみると、わがブログ掲載の写真は、写真の写真を写真に撮ったものということになります。どうか皆さま、この、写真の写真の写真を写真には撮らないで下さい(笑)。説明がとても厄介になりますよ。
2014.02.19
コメント(4)
-

偐万葉・若草篇(その12)
偐万葉・若草篇(その12) 白内障手術の術後の通院検診が明日。 医者からは、この検診が終わるまでは風呂は入ってもいいが、洗うのは首から下のみ、顔や頭は洗ったりお湯をかぶったりしてはいけない、と言われている。 頭髪は毎日洗っているヤカモチ。頭を洗えないのではお風呂に入った気がしない。そして、日に4回の3種類の眼薬の投与。これも面倒。 そんなことで、遠出の銀輪散歩もする気にならない。これでは病院が自宅に変っただけで、こと銀輪に関しては入院状態とさほど変らないのである。 かくして、ブログ更新だけは順調という次第。しかし、銀輪ネタはない。このような時にお助けマンとなるのが「偐万葉シリーズ」である。 と言うことで今日も同シリーズ第197弾・若草篇(その12)と致します。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 偐家持が小万知に贈りて詠める歌20首 並びに小万知が詠める歌1首ありゃ蟻も うつろひやすき 月草に つきて懲りずの 恋やするらむ (蟻原業平)春雨は 濡れても行けど 秋雨は 銀輪休めと 降るものならむ (月形輪平太) 次なる2首は小万知に贈りたる歌にはあらねど、小万知を詠める 歌にてあれば、此処に記し置くものなり。この秋も 小万知がくれぬ もみぢ葉は 絵に描くからに 匂ふ葉の色 (偐智麻呂) (本歌)初春の 初子(はつね)の今日(けふ)の 玉箒(たまばはき) 手に執るからに ゆらぐ玉の緒 (大伴家持 万葉集巻20-4493)ウメモドキ カボチャモドキも 持ち来たる 小万知も小町の モドキにあらむ (ヤカモチモドキ)葱食(は)めば 甘きに思はゆ やあやあの きみが笑顔の かなしきろかも (偐智麻呂)マンホールの 蓋にも千羽の 鶴ありて みたび原爆 許すまじとふ (広島家持)若松の 雪ふり置ける 鶴ヶ城 いざうち行きて つばらにぞ見むをのこやは かなしかるべき 年ほどの 豆も食はずに 胡麻数ふとは (山上憶豆) (本歌)士(をのこ)やも 空しかるべき 万代に 語り継ぐべき 名は立てずして (山上憶良 万葉集巻6-978)心あてに をらばやをらむ 初雪の おきまどはせる 白梅の花 (中河内躬雪) (本歌)心あてに をらばやをらむ 初霜の おきまどはせる 白菊の花 (凡河内躬恒 古今集277 小倉百人一首29) 小万知が贈り来れる歌1首妹が庭 見まくの欲しと 難波(なには)なる 吾(われ)も待たなむ 疾(と)く帰りませ (注)上の歌は偐家持が木の花桜氏に贈れる次の歌に追和せし歌なり。 妹が庭 見まくの欲しと をちこちの どちも待つらむ 疾(と)く帰りませ 偐家持が重ね追和せる歌神ともに ありて我妹(わぎも)を 守りませ 春の風もや 心して吹け 凡鬼が作れる句に偐家持が付けたる脇句1句 聖夜劇 星役の子は うとうとと (凡鬼) 揺れて光れと 言はれてなくに (偐家持) 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌10首併せ俳句3句 並びに偐山頭火が詠める歌1首併せ俳句1句 偐山頭火が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首因幡では 川氾濫し 道険し 国庁の跡 万葉の幕 (挫折山頭火)いなば去(い)ね 雨はしぐれぞ 山頭火 うしろ姿の 逃げ行くぞ惜し (因幡守家持) (注)いなば去ね=「因幡去(い)ね」と「去(い)なば去(い)ね」を掛けている。 (元句)うしろすがたのしぐれてゆくか (種田山頭火)スパルタン デュークダローが 酔ひどれの 寝言これにと 今朝届きたる (酔山頭火) (注)スパルタン、デューク、ダローはブルーベリーの木の品種名 西でなく 塔(たう)ある東(たう)だと 山頭(たう)火 「たう」が三つて 偐三たう火 (偐茶化持(にせちゃかもち))老犬は 歯も浮きたれば 魚肉なる ソーセージよし 君にまたよし (偐老頭火) 分け合っても 分け合っても 安い5本 (筆蕪蕉) (元句) 分け入っても 分け入っても 青い山 (種田山頭火) 偐山頭火が返せる句 分け合って 食べ合って 老犬と老人 (偐愛犬家) 対局に 水さすものぞ 碁のさ中 わが携帯に かけ来るは誰(たれ) なにとてか つとに知りたる 名を尋(と)ふや 囲碁にかまける 君とは知れど (偐郎女) (本歌)紫は 灰さすものぞ 海石榴市(つばいち)の 八十(やそ)の衢(ちまた)に 逢へる児や誰(たれ) (万葉集巻12-3101) たらちねの 母が呼ぶ名を 申さめど 路(みち)行く人を 誰と知りてか (万葉集巻12-3102)山頭火 この日ばかりは 山労火 訳言って分け入って 青い山かも (隣の家持) 酔っている間(ま)の楽しさは紋白蝶が舞ふ(偐山頭火モドキ) (元句)酔へなくなつたみじめさはこほろぎがなく(種田山頭火)和三盆 酒の肴に ならねども ブログのネタに 年の暮れゆく (偐山盆火) 北斎に 赤黒あれど 青なくば これぞ青富士 つばらにぞ見よ (負鹿漫才(まけしかまんざい)) (注)つばらに=くわしく 負鹿漫才=葛飾北斎のパロディ 初打ちや 囲碁よくもなき 出だし哉 (注)囲碁=「以後」を掛けている。 よくもなき=「良くもなき」と「欲もなき」とを掛けている。初春や ふくもぶらりの 新世界 なべて人みな まづまづの顔 (注)ふく=「河豚」と「福」を掛けている。 なべて=「並べて」と「鍋で」を掛けている。 まづまづ=旧仮名表記。新仮名表記は「まずまず」。 <参考>偐山頭火氏のブログはコチラ 掲載写真は同ブログからの転載。
2014.02.18
コメント(21)
-

偐万葉・木の花桜篇(その17)
偐万葉・木の花桜篇(その17)・・わが振る袖を妹見つらむか 木の花桜さんは長らくブログを休止されています。そんなことで木の花桜篇も一昨年の3月以来更新していません。彼女のおん身のことなども安じつつ、一日も早いご復帰を願って、本日は木の花桜篇(その17)とさせて戴きました。 <参考>過去の偐万葉・木の花桜篇はコチラから 木の花桜さんのブログはコチラから 偐家持が木花桜媛に贈りて詠める歌20首 並びに木花桜媛が詠める歌2首 木花桜媛が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首いにしへの 難波津(なにはづ)いづちと 尋ぬれど 問ひて答ふる 友しなければ (迷子の偐島子)難波津(なにはづ)は 難波(なんば)かと来(く)りゃ 地下走る 牛車(ぎっしゃ)の駅か なんば走るね (博多の島子) (注)難波=大阪ミナミのナンバのこと。近鉄、地下鉄、JRなどの難波 駅がある。やはらかに 雨降る梅の 花が下 人こそ知らね はこべら咲きぬはこべらの 浅き春なり よし雨も こころしあらば やはらにぞ降れ (梅) (はこべ)しのべとか ミニアイリスの 花ひとつ 咲きにけるかも 兄は逝きたり (ミニアイリス)褒め過ぎの 言(こと)にしあれり をこなれば 菊惑わせる 桜子の言(こと) (おその花冷え) (注)をこ、おそ=をこ(烏滸、尾籠)。おそ(遅、鈍)。馬鹿、鈍い。 ここでは偐家持が「をこ」「おそ」であるので、と いう意味である。さに(32)咲くや(398) 庭(28)に(2)し(4)咲くや(398) 花(87)咲(3)く(9)や(8) 見(3)に(2)来(5)よ(4)疾く(109)と(10) 庭(28)に(2)し(4)咲くや(398) (咲耶姫) (注)数字変換可能な音のみで作った歌 (クロッカス)むづかれる パソコンなだめ ムスカリの 咲きたる庭を 妹告(の)らむらし (ムスカリ)チューリップ 色さまざまに 立ちまじり 遊びせんとや 今咲きにけむ (平花盛または後白花上皇) (チューリップ) 木花桜媛が贈り来れる歌1首白峯の 配所の月に 風すさび 秋寒き夜の さびしさぞ知れ (怨・崇徳院) 偐家持が返せる歌2首頼長に せかされ兵は 挙げたれど 今ゆき悩む 春の月かも(偐崇徳)頼長に 依りしを悔いる 女々しさを さびしと云ふも おろかなりけり(偐崇徳) (本歌)瀬をはやみ 岩にせかるる 滝川の われてもすゑに あはむとぞおもふ (崇徳院 小倉百人一首77 詞花集228)いづかたや 蝶の来たれば わが庭の 花もつやめき 色益すならし (ノースポール)かなしみに いかにそはむと おもほへど うたよむほかに すべのしらなくなにとかも いひやるべきや 言の葉も 思ひ浮かばず 思ひつつぞ居りわがせこは いづちゆかめや はるの雪 ともにしみねば かなしけくやし赤磐の さくらがをかに 花は咲け きみはいまさず かへりきまさずあを山の みねにながるる しら雲に きみはしのべと 手をやふるらむ手をとりて 泣きし日もあり 笑みし日も きみとともにし 生きにしわれは今はもや 逢ひかつましじ 山の端(は)の 雲をきみとや しのびてをらむ高梁の 川になみだは ながさなむ ながしていまは 川渡らなむ妹が庭 見まくの欲しと をちこちの どちも待つらむ 疾(と)く帰りませ(注)掲載の写真は木の花桜氏のブログからの転載です。
2014.02.17
コメント(8)
-
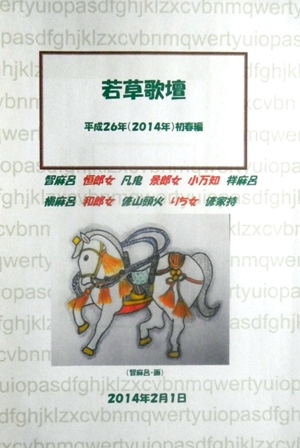
若草歌壇・2014年初春編公開
先の若草読書会での恒例の余興歌会の提出作品を纏め、河内温泉大学図書館にて公開となりましたのでお知らせ申し上げます。 同図書館は友人の偐山頭火さんが管理運営されているサイトにて、偐家持美術館編集・発行の図書なども収納されています。閲覧は無料・自由ですので、興味を持たれたお方はどうぞお気軽にご覧下さいませ。<参考>若草読書会新年会2014 2014.2.1.(偐家持美術館編集「若草歌壇2014年初春編」表紙)河内温泉大学図書館はコチラから閲覧できます。
2014.02.16
コメント(0)
-

昨日の雪に寄せて・芭蕉の雪の句
昨日は大阪も雪景色になりました。 先般の雪の時は入院中であり、病室の窓から眺めたきりでありましたが、今回は自由の身、枚岡梅林や枚岡神社の雪を見に外へ出てみました。午後遅くなってからであったので、かなり融けてしまっていました。 雪が滅多に降らぬ地に住んでいると、雪は「雪景色」というものとなり、「雪見」なんぞという言葉さえも生まれるのである。芭蕉さんも「馬をさへながむる雪の朝(あした)哉」(雪の朝というのは何もかもが新鮮で、旅人ばかりかその馬をさえ、普段と印象が違って、じっと眺めてしまう。)と吟じて居られますが、総じて我々は、そのようなのである。 もっとも、地域によっては、足止めを食ったり、大渋滞を引き起こしたり、便欠航で空港で一夜を明かしたり、事故に巻き込まれたりと、色々の難儀を生じさせた今回の雪でもあれば、そう呑気なことを言って居ては不謹慎の謗りも免れぬ処だが、雪国暮らしでないヤカモチとしては雪を目にすると自ずと心そわそわと「さやぎて」ということになってしまうのは、仕方なきことなのではあります。(2014年2月14日の雪)(同上・枚岡神社)(同上・枚岡梅林) ついでに、芭蕉さんの「雪」の句を列挙して置くこととしましょう。 はつゆきや幸庵(さいはひあん)にまかりある(待ちに待った初雪だが、幸いにも私は庵に居合せている。)初雪や水仙のはのたはむまで(水仙の葉がたわむほどに初雪が降り積もっている。)面白し雪にやならん冬の雨(面白いことに、冬の雨は雪に変りそうだ。)初雪に兎の皮の髭つくれ(初雪には兎の皮で付け髭を作って兎の気分になれ。)初雪やいつ大仏の柱立(はしらだて)(もう初雪が降り出した。大仏殿の柱立てはいつのことになるのやら。)はつ雪や聖小僧(ひじりこぞう)の笈(おひ)の色(初雪の中を行く行脚僧の笈の色は長旅を示すように色褪せている。)雪をまつ上戸(じやうご)の顏やいなびかり(稲光が走るたびに、雪を待つ上戸たちの顔が照らしだされる。)初雪やかけかゝりたる橋の上(初雪が架けかけの橋の上に積もっている。)たはみては雪まつ竹のけしきかな(この絵の竹はよくたわんでいて雪を待っている風情である。)霰まじる帷子(かたびら)雪はこもんかな(霰まじりの帷子雪は霰小紋のようだ。)時雨をやもどかしがりて松の雪(時雨はいくら降っても松の葉を紅葉させることはない。それをじれったく思って松は雪をかぶってしまった。)しほれふすや世はさかさまの雪の竹(雪の重みで竹が節をさかさまに萎れ伏している。子に先立たれたあなたのように。)波の花と雪もや水にかえり花(海に降り込む雪は水にもどって、波の花となって返り咲くのだろうか。)富士の雪盧生(ろせい)が夢をつかせたり(雪をかむった富士の姿は露生が夢で築かせた白銀の山のようなものだ。)今朝の雪根深(ねぶか)を薗(その)の枝折(しをり)哉(今朝はあたり一面の雪、頭を出している葱が畑の目印になっている。)雪の朝独リ干鮭(からざけ)を噛(かみ)得タリ(雪の朝に独り私は干し鮭を噛み得ている。)黒森をなにといふともけさの雪(黒森(くろもり)の由来を何と言おうが今朝の雪ですっかり白森だ。)馬をさへながむる雪の朝(あした)哉(上記参照)市人(いちびと)よ此(この)笠うらふ雪の傘(市に集まっている人々よ、この笠をあなたがたに売ろう。この雪の積もった笠を。)雪と雪今宵師走の名月歟(雪と雪が照り合って、今宵は師走なのに中秋の名月のような明るさだ。)君火をたけよきもの見せむ雪まるげ(君は火を焚け。私はよいものを作ってみせよう。雪の大玉を。)京まではまだ半空や雪の雲(京まではまだ道の半ば。中空には雪雲が居座っている。)ゆきや砂むまより落(おち)よ酒の酔(よひ)(下は雪の砂地だ。馬より落ちてみなさい。酒の酔いも醒めるから。)磨(とぎ)なをす鏡も清し雪の花(研ぎ直された鏡も清らかで、折しもそこへ雪が花のように降りかかる。)箱根こす人も有(ある)らし今朝の雪(今朝は雪。この雪の中を箱根を越えて行く人もいるらしい。)いざ行かむ雪見にころぶ所まで(さあ、雪見に行こう。転ぶ所まで、どこまでも。)酒のめばいとど寐(ね)られね夜の雪(酒を飲むといよいよ眠れなくなる雪の夜であることだ。)二人見し雪は今年もふりけるか(去年二人で見た雪は今年も降っただろうか。)少将のあまの咄(はなし)や志賀の雪(をのがねの少将と尼の話を聞いている中、ここ志賀の里には雪が降っていることだ。)ひごろにくき烏も雪の朝(あした)哉(日頃は憎らしく思っている烏も、雪の朝は風情がある。)貴(たふと)さや雪降(ふら)ぬ日も蓑と笠(尊いことだ。雪降らぬ日にも蓑と笠を身につけている小町の画像は。)比良(ひら)みかみ雪指(さ)シわたせ鷺の橋(比良山と三上山の間に、鷺よ、翼並べて、雪のように白い橋、鷺の橋を、さし渡せ。)雪ちるや穂屋(ほや)の薄(すすき)の刈(かり)残し(雪が降り散る枯れすすきは穂屋を作った際に刈り残したものだろうか。)庭はきて雪をわするゝはゝきかな(庭の雪を掃きながら、雪のことは忘れて、ただ無心に箒を動かしていることだ。)
2014.02.15
コメント(8)
-

第136回智麻呂絵画展
第136回智麻呂絵画展 偐家持美術館も館長が白内障で入院して居り休館の止むなき状況でありましたが、この程無事退院して参りましたので、本日より開館、その出所祝いも兼ねて、1カ月ぶりの智麻呂絵画展開催であります。<参考>他の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ず、ちょっと季節外れですが、柿の絵から始めましょう。 第132回展をご覧戴いた方なら、或いはご記憶かも知れませぬが、蜜柑の絵が冒頭にあったかと。その蜜柑を下さったのは智麻呂さんが検診に行かれる病院のお近くにあるお家の奥様。その奥様に蜜柑のお礼にと、蜜柑の絵とその絵が掲載されている第132回展の当ブログ記事の印刷したものをお持ちした処、大層喜んで下さり、「まあ、まあ、こんなに立派な絵にして下さり・・何かお礼に差し上げなくては・・」と庭先からお家の中に入って行かれ、「こんなものしかありませんが・・」と下さったのが、この柿でありました。(柿二つ)蜜柑の礼 絵を持ち行けば 大刀自が 嬉しみくれし 柿二つこれ (偐家持)うれしみと 画きたる柿の 絵を持ちて 行かば大刀自 何とや言はむ (柿本智麻呂) 以下の蝋梅、金柑、山茶花の絵は、智麻呂さんが通って居られるデイサービス施設「アンデスのトマト」さんの画材ご提供によるものです。 智麻呂邸に向かう途中ではその前をよく自転車で走っている偐家持であるが、一度、施設の中も見学したいものです(笑)。(先ず咲く花の蝋梅の・・) 蝋梅も智麻呂さんのお好きな花である。さ夜更けて 雪は降りつつ しかすがに 蝋梅の香の 流れ来るかも (偐家持)(金柑) 金柑は中国長江中流域原産らしいが日本に入って来たのは江戸時代頃だから、万葉集には橘はあれど金柑はなしである。 金柑は俳句では秋の季語とされるが、中国広東省や香港では旧正月を迎えるに当たって柑橘類の鉢植えを飾る習慣があり、中でも金柑が好まれるらしいから、この時期に金柑の絵は相応しいとも言えるのでありますな。 1月29日の誕生花はラナンキュラス、コブシ、苔類と並んで金柑も挙げられているから、金柑は偐家持にとっても縁の深い植物なのだ。 因みに、上の蝋梅は1月11日、1月21日の誕生花とのこと。(山茶花) 今回は誕生花に拘って参りましょうかね。 山茶花は12月4日の誕生花です。(三色すみれ) パンジーは1月9日の誕生花。 この絵のモデルは前回(第135回)絵画展に登場の「三色すみれ」と同じ。前回の絵では赤い色の花を省略したのでは「二色すみれ」だとクレームを付けられた智麻呂さんが一念発起、一色追加で完成させたのがこの絵であります。まあ、一念発起でよかったです。「二念発起」だったら「四色すみれ」になってしまっていたことでしょうから(笑)。(吾輩はチッチである。) これは「花」ではありません。まあ、「鼻」は利きますが犬です。一の姫様の愛犬チッチです。表情がなかなかよろしい。結構、動き回るので智麻呂さんは写生するのに苦労されたようですが、よく描けましたということで、これは鼻マル、ではなくて、「花マル」ですね。(プリムラ・ジュリアン) 上のプリムラ・ジュリアンと下のクレマチス・アンシュエンシスは小万知さんがお持ち下さった花です。 花の名が分からないので、Eメールで絵の写真を小万知さん宛てに送信して、その名を教えて戴きました。「覚えにくい名で済みません。」とまるで自身が名付け親みたいに小万知さんは返信メールに書き添えて居られましたが、万葉調の歌にはなるまいということへの思いからの言葉でしょうな。歌のことはさて置くとして、さほどに覚えにくい名でもない。アンシュエンシスというラテン語名はちょっと覚え難いと言えなくもないが、「あん(兄)酒宴しす」とか「庵主怨死す」という形で頭に入って来ました(笑)。 さて、プリムラ・ジュリアンは1月30日と12月29日の誕生花になっています。(クレマチス・アンシュエンシス) クレマチスは5月3日の誕生花です。 次の苺と蜜柑は、先の若草読書会のデザートにと偐家持が瓢箪山駅前のいつもの果物屋さんで買い求めて持参したものの残りを絵にされたものだとか。(苺たちの語らひ)苺らは 何や語らふ よたりして よからぬことを よもはかるまじ (偐家持) 苺は4月13日の誕生花です。(伊予柑) 蜜柑は、11月23日と12月28日の誕生花。 次の水仙と梅は当ブログ記事掲載の写真を絵にされました。 水仙は「墓参・梅と水仙」(2013.3.2.)に掲載の写真から、梅は「1296歳になりました。」(2014.1.29.)に掲載の写真から、絵にされたものです。(水仙) 水仙は雪中花とも呼ばれ、冬の季語となっている花。中国明代の作詩用の辞書、「円機活法」という書の中に水仙のことを「桃前梅後独リ春ヲ迎フ」とあるそうだが、実際には梅よりもずっと早くに「春ヲ迎フ」のではある。 で、いつの誕生花かと調べると1月3日のそれであるようです。もっとも水仙は水仙でもラッパ水仙は2月9日の誕生花です。(梅の花、今し咲き始む) そして最後は2月1日の誕生花、梅。 間もなく梅の花もその盛りを迎えることでしょうが、この時期に最も相応しきはこの花でしょうか。 この後も智麻呂さんは暫くの間、梅の花を描くことに忙しくなります。それが一段落すると春本番、桜の季節。いよいよ忙しく、桜、桜と西行にも東行、南行、北行にもなられるのでありましょう。 今日は大阪も大雪にて積雪。デイサービスも休業となり、ご自宅で無聊をかこっていらっしゃるとか、恒郎女さんのお電話でのお話でありました。ヤカモチ館長も同様であります。
2014.02.14
コメント(12)
-

偐万葉・英坊篇(その27)
偐万葉・英坊篇(その27) 偐万葉シリーズの記事は、それぞれの未掲載歌をそれぞれの篇ごとのボックスにコピー保存しているのを取り出して編集するのですが、気が付くと英坊篇ボックスが溢れそうになっていました(笑)。で、本日は英坊篇(その27)とします。 <参考>過去の英坊篇はコチラからどうぞ。 英坊3氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が英麻呂に贈りて詠める歌21首併せ俳句 並びに英麻呂が詠める歌11首併せ俳句 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 絵を見ては 頭献立 口よだれ (英麻呂) 下仁田葱に 下二句出ぬか (偐家持) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 いい句をば 詠もうするが 蓋重し (英麻呂) 真間の手児奈に テコなど借らな (偐家持) (注)真間の手児奈=下総国勝鹿(葛飾)の真間(現在の千葉県市川市) に奈良時代以前に住んでいたとされる女性。万葉集 には手児奈伝説を詠った歌がある。(巻3-431~433、 巻9-1807~8、巻14-3384・3385・3387) 英麻呂が作れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首税金を マン蓋意匠に 注ぎ込み 魅せる期待を 見せられるのか (英麻呂)玉くしげ 蓋のデザイン 尋(と)ひ行かば マンホールまた 楽しからずや 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句1句 銀(ぎん)〇(まる)の 正体知りたく 店覗き (英麻呂) 美食美酒にて 正体なくし (偐家持)もののふの 八十少女(やそをとめ)らと 家持も 西行なるらむ 高岡の駅 (本歌) もののふの 八十(やそ)をとめらが くみ亂(まが)ふ 寺井の上の かたかごの花 (大伴家持 万葉集巻19-4143) 英麻呂が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句並びに短歌1首 寒風に 紅顔と汗 青春魂 (英麻呂) トライの花を 明日は咲かさな (偐家持)花園は 春にも秋にも 見つれども いやラグビーの 冬ぞ見が欲し (本歌) たちばなは 花にも実にも 見つれども いや時じくに なほし見がほし (大伴家持 万葉集巻18-4112)瓢箪の 型にしめてや 藁馬が 笑ふまいとぞ 寄り添ひませる (笑馬麻呂) よき年は よしとよく明け よき人に よしと告(の)らして よしと言祝(ことほ)ぐ(偐武天皇) (本歌) 淑(よ)き人の よしとよく見て よしと言ひし 芳野よく見よ よき人よく見つ (天武天皇 万葉集巻1-27) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首大根の 個々の曲りは 現の世の 人の様にも 通じておかし (英麻呂)世のさまを 見れば大根 ならねども 臍も曲がれば つむじも曲がる (曲芸師千両大根)立山(たちやま)の 晴れたる姿 撮り集め ブログ飾らば 五万のアクセス (本歌)この頃の 吾が恋力(こひちから) 記(しる)し集め 功(くう)に申さば 五位の冠(かがふり) (万葉集巻16-3858)立山(たちやま)を カメラ片手に 七車(ななぐるま) 恋ひて撮りしや 七草の今日 (本歌)恋草を 力車(ちからぐるま)に 七車(ななぐるま) つみて恋ふらく わがこころから (広河女王 万葉集巻4-694) 英麻呂が作れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌2首キタキツネ カメラ目線の 愛らしき たが俊敏の 性を潜めて (英麻呂)麓郷は 北の国から キタキツネ 主役われにと 目線の言へる雪山は 晴天に映え 目にも映え だが残念な 撮の腕下手 (英麻呂)霊山に あれば立山 小手先の ことはな言ひそ 魂(たま)をぞ込めよ蟹かくに 玄関先は いかにかに 重いではさみ だるいで足も (石川沢蟹) (本歌)かにかくに 渋民村は 恋しかり おもひでの山 おもひでの川 (石川啄木 「一握の砂」) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が追和せる歌1首ダァ~リンを 来るを見つけて 喉ならし 媚をあらわす 見返りの猫 (英麻呂)さすらひの 猫にしあれば 見返りも 一瞥なれり 媚びにはあらじ (偐猫持) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首公園の 鹿にせんべい せびられて これでナッシ~と 言えば頭突きに (英麻呂)馬どしの 鹿にあるらし 頭突きとは しかりてしかと おしへ諭さむ (偐家持)天神光 まとひ大見栄 切るならし 今宵建物 みな歌舞伎たる (越の団十郎) 蜘蛛の巣を 払へばわが家 蜂の巣と なりて五軒の 阿吽の店に (家主の蜂麻呂) 英麻呂が贈り来れる上3句に偐家持が下2句を付けたる歌 楽しさの 鬨と笑いに 疾走す (英麻呂) 馬それぞれの 若草の原 (偐家持) 英麻呂が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌1首誕生の 祝い花鉢 貰う主 偐家持でなく けんの家持 (英麻呂)偐であれ けんでありとも 違ひなし ともにどのみち やかもちもどき難波形 ならぬ姿の いか焼きは 食はで参道 やり過ぐしてよ (偐烏賊持) (本歌) 難波潟 みじかき葦の ふしの間も 逢はでこの世を 過ぐしてよとや (伊勢 新古今集1047 小倉百人一首19) 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌2首片眼帯 ガーゼ取りたや もどかしい 美人ナースの 顔も半分 (英麻呂)眼帯を とれば世界は 新しく なりて逢ふ人 みな美しき輪行きで 古への跡 偲ぶりて 主の思いに 感応しきり(英麻呂)銀輪で 走るは現(うつつ) 立ち寄りて しのぶ古(いにしへ) 似たるか夢に 英麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌2首病室の 窓から見える 山姿 もやもかからず 発見あらた(英麻呂)目にさやか 生駒の山は はしきかも わが朝夕(あさよひ)に 見つつある山PC(パソコン)のご機嫌そこねまたの愚痴 これも届けと楽天へ愚痴(英麻呂)しかなればわれや名付けむ君が名は グッチ英麻呂ヴィトンにあらじ(注)掲載の写真は英坊3氏のブログからの転載です。
2014.02.13
コメント(4)
-

本日退院しました。
8日間の「健康的な入院生活」から追放されて、元の木阿弥の「不健康な日常生活」に本日無事復帰致しました。 昨日は、図らずも輪友の偐山頭火氏から陣中見舞いを戴きました。熱い珈琲を魔法瓶に入れ、苺大福を添えての陣中見舞いでありました。小阪から石切・水走まで自転車(MTB)でのご来駕、いや、ご来輪ですかな。その後、若草の智麻呂邸を訪ねるとのことで、暫しマイ・ルームにて歓談。退院後の銀輪行のことなども話題に上りましたが、これは本日の退院に際しての今後の注意事項や通院のことなどをよく確認してからのこととなるので、いつ頃から普段通りに走れるや否やによること、また、彼自身が俗世間の仕事から未だ足を洗い切れない往生際の悪さを生きる身にて、日程の調整が上手く行くか否かも分からぬことなど、不確定要素の多々なれば、曖昧模糊のままに置くの外なく、でありました。 彼が去るのと入れ替わりに、母や妹や姪や家内がうち揃っての来場。今度は、「のらやの手作りわらびもち」なる珈琲入りの蕨餅による陣中見舞いでありました。 珈琲好き家持ということで、偐山頭火さんも妹達も珈琲絡みの陣中見舞いでありました(笑)。それにしてもコーヒーゼリーは夙に存じ上げ候ひしもコーヒーわらび餅とは、初めて。まあ、いける。背水の 陣にしなけれ 水走(みづはい)の 陣なるわれに 輪(りん)の背子来(こ)し (偐家持)かたかごの 花より珈琲 含(ふふ)みたる わらび餅かと 姪もち来たる (偐家持)(のらやの手作りわらびもち) さて、病院の名は曖昧なままにして置くつもりにてありたれど、既にしてたれかれとなく知られたりければ、その名を明らかにせむとて・・(石切生喜病院)(同上)(同上)(同上6階休憩室<デイルーム>)(鬼虎川遺跡説明板) この病院のある地を中心とする一帯は弥生時代の一大集落があったとのことで、鬼虎川遺跡と呼ばれているそうな。 この病院建設に当たって大規模な発掘調査が行われたとのことで、このような説明文の付された大型の発掘状況写真パネルが院内に掲示されていました。邪馬台国は此処、水走の地にあったという説を打ち立てましょうかね(笑)。 このパネルは外来・一般病棟の2階に掲示されているのだが、入院病棟と一般病棟は2階で連結廊下で結ばれているため、われわれ入院患者が診察を受けに一般病棟へと向かう際には、このパネルの前を通ることとなる。そんなことで、たまたまそれと気付いたもの。(写真をクリックして拡大写真でご覧戴くと読み易いかと思いますので、興味ある方はどうぞ。)(梅・入院病棟東側通路) 徘徊家持、病院内を隈なく歩きました。殆ど誰も通らない病棟の片隅にも、ひっそりと紅梅が咲き匂っているのでありました。(同上) 一期一会の梅の花に送られての退院ですかな。梅の花 はしきと見れど また来むと 言ふ人ぞなき 病庭の隅 (偐家持) これにて、ヤカモチ入院始末記全5巻めでたく完結と相成りました。 どちら様もブログの上にてのご丁重懇篤なるお見舞い、まことに忝く、心より御礼申し上げ奉りまする。
2014.02.12
コメント(12)
-

退院決定
左目の覆いを取って戴きました。手術直後のそれは遮光不透明にて外界が見えないので片目生活となり、ちょっと鬱陶しいのであるが、翌日午前中にはもう、それを外して透明プラスティックのものに変えてくれる。 「手術後カッペをしますので絶対にはずさないでください。」と手渡された注意書きにはありましたが、この覆いがカッペである。 しかし、カッペがKappeというドイツ語であることに気が付くのに少し時間が掛かる。キャップという英語なら日本語にもなっているから、そういうことはないだろう。どうしてキャップという言葉を使わないのでしょう。 まあ、カードをカルテと言うのが医学の世界だから、そちら世界ではそれでいいとしても、カッペはカルテほどには一般化していないのだから、患者向けにはキャップを使う方が分かりやすかっぺ、と思いますがね、田舎っぺの田舎家持としては。 さて、そのカッぺであるが、これを取り外す瞬間が何とも素晴らしい瞬間なのである。始めに光ありき、または、世界は光と共にありき、などと言いたくなるような瞬間なのである。溢れる光と鮮やかな世界がそこに現出する。それは殆ど過剰なまでに鮮やかな世界なのである。 その鮮明さはまた視神経に過剰な刺戟をもたらしているのではないかとも思ったりもしている。その結果、どうも脳の方でこれを補正するようなのである。 と言うのは、6日に手術した右目のカッぺを翌日7日に外した時も同様な鮮やかさを感じたのであるが、その右目と今日の左目を比べると明らかに左目の方が色が鮮やかと言うかコントラストが鮮明なのである。これは右目が過剰な刺戟を回避するための補正を行った結果であり、やがて左目もそのように補正されて、現在の右目程度の鮮明度に落ち着くのだろうと推測される。 こういうのは馴化(順化)というのですかね。環境に適応するために生物が自らを変えることを馴化と言うが、過剰な光刺戟に対して感じ方の方を変化させるというのも、この能力と同じ性質のものであるように思われる。 生まれたての目は、今、必死に馴化しているのですな。このことによって、最初のあの感動的なまでの鮮やかさというのは、徐々に薄れて、ほどほどなものになる・・という次第。美女は3日で飽きる、ブスは3日で慣れる、というような言葉は品性に欠けるものにてヤカモチの好まぬ処なれど、この馴化というものの一面を言い得ている言葉ではある。 何であれ、当たり前になって行くというこの馴化というものは、個人にとっても人類全体にとっても、或る面で救いとなる一方、不幸や不満や諸々の悪しきことを招来する下地ともなるものなのではある。 など、思いつつ、わが病室とも明日12日でお別れである。 お世話になった先生や看護婦さんや配膳や掃除などお世話下さった皆さんに感謝しつつ、めでたく退院と致しまする。 では、病室君、あと一晩よろしくお願い申し上げまする(笑)(わが病室:マイン・クランケン・ツィマーと呼ばねばならんのか?)
2014.02.11
コメント(10)
-

次は左目
6日の右目に続いて、今日10日は左目の手術の日。 手術は午前11時から。この手術が終われば、わが「快適入院生活」も終焉を迎えることになる。と言っても明日11日は建国記念日にて、祝休日の退院は出来ないということで、1日延びて12日の退院となる。 入院したのが5日だから、今日は入院6日目。入院も今日を含めてアト3日を残すだけ。 されば、折角のことゆゑ、入院の記念にもと、当病院よりの眺めなど撮影しつつ、以って記事になどしてみむとて。 先ず、病棟からの東西南北の眺めです。(東方向の眺め・6階病室から) これは、わが病室からの眺め。(西方向の眺め・8階展望ホールから) これは、8階展望ホールからの眺め。こちらサイドは病院のすぐ前を恩智川が流れている。小生が常々銀輪で走る道である。(南方向の眺め) これは6階の廊下南端の非常口からの眺め。南方向は、南端の病室から以外は、この非常口扉越しにしか外は見えない。(北方向の眺め) これは6階休憩室からの眺め。各階の休憩室・食堂などは北側に配置されているので、北方向の景色は南方向のそれと違って容易に何処からでも撮影できる。 小生の病室は6階なので、行動するのは、この階と1階のロビー、屋外の喫煙所、そして8階の展望ホール位でしょうか。 8階展望ホールは写真家はどなたであるのか確認していませんが、美しい四季折々の風景写真パネルなども掲示されていて、なかなかいい空間になっている。テラスに出る扉はロックされていて、出られないのが少し残念。(8階展望ホール)(同上) 上は夜の佇まい。下は昼間の雰囲気です。(同上) そして、愛用の喫煙所。 入院スモーカーたちの社交場でもある(笑)。ただ、この季節は寒いので、社交も煙草1本を吸い終わるまでの数分という短い交流にならざるを得ない。(喫煙所) 喫煙所近くの梅の木。 昨日の記事に掲載の梅の花は、この木のものでした。 次の山茶花も同様です。(喫煙所近くにある梅の木)(同上・山茶花) (入院病棟と月) 喫煙所へは正面玄関を出入りしなくてはならないのであるが、出入り可能なのは午後8時まで。従って、午後8時以降は禁煙するしかないこととなる。 昨日の午後4時半頃、喫煙所から玄関へ回る途中で見上げると東の空に月が出ていました。左が欠けていますから上弦の月。ほぼ半月でしょうか。弓張月ですな。 入院中の小生の行動範囲は上の通りなのだが、一昨夜こんなことがありました。夜中0時半頃に目が醒めて、喉の渇きを覚える。冷蔵庫には飲み物がない。病室を出て同じ階の休憩室にある自動販売機でお茶を買おうとしたら、休憩室の扉が閉まっていて開かない。通りかかった看護婦さんが5階か7階の休憩室なら開いていると教えて下さった。1階まで下りる必要がないと階段で5階に向かう。ペットボトルのお茶をゲット。 ここまでは良かったのだが、5階に下りていることを忘れて6階のつもりで自分の病室へと向かう。ドアを開けると真っ暗。照明は付けたまま出た筈、部屋を間違ったかと外に出て確かめるが部屋の位置は小生のそれの位置。再び入ろうとすると、カーテンの向こうから「部屋を間違っていませんか。」という女性の声。それでようやく部屋を間違った(いや、正確には、部屋ではなく、階を間違った)ことに気付く。「失礼しました。」と慌てて外へ。 手術で目がよく見えるようになっても、肝心の脳の方がこれでは何にもならない。変だと思わずに入ってしまって、もしその部屋の女性が熟睡していて小生に気付かず、小生も亦真っ暗の中で彼女に気付かずにベッドに転がり込んでいたりしたら、そして、その瞬間に彼女が目覚め、キャーッとか騒ぎ立てたとしたら、これはもうとんでもないことになっていた可能性がありました。濡れ衣というのは、事実が無いのに疑われることですが、今回の小生のそれは外形的には事実を伴っていて、無いのは故意という主観的要素だけ。この場合「故意でない」ことを証明するのはかなり難しいような気もしますから、部屋の女性が起きていて下さったのは幸運なことでした(笑)。 5階を6階だと誤解していましたの「弁解」では洒落にもならぬ。 一つ階段を上って自分の部屋に戻ると、やはり照明は付いていました。真夜中の階段話は怪談よりも「怖い」、と言うか、要注意です。また、「ゴカイ」という陥穽にはくれぐれにもご注意ということですな。自分も他者も誤解するものである、ということを忘れてはいけない。どうぞ皆さまも「ゴカイ」には特にお気をお付け遊ばされますように。まあ、碁会所なんかは問題ありませぬが(笑)。(10日午前4時10分) そして、まだ明けやらぬ朝の窓外の眺め。 これは今日の朝の眺め。朝と言っても日の出にはまだ時間もあって夜景と変る処なしである。入院生活の一日は上のような景色で始まり、上のような景色で終るという次第。<追記>左目の手術も無事完了。今回は右目の時と違ってやや痛みがある。さて、手術を済ませて帰ってきたら、英坊さんからアベノハルカスは見えるかとのコメントを戴いていました。それで昼食後8階展望ホールで確かめて来ました。やや南寄りに見えていましたので、その写真を追加で掲載します。(アベノハルカスも見えています。) ついでに、7階休憩所も。各階とも同じ感じですが、7階のそれだけ8階と吹き抜けになっているので上からの撮影が可能です。(7階休憩所・8階展望ホールから) もう一つ、ついでに恩智川も。(恩智川) 花園中央公園は、画面左(即ち上流)に恩智川を行くとあり、右(下流)に行くと大東市になります。 高速道路は阪神高速13号東大阪線。中央大通り(国道308号)の上を走り、阪奈トンネルで奈良へとつながっている。小生が囲碁例会で梅田に向かう時は、この下を自転車で画面奥のビル街の方へと走っているのである。
2014.02.10
コメント(14)
-

梅の花咲きてぞ春は
1月31日の蝶麻呂君との銀輪散歩で立ち寄った緑ヶ丘公園の梅林はまだ蕾も固く、咲いている花は一つとてなかったのでありますが、こちらの病院の庭では梅が咲きましたから、今頃はかの梅林も馥郁たる梅の香に満ち満ちていることであるでしょう。 入院病棟の西側の庭に梅や山茶花の花が咲いている。 病室が6階なので庭に出るのは少し面倒。されど、喫煙場所がその一角にあるので、厭わずに通っています(笑)。それにエレベーターではなく階段を使って上り下りして居りますので運動不足も解消。因みに病室から喫煙所まで階段を使うと往復で約600歩。煙草1本吸うと600歩を歩くことになる。煙草を吸う度に身体が鍛えられるという寸法。これって健康に良いのか、悪いのか(笑)。 それはさて置き、今日は梅の花の記事です。 大伴旅人が大宰府で観梅の宴を開いたのは天平2年正月13日(730年2月8日)であるから(この宴での歌は、下記参考1.参照)、昨日8日にこの記事をアップすれば丁度よかったのですが、生駒山に先を越されて一日遅れとなりました。(病院の庭の梅)病棟の 庭に咲きたる 梅の花 春のさやぎを 何とてや告ぐ (偐家持)(同上) 梅に因んで1首作ってみましたが、面倒なので、過去の記事に掲載した偐家持作の梅の歌で代用することにしましょう。作った本人も忘れているのだから、読者諸氏もそれと気付く人はいないでしょう。ブログページ右欄のキーワードサーチで検索してみて出て来たものを少しばかり掲載して置きましょう。人みなは 春は桜と いふなれど まず咲く梅を 春とや言はむ (梅郎女)冬ごもり 春さりくれば 梅の花 見せばや妹に 今しぞ咲ける (偐家持) 朝鳥の 声のとよみて 白梅の 花は咲きたり 一輪二輪 (偐家持)くれなゐと 真白にぞ咲く 梅の花 春の競(きほ)ひの 見らくしよしも (偐家持)(同上)(同上)(同上)<参考>梅の万葉歌を掲載している過去の記事 1. 梅の花咲き始めにけり枚岡の・・ 2013.2.21. 2. 囲碁と梅と水仙 2011.2.9. 3. 枚岡梅林 2010.2.22. 4. 枚岡梅林、花園中央公園 2009.2.21. 5. 第26回智麻呂絵画展 2009.2.15. 芭蕉の梅の句を掲載している過去の記事 6. 墓参・梅と水仙 2013.3.2. そして、山茶花。白梅に続いて山茶花も白。 白い花が並びました。 上の梅では過去の歌を引っ張り出しての「手抜き」手法を採用しましたが、山茶花についても、この手を使わせて戴きましょう。 山茶花だけに、「手抜き」とは言わず、昔の歌で「お茶を濁す」と言うのでしょうな。わが屋前(には)に 咲ける山茶花 春立てば 咲けど葉陰に はにかむらしも (偐家持)春立てば 椿とも見む 山茶花の 八重にし咲くの 見らくしよしも (偐家持)今はもや 泣けと降るらし 夕寒の 山茶花時雨 間なくしあれば (偐家持)楚(しもと)踏む み山の奥の 山茶花の 咲ける静寂(しじま)に もみぢ葉散れる (偐家持)鶴見野も 山茶花梅雨(さざんかつゆ)と なるやらむ ポプラのほつ枝 暗き雲あり (偐家持)さざんかの さんざか咲いて 北風の 曲がり小道も いささかぬくし (垣根曲麻呂(かきねのまがりまろ))山頭火 茶化して見れば 山茶花に (筆蕪蕉)山茶花に 似て非なるかな 山頭火 (筆蕪蕉) 山茶花が「さざんか」なら、山頭火もいずれ「さとんか」か。(サザンカ・白) 白い花ばかりでは彩りと華やぎに欠ける。 赤い花も添えましょう。(サザンカ・赤)(サザンカ・赤)
2014.02.09
コメント(8)
-

生駒山見つつもをらむ病棟に
白内障も病気と言えば病気なのだが、ヤカモチの「病気」の範疇には入っていないので、入院などという大袈裟なことになっているのが何とも奇妙な感覚にて、場違いのわれにしあるや・・など思いつつブログなどアップしてみむとて。さればとて、銀輪家持なれば銀輪なきは筆なきがごと、すべもなければ病棟の窓にし見ゆる生駒山などを・・。 通常は、入院にてあれば「病床に・・」となるのでしょうが、本人は病気とは思っていないのだから、病床というのはしっくり来ない。さりとて入院はしているのだから入院病棟にいることには違いない、ということで折り合いを付けたのが、上のタイトル「・・・病棟に」であります(笑)。病棟に 見つつもをらむ 生駒山 何とてなすの こともなきわれ (偐家持)(病室から生駒山を望む。) これは入院した2月5日に、病室から生駒山を撮影したもの。病室は東に面しているので常に生駒山とご対面である。 下は、翌6日の早朝の生駒山である。(生駒山の夜明け) 生駒山の登場する万葉歌は6首ある。それぞれについてこれまでに何処かのページに掲載していると思うが、その全部をまとめての掲載はしていないかも知れないので、ここで掲載して置くこととします。・・・露霜の 秋去り来れば 射駒(いこま)山 飛火(とぶひ)が岳(をか)に 萩の枝(え)を しがらみ散らし さ雄鹿は 妻呼びとよむ 山見れば 山も見が欲し 里見れば 里も住みよし・・・(万葉集巻6-1047)妹がりと 馬に鞍置きて 射駒(いこま)山 うち越え来れば もみち散りつつ (同巻10-2201)君があたり 見つつもをらむ 生駒山 雲なたなびき 雨はふるとも (同巻12-3032)夕されば ひぐらし来鳴く 生駒山 越えてぞ吾(あ)が来る 妹が目を欲り (秦間満(はたのはしまろ) 同巻15-3589)妹にあはず あらば術(すべ)なみ 石根(いはね)ふむ 生駒の山を 越えてぞ吾(あ)が来る (同巻15-3590)難波津(なにはと)を 漕ぎ出(で)て見れば 神(かみ)さぶる 生駒高嶺(いこまたかね)に 雲そたなびく (大田部三成(おほたべのみなり) 同巻20-4380) 万葉人にとって生駒山は、恋人を思う山であったり、越えてぞ妻や恋人に逢いに行く山であったり、遠く故郷を偲ぶ山であったりしたのだが、今の偐家持にとっては、朝夕に見つつもあらむ生駒山であり、見るほかに何とてもなき生駒山である(笑)。(同上) 春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山ぎはの少しあかりてむらさきだちたる雲の細くたなびきたる・・でしたでしょうか。朝の生駒山の景も枕草子の景さながらに6日7日は明けて行ったのでありますが・・。(同上) 昨夜から雪が降り始め、翌朝には一面の銀世界と期待したのですが、起きての今朝の景色はご覧の通り、屋根にいささか白きもの降り積みたるのみにて、道路などは濡れているばかり。既に雨にと変わりたれば、更に積もることもこれなきかと・・。(2月8日の朝、雪の降れるに・・)な隠しそ 言ふに雪雲 烏滸なるや 今朝は隠しつ 生駒の山を (隠家持) など言っているうちに、山の稜線が次第にくっきりして来て、生駒山山頂部分のみが雲の中という状態にまでなっていますから、ようやく雲も反省し始めたと見える(笑)。 病院の庭にも出てみたれど、はだれの雪の消え残りたるが少しばかりあるのみ。白内障の手術も右目ばかりなれどひとまずは終りて、ものみなさやかに見えたれば、すももの花に見間違えることもなければ、白い山茶花が散ったのかなどと、とぼけたことを言ったりもしないのである。
2014.02.08
コメント(9)
-

宝塚・伊丹銀輪散歩(その4)
(承前) 右目の手術無事完了。次は10日に左目です。 先程、右目の覆いを外して戴きましたが、世界の明るさ、色の鮮やかさが一変。左目の旧来の目で見る風景と右目の新しい目で見る風景がまるで違う。物みなが新品に入れ換わったように鮮やかに見える。 さて、宝塚・伊丹銀輪散歩を続けましょう。これだけよく見えたら銀輪散歩もはかどるというものである(笑)。 猪名野神社を出て、県道13号を南下する。 猪名野と来れば、誰しも思い浮かぶのは百人一首のこの歌。ありま山 猪名の笹原 風ふけば いでそよ人を 忘れやはする (大弐三位 後拾遺集709 小倉百人一首58) 作者大弐三位は藤原賢子、紫式部の娘である。正三位大宰大弐高階成章の妻となり、後に親仁親王(後の後冷泉天皇)の乳母となったことで、後冷泉天皇即位後、従三位を賜る。というようなことで大弐三位と呼ばれることとなる。 「ありま山~風ふけば」の上3句は「そよ」を導くための序詞。「いでそよ」(いや、全くそうですよ。)という言葉を言いたいために、有馬山、猪名の笹原、吹く風まで動員して来るのだからすごい。そして、彼女が言いたいのは勿論「いでそよ」ではなくて、「人を忘れやはする」(あなたを忘れたりするものですか。)なのである。 この歌は「かれがれなるをとこのおぼつかなくなどいひたりけるによめる」とあるから、離れ離れになってご無沙汰の男から、あろうことか「貴女の気持ちがもひとつたよりなくて疑わしい」と言って来たことへの返事である。ご無沙汰男としては、あんたの心が離れているからだと相手の所為にする常套手段を取ったのだが、ピシャリとやり返されてしまったという次第。 以前にこの近辺を散策した折にはこの歌の歌碑や次の高市黒人の万葉歌の歌碑なども見た気がするのだが、下調べもなくやって来たので、それが何処にあるのか分からぬままでありました。しかし、このブログは偐万葉、万葉歌は歌碑を見落としても掲げて置かなくては義理が果たせない(笑)。我妹子(わぎもこ)に 猪名野(いなの)は見せつ 名次山(なすきやま) 角(つの)の松原 いつか示さむ (高市黒人 万葉集巻3-279)しなが鳥 猪名野を来れば 有間山 夕霧立ちぬ 宿(やどり)はなくて (万葉集巻7-1140)(猪名川) 県道ばかり走っていては、笹原もなく、風も吹かない。猪名川べりも少しばかり走ってみる。(神津大橋) 蝶麻呂君が橋の上から猪名川の写真を撮っています。わが背子に 猪名川見せつ 青屋根の ブロ友の店 つぎに示さむ (河内黒人) とて、この後、新伊丹駅に向かい、1月31日の記事に書いた通り、てらけん氏の経営される喫茶店へと向かうのでありました。 この段落は先の記事と重なるので省略。店を出た処から始めます。 「さあ、帰ろう。」と蝶麻呂君。 「まだ昆陽池が残っている。」とヤカモチ。 かくて、昆陽池公園に向かう。と言っても遠回りになるのではない。宝塚駅前へと戻る道すがらにあるのであれば。 ほどなく到着。 この池は天平3年(731年)に行基が灌漑用に開削した池である。大伴家持が13歳の時に出来た池ということになる。伊丹空港から離陸すると飛行機は左旋回するが、この時に左窓から見えて来る、日本地図の人工島のある池、と言えば、多くの人があれかと思い当たる池である。(国土交通省空中写真) 今は埋め立てられて小さくなっているが、対岸が霞んで見えないなどと詠っている歌があるように元は北の瑞ヶ池も含む広大な池であったようだ。余呉湖を少し小さくした位の大きさであったのだろう。 昆陽池公園には歌碑など文学碑が多く設置されているようだ。しかし、それを知ったのは帰宅してネット検索した結果であって、アトの祭。「獺の祭」なら、芭蕉さんも「見て来よ瀬田の奥」と言って居られますが、「後の祭」ばかりは誰も見ることを得ず、出直すの他なきものにてありまする。来(こ)や来(こ)やと 昆陽池(こやいけ)いへば くさぐさの 歌碑見むために また尋ね来(こ)や (偐家持)(昆陽池) <参考>昆陽池公園・Wikipedia それでも、偶々、待賢門院堀河さんの歌碑は見掛けることが出来ました。この女性は待賢門院璋子(藤原璋子、鳥羽天皇の中宮、崇徳天皇の母)に仕えた女性。(待賢門院堀河の歌碑)昆陽の池に 生ふる菖蒲の ながき根を ひく白糸の 心地こそすれ (待賢門院堀河 詞花和歌集) こちらは言わば「白の歌」。この女性の歌で皆が知っているものと言えば百人一首の次の歌。ながからむ 心もしらず 黒髪の みだれてけさは ものをこそおもへ (待賢門院堀河 千載集801 小倉百人一首80) こちらは「黒の歌」。どちらも意味や雰囲気は共通である。歌の出来は従って白黒つけがたい(笑)。 小生一人なら昆陽池公園を廻ってから帰る処なれど、今日は蝶と共にの散歩にてもあれば、堀河さんの歌碑のみ見てや帰りなむ、であります。 武庫川に出ればよし、で大雑把に方向感覚だけを頼りに走る。やがて武庫川べりに出る。この川は2011年に蝶麻呂君と河口までの往復を走っている。 <参考>武庫川銀輪逍遥 2011.1.14.(武庫川) 小さな川が流れ込んでいる処で武庫川に別れ、一般道に戻る。(宝塚歌劇場) 今年は宝塚歌劇団が誕生して百周年に当たるのだと蝶麻呂君に教えられる。そう言えば、道路(「花の道」という名が付いている。)にもその旨の旗が下がっていました。 歌劇場の前を通ると、沢山の女性たちが並んでいました。宝塚のスターのお出ましを待ち受けているのか、その辺の処は万葉ヤカモチの与り知らぬことである。 宝塚駅前到着午後4時40分位。自転車をたたみ、バッグに詰めて、本日の銀輪散歩終了。途中の昼食や喫茶店「青い屋根」での休憩時間なども含めて約7時間の銀輪散歩無事終了であります。お付き合い有難うございました。駅構内のレストランで蝶麻呂君と軽く夕食を取って家路に・・。(完)
2014.02.07
コメント(6)
-

宝塚・伊丹銀輪散歩(その3)
(承前) 中山寺山門前から南へ下り、国道176号に出て左折、東へ。中筋4丁目で南に入ると正面にJR中山寺駅。駅前ロータリーには真新しい聖徳太子の騎馬姿の像があったが、線路を渡る道はない。東側の池に沿う道を行くと果たして踏切。南下すること700m位で川に出る。橋の銘板には天王寺川とある。 (天王寺川) 川に出ると本能的にその川べりを走りたくなるのがヤカモチ。 暫く天王寺川に沿って走る。間もなく中国自動車道。これを潜った処で東に向かい荒牧交差点で県道336号に出る。これを暫く南下した後、地図での下調べで設定したのは天神川沿いの道であったので、左折して天神川に出る。(天神川) 天神川沿いを下り過ぎて、帰途に立ち寄る予定であった昆陽池の前に来てしまう。瑞ヶ池から緑ヶ丘公園へのコースに引き返すべしであるが、時刻を見ると11時55分。先ず腹拵えである。昆陽池公園入口前の中華レストランで昼食。 昼食後、緑道(遊歩道)に入り、瑞ヶ池に向かう。(瑞ヶ池)<参考>瑞ヶ池公園 瑞ヶ池に向かう途中であったか、その後であったか、今は記憶も曖昧になっているが、1月31日のブログ記事でご紹介したラクウショウの気根を見付けたのは、この緑道の何処かでありました。 瑞ヶ池から緑ヶ丘公園までは300mほど。 (緑ヶ丘神社) 先ず、公園の北東隅にある臂岡天満宮に立ち寄る。 ここは、大宰府に向かう菅原道真が立ち寄って休憩した場所とのこと。道真は万葉集を大事にした人物。今日に万葉集が残ったのは彼の力も大いに与っていると言うべきなれば、「このたびは幣もとりあへず」であるが、偐とは言え、万葉のヤカモチ。ご挨拶申し上げるのが筋と言うものでありましょう。(臂岡天満宮) 道真の叔母が道明寺に居り、大宰府に向かう折に彼はこの叔母を訪ね別れを惜しんだこと、翌朝に「鳴けばこそ 別れも憂けれ 鶏の音の なからん里の 暁もがな」という歌を詠んだということなどは、道明寺天満宮境内の一茶の句碑に関連して以前の記事で述べた処であるが、道真は夜明けと共に河内国の柏原を発ち、此処、猪名野に至って、休憩を取ったということになるのですかな。(同上)(同上・由来)(緑ヶ丘公園) 緑ヶ丘公園は、昔、友人の草麻呂氏と銀輪で訪れた他、何度か訪問しているが、久々の訪問にて懐かしきことしきり。 ここの梅林もなかなかいいのですが、まだ梅は早かったか、咲いているのは蝋梅ばかり。蝶麻呂君も梅林に入り込んで、花を探して居られましたが、さすがの「蝶」も花は見つけられなかったようであります(笑)。(同上・梅林)(同上・ロウバイ) 緑ヶ丘公園から猪名野神社へ向かう。 途中に和泉式部墓の標識があったので、それが示す方へと行く。 和泉式部や小野小町などの墓は銀輪散歩をしていると彼方此方で目にするので、そういったものの一つか。此処でもお隣の家の犬に吠えられましたワン(笑)。(伝・和泉式部墓)(同上・説明板) 緑道に戻って少し行くと。藤原良経歌碑や白洲次郎の実家の屋敷跡の碑などがありました。(藤原良経歌碑) 歌碑の文字はちょっと読み辛いが、歌は次の通り。猪名山の 道のささ原 埋れて 落葉が上に 嵐をぞ聞く (藤原良経 秋篠月清集)(猪名野の丘の道を行くと、道は笹の葉に埋もれて、その落ち葉の上を吹き抜けていく嵐の音が聞こえるばかり)(白洲屋敷跡)(同上説明碑) そして漸くに猪名野神社です。 猪名野神社の地は、戦国時代の荒木村重の居城・有岡城の北端を防御する砦(きしの砦)の跡地で、本殿裏には土塁の跡が今も残っている。我々は裏から境内に入ったので、それと知らずにその土塁跡を越えて来たのであった。詳しくは下記の<参考>をご覧下さい。(猪名野神社)<参考>猪名野神社・Wikipedia (同上・拝殿)(同上・本殿) では、そろそろ、手術の時間も迫って参りましたので、こんな処で切り上げることとします。続きはまた、明日、ということで(笑)。(つづく)
2014.02.06
コメント(4)
-

宝塚・伊丹銀輪散歩(その2)
(承前) 売布神社から中山寺へと向かう。参道入り口から、池の前の道を道なりに800mほど行くと中山寺の山門、大門である。 <参考>中山寺ホームページ 同・Wikipedia 中山寺は真言宗中山寺派大本山、本尊は十一面観世音菩薩、西国三十三所第24番札所である。聖徳太子が建立したと伝えられる日本最古の観音霊場である。 古来、安産祈願の霊場として信仰を集めた。豊臣秀吉が祈願して秀頼を授かったとされるほか、孝明天皇典侍、中山慶子(中山一位局)が皇子(のちの明治天皇)を出産する時に安産祈願をして無事に出産した寺ということで、明治天皇勅願所となるなど、安産の寺として全国にその名が知られるようになる。(中山寺山門・大門) 大門は天保3年(1646年)徳川家光による再建。(大門から本堂への参道)(本堂への石段にはエスカレーターも設置されていた。) 本堂への石段の右脇には屋根覆いのあるエスカレーターが併設されていました。スロープの設置などいささかの配慮もなくはない寺社ではありますが、まだまだこの面では立ち遅れているのが現状。もっとも、文化財としての原状維持・保存などとの関連で難しい問題もあるのでしょうね。そんなことでエスカレーター設置のお寺というのは珍しいことです。妊産婦のお参りも多いということでの設置ですかな。(本堂) 本堂は慶長8年(1603年)豊臣秀頼の命により片桐且元が再建。(本堂と大願塔) <御詠歌> 野をもすぎ 里をもゆきて 中山の 寺へまいるは のちの世のため 群雲の かかる浮世の 中山に 慈悲の光や ひとり晴れゆく(大師堂) 熱心に何やら見入っているをのこ一人。 友人の蝶麻呂氏でありますな。(同上説明板)(大願塔)(安産手水鉢) これは舟形石棺。仲哀天皇の皇子、忍熊王の遺体が収められていたものとの伝承のあるものだが、中世には手水鉢に転用されていたようで、この手水鉢で身を洗い清めれば安産が叶うという伝説が生まれ、「安産の手水鉢」と呼ばれるようになったとか。(同上説明板)(中山寺古墳・石の櫃) こちらは、忍熊王の母である大仲姫の墓と伝えられる古墳。 大仲姫は仲哀天皇の妃。香坂王、忍熊王を生む。 仲哀天皇の皇后は息長足姫、即ち神功皇后である。 仲哀崩御後、神功皇后の生んだ幼い皇子(のちの応神天皇)と香坂王・忍熊王兄弟との間に天皇位をめぐる争いが起こる。この辺の経緯は日本書紀神功皇后摂政元年2月の条から3月の条にかけて詳しく記述されている。 兄の香坂王は戦の先行きを占うための祈狩(うけひがり)で猪に食い殺されてしまう。弟の忍熊は明石から住吉、宇治と転戦する。最後に宇治川を挟んで武内宿禰の軍勢と対峙した時に、武内宿禰が「われわれは天下を貪らない。幼い皇子を擁してあなたに従うことにしたので、もう戦う必要がない。共に武器を捨てて和睦しようではないか。あなたが皇位につけばいい。」と言い、軍は武器を川に投げ捨てる。これを見て、和睦を信じた忍熊王は自軍に命じて武器を川に捨てさせる。 ところが、これが謀略。武内宿禰軍の捨てた刀は木刀であったりの贋物、見せかけの武器で、実際の武器は別に隠し持っていたのである。それを取り出した敵軍は一斉に川を渡って襲いかかって来る。忍熊王は逃げる。逢坂、瀬田へと逃げるが、逃げきれず、瀬田の渡しに身を投げて死ぬ。 川に沈んだ死体が見つからない。怒った武内宿禰が作った歌。 淡海(あふみ)の海(み) 瀬田の済(わたり)に 潜(かづ)く鳥 目にし見えねば 憤(いきどほろ)しも (武内宿禰 日本書紀) 死体は宇治まで流れ、そこで見つかる。で、彼が詠んだ歌。淡海の海 瀬田の済に 潜く鳥 田上(たなかみ)過ぎて 菟道(うぢ)に捕(とら)へつ (武内宿禰 日本書紀) このようなおどろしき話のある忍熊王の遺体が収められていたという石棺が、安産の願いを叶えてくれる手水鉢になったとは。 <参考>香坂王・忍熊王のことは以前にも記事にしていました。 兎我野に近づく勿れ 2012.3.9.(同上説明板)(無料休憩所の格天井) 写真には撮りませんでしたが、本堂下の境内には節分の豆まき用の足場がぐるりと設営されていました。宝塚歌劇団の生徒達による豆まき式が行われるのだそうな。 境内からは宝塚、伊丹の市街地が一望である。(中山寺境内から南方向、市街を望む。) 中山寺から、瑞ヶ池公園などを経て猪名野神社へと向かいますが、字数が丁度宜しい様で、続きは明日以降ということにします。 もう入院して病室でブログ記事を書いているのですが、手術は明日の午後3時から。明日は術後の状況次第で記事を書くか、書くことを欠くことにするかを決めることとします(笑)。 <つづく>
2014.02.05
コメント(11)
-

宝塚・伊丹銀輪散歩(その1)
(承前・「青い屋根」訪問) 1月31日の蝶麻呂君との銀輪散歩の記事アップが遅れていましたが、本日より取りかかることとします。 蝶麻呂君とは一昨年の2月17日に小塩山に登って以来の久々の再会。 <参考>小塩山登山 2012.2.17. 天王山紅葉ハイキング(上)(中)(下) 2010.11.17~19. 播磨富士 2009.1.15. 宝塚駅前でトレンクルを組み立て午前10時半頃出発。地図によって、小生が一応のコース設定をしたのだが、宝塚市民である蝶麻呂君の方が地理感があり、彼のリードするまま、地図で設定した道を取らずに走り出す。 先ず、目指すは清荒神。宝塚駅前からは結構な坂道を登ることとなるが、押して歩くということはしないで登り切ることが出来ました。 <参考>清荒神清澄寺のホームページ 同境内案内図(清荒神清澄寺山門) 駐車場から山門に至る参道には両サイドに露店がびっしり立ち並んでいて賑っていましたから、この日は祭礼の日に当たっていたようだ。 山門脇に駐輪し、徒歩で境内を廻る。 清荒神清澄寺( きよしこうじんせいちょうじ)は寛平8年(896年)宇多天皇の勅願寺として創建された寺。定円(じょうえん)作の大日如来像を本尊仏とし、叡山の高僧静観(じょうかん)僧正を開山の祖として迎え、東寺の益信(やくしん)僧都を導師として開創された。益信がこの地に荒神を祀り、仏法守護、三宝加護を祈った処、社前にあった榊の木に荒神の御影が現出したという。この榊は拝殿の奥にあり、「荒神影向(ようごう)の榊」と呼ばれている。この霊験の報告を受けて感激した宇多天皇から「日本第一清荒神」の称号が下賜された。 寿永2年(1183年)の源平合戦によって堂宇は焼失するが、源頼朝により再興される。しかし、織田信長に反旗を翻した荒木村重と織田方の戦(伊丹の合戦)により再び炎上。この時西の谷(現在地)にあった荒神社のみは炎上せずに残る。 江戸末期に浄界和上による諸堂の再建がなされ、昭和22年に真言三宝宗を新しく開き、荒神信仰の総本山清荒神清澄寺として現在に至っている。(詳しいことは上のホームページをご参照ください。)(三宝荒神社) 山門を入って、正面が本堂、左手奥に三宝荒神社の拝殿、諸堂がある。(同上) さて、荒神とは何か。 古代の人は、神には人に福をもたらす温和な和魂(にぎみたま)と害悪をもたらす荒々しい荒魂(あらみたま)の両面があると考えた。荒魂として山から里に降って来る神に対して畏敬を以てこれを祀り、和魂となっておとなしく山に帰って戴く、農耕儀礼の原点はこれであったと思われる。 このような中で、仏教の伝来と共に、ヒンドゥー教の悪神(夜叉、羅刹など)が仏教に帰依して守護神・護法善神となるという風習・考え方が入って来る。この考え方と荒魂とが結びついて「荒神」というものが生まれたのであろう。 荒神には屋内に祀られる三宝荒神と屋外に祀られる地荒神の二系統があるとされる。屋内の荒神は火の神や竈の神の荒神信仰と仏教・修験道の三宝荒神とが習合したものである。 かくて、拝殿脇には神変大菩薩として修験道の開祖、役小角の像も祀られているのでありましょう。(役小角像・神変大菩薩)(清荒神清澄寺本堂) 本堂には中央に本尊の大日如来、左に不動明王、右に弘法大師が祀られている。(清荒神清澄寺の文化財) 山門に戻り、自転車で参道を下る。途中でイカ焼きの屋台の青年から「兄ちゃん、兄ちゃん」と声を掛けられる。来る途中で彼から何やら声を掛けられ、「何?」と返事をしたら「イカ焼きを食べていかないか。」というものであった。咄嗟のことであったので「また、帰りに・・」と答えたものだから、彼は待っていたようで、再度呼び止められたもの。苦笑しつつ「やっぱり、遠慮しとくわ」と答えて通り過ぎる。 参道を下り阪急宝塚線の線路脇の道まで下ってから、売布神社駅の前で北に上ると大きな池があり、それを左に取ると売布神社への参道である。入口には石標があり、「日本第一清荒神霊社」という宇多天皇から下賜されたという清荒神の称号が刻されていました。これでは紛らわしいということか、脇には金属製の「売布神社」という標識が設置されていました。(売布神社参道入り口の道標) 売布( めふ)神社は推古天皇18年(605年)に創建されたという古社であるが、そろそろ字数制限にかかりそうなので、詳細は下記<参考>をご参照戴くこととしましょう(笑)。 <参考>売布神社・Wikipedia(売布神社)(同上) 鳥居の処で一人、拝殿の前で二人の若い女性に出会いましたが、女性に人気のある神社なんですな。 この神社の祭神は下照姫。卑弥呼を原像に記紀では、天上界ではアマテラス(天照)、下界ではシタテル(下照)ヒメと記載したという説のあることなども関係していて、卑弥呼関連で女性に人気があるのだろうか、などと勝手な想像をめぐらす。(売布神社の由来)(拝殿) (売布神社社号標石) 本日はここまでとします。(つづく)
2014.02.04
コメント(2)
-

なにとなく心さやぎて
今日は節分、明日は立春。 いよよ春にしなるにやあらむ・・ですが、昨日までの暖かさは去って、今週は再び厳しい寒さが戻って来るとか。どちら様もおん身お大切に。 良寛さんの歌にこんなのがあります。なにとなく 心さやぎて いねられず あしたは春の はじめとおもへば (良寛) この歌は立春の前日の歌ですから、今日の歌に相応しい歌でもあります。昔の人の感覚では立春が1年の始まりであったのですから、今日の我々の大晦日の感覚に近いと言うべきか。 さて、立春の前日は節分。冬と春との境目の日。「鬼は外~」の豆まき、年齢の数だけの豆を喰う。恵方巻にかぶりつく。人それぞれに今日の日を過ごされるのであるでしょうが、満年齢1296歳のヤカモチにとっての難関は何と言っても豆を喰うことであります。まあ、昔は数え年で年齢を数えていましたから、1297個も豆を食べなくてはならないということになる。 鬼(邪気)を払い、火で炒った豆は福豆となる。それを食することは、その豆の「福」を身内に取り込み、この1年も健康で幸せにありますようにと願う行為、儀式ということになる。であれば、胡麻ではやはり誤魔化せないのでありますな(笑)。 大豆には悪玉コレステロールを低下させる効用が顕著にあるとのことなので、もう長生きを願う年齢にはあらねど、生きている限りは健康にてありたきものと、ヤカモチも人並みにやはり大豆を食うのであります。 さて、昨日(2月2日)は月例の墓参をして参りましたが、その折に通る寺の門前に掲示されていた言葉は次のようなもの。(今日の言葉) 鬼は内にぞある。或いは、鬼を作り出すのはわが心なりけり、でありますかな。鬼と神は裏腹の関係。内なる鬼を神にぞ変へむと豆をまくべし、豆を食ふべし、なのであります。(ロウバイ)朝の雨 止みぬる道は 蝋梅の かほりほのかに 流れ来るかも (偐家持) 上の写真は2日の墓参の道の辺に咲いていたものですが、友人・蝶麻呂氏との1月31日の銀輪散歩で立ち寄った緑ヶ丘公園の梅林でも咲き匂っていました。梅は春告げの花と称されるが、今や蝋梅がひと足早くそれを告げる花となっているようで、その所為かあらぬか、近頃の梅は春を告げられてから咲くという、春告げられ花、になり下がってもいるような(笑)。 明後日から、白内障の手術のため暫し入院します。通常、白内障の手術は通院のみで済ませるようだが、小生の病院は入院して貰うことになっていると言う。是非に及ばずで、止むなく5日から12日まで入院です。銀輪散歩もお休みとなりますが、個室なのでパソコンを持ち込み、掲載遅れとなっている宝塚・伊丹銀輪散歩の道中記でもアップ致しますれば、ブログの方は開店営業中であります(笑)。
2014.02.03
コメント(18)
-

第14回和郎女作品展
第14回和郎女作品展 昨日(2月1日)の若草読書会で和郎女さんがお持ち下さった恒例の干支の押し絵を中心に、本日は久し振りに和郎女作品展を開催いたします。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 先ず始めに先の智麻呂絵画展(第134回)で智麻呂さんが絵にされた馬の押し絵からご紹介することと致します。 午年の今年の年明けに相応しい、見事な出来栄えの白馬の押し絵であります。(馬・黒)水鳥の 鴨羽(かもは)の色の 青馬(あをうま)を 今日見る人は かぎりなしといふ (大伴家持 万葉集巻20-4429)(水鳥の鴨の羽の色の青馬を今日、白馬の節会の日に見る人は永遠の生命を得るという。) 青馬というのは白馬のこと。白馬を青とはこれ如何に、であるが、陰陽五行説では、青は季節では春、方角では東、時刻では朝。青は生命力溢れる盛んな色として尊ばれた。白は清浄で貴い色であったから、両者はイメージとして重なるものがあったのであろう。それで白馬(神馬は通常は白馬)を青馬とも呼んだのであろう。 緑色の葉を青葉と言うのも同じようなことであろう。青には「盛んな」「生命力溢れた」という意味があるのだ。青年という呼び方もその類である。 この歌は1月7日の白馬の節会の宴に備えて大伴家持が作って置いた歌であったのだが、当日仁王会の仏事が催されることとなり、宴は6日に繰り上げて行われることとなった。それで、この歌は奏上せず没となり、その6日に詠んだ歌が次の歌。うちなびく 春ともしるく うぐひすは 植木の木間(こま)を 鳴き渡らなむ (大伴家持 万葉集巻20-4430)(うらうらと霞こめる春だとも、はっきりわかるように、鴬が植木の木の間を鳴き渡ってくれたらなあ。) 話が万葉にそれてしまいました。以下の白馬は1日に和郎女さんがお持ち下さったものです。同じデザインのものは撮影を省略していますので、実際の作品点数はこの倍以上はあったかと。 では、ごゆるりと白馬をご覧下さいませ。(馬・赤1)(馬・赤2)(馬・桜)(馬・赤と青)馬並(な)めて いざうち行かな 渋渓(しぶたに)の 清き磯廻(いそみ)に 寄する波見に (大伴家持 万葉集巻17-3954)(馬・黒い鞍)(馬・梅)(馬・金の鞍)(馬・梅2) 上の白馬は現在わが家に滞在いたして居ります(笑)。(馬・短冊)(ストラップ) 以下は、昨年の夏か秋に撮影したものであります。作品が4点と少なかったので、もう少し作品数が増えてからアップを、と思っているうちに年があらたまってしまいました。いささか季節外れとなりますが、今回遅ればせながら出展させて戴きます。(釣れたよ)(色には出でじ朝顔の花) 上は桔梗。万葉では朝顔です。この花と来ればやはりこの歌を書きたくなるのでありますな。顔には出さぬ恋。万葉の恋とはそういうものなのであります。恋転(まろ)び 恋ひは死ぬとも いちしろく 色には出でじ 朝顔の花 (万葉集巻10-2274)(秋の香ぞよし) もみじ、まつたけ、秋の香ぞよし、であります。高松の この峯も狭(せ)に 笠立てて 盈(み)ち盛りたる 秋の香(か)のよさ (万葉集巻10-2233)(うちわ) この団扇も我が家にご滞在であります。 今の時期に出すと、夏炉冬扇、万葉調に言えば「ときじくの」でありますが、なかなかに可愛いミニチュアの団扇なのであります。うちはなれば 冬には出さじ 朝顔の 花とし思へど 今日のみ出でよ (偐家持) どちらさまも最後までご覧下さり有難うございました。
2014.02.02
コメント(8)
-

若草読書会新年会2014
本日は本来なら、昨日の日記の続きで蝶麻呂君との銀輪散歩の道中記をアップしなくてはならないのですが、若草読書会の新年会がありましたので、そちらの方の記事を先にアップします。 午前11時半開始で智麻呂邸の若草ホールに集合。出席者は、智麻呂・恒郎女さんご夫妻、凡鬼・景郎女さんご夫妻、小万知さん、祥麻呂さん、和郎女さん、りち女さん、偐山頭火さんと小生偐家持の10名。謙麻呂さん、和麻呂さん、槇麻呂さん、香代女さんらの常連組は今回他用などの不都合があり欠席でありました。 新年はいつの頃よりか偐家持による万葉関連の講話ということが恒例となっていて、今年も1時間ばかり、万葉関連のお話。 今年は、山上憶良の志賀の白水郎の荒雄の歌を鑑賞することと致しました。山上憶良が筑前国守であった頃に家持の父大伴旅人が太宰府の帥(長官)として赴任して来ますので、物心ついたばかりの少年家持も山上憶良と面識を得た可能性が高いのではないかと思われます。家持は和歌の道を「山柿の門」と呼びました。柿は、柿本人麻呂。山は、山部赤人とも山上憶良とも言われますが、家持にとっては山部赤人よりも山上憶良の方が身近な存在、山上憶良説の方が自然なことで妥当かも知れません。 山上憶良さんのことは下記の参考をご参照戴くこととして、憶良さんが作ったとも、憶良さんが既に存在した民謡やその妻子が作った歌を採集したとも言われる、志賀荒雄の歌10首が今回のテーマでした。 小生の話は取るに足りないものであるので、此処では省略し、その歌だけご紹介して置きます。 <参考>山上憶良・Wikipedia 福岡県志賀島の漁師荒雄の許にやって来た宗像郡の津麻呂が、大宰府から対馬へ食糧などを運ぶ船の船頭をやれと命令されたのだが、自分はもう年老いて自信がない、代りに行って貰えないか、と言う。これを引き受けて出掛けて行った荒雄が遭難してしまう。それを嘆き悲しんだ妻子が詠んだ歌という形で10首は構成されている。大君の遣(つかは)さなくにさかしらに行きし荒雄(あらを)ら沖に袖振る (巻16-3860)(大君が命じたわけでもないのに、自ら買って出て、出かけていった荒雄が、沖で袖をふっている。) 荒雄らを来(こ)むか来(こ)じかと飯(いひ)盛りて門に出で立ち待てど来(き)まさず (同3861)(荒雄は帰って来るのだろうか、来ないのだろうかと、ご飯を盛り、門に出て待っているが、帰っておいでになりません。) 志賀(しか)の山いたくな伐(き)りそ荒雄らが所縁(よすか)の山と見つつ偲はむ (同3862)(志賀の山の木を、ひどくは伐らないで下さいな。荒雄ゆかりの山として、見つつ偲ぼうと思うから。) 荒雄らが行きにし日より志賀の海人(あま)の大浦(おほうら)田沼(たぬ)はさぶしくもあるか (同3863)(荒雄が行ってしまった日から、志賀の漁師(海人)の大浦田沼はさびしいことだよ。) 官(つかさ)こそさしてもやらめさかしらに行きし荒雄ら波に袖振る (同3864)(お役所の命令で行ったのならまだしも、自ら進んで行った荒雄が波間に袖を振っているよ。) 荒雄らは妻子(めこ)の産業(なり)をば思はずろ年の八歳(やとせ)を待てど来(き)まさず(同3865)(荒雄は、妻子の暮らしのことを思わないのか。長い間待っているが帰っていらっしゃらない。) 沖つ鳥鴨とふ船の帰り来(こ)ば也良(やら)の崎守(さきもり)早く告げこそ (同3866)(沖の鳥の鴨、その鴨という名の船が帰って来たなら、也良の崎の崎守はすぐに知らせておくれ。) 沖つ鳥鴨とふ船は也良(やら)の崎廻(た)みて漕ぎ来(く)と 聞(きこ)え来(こ)ぬかも (同3867)(沖の鳥の鴨、その鴨という名の船が、也良の崎を廻って漕いで来る、という知らせが来ないものか。) 沖行くや赤ら小船(をぶね)に裏(つと)遣(や)らばけだし人見て解きあけ見むかも (同3868)(沖を行く赤い小船に包みをことづけたら、もしやあの人が包みを開いて見はしないだろうか。) 大船に小船(をぶね)引き副(そ)へ潜(かづ)くとも志賀(しか)の荒雄に潜(かづ)きあはめやも (同3869)(大船に小船を引き添えて、海に潜って捜しても、志賀の荒雄に海中で逢うことができようか、いやできはしない。) 新年会の恒例はこの他に、昼食後の歌会と和郎女さんがお持ち下さった干支の押し絵の抽選分配、というのがあるが、歌については「若草歌壇」として追って河内温泉大学図書館にて公開し、押し絵の方は、後日「和郎女作品展」として当ブログでご紹介申し上げますので、此処では省略です。 今回は、景郎女さんの折り紙による「馬」の制作の指導があり、女性陣は熱心に作って居られましたが男性陣は呑んで食ってだべるばかりで折り紙に挑戦する者はありませんでした。 勿論、ヤカモチもその内の一人にて、眺めているだけでありましたが、景郎女さんの作品を写真に撮らせて戴きましたので、ご紹介して置きます。(折り紙の馬 景郎女作) そして、小万知さんがご用意下さったようだが、ヤカモチの1296歳の誕生日祝いということで、皆さんから花を頂戴いたしました。 紫の花はハーデンベルギアという耳慣れぬ名前の花。白いのはクレマチス。この時期、新年会に接近して誕生日を迎えるヤカモチの利点・利得と言うべきか、有難く頂戴仕りました(笑)。心より感謝申し上げます。 小万知さんは「ヤカモチさんには『和の花』と思ったがこの時期そういうのが無くて」と仰っていましたが、きっと歌に詠みにくい名の花にしてヤカモチを困らせてやろうとの「やさしい思いやり」もあったのではないか、ということに気が付きました。1296歳のヤカモチも、この花の名を万葉調の歌に折り込むことは至難のワザにて、諦めました(笑)。花の名に 困りにけりな いたづらか 歌も空振り ながめすぎたり (小野のコマネチ)(ハーデンベルギア)(追記) ネットで調べるとコマチフジという別名のあることが分かりました。小万知さんが選んで下さった花に相応しい名。これなら歌にもなりますかな。こまちふじ みなもにうつす かげきよみ ふるやこのみの うちもすむなれ (小町藤 水面に映す 影清み 経るやこの身の 内も澄むなれ<偐家持>)
2014.02.01
コメント(8)
全27件 (27件中 1-27件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンでパートナーと相談…
- (2025-11-13 20:30:13)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 【隠蔽】県職員への不適切行為を兵庫…
- (2025-11-14 17:19:56)
-
-
-

- みんなのレビュー
- 茅野市の…
- (2025-11-13 18:39:04)
-







