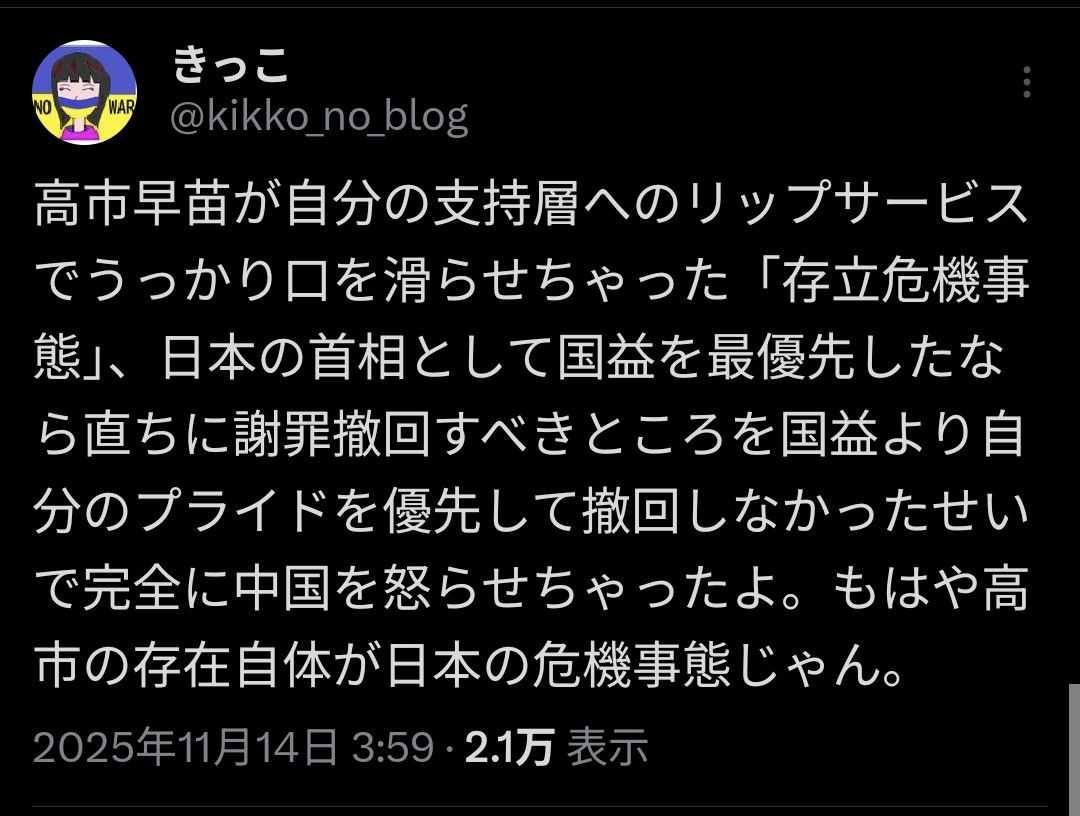2016年04月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

ブログ開設9周年
本日4月29日は詩人中原中也の誕生日でありますが、当ブログの誕生日でもあります。当ブログは2007年4月29日生まれです。 中也は1907年(明治40年)生まれですから、当ブログ開設は中也生誕100年のその日に誕生したことになります。これは意識してそうしたのではなく、後になって気が付いた偶然の一致であったのですが、愉快な発見でありました。 まあ、そんな訳で、本日(正確には本日の12時51分49秒)でブログ開設丸9年となり、今日から10年目に突入することとなります。 丸9年というのは日数では3288日(本日を含めると3289日)ということになります。この間にアップした記事は、今日の分を含み1959件となり、記事率は59.6%ということになります。最近は1日に複数件の記事を書くことはありませんが、開設当初は、短い記事を複数書くということもありましたので、記事をアップした日数の率ということになると、57.2%に下がります。(ブログ管理ページにはこの率が日記記入率として表示されていて、それを知ることが出来るのです。)それでも2日に1回よりも多い計算でありますから、9年間これを続けて来たというのは、閑人ヤカモチとは言え、大したものである。 因みに、年別の記事件数は以下の通りです。 2007年 128件(4月29日~12月・247日間) 2008年 193件 2009年 216件 2010年 203件 2011年 222件 2012年 233件 2013年 251件 2014年 241件 2015年 210件 2016年 60件(4月29日まで・120日間) ※1.上表では、2007年4月29日と本日2016年4月29日とを、つまり期間 の初日と末日とを両方数えていますので、正確には9年と1日になり ます。 2.年別記事件数の記録などとは几帳面なこととの感想を持たれるお方も あるようなので、付言して置きますと、ブログの「新着記事一覧」を クリックして戴き、表示されたページの上段の「月別記事」をクリッ クすると、各年別に各月の記事件数が表示されているので、それを集 計すればよいだけのことなのであります。 ご訪問下さる方々、コメント下さる方々を励みに今後も続けて参る所存でありますので、引き続きご厚誼のほど宜しくお願い申し上げます。 さて、上記だけで記事を終わっては、何とも素っ気ないこととなりますれば、銀輪散歩の道すがらに目にした花などをご紹介して、記事に些かの「いろどり」を添えさせて戴きます。(芽吹き) これは梅だろう。花が散ってしまうと新芽では何の木とも分からないのであるが、実が生っているので、梅だろうという次第。(西洋シャクナゲ) 石楠花の花。シャクナゲにも西洋シャクナゲと日本シャクナゲがあり、その区別は葉の裏を見ればすぐに分かるらしい。日本シャクナゲの葉は裏に毛があり、西洋シャクナゲのそれには毛がなくつるつるしているとのこと。TVでそう言ってました。 (同上)(オニタビラコ) これは、オニタビラコ(だと思う)。 もっとも、コオニタビラコ(タビラコ)とヤブタビラコというのもあるから、それかも知れない。オニタビラコはコオニタビラコよりも大型で花を沢山付けるとのことであり、これは小型で花も少数であるから、オニではなくコオニの方かも知れないという訳である。 大型だ小型だと言っても、育ち始めはみんな小型なのだから、小型のオニタビラコだってある筈で、もうちょっと明確な区別を示して貰わないと何とも判断しかねるのである。しかし、斜め読みのヤカモチ、詳細にわたる資料の説明文などは「面倒」と飛ばし読みしてしまうから、結局同じことではあるのだけれど(笑)。 (同上)(カエデの新芽) カエデの新芽も最初は??であったが、周辺のものなどをよく観察するとカエデらしくなった葉のものもあって、ようやくそれと知った次第。 しかし、次の新芽は全く手掛かりがなく何とも判断できないのでありました。 1ヶ月ほどして同じ場所を通りかかってみると、何とハナミズキの花が咲いていました。蝶がとまっているみたいな白い花が沢山。(ハナミズキの芽) 蝶は蛹からかえる。植物の花や葉はこの芽の殻を破って生えて来る。植物の芽や花芽は昆虫の蛹のようなものであるのだ、ということを実感した次第。昆虫は、きっと植物の芽を見て、蛹という形態を思い付いたに違いない(笑)。(同上) 以上は全てかなり以前、1ヶ月以上も前の写真である。いささか地味過ぎる写真が続きましたので、花らしい写真も掲載して置きましょう。(アネモネ)(同上) 銀輪で目にするのは花だけではない。花には蝶ですな。 勿論、蝶も目にする。 しかし、チョウと言ってもチョウでない「チョウ」も目にする。 鳥である。(コサギとアオサギ) ちょっと面白い取り合わせであったので撮ってみました。 何だか親子みたいな「取り合わせ」の「鳥合わせ」でありました。 (コサギ) (アオサギ) ということで、「トリあえず」偐万葉田舎家持歌集も満9歳になったという訳であります。 ハナはだ僭越でありますが、自分で自分のブログの誕生日のお祝と宣伝をさせて戴いたのでありました。 「オレオレ鷺」ではなく、「ヨレヨレぶろぐ」の10年目が今日から始まります。「オレオレ家持」と「ヨレヨレぶろぐ」の二人三脚。この後いかなことに相成りますやら。 <参考>ブログの歩み関連の過去記事一覧はコチラ。<追記> 当記事の冒頭の「中原中也」から、彼が結婚式を挙げたのが湯田温泉の西村屋という旅館であったこと、一方、西村屋の先代主人と種田山頭火とは親交があり、山頭火はしばしば西村屋に訪ねて来ては酒や料理を馳走になり、同旅館の湯に浸かったりしていたなどと山頭火所縁の旅館であったこと、とかで、山頭火の名前も飛び出すという、何やら「尻取り」みたいなコメントを、友人の偐山頭火氏から頂戴しました。(下記コメント参照) 更に、追いかけて、写真が4枚メールで送られて参りましたので、ご紹介して置きます。うち、2枚は湯田温泉の山頭火通りにあるマンホールの写真で、これは以前に送って戴いて、マンホール関係のブログ記事に掲載させて戴いているので、その記事をご参照願うこととし、重ねての掲載はしないことといたしました。 <参考>銀輪万葉・マンホール 2013.10.21.(西村屋 写真提供:偐山頭火氏)(風来の湯・説明板 写真提供:同上)<追記訂正2021年4月16日>上記各年別記事件数に一部誤りがあり訂正しました。
2016.04.29
コメント(14)
-

岬麻呂旅便り187・188・姫路、神戸そして東北縦断桜めぐり
岬麻呂氏からの旅便り188が本日到着、前便187と合わせ2件となりましたので、本日は合併号でご紹介申し上げます。この処、合併号や合併編というのが頻出の当ブログかな、であります。1. 旅便り187・姫路・神戸 岬麻呂氏の山梨ご在住のご友人が退職されて関西方面にご夫婦でご旅行。それではとそのご友人ご夫婦を、岬麻呂氏が姫路・神戸にご案内されたというもので、同氏ご自身の旅行とは違っていますが、写真でご紹介する景色は、旅の趣旨が如何なるものであれ、変わるものでもありませぬから、これも亦、岬麻呂旅便り、という訳であります。(姫路城)(同上)(同上・三国堀と花筏) 姫路は、山部赤人所縁の場所を訪ねての銀輪散歩で、今年の1月に小生は2回走っています。しかし、姫路城には、近くまで行きはすれど入場(入城と言うべきか)せずでありました。 <参考>山部赤人神社と赤人讃歌 2016.1.31.(神戸異人館・風見鶏の家)(同上・うろこの家) 新幹線で来られるご友人とは姫路駅で落ち合われて、姫路城を見学、その後、神戸異人館などをご案内されたようですが、詳しくは下の「旅報告187」をご覧下さい。 写真をクリックすると大きい写真に切り替わります。 (旅報告187) (旅報告188)2. 旅便り188・東北縦断桜めぐり 東北へと桜を追いかけての旅は、この時期の同氏の旅の定番のようなものですが、今年も、仙台から会津、喜多方、米沢、最上、横手、角館、盛岡、北上、そして仙台と、ぐるり937kmのロングドライブにて桜巡りをされたようであります。西行に あらぬ北行 岬麻呂 桜追ひ行く みちのくの旅 (輪行法師)角館 桜の盛り 見し日より 心は身にも 添はずや君も (輪行法師)(本歌)吉野山 梢の花を 見し日より 心は身にも 添はず成にき (西行 山歌集66) 旅の詳細は、上掲の「旅報告188」による岬麻呂氏ご自身のご説明に委ねることとし、我々は、みちのくの桜をゆるりと拝見仕ろうではありませぬか。(岳温泉・桜坂)(岳温泉・鏡が池)(川桁・観音寺川)(飯豊連峰・会津北西部)(米沢城址・松ヶ岬・上杉神社)(白鷹・十二薬師堂の十二の桜)(赤湯・烏帽子神社の大鳥居)(南陽市・赤湯・烏帽子神社のおとぎ桜ーエドヒガン) おとぎ桜と言うだけに、花咲か爺も居りますな。(おしら様<白山神社>の枝垂れ桜)(横手公園<横手城址>)桜花 今ぞ盛りと 行く君の みちのく春は 見らくしよしも (偐家持)(角館・桧木内川堤) さすがに角館。見事な桜並木であります。かくまでに 咲けるか桜 角館 桧木内川 花の長堤 (偐家持) 武家屋敷のこの一角は、定番の撮影スポットでしょうか。(角館・武家屋敷)(北上展勝地) 東北縦断の桜の風景、存分に堪能させて戴きました。銀輪散歩ではとても真似の出来ない広域・長距離移動であります。 <参考>岬麻呂旅便り関連記事一覧はコチラから
2016.04.26
コメント(8)
-

第175回智麻呂絵画展
第175回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。今回は13点と作品数も多く、力作揃いであります。どうぞ、ごゆるりとご覧下さいませ。 また、今回で、第1回展から、コツコツと描き続けて来られた智麻呂画伯の絵の数も、遂に1600点を超えることとなりました。 1000点突破は2013年2月28日開催の第115回展。 1500点突破が2015年9月19日開催の第165回展。 そして今回が1600点突破。1612点に。 昨年9月からの約7ヶ月で112点を描かれたことになります。 2日に1作品のペースでしょうか。凄いことです。ヤカモチのブログ記事記入率も50%強ですから、それとほぼ同じペースで作品を仕上げて居られることになります。ブログ記事は適当にちょいちょいというものですから、比べるのも失礼でありますが、長期にわたってのその衰えぬ創作意欲には脱帽、ヤカモチも頑張らなければ、と思うこと頻りであります。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 前回展で申し上げました通り、今回の冒頭の作品が1600点目の絵画ということになり、それをどの絵にするかは智麻呂さんご自身にお決め戴くこととして居りましたが、果たして、智麻呂さんがお決めになった絵は、これであります。(白いカタクリの花) 上の白いカタクリの花は、ヤカモチ館長のブログ友のビッグジョンさんが、福井県の文殊山に行かれた折に、出会われて撮影、同氏のブログ記事に写真を掲載されたものです。ヤカモチ館長が、この花は智麻呂さんの絵心に響くものがあるに違いないと、大判の写真に打ち出して印刷、お届けした処、このように素敵な絵になっていました。元の写真はこれです。 次の椿は当ブログ記事に掲載の写真から絵にされました。(椿)(桜) この桜は散歩の途上で写生されたもの。ヤマザクラでしょうか。(花桃) この桃の花は、デイサービス施設の「アンデスのトマト」で戴いたもの。省略した言い方だと「トマトのモモ」ということになって、何やら訳の分からぬ物言いになってしまうのでありますな。 以下の3点は、もう一つのデイサービス施設での、智麻呂さんのお知り合いと言うか、お友達と言うか、智麻呂絵画を愛して下さっているお方、友〇さんから頂戴した花を絵にされたものであります。(アイリス・紫)(アイリス・白)(グラジオラスのようにも見えるが・・) 花の様子から、黄色のそれはグラジオラスかとも思いましたが、白い花や真ん中のそれは、何とも分かりませぬ。ヤカモチ館長の乏しい花の知識では手が負えません。何の花かは不明ということにして置きます。※上の花はフリージアだそうです。下記の小万知さんのコメント参照。(山吹) この山吹は、上の花桃と同じく、トマトで戴いた花です。 つまり、トマトのヤマブキであります。(ハナミズキ) 上のハナミズキと下のシランは、散歩の折の写生です。 桜からハナミズキへ、確実に季節が移ろって行くのが、この絵画展からも見て取れます。早や季節は、見上げればハナミズキ、足元を見やれば風に靡くシラン、なのであります。(シラン) 以下の3点は、若草読書会のメンバー関連のものです。(花菖蒲) 花菖蒲は小万知写真集からの絵です。(ブルーベリーの芽) 上は、偐山頭火さんが持って来られた写真を絵にされました。 偐山頭火さんのご自宅の庭にあるという、余り「実のならない」(おっと、失礼<笑>)ブルーベリーの木の「芽吹き」を撮影されたものだろうと存じます。 しかしながら、木の芽なんぞというものは、ブルーベリーだろうが何だろうが、そう大差もなく、区別がつかない。そういう事情もあってか、智麻呂さんは背景をブルーにされました。木の芽では 何とも人は わかるまじ ブルーベリーの ならぬその木の (芽描き家持)(紫の小花の名前不詳の花) 次は、先般の若草読書会のお花見の折に、香代女さんがお持ち下さった鉢植えの花。今日、智麻呂邸で見たそれは、既に花が全て萎んでしまっていて、葉だけの状態。何の花とも分からない。絵を見ても思い付く名は浮かばない。 然らばと香代女さんにメールしたら、彼女も花の名はしっかりと確かめないまま、スミレに似た可愛い花であったので買い求めたもので、名前は知らないとのこと。万事休す。一応ネットでも探してみましたが、それらしき花は見つからず、「名前不詳」として置きます。そのうちに、どなたかが教えて下さることを期待して・・(笑)。※上の花はベルフラワーだそうです。下記の小万知さんのコメント参照。 以上です。本日は、偐家持美術館の不手際にて、おもてなしのお菓子などの絵が用意できませんでした。お詫び申し上げます。花より団子というお方は、次回智麻呂絵画展にご期待下さいませ(笑)。 本日もご来場、ご覧下さり、有難うございました。
2016.04.25
コメント(4)
-

偐万葉・あすかのそら篇(その3)
偐万葉・あすかのそら篇(その3) 本日は、偐万葉シリーズ第256弾、あすかのそら篇(その3)といたします。 あすかのそらさんは偐万葉では「あすかのいらつめ(明日香郎女)」と呼ばせて戴いて居りますが、時に戯れて、「あすかのそら豆」とお呼びすることもあって、「そら豆」については微妙な反応。「何とかならないか」というクレームも頂戴いたして居りますが、当面は何ともならないのであります(笑)。 <参考>過去の偐万葉・あすかのそら篇はコチラから。 あすかのそら氏のブログはコチラから。 偐家持が明日香郎女に贈りて詠める歌21首くやしかも 楚樹(しもと)おしなべ えたる実の オニグルミには あらなくあれば (鬼丸) (注)楚樹=行く手を邪魔する木々。オニグルミ とらむと来(こ)しに 似つきたる 実のみ摘みてぞ 帰り来()しかも (胡桃の空似)オニグルミ 欲しとしならば 山ならぬ 川の辺(へ)にこそ 行かせ吾妹子 (この実何の実?)(からたちの 雨にし濡れて 実の二つ ならびてあるも うれしとわが行く (昨日郎女(きそのいらつめ))枳殻邸 わが行く道の 石垣に はまれる石臼 うふふと笑みぬ (昨日郎女) (枳殻邸のカラタチ) (枳殻邸の石垣)鴨川の つきるあたりや 岩屋橋 傘もてわたろ 雨ふりくれば (かものあまぞら)すだますむ くもがはたかも ぐあんにんの はちまきぬらし あきのあめふる(注)すだま=魑魅魍魎、物の怪 くもがはた=雲ヶ畑。京都市北区、鴨川源流域の地名。 ぐあんにん=願人。願人坊主。江戸期、裸・はちまき姿で寺社への代参詣で を引き受けると称して家々の門口で鞍馬寺などの札を売り歩い たり、大道芸を行ったりした。志明院 杉の木(こ)の暗(くれ) ほそ道は 驟雨またよし をみながふたり (岩屋橋) (志明院へ)高取の 城はまだかと 猿石に 妹とふらむか もみぢ葉の道高取は 行くも帰るも 七曲 あすかのそらは ひとりぞ来(こ)しか (あさってのそら) (猿石) (高取城趾へ)枯葉ふむ 音をともとし ただひとり 恋ひぞわが来(こ)し 高取の城石垣や また石垣の 城跡に 吹き来(く)秋風 音のかそけき日は西に 傾くならし 二の丸に 落とす木の影 はやもや長き (高取城大手門跡) (高取城二の丸跡)春浅き 熊野に立ちて 妹のいふ 何(な)そ書きたるや 城の石碑(いしぶみ) (与太野晶子) (本歌)高く立ち 秋の熊野の 海を見て 誰(た)そ涙すや 城のゆふべに (与謝野鉄幹) (川上不白顕彰碑) (与謝野鉄幹歌碑)みやこべに あそぶあすかの そらの妹 なれも来(こ)しかや 梨の木神社 (本歌)ゆのはらに あそぶあしたづ こととはむ なれこそしらめ ちよのいにしへ (三条実美) (梨木神社)富山なる 文字にさそはれ わが来れば あすかのそらに 桃の花咲く (大伴家持とその妻・坂上大嬢の像)松山の 城の石垣 百重なす 心は思)へど 直)には見ざる (石垣本家持)松山の 城の石垣 百重なし 吾が恋ひ来れど 只事ならじ (あすかのそら豆) (本歌)み熊野の 浦の浜木綿(はまゆふ) 百重なす 心は思(も)へど 直(ただ)に逢はぬかも (柿本人麻呂 万葉集巻4-496) (備中松山城) (同・石垣)松山の 渓を埋むる あさ霧も 昇りやかねつ 城の石垣 (与太野石棺) (本歌)松山の 渓を埋(うづ)むる あさ霧に わが立つ城の 四方(よも)しろくなる (与謝野鉄幹) (与謝野鉄幹歌碑)吉備路なるに 道に迷ひて 粟食ふや あすかのそら豆 そらないでと言ひ (黍野粟麻呂) (吉備路サイクリング)意を決めて あすかのそらねに かへるとも よにそら豆の 席は渡さじ (清少納豆) (本歌)夜をこめて 鳥のそら音は はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言 後拾遺集940 小倉百人一首62)<注>掲載の写真は全てあすかのそら氏のブログからの転載です。
2016.04.22
コメント(8)
-

高校同期会
今日は高校の同期会でありました。 会場は大阪駅ビルにある、ホテルグランヴィア大阪20階鳳凰の間。 午後2時開会。(受付前は既に多くの同期生で混雑)(鳳凰の間入口) 開会の辞。来賓の先生、城〇先生、竹〇先生からのご挨拶。乾杯。という段取りの処、司会のミスで城〇先生のスピーチの後で開会の辞というハプニングも。開会の辞は児〇君。一学年のクラス数は11であったので、担任の先生も11名居られたことになるが、ご存命は7組担任であったかの城〇先生のみで、他の先生方は全て既に物故者となって居られる。来賓の竹〇先生は日本史の先生で我々の学年の担任はお持ちでなかったが、我々が入学した年に大学を卒業、八尾高校に赴任して来られたとのことで、同先生曰く「諸君とは八尾高校の同期のようなもの」ということで、ご出席戴けたよう。(城〇先生のご挨拶) さて、同期は全部で550名前後いたかと思うが、今日の出席者は100余名で盛会。東京など遠方からの参加者も多く、遠路大分から参加の女性も居られたよう。我がクラスは3組であるが、3組出席者は4名と全クラス中最少の人数でありました。20名近い出席のクラスもあると言うのに、である。そんな中でも同じクラスの岩〇君は今回が初出席で卒業以来の再会にて、懐かしさも一入で、嬉しいことでした。 我がテーブルは2組と3組との混成メンバー。クラス幹事の今〇君と岩〇君、平〇君、小生が3組、2組は、児〇君、山〇君、増〇君、東〇君、井〇君、横〇さんの6名。 一年の時は通常のクラス編成であったが、二年、三年は、進路に応じてレッスンクラスというのが編成され、週1回のホームルームの時間だけ、ホームルームクラスで集まり、それ以外は、つまり通常の授業はそのレッスンクラスで受けることとなっていた。レッスンクラスは文科系進学希望、理工系進学希望、就職希望に分かれて編成される。小生は法科希望で文科系のレッスンクラスで、それは2組と3組の文科系進学希望者で構成されていた。従って、2組の児〇君や山〇君はホームルームクラスは別であったが、普段の授業は同じレッスンクラスで受けていたので、クラスメートみたいなものである。また、理系の岩〇君、東〇君は一年生の時には同じクラスであったから、顔馴染みと言うか、よく覚えている。 3年になると、志望校も固まり、受験科目中心の勉強になり、受験に関係のない科目の授業の時は席を後ろに移動して、受験科目の問題集を解いていたりしたものである。それに熱中し過ぎていると、先生が近くに来ているのに気が付かないというようなことがあって、時々見つかって叱られたりというようなこともあった。 山〇君が小生の隣に座っていたこともあったらしく、小生が授業とは関係ない科目の勉強をしているのを見咎めた先生が、隣の山〇君も同じことをしていると誤解したことがあったようで、「一緒に叱られたことがある、とんだとばっちりであった。」というようなことを今日彼から聞いた。小生はそのことは記憶にない。しかし、迷惑を掛けたのであるから、その帰責事由のある小生が、覚えていないと言うのはいささか穏当を欠く。「ああ、そうだったね。」と相槌を打つしかないのでありました。 まあ、叱られることについては、中学時代から常習であったから、本人は全く気にしてはいないのだが、結構、周囲の友人にも迷惑を掛けていたのかも知れない(笑)。 女性二人による、フォークソングの披露もありました。どちらの女性も小生は顔も名前も存じ上げない、と言うか記憶にない。同じクラスになったこともなく、クラブその他での接点が全くなかったものかと思う。 各クラスからの幹事諸氏のお世話で、毎回このような同期会を何年かに1回開催して来たが、今回で幹事団は解散、学年全体での同期会は今回を最後にするとのこと。幹事の皆さん長きに渡りお世話になりました。まことに、有難うございました。 これは、喫煙ルームからの眺め。時々、中座してここで煙草休憩。喫煙者同士での交流を温めたのでもありました(笑)。 各クラスごとに壇上に上がり、近況報告。クラスごとの記念写真。全員での記念写真は開会前に撮影済みでした。 最後に恒例の校歌「若江堤に、草萌えて、金剛の山かすむ頃・・」を全員で合唱。1番の歌詞が上で、2番の歌詞が「高安山に、照る月を、長瀬の川にうつすとき・・」なのであるが、小生は何処で間違ったか、1番と2番の歌詞を取り違えて覚えていて、今回その誤りに気付きました。 まあ、そんなこんなで、楽しい時間を過ごしました。二次会もあったようだが、それは失礼して帰宅の途につきました。いくととせ へたるやけふの 思ふどち い群れて居れば うれしくもあるか (偐家持)(本歌)あらたしき 年の始めに 思ふどち い群れてをれば 嬉しくもあるか (道祖王 万葉集巻19-4248)
2016.04.21
コメント(7)
-

銀輪万葉・奈良銀輪散歩
本日は先の京都銀輪散歩に続いての奈良銀輪散歩の記事であります。 コースは、近鉄大和八木駅前~飛鳥川自転車道~藤原京跡~下八釣町の興福寺~古池~香具山・万葉の森~香久山公園・香久山墓園前~南浦町の桃畑~春日神社・吉備池~大神神社・狭井神社~箸墓古墳~大和川畔の道~素戔嗚神社~池坐朝霧黄幡比賣神社~帰仁橋・国道24号~嘉幡町交差点西へ・県道109号~近鉄ファミリー公園前駅。 将軍塚の前には桃の花も咲いていたので、随分以前に見て、何やら桃源郷とはこれかという印象を持った香具山の東側の丘辺の桃畑をもう一度見てみようということで、トレンクル持参でやって来た銀輪散歩でありました。 近鉄大和八木駅下車、そこでトレンクルを組立て、銀輪散歩いざ出発。飛鳥川に出て、飛鳥川沿いの自転車道を南へと走る。今井町の前を過ぎ、おふさ観音を左に見て、藤原京跡に通じる道の辺りで、飛鳥川と別れ、藤原京跡の北側の醍醐池を目指す。 醍醐池の北側は一面の菜の花畑。醍醐池の堤の桜並木は既に葉桜であったが、菜の花は今も盛りと真っ黄色。(醍醐池北側の菜の花畑)(同上)(同上)(同上・背後の山は耳成山) 菜の花畑の片隅にはレンゲソウも咲いていました。(レンゲソウ) 醍醐池畔の犬養万葉歌碑に挨拶して、藤原京大極殿跡を横目に、畑中の道から、高殿町の古い集落の路地を右に左にと走り、下八釣町埴安地区の興福寺と畝尾坐健土安神社の先の野道を行く。れんげ畑を眺めながらの銀輪散歩である。 昨年4月20日の万葉ウオークで歩いたのとほぼ同じコースを逆に辿っている趣である。 <参考>万葉ウオーク予定通り実施 2015.4.20.(香具山西麓のれんげ草畑) 天香久山神社へと通じる道を横切り、畑中の野道へと入り、竹林の中の細道を抜けて古池畔に出る。古池を巡るようにして進むと万葉の森である。昨年の万葉ウオークは雨のパラつく天気で、竹林の道はぬかるんでいるだろうと迂回したが、今回は天気も好く小生一人なので、近道を行くこととした。だが、古池に出る直前の場所は、やはり地面が柔らかく、足元に気を付けないとぬかるみに靴を突っ込んでしまうことになる悪路。 万葉の森到着。八木駅で買って来たお弁当を広げて、森の中のやや高い場所で昼食とする。 傍らにはタンポポとハルジオン。仲の良さそうなこの二人を見やりつつ、花より団子、いや弁当と、ひたすらかき込んでパクパク・ムシャムシャ。(万葉の森で見つけたタンポポとハルジオン)タンポポに 寄り添ひ咲ける ハルジオン 恋のゆくへは いかにかあるらむ (偐家持) (同上・タンポポの子ども) 万葉の森を抜けて、東側の入口から県道に出て、坂道を下る。香久山公園の前の道に出る。そこにはご覧のような見事なレンゲソウ畑。(香具山東麓のれんげ草畑・香久山公園付近)(同上) レンゲソウ畑の傍らにはアメリカフウロもひっそりと花を咲かせていましたが、レンゲソウの大群の前には、なすすべもなしといった風情でありました。 (アメリカフウロ・香久山東麓) 香久山公園への進入路には山桜が咲き匂っていましたので、公園の前の道を東へと辿った処にある丘の上の桃畑や如何にと走りましたが、時既に遅し、下のような状態でありました。残念。花の盛りの頃は、此処の風景、お薦めですよ。(香具山北東麓の桃畑・橿原市南浦町付近) 桃の花、散りぬるあとの名残り惜し、水なき空に波は立てまじ、とて紀貫之さんは苦情も言わず、「いい面の皮」と下手な駄洒落。面目なしの当て外れヤカモチ、身は用なきものと思いなし、さればとて、にわかに思い立ってのことか、三輪山にでも登らむと狭井神社に向かうのでありました。 途中、吉備池畔の大津皇子とその姉の大伯皇女の歌碑などにも挨拶し、春日神社の境内にも立ち寄る。境内の奥から出て来られた男性は、ひと抱えもあろうかという巨大な筍を2本抱えて居られました。神社の裏の竹林でとれたものだそうな。その大きさ、堂々たる筍を褒めると、男性は自分が褒められたように笑顔に。少し言葉を交わしました。 適当に走って、大神神社の鳥居前に出る。鳥居前を素通りして北側にある摂社の狭井神社へと行くが、結構な坂道。とてもこいで上れる坂道ではない。押して行く。 三輪山に登るには、この狭井神社の受付を通さなくてはならないのだが、受付は午後2時まで、社務所到着は午後2時20分頃。断られてしまった。またしても、是非もなし、是非に及ばず、の面目なしヤカモチである。 上って来た急坂を下る。此処でも道脇にムラサキサギゴケが咲き群れていました。京都も大和も、サギだらけ、です。(ムラサキサギゴケ) 仕方なく、やり過ごした大神神社にご挨拶申し上げることとする。鳥居前の駐輪場にトレンクルを停め、いつも裏やら横やらから入るヤカモチであるが、今回は正面から、即ち「表」からの「堂々の?」入場・参拝である。(大神神社)(大神神社・巳の神杉) 丘の上の桃畑を見るためにだけやって来たヤカモチ。この付近一帯は何度も来ているので、今回は地図は持たずに来ている。大神神社のアト何処に行くというアテもない。 さて、どちらに行かう。風が吹く。山頭火にもあらねば、青山へと分け入る訳にも参らず、久々に箸墓にでも行ってみるかと、大鳥居の先の国道169号に出て北へ。 箸墓は、卑弥呼の墓とも言われる大型の前方後円墳であるが、夜な夜な自分のもとに通って来る男(大物主神)の姿をひと目見たいと言い、朝、男が蛇の姿で現れるに及び、驚き、叫んでしまう、恥をかかされたと感じ、怒った男(神)は、二度と彼女のもとに現れなくなる、これを後悔、悲嘆して、ホトを鉄箸で突いて死んでしまうという伝説の女性、第7代孝霊天皇の皇女・ヤマトトトヒモモソヒメ(倭迹迹日百襲媛)の墓として宮内庁が管理する御陵である。 御陵北側の大池畔に歌碑があった。(箸墓古墳大池畔の記紀歌謡歌碑) ※この歌はこの墓を造るため、人々が列を作って大坂山(二上山の北側の山) の石を手渡しで運んだときに、当時の人が詠んだものだと、日本書紀に記 されている。大坂に 継ぎ登れる 石群(いしむら)を 手逓伝(たごし)に越さば 越しかてむかも (日本書紀 崇神天皇10年9月の条) (大坂山に下から上まで続いている石は、手渡しで渡していけば、渡せるだろうかなあ。)(キンポウゲ<ウマノアシガタ>) 池の畔には、キンポウゲ科のウマノアシガタが群れ咲いて、風に揺れているのでありました。池の辺に うまのあしがた 群れ咲くを 撮らむとすれば 風吹くらむか (偐家持) 写真に撮ろうとすると、風が吹いて来て揺れ動く花。ようやくに撮れたのがこの2枚であったという次第。(同上) 箸墓を出て、国道169号を渡り西へ。程なく大和川(初瀬川)に出る。川沿いの道を下流に向かって走る。当初、勘違いして大和川の支流の寺川かと思って走っていたのだが、川幅や四囲の景色から、大和川だと気付く。まあ、何処へ行くというのでもなければ、どちらであっても構わないのではある。 対岸に神社らしきものが見え、手前の橋から境内にかけて長大な藁綱が差し渡されているのが目に入る。何であるかと、立ち寄ってみると。(素戔嗚神社) こんなのでした。(同上) (同上)(大和川<田原本町>) 次に目に入った神社は、池坐朝霧黄幡比賣神社。(池坐朝霧黄幡比賣神社)(同上) (同上) 更に行くと小さな公園に、古代の楼閣を模した三層の展望塔があった。登ってみた。(三輪山・多武峰遠望・田原本町法貴寺地区の公園展望塔から) 南東方向には多武ノ峰、三輪山がその雄姿を見せている。小生は上の写真の道を右からやって来たのでありましたが、ご覧のように自転車で走るには快適な道でありました。自転車専用道というのではないが、車の走行も殆どなく、自転車道と変わらぬ走りよさである。 東方向、正面には、天理市の山、竜王山が見える。昔、父と石上神宮付近からこの山に登り、崇神天皇陵の辺りに下山したことがある。(竜王山遠望)(大和川畔の道)(同上)(同上) やがて、大和川沿いの道は行き止まりとなり、小さな人道橋を渡り、国道24号の帰仁橋北詰に出る。その小さな人道橋の上から撮った写真が下の2枚。(大和川<大和郡山市八田付近>上流側)(同上・下流側、奥に見えている橋が帰仁橋である。) 帰仁橋の南側に川沿いの道があったが、舗装されていなかったのと、既に午後5時を過ぎていたので、銀輪散歩も切り上げ時かと、国道24号を北に走り、嘉幡町交差点で西に入り近鉄ファミリー公園前駅へと向かう。改札前で自転車を折りたたみ輪行バッグに収納している時に電車が入って来る。大急ぎでホームに向かうが目の前で扉が閉まり、万事休す。次の電車となる。どうも、今回の銀輪散歩はタイミングを逸することの多い銀輪散歩でありました。<参考>銀輪万葉・奈良県篇
2016.04.20
コメント(4)
-
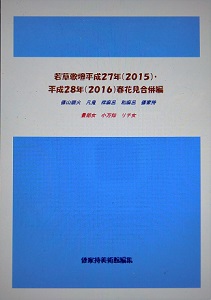
若草歌壇・平成27・28年春花見合併編
今日は、フォト蔵がメンテナンス中にて、登録画像を利用することが断続的に出来なくなる状態にあり、登録画像へのアクセスも断続的に出来なくなる状態です。 当ブログ記事の写真は殆ど全てがフォト蔵に登録したヤカモチのマイピクチャを転載して居りますので、どの記事の写真もNOT AUTHORIZEDという画面になって写真が見られないということが起こる場合があるかと思いますが、それはこのメンテナンスのために生じていることで、当ブログ記事に異変が生じている訳ではありません。 まあ、そんなことなので、今日は、若草歌壇についてのお知らせ、とします。 若草歌壇というのは、若草読書会の新年会やお花見の折の余興としてヤカモチの提案により、数年前から始めた、自作の短歌や俳句を持ち寄り相互披露する、という催しのことで、ヤカモチが戯れにこれを若草歌壇と命名しました。 その折々の歌を記録し、表紙や適当な写真を配するなどの編集をして、これをPDFに作成したものが「若草歌壇・0000年〇〇編」という電子冊子。この電子冊子は、友人の偐山頭火氏が運営管理する「河内温泉大学図書館」というネット図書館に収蔵して戴いて居ります。 今回、先日(3日)の若草読書会花見の折の短歌・俳句をまとめたものの編集が完了し、偐山頭火氏にメール送信して置いたところ、昨日、同氏より、図書館への収蔵が完了した旨のメールを頂戴いたしました。 昨年は、この編集を失念して居りましたので、今回の分は昨年と今年の2年分の合併号となりました。仲間内の「お遊び」に過ぎませぬ故、他人様には興味もないことかと存じますが、一応、どなたでもご覧いただけるネット図書館に収蔵し、不特定多数の目に触れる状態にしても居りますので、もし興味を覚えるという、まことに奇特なお方が居られましたら、図書館の方を覗いて戴ければ幸甚に存じます。 若草歌壇平成27年(2015)・平成28年(2016)春花見合併編 上記歌集は、上のタイトルをクリックすると内容がご覧いただけます。 河内温泉大学図書館は下記URLをクリックして下さい。 https://kawachionsen.wixsite.com/mysite<参考>若草読書会関連記事目次
2016.04.19
コメント(5)
-

銀輪万葉・清閑寺から将軍塚へ
(承前) 4月14日の銀輪散歩の続編です。 清閑寺の山門を潜って先ず目に入るのが、この小督の供養塔である。小督というのは、高倉天皇に寵愛された小督の局のこと。高倉天皇の中宮として自身の娘・徳子(建礼門院徳子)を差し出していた清盛にとっては、高倉天皇が小督に溺れるのは困ったこと。清盛の命により、二人の仲は引き裂かれ、小督は此処、清閑寺で無理矢理に出家させられてしまう。 前ページで紹介した高倉天皇陵がこの地にあるのは、「小督の居る清閑寺に葬ってくれ」との天皇の遺言によるものであったという次第。 <参考>小督・Wikipedia 清閑寺・Wikipedia(小督の供養塔) 供養塔の後ろにある桜の木は「小督の桜」と呼ばれているらしい。 (清閑寺説明板) (小督の局説明板) ※写真が小さくて読み辛いときは、クリックして大きいサイズに変 換の上、お読み下さい。 藤原定家も小督を見舞っていると言うから、偐定家を名乗ることもある偐家持としては、この寺に参るのも故なしとしないと言うべきか。(剃髪させられる小督) (謡曲「小督」と清閑寺) (与謝野礼厳歌碑) 小督の桜の前の木札の歌碑は与謝野鉄幹の父・礼厳の歌。妻を亡くして彼は此処・清閑寺に隠居したとのこと。年を経て 世にすてられし 身の幸は 人なき山の 花を見るかな (与謝野礼厳)(カラタチ) 清閑寺の境内は小ぢんまりとしたものであるが、色んな花も咲いて、人影もなく、その名の通り閑静、閑寂、いつまでもグズグズととどまっていたいような気分にもなる、まことによい雰囲気の寺である。 本堂の裏に回ると小生の背よりも高いカラタチの木が花を咲かせていました。 (同上)(これもスミレの一種だろうか。) ※ビッグジョンさんからキランソウ(別名ジゴクノカマノフタ) だと教えていただきました。 山門へと通じる石段の脇に咲いていた小さな紫色の花。これもスミレなんだろうか。初めて目にする気がする。 この後、訪ねる将軍塚でも同じ花を見掛けた。下の写真がそれです。 (同上) (ムラサキケマン<紫華鬘>) ムラサキケマンとクサノオウも咲いて目を楽しませてくれました。 (草ノ王)(名前不詳) 白い房になっている花を近付いてよく見ると、アセビの花のような釣鐘型をしている。多分初めて目にする植物。名前は勿論、知らない。ちょっと気になる花。まあ、木になっている花には違いありませぬが。 (同上) (同上) 清閑寺を出て、東山ドライブウェイの坂道をひたすら上る。 ウワミズザクラという名は、かなり以前に友人の小万知さんから教えて戴いたことは記憶にあって、ウ・ワ・ズ・ミ・ザクラという言葉が一時思い浮かんだが、違う気もして、結局、この時は思い出せず、ええ~と、ええ~と、と言うばかり。帰宅して過去のブログ記事を検索し、ウワミズザクラと分かりました。 <参考>花逍遥・何の花? 2012.5.15. 上の記事で、カキドウシの名もこの記事で教えて戴いていたことが分りましたが、教えて戴いても、すぐに忘れてしまう・・ビッグジョンさんもそんなことをブログに書いていらっしゃいましたが、まことに、まことに同様にて困ったことです(笑)。(ウワミズザクラ)(同上)(ミツバツツジ) ミツバツツジが花の滝となって流れ落ちてもいる。 ウワミズザクラもミツバツツジも自転車の足を休める口実を兼ねていたのだが、暫く見惚れる美しさ。写真を撮っていると、後ろから来た自転車の青年に追い抜かれてしまった。(同上)(枝垂れ桜) この枝垂れ桜は、東山ドライブウェイから将軍塚へと上る坂道との分岐にある。 敷島の大和心は、本居宣長流には「朝日に匂ふ山桜花」であるが、東山の 銀輪族の 心とは 疲れくたびれ 枝垂れ桜花 (銀輪家持)である。(同上) 枝垂れくたびれ桜から更に上った処に展望台がある。 此処は無料の展望台。(将軍塚手前の無料展望台からの眺め) そこから少し奥に入った処に将軍塚がある。 将軍塚は無料で見ることができるものと思っていたが、最近に移築され、広大な木製大舞台を持った青龍殿の一角になっているようで、500円の拝観料を支払わないと其処には行けない仕掛けになっている。 是非もなし。 <参考>天台宗青蓮院門跡将軍塚青龍殿ホームページ TOP 将軍塚 青龍殿 大舞台 青不動(将軍塚) 桓武天皇は、長岡京からの遷都を考えていた時に、和気清麻呂を伴って東山のこの地に立ち、平安京への遷都を決めたとのこと。遷都に伴い、平安京の守護とするため、将軍像を作らせ、これに甲冑を着せて埋めさせたという。それで、将軍塚と呼ばれるようになったとのこと。 山科の坂上田村麻呂公園には彼の墓と伝承される塚があるが、清水寺縁起によると、彼は甲冑を着け立ったままの姿で埋葬されたと伝えられているが、これは、この将軍塚のそれに倣ったものかも知れない。 <参考>銀輪散歩・坂上田村麻呂(上) 2013.3.13.(将軍塚と青龍殿)(青龍殿)(同上)(将軍塚隣の西展望台からの眺め) 500円を払っただけのことはあり、眺めは先ほどの無料展望台からのそれよりも格段によいように思われる(笑)。(青龍殿前の舞台からの眺め・北方向)(同上・西北方向)(同上・西方向)(将軍塚隣の枝垂れ桜) 桜、桃などが咲き匂い、うらうらに春日は照れり。庭の散策も楽しい。 足元にはタンポポやスミレの花も咲いている。 そんな中で、スミレのツーショット。いい写真が撮れました。春うらら さやかに風の 吹きも来て 添ひてたぐひて すみれはふたり (偐家持)(スミレ2輪と桜の幼木) カエデもさやさやと若葉をそよがせているのでありました。 カエデの花はこんな花でありましたか。(カエデの花)(同上) 将軍塚にお別れし、上って来た坂道を一気に走り下る。分岐の枝垂れ桜の処で東山ドライブウェイに入り、来た道の右ではなく左に走る。下り切ると地下鉄東西線の走る東海道になり、蹴上まではずっと下り坂。自転車は下りに限る(笑)。 南禅寺山門にご挨拶し、丸太町通りへ。(南禅寺大門) 丸太町通りを西へ。京都御苑に入って、走り難い玉砂利の道を少しばかり走る。 仙洞御所の手前で自転車を停めて草地に腰を下ろして休憩。 ムラサキサギゴケが群生。トキワハゼとも言うこの植物。ムラサキサギゴケというのも小万知さんに教わった名である。(京都御苑のムラサキサギゴケ) この花、ちょっと見はカキドウシと似ていなくもないので紛らわしいが比べれば花の形が全然違うし、葉の違いは一目瞭然である。 カキドウシは「垣通し」という意味で、垣根を通りこして侵入してくる厄介者というニュアンスのある名前だと思うが、このムラサキサギゴケも結構な繁殖力にて、垣根を越えて侵入してくる花ということでは同類かと。近頃はびこっているオレオレサギほどに悪質ではないから、はびこっても、まあ人畜無害というものである。世の庭に ムラサキサギゴケ はびこるも はびこるなかれ オレオレのサギ (鷺麻呂)(同上) ブロ友の「ふろう閑人」さんや「あすかのそら」さんがブログに掲載されていた、変わり果てた梨木神社にも立ち寄ってみるかと思いましたが、ムラサキサギゴケさんと遊んでいるうちに気が変わり、烏丸通りへ出て、京都駅方向に。帰途につくこととしました。以上で完結です。 <参考>銀輪万葉・京都府、滋賀県篇
2016.04.18
コメント(10)
-

銀輪万葉・清閑寺へ
熊本の大地震、お見舞い申し上げます。発生から4日目が終わろうとしていますが、今も熊本から大分にかけて地震が群発、一向に終息する気配のないのが心配です。被災された皆さんの不安いかばかりかとお察し申し上げます。一日も早く地震が終息しますように、そして支援の手が行き届きますように。 さて、暫くブログ更新を休んでいましたが、再開です。最初の地震があったのは14日の夜でしたが、その日は正午前に京都駅前を出発、京都を銀輪散歩していました。 ブロ友のふろう閑人さんがブログでご紹介されていた将軍塚に行ってみようというのがその目的でありました。 コースは京都駅前~智積院前・東大路通り北へ~馬町交差点・渋谷通り東へ~国道1号から東山ドライブウェイ~清閑寺~将軍塚~蹴上~南禅寺~丸太町通り~京都御苑~烏丸通り~京都駅前というもの。 渋谷通りの坂道を自転車(トレンクル)で上っていたら。民家の前に小さな赤い鳥居を括りつけた見覚えのある光景を目にしました。ふろう閑人さんのブログ記事「町角情景」(2016.3.1.)に掲載の上から3枚目・4枚目の写真で見たものが記憶に残っていたのでした。 その先の古い蕎麦屋さんで昼食。蕎麦屋なのにこの日は蕎麦を切らしていて、全てうどんでお願いしているという愉快な蕎麦屋さんでした(笑)。人の良さそうな老人ご夫婦がやって居られる蕎麦屋さん。名前は忘れたが、ご主人が獲得されたトロフィーや楯がズラリと飾られていましたから、そこそこの老舗の蕎麦屋さんではあるのでしょう。 (カリンの花) 渋谷通りから一つ北側の路地に入って行くと民家と民家の間にカリン(花梨)の花が咲いていました。山王神社という小さな神社にはシャガが咲いていました。更に上って行くと再び渋谷通りに出る。渋谷通りから国道1号を暫く行くと東山トンネルである。その手前に東山ドライブウェイがある。土日祝休日は終日自転車などは走行禁止という標識があったが、この日は金曜日。問題なかろうと自転車で喘ぎつつ坂を上るが、ところどころで息が切れて、押して上るしかない羽目に。 草苺の花が咲いていたので、などと口実を作っては休憩という東山ドライブウェイでありました。この後、道端の花の写真が出て来れば、休憩の口実とお考え戴いてほぼ間違いないかと。(草苺) (同上) 上り始めて直ぐに六条天皇陵と高倉天皇陵の前に出る。前には清閑寺の駐車場。清閑寺は御陵から更に石段を上った処にある。(六条天皇陵・高倉天皇陵) 初代神武天皇から後醍醐天皇までの歴代天皇の名はそこそこには覚えていて、この二条天皇、高倉天皇は「後白河・二条・六条・高倉」とセットで覚えている。4代ずつセットで覚えると語呂がよくて覚えやすいのであるが、神武から4代ずつセットにすると、この4人がセットになり、次のセットが「安徳・後鳥羽・土御門・順徳」となるのである。 六条天皇は二条天皇の息子。高倉天皇は二条天皇の弟。二条と高倉は後白河の息子である。二条が崩御すると、その子の六条が即位するが、生後7ヶ月と11日という「若さ(笑)」での即位。最年少即位日本記録を持つ天皇である。しかし、在位2年8ヶ月(満3歳)で退位、上皇となる。最年少上皇日本記録である。六条の後をついで即位したのが高倉天皇。彼も亦満5歳の子ども。後白河上皇の意向によって誕生した傀儡天皇である。二条親政派と後白河院政派との対立の中、二条天皇崩御によって、後白河院政派の強勢が決定的となる。二人はその時期の天皇である。後白河院政に翻弄された子どもたち二人が並んでここ清閑寺に眠っているというのも何やら面白い。(同上・清閑寺山門への石段の途中から)(清閑寺山門)(清閑寺境内から京都市街遠望) 清閑寺境内からの眺めもよろしい。 境内の説明板によると、この素晴らしい眺めが扇型になっていて、扇の要に当たる場所にあるのが下の写真の石で、よって、かなめ石(要石)と呼ばれているとのこと。(要石) この要石の傍らの木札には願いあらば あゆみをはこべ 清閑寺 庭に誓いの 要石ありとあるから、此処に立って祈れば願いが叶うということなのかも知れない。パワースポットという訳でありますな。 一方、鐘楼へと向かう通路には、六文銭のように石が六つ敷かれている。六文銭のように四角い穴がないから、三途の川の渡し賃にはならないだろう。尤も、三途の川の渡し賃も消費税率アップや外国為替の変動などで、いつまでも6文では済むまいと思うが、どうなっていますのやら。銭なくも あゆみをはこべ 清閑寺 庭に六文 まがひ石あり (偐真田丸) (大西郷月照王政復古謀議舊趾碑) ココ清閑寺は、西郷隆盛と清水寺成就院住職の月照とが王政復古についての謀議をした場所でもあるそうな。 小人閑居して不善をなす、と言うけれど、大西郷は清閑寺に居て謀議をなす、でありましたか。(副碑)<参考>月照・Wikipedia(本堂)(つづく)
2016.04.17
コメント(4)
-

囲碁例会・脱線花散歩
本日は梅田スカイビルでの囲碁例会の日。 前回、4月6日は、腎炎で入院していた母の退院の日と重なったため、欠席したので、今月はこれが初めての出席。午後から雨との予報があったのと、もう一つ別の理由もあって、いつもの自転車(MTB)は自宅に置き、電車で梅田へ。 予報通りに、梅田スカイビルに着いた頃には少し雨もパラつき始めていました。そんなこともあってか、出席者は福〇氏、村〇氏と小生の3人だけ。対局は、福〇氏に負け、村〇氏に勝ち、1勝1敗と可もなし不可もなしでありました。 自転車ではないので、昼食はいつもの「れんげ亭」ではなく、梅田スカイビルの里山にあるカフェテラスで。 雨は少しパラついただけであったので、外のテーブルで食事としました。外の方が風が心地良いし、煙草も喫える(笑)。 目の前には枝垂れ桜の木。左手を見上げると梅田スカイビルが桜の花越しに見えている。 食事の後は珈琲。 少し里山を花散歩。 黄色の小さな花が沢山咲いている。カタバミに似ているが、それより大きい花。花の形も少し違う。花の中央の丸いものを見ていて、気が付きました。蛇苺だ。 (ヘビイチゴ)(ヘビイチゴ) 花ビラが全て落ちたのを見ると、もっとよく分る。 ヘビイチゴと競い合うように群れ咲いている、この薄紫色の花は名前不詳です。(名前不詳) ホトケノザの花を平べったくしたような形の花。 何やら呑気そうな感じだから、オトボケノザという名にして置こう。(同上)<追記>上の花はカキドウシ(垣通し)という名前の花だそうです。 小万知さんが下のコメントで教えて下さいました。 これは、小生にも分る。(スミレ)(同上) 何スミレかと言われたら、分からない。 万葉びとは「何すみれ」なんぞという細かいことは気にしないのである。スミレはスミレでいいのである。 で、これは、スミレかと言うとちょっと自信がない。花ビラの下に写っているのがこの花の葉であるなら、スミレの葉とは違うようなのである。周囲にハコベや八重葎やホトケノザなどの葉が見えているからややこしい。万葉びとも、こうなると細かいことも気になるのである(笑)。(スミレのようでもあるが・・) で、その近くにあったこの白い花はやはり名前不詳。蕾では分らないのも無理はないと自分で自分に言い訳していたら、咲いている花もあるではないか。言い訳は許さない、とでも言わんばかりの、嫌みな花である。(名前不詳)言い訳言っても言い訳言っても白い花咲く (訳田山頭花)分け入っても分け入っても青い山 (種田山頭火) (同上)<追記>上の花についても小万知さんからヒメウツギだと教えて戴きました。 こちらの白い花も名前は知らない。 白蝶が群れ止まっているみたいな花である。<追記>この花も小万知情報です。名前はイベリスとのこと。 やっと知っている白い花にめぐり逢って少しばかり面目をほどこした気分になる。ハクサンボクである。(ハクサンボク) 実は赤いが花は白いから「白山木」という名でいいのである。 (同上) 白い花では、アセビも咲いていた。薄いピンクの花のアセビもあるが、白い花の方がよい。 (アセビ)(同上) ボクも白だもん、と割り込んで来たのは、シロダモの木。 アオダモは野球バットの木として知られているが、シロダモは素人野球用バットの材料に適している駄洒落の木であるから、こういう割り込み方も許されないでもないのである。(シロダモ) そういうことで、白なら、吾輩の「赤」も割り込んでもいいのではないか、と言って来たのが、アカシデの木。(アカシデ) 明石で夜明かしアカシデの木。もう何のこっちゃワカラン。 白に赤で二色(にしき)だから、ワシも割り込んでいいだろう、とニシキギ。 お前は、錦の方で二色ではないだろうと、さすがのヤカモチもこれは却下しました。 すると、ヤブコウジが割り込んで来て「遅ればせながら私も赤です。」 まあ、確かにヤブコウジの実は真っ赤であるが、山橘とも呼ばれるレッキとした万葉植物がこういうドサクサには参加して欲しくないもの。ヤブヘビのヤブコウジでありました。 (ニシキギ) (ヤブコウジ) まあ、こんなことでお茶を濁して置くこととします。という訳で最後はお茶の木。(お茶の木) 結局、花散歩が、滅茶苦茶、ハチャメチャのおチャラケ言葉遊びになってしまいました。 もうちっと真面目にせよ。 ハイ、以後(囲碁)よく気を付けます。 これで、元の囲碁に戻りまして、おアトがよろしいようで。
2016.04.13
コメント(14)
-

偐万葉・若草篇(その17)
偐万葉・若草篇(その17) 若草読書会のメンバーに贈った歌をまとめたものが、この若草篇なのであるが、当ブログにコメント下さるお方は、最近は、小万知さんと偐山頭火さんのお二人だけでありますので、若草篇とは言うものの、小万知・偐山頭火篇といった趣になっています。 まあ、今の世の中、日常的な交流の中で歌をやり取りするという習慣はありませんので、こういうことも致し方ありませんですな(笑)。 偐万葉シリーズ第255弾です。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 偐家持が小万知に贈りて詠める歌9首 わが庭に 山橘の 実の照れば いざや待たなむ 雪の降り来を (本歌)この雪の 消(け)残(のこ)る時に いざ行かな 山橘の 実の照るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226) みやびをと 言ふもおこなり 雪つむと 船岡山に 寄らず帰れり (本歌)遊士(みやびを)と 吾は聞けるを 屋戸かさず 吾を帰せり おその風流士(みやびを) (石川郎女 万葉集巻2-126) (船岡山) 榛原ゆ 広陵朝日野 奈良や久世 姫路相生 駆けて赤人 (山部神社)和歌の浦 漕ぎ廻(た)み行けど 難波潟 小万知は歌を 知らん橋とふ (海辺のカフカ)(注)和歌詠むは難しきことなり、思案橋どころか知らん橋なり、との 小万知の言葉に和して詠める歌なり。 「難波潟」に「難しいワ」の意を込めた。 船の絵に 会津はひろろ 野田川の 津田の細江は 淡路も見ゆる (偐播磨娘子) (注) 会津=「あひつ」で「逢ひつ」と掛けている。 淡路=「あはぢ」で「逢はじ」と掛けている。 ひろろ=会津ご在住のブログ友のひろろdecさんのこと。 豆食ふも 過ぎてはわれの 嘆きなり 胡麻で誤魔化し ならぬものかは (節分家持)(本歌)時により すぐれば民の なげきなり 八大龍王 雨やめたまへ (源実朝) 柿食ふと すなる猿連れ 家路かな (柿蕪蕉)牡蠣食はぬ 隣の客に 柿食はせ (柿蕪蕉) こはくてふ よみけるひとの ありしひの おもかげたちて はるひくれゆく 流氷の よりてきたれる オホーツク いつみきとてか こひしかるべし (紋別兼輔)(本歌)みかの原 わきてながるる いづみ川 いつみきとてか こひしかるらむ (藤原兼輔 新古今集996 小倉百人一首27) 道の辺に 咲く野の花も 照れる日も うららに春は 今盛りなり 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌12首 並びに偐山頭火が詠める歌6首 偐山頭火が贈り来れる歌1首 冬瓜も 三代に担がれ あな嬉し 阿武山下り 石川昇る (元祖冬瓜担) 偐家持が追和せる歌2首 恩智から 始め阿武山 石川で 三代なるか 冬瓜担ぎ 石川と 言へば源氏の 三代墓 越えて小万知の 冬瓜行くか 奥山に もみぢふみわけ 猿酒を 山の猟夫(さつを)は 求め飲むとふ (鹿丸大夫) (本歌)おく山に もみぢふみわけ なく鹿の こゑきくときぞ 秋はかなしき (猿丸大夫 古今集215 小倉百人一首5) おく山の さるのうはまへ はねるとは げにのんべえを 下戸とやいはむ (猿酒酒造) 餅切るも 切り時あれり 遅れては 餅焼く前に 手をば焼くなり (偐家餠) (猫餅)※偐山頭火氏撮影 わが思ひし 百実一首は ハナからの 頓挫にしあり 実にならじかも (偐定家) (本歌)吾妹子が 形見の合歓木は 花のみに 咲きてけだしく 実にならじかも (大伴家持 万葉集巻8-1463) 偐山頭火が贈り来れる歌1首 花曇り 晴天も良し 条件は 揃ったものの 我が花(歌)俄に (天気次第山頭火) 偐家持が返せる歌1首 雨ならば 朝寝もするを 曇りとは 早起き場所取り よしあし花見 (天気次第家持) 偐山頭火氏が贈り来れる歌1首 あけぼのの 花見も風流 舞台裏 見られたく無い 観せたくもあり 偐家持が返せる歌1首 写真とて われら舞台の それなくは 舞台の裏を 見せるほかなく 偐山頭火が贈り来れる歌1首 あれ描けと 下手な写真を 持参して 描けハラするも 画風を思うて (描けハラ山頭火) 偐家持が返せる歌1首 これ描けの 君がカケハラ ばらすとは バラスメントぞ ヤカモチわれも (何バラ家持) (注)カケハラ=これ描けあれ描けハラスメント。偐山頭火氏の造語。 これはパワハラに近い語。 何バラ=何でもバラスメント。偐家持の造語。 何でもばらしてしまうことであるが、勿論セクハラとは無関係。 偐山頭火が贈り来れる歌1首並びに偐家持が返せる歌3首 岬麻呂 海無き大和の 咲き巡る 桜は咲いたが 石楠花いまだ (偐山頭火) 頸椎の 傷なほらねば すべもなみ 自宅謹慎 偐山頭火 頸椎の ことも癪なり 石楠花の 花もいまだし われもいまだし (偐三等花) 山頭火 そらみつ大和 あをによし 奈良めぐれるは いつとや待たむ (馬見丘公園)※偐山頭火氏撮影 偐山頭火が追ひて返せる歌1首 山頭火 山頭花へと 成りにける 酒山頭火 へはリハの途次 (超変革山頭火)<参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。
2016.04.12
コメント(4)
-

岬麻呂旅便り186・奈良
本日は、岬麻呂旅便りの記事とします。 同氏の旅便りとしては、珍しい近場の奈良の便りでありました。同氏とは去る5日に或る方のお通夜で久しぶりにお会いしましたが、その折に奈良での写真をメールで送ると言って居られ、その通りに送られて来たという次第。 ならまちをゆっくり散策したいということもあって、奈良に一泊されたようだが、日付を見るとお通夜の日と同日。どうやら、奈良旅行とお通夜の日が重なってしまったというのが実のところで、小生がお会いした折にお聞きした「奈良へ行って来た」というのは、その日のことを言って居られたということのよう。 (旅報告186) 奈良と言えば、この景色が定番でしょうか。猿沢池から望む興福寺五重塔です。(猿沢池) 写真中央、池の向こう岸に右から1本目と2本目の柳の木の間に小さく写っているのが会津八一の歌碑である。昔、天皇の寵愛が薄れたことを嘆いて身を投げた采女がその衣を掛けたという柳の木を見たくて雨の中、池を経廻った、という歌であるが、右寄りに写っている石塔がその采女を供養する塔であったかと思う。 その歌碑の写真が掲載されている当ブログ記事は次の記事です。 <参考>柳生銀輪散歩(下) 2011.8.3.(東大寺大仏殿・南大門) 大仏殿など定番の観光コースは観光客で一杯ですな。それも外国人が圧倒的多数。岬麻呂氏は、99%外人、と書いて居られる。 大仏殿から二月堂へ。まあ、外人観光客に混じって岬麻呂氏も一応定番コースを歩かれたということのよう。(東大寺二月堂) そして、春日大社へ。万葉植物園に立ち寄られたようです。小生も何度か入っているが、最近はとんとご無沙汰している。少なくとも10数年以上のご無沙汰かと。 そこで、ご覧になった珍しい金色の椿・金花茶の花がこれ。(金花茶) 万葉に出て来る椿は「つらつら椿」。 金色の花など付けない(笑)。 で、カタクリの花。これは万葉植物。1首だけ歌がある。(片栗)もののふの 八十少女らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 (大伴家持 万葉集巻19-4143)(ヤブカンゾウ) 次はヤブカンゾウ。八重に咲くのがヤブカンゾウでノカンゾウは一重の花である。万葉では、これらを「忘れ草」と呼んでいる。わすれ草 わが紐に付く 香具山の 故りにし里を 忘れむがため (大伴旅人 万葉集巻3-334) 上の歌は、大伴旅人が大宰府の長官としてその地にあった折に詠んだ歌である。老いて妻を亡くし、都から遠く離れた地で、自らの死もそう遠くはないことを感じてもいたのだろうか、同時に作った歌にこのようなのもある。わが盛り またをちめやも ほとほとに 寧楽の京を 見ずかなりなむ (同上 巻3-331) さて、岬麻呂氏からお送りいただいた写真には、「ならまち」散策の方の写真はありませぬので、当ブログで「ならまち」を取り上げているものは、と探してみました。 <参考>ならまちの猫 2011.7.31. 中将姫伝説 2012.6.18. ならまち散策余聞 2012.6.19.(室生川に架かる、室生寺前の反り橋) 奈良の喧騒を避けて、ならまち早朝散策の後は室生寺へ参られたようです。桜がお目当てであったようです。境内のシャクナゲが咲くのは未だ少し先なんでしょう。 室生寺も高校時代が最初で以来何度となく訪ねている馴染みの寺。当ブログでも過去に関連記事があります。 <参考>室生銀輪散歩(室生龍穴神社へ) 2014.3.16. 室生銀輪散歩(龍穴から室生寺へ) 2014.3.17. 室生銀輪散歩(室生寺から室生口大野駅まで) 2014.3.18.(室生寺金堂) 室生寺はやはりこの五重塔を見なくては、見た気がしないというもののようです。一昨年の3月に小生一人で銀輪をお供に此処にやって来た時は、折しも春の雪がひとしきり降るという有様で、なかなか風情がありました。(室生寺五重塔) 今回の岬麻呂氏の旅便りは、小生にも馴染みの場所にて、色々と懐かしい思い出に浸ることができました。
2016.04.10
コメント(6)
-

偐万葉・ビッグジョン篇(その31)
偐万葉・ビッグジョン篇(その31) 気が付けば、ビッグジョン氏のブログへのコメントなどに付した偐家持の歌も20首になっていましたので、本日は久々に偐万葉の記事とします。偐万葉シリーズ第254弾の記事になります。 <参考>過去のビッグジョン篇はコチラから ビッグジョン氏ブログはコチラから 偐家持が歩麻呂に贈りて詠める歌20首 並びに歩麻呂が詠める歌2首とつくにの いにしへびとの ごとわれも クメール三山 めぐりて行かな (プノンバケン) クメールの 夕日今しも 沈みゆく なべて丘々 慈愛の色に (プノンクロムの夕日) プルメリアの 甘き香のして まぐはひも 聖となりしか シヴァの神殿 (プルメリアの落花) (リンガ) 昼と夜の 間にしばし ひとはみな 立ち止まるべし 夕日あふぎて (プノンボックの山上遺跡)クメールの 果てなき原に 落つる日を 眺めよ黙(もだ)に 千年(せんねん)の廃墟 (プノンボックの夕日) つつじ花 にほえをとめと ときじくに 咲きて中山 けふか越ゆなる (栄えをとめ) (ミツバツツジの狂い咲き) さくら花 栄えをとめは まだ咲かず 梅の中山 背子行くなるか (にほえをとめ) (中山梅園) 歩麻呂が贈り来れる歌2首並びに偐家持が追和せる歌1首 流氷を見たいと思いしあの日よりもう四十年いつ果たせるか (歩麻呂) ああ流氷、アムールの氷は何色か 音も聞きたしロックも飲みたし (歩麻呂) オホーツクの 青にし浮かむ 流氷の ロックで召されよ 竹鶴余市 (ニッカ家持) かたばみとふ 名ではかたみの 狭きとや オキザリスなど 気取りてもある (置き去り家持) 歩麻呂の句に偐家持が付けたる脇句 ウグイスの 初音聞きつつ 縦走路 (歩人) 南無法華経や 隈笹の道 (偐家持) (六甲縦走路・隈笹の道) 言はざりと 時に思へど あつかまし 駄洒落一つも 言はずは済まじ (戯家持) (改作)言はざりと 時に思へど 懲りぬわれ 駄洒落一つも 言はでは済まじ (本歌)かへらじと かねて思へば 梓弓 なき数にいる 名をぞとどむる (楠木正行) 折々の 花は愛づとも 銀輪に いやめづらしき 花は咲かなく 春まけて 李の花の 咲きたれば はだれと見し人 思ほゆるかも (本歌)わが園の 李の花か 庭に降る はだれのいまだ のこりたるかも (大伴家持 万葉集巻19-4140) (李の花) さんざめく 八十の少女の ごと咲ける 文殊の山の かたかごの花 (文殊山のカタクリの花)大土呂ゆ 半田小文殊 恋ひ来れば 山も狭(せ)に咲く 堅香子の花 (同上) (本歌)もののふの 八十少女(やそをとめ)らが 汲みまがふ 寺井の上の 堅香子の花 (大伴家持 万葉集巻19-4143) (白いカタクリの花)堅香子の 少女(をとめ)も今日は 嫁入りか 白無垢一輪 咲きぞ匂へる わが見しは み山の奥の 花の精 白堅香子は 今ぞ咲きたる 出し惜しむ 君がこころも げにこそと 白堅香子は 無垢にぞ咲ける 田を作る 人もなき田に 生えたるを 摘むひとなくて 撮れる芹これ (偐歩麻呂) 花園の 池の水際に 生えたるは 摘むひともなき 毒芹ぞこれ (芹) (本歌)あかねさす 昼は田賜(た)びて ぬばたまの 夜の暇(いとま)に 摘める芹子(せり)これ (葛城王 万葉集巻20-4455) (注)芹(せり)の語源は「競り」だとのこと。芹は春の七草の一つにて食用になるが、似 た植物に芹を大型にした毒芹もあるので、注意が必要。 葛城王=後の左大臣橘諸兄である。この歌は諸兄が山背国班田司長官であった 26年前(当時は橘姓を賜る前で葛城王であった。)に薛妙観命婦に贈っ た歌のことを思い出して披露したもの。命婦の返歌は以下の歌。 ますらをと 思へるものを 大刀佩きて かにはの田居に 芹そ摘みける (万葉集巻20-4456)この頃は 畦(あぜ)の上にも 早蕨の 萌えて妻摘む 春にありける (蕨) (本歌)石(いは)ばしる 垂水の上の さ蕨の 萌え出づる春に なりにけるかも (志貴皇子 万葉集巻8-1418) (脚注)掲載の写真はビッグジョン氏のブログからの転載です。
2016.04.08
コメント(12)
-

第174回智麻呂絵画展
第174回智麻呂絵画展 本日は智麻呂絵画展であります。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 只今、大阪は桜満開。明日は雨で、花散らしの雨になるだろうとのことですが、やはり、この時期の絵画展としては、桜の絵から始めるべきでしょう。 智麻呂画伯は、脳梗塞で倒れられ死線を彷徨われましたが、右半身麻痺という重い後遺症はあるものの奇跡的に復活されたのは、桜の咲く頃のことでした。混濁した意識が徐々に戻り、唯一動く左手で描かれた最初の絵が「桜」でありました。 写実的には、それは「桜」と呼べる「絵」ではありませんでしたが、車椅子で見上げた満開の桜が智麻呂さんに「描け」と働きかけたとでも言うしかない「桜」の「絵」でありました。智麻呂さんは以来何枚もの桜の絵を描いて来られましたが、智麻呂さんを今日の「画伯」にしたのが「桜」であってみれば、それはごく自然なことと言うべきでしょう。さまざまの事おもひ出す桜哉 (芭蕉 「笈の小文」) 智麻呂さんにとっても、桜はそのような特別な花であるのでしょう。(桜) これらの桜はヤカモチの写真から絵にされたもので、今年の桜のそれではないのですが、そういうことは、余り問題ではないでしょう。今年の桜も、今まさにこのように咲き匂っています。(大阪城の桜)(水仙) この水仙は恒郎女さんが智麻呂さんのためにご用意されたもの。もう水仙の時期ではありませんが、描かれたのは先月の上旬でありました。構図も決まっていい感じです。(タンポポ) このタンポポの絵は当日記掲載の写真からのものです。 背の高い真ん中の花を見て戴くと明らかですが、これは二ホンタンポポです。 <参考>このタンポポの写真が掲載されている記事 墓参・花散歩・枚岡梅林 2016.3.5.(チューリップfromトマト) 上の「チューリップ」と下の「コボウズオトギリの実」は、デイサービスの「アンデスのトマト」で戴いたものです。 デイサービスに行かれて、其処で花を写生されるのが智麻呂さんの楽しみの一つ。絵が未完成であったりすると、差支えの無い場合には、その花も持って帰ることができるように施設の方で、ご配慮下さっているようでまことに有り難いことです。(小坊主弟切<ヒぺリカム・アンドロサエマム>の実)(椿) この椿は、もう一つのデイサービス施設の福寿苑で、お仲間の友〇さんから戴いたものだとのこと。 この友〇さんも、智麻呂さんに画題としてお花などを時折お持ち下さるお方にて、智麻呂絵画のよき理解者のお一人であります。 智麻呂絵画は、このように多くの理解者のご支援・ご協力でなり立っているということ、そのこと自体が絵のすばらしさ以上に素晴らしいことだと小生は思うのであります。この絵画展もそれらのお方のご支援・ご協力の賜物という訳であります。(ケーキfrom五〇さん) では、ここで、いつもの五〇さんからの贈り物のケーキで一息ついて戴きましょう。花より団子ならぬ、花よりケーキというお方はご遠慮なくお召し上がり下さいませ(笑)。(ツルニチニチソウ) 上のツルニチニチソウは小万知写真集からではないかと思います。 下のオオキバナカタバミは当日記掲載写真からの絵です。 <参考>オオキバナカタバミの写真が掲載されている記事 墓参・花散歩・枚岡梅林 2016.3.5.(オオキバナカタバミ) 以上、本日は10点の作品をご紹介申し上げました。本日も、ご来場・ご覧下さり、ありがとうございました。 余談ですが、因みに、これまでの絵画展出展総作品数は、本日の10点を加えて、1599点となりました。次回絵画展で冒頭を飾る絵が1600点目ということになります。今から何の絵がそれになるのか楽しみでもあります。
2016.04.06
コメント(8)
-

岬麻呂旅便り185・四国の城と桜
本日の記事は、友人岬麻呂氏からの旅便り・四国の城と桜です。 <参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラから。 今回は3月28日~31日の3泊4日の四国桜巡りの旅。 28日・伊丹~松山空港~大角鼻~糸山公園~今治城~松山城~29日・大洲城~宇和島城~宿毛城趾~足摺岬~30日・四万十市立郷土資料館(中村城趾)~牧野公園・佐川城趾~鏡野公園~高知城~31日・室戸岬灯台~モネの庭~高知空港~伊丹という、いつもながらの精力的な旅程であったようです。 今治城、松山城、中村城趾、高知城などは小生も訪ねたことのある場所にて、懐かしく拝見させて戴きましたが、同氏からメール送信のありました写真を紹介させて戴くこととします。 当ブログの銀輪散歩(銀輪万葉)の記事で過去に紹介しているものについては、当該記事を参考までにリンクして置きますので、興味を持たれた方は覗いてみて下さいませ。(旅・岬巡り報告185)(来島海峡大橋) 来島海峡大橋は、以前、しまなみ海道銀輪散歩で渡った橋。自転車で走るとまことに爽快な橋である。今治へと降りて行く螺旋のスロープが印象に残っている。糸山公園は来島海峡大橋のたもとにある公園らしいが、記憶にないから小生は立ち寄らなかったのでしょう。 <参考>しまなみ海道(2)・伯方島~大島~今治 2008.11.14.(今治城)(松山城)城はあれど 花は盛りの 時ならで 今しばらくは まつの山なり (偐家持)(大洲城)(宇和島城)(足摺岬) 今回は城と桜巡りの旅とは言え、岬麻呂氏としては岬と灯台はやはり外せないというものでしょうな。(四万十市立郷土資料館・中村城趾) 四万十市立郷土資料館も2009年5月の四万十川銀輪散歩の際に立ち寄りましたので懐かしいことです。 <参考>四万十川・高知銀輪万葉(その2) 2009.5.17.(佐川城趾・牧野公園のジロボウエンゴサク) エンゴサクの花と来ると小生は北海道富良野のブロ友・furano-craftさんのことを思い出したりもしますな。あちらのそれはエゾエンゴサクでありました。 この牧野公園というのは、植物学者・牧野富太郎氏の郷里ということで、牧野博士に所縁の深い植物が多く植えられているそうな。岬麻呂氏はお花好きの奥様のことも思い、この公園や下に登場する「モネの庭」なども目的地に加えられたようです。見習うべし、ヤカモチということでありますかな(笑)。で、ヤカモチがこれを目的地に選ぶと「マネの庭・マネヤッタン」ということになる。(高知城)<参考>四万十川・高知銀輪万葉(その3) 2009.5.18.(室戸岬灯台)(吉良川町重要伝統的建造物群保存地区<室戸市>)(モネの庭・マルモッタン) 今回の旅のテーマは「四国桜巡り」であったようですが、桜の写真が主役にはなっていない処を見ると、少し早過ぎた旅であったのかも知れません。 小生なら「花巡り」として、その辺は桜以外の花も当初から射程に入っていたかのような曖昧性で誤魔化すのであるが、岬麻呂氏は左様な姑息なことはなさらぬのであります(笑)。桜巡りであったとしてもエンゴサクやチューリップを見て楽しくあったのだから、それでいいではないか。それに、花は盛りをのみ見るものかは、というのは兼好さんを待つまでもなく、風流人の常識というものではないか、と仰ることでしょう。 本日は、岬麻呂旅便りの記事でありました。
2016.04.04
コメント(4)
-

若草読書会のお花見
週間天気予報では降水確率60%で「曇り・雨」ということで、実施が危ぶまれた若草読書会のお花見でありましたが、その後天気予報も好転し、本日実施の運びとなりました。この花見、直近3年間は雨で流れていたのですが、仏の顔も三度まで、若草紳士・淑女の顔も三度まで、ということで、雨降らしの神様も流石に四度は、とご遠慮なされて、心置きなく過ごされよとて、曇り空の下、雨に降られることもなく、楽しいひと時を過ごすことができました。 花見の場所となっている花園中央公園はヤカモチの地元ということで、毎年場所取りはヤカモチの役目となっている。 今年も朝4時40分起床。身支度を整えて、愛車MTBにヒラリ飛び乗って5時に自宅を出る。途中、コンビニでサンドイッチと昼食用の弁当を買って、5時15分に花園中央公園に到着。既にブルーシートが敷かれていたり、ビニールテープで前夜に囲い込んだと見られるものなどもありましたが、早朝の5時過ぎとあっては、場所取りに困ることはない。 例年の場所にほぼ近い処に持参のシートを敷き、領有宣言であります。(花見の場所取り) シートも青春のブルーではなく、年相応にシルバーでありますが、これはそういう趣旨ではなく、銀輪家持だからシルバーなのであります。 シートを敷いて、これまた持参のタオルを水で濡らして、せっせと拭き掃除。片付いた処で、持参の電気カミソリで髭剃り。(同上・反対側から)(同上・北側から<少し遠くから>) そして、サンドイッチと珈琲で朝食。 シートから西側に少し離れた処に、前夜の花見客の狼藉の跡、発見。(前日の花見の狼藉の跡) 焼肉かバーベキューかは知らぬが炭と網に箸やら何やらのゴミが散らかされたまま。この公園はバーベキューなどは禁止の筈だが。それはさて置くも、このように後始末もちゃんと出来ない方々はお花見をする資格がありませんな。 暫くして、この近くにシートを敷いて場所取りをした青年が、目に入ると気分が損ねるとこれを片づけ始める。小生も手伝って一緒に片づける。人間することもなくボーっと場所の番をしているより、能動的に身体を動かしている方がいい。丁度良い仕事になりました。(これは情けない光景です。) 6時半になるとラジオ体操が始まりました。(朝6時半になるとラジオ体操が始まりました。) 同じく場所取りをしている人や犬の散歩に来られた人と立ち話をしたりと退屈を紛らせるが、集合時間は午前11時なのだから先は長い。 公園の清掃トラックがやって来て、ゴミ置き場のゴミの山を回収して行く。「手伝いましょか」と小生。そのオジサンと一緒に、ゴミをビニール袋に詰めてトラックの荷台へと放り投げる。たちまち荷台がいっぱいになって行く。 ひと仕事終えて、手を洗う。「足」を洗ったり、「首」を洗ったりすると、違う意味になるので、洗うのは勿論「手」だけである。そんなことをしていても時間はまだたっぷりとあるから厄介(笑)。 で、手あたり次第、桜を写真に撮ることに。これぞ、花見であります。(花園中央公園の桜たち)(同上・オオシマザクラ)(同上・オオシマザクラ) (同上) (同上)(同上・ソメイヨシノ) (同上・シロヤマザクラ)(同上・オオシマザクラ) (同上・ソメイヨシノ) そうこうしているうちに、10時10分、和麻呂さんが到着。昨夜彼から電話があり、10時過ぎには現地に行くようにする、とのことであったが、その通りに早めに来て戴けました。(同上) 続いて、祥麻呂さん到着。そして、智麻呂・恒郎女ご夫妻到着。続いて、小万知さん。更に凡鬼・景郎女ご夫妻と槇麻呂さん到着。 以上9名でお花見開始。と言っても、お弁当を開き、持参の酒やビールやワインを飲むということに過ぎないのであるが。ともかくもお花見である。飲み、食い、とりとめもない話。時折、はなびらがハラハラと舞い落ちて来る。(同上)(同上) 午後2時頃まで花園中央公園で過ごすという計画であったが、12時半を少し過ぎた頃に、何となく引き揚げる空気に。後片付けをし、智麻呂邸に場所を移すこととなる。 そんなことで、墓参を済ませてからコチラに向かうとされていたリチ女さんは間に合わないこととなったので、直接、智麻呂邸に向かうよう電話連絡。 恩智川の西洋芥子菜の群れ咲く景色や川べりの桜並木などを楽しみつつ、智麻呂邸へ。智麻呂邸前では、ひと足早く到着されていたリチ女さんと合流。 智麻呂邸での二次会では、最近に景郎女さんが長年やって来られた子ども文庫活動でさる財団から功労賞を授与されるという目出たいことがあったので、そのお祝いにと花束贈呈し、彼女から感想など関連するお話を伺いました。 <追記>若草メールで景郎女さんからお礼の言葉と共に花束の花の写真が送ら れて来ましたので、掲載して置きます。(2016年4月5日) その後、偐山頭火さん(同氏は都合により欠席)、リチ女さん、祥麻呂さん、小万知さんが作られた短歌と凡鬼さんが作られた俳句のお披露目を致しましたが、その途中に香代女さんが来られて参加。これで総勢12名となりました。 続いて、恒例のタコ焼きパーテイーへと移りましたが、ここで、小生は所用があって退席、その後のことは存じ上げませぬ。 今日の凡鬼さんの句に「蓑虫庵連子窓より初ざくら」というのがありましたが、それを文字って「若草庵連子窓より姥ざくら」という憎まれ口を残して帰途につきました。恒郎女さんの「くやしい~」の声を背後に聞きつつ(笑)。 肝心のお花見の宴会の写真が1枚もありません。皆を待っている間の写真ばかりで、宴会が始まるとカメラのことはすっかり脳裏からは消えていました。 では、今夜はこれにて失礼。若草読書会の皆さま、楽しい時間を有難うございました。 最後に、桜広場の一角にあったクヌギ。これも沢山の花を咲かせていましたが、誰もこれを花見の対象とはしませんな。せめてもヤカモチさんが眺めてあげることと致しましょう。(花園中央公園のクヌギの花) (同上)
2016.04.03
コメント(10)
-

墓参・カラスもスズメも
本日、4月2日は亡き娘の祥月命日。と言っても娘が亡くなったのは遠い昔のこと。毎月その命日に墓参するのは困難。また、父や祖父母、幼くして亡くなった妹などの命日もあり、その全てに墓参していては、連日の墓参となってしまうので、墓参は原則として月一回、皆の分をまとめて初旬に、というのが小生の墓参のスタイル。今日は偶々娘の祥月命日に当っていたと言うに過ぎない。 昨日は雨のパラつく生憎のお天気であったが、今日は青空の好天気。桜も満開にて、花の下行く墓参り、でありました。 しかし、桜は、明日がお花見の日なので、本日の記事には登場しません。登場するのはハコベだのカラスノエンドウだのと言った野草と言うか、雑草であります。(ハコベ) これは、墓参に出掛けようとして庭の片隅に咲いているのに気付いたハコベです。(同上) 花弁が10枚あるように見えるが、これは1枚の花弁の中央の切れ込みが深くなって2枚に見えるからであって、実際は5弁の花なのである。 3月19日の記事に掲載のハコベは花弁の切れ込みの浅い種類のものなので、見比べて戴くといいでしょう。 (同上) さて、墓参恒例のお寺の門前の言葉。本日はこれでした。(本日の言葉) スッキリ晴れて空気も澄んで眺めはくっきり、六甲の山々も淡路島も見える。(墓地からの眺め) アベノハルカスもよく見える。(アベノハルカス) 墓地と墓地の境目や通路脇にはカラスノエンドウが花を付けていて、モンシロチョウが飛び回っているのでありました。(カラスノエンドウ)(同上) カラスノエンドウがはびこる中、石垣の片隅に遠慮がちに咲いていたのはこの花。カラスノエンドウを小さく細くしたような草花。多分、スズメノエンドウなんだろうと思うが、カスマグサというのもあるらしい。 カラスノエンドウとスズメノエンドウとの中間位の大きさで「カラス」と「スズメ」の間と言うことで「カスマグサ」と呼ばれるらしいが、スズメノエンドウとの区別はヤカモチの手に余ることなので、これはスズメノエンドウということにして置きます。(スズメノエンドウ)<追記> これはどうやら、カスマグサのようである。スズメノエンドウはこれよりも更に小型の花のようです。スズメノエンドウは極小の花を沢山付けるのに対してカスマグサは小型の花を少数付ける、というのがWikipediaの説明。また、カスマグサの花の特長として青い縞模様というネット記事もありました。これらを総合するとこれはカスマグサとするのが順当なようです。遅ればせですが、カスマグサに訂正して置きます。(2016.5.3.)(同上) カラスノエンドウ位の大きさになると花も肉眼で見て取れるが、スズメノエンドウ位のサイズになると肉眼では詳細な部分は殆ど判別不能。 従って、カメラが捉える映像によって、その可憐な姿にあらためて感動するという、小さな花ならではの面白さがある。何やら宝石のような美しさではないか。スズメも捨てたものではない。
2016.04.02
コメント(12)
全17件 (17件中 1-17件目)
1