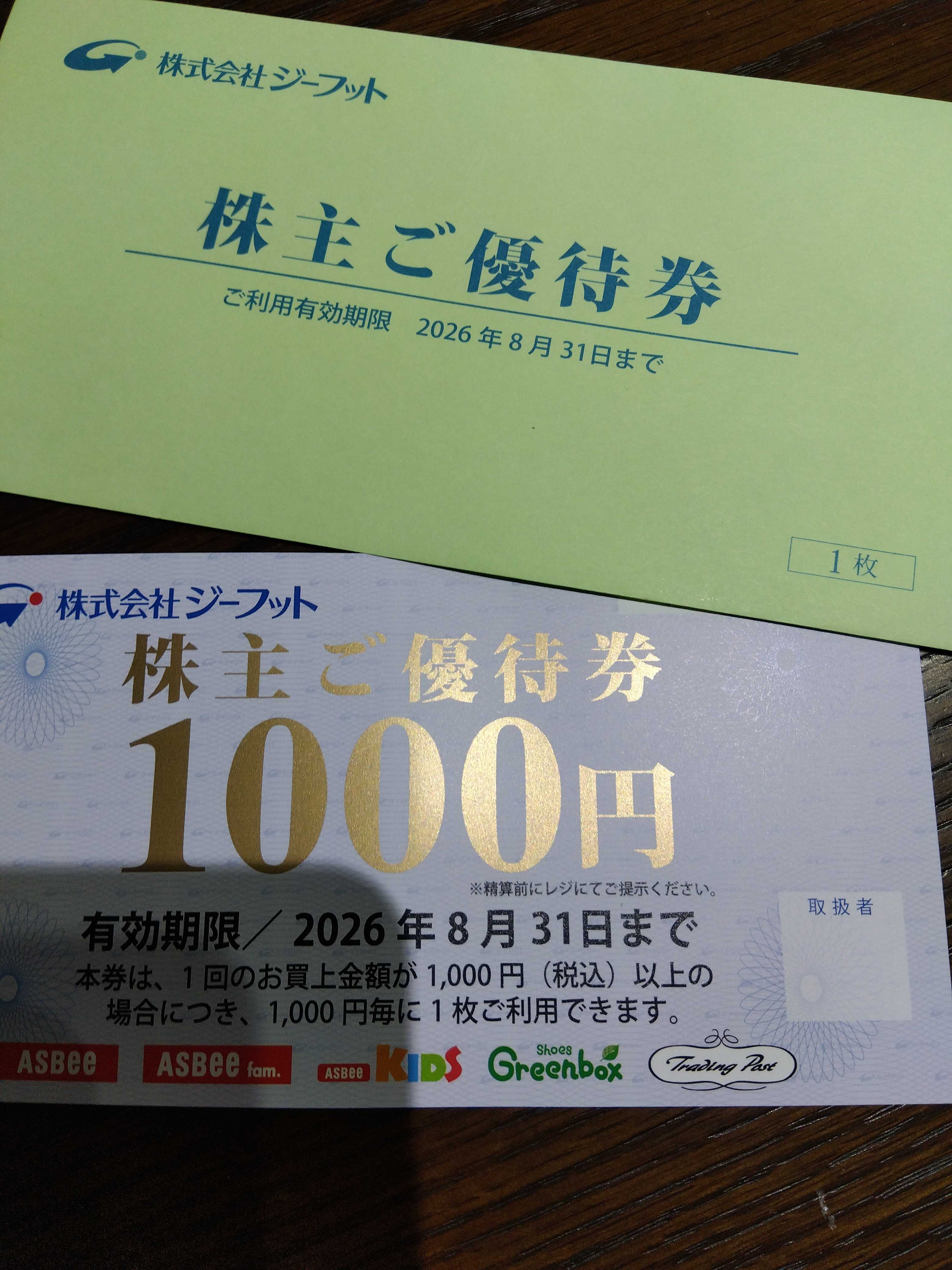2017年01月の記事
全18件 (18件中 1-18件目)
1
-

岬麻呂旅便り199・富良野
本日は、岬麻呂旅便りです。14日に続いての今年2回目の岬麻呂旅便りとなります。 前回は沖縄・与那国島でありましたが、今回は真逆の厳寒の北海道・富良野でありました。岬麻呂氏は小生よりも少し年長。この行動力には敬服のほかなし、であります。 そして、富良野と言えば、わがブロ友のfurano-craftさんの居られれる地。小生は富良野は未踏の地にて同氏とは直接にお会いしたこともないのですが、岬麻呂氏は当ブログのご縁で、同氏のことをお知りになり、既に2度同氏とお会いになって居り、今回もお会いになられたようで、随分と親しい交流が実現しているようであります。 (ふら麻呂ことfurano-craft氏)(木力工房・furano-craft氏の工房) 上左の写真は「furano-craftさんは、ブログなどネット上でご自身の画像を公開されているので、貴兄ブログにこれを掲載されるか否かは貴兄のご判断に委ねます。」とのコメント付きで岬麻呂氏が送って下さったものであります。 確かに、その通りであり、よく写っている写真でもありますので、小生もそのまま掲載することといたしました。furano-craft氏からのご了承は戴いて居りませんので、何らかの不都合があるようなら、今後削除もあり得るという留保付きの掲載であります。 さて、furano-craft氏と言えば、目下の処、富良野での個人住宅向け除雪サービス事業のプロジェクトを企画され、その立ち上げに奔走されています。 クラウドファンドでの第一目標金額は無事達成となり、プロジェクトの成立は確定したようで、ご同慶に存じ上げる処でありますが、更にも内容の充実を目指し、第二目標を設定、2月3日の支援募集期限までの、只今カウントダウン中にて、更なる支援を求めて居られます。 小生のブロ友さんでも既にご支援を賜っているお方が居られますが、更なるご支援をというお方が居られましたら、コチラからよろしくお願い申し上げる次第にて候。 岬麻呂氏もクラウドファンドとは別口でご支援を賜った由にて、有難いことでございます。 さて、話が横道に入ってしまいましたが、岬麻呂旅便りに戻ります。 <参考>過去の岬麻呂旅便り関連記事はコチラから。 例によって、旅の詳細は、ご本人の下掲「旅報告199」をご参照いただくこととし、ヤカモチの余計な説明は省略であります。掲載写真は全て、画像をクリックすると、フォト蔵画面に変り、更にその画像をクリックすると特大サイズの画面になります。旅報告もこれでご覧戴くと字も大きくなって読みやすいかと存じます。 この操作も面倒という向きもおありかと、「旅報告」については、キャプションの隣に「コチラ」というのを貼って置きました。これをクリックすると、直ちに特大サイズに切り替わりますので、ご利用下さい。(旅報告199・富良野 特大サイズでご覧いただくにはコチラ。) では、岬麻呂氏撮影の北海道の雪景色をお楽しみ下さい。(富良野盆地の冬の遊び<カイトを使ったスノーボード滑走>)(十勝連山の彩雲<日の出直前>)(白髭の滝))(旭岳ロープウェー山頂「姿見駅」)(層雲峡)(北西の丘展望台<美瑛>)(新栄の丘<美瑛>)雪や雪 雪雪雪や また雪の 北の旅行く をのこや一人 (大雪旅人)(富良野鳥沼公園)
2017.01.31
コメント(4)
-

第18回和郎女作品展
第18回和郎女作品展 本日は、今年2回目の和郎女作品展であります。 昨日29日開催の若草読書会にお持ち下さった沢山の作品から、ヤカモチが撮影したものをご紹介申し上げる次第であります。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 毎年、正月にその年の干支に因んだ押し絵作品を沢山作り、若草読書会の新年会参加者へのお土産にとお持ち下さるのですが、今年も例年通りにお持ち下さいました。昨年11月の読書会で、十二支すべての動物を貼り付けた押し絵のタペストリーを皆に下さったので、今年からは個別の干支の押し絵はないのではないかとも予想されたのですが、さに非ずで、今年もお持ち下さったという次第。かくて、今年は2回目の作品展を早くも開催できる運びとなりました。 今年は酉年。とりどりのトリの押し絵をお楽しみ下さいませ。 (鶏の壁掛け) (見とり、聞いとり、言うとり) 上掲左の壁掛けは、当日欠席のひろみの郎女さんにお渡しすべきものとして、ヤカモチが預っているもの。早くお届けしないといけないのであるが、本日現在、まだ果たしていません。松と竹と梅と尾長鶏のお目出度い図柄であります。壁掛けの 押し絵の鶏の しだり尾の ながくは持たず はや届けなむ (鶏家持)(本歌)あしびきの 山鳥の尾の しだり尾の ながながし夜を ひとりかもねむ (柿本人麻呂 拾遺集778 小倉百人一首3)と思っていますので、明日か明後日には・・(笑)。 上掲右は鶏の三態セット。去年の猿なら「見ざる、聞かざる、言わざる」となるが、鶏とあっては、そうも行かず、ヤカモチさんが大阪弁で「見とり、聞いとり、言うとり」にしてみました。「見とり」は「見て置きなさい」、「聞いとり」は「聞いて置きなさい」、「言うとり」は「ゆうとり」と発音し、「(勝手に)言ってなさい」と言う意味である。 その意味するところは、申年と違って酉年は、しっかり見て、聞いて、そして、それに丸め込まれるのではなく、しっかりした批判精神を以って己を持することが必要なのだ、ということなのであります。 そこのアナタ、ちゃんと聞いトリますか!! そこのアナタ「勝手に言うトリ。」(鶏の壁掛け・丸型) 丸型の壁掛け。幸運祈願とありますから、願掛けの壁掛け、という洒落になって居ります。(鶏の壁掛け・菱型) 菱型の方は、智に働けば角が立つ、とて角を予め欠いて居ります。 情に棹させば流される。「棹」が見当たりませぬ。既に、情に棹さして、棹も船も流されてしまったのであるか。 板に願掛けりゃ痛い目に合う、とて「願文」の文字もありませぬ。 まあ、これを壁に掛けて、願は掛けずに頑張りなさい、という戒めの板なのでありますな、これはきっと(笑)。(鶏の押し絵・満月と鶏なので「月鶏」) 古来、月には桂の大木が生えていて、玉の兎が住んでいるとされて居り、月が黄色く色づくのは、その桂が黄葉するからとされている。また、月のことを玉兎と呼ぶのもこの言い伝えによるもの。因みに太陽には3本足のカラスが住んでいるとされ、太陽のことを金烏とも言いますな。 しかし、偐万葉伝説では、兎ではなく鶏が住んでいるとされ、これを月鶏と呼ぶ。伏見の酒屋では月桂冠という酒があるそうだが、偐万葉の里、明後日村では酒は「月鶏冠」に限ると言って居るそうな。(鶏の押し絵・小判と鶏で「判鶏」) 人は小金を蓄えると、それを盗まれまいと番犬を飼ったりもするが、偐万葉の里では小判は鶏に守らせるのが相場となって居る。 盗人は夜陰に紛れてやって来るもの、夜明けは壬生忠岑さんに言われるまでもなく「あかつきばかりうきものはなし」と嫌って居る。従って、鶏が鳴くと一目散に逃げ出すのが彼らの習い。 そこで鶏を仕込んで、見慣れぬ奴を見ると「コケコケ、モオケッコー」と鳴かせるようにして、夜盗を追い払うのだそうな。そのような鶏を「判鶏」という。(鶏の押し絵・金糸銀糸と鶏で「糸鶏」) だんだん、ヤカモチも面倒臭くなって来た。与太話も一つ二つは面白く、でっち上げるのも楽しいのであるが、飽きるのも早いヤカモチは三つ目あたりから不機嫌になって来る(笑)のでありますな。 よって、三つ目の「糸鶏」については、作者の「意図」が分からぬなどと八つ当たりするのであります。それを清少納言とかいう女は「いとをかし」なんぞと言うから、いと胸糞悪い。(鶏の押し絵・南天と鶏で「南鶏」) この南鶏は、小生が貰って来たものにて、わが家に鎮座して居ります。 南渓和尚と言えば、只今放送中のNHK大河ドラマに登場の龍潭寺の坊主であるが、「諸行無常じゃ」が口癖ですかな。こちらの南鶏は「職業不詳じゃ」が口癖であるが、その実、何の職業にもつかず、銀輪散歩をしているだけの遊び人にて、ヤカモチさんと同類のトリなのであります。 この南鶏、遊び人にしてはバタバタし過ぎる点が難点であるということで、南天の実を描き添えたのであって、決して「難を転じる」なんぞという意図ではないのであります。(鶏の羽子板) 羽子板の形をした、これは自身で立つこともできる代物にて、なかなかの力作。まあ、羽子板は昔から押し絵と決まって居るから、これはその伝統に立った作品ということで羽目を外してはいないのでありますな。 (掛け軸・苺と椿) そして、最後は掛け軸型の押し絵。 と言っても、押し絵を貼った色紙を掛け軸型のものに嵌めるだけという簡易な仕掛けにて候へば、押し絵か嵌め絵か分からぬではないか、という見当はずれの批判もあるそうな。 ここで、ようやく鶏から離れて、苺と椿の登場であります。 されば1首。押し絵嵌め 苺と椿 並べるは 掛け軸やそれ 垂れもこそすれ (苺内親王家椿)(本歌)おとにきく たかしの浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ (祐子内親王家紀伊 金葉集501 小倉百人一首72) 以上です。本日もご覧下さり、有難うございました。 なお、ヤカモチ解説の中に於いて数々の不適切な冗談のありましたこと、トリあえず、謹んでお詫び申し上げます。
2017.01.30
コメント(8)
-

1299歳になりました・若草読書会新年会
今日は、偐家持の誕生日。満1299歳に相成りまして候。 そのめでたき誕生日に若草読書会の新年会が重なりました。 出席者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼氏、謙麻呂氏、小万知氏、祥麻呂氏、槇麻呂氏、りち女氏、和郎女氏、偐家持の10名、遅れて午後2時頃から香代女氏が参加されて計11名でありました。 読書会の新年会はヤカモチが万葉関連のテーマで話をする、というのが、この処の恒例になっていて、今年は「大伴家持周辺の人々の歌」というテーマで、大伴家持の祖父母を始め、周辺のご親戚の歌を取り上げ、鑑賞いたしました。 家持の祖父・大伴安麻呂の歌(巻2-101) 家持の祖母・巨勢郎女の歌(巻2-102) 家持の同母弟・大伴書持の歌(巻17-3910) 家持の妻・坂上大嬢の歌(巻4-581~4、729~31) 家持の叔母、義母・坂上郎女の歌(巻4-527、661、巻8ー1433) 家持の叔父・大伴田主の歌(巻1-127) 大伴池主の歌(巻17-3967~8) 大伴宿奈麻呂の歌(巻4-532~3)などを取り上げました。父・大伴旅人については、一昨年の新年会で取り上げたので省略し、最後に「偐家持」の歌(偐万葉集巻?-7335)を取り上げました(笑)。大伴家持との関係については、配布資料の記述では「家持を勝手に名乗る正体不明の怪人。但し、偐山頭火ほどには怪しくないというのが通説である。」とありました(笑)。 <追記2017.1.30.>上記の万葉歌等はコメント欄に注記1、注記2として記載し て置くことといたしました。 万葉の話の後は各自任意持ち寄りの短歌・俳句の披露会。提出者は、偐山頭火、祥麻呂、謙麻呂、小万知、景郎女、凡鬼各氏と偐家持の7名。偐山頭火氏と景郎女氏は都合により不参加でしたが、歌壇の方には歌・句をご提出下さいました。 ひろみの郎女氏(ブロ友・ひろみちゃん8021さんのこと、本日はご欠席でした。)がご紹介下さったという近くの寿司屋からの出前の寿司や持ち寄りの食べ物、酒などで、昼食というか宴会、雑談となり、デザートが出て、珈琲タイムが終了した処で、恒例の歌留多会となりました。男女別に分かれてそれぞれの組で札を取り合うということとなり、凡鬼さんが最多枚数獲得で優勝となり、優勝賞品獲得。準優勝はそれに次ぐ枚数獲得で恒郎女さんとなりヤカモチ賞の賞品獲得。ラッキー賞(優勝者が任意に引いた札と同じ札を取っていた人に贈られる賞)は小万知さんとなり、その賞品を獲得されました。 最後に、和郎女さんがこの日のために制作下さった押し絵作品の抽選会。(この押し絵は追って当ブログでご紹介申し上げます。)各自当選の作品を持ち帰りとなりました。また、ひろみの郎女さんと偐山頭火さん提供の賞品を参加賞として分配、めでたくお開きとなりました。 終了して、智麻呂邸を辞したのは午後6時過ぎ、降り出した雨の中を帰途につきました。次回の4月2日のお花見会の再会を約して。 ということで、写真は何と言ってないのでありますが、智麻呂邸の前の公園に植わっていた紫陽花がドライフラワーのようになって面白い姿であったのを撮影しましたので、それを掲載して置きます。 あぢさゐの 八重に咲くとも 生き過ぎて 立ち枯れになせそ 冬のあしたに (偐家持) ヤカモチ1299歳の誕生日とあれば、上のような花こそが似合いというものであるが、わが身世にふるながめせしまに、では悲しかろうと思われたか、小万知さんが花束をご用意して下さっていて、これを贈呈いただきました。帰宅して花瓶に生けたのが下の写真です。写真を加工して周囲を暗くしてみました。その心は、「立ち枯れ・たちがれ」は免れたものの、依然として「黄昏・たそがれ」は免れない、であります。(偐家持1299歳誕生日祝花)<参考>過去の「若草読書会」関連の記事はコチラから。
2017.01.29
コメント(9)
-

連続の新年会
25日、26日と新年会が続きました。 25日は健人会の新年会。今日26日はSS会の新年会でありました。 29日には、若草読書会の新年会がありますが、新年会はこれで終了となります。 20日は母の満中陰法要にて、ヤカモチも忌明けとなりましたので、新年会に出てもよかろうという次第。 (小ぼけ・京阪淀屋橋店) (ナンクルナイサ・きばぃやんせ~) 25日の健人会の新年会は、淀屋橋の「小ぼけ」という店(上掲写真左)で、午後6時開会。参加者は、木〇氏、杉〇氏、只麻呂氏、鯨麻呂氏、田〇氏、平〇氏、近〇氏、竹〇氏、岡〇氏、今〇氏、徳〇氏、森〇氏、正〇氏、木☆氏、関〇氏、生〇氏、草麻呂氏とヤカモチの18名。 26日、今日のSS会の新年会は、梅田、ヒルトンプラザイーストB2にある九州沖縄料理店「ナンクルナイサきばぃやんせ~」(上掲写真右)で、同じく午後6時開会。参加者は、福〇氏、福☆氏、中〇氏、川〇氏、古〇氏、山〇氏、松〇氏、矢〇氏、石〇氏、早〇氏とヤカモチの11名。 この店の名前は沖縄弁と鹿児島弁で構成されている。沖縄弁「なんくるないさ~」は「(これだけ頑張ったんだから)何とかなるさ」の意。鹿児島弁「きばぃやんせ~」は「頑張りなさい」の意。 これを大阪弁で言い換えれば「何とかなるさかい、頑張りや~」でしょうか。 この店で、与那国島の泡盛「どなん」を福〇氏が注文して呑まれたので、その名の由来を先の岬麻呂旅便りで知ったばかりであったので、ひとくさり講釈。勿論、岬麻呂氏からの便りで知ったことであるということは付言して置きました。福〇氏からの話でアルコール度数が60度だということも知りました。 <参考>岬麻呂旅便り198 2017.1.14. 本日の記事は備忘録程度にとどめて、これでおしまい。 なんくるないさ~。
2017.01.26
コメント(8)
-

明日香銀輪散歩(その2)
(承前) 昨日の記事は文武天皇陵へと向かう処で終わりましたので、そこから始めます。 フォト蔵写真へのアクセスが何故かうまく行かない。画面の切変わりが駄目で、呼び出した画面(写真)が表示されないのである。わがPCに原因があるのかも知れないが、そんな風になるのはフォト蔵だけなので、フォト蔵の方に原因があるのではないか、と勘ぐっている次第(多分、フォト蔵へのアクセスが集中して繋がりにくくなっているのだろうと推測しているのだが)。そんなことで、ブログの記事アップが遅々として進まない。 それはさて置き、文武天皇である。 文武天皇は、天武天皇と皇后鵜野讃良皇女(後の持統天皇)との間に生まれた草壁皇子と阿閇皇女(後の元明天皇)との間の子、軽皇子である。皇太子であった草壁皇子が亡くなった時は、軽皇子は未だ幼かった。そこで、皇后が天皇に即位して持統天皇となり、軽皇子の成長を待つこととなる。 成長して皇位につくものの、彼も病弱であったか、その子の首皇子(後の聖武天皇)が幼い時に亡くなってしまう。またしても、首皇子が成長するまでの繋ぎとして、母の阿閇皇女が即位し元明天皇となる。その娘・氷高皇女(文武天皇の姉、首皇子から見れば伯母)がその跡を継ぎ、元正天皇となることを経て、ようやくに聖武天皇へと皇位が承継されることとなるが、この時期の皇位承継は何とも綱渡り的である。それもこれも、草壁・文武の父子二代にわたる病弱が原因であったと言うべきか。(文武天皇陵) 文武天皇陵に来た時には雪がチラつき出していたが、急に激しく降り出した。下掲左の写真に白い横線が沢山写っているのは、風が吹きつけて来る雪である。 小生は直ぐに止むだろうと見て、雨具は着込まなかったが、蝶麻呂君は上下雨具の着用を始める。小生はそれを待ちながら煙草を一服。雨用の上衣を着て、雨用のズボンを穿く、それに要する時間は煙草一服の時間よりも少し長くかかるということを発見した次第(笑)。漸くに雪対策が整い、わが待つ場所に蝶麻呂君がやって来た頃には、雪が小止みになっていたのは皮肉なことでありました。 (同上) 文武天皇陵から坂を下って行く。桧隈寺跡のサインに従い行くとこの鳥居(下掲写真)の前に出ました。於美阿志神社である。 「おみ足神社か?」と蝶麻呂君。説明碑によると、「阿智使主・あちのおみ」を祭神とする神社とあるから、「あち・おみ」が入れ替わって「おみ・あち」となって「おみ・あし」神社となったものだろう。 阿智使主は阿智王、阿智吉師とも呼ばれ、後漢の霊帝の曾孫にして、東漢氏の祖とされる人物であるが、百済から渡来した東漢氏が祖先伝承として作り上げたものという指摘もある。桧隈寺は東漢氏の氏寺であり、当地に両社寺が併存していたのであろう。(於美阿志神社)(同上・拝殿)(同上・本殿)(桧隈寺跡・於美阿志神社説明碑)(檜隈寺跡説明板) 本殿の右奥には十三重石塔があって、此処が寺跡でもあることを主張している風でもある。(十三重石塔) 境内には、大正14年建立の宣化天皇檜隈盧入野宮趾碑がある。 宣化天皇は継体天皇の二男。父継体天皇亡き後を継いだ長男の安閑天皇も子のないままに亡くなったので、二男である彼が皇位につき第28代宣化天皇となる。本名(諱)が檜隈高田皇子であるから、檜隈(檜前)の地に深い縁があったものか、即位後直ちに、檜隈の地に宮を遷している。(「元年の春正月に、都を檜隈の盧入野<いほりの>に遷す。因りて宮号となす。」<日本書紀宣化天皇元年の条>)(宣化天皇檜隈盧入野宮趾碑) 日本書紀では、宣化天皇は人柄・器量が清らかで、人並みより優れ、才や地位を人に誇らず、王者ぶった顔もしない、人物と評している。宣化即位後、それまでの大連・大伴金村、同・物部麁鹿火に並んで、蘇我稲目を大臣に抜擢している。桧隈は東漢氏所縁の地、東漢氏はこの時期は蘇我氏の与党的一族であったこと、その地に宮を遷していること、などを考えると、宣化天皇は蘇我氏と深い縁があり、蘇我氏のバックアップによって天皇位についたのかも知れない。何れにせよ、稲目・馬子・蝦夷・入鹿へとつながる蘇我氏政権時代の幕開けをした天皇が宣化であったということになる。 <参考>宣化天皇陵の写真・記事は下記をご覧下さい。 明日香・橿原銀輪散歩(その2) 2014.3.20. 桧隈寺跡からキトラ古墳へと向かうのが予定コースであったが、キトラ古墳は中止し、来た道を引き返す。再び、飛鳥歴史公園への坂に取りかかり、これを越えると目に入って来るのが天武・持統合葬陵である。(天武・持統天皇合葬陵)(同上説明碑) 明日香というと亀石であり、元祖ゆるキャラみたいなものであるが、蝶麻呂君は実物を見たことがないというので、見て行くことに。まあ、蝶は花であり、亀には縁がなさそうです。(亀石) <参考>天武・持統天皇合葬陵、亀石の写真掲載の過去記事は下記です。 明日香小旅行下見・番外編 2009.11.26. 橘寺も遠望して、パス。門前素通りである。 謎の石造物を巡るというテーマなら、この寺の庭の二面石なども見て行くべきであるが、今回は何のテーマもない蝶との銀輪散歩、あちらへひらひら、こちらへひらひらである。(橘寺) テーマは無くとも、万葉歌碑は見逃せない。 まして、これは犬養万葉歌碑の一つである。(犬養万葉歌碑・万葉集巻16-3850)(同上副碑) はてさて、この歌ではないが、我が国もこの世界も、この先どのようになって行くのでありますやら。そして、わがブログもこの先どうなりますものやら。言の葉も 無駄に繁けき わがブログ この先いかに たづき知らずも (偐家持) 歌碑の道向かいは、川原寺跡。(川原寺跡)(同上説明碑) 板蓋宮趾に立ち寄る。皇極天皇の時代ここで蘇我入鹿の首が刎ねられ、大化の改新ということになるのであるが、壬申の乱の後、天武天皇が営んだ飛鳥浄御原宮もここであったということらしい。 下掲写真の後方の丘が甘橿丘である。蘇我氏は此処に邸宅を建てたらしいが、宮殿を見下ろす位置になる。飛鳥川はその甘橿丘の前を流れている。(板蓋宮趾) ほぼ、正午となったので、昼食にしようと、食堂・めんどやに行くが、生憎の定休日。ならば、万葉文化館の前のレストランにしようと行くが、万葉文化館も月曜日が定休日のようで、前のレストランや土産物店もお休み。 仕方なく、飛鳥寺、飛鳥坐神社へと走りながら、昼食のできそうな店を探すが、全て定休日であったり、「本日は予約客のみ」や「本日貸し切り」などの札が掛かっていて、アウトである。(明日香の白梅)(飛鳥寺) 飛鳥寺に初めて来たのは高校時代であったろうか。もう大昔のことである。その頃は、観光客も殆ど無くて、閑散とした古寺。寺のどの場所であったのか、部屋に上がらせていただいて炬燵に入って熱いお茶をご馳走になり、お坊さんのお話を聞かせていただいた記憶がぼんやりとあるのだが、話の内容も何とは覚えて居らず、夢まぼろしかである。この日のように雪の舞う、寒い寒い日であったかと記憶する。(同上説明碑)(明日香観光エリアマップ<飛鳥寺門前の看板>) 飛鳥坐神社も蝶麻呂君は初めてのようなので、立ち寄ることに。(飛鳥坐神社) 蝶麻呂さんは、何かでこの神社の「おんだ祭り」というものを知ったらしく、それがこの2月5日にあるので、それに合わせて明日香銀輪散歩をしないか、という提案であったが、却下しての22・23日実施となった次第。 おんだ祭りというのは、毎年2月の第一日曜日に行われる奇祭にて、おかめのお面を付けた男性と天狗のお面を付けた男性が、男女の行為を面白可笑しく演ずるというものであるようだが、小生もこの祭りは見たことがないので詳細は知らない。(同上・由緒) 縁結び、夫婦和合、安産などの神様ということでか、境内には男女のそれを模した石が並べられていたりする。さしてリアルなものではないから言われてみないとそれとは分からない。(同上拝殿) (同上) (境内の万葉歌碑・会津八一書) 境内には万葉歌碑が3基ありました。 正面石段の中ほど右手にあったのが上掲右の歌碑。会津八一の書から該当する字を拾って万葉集巻13-3222の歌に嵌め込んで作った歌碑である。みもろは 人の守る山 もとへは あしび花さき すゑへは 椿花さく うらぐはし 山そ 泣く子守る山 (万葉集巻13-3222)(三諸の山は、人が大切に守っている山。ふもとの方には馬酔木の花が咲き、上の方には椿の花が咲く。美しい山だ。泣く子の守をするように人が大切に守っている山である。) その石段を上った処にあるのが、犬養先生書の犬養万葉歌碑(下掲写真左)である。大君は 神にしませば 赤駒の 腹這ふ田居を 都と成しつ (大伴御行 万葉集巻19-4260)(大君は神でいらっしゃるので、赤駒が腹這う田んぼを都になさった) この歌の作者、大伴御行は家持の祖父安麻呂の兄である。 (境内の万葉歌碑・犬養孝書) (境内の万葉歌碑・巻13-3229) 拝殿左下にあるのが上掲右の歌碑。斎串立て 神酒すゑ奉る 神主部の うずの玉蔭 見ればともしも (万葉集巻13-3229)(斎串を立てて、神酒を据えて奉る神主の髪飾りのカズラを見ると心惹かれる。) (注)斎串=「いぐし」神を祭る時に立てる神聖な串。 うず=木の葉や金銀を髪に刺したもの。 玉蔭=玉は美称。「かげ」はヒカゲノカズラのこと。 (折口信夫歌碑) 万葉歌碑ではないが、国文学者で歌人でもある折口信夫の歌碑もあったので掲載して置きます。ただ、碑文は摩耗して判読不能。板書の副碑も読み辛い。 帰宅後、折口信夫全集(中公文庫版)21巻・22巻で掲載全短歌をざっと見てみましたが、それらしき歌は見つかりませんでした。ほすすきに 夕ぐもひくき 明日香のや わがふるさとに なけれともしもほすすきに 夕ぐもひくき 明日香のや わがふるさとと 見ればともしもほすすきに 夕ぐもひくき 明日香のや わがふるさとと 行けばともしも 副碑記載文字も4句目の末尾から5句目が判読できないので、小生が勝手に付加してみたのが、青文字部分です。元の歌がこうであったかどうかは保証しかねます。墨あとの かすれて薄き 歌碑の字を 何ぞと行けど 尋ふ人もなき (偐家持) 昼食場所が見つからないので、犬養万葉記念館の喫茶コーナーでも軽食なら食べられることを思い出し、そこへと向かう。 何年かぶりの犬養万葉記念館である。 懐かしい犬養先生の講義の声が流されているのを聞きながら入館する。 (犬養万葉記念館) (マスコット人形と犬養先生生前ご愛用の車椅子)(犬養万葉歌碑) 中庭のこの歌碑は既に当ブログで紹介済みなので、説明は省略します。 <参考>明日香小旅行下見・番外編 2009.11.26. 記念館では、古代衣装の復元展示をしていて、その着付け体験会もやっていました。女性グループ4人組がその体験会に来られていました。館長の岡本さんらに男性用の衣装もあるので、どうぞと勧められて、昼食後、それを着つけて貰い、その女性グループと一緒に我々も飛鳥・奈良時代の貴族の衣装についての説明を受けました。(天皇と皇后の衣装) これは、聖武天皇と光明皇后の儀式用の服を復元したものだそうな。 (古代貴族の衣装) 上の左の写真は高松塚古墳壁画に描かれた人物像の衣服を復元したもの。裳には白や黒の縦縞が入っているが、奈良時代に入ると、白と黒は葬礼の色というのが定着し、このような白い線は入らなくなったそうな。 記念館に居る間に雪が沢山降って来ました。かくて、雨具を上下着込んで出発することとしました。前方がよく見えない位に雪が降って来たので、他へ足を延ばすことは止め、帰途につくこととしました。飛鳥川沿いを走って橿原神宮前駅へ向かうべしで走り始めましたが、前がよく見えない位に雪が降って来る。 この雪の降りしきる景色を何処か眺めのよい場所で写真に撮ろうと、撮影する場所を決めかねているうちに、雪は小降りになり、止んでしまいました。 水落遺跡に来た頃にはご覧のように雪はすっかり止んでいました。(水落遺跡)(同上説明板) 午後4時少し前に橿原神宮前駅北側のホテルに到着。預けてあった荷物を受け取り、自転車2台をホテルから宅配便で自宅へ送る手続きを済ませ、ホテル隣の喫茶店「サンド」で珈琲タイム。その後、阿倍野橋方面へと帰る蝶麻呂君と駅で別れ、午後4時53分発京都行き特急に乗車、大和西大寺へと向かいました。 これにて、明日香1泊2日にしては内容に乏しい銀輪散歩完了であります。お付き合い下さった皆さま、どうも有難うございました。
2017.01.24
コメント(4)
-

明日香銀輪散歩(その1)
友人の蝶麻呂君より連絡あり、明日香を銀輪散歩することとなった。 この季節、蝶は仮に生きているとしても「凍て蝶」と言って、じっと動かないものであるが、わが蝶麻呂君は冬になると、何処かへ出掛けないかと連絡してくる変わった蝶なのである。 それはさて置き、では、久々に明日香を銀輪で走ってみようということになったのであるが、小生は当然に日帰りの心算でいたが、彼の住まいが宝塚であるところ、「宝塚から明日香へ日帰りはちときついので1泊でどうか」という提案が急遽舞い込み、小生が橿原神宮前駅近くのホテルの予約を段取りする羽目に(笑)。 ということで、22~23日の1泊2日にて、銀輪散歩して参りましたので、その紹介をして置きます。 蝶麻呂君は現地にてレンタルサイクルを利用すると言ってましたが、わが家には軽量小型自転車・トレンクルが2台ありますので、それを使っていただくこととし、予め宅配便でこれをホテルへ送って置きました。 22日12時半、橿原神宮前駅近くの喫茶店にて待ち合わせということになったものの、彼が到着したのは午後1時を過ぎていました。小生は12時過ぎでありましたから、1時間近くも待ったことになる。その喫茶店で昼食を済ませ、宿泊することになっているホテルで送って置いた自転車を受け取り、銀輪散歩をスタートしたのは午後2時を大きく回っていました。加えて、雨が降り出すということもあって、初日22日は予定したコースの3分の1位の距離で切り上げることとなった次第。 先ず立ち寄ったのは久米寺。(久米寺・北側門) 久米寺の創建は不詳であるが、出土の古瓦から奈良時代前期には存在していたと推定されているようです。聖徳太子の弟の来目皇子が建立したという説もあるようですが、日本書紀に、大和平定に功のあった将軍大来目について「亦大来目をして畝傍山の西の川辺の地に居らしめたまふ。今、来目邑と号くるは、此、其の縁なり。」(神武天皇2年2月の条)とあることから、軍事氏族である来目氏の氏寺であったと見るのが順当な処でしょうか。 (同上・本堂) (同上・観音堂) (同上・多宝塔) (同上・七重石塔) 上掲右の写真の七重石塔は平安時代後期のものであるとのこと。 山門を入った直ぐの処に大塔礎石がある。 (同上・大塔礎石)(同上・山門) 山門が最後に登場したのは、我々が裏から入って来たからである。ヤカモチは大抵裏口から入って表から出て行くという「空き巣狙い」の行動様式が身に付いて居り、今回もそうなりました。 <追記2017.1.26.> 我々は東側の裏門から境内に入ったのであるが、そこには虫塚がありました。 蝶麻呂君は「これはわが塚」と早速に反応し、写真撮影して居りましたが、そ の写真をメール送信して下さいましたので、追加掲載して置きます。虫塚だけ に「無視」いただいても宜しいかと。 (虫塚) 山門を後にし、橿原神宮前駅西口の駅前ロータリーから西へと延びている国道133号に出て、これを西へと走る。 程なく高取川に架かる橋に出る。橋を渡った先にあるのが益田池の堤の残存部である。益田池というのは平安時代初期に高取川を堰き止めて造られた大貯水池であるが、その堤の残存部が国指定文化財になっている。 高取川は桧隈川とも久米川とも呼ばれる。久米の仙人が洗濯する女の脛を見て動揺、「愛心たちまちおこり」神通力を失って墜落したという有名な伝説に登場するその女性が洗濯していたのは、この高取川の川辺であったのでした。(益田池堤址) 「日本紀略」によると、益田池の着工は弘仁14年(823年)とのことであるが、天長2年(825年)作の空海の「益田池碑銘」というのが存在したことが、「平安遺文」金石文編に収められていることから分かるので825年には池は完成していたのであろう。 なお、益田池碑銘には「来眼精舎」という記述があり、これは久米寺のことだと考えられているとのこと。 諸行無常、池も今は無く、高取川も護岸がなされて洗濯できる場所もない。従って、洗濯女の脛に見惚れて自転車から転落という危険は、久米のヤカモチにはない、という訳である。 (同上) 雨も止み、益田池堤跡では日差しも射していたのであるが、更に西へと走っているうちに再び雨が降り出しました。 そんな雨の中、何処へ向かっているのかと言うと、大和高田市根成柿町にある天満神社なのである。受験シーズンとは言え、我々の目的は勿論合格祈願などではない。何ヶ月か前に、ネット記事で、この神社に柿本人麻呂の妻の墓がある、と書いてあるのを見つけ、機会があれば、その墓なるものを見てみようと思っていた処、今回の銀輪散歩はまさにその機会ではないかと考え、蝶麻呂君の意見も聞かずにヤカモチの一存で決めた天満神社でありました。(根成柿天満神社) はい、到着しました。 しかし、鳥居横の説明板(下掲左)には人麻呂の妻云々の文字はない。何やら悪い予感。黄金塚と称する層塔がそれかと思うものの、「神域」たる本殿などのある区域には入れない。拝殿脇から覗くものの、下掲右のような写真が撮れただけ。社務所にも人影はなく、尋ねる人も居ない。まあ、他人妻の墓であるから、そんなにムキになって探すのもいかがなものか、と諦めることとする。 (同上) 何の成果もなく帰るのは口惜しいと、境内にあったセンダンの古木を撮影して置きました。枯れかかったセンダンの老大木がひこばえにより甦り、実を付けている。センダンは楝(おおち・旧仮名あふち)である。人麻呂の 妻にはあはじ あふちの実 なりてむなしく 雨も降り来や (偐家持) 「あふち(逢ふ地)」が実っているというのに、目指す人麻呂の妻の墓には「あはじ(逢はじ)」とは、これ如何に、である(笑)。(同上・境内のセンダンの古木) 帰宅後、ネットで調べてみると、小生の記憶違いではなく、そういう記述のあるネット記事が確かにありました。 人文研究見聞録 「依佐良姫の墓は根成柿村の天満神社の境内にあるという。」 神社と古事記 「依佐良姫の墓は根成柿村(現大和高田市根成柿町)の天満神社の境内にある とされ、」 予定では、この後、益田岩船から飛鳥駅前経由、高松塚古墳、キトラ古墳などを巡って石舞台などのある明日香の中心エリアに戻って来るという企画でありましたが、雨が本降りとなったため、中止。ホテルに帰ることとしました。 今日23日は、昨日中止した残りのコースを走り、後は気分の赴くままにということで、ホテル前を午前8時半頃に出発。先ず、益田岩船へ。 橿原神宮前駅西口から国道133号を西へ。これは昨日走った道。益田池堤の手前の辻を左(南)に入り、鳥屋近隣公園を左に見て、南進。やがて長い上り坂。ほぼ上り切った処の右側に益田岩船の登り口がある。益田岩船は何度か来ているが、直近に来たのは1994年9月であるから、20年以上も前のことになる。その当時は自然のままの細い道を草掻き分けながら上ったような記憶があるので、見違えるばかりに整備された現状は驚きでありました。(益田岩船への登り口)(益田岩船説明板) この巨石遺物が何であるかについては諸説あるようで、前述の益田池碑の台石説、占星術の天体観測台説、火葬墳墓説などもあるが、近くにある牽牛子塚古墳の発掘調査によって、同古墳の石槨の形状が益田岩船のそれと酷似していることから、横口式石槨の建造途中で、ひび割れが生じたため放棄されたもの、とする説が有力になっている。(益田岩船) (同上)(同上) 巨大な岩であるが、その大きさがどの程度のものであるかを知って戴くには、蝶麻呂君にご登場いただくのが一番でしょう。(下掲写真) (益田岩船と蝶麻呂君) (同左) <追記2017.1.26.> 右の写真は蝶麻呂君から送信されて来たもの。撮影者はヤカモチであるが、カ メラが蝶麻呂君のものであります。こういう場合、写真に著作権が成立すると したとき、著作権はやはり撮影者ヤカモチにあると言うべきか、蝶麻呂君のカ メラで異議を留保せず撮影したことは黙示的に著作権を蝶麻呂君に移転すると いう行為となり、著作権は蝶麻呂君に帰属すると言うべきなのか、どちらなん でしょう(笑)。どちらであれ、蝶麻呂君の姿はカラスアゲハ風にして置きま した。 益田岩船から近鉄吉野線に沿った細道を行き、飛鳥駅の北西側にある岩屋山古墳の近くに出たので、これに立ち寄って行く。 岩屋山古墳は7世紀代築造の方墳。詳しくは下掲の説明板をお読み下さい。(岩屋山古墳)(同上・説明板) 石室に入ってみた。 奥の玄室から石室入口を眺めた景色が下掲右の写真です。 (同上・石室) 墳丘にも登ってみた。 墳丘上には桜の木が何本も植えられている。 花の時期にはこの墳丘上でお花見というのも悪くはない気がしますが、お墓の被葬者が何と仰るか。まあ、石室内は空っぽですから、被葬者がお留守の空っぽの墓。問題はないということになりますでしょうか。この方墳は既に西半分が削られて存在せず、民家が建っているのでもあれば、墳丘上でのお花見を不敬とするのは、今更何を、という感じですかな。(岩屋山古墳の墳丘の上から多武峰方向を眺める) 墳丘上からは多武ノ峰や吉野の山々が一望であります。このような景色はパノラマ撮影でないと収まりません。(同上パノラマ写真)拡大画面はコチラ。 この岩屋山古墳の西側には牽牛子塚古墳があるのだが、今回はパスして、東に向かい、近鉄吉野線の踏切を渡り飛鳥駅の前に出て、高取川を渡り、飛鳥歴史公園に入る。(中尾山古墳<写真右手に見えるのが墳丘か。>の裏を通って) 歴史公園地域に入ると、先ず中尾山古墳がある。この古墳は文武天皇の御陵ではないかと言われているのであるが、宮内庁が文武天皇陵としているものは、高松塚古墳の南側にある。(同上パノラマ写真)拡大画面はコチラ。 高松塚古墳に向かう。昭和47年(1972年)の発掘調査で彩色壁画が発見されて話題騒然となったのも45年近くの昔の話になってしまいましたが、その壁画のレプリカが展示されている高松塚壁画館に立ち寄り見学して行くこととする。(復元された高松塚古墳)(同上説明板・拡大画面はコチラ) 築造当初の墳丘が復元された高松塚古墳を見た後、文武天皇陵へと向かいましたが、今日の記事はここまでとし、続きは明日の記事に譲ります。(つづく)
2017.01.23
コメント(4)
-

偐万葉・ひろみ篇(その10)
偐万葉・ひろみ篇(その10) 本日は、シリーズ第272弾、偐万葉・ひろみ篇(その10)であります。ひろみちゃん8021氏とのブログ上のお付き合いは、2014年6月18日以来でありますから、まだ2年7ヶ月に過ぎないのでありますが、彼女は中学の同級生で卒業後も何かにつけて集まっている男女10名程度のグループの一員にて、随分の昔から親しい間柄の御仁でもあります。 そんな彼女のブログとは気付かず、偶々目にとまった記事に小生がコメントを入れたことからブログの交流が始まり、やがてお互いの正体を知るところとなって驚くという面白い経緯もあったブログ友達ということになりますが、昨年からは小生が参加している若草読書会にもご参加戴いていますので、今では読書会のお仲間でもあります。 読書会のお仲間に関連の歌は、偐万葉・若草篇というのに収録して居りますので、これと合併してもいいのですが、「ひろみ篇」編纂当初には未だ読書会のメンバーではありませんでしたので、別立ての偐万葉となっています。まあ、そのような歴史的経緯を尊重し、今後も「別立て」で参りたいと存じます。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ では、偐万葉・ひろみ篇(その10)をお楽しみ下さいませ。 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌20首 並びにひろみの郎女が詠める歌2首わが庭に 咲きのこる菊 一輪を 添へて千両 実の照るも見む (本歌)この雪の 消遺(けのこ)る時に いざ行かな 山たちばなの 実の光(て)るも見む (大伴家持 万葉集巻19-4226) (センリョウ) 朝なさな わが行く道に 生駒山 神さび立てり 見れども飽かず (生駒山:偐家持撮影)わが庭の つらつら椿 太平楽を つばらに見つつ この日過ぐさな (偐ひろみの郎女) (本歌)巨勢山(こせやま)の つらつら椿 つらつらに 見つつ思(しの)はな 巨勢の春野を (坂門人足 万葉集巻1-54) (椿・太平楽) 三日月の 船にし乗りて わが母は 今し大空 渡りか行かむ (三日月:偐家持撮影) ひろみの郎女が贈り来れる歌1首ペリカンの 家のベンチは ぬくけれど 今は空しく 煙草くゆらす 偐家持が返せる歌2首母在りし 時によく見し ペリカンの 家の蜂たち いづちや行かむうらうらに 日は照りたれど 母は逝き 蜂の姿も 今は見えなく (喫茶店「ペリカンの家」:偐家持撮影) 今はもや 母は見ること 叶はじの 生駒の山に なびく白雲 (生駒山) 凍蝶と 見せて飛び去る 居眠り蝶 手向山なる やまとしじみか (蜆家持) (注)凍蝶=気温が低くなって動きが鈍くなったり、動けなくなった蝶。冬の季語。 手向山=園芸種カエデのベニシダレの別名。ヤマトシジミがとまっていた木が この木。 見るからに 色も形も 似てあれば むべまだ割れぬ あけびといふらむ (他人のそら豆) (本歌)ふくからに 秋の草木の しをるれば むべ山風を 嵐といふらむ (文屋康秀 古今集249 小倉百人一首22) (ムベ・智麻呂画:偐家持撮影)高々に 伊良部大橋 行く背子を 羨(とも)しとわれは 難波(なには)橋行く (伊良部大橋:岬麻呂撮影) ひろみの郎女が贈り来れる歌1首池間島 まん中欠けて 間抜け島 イイエうるはし 池島の町 偐家持が返せる歌1首池島で な遊びそ我妹(わぎも) 隣には ひょっこり瓢箪 山もあるなり (ドン・ガバチョ) (注)池間島=沖縄、宮古島の隣の島 池島、瓢箪山=東大阪市内の地名 むくろじの 実は石鹸に あるなるに 中なる種の などてや黒き (ムクロジの実:偐家持撮影) とりどりの 花をとりつつ とりあへず とり年過ぐさな 銀輪駆けて (鶏家持) 願はくは 何求むなく 願ふなく 紫煙のごとや 静かに消えむ (煙家持) 我妹子の 宿にも来たる アカイエカ 未受領二億余 あるとうるさき (蝿家持) (有害メール) スカイビルは かなしからずや すぐさまに 空の青にも 白にも染まる (里山牧草) (本歌)白鳥は かなしからずや 空の青 海のあをにも 染まずただよふ (若山牧水) (梅田スカイビル:偐家持撮影) 蝋梅の 花咲く庭の 南天の 実に朝鳥は 今日も来鳴きぬ (蝋梅) (南天の実と小鳥) 福寿草の 花に限らず 智麻呂は 今日も描くかや 福寿苑の花 (古市絵麻呂) 梅の木の 呻きの声を 聞き居つつ 咲かなく花を しのびてあらむ (梅家持) 梅林は 伐られ無残の 枚岡は 我とも同じ 喪中なりける (梅家持) (枚岡梅林:偐家持撮影) (注)掲載の写真は、偐家持撮影、岬麻呂撮影とあるものを除き、ひろみちゃん8021氏の ブログからの転載です。
2017.01.19
コメント(10)
-

祝・除雪支援サービスプロジェクト立ち上げ成功
今日午後5時少し前に、富良野のfurano-craftさんからお電話がありました。 メールやブログ上でのやり取りは何度もありましたが、直接お電話でお話するのは初めてのことでありました。お電話の主旨は、同氏が企画された、富良野での個人住宅向けの除雪サービス事業のプロジェクトが、今日、クラウドファンディングでの募集目標金額を達成し、プロジェクト成立となったとの、喜びのお知らせでした。 ブロ友のよしみにて、昨年12月21日の日記でこのプロジェクトを紹介するなど、小生もこれを応援していましたので、嬉しい限りです。 支援者・協賛者からご提供いただいた資金で小型除雪機など除雪支援事業を行うための機器・道具を購入されるとのことで、いよいよこのプロジェクトが始動する運びとなったことは、まことにめでたいことである。 とは言え、除雪は体力も要れば、危険も伴う作業。これからがむしろ大変なのかも知れません。同氏やそのお仲間の皆さんの頑張り過ぎない頑張りとご努力に期待であります。 雪掻きや雪下ろしというのは、大阪で生まれ育ち、今も大阪に住み続けている小生などには、生活実感のないものであり、想像力を働かせるしかない作業であるが、旅行者として、大雪の降り積む道を歩いたりした折の難渋に照らして、その必要性は十分に理解できるし、同氏がなさろうとされていることの意義も大いに共感できたのでありました。 まあ、そんなことで、ブログ記事などで、このプロジェクトへの応援をした者の一人として、このプロジェクトが無事成立し、スタートできる状態になったことをご報告申し上げるのも、礼儀のうちかと心得、今日は日記記事アップはしない予定でしたが、急遽これを変更し、ご報告記事とさせていただきました。 <参考>富良野での個人宅除雪サービス・プロジェクト 2016.12.21. (小型除雪機・furano-craft氏のブログから転載)<追記>なお、本プロジェクトの募集期間は2月3日午後11時まで申し込みを受け 付けて居りますので、引き続きご支援、ご協力のほど、よろしくお願い 申し上げます。 今日も各地、大雪のようでしたが、こちら大阪は晴れの好天気。雪の欠片もなしであります。ヤカモチは叔母の所用に付き合った後、一緒に昼食しただけということで、何と言って写真もないのであるが、叔母と待ち合わせた新石切駅とその帰途にちょっと覗いてみた枚岡梅林の写真でも掲載して置きます。(近鉄・新石切駅) 生駒市在住の叔母をこの駅前で迎え、所用の場所へ。 昼食の後、叔母の友人が胃の一部摘出手術を近く受けるらしく、そのお守りにと石切神社に立ち寄って行くというので、これに付き合う。 その後、石切駅から電車で帰ると言うので、神社から石切駅への参道の坂を上る。高齢の叔母はゆっくりした足取りなので、小生もこれに歩調を合わせてゆっくりと歩く。それでも、少し疲れた風でもあったので、途中の喫茶店で珈琲休憩とする。小生と同様にて叔母も珈琲好きなのである。 客は他になく、女店主と我々の三人だけ。店主は写真が趣味らしく、あちらこちらと旅行しては写真を撮り、それをファイルしてアルバムにしたり、額に入れて店内に飾ったりされている。そのアルバムを見せていただきながら、色々と楽しいお話を聞かせていただきました。(今日の枚岡梅林) 叔母を石切駅で見送ってから帰途に。 枚岡梅林は現在このような姿に。 2016年3月5日の日記に記載したが、枚岡梅林の梅の木の殆どがプラムポックス・ウイルスに汚染されたらしく、全ての木を伐採し、土も入れ替えるらしいのだが、その伐採作業が開始されたようです。 <参考>墓参・花散歩・枚岡梅林 2016.3.5.(同上) 枚岡梅林は無残な姿に変りつつあるが、昨年までは、下の写真のように花咲いて春を演出してくれていたのである。今年の春はそれは望むべくもない。 何年かは、梅の木などは植えられないそうであるから、再び花咲く梅林が見られるのはいつのことになるのやら、である。(2009年2月21日撮影の枚岡梅林) <参考>枚岡梅林・花園中央公園 2009.2.21.
2017.01.16
コメント(4)
-

福寿草
東京ご在住の川〇氏から寒中見舞いのハガキが届いた。 同氏は、小生が勤務していた会社の同業会社の監査役であったお方で、小生が自社の監査役スタッフをしていた頃に知己を得たもので、30年位昔のことになる。M社を含め同業4社で監査役及びそのスタッフで連絡会というものを持ち、年に1~2度集まっては情報を交換し合ったり、合同の勉強会を持ったりしていたのである。 同氏は、小生よりもずっと年長であられましたので、それほど親しいお付き合いというのはなかったのであるが、現在も年賀状の交換だけは続いているという関係である。 当方が今年は喪中ということで、年賀状ではなく寒中見舞いを下さったものかと思うが、そのハガキに短歌2首が記載されていました。1首は印刷されていて、もう1首は手書きで添え書きされていました。 印刷されていた方の短歌はこれ。物忘れ置き忘れ はた閉め忘れ 妻と競いて 老い勝るらし 同感ですな。 そして、手書きで添えられていた、もう1首はこれ。父母(ちちはは)と 弟たちの 守護霊に 護られ生きて 卒寿迎えぬ 「一昨年、満90歳を迎えた時の感慨です。」とも書かれていました。 もう少しお若いかと思っていたが、既に卒寿を迎えて居られたとは、気が付きませんでした。今年、満92歳になられるということでありますから、昨年暮れに亡くなった我が母よりも2歳年長ということになる。 同氏は、奇術がお得意で、懇親会の宴席などでは、面白い手品を見せて下さり、我々を楽しませて下さったものである。もう長らく、多分20年近くもお会いしていないが、お元気にされているようで何よりであります。同氏のご長寿とご健勝を心からお祈り申し上げる次第。 同氏のハガキには福寿草の絵が印刷されていましたが、それは「口と足で描く芸術家協会」に所属の大阪府のM氏が描かれた絵であることが表示されていましたので、これを写真に撮ってここに掲載することは著作権法に抵触することとなるでしょうから、小生のマイピクチャの中の福寿草の写真を掲載して置くこととします。(福寿草)(同上)福寿草の 継ぎて花咲く ごとにもや 八千代に君の 真幸きくもあれ (偐家持)<参考>花関連過去記事はコチラから。 花(1)・2007~2011 花(2)・2012~2016 花(3)・2017~
2017.01.15
コメント(4)
-

岬麻呂旅便り198
本日は今年最初の岬麻呂・旅便りであります。 今回は与那国島の旅。同氏にとってはこれが7回目の与那国島訪問とのこと。与那国島は、この地の方言では「どぅなんちま(渡難島)」と呼ぶらしい。渡り難い島、とは言い得て妙ですが、岬麻呂氏にとっては「どぅやっさんちま(渡易島)」(渡りやすい島)であるようです。「易しい」を沖縄方言では「やっさん」というらしいから、ヤカモチ流に作ってみた言い回しにて、沖縄の人がこのような言い方をするのか「どうなん」か知らぬことにて候。 では、今月9日~12日の同氏の2017年初旅、下掲の「旅・岬めぐり報告198与那国島」と「写真説明」並びに同氏提供写真にて、ご一緒にお楽しみ下さいませ。(旅・岬めぐり報告198)上の拡大画面はコチラから。(東<あがり>崎断崖の風景)(東崎、与那国馬と灯台)(西<いり>崎とフェリー)(西崎灯台) この灯台は、日本最西端にある灯台とのこと。同様に、写真左端に写って居る碑も日本最西端の石碑であるそうな。(ナーマ浜) 美しいナーマ浜から見えているのは、下の久部良漁港でしょうか。 久部良漁港の背後の山は久部良岳(198m)。(久部良漁港<西崎灯台から撮影>)(立神岩) この岩を見て、北海道・小樽銀輪散歩で、神威岬を訪ねた際のローソク岩とか神威岩とか蛸岩などのことを思い出しました。北と南、場所は異なっても、人はこのような岩には神が宿ると考えたり、何らかの立岩伝説を考えつくもののようです。 <参考>神威岬へ 2015.7.20. 上の立神岩の写真に写っている背後の岬が新川鼻で、この岬の直下の海底に、下の写真のような海底遺跡めいたものがあるらしい。(海底遺跡か自然のものか論争中の遺跡的なもの) これが何であるかは論争があるらしく、琉球大学が調査中とのこと。遺跡であると面白いのですが、「どぅなんちま」だけに「どうなん」でしょう。 今回は、日本で一番遅い日没が見られるという、この夕日を見ることも、旅の目的であったようですが、生憎のお天気にて、いい写真が撮れなかったと見えて、7年前に撮影されたという写真をオマケとして添えて下さいました。いり崎の いり日見むとて 来しわれは 果たせずどなん どちと呑みける (渡難家持) (注)どなん=与那国島の泡盛の名前。どぅなんちま(渡難島)に由来する命 名。ここでは「どうなん?」と掛けてみた。(日本で最後に見られる夕陽<平成22年2月24日撮影>) <参考>過去の「岬麻呂旅便り」関連記事はコチラからどうぞ。
2017.01.14
コメント(6)
-

偐万葉・ひろろ篇(その18)
偐万葉・ひろろ篇(その18) 本日は、今年最初の・・と思いましたが6日に若草篇を掲載していましたので、今年2番目の偐万葉であります(笑)。シリーズ第271弾となる今回は、久々に、ひろろ篇です。前回のひろろ篇は2014年12月5日でしたから、それ以降の同氏ブログに書き込んだコメントに付した歌などとなりますので、かなり古いものも登場であります。 <参考> 過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろdecさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌17首ほか 髪たけば 笑みもをとめの それにして やはらに春の 日は差し来たる こっちゃんの たけぬる髪の その先に 光れるものは 春にあるらし (注)たけば、たけぬる=「たく」は「たくしあげる」「束ねる」の意。 こっちゃん=ひろろの郎女さんのお孫さんの愛称。 (「或る日のスケッチ」) 舟木伐ると 家持言ひし 能登の島山 妹行けば ねぢ花咲くとふ 大橋がもと (本歌)とぶさ立て 舟木伐るといふ 能登の島山 今日見れば 木立繁しも 幾代神びそ (大伴家持 万葉集巻17-4026) (注)上2首は、577577の旋頭歌体の歌である。 (ネジバナ) (能登) ゆるやかに 瀬田の川面の 流れ藻の 去り行くひとや 別れ悲しも 春まけて 霞ケ浦に 遊びしも 夢か舟泊(は)つ 小雨に降り来 (く) (「ゆるやかなとき」<部分>)悲しみの 衣(ころも)着襲(きそ)はむ 悲しめる ひとにも添はな 秋雨降れば 磐梯を 雲な隠しそ 面影の 立ち別れにし ひとをしのはむあらたしき 年の始めに てふてふの こっちゃん帰り来(く) いやなつかしき (「ちょうちょ」)山々の 色そぎおとし 積む雪に さらにも川面(かはも) 色深みかも 偐万葉掲載に当り、追ひて和せる歌1首阿賀野川 眠れ静かに 山々の 色そぎおとし 雪は降りける (阿賀野川) アネモネの 青き花びら そよがせて 奥会津にも 春の風吹く (モノマネ家持) (アネモネ) マフラーも 萌黄色なり 芽吹く春 ももこの髪も 風にしなびく (黄色いマフラー) ひろろの郎女が作りたる句に偐家持が付けたる脇句 立葵(たちあふひ) 彼方人(をちかたひと)の けはひして (ひろろの郎女) 立ちてもゐても 恋(こほ)しきみかも (偐家持) (「彼方」<部分>) 桧原湖の みなもに映す 島山の ゆらめく影や 風渡るらし (桧原湖)昔見し ひろろ描きにし 絵を見れば しるくぞいよよ なつかしかりき (偐旅人) (本歌)昔見し 象(きさ)の小河(をがは)を 今見れば いよよ清(さや)けく なりにけるかも (大伴旅人 万葉集巻3-316) (「冬の朝」)ひろろとは 寒菅なりと 今日までは 知らず来にけり 我し悔しも (本歌)愛(かな)し妹を いづち行かめと 山菅の 背向(そがひ)に宿(ね)しく 今し悔しも (万葉集巻14-3577) あどけなき 少女の笑みの その先に 夢と希望と 無限の未来 (「髪飾り」) 遠山の 雪はも赤く 日に燃えて 嵐ものかは 今日も歩めと (雄国の風景)(注)掲載の絵画、写真は全てひろろdecさんのブログからの転載です。 本日はフォト蔵へのアクセスができない状況でありましたので、フォト蔵に 登録のマイピクチャを使用する必要のない記事ということで、偐万葉の記事 と致しました。
2017.01.13
コメント(8)
-

囲碁初め
今日は今年最初の囲碁例会の日。 朝10時に来客の用があったので、それを済ませてからの出発ということになり、マイMTBで家を出たのは10時40分頃。 何処にも立ち寄らず、大阪城公園経由で、れんげ亭到着が12時少し前位。今日は店が開いていました。この処、ランチが休みというのが2回続きましたが、店主のれんげの郎女さんのお話によると、ボランティアでお年寄りの病院通いやその他の介護・支援をやって居られて、その関係で、お昼の営業を休まなくてはならない、などのこともあったのだとのこと。 若草読書会の新年会が今月29日にあるので、それに都合がつくなら、ご参加下さいという案内だけはして置きました。昨年の新年会にご参加戴いて以来のことなので、ご参加戴ければ、嬉しい限りであるが、色々とお忙しいようなので、ご都合がうまく折り合うかどうか、が問題であります。 昼食のあとの珈琲までご馳走になり、梅田スカイビルを目指す。(本日の梅田スカイビル) 会場に着くと、既に村〇氏が来られていました。 早速に、同氏とお手合わせ。今年最初の対局は、序盤の優勢を活かしきれず、上辺の捨て石にすべき黒2子を助けようと動き出したのが悪手となって、形勢が段々におかしくなり、結局、中押し負け。 対局中に、福〇氏と竹〇氏が来られ、隣で対局。両者の対局が終了した処で、対戦相手をチェンジ。小生は福〇氏と打つ。福〇氏も早打ちタイプ、小生も早打ちタイプで、とんとんと進み、小生の勝ち、隣の竹〇・村〇戦は未だ中盤過ぎといった局面なので、福〇氏ともう1局打つ。これも小生の勝ち。今日の福〇氏は、小生並みの雑な打ち方となったようでありました。 最後に竹〇氏と対局。大石を殺しに行ったまでは良かったが、うまく凌がれてしまい、逆にこちらが殺される羽目となって、ジ・エンド。中押し負けでありました。 ということで、本日は2勝2敗。まあ、出足はこの程度でよしとしますか。 帰途も、何処にも立ち寄らず、でありましたが、花園ラグビー場まで帰って来た頃には、もう暗くなりかかっていました。 ということで、写真は、上のスカイビルの写真1枚があるきりです。
2017.01.11
コメント(4)
-

2億2千万円も給付して下さるそうな。
本日わが携帯にこのようなメールが入りました。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーこの度、個人給付支援団体 Personal Payment Association(以下【PPA】)による厳正な審査にて、2億2000万円の給付が確定しております。高額給付となりますが、PPAより給付させて頂きます。▼給付確認はこちらhttp://(4v0qe207で始まり、CR0393で終わるURLが記載され、そのサイトとリンクされている。)(注)長大なURLでしたが、このメールを送信した主は、このURLをクリックさせることが狙いでしょうから、そのまま引用したのでは、有害メールを拡散することとなりますので、中間部分を削除省略しました。※【PPA】について※【PPA】は個人への無償給付にて、救済、貧富格差の是正により地域経済の活性化を図っております。またこの活動により支援を受けた方から更に支援の輪を拡げて頂くことを目的としております。一切の見返りは求めず、完全無償となりますのでご安心のうえお受取くださいませ。▼2億2000万円受取はこちらhttp://(上と同じURLでリンクが貼られている。) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 随分前にも同じようなメールがあったかと思うので、これが初めてという訳ではなく、迷わずに削除であるが、ブログネタにでもしてみるかと、PCメールアドレスに転送して、これをコピーして上に貼り付けた次第。 何かで、わが携帯メールのアドレスが流出し、利用されているのだろうと思うが、同じようなのに、「メルアド変更しましたのでよろしく。」とだけあって、送信者の名前の無いメールとか、「今度、飲みに行きませんか。」というような、発信人不明のメールが時々届いたりする。 すべて即削除であるが、煩わしく、忙しい時などにこれが入ると腹立たしい思いになる。ということで、ブログネタにすることで、ちょっと鬱憤晴らし。迷惑メールも少しは役に立つ、と言うか、役立ててみた次第であります(笑)。 それにしても、2億2千万円をお受け取り下さい、とは笑止である。何処の世界にそんな上手い話があると言うのでしょう。これを信じる人は先ず居ないと思うが、疑問に思いつつも、貼られたURLを不用意にクリックしてしまう人もいくらかは居るのだろう。 まあ、クリックしたらどうなるのかは、小生もクリックしたことが無いので何とも分かり兼ねるのであるが、何か怪しげなサイトにつながっていたり、ウイルスが仕込まれていたり、ということであるのかも知れない。 ネット世界が発展し、便利になるのは結構であるが、こういう迷惑メールを排除できるシステムの方の開発もお願いしたいものである。望まぬメールの受け取りを拒否できる自由があってもいいかと思うが、それはごく限られた範囲でしか実現していないのが現状でしょうか。(パソコンにやって来た蚊) 上は、パソコンにやって来た蚊である。 迷惑メールを発信する輩は蚊のようなものであるか。 しかし、蚊は、蛙やトンボや小鳥など小動物の餌ともなって、この生態系を支えてもいるのであれば、人間さまには迷惑な存在であっても、それなりに存在意義を有していると言うべきで、迷惑メールを発信している輩はただ有害なだけの「蚊ほどにも価値がない」存在と言うべきである、とこの蚊は言って居ります。わが宿は蚊のちいさきを馳走也は芭蕉の句であるが、蚊ほどにも 価値なきやから 望まぬに あやしきメール 送るものども (偐家持)でしょうか。
2017.01.10
コメント(10)
-

今日は雨なので
今日は雨なので、一日中家に籠っていました。 こういうのを「雨つつみ(雨障み)」と言いますが、万葉の頃は、男が女のもとに通って行けないことの口実に「雨つつみ」を利用したとか。 ヤカモチさんには通って行くべき女性もありませんので、「雨つつみ」ではなく、単に「雨ごもり」と言うべきですかね。 雨つつみ、で思い出す万葉歌はこれ。以前にも紹介しているが、大伴家持のこの歌である。荊波(やぶなみ)の 里に宿借り 春雨に 隠(こも)り障(つつ)むと 妹に告げつや (大伴家持 万葉集巻18-4138)(荊波の里に宿を借り、春雨に降り込められていると、妻に報せてくれたか。) この歌の題詞には、墾田地の検察に出掛けていた越中守・家持さん一行は砺波郡の主帳(郡の四等官)である多治比部北里という人の館に宿をとることとなった。すると「たちまちに風雨起こり、辞去すること得ず」ということになってしまって、作った歌である、と書かれている。 この時既に、家持さんの妻である坂上大嬢が越中に来ていたとする説もあれば、未だ都に居たとする説もあって、定かではないが、この歌は、おそらく宴会の席で詠まれたか、随行の部下などに聞かせるための余興として詠まれたものと考えられるから、妻が越中に来ていて家持さんの帰りを待っているという状況を前提としたものではないだろう。家持さんとしては、随行の部下たちに、お前たちも「今夜は雨で行けない、帰れない」と、妻や恋人に報せを出したか、という冗談を言ったものではないか、と思う。家持の妻が遠く離れた都に居る方が冗談としての面白味は増すと言えるかも知れない。 何れにせよ、これがジョークとして成立するためには、「雨つつみ」というのは、他の女性のもとに通うための男側の口実の常套的手法であるということが、共通の認識として成立していなければならないだろう。 この歌の歌碑は富山県高岡市の荊波神社にある。 <参考>高岡銀輪散歩(その5)2012.6.27. さて、「雨つつみ」か「雨ごもり」かは別として、雨にてあれば銀輪散歩もなしで、ブログネタもない。手持ちの写真の中から、ちょっとほっこりするものを紹介して置くこととします。(退院のご老人とお孫さん 病院の玄関先で) これは、少し古い写真になりますが、母が生前入院していた病院の、或る日の風景です。この頃は、殆ど病院に居ることが多く、病院の庭先の花や木を撮ったり、飛来する雀を撮ったりしてブログにアップしていましたが、そのような中で撮った1枚です。基本的に人物の写真はブログに馴染まないので撮らないのですが、後ろ姿ならよかろうとカメラを向けました。迎えの車を待つ、退院されるご老人とそのお孫さんの姿に微笑ましいものを感じたからであります。 この日も雨が降り出していて、「雨つつみ」のお二人でしたが、程なく、少年の父親と思しき男性が運転される車がやって来て、それに乗車。ご自宅へと帰って行かれました。
2017.01.08
コメント(8)
-

偐万葉・若草篇(その20)
偐万葉・若草篇(その20) 本日は久々の偐万葉シリーズです。今年初めての偐万葉は、シリーズ第270弾、若草篇(その20)であります。 <参考>過去の偐万葉・若草篇はコチラから 偐家持が小万知に贈りて詠める歌14首ほか 並びに小万知が詠める歌1首 小万知が贈り来れる歌1首願はくは 月の下にて 秋死なむ もみぢばそよと 彩(いろどり)添へて (小万知) 偐家持が追和せる歌7首西行の ほどにはあらね 咲く花の 下に死ぬるも またよしわれも西行の うら行くつもり よもなけど もみぢ葉照れる 秋こそわれは願はくは 青葉の下に 夏死なむ 五月の風の さやと吹く頃 (南行法師)炎天の 下に死ぬるも またよしか 銀輪駆ける その道の辺に (輪行法師)願はくは 枯葉散るごと 冬死なむ 真綿に降れる 初雪の頃 (北行法師)願はくは もみぢが下に 秋死なむ 山金色(こんじき)に 照れるその頃 (東行法師)願はくは 朧月夜に 春死なむ 咲きて波うつ 菜の花の頃 (偐西行法師) 小万知氏に答へて作れる替え歌1編 「阿波踊り恋歌」淀川ササユリ 「風の盆恋歌」石川さゆり 道のはたから 踊り見る 蚊帳の中から 花を見る とんではねてる 阿波踊り 咲いて悲しい 酔芙蓉 さざ波か 美しい 若い日の 美しい 女踊りを 追いかけて わたしを抱いて 欲しかった 砕け散るかよ 男波 しのび逢う恋 風の盆 (阿波踊り) 思ほえば みなおかげさま あれもこれも わが身ひとつで なしたるはなし (自覚家持) ありがたき ことはまことに 有り難き ことと思へば なほありがたき (感謝家持) 実は丸く ありてこそなり なべてみな 角張るものは 実にならじかも (偐角丸) なやましき かへでなるかや あれと言へど これとも見えて なにとも言へず (楓家持) (ウリカエデ)母が行く 道の長手の 安かれと 父出(い)だせるか 三日月の船 (2016.12.3.の三日月) 吐く息の 白きあしたの 青空に まず咲く蝋梅 ほのかにかほりおけいはんと こまちは京都 やかもちは ひらかたまでの 銀輪伴走 (くらはんか家持) 偐家持が偐山頭火に贈りて詠める歌7首ほか 並びに偐山頭火が詠める歌5首ほか <参考>偐山頭火氏のブログはコチラから。 偐山頭火が贈り来れる歌1首越中から 上総伊勢へと 異動して 因幡で詠むは 言の葉の〆 (偽サカイ引越センター) 偐家持が追和せる歌1首越中ゆ 言の葉閉めし 因幡より 上総伊勢陸奥 死して隠岐なり (愚痴家持)岩代の 浜松が枝の 皇子(みこ)の歌碑 真幸(まさ)きくありて また来ても見よ (無間皇子) (本歌)磐白の 濱松が枝を 引き結び まさきくあらば またかへり見む (有間皇子 万葉集巻2-141) (有間皇子結び松記念碑 偐山頭火氏のブログより転載)秋づけば 河内街道 やかもちに 引かれて君や 八劔(やつるぎ)まゐり (菱屋東麻呂) 偐山頭火氏が追和せる歌1首と自由律俳句1句引かれ行く 我の前には 暗越(ただごえ)が 越すにこされぬ トレンクルでは (超リハビリ坂)分け入っても訳言っても 尻つき居らず 生駒高峰 (偐山頭火) (東大阪市菱屋東の八劔神社 偐山頭火氏のブログより転載) ゆゑありて 鳥のそらねは はづせるに よに逢坂は 清もゆるさじ (濁中納言) (本歌)夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ (清少納言 後拾遺集940 枕草子131段 小倉百人一首62) 偐山頭火が追和せる歌1首ゆゑあるか なからうとても 我知らず 逢坂の関は 餅と鰻ぞ (偐大納言) (逢坂の関址碑) 偐山頭火が贈り来れる句に偐家持が付けたる脇句 家持が ハチと向き合う カフェテラス <偐養蜂家持> ムシもならずや ハチ合ひしハチ <蜂の無視麻呂> (ペリカンの家の蜂) わが行くは まだ先なりと 思ほえど いささかわれも 疲れたりけり (弱音家持) 偐山頭火が贈り来れる句に下3句を付して仏足石歌体の歌にしたる1首 赤白か 白か赤かと 騒がしい (くる年いく年) 猿のお尻も 鶏のトサカも 赤いといふに (猿鶏家持) 偐山頭火氏が贈り来れる歌1首草香江の 若草ホールに 友集ひ フライドチキン 口騒がしく (偐カーネルおじさん) (本歌)草香江の 入江にあさる 蘆鶴の あなたづたづし 友なしにして (大伴旅人 万葉集巻4-575) 偐家持が返したる歌1首若草の ホールにつどふ よきどちの たのもしき顔 行きてはや見む 偐山頭火氏が贈り来れる歌1首ネコでない ペリカンもなく 季節風 東風(こち)や西風(ならひ)に まかせて頼む (古宅配便) 偐家持が返したる歌1首ネコでなく コネにて運ぶ 玉梓(たまづさ)の 使ひのふみに 歌もぞ添へて (白猫河内の宅持(やかもち)) (注)掲載の写真は、偐山頭火氏のブログからの転載のものを除き、当ブログ過去記事 に掲載のものの再掲である。
2017.01.06
コメント(8)
-

寒中お見舞い申し上げます
今日1月5日は小寒。今日より寒の入りであります。 大寒は1月20日。立春は2月3日。小寒から立春前日までを寒中と言いますから、寒中見舞いは、小寒から立春までの間に出す見舞状である。 ということで、今日の記事は、皆さまへの寒中見舞い状と致します。------------------寒中お見舞い申し上げます当方忌中につき新年年賀の儀はご遠慮申し上げました皆さまにおかれましてはよき新年をお迎えになられたことと拝察申し上げます旧年中に賜りましたご厚誼忝く心よりお礼申し上げます今年もよきお付き合いの程よろしくお願い申し上げます偐万葉田舎家持歌集けん家持(写真は昨年1月20日撮影の金閣寺です。)^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^偐万葉田舎家持歌集(にせまんよう いなかやかもち かしゅう)目次それぞれの項目をクリックすると その項目の記事をまとめて見ることが出来ます。 下記目次はヤフー版の偐万葉田舎家持歌集によって作成しています。絵画展ほか智麻呂絵画展和郎女作品展近江鯨麻呂絵画展偐万葉シリーズ松風篇 大和はまほろば篇 ビターc篇 ひろろ篇カコちゃん08篇 真澄篇 木の花桜篇 るるら篇 nanasugu篇 カマトポチ篇 くまんパパ篇 ビッグジョン篇 童子森の母篇 半兵衛篇 マダム・ゴージャス篇 英坊篇 アメキヨ篇オガクニ篇 ふぁみキャンパー篇 ウーテイス篇 ふらの篇閑人篇 LAVIEN篇 幸達篇 ひろみ篇 あすかのそら篇ローリングウェスト篇 若草篇 その他銀輪万葉シリーズ大阪府篇 奈良県篇 兵庫県篇京都府・滋賀県篇 和歌山県・三重県篇 北陸篇 新潟県・長野県篇 関東篇 中四国篇 九州篇 その他その他近隣散歩花(1)2007~2011 花(2)2012~2016 虫 マンホール若草読書会 囲碁関係 岬麻呂旅便り 万葉 ナナ万葉の会関係 短歌・俳句・詩・戯れ歌 言葉遊び・駄洒落集その他のカテゴリー自転車 絵画 能・狂言 友人ほか ブログの歩み カテゴリー未分類^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 当ブログ、昨年1年間で501049件ものアクセスを賜りました。 年間最多であった昨年(250713件)の2倍近い多数となりました。 まことに有難きこと、心より感謝申し上げます。 今年も引き続きご愛読賜りますれば幸甚に存じます。 <参考>過去の年間アクセス数<括弧内は年末時点のアクセス総数> 2011年 53664件( 151563) 2012年 48490件( 200053) 2013年 39816件( 239869) 2014年 78308件( 318177) 2015年 250713件( 568890) 2016年 501049件(1069939)(注)毎年元日に掲載していた年賀の記事に、このタイプの記事を収録して居りま したが、今年は忌中にて年賀記事を中止致しましたので、寒中見舞いの記事 として、これを掲載することと致しました。
2017.01.05
コメント(8)
-

第17回和郎女作品展
第17回和郎女作品展 わが偐家持美術館は元日から営業開始でありましたが、本日3日は新春企画第2弾として、第17回和郎女作品展をお届けすることといたします。 この処、すっかり年1回というのが定着してしまった和郎女作品展でありますが、昨年の2月11日に続いての久々の作品展であります。 では、ごゆるりとご覧下さいませ。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 今回出展の作品は、昨年暮れに智麻呂邸を訪問申し上げた際に、和郎女さんから頂戴したものだという、同邸に置かれていたものであります。 毎年、若草読書会に参加者へのお土産としてお持ち下さる押し絵などの作品を撮影させていただいて「作品展」を開催していたのでありますから、今年も例年通りであるならば、それまで待って作品展を開催してもいいのでありますが、当偐家持美術館は元日より営業を始めてしまった関係で、トリあえず只今の手持ちの写真だけで作品展を開催させていただくこととしました。 先ずは酉年ということで、「鶏」であります。(鶏1) これ「鶏1」は、前頁の第186回智麻呂絵画展の冒頭の「鶏」の絵のモデルとなったニワトリの刺繍であります。色糸で絵模様を縫い上げる普通の刺繍とは違って、こういうのは「つまみ細工刺繍」と言うそうですが、恒郎女さんから何となくお聞きした言葉からの小生の理解なので、或は小生の聞き違いか理解不足で間違った説明になっていましたならば、ご容赦下さい。 次の「鶏2」も酉年に因んで作られました。 鮮やかな色糸を束ねて表現された尾羽が印象的な作品であります。(鶏2) 万葉集では「鶏」は「とり」とも「かけ」とも呼んでいます。また、「家つ鳥」とか「庭つ鳥」とも呼んでいます。現在、我々がニワトリと呼ぶのは、この「庭つ鳥」がその語源なんでしょう。小生の印象に残っているフレーズは、天皇の妻問いの歌である巻13-3310の歌の中のこの一節でしょうか。「野つ鳥 雉(きぎし)はとよむ 家つ鳥 鶏(かけ)も鳴く」 雉と鶏が並んで詠われていますが、両者は生物分類上は共にキジ科の鳥でありますから、親戚みたいなものなんですな。 では、「鶏」の万葉歌を2首ばかり掲載して置きます。暁(あかとき)と 鶏(かけ)は鳴くなり よしゑやし ひとり寝(ぬ)る夜は 明けば明けぬとも (万葉集巻11-2800)里中に 鳴くなる鶏(かけ)の 呼び立てて いたくは泣かぬ 隠(こも)り妻はも (同巻11-2803) 次は、昨年11月の読書会の折に、参加者へのお土産にとお持ち下さった干支のタペストリーであります。読書会参加者は、各自1点ずつ頂戴して持ち帰りましたが、下の写真はヤカモチ館長が自宅に持ち帰ったものです。 この作品を制作するキッカケとなったのは、偶々「青い布」が沢山手に入り、これを何に使うかと思いあぐねていて、タペストリーにすれば面白いかも、と考え付いたことによるらしいのですが、いい着想です。 ヤカモチなんかは何日考えても思いつかないことでしょうな。それ以前にヤカモチには「青い布」なんぞを入手するということがそもそもないことでありますから、このようなことで思いをめぐらすということは生じようもない(笑)。 (干支のタペストリー) 次の「鶴亀松竹梅」も壁飾りタイプの作品。 下に付けられた鈴に引っ掛けることによって何連でも縦に繋ぐことができるようになっている。 (鶴亀松竹梅) 上の「鶏」の万葉歌にならって、「鶴亀」と「松竹梅」の万葉歌も掲載して置くこととしましょう。亀の歌は、万葉集には短歌はなく長歌が2首あるきりなので、その部分抜粋としました。 〇鶴亀の歌草香江の 入江にあさる 蘆鶴の あなたづたづし 友なしにして (大伴旅人 万葉集巻4-575)若の浦に 潮満ち来れば 潟をなみ 葦辺をさして 鶴鳴き渡る (山部赤人 同巻6-919)・・くすしき亀も 新た代と 泉の川に 持ち越せる・・ (藤原宮の役民の歌 同巻1-50)・・ちはやぶる 神にもな負ほせ 占部すゑ 亀もな焼きそ・・ (同巻16-3811) 〇松竹梅の歌一つ松 幾代か経ぬる 吹く風の 音の清きは 年深みかも (市原王 同巻6-1042)たまきはる 命は知らず 松が枝を 結ぶ心は 長くとそ思ふ (大伴家持 同巻6-1043)御園生の 竹の林に うぐひすは しば鳴きにしを 雪は降りつつ (大伴家持 同巻19-4286)我がやどの いささ群竹 吹く風の 音のかそけき この夕かも (大伴家持 同巻19-4291)春されば まづ咲くやどの 梅の花 ひとり見つつや 春日暮らさむ (山上憶良 同巻5-818)雪見れば いまだ冬なり しかすがに 春霞立ち 梅は散りつつ (同巻10-1862) 上の写真では、亀・鶴の順になっているが、正しくは鶴・亀の順なんでしょうか。 これは簡単に入れ替えできるので、好きな順番にすればいいのであって、どれが正しいというものでは本来ないのでしょう。連ねてもよし、単体で飾ってもよし、であります。(同上・亀部分)亀ハ萬年乃齢(ヨワイ)を経、鶴も千代をや重ぬらん・・(謡曲「鶴亀」より)(同上・鶴部分)(同上・松竹梅部分) 上の「松竹梅部分」でありますが、鶴亀との関連で「松竹梅」と名付けましたが、松と梅は間違いなく絵の中にあるものの、よく見ると、竹のそれは何やらカエデの三裂葉のように見えて、竹・笹の葉には見えないから、松竹梅ではないのかも知れない。 などということは、写真のキャプションを付けるに当って少し気になることではあるけれど、本来はどうでもいいこと。色や形の美しさ、それらが織りなす雰囲気を楽しめばいいことなのではあります。 作品点数は少ないですが、お正月らしい作品なので、偐家持美術館新春特別企画第二弾として、本日の記事アップとなりました(笑)。 以上です。本日もご来場・ご覧下さり、ありがとうございました。<追記>先程、小万知さんから、小万知さんがお持ち帰りになった和郎女作のタペ ストリーは種類の異なるものなので、併せこれを展示してはどうかと、メ ールでその写真を送って下さいました。 よって、下記に追加掲載させていただきます。 (尾長鶏・小万知氏撮影)
2017.01.03
コメント(12)
-

第186回智麻呂絵画展
第186回智麻呂絵画展 ヤカモチ館長は忌中につき年賀の儀は差し控えさせていただきますが、偐家持美術館は元日より営業開始であります。第186回智麻呂絵画展をお楽しみ下さいませ。<参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ずは、智麻呂・恒郎女様ご夫妻からの年頭のご挨拶であります。 皆さま、明けましておめでとうございます。 新年が皆さまによき年でありますことをお祈り申し上げます。 旧年中は何かとお世話になりありがとうございました。 本年も智麻呂絵画よろしくご愛顧のほどお願い申し上げます。 2017年 元旦 絵師 智麻呂 絵師補佐 恒郎女 では、智麻呂絵画をお楽しみ下さいませ。 先ずは、元旦らしい絵から。(鶏) このニワトリは、和郎女さんから智麻呂邸に贈られて来たお正月用の作品の一つを写生されました。年末近くに恒郎女さんよりお電話があり、今回の絵は食べ物ばかりで、お正月らしいのがない、新年の智麻呂絵画展では、和郎女さんから届いた作品がお正月にピッタリなので、その写真を絵画展冒頭に掲載してみてはどうか、とのこと。しかし、和郎女さんの作品は、別途「和郎女作品展」という形で、偐家持美術館にて展示するので、それを写生したものならOKだが、作品そのものの写真はダメとヤカモチ館長はこれを拒絶。そこで、急遽、この絵を描かれたようです(笑)。 この絵のモデルとなった作品は、追って、和郎女作品展の方でご紹介申し上げますので、それまでお待ち下さい。 次は、水仙二題です。 上は、ご友人の友〇さんから頂戴した水仙です。 下は、ひろみの郎女さんから頂戴した水仙です。(水仙 from友〇さん)(水仙 fromひろみの郎女) 次は、お馴染み下仁田葱です。 智麻呂氏の大学時代からの親友であった故・木〇氏の奥様が今も変わらずにこの葱を送って来て下さるので、この展覧会では何度も登場しているかと。(下仁田葱) 次は、凡鬼さん栽培の野菜たちです。 これも当絵画展の常連さんであります。(野菜 from凡鬼) 次は、蜜柑二題です。 上は、熊野の蜜柑。槇麻呂さんからの戴き物です。 下は、香川の蜜柑。ヤカモチ館長の友人が高松市で蜜柑栽培をやっているので、それを智麻呂さんにお届けしています。(熊野の蜜柑 from槇麻呂)(香川の蜜柑 from偐家持) 次は、五〇さんからのハムです。 これも、この時期の常連と言っていい題材です。(鎌倉ハム from五〇さん) 次のケーキ&クッキー二題の内の上のものも、多分五〇さんからのものかと思います。下のそれは、和郎女さんからのものです。(ケーキ&クッキー from五〇さん)(ケーキ&クッキー from和郎女さん) 次の「石切さん」は、ヤカモチ館長が智麻呂邸を訪問した折にお持ちした和菓子です。地元の菓子舗「寿々屋」の和菓子で、地元の石切神社に因んだものです。関西では神社や神社に祀る神様を「〇〇さん」と呼ぶのが普通です。春日神社は「春日さん」、住吉神社は「住吉さん」、八坂神社は「八坂さん」、伏見稲荷神社は「伏見さん」です。よって、「石切さん」というのは石切神社のことであります。(和菓子「石切さん」from偐家持) 次は、偐山頭火さん自家製の燻製です。(燻製 from偐山頭火) 以上、冒頭の鶏と水仙は別として、恒郎女さんが仰る通り、何やらスーパーマーケットか百貨店の食品売り場を巡っているような絵が続きましたので、最後に梟の絵といたします。 酉年なので、最初と最後が「鳥」の絵ということで、トリ合わせもよろしいかと存じ上げ候(笑)。 この切株の中に鎮座する梟も、偐山頭火さんが、昨年暮れに智麻呂邸に持参された写真から絵にされたものだそうです。 大阪城公園の「切株梟」は当ブログでも既に紹介済みなので、ご記憶のお方も居られるかと思いますが、参考までにその記事をリンクして置きます。切株の形や梟の位置が当ブログで紹介したものと微妙に異なっているので、或は、べつの場所のものであるのかも知れません。 <参考>大阪城公園のフクロウ 2016.7.30.(大阪城公園の梟) 以上です。 今年は、ヤカモチ館長が忌中につき、元日恒例の年賀のページは中止し、智麻呂絵画展とさせていただきました。 本日もご覧下さり、ありがとうございました。
2017.01.01
コメント(18)
全18件 (18件中 1-18件目)
1