2017年04月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

阿倍野から堺へ(その1)
4月28日は、阿倍野から堺まで銀輪散歩して参りました。目的は二つ。 一つは、四天王寺七宮めぐりの際に茶臼山に登ったことをきっかけにして、大阪5低山なるものを知ったのであるが、その5低山のうち、小生が未だ訪ねていないのは聖天山であるということが判明したことに加えて、この聖天山は吉田兼好(占部兼好)所縁の地でもあるということを知ったので、これは是非とも訪問せねばなるまいと思ったこと。 <参考>七宮めぐり余録 2017.4.23. 今一つは、堺市のマンホール図柄に旧堺燈台が描かれていて、なかなか味のある姿であったので、これを見てみようと思ったこと。 <参考>銀輪散歩・マンホール(その9) 2017.4.24. そして、長年、訪問してみようと思いつつ果たせていない、北畠顕家の石津川畔の墓も訪ねてみようというのが今回の主旨です。 実は、今月19日にも阿倍野筋を南へと走っているうちに、大和川を渡って堺市に入ってしまい、ならば与謝野晶子生家跡や千利休屋敷跡などを訪ね、ついでに堺市役所の21階展望室から仁徳天皇陵でも見てみようと思い付いたのでしたが、下調べの十分にされていない銀輪散歩の悲しさ、千利休屋敷跡は見つけられぬままであったのでした。その後の調べで、その場所は、旧堺燈台へ行く途中にあるので、往路か復路かどちらかでこれに立ち寄ることも可能、というもう一つの隠れた目論見があったのでした。 ということで、19日と28日の銀輪散歩を合併して一つの銀輪散歩記事に仕上げることとします。多分1回では済まず2回か3回の連載になるだろうと見込まれます。それを見越して、タイトルにも(その1)を付すという用意周到さでありますが、さて如何相成りますやら。 自宅を出てから天王寺駅前までのコースは19日と28日とでは微妙に異なりますので、原則28日のコースで記述することとし、19日のコースもその日の写真を掲載する必要に応じてこれを記述します。と言っても、おおよその見当をつけて西へ、南へと、いつもながらの適当なコース取りにて、今となっては何処をどう走ったのか記憶が曖昧になっている部分がかなりあります。 先ず、コリアタウンの東側入口・百済門に偶々さしかかったと言うか、出くわした処から始めることとします。まあ、中間にも百済門があります。 (東入口の百済門・御幸橋から) (中間にある百済門) コリアタウンの西出口(入口でもあるが)の南側にあるのが御幸森天神宮。この神社は下記参考の記事にて紹介済みなので、パス。 <参考>万葉ウォーク下見・すみのえの霰松原 2011.10.23. 神社の西側の道を左(南)へ。弥栄神社という文字が目に入ったので立ち寄ってみる。祭神はスサノオノミコト。それに仁徳天皇も祭神としているのが難波らしい。 (弥栄神社・東鳥居) (同・拝殿) さしたる発見もなく、神社を後にし、JR環状線桃谷駅前に出る。 JR環状線に沿って南へと走っていると、摂津国分寺跡→400mという標識が目に入る。国分町という地名。右手に小さな公園が見えたので行ってみると、そこに石碑がありました。国分町公園という公園らしい。帰宅後、地図で位置を確認していて、久保神社と河堀稲生神社と国分寺公園を線で結ぶとほぼ正三角形になることに気付きました。(摂津国分寺跡碑)(国分寺公園) (摂津国分寺跡碑側面と副碑) この付近は七宮めぐりをしたので、地理感が出来ている。玉造筋を直進。右にカーブして上り坂となって南河堀交差点を西へ。ホテルバリタワー大阪天王寺の前で裏道に入って、JR天王寺駅をぐるり回って、向かいのアベノハルカスのビルの下からアベノ筋に入る。19日は大和川までアベノ筋をひたすら南へと走ったのであるが、28日は松虫交差点で右折、西へと向かいました。聖天山へ立ち寄るためである。 阪堺電軌上町線の踏切を渡ってスグに松虫塚があるが、これも素通り。過去記事に紹介済みだからである。段々と近隣の銀輪散歩もこのようにして、題材が減少して行くのでありますな(笑)。松虫塚については下記記事をご参照下さい。 <参考>大阪市南部銀輪散歩(2.四天王寺、松虫塚、安倍晴明神社) 2011.7.16. 更に西へと下ると道端に詩碑がありました。伊東静雄の詩である。中学か高校かの教科書で彼の詩に接したことがあるが、その詩がどのようなものであったかは記憶していないし、その後、彼の詩集などを読んでいないので、書棚には中央公論社版「日本の詩歌」で伊東静雄の詩が収録されている巻もあるにはあるのだが、「積ん読」になって居り、従って、彼のこともその詩のこともヤカモチは何も知らないのである。(伊東静雄詩碑「百千の」・松虫通り) 伊東静雄は、長崎県出身であるが、住吉中学(現・住吉高校)の教師をしていた時期もあったので、此処にその詩碑があるという訳である。 さて、いよいよ第一の目的地・聖天山に到着である。 <参考>大阪再発見・聖天山 (女坂) (聖天山奥之院) 4月23日の記事でも書いた通り、大阪5低山というのは、天保山、茶臼山、御勝山(岡山)、帝塚山とこの聖天山を言うらしい。他の4山は訪問済みで、当ブログにもその写真を紹介しているかと思う。しかし、この聖天山はブログの上でも、ブログ外でも訪ねるのは今回が初めてである。 <参考> 天保山:銀輪渡船巡り 2016.8.25. 茶臼山:七宮めぐり余録 2017.4.23. 御勝山:御勝山から舎利寺へ 2014.9.2. 帝塚山:帝塚山古墳の写真はブログに掲載 がないようなので、当記事末尾に その写真を掲載して置きました。 (奥之院の手前にある門) (聖天山正圓寺・鳥居)(聖天山正圓寺・山門) 聖天山正圓寺については、下掲の「縁起」の写真または上記<参考>の「大阪再発見・聖天山」をご参照下さい。 山門の写真を撮った際、シャッターを切った瞬間に上空から木の葉が落ちて来たようで、それが写り込んでいます。 お堂の縁側に何故か巨大なアンモナイトの化石が置いてありました。何とも奇妙なとり合わせであります。不可解(貝)などと駄洒落を言ってみたくなると言うもの。 (同・本堂) (アンモナイトの化石)(聖天山正圓寺縁起) 鳥居脇に兼好法師藁打石と伝えられる石があるとのことで、その碑が建っている。大聖歓喜天と刻された石碑の台座石がその石らしい。 この付近に兼好さんは庵を構えていたらしい。正圓寺境内庭園には、兼好法師隠棲庵址の碑もあったらしいが、小生が見落としたのか見かけませんでした。(境内の句碑と兼好法師藁打石の碑) 藁打石の碑と並んで句碑もありました(下掲左)。 兼好の午睡さますな蝉しぐれ、という句であったが、誰の句かは存じ上げぬ。その句碑と並んで徒然草の碑もありました。当ブログでは徒然草の文章を引き合いに出しては、兼好さんを茶化したりもして居りますので、日頃の無礼をお詫びして置きました(笑)。 (同上) (徒然草の碑) 聖天さんを後にし、松虫交差点の手前から熊野街道に入り、阪堺電軌上町線のチンチン電車が走る道に出て、これを帝塚山3丁目停留所まで行く。停留所の先で右折し、西へ。南海高野線の帝塚山駅前の踏切を越えた処にある帝塚山古墳に到着。これを写真に撮る。(帝塚山古墳) カメラを構えていると山頂と言うか墳丘と言うか、丘の上に人影が見える。いつも鉄柵と施錠された門扉が進入を阻んでいたのだが、最近は自由に入ることもできるようになったのかと、門の前まで行ってみた。施錠されていない。門扉を開けて中に入ってみた。丁度、その時、反対側の山かげから小学生たちの集団が現れて門扉の方へと下って来た。男性の教師も。こんにちは、と笑顔で挨拶するも、何やら妙な空気。男性教師曰く「此処は立ち入り禁止です。我々は特別の許可を得て入山しています。」 とんだ闖入者となってしまったことに苦笑しながら退出。MTBで来た道を取って返したという次第。 本日の記事はここまでとします。続きは明日以降の記事になります。 (つづく)
2017.04.30
コメント(10)
-
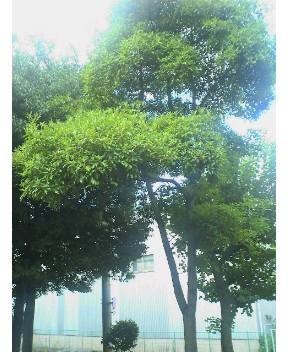
ブログ開設10周年
ブログ更新をサボっているうちに、4月29日を迎えてしまいました。 実は、4月28日付けで堺銀輪散歩の記事を途中まで書き始めていて、その下書きが保存されているので、今日、それを完成させる心算でいたのですが、その「今日」が4月29日という特別の日であることに、今日になって気付いた次第。 今日4月29日で当ブログは満10歳となるのである。ブログ開設10周年であります。 我々は、混沌よりも秩序だったものを、雑然としたものよりも整理されたものを好む習性がある。我々の「認識」というシステムは外界に雑然としてあるものに何らかの意味付けをしたり、共通項を見出したり、本質的でない相異を捨象したりして「整理」するという作用である。従って、この認識システムに馴染まないというか、整理しきれないものにさらされ続けることはストレスとなる。 話が横道にそれましたが、そんな訳で我々は「区切り」というものを好む。誕生日を目出度いと感じるのもそれと無関係ではあるまい。10という「区切り」の数字と「誕生日」という区切りが重なっている10周年は特に目出度いという訳である。 となれば、他の記事はさし置いても、今日の記事は、ブログ開設10周年をテーマにしなくてはならないのであります(笑)。 2007年4月29日12時51分49秒に「偐万葉田舎家持歌集」は誕生したのである。よって、本日午後1時少し前に満10年を迎えることとなる。<追記注>上記の「12時51分49秒」というのは、当該記事の改行などの乱れを修正するための編集をした2008年12月20日の訂正加筆時刻を誤って記載したもので間違い。正しくは「午後3時」である。よって、「本日午後1時少し前に満10年を迎える」という部分も「本日午後3時に満10年を迎える」に訂正です。> 十年ひと昔、と言うから、当ブログも「ひと昔」を経ることとなる。ヤカモチの ブログは見ても 根なし草 知恵浅からし ひと昔経ど (偐家持)(本歌)磯の上の 都麻麻を見れば 根を延へて 年深からし 神さびにけり (大伴家持 万葉集巻19-4159)(注)都麻麻=つまま。タブノキ(タモノキとも言う)のこと。 この手の記事には銀輪散歩記事と違って関連写真が存在しない。 ということで、上の万葉歌にかこつけて、タブノキの写真でも掲載して置くことといたします。何れも当ブログ過去記事に掲載のものを転載いたしました。写真キャプションのリンク部分をクリックしていただくと当該リンク記事のページに入れます。<都麻麻(つまま)2007.8.9.記事より転載> ※これは、近所の加納緩衝緑地公園で撮影したもの。<鶴岡銀輪散歩(6)2013.5.29.記事より転載> ※これは山形県鶴岡市内で撮影したもの。<高岡・氷見銀輪散歩(その4)2015.8.29.記事より転載> ※これは富山県高岡市の雨晴海岸で撮影したもの。 ついでに、4月29日についての余談。 これは、ブログ開設9周年の記事にも書いたことであるが、4月29日は小生が若い頃にその詩を愛読したこともある詩人・中原中也の誕生日である。彼は1907年4月29日に生まれている。当ブログは偶然にも中也生誕100年の日に誕生しているのである。従って、当ブログの〇周年の〇に100を足せば中也の生誕〇周年が分かるということになり、ブログ誕生〇周年を祝うことは、同時に中也生誕〇周年を祝うことでもあるという次第。 まあ、それはさて置き、何とか10年です。これも当ブログをご訪問下さる方々、コメントを下さる方々に励まされてのことでもありますれば、そのご好誼に感謝であります。10年は続けられました。次の10年もかくありたきものと存じますが、わが命がそこまで続いているかどうかは定かではありません。皆さま共々20周年を迎えられますことを祈りつつ、また新しい一歩を踏み出す、その一歩が今日から始まったということでありますれば、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。 恒例の年別記事件数を記載して置きます。 2007年 128件(4月29日~12月・247日間) 2008年 193件 2009年 216件 2010年 203件 2011年 222件 2012年 233件 2013年 251件 2014年 241件 2015年 210件 2016年 178件 2017年 62件(4月29日まで・119日間)<追記訂正2021年4月16日>上記各年別記事件数に一部誤りがあり訂正しました。
2017.04.29
コメント(12)
-

銀輪散歩・マンホール(その9)
今日はマンホール・シリーズ第9弾の記事です。 銀輪散歩で見掛けたマンホール蓋を写真に撮ってブログ記事にアップし出したのは2013年10月からで、もう3年半になります。今回掲載する23件の写真を加えて、これまでにアップした写真は203枚となり、遂に200件突破であります。 別にマンホールを目当てに銀輪散歩している訳ではなく、偶々に出くわしたものを撮っているだけなのだが、随分の数になったものです。 前回のマンホール記事は3月15日。この処、遠出もしていないのであるが、マンホール蓋の新しい図柄の写真が23枚も溜まりました。いつにない豊作でありますが、1枚が奈良県で残りは全て大阪府域内のものです。1.八尾市 八尾市のマンホールは(その1)と(その3)にも掲載して居りますが、これは(その1)に掲載のマンホールのカラー版です。2.松原市 松原市ということで、松とバラ。大阪らしい駄洒落の図柄であります。3.堺市 堺市ではこの図柄のマンホールが一番よく見かけます。市の花であるハナショウブが描かれています。左が普通サイズで右が小型サイズのものです。 左は上の一般的図柄のものの色違い版。右はその表面に樹脂製ステッカーを貼り付けたもの。こういうものをマンホール蓋の図柄に含めるのは邪道であるが、まあ、いいでしょう。 左は市制100周年(平成元年)の記念切手ならぬ記念マンホール。同様に右は、政令指定都市移行記念のマンホール。そして、これは親子型と言われるタイプの蓋である。 左は、菊と筏をあしらっていますが、由縁は思いつかない。何処かで見た図柄だと思うも、思い出せなかったのだが、今回のアップに際して、枚方市のそれ(コレ)であることに気付きました。従って、筏ではなく、これは「くらわんか船」であるようです。 しかし、何故、堺市内に枚方市のそれと同じ図柄のものがあるのか。 これを製造したメーカーが堺市にあり、何らかの手違いか事情があって、このマンホール蓋の管理・所有者の依頼により、これを流用したということではないかなどと推理してみたが、真相は不明。これは或る神社の境内にあったもので、堺市の管理するものではなく、当該神社の私的所有に属するマンホール蓋であるのだろう。 右は、旧堺燈台が描かれているが、白・青二色の美しい図柄である。 下の2枚も、同じ旧堺燈台の図柄で、色の異なるもの、ベージュ・モノクロ版である。右のそれはブルーとの2色であったものが色落ちしたのか、何らかの染料をかぶってしまって、はからずも下地に色が付いてしまったというものであるのか。 これは、旧美原町のもの。旧美原町は、現在は堺市に合併されて、堺市美原区となっている。町章を町の木であるクスノキと町の花であるツツジの花が取り囲んでいる図柄である。4.高石市 高石市の高師の浜には羽衣伝説があることから、中心に羽衣をまとった天女が描かれている。上下に配されているのは波。「おとにきく たかしの浜の あだ波は かけじや袖の ぬれもこそすれ」(祐子内親王家紀伊 小倉百人一首72)の歌ではないが、その「あだ波」であろうか。左右の図柄は、市の木が松であるから、松葉であるのかも知れない。 左が普通サイズのもの。右が小型サイズのものです。細かい処で微妙に違いがあります。5.泉大津市 泉大津と言えば毛布の町。八尾市のそれは河内木綿の糸を紡ぐ女性であるが、こちらの女性は毛布を織っているのであろう。6.河南町 河南町は百合と桜の図柄。町の木が桜で、町の花が百合ということのよう。まあ、桜を愛した西行さんが眠る弘川寺がある町ですから、桜は外せないでしょうね。百合と河南町との繋がりは思いつかない。7.千早赤坂村 千早赤坂村は、村の木・クスノキと村の花・山百合とを配した図柄。「太平記の村」と記載されている背景は金剛山のようでもあり、兜のようでもある。手前の流れは千早川であると共に、楠木正成の菊水の家紋を連想させるデザインになっている。8.その他・大阪府 これは大和川の遠里小野橋の下の河川敷にあったマンホール蓋。何処の管轄なのかは不明であるが、通信とあるから、河川管理のための通信用ケーブルが通っているのかも知れない。であれば、国土交通省の管理下ということになるのか、それとも通信ということで郵政省の管理下になるのか。 左は、外環状線道路(国道170号)で見つけたものであるが、下水道ではなく上水道の給水栓が下にあるらしい。災害時などにこれが使われるのだろうか。「あんしん給水栓」という文字からそんな風なことが水量、違った推量される(笑)。 右は「流域下水道」のマンホール。(その1)にモノクロ版のものを掲載済みであるが、こちらはそれのカラー版である。モノクロ版は寝屋川市か交野市かその辺りで見掛けたと記憶するが、こちらのカラー版は松原市か堺市かその辺りで見たもの。虫や植物の標本採取ではないから、何処で撮影したものかは必要なかろう(笑)。9.斑鳩町 これは、図柄の判別が困難なマンホール蓋であるが、よく見ていただくと法隆寺の五重塔と松が描かれています。この図柄のものは(その8)に普通タイプのモノクロ版とカラー版を掲載しています。それにしても何故このような不鮮明なものを使っているのでしょう。<参考>過去の「銀輪散歩・マンホール」の記事はコチラから フォト蔵のマイアルバムのマンホール写真はコチラから
2017.04.24
コメント(10)
-

七宮めぐり余録
記事が前後しますが、18日の七宮めぐりの記事の余録です。 四天王寺七宮めぐりの途中に立ち寄ったその他の場所や掲載漏れとなった写真などをご紹介して置きます。 <参考>四天王寺七宮めぐり 2017.4.18. 先ずは、大江神社境内の芭蕉などの句碑です。この句碑の写真は過去記事で紹介済みであると思い込み、掲載しなかったのですが、その過去記事では、句碑のことに触れた文章はあるものの、写真はピンボケで掲載できなかった、と記述していることが判明。ということで、今回撮った写真を掲載して置こうという次第。 (大江神社の芭蕉ほかの句碑)あかあかと 日はつれなくも 秋の風 (松尾芭蕉)よる夜中 見ても桜は 起きて居る (松井三津人)綱の子の 名にやあるらん 杜宇(ほととぎす) (松井千季)春風の 夜は嵐に 敷れ鳧(けり) (加藤暁臺) この句碑は松井三津人が文化14年(1817年)に建立したものらしいが、大坂入りした芭蕉が元禄7年(1694年)9月26日にこの神社の隣にあった料亭浮瀬にて句会を開いたことに因んでのものとのこと。 しかし、芭蕉の「あかあかと・・」の句は、おくのほそ道の金沢での句会で披露された句にて、此処で披露されたものかどうかは不明。夕陽ヶ丘の地ということで句碑建立者がこの句が相応しかろうと選んだに過ぎないのかも。でなければ、芭蕉さんが手抜きをして金沢での句を二番煎じしたことになる。 そもそも、松井三津人と芭蕉とは100年近い年代のずれがあるから、此処に記載の句は、浮瀬での句会の句とは無関係のものなんだろう。 千季は三津人の父で、その友人が加藤暁臺。暁臺は蕉門であったと説明しているサイトもあるから、三津人が任意に選んだ句を自身の句と並べてみたまでということかも。(同上・説明板) それよりも小生の目を引いたのは「元禄7年9月9日に大坂入りし」の部分。芭蕉のこの折の句に「菊の香にくらがり登る節句かな」というのがあり、その句碑がわが家近くの枚岡公園のくらがり峠へと続く坂道にあるからである。この句碑のことは過去の記事(暗(くらがり)峠 2009.1.29.)にも紹介しているが、この旅は芭蕉最後の旅となり、体調を崩し、病に倒れ「旅に病で夢は枯野をかけ廻る」の病中吟を最後に10月12日に亡くなっているのである。享年51歳。遺言により、遺骸は大津の義仲寺に葬られる。 <参考>行く夏も近江の人と惜しむべき 2012.8.30. 義仲寺余聞-木曽殿と背中合わせの暑さかな 2012.8.31. (茶臼山・登山口) 堀越神社の裏手は茶臼山である。 標高26mの名山。 七宮めぐりのオマケで登ってみました。 茶臼山という名の山は全国に200以上もあるらしいから、茶臼山と言っただけでは山を特定したことにはならない。此処で言う茶臼山は大阪5低山の一つ、天王寺区茶臼山町にある茶臼山古墳である。 <参考>茶臼山・Wikipedia 茶臼山古墳・Wikipedia 大阪再発見・大阪市内の山 因みに、大阪5低山とは天保山山岳会が選定した次の山とのこと。 天保山、御勝山(岡山)、聖天山、帝塚山、茶臼山(茶臼山・頂上) 頂上には、昨年の大河ドラマ「真田丸」のこともあってか、それとも1615年の大坂夏の陣から400年となる2015年に向けて一昨年にでも設置されたものか、真田幸村についてのパネル展示がなされていました。長らく立ち寄ったこともなく居ましたので、気が付かずに居ました。 <参考>大坂の陣・Wikipedia(山頂・三角点) (茶臼山・南東側から望む) (茶臼山・南西側から望む) 次は、四天王寺庚申堂。 四天王寺の南門から200m余南に入った処にある。七宮のうち、痕跡をとどめないという土塔宮(土塔神社)は、どの辺りにあったものかと適当に南門の南側を廻っていて見つけたもの。 土塔神社がこの辺りにあったとしてもおかしくはない位置取りではある。 <参考>四天王寺庚申堂・OSAKAINFO(四天王寺庚申堂) 七宮ならぬ七福神の像が境内にありました。(同上・七福神石像) そして、久保神社と清壽院との間にあったのがこれ。 関帝廟。大阪にもこのようなものがあったのですな。 <参考>関帝廟・Wikipedia(関帝廟) 次は五條宮。四天王寺の北東隅にある。 こちらは、関羽ではなく敏達天皇を祀る。 <参考>五條宮・Wikipedia 敏達天皇は第30代天皇。聖徳太子の父親・用明天皇とは異母兄弟になるから、聖徳太子から見れば伯父ということになる。皇后・額田部皇女が後に最初の女帝となる推古天皇である。五條宮は過去記事でも紹介しているので、それもご参照下さい。 <参考>銀輪散歩・住吉公園まで 2011.10.17.(五條宮) 銀輪散歩で訪ねたことがある敏達天皇関連の場所と言えば、今思い付くのは次の二つだろうか。 敏達天皇陵 太子町銀輪散歩(その3) 2010.3.10. 訳語田幸玉宮 磐余銀輪散歩(5)・走り過ぎて足に来るらし 2012.10.14. (同上) (同上・説明碑) 最後は、上宮之趾碑のある場所の南側にて見つけた小さな寺。 蔵鷺庵という石漂と永富獨嘯庵國手墓所という石漂が目に入ったので立ち寄ってみた。蔵鷺庵も永富獨嘯庵國手なる人物のことも存じ上げぬことにて、ネット検索してみたら、「上六うえいくネット・蔵鷺庵」というのがありましたので、これをご覧下さい。(蔵鷺庵・永富獨嘯庵國手墓所) ネット検索が面倒というお方のために、その一部をコピーして以下に貼り付けて置きます。 上宮高校のほど近く、路地を少し入ったところに小さなお寺があります。その歴史は古く、聖徳太子の祖父である欽明天皇の御代まで遡ります。四天王寺を鎮守する七宮のうち、鬼門にあたる北東の守りとされたのが上之宮神社で、ここで仏事を行う僧の住む坊が春海庵、すなわち蔵鷺庵の前身です。春海庵は長い間無住寺になっていましたが、1691年、阿波の藩主蜂須賀の家臣稲田稙栄の奥方が開基となり、天桂傳尊禅師が曹洞宗の寺院として再興されました。 蔵鷺庵には、全国にその名を知られる一人の人物が眠っています。名医として漢方医学や西洋医学に優れ、また日本で始めて本格的な白砂糖の製糖事業を始めた永富独嘯庵(どくしょうあん)です。 1732年、現在の山口県下関に生まれた独嘯庵は、幼年期より神童として知られ、後に江戸へ出て儒学の他に医術を学びました。35年の短い生涯の間、江戸と長州を往来する際、何度か大坂に立ち寄りました。 実は、独嘯庵と蔵鷺庵の関係について、詳しいことは分かっていません。しかし、没後かなりの時間が経って墓が建てられたことから、深い縁があったものと考えられます。 墓石は長年の風雪に晒され表面が浸食されたため、平成4年に再建されました。その際、旧墓石は剥落部分が多かったため、旧拓本の写真を原寸大に拡大して、それをもとに忠実に模彫、複製され、旧墓石は現在の墓石の下に安置されました。 現在の天王寺区には江戸後期から昭和にかけて、多くの文人墨客が集まってきました。蔵鷺庵は織田作之助の小説「夫婦善哉」にも登場しており、横山大観の友人でもある北野恒富も寄宿していました。(大正7年~2年)。 ※恒富が横山大観に送った関東大震災の見舞状が実在し、二人の交流を示す貴重な資料とされています。 (同上)(永富獨嘯庵國手墓) (墓碑) (副碑) 以上、四天王寺七宮めぐりのオマケ記事でありました。
2017.04.23
コメント(2)
-

千早城へ
千早城趾まで銀輪散歩して来ました。 石川沿いの道を行き川西大橋で国道309号に入り東へ。「道の駅かなん」で暫し休憩。この先、食事する店がないかも知れないと、昼食用に「山菜ごはん」のお弁当を購入。ついでに「よもぎ団子」も。 道の駅かなんの先の神山南交差点で右折し、南へ。直ぐに千早赤坂村となる。道の駅の手前までは富田林市、道の駅から神山南交差点までが河南町、交差点の少し南から先が千早赤坂村である。富田林市と千早赤坂村の間に割り込むような形で河南町の南端が突き刺さっているのであるが、その部分を通り抜けたことになる。 千早赤坂村に入ると道はひたすら上り坂となる。千早城趾まで約10km。ずっと上り坂が続くタフなコースである。花を見付けては写真に撮ったり、煙草を一服したり、お茶を一口飲んだり、これらを口実に足を休めながら、息を整えながらの、ゆっくり走行である。急坂ではギブアップして押して行く。復路の爽快な下りを楽しみにしての我慢・忍耐の往路である。 道は森屋交差点で国道309号と府道705号に分岐する。右側の府道705号を行く。府道705号は千早川沿いの道である。(千早川・森屋交差点南300m付近) 上の写真の千早川を渡ってすぐの位置に左に入る道があり、楠公誕生地という表示板が目に入る。S字カーブの坂道を上った処に、それはありました。千早赤坂村郷土資料館の前にその碑がありました。(楠木正成生誕地碑) 楠木正成は河内に生まれ育った小生には小さい頃から馴染んだ名前であるが、その誕生地を訪ねるのは初めてである。彼は湊川の戦いで亡くなるが、その地にある湊川神社は彼を祀る神社。あちら湊川の方はかなり前に訪ねているから、これでブログ上でも、誕生地と死亡地、両方の訪問を果たしたことになる。 <参考>神戸クルージング 2009.9.26. 道沿いにはレンゲ畑が広がって、丁度今が花の盛り。(レンゲ畑・千早赤坂村郷土資料館付近) (同上) 千早赤坂村役場を過ぎ、地元の物産直売所の前で右に上る坂道があり、下赤坂城趾の表示板。立ち寄ることにする。道は中学校の校門から敷地内へと通っている。学校の敷地内に無断進入しているみたいな居心地悪さを感じながらも、道なのだから自由に通れるのだろうと校舎の間を抜けて、上の高台に出る。(下赤坂城趾)<参考>下赤坂城・Wikipedia 上赤坂城・Wikipedia そこには、高々と「史蹟赤坂城趾」の碑がありました。(赤坂城跡説明板) 今回は上赤坂城趾には立ち寄らずでしたが、これは次の機会に挑戦します。(千早赤坂村文化財位置図) 高台からは下赤坂の棚田が一望できる。其処にはベンチや東屋があり、簡易トイレも設置されている。ということで、少し早いが此処で「お弁当タイム」とする。日本の原風景を眺めながらの昼食である。 <参考>下赤坂の棚田・千早赤坂村観光協会(下赤坂の棚田) 棚田では農作業する人の姿も見える。春草を除草して焼いているのだろうか、野焼きの煙がひとすじ空へと立ち昇る。雉の甲高い鳴き声も時折聞こえて来る。まだ田植えの時期でもなく水も張られていないが、水が張られたり、稲穂が黄金に実る時期には、さぞや素晴らしい眺めになることだろう。 この下赤坂の棚田は、日本棚田百選にも選ばれているとのこと。 昼食後、再び府道705号に戻り、だらだら坂の道を上る。 丁度村会議員選挙の最中らしく、候補者の車と頻りにすれ違う。何度も出くわすので、候補者の名前も4人ばかりは覚えてしまった(笑)。 河内長野市方向へと通じる道との分岐にて「山頭火」と遭遇。(山燈花) よく見ると「山燈花」であった。予約制とあるから、レストランか何かなんだろう。わが友人の偐山頭火氏に見せてやりたい看板である(笑)。矢印の示す方向は、わが行くべき道とは違っているので、その正体は突き止めぬままに、なお坂道を上る。 分け入っても 分け入っても 奥河内 で、延々と続く坂道は流石に疲れるのであります。(千早赤坂村の民家・薬師寺付近) 民家の佇まいも山々の景色もいい。 民家の写真を撮ったりしては、休憩。 山の景色を撮ったりしては、また休憩。 道の辺の草花を撮ったりしても、またまた休憩。 花については、最後にこれをまとめて掲載することとしますので、それまでお待ち下さいませ。 上の小さい写真は、やって来た道を振り返って撮ったもの。自動販売機があり、トイレもあったので飲み物とトイレ休憩をしたついでに撮ったものです。正面奥に見えている山が上赤坂城跡のある山であるのかも知れない。(千早赤坂村) 千早大橋を渡って少し行くと眺望が開けた場所に出る。眼下に集落がある。千早の集落である。千早城趾が此処から見えます、と道脇の看板に表記があったので、それとおぼしき方向にカメラ向けたが、よくは分からない。 (千早城趾のある山) (集落背後の山) 漸くにして千早城趾に到着である。いや、正確にはその登り口に到着である。 道の向かいに交番がある。交番脇の広場に自転車を駐輪して、石段を上る。何とも急な階段である。(千早城趾) 千早城に来るのも初めてである。 小学生の頃、父と銭湯に行った帰りに、その隣にあった貸本屋で本を借りて読むのが楽しみの一つであったが、3年生であったか4年生であったかは定かではないが、「風雲千早城」(このようなタイトルであったかどうかも記憶が曖昧であるが)とかいう本を借りて読んだことを何故かよく覚えている。太平記をネタ本にして、鎌倉幕府軍と楠木正成との千早城や赤坂城での戦いを物語にした本であった。(千早城跡説明碑) (千早城趾・千早神社への石段) この石段、とても長い。九十九折に延々とある。ちょっとした登山であります。長い坂道を自転車で上って来た足には応える石階段にて候。上の写真の鳥居から下の写真の「千早城趾・千早神社」までの間に長~い石段があるのです。そして、漸くに到着です。 (千早城趾) (千早神社鳥居) 二つ目の鳥居の奥に千早城趾の石碑があって、その更に奥の一段高い処に、千早神社本・拝殿がある。(千早城趾碑)<参考>千早城・Wikipedia 拝殿前にあるこの碑を撮影したところで、デジカメの電池切れ。 仕方なく、拝殿はスマホで撮影。 予定では、千早城の裏側の道の奥に楠木正儀の墓があり、それに立ち寄ってから帰る心算でいたのだが、電池の切れ目が縁の切れ目、そのことも忘れて、山を下りると、そのまま、自転車で帰途についてしまいました。(千早神社拝殿)<参考>千早神社・Wikipedia 帰途は延々10kmの下り坂である。ほんの一部に上りもあるが、それを除けばブレーキを掛けることはあっても、ペダルを漕ぐ必要はないという楽々走行なのである。2時半位に千早城趾前を出発し、道の駅かなんに到着したのが、2時57分。30分を要せずに走り下れてしまいました。往路のしんどさは何であったのか。 そんなことで、復路の写真はありません。 往路で、休憩の口実に撮った花の写真を以下に掲載して、記事のまとめといたします。ただ、最後の白い花については名前が分かりません。名前を知っていると否とにかかわらず、これらの花に疲れを癒されながらの銀輪散歩でありました。 (フウロソウ)何フウロかまでは分かりません。 ※写真をクリックして大きいサイズで見ることもできます。 <追記>小万知さんからヤワゲフウロだと教えていただきました。 (クサノオウ<草ノ王>)ちはや道 咲きたる花は 草の王 ふうろすみれに 紫華鬘 (草家持) (スミレ) (ムラサキケマン)(名前不詳) (同上)
2017.04.22
コメント(12)
-

四天王寺七宮めぐり
天王寺七坂は巡ったことがあるが、四天王寺七宮というのもあるので、今日はこれを巡ってみました。四国八十八ヶ所や西国三十三所に比べれば四天王寺七宮巡りはお手軽で、銀輪散歩向きである。 四天王寺七宮というのは、聖徳太子が四天王寺を建立した際に、その鎮護のため、周辺に造営された七つの神社のことである。<参考>四天王寺七宮・Wikipedia 1.上之宮神社(上之宮町) 2.大江神社(夕陽ケ丘町) 3.堀越神社(茶臼山町) 4.土塔神社(大道1丁目) 5.河堀稲生神社(大道3丁目) 6.小儀神社(勝山1丁目) 7.久保神社(勝山3丁目)の7社を言う。 このうち、現存するのは、大江神社、堀越神社、河堀稲生神社、久保神社の4社のみ。上之宮、土塔、小儀の3社の祭神は大江神社に合祀されている。しかし、上之宮神社と小儀神社については、その址を示す碑が存在しているということを、最近になって知ったので、これを巡ってみようと思い付いた次第。 但し、土塔神社はその痕跡をとどめず、これを偲ぶ如何なるものも存在しないとのこと。従って、正確には六宮巡りということになる。 先ず、上之宮神社。上宮高校の南側、道路を挟んで向かいにあるマンション・上之宮台ハイツのエントランス前に、上宮之址碑がある。 正確な場所は不明なるも、このマンションや上宮高校のあるこの付近に上之宮神社があったのだろう。(上宮之址碑) 上宮高校の南側道路を西へ。上町筋に出て左折、南へ。上本町9丁目交差点で右折、西へ。谷町筋に出る。 愛染堂の西側にあるのが大江神社。 この神社は天王寺七坂めぐりをした折などにも訪ねている。 <参考>天王寺七坂 2015.1.22. 大阪市南部銀輪散歩(1.上本町から天王寺へ) 2011.7.15.(大江神社)(同上・拝殿)(同上・本殿)(同上・由緒書) 谷町筋を更に南へ行くと、堀越神社である。此処も以前に訪ね、紹介済みである。 <参考>銀輪散歩・住吉公園まで 2011.10.17.(堀越神社)(同上・拝殿)(同上・由緒書) 次は、四天王寺の南大門前。この付近に土塔神社があったらしいが、今はその痕跡をとどめない。 土塔、と言うと、偐山頭火氏と訪ねた、堺の土塔のことが思い出されるが、勿論、両者は無関係である。 <参考>土塔を訪ねて 2010.4.30.(四天王寺南大門前) 南大門前の道を東へ下り、大道3丁目交差点で右(南)に入ると河堀稲生神社である。「河堀」を「こぼれ」と読む。地元・大阪人以外で読める人は少ないだろう。(河堀稲生神社)(同上)(同上・由緒書) 河堀稲生神社の東側の道を北へ行くと、寺田町公園があり、その公園の北側にあるのが久保神社。(久保神社)(同上)(同上・由緒書) そして、最後が四天王寺東大門付近にあったという小儀神社であるが、これは、東大門の前から東に延びている道路の道沿い北側に建っているマンションの脇に、その址を示す石碑という形で、その痕跡をとどめている。(小儀宮址碑)(同上) (同上) 小儀宮址碑から東大門に出て、右折し北へ。五條宮前経由、天王寺区役所の前に出て、その北側の道を東へ、大阪警察病院前で、その西側の道を北へと行くと上宮之址碑である。 これで七宮を一周したことになる。(四天王寺東大門)(同上) 七宮それぞれの詳しいことはWikipediaや上記参考記事並びに由緒書の写真などをご参照下さい。夜も更けたので、手抜きさせていただくこととします(笑)。
2017.04.18
コメント(10)
-

お見舞いかたがた銀輪散歩
昨日(16日)は、お見舞いを兼ねて寝屋川まで銀輪散歩でありました。お見舞いに行く病院は外環状線道路の豊野交差点近くにある。 友人でブログ友でもあるオガクニマン氏の奥様が病に倒れられたのは2月の初旬。京大病院での2度の手術を経て、現在はこの寝屋川の病院に転院されてリハビリ療養中。お見舞いは病人に対するものであるが、「夫の友人がお見舞いに来たりするのはノーサンキュー」という我が妻の意見もあり、それもそうだと、小生はオ氏をお見舞いすることにしたもの。オ氏もこの間、付き添いその他のお世話で大変な日々を過ごされて来たのであってみれば、お見舞いを受ける資格は十分にあるだろう(笑)。もっと早くにお見舞いに行くべしでオ氏に電話したが、「京大病院までのお見舞いは大変だろうし、近くの病院に転院してリハビリ療養となるだろうから、その折にでも。」ということであったので、今回のお見舞いとなった次第。 病院のロビーで午後2時にオ氏と待ち合わせ。瓢箪山駅前の馴染みの果物屋さんでメロンを買って、これをザックに入れて出発。 病院近くまで来たが早く着き過ぎるので、方向転換して打上川治水緑地公園に向かう。寝屋川沿いにあるこの公園は、その名が示す通り、寝屋川に流れ込む打上川の流水量が急激に増加した場合に、水をこの公園に引き込み、その流量を調節して寝屋川の増水を緩和することによって、下流域での氾濫・洪水を防ごうという遊水地公園である。深北緑地や花園中央公園と同じ機能を有する公園である。 この公園は2008年7月7日に天野川べりから自宅への帰途、出鱈目に走っていて、偶々に出くわしたのが最初。以来、何度か立ち寄っている。 <参考>七夕 2008.7.7. 打上川治水緑地公園など 2013.10.22.(打上川治水緑地) (打上川治水緑地のサトザクラ) 公園内のソメイヨシノはあらかた散ってしまっているが、八重のサトザクラが咲き始めて、主役交代の趣である。 公園を出て、北側を流れている寝屋川べりを少し走ってみる。(寝屋川) 道脇に小さな石漂があった。式内細屋神社とある。 見回しても神社らしきものが見えない。 (同上) (細屋神社) 細い道を下って行った先に見える小さな森がそれのようであるが、立ち寄ることはせず。少し下流に架かる橋を渡ると八幡神社があった。(細屋神社の杜) この付近は、讃良郡秦村と呼ばれていたらしい。 讃良と言うと持統天皇は鵜野讃良皇女であるから、何か関連があるのかも知れない。また、秦村からは古代にはこの地が秦氏の支配地であったことが分る。(八幡神社・寝屋川市八幡台) この小さな八幡神社は、説明板によると、秦河勝の勧請により創建されたという伝承があるらしい。秦河勝と言えば聖徳太子を支えた人物。 拝殿裏に井戸があって、井戸の中にはお地蔵さんが居られるそうだが、覗いてみた。水中の様子は、水面に浮かぶ落ち葉などが邪魔をして、上からは何とも見て取れなかった。 日照りが続くと、昔は、この地の農民は水底のお地蔵さんを引き上げてお祀りし、降雨を祈願したという。 (同上)※写真をクリックすると大きいサイズでご覧になれます。 この神社の拝殿・本殿はご覧のようにカラフルで一風変わった雰囲気である。 なお、お地蔵さんが居られる井戸は下掲写真の拝殿の左側にあります。また、上の神社由緒書きによると、細屋神社とこの八幡神社とを併せて宗教法人八幡神社になっているとのこと。(同上・拝殿) そろそろ時間なので、病院の方へ引き返すこととする。 打上川は寝屋川に流れ込む小さな川である。 枝垂れ桜が咲き乱れて川面に花筏をなしていました。 もう少し川幅があって、水量も多く水面が美しければ、と惜しみつつカメラを向けました。(打上川の枝垂れ桜と花筏) 治水緑地の西側には加茂神社がありました。こちらは鴨氏ですな。 (加茂神社<寝屋川市>) (同左) 病院に到着。駐輪場にMTBをとめて、入口前のベンチでお茶を飲んでいると、オ氏がやって来られました。 奥様を病室に見舞うのはご遠慮したが、1階ロビー近くのリハビリ室でリハビリ中であられたと見えて、看護師さんに付き添われて奥様もやって来られてご挨拶を受けることとなりました。順調に回復されているご様子にてひと安心。早期にご軽快されることをお祈り申し上げます。 近所に唯一ある喫茶店が日曜日でお休み。仕方なくファミレスのガストに入ってオ氏と暫く雑談。お昼の時間は全席禁煙らしく、オ氏も小生も喫煙者にてあれば、不本意なれど是非もなしである。30分か40分そこで彼と過ごし、店の前の灰皿の置かれている場所で煙草を一服した後、病院に戻り、MTBを引き出し帰途に。午後3時少し前頃であったかと。(第二京阪道路の陸橋から眺めた生駒山) 第二京阪道路は自転車や歩行者は斜路を上ってこれを渡ることとなる。 生駒山もこの付近から眺めると違った雰囲気に見える。 深北緑地まで帰って来ました。外環状道路の下を潜って深北緑地の池に流れ込んでいる水路の堤に、このような桜並木がありました。水路は干上がって春草繁きの状態にて花筏を浮かべる水がない。水が十分にあったら、ここなら美しい花筏が観察できたのではないかと思いましたが、そう都合よくは参らぬのが現実。(深北緑地東側・河北病院南側の水路の桜) 深北緑地、花園中央公園に立ち寄った後、自宅へ。4時半過ぎに帰宅。打上川治水緑地とあわせての3遊水地公園めぐりの近隣散歩でもありました。
2017.04.17
コメント(10)
-

第19回和郎女作品展
第19回和郎女作品展 本日は、偐家持美術館主催の第19回和郎女作品展とします。作品は、4月2日の若草読書会のお花見の折に、出席者へのお土産にとお持ち下さったものです。 作品点数は5点と少ないので、もう少し点数がまとまってから開催しようかとも考えましたが、次回読書会は6月開催、それまで待っていては、今回の作品の季節的なものを考えると遅きに失することになる。加えて、次回読書会に彼女がご出席になるのか、また、ご出席の場合でも、作品をお持ちいただけるかどうかは不明、ということで、偐家持美術館企画委員会の決議に基づき、同理事会の承認を経て、本日開催に踏み切ったという次第(笑)。 <参考>過去の和郎女作品展はコチラからどうぞ。 先ずは、桜です。(山桜) 上は、青い葉が見えるので、山桜でしょうか。 下は、八重桜ですね。(八重桜) そして、鯉のぼりです。 端午の節句も近づいて来ましたので、少し季節を先取りです。 このデザインの作品は、小生が頂戴したもので、我が家に現物があります。(鯉のぼり) 次も、端午の節句に因んだ作品。 兜と粽と鯉のぼりです。 尤も、よく見ると、幟は鯉ではなく、花模様ですから、鯉のぼり、ではなく、粋に「恋のぼり」とでも言って置きましょうかね(笑)。(兜・鯉のぼり・粽) ちまき(粽)は、茅巻である。茅・茅萱で巻いたものが「チ・マキ」である。茅の輪くぐりの神事が今もあるように、チは聖なるもの、邪を払う霊力のあるものと考えられていたのだろう。従って、チ(茅)で巻いたものを食べることによって、その霊力を身に取り込むことができるということになる。 そう言えば、「い・チ(一)」も、「いのチ(生命)」も、「チ(血)」も、「チ(地)」も、「チ・から(力)」も「チ」である。 チで巻いたものには霊力がある。で、頭に巻くものも「は・チ・巻」と呼ぶのだろうか。それは「チ・がうよ」と誰かさんが言っているような気もするが、そんなことは「チ・っとも」気にしないのが「ヤカモ・チ」である。 「チ・ゃんと」ヤカモチにも「チ」があるところがミソである(笑)。(同上) いつもながらの、心がほっこりとする、和郎女さんの楽しい作品でありました。皆さまもお楽しみいただけたでしょうか。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。<追記>書き忘れていましたので、追記です。上の写真は全てひろみの郎女さんが撮影されたもので、彼女から写真の提供を受けました。
2017.04.15
コメント(10)
-

囲碁例会・散らずあり待つ桜かな
本日は囲碁例会の日。雨の心配もないので、MTBで梅田まで。 西高東低の冬型の気圧配置で気温も低め。家を出た時はやや肌寒い感じであったが、自転車で走っているうちに体がヒートアップ、汗ばんで来たので、途中からは上着を脱いでの走行となりました。9日の雨と強風で散ってしまったのではないかと思われた桜であったが、どっこい「花の命は結構長い」のでありました。つぎつぎて咲くものならし桜花で、9日の夜半の嵐の時には、未だ蕾であったものも多くあったと見えて、道中の街路の桜はまだ満開と言ってもいい位に花がいっぱいで十分に「お花見」に堪える咲きっぷりでありました。 大阪城公園の桜も同様で、お花見をしている人たちの姿も多く見掛けたのでありました。 JR森ノ宮駅前から大阪城公園に入る。植木市の店が両サイドに並んでいて、これを見ながら行くのも楽しい。(大阪城公園の桜・森ノ宮駅前入口) 下掲は公園見取図。右下のJR森ノ宮駅前から、赤線のコースで大阪城公園を通過。(大阪城公園見取図) ーー線:往路コース、ーー線:復路コース(大阪城公園の桜・玉造口付近から東外濠を眺める) 桜だけでなく、桃の花も咲いている。桃園も見て行く。(大阪城公園の桃・桃園) 桜の花が大人の女性の妖艶な美しさというイメージなら、桃の花は少女の可愛らしさというイメージでしょうか。従って、夜桜見物はあっても、夜桃見物はない。これは青少年保護条例などとは無関係の、古来からの感性に由来するものだからである(笑)。(同上) 大阪城公園を出て、天満橋駅前から天満橋を渡るいつものコースを行こうとすると、駅前から造幣局に向かって、長蛇の人の列。例の「桜の通り抜け」に向かう人の群れである。天満橋を渡る際は、車道ではなく歩道を走るのが習慣になっているので、いつもの通り、歩道へと向かおうとして、この時期はダメであることに気が付く。歩道は左側一方通行になっていて、造幣局に向かう人と駅に帰る人とが左右サイドそれぞれに溢れんばかりに歩いている。とても自転車が進入できる状況ではない。車道側に進路を取り、大川を渡る。横断歩道では、交通整理のお巡りさんが何人も出て、ゴー、ストップの指示を出して、人波の整理に余念がない。 こんな風になるのは、「天神祭り」の時とこの「桜の通り抜け」の時くらいでしょうか。ともかくも人波を抜けて、昼食のため、れんげ亭へと向かう。 正午少し前位に、れんげ亭に到着。 男性客が一人、先客あり。れんげの郎女さんとの会話の様子から常連さんとお見受けしましたが、小生がお目に掛かるのは初めて。生駒山の麓から自転車で来ている、と聞いて驚いて居られましたが、此処での昼食のために来ているなら十分に変人であるので、変人ではないことを示すため、梅田まで囲碁をしに行く途中なのだと申し上げたが、それでもやっぱり変人かも知れないと、内心苦笑。 ややあって、先週もお見かけした、この付近の工事現場で働いている若者と見られる男性客4人が来店。更に、もう一人男性が来店。今日は繁昌です。 梅田スカイビル到着。 喫煙場所で煙草を一服しながら見上げて撮った写真が下の写真。青空にスカイビルはよく似合う。(今日の梅田スカイビル) 会場の部屋に入るが、人影はない。小生が一番乗りであった。 碁盤や碁笥を取り出して、設営していると、福〇氏がお見えになった。早速にお手合わせする。この処、同氏には3連敗か、4連敗中であるが、今回も、早々に左上辺部の黒石一団を捨て石にして左下辺の白石を取り込む振り替わり作戦が功を奏したかに見えたのだが、寄せでうまくしてやられ、2目半の負け。 対局中に友人の利麻呂氏より電話。同氏は先々月辺りから碁を覚えたいと、この囲碁サークルに顔を出すようになっている。今日も見学を兼ねての参加である。直接部屋に来ていただく。そこへ竹〇氏も来られ、小生らが対局中なので、竹〇氏が利麻呂氏に指導碁。福〇氏と小生の対局が終わったので、メンバーチェンジ。福〇氏と竹〇氏との対局となる。代って今度は小生が利麻呂氏に指導碁。福竹戦は竹〇氏の勝利。 次に小生が竹〇氏と対局。戦局は中盤位までは五分五分か少しばかり小生優位に推移していましたが、終盤にさしかかる頃に、左辺白模様に黒が覗きを掛け進入するぞと見せ、これを白が受ける。そこで、左辺下の白石3子を切断すべく左から黒石が突き出てこれを切断し、3子を取り込んだことによって、左辺下部の黒地が広くなり安定してしまったので、白の「投げ」となり、小生の中押し勝ち。 本日は1勝1敗。この処、負けが続いて大きく負け越しているので、1勝1敗では駄目で、勝ち越さなければ意味がないのであるが、実力不足、なかなかそうならない。「今度がんばろう。」である。 終了後、1階の喫茶店で、暫く利麻呂氏と雑談。 喫茶店で同氏と別れて、再びMTBの人となって、帰途へ。 帰途は、上の公園見取図に示す青線のコース取りで大阪城公園に入る。天満橋は混んでいるだろうと二つ下流の難波橋を渡って、北浜から土佐堀通りを東へ。天満橋駅前から谷町筋、上町筋経由で、大阪城公園に入ったという次第。(復路の大阪城公園の濠と桜) 今日2度目の花見。 夜半嵐 吹けど散らざる 桜花 今日まだありと われにし笑みぬ (偐家持)(同上) 大阪城公園で、暫し桜と遊んでから、中央大通りを東上。中央環状線を越え、荒本の先辺りで南に入り、路地などをジグザグに適当に走って、花園ラグビー場から花園中央公園に入る。 此処でも、桜は散り残っていて、まだ、お花見に堪え得る姿である。今日3度目の花見となりました。(今日の花園中央公園の桜) 此処の桜は、大阪城公園のそれに比べて、葉が少しばかり目立つように感じましたが、傾いた夕日に照らされて、これはこれでなかなかに美しいのでありました。(同上) この桜広場の一角に八重の桜のサトザクラの木が10本程度あるのですが、これはまだ蕾。1週間か10日位したら、今度はソメイヨシノに代って、このサトザクラが艶やかな咲きっぷりを見せてくれることでしょう。つぎつぎて 咲くものならし 桜花 散るるもあれば ふふめるもあり (偐家持) (注)ふふむ=「含む」。蕾の状態を意味する語。「つぼめる」と同義。
2017.04.12
コメント(8)
-

銀輪花散歩・花は盛りを見るべかりける
漸くに付近の桜も満開、今盛りなりとなりましたが、雨が降ったりのお天気続きにて、何となく出そびれていました。幸い、今日は曇り空なるも雨の心配はなさそうと、銀輪花散歩でありました。兼好さんのようにへそ曲がりでないヤカモチは「花は盛りを見るべかりける」なのである。 明日はまた雨の予報。風も強まるそうだから、散ってしまう前に見て置こうという次第。と言っても、朝のうちだけの近隣花散歩。昼食後は書斎にてゴロゴロして居りましたので、余り運動にはなっていない。それはさて置き、満開の桜をご紹介申し上げます。先ずは、近鉄奈良線額田駅南側の踏切前から枚岡公園への坂道の桜並木です。古木が枯れて伐られたりして、昔ほどではないのだけれど、それでも十分に花見が楽しめる道であります。(枚岡公園への坂道の桜) まあ、桜の名所と言う訳でもないので、無粋な看板などもあって、風趣を壊していたりするが、そういうものは見ないことにすればいい、と言う次第(笑)。 額田駅と石切駅の中間位にある小さな公園も、この時期は一年で一番華やかになるのであります。(額田公園の桜)(同上) 石切駅を過ぎて、旧生駒トンネル下の坂道を少し下った処に、日下新池というのがある。その池を取り巻く丘を「パンドラの丘」という。 此処も、桜が美しい。(パンドラの丘の桜)(パンドラの丘の桜) この丘を何故「パンドラの丘」と呼ぶのかは、2013年2月20日の記事を読まれたお方はご承知かと思いますが、太宰治の小説「パンドラの匣」の舞台となる結核療養所が此処にあったからであります。 <参考>パンドラの丘 2013.2.20.(新日下池・パンドラの丘) 今は、その昔を偲ぶものと言えば、このような石垣の残骸のみである。(パンドラの丘) それでは愛想なかろうと、3年前(2014年3月)にこのような説明碑が設置された。(パンドラの丘説明板・孔舎衙健康道場と大宰治) 日下新池から坂を下って行くと大龍禅寺という寺がある。ここの境内も桜が美しい。(大龍禅寺の桜) 大龍禅寺の写真はコチラの記事にも掲載されています。 寺の前の道端にはツルニチニチソウが自生、咲き群れていました。(ツルニチニチソウ)(同上) ノゲシも咲いていました。(ノゲシ) ヤエムグラも繁茂。思ふ人 来むと知りせば 八重葎 おほへる庭に 珠敷かましを (万葉集巻11-2824)玉敷ける 家も何せむ 八重葎 おほへる小屋も 妹とし居らば (万葉集巻11-2825) 葎は、万葉集にも数首登場するが、これは雑草が密生した状態を言う言葉で、このヤエムグラを指している訳ではない。クワ科のカナムグラやこのヤエムグラなどの総称という解釈もある。ハコベも語源は「はびこる」と言う言葉から転訛したという説があるが、ヤエムグラも八重にムグラなす草、というのが、縮んで、後世にこの草の名となったものだろう。確かにムグラなす草に相応しい命名である。(ヤエムグラ) 大龍禅寺から更に坂を下って行くと旧河澄家住宅。歌人・石上露子の母親の実家がこの河澄家である。今は市に寄贈され一般公開されているが、今日は休館日。 軒下で「鯉のぼり」が「雨やどり」、駄洒落のようで、面白い光景。 河澄家住宅と石上露子については、下記参考記事をご参照下さい。 <参考>旧河澄家ーゆきずりのわが小板橋 2013.2.22.(旧河澄家住宅)(スズメノエンドウ) カラスノエンドウはよく見るが、スズメノエンドウはカラスノエンドウほどには見かけない。そう言えば、鳥の方も、稲田などが減少している所為か、昔ほどにはスズメは多くない。カラスの方が目立つ、というのが都市部及びその近郊の今日の姿ではある。 (同上) (同上) そして、最近急速に増えているのが、このナガミヒナゲシ。 旺盛過ぎるその繁殖力は、他の草花たちには脅威かも。(ナガミヒナゲシ)花の数は あまた増えけり いたづらに ながみひなげし ながめせしまに (長実小町) (同上) (同上) こちらは、昔ながらの、ぺんぺん草こと、ナズナ。 ナガミヒナゲシのような外来植物がはびこると、何やら生態系の攪乱要因になるのではと、不気味な感じもするが、ナズナなど古来からある雑草はいくらはびこっても、そういう不気味さを抱かない、これは差別、偏見ですかね(笑)。 (ナズナ) (同左) ミミナグサも同様。在来種のミミナグサは枕草子にも登場する草で、春の七草の一つであるハコベと変わらぬ古来からの植物。これに対して外来種のオランダミミナグサというのがあって、どんどん勢力を拡大し、在来のミミナグサの生存地域を脅かしているらしい。 それでか、余りミミナグサはお目にかからない。目にするのはオランダミミナグサばかりである。で、今日、そのミミナグサらしきものを見つけたのであるが、果たしてこれはミミナグサなんだろうか。(ミミナグサ) ミミナグサは花弁と花柄の長さがほぼ同じで、花柄が長く、蕾が下に垂れる。これに対してオランダミミナグサは、花弁の長さに比べて萼の長さが短い。また花柄が短く、茎にくっつくように蕾が付くので、下に垂れるということがない。これが小生の理解であったので、これに照らせば、これはミミナグサであるということになる。 (同上) (同上) オランダミミナグサであると小生が思っている下の写真の草と比べていただければ分かるように、上の写真の草は、花柄が長く蕾が垂れている。花弁の長さも萼と同じか、それよりも短めで、蕾状態では萼に覆われて花弁が見えない。下の写真の蕾は花弁が萼よりも長く飛び出している。違いは一目瞭然である。 ところが、ネットで調べていたら、花弁と萼の長さはミミナグサもオランダミミナグサも同じ位の長さであるとするものもあって、少し頭が混乱し出しているのであります。まあ、そのサイトでも、ミミナグサは花柄が長く、オランダミミナグサは花柄が短いとしていますから、上がミミナグサで下がオランダミニナグサで間違いがないと思うのですが、元来花のことなどは門外漢の小生であるので、ちょっと異なる情報が入って来ると、自信が無くなってしまうのでありますな(笑)。みみなぐさ ありやなしやの 春の草 きくも咲かねば きくひともなし (耳家持)(オランダミミナグサ・再掲)(同上) 以上、花散歩の記事でありました。 明日は、また雨のようですから、花散歩もままならぬようであります。
2017.04.10
コメント(12)
-

偐万葉・ひろみ篇(その11)
偐万葉・ひろみ篇(その11) この処、雨が降ったり止んだりと不安定なお天気。菜種梅雨と言うのでしょうか。それも風情があると言えば言えますが、銀輪散歩には不向き、「雨つつみ」の銀輪控えめの日々であります。こういう時に重宝なのが「偐万葉」。ということで、前回に続き、本日も、シリーズ第281弾、ひろみ篇(その11)のアップであります。 <参考>過去の偐万葉・ひろみ篇はコチラ ひろみちゃん8021氏のブログはコチラ 偐家持がひろみの郎女に贈りて詠める歌24首 並びにひろみの郎女が詠める歌4首きつねうどん あげかぶりつき 明日香雪 見つ一時過ぎ ひたすらに食ふ (餓鬼皇子) (本歌)采女の 袖吹きかへす 明日香風 都を遠み いたづらに吹く (志貴皇子 万葉集巻1-51) 春花の 咲けるさかりに いざ行かな 明日香ふるさと ともしきろかも (注)ともしきろかも=「ともし」は「羨ましい」であるが、ここでは「心惹かれることだ」とい う意味で使用。朝駆けの 銀輪も無理 如何にせむ 富良野の里に ふれる大雪 (輪上是乗) (本歌)あさぼらけ ありあけの月と みるまでに 吉野の里に ふれる白雪 (坂上是則 古今集332 小倉百人一首31)ゆきゆきて ゆきに倒れむ ヤカモチは 紀の面雪(つらゆき)に なりて死ぬかも (奇貫之) 追ひて和せる歌1首願はくは 青葉さやげる 初夏行かん 富良野に花の 咲き満つる頃 (本歌)願はくは 花の下にて 春死なん そのきさらぎの 望月の頃 (西行 山家集77) 都会っ子も あるものならし 白花に 咲きて梅田に センダングサは都会っ子の 花にしあれば われ呼ばむ ウメダノシロバナ センダングサと (コシロノセンダングサ:けん家持提供)あれやこれ 何ともその名 知らぬ花 花の小万知に 聞きつつぞ来し (花家持)金色(きんいろ)の 豆にしあれど 棘ありて 邪鬼は禁ずと 金豆(きんず)は生(な)れる (金豆家持) (キンズ)鳩は居て 烏は無くも 大寺の 烏有(うゆう)に帰し跡 滝川の園 (旅烏家持) (注)初案「ふる寺」を「大寺」に修正した。 烏有=「烏(いずくんぞ)有らんや」で、何もかもが無いこと。火災などで家財などが 灰燼に帰すことに使う。 脇句なすは ひとによるなり 時による むやみになすは ひがごとなれり (僻事家持) (注)ひがごと=事実に合わないこと、間違い、過ち。道理に合わないこと、悪事。 ごんぼ汁 知るよしなけれ くらはんか 鮨もくらはじ 鍵屋はしるも (注)鍵屋はしるも=「鍵屋は知るも」と「鍵屋走るも」とを掛けた。 (くらわんか鮨) (ごんぼ汁)見違(たが)ふも 三度(みたび)までなり ホトケノザ さほど似ぬ葉の ヒメオドリコソウ (似ずの踊子) (注)偐万葉掲載に当たり、初案「見間違ふも」を「見違ふも」に修正した。 (ホトケノザ:けん家持提供) (ヒメオドリコソウ:けん家持提供) 母とふの 花は咲かねど 春されば 花は野に咲く 母の笑むごと春まけて ぐづれる鼻の いぶせきと 花見にそなへ われアレジオン (花粉症の郎女) (本歌)春まけて もの悲しきに さ夜ふけて 羽ぶき鳴く鴫 誰(た)が田にか住む (大伴家持 万葉集巻4-4141) (注)春まけて=春が来て いぶせき=気がふさいで、うっとうしい。 ひろみの郎女が返せる歌2首うらうらに 今を盛りの さくら花 鼻には告げよ 花粉症びとヒメジョオン 咲く頃までに 治ります お世話になりたい アレジオンさん (花粉症の薬アレジオン20) かささぎの 歌は誰詠む やかもちの 歌となす見て 余は困りける (偐家持 珍古今集) (本歌)かささぎの わたせる橋に おく霜の しろきを見れば 夜ぞふけにける (大伴家持 新古今集620 小倉百人一首6) (かささぎ橋) 待てとあれば 待つのほかなし 待たぬとは 言へぬ患者は 待ちて待つなり (病院家持) (本歌)来むといふも 来ぬ時あるを 来じといふを 来むとは待たじ 来じといふものを (大伴坂上郎女 万葉集巻4-527)待ち待ちて 人は満つなり 病院の 待合出でて 煙草一服 (喫煙家持) ひろみの郎女が返せる歌1首イライラと 言うに言えない 不満でも 待って待ちわび 五時間経って (イライラひろみ) 行きて待ち 帰りの道の 渋滞に またもや待ちて 身も疲れつつ (偐定家) (本歌)こぬ人を 松帆の浦の 夕なぎに やくやもしほの 身もこがれつつ (藤原定家 新勅撰集851 小倉百人一首97)待てと言ふに 待たぬ人あり 待てぬと言ふ 待てとは言はじ 待てぬと言ふものを (坂上郎子) (兵庫医大病院) (阪神高速の渋滞)手土産の 甘藍(かんらん)ごろりと 脇に置き 谷麻呂ひろみと 同窓談義 (注)甘藍=キャベツの別名 (花園中央公園・若草読書会花見) 耳なれぬ 名にしあるかも みみなぐさ 耳にしすれど その名のこらじ (耳無家持) (注)みみなぐさ=ハコベに似た草、ミミナグサのこと。外来種でオランダミミナグサとい うのもある。萼が長く蕾だと花弁が萼に隠れてしまうのがミミナグサ。 萼が花弁より短いのがオランダミミナグサ。また、花柄が長く蕾が垂 れるのがミミナグサ。オランダミミナグサは花柄が短く茎にくっつくよう に花が付くので蕾が垂れることはない。 (オランダミミナグサ:けん家持提供) 枚方の 浜を出で立ち こぎ来れば 桜の宮に 花咲きにけり (本歌)珠洲の海に 朝びらきして こぎ来れば 長浜の浦に 月照りにけり (大伴家持 万葉集巻17-4029) (大川端の桜) 枚方の 大橋過ぎて 鳥飼や 豊里大橋 今かこぐらむ (淀家持) (本歌)高島の あどのみなとを 漕ぎ過ぎて 塩津菅浦 今かこぐらむ (小辨 万葉集巻9-1734) ひろみの郎女が追和して詠める歌1首<追記:4月11日>八軒屋 着けば息つく 暇もなく 元の木阿弥 枚方帰り (熊野詣に憧れるひろみ) (豊里大橋)<注>掲載の写真は「けん家持提供」とあるものを除き、ひろみちゃん8021氏の ブログからの転載です。
2017.04.09
コメント(8)
-

偐万葉・もも篇(その1)
偐万葉・もも篇(その1) 本日は、偐万葉シリーズ初登場の「もも篇」であります。 偐万葉では「ももの郎女」とお呼びさせていただくこととしましたが、このお方は、小生の母が生前に入院していた病院の向かいにある喫茶店「ペリカンの家」の店主であられます。 珈琲タイムや昼食、時には朝食にこの喫茶店を利用させていただいているうちに言葉を交わすようになり、当ブログに初コメントを下さったのが昨年(2016年)の12月15日。以来ブログでの交流が始まりましたが、今年3月5日に楽天でブログを開設され、同6日に初記事をアップされたことから、文字通りのブロ友にもなったというのが今日までの経緯。 この交流の中で詠んだ歌もいつの間にやら20首を超えていましたので、これを編集することといたしました。 <参考>☆もも☆どんぶらこ☆さんのブログはコチラ 偐家持がももの郎女に贈りて詠める歌22首 並びにももの郎女が詠める歌3首あらたしき どちの来たるは いやうれし けふ望月の 師走なりけり (走るヤカモチ先生) (注)あらたしき=「あたらしき」の古語 どち=友達のこと わが宿の 前なる垣の やぶがらし それとし知れば 愛しくもあるか (偐ももの郎女) (ヤブガラシ 当ブログ2016年12月17日記事より転載)無患子(むくろじ)の 実の干からびて からからと 空しく音す 三年(みとせ)過ぎたり 妹来るを わが梟も 待つやらむ 桜広場の 切株がもと (袋の鼠家持) 春さらば また来む蜂を われもまた 待ちつつ居らむ 大寒の朝 (蜂家持) 漬けぬれば 色に出にけり わが蕪は よしとブログに 載せるほどにも (甘酢蕪村) (本歌)しのぶれど 色にいでにけり わが恋は ものやおもふと 人のとふまで (平兼盛 拾遺集622 小倉百人一首40) (蕪の甘酢漬け) ももの郎女が返せる歌1首初ブログ ヤカモチ流の 歌があり よしと心は 蕪色の春 月星に 重ね見よとや 花の川 オンシジウムの 咲きてぞ流る (コブリザブトン) (オンシジウム) (シラー)紫に 匂へるシラー 咲く見つつ ゆるり珈琲 するもよかりき (二月のペリカン)水仙の そよ吹く風に 波うちて ここだ咲きたる 見らくしよしも (偐家持推薦) (淡路島の水仙郷) 寒き朝は カフェオレ熱きに オレンジの マーマレード溶かし 飲むべかりける (白猫河内)ケーキなど 食ふとしあらば 珈琲は ブラックこそと 言はむやわれは (黒猫大和) (オレンジ風味のカフェオレ) ももの郎女が返せる歌1首黒猫も 白猫も春 待ちわびて 珈琲香る 陽のとける午後 ペリカンの 家の抹茶は うさぎの絵 名付けてこれぞ イスパニア式 (兎千家) (注)初案「これぞ名付けて」を「名付けてこれぞ」に修正。 イスパニア式=スペインの古名・イスパニア(ヒスパニア)は「ウサギの国・土地」と いう意味のフェニキア語に由来すると言われている。 (抹茶アートの兎の絵) 好日を 口実にして 今日もかも 妻より逃ぐや 銀輪駆けて (日々是逃亡)よき人に よき日よくあれ よき日々は よしとよく見ば 是よき日なる (偐武天皇) (本歌)よき人の よしとよく見て よしと言ひし 芳野よく見よ よき人よく見つ (天武天皇 万葉集巻1-27) ももの郎女が返せる歌1首三層の 山荘がある 口実村に 行きて楽しむ 言の葉の海 (日日字余り) (日々是好日)朝裳よし 紀ノ川の辺(へ)に 咲く花を 見つつや春の この日過ぐさな (紀家持) (注)朝裳よし=「紀」、「紀人」、「紀道」などにかかる枕詞。「麻裳よし」とも表記。 (紀ノ川)たんぽぽの ほどに知る人 なくあれど 咲くなりわれも 名はミミナグサ (偐繁縷(にせはこべ)) (オランダミミナグサ) (タンポポ)きみが行く 道の長手に 花とりて われは贈らな 真幸(まさき)くぞあれ (偐ももの郎女) 茶畑の 波打つ丘に 吹く風の 声もさやけし 和束の里は (和束家持) (本歌)一つ松 幾代か経ぬる 吹く風の 声の清きは 年深みかも (市原王 万葉集巻6-1042)遠山に 雲立ち昇り 風光る 和束の眺め 長くとぞ思ふ (和束家持) (本歌)たまきはる 命は知らず 松が枝を 結ぶこころは 長くとぞ思ふ (大伴家持 同巻6-1043) (和束の茶畑) ペンギンも 猫も居らぬは 万葉と 同じなるかや ペリカンの家 (ペンギン) (乾杯する猫)万葉の 人なるわれや にゃんと鳴く 猫なるものを にゃんとかも見む (猫家持) (本歌)うつそみの 人なるわれや 明日よりは二上山を いろせとわが見む (大伯皇女 万葉集巻2-165) 弥生にし 始めしブログ 月経ても 卯月の空に やよ励めとか (ひと月坊主) (桜) (注)掲載の写真は当ブログからの転載とあるものを除き、 全て☆もも☆どんぶらこ☆さんのブログからの転載です。
2017.04.07
コメント(10)
-

岬麻呂旅便り202・宮崎
先日、友人の岬麻呂氏より旅便りと写真が届きました。 今回の旅は宮崎。3月28日~31日の3泊4日の旅は、花見もその目的の一つであったようですが、今年は西日本でのソメイヨシノの開花が遅れたことにより「完全空振り」であったようです。それでもヤマザクラは全域で満開であったそうな。 例によって、詳しくは下掲の「旅・岬巡り報告202」をご覧下さい。写真下欄の「コチラ」をクリックして戴くと大きい画面に切り替わります。 (旅・岬巡り報告202)<拡大画面はコチラ> <拡大画面はコチラ> 先ず、向かわれたのは、西都原古墳群。桜並木に菜の花畑という風景であったようですが、満開は菜の花畑のみ。(西都原古墳群の桜と菜の花畑) 確かに、桜は「空振り」のようですね。 次に向かわれたのは、佐土原城址。二の丸御殿(鶴松館)が復元されて、佐土原歴史資料館となって居り、戦国時代以降の歴史に興味を持たれている同氏が予てより訪ねてみたかった場所であったようです。(佐土原城址・鶴松館<宮崎市佐土原歴史資料館>) 此処では、色々と突っ込んだ質問をされたものと見えて、館長とおぼしきベテラン学芸員から1時間半を超えての、特別な案内と解説をお受けになった模様。一般公開されていない資料室の方にまで見学を許されたようですから、特別待遇であったようです。(同上・接見の間) 次に向かわれたのは日向岬。岬麻呂ですから納得です。(願いが叶うクルスの海) この海岸の地形、真上から見ると「叶」の字に見えることから、「願いが叶うクルスの海」と命名されたそうな。 そういう予備知識を持って眺めると、下の斜め上からの写真でも「叶」であることが見て取れる。 潮が引くと、岩が二つ海側に並んで現れ、元々露出している岩と併せて「さんずいヘン」となるので「汁」になってしまうというのは、勿論冗談です。(同上)(日向岬・馬ヶ背) 上の写真は、一見、滝かと見誤りましたが、断崖の上から細く切れ込んだ海面を眺めたものでありました。滝とは逆に海水が流れ昇って来るのでしょうな。白く泡立っていますから。馬ヶ背に 白木綿花に 咲く波の 音もとどろに 日向の岬 (偐家持)(うまがせに しらゆふはなに さくなみの おともとどろに ひむかのみさき)(馬ヶ背から見た北側の断崖)(青島) ここまでが、29日。 翌30日は、高千穂峡、椎葉村へと向かわれました。(高千穂峡・真名井の滝) 真名井の滝の写真は以前にも掲載して居ります。 (参考)岬麻呂旅便り175 2015.9.10.(椎葉村・鶴富屋敷) 次は、平家伝説の椎葉村。上の鶴富屋敷の前の像は、那須大八郎と鶴富姫でしょう。二人の悲恋物語はコチラをご覧下さい。 (参考)椎葉村観光協会ホームページ (椎葉の天然川のり) (同左) この日のお昼は、名物の蕎麦と秘境の珍味・川のりで昼食であったそうな。川のりは学名は川茸だそうだが、これで思い浮かぶのは大伴家持のこの歌。雄神川 くれなゐにほふ 娘子らし 葦附採ると 瀬に立たすらし (大伴家持 万葉集巻17-4021) 雄神川(をかみがは)というのは富山県の庄川のこと。葦附(あしつき)というのは藍藻類ネンジュモ科の淡水藻である。赤い裳の少女たちが川に入ってアシツキを採っている景色である。多くの少女たちの赤裳で庄川が紅色に染まって光り輝いているようであるという春の景色である。この歌の歌碑は下記参考記事末尾に掲載されています。 (参考)高岡銀輪万葉・富山庄川小矢部自転車道(続) 2010.6.10. 椎葉の川のりも葦附も多分同じようなものではないかと思うが、小生はどちらも口にしたことがないから、風味のほどは存じ上げない。岬麻呂 昼餉に川のり 召すらしも 椎葉の蕎麦に 合ふと聞くらし (偐家持) 最終日31日は日南海岸を南下、都井岬へと向かわれたようですが、朝から雨、と書かれています。納得です。この日は小生も5人組ウォークで午後からの雨の中の大和盆地を歩いていましたから(笑)。(都井岬・岬馬)岬麻呂 なれば行くほか なかるべし 雨でも都井の 岬馬見に (偐家持) そして最後は、南郷の県立亜熱帯植物園。日南海岸・道の駅「なんごう」の丘には世界三大花木のジャカランダの森があるが、これの開花は6月初旬、まだその時期ではない。岬麻呂氏はこのジャカランダの花を見むとて、以前この地に来て居られますが、その花は下記参考記事でご覧下さい。 (参考)岬麻呂旅便り190・世界三大花木ジャカランダ 2016.6.25. 今回、植物園の温室でご覧になったのは、三大花木のもう一つのカエンボク。「望外の幸運」とご満悦であったようですが、ソメイヨシノのつれなさをカエンボクが補ってくれた形で、終わりよければ全てよし、のめでたし、めでたしの旅となったという次第。(カエンボク) 以上、岬麻呂旅便りを紹介申し上げましたが、岬麻呂氏も当ブログに寄せられるコメントなどをご覧になって、益々よい写真を撮って皆さまにご覧いただけるよう、旅に励むと仰って居られますので、お元気である限りは(これは小生も含めてのことになりますが)、このシリーズ記事はまだまだ続くかと思います。どうぞお楽しみに。<追記>岬麻呂氏より、追加でもう一つの世界三大花木であるホウオウボクの写真 が送られてまいりましたので、追加掲載して置きます。フォト蔵に登録し て貼り付けようとしましたが、トラブル中なのか、NO PHOTO表示になっ てしまい、うまくアップロードできません。よって、この写真は楽天写真 館に登録して貼り付けました。(ホウオウボク 小笠原諸島・父島で撮影されたとのことです。)<追々記> フォト蔵写真の方も遅ればせながら登録出来たようです。コチラ<参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからご覧下さい。
2017.04.06
コメント(6)
-

囲碁例会・桃や桜の咲く中を
本日は囲碁例会の日。お天気もよしで、MTBによる銀輪散歩を兼ねての自宅~梅田の往復という毎度のヤカモチ・スタイルの移動でありました。 先日2日の花園中央公園での読書会お花見は、チラホラ咲きの些か寂しい花見でありましたが、昨日、今日と気温が急上昇ということもあってか、途中通り抜けた大阪城公園の桜はもう満開に近く、あちこちでお花見をする人で賑やかなことでした。 そのお花見の人々の群れを背中に、お堀の方に向かって撮った写真が以下の4点。(大阪城公園の桜) (同上・城の石垣と桜) (同左)(同上) 大阪城公園の桜広場でお花見をする人たちの写真も1枚撮ったのだが、囲碁会場の部屋で、メンバーがやって来るのを待つ間にカメラをいじっていて、操作ミス。不要写真の削除をしているうちに間違ってその写真も削除してしまったという次第。(今日のれんげ亭) れんげ亭に到着が11時35分。久々に今日は此処で昼食です。 昼食を済ませてれんげ亭を出たのは12時5分頃。 梅田スカイビル到着が12時半頃。屋外の喫煙所で煙草を一服して、会場の部屋のある5階へ向かうべくしていた時に、小生が現役であった時の元部下で、現在は常務兼法務部長の中〇君と出くわし、やあやあ、と再び喫煙所に立ち戻って、彼と暫く閑談。河〇君や宮〇君その他の人たちの近況を聞く。現役を離れてもう11年になるので、会社の様子も、社員も随分変わってしまっている。10年ひと昔とはよく言ったものだ。 会場に行くと囲碁サークルのメンバーはまだどなたもお見えではなく、絵画サークルの指導者の小〇さんらが来て居られた。ブロ友のひろろさんのことや絵のことを同氏と雑談。同氏が帰られたのと入れ違いに竹〇氏が来られ、早速に同氏と手合わせ。これに勝って、漸く連敗脱出。対局中に福〇氏がお見えになっていたので、次に同氏と対局。これは負け。隣では、その後来場された平〇氏と竹〇氏が対局中で、未だ終わりそうにないので、福〇氏ともう1局打つ。これも負け。結局今日は1勝2敗。連敗は止めたものの、相変わらず不振が続いています。(大川端のお花見風景) 大阪城公園でのお花見風景の写真をカメラをいじっていて、間違って消してしまったので、帰途に大川端のお花見風景を撮りました。これらは今夜、夜桜花見をするための準備なんでしょう。既に始まっているところもありましたが。 そして、中央大通りを第二寝屋川まで帰って来た処で、桃の花の満開も撮影。往路でもこの花には気付いていたのだが、道路の反対側を走っていたので、帰りに撮影しようと決めていたのでありました。忘れずに撮影でした。(第二寝屋川沿いの「稲田桃」の花)(同上) 花園中央公園にも立ち寄る。 桜広場の、2日に我々がお花見の席とした、桜の木を見てきましたが、満開になっていました。我々の花見が三日ばかり早過ぎたのだということが分りました。そんなことが分ってもアトの祭、いや「アトの花見」ではありますが(笑)。 公園内にある花園ラグビー場は2019年のワールドカップ開催に向けて改装工事中。工事用の囲いのフェンスに工事完成予想図が掲示されていました。 こんな風にリニューアルされるようで、観客席も大幅に増えるようです。2019年には、花園までどうぞ皆さま観戦にお出掛け下さいませ。(花園ラグビー場改装工事完成予想図)
2017.04.05
コメント(2)
-

墓参・花散歩ー南天の露から苔の麦畑まで
記事が前後しましたが、今日は4月1日(土)の墓参の記事です。 前日に雨の中を20キロ余を歩いたので、朝の墓参のウォークは丁度良い馴らしになりました。 墓参は、例によって途上の寺の門前の言葉から始まる。(2017年4月1日の言葉) この日は4月1日でありましたから、この日の言葉は4月1日の言葉となる。4月1日の言葉となると、嘘が交じってもいい訳で、些か信用性には問題があるということになるが、山門の言葉はそのような悪ふざけとは無縁、常時真面目である。人と生まれた悲しみを知らないものは 人と生まれた喜びを知らない 「かなし」という言葉は、「前に向かって張りつめた切ない気持ちが、自分の力の限界に至って立ち止まらなければならないとき、力の不足を痛く感じながら、何もすることが出来ないでいる状態」(大野晋「日本語の起源」岩波新書)を表す言葉である。思いをつのらせ、思いつめて、なお思い足りないというような思い・感情のことを意味する言葉である。現代語では「悲・哀(かな)し」にのみ使用されるが、古代には「愛(かな)し」という用法もあった。 悲しみであれ、愛しさであれ、思いに思って、これ以上はもう限界というような地点に立って、言わば自らの限界・力不足を嘆くと言うか、その寂しさのようなものを感じる思いが「かなし」という言葉には内在している。してみれば「人として生まれた悲しさ」を知るということは、そういう限界のある、有限な存在としての命の「かなしさ」を知るということでもあり、他の命を犠牲にしなければ己の命すら維持し得ないという「存在」そのものの「かなしさ」を知るということでもあるだろう。 それを「知る」ことによって、人は他への「優しさ」というものを得る。この「優しさ」と物事に対して「喜び」に思う感情とは寄り添った関係にあるようです。この「優しさ」がベースにあって、日常の些事などにも「喜び」を見出すことが出来るというものであるのだろう。 前日の雨の名残の露が、墓地のナンテンの赤い葉にとどまって、きらきらと光っていました。これを見て「美しい」と喜びに似た感情が生まれるためには、柔らかな優しい心根が見る側の人間に存在していることが必要でしょう。 そして「逆も亦真なり」で、こういった美しきものを目にすることによって、人は優しい心を得ることができるのだとも言えます。(南天の葉の露) はい、このブログ記事をご覧になったお方は、ご覧になる前よりも幾分かは優しい心根になられたのであります。良かったですね(笑)。 そして、土筆です。 まあ、土筆は遅きに失する題材でありますが、最近、土筆の画像を取り上げていませんので、久々にこれを撮影、記事にしてみました。勿論、今年初めての土筆の画像。何年かぶりの画像アップであります。(墓地に生えていた土筆) (同上) (同上) 同じく、カラスノエンドウも花を咲かせていました。 子供の頃は、カラスのエンドウ豆、と呼んだりしていたので、長らく「カラスのエンドウ」だと思っていたが、そうではなく「カラス野エンドウ(烏野豌豆)」であることを知ったのは、いつのことであったろうか。 従って、カラスが食べる豌豆という訳ではなく、豆の莢が、熟れて弾ける頃には、真っ黒になるところから烏野豌豆という名になったようだ。もし真っ白になるのであったら、白鷺野豌豆・シラサギノエンドウとなるところであったのだ(笑)。(カラスノエンドウ) これの小振りな奴にスズメノエンドウというのがあるが、これは、カラスノエンドウとの比較からひと回りかふた回り小さいスズメを当てての命名であろう。その証拠に、カラスノエンドウとスズメノエンドウとの中間位の大きさのものは、カスマグサと呼ばれる。カラスとスズメの中間、つまり、「カ」と「ス」の間「マ」という訳である。 こんなズボラな命名をせず、ハトノエンドウとかモズノエンドウとかにすべきではなかったのか。(同上) 墓参の後の花散歩で写真に撮ったのは以上まで。 これでは花散歩には届かず、「花二歩」程度なので、2日のお花見の折に撮った写真も加えて、「花三歩」か「花四歩」にして置きましょう。と言っても、珍しい花などは登場しないのが当ブログの「花散歩」。そんなことから「今一歩」と陰口をたたく輩もあるそうな(笑)。(シロツメグサ) 朝日に匂うシロツメグサの花である。 赤い花のアカツメグサというのもあるが、下の写真の右側のそれはピンク色である。シロツメグサとアカツメグサの中間ということで、カスマグサの倣いに従うなら、アシマグサということになる。赤いシロツメグサということでアカシロツメグサなんぞという何色か迷うような名前よりはいいだろう(笑)。 (同上) (同上) 次も2日のお花見の待ち時間に撮影のもの。やはり、朝日に匂うオランダミミナグサである。青みがかっているのは光線の加減によるカメラの「困惑」が露呈したものであり、青花ミミナグサという訳ではない。(オランダミミナグサ) (同上) (同上、開花したもの) 上の写真・右は、花園中央公園でのお花見の待ち時間の撮影ではなく、第二部のたこ焼きパーティの折に、煙草休憩で席を外して、智麻呂邸前の公園でぷかぷか煙を吹かせながらに撮ったものであり、もう朝日に匂う、ではなく、午後の日差しに打たれつつのミミナグサである。 花を見る限りは、ハコベの花と変わりはない。ハコベとオランダミミナグサの違いは、茎が赤紫色で茎長が長く、背が高いのがオランダミミナグサで、ハコベは茎が緑色、茎長が短く、背が低い、という区別をしているのであるが、この区別がいかなる場合にも成立するのかどうかは自信はありませぬ。 次はナズナ。春の七草、セリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・スズナ・スズシロ・ホトケノザのうちの一つである。食用にするのはこれの若芽であって、このように成長して、花を咲かせてしまっては食えない。ただのぺんぺん草に成り下がるのである。 (ナズナ・薺) (不明) 上の右側の花は名前不明です。ナズナと同程度の極小サイズの花であるが、花の付き方や花弁の形状が異なる。葉の形状も違う。ナズナには似ていないから、一応「ニズナ(不似菜)」と呼んで置こう(笑)。 そして、麦畑です。(キンシゴケ) 勿論、麦畑ではありません。苔です。2~3cmの背丈の苔です。接写すると一見「麦畑」の写真のようにも見えます。この写真は花見の待ち時間での撮影です。 苔の名前などは殆ど知らない。ネットで苔図鑑に当ってみると、キンシゴケという名前のようです。錦糸苔と書くのでしょうね。まさか菌糸苔ではあるまい。近視苔、禁止苔などは論外。 (同上) (同上) 朝日に照り輝く様を、露出を落として撮影し、これを少し補正するとこのように幻想的な写真となりました。これなら、金糸苔と表記してもいい。(同上) 苔は、雨の後が美しい。 乾燥して、枯れてしまったかのように見すぼらしくなっていた奴が一斉に元気になって、「わが世の春」を謳歌し出す。裸足になってその上を歩きたくなるが、これはお薦めできない。足が濡れてしまって大変です。 (同上) (同上) 本日は、墓参&花散歩の記事でした。
2017.04.04
コメント(6)
-

若草読書会お花見・チラホラと咲きたるも見む
昨日4月2日は若草読書会のお花見会でありました。 例によって場所取りはヤカモチの役目。 今年は、開花も遅く、見頃は1週間程度先で、花見する人も少なかろうと家を出たのは朝5時半頃。途中のコンビニで自身の朝食用の珈琲と野菜ジュースとパンを買い、ついでに参加者用のカップみそ汁を9個買って、お花見場所の花園中央公園到着が6時少し前。 公園の桜広場には、早朝の散歩の人影はあるものの、お花見の席取りをする人の影はない。それもその筈、桜は全く咲いていないではないか。暫し茫然。持参したビニールシートを広げる意欲も失せたのでありました。 それでも、気を取り直して、少しでも咲いている木はないかと見回ってみる。よく見るとチラホラと咲いている木もある。花の付き具合が一番多いと感じられた木の下に、ビニールシートを広げる。公衆便所の向かいには、ほぼ満開と見られる細めの若い木が1本ありましたが、立地がよくないのでパスしました。(花園公園の桜) 下の写真は、昨年の4月3日のお花見会の時の写真です。昨年はこんな風に満開でありましたから、今年の咲きの遅さがよく分かると言うもの。 (昨年4月3日の記事から転用の写真2枚) それでもチラホラと部分的に咲いているのを写真で切り取るとこんな風に「春」なのであり、「花見」らしくもなるのでありました。(花園中央公園の昨日の桜) (同上) (同上) 6時半になると公園ではラジオ体操が始まる。それに集まる人が次々と来られて、いっとき賑やかになるが、彼らが引き上げてしまうとまたもとの閑散とした感じに戻り、犬の散歩の人がチラホラ。 そんな中に小型犬を連れた男性が傘型の円型ベンチに座って、その上で犬のブラッシングを始めた。抜けた毛の始末はどうするのだろうと見ていたが、長らくして、そのまま犬を連れて立ち去る。ベンチに行ってみるとびっしりと真っ白の毛がベンチを覆っている。「お~い。」と大声を出す。遠くまで立ち去りかけていた男性が振り向く。「アンタや。これどうするのよ。このままにして置くつもりか。」と怒鳴る。 無言で引き返して来た男性は「すみません。」と言って、手で積もった毛を地面に払い落して行く。ティッシュか雑巾などできれいに拭き取って貰うことを期待したがブラシは持って来ていても、そのようなものを持って来ているようでもない男性は素手で払うのが精一杯。従って、彼が立ち去った後もまだかなり毛が残っていた。気付かずに座るとズボンなどに毛がくっ付くだろう。仕方なくティッシュを出して全て拭き取る。糞の始末をしない飼主やベンチに毛をまき散らして平然と去る愛犬家は犬を飼う資格がないと言うべき。 カメラを首からぶら下げた男性がしきりに桜木の幹に見入っている。「何かあるのですか?」と近寄って声をお掛けすると、ひこばえに咲く桜を今年は撮ることに専念しているのだという。「この花は撮りましたか。」と小生が先程に撮った目の前のひこばえを指さすと、もう撮影した、とのこと。公園内の木々を見て回りながら、ひこばえの芽や枝先の花の付き具合や芽の状態を確認して、撮影時期の見通しを立てて居られるようです。(ひこばえの桜の花) ビニールシートを広げて、場所取りをする人たちもあちらこちらに現れて来て、漸くお花見の広場の雰囲気になって来る。 いつぞやは、待ち時間を野良猫たちと過ごしたこともあるヤカモチであるが、今年は猫は登場せず、代わりに雀や鳩や烏が目立ちました。日が昇り、人影が増えるにしたがって、鳥たちの姿も見えなくなったが、最初は彼らと時間を過ごしたのでありました。(スズメとヒヨドリ) (スズメ) (ヒヨドリ) ヒヨドリにしては茶色っぽいのですが、これは丁度朝日が昇ったばかりの頃でその光線の影響でこんな風な色に写ったものと思われる。もっと灰色がかった鳥の筈である。ひよどりは 昇る朝日に 茶毛なりて すましにけらし ひよとも鳴かず (偐家持) (群雀) (同左) むらスズメの写真。 右側写真の一番上の雀さんとは目が合ってしまいましたですな。 こいつは見張り役かも(笑)。 そうこうしているうちに、中学の同級生でもあるひろみの郎女さんがマイカーで到着。前日に智麻呂邸で積み込んだ椅子などを運んで来てくれました。彼女が同じく同級生の谷〇君を呼ばないか、と言うので、彼に電話する。 「今、ヒマか?」これこれこうなので、モーニング珈琲ご馳走するから、散歩を兼ねて「こちらに来ないか?」と小生。「今、畑に居るが、そのままの格好でいいなら、これから行く。」と彼。春キャベツとブロッコリを我々二人にとビニール袋に入れたもの二包を手土産に彼がやって来て、三人で同窓会でした。 また、これに先立って、ひろみの郎女さんが同じく同級生の塩〇さんにも電話し、小生も電話を替わって彼女と少し話をしたので、益々、同窓会でありました。 谷〇君が引き上げた後、先ず智麻呂・恒郎女ご夫妻がご来場。続いて、小万知さんと和郎女さんが来られ、次に祥麻呂さん、槇麻呂さんの順でご来場。最後に香代女さんが到着で宴会を始めました。常連の凡鬼・景郎女ご夫妻は渡英の日程と重なり欠席、和麻呂氏と偐山頭火氏は病後の養生で欠席。東京のリチ女さんは予定が合わずで欠席、読書会は今後不定期参加とすると昨年宣言された謙麻呂さんも前回はご出席されたものの今回は欠席、ということで、全9名の参加にとどまりました。(2017.4.2.の花園中央公園) 日が高くなるに従い、咲き出す花も幾分増えたようで、朝やって来た6時頃は5~6輪しか開花していなかった、我らが頭上の桜も、宴会を終えて引き上げる午後1時半頃にはもう数え切れないほどの数になっていました。夜まで粘ればそこそこの花見になるのでは、との冗談もあながち間違ってはいないかもであるが、そうも行かぬと撤収し、二次会の智麻呂邸、若草ホールへと向かうこととしました。香代女さんは、二次会までは無理と瓢箪山駅からお帰りになりました。 二次会は、恒例の「たこ焼きパーティ」である。暫くお茶を戴きながら談笑に時を過ごしましたが、いよいよたこ焼きタイムという時に、小万知さんと和郎女さんは帰宅の途へ。残り6名でたこ焼きとなりました。焼く途中で、たこ焼きをクルリとひっくり返す役目をいつも担って戴いていた名人凡鬼さんが欠席なので、それを恒郎女、祥麻呂、偐家持の三人でこれを行う。手つきの程は別にして、偐家持たこ焼きもちゃんと丸く仕上がりました。各人12~3個は食べましたが、3名が二次会を辞されたので、かなり材料が余ってしまいました。刻んだ蛸が無くなるまではとその後も焼き続け、最後は具の多いたこ焼きとなりましたが、タコの切れ目が終わり時で、無事終了。午後5時頃の解散となりました。 花の咲き具合は別にして、タコの焼き具合も、空の晴れ具合も申し分なく、楽しいお花見の一日となりました。
2017.04.03
コメント(10)
-

5人組ウオーク本番・王寺から大和郡山まで
昨日3月31日は友人の鯨麻呂、草麻呂、蝶麻呂、健麻呂各氏と偐家持による5人組ウォーク本番でした。天気予報では午後から雨であったが、降雨量が1mm程度ということでもあり、花粉症の蝶麻呂氏が雨は大いに歓迎ということでもあったので、決行ということとしました。 花の蜜を吸って花粉を運ぶ役割も担っている筈の「蝶」が花粉症というのも腑に落ちないことではあるが、仲間にこのような蝶がいる我々5人組の春のウォークは、時にこのような通常とは反対の選択もありなのである。 このコースは先に小生が下見をして居り、その様子をすでにブログに記事アップしているので、詳細は当該記事(下掲<参考>参照)をご覧下さい。 <参考>5人組ウオーク下見・王寺から郡山城まで 2017.3.13. 午前11時JR王寺駅北口改札前集合。小生は40分ほど早めに王寺駅に到着、喫茶店で皆の到着を待つ。10時50分全員集合。昭和橋で大和川を渡るべく東へと向かう。空はどんより曇って、気温も低いが、未だ雨は降っていない。 昭和橋を渡って、大和川沿いに竜田川合流点まで行き、竜田川沿いに上流へと歩く。斑鳩西小学校前の竜田川堤は桜並木になっているが、ソメイヨシノはかなり蕾が膨らんではいるものの、まだ開花は見られない。しかし、山桜は既に五分咲き程度になっているのでありました。 (竜田川の山桜) 三室山の手前の民家の庭にはシデコブシの花。 この花の名を知ったのは、ビッグジョン氏のブログ記事からであるが、その後、新潟での銀輪散歩や梅田の里山でもお目にかかっている。 <参考>津川・新津銀輪散歩(その3) 2012.4.27. 囲碁例会・桜さくら咲くさくら 2014.4.2.(シデコブシ) 三室山は全山桜の木と言ってもいいくらいに桜の木が植えられているが、ソメイヨシノはまだ蕾状態。見頃は10日後位だろうか。それでもシロヤマザクラだろうか、既にかなり咲いている木が1本だけありました。また、桃の大木が1本ほぼ満開になっていました。この2本だけが気を吐いていましたが、これらの写真は撮り忘れました。その代りと言っては何ですが、サンシュユの花は撮りました。 計画では、この三室山の桜の満開の下でお弁当、という予定であったのですが、雨の心配もあり、満開はおろか三分咲きも望めそうにないだろうということで、お弁当の購入は止めて、法隆寺前で食堂に入って昼食にしようということなりました。(三室山のサンシュユ) 花見は何も桜に限るまい。シデコブシでもサンシュユでも、花見には違いあるまい、とはいうものの、春花の咲ける盛りにいざ行かな、というのはやはり桜でなくてはならない。ソメイヨシノの古木の根方に生じたひこばえの枝には花を咲かせているものもあったので、未練がましくそれらにカメラを向けるヤカモチさんなのでありました。 (三室山のひこばえの桜) 頂上には、東屋があり、その脇には能因法師の供養塔と云い伝えられている石塔がある。以前のブログ記事でも紹介済みであるが、再度撮影しましたので、再掲載して置きます。下の<参考>記事には、供養塔のほか、東屋やこの後立ち寄った山頂脇の神岳神社の写真も掲載されていますので、ご覧下さい。 <参考>平群-竜田川-大和川-竜田大社-竜田越え 2009.9.4.(三室山山頂の能因法師の供養塔) 東屋で休憩しているうちに、雨が降り出しました。 以下は傘をさしての雨の中のウォークとなりました。 神岳神社に立ち寄る。社殿前には鳩のものと思われる羽毛が散乱していました。猫かカラスか肉食の猛禽かケモノが鳩を襲ったのでもあろうか。 三室山を下って、竜田川沿いの緑地、竜田川公園を竜田大橋まで歩く。何か所か朱塗りの橋が竜田川には架かっていて、いい雰囲気を醸しているのであるが、堂山橋のたもとには青柳が芽を吹いて「春」らしさを演出しているのでありました。 まあ、竜田は秋・もみぢ葉のイメージであり、竜田姫は秋のお姫様というのが相場。春のお姫様は佐保姫であり、青柳も佐保川にこそ似合いというものだが、竜田川にも春には桜が咲き、青柳が芽吹くことに違いはない。「相場」とは無関係の「自然の摂理」というものである。うちのぼる 竜田の川の 青柳も 今は春べと 芽吹きてありぬ (竜田家持) (本歌)うち上る 佐保の河原の 青柳は 今は春べと なりにけるかも (大伴坂上郎女 万葉集巻8-1433)(竜田川・堂山橋畔の青柳)(竜田川・竜田大橋の上から下流を望む) 竜田大橋で竜田川を渡り、東へと向かう。 旧道に入って暫く行くと、龍田神社。 下見記事では、このクスノキの大木を紹介していなかったので、掲載して置くこととします。(龍田神社のクスノキ) 藤ノ木古墳を経由して法隆寺へ。 午後1時になっていたが、門前の土産物店兼食堂で昼食とする。 三室山山頂の東屋でオヤツにパン(これは昼食が遅くなった場合、近江八幡など遠方からの参加者はお腹が空くのでは、とヤカモチが各人1個ずつの計算で計5個を途中乗り換えの近鉄生駒駅で買い求めて持参したもの。5個買ったら、お店の人が1個サービスですと下さったので全部で6個ありましたので1個余ってしまいました。)と柿の葉寿司(同じ考えでか、健麻呂さんは柿の葉寿司をご持参で、皆に一切れずつ配給がありました。)とを食べたので、左程に空腹でもなく、うどん位が丁度よかろうと、名物だという「太子鍋うどん」で昼食としました。(法隆寺) 法隆寺を通り抜け、下見では立ち寄った中宮寺宮墓はパスし、法輪寺、法起寺へと向かう。雨は本降りとなり、靴も濡れ、靴下まで滲みて来て不快。 法輪寺、法起寺を過ぎ、九頭上池畔の東屋で暫し、休憩を取る。九頭上池では鳩ならぬ大きな鯉が2尾、岸辺にその屍をさらしていました。 甲斐宮(甲斐神社)に立ち寄り、玉葉集(鎌倉時代後期の勅撰和歌集)に登場する田中宮の歌の歌碑を見つつ、暫し談義。甲斐宮は元は田中の宮と呼ばれていたということで、この歌は、この神社のことを詠ったものということである。山きはの 田中のもりに 注連はえて 今日里人は 神まつるなり 新木山古墳の先で、ネットから拾い出した大和郡山の観光地図に表示されている大光院跡と思われる場所に回ってみたが、新しい住宅が何軒か建っているばかりで、それを示す碑も案内板も見当たらない。大光院というのは豊臣秀長の菩提寺であった寺である。 諦めて、秀長の墓である大納言塚へと向かう。 大納言塚の前では、砂を通すための石櫃のようなものが置かれていて、「大納言塚にお参りを済ませた後、この石櫃の砂を手にすくい、自身の名前と願い事を言いながら、石櫃手前の窪みに穿たれた穴から砂を3回通すと、願い事が叶う」と書かれていました。鯨麻呂さんは、それをなさっていましたが、何を願われたのかは、遠く離れていた小生には不明。小生も砂を3回通しましたが、名も名乗らず、願い事もしなかったので、大納言豊臣秀長殿はきっと「何じゃこいつは。」と思われたことでしょうな。まあ、どう思われようと、名乗って居りませんので、ノープロブレムであります(笑)。 この後、剣豪・荒木又右衛門の屋敷跡の前を通り、永慶寺山門を見て、郡山城跡へと向かう。 (荒木又右衛門屋敷跡の碑) (同左・説明板) 郡山城のお堀端にはサギ集団。 と言っても、振り込めサギやオレオレサギではなくシラサギである。 (郡山城堀端の白鷺の群れ) そして、長らく整備工事中で立ち入れなかった天守台周辺が、工事も完了したようで、何日か前から、天守台に新設された展望台(展望デッキ)が一般公開となっていたので、柳澤神社の本殿裏から、天守台へと上る。(郡山城天守台からの眺め)(郡山城天守台説明板) 天守台石垣に使用されている石地蔵も久々に拝見。 写真では分かりにくいかも知れませんが、石仏が刻まれた石が頭部を下にした形で石垣に転用されているのである。さかさ地蔵の前に布製のカメラケースが雨に濡れたまま置き忘れになっていました。さかさ地蔵を撮影した折にケースを置いたことを忘れたまま立ち去ってしまわれたのであろう。持ち主が現れることはないであろうが、拾い上げて、「お城まつり」のテント張りの本部へ持って行き、係の人にお届けして置きました。(天守台石垣のさかさ地蔵) 郡山城の桜も見頃はまだ先。既に5時近くになっていたことに加え、雨ということもあって、観光客の姿も殆どなし。ズラリ並んだ屋台のテントもお団子を売っているおじさんの屋台を除き、みな店を閉じていました。 そんな中で、この枝垂れ桜はそこそこに咲いて見頃になっていました。(郡山城堀端の枝垂れ桜) 城跡会館(図書館)前の、森川許六の句碑を見て追手門より城外へ。帰途につきました。 会館前の許六の句碑は下見記事に掲載の写真でご覧いただくこととし、もう一つの句碑の写真を掲載して置きます。下見の時は、この句碑の前で数人のご婦人が談笑して居られて、撮影できなかったのでした。今回も碑の前にはテントが張られていて望ましいアングルは望めなかったのですが、何とか撮影できました。(山口誓子句碑)大和また新しき国田を鋤けば (山口誓子)大和まだ春雨の中五人組 (筆蕪蕉) もう午後5時を回っていたので、下見の折に思った通り、平城宮趾まで歩くというのは無理でした。駅前に向かい、喫茶店で少し休もうということとなる。JR大和郡山駅方向に少し行った処でやっと見つけた和風喫茶店に入り、珈琲タイム。既に5時半。6時閉店とのことなので、我々が最後のお客さん。6時少し前に店を出て、JR大和郡山駅へ向かう鯨麻呂、草麻呂、蝶麻呂3氏と別れて、健麻呂氏と小生は近鉄大和郡山駅へ。 健麻呂氏は生駒で下車。小生ヤカモチの最寄り駅「枚岡」に着いた時もまだ雨。雨の中を自宅まで。午後ずっと雨に降られての3月最後の一日でした。(注)当ブログ記事の掲載写真はフォト蔵登録写真を貼り付けています。楽天ブロ グが完全SSL化されたことに伴い一部写真が表示されないことがある、とい う現象が生じています。何れこの不都合を解消するための対処を楽天さんの 方でやっていただけるとのことでありますが、当面は、記事タイトルを再度 クリックしていただき画面を更新することによって、非表示の写真も表示さ れますのでお試し下さい。1回の更新では駄目な場合もありますが、2度、3 度行うと必ず、全写真が表示されます。
2017.04.01
コメント(8)
全17件 (17件中 1-17件目)
1










