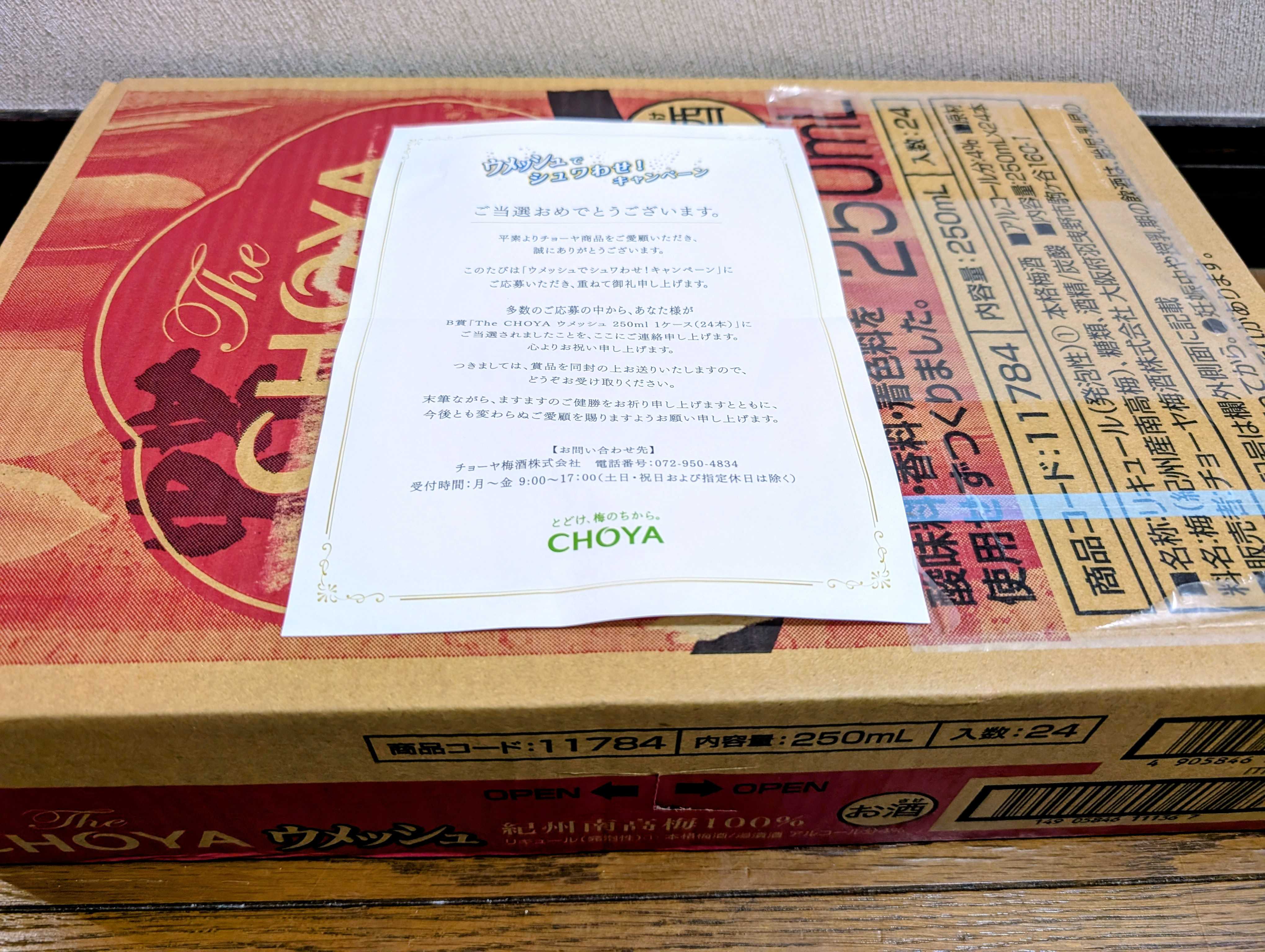2017年05月の記事
全16件 (16件中 1-16件目)
1
-

銀輪花散歩・大山蓮華と山法師ほか
過日、ブロ友のひろみの郎女さんとももの郎女さんがヤマボウシの同じ木の花を掲載されていましたが、小生もその同じ木の花を写真に撮っていました。遅ればせになったので、ブログ掲載は没にするかと思っていましたが、昔に撮ったワスレナグサに似た野の花の名前が分からず不明としていたのが、偶然にネットで見た花から、その名が判明しましたので、銀輪花散歩としてそれを含めて記事にすることとします。<参考> ひろみの郎女さんのブログ記事:コチラ ももの郎女さんのブログ記事:コチラ 先ず、そのヤマボウシです。お二人とも「低い処に咲いていました。」と下枝(しづえ)に咲く一輪の花の写真を掲載されていましたが、その木は勿論もっと高い処に沢山の花を付けていましたので、小生の写真は上枝(ほつえ)に咲く花のそれです。(ヤマボウシ)(同上) ヤマボウシは漢字では山法師とも山帽子とも書くようですが、花が上空に向かって空を仰ぐように花柄高々に咲くので、遠目には木全体が雪でも積もったように白く染まる。かなり以前のことであるがTVで知ったこと。山の中腹に白い機体の飛行機が墜落しているという通報が相次いであり、調べてみたらそれはヤマボウシの花が群れ咲いて遠くからだと飛行機の形に見えたことによるものと判明して、一件落着。そんな騒動もあったらしい。 ヤマボウシは花も目立つが、実も独特の形で面白い。食べられるそうだが、そんなに美味しくはない、と言うよりも不味い。かすかに甘味はあるが気の抜けた青臭い甘味。実際に齧ってみた小生の感想であるが、食べ頃というのがあってそれを外していたのであれば、小生のこの感想は「お門違い」ということになるが、もう一度試してみようとは思わない味でありました。 その実は、こんな姿です。下の写真は、2014年9月18日の記事に掲載したものの再掲載です。(ヤマボウシの実) 秋には、この木にも上の写真のような実が生るでしょうから、それを見るのも楽しみです。 このヤマボウシの木は、先にご紹介したオオヤマレンゲの木の近くにあります。小生お気に入りの花とは言え、またまたオオヤマレンゲではこのブログをご覧いただく皆さんにはいささか食傷気味ということも懸念されますので、小さい写真で掲載して置きます。 (オオヤマレンゲ) (同上) オオヤマレンゲの実は食べられないのでしょうね。ちょっと齧ってみる気にはならない姿形です。(オオヤマレンゲの実) オオヤマレンゲの手前にはシャクナゲの花。シャクナゲと言えば室生寺がその花の寺として有名であるが、こちらのシャクナゲは西洋シャクナゲである。日本シャクナゲは葉の裏に細かな毛があるのに対して、西洋シャクナゲの葉にはそういうものはなくつるっとしていることで区別できるとのこと。で、葉の裏を観察したら毛が生えていなかったので、西洋シャクナゲと結論付けた次第。(西洋シャクナゲ) もう花の盛りは過ぎていましたが、♪ひとり遅れて咲きにけり、というのがありましたので、ついでに撮影しました。そして、下掲の写真は昨年11月に撮影のもの。花芽と種子の状態です。花の一番美しい時期を外しているヤカモチ写真。これではシャクナゲに嫌われますな(笑)。(同上:2016年11月12日撮影) (同上・種子) さて、冒頭で触れた、名前が判明した花ですが、それがこれです。(ノハラムラサキ) 2015年4月26日撮影のものです。ワスレナグサとかキュウリグサとかの名が浮かびましたが、花の大きさや葉やその他で何か違う気がして「名前不詳」にしていました。ネットでたまたま見かけたノハラムラサキという花がこれにそっくりさんでしたので、ノハラムラサキということにして置きます。 ノハラムラサキならヨーロッパ原産の外来植物ということになりますが、さてどうなんでしょうか。(同上)(同上)むらさきのにほへる花の名を知らばノハラムラサキわれ忘れめや(偐家持)(本歌)むらさきのにほへる妹を憎くあらば 人妻ゆゑにわれ恋ひめやも (大海人皇子 万葉集巻1-21)
2017.05.28
コメント(12)
-

同級生たちと墓参
本日は、中学時代の同級生と恩師の墓にお参りして来ました。 参加者は喜麻呂、谷麻呂、木麻呂とひろみの郎女さん(ひろみちゃん8021氏のこと)、ヤカモチの5名と恩師の奥様。 ひろみの郎女さんの車に男どもが便乗させていただくという、どう考えても逆だろうという妙なパターンですが、これが我々の墓参スタイル。 ということで、喜麻呂、谷麻呂とヤカモチは外環状道路沿いのファミレス・フレンドリーの駐車場10時半待ち合わせで集合。ひろみの郎女さんにそこでピックアップしていただくことに。(フレンドリー駐車場) 10時過ぎに待ち合わせ場所に到着。スグに喜麻呂君が現れ、彼と雑談していると、ひろみの郎女さんの車が到着。続いて谷麻呂君が到着。10時25分出発。 外環を北に走り、善根寺陸橋下で木麻呂君をピックアップ。第二阪奈道路経由で恩師の墓がある霊山寺霊苑へ。 墓に到着後、男どもが墓の草取りをしたりしているうちに、ひろみの郎女さんは恩師の奥様をご自宅にお迎えに。 墓が綺麗になったところで、花を供え、線香を上げてお参り。喜麻呂君が般若心経を唱えてくれました。ひと通り終わった頃に、奥様とひろみの郎女さんが来られました。お二人のお参りも済んだところで、場所を変えて皆で昼食という段取り。 店は、ひろみの郎女さんの馴染みのお店で、彼女が予約してくれていました。ただ、お墓から店まで行くについては、車には5人しか乗れない。ということで、ヤカモチは自転車で来いとの仰せで、出発の時に折りたたみの自転車トレンクルを車に積み込んで置いたのでありました。 (霊山寺霊苑) 店に行くには、富雄川沿いに北へ走り、阪奈道路の手前で左(西)に入り、帝塚山大学の北門前を過ぎて、椚峠を越える坂道を登らなければならない。峠を越えるまでの延々の坂道は銀輪ヤカモチにもかなりな道で、少し息が荒くなりました。店は近鉄菜畑駅前に出る少し手前、峠を越えた下り坂の途中にある店、アルナッジョというイタリアンのお店でした。(アルナッジョ) 昼食後、男ども4人が珈琲をしている間に、ひろみの郎女さんは奥様を車でご自宅までお送りして再び店に。彼女が戻ったところで、我々4人も店を出て帰途に。 墓参兼ミニクラス会の一日でありました。 なお、本日の写真は、全てスマホによるものです。デジカメも持って出たのでしたが電池切れ。朝の待ち合わせ場所でカメラを取り出してみたら、全く反応なし。ウンともスンとも言ってくれなかったのでありました。 <参考>恩師墓への墓参関連過去記事 恩師の墓参 2007.5.13. 恩師の命日 2007.5.17. お墓参りが思わぬ大遠征に・・ 2008.6.14. 墓参と銀輪行 2009.5.24. 中学時代の同級生と一緒に恩師のお 墓参り 2009.9.12. 大和西大寺駅から矢田寺経由富雄駅 まで(その3) 2010.3.7. 恩師の墓に参り来しかも 2014.10.30. 中学恩師の墓参・ミニクラス会 2015.5.20. 見まくの欲しき瓊花そして墓参 2016.5.2. <追記>ひろみの郎女さんもブログに記事ア ップされましたので下記にリンクし て置きます。 今日は中学校の恩師のお墓参り 2017.5.26.
2017.05.26
コメント(10)
-

テントウムシの幼虫が居た
テントウムシの幼虫を発見。 蛹もありました。 見つけた場所は、花園中央公園の片隅にある桃の木。 虫は見るのも嫌いというお方はスルーして下さい。(ナミテントウの幼虫) 幼虫の姿からはテントウムシのあの愛嬌のある可愛らしい姿は想像できない。何やら獰猛な生き物という感じである。動き回っているのは未だ若い幼虫。じっと動かなくなっているのは、間もなく蛹に変態するのであろう。 (同上)(同上) 蛹になると、テントウムシの姿に近くなる。(ナミテントウの蛹)(同上) 成虫は盛んに動き回るので撮りにくい。カメラを近づけると葉の裏や枝の反対側に隠れてしまう。成虫を撮影するのは、気温が低い早朝がいいでしょう。気温が低いと虫は動き回ることができないから、じっとしている。(ナミテントウ・成虫) ナミテントウは最も普通に見られるテントウムシ。ナナホシテントウが赤地に七つの黒斑を持っているのに対して、ナミテントウは星のない無地のものから20個も星のあるものまで色々。地が黒で星が赤という反転タイプのものも居る。 ナナホシテントウが七つ星の模様の伝統的様式を頑なに守っている保守派なら、ナミテントウは自由主義者、好き勝手な模様の衣装をまとう革新派ということになる。 保守派も革新派も、そしてその成虫も幼虫も肉食派にて、アブラムシなどの小さな虫を捕食する。樹液や葉を齧る採食派は害虫ということになるが、この害虫を捕食する肉食派の虫は益虫ということになる。従って、テントウムシは益虫である。 子供の頃は、害虫は悪者で駆除されるのが当然、益虫は正義の味方で大切に守られるべきものと考えていたりもしましたが、益虫もその食料たる害虫が居なければ生きて行けない。正義は悪があることによってのみ存在し得るではないが益虫は害虫が居ることによって成立するのである。そもそも益虫・害虫も、この場合で言えば樹木や花や果物、野菜などを栽培する人間様の都合による分類に過ぎない。それぞれの虫がこの地上の生態系を維持する上でそれぞれの役割を担っているということであれば、ヒト様の都合でこれを攪乱してはいけないのである。 さて、このテントウムシたちが居た桃の木であるが、実が生っていました。(モモ) 桃の実は邪を祓う霊力があると信じられていたのでしょう。イザナギが黄泉の国へイザナミを訪ねて行き、逃げ帰る際に、追いかけて来る鬼女に対して投げつけたのは桃の実であった。鬼退治をするのは桃太郎であって、栗太郎や柿太郎でないのも同じ理由である。 桃の実はその表面に無数の細かい毛がある。これは虫の侵入を防ぐという機能もあるのでしょう。万葉では「毛桃」と呼ばれてもいる。わがやどの毛桃の下に月夜さし 下心よしうたてこの頃(万葉集巻10-1889)(わが家の毛桃の下に月光がさして、何やら心の中が楽しい。益々この頃は) (同上) 一つだけ赤く色づいている実がありました。 自然に熟したものか、中に虫が侵入してまだその時でないのに赤くなってしまっているのかは、見ただけでは分からない。芳香を発しているのだろうか、蝿だか虻だか小さな虫がとまっている。(同上) 桃の木の近くに欅の木があった。 何気なく見上げると沢山の実。はてさてケヤキの実はこんなであったのだろうかと近付いてよく見ると、それは虫こぶでありました。(ケヤキの葉に虫こぶ) これは、ケヤキフシアブラムシの虫こぶである。一つ割ってみたが成虫も幼虫もいないもぬけの殻。白い綿毛のようなものがあるばかり。もう孵化して外の世界へ飛び立ったよう。 それにしてもすごい量の虫こぶ。何万匹のアブラムシが生まれたのでしょうか。丹念に探せばまだ虫がご在宅の虫こぶもあるのでしょうが、ゴマ粒よりも小さいアブラムシですから、撮影するのは困難。ブログの役には立つまいと「むしこぶ」割は3個で止めました。 (同上) アブラムシはテントウムシの食べ物。アブラムシが大量に発生するケヤキの木の傍らの桃の木にテントウムシの幼虫が沢山居るのも首肯できるというもの。 しかし、それなら何故このケヤキそのものにテントウムシの幼虫が居ないのだろう。ケヤキそのものに卵を産み付ければ、孵化した幼虫は食べ物に不自由しないだろうに、と思うのだが、テントウムシの孵化の時期とアブラムシが孵化して虫こぶから出て来る時期とが違っていて、うまくないのかも知れない。 それに、このケヤキフシアブラムシは虫こぶを出るとスグに他へ飛んで行ってしまい、ケヤキの木にとどまるということはしないのだろうから、餌場としてはむしろ不適切なのかも知れない。(同上) 葉の裏に産み付けられたアブラムシの卵が出す何らかの物質の作用で葉がこのように変形して虫こぶとなるようだが、ケヤキはケヤキフシアブラムシの言わば保育園みたいなものですな。 以上、銀輪虫散歩でありました。
2017.05.22
コメント(12)
-

再生囲碁サークル&タイ・フェスティバル
昨日(20日)は大学の同窓会・青雲会の囲碁サークルの例会に出席して来ました。 昨年までは、北区堂島のビルの一室が青雲会交流センターになっていたので、そこを会場に使わせていただいていましたが、青雲会が昨年一杯でこの部屋を返還・明け渡すこととなったことに伴い、碁を打つ会場のない囲碁サークルとなってしまっていました。 山〇氏から囲碁サークルの世話役を引き継がれた銭〇氏に於いて、適当な代替の部屋を探していただいていましたが見つからず、先般から大阪駅前第三ビルの17階にある、囲碁サロン「爛柯」を会場とすることで、活動再開となったのでありました。 言わば「再生囲碁サークル」であるが、小生は「再生」後のサークル例会初参加である。(駅前第三ビル) 毎度のことであるが、今回も「お天気よし」で、自宅からMTBを走らせての、銀輪散歩を兼ねての囲碁通いです。 都合よく自転車を駐輪する場所があるかどうかが心配でしたが、ビルの前の有料駐輪場に空きがあって駐輪することができました。 囲碁サロン「爛柯」に入ると、見知らぬ男性二人が碁を打って居られました。奥には囲碁サークルのメンバーの若〇氏が来て居られました。 我々のサークルは法学部卒業生の集まりであるが、これとは別に、経済学部卒業生も交えた囲碁の集まりが此処で行われているらしく、その世話役を最近になって金〇氏から、若〇氏が引き継がれたとのこと。どうやら、この法経合同の爛柯でのサークルにわが法学部のサークルも便乗させていただくこととしたもののよう。 そこへ、中〇氏がご来場。若〇氏と中〇氏の対局が始まる。小生は、その後に来られた泉〇氏とお手合わせ願うことに。同氏とは小生は初対面であった。氏は2年ぶりの久々の参加と仰っていましたが、それは此処「爛柯」での集まりのことで、青雲会の囲碁サークルの集まりのことではないのだろう。 小生の先番で打ち始めましたが、中盤から激しい戦いとなり、右辺打ち込みの白石の半分を取り込んでこれを仕留めると、白は上辺の黒の大石を殺し、黒は左辺から中央に伸びている白の大石を切断して取り込むという、二転三転の展開。左辺の白の大石が死んだところで勝負あったで、小生の中押し勝ちとなりました。(囲碁サロン・爛柯) 対局中に、銭〇氏、廣〇氏、金〇氏その他名前を存じ上げないお方などが次々にご来場。小生は廣〇氏に1敗、銭〇氏に1勝1敗で、この日は2勝2敗。今年の青雲会囲碁は五分の成績でスタートしました。(同上) この後、懇親会と言うか二次会と言うか、皆さんで何処かで飲み食いされるとのことであったが、小生は自転車なので、暗くなるまでのお付き合いは致しかねると午後5時過ぎに失礼申し上げました。ヤカモチは今は罷らむチャリなれば 遠き夜道のいや難からむ(銀輪家持)(本歌)憶良らは今は罷らむ子泣くらむそれその母も吾を待つらむぞ(山上憶良 万葉集巻3-337) さて、話は変わって、往路でのことです。 いつもの通り、大阪城公園を走っていると、何やら賑やかな音、声、人の群れ。何事かと覗いてみるとタイ・フェスティバルという催しでした。通りすがりの野次馬にて、チラッと覗いてみただけでありますが、その風景を紹介して置きます。(15th THAI FESTIVAL 2017 in Osaka) 第15回目とあるから、この催しは長年にわたって行われているようですが、小生は初めてその存在を知りました。(同上) (同上) ステージでは何やら舞踏劇のようなものが演じられていました。(同上)(同上) (同上) 暫し見ていましたが、所作などから色々と想像はされるものの、通りすがりに途中から見ている小生には、本当の意味や内容は全く分からずです。 (同上) 以上です。実は当記事は昨日の夜に書き上げたのですが、ほぼ完成という段階で、取り敢えず下書き保存を、とその操作をしたら、PCがご機嫌を損ねたようで、インターネットへの接続が断線したのか、全部消えてしまいました。再度、始めから書き直す気力は失せてギブアップ。本日仕切り直しで当記事を書きましたので、随分と手間のかかった記事となりました。
2017.05.21
コメント(8)
-

夕々の会
本日は、大学入学同期の会・名付けて「夕々の会」の例会。 毎年5月と11月の2回、集まって旧交を温めているのである。 今回は、がんこ梅田OS店を会場として、13名が集まりました。 在関西の入学同期の者を中心に20数名が名を列ねているが、今回はいつになく集まりが悪く、約半分の出席率にとどまりました。(梅田OSビル) 会場は、幹事の守麻呂君が手配してくれて、このOSビルの地下にある「がんこ梅田OS店」となった次第。 そう言えば、昨年11月の会場も阪急石橋駅近くの「がんこ」であったから、頑固に「がんこ」が続いていることになる。守麻呂君も店の選定が面倒になったと見えて、次回以降も「がんこ梅田OS店」にしようということに決まったので、当分は「がんこオヤジの会」ということになりそうです。(がんこ梅田OS店) 午後5時半開会。小生が店に到着したのは午後5時になるかならないかの早い時刻であったので、一番乗りでありました。(同上・開会前の部屋) 部屋に通された時の状態は上の通り。来た者順に奥からということで、小生は右側の一番奥の席に。幹事の守麻呂君が続いて現れ、彼は手前左側で出席者からの会費徴収を担当。続いて、西麻呂君と古麻呂君が現れ、西麻呂君は小生の向かい側の席、古麻呂君は小生の隣の席に着席。雑談しているうちに、久麻呂君、黒麻呂君、佐麻呂君、谷麻呂君、蝶丸君(別の友人の蝶麻呂君と紛らわしいので「蝶丸」としました。)、堀麻呂君、道麻呂君と来場、最後に出麻呂君が来て、全13名が定刻2分前に勢揃いしました。 もう一人の幹事・谷麻呂君の乾杯の発声で開会。後は適宜に飲み、食い、お喋り、のいつもの通りの成り行き。今回は、黒麻呂君がこの3月で6年間務めた同窓会・青雲会の事務局長を退任されたので、その慰労の意味も含めて、彼からスピーチを頂戴しました。彼を同窓会の世話役に引っ張り込んだのは、小生で、小生が同窓会の会長をやらされた時には副会長の一人として、色々とお世話になったのでした。小生が会長を退任した後もずっと副会長の任にあり、6年前からは前任の青〇氏の後継の事務局長になられて、同窓会の裏方を支えて来られました。本当にご苦労様でありました。 さて、暫くした頃、道麻呂君が小生の方にやって来て、今、興味を持って読み始めている本だが、「ヤカモチさんならご存じだろう。」と見せてくれたのが、岩波文庫の「橘曙覧全歌集」。 橘曙覧については、越前福井藩主・松平春岳が彼を歌の師と仰いだことや、正岡子規が彼の歌を高く評価し「曙覧の歌」(岩波文庫の正岡子規「歌よみに与ふる書」に所収)という著述を著したことによって、彼の名が広く世に知られるようになった、ということ位の知識しかなく、独楽吟その他の歌を少しばかり知る程度であったので、何と言って彼について話せるものは持ち合わせなかったのでありました。 ということで、橘曙覧の独楽吟風に、1首作れば、たのしみは皐月霜月日を定め どちとし逢ひて飲み食ひするとき (橘家持)ということになる(笑)。 (注)「独楽吟」の「吟」は、正確には、口ヘンに金であるが、楽天ブログでは使用できない機種依存文字であるので、「吟」としています。 橘曙覧であれ何であれ、万葉風の歌に関心を持って「面白い」と感じて、このような話ができる友人・どちのあることは、まことに楽しく愉快なことではあります。
2017.05.19
コメント(6)
-

ふたたびオオヤマレンゲ
今日は、銀輪散歩のついでに例のオオヤマレンゲを見て来ました。 沢山の花を咲かせていました。 ということで、その花の色んな姿をじっくりとご覧いただくこととしましょう。(オオヤマレンゲ) このように茶色く変色したものもあるが、これは花の盛りを過ぎて、萎んで行こうとしている花ですな。花は開花する前は「つぼみ」と呼ぶが、花の命を終えて萎みつつあるものは特に名がない。つぼんでいるから「つぼみ」なら、しぼんでいるのは「しぼみ」であるのだが、誰もそんな呼び方はしない。やはり花は咲いているうちが花にて萎んでしまっては花ではないということですな。(同上) 下のそれは間もなく開花しようというオオヤマレンゲ。(同上) そして、このように美しく清らに咲く。 見れども飽かず、という花である。 (同上) しかし、花の色は移りにけりな・・である。やがてこのように黄色みを帯び、茶色く変色し、萎れて行く。 桜の花が潔いとされるのは、このように変色する前に散ってしまうからであるが、花弁が肉厚の花は「散る」ということはせず、このように変色して「落ちる」だけなのである。散らぬ花は興醒めなどと言うのは人間様の勝手な評価。花には花の都合があるのであって、人間様の興趣のために咲いている訳ではないのでありますな。(同上) ということで、オオヤマレンゲの「しぼみ」もつばらに見て進ぜようという次第。 (注)つばらに=くわしく、つまびらかに、の意。 下はもう落花寸前。実に姿を変えようとしています。 中央の黄緑色の芯が膨らんで実になる。その裾部分にまとわりついている雄蕊も実となる頃には剥がれ落ちてしまうだろう。(同上) オオヤマレンゲの近くに咲いていたのはベニウツギ。タニウツギの仲間である。普通のタニウツギはピンク色の花であるが、これは濃い紅色である。タニウツギの栽培種と言うから観賞用に品種改良された園芸品種のタニウツギということになるのでしょうか。(ベニウツギ<タニウツギの栽培種>)(同上)(同上) オオヤマレンゲとベニウツギ。この紅白の花たちと暫し遊んだアト、道向かいの喫茶店「ペリカンの家」で珈琲休憩。 お客様が3組居られましたが、その内のお一人は顔見知りの男性。と言っても名前は存じ上げない。この方も喫煙されるので、何度か店の前の喫煙ベンチでご一緒したことがあり、言葉を交わすようになったのであるが、今日は軽く会釈を交わしただけ。この近くの会社にお勤めのようで、昼食によくこの喫茶店をご利用になるので、昼食時間帯にはよくお会いするのである。 ペリカンの家の入口、左側にはシマトネリコの木と西洋イワナンテンの木、右側にはオリーブの木がある。そのオリーブの木が花を付けていました。オリーブの花を見るのは初めてのような気がする。微小の花なので、撮影には骨が折れるのだが、なんとか撮影できました。こんな花です。 ほとんどが未だ蕾。僅かに開き始めたものもある。完全に開花したのが一輪ありましたが、花の向きが悪くて撮影するアングルが取れないので撮影を諦めました。(オリーブの花) 花が咲けば、次は実。オリーブの実を期待したい処であるが、オリーブは自家受粉できない木である。近くに別のオリーブの木があれば、蜂などが受粉の手伝いをしてくれるのだろうが、そのような木も見当たらないから、この木に実が生ることはないのでしょうな。樫の実のひとり立つ木やオリーブの 花は咲けども実にならじかも(偐家持) (注)樫の実の=「ひとり」に係る枕詞。(同上・拡大) ペリカンの家では、店主のももの郎女さんと、珈琲をいただきながらお喋り。ももの郎女さんのお友達の「薫の郎女」さんも店のお手伝いに来て居られて、ヤカモチは初対面であったが、彼女も交えて、花や自転車やその他諸々についてのお喋りで、暫しの時間を楽しく過ごさせていただきました。 <参考>花関連の過去記事は以下の通り。<追記:2017.5.17.> 花(1)2007~2011 花(2)2012~2016 花(3)2017~2021
2017.05.16
コメント(12)
-

岬麻呂旅便り204 北海道・富良野
本日、友人の岬麻呂氏より旅便りが届きました。 今回は、北海道・富良野旅行。富良野は同氏には余程にお気に入りの土地らしく、何度もこの地を訪ねて居られます。従って、過去記事でご紹介済みの景色の写真などと重複する写真もあるかと存じますが、それはそれとして、今回は今回ということで、気にせず掲載させていただきます。 <参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。(旅・岬巡り報告204) 例によって、旅の詳細については、岬麻呂氏による、上掲の「旅・岬巡り報告204」をご参照いただくこととし、ヤカモチはそれを適宜につまみ食いしつつ、記事作りといたします。 今回の旅は、今月8日~11日の3泊4日の北海道・富良野旅行でありました。 初日8日は、新千歳空港からお知り合いの「佐藤さん」宅へ直行し、小樽、余市などをドライブされた由。この佐藤さんというのは、小生も存じ上げている佐藤さんであるのかどうかは不明(笑)。(小樽運河) この小樽や余市は、小生も銀輪散歩で訪れているので、懐かしい。 <参考>小樽銀輪散歩(その1)(その2)(その3) 余市へ ニッカウヰスキー北海道工場・余市川 2日目・9日は富良野へ。 山部桜街道(下掲写真)から麓郷の森へ。(R38富良野・山部、後方は芦別岳)(鳥沼公園) 此処、鳥沼公園は岬麻呂氏お気に入りの場所とか。氏が秋の紅葉のマイ標準木とされているという桜木が今は花の盛りでありました。 先の東北旅行が桜花を求めての旅であったように、今回の旅も幾分かはそういう目的もあったのやも。 それとも、富良野とあれば、花は花でもエゾエンゴサクの花がお目当てであったか。(エゾエンゴサク<白>)(エゾエンゴサク<青>) そして今回も麓郷の森のfurano-craftさんをお訪ねになったようであります。 <参考>furano-craftさんのブログはコチラから。 furano-craftさんのブログ、長らく訪問していなかったようですが、リンクを貼るために先程訪問申し上げたら、4月20日の記事以降、更新されていないということに気付きました。 岬麻呂氏のご報告でも触れて居られますが、furano-craft氏は体調を崩されて居られたようです。今はもう回復されてお元気とのことで、岬麻呂氏の森散策をご案内下さったようですから、心配はないのだろうと思いますが、ご無理なさらぬように、ご自愛専一のほどを願って居ります。 <追記> 先程、furano-crftさんのブログを再度覗きましたら、体調不良により暫くブログの更新を休ませていただくと書かれていました。心配です。どうぞ早くにお元気になられますように。(furano-craftさんのお店、木力工房・森の雑貨屋さん)(富良野岳と富良野盆地)(富良野岳の夜明け)(新富良野プリンスホテル・ニングルテラス) 新富良野プリンスホテルが岬麻呂氏の定宿なんでしょうか。このニングルテラスも以前の岬麻呂旅便りの記事で写真を掲載した記憶がある。此処に連泊し、3日目の10日は、美瑛の丘めぐりをして、旭川の上野ファームに立ち寄られたとのこと。 何度も当地への旅を重ねられているので、色々と新しいお知り合いやお馴染みも増えて、通りすがりの旅とはまた一味違ったいい旅をして居られるようであります。(上野ファーム) 以上、岬麻呂旅便りでありました。<追記:5月16日朝>岬麻呂氏よりメールが届きましたので、参考までに追記して置きます。下線部分は本名が記されていましたので、ブログ語に翻訳しました。furano-craftさんのブログ訪問いたしましたら、貴兄のお便りどうり「更新中断」の記事でした。まだ顔色が優れないように拝察したのが、その兆候だったのかと心配しています。一日も早い回復を祈念したいものです。(岬麻呂)「204報告」のブログコメントに補足説明1.天候の件 基本的には夫婦ともども晴れ男・晴れ女ですが、お天気ですからお天道様まかせですね。初日と最終日は雨の予報でしたから諦めていました。ところが札幌に着いたら晴れたり曇ったりでラッキーでした。さすがに最終日は一日中雨でしたが「イトウアイリスガーデン」でしたから、小雨の庭園めぐりも趣があり良かったです。2.高島岬の日和山灯台の件 この時には灯台に日が差さず、撮ったが「海・空の色」いまいちで以前のものの方が良いのでお届けしませんでした。3.写真の色ですが、これも「お天道様まかせ」です。今後も貴兄のブログの読者の皆様に「良い色の風景写真」お届けしたいと考えています。
2017.05.15
コメント(12)
-

偐万葉・LAVIEN篇(その5)
偐万葉・LAVIEN篇(その5) 当ブログは、フォト蔵にアップロードした写真をブログに貼り付けるという方法で写真を掲載しています。直接にPCのマイピクチャから掲載するという方法もあるが、そのためには写真のサイズを小さくしなければならず、それが面倒なこともあって、フォト蔵を利用することとしたもの。楽天写真館も一時利用したが、総登録ギガ数が一定数までという制限があるので、ブログ掲載写真がどんどん増えて来ると何れ満杯となって利用できなくなる可能性がある。ということでフォト蔵にしたもの。 さて、そのフォト蔵であるが、只今メンテナンス中で利用不可。フォト蔵の今回のメンテナンスは、単に新規写真のアップロードが出来ないということだけではなく、既存の記事に掲載の写真すべてがブログに表示されないというものであるので、メンテナンス中に当ブログをご訪問戴いた方は、写真が表示されていない記事をご覧になる訳でかなり興醒めなことでしょう。 それはともかく、こうなると通常の記事のアップは出来ないのであるが、偐万葉シリーズの記事だけは例外となる。偐万葉シリーズの記事は、対象となるブロ友さんのブログ写真をPCに取り込み、それをダウンサイズした上、PCから直接に楽天ブログに掲載しているから、フォト蔵とは無関係なのである。 フォト蔵のメンテナンスは既に終了し、通常の状態に復しているようですが、既に、記事の下書きに入ってしまっているので、本日は偐万葉シリーズ記事とします。 偐万葉シリーズ第282弾となる、偐万葉・LAVIEN篇(その5)であります。ブロ友のlavien10氏とのお付き合いは2013年12月6日からなので、3年半近いお付き合いということになる。この方の特長は、コメントは殆ど全て、ブログ記事本体の方ではなく、楽天プロフィールの方に書き込みされるという点にある。従って、記事コメント欄では殆どお見かけしないお名前となって居りますが、それは如上の理由によるものであります。<参考>過去の偐万葉・LAVIEN篇はコチラからどうぞ。 lavien10氏のブログはコチラからどうぞ。 偐家持が羅美麻呂に贈りて詠める歌19首ほか花あれば何とか記事にもなるやらむ 実のある記事にもとよりなけどたなばたに 似たるたなぼた さにもあれ 笹にしあるは 棚ぼたの夢 (棚上げの夢) つきづきの つきはみるもの つかむもの つきつかまぬは うんのつきなり (月光仮面)(月々の月<付き>は見るものつかむもの付き<月>掴まぬは運の尽き<月>なり)杉樽がありてこそなる酒なれど ほどは知るべし過ぎてはならじ(酒麻呂) 蝉の声止みて闇にし蚯蚓鳴く(筆蕪蕉) 月見れば知事もものこそ悲しけれ 築地に土の嘘もあるとよ(小池郎女)(注)初案「築地の土も嘘にしあれば」を「築地に土の嘘もあるとよ」に変更した。「あるとよ」の「とよ」は「豊洲」の「とよ」を掛けているつもり。(本歌)月みればちぢにものこそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど (大江千里 古今集193 小倉百人一首23)豊洲なる市場の土のごまかしは 誰やなせると知らずは置かじ(東京都民)(本歌)三諸の神の帯ばせる泊瀬河 水脈(みを)し絶えずは吾(われ)忘れめや (大神大夫 万葉集巻9-1770) 空見つつ雲の機嫌のよしと見て 近場足早銀輪散歩 (銀輪家持)尾も白き犬の歯無しに笑へとて 真っ赤ならざる真っ白な嘘 (偐犬丸)白袴穿ける紺屋を嗤ふとは おのれ知らぬか歯医者の歯無し(赤穂義歯)木石に あらねば悩み 尽きざれど 生きるといふは さにてこそあれ (石木人麻呂) 世間虚仮うつつも夢のごとなれば 夢もうつつも所詮変らじ 明日香なるにをととひ来よと定休日 とふ人まばら雪のしげけく(昨日香家持) (注)初案「来い」を「来よ」に修正。なつかしき顔見し時もいや遠み いつとも今は知らぬなりけり(黒式部)よもやまの話はこれぞスポーツの 罪なき話にしくものぞなき(スポーツ氏)よもやまの ネタにしなるは 身の不徳 よもやましきの 身にはなくとも (政官界麻呂) 豊洲なるあづまの乱れさて置くも 博奕で千金夢洲の夢(浪速博徒)桜花いまだ含(ふふ)めりしかすがに 銀輪万葉千花と咲ける(注)しかすがに=そうであるけれども不来方の春選抜は静岡に 敗れて負けぬ十の心か(石川敗北)(本歌)不来方のお城の草に寝ころびて 空に吸はれし十五の心(石川啄木 「一握の砂」) 羅美麻呂のブログへのjiq氏コメントに和して詠める歌1首わが岡の おかみが言へる 自己責任 腰も砕けて そこそこに去る (安倍の宮の役民の歌)(本歌)わが岡の おかみに言ひて ふらしめし 雪のくだけし そこにちりけむ (藤原夫人 万葉集巻2-104)<参考>藤原宮の役民の歌=万葉集巻1-50 <脚注>掲載の写真は全てlavien10氏のブログからの転載です。なお、写真と歌とは直接の関係はありません。
2017.05.12
コメント(6)
-

囲碁例会・梟の足のこしてや
本日は囲碁例会。梅田スカイビルまでMTB銀輪散歩でありました。 中央大通りやこれに並行する裏道などを走って、大阪城公園、天満橋経由梅田スカイビルまで、というのが銀輪のコースなのであるが、先日、ブロ友の「☆もも☆どんぶらこ☆」さん(以下、「ももの郎女さん」と言います。)が、そのブログ記事で、大阪城公園のフクロウ君が引越しをしたのか見当たらなかった、と書いて居られたのが気になって、そのフクロウ君の居た場所を訪ねてみました。すると、ももの郎女さんの仰る通り、フクロウ君の姿は見えないのでありました。 <参考>☆もも☆どんぶらこ☆さんのブログ記事 今日は大坂城まで 2017.4.29.(フクロウの足跡) ご覧のように「足」だけが、もう少し正確に言えば「足先」だけが、残っていました。 「立つ鳥跡を濁さず」と言いますが、このフクロウ君は足跡と言うか、足そのものを残して行きました。誰かが壊して持ち去ったということでもあるか。(大阪城公園のフクロウ) フクロウ君というのは、上の写真のように、大阪城公園の桜広場の近くにある桜の古木の切株に鎮座ましましたフクロウのことなのであります。 <参考>大阪城公園のフクロウ 2016.7.30. 小生が大阪城公園で見つけてブログ記事にその写真(上掲)を掲載したのであるが、その記事を見てであったか、「近くに行くことがあったら見てみたい」とももの郎女さんは仰って居られました。そして、先般お友達と銀輪散歩で大阪城公園に行かれる機会があり、このフクロウ君を探されたのでありました。探せどフクロウの居る切株が見つけられなかったのではないのか、などと小生は思ったりしていたのですが、さに非ず。ももの郎女さんのお言葉通りの「引越し」かどうかは別にして、切株には不在であったのでした。何者かに拉致されたのか。 もし、これが何者かの悪戯によるのだとしたら、酷いことをする奴が居るものです。尤も、このフクロウの設置そのものが、公園管理者の許可を得ず、何者かが無断でなした「違法」なものであって、公園管理者がこれを撤去した、ということも考えられるのであるが、それにしては、足だけ残すというのは、不徹底で美観上はむしろよろしくないことである。このような中途半端な撤去なら、フクロウ君をそのままにして置く方がはるかにいい。梟の足のこしてや消えし胴 (袋の鼠)(元句)五月雨の降のこしてや光堂 (芭蕉 おくのほそ道) 今日も昼食はれんげ亭。(2017.05.10.れんげ亭) れんげの郎女さんは、GWに東京から高校時代の友人が訪ねて来たので、京都を案内したが、何処もいっぱいの人で大変でした、と仰っていました。 梅田スカイビル到着が12時20分頃。 早過ぎる到着なので、久しぶりに里山を散策。 色んな花が咲いていましたが、エゴノキが丁度花の盛りでありました。 この花も万葉植物であることは、過去の記事でも何度か紹介しているので、詳細はパスします。興味ある方は下記<参考>をご参照下さい。 <参考> エゴノキ(ちさ) 2007.8.11. エゴノキ(ちさ)の花が咲いた 2008.5.6. チサの実のさはにぞなれる 2013.10.24.(エゴノキ) 花園中央公園にもこの木があるから、今頃は咲き匂っていることでしょう。(同上) で、これは何でしょう。 ムラサキシキブの花芽でしょうか。 これから更に芽が伸びて花を付けるのかも知れぬが、この白いモフモフとしたものからあの何やら旺盛な生命力を感じさせる花が出て来るのだろうか。非常に小さなもので、肉眼では白っぽい四角いものが4つ並んでいるだけという、何とも分からぬ代物である。 なお、念のため申し上げて置くと、コムラサキのそれではありません。コムラサキより葉も実も大きく、樹高も人の背丈よりも高い、ムラサキシキブなのであります。 ムラサキシキブの花は過去記事で紹介していますので、それをご参照下さい。 <参考>囲碁例会・ムラサキシキブの花 2012.6.13. 囲碁例会・花野散策 2012.7.4. 今年最後の囲碁例会・ドイツXmasマーケット 2013.12.11. 囲碁例会・可もなし不可もなし 2015.12.2.(ムラサキシキブの花芽?) さて、会場の方に行くと、竹〇氏が既に来て居られました。早速にお手合わせ。そこへ村〇氏、福〇氏、平〇氏に特別参加の利麻呂氏が来場。 利麻呂氏は小生の友人にて、碁を覚えたい、ということで、今年に入ってから、時々ご来場されているのである。まだ、対局できるほどではないので、手すきの者が番外で彼に指導碁を打って教えるというようなことをしている次第。今日は、小生が2局ばかり、彼と打ちました。 利麻呂氏への指導碁が一段落したので、福〇氏と対局。 今日はこの2局だけでしたが、共に小生の勝ちで、2戦2勝。久々に負けなしでありました。それでも今年は連敗が続きましたので、通算で漸く7勝14敗で、未だ7つ負け越しになっています。 囲碁終了後、利麻呂氏とタワーイースト1階の馴染みの喫茶店へ。先月の12日以来となるこの喫茶店での閑談。「お久し振りですね。」という女店員さんのお愛想から、顔を見知っていただいていることに気付く。以前よく来ていた頃の女店員さんは自転車に興味があったらしく、小生ともそんな話をしたことがあったが、彼女は店を辞めたのか見かけなくなって久しい、というのが小生の認識。今日の女店員さんは彼女とは別人だと思うのだが、この年齢になると若い女性の顔は似ているように見えてしまって、余り区別がつかないと言うか、記憶にしっかりとは残らないので、ひょっとしたら、あの女店員さんであったのかな、などと思ったりと何とも頼りないことなのである。 喫茶店を出て、利麻呂氏と別れて家路に。雨がパラつき出し、少し濡れる場面もありましたが、本降りになる前に止んでしまい、花園ラグビー場に着いた頃には濡れた服もズボンもすっかり乾いてしまっていました。 奥さんが入院されている友人のオガクニマン氏からは、「今月25日に退院できることに決まった」という嬉しい電話もあり、碁も2戦2勝で、今日は「先ずはめでたし」の一日でありました。
2017.05.10
コメント(8)
-

オオヤマレンゲ咲きにける
前回の記事(5月6日記事)で、昨年の9月以来、何の木か「気になって」いた木がオオヤマレンゲであることが判明したと書きましたが、ブロ友の「ももの郎女」さんからの情報で、その木に花が咲き始めたことを知りましたので、銀輪散歩のついでに、それを見て来ました。(オオヤマレンゲ) 小生の記憶では、薬師寺で見たオオヤマレンゲの花はもっと大きかったような気がするのだが、オオバオオヤマレンゲというひと回り大きい花を咲かせるものもあるそうだから、それを見たのかも知れない。 (同上) まことに美しい花である。(同上) 上と下の写真は後ろを向いて咲いていたので、花の付いた枝を左手に持って、こちらに引き寄せて、花を上に向かせて撮ったものであるので、自然のポーズではありません。上を向いて花を咲かせるウケザキオオヤマレンゲというのがあるが、オオヤマレンゲは下を向いて咲く。またウケザキオオヤマレンゲの花びらはオオヤマレンゲのように純白ではなく、ベージュがかった色である。(同上) そして、蕾はこのように茹で玉子を剥いたような感じなのである。このようになると2~3日中には開花し出す筈。(同上・蕾) 下は、花苞が弾けて蕾が顔を覗かせた状態。(同上) で、下の写真の実がこの植物の実である。昨年の9月17日に「何の実だろう」と疑問を持ったのが、この木との出会いでありました。 そして、6日にこの木がオオヤマレンゲであることを知ることとなったのであったから、実に8ヶ月を要してわが片恋が「遂に実った」ということになる。(オオヤマレンゲの実<再掲>) この木はブロ友の「ももの郎女」さん経営の喫茶店「ペリカンの家」の道向かいの病院の庭にある。 そんなことで、花の撮影を終えてから、ペリカンの家に立ち寄り、珈琲休憩としました。ももの郎女さんや店員の「越の郎女」さんらと雑談の後、智麻呂邸に向かいました。第190回智麻呂絵画展の記事を印刷に打ち出したものをお届けするためである。智麻呂さん、恒郎女さんと暫し談笑して、新作智麻呂絵画を3点撮影しました。GWは智麻呂邸もお嬢様やお孫さんたちが入れ替わり立ち替わりに帰って来られて、賑やかなことであったのでしょうが、それは智麻呂絵画にとっては逆風の環境。絵筆を握る暇が余りなかったようで、新作は3点に過ぎなかったのでありました。 最近は、絵のペースが落ちているというのが恒郎女さんの言でありましたが、智麻呂さんにとって、それが最適のペースなら、それはそれでいいということでもあります。ヤカモチ館長はいつも「智麻呂ファースト」、智麻呂ペースを最大限尊重、というのがその基本ポリシーである。描かざれば描かせてみよう智麻呂絵画、なんてことは言わない、描かざれば描くまで待とう智麻呂絵画、なのである。 それはさて置き、大和高田市にお住まいの「中のお嬢様」からヤカモチ館長にという、三輪の生素麺をお土産に頂戴しました。有難く頂戴仕り候、であります。(三輪山勝・生そうめん)<参考>過去の「花」関連記事はコチラからご覧下さい。
2017.05.08
コメント(8)
-

墓参と花散歩そして気になる木
今月の墓参は3日でした。 墓参に向かう坂道の民家の垣根に今を盛りと咲いていたのはハゴロモジャスミン。その強過ぎる香りは小生の苦手とするところ。辟易しながらも、一応撮影して置くこととした。花そのものは美しいので。(ハゴロモジャスミン) <参考>ハゴロモジャスミン・Wikipedia ハゴロモジャスミンは漢字では羽衣素馨と書くようです。 モクセイ科ソケイ属の植物。 ジャスミン(Jasmine)は、ペルシャ語に由来する名とのこと。 ジャスミンの仲間のマツリカ(茉莉花)はサンスクリット語に由来。(同上) ハゴロモジャスミンのあるお宅から更に坂を上ると蔓性のバラが咲き乱れているお宅がある。こういう咲き方を見るとモッコウバラかと思ってしまうが、普通に見るモッコウバラはもっと花が小さく八重で黄色に咲く。白で一重咲きのモッコウバラもあるそうだが、バラの品種は無数に近く、小生などの手に負えない。単に「白バラ」として置くのが無難というもの。(バラ)真っ白な 嘘が空まで 薔薇の花 こんな句は、このバラやこのお家の方に失礼であるか(笑)。 真っ赤な嘘は、正真正銘の嘘であるが、真っ白な嘘は分かりにくい。清廉潔白などという言葉があるように、白は「真実」や「無垢」と隣り合わせの色で「嘘」とは遠い色だから。嘘も方便と言う、優しい嘘が真っ白な嘘だろうか。 真っ青な嘘、となると嘘をついた方もつかれた方も真っ青になる「とんでもない嘘」という感じか。真っ黒な嘘は何やら悪質な嘘の感じがする。 そんな馬鹿なことを考えながら、そのすぐ上の辻を右に入るといつもの寺の門前である。この日の言葉は次の通りでした。(2017.5.3.の門前の言葉) 幸も不幸も相対的なもの。他者との比較、過去の自分との比較に於いてそれを量るというのが人間であるからです。「量る」と言うように、それは世間一般の尺度によって量的なものを量っていることになる。質的なものは量りにくい。個々人によって評価が異なるからである。そういう相対的な評価を用無きものとし、吾唯足るを知る、ことが幸福への鍵であるのでしょう。 この日の墓参で撮った花の写真はハゴロモジャスミンと白バラだけ。これでは花三歩に一歩足らないこととなるので、それ以前や以後の銀輪散歩で撮った草花の写真を並べて「花散歩」の体裁に整えることとします。(スズメノカタビラ<雀の帷子>) これは、道端や野辺にて、頻繁に目にする草。 雑草の代表みたいな草であるが、「雀の帷子」という、立派なと言っては言い過ぎになるが、それなりの名前を持っているのである。(同上)(同上) そして、コナラの花。スズメノカタビラの花もコナラの花も、我々の「花」の概念からは外れた形状であるので、勿論、花屋はこれを取り扱わない(笑)。 しかし、わが花散歩の花は、ハナから広い範疇としているので、このようなものも取り扱い品目といたして居ります。(コナラの花)(同上) クスノキも今が花の盛りである。この春に芽生えた若葉の浅い緑が照り映える中に、微小の白い花を咲かせている。春の山は「山笑う」と形容するが、クスノキも春から初夏にかけては笑っているようなのである。(クスノキの花) 接近して、よく観察すると、その微小な花は、ちゃんと6弁の白い花ビラを持った、花らしい形状をしている。(同上)(同上) クスノキの足元にはチガヤが銀色の穂を風になびかせている。(チガヤ) チガヤ(茅)は、浅茅(あさぢ)とも言う。背の低い茅(かや)という訳である。万葉の頃は、この若い花穂を摘んで食べたようである。ちばなとかつばな(茅花)とも呼ばれる。少し甘味のある味だそうだが、このように穂が弾けてしまっては食べられない。一度試してみようと思いつつ、花穂が目立つようになってからコイツに気がつくのが常でいつも手遅れ、未だ果たせていない。 大伴家持が若い頃、年上の女性であった紀女郎から「あなた痩せ過ぎ。これ食べてもっと太りなさい。」(万葉集巻8-1460)とからかわれたのがこの茅花なのである。(同上)(同上) 此処のチガヤは自生ではなく、人の手で植えられたもののよう。煉瓦ブロックで囲われている。その煉瓦ブロックにへばりつくように生えていたのがこの草。 ノミノフスマ(蚤の衾)かと思いきやそれよりも更に小型のノミノツヅリ(蚤の綴り)でありました。ノミノフスマは5弁の花弁に切れ込みが深く入って10弁の花弁のように見えるのに対して、ノミノツヅリは5弁の花のままである。(ノミノツヅリ<蚤の綴り>) 下左がそのノミノツヅリの花。 ちょっとピントが甘くなったので大きい写真には堪えられない鮮明度。小さめの写真で紹介して置きます。(同上) で、これは、ももの郎女さん(ブロ友の☆もも☆どんぶらこ☆さんのこと)のお店・喫茶「ペリカンの家」の近くで見つけたアカバナユウゲショウ。赤花夕化粧とは何とも色っぽい素敵な名を貰ったものである。「浴衣のきみ~は・・もう一杯いかがなんて、妙に色っぽいね」という昔に流行った歌を連想したりもする。 この花の名を教えて下さったのは、これもブロ友のビッグジョン氏である。(アカバナユウゲショウ) <参考>第7回ナナ万葉の会 2014.10.10.(同上) 先月の千早城趾への銀輪散歩で千早赤坂村で見掛けたレンゲ畑であったが、そんな遠出をしなくても、わが東大阪市内にもありました。我が家から北へ大東市に入る手前の善根寺町にそれはありました。 レンゲソウというのがこの草の名前であるから、レンゲソウ畑と言うのが正しいのかも知れないが「レンゲ畑」と言うのが我々の普通の言い方のような気がするので、レンゲ畑として置きます。 (レンゲソウ畑) (同左) そして、最後は、去年から気になっている木です。 喫茶「ペリカンの家」の前の病院の西側の庭にある木です。 小生が気にしているので、ブロ友のひろみの郎女さんやももの郎女さんまでもが気にしていただいて見守って下さっていますが、漸く蕾をつけたようです。花苞が取れて何やら茹玉子を思わせる白い肌を見せています。少なくとも白い花を咲かせる木であることが判明しましたが、どんな形の花を咲かせるものかは、この時点では未だ不明。 この時期の白い花となると、夏椿(シャラ)、クチナシ、ヤマボウシなどが思い浮かんだが、それらとは葉も実の形も違う。ひょっとしてオオヤマレンゲではないかとネットでその実を検索したら、何んとドンピシャ的中でした。 以前、薬師寺で見た、あの美しい花であったとは。開花が楽しみです。 <参考>銀輪花散歩・秋づけば 2016.9.17. この実何の実のその後 2016.10.20. 是非に及ばず 2016.11.5.(正体不明の木はオオヤマレンゲの木でした。) ※花の姿は下記参考記事をご参照下さい。 <参考>奈良銀輪散歩(その3) 2009.5.23.
2017.05.06
コメント(8)
-

あやめ草玉に貫く日
ほととぎす 待てど来鳴かず 菖蒲草 玉に貫く日を いまだ遠みか (大伴家持 万葉集巻8-1490)という歌がある。 歌の意は「ほととぎすを待っているが、いっこうに来て鳴いてくれない。あやめ玉を薬玉にさし通す日がまだ遠いからだろうか。」というもの。 大伴家持さんは、余程ホトトギスの声が好きであったようで、「玉くしげ二上山に鳴く鳥の声の恋しきときは来にけり」(万葉集巻17-3987)という歌なども詠んでいるが、それはさて置き、この「あやめ草玉に貫く日」というのは5月5日、端午の節句の日のことである。 あやめ草はショウブのこととされる。セキショウ説やカキツバタ説もあるが、一般には、サトイモ科の植物、ショウブのこととされている。 ショウブの香には邪気を祓う力があると信じられていたよう。古代の人は香の強いものには邪気を祓う霊力があると考えていたようで、橘の実やヨモギなども同様である。 端午の節句には、麝香や沈香など香料や香草、薬草を袋に入れて、橘の実やショウブやヨモギで飾り付けをし、五色の糸を垂らした玉にして、これを身に付けるということをしたようです。今日、薬玉と言えば、祝い事やイベントなどの折の割玉のことを言うが、その原型はこの邪気祓いの薬玉なのである。 旧暦の5月と言えば梅雨に入る時期。暑気と湿気でものが腐敗しやすい季節である。病気になりやすい季節の入口ということで、この夏も無事に乗り切れますようにと、この薬玉を身に付けたり、ショウブを頭にかざしたりしたのである。粽を食べるというのも、茅(ち)で巻いたものを食べることで、茅の邪気を祓う霊力を身に取り込もうということであったのだろうから、同じ趣旨の行為である。 今のような近代医学というもののなかった時代にあっては、単なる習俗、儀式というのではなく、薬玉を身に付けたり、ショウブをかざしたり、粽を食べたりすることは、もっと切実な行為であったと言える。 ショウブは漢字では菖蒲でアヤメと同じ漢字であるのでややこしいが、アヤメとは別の植物である。 大伴家持は、他にもあやめ草の歌を詠んでいる。白玉を 包みて遣らば 菖蒲草 花橘に 合へも貫くがね (大伴家持 万葉集巻18-4102)(真珠を包んで贈ったら、菖蒲草や花橘に合わせて通して欲しい。)ほととぎす 今来鳴き始む あやめ草 かづらくまでに 離るる日あらめや (大伴家持 万葉集巻19-4175)(ほととぎすが、やっと来て鳴き始めた。菖蒲草をかづらとする5月5日まで、飛び去ってしまう日がどうしてあるものか。) 芭蕉さんもあやめ草の句を作っている。あやめ草足に結ん草鞋の緒 (松尾芭蕉 おくのほそ道) で、ショウブの写真は、とマイピクチャを探せど見当たらず。 鯉のぼりの写真でお茶を濁して置きましょう。(鯉のぼり)<参考>ショウブ・Wikipedia 本日は、端午の節句特集でありました。
2017.05.05
コメント(0)
-

岬麻呂旅便り203・青森
今日は、岬麻呂旅便りの記事です。 岬麻呂氏は4月24日~27日の3泊4日でご夫妻で青森を旅行されました。弘前城の桜と下北半島の仏が浦が旅の目的であったと書かれている「旅・岬巡り報告203」と「『旅・岬巡り報告203青森』写真説明」とが封入された封書が届いたのが5月2日。写真の方はPCメールで4月29日に送信下さっていましたので、封書が届き次第、記事にアップしようと思っていましたが、他の記事の予定もあって、今日のアップとなった次第。 同氏は毎年のように桜を追っかけて東北に出掛けて居られますが、今年は青森であったようです。旅の詳細は、例によって「ご本人に語らせよ」で、下掲の「旅・岬巡り報告203」をご参照下さい。(旅・岬報告203)※拡大画面はコチラをクリック下さい。 24日、青森空港到着後、レンタカーで先ず向かわれたのは弘前城。堀端の満開のソメイヨシノを堪能されたようです。最終日27日にも弘前城を再訪されていますので、写真はどちらの日のものかは存じ上げませぬが、そういうことはどちらであってもいいことではあります。(弘前城・天守閣)(弘前城・追手門) 下の鷹丘橋の写真が岬麻呂氏お気に入りのアングルだそうです。(弘前城・鷹丘橋) 斜陽館にも立ち寄られて、太宰治のことなども偲び、(斜陽館) その隣駅だという芦野公園駅では、 桜の花の下のローカル列車を撮影され、(芦野公園駅) 龍飛埼灯台経由、龍飛崎温泉泊り。 翌25日は、日の出を撮影せむと早起きして龍飛埼灯台へ。 多分、下の写真がその折のものなんでしょう。(竜飛埼灯台)(竜飛埼港の日の出) 下北半島、津軽海峡に昇る朝日であります。これが、津軽海峡朝景色なら、下は津軽海峡春景色です。(津軽海峡春景色) そして、その下北半島の中央部の仏が浦を観光船で楽しまれ、(下北半島・仏が浦)(同上) この日は本八戸駅前に宿泊。 南部郷土料理と地酒を楽しまれたとのこと。 26日は、雨にも遭遇されたようですが、銀輪ヤカモチと違って、四輪岬麻呂、雨と言っても何ほどのことはない。 南下したり、北上したりと走り回り、十和田市官庁街通りでは、このような見事な桜を見物されました。(十和田市官庁街通り)(十和田官庁街通りの桜・市役所展望台から) そして、春景色だけでは物足りぬとでも思われたか、雪の大谷状態の八甲田山笠松峠を経て、弘前城近くのホテルに宿泊。(八甲田山・笠松峠付近) 最終日の27日は、再度弘前城を散策の後、岩木山の北側にある津軽富士見湖の鶴の舞橋まで足をのばされました。 鶴橋というのはJR環状線にも駅があってお馴染みであるが、こちらは焼肉の匂いが舞うだけで、見るべきものはない。鶴の舞橋となると、このようにも優雅な景色となるのでありますな。(津軽富士見湖・鶴の舞橋) 咲き始める林檎の花や板柳町河川公園の桜を見て、青森空港から伊丹空港へ帰還。 青森県内650kmのドライブの旅を楽しんで来られた由。 この鶴の舞橋、銀輪で訪ねてみたいものであります。 以上、岬麻呂提供「津軽海峡春景色」の旅でありました。 <参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。
2017.05.04
コメント(2)
-

第190回智麻呂絵画展
第190回智麻呂絵画展 「ブログ開設10周年」記事に続いて、「阿倍野から堺へ」の銀輪散歩記事が3日間にわたった関係などもあって、智麻呂絵画展の記事アップが少し遅れていましたが、本日これを開催することとします。 前回が3月28日の開催でありましたので、1ヶ月を越える久々の智麻呂絵画展ということになります。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ 先ず最初はモクレンです。 今回出展の絵の中で、ヤカモチ館長が一番気に入っているのがこの絵です。とても存在感のあるモクレンであります。当絵画展にご来場下さるご常連様のお一人、新潟のふぁみり~キャンパーさん風に、ヤカモチ館長も「勝手選び」をさせていただいたという次第(笑)。 このモクレンはご友人の坂〇さんからの戴き物だそうです。(モクレン) 次は、桜です。関西では、もう桜は散ってしまっていますので、ちょっと季節に後れてしまった絵ということになりますが、当絵画展は全国ネットで提供して居りますので、北海道は札幌の桜ということにさせていただきましょう。(桜咲く野辺に) 花より団子、というお方のために、花見団子もご用意させていただきました。これは、智麻呂邸訪問に際して、ヤカモチが花見頃の時期とて、手土産代りにお持ちしたものであります。(お花見団子) 次の花はカンアヤメ(寒菖蒲)です。 ブロ友である、枚方のビッグジョンさんが3月16日の同氏ブログ記事に掲載されていた写真を印刷に打ち出してお届けしたところ、このような絵になったという次第。同氏の花の写真はこれまでにも何枚も絵にされています。 アヤメは智麻呂氏が特にお好きな花でありますので、ヤカモチの目論み通りの結果となったのでありました。 <参考>ビッグジョン氏のブログ記事:カンアヤメ 2017.3.16.(寒菖蒲) 次のシャガやスイセンもお好きな花です。(シャガ)(イトスイセンとオオキバナカタバミ) イトスイセンという珍しい水仙ですが、これはひろみの郎女さんがご自宅庭に咲いていたものを摘んでお持ち下さったものであります。(アイリスfrom友〇さん) これは、ご友人の友〇さんから頂戴したアイリスです。今回はアヤメ系統の花などお好きな花たちが並びました。 で、次の絵。「魚の干物ですか。」というヤカモチ館長の間抜けな問いに対する、恒郎女さんのご回答は、「これです。」と手に取って見せて下さった、魚の形をした文鎮だか置き物だかでありました。これは過去にも絵にされたことがありましたので、現物には見覚えがあり、そのことをスグに思い出しましたが、絵を見た瞬間は、てっきり干物の魚かと思った次第。(魚型の文鎮) 恒郎女さんは「これを絵に描き出すと、絵の題材が欠乏し出した証拠」と笑って居られましたが、花は色々とアトリエにありましたから、題材の枯渇ではなく、気分転換にこれを描かれたのではないか、というのがヤカモチ説であります。例によって、その辺の動機や思いについては、智麻呂さんは黙して語らず、なのであります。 確かに、その通り、絵の鑑賞や見て楽しむということに関して言えば、ヤカモチ館長が提供している、これら解説にもなっていない諸々の周辺情報は、全く無用のもの、蛇足に過ぎないのでありますから、絵の作者としては、そんな誘いには乗らない、ということであるようです(笑)。(鮎のお菓子と柏餅) この鮎と柏餠もヤカモチの手土産です。 丁度、今の季節の絵ですね。 実際の「鮎」のお菓子は、もっと細長くてスリムなのですが、智麻呂さんはこの鮎のお菓子については、決まって短く、ゆるキャラ風に描かれます。ヤカモチからすると「メダカ」に見えてしまうのですが、これは「鮎」なのです。 何か楽しくなる絵ではないでしょうか。 勿論、「メダカの」ではなかった、「アユの」お菓子も、三色の柏餅もご来場者へのおもてなしでありますれば、どうぞ、どなた様もご遠慮なくお召し上がり下さいませ。 以上です。本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。
2017.05.03
コメント(6)
-

阿倍野から堺へ(その3)
(承前) 4月28日の銀輪散歩では宿院交差点で右折し、旧堺燈台へと向かったのですが、同19日の銀輪散歩は開口神社から堺市役所へと向かいました。 すると堺市合同庁舎前に人だかりがあってブラスバンドの音楽。何事かと覗いてみたら、特殊詐欺・ひったくり被害防止キャンペーンの催しでありました。 最近は、こういう催し物にはゆるキャラマスコットの着ぐるみが付き物のようですね。(特殊詐欺・ひったくり被害防止キャンペーン) 堺市役所庁舎は、この堺市合同庁舎の隣にある。 21階展望室は無料開放。初めて上ってみた。 巨大な仁徳天皇陵がどんな感じで見えるものか試してみたかったのであるが、21階(94.6m)程度の高さでは、仁徳さんは横顔しか見せてくれませんでした。よって、この企画は失敗。あべのハルカスくらいの高さでないと仁徳陵は太刀打ちできないようです。 地図で見ると、市役所ビルのある位置から仁徳陵のこちら側外周までの距離は約900m、反対側外周までの距離は約1500m。ということは、仁徳陵のこちら側外周から反対側外周までの長さが600mであり、反対側外周から仁徳陵中央部までの長さは300mということになる。 で、市役所ビルの地点(A点)にビルの高さと同じ長さの縦線(垂線・高さ)を引き、市役所ビルから反対側外周地点(D点)まで横線を引いて直角三角形を描き、こちら側外周の地点(B点)に縦線(垂線)を1本引き、陵中央部の地点(C点)にもう1本縦線(垂線)を引くと、横線が1500m、600m、300mという相似形の直角三角形が三つできる。 A地点の市役所ビルの高さは、B地点、C地点では如何なる高さに相当するかが、この相似形三角形から算出できる。A地点での高さを100mとすると、B地点では100の15分の6で40mとなり、C地点では100の15分の3で20mとなる。 通常、御陵の中央部が一番高いと思われるので、中央部C地点での木々の高さ以上の高さがなければ、反対側外周までは見えないことになるところ、この場合はC地点での高さは20mであるから、中央部の墳丘や墳丘上の木々の高さよりも低いことになり、反対側外周部分やその部分の樹木は見えないこととなる。よって、100mの倍200m程度の高さが必要なのではないかと推量される。 現実の市役所ビルは21階建で高さは94.6m。展望ロビーからの見学者の視線の高さはそれよりも低くなるからせいぜい90m程度か。その結果が下の写真のような眺めという訳である。(堺市役所21階展望室から仁徳天皇陵を望む) 写真中央が仁徳天皇陵。大仙公園を挟んで右奥の小高い墳丘が履中天皇陵。左に見える線路は南海高野線である。奥には金剛・葛城の山並。南東方向の眺望である。(堺市役所21階展望室から西方向、堺港方面を望む) 上の写真は、西方向の眺め。中央に海が見えているが、其処にあるのが大浜公園と旧堺燈台である。この後、立ち寄ります。 子供の頃は大浜海水浴場で、海水浴もできたのであったが、今は埋め立てられてコンビナートになっている。(堺市役所21階展望室から北方向を望む) 北方向は「来た方向」でもある。中央奥にあべのハルカスがかすかに見えている。あの下から自転車で走って来たのかと思うとある種の感慨も。ハルカスに向かって一筋に延びている道が阿倍野筋である。堺市役所庁舎も阿倍野筋に面して建っているのでありました。 展望室には喫茶もある。マンゴーのパフェを注文。しかし、館内は禁煙であるから長居は無用。地上に戻り、阿倍野筋を北へと戻ったのが19日の銀輪コース。28日のそれは、冒頭でも述べた通り、市役所には向かわず、宿院交差点から西へ、つまり海側へと走り、大浜公園の先の旧堺燈台へと向かったのでありました。 旧堺燈台は1877年(明治10年)に完成、1968年(昭和43年)1月29日まで現役であった、木製洋式灯台で、我が国最古の木製洋式灯台の一つとして、国の史蹟に指定されているとのこと。(旧堺燈台)<参考>旧堺燈台・Wikipedia 上の写真の左隅にも写っていますが、男性が一人、海の方を眺めて居られました。何となく哀愁を漂わせて・・と見えたのは、海辺と後ろ姿の所為がなせるワザか。(同上・南側側面から)(同上)(堺港・旧堺燈台付近からの眺め) 灯台の写真を撮り終えて、男性を見やると未だ同じ姿勢のまま海を見て居られる。少し離れた処に、ママチャリが一台。前カゴにザックが乗っかっている。この男性のものだろう。近寄って声を掛けてみた。「なかなかいいところですね。」などと挨拶代わりの短い会話。「では、お先に失礼します。」と小生はMTBで大浜公園正面ゲートの方へと引き返す。 大浜公園へと渡る横断歩道で信号待ちをしていると、先程の男性が自転車で追いついて来られました。「やあ、・・」と笑顔の交換。信号が青になると「お先に」と今度は男性が先に行かれ、大浜公園の正面ゲートの前の道を南へと走り去って行かれました。(大浜公園・正面ゲート) 小生は、大浜公園の中を暫く走ってから、東へと戻り、千利休屋敷跡へと向かう。こちらへ来る前に、屋敷の前まで行ってみたのであったが、中学生の遠足か何かなんだろう。大勢の生徒がその前に列をなしていて入場待ちであった。これでは、写真に撮れそうもないと、先に灯台へと向かったのでありました。 今度は、団体さんの姿はなく二人連れの見学者が二組居るだけ。彼らの姿が入らぬよう角度をずらして撮影したのが下の写真です。(千利休屋敷跡) 中に入るとボランティアガイドの方が二人居られました。その方の説明では、下の写真の井戸があるのみで荒地になっていたのを、道の向かいの「さかい利晶の杜」という施設の建設に合わせて、裏千家がこれを買取り、今のように整備したのだそうな。(利休顕彰碑)(井戸) 19日の銀輪散歩では、さかい利晶の杜に入場してざっと見て回ったので、もう少し注意力があれば、屋敷跡に気が付いた筈なのだが、何処でだか見かけた略地図で、宿院交差点と宿院東交差点を取り違えたようで、東交差点の西側の宿院頓宮の近くにあると思い込んでしまったものだから、さかい利晶の杜を出ると脇目もふらず、フェニックス通りを東へと自転車を進めてしまったという次第。間違いは思い込みによって生じるでありました。(利晶の杜展示室:駿河屋)(利晶の杜展示室) 「さかい利晶の杜」は、1階が千利休に関連する展示室、2階が与謝野晶子に関連する展示室になっている。「さかい利晶の杜」については、下記<参考>をクリックしてご覧下さい。 <参考>さかい利晶の杜 さて、利休さんにお別れして、阪堺線の走る紀州街道に戻り、南へ。石津川畔までは2km余である。最後の目的地、石津太神社と太陽橋南詰の北畠顕家墓へと向かう。(石津太神社) 石津太神社に到着。鳥居前に「五色の石」の碑がありました。 これを写真に撮って居ると、背後から来られたのは、何んとあの旧堺燈台でお会いした男性。「また、お会いしましたね。」と笑い合う。男性はこの近くの何処かで何やらを買い物しての帰りなのだと仰っていましたが、それが何であるのかはよく聞き取れませんでした。小生が、東大阪の石切方面からやって来たのだということを知って、驚いて居られました。まあ、自転車族は別として、移動手段としての自転車の実用的距離というものを考えれば、常識を超えた阿呆な自転車の乗り方ということになるのでしょうな(笑)。 それにしても、3kmも離れた場所で偶々出会い、別れた人物と再び偶然に出会う確率とはどの程度のものであるのでしょう。(石津太神社鳥居前の五色の石の碑) この地下に五色の石が埋まっているそうな。 蛭子命がこの地に漂着し五色の神石を此処に置いたそうな。 石津という地名はこれに由来するとのこと。 この話は石津川を500m程度遡った処にある石津神社を訪ねた際に知った話でもある。石津神社と石津太神社は共に日本最古の戎神社であることを主張しているということも、その折のブログ記事(下記)で紹介しました。 <参考>銀輪万葉・池上曽根遺跡へ 2017.3.23.(石津太神社説明板) <参考>石津太神社・Wikipedia(石津太神社拝殿)(同上本殿) 石津太神社から紀州街道を更に南へ200mほど行った処が石津川で、其処に架かる橋が太陽橋。太陽橋を渡った処に北畠顕家の供養塔がありました。今一つの顕家墓である。北畠公園の墓然とした立派なものではないが、地元の人々に大事に守られているということが見て取れる墓である。(北畠顕家供養塔・石津川畔、太陽橋南詰)(同上説明碑) 大型ダンプか何かが当て逃げしたのだろうか、それとも誰か心ない人間が故意に壊したのだろうか。傍らの石漂が一部欠けてしまっている。加えて、中央にひび割れが生じている。「防犯カメラ作動中」という看板表示がそんな不埒なことも推量させるのであるが、興醒めの心地こそすれ、である。(同上) <参考>北畠顕家・Wikipedia 石津の戦い・Wikipedia(同上説明板) 以上で阿倍野から堺への銀輪散歩は完結です。帰途は中央環状道路に出て、瓜生堂東交差点経由で帰りましたので、阿倍野経由よりも少し遠回りしたことになります。 ―完― <参考>近隣散歩シリーズの過去記事はコチラから。 <ご注意> 当ブログ記事掲載の写真はフォト蔵に登録したマイピクチャを貼り付けて居ります。そのリンクがうまく作動せず、写真の一部が表示されない場合があります。この場合は、当該部分をクリックしていただくと、フォト蔵画面に切り替わって当該写真を見ることができます。また、記事画面を新しく開き直していただくと非表示の写真が表示された画面に切り替わることが確認されていますので、お試し下さい。(複数回画面更新をしないといけない場合もあります。)
2017.05.02
コメント(8)
-

阿倍野から堺へ(その2)
(承前) 昨日の記事・4月19日と同28日の阿倍野・堺銀輪散歩の記事の続きです。昨日の記事は帝塚山古墳を立ち去ったところで終わりましたので、そこから始めます。 帝塚山古墳から万代池を廻って阿倍野筋に戻りました。 万代池については、過去記事でも取り上げています。 <参考>大阪市南部銀輪散歩(3.安倍王子神社から住吉大社へ)2011.7.17.(万代池) この後は、暫く19日のコースと同じ道を走りますが、その前に北畠公園の北畠顕家墓に触れて置きます。19日の銀輪散歩ではアベノハルカスのビル前から大和川を渡るまでずっと阿倍野筋を南下しましたので、途中の北畠公園に立ち寄ったのでありました。今回の28日銀輪散歩は石津川畔の北畠顕家墓に立ち寄るのも目的の一つであってみれば、北畠公園の顕家墓の写真も掲載して置いた方がいいでしょう。 北畠公園・北畠顕家墓は、上の<参考>の過去記事でも紹介しているほか、下記の<参考>記事にも関連の写真と記述があります。 <参考>銀輪散歩・住吉公園まで 2011.10.17. 浜寺公園の万葉歌碑を訪ねて 2008.4.27.(北畠顕家墓)(同上) 以前に訪ねた時と鳥居の様子などが違っていますから、最近に整備されたのでしょうか。以前は無かったかと思う「別当鎮守府大将軍従二位権中納言兼右衛門督陸奥権守源朝臣顕家卿之墓」というものものしい名札が立てられていました。 さて、万代池から阿倍野筋に戻った地点に立ち返ります。そこは大阪府立病院とスーパーのライフが道を挟んで向かい合っています。更に南下、住吉区役所の先、南海高野線の踏切の手前でトトロに遭遇しました。(止止呂支比賣命神社) 道の向かい側の神社の標石の「止止呂」という文字からトトロと思ったのですが、よく見ると「止止呂支」でありました。トトロではなくトドロキヒメでありました。(同上・拝殿) 祭神は、素戔嗚尊と稲田姫尊とある。 スサノオが出雲でヤマタノオロチを退治することに決めたのは、稲田姫の美貌に心奪われて、彼女と結婚させて貰えるならということであったようだが、隣のトトロならぬ向かいのトトロはこの稲田姫(古事記ではクシナダヒメ<櫛名田比売>)のことであったのでした。(同上・由緒)<参考>止止呂支比賣命神社・Wikipedia そして、大和川に到着です。(大和川・遠里小野橋の上から) 写真は遠里小野橋の上から上流を望んだもの。見えている鉄橋は、先程踏切を渡って来た南海高野線の線路である。下流側には阪堺電軌阪堺線の鉄橋がある。一両だけの電車がその橋を渡って行く姿はちょっと面白い眺めであるが、それがやって来るのを待ってシャッターを切るというほどの執心はないので、先へと進む。 因みに、遠里小野は「おりおの」と読む。万葉歌にも登場する地名であるが、万葉では「とほさとをの」である。万葉の頃は訓読みであったのが後世に音読みで呼ぶようになり、「おんりおの→おりおの」となったものだろう。住吉の 遠里小野の 真榛もち すれる衣の 盛り過ぎ行く (万葉集巻7-1156)住吉之 遠里小野之 真榛以 須礼流衣乃 盛過去すみのえの とほさとをのの まはりもち すれるころもの さかりすぎゆく(住吉の遠里小野の榛で摺り染めにした衣の、美しい色が褪せて行くことよ。)(注)真榛=「ま」は美称。榛はハンノキ。落 葉高木。実と樹皮が黒色染料にな った。煎汁に浸け染めにした。 実を蒸し焼きにして黒灰色の染料 を作り、摺り染めにもしたとのこ と。 遠里小野町は大和川を挟んで大阪市住吉区側と堺市側とにある。堺市側の遠里小野町の南隣が砂道町。砂道交差点で右折し西へ。南海本線七道駅前で内川につながる水路沿いの遊歩道に入る。桜並木の下のベンチで休憩しながら煙草をくゆらせていると、2~3歳位の小さな女の子を連れた若いお母さんが自転車を押しながらやって来られた。そのまま通り過ぎようとされていたようだが、女の子の方がママを引き止めて水辺の方に行こうとする。 ママも仕方なく自転車を停めて、水辺へ。小生のベンチの前の水辺で何やら楽しげな会話。思わずカメラを向けていました。後ろ姿なら問題なかろうと掲載することとします(笑)。 (内川沿いの緑地の若いお母さんと幼児) 内川沿いに行くと公園に出ました。ザビエル公園とも通称される戎公園である。この公園は堺の豪商・日比屋了慶の屋敷跡地である。聖フランシスコ・ザビエルが堺に上陸した時、日比屋了慶の屋敷で歓待を受けたという。(ザビエル公園)(同上・案内板)<参考>ザビエル公園・Wikipedia (左:聖フランシスコ・ザビエル芳躅碑、右:堺鉄砲之碑) ザビエル公園入口の案内板で見ると、小西行長の屋敷跡が近くにあるようなので、公園前の広い通り(紀州街道)を少し北へと戻る。(小西行長屋敷跡碑)<参考>小西行長・Wikipedia 小西行長屋敷跡の碑は阪堺線の妙国寺駅と神明町駅の中間にある。 路面を走る阪堺線が通るこの広い道の東側歩道部分が旧紀州街道である。従って、行長の屋敷は、現在歩道となっている紀州街道に面して、現在車道となっている西側に向けて、おそらくは反対側歩道も含む広い領域に跨っていたのであろう。 線路に沿ってツツジの花が盛りと咲いて美しい景観を醸している。下掲の写真は神明町駅に停車中の阪堺線の電車であるが、パンダをモチーフにした車両になっていました。(小西行長屋敷跡碑付近から北方向の眺め・紀州街道) ザビエル公園から300mばかり南に下ると道路西側の歩道上に与謝野晶子生家跡の碑がある。これは以前にも目にしているがブログには未掲載なので写真を掲載して置くこととします。 こちらの写真は、行長屋敷跡碑のあった歩道(つまり、旧紀州街道)とは反対側の西側歩道で撮影したもの。晶子の生家、駿河屋は反対側歩道の紀州街道に面して道を跨って建っていたとのことであるから、このアングルは言わば家の裏側から生家を眺めていることになるという次第。(与謝野晶子生家跡の碑) 碑に刻まれた歌は、海こひし潮の遠鳴りかぞへつゝ 少女となりし父母の家というもの。(同上)<参考>与謝野晶子・Wikipedia(駿河屋<復元>「さかい利晶の杜」ホームページより転載) 与謝野晶子の歌碑は、鳥取砂丘でも新潟県の瀬波や粟島でも、また富山県の高岡古城公園や浜名湖を望む浜松市の気賀でも見かけたと記憶するが、銀輪散歩でよく出会う歌碑でもある。それだけ人気のある歌人ということであるのだろう。 その晶子の出身地である堺市であるから、晶子の歌碑が多いのも当然。宿院頓宮を経由して、その晶子の歌碑がある開口神社へと向かうこととする。(宿院頓宮) 宿院頓宮は、住吉大社の祭神と大鳥大社の祭神を祀っているとのこと。両大社の勢力圏の境目をなす神社の様相である(笑)。 まあ、堺そのものが、摂津・河内・和泉の三国が境を接する地ということで「サカヒ」なのであってみれば、宿院頓宮の祭神の在り様も亦いかにも堺的であると言うべきものではある。 大鳥大社の祭神の大鳥連祖神というのは天児屋根命のことであるから、わが里の枚岡神社の神様でもあるということで、素通りもいかがなものかと、一応ご挨拶を申し上げたまでという次第。 (同上・説明碑)<参考>宿院頓宮・Wikipedia ※写真をクリックすると大きいサイズの写真になります。 宿院東交差点から北へ行くと開口神社がある 開口は「あぐち」と読む。 (開口神社・鳥居) (同左・拝殿)(同上・拝殿と鯉のぼり) 開口神社では鯉のぼりが泳いでいました。写真では分かりにくいのですが、堺の鯉のぼりの真鯉の背中には金太郎が跨っています。それに少しずんぐりむっくりの太目タイプなのが堺の鯉のぼりの特長だそうです。(同上・由緒)<参考>開口神社・Wikipedia そして、開口神社境内の晶子歌碑がこれです。少女たち 開口の神の 樟の木の 若枝さすごと のびて行けかし(与謝野晶子歌碑・開口神社境内)<参考>与謝野晶子の歌碑、堺で除幕式:朝日新聞デジタル 晶子の歌碑の隣には、泉陽高校発祥之地碑があり、境内の西鳥居前には三国ヶ丘高校発祥之地碑がありました。 そう言えば、わが母校の八尾高校には発祥地之碑なるものがあるのだろうか。八尾高校の前身、大阪府立第三尋常中学校は八尾市本町4丁目にある真宗大谷派別院大信寺内の対面所を仮校舎として出発しているから、其処が発祥の地ということになるのだろうが、そのような碑のことは耳にしたことがないから、存在しないということであるのだろう。 (泉陽高校発祥之地碑) (三国丘高校発祥之地碑) この後、堺市役所庁舎の21階展望室に昇りますが、それは明日以降のこととし、本日はここまでとします。(つづく)
2017.05.01
コメント(4)
全16件 (16件中 1-16件目)
1