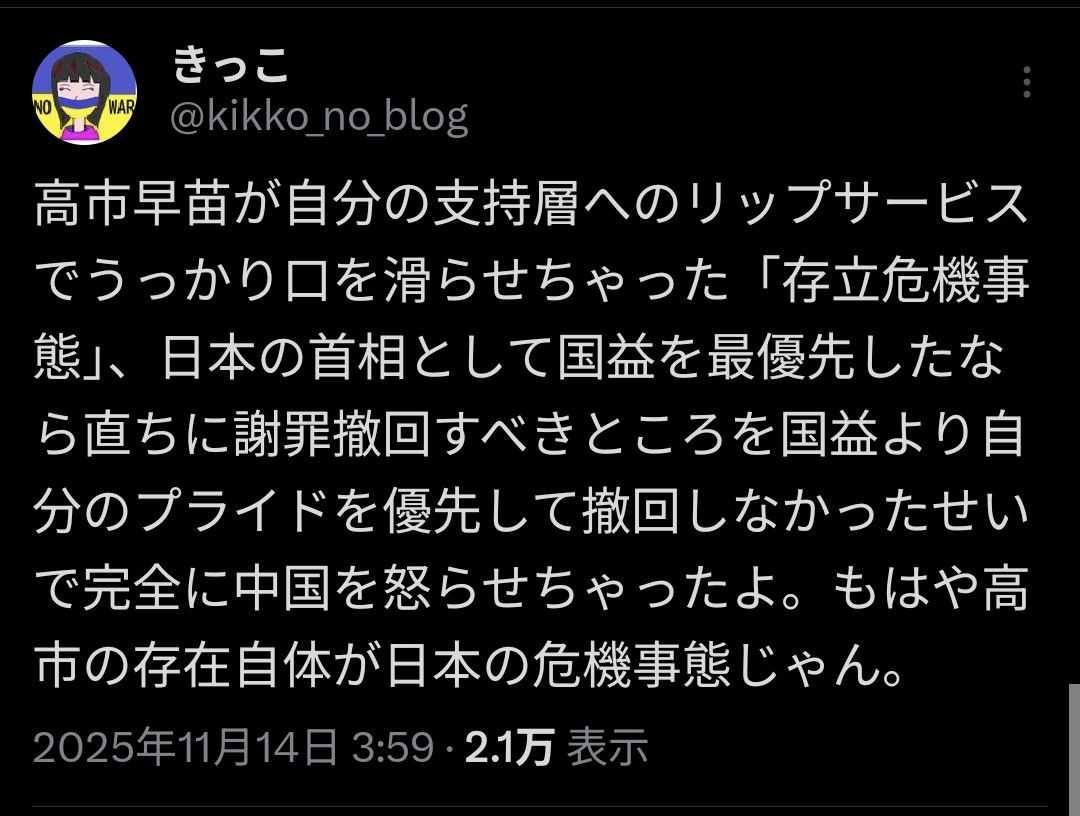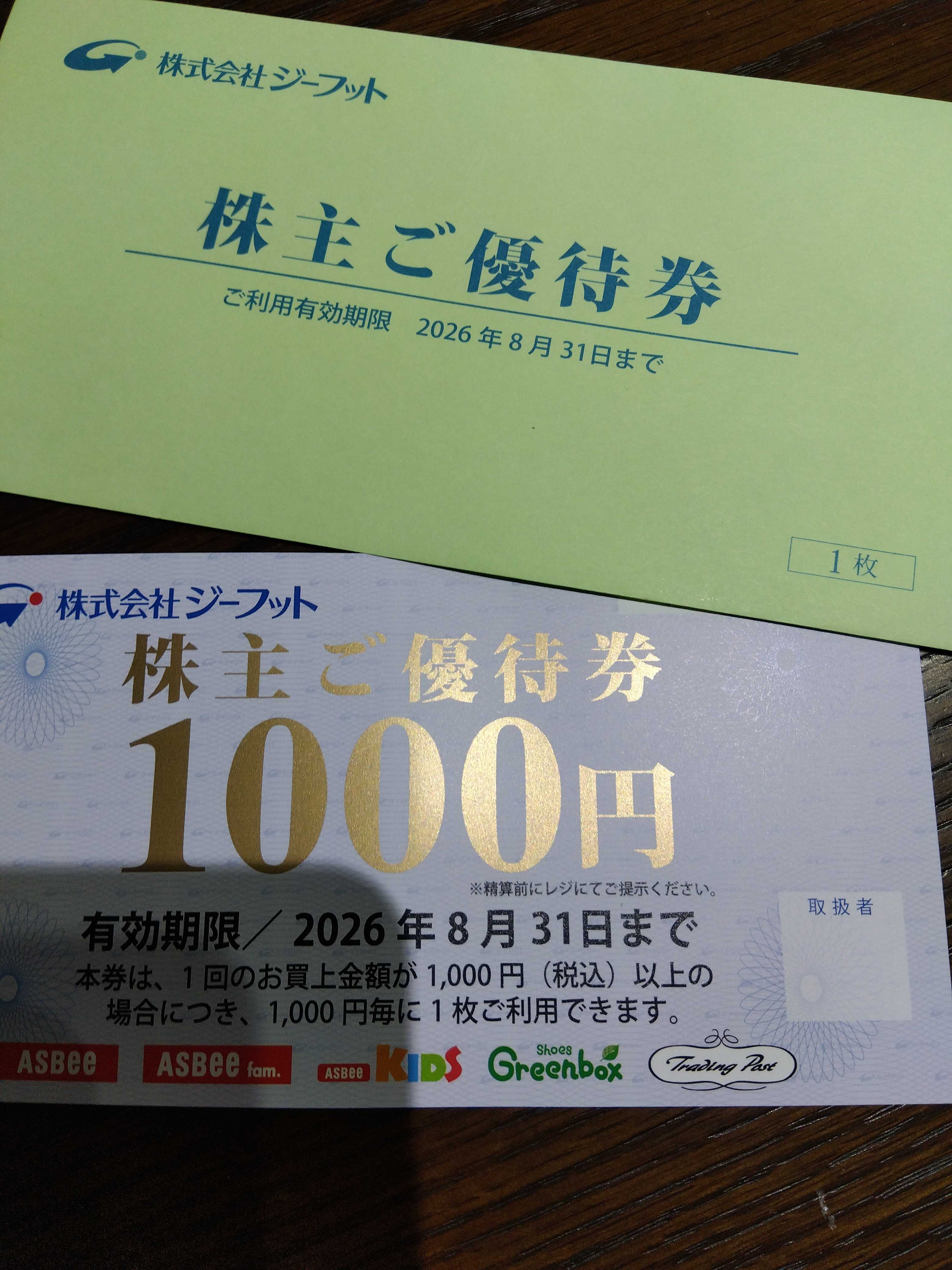2017年08月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

奈良少年刑務所、奈良豆比古神社、夕日地蔵
(承前) 29日の銀輪散歩の続きです。 北山十八間戸の見学を終えて、三角屋さんのお店の前に駐輪していたトレンクルのロックを開錠していると、店の前まで出て来られた吉備郎女さんが、奈良少年刑務所も廃止になったが、表から建物を見ることが出来るから見て行け、と仰る。で、既に何度も見てはいるが、ブログには掲載していないので、ともかくもと坂道を上って刑務所へ。<参考>奈良少年刑務所・Wikipedia※以下の掲載写真の特大サイズ画面はフォト蔵の画面でご覧いただくものでありますが、フォト蔵がメンテナンス中の場合やデータ障害などのトラブルを生じている場合はご覧いただけないこともありますので、ご了承下さい。(奈良少年刑務所)特大サイズ画面はコチラ 2020年を目途に、内部が改装されてホテルに生まれ変わるそうだが、 そうなれば、この鉄の門扉も開いたままとなり、自由に誰でも出入り出来るようになるのでしょう。(同上)特大サイズ画面はコチラ 奈良少年刑務所から、般若寺に出て、奈良坂を更に北へ500mほど行くと奈良豆比古神社である。 (奈良豆比古神社)特大サイズ画面はコチラ<参考>奈良豆比古神社・Wikipedia(同上・鳥居脇の説明碑)(同上・祭神)特大サイズ画面はコチラ<参考>志貴皇子・Wikipedia 春日王・Wikipedia 志貴皇子は天智天皇の息子、光仁天皇の父親、桓武天皇の祖父ということになるが、万葉集に秀歌を残す万葉歌人でもある。また、その志貴皇子の息子である春日王も1首万葉集に歌をとどめている。この二人が祭神とあっては、偐万葉の銀輪散歩としては近くを通りかかったからには是非にも立ち寄らねばならぬ神社ということになる。 では、志貴皇子の歌6首と春日王の歌1首を掲載して置くこととします。<志貴皇子の歌> 采女(うねめ)の 袖吹きかへす 明日香風 京(みやこ)を遠み いたづらに吹く (巻1-51)(采女の袖を吹き返す筈の明日香の風は、都が遠くなってしまったので空しく吹いている。)葦辺行く 鴨の羽がひに 霜降りて 寒き夕(ゆふへ)は 大和し思ほゆ (巻1-64)(葦辺を行く鴨の翼の重なる処に霜が降って、このように寒い夕べは大和のことが思われる。) むささびは 木末(こぬれ)求むと あしひきの 山の猟夫(さつを)に あひにけるかも (巻3-267)(ムササビは高い木の梢に登ろうとして、山の猟師に出くわしてしまったのだなあ。) 大原の このいち柴の いつしかと 我が思(も)ふ妹に 今夜(こよひ)逢へるかも (巻4-513)(大原のこのいち柴の名の如く、いつになったら逢えるのかと思っていた妻に、今夜は逢えたのだ。) 石(いは)ばしる 垂水の上の さわらびの 萌え出づる春に なりにけるかも (巻8-1418)(岩の上に流れ落ちる滝の傍らの蕨が芽を出す春になったのだなあ。) 神奈備(かむなび)の 磐瀬(いはせ)の杜(もり)の ほととぎす 毛無(けなし)の岡に いつか来鳴(きな)かむ (巻8-1466)(神奈備の磐瀬の杜のホトトギスは、毛無の岡にはいつになったら来て鳴くのだろう。) <春日王の歌>あしひきの 山橘の 色に出でよ 語らひ継ぎて 逢ふこともあらむ (巻4-669)(山橘の実のようにはっきりと色に出しなさい。そうすれば人々が語り伝えて逢う機会もあるでしょう。) (注)万葉集にはもう1首春日王の歌があるが、これは持統天皇の吉野行幸に付き従った折の弓削皇子の歌に和して春日王が詠んだ歌であり、時代が合わないので、別人の春日王と考えられている。滝の上の 三船の山に 居る雲の 常にあらむと 我が思はなくに (弓削皇子 巻3-242)(吉野川の急流の上の、三船山にかかっている雲のように、いつまでもこの世にあろうとは私は思っていないのだけれど。) 大君は 千歳にまさむ 白雲も 三船の山に 絶ゆる日あらめや (春日王 巻3-243) (大君は千年もすこやかにいらっしゃることでしょう。あの白雲も三船の山に絶える日がありましょうか。) (同上・本殿)特大サイズ画面はコチラ 今月14日に妹たちと、志貴皇子の山荘であったとされる白毫寺を訪ねたばかりであるから、今回、このように志貴皇子を祀る神社へと足が向いたのは、それと無関係ではないかも知れない。(同上)特大サイズ画面はコチラ 中央の本殿が平城津彦(この地の神様)、左殿(向かって右側)が志貴皇子、右殿(向かって左側)が春日王を祀る。(翁舞説明板)特大サイズ画面はコチラ 奈良豆比古神社から更に行って奈良自転車道に入り、磐媛陵などを経由して平城宮趾へと戻ることも考えられたが、昼食が未だであったので、奈良市街へと引き返すこととする。北山十八間戸の手前の夕日地蔵にご挨拶申し上げて、近鉄奈良駅方面へと走る。(夕日地蔵)特大サイズ画面はコチラ 夕日地蔵の傍らには木製の会津八一歌碑がありました。ならざかの いしのほとけの おとがひに こさめながるる はるはきにけり 偐家持も和して2首であります。ならざかの いしのほとけに あはむとて あせながしつつ われはきにけりならざかの いしのほとけは かはらねど きなるやいちの かひはあせける(会津八一歌碑)特大サイズ画面はコチラ これと言った店が目にとまらぬままに走っていると、近鉄奈良駅前は通過、いつの間にやらJR奈良駅前に。銀輪散歩の場合の店選択の基準は、自転車を駐輪するに適当な場所が店先にあること。次に、余り混んでいたりしないこと。 で、結局、新大宮駅近くままで来てしまい、余りはやっていそうでもない店のドアにOPENの表示があったので入ってみた。店の前に駐輪できる場所もある。パスタランチと昼のメニューが一つなのもいい。何にするか迷わなくていい(笑)。 少し遅めの昼食を済ませて店を出ると近鉄新大宮駅の前に出た。では帰るかとトレンクルをたたみ専用バッグに収納し、帰途に。急行が来た。乗る。わが最寄り駅は急行は停まらないので手前の石切駅で各駅に乗り換えないといけない。石切駅に到着。気が変ってこの駅から自転車で帰ることにする。石切駅前の道路脇でトレンクルを取り出し、組み立てて再びトレンクルの人に。 途中、東石切公園に立ち寄り木陰で涼む。そよ吹く風に吹かれながら、水分補給、煙草一服。公園の時計はまだ2時半にもなっていない。帰宅するには少し早過ぎるか。では、ペリカンの家にでも行って珈琲休憩にするかと、道を下る。ほぼ下り切った場所に喫茶・ペリカンの家はある。先客は二組。女主人のももの郎女さんと雑談。途中、越の郎女さんも立ち寄られました。その雑談の中でこの日走ったコースの途中にあった奈良育英高校がももの郎女さんの母校であったことを知ったのも愉快なことでありました。 というようなことで、叡尊墓及び北山十八間戸ほかのこの日の銀輪散歩は終了です。<関連過去記事>(志貴皇子関連)〇奈良銀輪散歩(その1) 2009.5.19.〇奈良銀輪散歩(その2) 2009.5.20.〇降る雪はあはにな降りそ・・ 2011.12.25.〇古事記撰上1300年銀輪散歩・頭塔から田原の里へ 2012.2.28.〇退院・墓参・燈花会 2017.8.15.(奈良自転車道関連)〇奈良自転車道銀輪散歩(平城京址公園から般若寺へ) 2010.3.10.〇奈良銀輪散歩 2010.11.7.
2017.08.30
コメント(8)
-

叡尊墓と北山十八間戸へ
本日(8月29日)は西大寺別院・体性院にある叡尊墓と奈良坂・般若寺の手前にある北山十八間戸を銀輪散歩して参りましたので、久々のブログ記事アップであります。 従来、ブログ掲載写真はフォト蔵に登録し、これをブログ記事に貼り付けるということをして居りましたが、今回から直接PCからのアップとしました。フォト蔵の度々のトラブルに嫌気がさしての変更です。ただ、過去のブログ写真はここ数年全てフォト蔵に登録してそのアルバム管理をしている関係で、フォト蔵への写真登録は今後共継続する予定ではあります。 まだ、直接のアップは、写真をダウンサイジングしなければならないなどの面倒もあって、長らくこのやり方をしていなかったもので、些か不慣れと言うか勝手が違って、少し戸惑って居ります。では、本論に入ります。 今回、叡尊の墓を訪ねようと思い立ったのは、先月28日に生駒市の竹林寺にある忍性墓を訪ねたことによるものです。忍性さんは叡尊さんの弟子ですから、そのお師匠さんのお墓にもご挨拶申し上げるべきかと思った次第(笑)。<参考>竹林寺・行基墓&忍性墓 2017.7.29. もっと、早くに訪ねる心算でしたが、トレンクルの入院治療やヤカモチのギックリ腰など、色々の差し障りが生じて、今日になってしまったのでありました。トレンクルを持って、近鉄西大寺駅下車。駅南口でトレンクルを組立て、銀輪散歩出発であります。 さて、叡尊墓のある体性院は西大寺の北側の道を西に数百メートル行くとある。途中に小さな神社があった。野神神社とある。(野神神社)特大サイズ画面はコチラ 境内を見て道路側へ戻って来るとジョギングの途中であるか、小生の方に向いて立っている男性と顔が合う。年齢は小生よりもかなり上のように見えたが、実年齢は定かではない。「顔が合った」と言ったが、上の写真で言うと、小生は社殿を背にこちらを向いて真っ直ぐに歩いて来る、道路側の男性は階段の下、中央に立って、社殿の方を向いているのだから、これは嫌でも顔が合うというものである。こういう場合声を掛けないのは気づまりであるから、「こんにちは、ジョッギングですか。」と話しかける。少しばかり立ち話。別院がこの先にあるがもう行かれたか、と男性。いえ、これから行くところです、と小生。 少し行くと小さな公園があった。野神緑地公園である。この公園に沿って坂道を上ると直ぐに目指す体性院である。(野神緑地・鋳物師池跡)特大サイズ画面はコチラ この地は奈良時代の鋳物工房跡が発掘されたとのこと。西大寺の草創時に係る金銅四天王像がこの地で鋳造されたという言い伝えがあるらしい。(同上)特大サイズ画面はコチラ(西大寺別院・体性院)特大サイズ画面はコチラ 西大寺別院・体性院に到着。 小さなお堂が二棟あるばかりで、アトは墓石があるのみ。その所為でか、それほど広くもない境内であるが、広々とした感じがあって何やらすがしき気分である。ひと際大きいこの五輪塔が叡尊の墓であろう。(同上・叡尊墓) 特大サイズ画面はコチラ(同上・境内西側の高みから叡尊墓を望む)特大サイズ画面はコチラ 境内東側にも、叡尊のそれほどには大きくはないが、立派な五輪塔が三基ある。西大寺所縁の高僧のお墓なんだろう。(境内の南東隅からの眺め)特大サイズ画面はコチラ(お堂)特大サイズ画面はコチラ 境内西側にも一般のお墓に混じって、立派な五輪塔が三基ありました。(お堂の西側の墓地)特大サイズ画面はコチラ<参考>叡尊・Wikipedia 体性院から西大寺駅へと引き返す。近鉄線(橿原線)の下を潜って、秋篠川を渡り、平城宮趾公園へ。(秋篠川)特大サイズ画面はコチラ 平城宮趾公園も久しぶりである。大極殿に挨拶をして行く。現在は回廊と大極殿南門などの復原工事に着手すべしで、その準備中である。傍らに第一次大極殿復原事業情報館がある。建物入口まで行くと、中から案内の男性が「どうぞ、どうぞ。」とドアを開けて招じ入れられてしまった。復原事業の紹介映画が始まるので見て行け、と仰る。(平城宮趾・大極殿)特大サイズ画面はコチラ こちらも急ぐ必要は無いので、ならばとお誘いに乗ることとする。丁度、冷房の効いた館内で休憩するのも悪くはない、という訳である。客は我のほか誰とても無かりき、で一人きりで映画を見させていただく。平城宮散策マップなども頂戴するが、行く先は奈良坂の北山十八間戸であるから、此処は単に横切るだけなのでありました。(同上・内裏の池)(同上・説明碑)特大サイズ画面はコチラ 平城宮趾から一条通りを東へ。佐保小学校、奈良育英高校の前を通り、500mほど先の聖武天皇陵の前で、一条通りにお別れし、佐保川沿いの細道を行く。しかし、この道は直ぐに佐保川の岸辺から離れてしまい、住宅街の中をジグザグに行くこととなったので、一条通りをそのまま東に直進して転害門前で左折という方が近道であったかも知れない。今在家交差点で奈良県庁から北へと延びて来る国道369号に出る。佐保川に架かる石橋を渡り、奈良坂、(旧)奈良少年刑務所、般若寺への坂道へと取り掛かる。(奈良市水道計量番室)特大サイズ画面はコチラ 直進すると(旧)奈良少年刑務所 であるが、坂の途中、右に入る道、即ち般若寺への道に、確かブロ友のひろみちゃん8021さんがブログで紹介されていた建造物ではなかったかと記憶するが、こんなのがありました。これと向き合ってあるのが三角屋というお好み焼き屋さん。このお好み焼き屋さんの裏手が「史蹟・北山十八間戸」なのである。この三角屋さんが奈良県から委嘱を受けて、施設建物の管理をなさっているのである。本来は、事前に電話で連絡し、三角屋さんの方で他用で手が放せないなどの不都合がなければ、敷地内に入れて貰えるというものであるのだが、駄目元承知で、事前連絡なしで行ってみた。 店はやっている気配ではなかったが表の戸は開いた。「こんにちは」と奥に声を掛けると、女主人と見られるご婦人が出て来られた。「お店は今日は定休日ですか。」と申し上げると、「お昼はやっていないのです。かき氷だったらできるけれど。」と仰る。小生としては、ここで昼食とし、その流れで施設の見学をさせていただこうという魂胆であったので、かき氷でも何でも取っ掛かりができればいいのであるから、「はい、氷をいただきます。」と答える。(お好み焼き・三角屋 TEL:0742ー22ー2594)特大サイズ画面はコチラ 女主人は広島か岡山か中国地方の訛りがあったので、「こちらの方ではないですね。広島あたりのご出身ですか。」と聞いてみた。「なんで、分かるの?」「いや、言葉に広島方面の訛りがありますから・・」「もう、こちらに来て35年以上になるのに、育った土地の言葉は抜けんのじゃねえ。」とか、叡尊墓を訪ねた後、西大寺から自転車でやって来たことなどを話し、裏の建物を見せていただけるか、と切り出してみた。 「ああ、いいですよ。」と気安く応諾いただけました。原則は、事前に連絡して貰わないと、留守にしていることなどもあるので、と仰っていましたが。 因みに女主人は岡山のご出身とのことでした。従って、吉備郎女さんということになる(笑)。(北山十八間戸説明板)特大サイズ画面はコチラ その吉備郎女さんは、建物の鍵を開けながら、今年が忍性生誕800年の年であることや、映画「忍性 NINNSHO」の撮影も此処で行われたことなどを説明下さいました。<参考>忍性・Wikipedia(同上・石碑)特大サイズ画面はコチラ 鎌倉時代に、叡尊や忍性らの僧によってハンセン病患者救済事業が既に行われていたというのは凄いことだし、記憶されるべき素晴らしいことである。<参考>北山十八間戸・Wikipedia(同上・敷地内側からの建物外観)特大サイズ画面はコチラ(同上・建物内部)特大サイズ画面はコチラ(同上)(同上・説明碑)特大サイズ画面はコチラ(同上・道路側からの建物外観)特大サイズ画面はコチラ 吉備郎女さんにお礼を申し上げて北山十八間戸を後にし、近辺を少し銀輪散歩しましたが、これらについては、ページを改めることとします。(つづく)
2017.08.29
コメント(4)
-

河内寺廃寺跡
国史蹟・河内寺廃寺跡の整備工事が完了したようです。 昨年12月28日の記事で紹介した河内寺廃寺跡の整備工事がいつの間にか完成していました。<参考>墓参・ロウバイ、ムクロジ、河内寺廃寺跡 2016.12.28. 写真は8月15日朝に撮影しましたが、ブログ記事にせぬままにいました。この日15日の記事は、と遡って見ると、愛車トレンクル君の退院他の記事でありました。馴染みの自転車屋さんから修理が完了したとの連絡を受け、この日の朝トレンクルを受け取りに出向き、その帰途にこの河内寺廃寺跡に立ち寄り撮影したのでありました。何れ記事にすることもあるかと、フォト蔵に写真を登録して置きましたが、その後他のテーマで記事をアップしたこともあってか、すっかりそのことを忘れてしまっていました。 この15日の昼食後、立ち上がろうとした瞬間に、腰の背面左側に何やら違和感を感じました。立ち上がって歩こうとすると、その部分にかなり強い痛みが走って、よろよろと何とも情けない姿の歩き方。これではお爺さんみたいだ、と言うと、妻から「もう十分お爺さんだわよ。」と言われて、それもそうだと納得したりもしましたが、或は、この腰痛に気が取られて、忘れてしまったということであったのかも知れません(笑)。 腰痛の方は、いわゆるギックリ腰としては軽度なものであったようで、21日頃からは左程に痛みも感じなくなっていました。それでという訳でもないのでしょうが、昨日22日にこの河内寺廃寺跡の写真のことを思い出し、これを記事にするかとPCに向かいましたが、何んと今度はフォト蔵が何かトラブルが発生したのかメンテナンス中で、アクセスが出来ない。で、本日23日の朝にあらためて記事にしようとPCに向かったのでしたが、フォト蔵にはアクセスできたものの、登録のわが写真はアチコチで「NO PHOTO」の表示になっていて、当該写真が表示できない状態。河内寺廃寺跡の写真も全10枚中4枚が「NO PHOTO」状態。フォト蔵さんは最近どうもトラブルが多いようです。突然のメンテがよくあり、それが正常に復するのにも随分の時間がかかるということが頻発している。小生のようにブログ写真はその殆どをフォト蔵に登録した上で記事写真としてこれを掲載している者にとっては、もう少ししっかりしたスピーデイな対応をして戴かないと困るというものである。 NO PHOTOとあるものをブログに貼るのは何とも心許ない気分であるが、フォト蔵のメンテ処理が適正に完了したなら、写真が正しく表示されるものと信じて、取り敢えず貼って置きます。メンテ中のものを貼り付けてもダメで、あらためてメンテ完了後のものを貼り付けないと正しくは表示されないということであるなら、追って、貼りなおしますので、暫くお待ち下さい(笑)。久々にブログ書かむとわれすれど フォト蔵メンテは興醒めなりき (偐家持)<追記:2017年8月24日午後10時58分> フォト蔵のトラブルによる一部の写真が表示されない不都合の解消は、今の処いつになるか分からないようです。長期化すると見込まれるので、再度写真をアップロードして下さい、という非現実的なことをフォト蔵さんは言って居りますが、小生の場合は、フォト蔵にアップした写真は、自身のPCからは全て削除しているので、この対応は不可能です。 仮にPCの画像が残っているとしても、非表示になっている写真の数は膨大な量であるし、ブログに貼り付けているのであるから、新しく元の写真をアップしてもそれは記事の写真には反映されない。新しくアップした写真に差し替えるべく過去記事の編集を行わなければならないことになる。そんなことは土台無理なこと。 ということで、過去の記事も含めて、フォト蔵の方でデータの復旧が行われるまでは、かなりの写真が非表示になっていると思われます。ご訪問戴いた皆さまにはまことに申し訳ありませんが、復旧作業が完了するまでは、この不愉快な状況が続きます。どうぞ、悪しからずご了承下さいませ。これは、楽天ブログの不手際でも、管理者けん家持の怠慢でもありませんので、念のため申し添えて置きます。今後の記事への写真掲載は別の方法で行うことといたします。<追記:2017.9.22.>2017年8月22日のフォト蔵メンテ作業中の誤操作によって発生したデータ障害により表示されなくなってしまった写真の復旧作業は、現在も進行中にて、未だ完全復旧とはなっていないようですが、本ページ掲載の写真に限っては、全て復旧したようです。(河内寺廃寺跡・全景)(河内寺廃寺・伽藍配置復元図)(河内寺廃寺跡説明板)(河内寺廃寺復元イメージ)(河内寺廃寺跡・金堂跡)(同上・説明板)(河内寺廃寺跡・講堂跡)(同上・説明板)(河内寺廃寺跡・回廊跡)(同上・説明板)
2017.08.23
コメント(6)
-

新古今集の大伴家持の歌
新古今集に大伴家持の歌として掲載されているものは全部で12首ある。また、「よみ人知らず」とされているが万葉集の方で大伴家持の歌となっているものが1首あるので、これを合わせると13首ということになる。しかし、うち2首は、万葉集では、ひとつは柿本人麻呂歌集の歌となって居り、もうひとつは大伴像見(かたみ)の歌となっているので、正確には11首ということになる。尤も、万葉集に登場しない歌は果たして大伴家持作の歌であるのか極めて怪しいのであるが、一応、新古今集の顔を立てて大伴家持さんの歌ということにして置きます。 いずれにせよ、当ブログは偐万葉田舎家持歌集であるから、大伴家持の歌でないものも大伴家持の歌として掲載しても一向に差し支えないということにはなるのである(笑)。ということで、その13首を書き出して置くことといたします。(注) 新古今集の歌は太字表記です。 岩波文庫「新訂新古今和歌集」よりの抜粋です。 万葉集に元歌があるものは、参考までにそれを併記しました。 現代語訳は小生が適宜に付けたもので、正確性は保証しません。 新古今と万葉の双方の歌の意味が同じものは、現代語訳は両歌兼用としました。まきもくの檜原のいまだくもらねば小松が原にあわ雪ぞ降る(巻1-20)(巻向の桧原はまだ曇ってもいないのに、ここ小松が原には淡雪が降っている。)巻向の檜原もいまだ雲居ねば小松が末(うれ)ゆ沫雪(あはゆき)流る(柿本人麻呂歌集 万葉集巻10-2314)(巻向の桧原はまだ雲もかかっていないのに、松の梢からあわ雪が流れるように降って来る。)(桧原社)行かむ人来む人しのべ春がすみ立田の山のはつざくら花(巻1-85)(往く人も来る人もみな思いえがきなさい、春霞が立つ、立田の山の初桜の花を。)ふるさとに花はちりつつみよしののやまのさくらはまださかずけり(巻2-110)(わが里の花は散りつつあるのに、吉野の桜はまだ咲かないでいる。)からびとの舟を浮べて遊ぶてふ今日ぞわがせこ花かづらせよ(巻2-151)(唐の人々が舟を浮かべて遊ぶという今日、皆さんも花かずらをお付けなさい。)漢人(からひと)も筏浮かべて遊ぶといふ今日こそわが背子花かづらせな (大伴家持 万葉集巻19-4153)(唐の人々も筏を浮かべて遊ぶという今日こそ、皆さんも花かずらをお付けなさい。)郭公一こゑ鳴きていぬる夜はいかでか人のいをやすくぬる(巻3-195)(ホトトギスが一声鳴いて飛び去って行った夜は、人はどうして安らかに眠られようか。)神なびのみむろの山の葛かづらうら吹きかへす秋は来にけり(巻4-285)(甘南備の三室山の葛の葉をうらさびしく風が吹き返す秋がやって来たことだ。)(注)万葉で「みむろ・みもろ」の山と言えば三輪山であるが、新古今では立田の三室山のことと考えられるので、三室山としました。みむろ、みもろは神のいます処という意味で、カンナビと同じ意味である。 (三室山)さを鹿の朝立つ野邊の秋萩に玉と見るまで置けるしらつゆ(巻4-334)さを鹿の朝立つ野邊の秋萩に玉と見るまでおける白露(大伴家持 万葉集巻8-1598)(牡鹿が朝に立つ野辺の秋萩に、玉かと見まがうばかりに置いている白露だ)今よりは秋風寒くなりぬべしいかでかひとり長き夜を寝む(巻5-457)(今からは秋風が寒くなるだろう。どのようにして一人で長い夜を寝ようか。)今よりは秋風寒く吹きなむをいかにかひとり長き夜を寝む(大伴家持 万葉集巻3-463)(今からは秋風が寒く吹くだろうに、どのようにして一人で長い夜を寝ようか。)わが宿の尾花がすゑにしら露の置きし日よりぞ秋風も吹く(巻5-462)(わが家のススキの穂先に白露が置いたその日から秋風も吹くようになった。)(尾花)鵲のわたせる橋に置く霜のしろきを見れば夜ぞ更けにける(巻6-620)(宮中の階段に霜が降りて白くなっているのを見ると、もうすっかり夜が更けてしまったのだ。)(鵲森宮の大伴家持歌碑)はつ春のはつねの今日の玉箒手にとるからにゆらぐ玉の緒(よみ人知らず 巻7-708)初春の初子の今日の玉箒(ばはき)手に取るからにゆらく玉の緒(大伴家持 万葉集巻20-4493)(初春の初子の今日の玉箒は手に取るだけで揺れて音がする玉飾りの緒だ。)秋萩の枝もとををに置く露の今朝消えぬとも色に出でめや(巻11-1025)(秋萩の枝もたわわに置く露が今朝消えてしまうとも、それを顔に出すことがあろうか。ない。)秋萩の枝もとををに置く露の消(け)なば消(け)ぬとも色に出でめやも(大伴像見 万葉集巻8-1595)(秋萩の枝もたわわに置く露のように消えてしまうなら、消えてしまってもいい。そうだとしてもそれを顔に出すようなことがあろうか。ない。)足引の山のかげ草結び置きて戀ひや渡らむ逢ふよしをなみ(巻13-1213)(<あしひきの>山陰に生えている草を結び置いて恋慕って居よう。逢うすべがないので。)
2017.08.18
コメント(6)
-

スズメも色々
何日か前にひろみちゃん8021さんがスズメノヒエの写真をブログにアップされていましたが、昨日、花園中央公園でもこれを見掛けましたので、小生もこれの写真を記事アップすることとします。(スズメノヒエ) スズメノヒエについて調べてみると、これにも色々の種類があるよう。スズメノコビエ という背丈の低い種類もあるから、上の写真のものはコビエの方かも知れない。 穂の裏側にびっしりと付いている黒い葯(雄蕊のこと)を接写してみると、こんな風です。遠目には黒く見えているが、茶褐色なのですな。(同上) 別の場所では、背の高い、少し穂の姿形が違って見えるスズメノヒエがありました。これはタチスズメノヒエという種類だろうと思う。あと、シマスズメノヒエという別の種類もあるようですが、まあ、ここまで深入りすると頭が混乱するので、すべてスズメノヒエという位で事を収めて置く方が素人には無難というものである。(タチスズメノヒエ) タチスズメノヒエの葯は遠目にも茶褐色で、スズメノヒエやコビエのそれのように黒くは見えない。 (同上) スズメのつく草花と言えば、スズメウリ、スズメノエンドウやスズメノテッポウなどが思い浮かぶ。スズメノテッポウは、その穂を抜いた茎を手に取り、葉を折り曲げ、葉の付け根にある白い膜のような葉耳の部分を口に入れて軽く加減して吹くとピーという音が鳴るので、子どもの頃はよくそんなことをして遊んだりもした。水田がすっかり姿を消してしまった所為か、近頃はこの草、近所で見掛けることはない。これを無鉄砲と言うなどと馬鹿な考えも浮かぶ。 スズメのつく虫はどうだろう。今すぐに思い浮かぶのはスズメガとスズメバチ。他に何が居るかと頭を廻らすが出て来ない。 ところで、スズメは何故スズメと言うのか。「語源由来辞典」によると、スズメの「スズ」は、小さなものを表す「ササ(細小)」から来ているか、またはその鳴き声から来ているらしい。笹やススキもこの「ササ(細小)」からだから納得。鳴き声由来説については、平安時代から室町時代まではその鳴き声を「シウシウ」と表現していたらしいが、その「シウシウ」が「スズ」に変化したというもの。 古代のサ行の音は、現代のような「s」音ではなく「ts」音であったとのこと。従って、「シウシウ」は「siusiu」ではなく「tsiutsiu」で「ツィウツィウ」または「チウチウ」に近い音に発音したのであろう。で、江戸時代に入ると「チーチー」または「チューチュー」と表記されるようになり、現代の「チュンチュン」へとつながるのである。 昔の人は、当初スズメのことを、細小説だと「ササメ」または「ツァツァメ」と発音し、鳴き声説だと「チチメ」または「チュチュメ」と発音していたことになるか(笑)。 スズメの「メ」は、群れを表す「メ」またはカモメ、ツバメなどと同じく鳥を表す接尾語の「メ」だそうです。 スズメノヒエの話なのにスズメのハナシに脱線しました。話題がヒエぬうちに元に戻して話をススメます。 このスズメノヒエに似た草にオヒシバがある。こちらの方がよく見かける草だと思う。(オヒシバ) (同上) スズメノヒエは穂が左右段違いに交互に一つずつ付くのに対して、オヒシバは同じ位置に向き合って付いている。最上部は3~5本の穂が輪状に付く。穂形も付き方も異なり葯も白色なので、両者を見間違えることはない。(同上) オヒシバは子どもの頃、この先端の穂をチョンマゲ風に結んで草相撲の遊びに使いました。地方によってはオヒシバでの草相撲の遊びをしない所もあったようで、ブロ友さんの中には、この遊びを知らないというお方も居られました。それで、以前この草による草相撲のことを記事にしたことがありますので、ご存じの無いお方は下記の参考記事をご参照下さい。<参考>草相撲・遊びをせんとや生まれけむ 2012.9.1. オヒシバに似ているが、穂が細く華奢なのがメヒシバである。こちらは草相撲には使わない。女の子が傘遊びに使ったようですから、男の子はオヒシバ、女の子はメヒシバで遊んだ訳で、その名の通りの遊ばれ方でありました。上の参考記事ではメヒシバによる遊びも説明しています。(メヒシバ)(同上)
2017.08.17
コメント(8)
-

退院・墓参・燈花会
退院しました。 と言っても小生ではなく、愛車のトレンクル君です。 先月26日に京都駅から東大阪市の自宅までこのトレンクル君で走りましたが、帰宅すると前輪のスポークが1本折れてしまっていました。その前にもスポークが折れて修理して貰ったことがあったのですが、この時に自転車屋さんから、全体に弱っていて車輪を取り替えて全部張り直した方がいいかも知れない、と聞いていましたので、先月末に入院させることにしました。 入院に先立つ先月28日の生駒の叔母宅訪問・竹林寺への銀輪散歩は、走行する距離も大したことがないので(その実は、スポークが折れていることをすっかり忘れていて、そのまま持って来てしまったので、止む無くというものでありました)、このスポークが折れたままのトレンクルで走行したのでありましたが、トレンクル君には悪いことをしてしまいました(笑)。 昨日、入院先の自転車屋さんから電話があり、修理が完了したとのことで、本日これを受け取って参ったという次第。トレンクル君の入院は15日間でありましたが、入院・治療費は9000円で大したことではありませんでした。<参考>健人会・琵琶湖畔銀輪散歩そして京都駅から自宅まで(前編) 2017.7.26. 同(後編) 2017.7.27.(退院したトレンクル君) 前輪の車輪を少し幅広の新しいものに取り替えたので以前よりはしっかりしたものになっているという話でしたが、 これによってまた少しばかり重量が増したのではないかと危惧、痛し痒しではある。この自転車、購入時は総重量6.5kgであったが、タイヤの取り換え、チューブも一般的なものへの取り替え、左側のペダルの取り換え、ライトの取り付け、チェーンロックの装備などによって、総重量6.5kgという軽量が売りであったトレンクルも現在は7.5kgから8kg程度になっているのではないかと思う。それはさて置き、何にせよお盆に退院して帰宅できたのは重畳と言うべきものではある。 お盆と言えば、今年のお盆は昨年暮れに亡くなった母の初盆ということになる。それで東京在住の妹が帰阪して来た。昨日はその妹と近所(と言っても石切であるから少し離れているのではあるが)に住んでいるもう一人の下の方の妹との3人でお墓参りをしました。12日には小生が妻と共に墓参して居り、11日には、姪が朝早くにお参りし、少し遅れて堺と生駒の叔母たちがお参りしてと、お墓はこのところ「来客」続きとなったようです。(201708言葉) 墓参と言えばいつもの門前の言葉であるが、今月のそれはこうでした。 つらくても おもくても 自分の荷は 自分で背負って 生きさせてもらう その隣には、「わたしたち一人一人が世界の宝物」という言葉も掲示されていましたが、これは夏休みの時期とて、子ども向けのメッセージでもあるか。 自分の荷は自分で背負って行くしかないのはその通りだが、自分のものでもない荷まで背負って不必要なことで悩んでいたりしないかということも考えてみるべきではあります。何れにせよ、人はその人自身が負える荷以上のものは負えないのだから。(201708墓地からの眺め) 上の写真2枚は12日の墓参の折のもの。昨日14日は曇り空でこのようにも青くはありませんでした。墓参の後3人で瓢箪山の商店街に出て昼食。我が家に引き返し、暫く休憩。ここで妹たちが奈良の燈花会に行きたいと言い出したので、小生も同行。下の妹の車は我が家の近くに停めて、電車で行くことに。午後2時過ぎに家を出る。燈花会の点灯は午後7時とのことで、それまで奈良を散策することに。 近鉄奈良駅から登大路を東大寺方向へ。鴎外の門で鹿さんを撮影。(鴎外の門の碑と鹿) 以前の記事(下記<参考>を参照)で紹介済みであるが、森鴎外は1917年12月から亡くなる1923年7月まで帝室博物館総長の任にあり、毎年秋になると正倉院宝庫の開封に立ち会うため奈良に滞在したとのこと。その折には奈良国立博物館の敷地の東北隅のこの地にあった官舎に滞在した。その官舎の門が遺っていて「鴎外の門」と名付けられている。傍らの石碑には鴎外の歌が刻まれている。<参考>参道の奥に憶良の歌碑ありて 2014.1.16.猿の来て 官舎の裏の 大杉は 折れて迹なし 常なき世なり 鹿は鴎外のことなど知ったこっちゃない。鹿の来て 官舎の跡の 鴎外の 碑の歌知らに 草をはむらむ (鹿家持)鴎外の ことは存外 鹿言ふに 人多過ぎの 燈花会なりと (鹿家持) 東大寺南大門の手前で吉城川沿いに芝生の広場を通り抜け、春日大社へと向かう。吉城川は立ち入り禁止のロープが張り巡らされていましたが、鹿はこれも知ったこっちゃない。河原に下りて水を飲んでいました。(吉城川で水を飲む鹿) 妹がこれを見て「煎餅をくれる人は居ても、水をくれる人は居ないからね。」と言って笑って居りましたが、いかにもである。 途中で北側参道の中ほどに憶良の歌碑のあったことを思い出し、芝生広場を横切り、北参道へ直進すると、丁度、その歌碑の前に出ました。この歌碑のことは上記<参考>の記事に写真と説明を掲載済みなのでここでは省略します。 万葉植物園の手前で本来の参道に出て奥へ。本殿前を通り、回廊の燈籠と背後の砂ずりの藤を見て外へ。(春日大社の回廊の燈籠) 若宮神社へと向かう。(春日若宮神社)(同上説明碑) 若宮神社から上の禰宜道を抜けて、新薬師寺・白毫寺方面へと向かう。白毫寺の裏門からも入れるかもと、下へ行かず上から回り込もうとしたのが間違いで、昔はなかったような道や道路脇には随分の住宅が建て込んでいるなどの様変わりで、どうやらその道は白毫寺の裏側を大きく迂回している道のよう。で途中で下へと下る道をとり、何んとかという緑地を抜けて、白毫寺の本来の参道に出る。時刻を見ると4時40分位であったろうか。拝観は5時までなので、急いで小生のみ山門へ。山門下で寺の女性の方が立って居られました。未だ大丈夫ですかと申し上げると、15分位なら大丈夫ですとのこと。(白毫寺山門) 急いで拝観の受付を済ませ、先ず犬養先生揮毫の笠金村の万葉歌碑の前へ。この寺が天智天皇の息子で桓武天皇の祖父にあたる志貴皇子の別荘であった地であることや歌碑の説明をして、本堂と宝蔵の仏像を拝観させていただく。(白毫寺境内から奈良市街を一望) 境内は、高円山の西麓の高みにあるので、奈良市街が見渡せる。 正面には生駒山が見えている。 (同上)<参考>奈良銀輪散歩(その1) 2009.5.19. ※笠金村歌碑、比売神社、鏡神社などの写真は上の記事に掲載済み。 白毫寺を出て、奈良市街へと高畑の道を引き返す。 能登川を渡り、新薬師寺の前の比売神社では十市皇女のこと、鏡神社では藤原広嗣の乱のことなどを説明しつつ帰る。途中通りかかった民家風の喫茶店で暫し休憩。 喫茶店を出て、鷺池の浮見堂までやってくると、燈花会の点灯を待つひとたちが既に沢山集まって来て居られました。しかし、点灯まではまだ1時間もある。先に夕食を済ませてしまおうと、商店街まで戻る。しかし、どの店もいっぱいで待っている人も居る。並んで待つなど真っ平のヤカモチ、どんどん南へと進む。やがて、見知った眼鏡屋さんの向かいに薬膳料理の店を発見。覗いてみると空席がありそう。そこで薬膳料理をいただくこととする。 夕食を済ませて外に出ると午後7時20分。なら町の路地に並べられた灯りの筒にも既に蝋燭の火が点灯されていて幻想的な雰囲気である。なら町を抜けて猿沢池へ。(奈良燈花会・猿沢池) 既に多勢の人で燈花会は始まっていました。猿沢池を半周して興福寺境内を横断し、登大路から東大寺前の浮雲園地へ。人混みの中をぞろぞろと歩く。 (奈良燈花会・采女供養塔と興福寺五重塔)わぎもこが きぬかけやなぎ みまくほり いけをめぐりぬ かささしながら (会津八一)<追記・歌意>(采女が身を投げたという猿沢池。彼女が身投げした時に衣を掛けたという柳の木を見たいと思って、池を廻ってみた。傘をさしながら。)(奈良燈花会・浮雲園地)(同上) 浮見堂の鷺池その他の会場はパスして帰路に。 何年振りかの燈花会でありました。牛に引かれては善光寺であるが、妹らに引かれての燈花会でありました。
2017.08.15
コメント(8)
-

岬麻呂旅便り207・信州、越後
本日(12日)、友人の岬麻呂氏より旅便りが届きました。 今回は「信州越後涼景大周遊(7秘境と5遊覧)」という旅行社企画のツアーに参加されての旅とのことでありました。8月6日~8日の2泊3日の旅程であったようですが、最終日の8日には例の台風5号の影響で帰路に乗車予定の金沢からの特急が運休。次発の特急が遅れていたのでそれに乗車するも、豪雨・徐行運転で大阪駅到着が日付が変わった9日午前0時45分。自宅へのご帰還は午前2時半。「2泊4日のひどい結末」となったそうです。 <参考>過去の岬麻呂旅便りの記事はコチラからどうぞ。 それはさて置き、岬麻呂氏からメール送信されて参りました写真を恒例によりご紹介申し上げることとします。その「2泊4日(笑)」の旅に皆さまにもご同行願おうという次第であります。詳細は、ご本人からの岬巡り報告207(下掲)をご参照下さい。(岬巡り報告207・同写真説明) ※画面をクリックするとフォト蔵画面に移行します。 同画面を再度クリックして特大サイズでもご覧になれます。 大阪駅からサンダーバードで金沢へ。金沢で北陸新幹線に乗り換え、上越妙高駅で下車。バスツアー開始。先ずは、野尻湖遊覧であったようです。(野尻湖) 次に5000株のヒマラヤの青いケシの花の盛りを見て、斑尾高原泊で初日6日終了。(ヒマラヤの青いケシ)<追記>本日(8月13日)岬麻呂氏より青いケシ畑の写真が 追加送付されて参りましたので、下に追加掲載させ ていただきます。 ヒマラヤの青いケシについては、小生は実物を見たことはないのであるが、写真や智麻呂さんの絵画でお馴染みではある。<参考>第1回智麻呂絵画展 2008.7.4. 第2日目(7日)は、新潟・長野県境にある苗名滝への往復45分の炎暑の中の苦行で始まったようであります。まあ、ツアーのタイトルには「7秘境・・」とあるのですから、当然ですな。(苗名<なえな>滝) そして、津南町見玉不動尊と見玉公園へ。見玉公園は秋山郷入口で柱状節理のこのような絶壁が見られるのですな。秋山郷と言うと鈴木牧之の「北越雪譜」を想起しますが、小生は未踏である。(見玉公園<柱状節理の絶壁330m>) 次は、毛渡沢橋梁、湯沢公園アルプの里植物園、湯沢不動滝と巡って、越後湯沢温泉泊。これが2日目。毛渡沢橋梁は1931年に完成した煉瓦造りの鉄道橋梁で、上越線の上り線として現在も使用されているとのことだから、気付かずに小生もこの上を電車で通過したことが何度かあるということのようです。アルプの里というのも随分以前に訪ねた記憶があるが、植物園は勿論、殆ど記憶に残っていない。(毛渡沢<けどざわ>橋梁) 最終日の8日は、台風5号の影響が出始めて時々小雨が降るという生憎の天気。この日は、五十沢渓谷へ。近くの藤原神社では本降りに、とか。(奥五十沢<いかざわ>渓谷) 八海山山頂へはロープウェイで。しかし、濃霧で視界不良。 (八海山大神の鳥居<八海山ロープウェー山頂駅>) 田中角栄の生家も「秘境」かと思いきや、これは単に通り過ぎただけとのことでありました。 (田中角栄の生家) で、行き先は出雲崎。良寛さんの故郷ですな。 (越後出雲崎、天領の里・夕凪の橋) 信越本線鯨波(くじらなみ)駅から列車で移動。隣の駅の青海川(おうみがわ)駅は日本で一番海に近い駅だそうな。確かに、プラットホームから釣りが出来そうな(笑)。(青海川駅) 柿崎で下車。高田城のお堀の蓮を見て、新幹線上越妙高駅へ。(上越高田城の「蓮の花」) で、金沢で、上述のように特急サンダーバード44号の運休に見舞われ、是非もなしとて、次発特急で台風5号の雨と風の中を大阪駅へとご帰還されたという次第。いやはや、2泊4日の旅、お疲れ様でございました(笑)。
2017.08.12
コメント(2)
-

カメムシ
鶴は千年、亀は万年。「亀ハ萬年乃齢(ヨワイ)を経、鶴も千代をや重ぬらん」(謡曲「鶴亀」より)。 鶴亀は長寿を呼ぶめでたき生き物として愛される存在であるが、亀は亀でもカメムシとなるとことは違って来る。カメムシと言えば嫌な匂いを発する虫。葉などを食べることから害虫として駆除の対象となる嫌われ者ということになる。 我が家の北側の空き地に最近ニョキニョキと育ち始めた見慣れぬ草本に小さなカメムシを発見した。この空き地は最近そこに建っていた家が取り壊されてできたもの。 その家の主人は小生の妹と同い年で、小生が高校生であった頃、彼は未だ小学生であったのだが、その家のおばさん、つまり彼の母親に頼まれて暫くの間、彼の家庭教師まがいのことをしたことがある。その頃、西隣の家の中学生の高校受験のための家庭教師をしていたこともあって、うちの子の勉強も見て欲しいと頼まれたのかも知れないが、昔の事なのでその辺の記憶は曖昧である。どういう事情かは存じ上げないが、この程その家屋敷を売却して他所へ引越しをされました。で、この物件は不動産業者の手に渡り、家が取り壊され、土地の造成が始まったという次第。子どもの頃から見慣れた家屋敷が消えるというのは何やら寂しいものがあるが、是非に及ばずである。 話が脇道に逸れました。カメムシに話を戻します。カメムシがいた見慣れぬ草というのはこれ。 (見慣れぬ草本) <追記>小万知さんからアオイ科のイチビだと教えていただきました。 <参考>イチビ・Wikipedia よく見る草のようにも思うが初めて見る草のようにも。造成のために運び込まれた土砂に種が混じっていて芽を出したものか、何本も大きく育っている。アカメガシワを草にしたような姿であるが、小さな黄色い花を付け、既に実らしきものもなっている。その実にとまっていたカメムシがこれ。体長は1cmにも満たない小さなカメムシである。(ブチヒゲヘリカメムシ) カメムシの種類なんぞよくは知らない。 ネットで調べたら、ブチヒゲヘリカメムシとしてアップされている写真のそれがよく似ていたのでブチヒゲヘリカメムシとしましたが、正解かどうかは保証の限りではない(笑)。 (同上)(同上) で、これに先立つ日に同じ草にいたカメムシを撮影し、その折にも同様の方法でその名を調べたのですが、その時にはスカシヒメヘリカメムシと判断して写真の整理を行いました。それが以下の写真です。その折のネット検索では、スカシヒメヘリカメムシとして画像紹介されているものによく似ていると思われたのでありました。しかし、比べてみると上も下も同じ種類のカメムシに見える。もう一つよく似たのにケブカヒメヘリカメムシというのもいる。ネットのそれらがどの程度信用の置けるものなのかも不明。と言うことで、当記事写真の虫名のキャプションは、かなりいい加減なものと言うか、「これかも知れない」という程度のものであるとお心得願いたく存じます。(スカシヒメヘリカメムシ) (同上) カメムシも実に種類が多く、その姿の色や形も多様、奥が深い。そのデザインとしての面白さもある。ということで、今後も種類の異なるカメムシを見掛けたら、マンホール蓋の記事ではないが、写真に撮って掲載して行くこととしたいなどと考えています。過去の当ブログ記事でもカメムシの写真を何度か掲載したことがありますので、今回はそれらの写真も併せ再掲載して置きます。我がブログはカメムシもウェルカメなのである。(ブチヒゲカメムシ)(キマダラカメムシ)(キマダラカメムシの中齢幼虫)(キバラヘリカメムシ) はい、本日はカメムシ特集でありました。<追記・参考>虫関連記事目次はコチラ
2017.08.10
コメント(10)
-

囲碁例会とSS会
本日は梅田での囲碁例会の日。夕刻からSS会の集まりで会食があるので、MTBではなく電車で梅田に向かう。昨日、利麻呂氏からメールがあり、今回も特別参加したいということで、梅田スカイビル1階で待ち合わせ、昼食をご一緒する。いつもの通り地下のレストラン四季彩に行く。そこで、かつての仕事仲間の勝〇君と原〇君の懐かしいお顔を拝見しご挨拶を交わす。 珈琲の後、会場の5階の部屋に行くと未だどなたもお見えでない。それで、利麻呂氏を相手に指導碁。暫くして、福〇氏、村〇氏がお見えになり、ややあって竹〇氏と平〇氏が来られ、本日の参加者は5名プラス利麻呂氏ということでありました。小生は福〇氏に負け、村〇氏と竹〇氏に勝ち、本日は2勝1敗の成績。これで、今年に入ってからの通算成績は15勝19敗。まだ4つ負け越しである。 囲碁例会の後、福〇氏とSS会の会場に向かう。今回の会場となっている店は、阪急グランドビルの30階にある「塚田農場」という名のお店。(塚田農場)(同上・店内) 店に入ると、辻〇氏が一番乗りで既に来て居られました。因みに辻〇氏も小生と同じく自転車を趣味とされる自転車族なのである。それもロードバイクで走られる本格派で、小生のようなマウンテンバイク族とは趣を異にするのであるが、それでも同じ自転車族として自転車に関しては話が合うのではある。 辻〇氏と談笑しているうちに、川〇氏、松〇氏、石〇氏、古〇氏が来られ、続いて福◎氏、山〇氏、早〇氏が来られ、本日の出席予定者全10名が勢揃いし、開会の乾杯。小生も乾杯だけはビールで行いましたが、後は専らウーロン茶であるから、飲み放題メニューと言っても有難みは殆どないのであります。まあ、これは下戸ヤカモチさんにとってはいつものことなので、普通のこと、毎度のことにて慣れっこなのであります(笑)。ところで、SS会というのはどういう会なのかについては過去のこの会についての記事<下記・参考>に記載していますので、それをご参照下さい。 <参考>SS会2015.8. と言うことで、本日はデーゲームとナイトゲームのダブルヘッダーでありました。
2017.08.09
コメント(0)
-

第193回智麻呂絵画展
第193回智麻呂絵画展 昨日・6日は、久しぶりに智麻呂邸を訪問し、新作絵画10点を撮影して参りました。先に撮影してストックしている作品5点と合わせて15点になりましたので、智麻呂絵画展の開催といたします。今回は、お孫さんのナナちゃんの絵も2点撮影して居りますので、久しぶりに彼女の絵もご紹介申し上げることとします。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずは凡鬼野菜の絵から。玉葱、胡瓜、馬鈴薯が凡鬼さん栽培の野菜です。先の若草読書会の折にお持ち下さったものかと思います。左側の赤いトマトは彩りにと恒郎女さんが添えられたもののようです。トマトの下の蜜柑とキーウイはヤカモチ館長が同じく読書会に持参した果物セットの中に入っていたものだそうです。(凡鬼野菜) 次のルドベキアはひろみの郎女さんがお持ち下さったものだそうです。 (ルドベキアfromひろみの郎女さん) 以上は7月6日撮影の作品です。 次はご友人の友〇さんから頂戴したグラジオラスです。 (グラジオラスfrom友〇さん) 次の百合2点はデイサービス施設の「アンデスのトマト」で描かれたものか、その花を頂戴して帰り、自宅で描かれたものか、定かには存じ上げませんが、そのどちらかです。 (百合<1>)道の辺の草深百合の花咲(ゑ)みに咲まししからに妻といふべしや(万葉集巻7-1257)あぶら火の光に見ゆるわが蘰さ百合の花の笑まはしきかも(大伴家持 同巻18-4086)(百合<2>) さて、ここで、お孫さんのナナちゃんの絵で、少し気分転換と言うか、和んでいただくことといたしましょう。ナナちゃんは第3回智麻呂絵画展に於いて「イエス・キリスト」の絵で「鮮烈のデビュー」(笑)をされましたが、以後、時々当絵画展にご登場いただいて居りますので、ご常連の皆さまには既にお馴染みのことと存じます。<参考>ナナちゃんの絵が展示されている絵画展は以下の通りです。 第3回展、第91回展、第99回展、第103回展、第177回展(野菜のタペストリーbyナナちゃん)(紫陽花と蝸牛byナナちゃん) ナナちゃんの絵。お楽しみいただけましたでしょうか。 以上、ナナちゃんの絵までの作品は7月17日に撮影のものです。 では、智麻呂絵画に再度立ち返っていただきましょう。 以下の10点は昨日6日に撮影の作品であります。 オンシジウムです。主役と言うよりも脇役という場合が多い花かと思いますが、そういう処をよしと好まれるのか、或はそのフォルムが絵心を刺激するのでもあるか、智麻呂氏はこれまでにも何度かこの花を単独で絵にされています。 今回もお嬢さんたちから贈られたバースデイ・プレゼントの花束から、このオンシジウムだけを抜き出して絵にされたそうな。(オンシジウム) 既に8月になっていますが、先月・7月は智麻呂氏の誕生月。 そんなことで、誕生日絡みの花が続きます。 ガーベラは、デイサービス施設「福寿苑」で頂戴したものです。 ガーベラは、ものの本によると2月11日、3月16日、5月9日、6月9日、7月1日、8月1日、27日、9月27日、10月1日、8日、12日、24日、11月2日、21日、12月30日の誕生日花らしいが、福寿苑では7月の誕生花をガーベラと決めて居られるのでしょうか。毎年、この花が登場しているようです。 (ハッピー・バースデイ・ガーベラ) 次はもう一つの施設「アンデスのトマト」の誕生日花です。こちらは毎年このようなブーケと決めて居られるようです。(ハッピー・バースデイ・ブーケ) 次は彦根城です。この絵は、「アンデスのトマト」で描かれたものですが、そこで戴いた写真の中から、彦根城を題材にされたという次第。ご家族でのご旅行や若草読書会の旅行で訪ねられた彦根城のことなどを思い出しながら描かれたのかも知れません。(彦根城) 次は椿。 これは、智麻呂絵画ではなく、塗り絵です。 本絵画展の作品と同列に並べていいものかどうか疑問ですが、番外作品として、展示させていただきます。 ご友人の友〇さんが「大人の塗り絵」という冊子を下さいました。それは色んな絵画の写真が片面に綴じてあって、その反対側のページ面にその絵画の線画が薄い色で印刷されているというものです。絵画の方の色づかいを参考にその線画に色を塗って行くというものです。 つまり、下絵のある模写とも言うべきもので、智麻呂絵画のようなオリジナルな作品ではありませんので、番外作品とさせていただいた次第。(番外作品・椿の塗り絵) 次の花も友〇さんから頂戴したものだそうです。キク科の花のようですが、名前が分かりません。メランポジウムという名が先ず思い浮かびましたが、スラリとした花姿の感じがそれではないと言っているようです。キクイモモドキとかルドベキアの仲間とかキバナコスモスとかでしょうか。 ということで、花の名前を以ってタイトルとするというヤカモチ館長のズボラな編集方法が通用しなくなりました。しかし、ズボラ編集の癖は治らず、タイトルは何やら聞いたことのあるような「幸せの黄色い花」となりました。 (幸せの黄色い花from友〇さん) 次は朝顔です。祥麻呂さんが朝顔市で買い求めて智麻呂さんに東京から送って下さった朝顔です。真っ赤な朝顔。二輪仲良く寄り添って咲いています。(朝顔from祥麻呂さん) 次は、趣が変って、ハムです。ハムと言えば五〇さん、と言うのが常識になっている当絵画展でありますが、今年もその季節になったという訳であります。 (ハムfrom五〇さん) 次はお嬢さん(つまり、ナナちゃんのお母さん)からのゴーヤと胡瓜です。グリーンカーテンとして植えていたゴーヤやキュウリに実がなったので、摘んで持って来て下さったそうです。 (ゴーヤと胡瓜) 最後は、やはり花の絵で締めるべきでしょうね。 ムクゲです。智麻呂邸の前の公園に咲いているものを写生されました。ムクゲは韓国語ではムグンファ(無窮花)。個々の花は一日花ですが、次々と咲くので無窮花という名で呼ばれることになったのかも。 智麻呂絵画展もムクゲに負けることなく次々と色とりどりに花を咲かせ、我々を楽しませて下さることを期待して居ります。(ムクゲ) 以上です。 本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。
2017.08.07
コメント(12)
-

囲碁例会<付・虫散歩>
本日は囲碁例会の日。今年に入って囲碁を覚えたいとしてこの囲碁サークルを覗きに来られるようになった友人の利麻呂氏よりメールがあり、久々に参加するので、正午少し前に梅田スカイビルで落ち合って昼食を一緒にどうかということであったので、それに間に合うように10時少し前にMTBで家を出る。 特段の寄り道もせず走ったので梅田スカイビル到着は11時25分。少し早いので喫茶店で時間潰し。汗が引いたところで11時45分に店を出てタワーイースト1階にある高速バス待合所コーナーへ。利麻呂氏の姿は未だ見えない。で、洗面所にて新しいTシャツに着替えて、出直すと、直ぐに利麻呂氏が現れました。地下の滝見小路にあるレストラン四季彩でランチ。会場になっている5階の部屋に上がると、既に福〇氏が来て居られました。 早速に同氏とお手合わせ。利麻呂氏は観戦。途中で村〇氏が来られ、隣で利麻呂氏への指導碁が始まりました。そこへ、平〇氏も来られ、本日は、利麻呂氏は会員でもないので除外するとして4名の出席でありました。福〇氏との対局は、手堅く地をまとめた小生の十数目勝ちで、先ず1勝。次に村〇氏と対戦しましたが、これは、上辺の黒石が、受け間違いで死んでしまった結果、セキとなっていた個所がセキ崩れで、全て白地になってしまうという大事件。これで一気に状況が不利に、中押し負け。ということで今日は1勝1敗。 帰途も立ち寄り先はなく、ブログネタとなるような写真もありません。ただ、中央環状道路近くの公園で一休みした際に撮ったクマゼミの写真がありますので、過去の銀輪散歩などで撮った虫の写真で「虫散歩」の記事に構成してみることとします。虫嫌いなお方はパスして下さい。(2017年のクマゼミ)(同上) 以下は、過去の(と言っても最近のものであるが)撮影にかかる写真です。 先ず、ムラサキシジミ。翅を広げると青というか紫というか美しい色なのであるが、警戒態勢なのか、翅を広げようとはしない。横目でこちらを見張っているみたいでもありました。(ムラサキシジミ) 次はマメコガネ。盛んにケヤキの葉を齧っている。マメコガネという名はマメ科の植物によく付き、その葉を食べることから付いた名前で、小さいからマメと言う訳ではなさそうです。(ケヤキの葉を食べるマメコガネ) そして、最後はアメンボです。 あめんぼ赤いな アイウエオ 浮き藻に小エビも 泳いでる 柿の木、栗の木 カキクケコ・・ というのは、北原白秋の「五十音」という詩ですが、アメンボは赤いですかね。(アメンボ) (同上) 水面をスイスイと素早く歩く。その動きは見ていて飽きない。いや、時には飽きますな(笑)。水面に空が映っていると、まるで空を泳いでいるようにも見える。 (同上)(同上) 何か小さなハエか羽虫かをつかまえて食べているのか、管を突き刺して体液を吸っているのか、そんなアメンボがいました。アメンボは肉食なんですね。トンボやカマキリやスズメバチのように丸ごとムシャムシャと虫の体を食ってしまうのではなく、その体液だけを吸う奴を肉食と呼んでいいのかどうか存じませんが、草食系ではないという意味での肉食系であります。 (虫を捕まえて食べているアメンボ)(同上) 囲碁と虫散歩。妙なとり合わせとなりましたが、囲碁サークルの面々は、小生も含めて「囲碁の虫」でもありますから、まあ、まんざら無関係ということでもないのではあります。<参考>囲碁関連記事・目次 虫関連記事・目次
2017.08.02
コメント(10)
全11件 (11件中 1-11件目)
1