2017年11月の記事
全15件 (15件中 1-15件目)
1
-
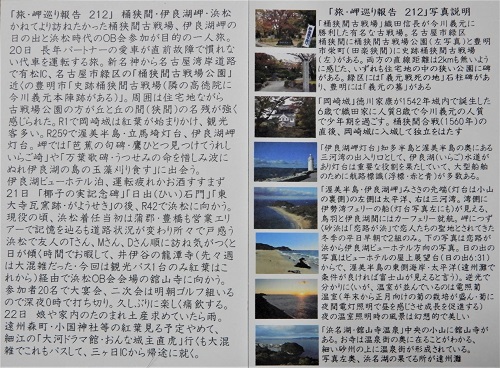
岬麻呂旅便り212・桶狭間・伊良湖岬・浜松
本日は、岬麻呂旅便りの記事とします。今回の旅は、氏が浜松勤務時代のお仲間とのOB会参加が目的の一人旅であったようです。(下掲「旅・岬巡り報告212」参照) (旅・岬巡り報告212及び写真説明)<参考>岬麻呂旅便りの過去記事はコチラから。 OB会参加のついでにお立寄りになられた桶狭間古戦場跡や伊良湖岬など、我々も写真で旅をさせていただくことといたしましょう。 (桶狭間古戦場公園・名古屋市緑区) (史蹟桶狭間古戦場・豊明市) (岡崎城) 古戦場跡、岡崎城の後は、渥美半島、伊良湖岬へ。 岬麻呂の旅とあれば、岬と灯台は基本的に欠かせないもの(笑)。 (伊良湖岬灯台) (渥美半島・伊良湖岬) (同上・恋路が浜から伊良湖ビューホテル方向を望む。) 伊良湖岬では芭蕉の句碑と万葉歌碑もご覧になられたよう。 (芭蕉句碑)鷹ひとつ見つけてうれしいらご崎 (芭蕉) 芭蕉は貞享4年(1687年)11月12日に伊良湖崎に立ち寄っている。門人の杜国(尾張の米穀商・坪井庄兵衛)が何かの罪に問われ、三河の保美村に隠棲中であったのを見舞ったようである。この折の句では、夢よりも現(うつつ)の鷹ぞ頼母しきというのもある。 旅報告には、万葉歌碑もご覧になり、その歌を記して居られるが、残念ながら歌碑の写真は届いて居りませぬ。うつせみの命を惜しみ波に濡れ伊良虞の島の玉藻刈り食(を)す(麻続王 万葉集巻1-24) (<うつせみの>命が惜しさに、波に濡れて、伊良虞の島の玉藻を刈って食べているのだ。)(注)刈り食(を)す=「刈り食(は)む」という訓もある。 万葉集によると麻続王(をみのおほきみ)が伊良虞の島に流された時に、それを悲しんだ人が作った歌「打麻(うちそ)を麻続王海人なれや伊良虞の島の玉藻刈ります(万葉集巻1-23)」(<打麻を>麻続王は海人ででもあるのか、伊良虞の島の玉藻を刈っていらっしゃる。)に感傷して麻続王が和したのが上の歌とされている。日本書紀やそれを引用する万葉集左注では麻続王は因幡に流されたとあり、常陸国風土記では行方郡板来村に流されたとあるなど、様々な伝承があったようだ。麻続王その人についても、諸説あって如何なる人物かよくは分からない。<参考>麻績王・Wikipedia 万葉集左注で既に「後人の歌辞によりて誤り記せるか。」と指摘されているように、麻続王がこの地に流されたというのは間違いであるとしても、「伊良虞の島」が伊良湖崎であるとすることには異論がないようですから、ここにこの歌の歌碑があることについても誰も異論は無いだろう。 (日の出、伊良湖ビューホテルの屋上展望台から 6:31) 初日は伊良湖ビューホテル泊。翌2日目は、椰子の実記念碑、日出石門、東大寺瓦窯跡などを廻られ、浜松へ。浜松のご友人を順次訪ねつつ、OB会の会場である舘山寺温泉へ。参加者20名の「大宴会」にて大いに旧交を温められたようです。 (浜名湖・舘山寺温泉)
2017.11.28
コメント(2)
-

中学時代同級生との大宇陀万葉ウオーク
今日は、中学時代の同級生男女8人での大宇陀万葉ウオークでした。今月9日にコースの下見をし、その様子をブログ記事にしていますので、立ち寄り先の詳細は、同記事にあるものについては省略します。同記事を併せご参照賜れば幸いです。<参考>中学時代の級友との大宇陀万葉ウオーク下見 2017.11.10. コースは、下見記事でも触れていますが、下記の通りです。榛原駅~榛原小学校前の墨坂万葉歌碑~(榛原駅前経由)~榛原フレンドパーク~榛原西小学校校庭の猟路池遊猟万葉歌碑~三十八神社~蓮昇寺境内の池上万葉歌碑~八咫烏神社(昼食休憩)~県道217号経由内原へ~松山西口関門(休憩)~大宇陀地域事務所前庭の万葉歌碑~阿紀神社(万葉歌碑)~かぎろひの丘(万葉歌碑)~人麻呂公園~道の駅宇陀路大宇陀~バスで榛原駅前 参加者は、男性陣が木麻呂(きまろ)君、喜多麻呂(きたまろ)君、谷麻呂(たにまろ)君と小生・偐家持(にせやかもち)の4名。女性陣は嶌郎女(しまのいらつめ)さん、堀郎女(ほりのいらつめ)さん、塩郎女(しほのいらつめ)さん、大郎女(おほのいらつめ)さんの4名。計8名である。大郎女さんのご主人、大麻呂(おほまろ)氏も特別参加される予定で、楽しみにしていたのですが、お風邪を召されたとかで、ご欠席となりましたので、元同級生だけの参加となった次第。 榛原駅午前10時25分着の急行に順次乗るべしで、鶴橋駅から嶌郎女さん、布施駅から男性陣4名、国分駅から堀郎女さん、大和八木駅から大郎女さんと塩郎女さんが乗車の予定であったのですが、我々男性陣が乗った瓢箪山発9時19分の電車が遅延し、布施駅に着いた時には、当該急行は出てしまった後。後発の20分後の急行で、追いかけることとしました。女性陣は全員、予定の電車にご乗車されたようで、我々男性陣が榛原駅に到着すると、改札口の処で待っていて下さいました。 という次第で20分遅れの10時45分出発となりました。先ず、駅の北側の墨坂万葉歌碑を訪ね、再び榛原駅前に戻り、駅前のコンビニでお弁当やおにぎりやサンドイッチなどを購入して昼食の準備を完了、榛原フレンドパーク経由、榛原西小学校へと向かいました。榛原西小の校庭にある猟路池遊猟歌の万葉歌碑を見るためである。 (猟路池遊猟歌の歌碑の前で) 万葉の頃は、榛原の地には大きな池(猟路池<かりぢのいけ>) があったそうだが、この地に長皇子(天武天皇と大江皇女の間の子。同母弟が弓削皇子)が狩をなさった時に、これにつき従った柿本人麻呂が作った歌が、この歌碑の歌である。 写真は歌碑を眺める大郎女さんと木麻呂君。奥で歌碑裏面に刻まれた長歌の方を見ているのが谷麻呂君。 榛原西小学校を出て三十八神社へ。 (三十八神社へ向かう道から眺めた榛原の山々) 三十八神社から蓮昇寺境内の万葉歌碑を見た後、八咫烏神社へ。 既に12時半を過ぎていたので、ここで昼食とする。拝殿横の八咫烏のヤタちゃんの像の前にビニールシートを敷いてお弁当タイムとなりました。 (八咫烏のヤタちゃん) 下見の折は、うだアニマルパークでお弁当タイムとしたが、歩くペースが見込みより遅いことと出発が20分遅れとなったことなどもあって、随分手前でのお弁当タイムとなりました。八咫烏のことやJリーグのシンボルマークに八咫烏が使われていることの経緯などを説明させていただいて、先へと進む。 県道217号で西へ。宇陀川沿いの道に出て、うだアニマルパークはパスし、松山城西関門で小休止。女性陣から戴いたキャラメルやチョコなど甘い物で気分転換。嶌郎女さんがご持参下さったインスタントコーヒーにお湯を注いで珈琲休憩が出来たのは偐家持にとっては何よりのことでした。ところが、ここで雨がパラつき出す。レインコートを着たり、傘を取り出したりして、雨対策。 宇陀市大宇陀地域事務所(旧大宇陀町役場)の前庭の万葉歌碑へ。軽皇子(後の文武天皇)の阿騎野遊猟の背景、意味などを簡単に説明させていただいて、阿紀神社の万葉歌碑へと向かう。ところが、ここで木麻呂君と喜多麻呂君がギブアップ。以下の行程をパスし最終地点の「道の駅」へと直接向かうことになる。そこで我々を待つという訳である。残り6名で、阿紀神社、かぎろひの丘、人麻呂公園をめぐって、道の駅・宇陀路大宇陀へ。そこで、木麻呂、喜多麻呂両君と合流。 15時35分発のバスで榛原駅へと帰還。駅前で珈琲でもという声があり、次発の急行までの時間、喫茶店で珈琲休憩とする。木麻呂君と塩郎女さんは先発の急行で帰途につくとして、先にお帰りになりました。喜多麻呂君、谷麻呂君、嶌郎女、大郎女、堀郎女、偐家持の6名は喫茶店で20分ほど雑談して過ごし、16時20分榛原発の急行で帰途につきました。 今回は、上に掲載の写真3枚を撮ったきりで、何も撮影しなかったので、立ち寄り先や道中の写真がありません。それで、2011年1月にこの辺りを銀輪散歩した時の過去記事を下に貼っておきますので、立ち寄り先などの画像を見たいというお方はこれら記事を併せご覧下さい。<参考>かぎろひの丘銀輪万葉(その1)(その2)(その3) (かぎろひの丘と万葉歌碑・再掲) <参考>フォト蔵アルバム2017.11.09.大宇陀万葉ウオーク下見・本番2011.01.07.かぎろひの丘銀輪散歩<追記>〇コース概略地図
2017.11.26
コメント(8)
-
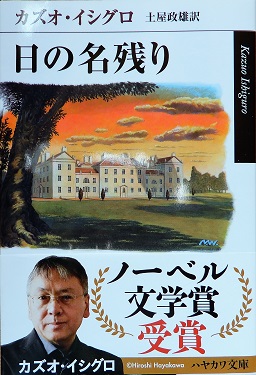
若草読書会・日の名残り(THE REMAINS OF THE DAY)
本日は若草読書会の例会でありました。参加者は、智麻呂・恒郎女ご夫妻、凡鬼さん、小万知さん、祥麻呂さん、偐家持の6名といつになく少人数となりました。 課題図書は、今年のノーベル文学賞受賞作家カズオ・イシグロの「日の名残り」(ハヤカワ文庫)でありました。発表者は祥麻呂氏。 祥麻呂氏から、著者の生い立ちやその他作品のことなども含め、この小説についての感想をお話いただいた後、この主人公の人物像や執事という仕事のことや品格や英国のことや日本人の働き方やその他各人が思い付くままの色々なことについての雑談となりました。 この小説は、本当の執事は英国にしかいない、他国の執事は単なる召使いにしか過ぎない、と考える英国の執事・スティ―ブンスという男の物語、本物の執事とは何か、執事の品格とはいかなるものかなどを問い続け、自身の私生活の全てを犠牲にして、完全無欠の執事になろうと努めた男の物語である。 自身が執事を務めるお屋敷を旧主ダーリントン卿から買い求めてお屋敷の新しい主となったアメリカ人・ファラディ氏から、休暇ドライブ旅行を勧められ、その主人の車で出掛けた旅(それは自分の下で働いていた元女中頭のミス・ケントンを訪ねる旅でもあったのだが)の6日間の記録で構成された小説である。その旅で出会う英国の田舎の温かい善意溢れる人々との出会いや「品格ある」風景との出会いの描写と自身の執事として過ごしてきた過去への回想や自身の執事としての信念の吐露とを織り交ぜながら、恰も英国の田園風景のように、ゆったりとしたテンポで展開して行く小説である。 彼の旅行は1956年の8月か9月ということになっている。この時期はスエズ運河をめぐるエジプトと英仏両国とが対立、米ソ冷戦の中で、中東をめぐって複雑な外交の駆け引き・思惑が交錯していた時期。事件はやがてナセルがスエズ運河を一方的に国有化するという挙に出たことから、それの権益と航行の自由を守らんとする英・仏にイスラエルも加わってスエズ戦争と呼ばれる武力衝突に発展するのであるが、英国の期待に反して米国が英仏の武力侵攻に反対の立場を取り、米ソや国連の介入によって、英仏は戦争には勝ちながら、撤退を余儀なくされ、外交的には敗北することとなるという、大英帝国の外交が挫折し、その威信が地に落ち、国際舞台に於ける米国の圧倒的優位が国際社会に於いて明白になる、その転換点とも言えるのがこのスエズ危機、スエズ戦争である。 大英帝国時代の古きよき昔に何かと思いをはせる主人公の姿(執事としてはそれが自然な姿と言うべきだが)に重ね合わせると、作者が主人公の旅をこの時期に設定したのも偶然のことではなく、意図的なものではないかと思われたりもする。 (「日の名残り」) 課題図書についての話が一段落した処で、恒郎女さんのご要望により、凡鬼氏が「月刊俳句界」に自作俳句と一文を寄せられたことに関連して、その経緯や当該俳句にまつわるお話をいただくこととなる。 (月刊俳句界) そのアトは、これも恒郎女さんの企画であるが、ご用意下さった下ごしらえでお好み焼きを焼いて皆で食べるという、「お好み焼きパーティ」と相成りました。焼くのは専ら凡鬼さんで、我々は焼き上がったものを食べるだけという楽な役回り。飲んで、食って、喋って、また食って、飲んで・・、凡鬼さんだけは、この飲んで、食って、喋っての他に「焼いて」というのがあった訳ですが、ともかくも、皆それぞれに楽しい時間を過ごしたのでありました。 そして、次回は来年1月27日(土)新年会ということに決めて、午後5時半頃の解散となりました。
2017.11.25
コメント(2)
-

母一周忌・父十三回忌
今日は、母の一周忌、父の十三回忌の法要でした。母が亡くなったのは昨年の12月3日、父が亡くなったのが12年前の2005年11月24日。ということで、母の一周忌と父の十三回忌を併せて、今日これを執り行うことといたしました。 母のカラオケ友達の嶋郎女さんもご参列下さいましたが、昨日わが家にお供えをお持ち下さった折にお持ち下さった封筒の中に、彼女が母の霊前にと詠んで下さった和歌が1首したためてありました。野や山に 匂ひかぐはし 四季の花 それ思ひ出の 花も匂へと (嶋郎女) 席を変えての食事会の場でのご挨拶の中で、この歌をご紹介させていただき、そのあと皆さんにもご唱和をお願いし、犬養節でこれを皆で詠って、母に捧げることとしました。昨夜のうちにPCでこれを打ち込み、出席者人数分を印刷に打ち出したものを用意して居りましたので、これはハプニングではなく、小生の予め考えたシナリオでありました。勿論、嶋郎女さんに事前のご了解を得てのことであったのは言うまでもありません(笑)。父母を しのぶこの朝 わが庭の 山橘は ひとつ実をつけ (偐家持) 法事の会場へと出かけるべしで、家を出る時、勝手口の前の庭の片隅の藪柑子が赤い実を一つ付けているのが目にとまりました。早朝の雨に濡れた赤い実は、ぽっちりと照り輝いているようでもありました。 (ヤブコウジ) (同上) ヤブコウジは万葉ではヤマタチバナである。山橘、夜麻多知婆奈、山地木などと書く。<追記> 読み返してみて、ヤブコウジの万葉歌を記載していないことに気付きましたので、何首かある中の一番有名なこれを追記して置きます。 この雪の消(け)残る時にいざ行かな山橘の実の照るも見む(大伴家持 万葉集巻19-4226) 話は変わるが、大伴家持の長歌に「知智(ちち)の実の 父の命(みこと) 柞葉(ははそば)の 母の命・・」(万葉集巻19-4164)というのがある。「ちち」というのはイチョウ説やイチジク説など諸説ある未詳植物であるが、一説にはイヌビワだとも言う。「ははそ」はコナラ、ナラガシワ、カシワ、クヌギなど、これも諸説あるが、コナラやクヌギなどのブナ科の落葉高木のことである。 防人の丈部真麻呂(はせべのままろ)の歌、「時時の 花は咲けども なにすれそ 母とふ花の 咲きで来ずけむ(巻20-4323)」という歌は「四季折々に花は咲くけれど、どうして母という花は咲いたことがないのか」と言っているが、母という名の花が無い訳ではないらしい。貝母(ばいも)とも呼ばれるアミガサユリがそれである。この花は古くは「母栗(ははくり)」と呼ばれていたそうな。 ということで、今日は父と母に関連した草木をとり上げてみました。 このアミガサユリとイヌビワは過去の記事でもとり上げているので、その折の写真を参考までに再掲載して置きます。写真をクリックすれば、拡大サイズの写真を、写真下のキャプションをクリックすれば、当該過去記事をご覧になれます。 (アミガサユリ) (同上) (イヌビワ)
2017.11.23
コメント(10)
-

サルの絵・真っ赤な嘘と真っ白な嘘
先日(11月1日)の囲碁例会の日に撮影させていただいたゴリラの絵をご紹介します。 囲碁の会のメンバーの福〇氏はゴリラなど猿の油絵を専らに描かれているユニークなお方でもある。今回の絵は原画からの撮影ではなく、原画を撮影された同氏の写真からの撮影でありますので、紙焼き写真の反りによって、少し歪みが生じて居りますが、この点はご了承賜りたく。 (眼力<めぢから>) ゴリラの表情が様々にとらえられ、高い知性や確固たる意志をさえ感じさせる力強い表情が魅力的です。まさに眼に力があります。 同氏の絵はこれまでにも何作か当ブログで紹介申し上げておりますので、それらの画像を下記に陳列して置きます。画像をクリックすると大きい画面に切り替わります。また、画像下のキャプションをクリックしていただくと、当該絵画の写真が掲載されている当ブログ記事を読むことができます。 (至福の時) (一休み) (ここまでおいで)(何か・・?) (望郷or・・) (目配り・気配り) サルと言っても種類は色々。<以下は南方熊楠著「十二支考」を参考にした。> 英語ではモンキー(Monkey) とエイプ(Ape)と区別している。長い尻尾のあるのがモンキーで尻尾が無いか短いのがエイプである。 尤も、16世紀までは全ての猿をエイプと言っていたそうだが、その後、尻尾の無い人類に近い猿のみをエイプと言うようになり、他の猿をモンキーと言うようになった。 モンキーというのはフランス語のモンヌ(monne)、イタリア語のモンナ(monna)に小さいを意味するキーを添えた言葉だそうな。そして、モンナもモンヌもアラビア語の猿の意味のマイムンが語源らしい。一方、エイプの方は、サンスクリット語(梵語)の猿を意味するカピから派生したギリシャ語名ケフォス、ラテン語名ケブスなどの「ケ」を「エ」と訛って生じたとも、その鳴き声に由来するとも。(注:追記)猿は、英語ではsimian(シミアン)とも。ドイツ語ではAffe(アッフェ)、フランス語ではguenon(グノン)又はsinge(サンジュ)、イタリア語ではscimmia(シンミア)。 中国ではもっと詳細な区別があったようで、猿を意味する語は、 猴、 キョ(據の手ヘンを取った漢字。ブログでは使えない文字なのでカタカナ表記して置く。以下同じ。)、 カク(攫の手ヘンをケモノヘンに変えた漢字。)、 禺(グウ)、 ユウ(ケモノヘンに穴と書く漢字)、 果然、 蒙頌(モウショウ)、 ザンコ(ザンはケモノヘンに斬と書き、コは鼠ヘンに胡と書く。)、 エン(ケモノヘンに爰と書く漢字。猿と同じ意味)、 ジュウ(ケモノヘンに戎と書く漢字。)、 独、 猩々、などなどである。 日本語では猿はサルにて(マシラなどという呼び方もないではないが、エテ公などと同じく別称と考えて置きます。)他の呼び名が無いのは、ニホンザル一種しか日本にはいなかった所為でしょう。 ところで、猿のお尻と言えば「赤い」というのが相場。真っ赤な嘘という言葉が発生したについては、この「猿のお尻」が関係していると南方熊楠先生は申して居られますな(笑)。赤いとは「まづかく」という言の訛りたるなり。「まづかく」は真如此(真此の如し)なり。それを丹心丹誠の丹の意にまっかいと言えるは偽りなきことなるを、のちにその詞を戯れて猿の尻など言い添えて、ついに真ならぬようのこととなりて、今は真っ赤な嘘と言う。こは疑いもなく明白なるをまっかと言うなれど、実は移りて意の表裏したるなるべし、と見ゆ。」(南方熊楠「十二支考」) 丹心は赤心とも言うが、まごころ。裏表のない誠実な心のこと。丹誠は丹精とも書くが、丹精込める、という言葉があるように、飾りや偽りのない心、誠意の意、或は心を込めて物事をなすことの意である。丹は丹砂(辰砂)またはそれから作る赤い顔料のことである。 では、何故、赤(丹)心が誠実な心の意になるかと言えば、赤(あか)とは、古代にあっては、我々が今日「赤い色」と呼んでいる色彩感覚とは異なる色の表現であったからである。「あか」とは「明るい」と言う意味であり、それは夜明けの清々しい色でもあったろう。従って、赤心は「明るい心」「明らけき心」ということになる。 この論の難点は「赤心」は大和言葉ではないという点。これを言い過ぎと言い、赤恥をかくことになりますれば、余り真面目に受け取られませぬように。単純に赤子の如き心という論には叶わぬことかと(笑)。しかし、成り行き上、もう少し続けます。これに対する語は「くろ・黒」、「暗い」である。夜の暗さ、黒から日が昇り明るくなって事物の色がはっきりして、輝いて見える様が「あか」なのである。 余談になるが、もう一つの色彩の区分は青と白である。「あを」は「淡い」色、はっきりしない色、目立たない色を言う。これに対して、はっきりした色、目立つ色が「しろ・白」である。目立っているさまを「いちしるく」とか「いちしろく」と言ったが、この「しろ」と「白」は同根の言葉であろう。 つまり、古代の日本人には赤(明)・黒(暗)・青(淡)・白(鮮)の色彩名称しかなかったのである。しかし、これでは具体的な物の色を表現し区別するのが不可能。そこで、桜色、桃色、紫色、灰色、水色、空色、萌黄色、朱華色、橙色、柿色など具体的な事物、花などの名を付けてそれに似た色を表現するようになったと見られる。 ということで、真っ赤な嘘とは、決してお猿の尻が赤いという意味での赤ではなく、明白な嘘、はっきりした嘘、ということになる。 「真っ白な嘘(A Little White Lye)」というのは、アメリカのSF作家、F・ブラウンの短編小説のタイトルであるが、「真っ白な嘘」という表現は小生のお気に入りで、随分の大昔に読んだ本にて内容は殆ど記憶に無いのに、このタイトルだけは記憶に残っている。 上記の古代人の色彩区分から言えば、「真っ赤な嘘」という言葉が成立するなら、同じ意味で「真っ白な嘘」という言葉が成立してもおかしくはないように思われる。然るに「真っ白な嘘」が成立しなかったのは、やはり熊楠先生の仰る通り、猿のお尻が真っ赤であって、真っ白ではなかったからなんでしょう(笑)。 「赤っ恥」という言葉があるが「白っ恥」という言葉がないのも、同様の理由であるかどうかは、諸説があって定まらない(笑)。
2017.11.20
コメント(4)
-

夕々の会・葡萄柿
昨日(17日)は大学同期会・夕々(よいよい)の会の日でした。 大学同期と言う場合、それは卒業年次で区分けされる。 大学の場合、留年する人も結構いるので、入学年次が同じでも、卒業年次が異なるということが多く生じる。卒業年次で同期を区分するのは大学側の管理の都合。学生側の意識は入学年次が同じ者の間にこそ「同期」意識がある。 ということで、この「夕々の会」は入学年次を同じにする者の集まりとしたもの。普通に言う「同期会」とは異なる。会社などでの「同期会」というのは入社年次を同じにする者の集まりであるから、それと同じ区分法である。 5月と11月、年に2回夕刻に集まるから「夕々(ゆうゆう)の会」とも言える。「悠々の会」とか「遊々の会」と言ってもいいが、これはまだ現役で頑張っている者もあったりと各人各様であれば、言い過ぎとなるので、今は「夕々の会」と言う訳である。 関西地域に在住する者を中心に集まろうということで始まったのであるが、その時既に東京方面在住者で同様の集まりがあって、その会の名が「よいの会」であったことから、われわれは「よいよいの会」としたもの。 平仮名で「よいよい」というのは足がおぼつかない老人を揶揄して言う言葉でもあるので、漢字で表現しようということになり、「良い良いの会」でも「酔い酔いの会」でも良かったのであるが、「夕々の会」となったもの。 会場は、前回と同じく梅田の「がんこ梅田OS店」。午後5時半集合・開宴。会場は幹事役の守〇君の手配。メンバーへの案内・連絡は、もう一人の幹事役・谷〇君の担当。 今回は18名(守〇君、谷〇君、西〇君、佐〇君、深〇君、黒〇君、岡〇君、道〇君、広〇君、山〇君、小〇君、中〇君、枦〇君、前〇君、古〇君、永〇君、紅一点の大〇さん、そしてヤカモチ)の出席でありました。 永〇君はこの会には今回が初参加。小生は10数年前に同窓会総会に彼が出席してくれた時に顔を合わせているので、それ以来の再会であるが、出席者の中には卒業以来の再会という人も居たようです。豆柿のごとや集へる思ふどち い群れて渋もぬける夕かも(柿渋王)(本歌)新しき年の始に思ふどちい群れてをれば嬉しくもあるか(道祖王 万葉集巻19-4284) 今回は掲載すべき写真もないので、先日(12日)の木津5人組ウオークで見掛けた豆柿の写真を掲載するための、無理矢理の歌であります(笑)。まあ、何にしても楽しく愉快なひと時でありました。 (豆柿 別名:小柿、葡萄柿、信濃柿) この柿は、小生初めて見ました。 一粒の大きさはブドウの一粒、ミニトマト位の大きさである。 すぐ隣に柿を直売している柿農家があり、そこに居られたご婦人に「これは何んという柿ですか?」とお尋ねすると、葡萄柿だと教えて下さいました。 帰宅してネットで調べると、コガキ(小柿)、マメガキ(豆柿)、シナノガキ(信濃柿)とも呼ぶということが分かりました。 猛烈な渋柿であるそうな。上の戯れ歌で友人たちを豆柿に喩えましたが、彼らが渋柿だという意味での譬えでは決してありませんので、誤解なきように(笑)。 東北アジア原産で、日本には柿渋をとるために移入されたとのこと。黒く熟すと甘くなるそうで食べられるらしいですが、赤黒い程度では未だ渋いらしく、その食べ頃の判定が極めて難しそう。まあ、元々が食用でないのであれば致し方なきことにて候。<参考>マメガキ・Wikipedia (同上) マメガキの学名Diospyos lotusは、ギリシャ神話に登場する「ロートスの木」に由来するとのこと。旧約聖書のヨブ記にもこのロートスの木が登場しているというので、手もとにある旧約聖書でその個所(第40章21節、22節)を開いてみた。 口語訳のそれでは「酸棗の木」と訳されているからナツメの一種と考えているよう。一方、文語訳のそれは「蓮(はちす)の木」となっている。<参考>「これ(河馬)は酸棗の木の下に伏し、葦の茂み、または沼に隠れている。酸棗の木はその陰でこれをおおい、川の柳はこれをめぐり囲む。」(口語訳)「これ(河馬)は蓮の樹の下に臥し 葦蘆の中または沼の裏に隠れをる。蓮の樹その蔭をもてこれを覆ひ また河の柳これを環りかこむ。」(文語訳)※レビアタン(リヴァイアサン)と並ぶ怪獣ベヒモスについての記述であるが、ベヒモスはカバやサイやゾウなどをモデルにした巨大怪獣であり、ここでは河馬と訳されている。 ということで、本日の記事は、同期会についての「ハシリガキ」でありました。(参考)夕々の会 2017.5.19.
2017.11.18
コメント(2)
-

第196回智麻呂絵画展
第196回智麻呂絵画展 本日、智麻呂邸を訪問、新作10点の絵画を仕入れて参りましたので、早速に智麻呂絵画展を開催させていただきます。 <参考>他の智麻呂絵画展は下記からご覧になれます。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵アルバム「智麻呂絵画集」はコチラ。 先ずは、ホトトギスの花です。この複雑な造形の花をどんな風に表現されるのか楽しみにしていましたが、見事な絵になりました。 (ホトトギス) 上のホトトギスと下のハクビクジャク2点とナデシコの花は、ひろみの郎女さんがご自宅に咲いていたものを、お届け下さったもの。 ホトトギスとハクビクジャクの花はヤカモチ館長が智麻呂邸を訪問した際に写真に撮り、その写真をご提供しましたので、これらの絵の完成には、ヤカモチも些か寄与しているのでもあります。 と言うのも、ハクビクジャクは一日花。絵を手早く写生しないと直ぐに萎んでしまうからです。写真に撮って置くことで、ゆっくり絵に仕上げることができたという次第。 (白眉孔雀A) (白眉孔雀B) (撫子) 次は、菊二題。菊Aは、ご友人の友〇さんが下さったものです。ふっくらとした可愛らしい菊です。 (菊A) そして、下の菊Bとリンドウは、デイサービスで行かれている福寿苑での催し、お買い物お出掛けタイムで智麻呂さんがご購入されたものです。どちらも素敵な色合いです。 (菊B) (竜胆) 次のフウセントウワタも智麻呂さんが買い求められたものですが、こちらはご近所のお花屋さんの前を通りかかった際に目に止まっての購入でありました。これは、本日の智麻呂邸でも未だ花瓶に健在でありましたから、一番新しい絵かもしれません。 (風船唐綿) コスモスは、取材不足で出処不明。ご近所の道の辺に咲いていたものを写生されたのかもしれません。 (コスモス) 今回は縦長タイプの絵が10点中8点と多く、ブログでの展示は横長の絵の方が収まりがいい処、縦長の絵が続き、ヤカモチ館長としては、2枚を並列して展示するか、1枚単独で展示するか迷いましたが、スマホでご覧になる方も居られるようなので、2枚並列では、スマホ画面では、上下に少しずれた表示になることから、1枚単独展示と致しました。 さて、最後は、岡山土産の「備前黒牛・牛肉と野菜のしぐれ煮」の絵であります。当ブログのご常連さんは先刻ご承知のことでありましょうが、ヤカモチ館長の岡山銀輪散歩の旅のお土産であります。 花より団子ならぬ、花よりギューと言うお方はご試食召されて下さいませ。 (備前黒牛しぐれ煮) 以上です。本日もご来場、ご覧下さり、ありがとうございました。
2017.11.15
コメント(10)
-
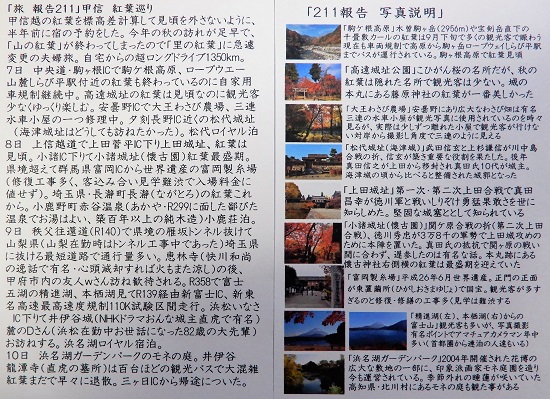
岬麻呂旅便り211・甲信紅葉巡り
友人・岬麻呂氏からの旅便り211号が届きました。 今回は11月7日から10日にかけての、ご自宅から長野県・山梨県・静岡県を廻る3泊4日、1350kmの超ロングドライブの夫婦旅であったようです。 旅報告211(下掲)によると、7日:駒ケ根高原~高遠城址~大王わさび農場~松代城址、8日:植田城址~小諸城址(懐古園)~旧富岡製糸場~埼玉県・長瀞~小鹿野町赤谷温泉、9日:恵林寺~精進湖~本栖湖~井伊谷城、10日:浜名湖ガーデンパーク・モネの庭~龍潭寺、という行程であったようです。 (旅報告211) それでは、岬麻呂氏提供の甲信地方の紅葉風景、お楽しみ下さいませ。 (駒ヶ根高原) (高遠城址) 高遠城址の燃え上がるような紅葉、見事です。 (大王わさび農場) (松代城址) (上田城址) 上田城址も小諸城址も、紅葉今盛りなり、です。 上田城と小諸城とは千曲川銀輪散歩で走った際に立ち寄ったことがあるので懐かしいですが、小生が訪ねたのは合歓の花や蓮の花の咲く季節でありましたから、印象がかなり異なります。(参考)千曲川銀輪散歩・岩鼻(2)・上田城公園 2008.7.24. 千曲川銀輪散歩・小諸懐古園 2008.7.25. (小諸城址<懐古園>)<追記>本日(11月16日)のメールで小諸城址の紅葉の写真を1枚追加で送って来て下さいましたので、追加掲載させていただきます。(冒頭の「211報告 写真説明」に記載の「懐古神社右側横の紅葉」がこれです。) (同上) (旧富岡製糸場) 世界遺産になって富岡製糸場も観光客が増えているのでしょうが、「修復工事多く、客混みあい、見学難渋で入場料金に値せず。」と岬麻呂氏の辛口評。 下仁田と高崎を結ぶ上信電鉄上信線の中ほどに富岡はあるのだが、この線の電車は自転車を輪行バッグに収納することを必要とせず、そのまま自転車を車内に持ち込める電車だと聞いている。 そんなこともあって高崎~下仁田をいつか銀輪散歩したいものと思っている小生であるが、富岡製糸場などもその際の立ち寄り先候補に当然なるところ、かかる評を聞くとパスする方がいいのかと思ったりも(笑)。 (精進湖) そして、富士山。富士山が入ると風景はそれだけでもう一つの景色となってしまうのは、流石であります。 (本栖湖) (モネの庭) この後、龍潭寺に立ち寄られたようですが、観光バス100台ほども来て大混雑で、早々に退散されたとか。NHK大河ドラマの威力恐るべしでありますな。こういう時期には行かないのが得策のようです。彦根の龍潭寺も同様なことになっているのでしょうか。何にしても超ロングドライブお疲れ様でございました。銀輪ヤカモチには真似のできぬ旅にて候(笑)。<参考>岬麻呂旅便りの過去記事はコチラから。
2017.11.14
コメント(4)
-

5人組木津ウオーク本番
今月2日の下見の記事・「木津5人組ウオーク下見銀輪散歩 2017.11.3.」で紹介した友人たちとのウオーク本番が昨日12日でした。午前10時半木津駅集合。メンバーは草麻呂、鯨麻呂、蝶麻呂、健麻呂と偐家持の5名。今年の春以来の5人組ウオークである。(参考)5人組ウオーク本番・王寺から大和郡山まで 2017.4.1. 定刻前に全員集合し、出発。今月2日の下見の際と昨日12日本番に撮った写真とを織りまぜつつ記事アップします。 先ず大智寺へ。この寺は木津八幡嵐山自転車道の起点である泉大橋のほとりにある。この自転車道は何度も銀輪で走っているので、寺の存在は知っていたのだが、訪問することはなかったので、今回のウオークの下見の折が初訪問、本番の今日が二度目の訪問ということになる。 (大智寺・2日) (同上・2日) 下見の日は、秋の特別公開の期間中で、見学者も居ましたが、それ程大勢でもなかったので、上の写真のように人影のない写真を撮影することができましたが、本番の昨日は、その特別公開の期間は終了していたのに、団体さんと鉢合わせとなって、狭い境内は人で溢れそうな状態でした。 (同上・12日) 人物が入っている写真は顔などを塗りつぶして誰とは分からぬように加工しなければならないので、ブログ写真としては有難くないのであるが、仕方なきことにて候。右側でこちらを向いている若いお嬢さんなどはなかなかの美人であったので顔を塗りつぶすのは勿体ないことでありましたが、不特定多数に公開するブログ写真とあっては、ご本人のご了承も得ずに掲載する訳には参らぬという次第(笑)。 大智寺から和泉式部墓へと向かいますが、その前にコース概略を地図上に表示して置きましょう。 (コース概略図)木津駅~大智寺~和泉式部墓~平重衡首洗い池~安福寺~御霊神社~西念寺~鹿背山城跡(昼食タイム)~鹿背山不動尊~大仏鉄道遺構(梶ヶ谷隧道・赤橋)~梅谷区公民館(珈琲休憩)~岡田国神社~木津駅 (和泉式部墓のある寺・2日) この寺・お堂の名は知らない。このお堂の裏に和泉式部の墓がある。何度か立ち寄っているので、ブログ記事にとり上げているもと思い、過去記事を調べてみましたが、見当たらない。どうやら、小生の思い違いで、この墓は記事にしていなかったよう。そのような思い違いもあって、これまでの何度かの立ち寄りの際にも記事にとり上げずにいたようです。 (同上・2日) (和泉式部墓この奥の碑・2日) (和泉式部墓・12日) 和泉式部墓は全国各地に多数あるようですが、滋賀県大津市坂本のそれと兵庫県伊丹市のそれとは、当ブログでも紹介済みである。(参考)日吉大社など坂本散策 2011.8.27. 宝塚・伊丹銀輪散歩(その3) 2014.2.6. このように和泉式部墓やその所縁の地が各地にあるのは、和泉式部のことを語り物にして、全国をめぐる女性の芸能集団があったことによると見られている。そのような女性のうちに行った先の土地に住みつく者もあり、土地の人は彼女らを和泉式部と同一視したり、その呼び名を和泉式部としたりした結果、彼女らと和泉式部との混同が生じ、彼女らの墓が式部の墓とされてしまう、彼女らの立ち寄り先が式部の立ち寄り先とされてしまう、というようなことがあった所為ではないかと言う訳であります。 この女性集団は京都・誓願寺に属する集団であったと見るのが柳田國男の見解。 (和泉式部墓説明碑・2日) 伝承では、娘の小式部内侍を亡くして悲しみ、苦しんだ和泉式部は誓願寺にて出家し尼となり、寺の域内に庵を構えて念仏の日々を送り、ここで亡くなったとのこと。その庵は藤原道長が彼女のために建ててあげたもので、それが今日の誠心院になっているとか。9月に京都を銀輪散歩した際に、誓願寺と誠心院にも立ち寄っていて、その折の写真がありますので、余談ですが、以下にこれを掲載させていただきます。 (誓願寺) (同上説明碑) (同上) (同上・阿弥陀如来坐像) (扇塚) (同上・扇塚の由来) 誠心院は誓願寺の南、新京極通りの商店街に面してあるので、うっかりすると気付かずに通り過ぎてしまいかねない。 (誠心院) (同上・和泉式部墓) (同上説明碑) (誠心院境内配置図) 今年9月に訪ねた時は本堂が工事中で、工事用足場が建物の周囲を取り囲んでいたので、写真には撮らずでした。本堂前に和泉式部の歌碑。霞たつ春きにけりとこの花を見るにぞ鳥の声も待たるる(和泉式部続集1071) 和泉式部続集のこの歌の題詞には「梅の花あるを見て」とあるが、和泉式部が愛したという「軒端の梅」を詠んだものであるのでしょう。勿論、鳥は鶯である。 (同上・和泉式部歌碑) (和泉式部と誠心院) 木津5人組ウオークから横道に逸れましたが、本題に戻ります。和泉式部墓から、来た道を取って返し、平重衡首洗い池・不成柿へと向かいます。 2日の下見の時と同様、鈴なりに実をつけている「成らずの柿」を見て、友人たちも笑っていました。下見の記事では首洗い池そのものの写真は掲載しませんでしたので、これを掲載して置きます。 ご覧のように「池」と言うも烏滸がましい「水たまり」である。草を引き抜くなどして、もう少し水面がよく見えるように手入れした方がいいのではないだろうか。 (平重衡首洗池・12日) そして、重衡墓とも言われている十三重石塔の重衡供養塔を見るべく安福寺へ。 (安福寺・2日) この日の安福寺は、特別公開も終了していて、人影はなく静かであった。かくて、漸く平重衡供養塔の撮影もできたという次第。 (平重供養塔・12日) さて、これも余談になりますが、重衡は鎌倉に送られる前に、法然上人に戒を授けられている。その授戒之地碑なるものが京都駅の近く堀川通に面した場所にある。一昨年の5月18日、蕪村関連の場所を巡る銀輪散歩の際に偶然に出くわして撮影したものでありますが、参考までに以下に掲載して置きます。 (平重衡授戒之地碑) (同上副碑) 安福寺の東側の御霊神社に立ち寄る。立派な構えの神社。 (御霊神社・2日) (同上拝殿・2日) (同上本殿・2日) 御霊神社から西念寺へはJR関西本線に並行する県道47号北東方向に進む。西念寺へと向かう分岐の手前で「鹿背山の柿直売所」なるものが店を開いていて、何人かのお客さんの人影。それにつられた訳でもなかろうが、我々の足もそこで停まる。冷やかすだけの心算であったが、大きな柿がひと盛1000円。鯨麻呂氏と小生は家づとにこれを買い求める。 分岐の坂道を上り、西念寺への道を辿る。2日の下見で工事中通行止めであった区間は未だ工事中で通行止めのまま。大きく迂回して行く。 (西念寺への道・12日) この道を下った処が鹿背山会館。 そこから坂道を上って、突き当りが西念寺。 (同上・2日) (西念寺・2日) (同上本堂・2日) 西念寺到着は正午を少し過ぎた位。鹿背山城址まで上って、山頂の城址でお弁当タイムということにする。食後、鹿背山城址碑の前で、健麻呂氏のデジカメで全員の記念撮影。 山を下る。下まで降りてくると、クロスバイクの青年が居て、城址まではどれ位かかるかとの質問を受ける。15分もあれば行けるでしょう、と説明して置く。実際は10分位で行けるかも。 坂の登り口まで下った辻で左折、南東方向に進む。途中で葡萄柿というミニトマトやブドウの粒位の大きさの、珍しい柿に出会う。これも撮影しましたが、これは別途の記事で後日また紹介申し上げます。<追記>葡萄柿の写真掲載記事はコチラ。(2017.11.18.) 地蔵堂のような小さな祠のある辻で右折し南へ。ゆるやかな下り坂。下り切ると一気に視界が広がる場所に出る。これを左に行くとJR関西本線をまたぐ橋の上に出る。不動山トンネルである。 (JR関西本線・不動山トンネル・2日) トンネル前を過ぎた付近に古い石標。鹿背山不動・稲荷への道標である。 (鹿背山不動への道標・12日) 振り返るとこんな景色。 (不動山トンネル付近・12日) そして、ここで左に入ると鹿背山不動尊である。 (鹿背山不動への道・2日) (鹿背山不動尊) 山門に記帳のためのノートが1冊置いてあるだけの、誰とても人影も無き静もれる小さな寺である。 (同上・2日) (同上・2日) 鹿背山不動から美加ノ原カントリークラブの正面入り口の前を通り、大仏鉄道遺構の梶ヶ谷隧道、赤橋を見て行く。 (大仏鉄道遺構・梶ヶ谷隧道<北側から>・2日) (同上・説明板・2日) (同上<南側から>・2日) (同上・2日)ほろびたるものに名残れる品格をそれ美しと人は言ふなり (偐家持) (同上・2日) (大仏鉄道遺構案内図・2日) (同上・赤橋・2日) (同上説明板・2日) 大仏遺構を巡る小径から広い道路に上がって来ると、城山台団地という大きな団地が道路の北側に広がっている。 (城山台団地の公園・2日) (同上公園から不動山を望む・2日) 広い道路は、木津芳梅園という老人ホームを過ぎた辺りから狭くなり、梅谷へと下り坂となる。日も傾き、影が長くなりつつある。 (梅谷へと下る友人たち) (梅谷付近・2日) 梅谷で道は県道44号に出会う。その角にあるのが、梅谷区公民館。古い建物で何と言うほどではないのだが、何やら郷愁を誘う風情がある。 (梅谷区公民館・旧木津小学校梅谷分校建物・2日) 草麻呂氏が建物の入口近くまで様子を見に行かれて戻って来られました。「珈琲が飲めますよ。一杯200円だそうです。」とのこと。 今日は収穫祭とかで、地元の若いお母さん方が、近くで農家から田圃を借りて子供たちと一緒に育て収穫したお米で、ご飯を炊き、皆でこれを食べるというような催しがあり、それが終わって一段落した処だとのこと。それはともかく、200円で珈琲とは有難いことなので、ここで暫し珈琲休憩とする。 そのお母さんたちに教えていただいたのであるが、この建物は、元は木津小学校梅谷分校の校舎であったそうな。別の場所にあったものを廃校となるに伴い、この地に移築し、公民館として、地域の活動の拠点として利用しているのだという。言われてよく見ると壁に木津小学校校歌の歌詞が書かれた額が掲示されていました。 梅谷からは井関川を挟んで県道44号からの道と並行して歩行者・自転車専用道がある。これを行く。川には沢山の鴨が居て、我々が近づくと一斉にバタバタと飛び立つ様もなかなかに楽しい景色でありました。 そして、最後の立ち寄り先の岡田国神社に向かう。この神社はJRの線路際にあるので、線路をまたぐ跨線橋が参道となっている。この神社は今年の3月に中学校の同級生と立ち寄っていてブログ記事(下記参考)で紹介済みなので、当記事では省略させていただきます。(参考)高の槻群 2017.3.10. (岡田国神社・12日) 岡田国神社から木津駅まで歩き、当駅で解散。 小生は、帰る方向が同じの健麻呂氏と近鉄生駒駅まで一緒に帰り、生駒駅で彼と別れました。帰宅した頃はすっかり日も暮れてしまっていましたが、心地よき疲れなるかなでありました。
2017.11.13
コメント(6)
-

中学時代の級友との大宇陀万葉ウオーク下見
今月26日雨天でなければ、中学時代の級友男女8人で榛原・大宇陀方面を万葉ウオークすることになっている。コース選定と案内が小生の担当。ということで、昨日9日、コースの下見をして参りました。お弁当持参方式としたので、適当な昼食場所の探索と、コースの確認、途中でのトイレの場所の確認などが目的の下見である。 午前10時5分頃に近鉄榛原駅到着。先ず持参の折りたたみ自転車トレンクルを組立て、駅前のコンビニでお弁当とお茶を買って出発。 予定コースは次の通り。榛原駅~榛原小学校前の墨坂万葉歌碑~(榛原駅前経由)~榛原フレンドパーク~榛原西小学校校庭の猟路池遊猟万葉歌碑~蓮昇寺境内の池上万葉歌碑~八咫烏神社~県道217号経由内原へ~(うだアニマルパーク※昼食場所に適当であるが時間がうまく合うかどうか)~松山西口関門~大宇陀地域事務所前庭の万葉歌碑~阿紀神社(万葉歌碑)~かぎろひの丘(万葉歌碑)~人麻呂公園~(余裕があれば神楽岡神社境内の万葉歌碑)~道の駅宇陀路大宇陀~バスで榛原駅前 当初は5~8km程度の軽いウオークを企画する心算であったが、参加希望者の内の一人が「かぎろひの丘」を要望されたので、それで企画すると、どうしても15km程度にはなってしまうのでありました。参加者の脚力の程は、今回が初めての実施にて不明。場合によっては、復路だけでなく往路も一部バス併用を考えましたが、日曜日のバスの便は少なく、うまく行くかどうかも不明。まあ、何とかなるかと見切り発車です(笑)。 最初に立ち寄るのは墨坂万葉歌碑。これは、駅から南方向へと歩くかぎろひの丘への道とは反対側、駅の北方向にあるので、割愛することも考えられるが、一応、立ち寄り場所にして置きました。 (墨坂万葉歌碑) 君が家(いへ)に我が住坂(すみさか)の家道(いへぢ)をも われは忘れじ命死なずは (人麻呂の妻 巻4-504)<あなたの家に私が住むという住坂を越えて通う家路を私は忘れない、命のある限りは。>(注)女性が男性の家に通うのは不自然なので、「妹が家に」という句が「君が家に」と間違って伝承されたもので、作者は人麻呂だという説もある。 再び、駅前に戻り、宇陀市役所の前を通り、その先の宇陀川と芳野川とが合流している地点に架かる橋を渡り、芳野川沿いの道を行く。小生は今まで芳野川を「よしのがわ」と読んでいたが、今回「ほうのがわ」と読むのだと初めて知りました。榛原フレンドパークの西側でその芳野川を渡る。 (榛原西小学校への道 奥に見えている白い建物が校舎) (榛原西小学校校庭の万葉歌碑・長皇子猟路池遊猟歌)大君は神にしいませば真木(まき)の立つ 荒山中(あらやまなか)に海をなすかも(柿本人麻呂 巻3-241)(訳)我が大君は神でいらっしゃるので、立派な木の立ち茂る、ひと気もない山の中にも海をお作りになることよ。 この歌は、長皇子(天武天皇と大江皇女の間の子)が「猟路の池に遊びし時に、柿本人麻呂の作りし歌」とある長歌の反歌である。こちらは「或る本の反歌1首」というもので、本来の反歌は次の歌。 お月様を傘にしているという大袈裟な、いや大傘な(笑)、いかにも人麻呂的比喩の歌である。 ひさかたの天(あま)行く月を網に刺し 我が大君は蓋(きぬがさ)にせり(同 巻3-240)(訳)(ひさかたの)大空を行く月を網でとらえて、我が大君はきぬがさにしておられる。 歌碑裏面にはその長歌が刻されているが、笹が生い茂っていて全ては見えない。 (同上裏面) 榛原西小の前の坂道を下って行くと芳野川に出る手前の右手奥に神社が見えたが、そのまま走り下る。二本杉橋を渡って芳野川沿いの県道31号を南へ。先程見かけた神社と川を挟んで向き合うようにして二本の杉の木。三十八神社拝所とある。上流側の宮橋を渡って三十八神社に立ち寄ってみることに。この神社は立ち寄り予定先には入っていないが、行きがけの駄賃である。 (三十八神社) この神社の主祭神はミヅハノメノカミ・彌都波能売命(罔象女神) である。記紀ではイザナミノミコトが火の神カグツチを産んで死ぬ時に彼女が産んだ神の一つである。水の神、五穀豊穣の神である。 罔象は水神また水中の怪物。淮南子、氾論訓の注に「水ノ精也」、荘子、達生に「水ニ罔象有リ」とあり、荘子釈文によると、罔象は「状ハ小児ノ如ク、赤黒色、赤爪、大耳、長臂」であるという。罔は、形を隠して見えない意。ミツハのミツは水、水は古くは清音ミツという形もあったらしい。<岩波文庫・日本書紀(一)39頁注記より> 三十八神社という名の通り、主祭神に種々の神々合わせて38柱が祀られている。創建は、平安時代後期、応仁2年(1162年)6月18日と伝えられているとのこと。 (同上・本殿) 芳野川対岸にある遥拝所の二本杉については、空海がこの地で弁当を食べ、その時に使った箸が芽を出して二本の大木になった、という伝説があるとのこと。何処かで最近耳にした話と思えば、今年9月に三雲城址への銀輪散歩をしましたが、その際に通過した大沙川隧道の傍らにあった弘法杉にまつわる伝説と同じであったのでした。(参考)三雲城址、野洲川、琵琶湖銀輪散歩(その1) 2017.9.7. これは全国各地にある二本杉についての伝説のお決まりのパターンなのでしょう。 (二本杉・三十八神社遥拝所) 二本杉から芳野川沿いに1.5kmほど上流に行き、右脇道に入ると蓮昇禅寺という寺がある。この寺の境内にも万葉歌碑がある。 (蓮昇禅寺)池神の力士舞(りきじまひ)かも白鷺の 桙(ほこ)啄(く)ひ持ちて飛び渡るらむ (長意吉麻呂 巻16-3831)(訳)池神の力士舞かなあ。白鷺が桙をくわえて飛び渡っている。(注)伎楽の力士舞。桙をうち振るって外道の崑崙を降伏させる力士の舞。 (池上万葉歌碑) 意吉麻呂さんは即興で歌を作る名人であったらしく、宴会などでは、あれとこれとを入れて歌を詠めなどと要望されて、即興歌を詠んで皆を楽しませていたようだが、上の歌もそうした即興歌の一つ。宴席で誰かから「力士」と「白鷺」を歌に詠めというリクエストがあり、これに応えて詠んだ歌かもしれない。 このような歌は言葉遊びであるから、歌そのものに深い意味などはない。「何のこっちゃ」という歌であるが、寄席の大喜利のようなもので当意即妙、機転を楽しむ遊びであるから、我々もそのようにしてこれを楽しまなければならないということになる。 (蓮昇寺境内 本堂と鐘楼 左端に少し写っているのが万葉歌碑) 蓮昇寺の前の道を南へ200mほど行くと八咫烏神社である。この神社は2011年1月7日の記事で紹介しているのでパスします。本番では立ち寄る予定ですが、今回は前を素通りです。(参考)かぎろひの丘銀輪万葉(その1) 2017.1.7. (八咫烏神社) 八咫烏神社から脇道伝いに300mほど行くと東西に走る県道217号に出る。これを右折、西に進む。ゆっくりとした上り坂。歩程を測ってみようとこの部分は自転車には乗らず押して歩いてみる。出発11:42、終点の内原到着が12:07。徒歩で25分かかった。 (県道217号を行く) (同上) 坂を登り切ると急な下りに入る。自転車で走り下りたいところであるが、歩きの場合の所要時間の見当をつけるのが目的であるから乗る訳にはいかない。歩き続ける。宇陀川に突き当たる。両岸に道があるが、右岸の道は歩道・自転車道のよう。これを行く。勿論、銀輪にてである。しかし、400mほどで橋があり、その先は右岸の道はない。橋を渡って左岸の道(一般道)を行くしかないかと思いつつ、前方を見るとうだアニマルパークである。広い舗装道路が左手に丘へと通じている。こんな公園いつ出来たのだろうと思いながら、この丘の上の公園でお弁当タイムにするかと行ってみる。結構な坂道であるが、舗装されているので走りやすい。 (うだアニマルパーク) 入口近くの高みにあるあずま屋に行き、眼下に居る2頭の乳牛を遠望しつつ昼食とする。少し風が強いが本番当日の昼食場所としては合格かも。 (同上) (同上) 昼食後、再び宇陀川沿いの道に戻り、上流へ。 (松山西口関門) 松山西口関門を過ぎ、大宇陀高校の先の辻で右折、西へ。 国道166号に出る。コンビニ・セブンイレブンの先、大宇陀地域事務所の前庭にある万葉歌碑に立ち寄って行く。 (阿騎野遊猟歌万葉歌碑・大宇陀地域事務所前庭)日並(ひなみし)の皇子(みこ)の尊(みこと)の馬並(な)めて 御猟(みかり)立たしし時は来(き)向(むか)ふ(巻1-49)(訳)日並皇子の尊が馬を並べて狩に出られた時刻に、今なろうとしている。(注)日並皇子=日(天皇)と並んで天下を治める皇子の意。ここでは草壁皇子を指す。 (阿紀神社) セブンイレブンと大宇陀地域事務所との間の細道を入って、阿紀神社へと向かう。 阿紀神社境内にも万葉歌碑がある。 これらの歌碑の歌は「阿騎野遊猟歌」と呼ばれる柿本人麻呂の長歌の反歌である。後の文武天皇である軽皇子が皇太子となる前、まだ数えで10歳の少年であった時、692年(持統6年)11月に阿騎野に舎人たちを従え、遊猟するのであるが、この時これに随行した人麻呂が詠んだ一連の歌である。 (阿紀神社境内万葉歌碑) 日がまだらに射している歌碑はうまく撮影できない。せめても文字が読み取れるようにと自身の体で日陰を作り、撮影した写真がこれ。 (同上)阿騎の野に宿る旅人うちなびき 寐(い)も宿(ぬ)らめやもいにしへおもふに(巻1-46)(訳)阿騎の野に仮寝をする旅人は、くつろいで眠ることができようか、往時を思うと。(注)うち靡き=「うち」は接頭語。「身体を伸ばして横たわって」の意。いも宿らめやも=反語表現。「い」は睡眠。「ぬ」は寝る意。「らめ」は現在の事態を推量する助動詞「らむ」の已然形。「やも」は已然形を受けて反語になる。 (人麻呂公園) 阿紀神社から主目的のかぎろひの丘に回るが、これは当記事ではパスです。本番の記事に残して置きましょう。かぎろひの丘から人麻呂公園に回る。本番まで待てないというお方は下記参考記事をご参照下さい。(参考)かぎろひの丘銀輪万葉(その2) 2017.1.8. 人麻呂公園から道の駅へ。 ここが本番ウオークの終点。ここからバスで榛原駅前まで戻る計画になっている。 (道の駅宇陀路大宇陀) ここには足湯もある。ウオークで疲れた足を足湯で癒すのも一案である。上の写真の建物の左側の小屋、青い軽自動車の向こうに葭簀が掛けられている建物が足湯の小屋である。定員は10数名くらいだろうか。無理すれば20名くらいまで入れるのでしょうか。 さて、メンバーに元気が残っていてバスの時間にも余裕があるのであれば、立ち寄ってもいいということにしている、神楽岡神社の万葉歌碑も見て行くこととします。 (神楽岡神社参道、奥右側が長隆寺、左側が法正寺) (神楽岡神社) (同上・本殿) (神楽岡神社境内万葉歌碑) 真(ま)草(くさ)刈る荒野(あらの)にはあれどもみち葉の 過ぎにし君が形見(かたみ)とぞ来(こ)し(巻1-47)(訳)芒や萱の生い茂った荒れ野ではあるが、もみじ葉が散り落ちるようにお亡くなりになられた日並皇子の形見の地としてやって来たことだよ。(注)真草刈る=「荒野」の枕詞。「ま」は「み」と同じ美称の接頭語。芒や茅などの草を指す。もみち葉の=「過ぎ」の枕詞。過ぎにし君=亡くなった君。日並皇子(草壁皇子)を指す。形見とぞ来し=「ぞ」は強意の係助詞。ぞが係ると連体形で結ぶ。(神楽岡神社境内からかぎろひの丘方面<西北西方向>を望む。) これで、全ての立ち寄り予定先とコースの確認が終了したので、あとは気ままに思いつくままに銀輪散歩し、概ねやって来た道を銀輪で榛原駅前まで。 (八坂神社) (同上) (八坂神社付近からの眺め) (県道31号沿いの紅葉) 榛原駅前帰着は午後2時45分。帰途は概ね下り坂ということで、たちまちに駅前到着、思ったよりも短時間で下見完了でありました。本番の26日の好天気を祈りつつ家路に。
2017.11.10
コメント(6)
-

囲碁例会・小雨の銀輪散歩
今日は囲碁例会の日。天気予報では正午までは小雨、その後は曇り。自転車で行くか、電車で行くか、悩ましい処であったが、合羽を着用してMTBで行くことに決める。雨の降り具合を様子見していたこともあって、いつもより遅い出発となりました。出掛ける支度をしていると、11時01分、利麻呂氏より「今日はどうするのか。」という電話が入る。「今から自転車で出掛けようと思っている。」と申し上げると、同氏も「出席する。」とのこと。既に11時を過ぎているので、自転車では梅田スカイビル到着は12時半位になってしまう。昼食はそれぞれ別で適宜に済ませることとし、会場で会いましょうということに決まる。 (大阪城公園) 大阪城公園に入った頃は、雨も小止みになっていて、傘が要らない程度の降り。先週よりも紅葉はかなり進んでいました。靄っている景色も風情があっていい。一人歩きの若い女性(上の写真に小さく写っている人物)が堀端で写真を撮って居られたので、小生もつられて撮影。 (同上) 紅葉した桜と靄っている遠くのビルとが織りなす堀の景色に見惚れていると、12時04分、電話の着信。福〇氏からであった。「今日は出席するのか」という電話であった。「今、大阪城公園まで来ている。」と申し上げると、では、これから自分も出ることにする、という話。竹〇氏、村〇氏、平〇氏から欠席するという電話があったので、小生の出欠の如何を尋ねて来られたという次第。碁ばかりは、打つ相手が居なければ話にならない。 (同上) 今日は、久々に「れんげ亭」でお昼にするかと思ったものの、店は「支度中」の表示で閉まっている。この処、「支度中」が続いているので、ちょっと心配な気も。或は、お昼の営業は中止されたのだろうか。帰り道でも店の前を走ってみたが、やはり「支度中」のまま。まあ、夜の営業開始時間には未だ早過ぎる3時半頃の時間帯であったので、これは「支度中」でも不自然ではない。 結局、今日の昼食場所は毎日新聞社ビルの1階にあるオキシゲン(Oxygen)ということになりました。昔はオリオンだったと記憶するが、何年か前に現在の名前に変っている。ランチ&珈琲の後、梅田スカイビルまで更に一走りで12時48分にスカイビル到着でした。 会場の部屋に行くと、既に福〇氏と利麻呂氏が碁を始めて居られました。始まったばかり。暫し、観戦。終了後、福〇氏と2局打ち、1勝1敗。まあ、いい別れ。よって、今年の通算成績は23勝24敗で、借金一つは変わらず。借金返済は来月に持ち越しとなりました(笑)。 帰途は、予報通りに雨も止んで、雨具の着用も不要。途中、布施駅方面に回り、ヒバリヤ書店に立ち寄る。次回読書会の課題図書が、祥麻呂氏からのご提案で、今年のノーベル文学賞受賞の作家カズオ・イシグロ氏の「日の名残り」(ハヤカワepi文庫)と決まったので、それを買い求めるための回り道である。ついでに、2冊買い、1冊は智麻呂邸に立ち寄り、恒郎女さんにプレゼントして置きました。 以上です。
2017.11.08
コメント(6)
-

和束茶源郷まつりに行って来ました。
本日は、喫茶・ペリカンの家の女主人であり、ブロ友でもあるももの郎女さん(ブログのハンドルネームは「☆もも☆どんぶらこ☆」さん)のお誘いで、「和束茶源郷まつり2017」に行って参りました。中学の同級生でもあり、ブロ友でもあるひろみの郎女さん(ブログのハンドルネームは「ひろみちゃん8021」さん)も参加の予定でしたが、法事と日程が重なってしまい、残念ながら不参加となりました。また、ももの郎女さんのご友人の「越の郎女さん」(これは、小生が勝手に付けた呼び名)も体調を崩され不参加となりましたので、参加者は、ももの郎女さん、そのご友人の「美加の郎女さん」(これも今回、小生が勝手に付けた呼び名)、それに、小生の友人の利麻呂さんご夫妻と小生の計5名となりました。 午前10時出発ということで、それまでにペリカンの家に集合。小生は利麻呂氏の車に同乗、美加の郎女さんはももの郎女さんの車に同乗、ほぼ定刻に出発。第二阪奈で宝来ランプ経由、国道308号、二条大路から国道24号に入り、泉大橋を渡って、木津川沿いの国道163号を行き、加茂から和束川沿いの府道5号を白栖橋まで、というコース。美加ノ原付近を走って行くコースにてあれば、美加の郎女さんがご一緒というのも語呂が合っていてよろしい(笑)。 茶源郷まつりの会場は白栖橋を渡って左の活道ヶ丘公園であるが、近くの駐車場は満車、或は関係者専用となっていて、誘導係の人から地図を渡され、かなり先の臨時駐車場となっている和束小学校の運動場へ行けと指示される。和束小学校から会場前まではシャトルバスが出ていて、ピストン輸送してくれていました。そんなことで和束茶カフェに着くのに、かなりの時間を要しましたが、ともかくも到着。 (和束茶カフェ前) (同上 背後に見えているのが、通称「太鼓山」の安積皇子墓) 先ず、皆で安積皇子墓へ向かい、ご挨拶申し上げることにする。安積皇子は聖武天皇の息子。母は県犬養広刀自で藤原系ではなかったため、聖武天皇と光明皇后(藤原不比等の娘)との間の娘・阿倍皇女が女性ながら皇太子に立てられていたので、次の天皇は阿倍皇女(後の孝謙天皇・称徳天皇)と決まっていたようなもの。しかし、女性天皇は男子の天皇が諸般事情により誰と決め難い場合の「繋ぎの」天皇。安積皇子が有力な皇位継承者であることに変わりはなかったろう。そのような状況の中で、天平16年(744年)閏正月の聖武天皇の難波行幸に随行していた安積皇子はその途上の桜井頓宮で病にかかり、同月11日に恭仁京に帰って養生することとなる。大伴家持は安積皇子の内舎人であったから、彼も安積皇子に同行したと思われる。 ところが翌々日の13日に急死してしまう。藤原氏にとっては邪魔な存在であったと見られるので、その不自然な死に方から、恭仁京の留守居を任されていた藤原仲麻呂に毒殺されたのではないかという説もあったりする。 時に安積皇子17歳。余りにも若過ぎる無念の死である。大伴家持も安積皇子こそは将来天皇になるべき人物と期待していたに違いないので、大いなるショックを受けたことと思われる。皇子の死を悲しみ長歌2首、短歌4首を詠んでいることからもそれが覗える。時に家持27歳である。 (安積皇子墓) (同上) 上2枚の安積皇子墓の写真は本日撮影のものではなく、2014年11月26日の当ブログ記事に掲載の写真の再掲載です。同年11月23日に銀輪散歩で立ち寄った際に撮影したものであります。ここで、皆さんに安積皇子のことや家持作の歌のことなどについて簡単に説明申し上げることとしました。予め、皆さんには小生作成のレジメをお配りしていたので、それを参照しながらの説明でした。レジメは末尾に掲載して置きますので、興味ある方はご参照下さい。 和束茶カフェ前に戻り、ももの郎女さん・美加の郎女さん達とはひとまず別れ、利麻呂ご夫妻と小生は、活道ヶ丘公園の一角で、ももの郎女さんが手配下さったお寿司のお弁当で昼食。食後、茶畑の小生お薦めビューポイントへご夫妻をご案内する。 (茶畑ビューポイント) 再び、和束茶カフェ前まで戻り、ここで利麻呂夫人は足を休めるということで、会場の活道ヶ丘公園内をぶらぶらされることになり、利麻呂氏と小生は白栖橋を渡った反対側の奥にある正法寺へと向かう。 和束には小生は何度か来ているが正法寺は存じ上げぬ寺でありました。今回のためにももの郎女さんが作って下さった栞の末尾に「安積親王の菩提をとむらうため行基が創建したと伝えられる寺」と正法寺が紹介されていて、その存在を知ったという次第。 (正法寺) なかなか風情のあるお寺です。 (同上) 山門は修理工事中でした。 (同上) (同上) (境内の銀杏の大木) 境内の大銀杏は美しく色づいて、日に輝いていました。 脇参道にあったカラタチの古木も目をひきました。 (同上・カラタチの木) さて、会場に戻って、利麻呂夫人と合流。ももの郎女さんもご一緒でした。 (茶源郷まつりメイン会場) (会場マップ・茶源郷まつり2017パンフレットより) (同上) ももの郎女さんが予約していて下さった「天空カフェ」に午後2時半集合。天空カフェは活道ヶ丘公園のひと際高い所に設けられた茶カフェで、定員は7名。予約制で30分貸切で利用できる。お茶を淹れていただき、お茶菓子をいただき、お茶の色々な事をご説明いただきながら、お茶が楽しめ、外の眺望も楽しめるというスペース。 (天空カフェ) 利麻呂ご夫妻と小生の3人は少し早く、天空カフェ前に到着したので、先客のグループのそれが終わるまで、また、ももの郎女さんと美加の郎女さんの到着を待ちながら、高所からの景色を楽しんでいました。 するとそこへ、地元のご年配のご婦人と京都からという30歳の青年が相前後してやって来られました。この天空カフェが予約制とは知らずやって来られたよう。貸切制なので、入店は無理と断られていました。 幸い、我々は5人なので、よろしければ我々とご一緒下さってもいいですよ、と申し上げて、お二人もご一緒することに。間もなくももの郎女さん、美加の郎女さんが来られて、天空カフェ・ティーセレモニー。 お茶を淹れて下さるのは、木津高校でお茶のことを教えて居られる男性の先生とその教え子の女子高生。一番煎じ、二番煎じ、三番煎じ・・とそれぞれに微妙に違う味わいの玉露を、色々とご解説付きで頂戴しました。吉田麻呂殿と佐用姫殿、ヤカモチが付けたご両名のあだ名です(笑)。 万葉集では、大伴家持に「鰻とり召せ」とからかわれたのが吉田石麻呂であり、沖行く大伴狭手彦に「帰れ」と領巾を振ったのが松浦佐用姫であるが、勿論、これらの歌とご両人とは何の関係もない。 (天空カフェからの眺め) 高所にあるだけに、眺望は頗るよろしい。 (同上) 茶源郷まつりのメイン会場も眼下に見える。 (同上) もう少しアップで撮影してみましょう。 (同上) 天空カフェから地上に舞い降りて、さてどうするか、ということになり、我々、利麻呂ご夫妻と小生ヤカモチとは帰途につくこととする。もう少し現地に残る両郎女さん達とは、ここで解散ということになりました。 帰途も往路と同じコースを取る。途中、恭仁京跡近くを通るので、少し回り道をして立ち寄って行くこととしました。 水走交差点手前、西石切で車から降ろしていただき、トランクに積ませていただいていたわがトレンクルを受け取り、そこから自宅までは銀輪走行で帰って参ったという次第。現地にレンタルサイクルもあると「ももの郎女」さんからお聞きしていたので、もしご夫妻がレンタルサイクルを楽しまれるのであれば、小生はこのトレンクルでお付き合いしようと、トランクに積み込ませていただいていたのですが、駐車場が会場とは随分と離れた場所であり、そこからのシャトルバス移動ではトレンクルを運ぶこともできないので、現地でのサイクリングという選択肢は没にし、ウオークに切り替えたという次第でありました。<追記>掲載字数関係で、写真の一部を除き、拡大サイズ画面とのリンクが出来ませんでしたので、フォト蔵のアルバム「茶源郷まつり2017」のリンクを下記に貼って置きます。 茶源郷まつり2017<追々記>ももの郎女さんも記事にしておられます。 茶源郷まつり 2017.11.5. 天空カフェ 2017.11.6. 以上、茶源郷まつり参加レポートでありました。では、最後にレジメを添付して置きます。<参考> 安積皇子関係の万葉歌●大伴家持による安積皇子への挽歌十六年甲申(かふしん)の春二月、安積皇子(あさかのみこ)の薨(こう)ぜし時に、内舎人(うちとねり)大伴宿禰家持(おほとものすくねやかもち)の作りし歌六首かけまくも あやに恐(かしこ)し 言はまくも ゆゆしきかも わが大君(おほきみ) 皇子(みこ)の命(みこと) 万代(よろづよ)に めしたまはし 大日本(おほやまと) 久迩(くに)の都は うちなびく 春さりぬれば 山辺(やまへ)には 花咲きををり 川瀬(かはせ)には 鮎子(あゆこ)さ走(ばし)り いや日(ひ)異(け)に 栄(さか)ゆる時に およづれの たはこととかも 白(しろ)たへに 舎人(とねり)よそひて 和束山(わづかやま) 御輿(みこし)立たして ひさかたの 天(あめ)知らしぬれ こいまろび ひづち泣けども せむすべもなし(巻3-475)(言葉にかけて言うことも、まことに恐れ多い。口に出して言うことも、憚り多いことよ。我が大君、安積皇子が、万代までお治めになる筈であった、大日本の久迩の都は、<うちなびく>春が来ると、山辺には花が咲きたわみ、川瀬には小鮎が勢いよく泳ぎ、日増しに栄えている時に、人惑わしのでたらめ言とでも言うのだろうか、白い喪服に舎人たちは身を包み、和束山に、皇子の御輿がご出発になって、<ひさかたの>天上界を治めに行かれたので、転び回り、涙まみれに泣くけれど、もうどうにもしようがないことだ。)反歌わが大君(おほきみ) 天(あめ)知らさむと 思はねば おほにぞ見ける 和束杣山(わづかそまやま(巻3-476)(我が皇子が天上界をお治めになるとは、思いもしなかったので、気にもとめずに見ていたことよ、和束杣山は。)あしひきの 山さへ光り 咲く花の 散りゆくごとき わが大君(おほきみ)かも(巻3-477)(<あしひきの>山までも照り映えて咲く花が、たちまち散り行くようにはかなく散って行ってしまわれた、我が皇子さまよ。)右の三首は、二月三日に作りし歌なり。かけまくも あやに恐(かしこ)し わが大君(おほきみ) 皇子(みこ)の命(みこと) もののふの 八十(やそ)伴(とも)の男(を)を 召(め)し集(つど)へ あどもひたまひ 朝(あさ)狩(がり)に 鹿(し)猪(し)踏み起こし 夕(ゆふ)狩(がり)に 鶉雉(とり)踏み立て 大御馬(おほみま)の 口(くち)抑(おさ)へとめ 御心(みこころ)を 見(め)し明(あき)らめし 活道山(いくぢやま) 木立(こだち)の茂(しげ)に 咲く花も 移ろひにけり 世の中は かくのみならし ますらをの 心振り起こし 剣(つるぎ)大刀(たち) 腰に取り佩(は)き 梓(あづさ)弓(ゆみ) 靫(ゆき)取り負ひて 天地(あめつち)と いや遠長(とほなが)に 万代(よろづよ)に かくしもがもと 頼めりし 皇子(みこ)の御門(みかど)の 五月蝿(さばへ)なす 騒(さは)く舎人(とねり)は 白(しろ)たへに 衣(ころも)取り着て 常(つね)なりし 笑(ゑ)まひ振舞(ふるまひ) いや日異(ひけ)に 変(か)はらふ見れば 悲しきろかも(巻3-478)(心にかけて思うことも、まことに恐れ多いことである。我が大君、安積皇子さまが、あまたの臣下のますらおたちを、呼び集め引き連れて、朝の狩に獣を踏み立て起こし、夕べの狩に鳥を踏み立て飛び立たせ、ご愛馬の手綱を控え、眺めては、御心を晴らされた、活道山の、木々の茂みの中に咲く花も散ってしまった。世の中は、かくも無常のものであるらしい。ますらおの心を奮い起こし、剣大刀を腰に取り佩き、梓弓を手に靫を背にして、天地と共に永久に、万代までもこのようであって欲しいと、頼みにしていた皇子の宮殿の<五月蝿なす>活気に満ちて仕えていた舎人たちは、真っ白に喪服をまとい、いつも絶えることのなかった笑顔も振舞いも、日ごとに変って行くのを見ると、悲しいことだ。)反歌愛(は)しきかも 皇子(みこ)の命(みこと)の あり通(がよ)ひ 見(め)しし活道(いくぢ)の 道は荒れにけり(巻3-479)(ああ、悲しいことだ。安積皇子様がいつも通って居られてご覧になって居られた、活道への道は荒れてしまった。)大伴(おほとも)の 名に負(お)ふ靫(ゆき)帯(お)びて 万代(よろづよ)に 頼みし心 いづくか寄せむ(巻3-480)(大伴氏の、名誉ある靫を身に付けて、万代までもと頼みにしていたこの心を、今後は何処に寄せたらいいのだろうか。)右の三首は、三月二十四日に作りし歌なり。(注)1.安積皇子(安積親王)(神亀5年・728年~天平16年閏1月13日・744年3月7日)は聖武天皇の第二皇子。母は県犬養広刀自。聖武天皇の難波行幸につき従っていた皇子は、閏正月11日脚病により桜井の頓宮から帰京。13日薨じた。時に17歳。藤原仲麻呂に毒殺されたという説もある。 同母の姉が井上内親王(光仁天皇の皇后)、不破内親王(塩焼王の妃)2.大伴家持は、安積皇子の内舎人であった。家持はこの時、27歳。●活道岡での饗宴の歌同じ月の11日、活道の岡に登りて一株の松の下に集ひて飲みし歌二首一つ松 幾代か経ぬる 吹く風の 音の清きは 年深みかも(巻6-1042)(一本松よ、お前は幾代を経たのか。松に吹く風の音が清らかなのは、経た年月が長いからか。)右の一首は、市原王の作なり。たまきはる 命は知らず 松が枝を 結ぶ心は 長くとそ思ふ(巻6-1043)(<たまきはる>人の寿命は分からない。しかし、松の枝を結ぶ気持ちは、命長くと思えばこそだ。)右の一首は、大伴宿禰家持の作なり。(注)1.上の2首は天平16年(744年)正月11日の作であるから、安積皇子の亡くなる一ヶ月前のことということになる。2.活道の岡は、安積皇子がしばしば狩に出掛けた場所。その所在については、和束町白栖説、湾漂山説、流岡山説などがあるが、流岡山説が有力と見られている。3.市原王は生没年不明。志貴皇子または川島皇子の曾孫とされる。天智系の皇族である。祖父は春日王、父は安貴王。光明皇后崩御の際はその陵墓を造る責任者、山作司を務める。藤原仲麻呂の乱では仲麻呂に組したので失脚している。
2017.11.05
コメント(6)
-

墓参・8と10そして笑うザクロ
本日は月例の墓参。 墓参の道にて見かけた虫は、蜂と天道虫。 よって8と10という次第。 (モンスズメバチ) スズメバチも色々と種類があるようだが、これはモンスズメバチという種類だと思われる。ツゲの木にやって来たこのスズメバチ。 見るとツゲには小さな白い花が咲いている。どうやらこの花が目当てらしい。 (同上) 花に首を近づけました。花蜜を吸っているよう。 先日、喫茶・ペリカンの家に立ち寄った際に、ももの郎女さんが店の前に沢山のスズメバチが来ていると仰っていましたが、その時の会話でスズメバチは他の虫をつかまえて肉団子にして食べる肉食だから花の蜜にたかることはないのではないか、などと小生の感想を述べたが、樹液にたかるスズメバチはよく見るから、やはり花蜜も舐めに来るようですな。 下の写真のように、この蜂、頭をすっぽり突っ込まんばかりにして、もうすっかり花に夢中であります。 (同上) 次は10です。テントウムシだから「10トウ虫」という駄洒落は余りにも低レベルの洒落でありますな。 星が七つあるから、これはナナホシテントウ。アブラムシなどを食べる肉食系のテントウムシである。ご覧のように葉はまったく傷ついていません。ナナホシだから10ではなく7として、タイトルは「8と7」とした方がよかったかも知れませんね。 (ナナホシテントウ) 少しカメラを近づける。 (同上) もっと、近づける。案外逃げない。気温が低くなると動きが鈍くなるから、逃げたくても逃げられないのかも知れない。理由は何であれ「テン逃虫」ではなかったよう。 (同上) 虫に関わり過ぎました。墓参と言えば、恒例の門前の言葉。 一度きりの 尊い道を 今 歩いている 一度きりのわが人生。その残高も少なくなって来ているが、この墓参の道もアト何回歩けるものであるかと思ったり、過ぎ行く時間はそれぞれがもう二度とは返らない時間、一度きりの時間であるのであれば、今日のこの道も亦一度きりの道とも言える、などと思ったり。 (今日の言葉) 振り返ると、ザクロの実。 パックリ割れて、「何を真面目くさって月並みなことを考えているのか」と何やら笑われているような気にも(笑)。そんなに笑わなくてもいいだろうと言い返しつつ、その大口を撮ってやりました。 (割れ柘榴) 先月の墓参で蕾のままであったので、何の花だろうと疑問を呈した花は、よく知っている花、アキノノゲシであったようです。通常は咲いた花の方に注意が行き、蕾のそれは見落としてしまうのだが、今回はむしろ蕾の方を注視。結果、前月のそれが90パーセントの確率でアキノノゲシであるという結論に達した次第。100%でないのは、これは近くの別の場所で咲いていたアキノノゲシで、前月に見た草の生えていた場所はすっかり草が刈られていて、その草が行方不明になってしまっていたからであります。(参考) 墓参・ナツメの実とムクロジの実ほか 2017.10.2. (アキノノゲシ) このような記事は、どのカテゴリにするか迷うが、一応「虫」にして置きます(笑)。
2017.11.04
コメント(6)
-

木津5人組ウオーク下見銀輪散歩
昨日2日は、今月12日に予定している友人たちとの木津ウオークのコース下見に行って参りました。この方面のコースを提案したのは草麻呂氏でありましたが、コース取りは小生の提案ということで、責任上、道に迷っては問題と念のため下見に出掛けた次第。距離からして歩程の心配は無かろうと自転車・トレンクルを持参で手早く回ってしまおうという魂胆。 乗った近鉄電車が西大寺止まり。西大寺駅で次の奈良行きを待って近鉄奈良駅からJR奈良駅まで歩くよりも、この駅から自転車でJR奈良駅に向かった方が快適で早かろうと、西大寺駅で下車し、トレンクルを組立て出発。平城京趾公園の西側に沿う道を走って、二条大路に出るべしで、爽やかな秋風に吹かれながら、気分良く走っていました。 (平城京趾公園) 遠く朱雀門が見え、手前にはススキの穂が銀色に輝き、風にそよいでいる。順調な滑り出しである。 ところが、二条大路を走っている途中で、左のペダルが何かにこすれてガリっという音。何だろうと見ると、ペダルの金属枠をペダルの芯に取り付けている四隅のネジが何と3個が脱落し、金属枠が下に垂れ下がってしまっていたのでした。ペダルを踏みこんで左ペダルが下になった時に、その垂れた金属枠が地面に接触して音を立てているのでした。 これではペダルが漕ぎ辛いということもあるが、地面の凹凸などに引っ掛かると危険でもある。仕方なく押して行く。 確か三条大路沿い、佐保川を渡った先に自転車屋さんがあった筈と行くが見つからない。信号待ちされている自転車の女性に自転車屋さんの所在を尋ねたら、もう少し先だと言う。漸く自転車屋の看板が目に入る。やれやれ助かった、と思ったのも束の間。Closedの文字。閉店しているのか休業日なのか。他を当らなければならないが、何処にあるのか見当がつかない。またしても自転車の人をつかまえて尋ねてみると、先程の店を教えられた。閉まっていると言うと、JR奈良駅の前の通りを南に行けばビッグというスーパーの中に自転車屋があるという。「遠いですよ。」と言われるが、行くしかない。JR奈良駅前から更に1km余歩いてビッグエクストラに到着。左ペダルを新しいものに交換していただく。ペダルは左右セットであるから、左だけを買うという訳にはいかない。セットの代金を払い、右は店にて処分していただくこととする。トレンクルの場合、コンパクトに収納するため、右ペダルは二つに折れる仕掛けになっているから、普通の市販品のものは使えない。よって、このようなことが起こると、右ペダルばかりが自宅に溜ることになる。 実は前回の同様のトラブルの時の右ペダルが未使用のまま自宅に死蔵されている。MTBの右ペダルが故障したらこれを使うことが出来るかと捨てずに置いているが、考えればこのようなことが起こるのは外出先や旅先でのことであるから、余り意味がないのではある。 このトラブルで1時間ほどのロス。木津駅到着は11時半近くになっていました。ということで、駅前の食堂で先ず昼食を取ることとする。 (JR木津駅) 当日の歩くコースは木津駅~大智寺~和泉式部墓~平重衡首洗い池~安福寺~御霊神社~西念寺~(鹿背山城跡・これは当日のオプション)~鹿背山不動尊~大仏鉄道遺跡(梶ヶ谷隧道・赤橋)~梅谷区公民館~岡田国神社~木津駅というもの。 和泉式部の墓と岡田国神社は過去に行ったことがあり、当ブログにも掲載済みであるが、他は未踏。特に重衡首洗い池は地図上にも出ていないので、多分此処だろうと思われる場所を念のため確認して置く必要もあった次第。もう一つ上津遺跡というのがあるようなので、その場所が分かり、コース取りの上で問題なければ、これにも立ち寄ろうという考えでしたが、この遺跡は何処とも発見できませんでした。よって、これは割愛する予定。 昼食後、先ず大智寺へ。大智寺は、木津嵐山自転車道の木津側起点の近くにある寺。自転車道の木津川堤防へと上がる道の脇から左に入って行くのが良さそう。次に和泉式部墓のある小さな寺へ。これは確かめるまでもないのであるが、下見なので一応自転車にてではあるが、当日の予定コースの通りに走ってみることとしました。それぞれのポイントで写真は撮りましたが、その全てを掲載してしまうと、当日の記事で書くものがなくなってしまうことになるので、多くは先送りすることとし、本日の写真紹介は、本日の記述の都合上どうしてもというものだけに限らせていただきます。 次に平重衡首洗い池に向かうが、見つからない。地図をよく確認すれば自身の思い違いに気づく筈であったのだが、その時は気付かず諦めて、先ず安福寺に回ることとしました。安福寺には重衡の墓と伝えられる十三重石塔がある。山門を入って直ぐ左側にそれはありましたが、他の参拝者たちが交互にその前でお互いの姿を入れた記念写真を撮り合うものだから、石塔だけを撮影しようとする小生になかなかチャンスが回って来ない。それで、仕方なくお堂に上がって堂内の仏像などを先に参拝させていただく。拝観料は300円。仏像など堂内の写真撮影もOKとのことなので、撮影させていただく。 (安福寺本堂<哀堂>) 平重衡は清盛の五男。武勇に優れ、容姿も牡丹の花に譬えられる華やかで気品のある美しい男だったようだが、一の谷の戦いで源氏方に捕えられる。彼は東大寺や興福寺など南都焼き討ちをした男として、南都の僧侶・衆徒たちの恨みを買っていた。彼らの要求により身柄が南都側に引き渡され、木津川の河原で処刑(斬首)されて果てる。この処刑の際に、重衡の願いに応じて、近くの古堂から阿弥陀像を運び出し、これを河原に置いたとのこと。重衡は、仏像の手に掛けられた赤紐の端を持ち、「浄土に迎えられますように」と念仏、南無阿弥陀仏を唱えながら、斬首されたという。この阿弥陀仏が安福寺本堂の阿弥陀如来坐像だということです。地元の人たちは重衡を哀れみ、この本堂を「哀堂(あわんどう)」と呼ぶようになったという。 (阿弥陀如来坐像) 阿弥陀如来坐像の左には法然上人像、右には善導大師像が安置されている。どちらも真新しいものである。 (法然上人像と善導大師像) 境内には何人かのボランティアと見られる男性が居られて参拝客のお相手をされてい ました。お堂から小生が外に出て来た時には、他に参拝客はなく、手持無沙汰にされていたので、「今日は好い天気で暑い位ですね。」などと話しかけたものだから、少しばかり彼らと会話することに。すると「首洗いの池はもうご覧になりましたか。」と仰る。「いや、先程近くまで行ってみたのですが、よく分からなくて・・」と申し上げると、その中のお一人が道案内して下さることになりました。 それがこれ。 (平重衡首洗い池・不成柿 背後はJR奈良線の線路) 写真右の植え込みの向こう側に池の痕跡かと思われる小さな水たまりの如き「池」がある。斬首された重衡の首をこの池で洗ったと伝えられている。重衡が斬首される前、最後に食べたのが柿で、その柿の種が此処で芽を出し、成長して柿の木となったが、何故かこの木には一向に実が生らないので成らずの柿(不成柿)と呼ばれるようになった、というのがその伝承であるが、ご覧のように柿の実がいっぱい生っていました。 重衡が亡くなったのは1185年だから、今から832年前。柿の木が830年も生きながらえることは先ずないでしょうから、この木は何代目かの柿。先代、先々代のことはいざ知らず、この木には「不成柿」の伝承は継承されなかったようです。 或は、新米の柿の木で「不成柿」になるのが「不慣れ」で修業不足、「不慣れ柿」という段階なのかも知れませぬ。そう思って見ると、実をつけてしまって「面目ない」と照れ笑いしている姿にも見えて来て、笑ってしまいました。案内して下さった方に「不成柿なのに実が沢山なっていますね。」と申し上げると「いやあ、そこの処は私にも分からんことでありまして」と笑って居られました。 安福寺に戻り、ご案内下さった方にお礼を述べて、トレンクルで寺を後にしましたが、重衡墓という石塔の撮影という本来の目的を果たしていなかったことに気付いたのは帰宅してからのことであったのは「お笑い種」でありました。成らずの柿は成ったのに、ヤカモチさんは「撮らずの写真」と相成りました。<追記(2017.11.4.)>平重衡首洗池・不成柿の説明板の写真も撮っていましたので、上の記述と重複しますが、追加で掲載して置きます。 東隣の御霊神社を経て、次の目的地西念寺へと向かう。分岐道の坂を上って、下って、また上りと行くと「工事中、この先、通行不可」の表示があって、道路工事中。通行止めになっている。先般からの雨で地盤が緩み、崩れたよう。重機が入って復旧工事中である。大回りして迂回するしかない。「10日後位には工事は完了していますか?」と作業されている男性に尋ねてみたが、「私らにはその辺のところは分からんです。」という返事。部分、部分をそれぞれの専門業者が下請けに入って工事をやっているのだろうから、末端の業者の作業員さんには、全体の工程表などは渡されてはいないのだろう。 場合によっては、12日当日も迂回することになるという次第。 そんなことを経て、ともかくも西念寺に到着です。 西念寺の拝観料は800円。安福寺に比べると随分と高い(笑)。 ざっと拝観して退出。西念寺の門前の奥に鹿背山城跡への登山口がある。12日の本番で、これを登るかどうかは、参加者の意向次第。しかし、どうであれ下見とあれば一応登って置かなくてはなるまい。 (鹿背山城跡案内板) (鹿背山城主郭跡)鹿背山と言えば、この万葉歌が思い浮かぶが、季節が合わない。 鹿背の山 木立を繁み 朝さらず 来鳴きとよもす うぐひすの声 (巻6-1057) 鹿背山城跡からの眺望は良くない。唯一西北西の方向だけが木立が無く開けていて、木津川が遠望できる。 (主郭跡からの眺望) 木津川を挟んで対岸にある狛山は、木立に遮られて見えない。その狛山の関連でもう1首万葉歌があるので掲載して置きましょう。何しろ銀輪万葉というカテゴリ記事なのですから。狛山に 鳴くほととぎす 泉川 渡りを遠み ここに通はず (巻6-1058) 対岸の狛山に鳴いているホトトギスが木津川の川幅が広いので、こちらに渡って来てくれない、と嘆いている歌である。 鹿背山側の女性が対岸の狛山側に居る恋人の男性に対して、近頃ちっともやって来てくれないわね、と言っている歌にも読めなくもない。 さて、この後、鹿背山不動尊を経由して、大仏鉄道遺跡などを見つつ、岡田国神社を経て、木津駅到着でウオークは終了となるのであるが、今回の下見では、岡田国神社は遠望のみで、スルーしました。 ということで、途中での写真2枚だけを次に掲載して本日の記事は完結とさせていただきます。他の写真は、12日本番の記事で紹介させていただくこともあるかと存じます。 (梅谷地区から少し下った処の公園から、西、北、東方向をパノラマ撮影) (天神山?) 上の写真は、天神山地区近くの道脇の池の水面に山影が映って美しくあったので撮影したもの。撮影者のヤカモチさんも影持君となって、図らずも登場であります。では、どちら様もご免下さいませ。
2017.11.03
コメント(2)
-

囲碁例会・もみぢ始む道、紫紺野牡丹
今日は、囲碁例会の日。お天気も申し分なく、爽やかな秋晴れの中、梅田まで銀輪散歩でありました。いつもの通り、中央大通りから大阪城公園経由、天満橋を渡り、れんげ亭前から天神橋筋商店街を抜け、国道1号に出て西へ、梅新交差点から先は国道2号と変わるが、これを直進、出入橋交差点で右折、梅田スカイビル、というコースである。 (大阪城公園の紅葉) 今年は、少し紅葉が遅いような気もするが、大阪城公園もチラホラともみぢ始む景色になりつつある。暫し、秋の葉と遊ぶ。 (同上・桜) 葉を日に透かして眺めるといい風情である。 (同上・枝垂れ桜) ケヤキも同じようにして撮ってみた。 (同上・欅) イチョウは普通の順光で撮る。黄金色に輝くのは未だ先のよう。 (同上・銀杏) 久しぶりにれんげ亭で昼食をと店の前まで行きましたが、「支度中」の表示。既に正午になっていたから、今日はお休みのようです。されば、何処か他の店でと物色しながら走るが、これと定まらぬまま、梅新交差点まで来てしまいました。東京・日本橋を起点とする国道1号はここが終点。この先は国道2号となる。 (梅新交差点 写真右が大阪駅方向、左が難波方向。奥が国道2号) 自宅を朝10時35分に出発。 梅田スカイビル到着が12時25分頃。 今日は途中の道草などもあって、1時間50分も掛かったことになる。 結局、昼食は梅田スカイビルの花野(通称「里山」)にあるカフェテリアで取ることとなる。 昼食後、自転車(MTB)を手押ししながら、駐輪場へと向かう際に目に止まったのがこの花。(梅田スカイビル敷地内は自転車乗り入れ禁止) (シコンノボタン)※1枚目は標準露出で2枚目は露出を下げて撮影。 一昨年に、この花の蕾と花弁が散ってしまった状態のものを写真に撮って、「見慣れぬ花」としてブログに掲載したら、紫紺野牡丹だとその名を小万知さんが教えて下さった花である。今回は、美しく咲いているところを撮影できました。(参考)囲碁例会・見慣れぬ実と花 2015.10.14. (同上) 上は、標準露出での撮影、下はマイナス1か2かに露出を落としての撮影。露出の加減で、花の印象も随分異なる。 (同上) (同上) 会場に行くと、既に、竹〇氏、福〇氏が対局中。村〇氏は小生より少し早い到着だったようで観戦中。早速、村〇氏とお手合わせ願うことに。これは小生、中盤以降劣勢にあると思い込んでいたのでしたが、終わってみると数目小生が上回っていて勝利。次の竹〇氏、少し遅れて来られた平〇氏との対局は、何れも小生の快勝にて、今日は久々に3戦全勝でありました。 これで今年の通算成績は22勝23敗となり、一時9もあった借金が漸く1まで減少。何とか勝率5割以上確保の望みも出て参りました(笑)。 以上、紅葉と花と囲碁の話でした。
2017.11.01
コメント(4)
全15件 (15件中 1-15件目)
1










