2019年05月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

銀輪花散歩・チチコグサとスズメノカタビラ
今日は左膝と腰の左後ろ側が痛むので整形外科に行って来ました。 随分の人で大入り満員。診察とリハビリが終わったのは午後1時を回ってしまっていたので、自宅には帰らず、MTBを走らせて馴染みの喫茶店「ペリカンの家」に行き、そこで昼食。 今日からアルバイトだという女店員の大谷郎女さんを店主のももの郎女さんから紹介されました。何故、大谷郎女とお呼びするかと言えば、石田三成や大谷吉継などが好きだという歴女、特に大谷吉継の大ファンという女性であったからであります(笑)。 関ケ原にも何度も訪ねて居られるようですが、ヤカモチが関ヶ原を銀輪散歩したのは、2013年1月16日のことですから、もう6年以上も前のことになる。尤も、ヤカモチが関ヶ原を訪ねたのは壬申の乱と大友皇子の首塚(自害峯)を訪ねてというのが主目的で、関ヶ原合戦古跡巡りはそのついでであったのですが。<参考>関ケ原銀輪散歩 2013.1.18~24. (その1)(その2)(その3)(その4)(その5)(その6) ペリカンの家の前庭にはももの郎女さんが大事にしておられる鉢植えや地植えの園芸種の花に混じって、アメリカフウロ、オオバコ、ヨモギ、チチコグサ、チガヤなどの雑草も。 ということで、帰宅途中に立ち寄った花園中央公園で見掛けた草花でも紹介して置きます。 先ず、チチコグサ。(チチコグサ<父子草>) この草の葉の裏はそれほど白っぽくはない。 草を横倒しにして葉の裏を撮るとこんな感じです。(同上・葉の裏) これに対して、葉の裏が白っぽいのがウラジロチチコグサ。 葉の色も、茎の色もチチコグサより色が濃い。背丈もチチコグサよりも高く、逞しい感じである。(ウラジロチチコグサ<裏白父子草>) 葉の裏がその名の通り白い。(同上・葉の裏) 次はスズメノカタビラ。 何処にでもある雑草の一つ。(スズメノカタビラ<雀の帷子>)(同上) スズメノカタビラはこのように今でもよく見かけるが、スズメノテッポウは近頃とんと見かけない。穂を抜いた後の茎を口にくわえて息を吹き込むとピーッと笛のように鳴るので、幼い頃そんなことをして遊んだものだが、近頃の子どもには縁のない遊びである。そもそもこの草が見かけないのだから是非もなしである。 次はヒメジョオン。 前ページでハルジオンの花をアップし、ヒメジョオンとの違いなどを少し言及しましたが、これがヒメジョオンです。(ヒメジョオン<姫女苑>)※苑の字は正しくは草カンムリに宛と書くがブログでは使用できない漢字(同上) ヒメジョオンの花弁は細いが、それでもハルジオンのような糸状ではなく少し幅がある。ハルジオンは蕾段階や開花した後もピンクや青みがかった色を付けているものがあったりするが、ヒメジョオンは常に白色である。 また葉の付き方も違う。(ヒメジョオンの葉の付き方) ハルジオンの葉を撮った写真が手許にないので、ネットから拝借したものを以下に掲載して置きます。(ハルジオンの葉の付き方) 以上、野の花・雑草銀輪散歩でありました。
2019.05.31
コメント(6)
-

銀輪花散歩・白赤黄色
本日も、銀輪散歩で見掛けた花たちです。 先ずはシロツメクサ。(シロツメクサ)(同上)(同上)(同上) 詰草にも色々な種類があるようです。 ピンク色に咲くのがアカツメクサ。花茎がシロツメクサのように長くなく、花のすぐ下辺りに葉があったりするほか、草丈がシロツメクサよりもずっと高いので違う品種であることが分かる。これで白い花が咲くのが、シロバナアカツメクサというから、面白い。いや「面赤い」と言うべきか。 アカバナやアカバナユウゲショウという花にも白花のものがあって、これらは白花種のアカバナ、アカバナユウゲショウと呼び、シロバナとかシロバナユウゲショウとは呼ばない。まあ、何にしても赤い花なのか白い花なのかは名前だけでは判断できないという次第。 随分前に撮ったアカバナの写真があるので、参考までに掲載します。<訂正追記> 下掲のアカバナの写真と思ったのは間違いで、正しくはハナハマセンブリという花でした。 小万知さんからの下記コメントで、アカバナとハナハマセンブリをネットで調べ直してみると、小万知さんの仰る通りハナハマセンブリでした。 近縁種の花にベニバナセンブリという花もあるようですが、どちらであるかまでは判断できませんので、ハナハマセンブリとして置きます。 2年前に撮影した古い写真ですが、その時にネットで調べたのか「アカバナ」という名を付けて保存されていました。それで、そのまま使用したのでしたが、掲載せずに居たのは、その名前にイマイチ信頼できないものを感じていたからかもしれません。 謹んで訂正します。 で、アカバナの写真はどうするの? 手持ちのものがないので、ネットで各自お調べ下さい(笑)。(アカバナ・・ではなくハナハマセンブリ)(同上) アカバナユウゲショウは下記<参考>の記事に写真を掲載していますので、それをご覧下さい。<参考>花の時期は過ぎにけらしや 2017.6.24. 続・恩智川畔の花たち 2017.6.19. 墓参と花散歩そして気になる木 2017.5.6. ピンクと言うより赤いと言っていい花が咲くツメクサもある。花の付き方と言うか花が付く形と言うか、それがアカツメクサやシロツメクサのような丸型ではなくやや細長い穂の型になるのがそれで、ベニバナツメクサ(紅花詰草)という。(ベニバナツメクサ) 花が黄色でずっと小振りなツメクサもある。コメツブツメクサである。 コメツブグサと書かれているネット記事もあるから、そういう別名もあるのかもしれない。(コメツブツメクサ)(同上) 同じく黄色い花ではキツネノボタンやマンネングサがある。(キツネノボタン)(マンネングサ)(同上) そして、マンテマ。(マンテマ) この花を初めて見たのは富山県滑川市でのこと。2011年5月のことであったから、8年前のことになる。 この時は、名前を知らなかったので、何の花だろうとブログに写真を掲載したら、友人の小万知さんから「マンテマ」だと教えていただいたのでありましたが、以来、この花の名は忘れないでいる。<参考>魚津から富山へ銀輪万葉(その2)2011.5.23.(同上) 花弁の赤い斑紋が可愛い花であるが、この赤い色素がないシロバナマンテマというのもあったかと思う。上の写真の右手前にぼんやりと写っているのがそれかもしれない。(同上) 次はハルジオン。 蕾がうなだれていないので、ヒメジョオンかも知れないが、花びらが糸っぽい細さなので、ハルジオンだろうと思います。 茎を折ってみて、芯が詰まっていればヒメジョオン、空洞ならハルジオンですが、これは些か乱暴な見分け方なので、紳士淑女にはお薦めできませぬ。 よく見ると、茎に虫が沢山ついています。(ハルジオン) まだ、銀色の穂にはなっていないが、チガヤが風に靡く。 浅茅(あさぢ)ともいう。「つばな」或は「ちばな」ともいう。(チガヤ) 周りにはマンテマやコマツヨイグサも咲いている。(同上) 続いて、オオバコ。(オオバコ)(同上) 葉が細長くて、背丈の高いのがヘラオオバコ。(ヘラオオバコ) そして、ラベンダー。 これは、野草ではなく、道端の民家の前の花壇に植えられていた花。 五月の風にはラベンダーの香が似合うか。 尤も、ヤカモチはこの香りはどちらかと言えば余り好きではない。(ラベンダー)(同上) そして、野バラ。 5月はやはりこの花です。 イバラ(茨、荊)ともいう。万葉では「うまら」ともいう。 こちらは、ラベンダーほど押しつけがましくはない香なので、ヤカモチ的には5月の風はこちらの香でお願いしたい(笑)。(イバラ)道の辺(へ)の茨(うまら)の末(うれ)に這(は)ほ豆の からまる君を別(はか)れか行かむ (丈部鳥(はせつかべのとり) 万葉集巻20-4352)(道のほとりのイバラの先に這い伸びる豆のつるがからまるようなあなたを置いて、私は別れて行くのか。)(同上)(同上) 以上でおしまい。 と思ったら、ニワゼキショウの花が残っていました。(ニワゼキショウ)(同上) 直近の銀輪散歩で見掛けた花はこれで全部ブログアップ完了。 以上、脈絡もなき銀輪花散歩でありました。
2019.05.27
コメント(6)
-

銀輪散歩・光と風と
五月の蠅と書いて「うるさい」と訓む。 五月のハエは「五月蠅・さばへ」。 尤も、「さ・はへ」の「さ」は小さいという意味であるから、「小蠅」が本来の意味だろうが、五月蠅と表記すると、異常繁殖して群がっているハエの光景が浮かび上がって来る。 陰暦で五月は梅雨の時期。ハエが繁殖する季節。 群がっているハエは、うるさく、煩わしいもの。 かくて、「五月蠅なす(さばへなす)」は「騒ぐ」、「満つ」などの枕詞となる。・・皇子の御門の 五月蠅なす 騒く舎人は 白たへに 衣取り着て・・ (大伴家持 万葉集巻3-478)・・ことことは 死ななと思へど 五月蠅なす 騒く子どもを 打棄てては・・ (山上憶良 同巻5-897) 五月の蠅は鬱陶しいが、五月の風となると爽やかなイメージになるのは、「風薫る五月」などという言葉の所為か。(五月の風) 風を感じる写真は無いかと探してみましたが、なかなかないものです。 ネズミムギが風に揺れてさやさやと・・。(同上・ネズミムギ) 風を待っているのはタンポポの絮。(タンポポの絮) タンポポの絮は、キラキラと五月の光を反射してもいるよう。 然らば、風は諦めて五月の光を撮りましょう。(光と影・ユキヤナギ) ユキヤナギの光と影。(同上)(同上)(同上) 足元ではヌカススキも、微塵の光を放散している。(ヌカススキ)(同上) そして、日に照るカナメモチの青葉。(照葉・カナメモチ)(同上)(ブタナ) 日陰でブタナが風に揺れている。 五月の光と風との花散歩でありましたが、ブタナの花が登場して何とか「花散歩」の面目が立ったので、ひとまず休憩であります。 それにしても、今年の五月は暑い。真夏のような暑さである。 温暖化で季節感もグジャグジャ。 この先、どうなって行くのでしょうね。
2019.05.26
コメント(4)
-

夕々の会・令和最初の例会
昨日(5/24)は、大学同期の会・夕々の会(よひよひの会)の例会でした。この会は毎年5月と11月に開催することになっている。 今回は、守〇君、谷〇君、中〇君、古〇君、西〇君、広〇君、蝶〇君、永〇君、枦〇君、岡〇君、深〇君、豊〇君、道〇君、佐〇君、前〇君、出〇君、楽老君、城〇君とヤカモチの19名が出席。 場所は、前回同様に「がんこ梅田OS店」。 城〇君は今回が初参加。同君とはまだ若い頃に同期有志の集まりで会ったこともあるほか、犬養万葉顕彰会や犬養万葉記念館(副館長)など万葉関連の催しで顔を合わせたりもしているので、この会へは初参加で卒業以来という向きも多かったようですが、小生には比較的顔なじみの人物。 また、楽老君ははるばる横浜からの参加ということで、皆さん大歓迎でありました。小生は先月16日に友人の家近氏の銀座での個展をご一緒するなどでお会いしているので、「その節はどうも・・」という程度の再会でありましたが(笑)。 定刻の午後5時半には全員が集合、幹事の守〇君の発声で乾杯、開会となりました。 この会が始まったのはいつからだろうと調べてみたが、正確なことはブログ過去記事を調べてもよく分からない。 2010年5月30日の記事がこの会の記事としては最初のものになるが、記憶では、これよりも前に1~2回集まりを持った筈であること、2007年の同期会関連の記事から推測すると、2007年段階では、まだこのような会を持っていなかったようなので、2008年か2009年かに定期的に同期の集まりを持とうということになったようである。 この会の発端は、楽老君がまだ現役で大阪勤務だった頃、同じく現役だった小生の勤務先に訪ねて来て、交流が始まったことを契機として、連絡のつく同期に声掛けをして飲み会を持つようになったことにある。守〇君が参加するようになって、彼が店の手配をしてくれるようになったことが次のステップへと進む状況が生まれたのではないかと思う。 次に、東京勤務だった谷〇君が定年退職してこの会に参加してくれることとなり、彼が会開催の連絡メールを手配してくれるようになって、今日の「夕々の会」の形が出来上がったという次第。 その意味では、楽老君、守〇君、谷〇君が夕々の会の生みの親ということになるかと思う。黒〇君、道〇君にヤカモチは当初からこれに参加しているから、会の成立にいささかの寄与はしているということになるか(笑)。<参考>夕々の会関連過去記事はコチラ。(夕々の会風景)(同上) 同期生は全100名。 この会は、開催場所が大阪市内なので、関西在住者が中心となるが、岡山や福井などから参加してくれる常連組もあるほか、今回の楽老君のように時に東京方面からの参加者もありで、このような人達にも案内メールを出しているので、登録メンバーは30名を超える。 この会が益々盛会となりますように、そして皆さんがいつまでもお元気でありますように。 最後に、幹事の守〇君から、令和最初の夕々の会ということで、令和に因んだ話で締めの挨拶をお願いしたい、という無茶振りの矢がヤカモチに飛んで来ました。 ご承知のように、令和は天平2年(730年)正月13日に大宰府の長官(帥)であった大伴旅人の屋敷に集っての宴会で、参列者が詠んだ観梅の歌32首(万葉集巻5-815~46)の序文の中の「初春令月、気淑風和」からのもの。 大伴旅人が大宰府長官となってこの時期に都を離れていたことの経緯や長屋王の変との関連などをお話してお茶を濁して置きました。 今から思えば、この時に大伴旅人が詠んだ歌を替え歌にして即興で戯れ歌でも詠んで締めればよかったのですが、突然のことにてそこまで気が回らず、まだまだ精進が足りぬようです。わが園に梅の花散るひさかたの 天より雪の流れ来るかも(大伴旅人 巻5-822) この会の生みの親でもある楽老君が久々に遠路横浜からこの会に参加してくれたことを感謝して、こんな戯れ歌にすればよかったのだが・・(笑)。我が園に楽老来たる久しぶり 浜よりこよひ流れ来たるか (偐家持) まあ、とにもかくにも楽しいひとときを過ごさせていただきました。 次回は11月15日開催ということで、午後7時45分頃に散会。<追記>太宰府銀輪散歩(4)・大野山霧立ちわたる 2015.1.17.
2019.05.25
コメント(0)
-

銀輪虫散歩・ハエトリグモとハシリグモ
ブログの更新を暫しサボってしまいました。 これという記事ネタもないのであるが、余り日数をあけるのもいかがなものか、ということで、虫の写真でも。(ハエトリグモ) ハエトリグモにも色々種類があるようですが、そこまでの詳しい分類はできないので、単にハエトリグモです。 家の中でも時々夜中に出て来て、チョコチョコと歩きまわるのを見掛けるが、結構動きが俊敏で、ピョンと跳ぶ跳躍力とその素早さはなかなかなものである。 こいつは墓参の折に石の上に居た奴で、家の中などで見掛けるハエトリグモと同種なのかどうかは、よくは分からない。見た感じでは、同じように見えます。 ちょっと近づいてみましょう。(同上) 活発に動くので、なかなかうまく撮れない。(同上) 目が何個あるのだろう。 正面に2個、左右側面にも少し小振りのものが2個ずつあるよう。 正面の2個の目は獲物との距離を的確に把握できる付き方である。 側面の目は補助的なもので、天敵から自身を守るための監視用に使うのでもあるのか、やや上向きに付いている。 見方にもよるが、ちょっと愛嬌のある顔をしている。小生にはそのように見えるのだが、皆さんはどうでしょう(笑)。 同じ石の上に凝っとしている白っぽい別の蜘蛛がいた。(ハシリグモ) こちらは肢を大きく広げて石にへばりつくような低い姿勢で、全く動く気配がない。突っついてみると漸く動き始めた。(同上) ハシリグモも色々な種類があるので、これが何というハシリグモであるかまでは分からない。 その名前と肢の長さなどから速く走れそうな蜘蛛だが、この日は走らず、のんびりとアルキグモの風であった。<参考>喜母にしあらむ 2013.8.28. 蜘蛛は毛嫌いされる人が多いかと思うが、もっと毛嫌いされる虫が毛虫。 その毛虫が月見草を食べていた。 蛾の幼虫だが、何という蛾の幼虫なのかは勿論存じ上げぬ。(月見草を食べる毛虫) 月見草とも呼ばれるマツヨイグサであるが、その花を食べる毛虫というのも、面白いと撮影してみました。 余り好かれない虫が続きましたので、好かれる方の虫もアップして置きます。チョウです。(キマダラヒカゲ) もう少しアップで。(同上) そして、モンキアゲハ。 こちらは、翅をパタパタさせて少しもじっとして居ないので、写りがイマイチです。(モンキアゲハ)(同上) 銀輪散歩などで見掛けた虫たちでした。 もう、虫たちの季節ですね。
2019.05.22
コメント(2)
-

銀輪花散歩・赤と白
昨日(17日)は、岬麻呂氏から届いたマンホールカードの受け渡し。 ペリカンの家で正午待ち合わせ。 そろそろ家を出ようかと思っているところへ、利麻呂さんから電話があり、相談したいことがあるとの話。ペリカンの家で午後1時の待ち合わせと決める。 ペリカンの家に行くと既にひろみの郎女さんは到着して居られて、昼食も済まされたらしく、珈琲タイムに入って居られました。 マンホールカードをお渡しし、日替わりランチを食いながら、雑談。 12時45分。ひろみの郎女さんは帰途に。小生は、利麻呂氏の到着を待つ間を利用して、向かいの病院の庭へ。 オオヤマレンゲの花が咲く隣にベニウツギの赤い花。(ベニウツギ)(同上)(同上)(同上) 網膜が赤く染まってしまったことでしょうから、白い花で中和させますかね。赤の補色は緑ですから、中和と言うなら緑色のものを呈示しなければならないということになりますが、赤に対抗する色と言えば白というのが相場と決まっているのが、源平時代以来の我が国の文化。(オオヤマレンゲ) 気品のある美しさ。(同上)(同上)(同上) オオヤマレンゲは俯いて咲くのが普通で、仰向いて咲くのはウケザキオオヤマレンゲという別品種。ホオノキとオオヤマレンゲの雑種だと推定されている。 ところが、オオヤマレンゲもたまには上を向いて咲くことがあるよう。(上を向いて咲くオオヤマレンゲ) なお、オオヤマレンゲの花を撮影したのは昨日(17日)ではなく、一昨日(16日)のことであります。 つまり、二日続いてペリカンの家で昼食であったという次第。 ベニウツギとオオヤマレンゲの向かい側にある大木。ネグンドカエデなのかウリハダカエデなのか結論が出ぬままになっている木であるが、実をいっぱい付けていました。(ネグンドカエデ) この木は枝によっては斑入りの葉を付けているものとそうでないものとがある。これは、枝によって栄養状態がいいものとそうでないものとがあるということなんだろうか。 中には葉全体が白っぽくなっていて、葉緑素を持たない葉だけ、つまり「斑」が全体に行き渡って、もはや「斑」ではなく「白葉」ばかり、という枝もある。枝に虫でも巣食っているのだろうか。(同上)(同上) 斑入りの葉の枝の写真を撮り忘れていました。 追って、下に追加で掲載させていただきます。 午後1時少し前に利麻呂氏が車で到着。 ペリカンの家にて、珈琲をしながらその相談なるものを聞く。 相談と言うより、小生の感想、意見を聞きたいという風な感じ。 然らばと、感想を述べて、この件はおしまい(笑)。 少し雑談して帰って行かれました。
2019.05.18
コメント(8)
-

偐万葉・ひろろ篇(その19)
偐万葉・ひろろ篇(その19) 久々の偐万葉シリーズ記事です。 偐万葉シリーズとしては第304弾の記事となる、ひろろ篇(その19)であります。 気が付けば、ひろろdecさん関連の歌が既に20首を超えていましたので、記事にまとめることとしました。 ひろろ篇は2017年1月13日以来ですから、2年4ヶ月ぶりになります。 <参考>過去の偐万葉・ひろろ篇はコチラからどうぞ。 ひろろdecさんのブログはコチラからどうぞ。 偐家持がひろろの郎女に贈りて詠める歌24首ほかわが里は まだ雪降らず 会津嶺(あひづね)の 妹が里には 二尺も積むに (難波天候)(本歌)わが里に 大雪降れり 大原の 古りにし里に 降らまくはのち (天武天皇 万葉集巻2-103)老いてゆく 己が身のほど 面白う 見るは気のほど いまだ若かり (大伴若持)かささぎの わたせる橋は なくあれど 柳津(やないづ)の町に 降れる白雪 (虚空蔵家持)(本歌)かささぎの わたせる橋に おく霜の しろきをみれば 夜ぞふけにける (大伴家持 新古今集620 小倉百人一首6) (↑20170210福満虚空蔵菩薩円蔵寺の撫牛) (↑20170210會津柳津町)盛り上がる 話に水を さすは烏滸(をこ) 写真に電線 写るは迂闊 (電線あっても飯豊) (↑20170320飯豊連峰)少女たち そのけがれなき まなざしを 花とやなしつ 明日は咲けかし(本歌)少女たち 開口(あぐち)の神の 樟(くす)の木の 若枝さすごと のびて行けかし (与謝野晶子) (↑20170514「まなざし'17」)踏切を 絵に描く君を 絵にせむと 囲める絵かきを 知らざりし君 (↑20170702踏切博士のY君)デジカメは わが宝物 愛犬の 散歩の時も 手放すべきや (額田少女)(本歌)三輪山を しかも隠すか 雲だにも 心あらなむ 隠さふべしや (額田王 万葉集巻1-18) (↑20170702デジカメと少女)作品は しばし試作に とどむべし めぐし孫らの 帰り来ぬれば (ひろろの刀自) (↑20170808「奏でる女性のエスキース」)髪飾り やや桃色に 頑是なき 女童(めわらは)今日は 自恃のあるごと (もも白書) (↑20171114ピンクの髪飾り) うしろの席で しぐれ煮食ふか (牛山頭火) (元句)うしろすがたの しぐれてゆくか (種田山頭火)わが君は いづくありしや 留守居とは ふて寝のエルに なるのほかなき (エル麻呂)蜜柑置き 待てお手伏せと リュウならぬ ひろろの刀自に われ遊ばれつ (エル麻呂)われはもや ふて寝などせじ 絵を描くとふ 刀自(とじ)の臥せにし 応へたるまで (エル麻呂)留守居なる エルとひろろを わが見れば かくにやあると 言ふのほかなき (↑20180209「える(部分)」)猪苗代湖 めぐれる道の いかにかも 行きて見が欲し もみぢ葉照るを (銀輪家持)猪苗代 いくのの道の 遠ければ いかがすべきと 決めかねつつも(本歌)大江山 いく野の道の とほければ まだふみもみず 天の橋立 (小式部内侍 金葉集586 小倉百人一首60) (↑20181101「磐梯」)ふるさとは 空も水面(みなも)も 金色(こんじき)の 慈愛の色に 染みて暮れゆく (偐中也)この年の よきもあしきも 押し包み 蜜柑の色に 暮れても行くか (偐中也)<参考>中原中也の詩「夕照」、「冬の長門峡」 (↑20181228暮色))なにあれど なんくるないさ なるやうに なるしかなけれ なるやうになる (やかもち)臈たけき 若きをみなの 眼差しは 光の春を 告げるとならし (↑20190217春の予感)もの思(も)へば 悲しと春は 娘子(をとめ)らに 微塵(みじん)の光 降り注ぎつつ (↑20190316春愁)プリマベーラ 目覚めの季節 会津嶺へ 届けむ笑みの ヴィオロンの声 (↑20190316会津ジャーナル表紙)しあはせは スープのむとき あたたかき 香をおしつつみ これをのむとき (偐曙覧)寒き日に 疲れ帰れば われを待つ 母のスープの 香のあたたかき (↑20190505「スープ」)猫だにも 恋ふるときあり 風をだに 君とし待てば かなしきろかも (猫家持)(本歌)君待つと 我(あ)が恋ひをれば 我(わ)がやどの 簾(すだれ)動かし 秋の風吹く (額田王 万葉集巻4-488)風をだに 恋ふるはともし 風をだに 来むとし待たば 何か嘆かむ (鏡王女 万葉集巻4-489) (↑20190515「気配」)(注)掲載の写真、絵画はひろろdecさんのブログからの転載です。
2019.05.16
コメント(2)
-
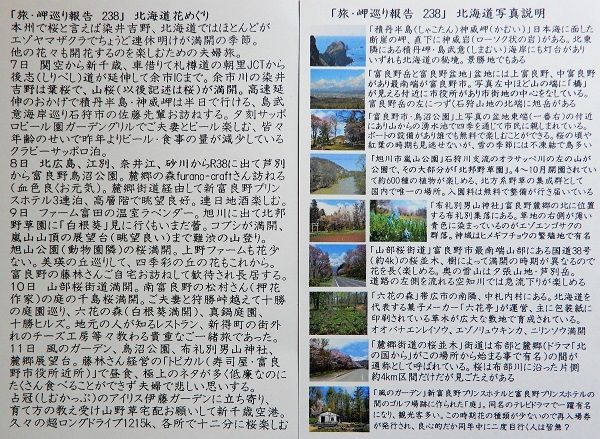
岬麻呂旅便り238・北海道花めぐり
今日(14日)、岬麻呂氏からの旅便りが届きました。<参考>岬麻呂旅便り関連の過去記事はコチラ。 フォト蔵の岬麻呂写真集はコチラ。 今回の旅は、5月7日~11日の4泊5日、北海道花めぐりのご夫婦旅であったようです。 まずは、例によって、下掲の「旅・岬巡り報告238&写真説明」をお読み下さい。(↓旅・岬巡り報告238&同写真説明) では、岬麻呂氏が送信下さった写真で、我々も花めぐりの旅にご相伴させていただくこととしましょう。 写真はクリックすると大きいサイズの画面が別窓で開きますので、それでご覧下さい。5月7日関西空港→新千歳空港→余市→神威岬→島武意海岸→石狩市→クラビーサッポロ泊(↓神威岬)<参考>神威岬へ 2015.7.20. 神威岬、余市川などを銀輪散歩したのは、もう4年近くも前のこと。懐かしい。5月8日北広島市→江別市→空知郡奈井江町→砂川市→芦別市→富良野・鳥沼公園→麓郷街道→新富良野プリンスホテル(3連泊) 旅便りには、この日に通過した町のマンホールカード(下掲)が同封されていました。これは、ひろみの郎女さんにという趣旨のようですから、、追ってお届けさせていただきましょう。 それぞれの地でわざわざご入手いただいたものにてありますが、そのご親切に感謝です。 マンホールカードはいずれひろみの郎女さんがそのブログでご紹介されるでしょうから、表面側のみ、フォト蔵写真とはリンクなしで「遠慮がち」に掲載して置きました(笑)。(↓富良野岳と富良野盆地) 雄大な眺めです。(↓富良野市・鳥沼公園) 麓郷と言えば、ブロ友のfurano-craft氏であるが、今回も岬麻呂氏はf氏をお訪ね下さったようで、同氏のお元気そうな写真も1枚同封(いや、メール添付だから、同封とは言いませんね。何と言えばいいのでしょう。)されていました(笑)。5月9日ファーム冨田→旭川市→北邦野草園・嵐山公園→旭山公園→上野ファーム→美瑛の丘→四季彩の丘(↓旭川市・嵐山公園) この日も旭川市のマンホールカードを手に入れて下さったようです。5月10日山部桜街道→南富良野→狩勝峠→十勝の庭園巡り(六花の森、真鍋庭園、十勝ヒルズ)→チーズ工房など(↓山部桜街道)(↓六花の森) 白い花はオオバナエンレイソウとニリンソウ、後方の黄色い花はエゾリュウキンカだそうです。5月11日風のガーデン→鳥沼公園→布礼別男山神社→麓郷展望台→アイリス伊藤ガーデン→新千歳空港→関西空港(↓風のガーデン)(↓布礼別男山神社) 畑の外縁の草地に青く見えているのは、群れ咲いているエゾエンゴサクの花です。(↓エゾエンゴサク)(↓麓郷街道の桜並木) ご夫婦で花を楽しまれた北海道の旅。 お天気にも恵まれ、何よりでございました。
2019.05.14
コメント(6)
-

壱師の花の・・
少し前の話。先月27日のことになりますが、友人の家近健二氏から絵を頂戴しました。 お礼のお電話を差し上げた際に「この絵のタイトルは何か?」とお尋ねしたつもりでしたが、「何の絵か?」と誤解されたのか「棚田に咲く彼岸花」との返答。或は、それが絵のタイトルであったのかもしれないが、ヤカモチには絵の内容を説明されているように聞こえました。 展覧会などに絵を出品するときは、絵にタイトルを付けることが必要なんだろうが、画家本人からすれば、タイトルそのものには、余り関心がなく、これでなくてはならない、というほどのこだわりがない、ということなのかもしれない。 ならばと、ヤカモチが勝手にタイトルを付けることとしました。(家近健二氏画「壱師の花のいちしろく」) 秋の田の畦に咲く彼岸花と黄金色にみのった稲穂。 豊穣の景色であるが、彼岸花の燃えるように真っ赤な色は恋の歌に相応しいか。ということで、万葉歌に因んだタイトルとしました。 万葉の「壱師」は彼岸花のことだとするのが、有力説であるが、万葉人はその激しい恋心をこの花の色に喩えたということなんだろう。路の辺の壱師の花のいちしろく人皆知りぬ我が恋妻を(万葉集巻11-2480)<道のべに咲く彼岸花のように目立ってしまって、私の恋妻のことがみんなに知れてしまったよ。> 「いちしろく」は「いちじるしい」で、よく目立つという意味。 「いち」は「いち早く」のように意味を強める接頭語。 単に「しろく」とか「しるく」でも同じ意味である。 彼女といちゃいちゃし過ぎて僕らの関係が皆に知れ渡ってしまったよ。まいった、まいった、と何やら嬉しそうにのろけている若い男の顔が浮かんでも来る、微笑ましい歌である。 結婚・出産は、共同体にとって、その未来への存続と繁栄のために祝うべきものであるが、その前段階の「恋・恋心」は当人たちの個人的なもので、共同体的価値からすれば基本的にどうでもいいこと。 個人的価値にかかわる「恋」は時には共同体的価値と衝突することもある扱いにくいものであったかもしれない。 共同体の一員、構成員の一人という存在に過ぎず、共同体を離れては自己の存在自体が成り立ちえないという古代人にとっては、共同体的価値が全てであって、これに対峙する個人的価値を意識することも多分なかったことでしょう。個人主義なんて言葉も考え方もなかった時代である。 従って、共同体が「祝い事」として受け入れてくれることが保証されている、或はその見込みが極めて高いというような「恋」でなければ、その機が熟するまでは、「秘め事」として他に知られないようにするということが必要であっただろう。 この歌の男の場合は、そういう「秘め事」の時期を経て、共同体に受け入れられる見込みが立った、それがほぼ確実になったということで、こんな風に「人皆知りぬ」と幸せそうに笑っていられるということなのではないか(笑)。 まだそういう状況でない段階では、恋は極力目立たないようにことを運ぶ必要がある。それを思わせるのが次の歌。青山を横ぎる雲のいちしろく我と笑まして人に知らゆな (坂上郎女 万葉集巻4-688)<青い山を横切る雲のように、はっきりと私に笑いかけたりして、人に気付かれないで下さい。> まあ、そんな中であるから、大津皇子の下の歌が何やら男らしくも見えて来る(笑)。大船の津守が占に告らむとはまさしく知りて我が二人寝し (大津皇子 万葉集巻2-109)<あの憎き(大船の)津守めの占いに現れるだろうことは、先刻承知の上で、私達は二人で寝たのだ。> これは、大津皇子が石川女郎と情を通じたことが、陰陽道の名手であった津守連の占いによって露見した時に、大津皇子が詠んだ歌。 皇太子の草壁皇子も石川女郎にぞっこんであったことが万葉集の歌からうかがえるが、二人が彼女をめぐって張り合っていたかどうかまでは、ヤカモチも存じ上げぬことであります(笑)。 話が脱線して居りますので、ここまで。 友人から頂戴した絵の話でした。 殆ど絵の話になっていない? それは失礼。 素敵な絵のプレゼント。 家近氏にあらためて感謝、お礼申し上げます。<参考>家近健二絵画写真(フォト蔵アルバム)
2019.05.13
コメント(2)
-

恩師17回忌・墓参
今日は中学時代の友人と一緒に恩師のお墓にお参りして来ました。 今回は、参加者が少なく、喜麻呂君、嶌郎女さん、ひろみの郎女さん、ヤカモチの4人だけ。 近鉄奈良線・生駒駅午前10時待ち合わせ。 少し早めに行って、お供えのお菓子でも買ってと、家を出たものだから、生駒駅到着が9時15分頃と、早過ぎる到着。 そして、迂闊なことに買い物をしようとした店が近鉄百貨店であったのだが、10時開店ということに気が回らなかったのでした。(生駒駅前) 仕方がないので、周辺をウロウロしたり、喫煙所でタバコしたりして時間を潰していると、嶌郎女さんがやって来られた。 暫くして、ひろみの郎女さんがその愛車で到着。お二人は車の中でお待ちいただくこととし、ヤカモチは生駒駅の改札口前に移動。喜麻呂君に電話を入れると「今、枚岡駅。間に合います。」との返事。生駒駅10時到着の電車の車内のよう。これをも「間に合う。」と言うか、であるが、まあ、そういうことはどうでもよろしい。 電車が生駒駅に到着と同時に百貨店が開店。両方一緒にはお迎えできないので、百貨店を優先。買い物を済ませることに。すると、喜麻呂君からの電話着信、「今、百貨店の中だから、そこで待っていてくれ。」と伝えて、支払いを済ませて、百貨店を出る。 嶌、ひろみ両郎女さんが待つ車へと向かい、我々もこれに同乗、霊山寺霊園へ。 墓の草引きをし、花を供え、線香を手向け、各自お参り。(恩師墓) 墓参を済ませた後、「山の音」という名のうどん屋さんで昼食。 我々が店に入った時は、一番乗りで他に客は無かったが、注文したのが出て来る頃には、店は満席に近くなっていました。どうやら、人気の店らしい。 昼食を済ませてもまだ11時半。何処かで珈琲でもと喫茶店で時間調整をすることに。 というのは、恩師の奥様から「今日が恩師の17回忌で、その法要を自宅で行うので、列席して欲しい」という話があって、12時半頃にご自宅に寄せていただく予定となっていたからでありました。 12時40分頃に恩師宅前に到着。 恩師にはお嬢様お二人、MちゃんとYちゃんがいらして、そのお二人とお二人の旦那さん、それにお孫さんらが来て居られました。 MちゃんもYちゃんも、二人がまだ小学生くらいの頃の面影しか記憶にないので・・実際はもう少し大きくなられてからも、また恩師のお葬式などでも顔を合わせているのだろうが、そういうのは記憶の外になっていて・・何とも久しぶりの再会という感じで、懐かしいことでした。 午後2時過ぎに恩師邸を辞し、生駒駅で皆と別れ、先般、脊柱管狭窄症の手術を受け、無事退院し自宅に戻っている叔母を訪ねる。 元気そうにしていて、ひと安心。午後4時半頃に叔母宅を辞し、午後5時半頃帰宅。 本日は、このようにして日が暮れました。
2019.05.12
コメント(4)
-

小浜・三方五湖銀輪散歩(その5)
(承前) 前頁は良弁生誕地碑のところで終わりましたが、その碑の左手にある建物が鵜の瀬公園資料館。 無人で、出入り自由となっている。(鵜の瀬公園資料館) 館内には、お水送りの儀式を人形で表現した陳列があった。(お水送りの儀式) お水送りの儀式は見たことがないので、こんな感じなのかと見入る。(同上)(同上) お水取りというのは奈良東大寺の修二会のことであり、関西人には馴染みの深いものである。ヤカモチも何度か二月堂の前で、その修二会の一つの行であるお松明を見物したことがあるし、若かりし頃には、その火の粉を浴びて化繊のコートに無数の穴を開けてしまうという失敗をしたこともあったりしたのだが、では修二会とは何か、その起源は、意義は、と問われるとよく理解できていないので説明に窮する次第。 稲作が始まるとともに、その豊作を願って若水を汲み、神にこれを供えて祈るという原始的な宗教儀式が生まれ、春の祭或は習俗となった。これと仏教とが合体して神仏習合的なものが生まれ、それがお水取りの原形となった、ということなんだろうとは思うが・・東大寺そのものの修二会の始まりなどについては、よく理解していない。 こういう時は無理に説明しようとせず、Wikipediaの記事などを引いて来るというのが、ブログとしては無難な方法(笑)。 同様に、お水送りについても下記に参考記事を掲載して置きます。<参考>修二会・Wikipedia以下は、「神宮寺「お水送り」小浜市・ニッポン旅マガジン」より転載 西暦710年、奈良に平城京が造られ、聖武夫皇ご在位の752年春に、東大寺において国家を挙げての盛大な大仏開眼供養が行われました。若狭ゆかりの良弁僧正がその初代別当(開祖)と言われています。 若狭神宮寺に渡ってきたインド僧「実忠」は、その後東大寺に二月堂を建立し、大仏開眼の二ヶ月前から(旧暦二月)天下世界の安穏を願い、14日間の祈りの行法を始められました。 修二会(しゅにえ)と呼ばれるこの行の初日に、実忠和尚は「神名帳」(じんめいちょう)を読み上げられ、日本国中の神々を招かれ、行の加護と成就を請われたのですが、若狭の遠敷明神だけが漁に夢中になって遅れ、3月12日、修二会もあと2日で終わるという日の夜中に現れました。遠敷明神はお詫びとして、二月堂のご本尊にお供えする閼伽水(あかすい)、清浄聖水を献じられる約束をされ、神通力を発揮されると地面をうがちわり、白と黒の二羽の鵜が飛び出て穴から清水が湧き出しました。 若狭の根来(ねごり)白石の川淵より地下を潜って水を導かせたと伝えられています。 この湧水の場所は、若狭井と名付けられ、川淵は鵜の瀬と呼ばれるようになり、古来より若狭と奈良は地下で結ばれていると信じられてきました。その若狭井から閼伽水を汲み上げ、本尊にお供えする儀式が大和路に春を告げる神事、東大寺二月堂のお水取りであり、その神約を獲り伝える行事が、若狭小浜のお水送りなのです。(お水送り説明板) 因みに、「閼伽」というのは、サンスクリット語の水・argha(アルガ)のことで、その音写である。功徳水と訳されるとのこと。インドでは古く、来客に対して足をそそぐための水と食後に口をすすぐための水が用意されたといい、それが仏教に取り入れられ、仏前や僧侶に供養されるようになったとのこと(以上、 Wikipediaより)。 水を意味するラテン語アクア(aqua)も同じ語源の言葉だという。 そうと分かると「閼伽」という何やらとっつきにくかった言葉が随分と近しいものになった気がする(笑)。赤の他人が友人になった感じか。 ついでに、白洲正子著「私の古寺巡礼」(講談社文芸文庫)の「若狭紀行」から、次のような文章も引用して置きましょう。二月堂のお水取りは、本尊の十一面観音にささげる香水を「若狭井」から汲むことが中心になっており、その水は若狭の遠敷川から来ると伝えている。一方、若狭の側でも、いつの頃か「お水送り」という神事が行われるようになって、毎年お水取りがはじまる前の三月二日、遠敷川の鵜の瀬において、奈良へ水を送る祭がある。若狭彦神社の旧神宮寺の住職が、この行事を司っており、後に私は拝見することを得たが、雪の中で土地の人々が手に手に松明をかかげ、「これから奈良へ水を送ります」という祝詞を、河原で読んで水を流す光景は、まことに感銘の深いものであった。(遠敷川とサトザクラ 後方の建物は給水所) サトザクラが丁度満開。 この桜の木の向かいに自販機があったので、飲み物を買って一息つけ、帰途につくこととする。 この地点からさらに2kmほど上流に行ったところにある、根来八幡宮もお水送りに関連する神社であることを、帰宅してから知ったのだが、それは後の祭り。自転車は既に下流へと疾駆していました(笑)。(忠野地区) 帰途は県道35号から外れて忠野の集落の中を通過する道を行く。 そして、再び県道35号へ。往路で見た「忠野」という看板のある合流地点に出る。(県道35号から忠野の集落を振り返る。) 往路でやり過ごした若狭神宮寺へ向かう。(神宮寺・横入りの東側参道) ここから入ると仁王門は通らずに、拝観受付所経由で本堂に行くことになるのだが、北門(仁王門)を通って参拝というのが、正式な順路のようだから、ここでもやはり裏口からというヤカモチ流参拝となった次第。(神宮寺由緒・案内板) 本堂に向かう。 ご夫婦と見られるヤカモチと同年齢くらいか少し若いくらいの男女が本堂から出て来られた。彼らと入れ違いに本堂に上がる。(同上・本堂) この寺も明治4年(1871年)の神仏分離令により、境内にあった遠敷明神社を若狭彦神社へ統合すべく、その社殿の取り壊しとご神体の差し出しを命じられたよう。 しかし、拝観パンフレットの記載によると、社殿の取り壊しには応じたものの、ご神体(男神・若狭彦像と女神・若狭姫像)については、身代わりを差し出し、本体は本堂内に秘蔵したと記されている。その結果、両ご神体は当寺に今も現存するということになった。 こういう反抗は健全な精神を示すものでまことに愉快である。(同上・本堂内) 堂内は通常撮影禁止であるが、外から撮影のこの程度なら許される範囲内かと勝手解釈であります。 外に出て、本堂前の枝垂れ桜にカメラを向けたものの、既にあらかた散った後なので、シャッターは切らず、立ち去ろうとして拝観入口の方向に向かうと、先ほどのご夫婦とすれ違う。奥様の方が「桜の盛りの時も写真を撮られたのですか?」と仰る。「いえ、大阪からやって来ましたので・・。」と返すと、「ああ、失礼しました。地元の方かと思いましたので。」と奥様。 ここでも地元人間に間違えられた。まあ、傘もささず、上下雨装束であるから、畑仕事の合間にやって来た近所の人間に見えたのであろう。 何故か、ヤカモチは旅先でよく地元人間と間違えられる。記憶するだけでも、小樽、高岡、新潟・・そして近くは先月の東京。 仁王門などの撮影は忘れたまま、県道35号に戻り下流へと走る。雨は小止みになっている。 若狭彦神社付近まで帰って来たところで、右手の遠敷川沿いの土手道を列をなしてランニングしている高校生の姿が見えた。雨が止むと心も積極的になる(笑)。県道を離れ遠敷川岸辺の道へと移動する。すると橋の先に萬徳寺という表示があった。橋を渡り行ってみることとする。 萬徳寺という寺は、上述の白洲正子の「若狭紀行」でも「ここには有名な枯山水の庭園がある」という書き出しで紹介されている寺である。(萬徳寺) ここは入口ではなく、もう少し先のよう。(同上) こちらが入口である。 石段下にトレンクルを駐輪し、門内へ。 拝観受付を済ませて、庭園へと入る。 先ずは庭園へ。(庭園説明碑) 国指定名勝書院庭園とある。白洲正子が「京都の名園のように完成されてはいず、したがってせせこましくはなく、周囲の自然の中に、ゆったりととけこんでいるのが気持よい。」と評している、枯山水風の書院庭園である。(萬徳寺・庭園) 中央に据えられた巨石は、真言密教の根本仏である大日如来を表し、脇石に阿閃如来、宝生如来、阿弥陀如来、不空成就如来の四仏、多数の小石組みを諸仏に見立てた金剛界曼荼羅の庭園である、とは寺のパンフレットの説明であるが、正面からの写真がないのでは話にならぬ(笑)。(同上) 庭園前から眺めると、雨の日ならではの眺め。 向かいの山々は「霧立ちのぼる」または「雲立ちわたる」といった風情である。(向かいの山に雲立ちわたる・・) 一段高い場所にある本堂へと至る前庭の高みから見おろすと。(本堂下の高みからの眺め) 本堂の前の楓の木はかなりの巨木である。 樹齢500年とか。(同上)(本堂前の楓) ここでも雨に濡れた楓の若葉が美しく、しばし見とれる。(本堂) 萬徳寺は高野山真言宗の寺。非公開の馬頭観音菩薩像があり、若狭観音霊場第16番札所となっている。 寺の沿革は、そのパンフレットに記載するところによると、「1370年頃(南北朝時代)、安芸国円明寺の僧覚応が廻国し、この地に以前からあった極楽寺にとどまり、寺号を正照院に改め真言宗を広める。戦国時代、若狭国を治めた若狭武田氏が当寺を祈願所として国中の真言宗本寺とした。また、武田信豊(第七代当主)が1544年(天文13年)若狭国における駆け込み寺とする旨の文書を記している。1602年(慶長7年)、城主京極高次の寄進を受け、空性法親王より萬徳寺の額面を賜り寺号を萬徳寺に改めた。」とあり、「1634年(江戸初期・寛永11年)、酒井忠勝が小浜藩主となった以後も代々の祈願所として庇護を受け、国主に尊崇された寺院である。」としている。 ご本尊は、一木桧造りの美しい阿弥陀如来坐像である。(阿弥陀如来坐像 萬徳寺パンフレットより) 萬徳寺を出て、先ほど渡った橋(萬徳寺橋という名だったかと思うが)まで戻って来る。遠敷川左岸が舗装された道になっている。往路で県道35号から桜並木が遠望されたその岸辺である。若狭東高校までのわずかな距離であるが、これを走る。(遠敷川左岸の道) 振り返ると、川原はアカメガシワの木が列をなし、左手奥に茅葺屋根の萬徳寺が見えている。 国道27号に戻って西へ。信号待ちしていて神通寺というのが目にとまったので、寺の前まで行ってみたが、寺の前の広場で小休止したのみで、寺には立ち寄らず小浜駅前へと走る。(神通寺) 多田寺や明通寺などの気になる寺の名も目に入ったが、今回の予定コース外であっため、道路からその寺までの距離・道順・所要時間不詳につき、寄り道はせずでありました。 ホテルに戻り、預けた荷物を受け取り、雨装束を解いて普通の服装に立ち返る。フロントでトレンクルを宅配便で送り、お世話になったお礼を述べてホテルを後にする。小浜駅前の中華食堂でランチ。 JRで、小浜→敦賀(特急サンダーバード)→京都。 近鉄で、京都→大和西大寺→枚岡。 鉄路で帰宅である。 以上で、小浜・三方五湖銀輪散歩、無事終了。(完)
2019.05.10
コメント(10)
-

小浜・三方五湖銀輪散歩(その4)
(承前) さて、再び、小浜・三方五湖銀輪散歩の記事です。 遠敷川に出たところから始めます。 これを「おにゅうがわ」と読める人は、少ないかと。 遠敷川は、滋賀県高島市と福井県小浜市の境にある百里ヶ岳に源を発し、一つ東側の谷筋から流れ出た松永川とJR小浜線の鉄橋付近で合流し、北川に注ぎ、若狭湾へとつながる川であるが、古くは(和銅5年・712年までは)「小丹生」と書かれていたとのこと。<参考>遠敷川・Wikipedia(遠敷川・下流側) 上の写真の下流側に見える橋は国道27号が通っている橋。 ヤカモチは国道27号の一つ南側の橋の上に立って、北方向の下流側を撮影し、続いて南方向の上流側を撮影したという次第。(同上・上流側) どの辺りから遠敷川の岸辺を走るかが問題であったが、ネット地図では、両サイドに道の表示があったものの、来てみればこの橋から上流側には舗装路はない。前方に見える白い建物は若狭東高校。この高校の向こう側から岸辺に上がると舗装路が川沿いに続いていたのだが、それを知ったのは帰り道でのこと。 岸辺を走るというのは諦めて、再び若狭姫神社の前に戻り、県道35号を行くことにする。(県道35号から見る遠敷川岸辺 左奥山裾に萬徳寺が見えている。) 若狭姫神社から1.5kmほど上流に行ったところにあるのが、若狭彦神社上社。(若狭彦神社上社) 鳥居の右手奥にトレンクルを駐輪して、参道を行く。 杉の大木が林立する参道。(同上・参道) 夫婦杉なる二本がくっついてしまった杉の木もある。(同上・夫婦杉) そして、神門を入ると、(同上・神門) 下社の若狭姫神社と似た造りの社殿。(同上・社殿) こちらの祭神は彦火火出見尊(火折尊、山幸彦のこと)で、これを若狭彦神として祀っている。 下社の若狭姫(豊玉姫)の夫であり、神武天皇の祖父である。<参考>ホオリ・Wikipedia(同上・由緒) これで、神武天皇の祖父母にご挨拶を済ませたことになる(笑)。 前日の三方五湖では神武天皇の父親であるウガヤフキアエズを祭神とする宇波西神社にご挨拶しているから、神武関連銀輪散歩の様相である。 再び、県道35号に戻り、南へ。(県道35号・鵜の瀬への道) 道はこの先の谷へと入って行く。 数百メートルほどで右手に神宮寺への入口が見えて来たが、帰途に立ち寄ることにして先に進む。(同上・忠野の里入口手前) 左手にいくつかの民家が見えて来る。忠野(ちゅうの)の集落。(忠野の入口) 県道35号と忠野の集落へと入る左の道とは、この先で再び合流するので、どちらを行ってもいいのだが、県道をそのまま直進する。 忠野の集落への反対側入口を過ぎて少し行くと遠敷川の岸に沿って舗装された細長い駐車場のようなスペースのある場所がある。 お水送りの儀式などの折に、車で見に来た人たちの車の駐車スペースかもしれない。そのスペースが尽きる地点にこんな表示板があった。(鵜の瀬まで直進500m) この案内看板の脇から遠敷川上流を撮ったのが下の写真。(鵜の瀬から500m下流の遠敷川) もう少し上流から撮った遠敷川。(遠敷川) この辺りから道は少し右にカーブして下り坂となる。 そして、鵜の瀬が見えて来た。(鵜の瀬) 鵜の瀬到着である。(鵜の瀬)(同上・説明碑) 川原に降りてみよう。(同上) 上流側と下流側を見ると。(上流側) 上流側左手は鵜の瀬公園資料館の建物。(下流側) この空間で、お水送りの儀式が執行されるのだろう。 清冽な水が流れている。(水は澄んで・・) 上流側の橋を渡って、鵜の瀬公園に入ると給水所がある。 コインを入れるところがあって、対応する金額を支払ってペットボトルなどで、水を持ち帰ることができるようになっている。 コインを入れるとその金額に見合う量の水が自動的に出て来るというようなものではなく、普通の水道の蛇口と変わらぬようなものだから、自己申告ということなんだろう。(白石神社) 正面の小さな祠が白石神社。 若狭彦・若狭姫を遠敷明神とも言うのだが、この両神は鵜の瀬にある磐座に降臨したという。従って、この白石神社は遠敷明神こと若狭彦と若狭姫を祀る神社である。 神宮寺で頂戴した拝観パンフレットによると、遠敷明神の直系子孫の和朝臣赤麻呂が8世紀初め山岳信仰で、紀元前銅鐸を持った先住民のナガ族の王を金鈴に表し、これを地主の長尾明神として山上に祀り、和銅7年(714年)に山の下に神願寺(神宮寺の前身)を創建した。翌年に元正天皇によって勅願寺とされ、その秋(霊亀元年<715年>9月)に遠敷明神を神願寺に迎え、神仏両道の道場となったとのこと。 因みに、鎌倉時代に若狭彦神社の別当寺となった時に神宮寺と改称したということである。 一方、若狭姫神社の資料によると、霊亀元年9月に鵜の瀬付近にあった遠敷明神を祀る仮殿を現在の若狭彦神社(上社)に遷宮、更に養老5年(721年)2月に若狭姫神社が創建されている。 といったことであるから、白石神社は若狭彦神社・若狭姫神社の元社ということになる。 遠敷明神ご夫妻は、鵜の瀬(白石神社)→神宮寺→若狭彦神社→若狭姫神社と時代が下るとともに、遠敷川上流から下流へと移動して来て居られることになる。(良弁生誕地の碑)<参考>良弁・Wikipedia<追記>良弁の碑の左にあるのは山口誓子の句碑 瀬に沁みて奈良までとどく蝉のこゑ (昭和41年11月建立) 白石神社の前に良弁生誕地の碑。 東大寺初代別当の良弁僧正。大伴家持よりも二回り以上年長であるが、言うなれば同時代人。その名は夙に承知して居りましたが、これも小浜と結びつく人物という認識はありませんでした。まあ、良弁の生誕地については諸説あるようで、相模説、近江説などもあるほか、この地、若狭下根来のそれは別人説とされているようだから、何とも言えないのだが、ここに来れば下根来説を支持するしかない。なお、根来は「ねごろ」ではなく「ねごり」と訓むとのこと。(良弁説明板) 本日はここまでとします。 次回で完結予定です。(つづく)
2019.05.09
コメント(2)
-

囲碁例会・西田當百川柳句碑など
小浜・三方五湖銀輪散歩の記事はお休みして、今日は囲碁例会の日でありましたので、その記事とします。 と言っても、小浜と少し関連した記事でもありますので、その余録編と考えていただいてもいいかもしれません。 というのは、(その1)で紹介した西田當百の川柳句碑が法善寺横丁にあるということを、小浜で見掛けた彼の句碑によって知りましたので、囲碁例会で梅田スカイビルまでMTBで出掛けるついでに法善寺横丁に立ち寄り、それを見て来ました。(西田當百の川柳句碑)上かん屋 へいへいへいと さからはず 「上かん屋」というのは「上燗屋」で、落語の「上燗屋」のことらしい。 上燗とは熱燗とぬる燗の中間の丁度良い具合の燗のことで、落語では、お燗の付け具合が自慢の屋台のオヤジが、燗が熱過ぎる、ぬる過ぎると難癖をつける客に「へいへいへい」とさからわず、「熱い」と言えば、冷酒をつぎ足し、「ぬる過ぎる」と言えば、熱燗の酒をつぎたしと、いいようになぶられるというお話だそうで、その可笑しさを川柳にしているとのことらしいが、イマイチ小生には可笑しさが伝わって来ないのは、その落語「上燗屋」のやりとりを知らないからでしょうか。 法善寺横丁からジグザグに西へ、北へと走っているうちに堀江公園の前に出た。休憩と立ち寄ると堀江川跡の碑が公園内にありました。(堀江川跡碑) 碑には「元禄11年(1698年)河村瑞賢により、西横堀川と木津川を結ぶ堀江川が開削された。これにより、堀江新地が開発され、北堀江では浄瑠璃、南堀江では大坂相撲、また各種産業が起こり、木村蒹葭堂や橋本宗吉などの文化人や学者を輩出した。」と記され、「昭和35年(1960年)に埋め立てられ、その役割を終えた。この地はその堀江川の跡地である。」とある。 堀江公園からなにわ筋に出て、これを北上。 梅田スカイビル到着が12時半頃。スカイビルのガーデン5棟1階の喫茶店で昼食。5階の会場に行くと、福麻呂さんが既に来て居られた。 早速にお手合わせ。これは小生の勝ち。そこへ村〇氏が来られたので、同氏と対局。これは中押し負け。遅れて来られた平〇氏と3局目を打ったが、これまた大差負け。結局1勝2敗で、今年の通算成績は14勝10敗。 帰途は、あみだ池筋を走る。<追記注:正確に言うと、当初はあみだ池筋を走っていましたが、堂島大橋から西に行き、中之島センタービルの前から図書館の先までは新なにわ筋を走りました。図書館を過ぎてからあみだ池筋に再び戻り、幸西橋で道頓堀を渡り千日前通りを東へというのが帰途のルートでした。> すると、大阪市立中央図書館の傍らに木村蒹葭堂邸跡の碑があることに気が付いた。往路で堀江川跡碑の碑文に記されていた木村蒹葭堂という人物の屋敷跡だという。これも何かのご縁と写真に撮る。(木村蒹葭堂邸跡碑)(同上・副碑) 本日の囲碁はイマイチでしたが、銀輪散歩の方は、西田當百さんとの再会と木村蒹葭堂こと木村巽齋さんとの初対面がありで、まずまずでありました(笑)。さからはず へいへいへいと ヘボ碁うち (二子田偐百)
2019.05.08
コメント(2)
-

小浜・三方五湖銀輪散歩(その3)
(承前) 三方石観音へ向かうべく国道27号までやって来たところから始めることとします。 国道27号までやって来て左手を見ると、名前は忘れたがレストランか喫茶店のような建物があり、店内に灯りもついている。まだ正午にはなっていないが、ここで昼食にするかと、建物前の広い駐車用空地にトレンクルを押しながら進んで行った。 その空地には1台の黒い軽自動車が停まっていた。その車に乗り込んだご婦人が車を発車、道路へ出るべしでヤカモチの方へバックして来られた。広い場所なので、少しバックして前方に方向転換するための広さを確保したら、前進に切り換えて道路へと出て行かれるものと理解し、バックして来る車とコチラとの距離もそこそこにあったので、また、運転者は後方確認をしながらバックしている筈だから当方の存在に気がついているものと、余り気にしないでゆっくりと歩を進めていた。 然る処、車はバックを途中で停止させることもなく、そのまま真っ直ぐコチラにスピードをゆるめず向かって来るではないか。ぶつけられると慌てて前方に走って車を回避、セーフでした。 我々は、経験則により、相手方が通常とるであろう行動というものを予測して行動している。赤信号の場合や歩行者が横断中の横断歩道の前では車は停車するだろう、バックして来る車の運転者は後方を注視しているだろう、ウインカーで右を点滅させている車は右折または右車線に移動するであろうとみて、それに応じた行動をとるといった具合に。 しかし、時にはそのような期待に反して相手方が期待通りの行動を取らなかったり、逆に自分が相手方の期待する行動に反した行動を取っていたりすることもあり得る。事故または事故になりかねないヒヤリハットが発生するのは、このような場合。 今回は、ヤカモチは車が途中でバックを停止し方向を転じて前方向に進むと、経験則から予測したのに対して、運転者は、後方を見ていなかった(これは後方には誰も居ないと予測したということでもある。)、または見てはいたが素早く回避して道をあけるだろうと期待した、というように相互の期待や予測に齟齬が生じていた結果生じたものであるが、どちらの予測・期待に無理があったのだろうか(笑)。 もし、運転者である彼女が後方を全く見ていなかったとすれば、彼女にとってとても大変なことが起こっていて、彼女は或る場所に急いで駆けつけなければならない、そのことで心がいっぱいで後方確認を失念してしまった、というような事情も考えられるか・・など、危ない運転への腹立たしさが去った今となっては色々と想像を巡らせてもいる次第。 それはさて置き、店の入口ドアにはお休みの表示。是非に及ばず。 石観音への坂道にとりかかる。(三方石観音・参道入口) 坂を少し上ったところに、「ようこそ」の碑。(ようこそ) 少し上ったところ、参道の左手にあった巨大な万葉歌碑。(同上・参道の万葉歌碑)若狭なる 三方の海の 浜清み い行き帰らひ 見れど飽かぬかも (万葉集巻7-1177)(若狭の国の三方の海の浜が清いので、行きつ戻りつしていつまで見ても飽きないことだ。)(注)帰らひ=返らひ 今回の銀輪散歩唯一の万葉歌碑である。 この歌碑が目的で石観音にやって来たのであれば、ここで引き返してもいいのであるが、折角なので本堂まで行ってみる。(同上・由来記) 三方石観音というのは、弘法大師が若狭遍歴中にこの山中に宿り、一夜にして彫り上げたという花崗岩の石仏である。 彫刻中に鶏が鳴いて夜明けを告げたので、右手首だけは彫り残したまま下山、よって片手観音だという。(同上・堂宇)(同上・本堂) 山や湖などの遠景写真は、レンズに付着した微塵の雨滴によって、部分的にぼやけても、それなりに風情があるというものだが、本堂など近景写真の場合は、何とも締まらない写真になってしまう(笑)。(本堂裏の楓) 石観音へは、小さな渓流沿いの道を上って来るのであるが、ずっと楓の木が植わっていて、雨に濡れた楓の若葉が実に美しいのである。 紅葉の季節もさぞやと思われるが、若葉の季節もいいものである。(同上) 石観音から少し下ったところにあるのが御方神社。 一応ご挨拶だけして置く。(御方神社) 三方の古い形が御方であることをこの神社の社名が示している。 白洲正子氏はその著「かくれ里」の中の「花をたずねて」の章で「三方は古く『御潟』であったに違いない。」と言って居られるが、その中間の形が「御方」と言えるだろう。まあ、これは見方の問題ではある(笑)。 石観音の参道の坂を自転車で走り下る。 国道27号を渡り、JR小浜線の踏切を渡ったところで、線路に並行している西側の道を三方駅方向へと走る。 三方駅前を過ぎ、何処かで昼食をと思うが見つからない。道の駅まで行けばレストランがあるのではとそれを目指す。 先にも述べた通り、もう地図は無いに等しい状態なので、記憶するところと道路標識とを頼りに行くしかない。 国道27号から分岐して西へと下っている国道162号に出る。記憶ではこの162号の道沿いに「道の駅三方五湖」があった筈。 国道162号は鳥浜交差点を直進、はす川に架かる橋を渡って直角に右に曲がっているのだが、橋の手前、鳥浜交差点を渡ってすぐの場所に設置されている標識には、右への矢印を示して「道の駅三方五湖⇒1km」と表示されていた。恰も鳥浜交差点で右折せよと表示しているかのように、小生には見えた。で右折する。県道だか町道だかは知らぬが、広いその道が国道162号だと思ってしまったからである。矢印の示すままに走ったが、何やら記憶する地図の感じと異なる。変だと引き返すことに。 ここでも亦、道に迷って随分のロスをしてしまう。再び鳥浜交差点に戻って来て、その標識の表示が、川を渡った先で右折せよということを示したものであることを理解したのだが、間違わないと「意味」が理解できない標識では「意味」がない(笑)。 このような矢印を標識に付けるなら、その設置場所は、橋の手前ではなく、橋を渡った先だろうと思った次第。(道の駅三方五湖) しかし、ここにもレストランなど食事のできる店はなかった。 物産販売所があったので入ってみたが、海産物や野菜・果物などの農産物、お菓子・酒その他の土産物が売られているだけ。唯一食事になりそうなのは鯖寿司であったが、鯖はノーサンキューなので、草餅を買って、これを昼食代わりにするというお粗末な始末に。 食べ物に頓着しないヤカモチではあるが、さすがにこれには「参った」でありました。 で、これが草餅を食べながら、道の駅の展望所から撮った三方湖の写真であります。(三方湖・2階展望所から)(同上・パノラマ撮影写真)(同上・1階に降りて来て) 三方駅に引き返すこととする。 一応、三方五湖すべてを垣間見たということで、ミッションコンプリートである。 隣接敷地にあるのが若狭三方縄文博物館。 立ち寄らず、外観写真だけ撮影。(若狭三方縄文博物館)(三方駅) 三方駅構内には喫茶店がありましたが、到着した時は午後2時を過ぎていて、ランチタイムは終了、喫茶だけでした。 結果論ですが、駅に先に立ち寄っていれば、草餅よりもましなランチにありつけていたのでした。 上の写真では左下隅にホースのついた水道蛇口が写っていますが、これを拝借して、トレンクルについた泥や枯葉などの汚れを洗浄、収納袋をざっくから取り出して収納。次の小浜方面行きが来るまでの時間、喫茶店で暫し珈琲休憩でありました。 小浜に戻って、早めの夕食でようやくまともな食事にありつけました。 今回の三方五湖銀輪散歩は、下掲地図のようにごく一部を巡っただけの三方五湖垣間見散歩に過ぎませんでした。要再挑戦でしょうか。最終日(4月26日) 朝起きて、ホテルの窓から外を見やると・・やはり雨。(小浜駅南東側の山々 ホテルの窓から) それでも、前日と違って、山の頂上が雲に隠れていないから、雨も少しはましなのでは、と希望的観測をしたり・・。 ホテルをチェックアウト。フロントに荷物を預けた上、トレンクルで外出。勿論、服装は上下とも雨仕様である。 途中の喫茶店で朝食を済ませて銀輪散歩、出発。 この日は、遠敷川上流の、お水送りの鵜の瀬まで行くのが目的。小浜駅の一つ東側の駅・東小浜駅付近から遠敷川沿いを上って行くというコースで、大した距離でもないので、鉄道は利用せずホテルから鵜の瀬までトレンクルで往復である。 小浜駅前の国道162号で東に走る。小浜線のガード下を潜り、国道27号に出て、これを東へ。南川を渡る。橋の名は湯岡橋。(南川 湯岡橋上から上流を望む。) 東小浜駅口交差点で右折し県道35号を行くと若狭姫神社があった。(若狭姫神社) 元々は遠敷川上流にある若狭彦神社を上社、当神社を下社とし、両社を併せて若狭彦神社とされているようで、地元の人は両方を併せて「上下宮(じょうげくう)さん」と呼ぶとのこと。若狭国一之宮とされるが、これも上下社を併せての一之宮だそうな。 下社の祭神は若狭姫。若狭姫とは豊玉姫のことだという。 豊玉姫とは海神・豊玉彦(綿津見)の娘。ホヲリ(山幸彦)の妻となりウガヤフキアエズを産み、ウガヤフキアエズと玉依姫(豊玉姫の妹)との間に生まれたのが神武天皇であるから、神武天皇の祖母ということになる。(同上・由緒) 境内に入ると、船の模型が収納されたガラス戸の建物があった。(弁才船?) 写真に撮ったものの、注意してよく見なかったので、何であるのかは推測するほかない。 似内恵子氏の「小浜漁港の『みなと文化』」によると、小浜の廻船問屋では弁才船(千石船)を所有し、日本海を舞台に広く国内交易を行っていたことから、その航海の無事を祈るため、船玉(霊)神社が各社の末社として祀られるようになったとのこと。弁才船の模型を神座として祀る船玉信仰は小浜独特のものだそうな。 この船も、そのような船玉信仰によるものであろう。(同上・神門)(同上・社殿) 遠敷川上流の上社、若狭彦神社は「若返り」のパワースポットであるのに対して、下社の若狭姫神社は「縁結び」のパワースポットだそうな。 しかし、境内に掲示されている「効能」は「安産育児」である。 まあ、豊玉姫の書紀伝説に因むなら、安産が本来の「効能」だろう。(神社の効能書き) 若狭姫神社の前の道、県道35号を行くのが鵜の瀬への道であるが、同じ走るなら、遠敷川の岸辺の道を走りたいものと、遠敷川に出てみることにした。しかし、本日はここまでとします。(つづく)
2019.05.07
コメント(2)
-

小浜・三方五湖銀輪散歩(その2)
(承前) 雨が降ったり止んだり。 覚悟を決めて、上衣もズボンも雨装束に身を固め、ショルダーバッグタイプの運搬袋にトレンクルを収納し、小浜駅へと向かう。 8時15分発敦賀行きに乗車。(小浜駅1番ホーム) 東小浜→新平野→若狭有田→上中→藤井→三方→気山、小浜駅から7つ目の駅・気山駅に到着、9時2分。無人駅。駅前にあるのは自動販売機とトイレだけ。人影はなし。トレンクルを組立て、出発。 駅の東側の高い場所を国道27号が通っている。その国道と並行してその下を通っている道を南に行き、踏切を渡って線路の西側に出る。(気山駅ホーム) 踏切を渡って広い道を北へ。 この道は県道244号、直進すると久々子湖の南西岸をかすめてレインボーライン自動車道を越えて日向湖へと通じている。 久々子湖の湖岸沿いの道を走って、その先でこの県道244号に出るべしで、右に入る道、若狭梅街道を行く。(若狭梅街道入口) 久々子湖に到着。「くぐしこ」と訓みます。(久々子湖) 梅街道は下の写真の建物が写っている側の湖岸を通っているのであるが、今回は、極力短い距離で三方五湖を巡るという計画なので、これを行かず、南岸沿いの細道を辿ることとする。(同上)(同上) ところが、この先辺りから舗装が無くなり、悪路となる。(同上) 天気が好ければ、道も乾いていて、デコボコ道も平気なのだが、折からの雨で道はぬかるみ、道全体が水没しているようなところまである。止む無く自転車を降りて、あぜ道に上がったりしてこれを回避するなど、悪戦苦闘の連続である。で、湖岸沿いの道は諦め、湖岸から奥に入った、今少しましな道を行く。 湖岸を離れて暫く行くうちに、広い舗装道路に出たが、既に方向感覚が狂ってしまっていたと見え、これが出発当初に走った県道244号で気山駅南側踏切に通じている道だとは気がつかず、右に行くべきところ、左に行ってしまう。(宇波西神社) そこで出会ったのが宇波西神社。 これで「うわせ」とは、万葉仮名風である。(同上・由緒)<参考>宇波西神社・Wikipedia ウガヤフキアエズ・Wikipedia 宇波西神社の祭神はウガヤフキアエズノミコト。山幸彦の子にして、神武天皇の父親である。 4月8日の例祭では、県の無形文化財である「王の舞」などが奉納されるとのこと。(王の舞の像) 持参の地図を確認。 逆方向に走って来てしまったことに気付き、引き返す。 引き返す前に目にとまった石碑。道を挟んで神社の反対側にあった。 何の碑かと見ると、行方久兵衛翁頌徳碑とある。(行方久兵衛翁顕彰碑)(同上・副碑) 行方久兵衛(なめかたきゅうべえ)は、水月湖と久々子湖をつなぐ浦見川を開削した人物で、この結果、三方湖や水月湖が大雨などで増水しても久々子湖経由で若狭湾へと流れ出ることが可能となり、周辺の村々が水没するなどの水害がなくなったとのこと。 わが河内で言えば、大和川の付け替え工事をした中甚兵衛さんのような人物である。 この後、その浦見川沿いを走って水月湖へと出るのが予定コースであってみれば、「この碑を見て置け。」という天の声であったか。右でなく左に来てしまった「逆走」も天の声に従ったまでということになる(笑)。 県道244号を北へと走る。 やがて右手に久々子湖が見え、その浦見川に架かる橋を越えると1kmほどで、レインボーラインの入口料金所である。これを左に見てレインボーラインを越える。越えてすぐに左折。レインボーラインに沿った北側の道を行くと日向湖畔に出る。 ネット地図でコース取りを検討した際に、湖畔に出る地点に喫茶店の表示があったので、ここで珈琲をとも考えていたが、店仕舞いをされたのか、人の気配がなくクローズ。(日向湖) これまでの写真でもお分かりのように、カメラのレンズに雨滴がついたりして、写真が点々とぼやけて写るという状態。時々、ティッシュやハンカチで拭うのだが、完全には拭えないので、写りの悪い写真になっています。 これも「雨」の感じが出て、一興という風に考えることとします。(同上) 雨天なのに、多くの船影。釣り船であるか。 雨なのに物好きなことだ・・と思ったが、雨なのに自転車で走っているヤカモチの方が余程に物好きであるということに気が付く(笑)。 ネットからの地図を印刷してコース地図なるものを準備してやって来たのだが、何度かこれを取り出して見ているうちに、雨に濡れ、ところどころ滲んで判読不能になりつつあるほか、紙と紙がくっついて、何やら雑巾か何かのような得体の知れない代物に変化しつつある。 どうやら、この先、地図に頼ることが不可能となるのは時間の問題のようである。 日向湖から来た道を浦見川へと引き返す。 浦見川沿いの道は渓谷の道を行く雰囲気である。 かなりの上りがあって、下りに入る。道は勿論舗装なしで、川側には転落防止用の柵などもないので、余り川側に寄り過ぎて崖下に転落しないよう要注意である。かなりの高低差であるから落下したら大怪我だろう。(浦見川) 水月湖に出る手前の橋の上から浦見川を撮る。 まるで自然の深い渓谷のような水路。とても人工のものとは思えない。 久兵衛さんが指揮を取った開削工事が、さぞかしの難工事であったことが自ずからに理解される。(同上・水月湖側 上部開けた先が水月湖である。) 水月湖畔に到着。 湖畔に旅館だか料亭だかそれらしき建物があるのだが、もう廃業されているのか、休業中なのか、何やら打ち捨てられた感じで、人の気配がありません。(水月湖) 相変わらず雨が降り続いている。(同上) 水月湖から菅湖への道は、暫し湖岸を離れての、畑や木立の中の道となる。南へと下って行くと、右手に菅湖が見えて来た。(菅湖) 菅湖は奥で水月湖とつながっているので、上の写真で言えば、左右の山影が切れている中央部分の奥は水月湖である。(同上) 上の写真の奥の山の向こう側が水月湖。ヤカモチはこの山の向こう側から右手の山沿いの道を湖岸沿いにこちらへと銀輪を走らせて来たことになる。(野鳥観察舎) 野鳥観察舎なるものが目にとまる。どんなものかと立ち寄ってみた。 利用する人も居ないのか、放置されている感じの丸太小屋。2階部分への木組みの階段には、狸か熊か野生動物のものと思われる糞が点々とある。それらを踏まぬように注意しながら、観察ルームに入ると、糞は更にも酷い状態で、とても足を踏み入れる気にはならない。 それに観察用の窓部分は、ビニールかプラスチック製の透明素材を貼り付けたものであるのだが、汚れていて余りよく見通せない。野鳥観察のためなら、これは無い方がいい。雨や雪が舞い込むかも知れないが、ケモノたちの糞の状況から見ても、冬の積雪期にこの小屋に来て野鳥を観察しようというような人は居ないのだろうと思う。 どうであれ、適切な維持管理ができないのなら、こんなものは造らない方がいい。不衛生極まりない気持ちの悪い物を見てしまって興醒めもいいところである。 これを過ぎたところで道は直進と右折の二股道になる。(菅湖から三方湖への道 ―線:予定のコース ー線:実際のコース) この先で道を間違うのであるが、その経緯を説明するのが難しいので、上の略地図で説明します。 A地点が野鳥観察舎のある場所。 これを南下すると道はカーブして東向きとなる。ここで東に直進する道と南へ右折する道とに分岐する。 右折する道を行く。ここまでは地図の予定コース通り。 B地点が問題の地点。 ここで―線のように直進なのであるが、―線のように左折してしまったのでした。 何故このような間違いをしたかと言うと、―線のような道はなく、道としては左カーブの一本道の形状をしていたからである。少しばかり左にカーブしてまた右にカーブして南に向くのだろうと思いながら走っていた次第。 ところが一向に右に入る道が無く、そのうちに頭の中で方角に混乱が生じて来て、どちらを向いて走っているのかが怪しくなって来た。 手許の地図は濡れて滲んでぐちゃぐちゃになっているから、確かめようもない。そうこうしているうちにC地点に出た。もう、方向感覚が狂ってしまっているから、右に行くべきか、左に行くべきかが分からない。すると運の悪いことは重なるもので、サイクリングロードと書かれた矢印の表示板があって、その矢印が「左折方向」を示していた。 で、D地点まで行ってしまう羽目に。ここで、何やら記憶にある景色となり、出発地点の気山駅の踏切近くまで戻って来てしまっていることに気付く。 こうなると、もう元の正しいコースに立ち返ることは困難。その気力もない(笑)。仕方がないので、国道27号を走って、三方駅まで行き、そこから三方湖に回ろうと、D地点から高い場所にある国道27号に出るためE地点に向かって坂道を上る。 ところが、国道27号は歩道が無く、折からの雨もあって、猛スピードで走る車が跳ね上げる水しぶき、特に大型トラックのそれなどを目にすると、とても車と並走して車道を走る気にはなれない。 D地点に引き返し、C地点経由でJR線沿いの道を南へ、F地点方向へと進み、三方駅を目指すこととする。 ネット地図で下調べをした―線の道は、舗装のされていない、久々子湖沿いのぬかるみ道のような道であったのかもしれない。B地点でその道の入口を見落としてしまうような細道であったのかも。図上作戦の限界という奴である。 そろそろ、昼食のことも考えなくてはならないのであるが、何処にもそのような店が無い。喫茶店などそれらしき店もあったが、どれも休業中なのか廃業したのか、店は閉じたままである。 三方まで行けば何とかなるだろうと南へと走る。 やがて、三方石観音という表示のある交差点に出る。ここの参道には万葉歌碑があることを下調べによって知り、三方五湖を巡った後に立ち寄る計画でいたので、道を間違って順番が狂うことになるが、三方湖よりも先にこれに立ち寄ることとする。 交差点を左折し、東へと坂道を上る。JR線(小浜線)の踏切を渡って、国道27号に出ると、道の向かい側に石観音の参道と駐車場への入口の表示があった。ここから上って行くようである。 さて、突然ですが、書くのに疲れました。 ここで、小休止とします(笑)。 続きは明日にします。(つづく)
2019.05.06
コメント(5)
-

小浜・三方五湖銀輪散歩(その1)
少し前のことになりますが、他の記事が色々とあってアップせぬままにいた銀輪散歩の記事をアップします。 小浜と三方五湖を銀輪で少しばかり走ってみようとやって来たのだが、三日間、酷い降りではないものの、ずっと雨でした。初日(4月24日) 京都発の湖西線敦賀行き新快速で敦賀へ。 敦賀から小浜線に乗り換え小浜へという段取り。 予めネットの路線検索で調べたところでは、敦賀着12時15分で、12時20分発の東舞鶴行きに乗り換えとなっていたのだが、京都発の時点で既に3~4分の遅れ、湖北に入って強風のための徐行運転と相成り、敦賀に着いたのは12時27分、乗る筈の電車は出たあと。次の電車は13時13分発。45分以上もの待ち時間となる。 敦賀での乗り継ぎ時間が短いので、京都で駅弁を買って、敦賀到着前に車内で昼食を済ませてしまったのですることもない。駅を出て、駅周辺をブラブラ。と言っても小雨が降っているので、アーケードのある通りだけであるから、意気は一向に上がらない。 既に出だしから雲行きの怪しいことになっていたのでありました。 尤も、近江塩津から新疋田にさしかかった頃から雨は降り出していたのであり、今更雲行きがどうのという問題ではなかったのであるが、それに追い打ちをかけての乗り継ぎ失敗は、わが前途を暗示していたのでありました。(敦賀駅) 崇神天皇の時代に朝鮮からやって来てこの地に来着、崇神天皇崩御に遭遇し、次の垂仁天皇に3年間仕え、帰国して任那を建国したという人物で、敦賀(角鹿・つぬが)の地名の由来となったという、ツヌガアラシトの像が駅前に建っていた。 敦賀は、気比神宮のすぐそばのホテルに宿をとって、金ヶ崎や海岸沿いを銀輪散歩したことがあるのだが、それはもう20年近くも昔の事であり、当時はこの像は無かった筈だし、以来この駅に降り立つということも無かったと記憶するので、ツヌガアラシトさんとは初対面ということになる。<参考>囲碁例会・比賣許曾神社 2012.2.8.(ツヌガアラシトの像)<参考>都怒我阿羅斯等・Wikipedia 敦賀発13時13分東舞鶴行きに乗車。 ワンマンカー2両編成で、ICOCAカードは使えないので、窓口で切符を買わなくてはならない。 小浜着14時17分。 予定よりも55分遅れての小浜到着である。(小浜駅 この写真は到着時のものではなく、翌日朝に撮影したもの。) 駅前のホテルにチェックイン。 宅配便で送って置いた自転車・トレンクルで早速に銀輪散歩に出る。 雨はパラパラ程度なので上衣だけ雨具を着用。 小浜城跡だけでも行ってみるかと走り出すが、少し商店街や路地なども走ってみようと暫くあちこちをウロウロ。徘徊である。 最初に目に入ったのは杉田玄白の顕彰碑。<参考>杉田玄白・Wikipedia(杉田玄白顕彰碑) この顕彰碑を見て、杉田玄白が小浜の出身であったことを初めて知る。 菊池寛の「蘭学事始」という小説をワクワクしながら読んだのは小学生の時。杉田玄白や前野良沢という名は、子供時代のヤカモチにも近しいものであったのだが、小浜とは結びつかぬまま今日まで来たようである。<参考>菊池寛「蘭学事始」青空文庫 隣の銅像が杉田玄白だろうと遠くからカメラを向けて撮影したる後、近寄ってみると、違った。 梅田雲浜という初めて聞く名前の幕末の志士であったが、安政の大獄で捕らえられた中の一人であったようです。<参考>安政の大獄・Wikipedia(梅田雲浜像) 安政の大獄で思い浮かぶ名前と言えば、吉田松陰や橋本佐内くらいですかな、ヤカモチ的認識は。 今日よりは、この梅田雲浜先生も覚えて置くこととしましょう。<参考>梅田雲浜・Wikipedia(同上・副碑) で、その杉田玄白であるが、その像は、ヤカモチの背後、顕彰碑や梅田雲浜像のある公園とは道路を挟んで向かい側の病院の前庭側の道路沿いに建っていたのでした。そして、この病院の名が杉田玄白記念公立小浜病院であるということにも気が付いたのでした。(杉田玄白像)<参考>杉田玄白・Wikipedia 杉田玄白記念公立小浜病院・Wikipedia(同上・副碑) さて、再び、前の公園に目を戻すと、もう一つこんな句碑があった。 西田當百という川柳作家の句碑であった。(西田當百句碑)天下泰平 晩酌の 量が増し (當百) 西田當百。この人物のことも存じ上げない。名前も初耳である。 大阪は法善寺横丁にこの人の句碑があると言うのだから、目にしたことがあったかも知れないのだが、記憶にはない。(同上・副碑) 路地に入ったり、広い通りに出たり、適当に走っていて、「蓮如上人御留錫舊地」という文字が目にはいったので、妙光寺という寺に立ち寄ってみたのだが・・。(妙光寺) 何と言ってこれに関する説明案内板のようなものは境内では見つからなかった。蓮如がこの妙光寺に立ち寄ったことがあるということなんだろうが、詳細は分からない。 ネットで調べると、この寺の開基は足利尊氏の孫で蓮智という人物によるもので、蓮如が1年間この寺に滞在した、と書かれている記事があったが、詳細が分からないので真偽のほどは不明である。(同上) 小浜城跡へ向かう。 小濱神社とあるのが小浜城跡でありました。 石垣が城跡であることを偲ばせる。(小濱神社) 小濱神社は、小浜藩初代藩主酒井忠勝を祀る神社。 旧幕臣らによって明治8年(1875年)に小浜城本丸跡に創建された。(同上・拝殿)(同上・本殿)<参考>小浜藩・Wikipedia(小浜城跡・天守台跡)<参考>小浜城・Wikipedia(同上) 本丸の石垣を残すのみ。 まあ、城跡なのだから、それでいいというものではある。(同上・説明碑)(同上・天守閣跡からの眺望 左:南、中央:西、右:北) 天守台に立ってパノラマ撮影したのが上の写真。 天守台に立つと西方向に若狭湾が見える筈なのだが、高さが不足、立ち並ぶ建物群に視界を遮られて、よく見えない。北寄り方向にわずかに小浜湾の海面が望まれる。(小浜城案内板)(初代藩主・酒井忠勝)<参考>酒井忠勝・Wikipedia 石垣を撮影していると、道端に出て居られたご近所の男性から「どちらから?」と声を掛けられる。 「大阪からです。」 「それはご苦労さま。」(小浜城石垣) パラパラ程度だった雨がそこそこに降って来たので、止む無し。早々に退散である。 ホテルへ引き上げる。二日目(4月25日) 朝、ホテルの窓から外を見ると、大した降りではないが、雨が降っている。山に雲がかかって、山上を隠している。(小浜駅南東側の山々 ホテルの窓から) ※写真左が東小浜・敦賀方向、右が小浜・勢浜・東舞鶴方向 小浜駅から鉄道で気山駅まで行き、そこを起点に三方五湖を最短コースで全部見て、三方駅に戻り、再び電車で小浜駅に帰って来るという計画であるが、それはページをあらためてということにし、本日はここまでとします。(つづく)
2019.05.05
コメント(2)
-
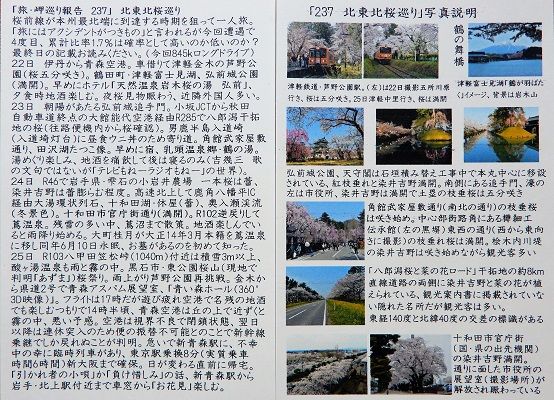
岬麻呂旅便り237・北東北桜巡り
昨日(2日)に届いた岬麻呂旅便り。写真の方はひと足早く4月27日にメールで送信いただいていましたので、実に平成時代と令和時代を股にかけての旅便りであったことになります。 今回は、桜を求めての、青森県、秋田県、岩手県を巡る全845kmロングドライブ、3泊4日の一人旅であったようです。(旅・岬巡り報告237&写真説明)4月22日伊丹空港~青森空港~津軽金木・芦野公園~鶴田町・津軽富士見湖~弘前城公園~ホテル天然温泉岩木桜の湯・弘前泊(津軽鉄道・芦野公園駅 22日撮影五所川原行き) この日の桜は五分咲き程度。 最終日25日に再挑戦することとなる。(津軽富士見湖・鶴の舞橋 奥は岩木山) 富士見湖の桜は満開。 対岸に見えている桜はソメイヨシノとヤマザクラだそうです。(弘前城公園 天守閣) 弘前城天守閣は只今石垣の積み替え工事中で、本来の場所から本丸の中心のこの場所に仮移設されているとのこと。 満開のベニシダレとソメイヨシノが寄り添っています。 夕食では例によって地酒を楽しみ、夕食後は夜桜見物。ここでも中国・韓国の観光客が多かったそうな。(弘前城・南濠夜景)4月23日弘前城追手門~小坂JCT~秋田自動車道・大館能代空港~国道285号~八郎潟干拓地~男鹿半島・入道崎~角館武家屋敷通り~田沢湖たつこ像~乳頭温泉郷・鶴の湯泊 朝日に照らされる追手門を見むとて・・。(早朝の弘前城南濠と追手門 朝7時49分撮影) 八郎潟干拓地へ。(八郎潟干拓地 往路便機内から撮影) 上は、往路便の飛行機の窓から撮影されたものとのことだが、「往路機内から桜確認」と記されている通り、大きいサイズの写真でご覧いただくと、桜並木がしっかりと見て取れます。(八郎潟・桜と菜の花ロード) この後、角館武家屋敷通りの桜に向かわれるのであるが、花よりウニ丼と、昼食のため男鹿半島入道崎に立ち寄られました。入道崎灯台が目的かと思いきや、うに丼とは・・。 昼めし時となると「岬麻呂」を返上「ウニ麻呂」となられるようであります(笑)。勿論、夕めし時は「酒麻呂」ですが・・。 さて、角館武家屋敷通りに到着です。(角館武家屋敷通りの桜) そして、乳頭温泉・鶴の湯に投宿、湯巡りを楽しみ、またまた地酒をたらふく飲んで、「寝るしかねェ~」とzzzzzzzzでありました。4月24日国道46号~岩手県雫石・小岩井農場の一本桜~鹿角八幡平IC~大湯環状列石~十和田湖・休屋~奥入瀬渓流~十和田市官庁街通り~国道102号~蔦温泉泊(蔦沼散策、大町桂月墓)(小岩井農場・一本桜) 十和田市官庁街通りの桜を楽しみ、(十和田市官庁街通りの桜)(同上・十和田市役所庁舎展望室から撮影) そして、この日も蔦温泉で地酒を楽しみ、でありました。4月25日国道103号~八甲田笠松峠~黒石市・東公園~芦野公園再挑戦~金木から県道2号~青森アスパム展望室、青い森ホール(360度3D映像)~青森空港(欠航)~新青森駅へ~新幹線乗車~東京駅経由・新大阪着(黒石市・東公園) 東公園の桜の後、芦野公園に再挑戦。 今度は満開の桜とご対面であったとか。(芦野公園・25日撮影、津軽鉄道・津軽中里行き) この後、青森空港は視界不良で閉鎖状態、復路便は欠航、翌日便への振り替えは、連休突入で満席状態で不可能、急遽、新青森駅へ急行し、新幹線確保。東京経由で日付の変わる直前になんとか無事にご帰宅あそばされたとのこと。いやはやお疲れ様でした。 旅にあっては、仰る通り、この程度のアクシデントは楽しむべしかも知れませんね(笑)。
2019.05.04
コメント(3)
-

墓参・花散歩とヌケガケレンゲ
昨日(2日)は、月例の墓参。 墓参に出掛けようとして、郵便受けを見ると、4件の郵便物の中の一つが友人・岬麻呂氏からの旅便りでした。 これは、明日にでも記事にするとして、本日は墓参の記事とします。 我が家の墓地は、生駒山の西麓の高みにあるので、結構な坂道を上って行くことになる。 さて、墓地への坂道にさしかかると、何やら甘い香り。ヤカモチは余り好きな香ではないのだが、ハゴロモジャスミンが今を盛りと咲いているのでありました。(ハゴロモジャスミン) ハゴロモジャスミンの咲いている場所は、ロウバイの咲く場所でもあるのだが、今はあの独特の形をした実をつけている。 そこから更に坂を上ったところの民家の門口を美しく飾っているのが、白いバラの花。(蔓性の白いバラ) バラの品種などは知るよしもないヤカモチ。 白いバラと言うしかない。(同上) 白バラの家からほんのちょっと上ったところで右(南)に入る路地がある。その角にある寺の門前が、墓参のたびに「門前の言葉」として毎度紹介している掲示のある門前なのである。(今月の言葉) 今日の言葉はこれ。毎月に更新されるので「今月の言葉」と言うのが正しい表現かも。 自然でない行いは、自然でない混乱を生む。 (病気になった心は、聞こえぬ枕に秘密を打ち明ける。) ――シェークスピア「マクベス」より 道理に外れたことを「それはおかしい」と言わず、受け入れていると、当人個人としても内部に矛盾が蓄積して人格の混乱・歪み・崩壊が生ずるだろう。そして、皆が皆そのようであれば、その社会も、その組織もやがては異様な歪みを生じ、混乱し、崩壊するというものである。 路地を突き当たった先にある、もう一つ南側の坂道を上って行くと墓地である。 その入口手前にある池の畔にある一本のアキニレ。 その若葉が美しい。5月、青葉の季節なのだ。(アキニレの青葉と青空) 墓地に到着。 花を取り替え、線香を立て、祈る。 祖父母、父母、幼くして先に逝ってしまった妹、娘らの面影を思い浮かべつつ、彼らのことを思う。(墓地から南西方向の眺め) 墓地は高みにあるので、大阪平野が一望である。 この日は、少し霞んでいて、景色はさほどに鮮明ではないが、あべのハルカスも見えている。 墓まわりの除草。 頻繁にお参りされる墓とそうでない墓とは、墓まわりの草の具合でそれと分かる。 墓まわりでよく見かける草は、カラスノエンドウ、スズメノエンドウ、アメリカフウロ、マツバウンラン、アメリカフウロ、ムラサキツユクサ、ヒメウズ、ホソムギ、オオバコ、マツヨイグサなどなど。(スズメノエンドウ) これはスズメノエンドウか。目視ではスズメノエンドウと思ったが、写真で見ると、それより少し大きいカスマグサかも知れない。 カラスノエンドウもスズメノエンドウも実を付けている。(カラスノエンドウ) カラスノエンドウの豆莢には、アブラムシが。(同上) スズメノエンドウも実を付けている。 カラスノエンドウにはアブラムシの姿が見えるが、スズメノエンドウには見られない。草の茎などから吸汁するアブラムシ。カラスノエンドウがあるのに、水分の少なさそうなスズメノエンドウにたかる必要はないということだろう。 白米のご飯よりも麦飯や五穀米ご飯という健康志向の人間世界を真似て、そのうちにアブラムシたちもスズメノエンドウを見直そうということになるのか。(スズメノエンドウ) 写真では、カラスとスズメの大きさの違いがよくは分らないでしょうから、両者を並べて撮ってみました。(カラスとスズメの大きさ比べ) カタバミが黄色い花を咲かせている。 普通のカタバミよりも、これはやや大きい花を付けている。オキザリスとして色々な園芸種のカタバミの仲間が最近は野生化して見かけるようになったが、これもその一種だろうか。 ブラックバスやブルーギル、アライグマやミドリガメ、ペットとして販売された動物が生態系に異変を生じさせたり、害獣化したりする問題を引き起こしているが、園芸植物も同じだろう。 余り繁殖力の強い植物はノーサンキューである。(カタバミ) こちらは、キュウリグサ。(キュウリグサ) キュウリのような香がするとのことだが、摘んで指ですり潰してその香を嗅いでみたことがあるが、タバコを喫いながらであったせいか、そんな香はしなかったように記憶する。(同上) これはセイヨウオオバコ。 オニオオバコともいうそうだが、在来の昔馴染みのオオバコに比べて茎も太く、背丈も高い。 最近は、こいつが圧倒的に多く、普通のオオバコを目にすることが少なくなっている。(セイヨウオオバコ) そして、マツバウンラン。 これも群生して咲き、風に靡いている眺めなどはいいものであるが、わが墓地では、どんどん除草されてしまうので、そのような景色にはなりそうもない。(マツバウンラン) これは、ムスカリの実。 墓地ではなく、帰途の民家の塀際にあったもの。 これだけを見たのでは、ムスカリのそれだとは気付かなかったと思うが、先月の墓参の折には花が咲いている時であったので、ムスカリの実であると気付いた次第。 殆ど実が零れ落ちた後のようですが、ムスカリの実がこのようなものであるというのを初めて知りました。(ムスカリの実) 次は、ナガミヒナゲシの実三態です。 繁殖力旺盛なナガミヒナゲシ。 先般、ブロ友のひろみちゃん氏、ふろう閑人氏などがこの花のことを記事にされていましたが、そんなことも記憶にあって撮影してみました。(ナガミヒナゲシの実) まだ花が咲いている状態で、既に実の方がかなり大きく育っています。 花が散った後で、まだ雄蕊の残骸が周囲にこびりついている状態が下の写真。(同上) 雄蕊の残骸が剥がれ落ちて、実だけになったもの。 まだ、頭頂部に蓋が付いているが、これが剥がれ落ちて坊主になると、実としては完熟ではないかと思う。 この実・芥子坊主の中に1000から2000もの種子が入っているというから驚きである。従って、若い未熟な実であっても、相当数の種子が発芽できる程度まで育っていることが多く、この植物を完全除去するためには、ロゼット状態の若いうちに引っこ抜く必要があるとのこと。(同上) 次はヤマボウシ。 これは、墓参の折の写真ではなく、その日の午後に銀輪散歩に出掛け、恩智川沿いの加納緑地で見掛けたものです。(ヤマボウシ) この花を見ていて、その葉の感じから、先般の向島百花園で見た「何の花であったか」と記した花はヤマボウシであったのではないか、などと思ったりも・・。(同上) 最後に、「抜け駆け」されたオオヤマレンゲの花です。 これは1日に石切にあるホームセンター、コーナンにコピー用紙ほかを買いに行く用があったついでに、4月29日の記事(下掲)にて紹介したオオヤマレンゲの蕾のその後を見てみようと、それが咲く病院の庭に立ち寄って撮影した写真です。<参考>ブログ開設12周年 2019.4.29.(オオヤマレンゲ) 同記事で「ゴールデンウイークのうちに咲くと見込まれる」と記した蕾は、一番外側の花弁が少し持ち上がって開花の準備に入った風ですが、このようにまだ蕾状態です。 ブロ友のひろみちゃん氏が「一輪咲いていたので」と「抜け駆け」された花(下掲<参考>参照)は、これとは別の蕾がひと足早く咲いたもののようでした。<参考>病院の花 オオヤマレンゲなど 2019.4.30.(同上) 上と下、二輪咲いていましたので、ひろみちゃん氏が撮られた「ヌケガケレンゲ」の花がどちらとは分かりませんが、どちらかが平成最後に開花し、どちらかが令和最初に開花した花ということかも。 29日の当ブログ記事で紹介した蕾は、27日の午後3時頃に撮影したものかと思うが、数個あった蕾の中で、その時点では一番大きなつぼみであったので、これが一番先に咲くだろうと見込んだのでしたが、競馬と同じで先行逃げ切りというのはなかなか難しいものらしく、他の二輪に追い抜かれてしまったようです。(同上) オオヤマレンゲよりもひと回り小さく八重咲の品種はミチコレンゲと名付けられているようですが、その名は美智子皇太后がお好きな花だからということらしい。そんなこともあって、一輪は美智子様がまだ皇后であられる平成のうちに、そして他の一輪は皇太后となられた令和の最初の日に開花して、その思いを表したということも言える。 一方、ヤカモチが目をつけたヤカモチレンゲの方は、そういう忖度とは無縁の「我が道を行く」タイプなようで、いたって呑気、まだつぼんだままなのであるが、これはこれでよろしい(笑)。 以上、墓参兼花散歩の記事でした。 虫の写真なども撮りましたが、花散歩なので、割愛。 これらは、追って、虫を取り上げる時に紹介申し上げます。
2019.05.03
コメント(2)
-

第210回智麻呂絵画展
第210回智麻呂絵画展 令和初日の記事は智麻呂絵画展であります。<参考>過去の智麻呂絵画展は下記から。 第1回展~第100回展 第101回展~第200回展 第201回展~ フォト蔵の智麻呂絵画集アルバムはコチラ。 前回が3月11日でありましたから、久々の智麻呂絵画展となります。 今回は令和初日ということで、こちらもおめでたい絵から始めます。(Happy Weddingーmay love bloom forever!) 智麻呂・恒郎女ご夫妻のお孫さんのK君が先般ご結婚されました。 その披露宴の折、智麻呂氏の席の卓上に飾られていた花でしょうか。 愛の花よ永遠たれ、との思いを込めて描かれたのでもあろうと、ヤカモチが上記のようなタイトルを勝手に付けさせていただきました(笑)。 この場合、個々の花が何であるかを問うのは「野暮」というもの。 すべてが愛の花であるのだから。 次は、「愛の花」ではなく、いわば「友情の花」であります(笑)。(アイリス) 上のアイリスと下の水仙及び喇叭水仙は、智麻呂氏のお友達である友〇さんが「絵の題材に」と下さった花であります。(水仙)(喇叭水仙) 次のクリスマスローズは凡鬼・景郎女さんご夫妻からのもの。 ご自宅の庭に咲いていたものをお持ち下さいました。(クリスマスローズ) 次は、桜と桃。 大阪では、もう桜も桃もその季節は過ぎ去ってしまいましたが、遅ればせながら、もう一度お花見をしていただきましょう。(桜)(桃) 桜はご近所に咲いていたのを、桃は大阪城公園の桃園に咲いていたのを描かれました。 次は、タケノコ。 恒郎女さんが食材にと買い求められたのを、「ちょっと待った」と絵のモデルにしてしまうというのが智麻呂流であります。(タケノコ) 金色に輝くタケノコでありますが、普通のタケノコ。 かぐや姫が生まれ出ることはありませんでした。 次は、気分を変えて、風景画。 こちらは、當麻寺ですから、かぐや姫ではなく中将姫ですな。(當麻寺の奥院楼門) これは、偐山頭火さんからいただいた写真から絵にされました。 写真の写りがどうであったのかは存じ上げないが、「楼門」の「楼」の字が読み取れなかったのか、「門」とだけあるのが、ご愛嬌であります。 次のワスレナグサも偐山頭火さんからのもの。(ワスレナグサ) 銀輪散歩でお近くまで来られたついでの智麻呂邸へのお立寄りの際にお持ち下さったものかも知れません。(八重のツツジ) これは、ご近所の玉〇さんが絵の題材にと下さったものです。 八重咲きの珍しい品種。とても可愛いツツジです。 咲き初めの状態だと薔薇の花のように素敵、とは恒郎女さんの言。 尤も、ツツジからすれば、これでも「にほへをとめ」、バラの風下に立つかのような物言いは失礼なるぞ、というものかも知れない(笑)。(椿・太神楽) これは、ひろみの郎女さんがお持ち下さったもの。 ひろみ邸の庭に咲いた最後の一輪だそうです。 以上です。 今回は、全12点。うち10点が花の絵と、花の智麻呂らしい絵画展となりました。 新しき令和の代が、皆さまに幸い多き代でありますように。そして、引き続き智麻呂絵画展をよろしくご愛顧たまわりますように。 本日もご覧下さり有難うございました。
2019.05.01
コメント(8)
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンでパートナーと相談…
- (2025-11-13 20:30:13)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 11月14日のツキアップ
- (2025-11-14 08:50:52)
-







