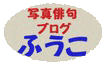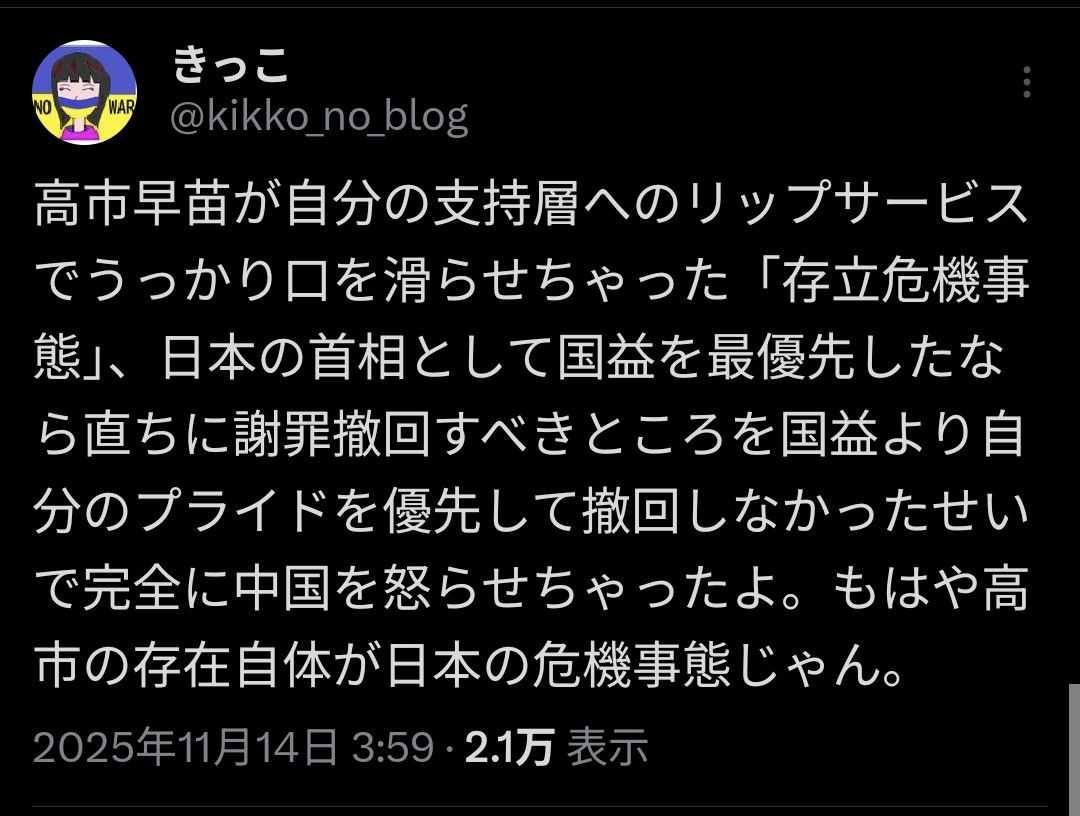2022年08月の記事
全12件 (12件中 1-12件目)
1
-

第19回青雲会囲碁大会2022
昨日(27日)は大学同窓会・青雲会の囲碁大会の日。 今年の会場は、阪急産業梅田ビルの5階にある梅田囲碁センター。 12時50分集合ということで、鶴橋経由大阪環状線で大阪駅へ。梅田地下街の喫茶店で昼食を済ませてから会場に向かう。会場は、梅田地下街・ホワイティうめだのイーストモールを東へ、突き当りの「泉の広場」の14番出口の階段で地上に出た先にある。 泉の広場にやって来るのも久しぶりのこと。 中央に沢山のヒマワリ。 ヒマワリの花を見ると、ウクライナのことが思われるが、これは別にそのようなことで飾られているのではなさそう。(梅田地下街・泉の広場) 地下街を歩いていると、浴衣姿の若い女性が目立ったが、この日は、淀川の花火大会がある日であったので、それに出かける予定の女性たちであるのだろう。 ヒマワリを横目に、14番出口の階段を上がって地上に出ると、右手一つ先にそのビルはあった。(阪急産業梅田ビル<右手>) 1階がコンビニ・デイリーヤマザキで、5階に「梅田囲碁センター」の袖看板が掲出されている。 青雲会の囲碁サークルの例会は、かつては毎月開催されていたが、最近は3ヶ月に1回のペースになっているらしい。ここ何年間は、例会は欠席続きで、年1回、この囲碁大会だけに参加しているヤカモチなので、例会のことはよく存じ上げない。従って、この梅田囲碁センターには初めて来たのだが、このところの例会は此処で行っているらしい。(エントランスの表示板) エントランスで表示を再確認して、エレベーターで5階へ。 すでに世話役の銭〇氏が来て居られた。 しばらく彼と雑談しているうちに出席予定者全員が集合。 今回は、銭〇氏、廣〇氏、五〇氏、山〇氏、川〇氏とヤカモチの6名。 昨年は4名という少ない参加者であったが、それに比べれば6名であるから、2名増ではあるが、それにしても少ない。コロナの所為もあるが、メンバーの高齢化によって、物故者、体調不良による退会者が出る中、新規に参加する若い会員が余り無く、会員数が減少して来ていることも影響しているのだろう。過去記事を参照すると2012年の19名参加を最高に、2017年までは12名を下回ることはなく、15名前後の参加があって、まあ、「大会」と称しても左程に違和感がなかったのであるが、このところは「大会」というは名ばかりなり、の状態である。 それはともかく、ヤカモチは2010年から毎年参加しているので、13年連続出場ということになる。(梅田囲碁センター) 上の写真は、我々とは関係ない皆さん。小学生の姿もありました。 さて、あみだくじの結果、対戦表が決まる。 一回戦は、五〇vs川〇、山〇vs銭〇と決まる。廣〇vsヤカモチは二回戦となり、この勝者と前記一回戦の勝者同士の対局で勝った者とで決勝戦を行うことと決まる。 一回戦の勝者は川〇氏と銭〇氏。この両者で決勝戦進出を争うこととなる。一方、最初から二回戦となった廣〇vsヤカモチ戦はヤカモチの中押し勝ちで、ヤカモチが先ず決勝戦進出を決める。川〇vs銭〇戦は銭〇氏の勝ちとなり、決勝戦は銭〇vsヤカモチということになる。 決勝戦は、終盤でコウ争いとなり、コウ立てにミスをしたヤカモチの逆転負けとなった。銭〇氏が昨年に続いての優勝でありました。 ヤカモチは、この本戦以外にも、五〇氏と山〇氏とも対局しましたが、何れも負けたので、本日の成績は1勝3敗でありました。<参考>過去の青雲会囲碁大会記事は下記の通り。〇青雲会囲碁大会2021 2021.8.28.(参加者4名)〇第17回青雲会囲碁大会 2020.8.22.(同8名)〇2019青雲会囲碁大会 2019.8.31.(同9名)〇2018年青雲会囲碁大会 2018.8.18.(同8名)〇2017青雲会囲碁大会 2017.7.8.(同12名)〇青雲会囲碁大会・秋の気配 2016.8.28.(同14名)〇青雲会囲碁大会2015 2015.8.22.(同16名)〇2014年第11回青雲会囲碁大会 2014.8.2.(同15名)〇第10回青雲会囲碁大会2013 2013.8.10.(同16名)〇青雲会・第9回囲碁大会 2012.8.11.(同19名)〇第8回青雲会囲碁大会 2011.8.13.(同14名)〇青雲会囲碁大会で優勝 2010.8.14.(同15名) 大会終了後、阪急東通り商店街の寿司屋に席を移して、懇親会。 川〇氏は、何か他用ありとのことで、帰途につかれたので、5人だけの懇親飲み会。旧交を温めました。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~We stand with Ukrainians.Wake up and look at the truth,Russian peoples.
2022.08.28
コメント(2)
-

健人会・納涼昼食会
今日は、健人会の納涼昼食会。 今年1月19日の新年会以来の参加なので、皆さんとは7ヶ月ぶりの再会である。会場は、その新年会と同じで、大津市・石山寺の近くの料亭「新月」で、正午開会。 JR石山駅前での送迎バス発車時刻11時35分という案内に合わせて、家を出る。今回もトレンクルによる銀輪散歩はなしで、電車での往復である。<参考>健人会新年会 2022.1.21. JR石山駅に到着すると、2階改札前の通路に既に数名の方が集まって居られました。地元の岡〇氏は料亭「新月」の徒歩圏内にお住まいなので、彼を除く出席予定者全員が揃ったところで、送迎バスに移動。(JR石山駅) JR石山駅の南口側、京阪・石山駅との連絡橋広場に芭蕉像があるが、送迎バスは北口側に駐車しているので、芭蕉さんにはご挨拶せぬままにバスに乗り込みました。(帰りは南口で送迎バス降ろしていただいたので、その気であれば、芭蕉さんにご挨拶可能であったが、彼のことは忘れてしまっていました。)<参考>石山駅前の芭蕉像の写真掲載記事は下記です。 またも唐橋 2013.1.17. 石山寺散策(続々) 2015.9.5. 今日の出席者は、只麻呂氏、平〇氏、岡〇氏、徳〇氏、今〇氏、草麻呂氏、森〇氏、竹〇氏、平〇J氏、正〇氏、〇庭氏、生〇氏、北〇氏とヤカモチの14名。 地元の岡〇氏が最後に来場されて全員集合。世話役の草麻呂氏による開会の挨拶の後、平〇氏の発声で乾杯。アトは例の通り、いつもの通りのワイワイガヤガヤの宴会。(瀬田川) 料亭「新月」の部屋からの眺めです。 左側が上流・琵琶湖方向、右側が下流・宇治方向。<参考>瀬田川・宇治川の銀輪散歩記事は下記参照。瀬田川・宇治川銀輪散歩(獺の祭見て来よ瀬田の奥) 2014.3.12.瀬田川・宇治川銀輪散歩(わが庵は都のたつみ) 2014.3.13.瀬田川・宇治川銀輪散歩(もののふの八十宇治川の) 2014.3.14.瀬田川・宇治川銀輪散歩(秋の野のみ草刈り葺き) 2014.3.15.(同上・上流、琵琶湖・唐橋方向) この会が終わり次第、米子へ友人とゴルフをするための3泊4日の旅に立つという正〇氏の都合に合わせた訳でもないのだろうが、いつもより早い2時半での中締めとなりました。 今回出席の最年長者只麻呂氏による締めの挨拶でお開きとなり、送迎バスで石山駅へ。 京都駅で皆と別れて近鉄に乗り換え、大和西大寺へ。 大和西大寺駅は、先月(7月)の8日以来。7月8日と言えば、安倍元首相が銃撃によってこの駅前で殺害された日。<参考>鈴木清方展 2022.7.8. 西大寺駅の改札前通路(2階)からは、その場所が一望である。(近鉄大和西大寺駅北口、安倍元首相が銃撃された場所) 来月27日に安倍さんの国葬をすることになっているが、今日閣議で予備費から2億5千万円をあてることが決定されたとのこと。 国葬についての根拠法もなく、国葬とは何であるのかが曖昧。国民にも反対意見や疑問視する意見の方が多くなりつつある。何故、政府・自民党葬ではなく国葬とする必要があるのか。銃弾に倒れたことや最長の在任期間であったということだけではその理由にならない。政治家としての評価も分かれている。桜の会やモリカケ問題・公文書改竄事件なども誤魔化してウヤムヤにしたまま逃げたとかアベノマスクなどの愚策もあった。アベノミクスも成果を上げたのかどうか、国民にとってどうであったのかは評価もイマイチ。要は、決して国民的尊敬を集めた政治家とは言えない。加えて、国葬決定に至るプロセスも説明も適切を欠く。ヤカモチは反対ですな。と言うより頗る不快である。(枚岡神社) 最寄り駅の近鉄・枚岡駅で下車して、枚岡神社の前を通ると、参道にずらりと提灯の列。 何があるのだろうと思ったら、燈明祭だそうな。毎年8月の第4日曜日に行われる行事とのこと。ということは、今年は28日(日)である。 今日の健人会で、平〇氏が越中八尾の風の盆のことを話されていたが、十数年前、この枚岡神社で「おわら風の盆」の踊りが奉納されるというので、見に行ったことがあったことを思い出した。 あれは、この燈明祭に奉納されたものであったのか。今年も同じく「おわら風の盆」踊りなんだろうか。その後、この燈明祭を見ていないので、その辺のところは不明である。<参考>おわら風の盆がやって来た。 2008.8.24.<参考>健人会関連の過去記事はコチラ。We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)
2022.08.26
コメント(0)
-

銀輪散歩・マンホール(その24)
マンホール写真のストックもそこそこ溜まりましたので、今日は「銀輪散歩・マンホール」の記事とします。マンホール写真は、フォト蔵のマイ・アルバム「マンホール」に登録して保存していますが、検索の便宜に資するため、写真のタイトルには当該マンホールの市町村の郵便番号を頭に付したものを使用しています。 これによって、同一市町村のそれはアルバムの中で同じ位置に並ぶこととなり、新規にとり上げるマンホールが、既に掲載済みのものと同一のものかどうかのチェックが容易になります。 今回とり上げる34枚を含め、アルバム内のマンホール写真の数は743枚の多数になっていますので、このような仕掛けをしないと、意図しない重複掲載を回避することが困難となります。 郵便番号で、気が付いたことは、北から、北海道、東北と並ぶだろうという予想に反して、北海道のブロックの中間に青森県や秋田県など東北の市町村のそれが割って入るということでした。 札幌市の郵便番号は001-ですが、秋田市は010-、青森市は038-などで、東北地方の市町村のそれが、函館市の040-~斜里町の099-より前に来ます。 これを防ぐためには、都道府県別に、北から南へ01~47の番号を定めて、これを郵便番号の前に付したものを、整理番号として使えばいいことになるが、今更、それを行うのも面倒なので、それは行っていません。 従って、下記<参考>のフォト蔵マイアルバム「マンホール」の写真は、如上のような配列で並んでいます。<参考>過去のマンホール関連記事はコチラ。フォト蔵マイアルバム「マンホール」の写真はコチラ。過去の岬麻呂旅便り記事はコチラ。フォト蔵・岬麻呂マンホールカード写真集はコチラ。 銀輪散歩・マンホールという記事タイトルですが、今回も、友人・岬麻呂氏提供のものなどが多く、ヤカモチが銀輪散歩で撮った写真は少数派であります。(注)★は、岬麻呂氏提供のマンホールカードを撮影したもの。 ●は、岬麻呂氏撮影のもの。1.大仙市 (左★、右●、大曲花火大会の図柄)※デザインの由来はコチラ。2.仙北市(●桜の図柄)※(その18)、(その19)に掲載のものと同じ種類でした。(●角館祭りのやま行事の図柄)※(その19)に掲載のものと同じ種類でした。3.北海道積丹郡積丹町(●ウニと島武意海岸の図柄)4.北海道余市郡余市町(●リンゴ、リンゴの花、カモメ、アユの図柄)※(その5)に掲載のものと同じ種類でした。5.小樽市 (●小樽運河の図柄) (●ラッコの図柄)※運河の図柄のものは(その17)にカラー版を掲載済み。※ラッコの図柄のものは(その5)に掲載のものと同じ種類でした。6.北海道勇払郡安平町 (●D51の図柄<青版と緑版>)(★同上)※デザインの由来はコチラ。7.北海道空知郡上富良野町(★ラベンダーの図柄)※デザインの由来はコチラ。(●同上<モノクロ版>)※(その21)に掲載のものと同じ種類でした。8.北海道上川郡当麻町(●蟠龍まつりの龍の踊りの図柄)9.釧路市 (●タンチョウの図柄)※釧路市のマンホール掲載記事は下記の通りです。(その13)(その14)(その15)(その21)※上掲のタンチョウの図柄のカラー版は(その13)に掲載しています。(●釧路湿原の図柄)10.北海道標津郡中標津町(●エゾリンドウの図柄)11.根室市(●規格品タイプ)(●北方領土返還祈念シンボル像の図柄)12.長野市 (リンゴの図柄 モノクロ版 右はモザイク仕様)(同上・カラー版)(1998長野オリンピックの図柄)13.千曲川流域下水道(長野市松代町 千曲川と鮭の図柄)14.東大阪市(希来里の図柄)(同上・樹脂製シール版)※東大阪市のマンホール掲載記事は下記の通りです。(その1)(その3)(その4)(その8)(その11)(その15)(その20)15.橋本市(太陽、紀ノ川、鮎、木々、柿の図柄)16.和歌山県伊都郡九度山町(九度山柿の図柄)17.神戸市 下掲のマンホール写真は、友人の蝶麻呂氏が撮影して送ってくださったものであります。(神戸港などの図柄 撮影者:蝶麻呂氏)※神戸市のマンホールは(その20)(その23)にも掲載されています。18.宮崎市(●ハナショウブの図柄)※(その19)に掲載のものと同じ種類でした。(●同上図柄、小型版)※このタイプのカラー版は(その13)に掲載されています。19.新潟市(NTT 鳥屋野潟の図柄)(NTT 鳥屋野潟の四季の図柄)※新潟市のマンホール掲載記事は下記の通りです。(その2)(その4)(その5)(その6)(その8)(その15)(その20)(その23) 以上です。 今日で、ロシアのウクライナ侵略が始まって半年。 依然として出口の見えない戦争が続いている。 一刻も早い、ロシアの撤退を。 ♪幾千万の母と子の こころに合わせいまいのる。 自分のなかの敵だけを おそれるものと なるように、 戦いよ、終われ、太陽もよみがえれ。 (讃美歌第二編70 詞:阪田寛夫、曲:大中 恩)We stand with Ukrainians.(STOP PUTIN STOP WAR)
2022.08.24
コメント(6)
-

大嶽和久君を偲ぶ会
2018年8月21日に逝去された友人・大嶽和久君を偲ぶ会に出席して来ました。彼は、高校時代からの古い友人。若草読書会の仲間でもあった。筝曲の演奏家、作曲家としての生涯でありました。<参考>和麻呂逝く 2018.8.23. 偲ぶ会は、コンサート形式で行われる。 会場は、東大阪市、近鉄若江岩田駅前のイコーラムホール。 午後1時開場、同1時半開演である。(近鉄・若江岩田駅)(同上、右側の建物の6階にイコーラムホールがある。) 駅前の喫茶店で昼食を済ませて、何処かでタバコ一服と店を出たところで、槇麻呂君とバッタリ。彼も高校時代からの友人で若草読書会の仲間。 少し、早過ぎるが会場へと向かう。 午後1時前後に恒郎女さんが来られ、しばらく3人で雑談。(イコーラムホール案内板) 午後1時を過ぎて、開場、受付が開始されたので、会場のホールへと向かう。開演までの時間、ホール前のホワイエで待っていると、偐山頭火君もやって来た。 若草読書会関係では、結局、この3名とヤカモチとの4名だけでした。凡鬼さん・景郎女さんご夫妻もご出席と思っていましたが、何か他用が入ってしまったようで、ご欠席でした。(偲ぶ会・パンフレット)(同上) ホワイエには、大嶽君の写真と、寄せられたお花が飾られていました。(お花) 開演前の会場です。(開演前のイコーラムホール) コンサートの演目は、6曲で、最初の「残月」を除き、他の5曲は全て大嶽君の作曲である。 開演の案内放送がホワイエに流れ、ホールに入場する。1.残月 峰崎勾当作曲2.華やぎ 大嶽和久作曲3.若草の頃 大嶽和久作曲4.夕影の島 大嶽和久作曲5.火の鳥 大嶽和久作曲6.筝協奏曲 大嶽和久作曲 大嶽君の面影やあれやこれやの生前のことを思い出しつつ、箏と三絃の調べに耳を傾けるひとときでありました。 最後に、大嶽五十鈴夫人からのご挨拶。(五十鈴夫人からのご挨拶) 終演後、ヤカモチは素早くホールの外に出たのだが、偐山頭火君はそれよりも早くに場外に出たのか、彼の姿は見当たらず。大嶽君のお嬢さんにご挨拶して、ホール前のロビーへ。 そこで待っていると、恒郎女さん、槇麻呂君が出て来られて、三人で階下へ。1階喫茶店で、また3人でしばし歓談。 帰宅すると、午後4時45分を少し過ぎていました。<追記・参考>若草読書会関係の過去記事はコチラ。
2022.08.20
コメント(2)
-

CB(クロスバイク)で墓参
今日はお盆のお墓参り。 毎月初旬の月例の墓参に加えて、お盆にも墓参をするので、今月二度目となる墓参。通常は自宅から徒歩で墓に向かうのであるが、今日は6月4日以来のマイCB(クロスバイク)による墓参であります。 と言っても、自転車には厳しい急坂を上らなくてはならないので、CBに乗ってというのは、途中の寺付近までで、アトは手押しスタイルで歩くことになる。その途中の寺の門前の言葉は、更新されず先月2日の墓参で見たものと同じなので、撮影せぬまま通過。(マイCB<クロスバイク>) お盆とあって、いつになく墓参の人の姿が多い。自家用車やタクシーでやって来る人も多く、坂を上って来る途中で、墓参から帰る人の車と4度もすれ違いました。狭い道なので、車が来ると道のへりに身を寄せて車を通さなくてはならない。 道幅は、対向車とすれ違える広さではないので、辻など何ヶ所かの少し広くなっている場所でしかすれ違えないから、車での上り下りも今日のような墓参の多い日には、必ずしも楽ではないだろう。 墓参を済ませて坂を下る。幸い途中タクシーが1台上って来ただけであったので、スムーズに走り下れました。一気に、瓢箪山の商店街まで走り下る。 実は、自転車での墓参には理由があって、郵便局に行く用事があったからである。ヤカモチの出身高校の同窓会の年会費と運営賛助金を送金するためである。 その同窓会総会は9月25日に予定されている。コロナ禍ということで懇親会はなく、総会議事と講演会のみで開催される。この点は先般の大学の同窓会と同じ形式である。 今、高校野球、夏の甲子園が開催中であるが、NHK高校野球解説者としてTVでもお馴染みの長野哲也氏が講演されるらしい。長野氏と卒業年次が同じ期が今年の総会の幹事役ということで、同期のよしみで講師をお引き受けになったのでしょう。ヤカモチは高校の同窓会総会はながらくご無沙汰しているが、今回も多分欠席することになりそうです。 郵便局からの帰りは、自宅に向かって坂道を上ることになる。途中で脇道に入って、河内寺廃寺跡のベンチで小休止。汗を拭って水分補給。(国指定史跡・河内寺廃寺跡) 河内寺廃寺跡は以前に紹介しているので、それをご参照ください。 <参考>河内寺廃寺跡 2017.8.23. ヤカモチが子どもの頃は、ここは何の変哲もない水田で、この付近のことをお年寄りたちは「こんてら」と呼んでいました。 かわちでら→こうちてら→こんてら、と訛ったのだろうが、子ども心には、意味不明の何やら不思議な音の響きでありました。 河内長野を経由して高野山へと至る東高野街道から数百メートル東に入った位置にある廃寺跡である。(河内寺廃寺跡から見た今日の空)墓参(ぼさん)すみ しばし憩(いこ)ひの 河内寺(こんてら)の 跡に眺むる 夏の白雲 (偐家持)<参考> 墓参関連の過去記事はコチラ。 自転車関連の過去記事はコチラ。
2022.08.13
コメント(2)
-

400万アクセス
昨日、夜7時47~8分頃、累計アクセス数が400万件に達しました。アクセスも 四百万葉(よほよろづは)を 数へては 葉月(はづき)半(なか)ばの さ夜更けにける (偐家持)(ブログ記事画面のアクセスカウンターの数字) この画面をタイミングよく撮るのは、なかなか難しいのですが、400万までアト30余となっているのに気づき、何回か画面更新をしているうちに、うまくヒットしました。 この時間帯が深夜とか早朝なら、撮影は困難であるが、今回は丁度良い時間帯での節目アクセス数到達時刻でありました。(ブログ管理ページの画面のアクセス表示)<参考>総アクセス数の推移 2007年 4月29日 ブログ開設 2015年10月11日 50万 2016年11月16日 100万 2018年 2月 9日 150万 2019年 3月21日 200万 2020年 1月21日 250万 2020年11月28日 300万 2021年10月28日 350万 2022年 8月11日 400万 四百万(よほよろづ)の 峰越えたれば 五百万(いほよろづ)の 峰の桜も 近しとそ見ゆ (偐家持)四百万(よほよろづ)の 峰は越ゆれど 眺むれば なほしそ遠き 千万(ちよろづ)の峰 (偐家持) まあ、他人様にはどうでもよい(本人にとっても思えばどうでもよい)ことでありますが、このタイプの記事を過去来書いて来て居りますので、継続性の原則により、記事アップであります。 で、ついでに、他人様にはどうでもよいことについての、いくつかの記事も、この際、併せ掲載であります。8月9日 第4回目のコロナワクチン接種完了。 花園ラグビー場の集団接種会場にて、モデルナワクチン。 注射した部分の軽い痛みは翌日にはありましたが、特段の副反応なしというのは、従前の三回のそれと同じでありました。8月10日 囲碁例会にて梅田スカイビルまで銀輪散歩。 猛暑の中の銀輪による自宅・梅田スカイビル往復でペットボトルのスポーツドリンク4本を飲み干しました。 この日の出席者は、福麻呂氏、村〇氏とヤカモチの3名のみ。 ヤカモチは福麻呂氏に勝ち、村〇氏に負け1勝1敗。 福麻呂氏は村〇氏に勝ち、全員1勝1敗。 これでヤカモチの今年の通算成績は18勝10敗。 この日の銀輪散歩は、前日のワクチン接種の影響もあってか、いつになく疲れましたが、冷たい飲料を沢山飲んだ所為でもあるか、食欲が無くて、ヤカモチとしては珍しく、いつものカフェ・レストランでのランチを少し食べ残してしまいました。 帰途は、靫公園、大阪城公園、花園中央公園などの木陰でたっぷりと休憩をとっての銀輪走行でありました。 にもかかわらず、撮った写真は靫公園でのこの写真1枚だけでありましたから、体調がイマイチであったのかもしれません。(梶井基次郎「檸檬」の文学碑・靫公園) 碑文は次の通り。 びいどろと云ふ色硝子で鯛や花を打出してあるおはじきが好きになったし 南京玉が好きになった またそれを嘗めて見るのが私にとって何ともいへない享楽だったのだ あのびいどろの味程幽かな涼しい味があるものか 梶井基次郎「檸檬」 梶井基次郎の作品は、「檸檬」は勿論、何ひとつ読んでいないので、ここは、Wikipediaを<参照>として貼って置くことといたします。<参考>梶井基次郎・Wikipedia 檸檬(小説)・Wikipedia カテゴリ「ブログの歩み」の過去記事はコチラ。 囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~
2022.08.12
コメント(6)
-

橋本銀輪散歩・紀ノ川(その3)
(承前) 真田庵こと善名称院の境内にまだ居ます。 境内に真田昌幸の墓がある。 元々が真田昌幸の屋敷跡であったのだから、昌幸の墓があっても不思議ではない。 <参考>真田昌幸・Wikipedia 上のWikipediaの記述によると、昌幸は慶長16年(1611年)6月4日にここ九度山で病死し、火葬されている。翌慶長17年(1612年)8月に分骨が上田に運ばれ、上田市の真田家廟所である真田山長谷寺に納骨されたという。また、長野市松代町松代の真田山長国寺に墓所があるという。長野市の松代なら、今年6月29日の長野銀輪散歩で松代大橋を渡っているから、比較的近くを走ったばかりということになる。そうと知っていれば足を延ばしたものを、と思ったりもしたのでありました。 しかし、元の墓所は此処であるのだろう。真田庵こと善名称院は昌幸の死から130年後の創建であるから、善名称院の境内に昌幸の墓があるというのは間違いで、昌幸の墓所の周りが善名称院という寺になったと言うのが正しいのだろう。(真田昌幸公墓)(真田昌幸墓地の説明碑) 墓の隣は、彼を祀る祠になっている。(真田地主大権現社)(同上・説明碑) 碑文は次の通り。 真田地主大権現 幸運の神地主権現として敬い奉る社であります。 是は真田家重大の宝物である比沙門天と真田家三代の御霊を合祀したものであります。昔から福徳を授け給う運の神として遠近を問はず多数の信者が訪れ何事によらず一心に祈願すると霊験あらたかであると伝えられております。 真田昌幸を「真田地主大権現」として祀っているのかと思ったが、「真田家三代の御霊を合祀」とあるから、祀られているのは昌幸だけではないのだ。三代というのは、昌幸、幸村、そして幸村の嫡男・幸昌(通称:大助)なんだろう。 隣には「真田家臣一族之墓」と刻された供養塔がある。(真田家臣一族之墓) 境内には蕪村の句碑が2基ありました。(蕪村句碑その1) かくれ住んで花に真田が謡かな (蕪村) 句碑の隣には真田幸村(信繁)とその嫡男大助(幸昌)の父子四百回忌碑がある。(蕪村句碑その2) 炬燵して語れ真田が冬の陣 (蕪村) ヤカモチの追和句。 汗ぬぐひ思へ真田が夏の陣(筆蕪蕉)(西門) 真田庵は、NHK大河ドラマ「真田丸」放映の頃は随分の人で賑わったようだが、この日は「我のほか客はたれとてもなかりき」でありました。 真田庵を出て、更に坂を上る。やがて下りに入り、丹生橋でもう一度丹生川を渡る。「←慈尊院」の看板に従い道を進む。 実は、丹生橋を渡らず道なりに先へ進めば、当初予定していた九度山橋であったのだが、この時はそのことに気づいていませんでした。 道の要所に慈尊院までの距離を示した表示板があるので、それに導かれての慈尊院参りであります。 やがて小さな水路に架かる朱塗りの橋に出る。慈尊院橋とあるから、橋を渡ると慈尊院なんだろう。(慈尊院山門<北門>)<参考>慈尊院・Wikipedia 山門前の道路脇に自転車を駐輪して境内へ。 山門を入ってすぐ右側にあるのが弘法大師堂。(同上・弘法大師堂 左奥は西門) 正面右寄りに多宝塔。(同上・多宝塔 正面奥は丹生官省符神社への石段)(同上・多宝塔説明碑) 左に入ると弥勒堂(本堂)と拝堂(同上・拝堂、本堂側から)(弥勒堂と乳房型の絵馬群) 拝堂と弥勒堂の間は接近していて狭い通路。 そこに乳房型の絵馬が沢山吊り下げられている。 弥勒堂を撮るアングルが見つからない。 慈尊院は高野山の表玄関・政所(寺務所)として創建された寺院。 母が亡くなったとき空海は弥勒仏の夢を見たので、その廟堂を建立し、自作の弥勒仏像と母の霊を祀ったのが、この弥勒堂である。弥勒仏のことを慈氏、慈尊とも呼ぶことから慈尊院と呼ばれるようになった。 空海の母は弥勒仏を熱心に信仰していたので彼女は死して本尊(弥勒仏)に化身したという信仰が広まり、女人の高野参りは慈尊院ということになり、女人高野ということになったらしいが、乳房型絵馬はいかにも女人高野のそれである。(同上・乳房型絵馬) そこそこの参拝者があり、弥勒堂と拝堂の間の狭い通路は参拝者で混み合い、歩きにくい。これを通り抜けると、広い空間に出た。(同上・ユネスコ世界遺産慈尊院の碑<平山郁夫書>) 中央に噴水があって、奥片隅に弘法大師の像。(同上・噴水)(同上・弘法大師像)(同上・拝堂) 拝堂の正面に回って、丹生官省符神社へ。 拝堂の前に人影はなし。 本来はここから参拝するのが礼儀だと思うが、本堂(弥勒堂)と拝堂の後ろとの通路が参拝の場所になっているのでは、こちらに回って来る人はいないのかも。(丹生官省符神社・参道石段) 何段あったか数えなかったが、この石段、結構疲れました。 徒歩で高野山に参るなら、ここが登山口ということになる。(同上・鳥居)(同上・拝殿) こちらは、他に人影もなし、である。 拝殿左側には、空海を高野山へと案内した、白犬、黒犬を描いた絵馬が設置されている。 ヤカモチは女人ではないが、高野詣は此処、女人高野までとして置きます。(同上・拝殿内と本殿 拝殿扉越しに撮影)(同上・説明板)<参考>丹生官省符神社・Wikipedia 慈尊院に戻り、山門前道路にとめて置いた自転車に乗る。 山門を背に道路を直進すると川に出た。 紀ノ川なんだろうが、紀ノ川のどの辺りに居るのかが分からない。 上流に向かうと、道の駅があったので、そこで少し遅めの昼食。(道の駅・柿の郷くどやま) 昼食を済ませて銀輪散歩再開である。 少し走ると、先ほど渡った丹生橋に出た。 これを渡って左にに行けば紀ノ川に架かる九度山橋に出るのだが、丹生川に出たものだから、今まで紀ノ川だと思っていた川が丹生川だと思ってしまった。丹生川は丹生橋の左側で紀ノ川に注いでいるのだから、紀ノ川だと思ったのは正しかったのであるが、紀ノ川から随分離れてしまったのだと思い込んでしまった次第。 ということで、来た道を帰れば迷うこともあるまいと、丹生橋を渡って右に道をとる。県道13号である。 しばらく上りが続く。往路の下りは上りであり、上りは下りとなる。 またしても上り下りの激しい道を走ることになった次第。 県道13号で丹生川を二回渡ったことは先に述べたが、その橋が一つは永代橋という橋であり、九度山交差点近くの方の橋が真田橋という名前であることを復路にて知る。 九度山交差点からは国道370号であり、これも急坂の上りと下り、結構ハードである。 学文路交差点まで戻って来たところで、前方に橋が見える。 岸上橋である。 九度山橋の一つ上流側の橋である。(岸上橋南詰) 岸上橋を渡ったところで、何処か喫茶店があれば、入って休憩したい、身体を冷房で冷やしたい、という気分になり、紀ノ川右岸の道に入らず、直進するが、喫茶店は見当たらない。 パチンコ店の看板が見える。パチンコ店の近くには喫茶店があるかもしれないと、右折して脇道をパチンコ店の方に入るが、やはり喫茶店はない。 雨がパラつき始める。ゴロゴロと鳴っていた雷鳴が、突然ドカーンと大きな爆裂音を轟かせた。 それで急遽、パチンコ店に避難することとする。 パチンコをする気はないので、店内のベンチに坐って、店内の自販機で買った冷たい飲み物を飲みながら、遊戯を楽しんでいる人たちを離れた場所から眺めているだけ。 雷鳴も収まったようなので、パチンコ店を出る。20分くらいは店に居ただろうか。パチンコをする訳でもないので、何となく落ち着かず、長居は出来ないのでありました。 岸上橋北詰に戻り、紀ノ川沿いの堤防道を走る。 ところが、走り出すと同時に大粒の雨。 堤防道では雨宿りする場所がない。背中のザックには一応雨具を入れてはいるが、以前と違って最近は、雨具を着てまで雨の中を走るということはなるべくしたくない、という心境。 すると、河川敷のパークゴルフ場にテントが張られている場所のあるのが目に入った。緊急避難。河川敷に走り下り、そのテントに駆け込む。 テントに駆け込んですぐに凄い雨となる。雷も鳴り出す。 テントは3張り連結となっていて結構広く、ベンチも設置されているので、雨宿りとしては申し分なしである。ただ、落雷があるといささか心もとないが、先ほどのドカーンというような鳴り方ではないから、落雷の心配はないだろうとタカを括ることとする。 パークゴルフ場では、男性1人、女性2人の3人組が遠く離れた場所でプレーをして居られたが、さすがにこの雨ではプレーは無理。奥の方にあるもう一つの小さなテントに避難、雨宿りされている。 40分くらい雨宿りを余儀なくされました。(神野々緑地・パークゴルフ場のテントで雨宿り) 上は、南東方向の山々。(同上) 上は南方向の山々。 しばらくは、上の写真のように山も雨に煙っていましたが、やがて南から青空が戻り、山々に日が射し始めました。 テントにも日が照り始めたが、雨はその後もしばらく続いたので、様子見はなおも続く。 ようやく小降りになったので、テントを出て道路に戻る。出発。 道路に上がった頃には、テントに避難していた3人組もプレーを開始していました。 堤防道から眺めていると、最初に打った女性のボールはホールの30cmくらいの至近距離にピタッと止まりました。 「ナイス・タッチ」と道路の上からヤカモチの声援。笑って居られました。次の男性は3mほどオーバー。3番目の女性は2m余ショート。 これには、ノーコメント。第二打目は見ずに先へと走ります。 最後の目的地は、橋本中央中学校です。 ここにある、犬養万葉歌碑が目的。(橋本中央中学校の犬養万葉歌碑)山跡庭 聞往歟 大我野之 竹葉苅敷 廬為有跡者 孝書大和(やまと)には 聞こえも行(ゆ)くか 大我野(おほがの)の 竹葉(たかは)刈り敷(し)き 廬(いほり)りせりとは (万葉集巻9-1677)<大和には風の便りに聞こえて行ってくれないものか。大我野の竹の葉を刈り敷いて仮寝をしていると。>(同上・副碑) 副碑の全文は下記の通り。橋本市東家しんし会創立二十五周年の記念事業として万葉歌碑の揮毫を大阪大学名誉教授、甲南女子大学名誉教授、文化功労者、文学博士 犬養孝先生に委嘱し郷土のためにこれを建つ平成四年三月十五日 しんし会 まあ、先ほどの神野々緑地のテントでの雨宿りの気分もこの歌のそれに近いかもしれない。河内には 聞こえも行くか 神野々の 緑地のテントに 雨宿りすと (偐家持) この後、途中の大森神社の木陰で小休止するなどして、橋本駅前到着。 近くのコンビニから自転車を宅配便で自宅に送り返し、橋本銀輪散歩終了であります。(完)<参考>銀輪万葉・和歌山県、三重県篇はコチラ。
2022.08.11
コメント(4)
-

橋本銀輪散歩・紀ノ川(その2)
(承前) 橋本五條線(県道55号)はゆっくりカーブして、再び上り坂となり、上り切ると快適な下りとなる。車の走行はそれほど多くないので、車道を走ってもいいのだが、広い歩道がついているので、それを走る。 下りに入ったところで、右側(川岸側)にあった歩道が行き止まり。その先は左側が歩道となる。道幅の関係で、歩道は左右どちらか一方にのみ設けられているようです。(南海高野線の鉄橋) ここは眺望がよく、前方に南海高野線の鉄橋が一望である。 前ページ記事の冒頭に掲載の、妻2丁目交差点から脇道に入った路地で撮影した写真の鉄橋がこれである。 写真の右奥あたりからこの鉄橋を撮影したのであるから、1時間半ほどで紀ノ川の反対側にやって来たことになる。 ここで、道路を渡り、反対側に設けられた歩道に移る。そこで見かけたのはムギワラトンボ。(ムギワラトンボ) ムギワラトンボとは名ばかりにて、炎天下にあってもムギワラ帽子を被ってなんぞいない。シオカラトンボのメスなのである。 南海高野線の鉄橋下を潜ると、右手河川敷に広いグラウンドが見えて来る。向副緑地公園である。(向副緑地公園) 上の写真のグラウンドの先にもう一つグラウンドがあり、そこではボッチかゲートボールか何かそんな競技をされている人々の姿が目に入ったが、それをやり過ごすと、橋本橋の南詰めである。(橋本橋南詰) 橋本橋を過ぎると道は和歌山橋本線(国道370号)となる。 これを少し走り、すぐに脇道に入る。清水小学校の裏手にある西行庵へと向かう。(西行庵) 西行がこの地に一時止住したと伝えられ、西行像とされる像が堂内にのこされていることから、西行ゆかりの地として西行庵とも呼ばれるということであって、西行がこの建物を庵としたという訳ではなく、本来は地蔵堂ということなのであった。その意味では、吉野山の西行庵などとは性格が違う。 北面の武士であった佐藤義清(西行の俗名)は、この地から30kmほど下流の紀伊国田仲荘(現、紀の川市、旧那賀郡打田町竹房)を知行地とし、それを弟に託して出家したのであるから、この付近に一時住んだことがあったとしても不思議ではない。 下掲の説明碑によると、当地(橋本市清水)から高野山までの6ヶ所に地蔵があって、「高野街道六地蔵」と呼ばれていたらしい。その第一の地蔵がこの地蔵堂のお地蔵さんだというのである。(同上・説明碑)(同上・石仏群) 六地蔵としたいところだが、そうでもないようなので「石仏群」としました。道路拡張工事などで移転・撤去を余儀なくされた各所の石仏を集めて収納したという感じである。右側の柱に取り付けられている板切れには「国城の里 観音霊場巡拝六番札所」とあるが、意味がよく分からない。 左隣に水道蛇口のある洗い場があったので、手と顔を洗わせてもらって、ついでに汗で濡れたタオルも水洗いさせていただきました。 西行庵から西に進むと、登録文化財・橋本家住宅なる大きなお屋敷がありましたが、その家の前に、道を塞ぐ形で乗用車が駐車していたので、やり過ごす。更に西進すると、高架道路の国道371号の下に出る。 事前にネットから転載して来た簡単な地図では、ここで左折して数十m南に行くと戸隠神社というのがあるように書かれていたので行ってみたが、それらしきものは見当たらない。 道の向かいにファミリーマートがあったので、そこに立ち寄り凍結したスポーツドリンクを購入する。熱中症対策グッズの補給である。 元の道に戻り、西へ。川沿いの道に出て進む。 しばらくは快適な自転車道である。(紀ノ川左岸の道) 川が南向きに蛇行するのに従い、道も南向きとなり、やがて国道370号に出てしまう。和歌山橋本線である。これをしばらく走ると「西光寺300m」という表示が目に入る。 これに誘われて、左折。かなりの急坂を上って西光寺・刈萱堂へと向かうのだが、この300mはかなり応えました。(西光寺への坂道の途中から眺める紀ノ川) 途中の高みから眺めた景色が上掲の写真。ここで一休み。 西光寺は更に100mほど坂道を上らなくてはならないのであった。(西光寺)<参考>西光寺・学文路苅萱堂/橋本市観光協会(同上・学文路苅萱堂) 学文路苅萱堂の「苅萱」と「人魚のミイラ」という文字に誘われて西光寺へと向かったのだが、わが書斎の書棚の奥にあった「説経節」という書物に「苅萱」という苅萱道心とその息子石童丸の話があったのを思い出したからでもある。 「学文路」は「かむろ」と読み、この付近の地名である。もっとも、説経節の苅萱では「かぶろ」というルビが付されているから、古くは「かぶろ」と言ったのかもしれない。(「苅萱」説経節所収)<参考>苅萱・Wikipedia 身ごもっている妻に生まれた子が男なら石童丸と名付けよと告げて出家してしまった父・刈萱道心をたずねて、大きくなった石童丸は母を連れて筑前苅萱庄から高野山に向かうという話であるが、西光寺の「人魚のミイラ」はその母が信仰していたものだというのである。(同上。苅萱堂内部)(同上・絵馬) 堂内に掲示の絵馬には、その人魚のミイラらしきもが描かれている。(同上・学文路苅萱堂説明碑)(同上・人魚のミイラの絵) お堂の外壁に掲示されている額にも人魚のミイラが描かれているが、かなりグロテスクな得体の知れない代物である。(同上・学文路苅萱堂平成の歩み)(苅萱道心・石童丸関係信仰資料説明碑) 境内脇に句碑が3基ありましたが、よく見ずにスルーでした。(句碑) 坂を下り、国道370号に戻ろうとするが、南海高野線の踏切の手前で左に入る道を進むと学文路駅に出た。しかし、ここは駅の裏側のようで、行き止まりになっていた。駅の南側を回り込んでその先で国道に出ようという目論見は失敗でした。 引き返して、上って来た道の一つ西側の道を下って、国道に出ることができました。左折して国道を進むと学文路駅の前に出ました。かなり高い位置にある。(南海高野線・学文路駅) 学文路交差点で、国道370号は直角に左に曲がる。予定では岸上橋方向に右折して、紀ノ川べりに近い道をジグザグに走り九度山橋で対岸に渡り、橋本方向に戻るということにしていたが、慈尊院という文字が目に入り、それが示す方向が国道のそれであったので、国道を道なりに進む。 ところが、しばらく行くと勾配のきつい坂道となる。なんとか上り切ると、前方に九度山交差点の信号が見え、下り坂。一気に下る。 丹生川に出る。ここで丹生川はA字型にカーブしていて、2回丹生川を渡ることになる。しかし、これは後で地図を見て気がついたことで、そのような地理勘のないヤカモチ、完全に頭が混乱していました。 2回目を渡ると道は再びゆるやかな上り。200mほどで、真田庵(善名称院)に到着。(真田庵<善名称院>・南門)<参考>善名称院・Wikipedia(同上・真田庵由緒) 善名称院は、大安上人が寛保元年(1741年)に、伽藍を創建したのが始まりとのこと。この地が真田昌幸の屋敷跡であったことから真田庵とも呼ばれるようになったとのこと。(同上・本堂他説明碑)(同上・本堂)(同上・大安上人廟所霊屋・土砂堂)(同上・土砂堂説明碑)(同上・大安上人説明碑) 境内には、真田昌幸公墓所や真田昌幸を祀る祠などがあるが、これらは、ページを改めて紹介することとし、本日はこれにて休憩であります。(つづく)<参考>銀輪万葉・和歌山県、三重県篇はコチラ。
2022.08.09
コメント(2)
-

橋本銀輪散歩・紀ノ川(その1)
(承前) 今日(7月28日)も、昨日と同じく国道24号に出て、紀ノ川上流方向に走ります。隅田郵便局付近までは概ね昨日に走ったコースを辿るので道を間違う心配は無さそうです。 妻2丁目交差点まで来たところで、妻の杜神社に万葉歌碑があったことを思い出し、立ち寄ってみようと、左折して北へと走る。JR和歌山線の踏切を渡り、どんどん行くがそれらしきものが見えない。坂道をかなり上ったところで、庭先に出て居られた男性に神社のことを尋ねるが、「この付近には神社はない。」との答え。早くも道を間違えた。 反対方向に来てしまったかと引き返し、交差点まで戻り、細い路地を南に入ると、南海高野線が見下ろせる場所に出た。(南海高野線)(同上) 路地を道なりに進むと、妻社・東の森という小さな祠がありました。(妻社・東の森) 後で地図を見たら、妻の杜神社は、西社、中社、東社とあって、この東の森というのは、中社の北東側に位置している。これが東社なのかどうか定かではないが、多分、東社なんだろうと思う。 万葉歌碑があるのは西社で、妻2丁目交差点の300mほど手前の分岐で国道から脇道を左に入った処にあったのでしたが、見逃しました。(妻の杜神社・西社) ということで、「和歌山歴史物語100」というサイトの写真を借用させていただきましたが、そこには、こんな歌碑があるようです。紀伊きの国に 止やまず通はむ 妻の杜もり 妻寄よし来こせね 妻といひながら (坂上人長 万葉集巻9-1679)<紀伊の国に絶えず通おう。妻の杜よ。妻を寄越して下さい。その名が妻というなら。> 国道24号に戻り、大和街道に入り、隅田郵便局の前で左折し北へ。 昨日に立ち寄るのを忘れていた隅田八幡神社へと向かう。(隅田八幡神社参道・隅田川を渡る) 国道24号、隅田八幡神社入口交差点から500mほど北に行くと隅田八幡神社の神門に突き当たる。(隅田八幡神社・随神門) この神門の前に自転車を駐輪してと思ったが、適当な駐輪場所がなかったので、右側の坂道を上り、境内に入りました。またしても、裏口と言うか、横入りヤカモチでありましたが、そんなことでこの神門は潜っていない。この神門の龍の天井画が見事なのだということを知ったのは、後日のことでした。それは、こんな画だとのこと。(同上・天井画 「和歌山歴史物語100」というサイトからの転載) 先ずは、隅田八幡神社の案内図を掲載して置きましょう。(同上・案内図)※原寸サイズの写真はコチラ。<参考>隅田八幡神社・Wikipedia 当神社は、神功皇后が外征後、大和還幸の途次、この地に滞留されたということから、貞観元年(859年)に石清水八幡宮より勧請したのが創祀とのこと。(同上・左:西神楽殿、中央:拝殿、本殿、右:東神楽殿) 当神社に伝わる人物画像鏡は国宝に指定されている。(同上・人物画像鏡の碑)<参考>隅田八幡神社人物画像鏡・Wikipedia)(同上・人物画像鏡説明碑) 銅鏡に刻された四十八文字の銘文は下記の通りであるが、その解釈については諸説があって定説をみないとのこと。癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟(同上・馬蹄石) 神功皇后伝説に関係するものとしては、上のような馬蹄石がありました。「馬をとどめし足跡と伝承されている」という石板の説明であるが、馬蹄石が馬締石になってしまっているのは何かの手違い。ここで締めては締まらないだろうと突っ込みを入れるのは野暮であるか。 本・拝殿の左奥にある大高能寺は、この神社の元・神宮寺であったとのこと。(同上・大高能寺) もう一つ気になったのは隅田党発祥の地という碑。(同上・隅田党発祥の地碑) 裏面の由来を読むと。(同上・隅田党発祥の地碑の由来) 隅田党というのは、隅田八幡宮の祭祀とこの地、隅田荘を基盤とした武士団のことで、太平記や畠山記に登場するらしいが、その子孫の人たちの隅田党一族の会というのがあり、平成29年(2017年)にその会によって建立されたもののようです。 隅田八幡神社を出て、隅田郵便局前まで下り、大和街道に戻る。 一つ先の辻で右折、山内恋野線を南へ。JR和歌山線を渡り、隅田中学校を右に見て、ゆるやかにカーブする下り坂の道を進むと、紀ノ川に架かる恋野橋である。(恋野橋)(同上) 橋の中央から紀ノ川下流方向を望む。(紀ノ川 恋野橋から) 橋を渡ると橋本五條線(県道55号)、紀ノ川左岸の道に出る。 これを右折して、紀ノ川下流方向に走る。恋野小学校を右に見て、しばらくは上り坂である。恋野小学校の校庭には「こいの池」という標識の掲示された池らしきものがあった。「恋の池」ではなく「鯉の池」なんだろうが、何やら面白い。旧仮名遣いだと恋は「こひ」で鯉は「こい」だと思っていたが、手許の辞書によると、どちらも「こひ」であるようだ。 坂の途中で、左手を見ると中将姫の文字と絵が目に入る。彼女が母様恋し恋し野の・・とかなんとかと言ったので「恋し野」→「恋野」になったのかどうかは存じ上げないが、彼女がこの地に隠れ住んだという伝説があるようで、その旧跡もあるようです。しかし、今回は中将姫はパスです。折あらば また訪ね来よ 恋し野に われはまつちの 山にて待たむ (偐中将姫)とかなんとか詠む声を空耳に聞きつつ、坂を上り切る。 因みに、その伝説とは次のようなもの。橋本市恋野の中将姫伝説恋野地区には今も中将姫ゆかりの場所が数多く残されており、中将姫の伝説に触れながらたどることが出来ます。中将姫は幼くして母を亡くし新しく継母を迎えますが、継母は美しく才能豊かな中将姫を憎み、父豊成の留守中に、恋野地区にある雲雀山での殺害を計画しました。しかし、罪もない姫を殺すことが出来なかった家来の嘉籐太は、雲雀山で妻と共に姫を育てながら隠れ住んだと言われます。「恋野」という地名は、姫が母を恋しがって「母様恋し、恋し野の…」と詠んだ歌にちなんで名づけられたものです。その後、姫は父親と涙の再会を果たし、都に帰ることとなります。その際、中将姫が村人に残した観音像が、中将が森に祀られています。この後に中将姫は当麻寺で剃髪し、法如比丘尼となり29歳で波乱の人生を閉じますが、中将姫の最期は二十五菩薩来迎があり、天国へ召されていったとの伝説が残っています。(橋本市観光協会のサイトより) 坂を上り切る手前で、「筒香選手ガンバレ」と書かれた手書きの小さな板が民家の庭に掲出されていましたが、帰宅後調べると筒香選手は橋本市の出身であることを知り、納得でした。 何処か木陰に入って、水分補給の休憩を取りたいと思うが、なかなか適当な場所が見つからず、もう少し、もう少しと走り続ける。 ようやく、サルスベリの咲く、ちょっとした空地に出くわし、蔵のある民家が太陽を遮って日陰をつくってくれている場所で小休止。奥には大きな栗の木があり、もう実をつけ始めている。(栗の木 橋本市中道付近)(同上) 道の反対側前方には、白いサルスベリの花が満開。(サルスベリの白い花) まだ、しばらくは橋本五條線を走りますが、休憩が入ったことでもあり、本日はここまでとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・和歌山県、三重県篇はコチラ。
2022.08.08
コメント(4)
-

橋本銀輪散歩・真土万葉の里
先月(7月)27~28日と橋本市を銀輪散歩して来ました。 遅ればせですが、その折の旅報告です。 犬養万葉歌碑を訪ねるついでに、紀ノ川畔を走ってみようというもの。 南海高野線で橋本駅下車。 橋本駅は、南海高野線とJR和歌山線の両駅のホームが並列し、跨線橋で両駅が連結されるという構造になっている。(JR橋本駅) 駅前広場にある万葉歌碑がこれ。(駅前の犬養万葉歌碑) 碑文は次の通りです。 紀ノ川の万葉 犬養 孝こんにちは、草ぼうぼうになった古い小道をくだると、土地の古老らが、“神代の渡り場”と称している、落合川(真土川)の渡り場に出る。ふだんは水の少ない涸川だから、大きな石の上をまたいで渡るようになっている。ここがおそらく古代の渡り場であったろう。白栲(しろたへ)に にほふ信土(まつち)の 山川(やまがは)に わが馬なづむ 家恋ふらしも -作者未詳-(万葉集巻七-一一九二)(副碑) 橋本の万葉歌碑 歌の意味信土山の川(落合川)で私の乗る馬が難渋している。家人が私を心配しているらしい。第八回橋本万葉まつりと併せてJR和歌山線の全線の開通百周年を記念し、大阪大学名誉教授 甲南女子大学名誉教授 文化功労者 文学博士 故犬養孝先生著書「紀ノ川の万葉」よりその遺墨を刻し 郷土のためにこれを建つ二〇〇〇年十一月 第八回 橋本万葉まつり実行委員会 駅前の喫茶店で昼食。 駅近くのホテルで、前もって宅配便で送って置いたトレンクル(折りたたみ自転車)を受け取り、銀輪散歩に出発である。 国道24号を暫く走り、途中から古道・大和街道をゆく。(JR和歌山線・下兵庫駅東側の踏切、隅田駅方向) JR和歌山線の踏切を渡って北へと進むと、国道24号にぶつかる少し手前にあったのはこんな祠。(左から、地蔵堂、阿弥陀堂、白石稲荷神社) 国道24号にぶつかったところで旧道は直角に右に折れて東へと進む。 高橋川という川に架かった西国橋を渡ったところにあった道標で、道を間違えてはいないことを確認。(大和街道の道標) ところが、県道108号(隅田停車場線)を右折すべきところ、直進してしまい、国道24号に出てしまった。 ヤカモチが走って来た古道・大和街道は国道24号と並行してその南側を走っていた筈なので、国道24号に出てしまったことで、頭が混乱、自身の現在地が何処なのか分からなくなってしまう。 国道脇、工場の出入り口で出入りするトラックの誘導をされていたガードマンの青年に尋ねて現在地を把握。 何のことはない。国道24号は県道108号と交差する真土西交差点の先で右にカーブして大和街道と合流しているのでありました。 自分の左手にあった筈の道路が正面に来たのだから、その道路がカーブして正面に来たと考えるべきなのに、自分の方が何処かで曲がって方向違いに来てしまったのではないかという疑問を持ったことによる頭の混乱でありました。 辻を一つ戻って、県道108号に入り南へ。 JR和歌山線の踏切が見えて来る。踏切の手前で左折。 隅田駅前に到着。(JR隅田駅 左端は女の子が飛び越え石を飛び越えている絵である。) 隅田駅は「すみだ駅」だと思い込んでいましたが、正しくは「すだ駅」でありました。 駅前に万葉歌碑がありました。(JR隅田駅前の万葉歌碑)真土山まつちやま 夕ゆふ越え行きて 廬前いほさきの 角太河原すみだかはらに ひとりかも寝む (弁基 万葉集巻3-298)(左注)右は、或いは云はく、「弁基とは春日蔵首老の法師名なり」といふ。 この歌の「角太河原」というのは、この隅田地区の紀ノ川の河原ということなんだろう。廬前は隅田町あたりの総称とみられる。 隅田駅から200mほど南に行くと紀ノ川である。また、400mほど東に行くと、紀ノ川に流れ込む落合川である。 現在は、この落合川が和歌山県(橋本市)と奈良県(五条市)との県境になっている。 その落合川にある「飛び越え石」が、橋本駅前の歌碑に刻されていた犬養先生の著書「紀ノ川の万葉」で「古老らが”神代の渡り場"と称している渡り場・・ここがおそらく古代の渡り場であったろう。」とされている場所である。そこは、「真土万葉の里」という公園になっている。 今日の銀輪散歩の目的地である。 その万葉の里へは、隅田駅から細い急坂を上って行くことになる。(隅田駅から万葉の里への坂道) 自転車には辛き急坂であるが、猛暑の炎天下を走って来た身には、心地よい木陰の道でもありました。 上り切った四辻を右に行くと万葉の里の入り口である。尤も、国道24号側からの入り口の方が本来の入り口なんだろうが、ヤカモチは裏から入るのが習いとなっているから、これでいいのである。(万葉の里入り口の万葉歌碑) 真土万葉の里の入り口にあったのは笠金村の歌碑。 万葉集巻4-543の歌である。この歌の題詞には、神亀元年(724年)冬10月、紀伊国に行幸のあった時、お供の人に贈るために、或る娘子に依頼されて作った歌1首(神亀元年甲子の冬十月、紀伊国に幸したまひし時に、従駕の人に贈らむが為に、娘子に誂へられて作りし歌一首)とあるが、聖武天皇の紀伊国行幸の折に笠金村が詠んだ歌である。大君の 行幸(みゆき)のまにま もののふの 八十伴(やそとも)の男(を)と 出でて行きし 愛(うるは)し夫(つま)は 天飛ぶや 軽の道より 玉だすき 畝傍(うねび)を見つつ あさもよし 紀伊路(きぢ)に入り立ち 真土山(まつちやま) 越ゆらむ君は 黄葉(もみぢば)の 散り飛ぶ見つつ にきびにし 我(われ)は思はず 草枕 旅をよろしと 思ひつつ 君はあるらむと あそそには かつは知れども しかすがに 黙(もだ)もえあらねば 我が背子が 行きのまにまに 追はむとは 千度(ちたび)思へど たわやめの 我が身にしあれば 道守(みちもり)の 問はむ答へを 言ひ遣らむ すべを知らにと 立ちてつまづく (笠金村 万葉集巻4-543)<天皇の行幸に従って、文武の百官たちと共に出発して行ったいとしい我が夫は、(天飛ぶや)軽の道から(玉だすき)畝傍山を見ながら、(あさもよし)紀州路に進み入り、今頃は国境の真土山を越えているであろうそのあなたは、色づいた葉が風に散り飛ぶのを見ながら、馴れ親しんだ私のことは思わず、(草枕)旅も悪いものではないななどと思ってあなたはいるだろうと、うすうすは承知しているけれど、それでも黙っても居られないので、あなたの行った道のままに、追いかけて行こうとは何度も思うのだが、かよわい女の身なので、途中で道の関の番人が咎めた時の答えを、何と言ってやればいいのか、そのすべも分からず、進みかねためらっています。> 続日本紀によると、聖武天皇はこの年の10月5日に紀伊国に行幸し、和歌の浦の景色を愛で、同月23日に平城京に帰っている。 歌碑には刻されていませんが、上の歌の反歌2首も次に列記して置きましょう。後(おく)れ居(ゐ)て 恋ひつつあらずは 紀伊の国の 妹背(いもせ)の山に あらましものを (万葉集巻4-544)わが背子(せこ)が 跡(あと)踏み求め 追ひ行かば 紀伊の関守 い留(とど)めてむかも (同巻4-545) 歌碑の左側に狭い急な階段道がる。これを下ると万葉の里のようだ。トレンクルを肩に担いで行くことも考えたが、階段を少し下った処に駐輪して置くこととする。 木立の繁る狭い階段道を抜けると開けた田畑のような空間に出る。 オニユリも咲いている。(万葉の里のオニユリ) ここにあった犬養万葉歌碑はこれ。(万葉の里の犬養万葉歌碑) 碑文は次の通りです。紀ノ川の万葉 犬養 孝まつちの山越え 大和の万葉びとが紀伊の国にはいる最初の峠は、紀和国境のまつち山である。そこは五条市の西方、和歌山県橋本市(旧伊都郡)隅田眞土とのあいだの山で、昔は山が国境であったが、現在は、山の西方、落合川(境川・眞土川)が県境となって、その間に両国橋が架けられている。石上乙麻呂卿配土佐国之時歌石上いそのかみ 布留ふるの尊みことは たわやめの まとひによりて 馬じもの 縄取りつけ ししじもの 弓矢かくみて 大君の みことかしこみ 天ざかる 夷ひなへに退まかる 古衣ふるころも 又打山まつちのやまゆ 還り来こぬかも (巻六-一〇一九)(副碑)真土の万葉歌碑第八回橋本万葉まつりを記念し、又永く橋本の万葉が受け継がれる事を祈り大阪大学名誉教授 甲南女子大学名誉教授 文化功労者 文学博士 故犬養孝先生の著書「紀ノ川の万葉」よりその遺墨を刻しここ万葉のふるさとにこれを建つ。二〇〇〇年十一月二十三日橋本万葉の会 歌の現代語訳は次の通り。石上の布留の君は、たわやめゆえの心惑いによって、馬のように縄を取り付け、鹿や猪のように弓矢で取り囲まれて、大君の仰せを畏れ多くも承って、(天ざかる)遠くの国に流されて行く。(古衣)真土山を越えて帰って来ないものかなあ。 続日本紀(天平11年3月28日条)によると、石上乙麻呂は藤原宇合の未亡人、久米連若売と密通し、乙麻呂は土佐へ、若売は下総へ流罪となっている。万葉集にはこの時の乙麻呂の配流に同情した誰かが詠んだのであろう歌が3首掲載されているが、そのうちの1首である。 犬養万葉歌碑から少し下ったところにも万葉歌碑。(万葉の里の万葉歌碑)橡之 衣解洗 又打山 古人尓者 猶不如家利橡つるばみの 衣きぬ解き洗ひ 真土山まつちやま 本もとつ人には なほしかずけり (万葉集巻12-3009)<つるばみで染めた衣を解いて洗い、真土山、本の妻にはやっぱりかなわぬものです。>(注)橡=クヌギのこと。橡で染めた衣は普段着。 又打山=衣を洗うには砧で打って洗うから、「又打つ」で「又打山(真土山)」を導き、「まつち(真土)」の類音で「もとつ(本つ)人」を導いている。 万葉歌碑の後ろはハス畑。 ハスとスイレンも咲いていましたが・・。写真はイマイチ。(同上・スイレン、奥にハス畑) 奥のハスが大賀ハス(古代ハス)だということは、帰宅後のTVで、ここのハスが見頃になっているということが紹介されていて知ったもの。 スイレンの池の前に「飛び越え石」の説明碑。(飛び越え石の説明碑) ここから更に狭い石段を下ると落合川の河原になる。そこに飛び越え石がある。深い谷となっているので、両岸に繁る鬱蒼とした木々に囲まれて薄暗い。その所為でもあるか、写真のピントが甘くなってしまいました。(飛び越え石) この石を跨いで向こう岸に渡れば、もう奈良県五條市である。 折から雨がパラつきだし、石が濡れているので、渡るのは差し控えて引き返すこととする。(落合川、飛び越え石の上流側) 薄暗く感じたのは、いつの間にか空には黒い雲が広がり、雨が降り出し、雷も鳴り出したという天候の急変の所為もあったのかも。 戻る途中の石段脇にあったのが、この歌碑。(飛び越え石近くの歌碑)いで我(あ)が駒 早く行きこそ 真土山(まつちやま) 待つらむ妹を 行きてはや見む (万葉集巻12-3154)<さあ、我が駒よ、早く行け。真土山、その名のように待つだろう妻を、行って早く見よう。> 右面には、新千載集の807番の歌が刻してある。誰にかも 宿りをとはむ 待乳山 夕越え行けば 逢ふ人もなし 作者不詳の歌ではないかと思うが、新古今集の小野小町の歌、「たれをかも まつちの山の 女郎花 秋とちぎれる 人ぞあるらし」(巻4-336)を思い出させる歌である。 反対の左面には「いつしかと 待乳の山の 桜花 まちてもよそに 聞くが悲しさ」(作者不詳 後撰和歌集)という歌が刻されているようだが、写真には撮っていない。 いよいよ、雨が本降りになって来たので、急いで、万葉の里にある休憩所に駆け込む。 雨と雷に気を取られていた所為か、休憩所の建物の写真を撮り忘れ。ということで、他者のサイトの写真を借用転載です。(とびこえ休憩所 和歌山歴史物語100から転載。)(同上 トヨタカローラ和歌山橋本店「真土万葉の里プロジェクト」から転載) しばらく雨宿りするうちに、天気は回復。 階段途中にとめて置いた自転車・トレンクルのもとに戻る。 雨にすっかり濡れているのではと心配したが、幾重にも重なる枝葉が濡れるのを最小限にとどめてくれたようで、サドルを拭く必要もなしでありました。来た道を引き返し、国道24号線へと向かう。少し上った後は急坂を下ることになる。下りきったところが国道24号で、橋本浄水場への進入道路の前である。ここに犬養万葉歌碑が道路を挟んで向き合う形で存在する。浄水場入口側の歌碑は、こちらに向いて居らず、南西方向を、つまり横を向いているので、正確には向き合っているとは言えないのではあるが。 そこにあった犬養万葉歌碑は真土山の万葉歌の中でも最もよく知られている歌のそれである。(国道24号沿いの犬養万葉歌碑)朝毛吉 木人乏母 亦打山 行来跡見良武 樹人友師母あさもよし 紀人きひと羨ともしも 亦打山まつちやま 行ゆき来くと見らむ 紀人羨しも (調首淡海 万葉集巻1-55)<(あさもよし)紀伊の人は羨ましい。真土山を行き来に見るのだろうから。紀伊の人は羨ましい。> (同上) この歌碑の右隣に、大師井戸という碑があったが、詳しくは探索せずでありましたので、詳細は何とも存じ上げず、であります。(大師井戸) まあ、この地は、高野山のお膝元みたいなものですから、弘法大師が掘った井戸があっても不思議ではないが、通りがかりに弘法大師が掘った井戸や杖を突き立てると水が湧き出したとか、これに類する伝説は全国各地にありますから、珍しいものでもありません。 国道24号を橋本浄水場入口側に渡ったところにあるのが、もう一つの犬養万葉歌碑。(橋本浄水場入口の犬養万葉歌碑) 碑文の全文は次の通り。紀ノ川の万葉 犬養孝こんにちは、国道24号線が山の北側を通り、鉄道が南側の山裾の川べりを通っているが、古代は川べりを避けて、現、国道より南の低い、川ぞいの丘辺を越えていた。峠の上は、東方は五條一帯の吉野川の広い流域を望み、一方西方には紀ノ川(和歌山県にはいると吉野川は紀ノ川と呼ばれる)の明るい河谷を望む。紀路にあこがれる旅人のエキゾチシズムを刺激するのは当然のことであろう。あさもよし 紀へ行く君が 信土山(まつちやま) 越ゆらむ今日(けふ)そ 雨な降りそね 作者未詳(巻九-一六八〇) 副碑の文面は、上掲の「万葉の里の犬養万葉歌碑」と同文なので省略しました。 歌の意味は下記の通りです。<(あさもよし)紀の国へ行くあなたが、真土山を越えているであろう今日あたり、どうか雨よ降らないでほしい。> 以上で、目的は一応果たしたので、橋本駅前へと戻ることとする。 国道24号を下って行くと、往路で道を尋ねたガードマンの青年にまた出会った。軽く会釈して、そこから大和街道に入る、(紀ノ川南岸の山々) 真土山がどの山とも分からず仕舞いで帰途についてしまい、真土山の写真がありません。大和街道を走りながら、紀ノ川方向(南側)の山々を撮ったのが上掲の写真です。 雨上がりとあって、盛んに雲が立ちのぼっています。 隅田八幡神社にも立ち寄るつもりでいたのに、やり過ごしてしまったので、これは翌日の銀輪散歩で立ち寄ることにします。 炎暑の中を走っていると注意力が散漫になるようです。年齢による認知機能の衰えだろうという声も何処かから聞こえて来そうですが、それは聞き流すこととしましょう。(紀ノ川 橋本橋の少し上流付近 奥に見える鉄橋は南海高野線) 橋本市街に戻って来て、少しばかり市街を「徘徊」。 紀ノ川沿いのポケットパークのような場所で休憩。今日(27日)は紀ノ川の写真も撮っていなかったことに気づき、1枚撮影。 明日(28日)は、この写真の奥、上流側へと再び走り、恋野地区で橋を渡って紀ノ川左岸に移り、下流の九度山橋まで走り、九度山大橋で右岸に移り、今度は右岸を上流側へと走り、橋本駅前まで帰って来るという計画であるが、寄り道次第によってはどうなるか分からない。(旧橋本町道路元標)(同上・説明碑) 橋本橋の少し下流まで走って、この日の銀輪散歩は切り上げとし、ホテルに戻りました。今日はここまでとします。(つづく)<参考>銀輪万葉・和歌山県、三重県篇はコチラ。
2022.08.07
コメント(2)
-

囲碁例会・雀の砂風呂と梅田の里山
昨日(3日)は囲碁例会の日。この日の大阪の最高気温は36度という予想であったが、いつもの通りCB(クロスバイク)で梅田へ。 先ず、花園中央公園北側のコンビニに立ち寄り、氷結したスポーツドリンクと氷結していない普通のもの各1本を購入して熱中症対策です。 氷結したものはすぐには飲めないので、少し融けるまでは凍っていないものを飲む。しかし、凍っていないものは、時間の経過によって冷たさが失われてしまう。その頃には氷結したものが融けだして飲めるようになるので、こちらを飲む。飲んだ後、冷たさが失われてしまった方の飲み残しを、氷結の方のボトルへ注入する。これを繰り返すことで、常に冷たいものを飲むことができるという次第。ヤカモチの夏の銀輪散歩の定番スタイルである。 自宅から囲碁例会の会場となっている梅田スカイビルまでは1時間半程度の行程、信号の具合や途中の寄り道、休憩の具合で2時間近くになることもあるが、この位の時間だと梅田スカイビルに着いた頃でもペットボトルの飲料にはまだ氷塊が残っていて、道中ずっと0℃の水分補給ができるのである。 JR森ノ宮駅前から入り旧砲兵工廠の建物が残る北西出口まで大阪城公園を通り抜ける。 その出口手前の堀端の林の中ではいつもの麻雀グループの男性4人がいつもの通りテーブルを囲んで麻雀に興じて居られました。 近くのベンチでヤカモチも水分補給休憩。 すると目の前に雀たちの砂風呂がありました。以前、花園中央公園で目撃したものと同じような光景です。(大阪城公園の雀の砂風呂) 花園中央公園のそれよりも「大規模」であります(笑)。(同上)<参考>何の穴? 2022.6.18. スマホの着信履歴を見ると1時間前に平〇氏よりの電話が入っていた。 遅ればせながら電話をすると、今日の例会は欠席させてもらうというのが電話の用件でした。暑すぎるので外出を控えることにするというもの。 平◎氏からも欠席する旨のメッセージが入っていました。 大阪城公園を出て、天満橋で大川を渡り、滝川公園西隣の寺の前を通ると、こんな門前の言葉が掲示されていました。(門前の言葉) 心がふわふわして より道ばかり していると もとの道に 戻れなくなるよ 寄り道の多いヤカモチの銀輪散歩では、もとの道に戻れなくなることも時々ありますが、まあ、それでも何とかなるというものでもあります。 最近の囲碁例会に合わせての銀輪散歩は、自宅と梅田スカイビルを単純往復するのみで、余り、寄り道、遠回りというものをしなくなった。これも年齢の所為ですかね。 梅田スカイビル到着は11時45分。 前回同様に、ガーデン5棟の1階のレストラン&カフェで昼食&珈琲。 昼食後、里山を散策。(梅田の里山) 里山を散策するのも久しぶり。 幼い子ども二人を連れた若いお母さんが散歩されていました。(同上) 石を積み上げたり、丸太を積んだりしているのも「里山」らしい風景を醸すための仕掛けであるのだろうが、これらによってできる隙間がトカゲなどの小動物の巣や虫の棲家になるという狙いもあってのもの。(里山のクマゼミ) クマゼミがいました。 翅が少し破れたアゲハチョウが休息している。(里山のアゲハチョウ) ユリの花やシコンノボタンなどが咲いていましたが、撮影はせず。 茶トラの猫もいましたが、写真がピンボケだったので没。 そして、見慣れぬ実がなっているこの木は何の木なのか。(何の実、何の木)(同上) ガーデン5棟の5階にある部屋に行くと、ヤカモチが一番乗りであったようで、誰の姿もなし。設営を済ませて待つこと20分程度。 福麻呂氏がご来場。 早速、同氏とお手合わせ。 少し負けているかと思っていたが、2目半だか3目半だかの勝ち。 対戦中に青◎氏がご来場 今日はこの3人だけの出席。 青◎氏と交代して、福麻呂・青◎戦。ヤカモチは観戦。 中盤まではほぼ互角であったが、終盤に入って青◎氏にやや消極的な手が続き、数目の差で福麻呂氏の勝ち。 最後は青◎氏とヤカモチの対戦。これは青◎氏の勝ち。 ということで、全員が1勝1敗で、めでたし、めでたしでありました。 これで、ヤカモチの今年の成績は17勝9敗。 午後2時半の散会。いつもより1時間以上早い散会。 まだ暑い盛りの帰路。 大淀南公園からなにわ筋を南へ走り、靫公園を通り抜けて、四ツ橋筋から御堂筋に移り、途中のコンビニで氷結スポーツドリンクを1本購入。 本町通りを東上。大阪府警本部とNHK大阪局の間を抜けて、馬場町で大阪城公園に入る。公園に入るごとに木陰に入って水分補給、「煙」分補給をしたりの休憩で身体を冷やし、と「急がない」銀輪走行。(大阪城公園のバス専用駐車場) ひと頃はガラガラでバスの影もなかった駐車場であるが、沢山の観光バスが駐車していました。コロナ感染第7波の大波のさ中であるが、行動制限のないこの夏、観光客も増加しているようです。 帰宅は4時半。2時間を要しましたから、途中の休憩が多かったことを示しています。<参考>囲碁関連の過去記事は下記参照。 囲碁関係(その1) 2008年~2019年6月 囲碁関係(その2) 2019年7月~We stand with Ukrainians.
2022.08.04
コメント(4)
-

墓参・花やカボチャの
今日は月例の墓参。 墓地は生駒山系の山の西麓の高みにあるので、坂道を上るだけで、今日のような暑い日には汗だくになるが、その分、眺望がよい。(墓地から、あべのハルカスを望む。) 左手方向遠くにはあべのハルカス。 正面近く、眼下に花園ラグビー場。(眼下に花園ラグビー場) 奥にはOBPのビル街。遠くに六甲の山々。 そして、ぐるり一望すれば、下のような眺め。(南から北へぐるりパノラマ撮影) 墓地の裏の空き地に咲いていたのはヒルガオと野菊。(ヒルガオ)(野菊、ヨメナ?) 墓参を済ませて、坂道を下る。 墓地入口近くの民家の前の畑に大きなカボチャ。(カボチャ) 少し下った、右手の民家の前にはヒマワリが、左手の民家の前にはアメリカフヨウが咲いていました。(ヒマワリ)(アメリカフヨウ) 更に下ったところ、テニスクラブの手前にムクロジの古木がある。実が鈴なりになっている。(ムクロジの実) その近くの民家の前には、最近は余り見かけることがなくなったナツメの木も実をつけていました。(ナツメの実) そして、いつもの門前の言葉の寺の前を通過するのですが、今日の門前の言葉は、先月2日の墓参の時のそれと同じであったので、撮影はせず。 往復40分ほどの朝の外出でありました。 本日の外出はこれのみ。アトは家でゴロゴロして居りました。墓参とて 朝の坂道 われ行けば 花やかぼちゃの 道にしあれり (偐家持)(本歌)行き暮れて 木の下陰を 宿とせば 花やこよひの 主ならまし (平忠度)<参考>花関連の過去記事 花(5)・2022~ 花(4)・2020.4.~2021 花(3)・2017~2020.3. 花(2)・2012~2016 花(1)・2007~2011 墓参関連の過去記事はコチラ。We stand with Ukrainians.
2022.08.02
コメント(2)
全12件 (12件中 1-12件目)
1