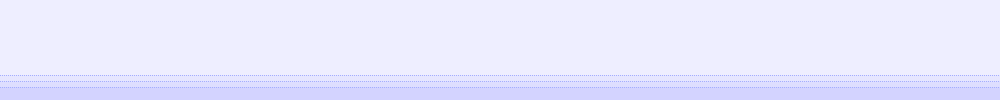『天井とスニーカー』
僕はロフトで寝ていた。ロフトには僕を含めて4人寝ている。隣にはM子が寝ている。M子とは同じ広告業の仲間で、価値観も恋愛の考え方も似ている。でも、隣にあるのはそういった社会的なM子ではなく、生物的なM子だ。肉体的ともいえるかもしれない。
化粧を落とした顔には、疲れのたまった肌と、素の肌がごっちゃになり、大人と子供が混じったように、不安定さをおびさせていた。素顔を見たのは初めてだった。なにか、歩いているときに並びの家をなんとなく眺めて家の中を覗いてしまったようなバツの悪さを感じてしまう。悪いなと思って、布団を頭まで被り、M子に背を向ける。
いっこうに眠りが訪れないな・・・僕は思った。疲れているはずだった。なぜなら、昨日も4時間しか寝てないし、今日も足がふらふらになるまで飲んだのだ。それに、いまはもう朝の6時を回っている。
カーテンからは、少しずつ白さを増した光が漏れ始め、それは順に濃厚になっていく。
下の階から、寝息がいくつも聞こえてくる。寝返りをして布団のこすれる音も聞こえる。たまに誰かのケータイの音が鳴って、何人かが反応する。しかし、それでもだれも起きはしないのだけど。
気持ちが高ぶっているのかもしれない。そして、それはめずらしいことではない。家で寝るときだって不眠に悩まされることがあるのだ。コテージで10人で遊びに来ていれば、自然とそうなってしまっても不思議でないのだ。
M子が寝返りを打つ音が聞こえる。おそらく彼女は気持ちよく寝れているのだろう。虫に何かを話しかけるように、ほんとに小さな寝息だけを立てている。
天井の闇は少しづつ朝の陽に侵食され始め、木の筋がだんだん見え始めている。
僕ははもう寝ることをあきらめていた。いつもそうなのだ。カーテンからの光がだんだん濃密になるにつれて、僕の頭の意識もはっきりしてしまうのだ。もちろん寝てないのだから、完全にはっきりするわけではない。それは、雨の日の道路のように、雨とどろでぐちゃになった道に、白い車線だけが浮かび上がってるような、そういう種類のはっきりさだ。
僕は、枕元に置いてあったコンタクトレンズをはめて、静かに階段を降りた。薄暗いその空間では、ベットの上で寝ているのもいれば、キッチンテーブルの下に寝袋で寝ているのもいる。しかし、彼らは完全に寝ていた。
もちろん、普段はキッチンテーブルの下で寝るなんてうらやましくもなんともないけど、今の僕にはそれすらひとつの幸福の風景に見えた。
そのテーブルの上には空いたビールの缶やら、タバコが何十本も入った黒い水だとか、かすだけが隅に残ったポテトチップスの袋だとか、飲みかけのウーロン茶の缶だとかが、散乱していた。それはこの世界にキッチンだけの世界があって、そこでキッチンサイズの台風が通過したみたいだった。完璧なまでの、完璧がない世界だった。
僕は、バックの中から村上春樹の小説を尻ポケットに差し込んで、コンバースのスニーカーをはいた。
ドアを静かに開け外にでると、そこは朝だった。木が周りにあって、小鳥の音がして、白い朝日の筋が何本も降りていた。辞書で調べたら、例えに使われそうな朝だ。 富士山のふもとの空気は、静かさを内包し澄んでいて、かつ、ぬくもりがあった。
僕は木々の小道を散歩に出かけた。闇のかかった天井の下では、僕に眠りが訪れる世界はなかった。しかし、この朝の世界では、どこか座れる場所があって、少し小説を読むことぐらい許されるかもしれない。そしてその世界で、みんなが薄暗い世界から目覚めるのを待つことが許されるかもしれない。コンバースの靴音と息使いだけが、僕を満たしていった。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 株式投資日記
- サイエンスアーツが新代表取締役社長…
- (2025-11-27 16:49:05)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 美容院に行ってきました。安くすみま…
- (2025-11-27 17:02:11)
-
-
-

- ★つ・ぶ・や・き★
- 浜田聡さん、スパイ防止法成立を妨害…
- (2025-11-27 17:04:35)
-
© Rakuten Group, Inc.