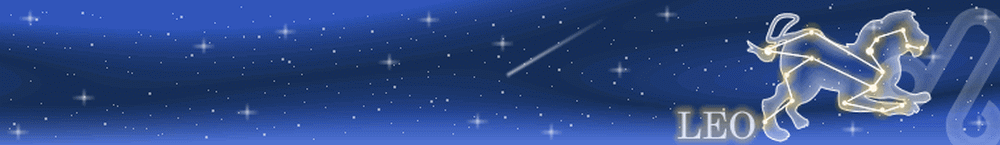第一部第8話
ファミレスで食事を終え、食欲も会話もすっかり満腹になった二人。車に乗り込むと
彼女「これから、どうするの?」
彼「う~ん、そうだなぁ。まだ時間も早いし、これでじゃぁ・・・ってのもまだだね。」
彼女「そうだね~。何しようかぁ?」
彼「そうだ!あのスーパー(待ち合わせ場所)にある映画館、見たい映画やってるんだ。今からすぐ行けば間に合いそうだから、行かない?行こうよ」
彼女「え~!二人で映画見に行くの~?やらしぃ~!二人で暗~い映画館なんて、何考えてるの?ホント、いやらしぃ~。」
彼「おいおい、何で映画見に行くことがいやらしいんだよ。そう考えてるお前の方がいやらしいよ。」
彼女「え~?いやらしくない?男と女が二人で映画館だよ?私は一人で映画館に行く人だから、二人じゃ行かないの!」
彼「(何を想像してるんだ、と思いながら)分かった分かった。じゃぁ、止めよう。そしたら、夜景でも見に行こうか?今日は天気いいし。」
彼女「うん。夜景みたい。行こう行こう!」
という会話の後、車を走らせ夜景を見に行くことに。
その場所は市街地から少し離れた山に続く小高い丘の上で、冬場は「チェーン装着場」として使われるため、かなり広いスペースがあり、かつ、街灯もほとんどないことから、二人の間では「密かな夜景スポット」としている場所でした。
ちなみに、彼の彼女への告白も、この場所で行われたのです。
まぁ、夜景、と言っても住宅街と、その先にある街の明かり程度なんですが・・・。
彼女「結局、またここになっちゃったね。」
彼「まぁな。なんだかんだ言いながら結局ここになるのはいつものことじゃん。」
彼女「うん。でも、この場所でこの景色見るのはすごく好きなんだもん。」
彼「なるほどねぇ。」
彼女は身を乗り出しながら景色を眺め始めました。彼はこういうとき、彼女には声をかけません。
以前声をかけたときに「今景色見たいから、静かにしてよ~。話しかけないで!」とダダをこねられたためです。
そして、しばらく沈黙が流れ始めます。
しかし、その沈黙はすぐに破られました。
彼女「ここに前来たのって、いつだっけ?」
彼「あの時(彼の告白)以来かな?」
この時、彼は「あっ!」と思いました。「その話に持って行くの、今はまだ早い」と思ってはいたのですが、思わず口に出てしまったのです。
彼女「あの時って・・・!」
その瞬間、彼女から笑顔が消え、二人の間に重苦しい雰囲気と沈黙が流れ出しました。
そして、それはそれまで二人の間に流れたことのない、重く、そして長く感じるものでした。
「この沈黙を長く持たせるのはまずい」と思った彼は
彼「あのさ・・・」
と言いましたが、彼女からは意外、というか何となく分かってたような言葉が返ってきました。
彼女「ごめんね。私、やっぱりあなたの気持ちに応えられない・・・」
彼女の目からは涙が溢れ出しました。
彼女「ねぇ、仲のいい友達じゃだめなの?一緒に会って、遊べるなら友達でもいいじゃない!なのにどうして!?どうして恋人同士でなきゃいけないの!?ねぇ、どうして!?」
彼女の声はまさに「悲痛」そのものでした。
さらに彼女は続けます。
彼女「私、やっぱり忘れられないし、今でも好きなの。あの人のこと。だって、私が本気で好きになった初めての人だし、本気で結婚したい、って思った初めての人だし、他にもいろんな意味で本当に初めての人なんだもん。忘れられるわけないよ。本当に好きなの!忘れるなんて無理なの!それなのにあなたはどうして!?いつも一緒に会って、一緒に食事して、遊ぶだけじゃダメなの!?私はそれで満足だし、あなたがいつもそばにいてくれるだけで幸せなのに、どうして私の気持ち分かってくれないの!?どうして!?ねぇ、どうしてなの!?」
ここまで一気にまくし立てた彼女は言い終わると下を向き、手で顔を覆いながら泣きじゃくりました。
彼は肩を震わせながら泣き続ける彼女を見つめるだけで、何も言うことができない、というより何も言えませんでした。
彼は、落ち着かせようと彼女の肩に手を置こうとしました。
ところが、彼女はその手を振り払い、こう叫んでしまったのです。
彼女「今でも好きだよ~!」
この時、彼の心は敗北感で満たされました。
そして、今持っている自分の思いに猜疑心が芽生え始めました。
彼はもはや彼女にかける言葉を見つけることが出来ませんでした。
自分のためにも、彼女のためにも早くこの場を立ち去りたい、彼女の気持ちが分かったから自分自身、一人になって彼女とどうするかを決めたい、そう考えてました。
彼は、彼女が泣き止むまでそっとしておきました。
そして数分後、彼女は泣き止みました。
彼女「ごめんね。気に障ったでしょ?イヤな女、って思わなかった?」
彼「ううん、いいよ。」
彼女「ありがとう。やっぱりあなたは優しいね。もう時間遅いし、明日仕事だから帰ろうよ。」
彼「そうだね。引き上げるとしますか。」
彼は車を走らせ、彼女をいつもの場所まで送りました。
そして、彼は、泣き続けた彼女の腫れぼったい目と赤くなった鼻先を見ながら、そこにいるのがいつもの彼女ではなくて、何か手の届かない存在のようなものを感じ始めていたのでした。(続く)
第9話へはこちら
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- あなたのアバター自慢して!♪
- 韓国での食事(11月 12日)
- (2025-11-15 02:35:31)
-
-
-

- 政治について
- クマ対策に自衛隊が派遣された理由
- (2025-11-30 19:11:43)
-
-
-

- ひとりごと
- 丸山純奈 Sing & Sing- Live at WWW X
- (2025-11-28 21:10:35)
-
© Rakuten Group, Inc.