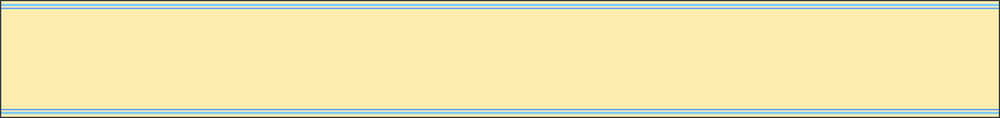西郷と山県
NHK「その時歴史が動いた」で「サムライの最後」と題して、廃藩置県、徴兵制から西南戦争までの動きを追っていた。
「サムライ=武士=士族」という制度、存在 を維新後においてそのままにしておくことは近代国家として立ちいかない。
こうした強固な考えを持っていたのが山県。だから、 サムライを解体して近代軍隊を創設する必要がある。
陸軍郷として、明治6年の国民皆兵による徴兵制によって、まず、軍事を独占していた武士の特権をなくした。
ついで、9年には廃刀令を出し、武士のシンボルを取り上げた。
同じ年には、秩禄処分を実施した。
これらの一連の改革は、 サムライという存在の否定、精神的な誇り・プライドと経済的にも打撃を与えたということができる。
山県には、自身の出自、長州は最下級武士の生まれであることの鬱屈した恨みにも似た思いが根底にあったのではないか。
一連の改革以前、これらの基底をなす改革があった。「廃藩置県」である。この実現にあたっては山県は西郷に強い恩がある。西郷の指導力、決断があったからこそだったからだ。それは徴兵制の実施でも然り。陸軍卿になったのも西郷の取り立てがあったからこそなのだから、それは強い恩情の念を持っていただろうし、尊敬していただろう。
だから、この両者が真っ向からぶつかることとなった西南戦争というのは、山県にとって心情としてつらかったのだろうと思う。そして、西郷の指導力からして手こずることを覚悟していただろうし、恐れすら抱いていただろう。何といっても、鹿児島では、西郷が「私学校」を創設し、まだ サムライが生きていた のだから。
作り上げた軍隊で各地の反乱を鎮圧した山県だが、西郷と共に作り上げた訳で
、西郷が敵になるというのは、本当にきついなと思ったことだろう。
そうした心情の機微、敬意を抱いていた人物と戦わなければならないきつさを山県はどう払拭したのか。運命として淡々と受け入れていただろうか。
指導者たるものは、恩情、敬意や恐れといった心情にほだされることなく、惑わされることなく、ただただ任務を遂行するしかないのだろう。
さて、サムライの制度、経済的基盤を解体し、誇りを奪ったこれらの政策は西郷なしではなしえなかったわけだが、鹿児島には誇り、国家への誇りを持ったサムライが日々西郷の元で鍛錬されていたのである。
カリスマ西郷に付き従い戦う武士の魂を持つサムライvs物量でまさる山県率いる政府軍。 装備が充分な政府軍はサムライの志気の前に苦戦を強いられる。
最後には田原坂で政府軍が勝利するわけだが、西郷を討ち取った山県の思いはどうだっただろう。
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 本日の1冊
- 読んだ本(浅暮三文)・・その百六十
- (2025-11-19 20:55:43)
-
-
-

- これまでに読んだ漫画コミック
- 山と食欲と私 エクストリーマーズ …
- (2025-11-21 12:38:54)
-
-
-

- ボーイズラブって好きですか?
- ヒロアカのBL同人誌!緑谷出久と爆豪…
- (2025-07-10 07:00:04)
-
© Rakuten Group, Inc.