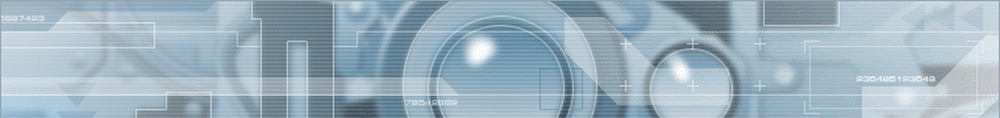小説:Hi作 ピース
小さい時からぼくら三人組は同じ時間を過ごし、同じ楽しさを共有してきた。それは創哉先輩と明美先輩が恋人同士になっても変わらなかった。ぼくとしては二人の邪魔をしたくはなかったが、同時にこんな時間がずっと続いて欲しいと願っていた。しかしその願いは『死』という最も残酷な方法で唐突に打ち砕かれた。
創哉先輩が亡くなって三週間経つというのに、明美先輩とぼくはいつもの教室にいた。
「人との繋がりってパズルと似ていると思わない? 正確に組み合わせることのできるたった一つだけのピースを求めて、いくつも合わせていく」
先輩は自分に言い聞かせるように一人でぽつりと呟くと、机の上にある作りかけのパズルに新しいピースを当てはめる。
光がほとんど届かない中で、窓際に立つ先輩の姿だけが月の光に照らされ、柔らかい輪郭を浮かび上がらせていた。自然と先輩の魅力が織り成す神秘的な美しさと、手を伸ばしてしまえば一瞬で消えてしまいそうな儚さがそこにあった。ぼくはその姿を呆然と眺めることしかできない。
「でも、その唯一のピースを失くしてしまったら、どうしたらいいのかな?」
窓から入り込んだ一月の風が先輩の長い黒髪を撫で、淀んだ教室の中を吹き抜けていく。先輩は僕の視線から逃れるように背を向けると「ごめん」と消え入るような声で呟いた。
こんな時創哉先輩ならなんて声をかけたのだろうか? きっと誰もが満足するような答えを用意できたに違いない。そう考えると、自分の非力さが情けなくなる。同時に、この場にいない立川創哉という存在自体が恨めしく思えてしまう。
結局、ぼくは先輩の問いに答えることができなかった。大切なものを失った悲しみや絶望に染められた世界で生きていく苦痛から救うことのできる言葉を持ち合わせていなかったから……
そのせいでぼくは何もできないまま二つの大切なピースを失い、漠然とした疑問だけを抱えただただもがき続けている。
クリスマスまで後三日と迫り、商店街はすっかり赤と白に染め上げられている。
その中にあって唯一普段通りの営業を続ける喫茶店『ピース』壁にはマスターの趣味なのかいくつかパズルが飾られ、店内を薄く流れるクラシックジャズのBGMが雰囲気を一層落ち着いたものにしている。
カウンター席の一番奥。そこがぼくの指定席だ。一年前まで奥三つの席は毎日のように埋まっていたのに、今は一つだけ。常連客しか見たことのないこの店で二つ席が多く空いていても様子が変わるはずがない。それでも、十席ほどしかない店内が妙に広く感じてしまう。
席に着くとマスターは表情一つ変えず、作業を始める。芳ばしい湯気を昇らせる淹れたてのコーヒーがぼくの目の前に置かれた。彼には客の好みと現況に応じた行動を取れるかなり優秀なコンピュータが内蔵されているに違いない。それほど、一連の動きに迷いも無駄もない。或いはそれがプロの業というものであろうか?
待ち合わせの時間まであと十分強。このコーヒーを飲みほせばちょうどいい時間だ。ぼくは一年ぶりに口にする懐かしい味をじっくり堪能することにした。
コーヒーを飲みほすのとほぼ同時に、カラン、カランとドアに据え付けられた呼び鈴が鳴る。ぼくが扉の方に振り返ると細身のコートにジーンズというあまり飾り気のない服装の一人の女性が立っていた。
ぼくがリアクションを起こす前に女性は綺麗に整った栗色の髪を弾ませながら近づいてくる。
「待たせちゃったかな? ごめん、ごめん」
一瞬だけぼくの手元にある空のカップに視線を送ると、両手を顔の前に合わせて、小さく頭を下げる。
「ぼくが勝手に早く来ただけだから気にしないで」
彼女のかわいらしい所作を見て、行動の甘さに後悔する。
「それに今日はぼくの買い物に付き合わせちゃうわけだしさ」
「それもわたしへのプレゼントを買うためでしょ? やっぱり、気が引けるな」
「じゃあ、この一杯は君のおごりということで」
「オッケー、これで貸し借りはなしね」
伝票を手に取ると彼女は満足げに笑ってくれた。その笑顔にぼくの顔も自然と綻ぶ。
彼女は同じクラスの斉藤恭子。あだ名は『さいきょう』。本人はこの名前を非常に嫌っているが、小学校の時につけられて以来からのもので、中学時代剣道で全国大会に出場してからは男女問わず定着しているらしい。
どうして「らしい」としか言えないかというと、ぼくは一ヶ月前まで彼女の名前すら知らなかったからだ。
自慢ではないが、ぼくはクラスから少し浮いていた。授業中であろうとふらふらといなくなるし、文化祭などのイベントにもほとんど参加したことがない。だからクラスの人気者である彼女がぼくに告白してきた理由が未だに理解できない。まあ、請われるままに承諾してしまった自分もどうかと思うが……彼女の整った顔立ちに惹かれた、ということだけは否定しておきたい。
ぼくの知っている『さいきょう』に関するデータは余りにも少ない。おそらく、彼女の女友達Zにも劣るかもしれない。
それでも付き合い始めて約一ヶ月。デートも何回か行ったし、手をつないで歩く程度には進展した。彼女の快活な声も女の子らしい仕草も頑固なところも魅力的だと思える。会うたびに新しい魅力を発見できるというのも楽しい。
ただ、彼女の告白に正式な答えを出せていないことだけが心残りだった。
サンタの衣装を着てチラシを配る人。親にプレゼントをねだる子供。仲良く手をつないで歩くカップル。商店街にいる全員の足取りが軽く、表情も華やいでいるように思える。
かく言うぼくの隣にも最高の笑顔を振りまいて、手をつなぐ女性がいるわけで。そう思うと、急に顔が熱くなり、体の動きが強張ってしまう。
アクセサリー、洋服、果てはブランド物まで商店街の目ぼしい店は大方見てまわり、彼女の嗜好は大分掴めてきた。
「大分、連れまわしちゃったね。どこか休めるところに行こうか?」
「帰宅部のクセに意外と体力あるよね」
「伊達に学校抜け出してふらふらしてないから」
「それ体力と関係ないし」
できるだけ強気に笑って見せたつもりだが、足はパンパンで椅子があれば一刻も早く座りたい気分だ。彼女の方がまだ体力が有り余っているといった様子で余裕の笑顔を見せている。
「ねえ、あそこに寄ってもいい?」
彼女が指差す方には店頭に大きなツリーを飾るおもちゃ屋があった。さすがにそこはノーマークだ。おもちゃ屋で見たいものとはなんだろう? そこに特別なものが置いてあるとは思えないが、また新たな発見があるかもしれないと期待してしまう。まさかぬいぐるみと言い出すのではないか? それはそれで可愛らしいと思うが……
ぼくの腕を引き、店内に入るとなぜか彼女はプラモデルのあるコーナーに歩いていった。しかし、彼女の視線が注がれていたのは正確にはその隣の最も下段にあるものだった。
「ジグソーパズル?」
「私、結構こういうの好きなのよね」
彼女はしゃがみこむと色彩豊かにプリントされたパッケージを見比べ、童心に返ったように大きな瞳を輝かせている。実に微笑ましい光景であるというのに、その姿をもう一人のパズル好きな女性と無意識のうちに重ねてしまう。
「そんなに私がパズル好きなのが意外?」
「え?」
少し不機嫌そうな声で我に返ると全国レベルの剣士の瞳がぼくを捉えていた。
「どうせ『さいきょう』の私には細かい作業は似合いませんよ」
彼女は手にしていた蛍光色でクリスマスツリーとサンタが描かれた箱を乱暴に元に戻す。
「意外な趣味だな、とか、全然想像できないや、とか思ってないから」
動転する頭で何とか弁解しようと試みるが、雲行きはみるみる怪しくなっていく。
「えーっと、そういう意味じゃなくて、とにかくごめん」
殴られることを覚悟で頭を下げるが、予想に反して彼女は頬を少し膨らませ、不満の声をもらした。
「やっぱり、和輝君も私をただの『さいきょう』としか見てないんだ」
「ただのさいきょう」って日本語おかしいな。じゃなくて、怒った顔もかわいい。でもなくて……
「そんなことないよ。斉藤さんの女性らしい仕草も可愛らしい笑顔もぼくは知っているよ。ぼくはそんな斉藤さんがとても魅力的だと思う」
一か八か脳内にある小説かドラマかわからない台詞を引用して慰める。同時に彼女の髪をゆっくりと撫でる。
「……一ヶ月前まで名前も知らなかったくせに」
「うん。だから新しい斉藤さんの一面が知れて嬉しかったんだ」
「そんなことだけじゃ誤魔化されないから」
僕の手を払いのけると、声にいつものような強気な感じを取り戻していることに安堵する。
この手段は思った以上に有効だな。次までに少し練習しておこう。そんなことを考えながら、うれしくて笑い返した。
「うわー、お兄ちゃんがお姉ちゃんいじめてる」
後ろから突然かけられた声に振り返ると、小学校高学年くらいの三人組の一人がこちらを指差していた。
「ちがうよ。あれはただのちわげんかだよ」
「うんうん。ラブラブだね。青春だね」
隣にいた女の子と男の子もニヤニヤしながらこちらを眺めている。
ぼくは恥ずかしいやら後ろめたいやらの気持で一杯になり、斉藤さんの手を引いて、慌てて店を飛び出した。
思いつくままに走り抜け、ぼくたちは茜色に染まる公園まで辿りついていた。
「お疲れさま」
息を弾ませるぼくに斉藤さんはどこで手に入れたのかわからない缶ジュースを差し出し、ベンチに腰を下ろした。機嫌はすっかり直ったみたいだ。
ぼくが慌てて財布を取り出そうとすると、それを手刀で弾かれる。
「こういうのは気付いたもん勝ち。先手必勝! 貸し一つ」
笑顔で受け取りを拒否して、手で作った一をビシッとぼくの鼻先に突き立てる。「貸し一つ」は彼女の口癖であるが、一から増えた例はない。もし、それが加算されていたらぼくは莫大な借金地獄に陥っているだろう。
「ふふふ、全部覚えたいたらどうする?」
まるで思考を読み取ったかのような言動に恐怖を覚える。
「やっぱり、払っておこう」
「冗談だよ。そんなのいちいち覚えてないって。例え覚えていたとしても請求しないから安心して」
あたふたと財布を取り出した姿を見て、いつもの笑顔に戻る。
「ほんと、考えがすぐ行動に出る人だよね」
「そうかな?」
ヘビに追い詰められたカエルのように逃げ道を探して、目にとまった缶ジュースのプルタブに手をかける。缶を一気に傾け、誤魔化すように中身を流し込む。急激に進入してきた喉を刺激する液体に思わずむせ返り、そのほとんどを吐き出してしまう。
顔を上げるとしてやったり、というように微笑を浮かべる斉藤さんと目が合い、気恥ずかしさに頭を掻く。
「剣道には向いてないね。人間関係でも結構損してそう」
「嫌気が差した?」
「ううん、私は好きだけどな。そうやって他人に巻き込まれちゃうところとか、その割に相手のことちゃんと見て気遣ってくれる所とか」
もじもじと缶ジュースをいじりながら空を見上げる斉藤さんの顔が赤く見えたのは夕日のせいだけではないだろう。
普段は見た目以上に大人っぽく構えている彼女が時折見せる女の子らしい仕草にぼくの鼓動も自然と早くなる。斉藤さんと付き合う前のぼくでは考えられなかったことだ。
去年の今頃は創哉先輩のプレゼント選びにつき合わされていた。創哉先輩は女性が喜ぶプレゼントについてびっしりと書き込まれた大学ノートを片手にぼくを一日中引きずり回した。男二人が真剣に女性物のアクセサリーやバッグを品定めする姿は泥棒にしか見えなかったであろう。「クリスマスに明美に渡して告白する」と豪語していたというのにそのプレゼントが活躍する機会はやってこなかった。
「和輝君。もしも~し、聞いてますか? 岡田和輝君」
気が付くと斉藤さんはぼくの顔を訝しげに覗きこみ、手刀で眉間を叩いている。
「斉藤さ……」
いきなり飛んできた目潰しをかわそうとしてベンチから転がり落ちた。
(ちっ)
「ちょっと、何するんですか?」
「あはは、あんまり反応がなかったもんで、つい」
「つい、で人を失明させないでください。しかも舌打ちしましたよね? 確信犯じゃないですか?」
「あ、ばれた?」
斉藤さんは悪びれた様子もなく舌を出し、笑いながら手を差し出す。
「勘弁してくださいよ」
「デート中にぼーっとしてたのは誰だ?」
起き上がったぼくの顔に人差し指を突きつけ、問い詰める。その迫力はさすが『さいきょう』の異名をもつことだけのことはある。
「なんか、たまにそういう時あるよね? どこか遠くの世界に行っちゃってます。みたいなさ」
ごめん、と歯切れの悪い返答をすると、斉藤さんはやれやれといった感じで肩を落とす。
「さあさ、お姉さんに話してみなさい。誰かに話してみることで何か変わるかもしれないよ」
声はさっきと同様茶化すような調子だが、真剣な目つきで彼女はぼくに正面から向き合ってくれている。
彼女の明るい声、ぼくにだけむけられる優しい瞳に少しだけ甘えたくなった。そして、今まで何度も自分の中で繰り返してきた答えのない疑問を口にした。
「例えば、作りかけのパズルがあったとして、とても大切なピースを失くしてしまったらどうする?」
「うーん」
彼女は一度だけ唸った後、腕を組んだまま考え込んでしまった
「私ならそのまま組み上げちゃうかな」
長い思案の末、彼女の出した答えはシンプルなものだった。
「そのパズルは絶対に完成しないのに?」
「私はそんなことで諦めたくないな。今まで組み上げてきた時間を無駄なものとは思いたくないし、他のピースに失礼だからね」
明るくて前向きな彼女らしい意見だと思う。ぼくには到底真似できない。
「それに失くしたと思ってたピースが思いがけないところから出てきたりもするから」
最後の言葉は経験談だろうか。懐かしむようにくすくす笑っている。
「きっとその人は何かすごく心残りなことがあって、その場を動けなくなってるんだね。パズルを完成させるには一箇所からだけじゃだめなのに」
少し俯き加減に彼女の口から放たれた言葉は寂しく、重いものだった。本当に全て見透かされている気がする。ぼくは彼女の言葉を反芻しながら黙って耳を傾けていた。
「すっかり暗くなっちゃった」
「うん。変な質問しちゃってごめん」
「いいよ。これで貸し二つだから」
「やっぱり加算されてるじゃん」
戸惑い続けるぼくに追い討ちをかけるような言葉を投げかけた後、えへへ~、と舌を出し、ぼくの腕にしがみついてくる。
そのあともぼくたちは他愛ない会話をしながら外灯の少ない暗い道を彼女を家までおくっていった。家の前まで来ると寒いことも時間も忘れて彼女を三十分も引き止めてしまった。今日は今まで以上に彼女のいろんな顔が見られた気がする。時間と体力のほとんどを使い果たした代償としては十分すぎるものだ。貸しを一つ積み上げたようにぼくたちは関係を積み上げていくことができるのだろうか……
翌日、一日の授業が全て終わったことを告げるチャイムが鳴るとぼくはふらふら席を立つ。一瞬、斉藤さんと目があったような気がするが、構わず教室を出た。
「和輝君。今日部活ない日だからたまには一緒に帰らない?」
廊下に出た直後、後ろから声を掛けられる。その声を聞けただけテで嬉しくなるぼくはなんとも単純だな。
「ありがと、斉藤さん。でも、用事があるから。それに……」
ぼくは彼女の机の周りに集まっている女生徒たちを指差す。みなこちらを訝しげな視線で眺めている。
「ううん、こっちこそ無理言ってごめんね」
ぼくの言いたいことをすぐに理解してくれた彼女は寂しげに俯く。こんな無愛想な彼氏にも笑顔で声を掛けてくれる斉藤さんには本当に感謝のしようもない。せっかく前進したはずの関係もぼくのせいで台無しにしてしまっている気がする。
せめて気持だけは返しておこうとぎこちない笑顔を作って、その場を後にした。
南北に長い校舎の三階。最も北にある空き教室。ほとんど物置と化した教室がぼくらの秘密基地。度々授業を抜け出しては三人で昼寝ばかりしていた場所。今ではここを使う生徒はぼくくらいのものだ。
誰もいないと思い、遠慮なくドアを開けると中には見知らぬ男子生徒が部屋を物色していた。
「何しているんですか?」
急に空気が静まり返り、全員の視線がぼくに注がれる。
「噂のユーレイさんを見とこうと思ってな」
「もしかしてあんたがユーレイさんかい?」
手前にいた体格のいい二人が耳障りな笑い声を上げると後ろのもう一人もつられて笑い出す。
『幽霊』か。確かにぼくを表現するのにこれ以上相応しい言葉はないかもしれない。
「だったらどうします? お友達にでもなるつもりですか」
「いやいや、面を拝めて満足ですよ。これ以上、こんな空気の悪いところにいたらオレたちまでユーレイになっちまう」
さっさとこの場からいなくなってほしい。言葉とは裏腹に未だにその場に居座る男たちを睨みつける。その時一人の男の手が机の上に伸ばされるのが視界に映った。
「それに触るな」
「あ? 何だって?」
「触るなって言ったんだよ」
男の肩を掴み、顔面を殴りつける。
気の弱そうな男の突然の行動に一瞬呆気にとられた顔をしたが、何しやがる! と大声を張り上げた別の男の拳が頬を叩く。たった一撃で勝負はついた。ぼくは轟音と共にあたりの机を転ばし、倒された。同時に机の上にあった作りかけのパズルが床にばら撒かれる。
三人の男はそれを容赦なく踏みにじり、ぼくを囲むように立ち塞がると容赦なくけり始める。ぼくは自分の体の痛みよりも何故か散らばるパズルの方を守ろうと必死になっていた。
「こんなもんがそんなに大事かよ」
最初にぼくが殴りつけた男がわざわざ見せ付けるようにパズルを踏む。その足を払おうと手を伸ばしたところへ別の男の蹴りが思い切りわき腹に入った。咳き込むぼくにさらに二発、三発と加えられる。
三人の男は捨てられた空き缶を潰すかのように醜悪な顔に下卑た笑いを浮かべて、その行為に没頭している。
「貴様ら! 何をしているんだ!」
騒ぎを駆けつけたのか、数人の教師が教室に入ってくる、三人組はやべー、と言い放ち逃げ出そうとするが、唯一の入り口を塞がれてはそれもできずに全員連れて行かれた。
「君も生徒指導室まで来るんだ」
地べたに這いつくばってパズルを集めていたぼくの頭上に生活指導の教諭が声を掛ける。
「はい」
「早くしなさい」
ぼくは目に付く限り拾い集めることのできたパズルを箱に戻すと、教諭に連れられて教室を出た。
生徒指導室では三人組が教諭たちの前で正座させられ、いろいろと弁解していた。
ぼくも彼らに習い、体中から発する痛みを我慢して平然と少し離れた場所に正座する。
「最初に手を出したのは君というのは本当かね? 岡田君」
「はい」
そのことを信じられないといった風に数人の教諭が息を呑む音が聞こえた。大抵のあらましは彼らから聞いたらしい年配の教諭は質問し始めた。
「何故かね?」
「言いたくありません」
「真面目に答えんか!」
「言いたくありません」
同じような質問を繰り返す教諭たちにぼくは全て「言いたくありません」としか答えなかった。三人組は必死に弁解の言葉を並べている。そんなことをしても無駄だ。ぼくには弁解する気持ちさえ起きない。教諭たちにとっては問題児が四人厄介ごとを起こした程度にしか考えていないだろう。
そんなやり取りが一時間ほど繰り返された後、教諭たちも呆れてしまったのか、考え付く限りのお叱りの言葉を並べ立てた後、その場はお開きとなった。
軋む体を抑えながら三人組に続いて部屋を出て行こうとすると年配の教諭に声を掛けられる。
「君の事情は知っている。しかし、それが何をやっても赦されるという理由にはならない」
「失礼します」
その後にも話が続きそうだったので、遮るように一言だけ告げると静かにドアを閉ざした。
体を動かすたびに骨や筋肉に電気が走るように痛む。まだどこかを蹴られているような感覚さえある。冬の寒さが体を走る痛みに拍車をかけている。
下駄箱で靴を履き終わると、制服姿の見知った女性がポツンと立っていた。
「斉藤さん? 帰ったんじゃなかったの」
「忘れ物を取りに来ただけど、ちょうどいいから一緒に帰ろうよ」
見え透いた嘘をついてこちらに寄ってくる彼女から一歩身を引いてしまう。普段なら手を取るのだが、今はそんな好意さえ煩わしい。
さすがに驚いた表情を見せる彼女に謝ろうと思ったが、やはりやめた。
「一人にしてください」
ぼくが見せた初めての拒絶に彼女の顔が曇る。今にも泣き出してしまいそうなくらいだ。
「辛いことがあったら相談してよ。私は和輝君の彼女でしょ?」
「違うよ」
もうぼくの表情から感情を読み取るのはやめてくれ。それ以上言ってはダメだと心の中の自分が警鐘を鳴らしているにも関わらす、一人の少女を傷つけることに対する一種の嗜虐心の前に理性は紙屑同然に吹き飛んだ。
「『さいきょう』の君ならわかるだろ? 君を誰と重ねているか、ぼくが誰の影を追っているのか」
言ってしまった。絶対に口にしてはいけない言葉を最悪の形で表してしまった。これで
その瞬間全てが終わった。積み上げてきた関係。新しく組み始めたパズル。全てを自らの手で失わせた。
「そんなことわかってるよ! 一年前、立川先輩が事故で亡くなった日から和輝君が浅沼先輩を励まそうと毎日あの教室に行ってたのも知ってる。浅沼先輩が自殺しちゃったあとも一人で変わろうと努力してきたことも知ってる」
彼女がそこまでぼくのことを気にかけていたことは正直驚いたが、もう引き返せない。
そのまま背を向けると離れていく。
「私は諦めないから。パズルがどんなにバラバラになっても私は絶対に諦めたくない……」
背中から聞こえる彼女の震える声を振り払うように黙々と歩く。早くその場を離れようと自然とスピードが速くなる。すっかり冷静になった頭は悔恨と自責に押しつぶされそうになる。今までの高揚の反動を受け、心は深く、深く沈んでいく。
校門を出て左に折れるとすぐに柱を殴りつけた。全身をめぐる痛みに新しい痛みが加算される。
それでも二発、三発と殴ることをやめなかったのは次に来るものが何か知っているからだ。
絶望と諦め。
どれほど感情が昂ぶろうと心は平穏を求める。
どれほど苦悩しようと脳の活動はいずれ低下する。
だからこそ今のうちに刻んでおきたかった。この痛みを感じるときに彼女の言葉と自分の愚かさを思い出せるように。
しかし、精神力の弱いぼくは十発も殴らないうちに諦めていた。そしてそのまま家路につく。
変わらない。
一年前と何も変わらない。
ぼくは何度も同じ過ちを繰り返す。
いや、一年前より最低だな・・・・・・
十二月二十四日。
この国の人間が最も浮かれる日。
たくさんの笑顔が溢れて、幸せを実感できる日。
夜になるとぼくは学校に忍び込んでいた。
ぼくが小さい頃から世界中を飛び回っている両親とは最近まともな会話すらしていない。口うるさい両親がいないことをいいことに昨日も今日も一日中家に引きこもっていた。どんなに振り払おうと思っても彼女の言葉が頭を回り、次に思考停止。その堂々巡りを何度も繰り返すうちに時間は過ぎていった。
自分の中でどんな心境の変化があったのかはわからない。ただ、足が勝手にいつもの空き教室に向かっていた。
ここには電飾で飾られたイルミネーションの光もクリスマスを堪能する明るい声も届かない。いまのぼくにはそれが何より心地よく感じる。
ドアを開けると外と余り変わらない冷たい空気と埃っぽい匂いが流れ出る。一歩足を踏み入れた瞬間からぼくの体は闇に包まれる。電気をつけるわけにいかず、漠然と辺りを見渡す。その闇の中で唯一人工的な光を放つ物が目に留まる。箱に収められたジグソーパズル。蛍光塗料が表面に塗られたそれに引き寄せられるように近づく。
おもむろに中のピースを机に並べて、組み合わせる。
ピタリと合う。
新しいピースを取り出して再び組み合わせる。
ピタリと合う。
窓からの月明かりとパズル自体の光だけを頼りに解いていく。次第にぼくはその行為に没頭し始めた。
バラバラになったとはいえ、一度途中まで組み合わされたパズルは大きな塊になっているものも多く、作業は思った以上に順調に進んでいく。箱の中身が残り少なくなってきた。ぼくは明美先輩がまだ手を出していなかったところも組み始める。ペースは若干落ちたが、ほぼ全景がつかめる為、ヒントが多くてわかりやすい。
(これならぼくでも完成できるかもしれない!)
わずかな希望に時間が経つのも忘れ、ひたすら同じ行為を繰り返す。
八割方完成したところでパズルの空きと残りのピースの数があっていないことに気付く。
構わずあるだけのピースを全て組み合わせてみたがやはり三十ピースは足りない。
一昨日落としたときに拾い残しがあったのか? 暗くてほとんど何も見えないというのに必死に目を凝らして、床を隅々まで調べる。
書棚の下にようやくひとつ見つけると手を伸ばして拾い上げる。その瞬間、右手に激痛が走る。ろくな処置をしていなかった拳が寒さと乾燥で皮が剥け、血が滲み出る。
「フフ……ハハハハ」
自分でもわからないうちにこみ上げてくる笑いを抑えようともせず、教室中に響く大音量で吹き出した。
どんなに諦めず努力してもダメなものはダメなんだ。
その場に座り込み、見つけることのできた唯一のピースを眺める。
「ごめんね。斉藤さん。ホントにごめん……」
誰に届くことない言葉を白色の溜息と共に投げ捨てる。
「ダメです。その程度じゃ赦してあげません」
聞こえるはずのない声に反応し、入り口に目を向けるといるはずのない人物の姿があった。
「何で……いるの?」
「これが必要なんじゃないかと思って」
彼女が手にしているビニル袋の中には色とりどりの蛍光色のピースが納められている。
「どうしてだよ? 何で諦めてないんだよ? あれほどひどいこと言ったのに。斉藤さんのこと好きじゃな……」
「ストップ!」
さっきのぼくの笑い声以上の大喝が教室をこだまする。
「まだ最後の言葉は言われてない。それに私は諦めないって言った」
ぼくのなかの反論しようとする意思は彼女の一言で全てかき消された。
「和輝君だって諦めなかった。だからここにいるし、それを見つけられた」
「違う。ぼくは諦めていたんだ」
どうにか言葉を口にすると二人の間に沈黙が流れる。
「ホントは私も諦めてた。ここに来てもムダだ。ってね」
彼女は自分を恥じ入るように大きく肩を落とす。
「それでもこれだけは届けたいって思ってなんとかここまで来た。そしたら和輝君もやっぱりここにいて、パズルもほぼ完成していて、足りないピースを探して必死になっていた」
ぼくには彼女が諦めていたなんて全く予想がつかなかった。前向きで迷いのない女性だと思っていた。それが自分と同じようなことに悩んでいたなんて。
彼女から手渡された袋を受け取るとぼくたちは二人でパズルを組み始めた。
「和輝君が聞いた質問にもう一度答えていいかな?」
「うん」
「パズルがバラバラになっても今まで組んできたものは決して無駄じゃない。大切なピースがないことがわかってもここまで自分の手で組みなおせる」
「うん」
「それでも足りない所はある。私は和輝君とそれを繋ぐ最初のピースになりたい」
「ありがと」
ぼくの目からは自然と涙が零れてきていた。それが一年間求めた答えだったかはわからない。いや、正しい答えなんておそらくない。これは彼女がぼくにくれた二人だけの答え。
「ぼくも斉藤さんに答えなくちゃいけないことがあるんだ」
それはぼくが今まで言えなかった言葉。
「ぼくは斉藤さんのことが好きです。だからもうぼくと付き合ってください」
涙でくしゃくしゃになりながらのとても情けない告白だ。けれど気持ちは伝えられたと思う。
「じゃあ、名前」
「え?」
彼女の返答の意図がつかめず間の抜けた返答をしてしまう。
「だから名前。斉藤じゃなくて下の名前で呼んでほしい」
彼女はぼくの言葉を期待するようにじっと見つめてくる。
「……さいきょう」
「本気で殺すわよ」
急に照れくさくなりお茶を濁そうとしたのだが、恐ろしいほどの握力で顔を掴まれる。彼女の指の隙間から見える目が本当に『さいきょう』になっている。
「ごめん。恭子さん。面と向かっていきなり言うのが恥ずかしかったから。そんなに怒らないで、可愛い顔が台無しだ」
いつかのように脳内から必死に引用したセリフを言いつつ、彼女の髪を優しく撫でる。
「ブッブー。同じ手がもう一度使えると思ったら大間違いですよ」
不機嫌そうな声を出すが、その瞳に『さいきょう』の姿がすっかり消えていることに彼女自身は気付いていないようだ。
「わかった。貸し一つでいいから」
「言ったね。これで六つだから」
「やっぱり加算されてる! っていうか計算おかしいでしょ」
今回の件ではずいぶんと迷惑をかけてしまったが、さすがに理不尽すぎる気がする。
「細かいことは気にしないの。それより今日は遅いからこれくらいにして早く帰ろう」
自らの後ろめたさから強く言い返すこともできずにぼくは恭子さんに引きずられていく。ぼくの手にはひとかけらのピースがしっかりと握られていた。
年が明けて三学期が始まった直後、ぼくは喫茶店『ピース』でアルバイトを始めた。
最初は何度も断られたが「給料は要らない」「雑用だけでいい」と頼み込むと渋々承諾してくれた。
さすがに給料は出してくれるが、マスターはぼくの宣言どおり雑用として徹底的に使ってくれている。床は顔が映るまで磨かされ、コップや皿は曇り一つなくなるまで洗わされる。仕事自体は辛いことばかりであるが、ここには様々な人との交流がある。彼らは皆飲み食いし、マスターと語らった後必ず満足した笑顔で店を出て行く。それを見られただけで、ここで働いてよかったと思える。いや、いつかはマスターのようになりたいと密かな野心を燃やし、隅々まで観察している。
「ラブラブ兄ちゃん今日もいるー?」
店の雰囲気をぶち壊すように勢いよく扉が開けられる。店内におもちゃ屋であった三人組が声をユニゾンさせ、入り込んできた。
「お前ら少しは静かにしろ。それにぼくの名前は和輝だ」
幸いお客は恭子さん一人だけなので助かったものの、そうでなければマスターに怒られているところだ。特にぼくが。
三人組はぼくの気苦労など微塵も気にせず走りぬけ、席に着く。カウンター最奥の席は彼らの指定席となっていた。マスターは黙ってジュースを三つ差し出す。彼らは実に楽しそうにそれを飲み、談議に花を咲かせている。どうやら話題は壁に飾られたパズルのことのようだ。
「兄ちゃん、何であのパズルだけ完成してないの?」
ぼくと恭子さんは顔を見合わせて微笑んだ。一番年下の子が指差す先にはところどころピースが欠けているパズル。それはぼくたちが完成させようと必死になっていたパズルだった。
恭子さんが持ってきたピースをあわせても完成させるまでには至らなかった。マスターに話すと「とりあえずそこに飾っておきなさい」と言われた。糊付けしないまま額に納められ、仲間と一緒に飾られている。
「あれはまだ作ってる最中なんだよ。だからピースが足りてないのはぜんぜん不思議じゃない」
三人組のリーダーっぽい男の子はぼくが言うより早く答えていた。
全くその通りだ。パズルはまだ完成していない。だからぼくたちは今日も新しいピースを求め、組み上げていく・・・・・・
© Rakuten Group, Inc.