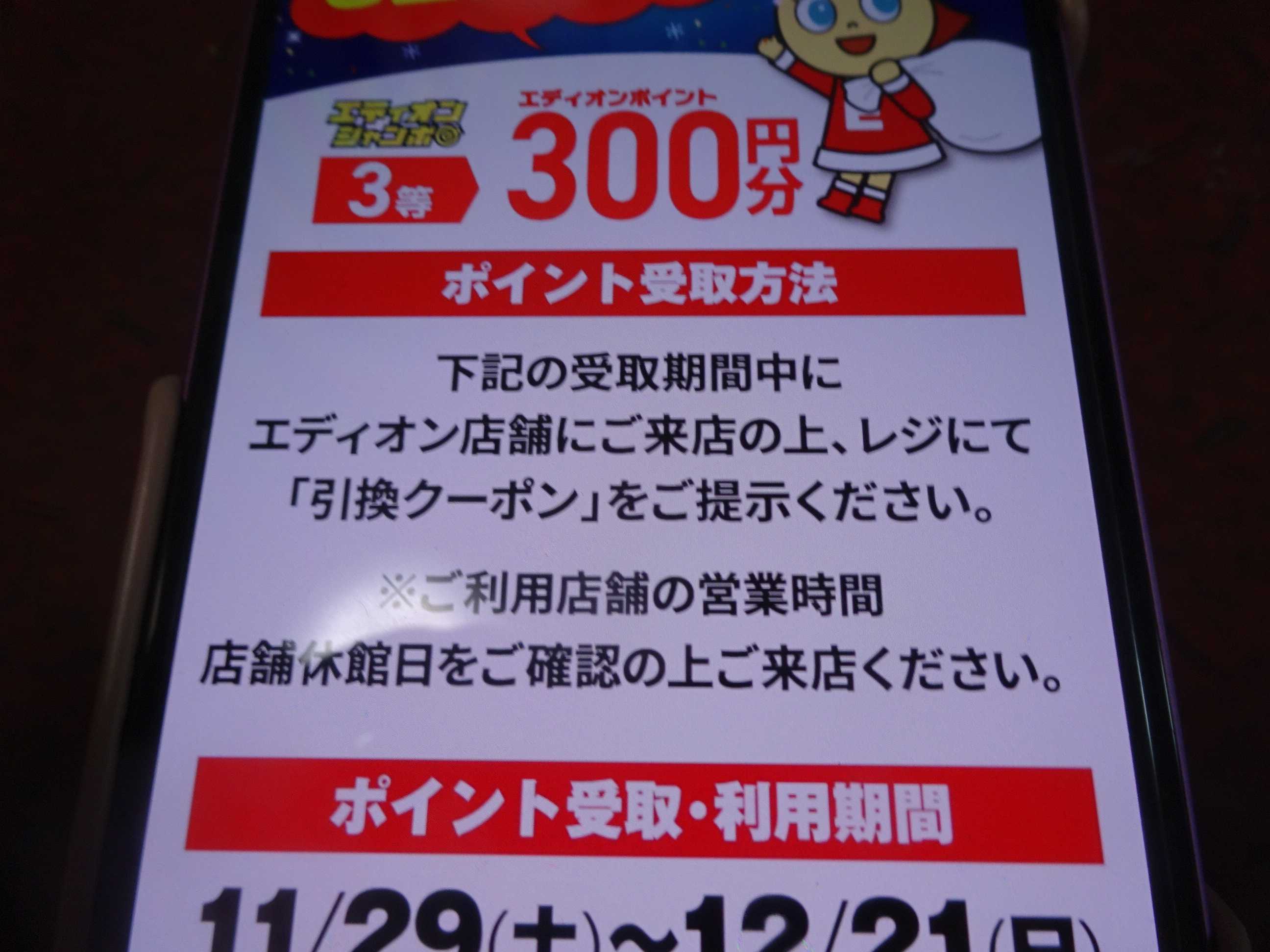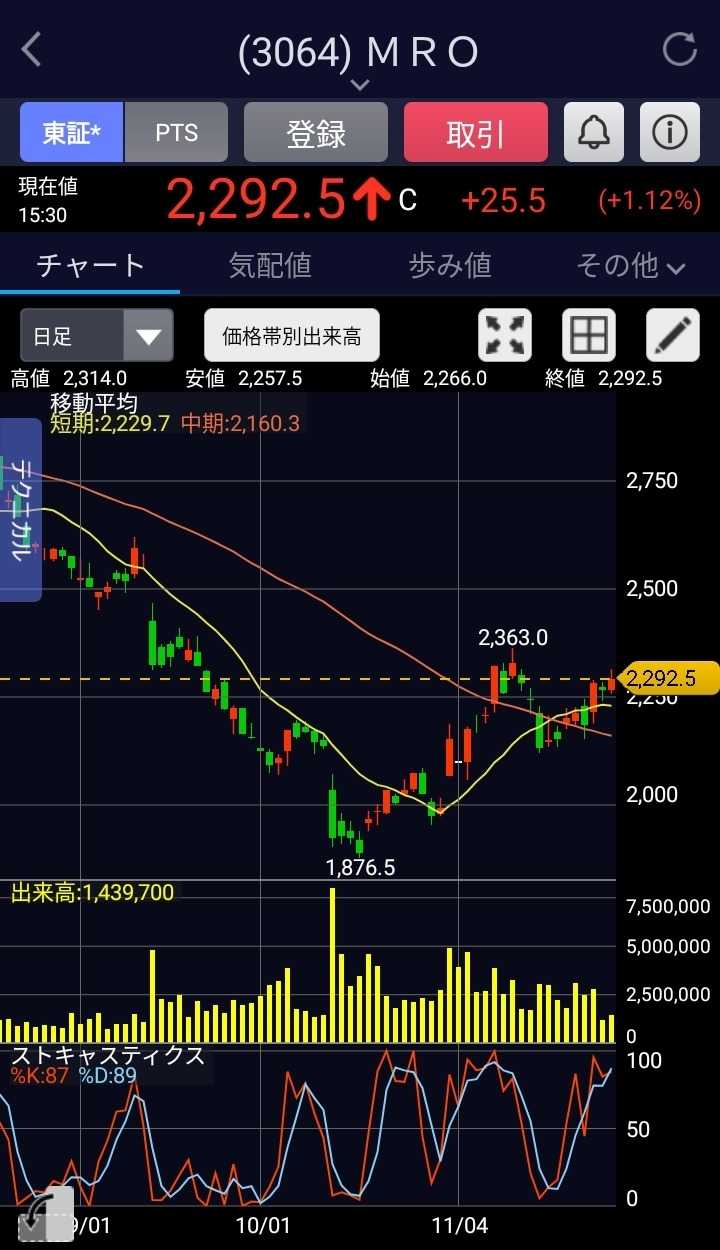「ダス・ゲマイネ」 3
それは、芥川賞との関わりが重要だ。1935年の2月に初めて、「逆行」で商業誌にデビューする。初めて太宰が、素人の同人誌から抜け出て、商業文芸詩にデビューして、さらに第一回芥川賞の候補になる。1935年に、菊地寛によって創設された芥川賞だが、この7月に選考会が開かれた。その選考の様子が文芸春秋の9月号に載っている。ここで「逆行」が芥川賞で外れて、そのことが要因になって「ダス・ゲマイネ」が発表されてのではないか?というのが私の見方なのだ。まず、なぜ文芸春秋に載ったのか?蒼茫で石川淳が芥川賞をとるのだが、その落選した作家にそれぞれ作品を書かせ特集をとる。したがって「ダス・ゲマイネ」に書き始めた時に、すでに芥川賞に関わっていた。太宰が候補になったということだけではなくて、もっと深いところで「ダス・ゲマイネ」の発表の要因がある。それは、第一回選考会で、川端康成が太宰を批判したことだ。選考委員の6人のうちの、佐藤春夫は太宰の支持者だったが、
同じ時期の「道化の華」を推した。しかし、この選評で川端康成が批判的な事を文春の9月号に書いた。これを、太宰がいつ読んだのか?それは、川端康成宛に書いた文章が残っている。8月の末に読んだと書いてある。激こうして「文芸通信」の10月号に書いている。文春9月号の2カ月後になる。太宰は特有のペーソスと批判でたっぷりと書いている。川端を挑発するような言葉がある。
したがって、太宰が少なくても前後には読んでいたことが分かる。自分の評価に対して、極めて敏感になっていた時期。芥川賞に落ち、落ちた文芸春秋からの依頼で「ダス・ゲマイネ」を書いた。先ほどの、人格の乱反射ということは、自分の評価に対して極めて敏感になっていた結果なのである。人格が4つに分化したのはその為なのだろう。ここには、芸術に対しての「自己意識の喚起」ということも挙げられるだろう。または、自分のことを戯画化して「ダス・ゲマイネ」というのは成立したということになるのだろう。実際に作品の中には、佐竹に託して川端に反応しているところもある。
「...自尊心の高さには、ぞっとするが、あいつの絵だけは認めなければいけない。」という部分だ。
これは、いわば、川端が、作品とは別のところで「生活に暗い影あり。」とした事に対する「返歌」であるとも言えるのだ。性格は、どうであれ、作品は正当に評価されなければいけない、ということを、ここで佐竹に語らせているのである。これは、一種の意趣返しということになるのだと思う。
「もの思う葦」で、1935年には「ダス・ゲマイネについて」を書いている。
「ダス・ゲマイネ」というのは、卑俗性という意味であるが「ウール・シュタ」ンド(本念の状態)葛西善蔵は「ウール・シュタンド」、「ダス・ゲマイネ」は菊池寛である。優劣をここで審判するのは持っての他だ、と書いている。菊池寛は、卑俗の象徴であると書いている。評価というものに対しての批判を書いている。
「作品を審判するのはおかしい」と、太宰は書いていて、そういった意味でも、芥川賞で批判されたことに対する気持ちが表れていると思う。
この「ダス・ゲマイネ」の位置づけは、それは「逆行」に似ている。破滅型でユーモラス、自己否定でズッコケル。「逆行」に似たものがある。したがって、「逆行」のスタイルは、これに一脈通じるものがある。重要な点は、まだ「晩年」が出ていないこの時期から「晩年」の発想が、「ダス・ゲマイネ」にはあった、という点だ。「晩年」の翌年に書かれた「二十世紀旗手」には、過剰な自己意識と自己否定の相克が描かれている。高い絶望感と自己意識の間を、なぜ往復していたのか?
それは、生まれの問題、(富豪の6番目の息子として生まれ)非合法の左翼活動に走ったり、つまり自己否定をしたり、内縁の妻の過ち、都新聞の就職の失敗、出身階級の悩みと、女性問題、就職の悩みに、すぐに傷つく。つまり、太宰という人間は、極めて繊細で、いつも自己否定に走るが、「作家としての自分は大したものだ。」という、プライドの高さも持っている。
自負と自己否定の間を往還しているというのが、太宰のいつものパターンである。これが、4つの分身に投影されているのだ。そして「走れ メロス」は中期の作品だが、その中の「ダス・ゲマイネ」は初期の作品に属する。
「ダス・ゲマイネ」に出てくるが、ビアズリーというのは、悪魔的な作風の絵を描く人。オスカー・ワイルドの挿絵を描いたことで有名で、夭折した画家。破滅型の人格なのである。こういった画家を出すことも、やはり意味がある。
太宰治の現代作家への影響を取材すると、漱石よりも太宰が好き、と言う人が多い。
1996年芥川賞受賞の柳美里さんは「カチカチ山」が好き。
10代で史上最年少で芥川賞をとった綿谷さんも、太宰が好きで、卒論は「走れ メロス」。
町田康氏も、その文体には確実に太宰の影響がある。
太宰本人は、芥川賞をとれなかったが、その太宰の影響を受けた現代の作家たちが芥川賞をとっているというのは、皮肉な現象である私と思う。
(注2~注5資料不明)
© Rakuten Group, Inc.