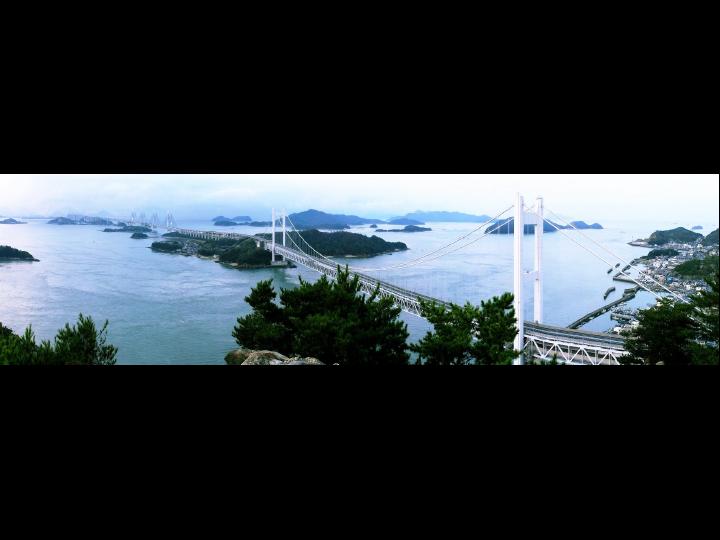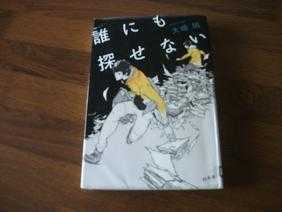2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2016年08月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
きのうこんなことを書いて見た・・・。
文学と言う謎の言葉 2016/8/24 私はこの言葉を心において生きてきた。「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」 長谷川伸の「関の弥太ッペ」のなかの名セリフだ。 この言葉にどれほどいやされたことだろう。 私はこのような言葉が書きたくて、今まで沢山の作品を書いてきたのかもしれない。心に残る、いや遺すその言葉を…。 今まで生きてきてついぞその言葉以上に感銘を受け前向きに生きる上での励ましを受けたことがない。 私は一貫して物のあわれを書いてきたが、そこにはこの台詞が常に記憶の中から滲み出てきて書かせてくれたものだった。 時に、「関の弥太ッペ」を見ることがある。中村錦之助の名演技がさらに涙を誘うものになっている。 私も若い頃その世界にいたことがあるが、股旅ものをさせたら錦之助にかなう人はいなかった。今でもそれを超えた人はいない。なかでもこの作品は秀逸なものだ。台詞が生きいいる、これはなかなか出来るものではない。感情を如何に表に出さなくて人の心をとらえるか、錦之助だから出来たことだろう。 まず、それを言って、今の文学が意味のない事をつらつら書きすぎていることにいらだちと不満を感じる。 物を書くと言う事はその作品の中に伝えたいと言う気持ちがあってのことだろうが、それがなぜ伝わらなく書いているのか。書き手の未熟なのか、人間の心を知らない故なのか、また、そんな生活をしてこなかったという事なのか、書くことの必然がないという事に尽きる。「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」 長谷川伸はこの台詞を書くために「関の弥太ッペ」と言うやくざの世界の醜さや、義理と人情、対立を書いて物語を作ったと言えよう。 この二行の台詞のために作者はそれを貫通行動にして色々な反貫通行動を絡ませて書いた物だ。 私は、長谷川伸、山本周五郎の作品を好んで読んだ時期がある。西洋の古典物や、日本の純文学にもよくなじんだが、この台詞以上に感動をしたものはない。 日本人のきっても切れない人情が横溢している。また、池波正太郎の作品には江戸時代の人情風俗食生活が巧みに織り込まれていて、日本人の精神と感性、社会の成り立ちがよりよく伺い理解させてくれる。 長谷川伸には、「瞼の母」「一本が刀土俵入り」などの作品の中に名セリフが溢れている。 その言葉を読む人の心を震わせ心の糧にすべきものが多い。 山本周五郎の作品で一番好きなのは「日本婦道記」のなかの「墨丸」である。これは人が人を愛すると言う根源の在り方を書き現わしている。愛すると言う事はその相手の人の幸せを願う事なのだと作者は言ってはばからない。この物語はかなしいほどの美しさを漂わせている。 また、周五郎の書いたものが映画にテレビになって公開されたが、この人の作品ほど公開された作家の作品は見ない。日本人に馴染んだものだからだろう。武家もの、町人もの、歴史ものにも日本人の心情が満ち溢れている物が多い。稀有の作家と言えよう。 こうして見てくると純文学の小難しい表現になにを言おうとしているのか分からなくなる。 大衆、中間、純文学と分け隔たりをしているが、読む人に与えるインパクトは一番低いのが純文学であろう。 かつて持っていた日本人の精神と心得を思い出させてくれけるものが、本当の文学であろう、人間の側面、新しさをいくら書いても、その前に人間の本質を知らなければ何もならない事を言いえているのだ。 先輩たちが書き遺してくれた物を修学し、その上に新しい物を発見して書き現わす、今の人間、これからの人間の姿勢を書き現わすとしても、「この娑婆には、悲しい事、辛い事が沢山ある。だが、忘れるこった、忘れて日が暮れりゃあ、明日になる…」 この台詞以上の物がはたして書ける人が出てくるだろうか…。
2016年08月26日
コメント(0)
-
NHKが今なぜ坂口安吾『堕落論』なのか…。
NHKが今なぜ坂口安吾『堕落論』なのか…。 若い頃「日本文化私観」を読み「堕落論」読んでいる。無頼派らしい考え方ととらえていた。戦後の混乱期には開き直りが必要であることを実感していたがここまでとは考えられなかった。 今まさに戦後の混乱に似た世相であるようにも思えるが、総てを壊し焼き尽くす事は非常に簡単だが、それは人間の心も失う事、安吾はそれが人間だと断言している。 今、この安吾の思考から生まれたものをNHKが取り上げることに何かきな臭い感がする。 ます、「日本文化私観」そばにおいて「堕落論」の粗筋をここに載せみなさんの判断をお聞きしたい…。 「半年のうちに世相は変わった」と始まる。 戦地から帰ってきた兵士たちは闇屋となり、 また、男を戦地に送った女たちは 夫の位牌を事務的に扱うようになった。 そのようになったのは 「人間が変わったのではない。」 「人間は元来そういうものであり、 変わったのは世相の上皮だけのことだ。」 という。 終戦後、わたしたちは、 あらゆる自由を許されたわけだが、 人間はあらゆる自由を許されたときに、 みずからの不可解な限定と その不自由さに気づくものなのである。 人間は、永遠に自由ではあり得ないのである。 なぜなら、人間は日々生きていて、 また、いずれは死なねばならず、 そして、人間は考える生き物だからである。 政治改革は、一日にして行なわれるが、 人間の変化はそう簡単には行かないものである。 戦争がどんなに物凄いものであっても 人間自体がどうにかなるものでもない。 人間の本質は変わることはない。 ただ、人間へ戻ってきただけなのだから。 人間は堕落するものである。 義士も聖女も同じように堕落するものだ。 それを封じることはどうしてもできないし、 また、押さえ込むことによっても、 人を救うことはできないのである。 人間は生き、人間は堕ちる。 そのこと以外には、 人間を救うための便利な近道はないのである。 これは、戦争に負けたから、敗戦したから 堕ちるとうことではない。 人間だから堕ちるのであり、 生きているからこそ、 堕ちるということだけのことなのである。 堕ちる道を堕ちきることで、 自分自身を発見し、救わなければならないのである。 坂口安吾『堕落論』の詳しくはこちら↓ <img src ="http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/?pc=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5451%2f9784758435451.jpg%3f_ex%3d300x300&m=http%3a%2f%2fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2f%400_mall%2fbook%2fcabinet%2f5451%2f9784758435451.jpg%3f_ex%3d80x80" border="0">
2016年08月07日
コメント(0)
-
年寄りの定年をなくし、議員の定年を作れ…。
なぜ老人は消費しないのか?https://www.youtube.com/watch?v=5NceNGqlvns
2016年08月02日
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1