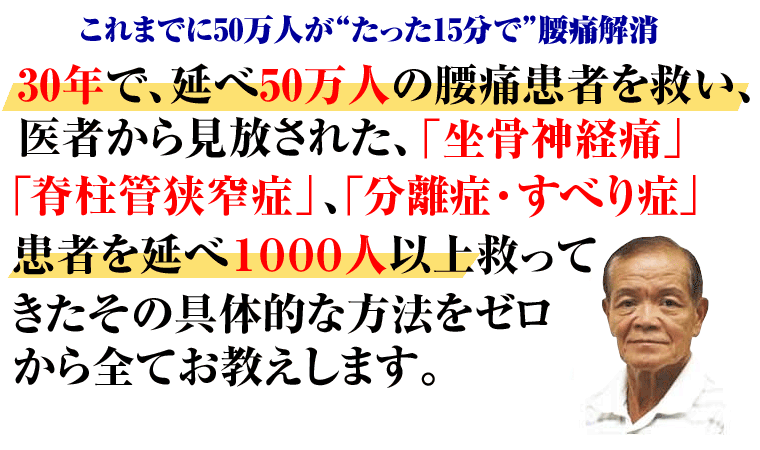看護師など犬に喰わせてしまえ
高度に発達した看護師は魔法と見分けがつかない
どんな人間にも共通していることがある。少なくとも、俺はこれまでの人生で自分と違う人間を見たことはない。年齢や性別はもちろん、肌の色が違ってもそれは同じである。たとえ絶望しても、病に侵されても、決して変わることはない。命の鼓動が続く限り、人間には赤い血が流れ続ける。
その日、俺は駅での作業を終えた後、献血ルームの清掃に向かった。週に数回、俺は二つの現場を掛け持ちしている。朝とは違い、夜の数時間の仕事にはなかなか働き手が集まらない。多くの人にとっては、家族との団欒を楽しむ時間であったり、学校や仕事から帰宅して羽を伸ばす時間である。僅かな賃金の為に、その貴重な時間を投げ出す人は少ないだろう。俺だって本当は帰りたい。遊びにだって行きたいし、相手がいればデートだってしたい。だが、そこに仕事があるならば、誰かがやらなければならない。
献血ルームの清掃は、全てのドナー(血液の提供者)がルームを後にしてから行う。その為、作業の開始時間はまちまちである。この日はたくさんのドナーが来所したようで、なかなか作業を始められなかった。だが、自動ドアの前で今か今かと待ち構えるわけにもいかない。俺は同じフロアの端にある大きな窓から外を眺めて待つことにした。
たくさんのサラリーマンが駅に向かって歩いていた。サラリーマンに未練はないが、もう一度スーツを着て働きたいと思うことはある。ただ、俺は少し自由になり過ぎた。業務に決められた作業工程はあるが、誰に指示を受けるわけでもない。自分で考え、自分のペースで働くことが当たり前になっている。果たして、目の前に上司が座っている机で仕事をすることが出来るだろうか。たぶん、相当に骨が折れることだろう。だから、俺はサラリーマンを尊敬している。馬鹿にしているわけではない。自分には出来ないことが出来る人間に敬意を覚えるのは、至って自然なことである。
物思いに耽っていると、こちらに向かって歩いてくる人影が窓ガラスに映った。振り返ると、献血ルームの受付の職員だった。
「田吉さん、お疲れ様です。どうされました?」
「清掃氏さん、お待たせしてしまい申し訳ありません。今日はもう少し時間がかかりそうで…」
「あっ、いえ…、大丈夫ですよ。気になさらないで下さい」
「今、A型の血液が不足しているんですよ。清掃氏さんは何型ですか?」
「A型ですよ」
「明日でも構いませんので、献血にご協力いただけませんか?」
「俺のような清掃員の血で良ければ、喜んで提供しますよ」
「清掃氏さん…、血液には様々な分類方法があります。ですが、その人の職業や社会的立場で血液の重さは変わりません。だから、そんなことを言っちゃダメです」
「そうですよね…、すみません。明日、仕事が終わったら来ますね」
「本当にありがとうございます。予約を入れておきますので、今日のような待ち時間はありません」
「仕事の待ち時間は気になさらないで下さい。貴重な妄想タイムですから」
「どんなことを妄想されているのですか?」
「まぁ、それは色々と…」
「ははは…。では、明日はどうぞよろしくお願いいたします。職員一同、お待ちしております」
作業を始めたのは、それから一時間が経とうとしていた頃だ。職員も帰宅し、一人で掃除機をかけていると、ロックされた自動ドアの外側に男性が立っていた。忘れ物でもしたのだろうか。俺はドアの隙間から声をかけた。
「どうなさいました?」
「今日はもう終わっちまったのか?」
「受け付けは10時から18時迄ですよ」
「…朝から何も食べてないんだ。飲み物だけでも貰えないか?」
ルームにはドナーに提供するパンやドリンクの無料自販機がある。男性はそれを目当てに来たのだろう。
「私は見ての通り清掃員です。ここの職員ではないので、それは出来ません」
「お兄さん、頼むよ…」
「申し訳ございませんが、部外者は中に入れられません。私の責任問題になってしまいます」
「お兄さん、赤い血は通(かよ)っているか?」
「通っていますよ」
「俺が汚い格好をしているホームレスだから入れられないんだろ?」
一見してホームレスと分かる感じではなかったが、本人がそう言うのだから帰る家はないのだろう。
「いえ…、どなたであっても入れられないんです。その代わりというわけではありませんが、私の飲み物を差し上げます。そちらでお待ち下さい」
俺はリュックサックから自分の飲み物を取り出し、それを手にして職員用の出入り口から供用通路に出た。
「まだ蓋は開けていませんから、安心して飲んで下さい。それと…、これでパンでも買って下さい」
「100円じゃ買えないよ」
「いや、買えますって!」
「…分かったよ。お兄さん、ありがとな」
自称ホームレスの男性は、エレベーターホールに向かってのそのそと歩いていった。とんだ時間のロスである。だが、お客様のお客様であると考えれば、無下には出来ない。俺はルームに戻り、大急ぎで作業を終わらせた。翌朝は5時半起床…、帰宅後は歯を磨いて顔を洗い、パジャマに着替えて布団に直行である。
そして、翌日…。駅での作業を終え、詰所を出ようとすると、後ろから声をかけられた。
「清掃氏さん、お疲れ様でした。これから違う現場に移動ですか?」
「妹子さんもお疲れ様! 今日はもう終わりなんだけど、献血を頼まれてさ…」
「清掃氏さん、最近疲れた顔をしていますよ。献血をして倒れないで下さいね」
「大丈夫だよ。倒れたら、婆さんに迎えに来てもらうよ」
「わっ、私が迎えに行きますよ」
「ははは、ありがとう。妹子さんは献血ってしたことある?」
「なっ、ないです」
「一緒に行く? あっ、いや…、早く帰りたいよね、ごめん」
「行きたいです! 帰りが少し遅くなることを母にメールしておきますね」
「あっ、いや…、無理はしないでね」
「私も勉強で頭が疲れ気味なので、気分転換したいんです」
「献血は気分転換になるのかな…。えっと…、帰りに食事くらいご馳走するよ」
「あっ、ありがとうございます。嬉しいです…」
俺は妹子さんと献血ルームに向かった。着いたのは予約時間の5分前だった。自動ドアをくぐると、受付の女性が笑顔で出迎えてくれた。
「清掃氏さん、今日はお忙しい中ご足労いただきまして、本当にありがとうございます。可愛い彼女さんですね!」
「いっ、いや…、彼女では…」
「彼女さんは何型ですか?」
「わっ、私はA型です」
「献血をされたことはありますか?」
「はっ、初めてです。わっ、私なんかの血でいいんですか?」
俺と同じことを言っているなと思った。どうしてか分からないが、それが嬉しかった。緩んだ頬を締め直そうとしていると、横から大きな声が聞こえた。
「おぉ! 清掃のお兄さんっ!」
少しばかり嫌な予感がした。声が聞こえた方向に顔を向けると、昨夜の男性が手を振っていた。
「昨日はどうも…」
「お兄さんのおかげで美味いパンが買えたよ。ありがとな! 今日は可愛い彼女と一緒に献血かい?」
「いっ、いや…、職場の後輩ですよ」
「お嬢さん、このお兄さんはなかなかの男だぞ。見ず知らずの俺に飲み物とお金をくれたんだ」
「お金って…、百円玉一枚ですよ…」
「金額の問題じゃない。俺はこのお兄さんのおかげで一命を取り留めたんだ」
「そんな大げさな…」
「俺はろくな人間じゃないが、献血くらいは出来る。知らない誰かの命を救えるってカッコイイよな」
「そうですね…。あのっ、失礼なことをお聞きしますが、本当にホームレスなんですか?」
「夏季限定のな!」
「夏季限定??」
「冬はな、住み込みで除雪の仕事をしてるんだ。帰る家がなかったら、凍死しちまうだろ…。そんで夏はな、気が向いた時に日雇いの仕事しながら漫画喫茶暮らしよ」
「なるほど…」
「これでもな、俺は北大(北海道大学)を出てるんだ。もう何の役にも立たないがな…」
「俺も北大ではありませんが、国立大学卒ですよ」
「はっはっは、国立大学卒の清掃員とホームレスか! こりゃ面白い!」
「いや…、面白くないです」
「そんなこと言うなって! 色んな人生があっていいじゃないか! 成功することだけが人間の幸せか? 成功すれば幸せになれるのか? 違うだろ? 幸せの形は決まってないんだよ」
成功することだけが人生の目的ではないし、成功すれば100%の幸せが待っているわけでもない。それは確かだろう。だが、俺や彼がそれを声高に叫んでも、負け犬の遠吠えにしか聞こえないかもしれない。だから、俺は清掃員という職を捨てずに夢を叶えたい。
「おっと…、ついつい熱くなっちまった。お嬢さんと受付の皆さんが固まっちまったな」
「…西島さんも清掃氏さんも国立大学卒なんですね。お二人とも常識にとらわれない素敵な生き方をされていると思いますよ。サラリーマンしか出来ない私には羨ましい限りです。まだまだお話を聞かせていただきたいのですが、お時間にも限りがございますので、そろそろ採血室へお入り下さい」
どんよりとした重たい空気を受付の田吉さんが半ば強引に振り払ってくれた。サラリーマンとして培ってきた危機管理能力のようなものだろう。
「そっ、そうですね。妹子さん…、俺は先に中に入るけど、献血をするかしないかは受付の人の説明を聞いてから決めても大丈夫だよ」
「はっ、はい、そうします」
採血用の椅子に座り、背もたれを倒してテレビを観ていると、妹子さんが隣の席に案内されてきた。季節限定ホームレスの男性は離れた席に座っている。職員から話を聞いた 看護師 さんが配慮してくれたのだろう。
「妹子さん、注射は怖くないの?」
「もうすぐ18歳になるんです。怖いなんて言えませんよ」
「ははは、そうだよね。俺は成分献血だからちょっと時間がかかるけど、妹子さんはすぐに終わると思うよ。終わったらさ、違う場所で待っていてもいいよ。さっきの人に話しかけられたら嫌でしょ…」
「大丈夫ですよ。清掃氏さん、いつも優しいですね。私、いつも清掃氏さんに救われています」
「妹子さんだって…、色んな人を救っていると思うよ。人間はさ、存在しているだけで誰かの力になれることもあるし、無意識に人を救っていることはたくさんあると思うんだ。もちろん、こうやって献血をしたり、意識して誰かを助けたりもするけど、そうとは意識しない行動の中で救いを与えていることもたくさんあるはずだよ。俺も…、妹子さんに救われているからさ」
「清掃氏さん…」
人は常に流れている。体の中を流れる血液のように、人生という海図のない世界を巡り続ける。その航路の中で、救う立場になることがあれば、救われる立場になることもあるだろう。誰も救えない人などいやしない。誰からも救われない人などいやしない。人は誰かを救い、誰かに救われ、生きていく。
長く記憶に残るのは、目に映った光景よりも心に刻んだ情景だろう。 だから、人は心で感じようとする。 だから、想いは心に届けようとする。 俺は心で感じ、心に届けたい。 この気持ちを、この想いを…。
ブログに関するお問合せ、お仕事のご相談は、からお願いいたします。


![看護師国家試験高正答率過去問題集(102?106回試験問題) でた!でた問 [ 東京アカデミー ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3094/9784864553094.jpg?_ex=256x256)