【解説】交際費と福利厚生費の違いは?
交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
一方、福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用をいいます。
また、社内の行事に際して支出される金額などで、次のようなものは福利厚生費となります。
1創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用。
2従業員等(従業員等であった者を含みます。)またはその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用。
例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。
交際費等には、上限があります。上手に使い分けしましょう。
2023年12月09日
2023年04月08日
【必読】誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか?
誤って納付した印紙税は還付されるのでしょうか。
還付されます。
たとえば、次のような事例があります。
当社は機械を製造している会社です。
1. 先日、機械の発注があったので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参しました。
2. ところが、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれ、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡しました。
3. 先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどうなるのでしょうか。
答え:還付されます。
「理由」
印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる作成をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。
請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。
印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、あらかじめ印紙を貼り付けたが、何らかの事情で、相手方に渡すことなく終わることがしばしば生じます。
このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、
結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますので、
その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象になります。
【肝付を受ける方法】
還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。
税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、
過誤納金を還付することになります。
この場合、還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみていただくことが必要です。
(PR)
男性のエステは今最も注目されています。
エルセーヌのメンズエステを体験してみませんか。
¥3,300のトライコースがあります。

還付されます。
たとえば、次のような事例があります。
当社は機械を製造している会社です。
1. 先日、機械の発注があったので請書を作り、1万円の印紙を貼って先方に持参しました。
2. ところが、機械の設計変更をしたいので請書を書き換えてくれといわれ、新たに請書を作り直し別の1万円の印紙を貼って先方に渡しました。
3. 先方に渡すことなく不要となった請書の印紙はどうなるのでしょうか。
答え:還付されます。
「理由」
印紙税は課税文書の作成があった時に納税義務が成立するのですが、ここにいう「作成」とは、課税文書の単なる作成をいうのではなく、その文書をその目的に従って行使することをいいます。
請書は相手方に渡すことを目的として作成される文書ですから、その作成の時とは相手方に渡した時となります。
印紙は課税文書の作成の時までに貼り付けることが原則となっていますから、あらかじめ印紙を貼り付けたが、何らかの事情で、相手方に渡すことなく終わることがしばしば生じます。
このように、あらかじめ文書に印紙を貼り付けておいたが納税義務が成立しないまま終わった場合は、
結果からみれば納税義務がないにもかかわらず印紙税を納付したことになりますので、
その文書に貼り付けた印紙の金額に相当する金額は、過誤納金として還付の対象になります。
【肝付を受ける方法】
還付を受ける方法ですが、まず、印紙税についての過誤納の事実があることについて所轄税務署長の確認を受けなければなりません。
それには、「印紙税過誤納確認申請書」を提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示することが必要です。
「印紙税過誤納確認申請書」の用紙は税務署に用意してあります。したがって、印紙税の過誤納金の還付を受けようとする人は、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑を税務署に持参すればよいようになっています。
税務署長は、提示された文書について印紙税の過誤納の事実を確認した場合には、その文書に貼られている印紙に「過誤納処理済」等と表示した印を押して返戻するほか、
過誤納金を還付することになります。
この場合、還付は現金を直接渡すことはしないで、銀行か郵便局を通じてなされますから、還付金を受け取るまでには若干の日数をみていただくことが必要です。
(PR)
男性のエステは今最も注目されています。
エルセーヌのメンズエステを体験してみませんか。
¥3,300のトライコースがあります。
2023年01月02日
【必読】ゴルフ代は、どこまで経費で落とすことができるのでしょう:しばらく取引のない相手とのゴルフ代は、経費で落とせるの?
取引先とゴルフに行きましたが、この取引先とは、しばらく取引をしていませんでした。
この場合でも、経費で落とすことはできるでしょうか。
答えは、yesです。
接待交際費で経費として計上することができます。
接待交際費は、
・直接取引をしている相手だけに適用されるものではなく、
・間接的に取引をしているところや、
・将来取引があるかもしれない相手先であっても、
経費として計上することができるのです。
したがって、しばらく取引がない相手先であっても、
今後取引があるかもしれませんので、
事業の接待であることは間違いありません。
接待交際費として落とすことができるのです。
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
この場合でも、経費で落とすことはできるでしょうか。
答えは、yesです。
接待交際費で経費として計上することができます。
接待交際費は、
・直接取引をしている相手だけに適用されるものではなく、
・間接的に取引をしているところや、
・将来取引があるかもしれない相手先であっても、
経費として計上することができるのです。
したがって、しばらく取引がない相手先であっても、
今後取引があるかもしれませんので、
事業の接待であることは間違いありません。
接待交際費として落とすことができるのです。
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
2022年12月22日
【必読】長年タバコを吸っているあなたへ! 禁煙治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
長年タバコを吸っていたあなたは、喫煙場所を探すのにとても苦労したり、タバコ税の増税が議論されていることもあって、禁煙したいと思っていませんか?
または、禁煙しようと毎回頑張って、失敗を繰り返していませんか?
そのような場合、病院で、禁煙治療を受けるしかありません。
しかし、禁煙治療は、けっこうお金がかかります。
数万円から数十万円かかるケースもあるようです。
それでは、この禁煙治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
こたえは、yesです。
禁煙治療費も、医師による診断とみなされ、医療費控除の対象となるのです。
ですから、一旦、自腹で払っておいて、所得税の確定申告で、医療費控除の申請をすればいいのです。
会社経営者や個人事業主やサラリーマンのあなたはも、医療費控除をご活用ください。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
禁煙にはこちらのフレーバーミストを
カートリッジ内のリキッドを蒸気化し、霧状の煙を吸引しフレーバー(香り)を楽しむフレーバーミストです。

または、禁煙しようと毎回頑張って、失敗を繰り返していませんか?
そのような場合、病院で、禁煙治療を受けるしかありません。
しかし、禁煙治療は、けっこうお金がかかります。
数万円から数十万円かかるケースもあるようです。
それでは、この禁煙治療費は、医療費控除の対象になるのでしょうか。
こたえは、yesです。
禁煙治療費も、医師による診断とみなされ、医療費控除の対象となるのです。
ですから、一旦、自腹で払っておいて、所得税の確定申告で、医療費控除の申請をすればいいのです。
会社経営者や個人事業主やサラリーマンのあなたはも、医療費控除をご活用ください。
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
禁煙にはこちらのフレーバーミストを
カートリッジ内のリキッドを蒸気化し、霧状の煙を吸引しフレーバー(香り)を楽しむフレーバーミストです。
2022年12月21日
【必読】従業員を飲みに連れて行った場合でも、飲み代を経費で落とせるのでしょうか?
会社でも、個人事業主でも、従業員を飲みに連れて行くことは多いと思います。
では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。
答えは、イエスです。
それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。
それは、接待交際費です。
接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、
従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。
この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。
ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。
それは、従業員の慰労の範囲を超えており、
社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。
平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。
【書籍紹介】
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
では、この飲み代は、経費で落とすことができるのでしょうか。
答えは、イエスです。
それでは、経費の中でも、どういう費用で落とせるのでしょうか。
それは、接待交際費です。
接待交際費と聞くと、お客さんが相手だけだと思いがちですが、
従業員を飲みに連れて行くことも、慰労という意味で、会社からは接待交際になるという解釈です。
この場合は、一部の社員だけ連れて行ってもOKです。
ただし、二次会でクラブまでいく時にも、それが使えるかというと、やめておいた方が無難です。
それは、従業員の慰労の範囲を超えており、
社長が自分の楽しみのために行っているのではないか、ということになるからです。
平等に、従業員全員が相手であれば、福利厚生費で落とすことができます。
【書籍紹介】
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
2022年12月03日
【必読】副収入が20万円を超すあなたへ:帳簿などをきちんとつけないと、所得税が高くなりますよ!
副業などで得た所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。
それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。
それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。
雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。
国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。
この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。
ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。
つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。
「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。
今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。
つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。
そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。
帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。
これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。
どの税理士に依頼すればわからない方は
税理士紹介ネットワーク
税理士紹介ネットワーク
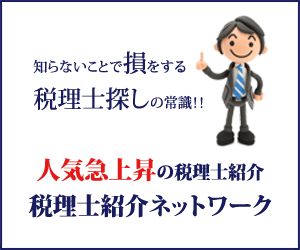
それを事業所得にできるか、事業所得とできずに雑所得となるかは、大きな問題です。
それは、事業所得は給与所得等と損益を通算(プラスマイナス)できるのに対して、雑所得はできないからです。
雑所得でも損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の所得の金額から控除することはできないのです。
国税庁は、所得税法基本通達の改正案で、「年収300万円以下の副業は原則として雑所得とする」という案を出して、巷は騒然となりました。
この案は意見公募により修正されて、「収入金額が300万円を超えない」という文言が消えました。
ただし、「帳簿保存がなければ雑所得」とされました。
つまり、事業所得のわかりやすい判定基準として「帳簿保存」が示されたのです。
「帳簿さえあれば基本的に事業所得」となるのです。
今回の通達改正の背景には「赤字の副業を事業所得で申告して給与所得と損益通算をし、還付を狙う」スキームを封じるという意図があると言われています。
つまり、節税目的の副業は雑所得にしてしまおうというわけです。
そうならないためには、帳簿をしっかりとつけて、副業収入は事業所得としないといけないのです。
帳簿をきちんとつけるためには、税理士を活用することが、最も早道です。
これまで、税理士は関係ないと思っていた個人事業主のあなたも、税理士を活用して、税金対策をしてみましょう。
どの税理士に依頼すればわからない方は
税理士紹介ネットワーク
税理士紹介ネットワーク
2022年11月21日
【必読】売上高が1000万円以下のあなたへ:お急ぎください! 令和5年3月末までに決めなければいけません
インボイス制度が、令和5年10月1日から始まります。
消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。
そもそもインボイスとは、何でしょう。
インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。
具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。
消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。
インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。
それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。
これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。
そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。
免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。
ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。
以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。
課税事業者になるには、原則として、令和5年3月31日までに、税務署に登録申請を行う必要があります。
課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。
そういう方は、税務の専門家である税理士に依頼しましょう。プロの仕事は、プロに任せるのが、最も時間の節約になります。その時間を、本業に費やしましょう。
税理士紹介ネットワーク
消費税の免税事業者は、令和5年3月31日までに、課税事業者となるために税務署に届け出るか、そのまま免税事業者を続けるかを決めなければなりません。
そもそもインボイスとは、何でしょう。
インボイスとは、適格請求書と言われるもので、売り手が買い手に対して発行する請求書で、そこに正確な適用税率と税率毎に区分した消費税額を記載したものです。
具体的には、8%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるか、また、10%の消費税の請求額はいくらで、消費税額はいくらであるかを記載した請求書のことです。
消費税は、売上げに含まれる消費税額から、仕入れ等に含まれる消費税額を差し引いて計算します。
インボイス制度が導入されるまでは、消費税込みの金額が請求書等に記載されていれば、買手側は「支払ったであろう計算上の消費税」を差し引いて国に納付計算することができました。
それが、インボイス制度の導入によって、インボイス(適格請求書)に記載された消費税額のみを差し引けることになるのです。
これまでは、売り手が免税事業者で消費税を納めていなくても、買い手は計算上の消費税を差し引ける仕組みでありましたが、それができなくなります。
そうなると、これまで買い手であったところは、免税事業者からの仕入れを止めて、消費税の課税事業者からの仕入れに切り替える可能性が大きくなります。
免税事業者にとっては、納入先を失うことになるかもしれない一大事なのです。
ただ、売り先が、消費者や免税事業者である場合には、免税事業者のままでかまいません。
以上のことから、消費税の課税事業者として登録し、消費税を納める形にするのか、今まで通り免税事業者のままで行くのかを、決めなければなりません。
課税事業者になるには、原則として、令和5年3月31日までに、税務署に登録申請を行う必要があります。
課税事業者になるのはいいけれども、税務署への届出の仕方がわからない方や、インボイスの作成方法(適格請求書)がわからない方、また、消費税を納入する必要が出てきますがその書類の作成方法がわからない方もいらっしゃると思います。
そういう方は、税務の専門家である税理士に依頼しましょう。プロの仕事は、プロに任せるのが、最も時間の節約になります。その時間を、本業に費やしましょう。
税理士紹介ネットワーク
2022年11月13日
【必読】衣を住の費用を経費で落としたいあなたへ:どのようにしたらできるのか?
衣食住の費用を、事業経費で落とすことはできるでしょうか。
一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。
実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。
高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。
それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。
では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。
それには、2つのルートがあります。
1. 福利厚生費で落とす。
会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。
この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。
役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。
ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。
2. 事業関連費で落とす。
これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。
たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。
また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。
ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。
以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。
ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。
【税理士紹介ネットワーク】
税理士紹介ネットワーク
【書籍紹介】
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
一定の手続きを踏めば、落とすことができるのです。
実際、収入はそれほど高くないのに、いい生活をしている経営者はたくさんいます。
高級マンションに住み、たびたび高級レストランで食事をして、いい服を着ている、しかし税金は非常に少ないという人はいるのです。
それは、衣食住の費用のできるだけ多くを、事業の経費で落としているのでしょう。
では、どうやって事業経費として落とすのでしょうか。
それには、2つのルートがあります。
1. 福利厚生費で落とす。
会社の場合は、社員の福利厚生に関する費用は支出してもいいことになっています。
この福利厚生費は、とても広い範囲で認められています。
役員を含む社員の住居に関するもの、食事に関するもの、健康に関するもの、レジャーに関するものなども、社員全員を対象としているなど、一定の条件をクリアしていれば、福利厚生費で落とすことができます。
ただ、この方御法は、個人事業主は使えません。税務署は、個人事業主本人やその家族への福利厚生費を認めていないからです。
2. 事業関連費で落とす。
これは、衣食住の費用を、事業に関連付けて、事業経費として支出する方法です。
たとえば、食事代を、会議費や交際費などで負担するのです。ただし、しっかりとした相手先がいないといけません。
また、自宅の家賃については、自営業者やフリーランスの人などが、事業の経費として支出することができます。
ただし、全額というわけではなくて、プライベートな部分と仕事の部分で、案分計算しないといけません。
以上の方法によっては、事業の関わる費用は、事業経費として落とせます。
ただし、決して脱税とはならないようにしましょう。
【税理士紹介ネットワーク】
税理士紹介ネットワーク
【書籍紹介】
スバリ回答!
どんな領収書でも経費で落とす方法
大村大次郎(元国税調査官)
2022年11月05日
【必読】従業員のレジャー費は、どこまで会社の経費で落とせるのでしょうか?
従業員のレジャーに関する費用で、会社の経費でどこまで落とせるのかで、お悩みではありませんか。
レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。
福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。
たとえば、
○コンサートやスポーツ観戦のチケット
○スポーツジムの会費
○従業員の家族が遊園地に行った費用
○従業員全員を対象にした慰労会
○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。
これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。
それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。
福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。
(1)社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。
世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。
(2)一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。
これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。
スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。
(3)会社が準備すること。
社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。
この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。
なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。
従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は福利厚生費として認められますが、自分自身や家族のために支出したものは、認められないのです。
従って、福利厚生費については、個人事業でやるよりも、会社組織にした方が得だということになります。
【参考】国税庁のタックスアンサーによると
従業員のレクリエーション旅行については、次のようになっています。
その旅行によって従業員に供与する額が、
・少額の現物給与は強いて課税しないという趣旨を逸脱しないものであると認められ、
・その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
従業員のレジャー費は、できるだけ会社の経費で落としましょう。
税理士紹介ネットワーク
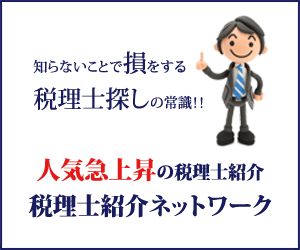
レジャー費を会社の経費で落とすには、最もオーソドックスな方法は、福利厚生費を使うことです。
福利厚生費は、会社の従業員の福利厚生にかける費用ですが、その範囲は非常に広いのです。
たとえば、
○コンサートやスポーツ観戦のチケット
○スポーツジムの会費
○従業員の家族が遊園地に行った費用
○従業員全員を対象にした慰労会
○なかには、会社内にバーをつくって、そこで自由に飲み食いができるようにしている会社もあります。
これらの福利厚生費について、税務署が明確にOKを出しているわけではありません。
それぞれの会社が、次の考え方をもとに、独自に判断しているのです。
福利厚生の基本的な考え方は、以下の3つです。
(1)社会通念上、福利厚生として妥当なものであること。
世間の価値観からして、そこからかけ離れていないならば、大丈夫ということです。
(2)一部の社員のみが享受するものではなく、社員全員が享受できること。
これは、誰もが同じだけ使わないといけないというものではありません。
スポーツジムなど、誰もが行ける状況さえ、作っておけばいいということです。
(3)会社が準備すること。
社員が自分で何かを購入したり、サービスを受けたりして、会社はお金を出すだけではダメです。
この3つをクリアしていれば、だいたい福利厚生費として認められるというわけです。
なお、個人事業主自身や事業主の家族への福利厚生は認められていません。
従業員のいる事業者が、従業員のためにレジャー費を出した場合には、従業員の費用は福利厚生費として認められますが、自分自身や家族のために支出したものは、認められないのです。
従って、福利厚生費については、個人事業でやるよりも、会社組織にした方が得だということになります。
【参考】国税庁のタックスアンサーによると
従業員のレクリエーション旅行については、次のようになっています。
その旅行によって従業員に供与する額が、
・少額の現物給与は強いて課税しないという趣旨を逸脱しないものであると認められ、
・その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
(1)旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
(2)旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50パーセント以上が参加することが必要です。
従業員のレジャー費は、できるだけ会社の経費で落としましょう。
税理士紹介ネットワーク


