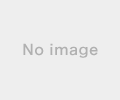2018年09月30日
9月30日は何に陽(ひ)が当たったか?
1848年2月に勃発したフランスの 二月革命でウィーン体制は崩壊に追いやられ、諸国民は自由主義社会を切望していきました("諸国民の春")。この間プロイセンでは、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世(位1840-61)が即位しましたが、王は"王座のロマン主義者"の異名を持つほどの完全な空想的ロマンティストで、自由主義や立憲主義を嫌い、ウィーン体制の存続を主張、反動政治を展開していました。しかし二月革命の影響がプロイセンにも波及し、1848年3月18日、首都ベルリンでブルジョワや労働者による暴動が発生したのです(ベルリン暴動)。
これにより、フリードリヒ・ヴィルヘルム4世は政務を退き(22日)、ゴットフリート・カンプハウゼン(1803-90)が首相に就任して自由派政府がおこりました( ドイツ三月革命)。その前1847年に、ユンカー(領主貴族)出身だったビスマルクがプロイセン連合州議会議員となって政界に登場し、反革命派として王政を護り、国王から大いなる信任を得ました。
フランクフルトでは1848年5月、自由主義者を中心に「統一と自由」を求めて、国民会議が開かれました。歴史的に有名な、 フランクフルト国民議会の開催です。しかし大学教授や学者も参加するため論戦が展開し、議会が長期化しました。フランス二月革命後に起こった暴動(六月暴動)の鎮圧などに悩み、8月以降、この議会は反動化していきました。11月には制憲議会も弾圧され、ドイツ三月革命は失敗となりました。
このフランクフルト国民議会では、新たな紛糾が発生しました。オーストリアを除外し、プロイセン国王を統一国家の王とする 小ドイツ主義と、オーストリアのハプスブルク家を王とし、オーストリアのドイツ人居住地域並びにベーメン(ボヘミア)を含めた、以前の神聖ローマ帝国の全領域を統合する大ドイツを建設しようとする 大ドイツ主義との対立でした。当然のことながら、内容から大ドイツ主義には保守派が募ったが、一方の小ドイツ主義派は自由主義的でプロテスタント色が強く、統一言語をドイツ語としていました。大ドイツ主義にはハプスブルク家領などのスラヴ人やハンガリー人も当然含まれる、複合民族国家ということになります。
プロイセンでは1848年12月に国民基本法、翌1849年3月にはドイツ国憲法を制定、さらに長期に渡った議会での論議の結果、 小ドイツ主義が採択され、プロイセン国王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世にドイツ皇帝として就任要請しました。しかし、基本的には自由主義・立憲主義を嫌っていたため、自由主義者によって開催された会議のもとで、帝冠はうけられないとしてドイツ皇帝としての戴冠を拒否したのです。1861年にフリードリヒ・ヴィルヘルム4世は晩年、病身のためたびたび発狂を繰り返し、1858年から弟ヴィルヘルム1世(1797-1888)がプロイセンで摂政として政務を代行していました。
ヴィルヘルム1世は陸軍元帥であり、典型的な軍人気質の政治家でした。ドイツ三月革命では、ベルリン暴動の弾圧に一役買ったものの、国民には人気がなく、ロンドンへ亡命していた時期もありました。1861年に兄王フリードリヒ・ヴィルヘルム4世が没し、正式にプロイセン国王 ヴィルヘルム1世として即位(位1861-88)、名目上は自由主義的改革を宣言して(" 新時代")、参謀総長 モルトケ(大モルトケ。1800-91。任1858-88)や陸相ローン(1803-79。任1859-73)らと軍政改革を断行、軍備強化を推進しました。
ところが、議会では軍拡予算をめぐって紛糾が続発したのです。このため翌 1862年、ヴィルヘルム1世は ビスマルクを首相兼外相に就任させたのです。ビスマルクはこれまで、フランクフルト国民議会のプロイセン代表を務め(任1851-59)、その後駐ロシア大使(任1859)や駐フランス大使(任1862)を果たしてきた敏腕政治家でした。この議会の紛糾に対しても、陽の当たった 1862年9月30日の下院予算委員会で、歴史的に残る有名な言葉を投げかけたのです。
「プロイセンの国境は、健全な国家の国境にふさわしいものではない。言論や多数決は1848-49年の欠陥(→三月革命のこと)であった。現下の問題はそうした言論や演説、多数決によって解決されるのではない。 鉄(→武器)と 血(→兵士)によって解決されるのだ。」
と議会演説をおこない、"鉄"と"血"、つまり 鉄血政策の必要性を主張し、議会の反対を押し切って予算案を議決させたのです。このため、彼は" 鉄血宰相"と呼ばれるようになります。こうしてヴィルヘルム1世とビスマルク首相による武力によるドイツの統一政策が始まったのです。軍隊組織の再編では、モルトケ参謀総長による参謀本部制度をもうけました。軍隊のことだけを考え、政治分野には一切野心を持たないモルトケ自身は"偉大な沈黙者"と呼ばれ、後に甥のモルトケ(小モルトケ。1848-1916)も参謀総長として活躍することになります(任1906-14)。
軍拡によってプロイセン国内の産業も発展した。軍需産業界では、 クルップ(創設者フリードリヒ・クルップ。1787-1826。息子で2代目社長アルフレートの時に鉄鋼独占企業となる。1812-71)などの代表的な鉄鋼工場が大躍進しました。またイギリスの ヘンリー・ベッセマー(1813-98)による転炉法(ベッセマー製法)によって良質の鉄鋼の大量生産を可能にし、後に"クルップ砲"が完成、"死の商人"といわれるようになります。
その後のプロイセンでは、宰相ビスマルクの鉄血政策と巧みな外交戦略が実を結び、1871年1月の ドイツ帝国誕生へと導くのでした。

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |
2018年09月29日
9月29日は何に陽(ひ)が当たったか?
当時ドイツは アドルフ・ヒトラー(1889〜1945)の率いる ナチスの支配でした。ドイツは1933年の国際連盟脱退以降、周辺の地域を占領して国力を拡大させていき、1936年に ベニート・ムッソリーニ(1925-43)率いるイタリアと ベルリン・ローマ枢軸を形成して強勢化につとめました。一方この勢力に対して、イギリスとフランスは戦火の拡大を恐れ不干渉政策を通していました。ドイツは英仏不干渉を先読みして1938年3月にはドイツ人居住区の拡大を目的に オーストリアを併合しました。
オーストリア併合後、ナチス・ドイツはドイツ人が多く居住する、ドイツ側国境地帯 ズデーテン地方の割譲を、これらを領有する チェコスロヴァキアに要求しました。すでにチェコスロヴァキアはフランスやソ連と相互援助条約を結んでおり、要求をかたくなに拒否しました。ヒトラーは英仏の不干渉を期待して戦争で脅しをかけ始めました。これにおいてもイギリス・フランスは戦火拡大を避けるために不干渉に乗り出そうとしますが、チェコスロヴァキア大統領 エドヴァルド・ベネシュ(任1935-38,46-48)は英仏不干渉に反対しました。このため、イギリス・フランスは観念してイタリアのムッソリーニの仲介によって、 1938年9月29日、ソ連とチェコスロヴァキアを除いて、イギリス首相 ネヴィル・チェンバレン(任1937-40)、フランス首相 エドゥアール・ダラディエ(任1933,34,38-40)、ドイツのヒトラーそしてイタリアのムッソリーニの4者4国の間で ミュンヘン会談が開催されることになりました。
この会談でドイツはズデーテン地方を最後に、これ以上の領土は要求しない約束を取り決め、これを交換条件として、ズデーテン地方獲得を認めました( ミュンヘン協定)。チェコスロヴァキアは英仏のここまで来た対ドイツの 宥和政策( アピーズメント・ポリシー)に呆れ果てて、チェコスロヴァキア大統領のベネシュは大統領を辞任、国外亡命することになりました。会談に呼ばれなかったソ連もイギリスとフランスに不信感を募らせる結果となってしまいました。
この宥和政策は、平和主義イギリスにとっては、ミュンヘン協定によって世界大戦を防げたと大喜びしたわけで、これまで行ってきた不干渉政策は間違いなかったと主張しました。しかし、宥和政策は思わぬ結果をもたらしました。1939年3月ドイツはすぐさまミュンヘン協定を無視して チェコスロヴァキアを解体し、チェコ内のスラヴ系民族が居住するベーメン(ボヘミア)・メーレン(モラヴィア)両地方を併合、またスロヴァキア地方を独立させた後すぐにドイツ軍が制圧してこれをドイツの保護国にしたのです。これによってチェコスロヴァキア共和国は崩壊しました。これによって、併合の今後の矛先は、ドイツと完全な隣国となったポーランドに向けられることは明らかでした。
ミュンヘン会談後のドイツの行動に対して、イギリス・フランスは遂に宥和政策の道を捨てることに決心し、ポーランドの安全保障に気持ちを集中します。1939年4月イギリスはポーランドと安全保障を約束しました。ドイツは当然ポーランド進出を計画し、ポーランドに対してまず、ヴェルサイユ条約(1919)によって国際連盟が管理する自由都市となったポーランド唯一の海港ダンチヒ市の割譲、そして、同じくヴェルサイユ条約によってポーランド領となったドイツ人の多いポーランド回廊の割譲を要求しました。要求を断れば軍事行動に出るとヒトラーに脅されたポーランドは当然イギリス・フランスの援助に期待しました。しかしこの時のイギリスとフランスは、チェコスロヴァキア解体と同様、早急の妥結は見出されないままでいました。それよりもイギリスとフランスは、ドイツがポーランドを割譲した後は、ポーランドの東隣国ソ連と、防共・反共の立場から戦争するだろうと固く信じていたのです。一方のヒトラーも、ポーランド要求に際して、ミュンヘン会談に続く首脳会談を期待したと言われています。
このような情勢の中で、 ヨシフ・スターリン(1879-1953)の率いるソ連では、ドイツのポーランド要求に対するイギリス・フランスの消極的な態勢をみて、イギリス・フランスがドイツの反ソ反共に協力するのではないかと錯覚するようになりました。また、ドイツのヒトラーも、ポーランド要求に対する不利を避けるには、共産圏ながらもポーランドの東隣国ソ連に接近した方が得だと考えました。ただ、ポーランド割譲した後は、遅かれ早かれソ連と戦争になるだろう、一方でイギリスやフランスはいつものように戦争を避けるため、不干渉で貫くだろうとヒトラーは読んで、ここはひとまずソ連と握手しようと、1939年8月23日、ドイツとソ連間に 独ソ不可侵条約を締結するという想定外の行動に出たのです。ファシズムと共産勢力が手を結んだことに、独ソ戦を期待したイギリスとフランスは驚き、一方で防共協定を結び、ソ連と戦う姿勢だったイタリア・日本・スペイン、そして西ヨーロッパ各国の共産主義者や共産党組織も愕然とし、動揺を隠せませんでした。
1939年9月1日、ドイツはソ連との間に挟まれた ポーランド侵攻を決行しましたが、9月3日、ヒトラーが参戦しないと踏んだイギリス・フランスがドイツに対して宣戦し、列強を巻き込む第二次世界大戦が勃発してしまいました。形骸と化したミュンヘン会談の結末は、歴史上稀に見る大戦争を迎えることになるのでした。

|
|---|
| ミュンヘン会談への道:ヒトラー対チェンバレン 外交対決30日の記録 (MINERVA西洋史ライブラリー) 新品価格 |
中古価格
¥9,899 から
(2018/8/25 20:30時点)
ヒトラーとミュンヘン協定 (1979年) (教育社歴史新書—西洋史〈A4〉)
中古価格
¥849 から
(2018/8/25 20:31時点)
2018年09月28日
9月28日は何に陽(ひ)が当たったか?
エジプトは当時、 プトレマイオス朝(B.C.306-B.C.30)が支配していました。その王プトレマイオス11世(位B.C.80)が後継者をつくらずに暗殺されたため直系は途絶えたましたが、従兄弟の プトレマイオス12世(位B.C.80-B.C.58,B.C.55-B.C.51)が即位し、王朝を維持しました。このプトレマイオス12世は暗愚な王でしたが、ローマのポンペイウスの支援もあって没するまで政権を維持し、当時18歳(?)だった王の娘と、その弟で当時7歳の息子を結婚させて、共同統治者としてファラオに就かせることを遺言に、B.C.51年没しました。その娘が クレオパトラ7世(B.C.70.12?/B.C.69.1?-B.C.30.8.12)で、その美貌で多くの人を魅了し、"絶世の美女"と呼ばれた、世に言うプトレマイオス朝女王 クレオパトラです(位B.C.51-B.C.30)。クレオパトラの弟であり夫である プトレマイオス13世(B.C.63-B.C.47。位B.C.51-B.C.47)は幼かったので、後見人がたてられていました。
紀元前60年に始まる第一次三頭政治(B.C.60-B.C.53)では、ポンペイウス、 ガイウス・ユリウス・カエサル(B.C.100-B.C.44)、 マルクス・リキニウス・クラッスス(B.C.114/115-B.C.53)によって構成された国政体制で、ポンペイウスはヒスパニア地方(イベリア半島)、クラッススはシリア地方、そしてカエサルは当時では未開だったガリア地方(現在のフランス、ベルギー一帯)のそれぞれの軍令権を得て統治に当たりましたが、紀元前53年のクラッスス戦死によって崩壊し、抑えられていた元老院がポンペイウスに取り付いてカエサル側と対立しました。ポンペイウスとカエサルの敵対はギリシア、テッサリア地方のファルサルスでの戦いに発展していき、ポンペイウスは劣勢を強いられます。そして、ポンペイウスは過去の軍人としてのキャリアの中で、この ファルサルスの戦いで初めての敗北を経験するのです。ポンペイウスは縁のあるプトレマイオス家のエジプトに逃げ込むことを決意しました。
そのプトレマイオス朝のエジプトでは、父プトレマイオス12世没後に即位した姉クレオパトラと弟プトレマイオス13世でしたが、共同統治といえども実質は弟は7歳、姉18歳の国家統治であるが故、姉がほぼ単独で統治する形態でした。このため弟プトレマイオス13世の側近は姉の廃位と追放を求めて、エジプトで内戦が勃発しました。
クレオパトラがは父と同様、ポンペイウスを支持していました。ファルサルスからガレー船に乗ってエジプト領内に入ろうとするポンペイウスに対し、クレオパトラ側は喜んで出迎えることになりました。しかし弟プトレマイオス13世は一時的に姉クレオパトラを幽閉して、首都アレクサンドリアを占領しました。反クレオパトラの姿勢から、プトレマイオス13世側はエジプトに逃げ込んできたポンペイウスを暗殺することを計画しました。紀元前48年9月28日、ガレー船から首都アレクサンドリアに降り立ったポンペイウス一行は、直後に反クレオパトラ派の軍人達に奇襲を受け、暗殺されてしまいました。かつてファラオ(エジプトの王号)を助けたエジプトで余生を送るはずであったポンペイウスは、その夢も一瞬で崩れ去り、最期を遂げたのでした。

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
| 週刊 古代文明ビジュアルファイル no,64ポンペイウス英雄の陰に消えた英雄 中古価格 |
2018年09月27日
9月27日は何に陽(ひ)が当たったか?
第10代オスマン皇帝に即位したのは、"大帝"、"壮麗"の帝"、そして"立法帝"など、偉大なる名を世に轟かせ帝国の黄金期を現出した スレイマン1世(帝位1520-66)です。即位時彼は26歳であり、その美貌で秀麗な姿は過去の皇帝とは引けを取らないほどでありました。
オスマン帝国では、"クズル=エルマ"の獲得をめざし、達成されるまで聖戦を行うとされました。この"クズル=エルマ"とは"赤いリンゴ"を意味し、それはヨーロッパをさすものと言われ、スレイマン1世もその"赤いリンゴ"の征服を目指したのでした。
スレイマン1世は1521年、25万の兵力で ハンガリー王国(1000?-1918,1920-46)からベオグラードを獲得し、ヨーロッパ遠征の滑り出しに成功しました。"ヨーロッパへの入り口"であるベオグラードを手中に収めたスレイマン1世率いる軍は、1526年、北進してハンガリーへ侵攻を開始しました。当時18歳で親征したハンガリー王ラヨシュ2世(位1516-26)は、援軍を待たずして開戦に踏み切りましたが、オスマン軍の誘導戦術と強力な大砲に倒れていき、ハンガリー軍は潰滅しました。この1526年に行われた戦争は モハーチの戦いといいます。
モハーチの戦いに敗れたハンガリー王国は、オスマン帝国によって、領土の大部分を占領されました。しかしオスマン帝国にとって、この戦における最大の誤算はラヨシュ2世を戦死させたことでありました。ラヨシュ2世が亡くなったことで、次期ハンガリー王の後継者が選定されることになり、ラヨシュの妃マリア(1505-1558)の血筋から選ばれることになったのです。
マリアは オーストリア大公国(1457-1804)を拠点とする ハプスブルク家のブルゴーニュ公フィリップ4世(フィリップ美公。公位1482-1506)とイベリア半島の カスティリャ王国(1035-1715。スペインの前身)の女王 ファナ(1479-1555)の娘で、兄たちには神聖ローマ帝国(962-1806)皇帝 カール5世(帝位1519-1566。 スペイン王カルロス1世。王位1516-56)と、その弟でオーストリア大公、のち次の神聖ローマ皇帝となる フェルディナント(大公位1521-64。帝位1556-64)がいました。フェルディナントはラヨシュ2世の姉と結婚していたため、次期ハンガリー王として推戴された場合、政略結婚で領土を拡大していったハプスブルク家が、国家規模に発展するいわゆるハプスブルク君主国(ハプスブルク帝国。1526-1806)の形成を意味したのです。
結果、フェルディナントはハンガリー王 フェルディナーンド1世(位1526-64)として即位しました(同時にベーメン王にも即位。位1526-64)。ハプスブルク家はハンガリーとベーメンを領有した大家としてヨーロッパ世界に君臨することになります。つまり、 ラヨシュ2世の死は、ハプスブルク家を台頭させる要因にもなったのです。
とは言っても、ハンガリー王国を支配したのは、モハーチの戦いに戦勝したオスマン帝国です。スレイマン1世はハンガリーにオスマン軍を駐屯させました。ハンガリーの貴族達は、神聖ローマ皇帝の権力で議会を招集し、ハンガリー王位を継承したハプスブルク家の介入に異議を唱えました。オスマン皇帝スレイマン1世は、"クズル=エルマ(赤いリンゴ)"の獲得に躓きを許さない立場で、敵国であるローマ帝国打倒に執念を燃やし、反ハプスブルクを掲げるハンガリーの貴族達を支持し、ハプスブルク家のフェルディナントと真っ向から対立し、ついに神聖ローマ帝国に侵攻することになりました。これが、陽の当たった 1529年9月27日に始まる、世に言う ウィーン包囲です( 第一次ウィーン包囲。1529.9-29.10)。
オスマン帝国軍の兵力は12万で、イェニチェリ軍団、常備騎兵団、地方騎兵団、砲兵団で構成、300門の大砲を引っさげて、ハプスブルク家の拠点であるオーストリア大公国の首都ウィーンに侵攻しました。ウィーンを防衛するオーストリアの兵力は、スペインやドイツ領邦からの支援があったものの、オスマン軍に遠く及びませんでした(約1〜2万数千。最大でも約5万数千。大砲もおよそ70門)。
当時神聖ローマ帝国はフランスと イタリア戦争(1494-1559)で交戦中でした。特に1525年のパヴィア(イタリア北西部。現ロンバルディア州)での戦闘では、カール5世が軍を指揮したフランス国王フランソワ1世(王位1515-47)を一時的に捕虜にし、その後フランスがローマ教皇やミラノ、フィレンツェといったイタリア都市と同盟を結んで強化をはかるも、カール5世の軍勢に敗れました。イタリア戦争ではドイツ(神聖ローマ帝国)が優勢でありました。
その一方ドイツ国内では新教ルター派による 宗教改革(1517-1555)で揺れ動いていました。モハーチ戦勃発直前、神聖ローマ皇帝カール5世はオスマン帝国軍のヨーロッパ進出に備え、第1回シュパイエル帝国議会(1526.8)を召集し、ルター派を容認して国内安定をはかりますが、ルター派諸侯の台頭を招いてしまいました。このため、オスマン帝国軍のウィーン入城前の4月に第2回シュパイエル帝国議会(1529.4)を開催、カトリック諸侯を擁護してルター派再禁止を決議しました。
こうしたドイツの状況を捉えたフランスのフランソワ1世は、敵対するカール5世を倒すため、カール5世と同じカトリック教徒でありながら、ドイツでは再び異端となったルター派を支援して国内をより混乱させようとし、しかもウィーンを包囲するオスマン帝国に対して、異教国ながら友好な関係を結んだのです。フランスにしてみれば、オスマン帝国との関係が良好であれば、ドイツを挟撃可能な状態であり、カール5世を牽制するには充分の材料でした。
ウィーンを包囲したスレイマン1世はただちに攻撃を始めましたが、オーストリア軍は兵力の差から攻撃面よりも防衛面に重視し、堡塁や土塁で防衛線を固めてオスマン軍の砲撃から死守しました。このため、攻城が予想外に手間取り、しかも悪天候で輸送困難な行路でしたので、すべての大砲が揃わないアクシデントもありました。しかも、包囲をはじめた時期は10月で、冬の到来の早いウィーンでの攻防戦となると、防寒対策に予断を許したオスマン帝国軍はいくら兵力が多くても長くは続かなかったのです。このためスレイマン1世は10月半ば過ぎにウィーンからの全軍撤退をはじめました。
オスマン帝国はウィーン包囲でその勢力をヨーロッパ諸国に見せつけたものの、ウィーンを陥落させることはできませんでした。ハプスブルク家の外敵フランスから支援されても、またドイツ国内で宗教改革に揺れている状態でも、自軍の兵力が桁外れに備わっていても、"赤いリンゴ"を射止めることはできなかったのです。一方、西ヨーロッパ世界側にとっては、ハンガリーの国土大半を奪われ、ウィーンが1ヵ月近く包囲されたことは、ビザンツ帝国(395-1453)の滅亡(1453)以来の大きな衝撃でした。スレイマン1世の率いるオスマン帝国軍の際だった強さは、西方世界にとっては脅威となったのでした。
引用文献:『 世界史の目 : 第266話 』より

|
|---|
| オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」 (講談社現代新書) 新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
| オスマン帝国六〇〇年史 三大陸に君臨したイスラムの守護者 (ビジュアル選書) 新品価格 |
2018年09月26日
9月26日は何に陽(ひ)が当たったか?
1985年に Roger Waters( ロジャー・ウォーターズ。bass,vo)が脱退したPink Floydは、 David Gilmour( デヴィッド・ギルモア。guitar,vo)と Nick Mason( ニック・メイスン。drums)の二人となりましたが、"A Momentary Lapse of Reason"の制作では元メンバーの Richard Wright( リック・ライト。key)もサポートとして参加し、今回紹介する"Learning to Fly"にも参加しました。またプログレ界の著名ベーシスト、Tony Levin(トニー・レヴィン。bass)も参加したほか、本作プロデューサーのBob Ezrin(ボブ・エズリン)がミュージックシーケンサーやパーカッションも担当しました。
ソングライティングの中心がRogerからDavidに移った本作は、アルバム・タイトルや収録曲のタイトル、シニカルな詩、そしてヒプノシスの意味深なジャケットから、非常に抽象的で深い精神世界を表現した内容に見えますが、音楽自体が非常にソフトになり、これまでのアルバムほどの過激さや悲痛さは持ち合わせておらず、Davidの温かみのある歌声である意味聴きやすいアルバムですが、やはりうメンバーの奏でる重厚さはしっかり備わっておりプログレッシブ・ロックらしい最後までじっくりと聴き応えあるアルバムです。
アルバムの2曲目に収録された" Learning to Fly"は、1曲目のインストゥルメンタル、" Signs Of Life(邦題: 生命の動向)"による静かで分厚く、幾分感傷的ですらあるギター・ソロを聴かされた後に、間髪入れずイントロがズシンと入り込む、ややミドルテンポのロックナンバーです。プロモーション・ビデオはカナダのバンフ国立公園で撮影され、メンバーの演奏シーンに合わせて時折登場する空を飛ぶ鷹の化身らしき人物、そして鳥を夢見た青年が高い崖から飛ぼうとする壮大かつドラマティックなシーンで構成されたスケールの大きい内容ですが、リリース時にはこの内容にもう1つ別カット(別の会社員らしき男性がロッカーに物を入れるシーンや最初のギターソロでDavidもロケ先でプレイしているシーンなど。記憶が曖昧ですみません)の入ったヴァージョンもあったと思います。私自身が少年期にビデオ録画した80年代のMTVの中にあると思うのですが、如何せんビデオデッキを所有しておらず、現在では確認できませんでした。
Billboard HOT100シングルチャートでは1987年10月31日にて70位を記録し、8週間チャートインしましたが、本場のロック部門であるAlbum Rock Tracksでは本領を発揮しました。1987年9月5日に5位に初登場したこの曲は翌週と翌々週に3位を記録して、陽の当たった9月26日付で1位に輝き、 3週間1位を維持しました。その後は下降していきましたが、12週チャートインし、この曲がチャートインしていた時には他の収録曲も軒並みチャートインしていました("The Dogs of War"、"One Slip"、"On the Turning Away"など)。

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |
2018年09月25日
9月25日は何に陽(ひ)が当たったか?
オスマン帝国皇帝、 バヤズィト1世( バヤジット1世。帝位1389-1402)は" イュルドュルム(「電光」「稲妻」)"の異名を取るほど、あらゆる軍事戦略への行動が迅速であり、コソヴォ戦(1389.6)以降も征服戦争を矢継ぎ早に行い、バルカンとアナトリアを攻略していきました。とりわけビザンツ帝国(東ローマ帝国。395-1453)においても数度にわたって首都コンスタンティノープル(現イスタンブル)を包囲するなど、勢いはますます加速していきました。
この脅威にさらされたヨーロッパ諸国は、ハンガリー王 ジグモンド(王位1387-1487。のちの 神聖ローマ皇帝ジギスムント。帝位1410-37)を中心に、国籍を超えたキリスト教世界の軍、いわば 中世最後の十字軍を結成し、陽の当たった9月25日、バヤズィト1世率いる イェニチェリ軍団および シパーヒーをはじめとする騎兵団によるオスマン帝国軍と ニコポリスで会戦することになりました。
バヤジット1世はジグモンド王の十字軍について、西欧式戦法である一騎打ちを仕掛けてくると判断し、中心に歩兵であるイェニチェリを従え、前面にアザプと呼ばれる不正規の軽騎兵を配置、その周囲に奴隷出身の常備騎兵、そして左右両翼にアナトリアとバルカンのシパーヒー騎兵を配置させ、集団戦法の態勢に入りました。バヤジット1世の思惑通り、一騎打ちにこだわったフランス軍の騎士たちが、ジグモンド王の制止を振り切って我勝ちに突撃、オスマン帝国軍前線のアザプを追い散らしましたが、バヤズィト1世は中心にいたイェニチェリを後退させ、誘い込まれたフランス軍がさらに前進したところを待機していたシパーヒーの猛反撃にあい、ジグモンド王の十字軍はあえなく潰走しました。オスマン帝国軍は、ヨーロッパの十字軍をも撃退するにまで発展したのです。
すでにアッバース朝(750-1258)は滅亡していましたが、アッバース家の カリフ(預言者の代理とする、ムスリム全体の最高指導者)は、エジプトの マムルーク朝(1250-1517)に守られていました。時のカリフであったムタワッキル1世(カリフ位1389-1406)は、ニコポリスの戦いにおいて、イェニチェリとシパーヒーを頭脳的に率いて、キリスト教世界の十字軍を撃破したバヤズィト1世を讃え、彼に" スルタン"の称号を付与したのです。その後もバヤズィト1世は、征服活動を休む間もなく続けていき、アナトリアおよびバルカンのほぼ全域を支配下におさめていくのでした。
引用文献:『 世界史の目 第264話 』より

|
|---|
| オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」 (講談社現代新書) 新品価格 |

|
|---|
|
中古価格 |

|
|---|
2018年09月24日
9月24日は何に陽(ひ)が当たったか?
Dennis DeYoung( デニス・デヤング。Key,vo)、 Tommy Shaw( トミー・ショウ。gtr,vo)、 John Panozzo( ジョン・パノッツォ。drums)、 Chuck Panozzo( チャック・パノッツォ。bass)、そして James [JY] Young( ジェームズ・ヤング。guitar)の布陣で制作されたのは、前作" Crystal Ball(邦題: クリスタル・ボール)"に続く2枚目で、この布陣でのシングルは前作よりTommyの歌う" Mademoiselle(邦題: マドモワゼル)"と" Crystal Ball(邦題: クリスタル・ボール)"が選ばれ、前者はTop40入りして1976年12月25日付HOT100シングル・チャートで36位を記録しました。Dennisがヴォーカルをとった最大のヒット曲は1975年3月に6位を記録した" Lady(邦題: 憧れのレディ)"がありますが、この布陣での、Dennis作で彼の歌うシングルはこの"Come Sail Away"が初のチャートインとなります。
このナンバーはシンセサイザーが大活躍します。サビから間奏に入るパートでの出航の汽笛や、間奏部分での"永遠の航海"に合わせたかのような表現を見事に音で表現しています。Dennisに加えて、JYの手がけるARP Odysseyのシンセサイザーで見事なハーモニーを聴かせてくれます。後半は美しいギター・ソロを展開させ、プログレッシブ・ロック・バンドとしてのStyxの本領が発揮されたドラマティックなナンバーです。
この曲はアルバムでは6分5秒のサイズでしたが(音源は こちら 。 Youtube より)、シングルでは3分10秒に削られました。2番がまるまるカットされ、間奏の幻想的なシンセサイザー・ソロがそっくりなくなっています(音源は こちら 。 Youtube より)。
さて、チャートの順位を見てみると、陽の当たった1977年9月24日にめでたく89位にエントリーしたこの曲は、翌週より78位→67位→56位と毎週11ランクずつ上昇、続く50位を記録後、6週目で35位と大きくジャンプアップしてTop40入りを果たします。その後はじわじわと上昇し、32位→26位→25位→23位→21位→18位→16位→14位→14位→11位と上がり、年も明けた1978年1月14日にようやく9位とTop10を果たし、1月21日付も9位、そして翌1月28日付で最高位8位を記録しました。その後は18位→51位→69位と下降し圏外へ消えましたが、この曲が69位の時点で、Tommy作で彼のヴォーカルによる次のシングル Fooling Yourself( The Angry Young Man)(邦題: 怒れ!若者)"が88位にエントリーしていました。この曲は1978年4月22日に29位を記録し、14週チャートインしています。
"Come Sail Away"はその後国内でもテレビや映画で数多く挿入され、Styxの代表曲に数えられました。Year-End チャートでは1978年の方で集計され、100以内で56位を記録しています。

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
| THE GRAND ILLUSION - LIVE 1977 新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |
2018年09月23日
9月23日は何に陽(ひ)が当たったか?
レーベルを、これまでのCBS(現ソニー・ミュージックエンタテインメント)傘下のEpicレコードから、MCAレコードへ移籍してリリースされた本作は、1980年から1986年の間にレコーディングされた楽曲が本作品に収められました。レコード移籍については、グループのリーダーでギタリストの Tom Scholz( トム・ショルツ)の完璧な音作りへのこだわりにより、レコーディングに長時間を費やしたことに業を煮やしたEpic/CBSから契約違反の訴状を突きつけられ、Bostonは音楽活動が停滞しました。このため8年という沈黙期間によりメンバーのラインナップも大幅に変更となり、"Third Stage"制作時点でのメンバーは Tom Scholz( トム・ショルツ。gtr,key,bs,drm)、 Brad Delp( ブラッド・デルプ。vo。2007年没)以外は流動的で、過去2枚に参加した Sib Hashian( シブ・ハシアン。drm。2017年没)も制作初期段階ではメンバーに入っていましたが、デビュー作" Boston(邦題: 幻想飛行)"収録の"Rock & Roll Band(邦題:ロックンロール・バンド)"のみ参加したオリジナルメンバーの Jim Masdea( ジム・マスデア。drm)に交代、またギタリストでは、本作不参加のBarry Goudreau(バリー・グドロー。gtr)に代わって、 Gary Pihl(ギャリー・ピール。gtr)が参加しました。
法廷での係争が落着後、1986年にMCAへ移籍したBostonは、ようやく6年間分のレコーディング、そして8年のブランクを経て、陽の当たった1986年9月23日にリリースされる運びとなりました。ジャケットが秀逸で、あの宇宙から見た広大な地球へ帰還しようとしている"ボストン号"の雄大な姿が表と裏を合わせたスリーブ・デザインとして描かれ、過去2作のジャケット以上に、壮大なスケールとして心を奪われる様です。当時はアナログ盤(LPレコード)で購入しましたので、壁に飾れるほどの価値のあるジャケットです。
さて、曲目は以下の通りです(アナログ盤表記。最後の数字は制作年)。
A面
1." Amanda(邦題: アマンダ)"・・・Scholz作(以下、単独Scholz作は表記略)。1980-81。
2." We're Ready(邦題: ウィ・アー・レディ)"・・・1981。
3." The Launch(邦題: ザ・ローンチ)":
a) 'Countdown(邦題:カウントダウン)'
b) 'Ignition(邦題:イグニション)'
c) 'Third Stage Separation(邦題:サード・ステージ・セパレーション)'・・・1982。
4." Cool the Engines(邦題: クール・ジ・エンジンズ)"・・・Scholz, Fran Sheehan, Brad Delp作。1981-82。
5." My Destination(邦題: マイ・デスティネーション)"・・・1982。
B面
1." A New World(邦題: ニュー・ワールド)"・・・Jim Masdea作・・・1982,85。
2." To Be a Man(邦題: トゥ・ビー・ア・マン)"・・・1984,85。
3." I Think I Like It(邦題: アイ・シンク・アイ・ライク・イット)"・・・Scholz, Jon DeBrigard(Jon English)作。1985,86。
4." Can'tcha Say( You Believe in Me) /Still in Love(邦題: キャンチャ・セイ)"・・・Gerry Green, Scholz, Delp作。1981,82,83(Can'tcha Say)。1983(Still in Love)。
5." Hollyann(邦題: ホリーアン)"・・・1980,81,82,1984-85。
サウンド面に関してはBoston流のメロディアスでスペーシーなハード・ロックは基本的には変わってはいませんが、過去2作と比べて非常にマイルドになり、より聴きやすくなっています。ファースト・シングル・カットされたA-1の"Amanda"を筆頭に落ち着いたナンバーが多く、かつTomの音へのこだわりを失わない仕上がりで、非常に聴き応えのあるアルバムです。
またこのアルバムではTomが開発したギター・プロセッサー、" Rockman"が披露されます。持ち運びが可能なポータブルヘッドフォンアンプで、レコーディングで生み出されたサウンドをライブでも再現できるように開発されました。
Bradの美声とTomの12弦ギターが美しいバラード、" Amanda"は3日後の26日にリリースされ、11月8日付Billboard HOT100シングルチャートで彼ら初の1位を獲得し、2週記録して18週チャートインしました。現時点でBoston唯一のHOT100での1位獲得曲です。集計期間の関係でチャート・イン週数は少なかったですが、その年のYear-Endチャートでは100以内50位を記録しました。メインストリーム・ロックチャート(当時はAlbum Rock Tracks)では1986年10月11日付で1位を獲得、3週間記録しました。
オープニングで珠玉のバラードを持ってくるあたりはハードロック・グループとしては独特ですが、単なるスロー・バラードに終わるのではなく、後半のクライマックスにおける特徴的なツイン・リード・ギターによる美しいハーモニーも健在で、この1曲で落ち着いて全編を聴くことができる安心感が備わります。A-2の" We're Ready"もそれほどヘヴィーな楽曲ではないものの、後半ではやはりBostonならではのツイン・リード・ギターが展開します。この曲はセカンド・シングルとしてカットされ、翌1987年2月14日付HOT100では9位まで上昇、Album Rock Tracksチャートは1986年12月6日付で2位を記録しています。
A-3" The Launch"のドラマティックなインストゥルメンタル、A-4" Cool the Engines"のアップ・テンポのハード・ロックの構成は前作"Don't Look Back"収録の"The Journey(邦題:ザ・ジャーニー)"、"It's Easy(邦題:イッツ・イージー)"の構成に似ています。特にA-3の" Third Stage Separation"での"ボストン号"打ち上げをエフェクトで表現しているパートは圧巻です。この流れに切れ目なく入り込むA-4はシングルとしてもエアプレイに頻繁にかかり、Album Rock Tracksチャートは1986年12月27日付で4位を記録しています。A-5の" My Destination"もスーッと入り込むA-1のリプライズ的なナンバーで、A面の最後を飾る素晴らしいバラードです。
B面はオリジナル・ドラマーのJim Masdeaによるインストゥルメンタル" A New World"で始まります。30秒程度の短い中でドラマティックに展開していき、そのまま" To Be a Man"に入ります。スロー・テンポでありながら、美しいギター・オーケストレーションを聴かせてくれます。
B-3の" I Think I Like It"はGary Pihlが参加したナンバーです。Bradのヴォーカルも少々控えめで軽快なポップ・ロック路線でありながらも、美しいギター・ソロは健在です。個人的にも気に入っているロック・ソングです。導入部におけるBradのシャウトで始まるB-4" Can'tcha Say( You Believe in Me) /Still in Love"はRockmanのエフェクターを初めて使用した楽曲とされています。もともと2つの楽曲がくっついて完成した美しいナンバーで、発売時期によってこの2曲が分かれている表記も見られますが、個人的にはくっついている方がアメリカン・プログレっぽくて親しみやすいです。この曲はシングルとしてもカットされて、HOT100では1987年4月18日付で2週続けて20位、Album Rock Tracksチャートでは1987年2月28日付で2週続けて7位を記録しました。アルバムの最後を飾るB-5" Hollyann"はチャートインは成し得なかったですが、シングルとしてもカットされた美しいロック・バラードです。ここでも単純なバラードに終わるのではなく、スケールの大きいギター・オーケストレーションが存分に味わえます。
"Third Stage"は内容から全体的にはミドル・テンポやバラードが多いものの、これらを全編ギターで展開すれば、普通なら飽きやすいところですが、Bostonはリズム、メロディそしてハーモニーすべてをBostonnらしくアレンジを施し、奥行きのある、かつ聴きやすく馴染める音楽に完成させるところが素晴らしいです。音を楽しみ、感動するグループであるがため、MTV全盛期でプロモーションビデオが制作されなかったのもうなずけます。このアルバム”Third Stage”は1986年11月1日付Billboard200アルバム・チャートでは1位を獲得、 4週連続ナンバーワンに輝いて、翌1987年のYear-Endアルバムチャートでも17位を獲得しました。セールス面でも全米でクアドラプル(4×)・プラチナに、カナダでもトリプル(3×)・プラチナに認定、Bostonは華麗な復活を遂げたのでありました。

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
中古価格 |

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |
2018年09月22日
9月22日は何に陽(ひ)が当たったか?
オスマン帝国の常備歩兵軍団、イェニチェリに支持されて後継者争いに勝ち、オスマン皇帝に即位したセリム1世は、アナトリアに進出する サファヴィー朝(1501-1736。シーア派のペルシア国家)の初代シャー、 イスマーイール1世(シャー位1501-24)が率いるクズルハシュ(キジルバシュ。トルコ系遊牧民からなるサファヴィー教団信徒が発端)の騎馬部隊と一戦を交えることになります。これまでのイスマーイール1世の治世では、クズルハシュで構成された騎馬部隊は無敵を誇っていました。
オスマン帝国とサファヴィー朝両軍の戦闘は東アナトリア地方のチャルディラーンで行われました( チャルディラーンの戦い。1514.8)。無敵を誇るサファヴィー朝軍に立ち向かうため、兵力の数においては圧倒的にオスマン軍が多く、これらを指揮するセリム1世は、オスマン軍の布陣は鉄砲を装備したイェニチェリ歩兵隊を筆頭に、砲兵と常備騎兵が構え、騎兵軍の前に鎖でつながれた大砲が並べられ、その大砲を別の騎兵が隠すように陣取りました。敵の突撃と同時に大砲を隠していた騎兵が左右に移動して大砲を出し、砲撃するというしくみです。また右翼にはアナトリア騎兵が、左翼にはバルカン騎兵がそれぞれ配置され、軍の前方に駱駝と車で柵が作られました。
一方のサファヴィー朝軍は、ほとんどが騎馬部隊の戦力となっており、イスマーイール1世は左翼を指揮しました。オスマン帝国軍より先に布陣を終えたイスマーイール1世は、夜襲攻撃をせずオスマン軍の布陣を待って、正面から攻撃することに決めました。
1514年8月23日、戦闘が始まりました。イスマーイール1世が指揮する左翼騎馬兵を中心に、凄まじい猛攻を繰り広げ、オスマン帝国右翼のアナトリア騎兵隊はたちまち倒れはじめて、オスマン軍は劣勢と化しました。しかしオスマン軍の火砲はサファヴィー朝軍の中央と右翼で大きく発揮されており、なおもイェニチェリの手は休むことなく鉄砲射撃を続け、そしてイスマーイール1世の攻撃に防戦一方だったオスマン側右翼にも駆けつけて一斉に射撃、サファヴィー朝軍左翼の将軍を戦死させ、さらにイスマーイール1世をも負傷させて形成が逆転、オスマン軍優勢となりました。結果、イスマーイール1世と潰滅したサファヴィー朝軍は逃げ去り、チャルディラーンでの一戦はオスマン帝国軍の勝利をもたらしたのです。この戦争で、サファヴィー朝が入り込んだ東アナトリア地方はオスマン帝国に帰順しました。
最強の騎馬兵で構成されたサファヴィー朝クズルハシュ軍の不敗神話が脆くも崩れ去る一方で、鉄砲や大砲といった新型兵器でこれらを倒したオスマン帝国イェニチェリの活躍は、弓矢や刀剣の時代から火器の時代への移り変わりを世に知らしめ、軍事の歴史において重要な意味を持ったのです。
サファヴィー朝との抗争を終えたセリム1世はエジプト〜シリアのスンナ派国家、 マムルーク朝(1250-1517)に標的を絞りました。すでに全盛期が終わり弱体が進むマムルーク朝でありましたが、アッバース家の カリフ(預言者の代理とする、ムスリム全体の最高指導者)を保護しており、いまだ威光を放つ存在でありましたが、シーア派国家のサファヴィー朝を戦争で打ち負かした、マムルーク朝と同じスンナ派国家のオスマン帝国の存在は、マムルーク朝にとって脅威にほかなりませんでした。
1516年8月、オスマン帝国軍を自ら率いたセリム1世は、シリアの都市アレッポ北方のマルジュ・ダービクで、マムルーク朝軍との戦闘を開始しました(1516.8)。オスマン帝国軍の布陣はこれまでと同様、中央にイェニチェリと常備騎兵軍、左右両翼に騎兵軍という布陣であり、陣の前後に多数の大砲が鎖でつながれて置かれました。兵力は6万を越え、大砲は500〜800門に達しました。一方のマムルーク軍は騎兵軍8万と、オスマン帝国軍を上回った兵力でした。マムルーク騎兵は勇猛果敢に突撃し、オスマン帝国軍の左右両翼が崩れはじめ、オスマン帝国軍は劣勢に立たされましたが、前回のチャルディラーン戦同様、イェニチェリ軍による左右両翼への救援で盛り返し、銃撃および砲撃を巧みに仕掛けて反撃、相手の指揮官を戦死させて形成を逆転させることに成功したのです。旧来の弓矢と刀剣で戦おうとしたマムルーク軍は潰滅、あれだけあった戦力は1万人も残っておらず、ついには退却しました。翌 1517年にオスマン軍は首都カイロを攻め落とし、 マムルーク朝を滅亡に至らしめました。これによりオスマン帝国はエジプト、シリア、パレスティナを領有することになり、さらに、聖地であるメッカとメディナの守護者とする称号がオスマン帝国スルタンに与えられました。マムルーク朝に保護されていたカリフに至っては、セリム1世自身がカリフの位を禅譲したという史料記述はなく、世俗的権威を持つスルタンが、宗教的権威を持つカリフとして立ったという政教一致の体制(いわゆる" スルタン・カリフ制")は、後世の創作である可能性が高いといわれています(19世紀に広まったこの伝説は、キリスト教列国との東方問題で揺れ動いた時代、オスマン帝国に最大最強の権威を示すために主張されたものと思われます)。
サファヴィー朝、マムルーク朝と立て続けに戦勝したセリム1世はアナトリア沿岸部のロドス島遠征を計画しました。14世紀に聖ヨハネ騎士団(マルタ騎士団)によって占領されたこの島は城壁は難攻不落で、かつて、あのビザンツ帝国(東ローマ帝国。395-1453)を滅ぼしたセリム1世の祖父で、オスマン皇帝 メフメト2世(位1444-46,1451-81)も出陣したことがありましたが、攻撃をはね返され失敗し、今度はセリム1世が挑むところでありました。しかしその志もかなわず、 1520年9月22日、セリム1世は病気のため没しました。54歳でした。その志は、子の スレイマン1世(帝位1520-66)によって受け継がれ、過去にない全盛時代を現出することになるのでした。
引用文献『 世界史の目 第265話 』より

|
|---|
| オスマン帝国六〇〇年史 三大陸に君臨したイスラムの守護者 (ビジュアル選書) 新品価格 |

|
|---|
| オスマン帝国 イスラム世界の「柔らかい専制」 (講談社現代新書) 新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |
2018年09月21日
9月21日は何に陽(ひ)が当たったか?
1792年8月10日、フランス国王 ルイ16世(位1774-1792)一家がタンブル塔に幽閉された、いわゆる 8月10日事件 によって、ブルボン王政の停止が決まり、9月20日に国民公会(1792.9.20-95.10.26)が発足、陽の当たった翌日に 第一共和政が宣言されました。
国民公会発足時では、上流ブルジョワに支持された立憲王政を唱えるフイヤン派は活躍の場を失い没落していきます。そして議会は右派に中流ブルジョワによって支持された穏健共和派の ジロンド派、左派に下流ブルジョワや貧困層らに支持された急進革命派の 山岳派(モンターニュ派)などでそれぞれ構成されましたが、やがてジロンド派党員が、フイヤン、ジロンド、山岳諸派を構成してきた ジャコバン・クラブから次々と脱退していき、左右両派の対立はより一層激化しました。フランス最初の共和政である第一共和政は1804年まで続きます。
左右の対立激化を加速させた国王ルイ16世の裁判では、政権を握るジロンド派は執行猶予と国民投票を行おうとしましたが、山岳派は国王の即刻処刑を要求しました。この勢いに呑まれ、政権を握っていたはずのジロンド派は結果的に山岳派の主張を抑えることができず、翌1793年1月21日、国王 ルイ16世の処刑が執行されることになりました。国王処刑事件は他国に脅威をもたらし、革命戦争に対する警戒心をより深めました。イギリスの ピット首相(任1783〜1801,04〜06。小ピット)は、オーストリア・プロイセン・スペイン・ロシア・ポルトガル・オランダなどにヨーロッパ諸国に呼びかけて、1793年4月、 第1回対仏大同盟を結成しました。国民公会は2月にイギリス・オランダ、3月スペインに宣戦、同年末まで戦乱が続きました。
山岳派に圧倒されていたジロンド派は革命戦争を起こして失敗していただけに、国内外で孤立したため、共和政が実現できたにもかかわらず、ジロンド派政府は行政ができる状態ではなく、少数の山岳派議員や民衆の怒りを買うばかりでした。そして国王処刑を機に山岳派に支持が集まり、1793年3月に反革命派・反体制派を裁く革命裁判所が設置され、4月に公安委員会と言われる、事実上の山岳派が主導する中央委員会が発足されます。この公安委員会が革命の中枢となっていき、強力な行政活動を遂行していきました。これによって追い詰められたジロンド派は急転落の一途をたどり、山岳派はジャコバン・クラブ内におけるジロンド粛清にとりかかり、ジロンド派の政治活動が停滞することになりました。ジロンド派の抜けたジャコバン・クラブは山岳派が支配することになり、最左派だった山岳派はジャコバン派の主流となって、過去の広義の革命団体とはもはや異なる、急進的な共和派となっていき、ジャコバン派=山岳派となって、大胆な" 恐怖政治"を繰り広げていくことになります。
国民公会政府から 総裁政府(1795.11.2-99.11.10)に移っても安定しなかった第一共和政は、軍人 ナポレオン・ボナパルト(1769.8.15-1821.5.5)の登場で 統領政府(1799.11.10-1804.5.18)にとって代わられ、1804年5月18日、ついにはナポレオンの主導で帝政( 第一帝政。1804.5.18-14.4.11、1815.3.20-15.6.22)へと置き換えられ、第一共和政は終焉を迎えました。
引用文献:『 世界史の目 』より

|
|---|
|
新品価格 |

|
|---|
| ルイ・ボナパルトのブリュメール18日—初版 (平凡社ライブラリー) 新品価格 |

|
|---|
| 革命の終焉 小説フランス革命 XII (小説フランス革命 12) 新品価格 |

|
|---|
|
新品価格 |