4月9日(巡礼9日目)Najera ナヘラ 〜 Ciruena シルーニャ (15.5km)
「巡礼者を突き動かすもの What makes pilgrims go forward」
ナヴァレッテで母親のようなおばさんに会った後、歩くのをもうやめたいという気持ちは不思議にもきれいさっぱり消えていた。
おばさんの好意を無にした分、最後まで歩くのだという気持ちが芽生えていた。それが、いろいろと世話をやいてくれたおばさんへの礼儀である気がした。
彼女は4回目の巡礼だと言っていたが、何を思って、何のために、サンティアゴ・デ・コンポステラを目指していたのだろう。
ナヴァレッテの宿は若い人たちが多かったが、入り口でオーストラリアから一人で来たというきれいな女の子と少し話した。学生のようだったが、あの若さで一体何をきっかけに巡礼を思い立ち、何を考えながら歩いているのだろう。
夕食付きのアルベルゲでテーブルを囲むとそういった質問をされることがあるが、私は自分があまり尋ねられたくはなかったし、皆それぞれ心に秘めるものがある気がして、自分から他人へその質問をしたことはなかった。若い彼女のつま先はテーピングだらけだった。それ程までに過酷な道程をひたすら耐え続ける、どんな理由があるのだろう。
歩き始めた頃は「どうせ途中で投げ出すに決まってる」と、ゴールのサンティアゴ・デ・コンポステーラどころか「どの辺りまで行けるかな」と思っていた。
それでも私が巡礼を途中で放棄しなかったのは、いろんな人の励ましに支えられていたからでもあるし、自分の中で「絶対に自分の足でサンティアゴまで行く」という思いが、日々強くなっていったからである。
そして何よりも、歩くことに喜びを感じ始めている自分がいたからだと思う。東京にいた頃は朝まともに起きられなかった私が、毎朝遅くとも8時半には歩き始めていたし、毎晩違う所に違う人たちと泊まるのだ。
今日は遅くまで寝ていたい、というような週末感覚もなく、毎日ただひたすら朝は8時までには起きて支度をし、宿を出て荷物を背負いながら歩き、次の宿に辿り着き、そしてまた翌朝のために9時には寝袋にもぐりこむ。
毛布がなくて寒さに震えながら、エビのように丸まって眠る夜もある。同室の人の鼾に悩まされ、朝方まで眠れない夜だってある。それでもそんな日々を40回も繰り返すことができたのは、歩くことが楽しかった、幸せを感じていたからではないかと思えるのだ。特にナヴァレッテの後、絶対に投げ出さない、と決めてからは何だかがむしゃらに歩いていた気がする。
それでもやはり午後になり、ある程度の距離を歩いてくると疲れて「もう歩けない」「もうイヤ」と思うことは多々あった。そんな状態で辿り着いた宿がハズレだった日の気分的な落ち込みはなかなか回復できるものではないのだが、当たりだった場合、翌朝にはまた幸せな気持ちで歩き始める活力となるのだった。
9日目はオスタルに泊まってしまったのでラクをした分キツく感じられる行程だったうえに殺人的な暑さで、精神よりも体力との勝負になっていた。予定では21キロ歩くつもりだったのだが、4月にしては異常に暑すぎる日光の下、精神的にもまだナヴァレッテでの痛手を抱えていたので、ペースは落ちるばかりだった。
ガイドブックでは次の町までアルベルゲはないはずだが、手前のシルーニャという小さな町でアルベルゲの矢印を見つけた。そして暑熱に傷めつけられた体に、もうひと山越える力は残っていそうもなかった。
ガイドブックに載っていないのでどんな宿か想像がつかないが、すでに巡礼路を外れ矢印に従って100メートルほど歩いていた。100メートルといえども、引き返すには重い荷物を背負って疲れきった身にはかなりの距離に感じられる。私は賭けをするつもりでその予想外の地点に現れた宿に入ることにした。
引っ張ってもドアが開かないので呼鈴を押して待つことたっぷり1分、ドアを開けたのはマーロン・ブランドのような濃い眉の下の目は眼光鋭く下顎も張り気味の、不機嫌そうなコワモテ親父だった。
ドスの効いた野太い声で料金等の説明をするそのコワモテ親父は太っているわけではないのだが、大きな体は意外と緩慢な動きで、階段を登る時息を切らしていた。
どおりで呼鈴を押してから出て来るのに時間がかかった訳だ。そして宿の奥の方からシャンソンのような古い映画音楽が流れてきていて、何かレトロなクラブにでも入ってしまったような不思議な感覚を覚えた。
4時に再び呼鈴が鳴り、中年女性が二人到着したが、オーナーは二人を別の部屋へ案内してくれたので、その夜私は一人で広い部屋を独占でき、ゆっくり疲れを取ることができたのだった。
その夜の夕食は少し他のアルベルゲとは違っていたので、強く印象に残っている。
6時半という少し早めの時間に呼ばれて案内されたのは普通の家庭のような小さなキッチン。オーナーも含めて4人座るとほとんどいっぱいになってしまうようなこじんまりとしたキッチンで、棚には地元で採れたというトウモロコシや巨大なキュウリ、トマトといった野菜やバナナなどの果物が所狭しと置かれていた。
そしてこのオヤジ、見かけは怖いし、ぶっとい大声で喋るのだが、恐らくゲイに違いない。小指を立てるしなっとした仕草がその巨体に不釣り合いで逆にキュートなのだ。
ご自慢の手料理なのに、ツナサラダ(これが意外に絶品だった!)もチョリソーと豆のスープもあまりおかわりの声がかからないのが御不満らしく「何よ、あんたたち少食ねェ」とばかりにしなを作ってみせた。(このセリフは私の想像。)
翌朝は、大きなカフェオレ・ボウルにたっぷりのカフェ・コン・レチェ、トーストとマフィンの幸せな朝食で始まり、7時半という健康的な時間に宿を出発。
可愛いらしいオヤジが一人で切り盛りする、ガイドブックには載っていないが「めっけもの」のアルベルゲだった。シエスタをとったわりには8時半に寝てしまったが、快適で満たされた眠りだった。
★スペイン巡礼記?Lへ続く…
(表題上部の>>をクリックしてください)






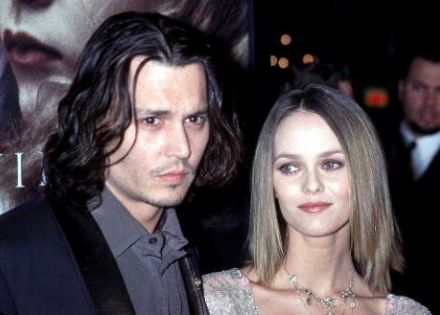


![WEB_Juric_Loneliness_Art[1].jpg](https://fanblogs.jp/wanderingsugar/file/WEB_Juric_Loneliness_Art5B15D-thumbnail2.jpg)


