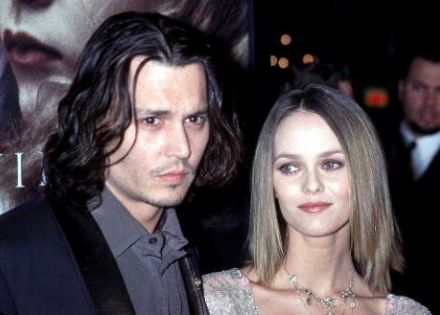4月14日(巡礼14日目)Burgos ブルゴス 〜 Rabe de las Calzadas ラベ・デ・ラス・カルサダス (11.8km)
「人がいない! Nobody is there!」
昨日ブルゴスを発ち、ほとんど巡礼者どころか一般人にも会わないまま、約12キロ先の小さな村でアルベルゲに入った。
何かと親切なおばさんの営むB&Bのように居心地の良いそのアルベルゲには結局、私一人が泊まっただけだった。夜中一時間ごとに隣りの教会の鐘が時を告げるたびに目を覚まし、一人で快適だったはずなのによく眠れなかったので、これ以降私は教会の近くのアルベルゲは避けるようになった。
巡礼道に点在する小さな村のアルベルゲには何度か泊まったが、スペインは国土が広いからなのか、各村の人口が圧倒的に少ない。一つの集落に10から20軒の家があっても外には人っ子一人歩いていないのだ。
見渡す限り緑の麦畑が広がる広大な大地の谷間にぽつんと現れる集落は、よく映画で見るメキシコの渇いた大地を想起させる。ひび割れた土壁の家々が多く、家畜小屋を併設している場合が多い。なのに人は全く見当たらない。一体人々は昼間どこへ消えてしまうのだろう。
4月15日(巡礼15日目)Rabe de las Calzadas ラベ・デ・ラス・カルサダス 〜 Hontanas オンタナス (19.7km)
「理想の人、現る! An ideal man appears! 」
15日目、ブルゴス近郊の村から次の目的地への約20キロの道のりはアメイジングだった。
なだらかな緑の麦畑がずっと広がっていて、少し強い風が吹いていたが、見渡す限り人影もなく、緑の谷間を渡る風の音だけが聴こえていた。カスティーリャ地方のメセタ(台地)に入ったのだ。
左右に石灰岩のような白い岩肌を見せる小高い丘や、黒く硬そうな玄武岩らしき岩肌を晒す尾根を眺めながら、果てしなく目の前に延びる砂利道を、暑すぎず寒すぎず、快適な気温の中ゆっくりと歩いたので、一回休みを取っただけで20キロ近く歩いてしまった。
その一回の休憩のためカフェオレを飲んだオルニージョスという集落に入る手前で、あるイギリス人青年に出会った。彼は自転車に乗って、後ろからやってきた。誰にも会わないと思って歩いていたので、突然後ろから声をかけられて少しドギマギした。
体の弱そうな蒼白な顔に競輪選手のようなぴっちりと目を覆うゴーグル風サングラスをかけた、見るからにイギリス人の彼は、マンチェスターから来た学生でクレイといった。芸術系の大学で写真を学んでいるクレイは、2週間で約800キロを自転車で走破する予定だという。
自転車から降りて、そんな話をしながら私の横を歩いていたのだが、彼がとても礼儀正しくいかにもイギリス紳士然とした口調で写真を撮らせてくれないか、と申し出た。
ヤンの時の「写真撮ってもいいか〜い?」的な軽いノリではなく、旅の途中出会った魅力的な人たち、人間を撮りたいんだ、と彼は写真撮影も旅の目的の一つであることを丁寧に説明し、もし君が不快に思わなければ、君の写真を何枚か撮らせてもらえないか、と惚れ惚れするようなブリティッシュ・イングリッシュで言われて「イヤです」と言える日本人ではない。
「私なんかで良かったら…」と付け足したいような気持でOKすると、彼は自転車の後ろに括り付けた荷物の中から、大事そうに本格的な大きな一眼レフカメラを取り出すと、ここに立ってとかあっちを向いて笑って、など指示を出しながら撮影を始めた。
すごいすごい、と感動する私に照れながらも、彼はカメラをしまうとなだらかな坂を下った先に見えているオルニージョスの村を指しながら尋ねた。
「あの村で僕は後から来る友人と合流して朝食をゲットする予定なんだ。君は?」
私も喉が渇いていたし少し休みたい頃だったので、バルがあれば入るつもりだと答えた。
ヒラリと自転車に跨ったクレイは「じゃ、あそこでまた会えるね。写真撮らせてくれてどうもありがとう」と言い、「See you later.」と手を振りながらペダルをこぎ始めた。徐々にスピードを上げて坂を下り始める彼の背中に私も「See you later.」と返す。
坂を下り終えるころ、バイカーが一人スピードを緩めず「ブエン・カミーノ!」と叫んで私を追い越していった。きっと今のがクレイと合流するはずの友人なのだろう。かくして再び会えるのを楽しみにオルニージョスの村へと入っていった私だった。
「後悔先に立たず… Repentance always comes too late」
が、結果的に私はクレイに会えなかった。いや正確には、会ったことは会ったのだ、ほんの一瞬。だが私はクレイと友達になる機会を逃した。
オルニージョスの村の中ほどで私は一軒の店に入った。バルだと思ったのだが中にテーブルはなく、ジャムや牛乳を売るグロッサリー、いわゆる小さな食料品店だったので店を出ようとしたとき、外から店に入ってきた人がいた。
イギリス人俳優エディ・レッドメインを思わせるハンサムなその若い男性は私を見てニッコリとほほ笑んだ、気がした。すれ違いざま「ハイ!」と言われた気がしたが、私は「あなた誰?」とでもいうように首を傾げて小さな声で「ハイ」と返しただけだった。それすら相手には聞こえていなかったかもしれない。
私にはわからなかったのだ、それがクレイだということが。オルニージョスの手前で会ったクレイはグラサンとヘルメットというフル装備だった。でも今すれ違った人はグラサンもヘルメットもしていなかった。だからクレイだとは思わなかったのだ。ただ、私がクレイだと認めて立ち止まらなかったので、彼もあえて私を追いかけて呼び止めはしなかった。
そしてそのすれ違いのわずか5秒後に私の中で「ひょっとして今のはクレイ?」という疑念がはじけたのだが、すでにその時足は一軒先の家の前を歩いていたし、クレイは友人と店の中へ消えていた。そこでハッと気付いて店に戻りクレイに声をかけられるほどの積極性は私にはなかった。
数メートル先にみつけたバルでカフェオレを飲み、再び緑の野を歩き始めたとき、私の中に「もう彼とは二度と会えない」という思いが立ち昇ってきた。自転車を使う巡礼者は一日に100キロ近く進む。私が暗いバルの奥でカフェオレを飲んでいる間にオルニージョスを出発したであろうクレイは、すでに何キロも先を走行しているに違いない。その距離はどんどん離れていくだけで、永遠に縮まることはない。
しかし彼に再会して撮影した私の写真を送ってほしいとアドレスを交換したり、6月にイギリスを旅する予定なのでいろいろイギリスのことを教えてほしいと親交を深めるチャンスはもう二度とない。
あのすれ違いの一瞬が、たった一度のチャンスだった。徐々に重くのしかかる深い後悔の中で私は悟った。勝ち犬と負け犬と呼ばれる女の違いを。
勝ち犬はたった一度与えられたチャンスを決して逃さない。常日頃から周囲の物事にアンテナを張り巡らし、チャンスを確実に成功に変える、という明確な意思。それが欠けている私は一生負け犬だ…。
普段から自分の興味のある物事にしか関心を示さず、ぼーっと生きている私はクレイが何色のレイヤーを着ていたかさえ覚えていなかった。だからサングラスとヘルメットをとったあのイケメンがクレイだとすぐにわからなかった。
更に気付いた後、一瞬の判断で振り返る、ということができなかった。そうやってどれだけ私は貴重な出会いのチャンスを逃して来ただろう。気恥ずかしさとか、ほんの少しの面倒くささとか、あとわずかの積極性、そういったものが人生を左右する。私はこれまでも、この先も、そんな一瞬の迷いで人生の幸運をいくつもフイにすることになる。
負け犬が勝ち犬になれる日はくるのだろうか。ヒトメボレ、だったのかもしれない。
イケメンイギリス人青年クレイとの、一瞬で終わった邂逅を慰めるかのように、風が緑の海原を波打たせながら、穏やかに吹き抜けていった。