4月16日(巡礼16日目)Hontanas オンタナス 〜 Boadilla del Camino ボアデリャ・デル・カミーノ (26km)
「初めて日本人に出会う
For the first time I met Japanese on Camino 」
巡礼は一期一会の連続だ。
40日間に一体どれだけの人と出会っては分かれることを繰り返したのだろう。人生を短時間で早送りして見たように、様々な人々が私の傍らを通り過ぎていった。
昨日クレイという、私が最も会いたいと思っていたイギリス人と、二度とないめぐり逢いのチャンスをフイにした私は、オンタナスという谷間の村のアルベルゲに泊まった。
緑色のパッチワークの中に一本続く白い巡礼路が急降下したとき、不意に眼下に出現したオンタナスはすり鉢状の谷底に位置する小さな集落だ。
元気いっぱいの女性達のみで経営されているそのアルベルゲで、私は初めてカミーノを歩く日本人に出会った。
ブラジルに一年近く滞在したりして世界一周旅行中のケンタロウ君と、愛媛県から休暇を取って歩きに来たという社会人のタケシ君の二人だ。二人も前日会ったばかりだという。
彼らからしてもカミーノで日本人女性に出会ったのは私が初めて、ということでお互いに驚いた。とても礼儀正しくおとなしい子たち(といっても二人とも20代後半)で、やっぱり日本人はいいなぁ、と久々の日本語を楽しんだ私だった。
ケンタロウ君は偶然にも私の上のベッドだったのだが、ベッドの脇に置いた彼のバックパックからは整髪料やドライヤーまでがのぞいていて、イマドキの男の子は旅に出てもオシャレに気を遣うんだなぁと微笑ましく、またそんな必要最低限の中に入らない余計な荷物さえ持ったまま歩けるパワフルな男の子が羨ましかった。そういえばヤンもバナナをひと房持ち歩いていたっけ。
オンタナスのバル併設のこのアルベルゲには『チュロス・コン・チョコラーテあります』と貼り紙が出ていたので翌朝オーダーしてみたら、すでに終わってしまったという。朝8時とはいえ私は相変わらず最後の客だったので仕方がない。
「越えられない壁はない There is no wall that you can't overcome 」
さて、昨日はベッド数35のアルベルゲに日本人が3人も集まり、日本人率の高さに驚いた晩だったが、16日のボアディリャ・デル・カミーノのアルベルゲには、なんと日本人3人、韓国人2人と、アジア人集結状態になっていて、後にも先にもない珍しい一夜となった。
この日私は、初めて一日30キロを歩いた。オンタナスを出て前日と同じような緑の丘にうねうねと続く一本道をしばらく進むと平地に出る。道の両脇に糸杉や欅のような街路樹の続くコンクリートの歩道を少し歩くと、サン・アントン修道院の廃墟が姿を現した。
緑の麦畑が途絶え、灰色の岩肌をむき出しにした急斜面を持つその丘、いや山のような絶壁に、くっきりと白い巡礼路が蛇のようにくねくねと這い上り、丘の向こう側へと続いているようだ。丘の向こうは下からではどうなっているのかわからない。まさに山あり谷ありの人生のような巡礼路。
日によっては激しいアップダウンを繰り返して33キロの道のりを歩かなければならない。イギリスで「丘があれば越えたくなる。階段があれば登りたくなる」と思った私も、この気の遠くなるような絶壁を前に、道路にへたりこんでしまいたくなった。カストロへリスの村で入ったバルの優しいオジサンの元へ戻って、今夜はそこに泊まろうかという思いもよぎった。
しかし、この目の前に立ちはだかる高い壁を越えなければ、先へは進めないのだ。バックパックのお腹のベルトを締めなおすと、私は覚悟を決めて登り始めた。
45度くらいの傾斜と思われる坂道を、ひたすら地面を見つめながら一歩ずつ足を前に出す。実際は30度にも満たない傾斜なのだろうが、重いバックパックを背負っているので、まるで地面に鼻先をくっつけるように前のめりになって歩いていると、後ろから歩いてきた人達が私のバックパックを押しながら、頑張れと声をかけてくれたりする。皆、息が上がっている。
今にも心臓発作を起こしそうなまんまるの巨体を揺らしながら、亀のごとく小さな一歩を進めるオバサンに声をかけて追い越し、私も一歩ずつ更に上へと進む。
そしてついに頂上に立ったとき向こう側に広がっていたのは、今まで歩いてきた道と何ら変わらない、緑の麦畑がどこまでも広がるスペインの大地だった。
茶色く乾いた砂地も所々認められるが、イメージとは違いスペインには意外と緑が多い。頂上までの砂利道にかわり、今度はコンクリートの急な下り坂が巡礼者を苦しめるために待ち構えている。
小さな集落がぽつぽつと見えるが、巡礼路は遥か彼方の緑の絨毯の先へと溶け込んでいて、アルベルゲのある村がどのあたりなのか視認することはできない。確かなのは、まずこの急な下り坂を制覇し、再び緑のゆるやかな丘をいくつも越えていくということだけ。
しかしこの絶壁を越える前と後とでは、似たような風景なのに気持ちの中で何かが違う。一山越えた巡礼者は皆、汗の滴る顔にどこかやりとげた満足感のようなものを湛え、微笑んでいる。こうやって旅人はスペインの広大な大地を歩きながら、自分への信頼感を取り戻していくのかもしれない。
アルベルゲ併設のレストランでミートソースのショートパスタを食べ終わった時点で2時15分、微妙な時間だ。今日はまだ15、6キロしか歩いていないし、この時間にアルベルゲに入るとやることのない長い午後を過ごさなければならない。
その時、クレイやヤンの姿が頭をかすめた。ここで泊まっては彼らとの距離が開くだけだ。もう会えないとわかってはいても少しでも彼らに近付きたい。その思いが私にもう10キロ歩くことを決意させた。
すでに経験で、どんなに疲れていても、わずかの休憩で驚くほど体が回復することを知っていた私は、あと10キロまだ歩ける、と判断した。
あと10キロ、時間にすると2時間半。遅くとも5時には次のアルベルゲにたどりつけるだろう。日の入りの遅いヨーロッパでは、それでもまだ充分明るいはずだ。
「この星に私だけ... I am the only one human in this planet... 」
そして私は再び歩き出した。約30分のランチ休憩で充分英気を養ったつもりだったが、やはりあの丘越えの後の10キロはキツかった。なだらかな丘の連なりだけが救いだったが、この10キロの間私を最も苦しめたのは、足の裏の痛みでもなく肩に食い込むバックパックの重さでもなく、孤独だった。
歩き始めこそ「I can do it!」と心の中で唱え、強気で歩いていた私だったが、行けども行けども似たようななだらかな麦畑の中の一本道が続き、若干の起伏があるため次の丘に阻まれて道の先が見えない。
背の高いススキに覆われた谷などをとぼとぼと歩いているうち、誰とも会わないことが、恐怖感となって私を襲い始めたのだった。
明けない夜はないし、道は必ずどこかへ通じている。そう思っても誰にも追いつかず、誰も追いついてこない状況が続き、視界の狭まった谷の最深部を歩いているとどうにも怖くなり、背中の荷物の重さも構わず走り出したこともあった。とにかく視界の開ける場所へ出ようと、その思いだけで。
亡き両親が共に歩いてくれているのは感じていた。時おり私を励ますかのように番いで飛んできては私の周囲をヒラヒラと舞い、どこかへ飛び去る蝶。一日に一回は必ず現れるその白と黄色の小さな蝶々を、私は両親だと思って毎日歩いていた。だからこの時も、私の背丈より高いススキの原をたわむれて舞う蝶に勇気付けられて歩いた。
それでもこの時の10キロは果てしなく遠く感じられた。大声でアルフィーの歌を口ずさむのにも疲れ、何かから逃れるように足早に歩きながら、私は必至で神に祈った。
「たった一人でもいい、神様お願い、誰か、誰か人間に会わせて…」
クレイやヤンとはいわない、誰でもいい。誰でもいいからこの世に私ひとりしか存在していないのではないかと思えるような、この気の遠くなる孤独から解放して。
まだ明るい、白く眩しい空に向かって私は祈った。
そして、祈りは通じた。
ふいに後ろから車輪の音が聞こえたかと思うと、バイカーが一人「ブエン・カミーノ!」と叫び手を振った。
それがイエス・キリストなのかは知らないが神はいる、確かに宇宙を統べる何か大きな、とてつもなく大きな、一般に人々が神と呼ぶものは存在する、とはっきり感じた瞬間だった。
私は世界にひとりぼっちなんかじゃない。見ている者は必ずいる。その確信から、両親やご先祖様、日本にいる友人たち、神と呼ばれるもの、全てに感謝したい気持ちが私の背中を押した。
そして辿り着いたボアディリャ・デル・カミーノのアルベルゲで、私は何人かの懐かしい顔と再会した。
その村の入り口にあったアルベルゲはすでに満員で、少し先に大きなアルベルゲがあると教えられた。時刻は4時15分。恐怖に駆られて小走りで歩いたためか予定より早い到着だったが、やはり体はもう一歩も歩けない、と思うほど疲れていた。
私はフラフラしながら2軒目のアルベルゲに向かった。今まで宿に入る時間は大体3時頃と早かったため、満室などという事態は初めてで、もし次も満室で泊まれなかったらどうしよう、という懸念で私の顔は蒼白だったに違いない。
クリーム色の石壁の門を入り、人で溢れる芝生の中庭をヨロヨロと受付に向かって進む私に走り寄り、背中のバックパックを下ろすのを手伝ってくれたのは、日本人の男の子だった。
「今日はアジア系が多いなぁ」と言いながら私のバックパックを受付まで運んでくれたその男の子は、リョウタ君といった。勝手知ったる、という感じで案内したりファンキーなアルベルゲのオヤジ、エドゥアルドとやけに親し気だなぁと思ったら、彼は巡礼者ではなくここのアルベルゲでバイトをしているのだという。
「女4人、恋バナで盛り上がる
Four women became over love stories 」
ランチが遅かったので、夕食を付けるかどうか聞かれて迷っていた私に「今日は日本人も韓国人もいるからきっと楽しいし、おいしいよ、ここの食事」とリョウタ君が言うので、お腹は空いていなかったが疲れをとるためにも夕食をお願いすることにした。
彼の言った通り、2日前オンタナスで一緒になったタケシ君と再会。ケンタロウ君はもっと歩くといって先へ行ったらしい。4時過ぎに宿に入ってシャワーを浴び、洗濯をしてもまだ外は暖かく明るい。7時の夕食まで日向ぼっこをしようと外へ出るとタケシ君が話しかけてきた。
「オレ、英語も喋れへんから友達いないんすよー」と日本人に会えたのが嬉しそうだ。
夕食で、私は韓国人の女の子、サンと同席になった。
レストランに入った時「あなた、Izumiでしょ?」と話しかけられたのだ。「なんで私のこと知ってるの」と驚いた私に、サンは頷きながら答えた。
「ヤンに聞いたの。夕方あなたが入ってきた時『あの人が38歳の日本人だー!』ってすぐわかった」
ヤン———。
おしゃべりヤン。フレンドリーでファンキーで軽いノリで、ちょっぴりいい人だけど、あのおしゃべりヤン!
サンによると、いろんな人に私の写真を見せていたのだという。知らない人が、まるで私のことを旧知の間柄のように親しげに頑張れ、とかファイト、とか言って笑いかけていったのはもしや、ヤンのせいか?
私は正直むかつく気持ちを抑えながらサンとテーブルについた。向かいに座ったのは、ヴィロリア・デ・リオハの宿で一緒だったメキシコからのダミ声お姉さん。
彼女はレストランの入口で私を見つけると「オー!」というダミ声で絶叫して力強いハグをしてくれたのだ。英語は喋れないながらも身振り手振り付きのスペイン語で「あなたにまた会いたかったの!」と再会を喜んでくれた。
そうして私との再会を喜んでくれる人々の記憶の中には「自身より重そうなバックパックを背負い、一人で歩いている小さな日本人の女の子」というイメージが強烈にあるらしく、皆がすごいとかエライなどと褒めてくれる。彼らのイメージの中では私はまだ子供、よくて大学生なのかもしれない。
だから普通の人より大きなハンディを背負って歩き続けているという錯覚を与えることに加え、私がカミーノでは珍しい日本人であることが、彼らにとって私のイメージを強烈にしているのだと推測する。
メキシコのダミ声お姉さん以外にも、ずっと同じペースで歩いているらしいドイツ人のでこぼこ夫婦、ゲイのオヤジが営む宿で一緒だったアメリカ人女性など多くの再会が、この古くて寒い厩舎を改造して巡礼者用の寝室にしたアルベルゲでの滞在に光を灯してくれた。
テーブルを囲んだ私と韓国人のサン、メキシコ人のダミ声お姉さん、そして彼女と今一緒に歩いているというイタリア人女性の4人は、豆のスープなどの美味しい料理とワインを堪能しながら、ダイエットや恋バナといった、いわゆるガールズ・トークで盛り上がった。
タケシ君は、というと残念ながらテーブル人数の都合ではじき出され、幸か不幸か別の美女軍団のテーブルに男ひとりで座らされていた…。
その夜私達のテーブルで話題をさらったのは、30前後とおぼしきイタリア人の女性だった。彼女は前回の巡礼中に出会った同じイタリア人の男性と恋に落ちたのだという。そして彼女はローマ、彼はフィレンツェで遠距離恋愛を続け、ついに先日彼からプロポーズされたというのだ。
今回はそのプロポーズに対する答えを出すためにカミーノを歩きに来たのだと、良く似合うショートカットの髪型に大きな目を持つ彼女は、幸せオーラを周囲に放ちながら説明した。同テーブルの女子が「ロマンチック〜!」と大絶賛したことは言うまでもない。
カミーノにはそんな恋物語がいくつも存在する。私がそれらの登場人物の一人になれないのは悲しいことだが、仕方がない。
まだ決めていないけれど、たぶんプロポーズを受けて彼と結婚すると思う、と言ったイタリア人の彼女の目は、愛される自信に満ち溢れ、関わった誰をも虜にするようなキラキラした光を宿していた。






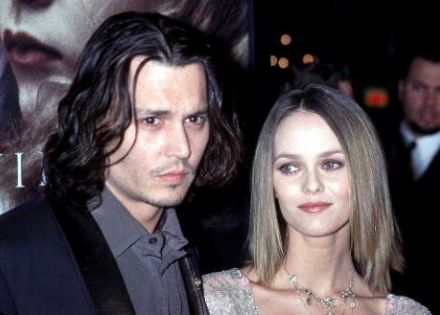


![thumb5[2].jpg](https://fanblogs.jp/wanderingsugar/file/thumb55B25D-thumbnail2.jpg)

