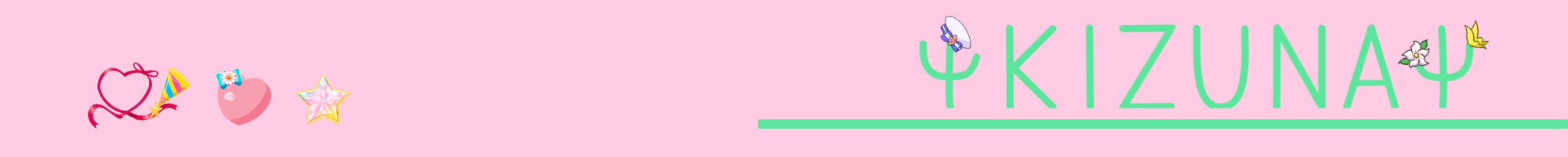第一章 降ってきた厄災(A)
第一章 降ってきた厄災
誰もが眠る真夜中。とある家の窓に、小さな明かりが揺れていた。
試験管や薬品瓶が並ぶその部屋では、男と少女が机の前に立っている。
二人は、明かりの灯ったランプの下で行っている実験の過程を、じっと見守っていた。
どれくらいのときがたったのだろう。
机の上から目映いばかりの光が溢れだした。
光は徐々に大きく広がり、男も、少女も、部屋も、なにもかもを白く飲み込んでいく。
目を開けていることができないほどの光の中、それでも男は懸命に瞳を見開いた。
その瞳に映ったのは、一枚の美しい羽。
実験の成功を意味するそれに、男は手を伸ばす。
だが、輝くその羽がもたらしたのは成功の喜びなどではなかった。
─次の瞬間、部屋に響き渡ったのは、少女の長い悲鳴だった。
山々の間を一本の列車が走っていく。谷を跨ぐ石橋を通り、樹木の間をすり抜け、列車はひたすら目的地に向かって進む。蒸気機関車特有の車輪の音が森の中に吸い込まれ、先頭の機関車から吐きだされた煙は長く後ろに伸びていった。
午後の陽射しを受けながら走る列車の中で、乗客たちの多くは列車の心地よい振動に身を委ね、遠くに見える麓の草原と点在する家々を眺めたり、連れと談笑したりしてゆったりと過ごしていた。
だが、旅の途中にできたこの穏やかな時間を楽しむことのできない少年が、一人いた。
「なんて退屈なんだ……」
窓枠に頬杖をつき、流れる景色の上に広がる青い空を眺めながらエドワードは大きく息を吐いた。
心底つまらなそうなその声に、向かいの座席に座って本を開いていたアルフォンスが顔を上げる。
「兄さん、そこの本は読み終わったの?」
アルフォンスはエドワードの横に積まれている数冊の本を指し示すが、エドワードは見向きもせず、外を見たままぼそりと答えた。
「とっくに読み終わった……」
「もう一回読んだら? ボク、この本三回目だけど、読むたびに発見があっておもしろいよ」
手にした本を持ち上げてそう提案するアルフォンスを、エドワードはチラリと横目で見る。
「……ここにある本は全部、五回も読んだ」
「じゃ、少し寝たら?」
「……眠くない」
「景色でも眺めれば?」
「……見飽きた」
「じゃあ、たまにはぼんやりと旅を楽しもうよ」
のんびりとしたアルフォンスの言葉にボソボソと答えていたエドワードは、そこでついに声を張りあげた。
「暇なのは性に合わねぇ~っ!」
「結局またそれか……」
今日になってすでに七回も聞いたその叫びに、アルフォンスはやれやれといった感じで肩を竦めたのであった。
列車の中で暇を持て余すエドワード・エルリックは、金色の髪と金色の瞳が印象的な十五歳の少年である。黒い服の上に赤いコートを纏った身体は小柄ではあるが俊敏そうで、きつい眦は生意気そうな雰囲気を醸しだしていた。一見どこにでもいそうな少年だったが、鈍く光る右腕と左足の機械鎧が、少年にしては不釣り合いな重い過去を背負っていることを物語っている。
その向かいに座るアルフォンスはエドワードの弟である。兄よりも遙かに大きな鎧姿という出で立ちだが、実際には鎧の中は空洞で、誰の身体も入っていない。からっぽの青銅色の鎧の内側には血文字が描かれており、その血文字によってアルフォンスの魂は鎧に繋ぎ止められているのだった。
二人は幼い頃に亡くした母を取り戻そうとして、禁忌である人体錬成を行い、失敗した結果、エドワードは左足を、アルフォンスは全身を失ってしまったのである。たった一人の弟を救うため、エドワードはもう一度人体錬成の術を行い、アルフォンスの魂を鎧に繋ぎ止めることができた。しかし、その代償としてエドワードはさらに右腕までも失ったのである。
だが、絶望に打ちひしがれている時間はそう長くはなかった。
すぐに二人は元の身体に戻ろうと固く決意し、エドワードはそのために錬金術の研究機関も特殊文献も自由に使え、高額の研究費とさまざまな特権が手に入る国家錬金術師の資格を取ったのである。
それからというもの、二人は元の身体に戻るための情報を探して旅を続け、今回、その手がかりとなる物質『賢者の石』の資料が中央にあるとの情報を得て、こうして列車に乗っていたのであった。
列車に乗っている間にエドワードが退屈だとぶつぶつ言い、アルフォンスがそれを宥めるという会話は今までの旅でもよく交わされていたが、今回の旅に限ってこのやりとりに新たな人物が加わってきた。
「情けないぞ、エドワード・エルリック」
通路を挟んで反対側の席からそう声をかけてきたのは、軍服姿の大男である。
「そんなことで弱音を吐いているようではこの先が心配である。やはり我が輩がついて来て正解であったな」
外側にカールしている口元の髭を丁寧に撫でつけながら、ふむふむと頷く男はアレックス・ルイ・アームストロングといった。地位は少佐であり、豪腕の錬金術師という二つ名を持つ国家錬金術師である。アルフォンスと比べても見劣りのしない大きな身体に立派な筋肉をつけた男であるが、性格は親切で情に厚く、感激屋で涙もろいという、その姿に似合わない一面を持っていた。
近頃、国家錬金術師の命が狙われるという事件が多発しており、つい先日まで右腕の機械鎧を壊していたエドワードの護衛役として、アームストロングはその任に当たっているのである。エドワードの腕はすでに直っているが、護衛は中央に着くまで続けられることになっており、三人はこうして道行きをともにしているのであった。
だが、自由に行動するのが好きなエドワードにとって、なにかにつけ口を出してくるアームストロングは少々暑苦しい存在だった。
「ずーっと椅子に座って揺られているだけなんて、オレには向いてないの!」
ベッ、と舌を出すエドワードを見て、アルフォンスは苦笑を漏らす。
「確かに静かにしている兄さんなんてらしくないけどね。でも、もうそろそろ中央に着くはずだから我慢してよ。……ですよね、少佐?」
アルフォンスが手持ちの本を閉じて聞くと、アームストロングが大きく頷いた。
「うむ。今、ヒースガルド地方を大きく迂回するようにして走っているところだ。中央駅はその先である。あと少しの辛抱というところだろう」
「ヒースガルド? そっか。この辺りはもうヒースガルド地方に近いんだ」
地名を聞いたアルフォンスは、つまらなそうに頬杖をついているエドワードに向き直る。
「兄さん、覚えてる? ほら、何年か前に一度だけ、師匠と一緒にヒースガルドに行ったことがあるよね」
「ん? ……ああ、そういえばそうだな」
「ほう、ヒースガルドに友人がおるのか」
「いや、師匠の知り合いに会いに行っただけだよ」
アームストロングの問いに、暇つぶしを兼ねてエドワードが答える。
「ヴィルヘルム・エイゼルシュタインっていう錬金術師なんだけど。……少佐ももしかしたら知っているかもな」
「おお! ヴィルヘルム教授! 会ったことはないが名前は聞いたことがあるぞ。十賢とまで呼ばれた錬金術師ではないか?」
「そ。その人」
感嘆の声をあげるアームストロングに、エドワードは頷いた。
国家資格を持っていなくとも、その実力の高さから自然と名前が広まっていく錬金術師たちは数多くいる。そういった一部の高名な錬金術師たちは十賢と呼ばれ、高い技術と深い知識を持つ者として尊敬を集めていた。
とはいっても、十賢という名称の地位があるわけではなく、地域によって挙げられる人物も違い、場合によっては聞いたこともないような者の名前が出ることもある。
しかし、ヴィルヘルム・エイゼルシュタインという名は、錬金術に携わる者ならば知らない者がいないほどの有名な錬金術師であった。
「噂通りですごい錬金術師だったよ。師匠並みに早くて正確な錬成ができたし、いかにも賢者って感じの、穏やかないい人だった」
当時のことを思い出すかのように斜め上に視線を彷徨わせるエドワードの前で、アルフォンスも言う。
「それに教授だけじゃなくて、娘がまたすごかったんですよ」
「娘?」
「ヴィルヘルム教授の娘でセレネっていう子がいたんです。ボクたちと同じくらいの年だったのに、大人顔負けの錬金術を使えたんですよ。今頃きっと、すごい錬金術師になってると思います」
「なるほど。天才少女錬金術師というわけだな」
錬金術師にはなろうと思ってなれるわけではない。それなりの勉強と研究、加えてそれを行えるだけの才能が必要であった。ましてや大人顔負けの技術となると、それはもう天性の才能と言っても良かった。
だが、セレネという少女を褒めるアルフォンスと、それを聞いて感心するアームストロングに対して、エドワードはおもしろくなさそうな表情を作った。
「天才かもしんねえけど、やたら無口で薄情なヤツだったよ。少しは仲良くなれたと思ってたのに、オレたちがダブリスに戻るときに見送りにも来なかったんだからな」
数日間とはいえ一緒に遊べば親近感も湧く。だが、師匠であるイズミの家があるダブリスに戻る日、セレネは顔すらも見せに来なかったのだ。そのとき感じた少しばかりの腹立たしさを口調に乗せたエドワードに、アームストロングが年上らしい言葉を述べた。
「風邪でも引いたのかもしれんぞ。……或いは、別れが言い辛かったのかもしれん」
「まさか。面倒くさくて挨拶する気にならなかっただけじゃないのか?」
「だが、無口な少女だったのだろう?」
「……」
エドワードはそこではじめて、内気で無口なセレネだからこそ、別れを口にできなかったのかも、と考えた。しかし、どちらにしてもすでに思い出になりつつある出来事だ。会ってまで確かめるつもりはなかった。
「ま、どっちにしても昔の話だよ。オレたちにはオレたちの行く先があるし、セレネはセレネで元気でやっているだろう。それでいいさ」
そう言って、肩を竦めたときだった。
耳をつんざかんばかりの音が響き、列車が大きく揺れた。
進行方向に背中を向けて座っていたエドワードは大きく前につんのめる。
「うわわっ!」
前の席に顔を突っ込んでしまったエドワードの横で、なんとか衝撃に耐えたアルフォンスとアームストロングが後ろを振り返った。
「なんだろう、今の。爆発?」
「後ろの方からだな」
列車は一時大きく揺れたものの、そのまま走り続けている。これほどの爆発音が聞こえたにもかかわらず、運転手が緊急停車させないのはおかしかった。
「もしや……」
アームストロングが眉をひそめたとき、車両につけられたスピーカーからガラの悪そうな男の声が聞こえてきた。
「我々は東部人民革命戦線である。この列車は我々が占拠した。繰り返す。我々は東部人民革命戦線である。乗客は大人しく言うことに従え」
「むう。やはり、トレインジャックか」
アームストロングはおもむろに立ち上がる。
このご時世、勝手な政治スローガンを掲げ、強引な行動に出る者たちは珍しくない。そんな時代故か、乗客たちは慣れており、列車内でパニックが起きたような悲鳴は聞こえてこなかった。
しかし、だからといってこのまま見過ごすわけにはいかない。軍人としての職務を果たすべく、アームストロングは腰を上げ、そのまま横を見た。
「……」
視線の先は、隣の座席である。
「兄さん、聞いた? 東部人民革命戦線だって。なんか色々な言葉を切って貼ったような名前だね」
「また新手の過激派かなんかだろ」
爆発の衝撃で座席から転げ落ちたエドワードは、ぶつけた顎先をさすりながら座席に腰をかけ直す。
「世も末だよ、まったく」
再び窓枠に頬杖をついて外の景色を眺めだしたエドワードだったが、首筋に刺さるような視線を感じてゆっくりと振り返った。
「エドワード・エルリックよ、貴殿はなんとかせんのか?」
アームストロングが、じぃっ、とエドワードを見つめていた。
「なんでオレが? 関係ないじゃん」
面倒に巻きこまれるのはごめんだとばかりに、一乗客として事をやり過ごそうとしたエドワードだったが、アームストロングは諦めなかった。
「軍にかかわる者として、ともにトレインジャック犯と戦おうではないか!」
「オレはいいって。中央に着く前に体力を消耗するのは嫌だし」
「先ほどまで、その体力を持て余していたように見えたが?」
「でも、あんな連中なんて、少佐一人で十分でしょ」
「……フッ」
キランと、アームストロングのつぶらな瞳が光った。
豪腕の錬金術師が繰りだす錬成力を認めた故の台詞だったのだが、それは違う意味でアームストロングに自信を持たせたようであった。
「いかにも!」
上着を脱ぎ捨てたアームストロングは、見事な筋肉に覆われた肉体を披露する。
「我が輩は賊どもの蛮行を許しはせん! この豪腕の錬金術師、アレックス・ルイ・アームストロングがいる列車を乗っ取ったのが運の尽き! 賊どもよ、我が輩のこの肉体に恐れをなすが良い!」
盛り上がった二の腕、割れた腹筋、隆々とした背筋を誇示しながら、アームストロングは自信満々に言い放った。
そこへ、銃を持った賊が二人、車両の扉を開けて飛び込んできた。
「やい、てめぇら! 大人しく……うわあっ」
ドスの効いた声で脅しつけながら車両に足を踏み入れた男は、セリフの途中で悲鳴を上げてしまった。
ここに来るまでの車両にいた乗客たちは全員おとなしく座っていた。しかし、この車両では、大男が上半身裸になって、なぜか筋肉を一番美しく見せるポーズを取っている。加えてその隣の座席では、これまた大きな青銅色の鎧が座っているのである。
「な、なんなんだ、おまえら!」
思いもよらなかった光景を目にして男は持っていた銃を落としそうになったが、すぐに銃を構え直す。
「と、とにかく、さっきの放送は聞いたな? この列車は俺たち東部解放連盟が占拠した! 分かったか!」
「さっきの放送と名前が変わってるね」
アルフォンスが座ったままのエドワードに囁く。
「ホント。全く付き合いきれねぇな」
呆れながら頷いたエドワードだったが、すぐにこの状況が初めてではないことに思い当たる。
「……そーいや、前も似たようなことなかったっけ?」
「あったね」
エドワードとアルフォンスは、以前にもトレインジャックされた列車に乗り合わせてしまい、犯人たちとやり合った過去があった。
「もしかして呪われてるかも、オレたち」
がっくりと首を垂れたエドワードに気づいたもう一人の男が、銃をそちらに向けた。
「おい、おまえ! 勝手に喋ってんじゃねえ! おとなしく金目の物を出せ!」
「あん?」
うるさそうに顔を上げたエドワードの小柄な身体を見て、賊たちは筋肉男と鎧よりは命令しやすいと判断したようだ。
「よし、おまえがそこの筋肉男と鎧の持ってる金を集めろ! いいな、チビ!」
あ、と小さく声を上げたのはアルフォンスだった。
アルフォンスの前で、エドワードがゆらりと立ち上がる。
「……チビって言うのは、誰のことだ……?」
歯ぎしりをしながら、エドワードが低い声で問う。その重大な問いの結果がなにをもたらすのか、男たちは知るよしもなかった。
「おまえに決まってんだろ。他に誰がいるんだ、このチビ!」
「!!」
無言のまま頬を引きつらせたエドワードの両手が、パンと合わさった。
「……なんだ?」
その行動を賊たちが訝しむ間もなく、エドワードが飛びだした。
左手を機械鎧の右腕の上に重ねるとバチバチと錬成の光が飛び散る。光が消えたときにはエドワードの右手がハンマーに変化していた。
「だ~れ~が~、ギネス級チビかあぁぁぁ~っ!」
エドワードの怒りの叫びとともに、男の一人が殴られ吹っ飛んだ。
「うわあぁっ!」
窓を突き破って列車から落ちた男は、レール脇の樹木に引っかかる。
「れ、錬金術師か?」
残されたもう一人の男は慌てたようにポケットを探る。しかし、ポケットから目的の物を取り出すことは叶わなかった。
「ぬぅん!」
アームストロングが先ほどまで座っていた座席を拳で叩く。錬成反応の光と空気を振動させるような音が車両内を満たし、それが収まると座席は大きな丸い球に錬成されていた。巨大な木の球はアームストロングが拳で叩いた勢いのまま、他の座席の背もたれをぶち抜きながら飛んでいく。
「ぐあぁっ!」
まっすぐに飛んできた球を食らって、男はポケットに手を入れたまま気絶した。
「……結局巻き込まれちゃったねぇ」
倒れた男の傍らに膝をつき、ケガの度合いを診るアルフォンスの横で、エドワードは溜め息をついた。
「やっぱ呪われてんだ、オレたち……」
「取り憑かれてるんじゃない?」
「は? なにに?」
エドワードは立ち上がったアルフォンスを見上げた。
「だから……」
アルフォンスは目の前の扉に視線を向ける。すると、タイミング良く扉が開いた。
「どうした? なにがあっ……いてっ!」
物音を聞きつけて他の車両から駆けつけて来た賊が、扉の前に立っていたアルフォンスの鎧に頭をぶつける。
「な、なんだ?」
額を押さえながら頭上を振り仰いだ男に、アルフォンスの拳がヒットした。倒れる男を一瞥したあとアルフォンスはエドワードを振り返る。
「だから、こういう人たちに、さ」
「なるほどね」
エドワードは遠くから聞こえてくる足音に顔をしかめながら頷いた。旅を邪魔するトラブルの火種たちはまだまだたくさんいるらしい。
「しゃーない」
エドワードは後ろに立つアームストロングに顔を向ける。
「少佐、後ろの車両を頼むよ。オレたちは前に行く。二手に分かれて賊を片づけちまおう」
「うむ。了解した」
「それと……」
エドワードは、先ほどアームストロングが倒した男のポケットから一枚の紙切れを取り出した。その紙には錬成陣が描かれていた。
男たちがはじめにこれを使わず銃で脅そうとした様子から、錬金術には自信がなかったことが分かる。しかし、そこに描かれた錬成陣はなかなか高度なもので、彼らの仲間にはそれを使いこなせる錬金術師がいるかもしれないことが窺えた。
「過激派の中には錬金術師も混ざってるみたいだし、お互い気をつけるってことで」
エドワードが指先で挟んだ紙を見せると、アームストロングは重々しく頷く。
「肝に銘じよう」
アームストロングが後ろの車両に続く扉の取っ手に手をかけ、エドワードとアルフォンスは前へと続く扉の前に立つ。
「ではな」
「おう!」
三人は肩越しに振り返り顔を見合わせると、トレインジャック犯たちを鎮圧するために目の前の扉を開いた。
山岳地帯にさしかかろうとしていた列車の中で、異変に気がついたのはアルフォンスだった。
「兄さん、なんか列車の行く先が変わってない? さっきまで太陽はこっち側に見えていたのに」
今いる車両を占拠していた賊を倒し終わったアルフォンスは窓の外に顔を向ける。
先ほどまで進行方向右側に見えていた灰色の岩肌と太陽の位置が、いつのまにか変わっていた。
「……本当だ」
エドワードも窓に顔をくっつけて確かめる。
「これじゃ、中央じゃなくてヒースガルドに行くことになるぞ」
おそらく賊たちがレールの分岐点で方向を変えたのだろう。列車は本来ならば通らないはずのルートを走っていた。
「とにかく急いで犯人を捕まえるしかないな。早く中央に行きたいのに、列車の行く先を変えられるのは迷惑だ」
エドワードとアルフォンスは窓から顔を離すと先頭の車両に向かって再び進みだす。
行く先々の車両で待ち受ける賊たちの攻撃に錬金術と格闘で応戦していたエドワードはもうすぐ先頭車両というところで動きを止めた。
「なんだ、これ」
倒した賊が着ていた上着の下に、見慣れた物がついていたのである。
「この模様って……」
男のシャツにはエドワードが身につけている銀時計と同じ、軍の紋章が入ったボタンが付いていた。
「兄さん、まさかこの人って、軍人なの?」
「みたいだな。でもなんで……」
予想もしていなかった事実に二人が首を傾げていると、奥から足音が聞こえてきた。
「ちっ」
エドワードが顔を上げると、十人近い男たちが扉を開けて車両に入ってくるところだった。その中には軍服を着込んだ男たちが数人混ざっている。
「ふん、まあいい。軍人の犯罪者なんてそう珍しくもないだろ。とりあえずあいつらを全員叩きのめして、首謀者を聞き出せばいいだけの話だ」
言うが早いかエドワードは手を合わせ、右腕を鋭い刃に錬成する。
「アル!」
「うん!」
屈んだアルフォンスの肩に足を乗せると、エドワードはそこからジャンプし、座席の上に降り立った。狭い車内の通路では並んで歩くことはできず一対一で戦うしかない。だが、通路で縦一列に並ぶ男たちがろくに動けないのを逆手に取り、エドワードは横から器用に攻撃を仕掛けていった。座席の背もたれの上を飛び越え、網棚を掴んで通路の反対側に大きく飛んでは、その動きについて来られない賊たちを峰打ちで倒す。
「こいつっ! 猿みたいに動きやがって!」
前方の扉の前で仲間がやられるのを歯噛みしながら見ていた軍服の男が、扉の鉄枠に触れた。
身体のどこかに錬成陣が描いてあったのだろう。光が散り、鋭い矢尻がついた槍が現れる。最初にエドワードたちにやられた賊たちとは違う慣れた手つきであった。
エドワードは目を細めるようにして、軍服の男を見定めた。
「あんたのその制服……。国家憲兵だな? なるほど、錬金術もそこそこ使えるってわけだ。それにしても天下の国家憲兵が賊に身を落とすとは驚いたね」
国家憲兵といえば軍の中でも特別な訓練を受けた階級の高い軍人である。錬金術を使え、武術も優れている彼らはいわゆるエリートと呼ばれる者たちであった。
「ふん、ガキになにが分かる!」
ブンと風を切るようにして、男はエドワードに向かって槍を振り下ろした。
だが、エドワードは最年少で国家錬金術師の資格を取るほどの少年である。国家憲兵の技量程度で敵う相手ではなかった。
エドワードは槍を持っている相手の手を素早く掴むと、手加減しながら鳩尾を蹴り上げた。
「うぐうっ!」
鳩尾を押さえ蹲った男の前に、エドワードは立つ。
「さあて、それじゃさっそく、国家憲兵がトレインジャックなんかしたわけを聞かせてもらおうかな」
「まさか単純な強盗目的なんかじゃないよね?」
他の賊たちを倒し終わったアルフォンスも男を見下ろす。
「……く、くそ…。誰が、誰がおまえみたいなクソガキに言うものか!」
エリートであるはずの自分が子供に負けたことがよほど悔しいのだろう。男はせめて言いなりにはなるまいと、エドワードを憎らしげに睨んだ。
だが、そんなやりとりに慣れているエドワードは遠慮無く、刃となっている右腕を男の首に突きつける。
「じゃ、まずはそんな悪態をつくことができないようにするしかないな」
茫洋とした言い方ながら、右腕の切っ先はまっすぐに喉に向いている。その微動だにしない刃が、エドワードの踏んできた場数を物語っていた。
「や、やめてくれ! 分かった、言う! 言うから…っ」
男は首をチクチクと突く刃から逃げようと、身体を引きながら両手を振った。
「俺はただ、軍から逃げていただけなんだ!」
エドワードとアルフォンスは互いに目を合わせ、それから目の前の男を見下ろす。
「……軍からだって? なにをしでかしたんだ」
「早めに自首した方がいいよ」
軍に追いかけられているということは悪事をしたからに他ならない。そう思ったエドワードとアルフォンスだが、男は何度も横に首を振った。
「違う! 俺はなにもしていない! だが、誰かに無実の罪を着せられて、仕方なく逃げていたんだ! 本当だ!」
「だったら逃げないで、そう言えばいいじゃないか」
「言った! だが、いつのまにか俺の隊全員に逮捕状が出ていて弁解する時間も場所もなくなっていたんだ! これは誰かの陰謀だ!」
「隊の全員に逮捕状?」
なにやら思ってもいない方向に話が転がりだしたのを感じて、エドワードは男の前に屈み込む。
「どういうことだ?」
「途中で仲間になった何人かを除けば、俺たちは全員同じ部隊の錬金術師だ。国家資格は持っていないが、いずれ取ることを目指していた仲間たちなんだ。だが、隊長の俺を含めて、新人の隊員までもがいきなり無実の罪で追われる羽目になってしまった……。俺たちは誓って潔白なのに!」
「隊の人全員に、無実の罪、ねえ」
必死になって答える男の様子からは嘘をついているようには見えなかった。
「けど、トレインジャックをした今は無実とは言えねーだろ。しかも金目の物まで盗ろうとしてさ」
アルフォンスも同じように思ったのだろう。同情を込めた声で男に尋ねる。
「そうだよ。どうしてこんなことしたの? 他の方法もあっただろうに」
すると男は項垂れた。
「俺だってもっと穏便にすませたかった。だが、ヒースガルドに行くためにはこうするしか……」
「やっぱりヒースガルドに行くつもりだったのか。でもどうしてだ?」
ヒースガルドは中央へ向かうこの列車が止まらないほどの小さな町である。そんな町にトレインジャックをしてまで行こうとする理由がエドワードには分からなかった。
だが、男にはヒースガルドでなければいけない理由があったらしい。
「唯一、俺たちの味方をしてくれた上官のガンツ上級大佐に、ヒースガルドでは今、錬金術師を集めているからそこに行け、と言われたんだ。たとえ罪を背負った者でも錬金術師であれば町の指導者が匿ってくれる、と。……だが、俺たちは手配中の身だ。ヒースガルドに行くにはトレインジャックを決行するしかなかったんだ。金目の物を盗ったのだって、これからしばらくの間、ヒースガルドで隠れて生きるために仕方なく……」
すべてを話し終わった男は、疲れたように床に手をついた。
「ふうん。そういう事情だったわけね。……けど、ヒースガルドに錬金術師を集めているなんて話は聞いたこともないな」
「しかも法を破った人まで匿ってくれる人物がいるなんてねぇ……」
首を傾げるエドワードとアルフォンスだったが、男はそんな二人にその人物の名前を告げた。
「詳しいことは知らないが、国中から錬金術師を集めている町の指導者は、ヴィルヘルム・エイゼルシュタイン教授だって話だ」
項垂れたままの男が言った名前に、エドワードとアルフォンスは驚いた。
「なんだって?」
「ヴィルヘルム教授って、まさか……!」
それはつい先ほどアームストロングにも話した、男の名前であった。
「一体どういうこと? 錬金術師を集めてるっていったいなんのために?」
「オレにもサッパリだ。そもそも本当にあのヴィルヘルム教授なのか…?」
二人の記憶の中のヴィルヘルム教授は、静かな声と落ち着いた物腰を持つ、とても思慮深い人物だった。その教授が犯罪者まがいの男たちを集め、町で受け入れているなど、エドワードとアルフォンスにはとても信じられなかった。
話に気を取られたエドワードたちが隙を見せたそのとき、男が突然立ち上がった。
「とにかく俺は逃げてみせる…! ガンツ上級大佐に指示を仰がなくては!」
男は走りだすと、先頭車両に繋がる扉の向こうに消えていく。
「あ! 兄さん!」
「しまった! 待ちやがれ!」
無実の罪だろうがなんであろうが、彼らを野放しにしては自分たちが中央へ辿り着けない。エドワードとアルフォンスはすぐに追いかける。
扉を開けるとそこは先頭の機関車と繋がる連結部分であった。機関車内部に出入りする扉の横には、屋根へと続く梯子がかかっており、男が扉と梯子のどちらに進んだかは分からない。
風に舞う前髪を払いながら、エドワードはアルフォンスに二手に分かれようと提案しかける。しかし、口を開く前に機関車の上で光が瞬いた。
「!?」
上を向いたエドワードとアルフォンスの視界に光の中に浮かぶ人影が映った。人影は二人の足下に落ち、大きくバウンドしたあと動かなくなる。
「……!」
苦しそうな表情のまま気を失っていたのは、二人が追いかけていた男だった。服はボロボロになっており、合間から覗く肌の上には太い鞭で打たれたような幾筋もの痣がついている。
先ほどの光は明らかに錬成反応のものだった。
「兄さん!」
「ああ……!」
アルフォンスが手を組み、エドワードはそこに足を乗せる。
「それっ!」
大きく上に放り投げられ、エドワードは機関車の屋根へと飛び乗った。
風を全身に感じながら着地して顔を上げると、機関車の屋根の上に黒い軍服に身を包んだ男が座っていた。
エドワードは、ニヤニヤしながら葉巻を吸っているその男の制服と階級章が国家憲兵上級大佐のものであることに気づく。
「……おい、あんた。ひょっとしてガンツって奴だな」
「くっくっく……。だとしたらどうだって言うんだ小僧」
男が低く笑った。
エドワードが現れ、アルフォンスがあとから梯子を登ってきても、男は葉巻を吸うのをやめなかった。そのふてぶてしい態度にエドワードはこの男が主謀者だと直感する。
「おまえが部下をそそのかせてヒースガルドに向かわせた本当の黒幕ってわけだな。どういうことか、キッチリ聞かせてもらおうじゃないか」
すると男は葉巻を銜えたまま、唇の脇から煙を吐き出した。
「けっ。さっきの奴が喋ったのか。…だが、これ以上おまえらが知ることはねぇ」
機関車から流れる黒い煤に混じって葉巻の匂いがエドワードの元にも届く。嫌そうに眉をしかめたエドワードを眺めながら、男が立ち上がった。
身長も、胸板も、肩幅もあるごつい身体だった。黒い軍服のボタンは留めておらず、その下のシャツは筋肉に沿って盛り上がっている。茶色の髪は頭頂部で上に立てられ、襟足部分の長い髪は後ろで三つ編みとなって風に揺れていた。
なにより目立つのはその左腕だった。
ガンツの左腕はエドワードと同じ機械鎧であったが、それはエドワードの頑丈でありながらも器用そうなフォルムと違って、生身の右腕にくらべて異様なまでに大きな機械鎧だった。二の腕から手首は幅の広い一枚の鉄甲で覆われ、迷彩色と錬成陣が施されている。指先に当たる部分には五本のかぎ爪が付けられ、鈍く光を放っていた。
「おまえらにはここで死んでもらうぜ。だが、せめて冥土の土産に俺様の名前だけは教えといてやる」
男は葉巻を捨てると、高々と言い放った。
「軍最強の錬金術の使い手『徹甲の錬金術師』ガンツ・ブレスローとは俺様のことよ!」
言いながら、ガンツは左腕を大きく振りかぶった。錬成陣が光り、振り下ろされた左手のかぎ爪が触手のように伸びる。
「徹甲の錬金術師なんて二つ名、聞いたことねえな!」
エドワードは足下を抉る触手を難なく避けると、右腕を刃へと錬成した。
「どうせそうやって自分を偉そうに呼ぶ奴ほど、大したことねぇんだよ!」
ガンツの懐に飛び込むと、エドワードは腕を水平に薙ぎ払う。ぶつかった金属同士が悲鳴を上げた。
「ん? おまえの右腕……。まさか小僧、あの鋼の錬金術師エドワード・エルリックか? そうか? そうなのか! はーっはっは!」
エドワードの一撃を防いだガンツの瞳がギラギラと光りだした。
「会いたかったぞ。鋼の錬金術師! 俺の左腕とおまえの右腕、どっちが『フルメタル』の名を冠するに相応しいかここでハッキリさせようじゃないか! といっても、最強はこの俺だがな!」
挑発するように笑ったガンツに、エドワードは呆れたような視線を向ける。
「はあ? 最強? くだらねえの」
エドワードは強さを誇示するためだけの勝負になど興味がなかった。だが、勝負にこだわるガンツは再び腕を振り上げる。
「俺と勝負しろぉっ!」
勢いよく伸びてきた触手がエドワードの眼前に迫る。機関車の屋根から錬成した壁で触手を防ぐと、エドワードはその壁を蹴って後ろへ跳んだ。
「なんだ、俺が怖いのか? はははははっ!」
ガンツは嘲笑しながら、さらに遠くに逃げるエドワードに触手を伸ばす。
「逃げてばかりじゃ退屈だぜ!」
「逃げてねえよ!」
エドワードが突然ガンツの元へとダッシュした。
「な……!」
いきなり方向転換をして迫ってくるエドワードを見て、ガンツは慌てて触手を戻そうと手を振り上げた。だが、遠くに伸びきった触手はすぐには戻らない。
ガンツの目の前で、エドワードが言った。
「最強を語るよりも、まずは少しくらい頭使えば?」
エドワードはパンと手を叩いて、右腕をいつもの腕に戻すと拳を固める。
「おまえ相手に錬金術を使う気にもなれねぇよ!」
先ほど機械鎧の腕同士でぶつかり合ったときに入れておいた、ガンツの肩の亀裂目がけて、エドワードは思いきり拳を叩きつけた。
「ぐあああああ!」
殴られた左肩を抱えるようにして、ガンツが後ろに下がる。生身と機械鎧の左腕を繋ぐ部分が壊されたのだろう。部品がいくつも零れ落ち、その上に血が垂れた。
「バカな……! この俺が…誰にも負けたことのない最強の俺が…!」
信じられない、とばかりに目を見開くガンツの前で、エドワードは飄々と言う。
「これで分かってもらえたかな? 格の違いってヤツをさ」
兄の邪魔にならないよう、後ろで見ていたアルフォンスもあまりのあっけなさに呆れたように呟く。
「勝負にもならなかったね。これで最強を自称するなんて……」
「これまで楽に人生を生きてきたんだよ、きっと」
掌を上に向けてバカにしたように首を振るエドワードの仕草を見て、ガンツが怒りに震えながら身体を起こす。
「きっさまらぁー……っ、あ、あ、あぁ~っ」
しかし、怒声は途中で痛みに耐える呻きに変わっていった。ガンツはぎりぎりと歯を合わせてエドワードとアルフォンスを睨んだ。
「ぐ……ぐぅぅ~! これで勝ったと思うなよ。今度会ったときはギタギタにのしてやるからな!」
あまりにもありきたりな台詞に、エドワードは心底呆れる。
「そんな陳腐なことしか言えない奴は覚えられないな。ついでに最近のオレは物忘れが激しくってねぇ」
「そだね」
しつこいガンツに対してわざとそう言ったにもかかわらず、神妙な声で頷いたアルフォンスをエドワードはくわっと目をむいて見上げる。
そんな二人の前で、ガンツが列車の脇へと身体をズラした。逃げようとするその姿勢を見て、アルフォンスが慌てる。
「あ、兄さん! あいつ逃げるよ!」
「放っておけって。あんな奴、この先なんにもできはしねぇよ。しっかし、あんなのが黒幕だったなんて拍子抜けだぜ……」
「く……この……っ」
ここでガンツがなにも言わずに退散すればそれで良かった。だが、そういうときほど、人は一言多く、そして言ってはいけない言葉を口にしてしまう。
悔しさに顔を歪めながら、ガンツは最後の捨て台詞を吐いた。
「覚えてろ、クソチビ!」
「!!!!!!」
次の瞬間、先ほどまで敵に同情すら見せていたエドワードの表情が激変する。
「だ~れ~が~、豆粒ドチビかあーぁっ!」
かつてないほどの早さで機関車の一部から巨大な大砲を錬成すると、エドワードはためらいもせずにガンツに向かって撃ち放った。
しかし、怒りに任せたその球は狙いが甘くなり、ガンツは簡単に身をかわすと列車から飛び降りてしまった。 目標物を失った球は、慣性の法則にのっとって前へ飛び、その先にあるトンネルへと吸い込まれていく。
「あ」
ドカーン、と衝撃音が山々に響き渡り、今まさに進入しようとしていたトンネルからもうもうと煙が溢れでてきた。
「ヤバ……!」
我に返ったエドワードは斜め後ろにいるアルフォンスに縋るような視線を送る。だが、アルフォンスには大きく溜め息をついて首を振ることしかできなかった。
トンネルに半分突っ込んで止まった列車は、後方の車両を夕日に、前方を炎に照らされながらレールの上で傾いていた。
「……派手にやっちゃったねぇ」
トンネル手前でアルフォンスがしみじみ言うと、後ろで瓦礫を片付けていたエドワードがげんなりとした顔をする。
「……の割に、ガンツには玉は当たらなかったし、トンネルは壊れるし……」
エドワードは脱線した列車とその周りにいる乗客を眺める。
食堂車から上がった火はすでに鎮火しつつあり、乗客たちもすり傷を作った者がいる程度ですんだ。火薬を仕込んだ大砲ではなかったことに加えて、トンネル手前の大きなカーブでスピードが落ちていたのが幸いした。さらに、過激派に拘束されていた運転手が、エドワーたちが暴れたことによって隙を見つけ、自らが運転レバーを握ってうまく列車を止めたのが良かった。
エドワードたちのお手柄でこの程度ですんだといっても良いのだが、それでもエドワードはせめてもの罪滅ぼしとして、片づけや乗客の誘導を行っていたのである。
「……さて、と。ボクたちがお手伝いできることはもう無いみたいだね」
兄とともに乗客の荷物を運んだりしていたアルフォンスは、一段落してからエドワードを振りかえった。
「これからどうする、兄さん?」
「ここにいても仕方ない。中央へ行くに決まってんだろ」
元のからだに戻ることが最優先であり、そのための手がかりを求めて中央に行かなければならないのだ。
二人が列車を使わずに中央へ行く手段を検討していると、トンネルの奥からアームストロングが現れた。
「あ、少佐」
額についた煤をハンカチで丁寧に拭いながら、アームストロングはエドワードとアルフォンスの元にやってくる。
「おぬしたちが聞いたトレインジャック犯人についての情報は、すべて中央に連絡してきた。救援もすぐに来てくれるそうだ」
担当した後部車両では雑魚しかいなかったため、事故の詳細と首謀者をエドワードたちから聞いたアームストロングは、急いでその詳細をトンネル内部にある非常用の電話を使って軍に報告してきたのであった。
「しかし、一体なんのために国家憲兵たちをヒースガルドに向かわせたのか……。さらにこんな惨状まで引き起こすとは……! 許すまじきガンツ! 己の逃亡のために汽車をむりやり脱線させてしまうとはなんたる悪行!」
アームストロングは拳を震わせる。
「あは……ははは……」
不可抗力だったとはいえ、その悪行の責任の一端を自覚していたエドワードはなんとも言えない笑いでごまかすしかなかった。
「……兄さん、訂正しなくていいの?」
小声でアルフォンスが耳打ちしてきたが、エドワードはそれを素早く遮った。
「いいんだよ! ガンツのせいであることには変わりねぇんだから!」
「まぁ、そう言えなくもないけどねぇ……」
アルフォンスは軽く肩を竦めてから、アームストロングの方を向く。
「誘導や荷物の運び出し、ケガ人の手当ては終わりました。……で、あの、ボクたち中央に向かいたいんですけど、どうすれば……」
「この列車は当分動けん。ここから一番近い駅はヒースガルドになるが……」
「よし行こう!」
すぐさまエドワードは足元のトランクも持つ。だが、それをアームストロングが止めた。
「ちょっと待て。我輩はここを離れるわけにはいかんぞ。本部への追加報告、逮捕者の拘束、乗客の保護に復旧作業までの現場保存。軍人としてやらねばならんことが山積みだ」
目下の仕事はエドワードの護衛であるが、一般市民を助ける職業についている者として、この場を立ち去ることはできないのであろう。また、救援が来るまでの間くらい、エドワードたちもおとなしくしていると思ったのかもしれない。
だが、エドワードはアームストロングの思っていた以上に素早い行動力の持ち主だった。
「じゃ、オレたちだけでも先に行ってるから」
元々護衛をうざったく思っていたエドワードは、チャンスとばかりにダッと走り出す。
「むっ!? 待て! 待たんか! 護衛役である我輩と別行動を取ることはならん!」
「こんな山奥で護衛が必要なほど危険なことなんてねーよ。それよりオレたちは一日でも早く中央に行きたいんだ。じゃな!」
「こら!」
止めようとするアームストロングに一礼すると、アルフォンスも兄に続く。
「ごめんなさい少佐。でも、本当に心配しなくていいですから」
「ならんと言っているだろう! 二人とも大人しく我輩と一緒にいるのだ! 行くではない! エドワード・エルリックー!」
しかし、事故現場に残ろうとする使命感と、追いかけなくてはという思いのは板ハ挟みになって出遅れたアームストロングを置いて、エドワードとアルフォンスはあっという間にトンネル脇の山道へと走り去ってしまった。
「うぬぅ! なんと素早いのだ……!」
列車の旅が暇だと喚いたかと思えば、トレインジャック犯の鎮圧など自分には関係ないと突っぱね、今度は中央には先に行くからと、さっさと走り去る。
精神的なフットワークの軽さを持つエドワードに、アレックスは振り回されてばかりである。
「我輩としたことが護衛すべき相手に逃げられるとは……!」
アームストロングは額を抑えて大きく唸ったのであった。
壊れたトンネルを出て山道に入ると、エドワードとアルフォンスはその先にある谷を渡る鉄橋の端まで一気に走った。
「……よし、ここまで来れば追いかけてこないだろ」
エドワードは後ろから誰も追ってこないと分かると、走るのを止めた。
「少佐には悪かったけど、足止めされたら時間がもったいないもんね」
「あたりまえだよ。元の身体に戻れるかもしれない資料を目の前に、グズグズしてられっか。さ、行こうぜ」
元の身体に戻るための情報は今までもたくさんあった。しかし、今回はその中でも一番有力と思われる情報を手にしているのである。エドワードとアルフォンスはそれを確かめるために、一刻も早く中央へ行きたいのであった。
二人は谷に架けられた鉄橋の上に立つと、反対側から列車が来ないことを確認してから歩きだす。
鉄橋の下は険しい谷で、枕木の合間からは冷たい風が吹き上げている。しかし、それにふらつくことなく、二人は枕木と枕木の間を器用に渡っていった。
真横から照らす夕日が、エドワードとその少し後ろを歩くアルフォンスの身体を紅く染めていく。
「きれいだねぇ」
アルフォンスは足を止めると、ひときわ美しいオレンジ色の太陽を眺めた。まっすぐに伸びる光線は山々を照らし、その山の一つに、向かっているヒースガルドの町があるはずだった。
「列車の中で話題にしたとはいえ、まさか本当にヒースガルドに行くことになるなんて思わなかったね」
アルフォンスは止めていた足を踏みだしながら、エドワードに話し掛ける。
「ねぇ、兄さん。せkっかうヒースガルドに行くんだからついでにヴィルヘルム教授に会いに行こうよ。あの穏やかな教授が罪を犯した者まで匿ってるっていうのは、さすがに嘘だと思うけど、トレインジャック犯が錬金術師を集めている人物として教授の名前を出したのは、ちょっと気にならない?」
昔一度行ったきりの町とはいえ、エイゼルシュタイン家の場所は覚えている。駅に行く途中に寄るくらいならいいだろうと思ったのだが、エドワードは首を振ってその提案を却下した。
「行ってどうすんだよ。教授が錬金術師を集めてるってのも、おおかた有能な助手が欲しくて募ってるとかそんな理由だろ。よくは知らないけど、教授がやっていた触媒法とかいう研究はやたら難しいらしいし」
「難しいって……。そっか、教授は『賢者の触媒』を作ろうとしているんだっけ?」
『賢者の触媒』は『賢者の石』と同じく、あらゆる法則に縛られずに錬金術を行えるだろうと言われる幻の物質である。ヴィルヘルムは、その幻の物質を完成させようとしている研究者なのである。
アルフォンスは触媒法研究の第一人者であるヴィルヘルムが、研究には助手が不可欠なのについてこれる者がいない、と零してしたことを思い出す。
「そういえば、助手をできる者が一人もいないからって、セレネが手伝ってたくらいだったね」
「だろ? セレネの奴、研究室に籠もってばっかりだったじゃないか」
二人は、一度だけヴィルヘルムの研究室に入ったことがあった。数々の試験管と大量の蔵書、そして何十年間分ものレポートが積まれた研究室では、ヴィルヘルムの娘、セレネがしょっちゅう手伝いをしていた。
背中まで伸びたセレネの長い銀髪が研究室の中を行き来し、赤みがかった茶色い瞳が、蔵書にかかれた文字の羅列を一心不乱に追う姿を、エドワードとアルフォンスはよく覚えている。
エドワードと同じ年の頃でありながら、白いワンピースの裾が汚れるのにも気にせず研究室に閉じこもるセレネとは、なかなか会話の視点が見つからなかった。とりあえず錬金術の話題を振ってみると、聞いたこともない単語ばかりが返ってきて、エドワードとアルフォンスはその知識の多さに圧倒されたのである。
「あのときも思ったけど、教授の研究を手伝えるセレネはやっぱり天才だよね。十二歳で国家錬金術師の資格を取った兄さんと一緒だ」
天賦の才能を持つ二人に尊敬の念を込めてアルフォンスはそう言う。
「兄さんは、同じ天才のセレネが、どんな錬金術師になったか興味はない? 教授が錬金術師を集めてるのは別としても、久しぶりに会いに行くだけならいいじゃない?」
だが、エドワードは頑なに拒否をする。
「行かないったら、行かねーよ。それにオレにはセレネと話すことなんかない」
「もう、頑固だなあ」
どうやらエドワードは、セレネが見送りに来なかったことをいまだに気にしているらしい。そう思ってアルフォンスは笑ってしまう。
「兄さんてば、まだこだわってるの? だったら、セレネに会って仲直りだけでもしてくればいいじゃない」
鉄橋を渡り切り、崖に挟まれた山道を先に進む兄の背中にアルフォンスが言うと、エドワードがくるりと振り返った。
「違う!」
エドワードはアルフォンスを見上げ、人差し指を突きつける。
「忘れたのか! 教授は師匠と友達なんだぞ!」
その一言と、突きつけられた人差し指の僅かな震えを見て、アルフォンスは、あ、と声を上げた。
硬直したアルフォンスの目の前でエドワードは続ける。
「のこのこ会いに行ったらどうなるか考えてみろ! 教授ほどの人ならオレたちの身体を目にしただけで、禁忌の人体練成を試みたことを見抜くかもしれない。それで……それでもし、そのことを師匠に報告なんかされてみろ。そうなったら、オレたちは……」
「そ、そうなったら、ボクたち……」
エドワードの人差し指の震えが大きくなり、それを見ていたアルフォンスの声も震えだす。
二人はヴィルヘルムが人体練成のことを師匠のイズミに話し、それに怒ったイズミが自分たちに行うであろう鉄拳制裁を想像して硬直した。
「「……殺されるッ……!」」
同時に言った二人の声は、恐怖のあまり裏返っていた。
師匠であるイズミは、竹を割ったようなさばさばした性格と、深い思いやりを持つ女性である。だが、そのイズミの主義は『経験に勝る知識なし』『精神を鍛えるにはまず肉体から』というもので、エドワードたちは無人島に放り込まれ、毎日のように厳しい修行をさせられ、それに口答えした際には拳で殴られる、という体験までしていた。
エドワードとアルフォンスにとっては、尊敬と同時に大きな恐怖を感じる存在なのである。
「オレが教授の家に寄りたがらない理由がわかっただろ?」
「そ、そうだね。会わないほうがいいよね!」
「ここを通り抜ければヒースガルドまでもうすぐだ。町に着いたらまっすぐ駅に向かうからな!」
「うん」
エドワードは想像してしまったイズミの拳の強さを忘れようと足を早め、アルフォンスもそれに続こうとする。しかし、カツン、という金属音にアルフォンスは動きを止めた。
「……あれ? なんだろ?」
足元を見ると、鎧に当たった小石が地面に転がる所だった。
「ねぇ、兄さん」
石が落ちてくるから気をつけて、と言おうとしたアルフォンスの目の前で、エドワードの頭の上に石が落ちた。
「~~~~~~っ!」
第一章 降ってきた厄災(B) に続く・・・
© Rakuten Group, Inc.