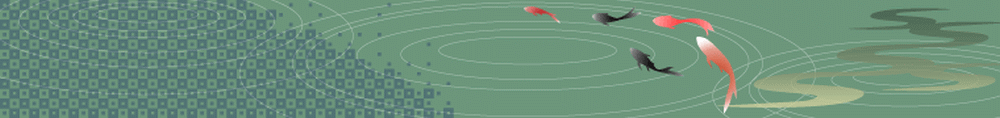[歴史・考古学] カテゴリの記事
全131件 (131件中 1-50件目)
-

宣伝です
最近(ここ2年間以内)自分が関わった本の宣伝です(間接的な協力も含む)。
2015年10月22日
コメント(0)
-
考古学のニュース
最近ご無沙汰していた考古学関係のニュース紹介。といっても自分の興味関心に従って選んでいるので西アジア限定、しかも時代もニュースソースサイトも限られていますが。1.「塩人間」発見の鉱山の操業停止が決定。 オーストリアとイタリアの国境の高山氷河で発見された「アイスマン(氷人間)」は有名だが、イランのザンジャンという所では15年ほど前に「塩人間」(真空カプセルに保存されているが、首だけなので結構えぐい)なるものが発見され話題になった。テヘランの北西25kmにある岩塩鉱山からはおよそ1700年前のものとみられる人間の遺体が見つかったが、塩分のおかげでミイラ化し、髪の毛や耳たぶの金のイヤリングの穴はもちろん、羊毛などの持ち物もしっかりと残っていた。 見つかった遺体数は6人分になり、研究者は採掘の停止と遺跡としての保存を求めていたが、イラン鉱業省は2007年にも操業の10年延長を決めていたが、急転して採掘中止と遺跡公園としての保存が決まったという。 それはいいのだが、結局この遺体になった人たちはこんな山の中で何をしていたのだろうか?岩塩を採掘していたのだろうか。似たような塩漬けミイラの例はオーストリアのハルシュタット(ヨーロッパの鉄器時代の示準遺跡として有名)やデュルンベルクなどにもある。2.「最古のヘブライ文字」見つかる? 僕も今年の夏はイスラエルでの調査に参加したが、そのイスラエルからのニュース。エルサレム近郊のエラーで調査しているヘブライ大学のヨセフ・ガーフィンケル氏らは、紀元前1000年頃の土器に(墨で?)書かれた「最古のヘブライ文字」を発見したという。土器の年代は一緒に出土したオリーブだかブドウだかの放射性炭素年代で測定したそうだ。5行にわたる文面はきわめて短く、判読も難しいようだが、「王」「奴隷」「士師」などの言葉が読み取れるという。 それは結構なのだが、当時はヘブライ文字もアラム文字もフェニキア文字も分化していなかったのではないかと思ったりするのだが、同氏によると、ヘブライ語でしか使われない動詞とかが文中に登場するのだという。へえ。もちろんこの意見に不承諾の学者も多い。 このチームが調査しているエラーの砦の遺跡は、当時統一国家形成に向かっていたイスラエルと、その最強の敵であるペリシテ人の領域の境にあり、有名なダビデとゴリアテの一騎打ちもここで行われたそうなのだが、最近もこの調査団の「旧約聖書の記述通りの、2つの城門がこの遺跡から発見された」というニュースがある。聖書にあまり興味のない僕には「はあそうですか」としか言えないのだが。3.フェニキア人のDNA ベイルート大学の研究チームが、現在の地中海沿岸諸国に住む人から採取したDNAを分析したところ、17人に一人からフェニキア人のDNAが発見されたという。聖書の記述どうこうはともかく、こういう「フェニキア人の島女房」みたいな下世話なニュースは僕も好きですな。 まあフェニキア人の交易活動を考えれば当たり前と言えば当たり前のニュースだが、地域により濃淡(出現頻度の高低?)があって、フェニキア人の故地であるレバノンはもちろんだが、キプロス、スペイン、シチリア島、モロッコでは濃く、イタリア本土、ギリシャ、チュニジアでは割合薄いようだ。あれ?チュニジアにはカルタゴがあったのに、ローマ帝国に皆殺しか売り飛ばされたせいかな? モロッコではフェニキアの遺跡はまだあまり調査されておらず、僕の知り合い(ドイツ人)などドイツ考古学研究所がモロッコでの調査を進めているところだが、DNAからはフェニキア人の大西洋進出が先に裏付けられたことになる。ところでこの手のニュースでいつも思うんだけど、このDNAの拡散がどうしてフェニキア人に帰されるのだろうか?アラブの大征服とかオスマン帝国の遠征による移住の結果とは関係ないのかな?4.アッシリア総督の宮殿を発見! アッシリア帝国というと、紀元前7世紀に西アジアをほぼ統一した史上最初の大帝国だが(その分滅亡も早かった)、その総督のものと思われる宮殿がトルコ南西部ディヤルバクル県のズィヤーレット・テペにおけるトルコ・アメリカなどの合同調査により発見された。 アッシリア粘土板文書?の記録によると、紀元前882年、アッシュルナシルパル2世の治世、この地にはトゥシャンという名の総督がいたことが伝わっているが、その記録よろしく壁画が描かれ床暖房施設を備えた豪華な宮殿、そして銅製の容器20点などが発見されたという。また墓も見つかっており、印章や象牙製品、装身具などが豊富に副葬されており、匹敵する類例はアッシリア本国(今のイラク北部)のアッシュルやニムルードに限られるという。5.カトナでまたまた大発見 シリアのテル・ミショルフェ遺跡(古代名カトナ)では、ドイツのチュービンゲン大学による再調査ですでに未盗掘の王墓から豪華な副葬品などが発見されている(シリア、イタリアとの合同調査だが、いいものはドイツ隊の担当部分からばかり出て来るので紛争になっていると聞く)。僕もドイツ隊による発見についての講演を聴いたことがあり、来年10月からシュトゥットガルトにあるヴュルテンベルク州立博物館で特別展が予定されている。 今年の調査では最近(1980年代)まで人が住んでいたミショルフェ村の民家の下に眠る青銅器時代(紀元前1400年頃)の宮殿(王墓はその一角の地下室から発見された)が調査された。宮殿の壁は、極めて稀なことであるが高さ5m以上も残っており、また二階分の床が崩落して堆積していることが確認された。つまり少なくともこの宮殿は三階建てであり、その高さの日干し煉瓦(西アジアでは木材は貴重品である)建築物の重量を支えるには少なくとも深さ3m以上の地下基礎壁が必要になるという。またこの宮殿跡からは完全に残っている部屋のアーチ状の入口や、宮殿内の井戸に落ち込んだ木製の梁材が腐らずに保存された状態で発見された。梁材はほぞ穴まで残る遺存状態である。 また面白いのはこの宮殿の一室からゾウの骨が発見されていることで、おそらくカトナ王の狩りの成果を誇示するため展示された、あるいは王の宴会の料理として出された可能性があるという。シベリアの氷漬けマンモスの試食の限りでは、象の肉はあまり美味しくないということだが。今でこそシリアの多くは乾燥地帯で、大型野生獣は生息していないが、青銅器時代までは湿地帯などにゾウの一種(アフリカゾウやアジアゾウとは別種らしい)が生息し、エジプトのファラオなどが狩りに来ていたという。象牙目当ての人間による狩猟や気候の変化で、シリアゾウはその後間もなく絶滅した。6.ヒッタイト帝国の都の調査 ステップ地帯の交易都市として栄えたカトナ(上記)を紀元前1340年頃に滅ぼしたのは、北から攻め込んできたヒッタイト帝国だったが、その都ハットゥッシャは現在のトルコ中部、ボアズキョイの遺跡にあたる。 1906年以来ドイツ隊による発掘調査が進められ(本格的な考古学調査は1932年から)、五代目にあたる現在の発掘隊長は僕の知り合いである(同時期に同じ大学にいた)。今年の調査では紀元前1300年頃の建物の火災層の下から70点以上の完全な土器が発見されたという。 それ自体も珍しいことだが、土器の器形そのものもかなり異様なものである。写真右端の壺、なんだこれ?注ぎ口から下の部分だけ見れば、ヒッタイトの遺跡にはよくあるタイプの壺(水差し)だが、注ぎ口の部分の牛の頭は異様である。おそらく注ぎ口は牛の口にあたる小さな穴だけだと思うが、肝心の中身(水、ビールなどなど)はどうやって中に入れるのだろう?それとも日本の埴輪のように置いていただけなのだろうか。
2008年11月26日
コメント(2)
-
ウズベキスタン 1:1 日本
日本代表だめかもしれんね。・・・・・・・ 僕は多年トルコに行き来しているが、そこで「日本人か?」と聞かれることは最早ほとんどなく、大抵東南アジアか中央アジアの国名が挙がる。トルコ人とは似ても似つかない僕のモンゴロイド顔からそうした地域が挙がるのだろうが、東南アジアは僕が日に焼けて黒くなっているせいとして、中央アジアのほうは僕の話す流暢だがやや拙いトルコ語のせいだろうか。中央アジアにはトルコ語と同系統の言語を話す民族が広く分布している。 特に「オズベキ」に似ていると言われたことが何度かある。「オズベキ」とは日本では通例「ウズベク」と称される、中央アジアのウズベク人のことである。トルコ人にとって最も身近なモンゴロイドの代表が、ウズベク人なのだろうか。 ウズベキスタン共和国は、サッカー日本代表の国際試合などで耳にするほかは、日本人にとって馴染みが薄い。この国は隣接する中央アジアの国々(トルクメニスタン、カザフスタン、キルギス、タジキスタン)とともに1991年にソヴィエト連邦から独立した。「一衣帯水」という言葉があるが、内陸国であるこの国は隣国(旧ソ連諸国とアフガニスタン)も全て内陸国という稀有な二重内陸国で、そういう意味では島国の日本から最も「遠い」かもしれない。 ウズベキスタンは面積44万平方キロ(日本の1.1倍)で、世界で4番目に大きい湖だったアラル海から、中国の国境に程近いフェルガナ盆地までの東西120kmに及ぶ国土がある。その多くはキジルクム(「赤い砂」)など砂漠に覆われているが、アラル海に注ぐアム川沿いや、点在するオアシス、そしてフェルガナ盆地などは対照的に肥沃であり、人口2700万と中央アジア諸国で最多の人口を擁する。国民の約4割が18歳以下ときわめて「若い」国でもある。 「ウズベキスタン」という国名は「ウズベク人の国」という意味だが(ウズベク人は少数民族として中国やアフガニスタンにも居る)、ウズベク人は全国民の7割程で、かつてのロシア帝国やソ連支配の名残でロシア人が5%いる。またウズベキスタンの西端1/3はカラカルパク自治共和国となっているが、同じトルコ系ながらウズベク人よりモンゴロイド形質が強いカラカルパク人は、国民全体の2%に過ぎない。 東部のフェルガナ地方では、旧ソ連時代に画定された隣国タジキスタンやキルギスとの国境が複雑に入り組んでいるが、それはこの地域の多様な民族構成を反映している。そもそも「ウズベク人」という民族概念は、近世の部族名を20世紀になってこの地のトルコ系民族の総称として採用したもので、例えば古都サマルカンドやブハラではトルコ系のウズベク語とペルシア系(印欧語)のタジク語の両方を話すバイリンガルが普通だった。公式にはウズベキスタンのタジク系国民は5%程度ということになっているが、タジク人の主張ではもっと多く、政府により少数派のタジク人は弾圧されているという。 乾燥しているウズベキスタンでは、夏は雲一つない青空が広がり降水は無い。灌漑などで水を得れば豊かな実りが得られるが、ソ連時代の計画経済の名残で、耕地面積の8割が国家主導の綿花栽培にあてられ、食料自給率は低い。また灌漑による大規模な自然改変の影響で、流入水量が減少したアラル海の縮小が進んで現在はかつての面積の四分の一になり、干上がった湖底に漁船が放置される死の光景が広がり、漁業は壊滅した。他方独立以来の経済改革により外資を導入し、金、天然ガス、ウランなどの地下資源開発が進んでいる。地下資源輸出額は金が最多であるが、最近開発が進む天然ガスはパイプラインを通じてヨーロッパなどに輸出されている。 ウズベキスタンでは古くは中期旧石器時代(ネアンデルタール人)の遺跡が発見されている。紀元前2000年前後には南部のオアシス地域に都城を伴う高度な文明が出現した。一方同じ頃北部にはアンドロノヴォ文化が及んだが、この牧畜民はのちに騎馬を利用した遊牧民になり、オアシス地帯の農耕・都市民とステップ地帯の遊牧民という、この地域を特徴付けていた二つの生態が成立する。 この地域は古代にはソグディアナあるいはバクトリアと呼ばれたが、紀元前6世紀頃に西アジアを統一したアケメネス朝ペルシアの支配下に入った。西方の西アジア文明、そして東方の中国文明の中間という位置により、ユーラシア大陸のほぼ中央にあたるこの地は、「シルクロード」と通称される東西交易の主役となる。 アケメネス朝を滅ぼしたマケドニアのアレクサンドロス大王は、紀元前328年にこの地に遠征して越冬し、当地の豪族の娘ロクサネを最初の正妻に迎えている。アレクサンドロスの東方遠征とともにヘレニズム(ギリシャ)文明がこの地に伝わる。紀元前240年にはギリシャ系支配層によるバクトリア王国が成立、インド北部まで勢力を伸ばし、そこで仏教はヘレニズム文化と融合して優れた偶像芸術を持つことになる。 紀元前140年頃から、東方から遊牧民である月氏(中国の史書での呼称。印欧語族)がこの地に移って来る。紀元前1世紀にはクシャン朝を樹立してインド北部にまで進出し、カニシカ王は仏教を保護した。 一方中国を統一した前漢も西方への関心を持つようになり、中国の史書は張騫が探検した、馬と葡萄を豊富に産する「大宛国」について伝えているが、この大宛とはフェルガナ地方のことである。東西交渉は活発になり、仏教やその美術はこの地を通って中国へ伝わり、さらに6世紀には日本に伝来することになる。 交易と農耕の富に恵まれていたが故に、この地は様々な民族の支配を受けることなった。5世紀半ばには東方から騎馬民族エフタルが現れ、それを追うように6世紀にはやはり東方から突厥が出現し、この地のオアシス都市を支配した。「突厥」とは中国史書での呼称であるが、「テュルク」すなわちトルコの音写である。7世紀初め、仏教の経典を求めて天竺に旅立った玄奘三蔵は、この地を通ってインドに辿り着いた。 やがて突厥が分裂して中国の唐王朝の勢力が及ぶようになり、この地に住むペルシア系のソグド人たちは、商魂たくましく中国との交易に従事した。しかし中央アジアに勢力を伸ばしていたイスラム教徒のアラブ軍(アッバース朝)に751年のタラス川の戦いで敗北し、またソグド人安禄山が起こした反乱で国内が混乱したため、唐の中央アジア支配は後退した。この地にはゾロアスター(拝火)教徒のほか、ユダヤ教徒、仏教徒やキリスト教ネストリウス派もいたが、以後はイスラム化が進んでいく。 アラブ人たちはこの地を「マーワラーアンナフル」(川の向こう側)と呼んでいた。アッバース朝が衰えると、819年にブハラを都とするサーマン朝が分離独立した。「知の鉱脈」と謳われたブハラはバグダッドなどと並ぶイスラム世界の中心地となり、ブハーリー(ハディース=預言者ムハンマド言行録の編者)、イブン・シーナ(医学・博物学者)などを輩出する。 サーマン朝は地元のペルシア系官僚や東方遊牧民出身のトルコ系軍人を重用したため、ペルシア語文学が隆盛する一方、トルコ系軍人が実権を握り、その西方移住が促進された。サーマン朝はカラ・ハン朝に代わられ(999年)、ついで現れたセルジューク朝は11世紀にアム川を越えてペルシア、さらに小アジア(現在のトルコ共和国の領域)へと進出してゆく。1141年にセルジューク朝を破ったホラズム朝もまたトルコ系である。 1219年、東方からチンギス・カン率いるモンゴル軍が侵攻してホラズム朝を滅ぼし、中央アジア全域を支配下に収めた。1227年にチンギスが死んだ後、モンゴル帝国は分割され、この地はチンギスの次男チャガタイの子孫が継承するチャガタイ・ウルス(国)の領土となった。モンゴル帝国もトルコ系軍人・官僚を重用したため、中央アジアのトルコ化はさらに進んだ。 1336年4月にシャフリサブズで生まれたティムールは、チャガタイ・ウルスの一部将から身を起こし、一代で中央アジア・西アジアを制覇した。故郷近くのサマルカンドに都したティムールやその孫ウルグベクは、碧いタイルも鮮やかな壮麗な建築物を数多く建設したが、その王朝は数代で分裂・衰退した。 それに乗じてこの地を征服したのが、北方のトルコ系遊牧民ウズベク族(シャイバーン朝)である。ウズベク(オズ・ベク)とはトルコ語で「真の君主」くらいの意味だが、その名はチンギス・カンの子孫で敬虔なイスラム教徒君主ウズベク・ハンに因むとされる。1512年にウズベク族はティムール朝のバーブルを破って中央アジア支配を確立した(敗れたバーブルはインドに転進しムガル帝国を樹立する)。 しかしウズベク族は内部抗争や南方のペルシア、北方のカザフ族との戦いで疲弊し、ブハラ、ヒヴァ、コーカンドを拠点とする小ハン(王)国に分裂した。 中央アジアでこうした盛衰が繰り返される間に、世界情勢は大きく変わっていた。シベリアを征服したロシアが南下して中央アジアを窺うようになる一方、インド支配を確立したイギリスもまた中央アジアに関心を持つようになった。産業革命による紡績業の発達やアメリカ南北戦争の混乱による綿花の品薄感が、両帝国をして綿花栽培の盛んな中央アジアに目を向けさせた。 イギリスがアフガニスタンで手を焼くのをしり目に、1860年代からロシアは中央アジア征服に乗り出す。かつて無敵を誇った遊牧民の騎兵もロシア軍の火器には勝てず、敗れた各ハン国は1876年までに全てロシアの支配下に置かれた。 ロシアはタシュケントにトルキスタン総督府をおいて植民地経営を進め、綿花増産を強制し、鉄道を建設した。伝統の崩壊を危惧したウズベク人の反乱は容易に鎮圧され、ジャディードと呼ばれる知識人たちは、ロシアやオスマン(トルコ)帝国、日本などに習いトルコ民族の統一・近代化を目指す運動を始めた。第一次世界大戦中の1916年にはロシア支配に反対するバスマチ蜂起が発生し、さらに翌年にはロシア革命が起きたが、ジャディードたちの多くは革命で成立した社会主義ソヴィエト政権に合流した。 1924年にソ連内の一国としてウズベク・ソヴィエト社会主義共和国が成立、1929年にはタジクと分離した。ソ連の独裁者スターリンの下では、1930年代に「民族主義者」の烙印を押されたウズベク人が多数粛清された。第二次世界大戦中はスターリンに敵性国民とみなされたドイツ人、高麗(朝鮮)人、タタール人などが前線に近い地域からこの地に強制移住させられ、現在も少数民族として残っている。 1959年にウズベク人シャラフ・ラシドフがウズベク共産党第一書記に就任し、20年以上その地位にあったが、その下では縁故主義や汚職がはびこった。ラシドフは中央からの綿花増産指令も嘘の達成報告で乗り切った。ソ連は綿花大増産を「社会主義の勝利」として宣伝し、その褒賞としてウズベキスタンには資本が分配され、1977年には中央アジアで唯一の地下鉄が首都タシュケントに開通している。 ラシドフの死から3年後の1986年、ソ連ではミハイル・ゴルバチョフ書記長による改革が始まってウズベク共産党の偽装や汚職が明るみになり、指導部が総入れ替えされた。改革でソ連政府の権威が弱まると、1989年にはフェルガナ地方で民族紛争が発生した。その結果イスラム・カリモフがウズベク共産党第一書記に任命された。 しかしソ連は崩壊し、1991年にウズベキスタンは独立した。カリモフはそのまま大統領に就任し、国民投票を根拠に、憲法の規定に背いて現在まで任期を延長し続けている。外交ではロシアから離れて西側に接近する姿勢を見せ、2001年以降のアメリカによるアフガニスタンでの「対テロ戦争」にも協力し、アメリカ軍やドイツ軍の駐留を認めた。国内でも1999年や2004年にイスラム原理主義勢力によるテロが起きている。 2005年5月、アンディジャンで反政府暴動が発生し、当局による発砲で市民数百人が死亡したといわれる。非難声明を出した欧米の姿勢に対抗して、ウズベキスタンはアメリカに米軍の駐留延長拒否を通告、同年11月に米軍は撤退した(ドイツ軍は今も駐留)。同月ロシアと軍事同盟を締結、また上海協力機構にも加盟して、ロシアや中国との関係強化に乗り出している。
2008年10月15日
コメント(0)
-

遺跡めぐり(写真多数)
この日は午前に少し室内作業をしたのち、午後はT団長に遺跡めぐりに連れて行ってもらうことになった。 同行するのは車を運転するT先生(R大教授)、そして僕と同じくイスラエルは初めてのM君(R大院)、そして急きょ同行が決まったK君(K大院)の四人である。何やかんやで出発が遅れて2時を過ぎてしまった。 まずはここからは北にあたるテル・ハツォールの遺跡に向かう。高速道路みたいな道を飛ばしても1時間以上かかる。ハツォールは軍人・政治家(副首相)でもあったイガエル・ヤディンによる発掘が有名だが、現在もヘブライ大学による発掘調査が続いていて、K君は昨年ここの調査にボランティアとして参加したそうだ。 ヤディンの発掘報告書などは以前からよく見ていたが、実際にその地に立てるのは感激である。入場料18シェケルを払って遺跡の丘の上に上る。観光用に整備されているのはアクロポリスの部分のみだが、それはこの遺跡のほんの一部に過ぎず、この遺跡は総面積80haに及び、テル(遺丘)型遺跡としてはイスラエルで最大の規模を誇っている。青銅器時代にはメソポタミアやエジプトにも知られた大都市だったのだから当然だが、今は一見ただの丘である。↓↓鉄器時代(紀元前1000年頃)の城門。ただし上部構造の多くは復元。旧約聖書のソロモン王などで名高い時代だが、ハツォールの最盛期はさらにそれ以前だった。↓保護のための屋根で覆われた、後期青銅器時代(紀元前1300年頃)の宮殿。この時代のこの地域の建築物としては破格の規模であるらしい。梁やオルトスタット(腰羽目板)を多用する建築技法は、同時代のヒッタイト帝国のそれを彷彿とさせる。↓巨大な玄武岩製の柱の基礎石。玄武岩でこんなに大きいのはトルコでもシリアでも見たことがない。イスラエルの遺跡も侮りがたい。↓宮殿の脇にあるトンネルの入り口。宮殿の地下へと続いているのだという。↓穴があったら入りたくなる性分なので入ってみる。岩盤をくりぬいたトンネルの下り坂を10mほど進んだが、えんえんと続いていて途中で右に屈曲する。シリアのカトナで発見されたような王墓の入り口か、あるいはエルサレムで見たような地下水源への入り口なのか??足もとが悪くて滑りやすく、地上に戻れないと困るので引き返す。↓鉄器時代に典型的な列柱式建物。↓鉄器時代?のオリーブ油搾油施設。↓鉄器時代?の貯水槽。巨大。水の確保は死活問題だったようだ。 感激のあまりハツォールで思わぬ時間がかかってしまったのと、そもそも出発が遅れたこともあり、当初予定していたメギド(「ハルマゲドン」の語源ですな)訪問をあきらめ(メギドはハツォールと逆に僕らの宿舎から見て南方にある)、手近な場所にあるベトサイダ訪問に切り替える。 ベトサイダはガリラヤ湖北岸にある遺跡である。イエスが5000人に食事を振舞ったとか、盲人の視力を回復したなどの「新約聖書」に記載された奇跡で知られているらしく、またその時代の遺跡もあるが、鉄器時代の城門も発掘されている。遺跡はキャンプ場の中にあり、入場料として4人で45シェケル取られた。↓ガリラヤ湖↓鉄器時代の城門。なかなか立派だが、むやみに石が多く発掘は大変そうだ。↓ローマ時代(イエスの時代)の住居。ここも黒い石だらけでお世辞にも住み心地は良さげとはいえない。↓ローマ時代の住居にある地下貯蔵室。ワイン入りの大甕でも置いていたのだろうか。 このガリラヤ地方は緑溢れる風光明媚な地ではあるが、とにかく蒸し暑い。遺跡にじっと立っているだけでも汗が噴き出してくる。 この辺りはマリンスポーツが盛んだが、水にでも入ってないと気持ちが悪い。さっきローマ時代のワインセラーを見たが、酒でも飲まないと我慢できねえぞこりゃぁ。もうそろそろ帰ることにした。 帰り道では事故渋滞やラッシュに巻き込まれたが、T先生のアグレッシブな運転にドキドキしながら無事に宿舎であるキブツに戻った。 晩御飯は先日と同じく変わり映えしないピザの山だった。・・・・・・・・ あなたがいつか話してくれた 遺跡を僕はたずねて来た 二人で行くと約束したが もったいないので4人で来た 遺跡めぐりの車は走る 窓に広がるガリラヤの湖よ 汗にまみれて服はぐしょぐしょ この旅終えて キブツへ帰ろう
2008年08月28日
コメント(6)
-

休日
例のごとく金曜・土曜は休日である。今週はエクスカーションもなく、三々五々日本へ帰国していくボランティアさんたちを終日見送った。ぶらぶら過ごして調査の最後の追い込みに鋭気を養う。 土曜(23日)の午前中は、車数台に分乗して近くにある遺跡を見に行くことになった。ベート・アルファという、6世紀ころに建設されたシナゴーグ(ユダヤ教の集会所)の遺跡である。 ↓遺跡入口の前にいた子猫。似た模様の三匹兄弟らしい。↓遺跡入口に置いてあるシナゴーグの復元模型。 遺跡への入場料は18シェケル(学生15シェケル)。日本円でおよそ500円といったところで、多少高く感じる。お土産売り場兼入場券売り場を通って中に入ると、保護の建物に覆われている発掘されたシナゴーグの遺跡がそのまま保存してある。また英語・ヘブライ語でシナゴーグの建設に関する再現劇(推定)のビデオが上映される。↓遺跡全景。中は薄暗い。↓この遺跡の売りである床面のモザイク。画題は手前からアブラハムの物語、12星座、ユダヤ教の祭壇。率直に言って絵は下手で、子供の落書きのように見える。建設費をケチって技量の劣る職人に依頼したのだろうか。当時のビザンツ帝国の国教だったキリスト教の教会の影響もあるそうだ。↓もう一度玄関前のシナゴーグの復元模型を見る。ホールの床全面にモザイク。写真上方の丸い部分が祭壇で、ユダヤ教の経典?が祀られる。建物には吹き抜けの二階があり、女性のみが二階に上って男性と顔を合わさないようにする。異性に気を取られず祈りに集中するための措置だそうだ。イスラム教のモスクも同様に男女別席である。
2008年08月23日
コメント(2)
-

試掘終了
調査終盤はこの夏一番の暑さに見舞われた。 それでもY君と僕の担当する発掘区の作業は順調に進み、ローマあるいはビザンツ時代のものと思われる壁がきれいに出てきた。出土する土器を見る限り、この壁の年代はほぼローマ時代、しかも1~2世紀頃と考えていいようだ。 それが分かっただけでも試掘の目的はほぼ達成できたし、団長の狙い通りイエスが生きていたローマ帝国の時代の遺構だったということになる。↓キブツ内の博物館にある、近隣の遺跡で出土したローマ時代の土器。試掘でも同じようなものが出土した。 さらに掘り下げると下の層の壁が検出されたが、出土土器を見る限りこちらは鉄器時代後期またはアケメネス朝ペルシア時代になるという。遺跡の堆積はまだ下に続くが、この壁の検出を以て今年の試掘を終える。↓奥に見えるのがローマ時代の壁。手前の地表に下層の壁が見えている。・・・・・・・ 発掘現場点描。↓陽が短くなってきたので5時過ぎに現場に到着してもまだ月が出ていて辺りは真っ暗である。しばらく明るくなるのを待たねばならない。↓朝の休憩時間にイスラエル人スタッフのNが作ってくれる野草茶。さわやかな口当たりとほのかな甘みが暑さで疲れた体に沁み入る。左はお茶に入れているセージの葉。↓お茶の原料。すすきの葉っぱみたいなのはキブツ内に生えているのをNが自分で採ってくるらしい。↓カマキリ。トルコやギリシャの海岸部にいたセミは、ここでは見かけない。シリアと同じく、暑さや乾燥が強すぎるせいか。
2008年08月19日
コメント(2)
-

発掘現場訪問
今日も測量を続ける。大分操作に慣れてきた。今日は正午近くになるとかなり気温が上がり、厳しい暑さの日だった。そのためかこの数日スタッフにも体調不良で寝込む人が出てきている。↓発掘現場で迎える夜明け↓狭い穴の中での作業↓車に分乗して現場と宿舎を移動する・・・・・・・ 夕方、ここから車で30分?くらいのところにあるイフタヘル遺跡の発掘現場を訪問。 先土器新石器時代B期(PPNB)から前期青銅器時代にかけての遺跡であるが、特にPPNB期のプラスター床住居や、祖先崇拝に使われたプラスター塗り頭骨の出土で知られる(らしい)。普通発掘では土器が最もたくさん出てくるものだが、ここでは土器はほとんど出土せず、石器が山のように出土する。面白い遺跡だった。↓高速道路(後方)の拡張工事により、一度は開発による破壊を免れたこの遺跡も消滅する運命にある↓PPNB期のプラスター張り床をもつ大型建築物↓1万年前(PPNB期)の人々が使っていた住居のプラスター張り床面
2008年08月11日
コメント(4)
-

エクスカーション(1)(写真多数)
北京五輪が開幕。しかし僕にはグルジアとロシアの武力衝突のほうが気になる。グルジアは総動員体制のようだが、どこで落とし所をつけるのだろうか。・・・・・・・・ 今日は休日である。それを利用してガリラヤ湖方面へ発掘隊の一部でエクスカーションに出かける。おもにキリスト関係の遺跡・名所である。僕は予備知識がほとんどないが、人が尊ぶものはありがたく拝見することにする。 まず最初はマリアがイエスを身ごもったというナザレの町に。今はアラブ人(ただしキリスト教徒が多い)の町だそうで、看板もアラビア文字が多く、町の感じは結構シリアに近いなあと思う。↓受胎告知教会(カトリック)↓内部にあるビザンツ時代の教会跡。この下にマリアが受胎告知されたといわれる洞窟がある。 ギリシャ正教系の受胎告知教会もあるが、感じが悪かったので写真を載せない。↓ナザレの町で見かけた香辛料商店の店先。↓イエスが水をワインに変えた、最初の奇跡を行った場所の跡とされるカナの町の石畳。↓ナザレで食べたシャワルマ(トルコでいうドネルケバブ)。1個16シェケル(500円)。僕の歯型付き。↓イエス時代の集落跡とされるカペルナウム。白い石で出来たシナゴーグ跡は紀元後4世紀のもの。↓カペルナウムに残るペテロの家とされる遺跡。現在は上にカトリック教会が立っている。↓イエスが「山上の垂訓」をした場所とされる跡地に建つ教会(1930年代の建築)。↓日本隊が発掘したエン・ゲヴ遺跡。鉄器時代(紀元前9世紀ころ)。↓エン・ゲヴのキブツに残る、第一次中東戦争(1948年)当時の手作り装甲車。遺跡には当時の塹壕も残る。↓ガリラヤ湖畔にあるペテロの首位権教会(イエスがペテロに信徒の指導を委ねた地とされる)↓ガリラヤ湖。魚が美味いらしいが食べなかった。・・・・・・・ 夕方宿舎に戻る。北京五輪の開会式の録画中継を見る。 その後Thucydidesさんが持参した「インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国」のダウンロード版(たぶん違法)を見る。なんじゃこりゃ。映画館に見に行かなくて良かった。
2008年08月08日
コメント(6)
-

三日目
今日はよその地区から手伝いがきて、草刈りや石転がしの作業が比較的進んだ。数か所で草の下から壁の跡がはっきりと分かる石列を見つけた。↓採集土器。ローマ時代あるいはビザンツ時代? 今日は朝早くは雲が出て割合涼しかったのだが、湿度がかなり高く昨日以上に汗まみれになった。正午近くになると太陽が出てかなり気温が上がった。 朝に休憩時にイスラエルの学生と話す。彼らはテルアビブ大学の学生だが、そこの教授であるジャック・ヤカル氏はイスタンブル生まれのユダヤ人である。1970年代にキプロス紛争のあおりでトルコ国内のマイノリティに対する風当たりが強くなったとき、彼はイスラエルに移住した。 なかなか面白い教授らしく、トルコ軍の兵役で将校としてトルコ東部に駐屯していた当時の話を面白おかしく聞かせてくれるそうだ。あと採点が甘いので学生には人気らしい。 今朝韓国からの参加者が到着。学生4人に教授一人。教授は日本語ができるが、学生は英語も日本語もあやういらし。彼らは辛ラーメン二箱にコチュジャン、キムチを持参してきた。噂通りだな。日本人学生が早速ラーメンをもらっている。 出土した土器洗いをするボランティア参加者の皆さん↓
2008年08月05日
コメント(4)
-

二日目
今日もY君(チュービンゲン大学)と遺跡の頂上を歩き回り、壁の跡を探し回った。 ところどころごっつい壁はあるのだが、埋まってしまったり崩れているせいで建物の全体像がつかめない。果てさてどうしたものか。発掘に着手してもいいのだが、規模が大きいので中途半端に始めても始末に困る可能性もある。 今日ももちろん暑かったが、雲がかかったり風が吹いたりして、日陰にいる分には苦痛ではなかった。それでも5時間ほどの作業時間で1.5リットル入りのペットボトルの水を全部飲みほし、さらに休憩時間にお茶をがぶがぶ飲んだので水の出入り量は相当なもののはずだ。 今日はある発掘区で地山(人間が居住する以前の岩盤)に達したそうだ。地山のすぐ上に前期青銅器時代あるいは後期青銅器時代に属する壁がある。その結果、この遺跡に人が住んでいたのは前期青銅器時代、後期青銅器時代(エジプトでいえばツタンカーメンだのラムセス2世だのといった時代)、鉄器時代(旧約聖書のダビデ・ソロモン王の時代)、ローマ・ビザンツ時代ということになる。 まあ僕が調査(というほどのことはしてないが)を担当しているローマ・ビザンツ時代の遺跡は、住居というより宗教施設の可能性が高いが。・・・・・・・・ 一日のスケジュールは以下のとおり。 4:30 起床 4:55 宿舎を出発 5:30 作業開始 9:00 朝食休憩(現場にて) 11:30 作業終了 12:00 昼食(キブツの食堂) 16:00 土器洗い 19:00 夕食(キブツの食堂) 20:00 ミーティング その後 作業、宴会、各自適宜就寝 今日のミーティングは各地区の作業状況について詳しい説明があったが(英語)、「青銅器時代」「鉄器時代」という言葉にすら慣れていないボランティアの人に、「EB」だの「LB」だのという話をして面白いものだろうか。・・・・・・・ 遺跡で見たバッタ↓ほかにゴミムシとかも見た。植物は乾燥地らしくトゲの生えたものが多い。
2008年08月04日
コメント(4)
-

遺跡初訪問
昨日の夜知らぬ間に寝ていた。明け方、日本から次の集団が到着した。 僕はいびきがすごいので(そのことについては書くことがいっぱいあるが、ここでは措く)、同じくいびきで評判のK大のS先生とT大のK先生と同室になった。昼寝の時間に二人が寝ているのをみたが、なるほど噂に違わぬいびきっぷりである。片方が速射砲なら片方は大口径の榴弾砲、いずれ劣らぬ音響であった。面白いのは、聞いているうちになんだか喋っているように聞こえてくることである。 しかし僕より強烈ないびきをかく人が他にいることが分かり、結局僕はすぐに引っ越しさせられた。新しく入った部屋の住人は、僕を含め(現・元)ドイツ留学組という共通項がある。 午後、初めて遺跡に行く。暑いのは暑いが、風が吹いてきて夕方になるにつれ過ごしやすくなってきた。イスラエルは暑いと脅かされていたが、これならなんとかなりそうだ。 遺跡からはタボル山がよく見える。僕は聖書の知識(及び興味)が全然ないので知らなかったが、ここはキリストが変容(変身??)したと伝えられる場所と考えられるという(ただし別にシリアとの国境にあるヘルモン山も候補になっているそうだ。どっちでもいいけど)。山上にはカトリックやギリシャ正教の修道院とか教会がある。 遺跡の近くの電線には、ヨーロッパから帰ってきたのか、ツバメがたくさんとまっていた。 夜、全体ミーティング。日本人のボランティア参加者の人たちの自己紹介などを聞く。20歳前後の若い人(学生)がほとんどで、今まで僕が参加した発掘とはまるで違う。こっちまで若返りそうだよ、ごほごほ。
2008年08月02日
コメント(4)
-
ドイツ版「ストーン」ヘンジ
シュピーゲル・オンラインで見た記事を紹介。 イギリスのストーン・ヘンジは「謎の古代遺跡」として知っている人も多いかと思う。なんといっても世界遺産にも登録されているし、宇宙人との交信だの、ドルイドの秘儀だのといったさまざまなロマンや想像を掻き立てる遺跡でもある。 実はこの「ストーン」ヘンジ、今のように石造りになったのは最初の建設(紀元前3100年頃)から500年ほど過ぎた頃のことで、それ以前は木の柱で出来ていた「ウッド」ヘンジだったことが、発掘調査から分かっている。実はストーンヘンジの近くにはやはり「ウッドヘンジ」と呼ばれる柱穴が並ぶ遺跡が発見されている。そもそも「ヘンジ」は土塁や堀で区画された円形の大型遺構を指す一般名詞で、ストーンヘンジは残りの良さや巨石の使用で際立っているものの、遺跡の性格としては唯一無比というものでもない。 このような遺構はブリテン島に特有と思われていたが、現在ドイツのザクセン・アンハルト州ペメルテではストーンヘンジを思わせる遺構が発掘されている。ただしここも石ではなく木の柱なので、痕跡は地表面下に埋もれている柱穴や堀、土塁の跡しかないのだが。 この遺跡は1991年に飛行機からの地表面観察で発見された。地下に遺跡があると、地上の麦の生育具合が影響されるので、麦の背丈の長短により畑に地下の遺跡の輪郭が浮かび上がる(これをクロップマークと呼ぶ)。現在行われている発掘では、最大直径115mの円形に並ぶ木柱群や、堀に囲まれた直径80mの円形の遺跡(の一部)が発見されているという。 時代はイギリスのストーンヘンジが機能した中期に当たる時代、すなわち紀元前2300年頃から2100年頃が考えられるという。時代で言うと新石器時代の末期(「石器」時代というが、銅も利用されていた)、すなわち釣鐘形土器文化あるいは縄文土器文化(日本の縄文文化と名前は同じだが無関係)の末期くらいだろうか。この当時は似たような土器がヨーロッパの広い範囲に分布しており、例えば釣鐘形土器はスペイン、イギリスからドイツまで、縄文土器はロシアからドイツにまで広がっており(ドイツは両者の重なる地であり、この頃から東西分断?の地だった訳だ)、広域の交易や交流が想定されている。釣鐘形土器文化圏の西部では巨石を用いた建造物(多くは墓)も多く、ストーンヘンジは異質だがその一種と捉えられなくもない。 ストーンヘンジの発掘では近年人骨とかも出土しているようだが、このドイツの遺跡でも人骨が出土しており、天文・祭祀のみならず葬送に関係する場所だった可能性があるという。 ザクセン・アンハルト州は旧東ドイツ地域での再開発、そして金目当ての人による盗掘が盛んなせいか、最近考古学の大きな発見が続いている。盗掘で発見されたネブラの天文盤、「欧州最古の文明」と報じられた(んなアホな、と思ったが)「神殿」群、そして最近では同州ゴゼックに直径70mの木造円形遺構である「新石器時代の太陽観測所」が発掘・復元された。 ゴゼックの観測所は今回の「ドイツ版ストーンヘンジ」より2000年前、ネブラの天文盤は500年ほど後のものだが、いずれも天文がらみというのは面白い。
2008年07月28日
コメント(2)
-
こういう発掘は勘弁
とりあえずこのニュース。(引用開始)<ICC>スーダン大統領の逮捕状請求 3万5千人虐殺容疑7月14日21時53分配信 毎日新聞 【ブリュッセル福島良典】スーダン西部ダルフール地方の紛争をめぐり、国際刑事裁判所(ICC、オランダ・ハーグ)のモレノオカンポ主任検察官は14日、大量虐殺と「人道に対する罪」、戦争犯罪の容疑でスーダンのバシル大統領(64)の逮捕状を請求したと発表した。02年のICC設立以来、現職国家元首の逮捕状請求は初めて。スーダン政府は大統領訴追の動きに反発しており、ダルフール和平協議への影響も懸念されている。 主任検察官は14日、バシル大統領指揮下の「部隊と要員」が少なくとも3万5000人の民間人を殺害し、「(大統領は)国家機関や軍部隊、民兵組織ジャンジャウィドを使って虐殺を犯した」と指弾する文書を法廷に提出。会見で虐殺の模様を詳述し、「ダルフールで起きたことはバシル(大統領)の意思の結果だ」と断じた。 ダルフール紛争は03年初めの発生後、ジャンジャウィドの住民襲撃などで約20万人が死亡。国連安保理は05年、残虐行為に関与した容疑者を訴追するよう決議し、ICCが捜査を続けていた。 ICCは今後、判事3人で構成する予審法廷が逮捕状を発行するかどうかを決める。ただ、実際に逮捕状が出てもスーダン政府が引き渡しに応じないのは確実だ。ICCは昨年5月にもスーダンのルアル人道問題担当相とジャンジャウィド幹部の逮捕状を出したが、同国政府は引き渡しを拒否している。(中略) ダルフールには現在、国連平和維持活動(PKO)である国連・アフリカ連合(AU)ダルフール合同部隊(UNAMID)が駐留。潘基文(バン・ギムン)国連事務総長は仏紙フィガロとのインタビューで、ICCによるバシル大統領訴追の動きについて「誰も法の裁きから逃れられない」としながらも、「PKOや政治プロセスに重大な結果をもたらすだろう」と懸念を表明した。 【ことば】▽国際刑事裁判所▽ 02年7月、設立条約が発効。集団殺害犯罪▽人道に対する犯罪▽戦争犯罪--などを犯した個人を当事国に代わって訴追、処罰する。加盟は日本を含め106カ国。検察局、裁判部などに分かれ、判事(18人)の中には斎賀富美子・元外務省人権担当大使がいる。現在、スーダン、ウガンダ、コンゴ民主共和国、中央アフリカの計4カ国の案件が付託されている。 (引用終了) へえ、すごいな。ミロシェヴィッチにもサッダームにもこういうのは無かったろうに。 折りしも、なんでもBBCが、中国がスーダンに不法に武器を供給していた証拠を掴んだというニュースも流れてるみたいですが。・・・・・・・・ それはともかく、ダルフールにも少し関係する考古学?の記事。 イギリス南部、ドーセットである発掘の実習が行われているそうで、この発掘現場からは大量の人骨が出てくる。人骨と共に、生々しくも衣類片や目隠しの鉢巻、タイヤの跡、コンドーム、薬莢、自動小銃の弾丸マガジンが出土する。そういう遺物は貴重な証拠品になるため、ヘラで丁寧に掘り出さなくてはならない。薬莢はこの遺骨の主を「骨にした」犯人が誰かを、そして出土した硬貨はこの遺骨の主がいつ骨になったかのヒントになる。前日の雨で地面はぬかるみ、調査員たちは泥まみれである。 遠くには軍用ヘリのローター音や戦車のキャタピラ音が鳴り響く。国連軍からの電報で、事態が急を要するため平和維持部隊はこれ以上待てない、この週末までにはこの発掘を終わらせなくてはならないと要請される。と突然誰かの「地雷だ、全員退避!」という叫び声で、白い雨合羽をまとった30人ほどの参加者は一斉にその場から避難した・・・・。 ・・・・実はこの地雷は贋物で、出土している人骨もハリウッドから購入した精巧なプラスチック模型である。出土遺物も全部、この実習のために一週間ほど前にわざと埋められたもの。ヘリや戦車の音は(たまたま)隣接する英軍の基地から聞こえてきている。国連軍云々はシチュエーションつくりの演出ですな。 この発掘実習はボーンマス大学のイアン・ハンター准教授が行っている。ハンター准教授の専門は「司法考古学」だそうで(ほう、そういう分野もあるのか。日本やドイツじゃまだ聞かんね)、彼は1997年から2001年までボスニア・ヘルツェゴヴィナに滞在、その他コンゴ、イラク、グアテマラ、キプロスで、内戦による大量虐殺の犠牲者の集団墓地を調査してきた。彼の調査は国連戦争犯罪法廷に数々の証拠を提供している(国連のこうした調査に考古学者も絡んでいるとは不覚にも知らなかった)。この実習は徹底的にリアルさを追求していて、学生たちは集団墓地の位置を正確には知らされず、まず森の中で集団墓地を探すことから始めるそうだ。 骨を掘り出すのは家族の元に返すためのみならず、虐殺を引き起こした犯人を特定する手がかりを得るためでもある。ハンター准教授は「ここで司法考古学の専門家を育てることが、世界中の戦争犯罪人に対して『虐殺を引き起こしていくら隠しても、必ず証拠を見つけ出してみせる』という抑止力になれば」と語る。彼が今行きたいのはジンバブエだそうだ。・・・・・・・・・・ 僕もまあ専門の関係で人骨にはたくさん接してきたけれども、こういうのはないな。僕が接してきたのは少なくとも2000年以上前の人骨ばかりだしな・・。 え?古かろうが新しかろうが人の骨は骨だろう?うーむ、そうなのだが、どの辺で線引きされるのかな。やはり着ていたものがそのまま一緒に出てくるようなのはちょっと勘弁して欲しい。聞いた話では、トルコの場合だと20世紀初頭の遺体はまだ服を着たまま出てくるそうだ。東京なんかだと水分のせいで有機質の残りがいいもんだから、江戸時代の頭蓋骨がちょんまげつけて出てきたりするんだってね。ああ気色わる。徳川14代将軍家茂(今大河ドラマやってますね)の墓が発掘されたときも、彼のふさふさの美髪がちょんまげそのまま残っていたそうだ。 そういや「日本のインディ・ジョーンズ」(笑)こと、サイバー大学の吉村先生も、ミイラだらけのエジプトが専門なのに「俺はミイラが嫌いだ」とか公言してたそうだな(今は平気になったんだっけ?)。それは僕もよく分かる。 あ、そういや今ちょうど東京・池袋のサンシャインシティにある古代オリエント博物館で、吉村先生が発見した古代エジプト遺物の特別展やってるので、皆さん見に行って下さい(ミイラはなかったっけな?)。今見逃したらエジプトに行かないと見られなくなるそうですよ。 ・・・宣伝はともかく。 お墓だったらまあ一応お葬式とかして丁寧に葬られたものだろうからいいとして、殺されてそのまま埋められた人の遺骨はやはり見るに堪えない。一度テレビのドキュメンタリー番組で、イラク南部でフセイン政権に虐殺された人の遺骨の発掘作業してるのを見たけれども、あれには思わず目を背けてしまった。僕は発掘現場じゃ骨見ても平気だし、発掘隊の宿舎の部屋で夜中に誰かさん(今から2300年位前の人)の骨と「二人きり」になっても平気だったのだが。・・・・・・・・・ しかしまあ、こういう専門(司法)の考古学が必要とされない世の中になればいいのだが。まだまだ需要は多そうだが、これも世界平和への貢献の一つのあり方なのかなとも思う。
2008年07月14日
コメント(10)
-

「最初のアメリカ人」の・・・/聖火リレー
「次回こそニュース貼り付け日記ではなくオリジナル文を」と書きながら、なかなかブログまで文章を書く気が回らず、今回もニュースを貼り付けてコメントするだけの手抜き日記です。 昨日はイスラエル人の夫妻と会話する機会があったのだが、大昔に習ったヘブライ語はすっかり忘却の彼方で(挨拶と数字、あと単語がところどころ聞き取れるくらい)、結局英語での会話になった。イスラエルの人と話すのは久しぶりだが、やっぱ自己主張が強いねえ・・・。・・・・・・・・・ 今日のニュースから。 アメリカ大陸にいつ人類(「最初の「アメリカ人」)が現れたのかという問題は、今もなお解決を見ていない。一般には1万3千年くらい前にアジア大陸のモンゴロイドがベーリング海峡を渡って来たのが最初といわれていて、精巧な石槍が製作されていたクローヴィス文化が最古とされる。 一方でクローヴィス文化よりも古い、2万年前以上の炉跡だとか石器だとかの報告例がぽつぽつ報じられているのだが、年代測定や遺物・遺構の性格をめぐって、それを決定的な「最初のアメリカ人」存在の証拠と認めない意見が多い。 ところがオレゴン州で発掘されたあるモノの年代を放射性炭素年代法で測定したところ、1万4300年前と、今までの通説よりも1200年ほど古い年代が出た。それは焚き火の跡や石器のかけらといった、本当に人為的なものか分からない曖昧なものと違って、そこに人間がいた決定的な証拠である。 ぱっと見ると犬のものだか人間のものだか分からないのだが・・・。このモノから取り出したDNAの解析で、先祖といわれるアジア人との関係も明らかになるかもしれないという。 中近東なんて乾燥してるから、こういうモノは結構見つかりそうなものだが、僕はまだ発掘でお目にかかったことはない。 さて、この「モノ」とはいったい何でしょう???リンク先の画像を見れば分かるとは思いますが・・・・。↓ヒント・・・・・・・ さて北京五輪の聖火リレーは順調に抗議活動に見舞われているようですが・・・・(引用開始)<トルコ>ウイグル族支援グループが聖火リレー妨害4月4日11時47分配信 毎日新聞 【エルサレム支局】AP通信などによると、トルコのイスタンブール市内で3日、北京五輪の聖火リレー隊が、中国新疆(しんきょう)ウイグル自治区での人権侵害に抗議するグループに妨害される騒ぎが起きた。トルコ警察は少なくとも6人のウイグル族を拘束した。 聖火リレーは2日にカザフスタンで始まり、3日に2カ国目のトルコに到着。同市中心部の広場で式典が行われたあと、最初のランナーがトーチを持って走行中、ウイグル族を支援する団体のメンバーが駆け寄った。妨害者は周囲を警備していた警官らに取り押さえられ、リレーは続行された。広場周辺では当時、ウイグル族ら約200人が中国政府を批判する抗議デモを行っていた。 聖火リレーは残り19都市・地域を巡る予定だが、チベット暴動を鎮圧した中国当局への批判は強く、各地で同様の抗議行動が懸念されている。 (引用終了) やはりねえ・・・・。イスタンブルで絶対起きると思ったんだな、抗議活動。 というか3月にチベットの騒動がなくても、北京五輪の聖火リレーがイスタンブルに来る時点で抗議活動は十分予想できたと思うんですがね、ウイグル族との関係で。トルコは同じトルコ系であるウイグル族独立運動の最大の拠点の一つで(亡命政府を名乗る機関はアメリカにあるそうだが)、90年代には中国政府がウイグル族を支援しないようトルコ政府に警告を発したこともあった。どのくらいいるのか知らないけどトルコ国内に亡命ウイグル人もたくさんいて、豆腐とか麺類(中近東では珍しい)を売っていると聞くんだが。ねえ、iskenderさん・・・。 そもそもイスタンブルに聖火リレーが行った選考基準はなんだろうか。IOCが決めてるのか、それとも中国政府が決めてるのか。イスタンブルは何度も落選しながらもオリンピック誘致に名乗りを上げているからだろうか? 他に中国に友好的な国など中東にはごろごろあると思うし、むしろトルコはウイグル族問題のほかに織物製品の貿易摩擦もあるし、中東ではあまり中国と仲が良くないほうだと思う。 聖火リレーの妨害はいかがなものかと思うが(逆効果じゃないか?)、黙ってチベットの旗とか抗議のプラカードを持って沿道に立っているだけでも排除されちまうのかね。よく自称平和団体が「人間の鎖」とか言って米軍基地を囲んだりしてるけど、あれと同じように切れ目なしにそういうチベット問題を連想させる人を黙って沿道に立たせておけばどうしても映像に映っちゃって、中国国内での聖火リレーのニュースで「無事に盛り上がってます」などと下手な小細工が出来なくなると思うんだが。 まあ、共産党政府の「大本営発表」を一番信じてないのが中国人自身だといいのですが。「政治問題化させるな」とかいいながら、ものものしい警備の中で聖火受け取ったのが北京市長じゃなくて国家主席という時点で語るに落ちているだろうに。 エベレスト山頂に火を持っていくというのは、中国の宇宙観とか世界観を反映してて面白いですな。 チベットといえば、ハンブルク市の左翼党市議が「ダライ・ラマを見ているとホメイニ師を連想する」(ネガティヴな意味で)とか、「ダライ・ラマを尊敬するのは前民主主義的」とか発言して物議を醸している。言ってることが北京政府の主張と同じで微笑ましいですな。 ニーダーザクセン州の左翼市議が「保守反動を押さえ込むために、シュタージを再建しろ」とか言って党を除名されたこともあったが、日本のみならずドイツにもアナクロなサヨク(左翼ではなく)はいるものか。映画の上映をやめろとか騒ぐウヨクにも困ったもんだけど。
2008年04月04日
コメント(2)
-

環境考古学/カンボジアのアマゾネス?
メモ代わりの日記。 考古学の分野に環境考古学というのがある。考古学というと穴掘りとか宝探しとか言うイメージがあると思うが、理屈上はこの世に存在したありとあらゆるものが研究対象となりうる。もちろん何らかの痕跡を残していないと研究対象にならないのだが。 極端な例だとゴミ収集所に捨てられているゴミでも研究は出来ることになる。発掘して出てくるのはお宝ばかりではなく(もちろんナントカ王のお墓の発掘なら、副葬品の財宝が出てくることになるが、そのナントカ王の遺骨自体がより興味深い情報を提供することもある)、たとえば割れて捨てられた土器とか、食べて捨てられた魚の骨とか、むしろゴミの方が多い。こういうものの分析には理化学的手法やたとえば法医学や生物学の知識が重要になる。 そうした「~考古学」の中でも割合ポピュラーになったものの一つが環境考古学だろうか。去年の日記に一度書いたが、最近話題の地球温暖化とかの研究で過去数百年の気候変化とかいうグラフにお目にかかれるが、あれだって広い意味での考古学といえなくもない。過去の気候変化を探る時に対象とされるのが、湖底などの土壌内に残っている植物の花粉などである。 ある種の花粉が増えるということはその地域の植生が変わったことを示すが、植物というのは周囲の環境や気候に大きく影響されるものだから、気候変動や土地利用の変遷を示す資料として貴重な資料となる。僕も手伝ったことがあるが、土中に直径5cmから10cmくらいの長い金属の筒を打ち込んでサンプル土壌を採取し、その中に残っている花粉や生物の遺存体を探して時代による傾向を分析する。 ごたくが長くなったが、その関連のニュース。スペイン南部でヨーロッパ最古の青銅器文化の一つとして栄えたエル・アルガル文化(紀元前1800-1300年頃)の滅亡が、人間による森林伐採だったとする説が発表された。 スペイン南部は銅や錫の山地に恵まれているが、一方で乾燥した気候で土地は岩がちで言ってみればトルコに近い気候である。花粉分析の示すところでは、紀元前1800年頃から栄えたエル・アルガル文化は青銅器生産を盛んに行っており、その燃料とするためにさかんに森林を伐採してはげ山にしてしまい、不毛の地になって滅亡したのだという。それを示すものとして木が燃えた炭化物の層や採取された花粉の種類の変化が証拠となっているようだ。 ただこの記事、同時に「紀元前2200年頃からこの地域では乾燥化が始まっていたが、人間による環境の改変(悪影響)のほうが大きかった」と書いてある。植生が変わったことは花粉が示す通りなのだが、それが気候の変化によるものなのか、人間が木を切って周囲の植生を変えたせいなのかは最後は想像になってしまう面もあるのだろうか。 例えばトルコだと「文明」の栄えたヒッタイト時代とローマ時代、そして19世紀以降の現代は森林が大きく後退し土砂が流出していることは分かっているのだが、卵が先かニワトリが先なのか。それ以外の時代も当然木は切っていたはずだが、気候の変化により降水量が多ければ森林の回復力は大きくなる。「たたら製鉄」のあった日本なんかは降水量の多い国だが、中国山地の製鉄業者は鍛冶屋の元締めであると同時に大地主で、計画的に植林して将来の木炭の原料確保に努めていたと聞く。 降水量の多い日本でさえそうしないと山ははげになるが、雨の少ないトルコやスペイン、あるいは中国で無計画に森を伐採するとどうなるか・・・・。最近では「大躍進」(1950年代末)時代の中国やもっと最近の北朝鮮で、鉄や農産物の増産が叫ばれて山の木がどんどん切られる→山の保水力が減り土砂が流れる→洪水・不作→飢饉(中国では1960年前後に2000万人が餓死したという説もある)→鉄はくず同然で使い物にならなかった、という悲劇的な負の連鎖が見られたが、気候変化や人間の環境破壊もさりながら、何よりもバランスが肝心ということか。・・・・・・・ 日本の環境考古学の第一人者というかはしりの方がいらっしゃって、僕も大昔にさる現場で二言三言言葉を交わしたことがあるが、その人の関係するニュース。(引用開始)<カンボジア>紀元前後の大規模集落確認 女性が支配者か11月14日20時13分配信 毎日新聞 カンボジア学術調査団(団長=安田喜憲・国際日本文化研究センター教授、東京財団主任研究員)は14日、カンボジア北西部のプンスナイ遺跡で、紀元前後に成立した、環状の堀に囲まれた大規模集落を確認したと発表した。これまでベトナムのオケオ文化(5~7世紀)が東南アジアの文明の源流と考えられていたが、それ以前に高度な文化があったとみられ、議論に一石を投じそうだ。 調査は07年1~3月に実施された。南北3キロ、東西4キロの楕円(だえん)の堀(深さ約1.5メートル)を確認し、その内側5地点を発掘したところ、37個の墓から紀元前1世紀前後の人骨35体や土器167個分相当の土片、青銅1000点、鉄200点、ガラスやこはくなどでできた玉100万個を発見した。 人骨は、5体が女性で、いずれも体のわきに鉄製の武具があったことから、安田教授は「女性の戦士の人骨で、支配者も女性だった可能性が大きい」と話している。 (引用終了) へえ、中国で長江文明を探してると思ったら、今度はカンボジアか・・・。まあ華南と東南アジアはお互いに関係しているということで調査しておられるんだろうけど。あとは「森の文明」がらみでかな?ところで東南アジア文明の源流はオケオ文化なんすかね?僕は銅鼓で有名なドンソン文化だと思ったんだが。まあ毎度の如く文明の定義にもよるんだろうけど、この場合決め手は大規模な環濠集落の存在になるか。ドンソン文化も精巧な青銅器は残してるが、その集落の事は僕はよく知らない。 結構鉄器が普及してるみたいですな。一時期「タイに中国よりも古い独自の銅器文化が栄えた」と唱えられた時期があったが、最近は年代観に修正があったのか見なくなった。レンフリューが唱えたバルカン銅器文化と似たような顛末か。 写真も載っているドイツ語版の記事だと安田教授のコメントが載っていて「『女性は弱く守られるべき存在』という考え方は西洋起源である(=それゆえ女性戦士や支配者がいても不思議ではない)」とあるが、どうなんだろ(「森の文明が人類を救う!!1!」というコメントじゃなかったか)。ケルト人にもボウディカ(ブーディカ)という女性軍事指導者の例もあるし(まああれはあくまで「夫の代わり」だが)、西洋というよりキリスト教(もっと進めたのはイスラム?)かな・・・。ボウディカとこのカンボジアの女性戦士たちはほぼ同時代、日本の「女王」卑弥呼はおよそ200年後の人物ですが。 むしろ日本の弥生時代や古墳で武器が副葬された女性の例は皆無なんだろうか。確か無かったような。ポリネシアのなんとか族は男が家事をして女が狩猟や戦争をするとか中学の頃保険体育の資料集(笑)で見た記憶があるが、女性が武装するというのは世界的に見てもきわめて例外的であるのは間違いない(最近は知りませんが)。あと武装してるからって戦士と断定できるのかな。女剣撃じゃないが巫女とかの線はないのかね。その辺の続報が気になるところ。 ドイツ語版の記事のタイトルは「カンボジアのアマゾネス」とある。アマゾネスは今のウクライナあたりにいたという女戦士の民族で(ブラジルじゃないよ)、ヘロドトスの「歴史」にも登場するが、おとぎ話とみなされている。
2007年11月18日
コメント(8)
-

「世界最古」ネタ二題
シリア北部、トルコ南部ではダム建設に伴う水没遺跡の緊急発掘が数多く行われているが(日本の調査隊も加わっている)、最近目覚ましい発見が多いようだ。その中から最近報じられた「世界最古」の発見ネタを二題紹介。 記事の解説が面倒なのでとりあえず「Abenteur Archaeologie」のホームページの記事から、抄訳だけ載せることにする。・「世界最古のカップルの墓発見」(リンク先に写真あり)(訳出開始) トルコ東部で珍しい発見があった。ハケミ・ウセの遺丘で、おそらくカップルとみられる二人が葬られたおよそ8000年前の墓が発見された。二人は新石器時代の20代の女性と30代の男性で、互いに抱き合うように一つの墓に葬られていた。 ハジェテペ大学のハリル・ティルキンによれば、この二人の関係を示す埋葬方法であるという。死因についてはまだ不明であるが、二人は疫病か不自然な理由で死んだ可能性がある。 最近イタリアのマントヴァで抱き合う二人の墓が発掘されている(関連記事)。約6000年前の新石器時代のこの墓はこれまで世界最古の「愛する二人」の墓と見られてきた。それまで新石器時代のカップルの埋葬は見つかっていなかった。 ディヤルバクルの70km東方にあるハケミ・ウセの発掘は、ウルス・ダム建設に伴う古代遺跡緊急調査の一環として2001年に始まっている。(ミリアム・ミュラー)(訳出終了) マントヴァの発見の時に僕も日記に書いたけど、「世界最古」ってのはミスリードじゃないかな・・・?ドイツを調べただけでも、旧石器時代にもあるぞ。しかも写真を見るとこの二人、並んではいるけど向き合っても抱き合ってもいない。男が女に背を向けてるように見える。 ま、「墓まで一緒」ってのは夢のある話ではあるけど。マントヴァのカップルが「新石器時代のロミオとジュリエット」なら、こちらはさしずめ「新石器時代のライラとマジュヌーン」か。でもあれは男が女に恋い焦がれて発狂する話だから、女に背を向けているのはおかしいな。・「世界最古の壁画」発見(リンク先に写真あり)(訳出開始) 「これはパウル・クレーの絵のように見える」、とエリック・コクーニョ(訳注:読み方これでいいのかな?)は呟いた。この考古学者やフランス国立科学研究センターの発掘チームは、9月末におよそ4平方メートルの大きさの壁画をユーフラテス河沿岸のジャアデ・エル・ムガラにある新石器時代集落で発掘した。それは今のところ世界最古と呼べる壁画である。白地に碁盤の目状に赤や黒で描かれた図柄である。 放射性炭素測定法にそれば、この壁画は紀元前9千年紀、つまり1万1千年前のものである。 この壁画が見つかった円形遺構は、集落内のおそらく公的な建築物だったと推測される。住民たちは集会や祭礼のときにこの建物を使ったのであろう。 このような公共建築物はユーフラテス河沿岸の新石器時代の遺跡でも見つかっているが、壁画が見つかったのは今回が初めてである。これまで世界最古の壁画といわれていたのは、トルコ東部(訳者注:トルコ東部じゃないだろ!)にあるチャタル・ホユック(ホームページ)で見つかったものである。 ジャアデ・エル・ムガラの発掘調査はユーフラテス河中流におけるティシュリーン・ダムの建設に伴う遺跡の緊急発掘調査として1990年代初頭に始められた。(ミリアム・ミュラー)(訳出終了) チャタル・ホユックの壁画は紀元前6000年くらいだっけ。あと「壁画」というなら旧石器時代にも洞窟壁画があるが、あれは建物の壁じゃないので、厳密には「壁画」ではないのだろうか。まあ「最古」をつけるのは考古学報道の常道だからな。 トルコ南東部やシリア北部では新石器時代に関する目覚ましい発見が相次いでいるなあ。この10年だけでも新石器時代像はだいぶ変わったように思う。考えられていた以上に複雑で深い信仰や祭司が行われていたことが明らかになってきた。都市の起源は経済活動に求める説が強かったが、最近ではこうした祭祀センターこそが人間の集住の始まりと唱える人もいる。僕はこの時代は専門じゃないのであまり書くとボロが出るから深入りしないけど(笑)。 ただまあ、ダム建設に伴う緊急調査、というのが複雑なところ。遺跡によっては水没して失われてしまうし(1990年代に調査が始まってもまだ沈まない遺跡もあるが)、調査されなかった遺跡も数多い。ティグリス・ユーフラテス河の水資源をめぐっては、上流から順にトルコ・シリア・イラクがそれぞれダムを建設して争奪戦が起き(上流のトルコが一番有利ではあるが)、対立の原因にもなった。 この地域のこの時代の遺跡では、日本隊も紀元前7000年頃の完全に残った女性土偶を発見・修復して5月に朝日新聞で報じられたが、元記事のリンクが切れてしまっている。残念。ここに写真が出てるけど。ちなみにこれは「世界最古」じゃないです。
2007年10月22日
コメント(2)
-
メモ:ニワトリ史
ヤフー・ニュースでこういうニュースを見た。(引用開始)<秋篠宮さま>鶏の起源や家きん化などを講演10月5日20時18分配信 毎日新聞 秋篠宮さまは5日、東京大学(東京都文京区)での「第11回人と動物の関係に関する国際会議」(同会議実行委主催)で、自身の研究テーマの鶏に関して特別講演した。学者ら数百人を前に約30分間にわたって語った。 スライドを示しながら、鶏の起源や家きん化などについて言及。野生の鶏は赤色、灰色、緑色など4種類あり、DNA調査から赤色野鶏が鶏の祖先と考えられること、家きん化は食用が目的ではなく、闘鶏、占い、シンボルとして飼われたのが始まりではないか、などと話した。 (引用終了) へええ、この宮様ナマズじゃなくて鶏が専門だったっけ?、鳥は山階鳥類研究所に出入りしてるというサーヤのほうが専門じゃなかったっけ?と思ったのだが、まあ、それはいい。 ニワトリなんて世界中どこにでもいるもんかと思っていたが、これもネコやほとんどの農耕作物と同様、ある特定の場所で家畜化され、人間の移動や交流によって世界中に広まったものであると知ったのは不覚ながら割合最近(ドイツに行ってから後)だった。実際のところ、ニワトリの家禽化については以前は世界(複数)多元説が強かったみたいなのであながち無理もないか。 DNAとかのことはわからないが、家禽としてのニワトリの歴史に興味をもったのでメモ。・・・・・・・ ニワトリの祖先と考えられるのはセキショクヤケイであるという。上述のように以前は多元説があったが、ほかならぬ秋篠宮らの分子系統学的解析でセキショクヤケイ単元説が確定したのだという(上の記事にある研究ですな。 "Akishinonomiya, F. et al. 1996: Monophyletic origin and unique dispersal patterns of domestic fowl. - Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 93: 6792-6795")。このセキショクヤケイというのはインドから東南アジアにかけて分布している。なかでも今話題のビルマに住むビルマセキショクヤケイがそれらしい。 一方家禽としてのニワトリの遺跡からの出土例は、紀元前6千年紀、新石器時代中期の中国北部(山西省廟底溝、陝西省北首[山令]、陝西省姜寨など)の遺跡で見つかった骨が最古であるという。この骨は正確にはニワトリそのものではなくその祖先のものであるが、本来この地域に分布していない種類であるため、人間によって余所から(おそらく中国南部から)連れてこられた(=飼われていた)と考えてよい。どういう目的で飼われたのかは分らないが、宮様の研究発表にあるように独特の鳴き声や姿が珍重されたのかもしれない。 では原産地に近いインドではどうなのかというと、紀元前3千年紀後半のインダス文明の遺跡から見つかる例が最古になるという。上掲の中国の出土例はニワトリそのものではないので、確実な家禽種としてのニワトリの最古の出土例もこれになる。 中国古代文明とインダス文明の間の交通・交流についてはよく分からないことが多いのだが、インダス文明とメソポタミア文明の間には、ペルシア湾を通った交易網が発達していた。ほどなくメソポタミアやシリアにもニワトリが伝播し、紀元前二千年紀後半(紀元前1500年~1000年)にはエジプトにも伝わっていたらしい。紀元前二千年紀前半(えと、所謂アッシリア・コロニー時代ですね)のアナトリア(現在のトルコ)の遺跡からはニワトリ形の土器が出土している。ややのちのことであるが、拝火教が広まったこんにちのイランでは、ニワトリは神聖な光(日光)の使者として「真実」のシンボルとなった。 中国あるいはインドから世界中に広まった有用動植物というと、養蚕やサトウキビ、米、お茶などが挙げられるが、それらが西洋に伝わったのは初期中世のことだから、ニワトリはずいぶんと早い。インドと西アジアの間の交通・交渉は今後の面白い研究課題になりそうだ。 紀元前8世紀ころのギリシアの詩人ホメロスの作品にもニワトリが登場し、ニワトリは太陽神の使いの見張り役であり、アレス神とアフロディテ女神の密会を密告する。そのころまでにはアナトリアからギリシアに伝播していたと考えられている。ニワトリの骨の出土例はそれ以前の紀元前二千年紀後半の遺跡に見られるのだが、そこで飼われていたのか外部から持ち込まれたのか断定できない。ともあれ遅くとも紀元前600年頃のコリントの黒絵式壺にはニワトリが描かれている。 ギリシア人はニワトリの卵や肉も当然食べただろうが、何より好んだのは闘鶏で、その図柄が壺絵にも描かれ、また雄鶏は勇気のシンボルとなった(現代の英語じゃ「このチキン野郎」とかいうけどね。)。ギリシアの戦士は勇気の印としてその楯に雄鶏を描いた。なおニワトリが食べられていたのはシンポジオンといわれる有力者の宴会に限られ、また古代ギリシアにおける養鶏の中心地はデロス島であったと推測されている。 ニワトリは古代ギリシアの文学作品にも登場しているが、紀元前5世紀の詩人クラティノスはニワトリを「ペルシアの警報」と呼び、またアリストパネスの喜劇「鳥」(紀元前414年)ではやはり「メディア(現在のイラン)の鳥」と呼ばれているところからみて、ギリシア人は東方起源というこの鳥の来歴をなおも記憶していたらしく、また家禽化されていたとはいえなおもエキゾチックな鳥だったことがうかがえる。ニワトリは同性愛の美少年への贈り物として好まれ、ゼウス神がお気に入りの美少年ガニュメデスにニワトリを贈る図柄も残されている。 なお紀元前399年に毒を仰いで自殺させられた哲学者ソクラテスの最後の言葉は「「クリトン、アスクレピオス(医の神)に鶏を一羽、お供えしなければならなかった。忘れずにやってくれ」である。ニワトリが高価な供物として神に捧げられていたことをよく示している。 ヨーロッパへのニワトリの導入経路には、ギリシアのほかに地中海ルートがあり、北アフリカやシチリア島、イベリア半島などに入植したフェニキア人によって、ギリシアとほぼ同時期の紀元前8世紀ころにスペインに持ち込まれたものとみられている(これはオリーヴやブドウの栽培と同じですな)。 フェニキア人と交易したギリシア人やエトルリア人を通じて、ニワトリはさらに北方のアルプス以北のケルト人の領域にもに持ち込まれ、ホイネブルク(ドイツ)から出土した紀元前6世紀(ハルシュタット文化)のニワトリ骨が、アルプス以北で最古のニワトリの出土例である。この頃のニワトリはまだ飛ぶことができたらしく、放し飼いではなく小屋の中で飼われていたようである。スイス(ゲルターキンデンおよびメーリン)でも紀元前4世紀ころのニワトリが出土している。 しかしヨーロッパにニワトリを定着させたのはなんといってもローマ人である。ローマ人は養鶏を商業レベルにまで発展させ、コルメッラは地方ごとのさまざまな品種や餌の調合、去勢など詳細な飼い方を伝えている。ミルクを浸したパンを与えられて丸丸と太ったニワトリの料理が好まれ、アピキウスは17種類のニワトリ料理のレシピを伝えているが、多くは煮て甘いソースをつけて食べる料理である。当時ニワトリはガチョウよりも高価だった。 一方でローマ時代の後期(4世紀ころ)にはニワトリの卵は再生のシンボルとして墓に副葬されるようになり、これはキリスト教にも取り入れられた。イースター(復活祭)に隠した卵を探す習慣があるが、これはキリスト教以前の信仰が取り入れられたのだろう。ニワトリを使った占い(小屋にとどまるか飛び去るか、食べ方はどうかなどで判断)が行われ、またニワトリが左から現れるのは縁起が良いとされていた。第一次ポエニ戦争の際の紀元前249年に行われたドレパナの戦いでは、餌を食べないニワトリの様子を見たローマの将軍の「食べなければ、飲むだろう」という事前の予言どおりに、ローマ海軍は大敗して海水を飲む羽目になった。 ニワトリの原産地である東南アジアからは、ポリネシア人が船に乗って太平洋の島々に伝えている。南米にはスペイン人の来襲(16世紀)以前からニワトリの一種がおり、ニワトリ家禽化多元説の根拠にもなっていたのだが、チリで発掘されたニワトリの骨の年代測定やDNA分析から、このニワトリはコロンブス以前にポリネシア人がもたらしたものと結論付けられた(リンク)。 なお日本だが、これはおそらく弥生時代に稲作とともに中国大陸から伝わったと考えられる。神社の鳥居が象徴するように、鳥は稲魂を運ぶ神聖な生き物である。日本神話では天岩戸の物語にもニワトリは登場するし(常世長鳴鶏)、闘鶏も行われていた。 日本語のニワトリの語源は「庭の鳥」という以外に「丹羽鳥」、すなわち丹(硫化水銀)のように赤い羽の鳥という説もあるが、秋篠宮の講演にあるように赤色野鶏(セキショクヤケイ)がニワトリの祖先ということなら、後者の方が噺としては面白い。・・・・・・・・ なお世界の2004年の鶏肉生産量は以下の通り。1.アメリカ 1553万(トン、以下略)2.中国 947万3.ブラジル 866万4.メキシコ 225万5.インド 165万6.スペイン 126万7.イギリス 124万8.日本 124万9.フランス 113万10.インドネシア 110万 :14.トルコ 94万 ドイツは20位以内に入ってないのか(その分ガチョウなどが多いのかも)。鶏肉が結構高い訳だ。まあ世界的に鶏肉が安くなったのはアメリカで産業的養鶏が始まった1950年代以降らしいけど。イスラムやヒンズーといった宗教の禁忌にも引っかからないし、割合ヘルシーだというので世界的に消費されている肉である。 僕は鶏肉が好きではなかったが、加齢とともに食べるようになってきている。ただ煮たものより焼いたのが好きだな(煮た鶏の匂いが苦手)。あと毛穴が分かる皮とか臓物系は今もダメ。
2007年10月05日
コメント(4)
-
命婦のおとど
今日はネットで見かけた小ネタ。(引用開始)古墳時代にネコ渡来? 須恵器に足跡9月4日6時1分配信 産経新聞 兵庫県姫路市四郷町の「見野(みの)古墳群6号墳」から、ネコではないかとみられる小動物の足跡がついた6世紀末~7世紀初頭の珍しい須恵器が発掘された。ネコの足跡とすれば、渡来は奈良時代(8世紀)という通説を覆し、古墳時代にすでにネコが渡来していたことになり、日本史を塗り替える“新発見”となるかもしれない。 足跡は、「杯身(つきみ)」と呼ばれるふた付き食器の内側に、直径約3センチほどのツメのない5つの肉球と掌球とみられる形がくっきりと残っていた。発掘後に洗浄作業をしていた立命館大の学生が見つけた。 焼く前の器を乾燥させているときに、偶然踏まれてついたとみられる。調査にあたった立命館大の南部裕樹講師によると、小動物の足跡が残っている土器が発掘されるのは「極めてまれ」で、ネコとみられる足跡がついていたことについても「見たことも聞いたこともない」と話している。 (引用終了) へえ、僕は大の猫好きだけに、これは面白いな。でもこれ本当に猫の足跡なんだろうか?動物の専門家が見れば一目瞭然なんだろうが。こちらには実際の写真もあるが、うーむ。確かに猫みたいだな。 僕はあまり須恵器の型式に詳しくないので書くとボロがでるから書かないけど(笑)、どの型式になるんだろうか。「6世紀末から7世紀初頭」と書くと無味乾燥だけど、分り易く言えば要するに聖徳太子の時代ですね。須恵器の工房や大王(天皇)の宮中を猫がウロウロしてたと思うと面白いのだが。 猫も好きだけど、僕は大学(日本)の時に須恵器を焼いた窯(7世紀頃)の発掘を見学したことがあるし、須恵器を自分で作って窯で焼く実験に参加したことがあるので、とても興味深いニュースではある。 僕も動物の足跡がついた土器を見た記憶がないが(ましてや古墳の副葬品には)、西アジアで建築材として使われる日干し煉瓦に大きな犬の足跡や子供の足跡が付いているのは見たことがある。日干し煉瓦は粘土を型枠にはめて成形し、長期間その辺の庭で野ざらしにして乾燥させるから、その上を犬や子供が走り回って誤ってついてしまったというのはよくあったことだろうと思う。もっとも僕が見た足跡付きの日干し煉瓦があったのは、農村とかの遺跡ではなくてヒッタイト帝国の神殿の跡なんですけどね・・・・。 副葬用の須恵器に猫の足跡が付いていたら、いわば「不良品」なんだが、当時は工業規格なんて考えもないだろうし、猫も須恵器も割合貴重品だったからむしろステータスシンボルになるし(?)、そもそも「杯身はどうせ蓋をしちゃって中をあまり見られないから問題ない」と思ったんだろうか。 ネコの歴史については以前日記を書いたので繰り返さないが、その補足をメモしておく。 この日記を書いたときは知らなかったが、その後遺跡から発掘された「世界最古の猫」の骨というのが報告されていて、それは地中海のキプロス島にあるシロウロカンボスという遺跡で、紀元前7500年頃の新石器時代のお墓から猫の骨が見つかったという。たまたまヤマネコか何かが紛れ込んだわけではなく、明らかに人間と一緒に埋められていた(つまり猫は人間のお供をさせるため殺された?)。しかもキプロスには山猫はおらず、明らかに外部からもちこまれたものであるという。これは猫の家畜化の証拠にはならないが、人間にとってすでに何か意味のある動物になっていたことは間違いない。 おそらくは農耕とともに西アジア(ヤマネコがいる)から来たのではないかと思うのだが。やはり「猫は文明とともに」だな。なおこうした明確な証拠ではなく、単に猫の骨片が出土したというのならばやはりシロウロカンボスよりやや遅い時期の西アジア(イラク、ヨルダン、トルコ)の複数の遺跡に出土例があるということだ。パレスチナのイェリコでは紀元前6千年紀の猫の骨格が発見されているが、こちらは家畜というより狩られたものとみられるという。 ヨーロッパに猫が出現した時期を研究することは意味があって、それはつまり西アジア文明との交流を示しているからである。ごく最近、「サイエンス」に世界の猫900匹以上のミトコンドリアDNAを分析したところ、その祖先は13万年前のリビアヤマネコであることが判明したという研究成果が報じられたが、つまり猫は野生のヤマネコが生息している各地でばらばらに家畜化されたわけではなく、おそらく西アジア(及びエジプト)で一元的?に家畜化した可能性が高くなった。ヨーロッパにもヨーロッパオオヤマネコがいるが、気が荒いこともあって家畜化はされなかったらしい。何よりローマ人は猫を珍しがっているのだから、猫が当たり前な動物ではなかったろう。 通説では、ヨーロッパ(この場合ギリシア、イタリア、スペイン)に猫をもたらしたのはフェニキア人であるとされている。古代エジプトでは猫が大切にされていて、その持ち出しは厳禁だったのだが、フェニキア人が船でエジプトからこっそり持ち出したのだという説もある。まあフェニキア人の船に猫が勝手に乗り込んだのかもしれないが(でも猫は臆病だからそれはないかな)、船荷をネズミから守るのに猫は重宝する。そもそも猫はエジプトだけにいたわけではないから(フェニキア=今のレバノンにもいたはず)、この噺はちょっとおかしいんだが。 ギリシアの壺絵では紀元前5世紀ころから猫が描かれ始めている。この地域からさらに北方に広まっていったが、ケルト人やゲルマン人にとっては猫はまだまだきわめて珍奇な動物だったようである。 ところがオランダのアムステルダム近郊では、紀元前2000年頃の遺跡から猫の骨が発見されているという。もしこれが家畜猫だとすれば、この地域と西アジアあるいは地中海世界との接触が既にあったことになるのだろうか?これまた最近北海沿岸の遺跡からミノア文明(ギリシア)の遺物が発見されたというニュースがあったし、またドイツ南部でも地中海系の遺物(牛皮形青銅インゴットの一部)が発見されている。これらはモノだから人の手を伝って移動することもあるだろうが、猫は生き物だからなあ。地中海世界(及び西アジア)と北方ヨーロッパとの早期接触はもっと評価したほうがいいのかもしれない。 アルプス以北のヨーロッパに猫が広まったのは、ローマ人による普及もあるだろうがやはり民族大移動の時代(5世紀)以降ということになると思う。やはりオランダのトフティングというところでは紀元後1世紀頃の猫の骨が発見されている。
2007年09月04日
コメント(15)
-

戦死者の集団墓地
本題の前にちょっと。 7月29日の参議院選挙は予想されていたとはいえ自民の大敗、民主の躍進という結果に終わった。正直ここまで自民が負けるとは思わなかった。安倍首相が辞めなければならない法的根拠もないが、このまま続けるのもいかがなものかと思える。ただ「勝った」(僕には「自民が負けた」といったほうが正確だと思うんだが)民主党のほうが、これからの一挙手一投足に気をつけてゆかねばならないのだと思う。 さっそくイラク特措法がらみでアメリカのほうから動きが出てきているみたいだが、1991年の湾岸戦争の時に自衛隊をペルシア湾に送ろうと奔走し、日本に対して機嫌を悪くしていたアメリカの在京大使館詣でをしていたのは現在の民主党の顔である小沢氏(当時自民党幹事長)だった。その小沢氏が「アメリカ大使に会う必要はない」とこれをこれを断ったり、自衛隊派遣に青筋立てて反対した社会党議員と同じ党にいるというのは、時の流れというかなんというか。・・・・・・・ もう8月になったか。 日本では8月というと原爆忌や終戦記念日やらで戦争(といっても一つに限るが)についての話題が多くなる。ドイツだとそれは5月にあたるんだろうが(降伏調印が行われたのは5月8日)、日本のような「ハイここまで」ではなく、本土をほぼ完全に占領されるまで戦争を続けたから地域によって敗戦の日は違うし、そうした時季感覚はあまりないかもしれない。 ドイツは歴史上何度か戦争の惨禍に見舞われているが、第二次世界大戦は(ドイツ自身が起こしたものではあるが)その最たるものかもしれない。 第二次世界大戦におけるドイツの死者は資料によって異なるが、ウィキペディアを見ると軍人・軍属553万人、民間人181万人、ホロコーストの犠牲者16万人、合計750万人で、当時の総人口の1割に上るという。これは日本の3.6%に比べかなりの高率で(日本の死者数の見積もりも資料によりかなりばらつきがあるが)、これを上回るのは当のドイツに蹂躙されたポーランド、ソ連など東欧諸国しかない。 この数字にはおそらく、戦争の結果として敗戦後に東欧諸国から追放され、その際に報復で殺されたり野垂れ死にしたドイツ系住民147万人の数字は入っていないので(それを戦争犠牲者に含むことを東欧諸国は拒否するだろうけど)、それを含むと割合はさらに上がる。 ところが歴史上、これ以上の惨禍をドイツにもたらした戦争があった。1618年から48年まで三十年にわたってドイツを舞台に行われた、その名も三十年戦争である。もちろん30年間休みなく戦争していたわけではないが、緊張にあったことは間違いない。 当時ドイツの人口は推定1600万人くらいであるが(同時代の日本よりやや少ないくらい)、それが戦後に1000~1100万になったというから、人口の3分の1が失われたことになる。これほど深刻な人口減少は14世紀のペストの大流行以外に例がない。日本史上でもここまでのものはないだろう。 実例を挙げると、・1631年のマクデブルク攻略の際、市民の3分の2にあたる2万人が殺され、残った都市も完全に破壊された・1634年のアウグスブルク攻防戦の際、周辺農村から逃げ込んだ農民も含む6万人が戦闘、飢餓、疫病で死亡・ヴュルテンベルク公国の人口が40万人から5万人に減少・ヘンネブルク伯領の人口が6万→1万6千に減少・プファルツ地方のフランケンタールでは、1万8千人のうち生き残ったのは324人・レーヴェンブルクの人口は6500人から40人に減少し、この町の人口が1618年のレベルに回復したのは20世紀のこと こうも人口が減少したのは、戦闘そのものの惨禍もさることながら(この時代の戦争は都市の攻防戦以外は無人の野外で行われることが多い)、参戦した諸国の兵士による略奪や疫病の蔓延によるところが大きい。 本来ドイツ国内のキリスト教の宗派対立が引き金となったこの戦争には、旧教側のオーストリア、スペインに加え、デンマーク、スウェーデン、フランス(旧教国だがオーストリアとの対抗上、新教側に味方した)といった列強が直接介入した。戦争はいつしか本来の大義を忘れて西欧列強のパワーゲームの場と化したが(スペインの凋落とフランスの興隆を決定づけた)、分裂状態にあって介入を招いたドイツこそいい面の皮である。ドイツの各都市の歴史を見ると「スウェーデン軍に攻撃された」「フランス軍に攻撃された」という記述を実に頻繁に見る。 この時代の戦争は主に各国に雇われた傭兵によるもので(スイスやスコットランドがその主な供給源)、ヨーロッパ各地からおよそ100万人もの兵士が職(=戦争)を求めてドイツに流入したといわれる。こうした兵士は国王などからもらう俸給のほか略奪で財をなし、「戦争が戦争を生む」という状況が繰り広げられた。自ら軍を編成し、戦利品でそれを維持した傭兵隊長ヴァレンシュタインなどはその典型である。「我思うゆえに我あり」の哲学者ルネ・デカルトも、若い頃風雲を求めて傭兵になっている。 こうした悲惨な戦禍(周りの人の三人に一人が消える事態を想像してみるとよい)を受けたドイツでは国民性までもが変わってしまい、酒の飲み方が変わったとさえ言われているのだが(バカ騒ぎしなくなったという)、それがやがてもっとも先鋭で攻撃的な民族主義を生み、さらに20世紀には2度の世界大戦の主役となるのだから、歴史とは「流れる」ものだと思う。・・・・・・ やっと本題。 今年6月、ドイツ東部ブランデンブルク州ヴィットシュトック近郊の採砂場で偶然遺骨が発見され、発掘調査の結果これは三十年戦争当時の戦死者の集団墓地であることが判明した。発見された遺骨は100体に及び、狭い間隔で横向きに寝かされて並べられて埋められていた(記事=英語)。 実はこうした古戦場で戦死者の遺体がまとまって発見される例はあまり多くないという。戦闘が行われれば当然多くの戦死者が出るが、その遺体は係累に引き取られることがなければ放置されることになる。しかしほうっておくといくら野犬やカラスが片付けるといっても腐敗するし疫病の原因にもなるので、誰かがこれを埋めたり焼却せねばならない。そこに駐留する勝利者の軍勢、近隣住民、聖職者(日本だと時宗の僧侶か)などがそれをすることになる。しかし埋葬というよりは「処分」なので、人知れず忘れられていくことが多い。しかも記録に残る戦闘と照合されることは滅多にないだろう。 この記事には、ヨーロッパにおける13世紀から19世紀までの古戦場の集団墓地の数少ない発見例として以下を挙げている。古来戦争を繰り返してきたヨーロッパにしては少ない気もするが。・スウェーデンのゴトランド島で発見された、1361年のデンマーク・ハンザ戦争の集団墓地・イギリス北部タウトンで発見された、1461年3月29日のタウトンの戦い(ばら戦争)の戦死者43人の集団墓地・1500年2月17日、ドイツ農民軍がデンマークの騎士軍を破ったヘミングシュテットの戦いの集団墓地・リトアニアの首都ヴィリニュスで2002年に発見された、1812年のロシア遠征に参加したナポレオン軍兵士2000人の集団墓地。興味深いことに遺体には傷はなく、多くは飢えや寒さ(「冬将軍」)で死んだものと考えられている ふむふむ。日本だと鎌倉でそういうのがあったような(材木座)。関ヶ原とか川中島とかにも探せばそういうのがあるかもしれない。アメリカだとスー族がカスター中佐率いる第七騎兵連隊を壊滅させた(1876年6月25日)リトル・ビッグホーンの古戦場における発掘調査が有名ですかね。 まあそんな古いのを出さなくとも、20世紀にはヴェルダンとかソンムとかカティンの森とかスレブレニツァとか南京とか太平洋の島々でそういうのが見つかっているそうだし(南京じゃ陳列してるんだってね)、今も世界のどこかで日々生産されているかもしれないわけですが。 話をヴィットシュトックに戻す。 この戦いは1636年10月4日、新教側のスウェーデンと旧教(神聖ローマ帝国)側のオーストリア・ザクセン連合軍の間で行われた。当時スウェーデンは国王グスタフ・アドルフを失って劣勢に立たされていたが、この戦いでの勝利を期に盛り返し、結局三十年戦争はだらだらと続いて明確な勝者のないままヴェストファリア条約(1648年10月24日)で休戦することになる。 この戦いに加わったのはスウェーデン軍が1万6千、旧教側が2万2千で、規模としてはおよそ1世紀前の川中島の戦いに近い(日本の場合は農兵を多く含んだ数だろうけど)。数的に劣勢なスウェーデン軍が「啄木鳥の戦法」のような迂回・挟み撃ち作戦で苦戦の末勝った。スウェーデン側は死傷3100、旧教側が死者5000、捕虜2000という。同時代の日本の戦争に比べ死者がずいぶん多いような気もするが(大砲のせいかな?)、スウェーデンの捕虜となった兵士たちの多くはそのままスウェーデン軍に加わったというから、傭兵が主体のこの戦争らしいともいえる(関ヶ原の合戦でも、西軍の敗残兵が紛れ込んで決戦前よりも兵士が増えた東軍の部隊があったというが)。 発掘された約130の遺体は上述のように何列にも窮屈に、そして折り重なるように並べられていた。年齢は当然ながら20歳から35歳くらいの若い男性のもので、三体には梅毒の痕跡が残っていたという(四六時中戦争していたヨーロッパでは、兵士を媒介としてこのアメリカ大陸起源の伝染病が瞬く間に広まった)。多くは刃物で叩き切られたり、銃弾に貫かれた痕跡が骨に残っており、まぎれもなく戦死者の遺体である。埋葬の前に身ぐるみ剥がれたらしく、身につけた下着の痕跡以外に武器などの副葬品はまったくなかった(上着や武器は当然生き残った兵士が使う)。兵士といっても雑兵だったのかもしれない。 この戦闘にはスウェーデン人やドイツ人、オーストリア人のほか、スコットランド(スウェーデン方)やイタリア(オーストリア方)の傭兵が多く参加していた。そうした民族帰属も分るかもしれないという。現場主任のアニヤ・グローテ氏は出土人骨の詳細な分析を希望しているが、それには資金調達が先決なのだという。
2007年08月03日
コメント(7)
-
女王のミイラ
あちこちで大きく扱われたこのニュース。 僕はエジプト学が専門ではないのだが、今年に入って古代エジプト最後の女王クレオパトラ、美貌の王妃ネフェルティティについての日記を書いたが、今度は女王ハトシェプストに関するニュースだった。 (引用開始)<ミイラ>古代エジプトの女性「ファラオ」と特定6月27日21時25分配信 毎日新聞 【カイロ高橋宗男】エジプト考古庁のザヒ・ハワス局長は27日、古代エジプト第18王朝(紀元前16~同14世紀)で君臨したハトシェプスト女王(在位・紀元前1502~同1482年)のミイラを特定したと発表した。局長は毎日新聞に「ツタンカーメン王のミイラ発見以来、最も重要な発見の一つ」と強調した。 ハワス局長によると、このミイラは1903年にエジプト南部ルクソールの「王家の谷」で発見されたミイラ2体のうちの1体。1922年にツタンカーメン王のミイラを発見した英国人考古学者、ハワード・カーター氏が発見した。しかし墓自体が小規模で粗末だったため、当時は重要とみなされなかった。 ハワス局長らのチームが、ミイラや所蔵品を調査したところ、1881年に別の墓から発見された、ハトシェプスト女王の名前が刻まれた箱にあった臼歯と、1903年発見のミイラの歯茎の穴が一致した。 ミイラのDNA(デオキシリボ核酸)と、女王の父親にあたるトトメス1世や、祖母にあたる人物のミイラのDNAも極めて似ていたという。 ミイラを調べたところ、女王は太り気味で虫歯があり、糖尿病に苦しんでいた。後継のトトメス3世との不仲から謀殺説もあったが、50歳前後にがんで死亡したという。 同女王は第18王朝第5代で、「ファラオ」の称号を持つ古代エジプトの数少ない女性として知られる。トトメス2世と結婚して王妃に。2世の死後はトトメス3世の摂政として実権を握り、後に自ら女王に即位した。 第18王朝は、現在のソマリアにあたるプントとの交易を行うなど、古代エジプトの栄華を体現した。ハトシェプスト女王は常にひげをはやした男装スタイルの彫像や絵が残されており、長く女性と知られていなかった。 (引用終了) ハワス長官(彼のホームページはこちら。なんとなくセンスがマヒル・チャールのホームページに通じるものを感じるのだが・・・)になってからというもの、センセーショナルなニュースが続きますね・・・。ツタンカーメンのミイラの最新技術での分析、クレオパトラの墓が云々、ネフェルティティ像の返還要求・・・・などなど。漏れ聞くところでは彼はヨーロッパのエジプト学者にはあまり評判が良くないみたいなのだが、彼はエジプトでの発掘調査を統括する地位にあることから、エジプト学の最先端にあることは間違いない。 このニュースも「おお、大発見!」・・・・と言いたい所なのだが、欧米の専門家には「断定するには時期尚早」という意見もある。僕も断定への経緯について興味が沸いた。以下ちょっと調べてみる。上の新聞記事はすっきりとまとめてあって分かりやすくていいのだが、ことはなかなかややこしかったようだ。 先に復習のため、ハトシェプスト女王について軽くおさらい。 ハトシェプストはエジプト第18王朝第五代の女王で、古代エジプトでは数少ない女王である(「最初」ではない)。在位年は上の引用記事では紀元前1482年までとなっているが(ハワス教授が採る説だろう)、1458年までの約20年とする説のほうが大勢らしい。「ハト・シェプスト」は「女性の第一人者」くらいの意味がある。 彼女はエジプト王トトメス1世の娘で、異母兄弟のトトメス2世と結婚している。二人の間には娘しか出来ず、トトメス2世が死んだあと、別の妻との間に出来たトトメス3世が後継者となった。ハトシェプストは義理の息子にして実の甥にあたるトトメス3世の摂政となり実権を握る。 ところが摂政になって6年目の頃、彼女は自ら即位して「マアト・カ・レ」(正義と太陽神の生命)という即位名(王としての名)を名乗り共同統治者となった。名前も女性形のハトシェプストから男性名のハトシェプスに改め、付け髭をして男性として振舞った(付け髭自体は男の王もつけていたのだが)。 彼女の事績の中心は建設活動で、とりわけデイル・エル・バハリにある壮大なハトシェプスト葬祭殿は建設に15年を要し、今はエジプト観光の目玉の一つになっている(日本人新婚旅行客が巻き込まれた1997年のテロ事件の舞台になった)。対外的には平和外交・善隣政策だったという。交易促進のため南方のプント(現在のソマリアか)に探検隊を送り、黒檀や乳香の木(ボスウェリア属)、珍獣を採集させている。 彼女の平和外交はしかし、帝国としてのエジプトの威信低下を招いたという。彼女の治世の間に何度か討伐遠征が行われ、最晩年にはパレスチナのガザに対する遠征(彼女の治世で唯一の外征という)が記録されているが、この遠征はトトメス3世によるものとされており、その頃には実権を失っていたと見ることも出来る。・・・・・・・ 彼女の遺体が同定された経緯だが、ハワス教授は最新のDNA解析技術を用いて、女王ハトシェプストのミイラを見つけようと考え、カイロのエジプト博物館に所蔵されている当該時代の女性のミイラを全て分析したらしい。 ハトシェプストの父親トトメス1世、異母兄弟で夫のトトメス2世、甥で義理の息子のトトメス3世のミイラはまとめて一箇所から発見され誰のものか判明しているので(後述)、DNAを調べれば分かる。ところが該当する女性のミイラは見つからなかった。 ところでカイロ博物館にはハトシェプスト女王の乳母(侍女)の墓から発見されたミイラが所蔵されていた。このミイラが発見されたKV60号墓は上の記事にあるとおり1903年にハワード・カーターにより発見された。ところが墓が既に古代に盗掘されて副葬品に乏しかったためカーターはほとんど手をつけずに放置した(彼はのちに未盗掘のツタンカーメン王墓の発見で名を残す)。 1906年、エドワード・アイルトンがこの墓を再調査し、墓室で二体見つかった女性のミイラのうち、棺に「ハトシェプストの乳母」と記してある一体のみをカイロに運び出し、何者か不明なもう一体は墓に残した。しかしこの墓はろくに位置の記録が残されなかったため、どこにあるかも分からなくなってしまった(今では考えられないことだが)。 1966年、エジプト学者エリザベス・トーマスはこの「乳母」の墓で見つかった二体のミイラのうち一体が墓の主である乳母、もう一体はハトシェプストのものではないかという説を立てた(後述)。しかし当時はDNA鑑定もなく、また墓の位置も分からなくなっていたので証明のしようもなかった。 ところが1990年、KV60号墓がドナルド・ライアンにより再発見される。そこにはアイルトンが残したミイラ一体があった。そのミイラは左手を曲げた王家に属する者のポーズをとっていて、トーマスの説を裏付けるかと思われたが、その墓にはハトシェプストの時代に属する副葬品が全くなかった。そもそも粗末な墓で副葬品が少なく、見つかった土器にも第20王朝(ハトシェプストよりも300年後の王朝)以前のものはなかった。木製のマスク片が見つかったが、それは男性のものだった。ただしハトシェプストが男装していたことを思えばそれはトーマスの説と矛盾しない。 このミイラは新しい木製の棺に入れられて墓室に戻され、墓は再び封印された。 エジプトの全ての発掘調査を統括するハワス教授は、このKV60号墓のことを思い出した。彼はKV60号墓からミイラをカイロ博物館に運び出させ、あとは上の記事にあるとおりだが、葬祭殿から見つかった彼女の名を記した木箱に入っていた歯(注・記事によってはDB320号墓とあるが、どっち??)、そしてDB320号墓から見つかった、やはり彼女の名を記したカノプス壷(ミイラを作る際に取り出した内臓を収める壷)に入っていた肝臓のミイラ、そしてハトシェプストの親類のミイラのDNAとの照合が行われた。こうしてハトシェプストのミイラは同定されたという。 ところで1881年に発見されたこのDB320号墓というのは、そもそも紀元前10世紀の神官の墓だったのだが、盗掘で荒らされた紀元前16世紀から12世紀にかけての50体以上のファラオや貴族のミイラがまとめて収められていた(ハトシェプストゆかりのトトメス1世、2世、3世の他、アメンホテプ1世、セティ1世、ラムセス2世といった著名なファラオのミイラもあった)。ハトシェプストの名が刻まれたカノプス壷はその中の一つである。 ただし第21王朝には同名(「ハトシェプスト」)の女性の存在が確認されており、そちらの可能性も排除できないという。まあトトメス1世などとのDNAと照合したというのだから確実性は高くなるとは思うのだが、そもそも技術的にDNA分析に耐えるのかという批判もあるらしい(その辺はよく分からないけど、今の技術なら大丈夫じゃないか?)。まあこれは詳報を待つよりない。・・・・・・ ところでハトシェプスト女王はなぜこのような粗末な墓(乳母の墓)に埋葬されていたのか? もちろん彼女の本来の墓は別にあった。当初彼女は夫のトトメス2世と同じ墓に葬られるはずだったが、彼女自身が女王になると、即位と同時に王者にふさわしい墓の建設に着手したと思われる。それがKV20号墓で、計画では地上に建設した葬祭殿の真下まで長大なトンネルを掘って墓室を作る予定だったが、地盤の関係で長さ200mのトンネルが掘られた時点で中止され、地下97mのその地点に墓室が作られた。 彼女はこの墓室の下にさらに墓室を増築し、KV38号墓にあった父トトメス1世の遺体をそこに移した。父親と同じ墓に入ったのは、彼女が王位にあるかけがえのない根拠はトトメス1世の娘(男の振りをしていたが)であることと関係するのだろうか。彼女も当初はここに葬られたはずである。 ところが彼女の死後、トトメス1世の遺体は再びKV38号墓に戻された(上に書いたとおり、結局彼の墓はまもなく盗掘され、そのミイラは他のファラオたちの遺体と共にまとめてDB320号墓に移されることになる)。KV20号墓は空にされて彼女のミイラは行方不明になり、1903年にカーターがこの墓を発見したときに残されていたのは、玉座(ベッド)、ゲーム盤(セネトと呼ばれる双六のようなもの)といった副葬品の一部のみだった。 トトメス1世の遺体をKV38号墓に戻し、KV20号墓を空にしたのは、他ならぬ彼女の共同統治者にして義理の息子であるトトメス3世だと考えられている。対外強硬派のトトメス3世(のちに遠征を繰り返して武名を残す)と善隣外交のハトシェプストという二人の共同統治者の間には微妙な競合関係があり、トトメスは彼女の死後復讐に出たというのである。 今回同定されたのが本当にハトシェプストのミイラだとすれば、彼女はその乳母の粗末な墓に移されたことになるが、それをやったのがトトメス3世自身か、それとも別の人物がトトメスの復讐から彼女のミイラを守ろうとしたのかは定かではない。ハワス教授のひらめきの元となったエリザベス・トーマスの説は、こうした背景に基づいている。 ハトシェプストの名はその死後建築物の碑文などから削られ、その彫像の多くも破壊されてしまった。これもトトメス3世の仕業と長らく考えられてきたのだが、実際はこの破壊が行われたのはやや後のことで、女性が王位にあったことを嫌った後世のファラオが彼女の姿や名前を抹殺してしまったという説もある。仮に今回彼女のミイラが発見されたのだとしても、依然それは謎のままである。 あまつさえハトシェプストはトトメスに暗殺されたのだとする説もあったのだが、彼女が糖尿病に苦しみ癌を患っていたこと、外傷がないことがこのミイラからは窺える。この「大発見」により、歴史の謎がまた一つ解き明かされたといえるかもしれない。
2007年06月27日
コメント(8)
-

エトルリア人の起源
歴史好きならローマ帝国を知っている人は多いと思うが、「エトルリア人」という民族を知っている人はそれほど多くないと思う。しかしながら、ヨーロッパの大部分を制覇したローマ帝国もかつてはエトルリアの属国で、その文化もエトルリアから多くを学んでいる(というか模倣)、といえば異様に聞こえるかもしれない。まさに「ローマは一日にしてならず」である。 ローマ人は紀元前500年頃にはエトルリアから独立し、紀元前1世紀までにかつての支配者エトルリア人を征服してしまった。ローマ人たちはエトルリア人の痕跡をほとんど抹殺してしまったので、いまやエトルリア人は「謎の民族」になってしまった。ただギリシャやローマの史書にはエトルリア人がたびたび登場する。だからヨーロッパではエトルリアというのは結構知名度が高く、エトルリア学は早くもルネサンス時代に始まっている。 エトルリア人は遅くとも紀元前8世紀には存在しており、イタリア中部のトスカナ地方を中心としていくつかの都市国家を営み、統一国家を持たなかった。紀元前6世紀頃、ギリシャ人やフェニキア人との交流をきっかけに興隆する。この頃の土器には彩文や把手の形態がトルコで出土するものとそっくりのものがあるが、これは東方様式化時代という同時代のギリシャ陶器の影響の結果である。 海上交易に活躍したエトルリア人は、イタリア南部に入植したギリシャ人とやがて商売仇になり、カルタゴ(フェニキア人が北アフリカに建設した都市国家)と結んでこれに対抗する。紀元前540年、サルデーニャ島アラリアの沖でエトルリア・カルタゴ連合軍はギリシャ人と海戦し、ついに地中海西部の制海権を握り、その繁栄は絶頂に達する。上にローマへの影響について触れたが、アルプス以北に居たケルト人などはエトルリア人を通じて地中海(西アジアやギリシャ)の文明に触れており、ドイツやフランスの先史時代にもエトルリアは無縁ではない。 ところが紀元前500年頃、支配下においていたローマ市が離反して独立し(共和制ローマの始まり)、紀元前478年にはナポリ湾のキュメ(クマエ)沖の海戦でギリシャ人に敗れてその繁栄に翳りが見え始める。紀元前4世紀には北方からケルト人が南下してきて荒らしまわり、エトルリアにさらなる打撃を与えた。 その一方でローマはその勢力を着実に拡大し、エトルリアの都市国家は南から次々とローマに征服されていった。上記のように紀元前1世紀にはローマに完全に併合され、エトルリア人たちはローマに同化されてしまった。 エトルリア人は華麗な壁画古墳や印象的な人形陶棺を残したが、そのうちチェルヴェテリとタルクイニアの古墳群は2004年に世界遺産に登録されている。また世界地図を見て欲しいが、観光地として人気のあるトスカナというイタリアの地方名は、エトルリア人のラテン語での別称「トゥスキ」に由来する。イタリア南部の海はティレニア海と呼ばれるが、これはエトルリア人のギリシャ語名「テュルセノイ」あるいは「テュレノイ」に由来している。 ところでこのエトルリア人、ギリシャ人から導入したアルファベットを使っていたのでその残した文字を読んで発音することは出来るのだが、まだ解読されていない。彼らは自身のことを「ラセンナ」、転じて「ラスナ」などと呼んでいたことは判っているのだが、エトルリア語は言語系統が不明なのである。 不明といえばエトルリア人の起源もよく判っていない。これは古代からすでにそうだったらしく、ギリシャの歴史家はさまざまな説を伝えている。紀元前1世紀の歴史家ディオニシオスが、エトルリア人はイタリア固有の民族であると伝えている一方で、著名な歴史家ヘロドトス(紀元前5世紀)はその著書「歴史」の中でエトルリア人の起源について以下のように伝えている(巻1、94節。訳は松平千秋による岩波文庫版)。 ・・・リュディア全土に激しい飢饉が起こった。リュディア人はしばらくの間はこれに耐えていたが、一向に飢饉がやまぬので、気持ちをまぎらす手段を求めて、みながいろいろな工夫をしたという。そしてこのとき・・・(サイコロ遊びなど)あらゆる種類の遊戯が考案されたというのである。・・・さてこれらの遊戯を発明して、どのように飢餓に対処したかというと、二日に一日は、食事を忘れるように朝から晩まで遊戯をする。次の日は遊戯をやめて食事をとるのである。このような仕方で、18年間つづけたという。 しかしそれでもなお天災は下火になるどころか、むしろいよいよはなはだしくなってきたので、王はリュディアの全国民を二組に分け、籤によって一組は残留、一組は国外移住と決め、残留の籤を引き当てた組は、王自らが指揮をとり、離国組の指揮は、テュルセノスという名の自分の子供にとらせることとした。国を出る籤に当った組は、スミュルナに下って船を建造し、必要な家財道具一切を積み込み、食と土地を求めて出帆したが、多くの民族の国を過ぎてウンブリアの地に着き、ここに町を建てて住み付き今日に及ぶという。彼らは引率者の王子の名にちなんで、・・・テュルセニア人と呼ばれるようになったという。 「寝食を忘れて」とはいうけど、実際に出来ますかね? それはともかく、リュディアというのは現在のトルコ西部、スミュルナというのは現在のイズミル市(エーゲ海岸にあるトルコ第三の都市)にあたる。つまりエトルリア人は現在のトルコからイタリアに移住した者の子孫だというのである。そういやローマ市を建設したアエネアスも、トロイア(トルコ北西部)出身ということになってますな。 ただし上記ディオニシオスはこのヘロドトスの記述に対して、リュディア人とエトルリア人では言語も宗教も違うので信じられない、とコメントしている。ただ現代の学問ではディオニシオスの主張を裏付けることも出来ないし、彼の時代にはエトルリア人はほとんどローマ化していたということも出来る。 ローマ文明の起源にもつながる問題だけに、これについては長らく議論がなされてきたが、なにぶん考古資料を除いて歴史資料の少ない時代のことでもあって結論を見ず、起源そのものよりもむしろどのようにしてエトルリア人という民族が成立したのか、その過程に研究の興味は移っていた。 ここでやっと本題だが、この起源論争に一石を投じる研究成果が先日発表された。古色蒼然としたこの問題に使われた研究方法は、DNA解析という最新技術を使ったものだった。 トリノ大学のアルベルト・ピアッツァ教授を中心とする研究グループは、かつてのエトルリアの中心地であるトスカナ地方のムルロ、ヴォルテッラ、カセンティーノといった町に代々住む住民のDNAを採取し、イタリアはじめヨーロッパ各地の住民のDNAと比較した。この地の住民のY染色体はハプログループGに集中しているのだが(済みません、僕自身はなんのことやらさっぱり分からんのですが)、この特徴を持つ集団はイタリア国内には他にいなかった。似た傾向を持っていたのが、なんと現在のトルコに住んでいる人々だったという。 エトルリア人のDNAに関する研究はここ数年すでに行われていて、イタリア・スペインの別の研究グループがエトルリアの遺跡から出土した人骨80人分のDNAを分析したところ、互いには非常に近いものの、現代イタリア人のそれとはかけ離れていることが判明したという。また現代のトスカナ地方の牛のミトコンドリアDNAを分析したところ、親縁性のある例はイタリアはおろかヨーロッパに全くみられず、中近東にあったという。 これらの結果からピアッツァ教授らは、エトルリア人が小アジア(アナトリア)からイタリアへ移民したというヘロドトスの記述は信憑性がある、と結論付けた。牛については、テュルセノスに率いられたエトルリア人が最低限の家畜を連れていたためだろう、という。 この記事を見たときは、ほう面白いな、とは思ったのだが、すぐに「ホンマかいな」と思うようになった。今のトスカナ地方の住民とエトルリア人を同一に見ていいのだろうか? イタリア数千年の歴史の中で、東方から多くの移民がやってくる時期はいくつもある。エトルリアののちのローマ帝国は西アジアにまで版図を拡大していたので、そこの出身者がローマ兵士としてイタリアに来ることもあったろう。また5世紀の民族大移動の時代には、ゲルマン人のほかアッティラ率いるフン族など、東方からさまざまな民族が到来した。現在だってトルコ人やアルバニア人がどんどん来てるんじゃないだろうか。 まあ「エトルリアの遺跡から出土した人骨」というのだから、遅くともエトルリア人は東方と関係があったかもしれないが、この分析だけではこの特徴を持つDNAが「いつ」イタリアに来たのかは分からないので、エトルリア人よりもはるか以前、たとえば西アジアから農耕が伝わった新石器時代のカーディアル文化の名残り、と考えてもおかしくはあるまい。 まあもう少し成り行きを見守ってみますか。 ところでエトルリア人移民のエピソードは僕の専門にも無縁ではない。 紀元前12世紀初頭にヒッタイト帝国などを滅ぼしてエジプトに襲来し、西アジアを混乱に陥れたという「海の民」にはいくつかの部族名が言及されている。「海の民」を撃退したエジプト王メルネプタ(紀元前13世紀末)の碑文には、「海の民」としてシェルデン、シェケレシュ、エクウェシュ、ルッカ、テレシュといった集団の名前が言及されるが、これはサルデーニャ、シチリア、アカイア、リュキア、ティレニアといった後世のイタリアからトルコにかけての地名に比定されている(異説もある)。繰り返すがティレニアとはエトルリア人のギリシャ語名である。またヒッタイト帝国の末期には飢饉が頻発していたことが文字資料から窺えるのだが、これとヘロドトスの伝える「18年に及ぶ大飢饉」は同じものか。 飢饉に苦しみ新天地を目指し海に漕ぎ出したリュディア人たちは、エジプト経由でイタリアへ向かったのか?逆にイタリアからエトルリア人の祖先がアナトリアに向かったのか?それとも別の時代の全く関係ないエピソードなのか。あるいは数世紀に及ぶ文化交流(民族移動ではなく)を掻い摘んで述べたものなのか?あるいはアエネアスと同じく民族起源伝承の類なのか。 出土する考古遺物でいうと、紀元前12世紀以前には該当地域ではいずれもミケーネ式の土器や牛皮形青銅鋳塊が出土するので、地中海で活発な交易網が形成され人的交流があったことは間違いないし、紀元前12世紀頃からは手づくねのブッケロ(瘤つき)土器という特徴的な土器が見られることも共通する。 肝心のアナトリアとイタリアを直接結びつけるこの時代の遺物は今のところ見つかっていないのだが、興味は尽きない。 Asia Etruscos sibi vindicat.(セネカ)
2007年06月24日
コメント(6)
-

Der Mann aus dem Eis
今日の日記(?)は、たまゆら1/fさんも書いておられたこのニュース。(引用開始)アルプスで5000年前に殺人?=「アイスマン」、矢を受け致命傷-CTで確認6月16日9時1分配信 時事通信 アルプスの氷河で1991年に発見された約5300年前の氷漬けのミイラ「アイスマン」は、左肩に矢を受けて動脈に傷を負い、間もなく死んだことが分かった。発見場所付近ではおのも見つかっており、争いの犠牲になったとみられる。スイス・チューリヒ大などの研究チームが死因を解明し、16日までに考古学誌ジャーナル・オブ・アーキオロジカル・サイエンス電子版に発表した。 アイスマンは、海抜3210メートルのイタリア・オーストリア国境のエッツ谷で、登山者によって発見された。40代ぐらいの男性とみられ、新石器時代の人類の身体状態や暮らしぶりを探る手掛かりとして、研究者の注目を集めてきた。 死因をめぐっては、極度の疲れや心臓発作、脳卒中など、さまざまな見方があったが、オーストリアの研究チームが2001年、X線写真撮影で左肩内部に石でできた長さ約2センチのやじりがあるのを発見したと発表。今回、コンピューター断層撮影装置(CT)で動脈の傷が詳細に分析され、命取りになったことが確認された。 (引用終了) このニュース、10日くらい前にドイツのヤフーで見かけたのだが、それはチューリッヒ大学の記者発表を元にした記事で、正式に発表されたのが今日ということか。 この記事にあるように、すでに「アイスマン」の死因は2001年に死因は肩に鏃を打ち込まれたこと、すなわち他殺だったと推測されていたのだが、今回それが証明された、ということか。 日本では「アイスマン」というなんだかヒーロー漫画のキャラクターみたいな名前が通称になっているが、ドイツなどでは発見地のヱッツ(Ötz)渓谷にちなんだ「ヱッツィ」というあだ名が定着している。「ネブラの天文盤」にならぶ、近年のヨーロッパ考古学上の大発見ということもあって、ヨーロッパでは一般にも広く知られている。 ヱッツィが展示されているイタリア最北部のボーツェン(イタリア名・ボルツァーノ)にはドイツとトルコの間を車で往復する際に何度も通ったので、僕は実際に何度も見ている。ヱッツィは冷凍カプセルみたいなところに、死んだときの状態のまま素っ裸で寝かされて展示されていて(性器はほとんど分からなくなっているが)、ちょっと可哀想に思ったものだった。 ボーツェンはあの辺では一番大きな町で、ヱッツィという目玉商品があるせいか、そこの南チロル(アルト・アディージェ)考古学博物館は、町の規模に似合わぬかなり立派なものだった(外見は地味だけど)。ボーツェンでは車上荒らしにあったりいろいろ思い出があるのだが、それはまた別の話。周りも風光明媚でいい町です。 ヱッツィについては、調査にあたったインスブルック大学のコンラート・シュピンドラー教授(故人)による一般向けの本も出ているので、詳しくはそちらを見てもらえばいいのだが、最新の技術を使った研究が日々進んでいるのはこのニュースが示すとおりである。 ヱッツィが発見されたのは1991年9月19日だった。標高3200メートルというのが示すように、普通は登山者しか寄り付かない場所である。発見したのは登山中のドイツ人の夫妻だった。なお第一発見者については俺が私がという人物(スイス人やスロヴェニア人など)が現れ、「お前は私に呼ばれて写真を撮っただけだろう」などと論争になり、さらには居合わせた著名な登山家のラインホルト・メスナーまで巻き込んでついには裁判沙汰にもなったのだが、ボルツァーノ地方裁判所の判決ではこのドイツ人夫妻ということが認められている。 発見当初は当然ながら登山して遭難した人物の遺体だろうと推測された。アルプス山中では氷河の中から遺体が腐らずにミイラ化した状態で発見されることがしばしばあり、2004年にも第一次大戦当時のオーストリア兵の遺体がやや南のトレンティーノ州の氷河から発見されている。通報を受けたオーストリア当局の担当者は遺体を覆っていた氷をピッケルで砕いたため、傷をつけてしまった。 なおこの遺体が1991年になって発見されたのには、地球温暖化による氷河の後退も関係している。 氷を溶かして運び出された遺体はオーストリアのインスブルックにある遺体安置所に運ばれ記者に公開されたが、その際写真撮影はおろか触ることも許可されたので、のちの遺体保存に悪影響を残すことになった。ところが実際はかなり古いものらしいというので当地の大学に移されてシュピンドラー教授(考古学)の調査を受け、なんと5000年前の遺体であると判明することになった。 ところで発見されたヱッツ渓谷は、1918年に終戦した第一次世界大戦の結果、頂上はオーストリア領、その下の裾野はイタリア領になったという微妙な地点である(それ以前はオーストリア領)。すぐにこの遺体の所属をめぐってオーストリアとイタリアの間で論争が起きたが、詳細な調査の結果イタリア側に92m入った地点だったことが判明した。このためドイツ(ローマ・ゲルマン中央博物館)での保存処置ののち、遺体はイタリアのボルツァーノで展示されることになり、こんにちに至っている。 ヱッツィという愛称をつけられた男性の遺体は、驚くべき調査成果をいろいろともたらした。5000年前の遺体が腐朽せずに残っているのも奇跡だが(中国にも同じくらい古いミイラがなかったっけな?)、胃袋の中身から既往症、DNAまでありありと判明したのである。さらに彼の持っていた持ち物や衣類も回収されて詳細な調査を受けた。 ヱッツィは身長158cm、水分が抜けて収縮した現状の体重は38kg、死亡時の年齢はおよそ45歳、さらに自然科学による年代測定により、彼が生きていたのは紀元前3340年頃の新石器時代と判明した。歯は激しく磨耗しているが、これは摺石で麦を脱穀していた当時としては特段珍しいことではない。 興味深いのは腰や右足などに15箇所に刺青がしてあったことで、これは現代でいう鍼・灸のツボにあたる箇所に施されていた。薬草を針で皮下に押し込むやり方で行われた刺青は並行する複数の線状や十字形をしており、全部で47個あった。彼はリウマチもちだったのかもしれない。 新石器時代といえば石器を使っていた時代だが、彼の髪の毛からは砒素が大量に見つかっており、おそらく銅の冶金に携わっていたことが推測される(青銅が発見される以前の銅は、砒素を含ませる、あるいは含んでいることで硬度を得た)。 それと符合するように、おそらく当時としては珍しかったであろう銅の斧を彼は携帯していた。この銅斧は銅が99%と純銅に近く、オーストリアのザルツブルク近辺で採掘されたものと判明している。この時代の銅斧はいくつか発見例があるが、このヱッツィの斧のように、木製の柄まで残っている例はもちろん皆無である。これで木を切ったのだろうか。 またヱッツィはフリント(火打石)製の短剣をもっていた。この火打石はイタリア北部で採掘されたもので、すでに5000年前に人も越えぬと思われがちなアルプス山脈を越えて南北で交易が行われたことを示している。もちろん彼自身の遺体が、アルプス越えの実態を如実に示しているのだが。斧や短剣のほか、弓矢も持っていた。 彼の衣服はおおむね皮製で、上着や下着、靴や帽子まで揃っていた。彼の死亡時期は付着していた花粉などから晩春と推測されるが、残雪厳しいので防寒はばっちりである。地面に敷いて寝るためのマット(布)まで携帯していたので、山中での野宿もしていたはずである。 残雪のある3000mの高山で彼は何をしていたのか、そしてなぜ死んだのかは大きな謎である。 死因が特定されるまでは、事故死や生贄、病死などの説が提出されていた。ボーツェンの博物館では高山でのヤギの移牧の様子が映し出され、ヤギが雪に足を滑らして谷底に落ちていく様子を写したビデオが上映されていたのを覚えている。 ところが上のニュースのように、ヱッツィは肩に矢を受けて出血多量で死んだことが判明した。上の記事には触れられていないが、彼は左手にも切り傷を負っており、さらに少なくとも4人にのぼる他人の血が彼の衣類に付着していたことも判明した。彼の携帯していた矢(多くは未成品)にも少なくとも二人の人物の血液が付着していた。明らかに彼は、3000mの高山で集団で何者かと殺し合いをしたのである。そして逃げようとして背後から射殺された。 彼の腸内には植物遺存体が残っていたが、それは標高2400m辺りに生える植物のものだった。彼は殺害される6時間前に近くの谷(シュナルス、あるいはエッチュ渓谷か)の野営地でそれを食べ、北へ向かって死出の旅に出たと思われる。 なお発見者のドイツ人は2004年に山で遭難、シュピンドラー教授も2005年に急死した。これまで7人の関係者が事故などで死んだため、「ヱッツィの呪い」が地元でささやかれたそうだが、ヱッツィの「関係者」は数百人にのぼるんだから、これはまあ「お話」ですな。・・・・・・・ 先週までドイツのテレビ局ARDでは、ヱッツィの時代の生活を再現したドキュメンタリーを放映していた(ホームページ)。二家族13人を二ヶ月間、当時そのままの住居に住まわせ(もちろん完全に再現、とはいかなかったようだが)、食料もいちいち自分で加工させ、それを記録していった。共同生活の住人の生活(喧嘩まで)を露悪的に伝える人気番組「ビッグ・ブラザー」の石器時代版というべきか。 僕自身は見ていないのだが、この番組を見た人によれば当時の生活はまさに「食うために一日を過ごす」ようだったという。パンを焼くための小麦からして自分で脱穀せねばならないのだから(しかも石を使って手で)、その苦労は察するにあまりある。 この番組の一回はヱッツィのアルプス越えの再現に当てられており、ヱッツィの着ていたそのままの衣服(これも完全に同じじゃないかもしれないが)を来た人がアルプスを歩いてゆく。 とてもよく出来たホームページで、ドイツ語が出来なくてもヴィジュアル的に楽しめるので、ぜひご覧ください。環境によってはちょっと重いかもしれませんが。・・・・・・・ 最後に、ヱッツィに関する(あまり面白くない)冗談を紹介。ヱッツィの所属をめぐってオーストリアとイタリアが論争したときに作られた冗談だろうか。 「彼はイタリア人ではなかった。なぜなら自分の道具を携帯していたから。彼はオーストリア人ではなかった。なぜなら脳が残っていたから。彼はスイス人かもしれない。なぜなら氷河の中で発見されたから。いや、もしかするとドイツ人かもしれない。ドイツ人以外に誰がサンダル履きで高山に行くというんだ?」
2007年06月16日
コメント(4)
-
宗教改革の証人
いつものように考古学関連のニュースから。 チューリッヒは人口37万、スイス最大の都市である。僕はだいぶ前に一度行ったきりだが、大きな谷を流れる川沿いに広がる広々とした市街と、高台の上にある立派な大学が印象に残っている。 さてそのチューリッヒの旧市街の中心にはミュンスター(大聖堂)があり、その前は広場になっている。その広場にゴミ用の地下コンテナを建設することになり、発掘調査が行われた。近代になって市営墓地が別に作られるようになるまで、ヨーロッパの都市では死者は教会の周囲に埋葬されるしきたりで(破門者や異教徒は当然別の場所だが)、教会の周辺を発掘するとその周囲は大抵墓地になっていて、前近代の墓が見つかることが多い。 ここでも予想通り墓地が見つかったのだが、そのうち一つの穴が異様だった。2.5x5mの大きさの穴の中に人骨がぎっしりと埋められていたのである。頭蓋骨、肋骨、手足の骨などがばらばらかつ乱雑に投げ込まれていた。まだ穴の底に達していないので深さが分からず、どのくらいの量の骨が埋められていたのか分からないという。 教会の周囲の空き地は面積が限られているので、新しく埋葬するときに掘り返して出てきた古い墓の骨をどけてまとめて埋め直すことはよくある。しかしこのような大穴にこれだけ大量の人骨が埋められていることは極めて異常である。 ぱっと思いつくのは、戦争や疫病で大量の使者が出たのでまとめて埋められた、という解釈だが、その場合骨がばらばらになって出てくるというのは不自然である(火葬にすれば骨もばらばらになろうが、その痕跡はない)。しかもこの穴から出てきた骨は明らかに様々な時代のものが混ざり合っていたので、一時に死んだ人のものとは考えられない。 そこでこの発掘担当者が思い当たったのが、このチューリッヒ市の歴史上のある出来事だった。それはチューリッヒだけでなく、むしろヨーロッパ的規模の出来事といえるかもしれない。・・・・・・・・ チューリッヒの大聖堂は、フェリックスとレグラという聖人の墓の跡地という伝説をもつ、由緒ある教会である。この二人は軍団ごとキリスト教徒に入信したテーベ軍団の兵士で、ために時(4世紀初頭)のローマ皇帝ディオクレティアヌスによって迫害され、逃亡先のこの地で処刑されたのだという。 伝説では8世紀にフランク王国(神聖ローマ帝国)のカール大帝が二人の墓を発見し、その場所に教会を作ったとされる。この時発見されたという二人の遺骨、さらに1223年以降カール大帝自身の遺骨が聖遺物として展示され、敬虔な老若男女が巡礼に訪れるようになった。 時は流れて1517年、堕落した教会に異議を唱えたマルティン・ルターが宗教改革を開始し、全ヨーロッパ、とりわけルターのお膝元であるドイツは激しく動揺した。これまで絶対と思われていたキリスト教やローマ教皇の権威に真っ向から刃向かう人物が現れたのである。しかし時代はルネサンスを経た後であり、ルターに賛同する者は多かった。 そんな最中の1519年、ウルリッヒ(フルドリッヒ)・ツヴィングリという人物が説教師としてチューリッヒ大聖堂に着任した。当時流行の人文主義を学びエラスムスの影響を強く受けていた彼は、ルターの始めた改革に共鳴し、自らも宗教改革を行うことになる。 彼の考えによれば、現在行われているキリスト教の慣習には後に加えられた夾雑物が多すぎる、ゆえにキリストの教えの根拠とすべきはただ聖書のみであった。この考えからすれば、偉いのは神と聖霊とキリストのみであって、信仰は各人の中にあり、俗界の権力者でもある教皇や司教は虚職に過ぎない。閉鎖的な修道院もなくすべきである。聖職者もまた人間であるから、妻帯してもおかしくない。彼は既にある未亡人と同棲していたし、ルターも還俗した修道女と結婚している。 聖書(福音書)に書かれていないものは全て廃すべきである。偶像である聖像(イコン)も破壊すべきである。こうして彼は教会音楽を禁じ、聖餐の儀式もやめてしまった。これは儀式としての聖餐を重んじたルターよりも過激な主張だった。こうした原典主義、宗教活動の世俗(日常)化、音楽の禁止、偶像の禁止などは、時代や地域こそ違うものの、イスラム教に通じるものがある(イスラム教も長い歴史の中で変化しているし、イスラム自体が先行するユダヤ教やキリスト教に対する改革運動と捉えられなくも無いが)。また鎌倉時代の法然、一遍、親鸞、日蓮などによる仏教改革に通じるものがある。ツヴィングリと同じ時代、京都で町衆による法華一揆、地方では一向一揆が起きていたことを連想するといっそう興味深い。 こうした改革を唱えるツヴィングリにとって、大聖堂に展示されて信仰を集めている聖遺物は、ただの骨に過ぎない。聖人は「ただの人」であるし、ヨーロッパにキリスト教を布教するために異教の要素を取り入れた名残りでもある。 また当時の教会では、信者たちに死を意識させるために(これはとりもなおさず信仰心の強化になる)、墓地にお堂を建てて遺骨を並べ「展示」していた(カトリックに留まったオーストリアの田舎などでは今も残っている)。少なくとも三つの納骨堂がチューリッヒの大聖堂の周囲にあったという。これもまたツヴィングリにとっては聖書の記述と関係のない無用のものだった。 つまり、冒頭のニュースで発見が報じられた人骨がぎっしり詰まった大穴は、1524年にツヴィングリがこうした聖遺物や展示されていた人骨を取り払って、まとめて墓地に埋めた痕跡であると考えられるのだという。・・・・・・・ 以下は後日談。 過激なツヴィングリの宗教改革には反発もあったが、チューリッヒ市民は受け入れた。しかし当時からスイスは諸州の連邦国家であり、ツヴィングリの改革に激しく反発する州も多かった。ドイツ(オーストリア)からの独立という共通の目的のために団結していたスイスは、分裂の危機を迎える。 さらには宗教改革に呼応した農民反乱がドイツ中部・南部で発生した(ドイツ農民戦争)。その一派のトーマス・ミュンツァーの乱は宗教権威のみならず世俗権力をも否定した大一揆になった。宗教改革を始めたルターは最初こそ農民たちに同情的だったが、社会の枠組みが根底から崩れてしまうことを恐れこの反乱を非難した。結局ミュンツァーの反乱軍はヘッセンやチューリンゲン(ルターをヴァルトブルク城に匿っていた選帝侯)といった諸侯の連合軍に敗れて処刑された。プロテスタントが鎮圧されたため、南ドイツは今もカトリックが強い。 しかし宗教改革が農民にとって自由への希望だったように、諸侯にとっては権力強化に便利なものだった。宗教改革を口実に教会や修道院の領地を取り上げて領国の一円支配が可能になるからである(政教分離の始まりといえるか)。ルターの宗教改革を熱心に支援した一人が、マールブルクを居城とするヘッセン方伯フィリップ寛容公だが、彼は農民反乱の指導者トーマス・ミュンツァーをだまし討ちにして処刑した当人でもある。(同じように反カトリックの立場をとったのがイングランド国王ヘンリー8世だが、彼の場合はカトリックが禁じる離婚のためだったというのは有名なお話) 時の神聖ローマ皇帝(≒ドイツ皇帝)はオーストリアとスペインの国王カール5世だったが、彼は立場上ローマ教皇を支持していた。自分の権力を強めたいフィリップにとって、目の上の瘤であるカールと対抗する上で、宗教改革は利用するに値する。1527年、彼はマールブルクに最初のプロテスタント系の大学を設置したが、その財源は教会や修道院から没収した土地であり、教授の宿舎には修道会から没収した住居を宛てた。 しかしプロテスタントによるカール包囲網を形成したいフィリップの思惑と裏腹に、プロテスタントの思想的指導者はそれぞれ自説を枉げないため折り合わず、その勢力は統一を欠いた。憂慮したフィリップはルターやツヴィングリらを説き伏せてマールブルクに呼び寄せ、会議を行わせた。1529年10月のマールブルク宗教会議だが、過激なツヴィングリが聖餐を廃すべしと主張したのに対してルターは形式としての聖餐の維持を主張、この一点で折り合わず両者は物別れに終わった。 なお人文主義者エラスムスはこのときスイスのバーゼルに居たのだが、過激なツヴィングリの改革に辟易して同地を去っている。 ツヴィングリはスイスをプロテスタントで統一しようと、カトリック側の諸州に経済的圧力をかけた。カトリック諸州は対抗して兵士を集めたが、ツヴィングリは先制して挙兵し兵士を率いカペルに至った。しかしそこでカトリック州連合軍の不意打ちに遭い、捕らえられて面罵された挙句処刑された。時に1531年10月11日、47歳だった。 両派は結局和平してスイスの統一は保たれた。ツヴィングリのプロテスタント派はジュネーヴを拠点とした「第二世代」のジャン・カルヴァンの改革長老派に合流して確固とした地位を得ることになる。 スイスのみならずフランス、ドイツ、イギリスなどでも宗教改革に起因する騒乱や戦争は枚挙に暇が無いが、ここでは措く。ツヴィングリは文字通りその火付け役になったといえる。同時代の日本だと上に挙げた法華一揆とか一向一揆、比叡山を焼き討ちした織田信長とか島原の乱などが連想されるが、どこでもいつの時代も、信じる宗教(正義といってもいい)のために人間は血を流すことを厭わなかった。あるいは宗教の名を利用した行為だったといえるかもしれない。そろそろ終わりにして欲しいものだが。 チューリッヒは長らくプロテスタントの牙城だったが、20世紀後半になるとスイス各地や外国から人口が流入、統計によれば現在チューリッヒで最大の勢力は33%を占めるカトリックであり、プロテスタントは32%と僅差で二位に転落している。なおチューリッヒの住民の30%はスイス国籍を持っておらず、特にトルコ系などムスリム住民の人口が急増しているという。
2007年05月22日
コメント(4)
-

突堤攻め
人類は戦争に勝つために様々な技術を発達させてきた。 最近映画化された「墨攻」(酒見賢一作。ただしこれを原作とした漫画のほうが人気らしいけど、僕は漫画のほうは見ていない)は、中国の戦国時代を舞台とした架空の物語だが、その辺の苦労を描いている。攻撃側は地下トンネルを掘ったり高台を築いたりしてなんとか城壁を越えようとし、防御側は奇想天外な策や兵器でこれを撃退しようとする。西洋や中国と違い日本史ではこうした城郭都市というのはほとんど無かったので、備中高松城の水攻めとかを除くとこうした土木工事のような戦争はほとんど起きなかった。 しかしどんなに技術が発達しようとも(核兵器のような破滅的な大量破壊兵器は別として)、地形が戦争に及ぼす影響は今でも変わらない。 上に挙げた「墨攻」とほぼ同時代、ユーラシアの反対側ではマケドニア(ギリシャ)のアレクサンドロス大王が東方大遠征をしていた。それについては映画化もされているし、アレクサンドロス大王の実像に迫る実証的な研究を続けている森谷公俊氏による手頃な好著が最近出版されている。 さて現在の国名で言うとルーマニアからパキスタンに及ぶ長大な遠征をしたアレクサンドロスだが、そんな彼も何度か苦戦を強いられている。そのうちの一つが紀元前332年のテュロス攻防戦だった。 テュロスは現在のレバノン南部にあったフェニキア人の都市国家で、スールと呼ばれる現在は人口11万の小都市で、遺跡は世界遺産に指定されており、日本人による調査も行われている。昨年のイスラエル軍レバノン侵攻の際に名を挙げたイスラム教武装組織ヒズボラの支配地域でもある。 「ヨーロッパ」の語源はテュロス王アゲノルの娘エウロペの名前にあり、好色な神ゼウスが牛に化けて彼女を拉致した先(ギリシャ)の大陸が「ヨーロッパ」と呼ばれるようになった。彼女を探してギリシャに赴いた弟のカドモスが建設したのが、やはり著名な都市国家テーベ(テバイ)である。また古代イスラエルのソロモン王がエルサレムに神殿を建設した際テュロスは工人や建材を寄進したというし、のちにローマ帝国と興亡を競った北アフリカの都市国家カルタゴ(カルケドン)は、紀元前814年にやはりテュロス王の娘ディドによって建設されたという。 まあとにかく、西洋古典の主役たちが交差する由緒ある都市ということである。 このテュロス攻防戦の様子はアッリアノス(2世紀の歴史家)の「アレクサンドロス大王東征記」にその様子が詳しく伝えられている。以下はその梗概。 イッソスでの決戦(紀元前333年)でペルシア軍に勝利したのち無抵抗でフェニキアに侵入したアレクサンドロスは、テュロス市の参事会に対し「名高いテュロスのヘラクレス(メルカルト)神殿に捧げ物をさせてくれ」と申し入れる。アレクサンドロスと一緒に当然マケドニア軍も街に入るわけで、つまりは無血開城せよというわけである。 フェニキアの都市国家はペルシア帝国の支配下で自治を許されて莫大な富を手にし、見返りに艦隊を提供していた。テュロス王アゼミルコスもペルシア軍と共に海上にあって不在だったが、参事会は「ペルシア人もマケドニア人もテュロスに入ることは許さない」と、事実上の拒否回答をする。 激怒したアレクサンドロスはテュロス攻撃を決意する。この都市自体は無害でも、その海軍を放置しておくとペルシア側に地中海の制海権を握られたままであり、これからエジプトに攻め込もうとするマケドニア軍にとって背後が危険極まりない。 テュロスが強気に出たのも無理はない。テュロス市は海岸から700m離れた周囲3.9mの島を中核としており、島の周囲は高さ40mの城壁で頑丈に守られていた。しかもテュロスは強力な海軍で知られており、海から攻撃することはおぼつかない。まさに難攻不落で、持ちこたえれば態勢を立て直したペルシアの大軍が救援に来るかも知れず、また姉妹(母娘)都市カルタゴが救援に来るという希望もあった。 この難攻不落の海上都市に対してアレクサンドロスが思いついたのは、海岸と島の間を土砂で埋めて島を地続きにしてしまうことだった。アレクサンドロスは英雄ヘラクレスを崇拝しており、ゼウスにより数々の難業を強いられたヘラクレスに自分をなぞらえ、この難事業に取り掛かったという。 この海峡は水深およそ5mだったが、総勢4万以上のマケドニア軍は大陸側にあった旧市街の建物も破壊して埋め立てに使った。幅60mあったというこの突堤は徐々に島に向かって延びていくが、テュロス側も敵の工事を傍観していた訳ではなく、船を出して工事を妨害した。マケドニア軍は突堤の先に櫓を立てて敵船の攻撃から守ろうとしたが、テュロス側は可燃物を満載した船による自爆攻撃でこの櫓を焼き払ってしまう。 やがてアレクサンドロスに降伏した他のフェニキア都市(シドン、ビブロス、アルワド、キプロス)の艦隊200隻が来着してテュロスを海上封鎖した。これらの都市はかつてペルシア帝国に対して反乱を起こし報復を受けており、ペルシアを恨んでいたのだった。これに勢いを得たマケドニア軍は突堤から投石器などを使って城壁の破壊を試みるがあまり効果が無く、今度は船に載せて海上から城壁を崩そうとした。ある程度城壁が崩れると船から板を渡して城壁の崩れた上端に乗り移り、ついに市街への突入に成功した。 市街に突入されると、七ヶ月持ち堪えたテュロス軍は形無しだった。苦難に満ちた攻城戦で猛り狂うマケドニア軍によって、神殿に逃げ込んだアゼミルコス王や参事官、カルタゴからの使者たちを除く(メルカルト神殿=アジールに逃げ込んだ難民は俗界権力から守られる決まりだった)8000人が殺され(2000人が海岸で磔刑にされたともいう)、生き残った三万人(13000人とも)は奴隷として売り払われたという。この攻城戦でのマケドニア軍の損害は400人、うち市街戦で死んだのは20人だった。 こうしてテュロスは陥落した。最終的には役に立たなかったアレクサンドロスの突堤はやがて砂州になり、現在テュロス島はこの厚さ8mに達する砂州によって大陸と地続きとなっている。日本でいうと江ノ島のような地形を連想すると分かり易いだろう。 さてようやく本題だが、フランスの地質学者などが最近、このテュロスの砂州をボーリング調査した。彼らのボーリングは現在の海水面下10mまで到達したが、アレクサンドロスによる突堤の痕跡と思しきものは見つからなかったという。果たしてアッリアノスの伝えるアレクサンドロスの大土木工事は幻だったのか? ボーリングの結果によると、土中の貝の種類が紀元前6000年くらいの層を境に変わることが分かった。古い時代は波の少ない珊瑚礁や湾内に住む種類だが、新しい時代は波の激しい普通の海岸に住む種類だという。つまりテュロス島はその頃まではもっと長大で、島と対岸の間は波から守られていたわけである。 一方テュロス島の岩盤は砂岩で波の侵食に弱く、崩れると砂状になる。大きかったテュロス島は海水面の変化などでその形を割合急速に変え、それにより海岸線も大きく変化した。テュロスの場所に最初の都市が建設された紀元前三千年紀、長さ1kmほどに縮小した島は完全に対岸から離れていて理想的な海上都市の地勢だった。 ところがこの島と対岸の間の海峡には、地形変化に影響された波や海流の向きによって、徐々に海底で砂が自然堆積していたのである。アッリアノスはこの海峡の水深が5m以上と記しているが、ボーリングによればおそらく2mにも満たなかったとみられる。海底には砂嘴状の隆起が島に向かって形成されていた。アレクサンドロスが突堤を築かなくとも、自然に時と共に現状になったはずだという。テュロス島が現代でいう離岸堤の役割を果たしていたことになる。ただ神ならぬアレクサンドロスは急いでいた(ちなみに彼はたった10年後に33歳で急死した)。 土砂を埋め立てて幅60mの突堤を作らなくても、堤で海流や波を遮断すればそこに近くのリタニ川から流れ込む土砂が短期間で自然堆積するようになっていた。このダムは土砂だと波に流されてしまうので大石である必要はあるが、その痕跡はボーリングでは見つかっていない。波を遮断するには別に分厚い堤である必要は無いので、ボーリング地点が外れただけかもしれない。アレクサンドロスがこうした工学や流体力学の知識を生かして何らかの土木工事をした可能性はある。 テュロスと同じように、かつての島が人工的な突堤によって陸続きとされ、その突堤が後世に砂州となった例がもう一つある。エジプトのアレクサンドリアがそれで、沖合いのファロス島(かつて世界七不思議に数えられた大灯台が立っていた)と対岸が長さ1200m以上の突堤(ヘプタスタディオン)で結ばれ、今は砂州になっている。この突堤のおかげで、入港した交易船が安心して帆を休めることが出来た。 いうまでもなくアレクサンドリアはアレクサンドロス大王その人の名に由来し、テュロス攻略後にエジプトを無血占領した大王自身が都市計画したともいう。彼は一方は都市を滅ぼすため、他方は建設するためという正反対の目的で突堤を作った(とされる)訳である。 アレクサンドロスによる攻略で衰えたテュロスに代わって地中海交易の中心となったのは、まさしくこのアレクサンドリアだった。テュロスが現在人口11万の小都市に過ぎないのに対し、その後も女王クレオパトラなどの歴史に彩られたアレクサンドリアは現在もエジプト第二の都市である。興亡の世界史に思いを致さずにはいられない。
2007年05月17日
コメント(10)
-
「3000年前の美女」をめぐる争い
ベルリン観光するといろいろ行くところはあると思うが(僕は何を措いてもペルガモン博物館に行きますが)、その目玉の一つとなっているのが「ネフェルティティの胸像」である。1912年にエジプトのテル・エル・アマルナ遺跡で発見され、翌年ベルリンに移された。3000年以上前のものとは思えない、写実的かつ洗練された美女の胸像で、観光客を魅了している。 僕は1992年に初めてお目にかかり、一番最近では二年前に実物を見ている。 ネフェルティティ(ドイツではノフレテテと表記されることが多い)とは今から3400年前の紀元前14世紀のエジプト王妃である。彼女の夫となったアメンホテプ4世(エクナトン)は史上確認されるうえで最古の一神教に基づいた大改革を行ったことで著名なファラオ(古代エジプトの王)なのだが、それについては詳しくは触れない。 彼女はややのちのネフェルタリ(ラムセス2世の妃)やクレオパトラ7世(古代エジプト最後の女王で、カエサルやアントニウスとの恋愛で有名)と並んで有名な古代エジプト女性であるにもかかわらず、その出自ははっきりしていない。イラク及びシリア北部にあったミッタニ(ミタンニ)王国の王女タトゥ・ヘパトとする説も以前あったが、エジプト王家の傍流とみるむきが強い。分かっているのは、彼女の名前は「美しい者が訪れた」という意味をもつことである。この胸像を見れば頷ける名前ではある。 彼女は19歳で5歳年下のアメンホテプ4世と結婚し、6人の娘を産んだ。アメンホテプはさまざまな改革を行ったが、その一つに以前のファラオが神秘化に勤めていた自らとその家族の姿を、多数の彫像などによってむしろ公に示したことである。アメンホテプとネフェルティティが仲良く手を繋いでいる姿の像が残されている。 彼女はアメンホテプの治世14年目(紀元前1338年か?)に死去し(理由は不明。なお彼女がもっと長命して夫の死後女王になったという異説もあるらしい)、アメンホテプの改革はその死後頓挫した。伝統宗教を維持したい勢力によってアメンホテプとその家族は忌避され、アマルナの都は放棄されて廃墟となり、王名リストからも削られてその存在を抹殺されてしまった。その墓は今でも不明である(2003年にイギリスの考古学者ジョアン・フレッチャーが「王家の谷」KV35号墓の女性のミイラがネフェルティティの遺体であると主張したが、他の学者は否定している)。 20世紀、イギリスの保護領となっていたエジプトは欧米列強の発掘競争の場となっていた。各国は考古学者を送り込み、国威を発揚すべき自国の首都の博物館を飾る大発見を狙っていたのである。海外進出を始めたばかりのドイツも例外ではなく、ルートヴィヒ・ボルヒャルトをカイロに送って発掘に当たらせていた。 他国の調査隊に出遅れたボルヒャルトは、ベルリンの富裕な繊維商ジェイムス・ジモンの出資を得たドイツ・オリエント協会の支援で1906年にテル・エル・アマルナの発掘に着手した。1912年12月6日、P47と通称された家屋跡の19号室を発掘していたボルヒャルトは、ネフェルティティの胸像を発見した。そこは彫刻師トゥトモシスのアトリエだったのである。その日の発掘日誌にボルヒャルトはこう記している。「実物大の彩色された女王の胸像、高さ47cm。天辺をまっすぐ切ったような形の青いカツラを被り、その真ん中の高さに帯を巻いている。色は塗ったばかりのようだ。素晴らしい細工。いかなる描写も無意味で、実見するよりない」 当時のエジプト政府と各国発掘隊の取り決めでは、出土品は折半されることになっていた。詳しい経緯は分からないが、ネフェルティティの胸像はドイツに持ち出すことが許された。ドイツに送られた胸像はまず出資者であるジモンの別荘に飾られ、ついでベルリンにある国立のエジプト博物館に寄贈された。 第二次世界大戦中の1943年、激しくなる連合軍の爆撃から美術品を守るため胸像は梱包され帝国銀行の金庫に保管され、次いでベルリン動物園にあった高射砲塔の防空壕、さらにベルリンに迫るソ連軍を避けてチューリンゲンの岩塩坑に移された。終戦後、岩塩坑に隠された財宝を押収したアメリカ軍は司令部のあるヴィーズバーデン(ドイツ西部)に財宝を移した。ネフェルティティの胸像はワシントンに送られそうになったが(「トロイアの黄金」などはソ連軍によって実際にモスクワに運ばれている)、美術品担当士官のウォルター・ファーマーにより阻止された。 数年間箱の中で埃を被っていた胸像は、そのままヴィーズバーデン市立博物館に展示されたが、1956年にベルリンのダーレム美術館に移された。当時は東西冷戦のさなかゆえ、当然西ベルリンの美術館である。ついで1967年に西ベルリンのシャルロッテンブルク地区に出来たエジプト博物館に移された(僕は最初にそこで見た)。東西ドイツが統一してベルリンの再開発が始まると、2005年8月に「博物館島」にある旧博物館に移された(僕はその直前に別の場所での特別展で見た)。現在再建中の新博物館が完成し次第(2009年の予定)、そこに移される予定になっている。 ところでネフェルティティは古代エジプト王妃、そしてこの胸像の発見地もエジプトで、本来ドイツは全く無関係のはずである。エジプトが植民地支配されていた当時の発見、そして不公平な取り決めによる持ち出しは「固有の文化財の略奪」ということで、エジプトは自国の文化遺産の返還を要求するようになった。中でも最高傑作のひとつであるネフェルティティの胸像はそのシンボル的存在となる。 既に1930年に最初の返還要求がなされたが、ドイツ側は他の遺物を返還して切り抜けた。さらに1956年にはエジプト側が「ロンメル元帥(ドイツ・アフリカ軍団司令官)の元帥杖」と交換でネフェルティティ像の返還を要求したが、ドイツ側は拒否している。 ところが最近になってこの「ネフェルティティ問題」が再び浮上してきた。ドイツの団体(CulturCooperation e.V)がネフェルティティ像を巡回展示させるようドイツ政府に要求している。巡回先には発見地であるエジプトも含まれている(というよりエジプトへの返還が目的のようだが)。 この団体の主張は「文化財は本来属する国にあるべき」であり、「人類の宝をドイツ国内で独占してよいのか?」という問いに対し、国際巡回展を開くことでネフェルティティのあるべき場所を模索し、議論を期すものである。この団体はヨーロッパ委員会の支援も受けており、国際的な文化財の保護や美術品の違法売買防止を目的としている。彼らの主張では、ネフェルティティ像は忌むべき帝国主義の時代にドイツに持ち込まれたものであるし、当時としては「合法的」に持ち出されたとはいえ、ドイツ政府が交渉したのはエジプトの宗主国だったオスマン帝国(トルコ)政府だった。 先週金曜日、ドイツ政府のベルント・ノイマン文化担当国務大臣は、ネフェルティティ像の長距離輸送は損壊を招く恐れがある、としてこの団体の要求を拒絶し、またネフェルティティ像のドイツ移送は合法的に行われたものであり、エジプト政府からも正式な返還要求は今までなかった、と強調している。 これに噛み付いたのがエジプト考古局のザヒ・ハワス長官だった。過去の経験から、エジプト政府は外国隊による考古学調査を厳重にチェックしているが、ハワス長官(インディ・ジョーンズのようなカウボーイ帽姿で日本のマスコミにも登場している)はエジプト国内の発掘調査を全て管理下に置き、長官立ち会いの下でなければ墓の開封やマスコミ発表もしてはならない決まりになっている。もちろん出土遺物の国外流出は論外である(エジプト政府の許可した貸し出しはある)。かつて「トロイアの黄金」をハインリッヒ・シュリーマンによって違法に持ち出されたトルコももちろん外国隊の行動に神経を尖らせているが、ここまで徹底していない。ハワス長官は昨年9月にドイツに対し返還要求を行っている。 ハワス長官は日曜日に議会の前でマスコミに対し「(ドイツ考古学研究所カイロ支部の設立100周年記念展を期して)ネフェルティティ像のエジプトへの三ヶ月間の貸し出しをドイツ政府に対し今週中にも正式に申請する。ドイツ政府が許可しなければ、ドイツでのエジプト考古学に関する展覧会には一切協力せず、ドイツへの遺物貸し出しも許可しない」という声明を発表した。 これに対して今日ベルリン・エジプト博物館のディートリッヒ・ヴィルドゥンク館長はラジオ放送で反論し、「エジプトからの遺物貸し出しは1985年以来行われていないが、問題なく展覧会を実行できている。そもそもエジプト政府から貸し出しの正式な要請はないし、ネフェルティティ像は現状にあってこそ光芒を放っているのであって、エジプトで他の遺物と並べられたら今のような輝きはなくなるだろう」と述べた。 一方ネフェルティティの巡回を要求している団体は、「ネフェルティティの国外巡回は破損の恐れがあるというが、それが本当かどうか内外の第三者の専門家の意見を徴すべきである」とノイマン大臣やヴィルドゥンク館長の姿勢を批判している。 考古学者としては、遺物はやはり出土地にあるのが一番であると思うのだが、カイロよりもベルリンにあるほうが保存技術や人目に触れるという点で有利なのもまた事実である(手狭が指摘されていたカイロ博物館は日本のODAで新築されるそうだが)。 既に100年近く前にドイツに持ち出されてしまったものを故国に戻せ、というのもなんだか歴史を遡って裁くみたいで現実的とも思えないのだが、こうした遺物が集中する欧米日といった先進国での古美術品売買が第三世界での盗掘を助長している(特に最近はイラクとアフガニスタンがひどい)のもまた事実であるし、難しいところである。なおドイツ政府は2007年2月にユネスコの「文化財の不法な輸入、輸出及び. 所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約」(1970年締結)を批准した。同条約は文化財返還要求に根拠を与えるものだが、ネフェルティティ像は批准前の事由なので適用されない。 よく似た例に上で少し触れたトロイアで発見された黄金の例があり、トルコ、ギリシャ、ドイツ、ロシアの四ヶ国が所有権を主張している。発見地は現在のトルコ領内だが、黄金は現在はモスクワにある。発見したのはドイツ人のシュリーマンで、第二次世界大戦の戦利品としてソ連軍が押収するまではベルリンにあった。ギリシャは「トロイアはギリシャ文明の一部だ。今のトルコ人は中央アジアから来た連中の子孫で、トロイア人と関係ないではないか」と主張している。それを言っちゃあ「現代の」ギリシャ人だって全く怪しいのだが。 歴史とは難しいものである。
2007年04月16日
コメント(6)
-

ミイラをめぐる謎二題
いつものようにドイツの週刊誌「シュピーゲル」の電子版を見ていたら、たまたま古代エジプトのミイラに関連する記事が並んで出ていたのでその紹介。 ただ「古代エジプト」といっても、このニュースの舞台は奇妙なことにエジプト発ではなく、一つはフランス、一つはドイツでのニュースである。 まずはフランスからのニュース。 フランス中部の都市シノンというと、フランス史上最大のヒロイン、ジャンヌ・ダルクゆかりの町として有名である。 百年戦争のさなか、イギリス軍にパリを追われていたフランス王太子シャルル(のちのシャルル7世)は失意のうちにこの城に住んでいた。1429年3月9日、ロレーヌ地方のドンレミなる田舎村出身のジャンヌという17歳の小娘がシャルルを訪ねてきた。なんでも彼女はフランスを救えという神のお告げを聞いたのだという。皆は最初彼女をあざ笑ったが、ジャンヌは影武者と入れ替わっていたシャルルを見事に当ててみせた。 その後フランス軍の先頭に立ったジャンヌがイギリス軍を次々と打ち破ったのは周知の通り。しかしジャンヌは詭計にかかってイギリス軍に捕らえられ、神の名を騙る魔女と宣告されて1431年5月30日にルーアンで火刑に処された・・・・ ・・・それから400年後の1867年、シノンにある古い薬屋の屋根裏で「ジャンヌの火刑地跡から発見された遺物」と貼り紙された容器が発見された。現代の我々からするとなんだかいかにも嘘臭く聞こえるし、ジャンヌの遺灰はフランス人の崇拝を避けるためイギリス軍によってセーヌ川に流し捨てられたとも伝わっている。しかし民族主義盛んな当時、人々はそうは思わなかった。この「ジャンヌの遺体」はシノンの博物館に収められることになったのである。 普仏戦争でのドイツに対する敗戦(1871年)、帝国主義、第一次世界大戦と続く時代の中で、フランスの「救国の英雄」ジャンヌ・ダルクは神話となった。百年戦争終結直後の1456年に既に名誉回復されていた彼女は1909年に列福、そしてイギリスとフランスが協力して勝利を収めた第一次世界大戦が終結した直後の1920年にはローマ教皇ベネディクト15世により聖人に列せられた。彼女はフランスの守護聖人となり、シノンの博物館に収められている「彼女の」遺骨は、疑いの眼差しを向けられながらも大切に守られてきたのである。 ところが昨年2月から、法医学者のフィリップ・シャルリエ氏を中心とする20名の科学者によってこの「ジャンヌの遺骨」が調査されていた。その結果がイギリスの科学誌「ネイチャー」最新号に掲載されている。 容器の中に入っていた遺物は真っ黒に変色した人間の肋骨、黒っぽい木片、長さ15cmくらいの布、そして猫の足の骨だった。骨が真っ黒なのは火刑にあったジャンヌの死に際に適合するし、猫の骨は中世には女性が火刑にあうときにその炎の中に魔女の象徴である猫を投げ入れたという習慣を証拠付けるものと思われていた。 ところがシャルリエ氏らが電子顕微鏡やDNA検査、レントゲン検査などを行ったところ、骨が黒いのは焼けたせいではなく黒い物質の付着によること、一緒にあった布にも焼けたものを包んだ様子がないこと、そして容器の中にはフランスには生育しない種類のマツ科植物の花粉が多く入っていたことなどが明らかになった。さまざまな証拠から察するに、この遺体はジャンヌ・ダルクのものではありえず、はるかに古い紀元前6世紀から3世紀頃の古代エジプトのミイラの一部であることが判明した。 科学者たちはこの結果に落胆こそしたが、特段驚きはしなかったという。というのは中世以来19世紀頃まで古代エジプトのミイラは細かく砕かれて「mumia vera」と称する薬品として西アジアからヨーロッパにかけて広く流通しており、フランスの薬局に古代エジプトのミイラがあってもなんら不思議はなかったためである。元を糺せばアラブ人が防腐用にミイラを覆っていた天然ゴムが酸化して黒くなったのをアスファルト(薬品にもなる。アラビア語でムミヤ)と勘違いし、薬品として使用したのが始まりのようだ。 要するにジャンヌ・ダルク崇拝に浮かされた19世紀のフランス人がやった捏造だった、というお話。まあ古代エジプト末期王朝期の文化財には変わりないんだけど。・・・・・・・・・・ 次はドイツでのお話。こちらは捏造ではなく本当の謎。 2002年、ドイツ東部イエナ市のザンクト・ミヒャエル教会の裏手で複数の墓が発掘された。そこで発見されたある男性の遺体は身長169cm(さすがこの時代にしてはデカイな)、死亡推定年齢は30歳から50歳の壮年期だった。ところがこの男性の頭骨には異様なものが残っていた。左の鼻の穴の辺りから頭蓋骨内部(後頭部)にかけて黒っぽい物質が残されていたのである。 分析の結果、この物質はビチュメン(天然アスファルト)と分かったが、その産地も同位体分析の結果、現在のイラク辺りと判明した。さらにレントゲン検査にかけると、明らかにこの物質は脳を取り除いた後に鼻腔から頭骨内に充填されたことが判った。さらにこの遺体が天然ソーダやナトロンに漬けられて脱水処理されていたことも判ったという。こうした処理は古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが「歴史」の中で伝えているように、古代エジプトのミイラ作りに特徴的なものである。イエナ市の埋蔵文化財担当者であるマティアス・ルップ氏は「この骨だけ見れば、古代エジプトのものだと思うだろう」という。 ところが問題は、この男性が葬られていた墓地はどうみても13世紀に属することだった。しかも男性の遺骨をやはり同位体分析にかけたところ、この男性はイエナ近辺の出身であることが判明したという(本当に判るんだろうか?)。ましてやこうした古代エジプト式のミイラがエジプト外で出土した例は、今のところ皆無という(上のジャンヌの偽遺骨のように、盗掘されたミイラが流通はしていたが)。 13世紀というとエジプトは既にイスラム化しており、紀元前のミイラ作りが一般的に行われていたとも考えにくい(紀元前13世紀ならばミイラ作りの最盛期に差し掛かる時代だが)。イスラムでは火葬も遺体のいかなる損壊もタブーで、死亡後一日内に土葬することが定めだからである。もちろんエジプトには現在もコプト教(キリスト教の一派)など非イスラムの宗教的マイノリティが存在するのだが。 ルップ氏らは、この遺骨の主は確かにイエナ近辺出身だが、おそらく中東のキリスト教聖地に巡礼している間に死亡し、遺体を故国のドイツへ持ち帰って埋葬するために現地でミイラにされたのではないか、と推測している。ただそうした例は記録にもなく、上記のように既に中東でもミイラ作りは一般的ではなかったことを考えると、きわめて異例と言わざるを得ない。 こうした稀有な遺体処理の例は「ヨーロッパの巡礼者がいかにオリエントの高度な技術や文化に魅了され、それを素直に受け入れたかを示すのではないか」とはルップ氏の弁。
2007年04月05日
コメント(2)
-
七星剣
僕の関係者のニュースを見かけたので貼り付けておく。(引用開始)稲荷山遺跡 9世紀の「七星剣」確認、関東で初めて 千葉3月6日17時25分配信 毎日新聞 千葉県成田市稲荷山(とうかやま)の稲荷山遺跡発掘調査で、1983年に断片が出土した剣が全国的にも珍しい「七星剣」であることが筑波大の調査結果で分かった。9世紀ごろのものとみられる。東京国立博物館によると、発掘で七星剣が見つかったのは全国初のケース。七星剣は奈良の法隆寺と大阪の四天王寺などに4点あるが、関東から見つかったのは初という。 出土品は、刀身の先端の長さ約13センチの部分と中間の同約6センチの部分など。象眼跡が北斗七星の形を示しており、四天王寺伝来の国宝で「聖徳太子御佩用(ごはいよう)の剣」とされている七星剣と酷似していることから七星剣の一部と分かった。 稲荷山遺跡は縄文中期の遺構が集中している。発掘調査は宅地造成に伴い、83年3~11月に実施された。剣の断片は縄文遺構から離れた比較的新しい土坑(どこう)で見つかったが、この時は判別が付かず、ほかの出土品とともに筑波大が調査していた。 同大が03年にX線調査をしたところ、さびに覆われた剣に丸や線状に金属が埋め込まれているのが見つかり、北斗七星を示していることが判明したという。【柳澤一男】 ▽東京国立博物館・日高慎主任研究員の話 当時、国の中央(畿内)から離れていた千葉県で見つかったのは驚きだ。七星剣は、高貴な身分の人の持ち物とみられているが、実はたくさん作られていたのか、あるいは、特別な理由があって千葉から出土したのか、現段階では不明だ。 (引用終了) この辺のことはよく知らないので、七星剣そのものについてはコメントのしようがないが・・・。そういやこれの図面とかレントゲン写真を見せてもらったことがあったなあ。「こんなん見たことある?」と聞かれたので、正直に「ない」と答えただけだったが。 記事をよく読むと分かるとおり、発掘されたのは20年以上前のことで(僕も新たに発掘したのかと一瞬勘違いしたが、今は団地のはずだ)、ずっと未整理のままだったものをここ数年整理と報告書の刊行を集中的にやっているわけである。 この遺跡は縄文時代がメインで、ものすごい数の土坑(貯蔵穴あるいはごみ捨て穴)と数軒の竪穴住居址が発掘されたのだが、「どうせ新しいもんだから」とあまり見向きもされなかった錆び付いた鉄片が実は一番珍しいものだった、というわけか。これ一点だけがぽつんと出たらしいので、「稲荷山」の名のとおり、奉納か何かの意味で埋められでもしたんだろうか? 「北斗七星」ってドイツ語でなんていうのか知らんかったので調べると、großer Wagen(大きな車)というらしい。なるほど、「柄杓」の柄の部分が轅(ながえ)、椀の部分が輿(人間が乗る部分)に見えなくもない。古代戦車の構造はこちらを参照。 そのほか国による呼び名を抜き出すと、・イギリス北部 「犂」(牛に曳かせる大きいやつ)あるいは「肉屋の大鉈」・北欧 「カールの車」(イギリスでも以前はそう言ったらしい)・ドイツ語などゲルマン系言語 「大きい車」オーディン(神)の車という神話が背景?・スラヴ系言語やルーマニア 「大きい車」(霊柩車のことか)・アイルランド 「犂」 ケルト文化の名残りか?・フィンランド 「オタヴァ」・フランス南部 キャセロール(フライパンみたいなの)・ローマ セプテントリオ(七つの星)→転じて英語や仏語で「北」の形容詞になる・インド サプタ・リシ(七つの経)・アメリカ big dipper(大きな柄杓)←起源はアフリカ黒人らしい・中国など東アジア 北斗七星あるいは柄杓・聖書 七星(アモス書に言及あり)・北米インディアン 親子の熊・キルギス族 七匹の狼・アラビア 霊柩車と泣き女 北斗七星は中国ではよく図案化されてこうして日本にも入ってきているが、西洋ではおおぐま座の一部であり多用されたモチーフでもなさそうだ。例としてはアイルランドのイースター蜂起(1916年)の際にシンボルとして使われたこと、アラスカ州旗に北極星と共にモチーフとなっていることくらいか。フィンランドにもこのシンボルはあるようだ。 しかし目立つものだけに古代から既に認識されていた。中近東では天文学が発達したが、西洋では北斗七星を構成する星の名前もアラビア語で呼ばれている。 ドゥーべ(熊)別名アッ・タハル・アッ・ドゥッブ・アル・アクバル メラク(腰) フェクダ(腿) メグレズ(尻尾の付け根) アリオト(ヤギの尾?) ミザール(帯) バナト・ナアシュ(泣き女)別名アルカイド 七星剣の画像を探したが、ネット上にはあまりいいものがなさそうだ。 昨年大阪の四天王寺で寺宝の伝聖徳太子所用七星剣(国宝。現在東京国立博物館に寄託)が特別展示されたようなので、そのポスターを紹介(こちら)。四天王寺に寺宝として収蔵されていて、鎌倉時代には既に錆だらけだったものが、昭和になって研ぎ直して往年の輝きを取り戻したという。 聖徳太子云々はともかく(稲荷山のは9世紀ということだが)、平安時代後期に日本刀の湾曲化が始まる以前の、古式な直刀の姿を伝える名品だそうだ。
2007年03月06日
コメント(2)
-
半世紀後の「冤罪」
なんか最近掲示板やトラックバックのスパムが甚だしいな。一時沈静化していたと思ったんだが、最近は本当に目に余る。そのことごとくがエロ系というのも大笑い。ああいうのはいたちごっこで取り締まるだけ無駄なんだろうか。 よそのブログみたいに、承認制とかコード記入の義務化とか導入して欲しいものだ。・・・・・・・・・・ 最近歴史・考古学系ニュース記事の紹介ブログと化してしまっているのだが、今日もそういうエントリー。今日のはいつにも増してマニアックなので完全に自分のためのメモだな。 記事の出所は「シュピーゲル」に出ていたこちらの記事。ただこの記事が報じられる前から、ハノーファーのニーダーザクセン州立博物館に勤めているCにこの話は聞いていたのだが。ちなみにこの記事を書いている人はAの同僚のようだ。この記事は現在シュレスヴィヒの州立博物館(何年か前に行ったが、なかなか気合の入った博物館だった)で行われている特別展「鉄器時代の人類」の関わりで出たようだ。・・・・・・・・ ドイツ北部やデンマーク、イギリスなどには、氷河期の名残りで出来た泥炭湿地と呼ばれる地形がある。底なし沼のような湿地なのだが、水面下に堆積した泥状の植物遺存物が炭化過程にあり、質の劣る燃料として使用できるので19世紀にはさかんに採掘された。最近では石油に代わる火力発電燃料としてフィンランドで採掘が盛んであり、同国の発電量の7%を占めるという。ただ二酸化炭素排出の問題はあるのだが。 この泥炭は古くから採掘されていたが、泥炭湿地からしばしば人間の遺体やその一部がミイラのような生々しい残り具合で発見されることが知られていた(酸性の泥炭による作用で皮膚や毛髪が腐朽せずに残った。むしろ骨の残りが悪い)。泥炭の採掘が盛んだった20世紀にはその発見が相次ぎ、現在までにおよそ1000点が知られている。最近では2005年に発見され、僕も日記に書いている。こうした遺体の多くは3世紀や4世紀のものが多いとされ、当時の北ヨーロッパに住んでいたゲルマン人の生贄や処刑、埋葬といった風習と関係すると考えられている。 その中で最もセンセーショナルだったのが1952年5月にドイツ最北部のシュレスヴィヒ・ホルシュタイン州ヴィンデビューで発見された遺体である。泥炭採掘のため排水工事をしていた4人の作業員が偶然発見した。最初は鹿の骨だと思っていたのだが、それは人間の腕の骨だった。早速近くのシュレスヴィヒ州立博物館のカール・シュラボウが、遺体の取り上げと調査のため現地に赴いた。 シュラボウが調査したところ、その遺体は頭髪や皮膚が非常によく残り、さらには目隠しのような状態で布きれを顔に巻いていた。遺体の上は木切れや石が覆っていた。四肢や頭部などの残りは良いが、胴体は残りが悪かった。 さらに掘り下げると深さ1.29mのところからその人物の右手が出てきたが、異様なことに親指を人差し指と中指の間に挟んでゲンコツをした状態で見つかった、とシュラボウは報告している。ちょっと恥ずかしいのでこの仕草の意味は詳しく書かないが、恥ずかしいのはヨーロッパでも同じで、女性器や姦通(貫通?)などの性的な意味をもつ仕草である。シュラボウの報告によれば、この遺体はさらに異様なことに髪の毛を頭の片面だけ剃られたのち2mmだけ伸びており、おそらく死の直前に剃られたものと推測された。 この異様な遺体の状況を説明すると考えられたのが、ローマ時代(2世紀前半)の歴史家タキトゥスの著書「ゲルマーニア」に出てくる記述である。ゲルマン人の社会では不義密通罪に対して厳しい処罰が行われ(姦通だらけのローマ人とは正反対である)、男は不貞の女の髪を剃り、親戚縁者の目の前で裸にし、村中を引き回すことが許されていたという。この記述に基づき、この異様な遺体(「ヴィンデビューI」)は姦通の結果私刑されて湿地に沈められた女性(少女)の遺体と考えられた。 シュラボウがこの「少女」の遺体発見現場を調査したところ、20日後に5m離れた地点で男性の遺体が見つかった。遺体は杭状の木切れであたかもテントの骨組みのように覆われ、また遺体の首の部分には紐がかかっていたという。この遺体は「ヴィンデビューII」と名付けられた。 一年後、ドイツの有力週刊誌「シュテルン」がこの発見を大々的に報じた。「彼らは姦通して殺されたのか?二千年前の男女の遺体が泥炭湿地で発見される」という見出しだった。この(悲)劇的な発見の物語は、あっという間に人口に膾炙する。 正式な学術報告がシュラボウによって刊行されたのはその6年後である。シュラボウが発見状況を報告した他、形質人類学者ウルリヒ・シェーファーはこの「少女」を14歳と鑑定、考古植物学者ルドルフ・シュトルンプフは花粉分析からこの遺体を5世紀のものとする所見を加えている。この報告に接したゲッティンゲン大学教授で考古学の権威ヘルベルト・ヤンクーンは「この二人は姦通の罪で周囲の者に処刑され、湿地に沈められたものと見て間違いない」とのお墨付きを与えた。「少女」の遺体の目隠し布や剃られた髪、男性の遺体の首の縄が、それを雄弁に物語っているではないか。 こうしてこの大発見は大学のゼミで研究テーマとして論じられ、外国の教科書にまで掲載され、この若い二人のゲルマン人男女の悲劇に触発された小説や映画が発表されることになった。 ところが発見から20年以上経った1978年、シュレスヴィヒ州立博物館に勤めるミヒャエル・ゲビュールは、この二体が姦通のため処刑されたものだとするヤンクーンらの解釈を否定し、この遺体は単に貧しい死者が遺体処理の簡単な泥炭湿地に沈められたもの、つまり単なる埋葬行為の結果ではないか?とする論文を発表した。 その論拠とされたのは、報告書に掲載されている「少女」の恥ずかしい指の仕草の写真は、出土した当時そのままではなく、何者かが遺体をいじってこの仕草をさせたと考えられること(新しい指の跡があった)、また「少女」の遺体の周囲には少数の土器片しか見つかっていないと報告されているのに、発掘作業員の証言や作業中に撮影された写真は、少なくとも4点の完全な土器が「少女」の遺体の周りに置かれていたこと、つまりこの遺体が処刑されて捨てられたのではなく、埋葬され土器まで副葬されている可能性があることを示していた。報告書の実測図や出土地点の記載にも、後から辻褄あわせをした疑いが出てきたのである。 この論文は多少の議論を引き起こしたものの、ドイツの考古学界のほとんどは、この男女が姦通罪で処刑されたというヤンクーンの「定説」を枉げようとはしなかった。 新たな議論が巻き起こったのはそのさらに20年以上のち、発見から半世紀を経た2002年になってからだった。ミヒャエル・ゲビュールがこの二人の遺体を放射性炭素測定法(C14)にかけたところ、男性は紀元前380年から185年の間、「少女」のほうは紀元前41年から紀元後118年の間に死んだということが判明したのである。なんとこの二人の間には少なくとも140年、最大で400年以上の時間差が存在することになる。これでは出会えるはずの無いこの二人が姦通のしようもなく、二人は全くアカの他人ということになった。「神話」は崩れ始めた。 さらに衝撃は続く。カナダの法医学者へザー・ジル・ロビンソンやイスラエルの研究室による29点のDNA試料の鑑定で、この「少女」がなんと男性であるという結果が出たのである。しかしゲビュールはこの結果を疑った。彼を含む考古学者たちには、発掘で出土した遺体からDNAを取り出して分析できる訳がない、という思い込みがあったのである。彼らは「調査の際に調査作業員の男性のDNAに汚染(コンタミネーション)されてしまったのではないか」、つまりこのDNAは少女のものではなく調査で遺体に触ったシュラボウのものではないか、と疑ったのである(余談だが、北朝鮮が提出した「横田めぐみさんの遺骨」は偽物と主張する日本側と、北朝鮮及び「ネイチャー」誌の論争をちょっと連想した)。 しかし「少女」のDNAは骨の内部から採取されており、またロビンソンの用いた最新の分析法では汚染するリスクはきわめて低いものだった。何よりロビンソンによる形質人類学鑑定で、この遺体が男性のものであることは明らかだったのである。「神話」は崩壊した。 「神話」が崩れたとき、その原因に目が向けられた。この遺体を発掘調査して報告書にまとめたカール・シュラボウにである。1891年に生まれた彼は画家としての教育を受け、博物館には繊維(衣類)の保存復元の専門家として勤務していた。のちにシュレスヴィヒ州立博物館で考古部門の責任者にもなったが、彼は正規の考古学教育は受けていなかった。 彼は出土した遺物を明らかに「復元しすぎる」傾向があった。報告書でも、明らかに薄弱な根拠に基づいた推測を述べたり、彼が「跡が見えた」と主張するが写真などの証拠からは判別できないものを根拠とすることもあった(また実際には発見されていない泥炭湿地遺体を「発見した」と報告した疑いもある)。こうして「紀元前400年頃の木像」を大胆な想像に基づいて「完全」なものに復元してしまったり、おそらく死産だった嬰児の埋葬を「人身生贄の風習によるもの」と報告したり、オステルビューで出土した男性の泥炭湿地遺体の頭蓋骨に別人の下顎骨を宛がったりしている。 ミヒャエル・ゲビュールは1978年に上記の論文を発表した際、当時88歳で存命していたシュラボウに面会している。ゲビュールはシュラボウに疑念を指摘したが彼は認めず、また発掘現場の写真を見せると「この写真をどこで手に入れた」と逆に聞いてきたという。その写真はシュラボウ自身が刊行した報告書に載っていたものだった。 「しかしおそらくシュラボウは意図的な捏造者ではなかった」とゲビュールは言う。「彼は芸術家ではあっても科学者ではなかった。彼の復元図の素晴らしさは否定できない。彼は出土遺物を研究者ではなく芸術家の目で見て、その欠けた部分を考古学者ではなく芸術家の手法で補った。そして『ヴィンデビューの少女』の遺体も、彼のこうした手法で出来上がった『作品』だったのだと思う」 「芸術家としては、彼は無罪だろう。裁かれるべきは、こうした空想的で学問的手法を経ずに出来上がった彼の作品を、鵜呑みにしてそのまま受け入れ検証も反論もしなかった彼の同僚の『専門家』たちであると思う」とゲビュールは結んだ。 上述のように、仮にロビンソンの鑑定でDNA汚染があったとしても、現代の法医学では身体そのものから「ヴィンデビューの少女」は実は若い男性であったと結論付けることが出来る。15~17歳の「ヴィンデビューの少女」の身長は165cmの痩せ型で、骨に残る痕跡(ハリス線)をみると彼はその短い人生の中で11回の栄養失調を経験していることが窺える。 また死因として考えられるのはひどい歯槽膿漏からの細菌感染で、処刑の際の目隠しと思われていた布切れは実際は鉢巻がずれて目のところに降りていただけではないかと推測される。処刑されて湿地に沈められたという「神話」の最後の砦も、法医学の前に崩壊しつつある。 そしてあの恥ずかしい「手の仕草」だが、これはもはや元に戻すことは不可能である。付け加えておくと、ヨーロッパで性的な意味をもつこの仕草が登場するのは中世以降のことだそうだ。 この遺体は現在シュレスヴィヒ州立博物館の三階に展示されている。
2007年02月18日
コメント(4)
-

ブサイクなクレオパトラ?
(引用開始)【こぼれ話】クレオパトラは美女じゃなかった?=古代貨幣に肖像2月15日2時7分配信 時事通信 【ロンドン14日】「絶世の美女」だったといわれる古代エジプトの女王クレオパトラ。しかし、英ニューカッスル大学で13日から展示されている紀元前32年の貨幣に描かれた肖像によれば、実際にはそれほどでもなかったようだ。 肖像のクレオパトラはとがったあご、薄い唇、鋭角的な鼻の持ち主で、飛び切りの美人というわけではない。英劇作家シェークスピアはクレオパトラの容貌について、言葉では描写できないほど美しいとして「とても言い表せない」と表現したが、これには図らずも別の意味があったことになる。貨幣の裏側には恋人とされたアントニー(アントニウス)の肖像もあるが、こちらもかぎ鼻、どんぐり眼、太い首と冴えない容姿だ。 ニューカッスル大の考古学者リンゼー・アラソンジョーンズ氏によると、絶世の美女とのクレオパトラのイメージは、英国では中世の詩人チョーサーの作品までさかのぼれるものの、比較的新しい。古代ローマ時代に書かれたものでは、クレオパトラは知的でカリスマ性があり、魅惑的な声をしていたとなっているが、美女との言及はないという。 同氏は、美女であるとのイメージは、米映画「クレオパトラ」(1963年)でクレオパトラ役にエリザベス・テーラーのような美人女優が起用されたことで確立した「永遠の神話」の一つだとしている。 (引用終了) 同じニュースのドイツ語ソースはこちら。 へえ・・・・・。そういう話は以前から聞いているが、たった一つのコインの肖像を元にそんなこと言っちゃっていいんですかね。確かにそのコインの写真を見ると、少なくとも現代人の感覚では美人とは言いがたい横顔ではあるが・・・。ずいぶん摩滅してるね、これ。 現代のコインと2000年前のコインとでは製作技法も表現の精密さも違うが、参考までに現代の女王たちと彼女たちの顔が彫られたコインを紹介してみる。どうです?どのくらい似てます?金正日のアレな宣伝画よりは似てるかな。 ・イギリスのエリザベス2世とそのコイン ・オランダのベアトリクス女王とそのコイン ・デンマークのマルグレーテ2世とそのコイン クレオパトラは「世界三大美女」の一人(誰が決めたんだ?)として美女の代名詞になるほど、あまりに有名なエジプト女王だが、その名前ほどにはどういう人物か知られてないんじゃないだろうか。 細かいことは書かないが、彼女の事績をざっと年表にするとこんな感じ。・紀元前70/69年 エジプト王プトレマイオス12世の三女として生まれる・前51年(18歳) 父の死を受けて女王に即位。 弟プトレマイオス13世と結婚し共同統治者に・前48年(21歳) 夫(弟)との政争に敗れ追放される ローマ軍の司令官ユリウス・カエサルの支援で夫を敗死させる 別の弟プトレマイオス14世と結婚するが、カエサルと交際・前47年(22歳) カエサルの子カエサリオンを産む。ローマに渡る・前44年(25歳) カエサル暗殺される。エジプトに戻る 夫が死去、カエサリオンをプトレマイオス15世として共同統治・前42年(27歳) ローマ帝国の有力者マルクス・アントニウスとタルススで会見・前40年(29歳)(アントニウス、オクタウィアヌスの姉オクタウィアと結婚) クレオパトラはアントニウスの子(男女の双子)を出産・前36年(33歳) アントニウスの男子を出産 ・前32年(37歳)(アントニウス、オクタウィアと離婚) アントニウスとクレオパトラがオクタウィアヌスとの対決を明確に (ローマ帝国が内戦に)・前31年(38歳) アクティウムの海戦。 クレオパトラの敵前逃亡により、アントニウスが大敗・前30年(39歳) ローマ軍エジプト侵攻。アントニウスに続きクレオパトラも自決 カエサリオンがオクタウィアヌスに処刑され、エジプト王国滅亡 彼女はエジプト人のエキゾチックな姿で表現されることが多いが(アフロ・アメリカンの中には、クレオパトラを黒人女性と固く信じる説がある)、プトレマイオス王家はマケドニアのアレクサンドロス大王の部将がエジプト王になった家系であり、歴代の近親結婚もあって彼女の風貌は間違いなくギリシャ人のそれだった。 このコイン以外での絵画や彫像に表現されたクレオパトラの風貌はいかなるものか。まず彼女の若い晩年に作られた大理石像(ヴァチカン博物館像)が挙げられる。「修正」が入ってかなり美化されているのかもしれないが、この像を見る限りでは醜女というには当たらない。同様な大理石像はベルリンのアルテス・ムゼウムやフランスの個人コレクションにも収蔵されている。 またルーヴル美術館には彼女がイシス女神に拝礼する姿を描いた石碑が所蔵されているが、彼女の風貌を窺うのは困難である。 彼女の風貌についての文字での記録は、史料的価値はさほど高くないとはいえ、ほぼ同時代(100年後)の歴史家プルタルコスが書いた「対比列伝」のアントニウスの項の記述(第27節)がある。以下ちくま学芸文庫版(秀村欣二訳)から引用。彼女の美もそれ自体では決して比類のないというものでもなく、見る人を深くとらえるというほどのものではなかった。しかし彼女との交際は逃れようのない魅力があり、また彼女の容姿が会話の際の説得力と同時に同席の人々のまわりに何かふりかけられる性格とを伴って、針のようなものをもたらした。彼女の声音にはまた甘美さが漂い、その舌は多くの弦のある楽器のようで、容易に彼女の語ろうとする言語にきりかえることが出来、非ギリシア人とも通訳を介して話をすることは稀で、大部分の民族には・・・・・いずれにも自分で返答した。その他多くの民族の言葉を彼女は習得していたと言われているが、彼女より前のエジプトの諸王はエジプト語さえ学ぼうと努めず、マケドニア語さえお手上げであったものもあった。 今でいえば教養に満ちたマルチリンガルの才女、という訳か。彼女の交際相手だったカエサルは弁舌も巧みで頭も良さそうだが、アントニウスのほうは勇猛だが粗野で無教養な人物として描かれている。まるで反対のタイプだが、うまく誘惑できたものだ。 プルタルコスはまた、アントニウスの正妻であるオクタウィア(クレオパトラと同い年)のほうが、貞淑さでも美しさでもクレオパトラよりずっと上だと書いているのだが、アントニウスには退屈な女だったのだろうか?まあ政敵オクタウィアヌスとの和解のための政略結婚だったから、仕方ないかもしれない(なお子供はしっかり作っている) 新聞記事にあったように、彼女の美化が始まったのはむしろ後世のようで、特にエリザベス・テーラーの演じたクレオパトラ像が決定的な役割を果たしたようだ。ドイツなどヨーロッパで広く親しまれているフランスの漫画「アステリクス」にもクレオパトラが登場するが、その姿はリズのそれに強く影響されている。これを原作とするフランス史上最高の制作費を投じた映画「ミッション・クレオパトラ」では当代随一のイタリアのセクシー女優モニカ・ベルッチが演じている。(なんかこの映画、日本ではクレオパトラ=モニカ・ベルッチが前面に押し出されて宣伝されたみたいだな。本当の主人公はアステリクスとオべリクスという二人のガリア人なんだが・・・・) 僕としては、モニカ・ベルッチはまんざらでもないが、エリザベス・テーラーのクレオパトラはちょっと引いてしまうなあ。それより何より、僕はにっこり微笑むだけが能のウルトラ美女よりは、話して面白い「並な風貌」の女性のほうが良いように思う。
2007年02月15日
コメント(12)
-
考古学の光と影(あるいはロマンと現実)
考古学についての対照的なニュースが続いたので、メモがてら記す。 まずは「影」あるいは「現実」のニュースから。(引用開始)聖地発掘にパレスチナ人抗議、イスラエル警察と衝突2月9日22時36分配信 読売新聞 【エルサレム=三井美奈】エルサレム旧市街地にあるユダヤ教とイスラム教の聖地「神殿の丘」(イスラム教側呼称ハラム・アッシャリフ=「高貴な聖域」の意)で9日、イスラエル考古学庁が行っている周辺の発掘調査に抗議してパレスチナ人数百人がイスラエル警察に投石した。 警察は催涙ガスやスタンガンで応じ、双方で数十人が負傷した。 同庁は今月初旬、丘に通じる橋の架け替えに合わせて工事予定地の調査を開始。「丘には立ち入らない」と主張しているが、パレスチナ側が反発し、イスラム教礼拝日にあたる同日、約200人が丘の中心にあるアルアクサ・モスクに立てこもったほか、周辺で数百人が「神は偉大なり」と叫ぶ抗議デモを行った。 (引用終了) これは現地の地理がよく分からないので、調査そのものについてはコメントのしようがない。 ただ揉めることは事前に分かっていたようで、アミル・ペレツ国防相は危険回避のためオルメルト首相にこの調査(と工事)の即時中止を要請していたようだ。オルメルト首相は「工事は必要であり、アル・アクサ・モスクに害が及ぶことはない」とこの要請を却下している。 まあムスリム側としては、聖地の被害どうこうよりも、どこであろうがイスラエルがこの丘を掘り返すことが許せないんだろうけど。1996年に同じようなことがあって、そのときはパレスチナ人61人、イスラエル兵15人が犠牲になっている。 宗教施設とか墓の調査っていうのは本当に注意しないとえらい騒ぎになることがある。イスラム世界ではそれが顕著だが(そのほかアメリカ・インディアンが祖先の墓を荒らされたことに抗議して受け入れられたもある)、政教分離しているトルコでもこういうことはある。漫画の「マスターキートン」で、タクラマカン砂漠を舞台にしたエピソードでそういう話があったが、やはりモスクやその跡地を壊すような調査はまずい。 お墓の場合は、その墓が自分たちの先祖だと周辺の人たちが信じているときはまずいことになる。トルコ人は自分たちは中央アジアから来たと思っているので、古いお墓の場合は余所者のアルメニア人やギリシャ人の墓だと思っているので、それほど問題になることはないが。 ただ僕らもいっぺんそういう騒ぎに巻き込まれたことがある。 何年か前、僕の先生(ドイツ人)がトルコのある町の古い墓地で、ヒッタイト時代の石碑を墓石に転用したものを発見した。その墓地はかなり古いもので、今はお参りする人もなさそうだが、周りには人が住んでいる。その墓石には鹿の上に乗る神像(こう書くと春日大社の祭神・武甕槌みたいだが)をあしらった立派なレリーフ(浮彫)が彫刻されていて、明らかにどこか他所に立っていたものを、墓石に使うため運んできたものである。 先生は地元の博物館と憲兵隊に連絡し、その墓石を博物館に運び出そうとした。その墓石が価値があるものだと周囲に知れると、その石の中に金が入っている(石棺ではないのでそんなことはあり得ないのだが)、と信じる地元の不心得者に割られてしまう恐れもあった。 ところが運び出す作業になると案の定周辺の住民がわらわらと出てきて取り囲み、大騒ぎになった。彼らは普段この墓に見向きもしていなかったのだが、価値があると分かると持ち出すことに反対しだしたのである(怪しいドイツ人がドイツに持って帰るという噂も出ていた)。仕方なく見張りの兵士を置いていったん引き上げざるを得なくなった(僕は留守番でその場に居なかった)。 後日護衛の兵士を増やして厳戒態勢の中で墓石の運び出しが行われ、墓石ならぬその石碑は現在は博物館の庭に立っている。 次は「光」あるいは「ロマン」のニュース。(引用開始)「永遠の抱擁」、5000年前の男女か=イタリア発掘調査2月7日14時37分配信 ロイター [ローマ 6日 ロイター] イタリア北部のマントバ近郊で、5000─6000年前に埋葬されたとみられる抱き合った男女の遺骨が見つかった。発掘調査チームの責任者、エレナ・メノッティ氏は、「これまで新石器時代に2人一緒に埋葬された例はもちろん、こんな風に抱き合った形で発見されたことはなく、驚くべきケースだ」と語った。 同氏によると、埋葬されていた2人は男女にほぼ間違いなく、彼らの歯がほとんど原型のまま磨耗もしていないことから、未確認ではあるが若くして死亡したとみられるとの見解を示した。 同氏はまた、ロイターに対し「遺骨を発見した時、われわれ全員がとても興奮しました。私はこの仕事を25年間続けており、ポンペイをはじめあらゆる有名な遺跡の発掘に携わりましたが、これほど感動したことはなかった」と述べ、今回の発見がこれまでの発掘をしのぐほどの特別なケースだと説明した。 発掘調査チームでは、今後発掘された遺骨の死亡時の年齢や埋葬された時期の特定を進めることにしている。 (引用終了) こちらやこちらでその写真を見ることが出来る。 CBSニュースでは「6000年前のロメオとジュリエット」と報じているが、なかなか上手い命名だなあ。ロメオとジュリエットの舞台となったヴェローナはこのマントヴァから20kmくらいの所である。 マンドヴァには何年か前に行ったことがあるが、案外小さい町だったような記憶がある。おそらく今回の発掘を担当したであろう地元の博物館も見学させてもらったのだが(当時は改装中で閉まっていた)、接合中で接着剤を乾かしている最中の土器を何気なく触ったら崩れてしまい、慌ててその場を離れたことが記憶に残っている(博物館の方、済みませんでした!!)。 それはともかく、写真を見る限り確かに睦みあう男女のように見える。しかし遺骨のこの残存状況を見ると、人骨鑑定のよほどの熟練者でないと「男女」と断定できないんじゃないかと思う。まあ埋葬状況や体格の違いを見れば「男女」と思いたいし、実際その可能性は高いが、100%ではない。男女だとしても、恋人同士かどうかは慎重に判断しないとなるまい。 上の記事にあるが、「齢」という漢字が示すように、歯を見ればある程度の年齢を推測することが出来る。特にこの時代、主食である小麦(パン)は石臼で挽いていたのだが、どうしても石粉が小麦粉に混じることになる。そういうパンを食べていれば歯のエナメル質の摩滅が現代人や米食よりも早まるのは仕方がなく、また歯の摩滅具合で年齢の推定がかなり出来る。食事は毎日欠かせない習慣だからね。 それとこうした合葬の例だが、ドイツではオーバーカッセルという所で一万年前(後期旧石器時代)の男女の合葬の例が1914年に見つかっている。またこのイタリアの例と同じ時代のものとして(紀元前4500~3500年、ミュンヒスへーフェナー文化)は、ドイツ南部フライジンク近郊のムルというところでやはり男女の合葬例があるようだ。今年一月にはドイツのザクセン・アンハルト州カルスドルフで、母親と息子(10歳以下)と思しき合葬の発見例があるそうだ。いずれにせよ二人の関係はDNA鑑定の結果なども見ないといけないのだが。 この「ロメオとジュリエット」の脇からは石鏃(矢の先の刃)や石のナイフ(鎌刃?)が発見されたという。まさかロメとジュリエットのように心中したんじゃないと思うが、この副葬には魔よけ(破魔矢)の意味でもあったんだろうか。 道具が石で作られていることが示すように、この二人が住んでいた時代は新石器時代と呼ばれる時代である。住居を建てて定住し、農耕(小麦?)や牧畜(ヤギ・ヒツジ・ウシ)、そして漁業の生活をしていたが、まだ金属の加工も知らず、都市もなければ国家もない時代である。日本で言えば縄文時代とほぼ同じである。イタリアというとオリーブやトマトというイメージがあるが、どちらもこの時代のイタリアには存在しない。スパゲッティも無かったはずだ。 ざっと調べた限りなので確信は持てないのだが、この二人が生きていた時代のこの地域は「カーディアル文化」別名「インプレッソ文化」に属していたと思う。「カーディアル」は貝の品種(Cardium edule、二枚貝の一種で、日本だとサルボウに近いのかな?)、「インプレッソ」は「圧痕」くらいの意味だが、その名の通り貝殻を連続して表面に押し付けた装飾をもつ土器を指標とした文化である。似たような土器はアドリア海沿岸、イタリアの沿岸部、シチリア島、スペインのカタルーニャ地方でも見られる。 この文化の起源はよく分からないが、レバノンのビブロスやギリシャのセスクロといった先行する新石器時代遺跡で似たような土器が見つかっているので、おそらく紀元前6000年頃に西アジア・ギリシャから、土器作りや農耕技術が地中海を通って西方に伝わったものと考えられる(日本で言えば弥生時代初期の遠賀川式土器のようなものか)。この時代の遺跡から沖合でしか捕れない魚の骨が出土していることが示すように、彼らは航海に長けていたようだ。 この記事では年代を「6000-5000年前」としているので、あるいは後続する後期新石器時代の続カーディアル文化あるいはボッコ・クアドランタ文化に属するものかもしれない。
2007年02月09日
コメント(2)
-

リビア砂漠 死の彷徨
前回のエントリーの関連で。自分の専門関連のメモなのでつまらないと思います。 伝説のオアシス都市ゼルズラを発見したと信じたアルマーシ・ラースロー(「イングリッシュ・ペイシェント」の主人公のモデル)が次に目指したのが、紀元前524年にリビア砂漠(エジプト西部)で遭難したペルシア軍の痕跡を発見することだった。第二次世界大戦の勃発でその夢は叶わず、また現在に至るまで発見されていない。 この「砂漠に消えたペルシア軍」についての記録は、紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスの「歴史」による簡潔な記述しかない。以下松平千秋訳の岩波文庫版から当該箇所(巻3・26節)を抜粋してみる。・・・アンモン攻撃に向かった分遣隊はテバイを発し、道案内人を伴って進み、オアシスの町に到着したことは確実に判っている。オアシスの町は・・・(略)、テバイから砂漠を越えて七日間を要する距離にあり、(略)。ペルシア軍はアンモンに達することがなかったし、引き返したのでもなかったのである。当のアンモン人の伝えるところはこうである。遠征軍はオアシスの町から砂漠地帯をアンモンに向かい、アンモンとオアシスのほぼ中間あたりに達した時、その食事中に突然猛烈な南風が吹きつけ、砂漠の砂を運んでペルシア軍を生き埋めにしてしまい、遠征軍はこのようにして姿を消したのである。 「イングリッシュ・ペイシェント」でも猛烈な砂嵐で車が生き埋めになる場面があったが、5万もいたペルシア軍を飲み込むとは、砂漠の砂嵐というものはかくも恐ろしいものなのか。 なおこの逸話は最近「カンビュセス王の秘宝」(ポール・サスマン作)というミステリー小説でも扱われている。僕は読んだことが無いが(ていうかさっき知った)、やはり消えたペルシア軍の遺跡を探す考古学チーム同士の競争が背景となっているそうだ。 ペルシア軍が向かっていたアンモンというのは現在のシワ・オアシスにあたるという。ここにはアモン神の神殿があり、その託宣は非常に敬われており、ギリシャにまで聞こえていた(ギリシャ人はアモン神をギリシャ神話の主神ゼウスと同一とみなしていた)。 ペルシア軍の遭難からおよそ200年後の紀元前331年2月、ペルシア軍を逐ってエジプトに入ったアレクサンドロス大王は、神託を得るためわざわざこの砂漠の中の神殿に赴いているのだが、そのとき神官に「神の子よ」と呼びかけられ、自己のエジプト支配の権威付けに利用していることからも、その権威のほどが分かる。 またペルシアが滅ぼしたエジプト第26王朝の王墓はここにあるそうで(よく知らないがリビア系王朝なのかな?)、エジプト人に「セフト・アム(椰子の地)」と呼ばれていたアンモンを征服することは、エジプト支配を完成する上で欠かせなかったのだろう。 もっともアンモン遠征軍を送り出したペルシア王カンビュセス(ペルシア語でカンブジャ)は、アモン神の権威を利用するのではなく、その神殿を焼き払うために遠征軍を送った、とヘロドトスは記しているのだが。 アレクサンドロス大王はアンモンに向か際、ナイル河から西へ砂漠を突っ切ることをせず、いったん地中海に出てから海岸沿いに進み、そこから南下してアンモンに至ったのだが、なぜカンビュセスは派遣軍に無謀な砂漠横断をさせたのか。 ヘロドトスの記するところではカンビュセスは「もともと気違いじみた性格で、冷静さを欠く人物であった」といい、このアンモン遠征や同時に行われたエチオピア(現在のスーダン)遠征は水や食料の補給をろくに準備もせずに踏み切った、という。 カンビュセスは一代で現在のイラン、トルコ、イラク、シリアを征服したキュロス大王の息子で、父の急死を受けて紀元前530年頃に即位した二代目である。こう書くといかにも苦労知らずな人物が想像されるが、その他ヘロドトスがカンビュセスを気違い呼ばわりした所業として挙げているのは、・ペルシアの掟に背いて実の妹と結婚し、あまつさえ身重になった妹を殴り殺した・弟スメルディスを疑って殺した・エジプト王の墓を暴いて遺体を焼き捨て嘲笑した (火葬はペルシア・エジプトいずれの風習にも背く)・アンモンの神殿も焼き払おうとした・エジプト人が崇拝する聖牛アピスを殺した・近臣(元リュディア王クロイソスなど)を手討ちにしたり残虐に扱った点である。 ところがこうしたヘロドトスの伝える暴君像とは異なる記録もある。 聖牛アピスを殺したというが、実際には紀元前524年の銘をもつ石碑が発見されており、そこにはアピスを拝むカンビュセスの姿が彫られている。聖牛アピスは滅多に居ないある特徴をもった牛で、エジプト人は神の顕現とみなすのだが、この石碑はカンビュセスがエジプトの風習を尊重していることを示す。 実妹との結婚だが、これは古代王朝では「血の純粋性」を守るためとしてよく行われていたことであり、特別異常ではない。イランではペルシア人以前のエラム人にも見られるし、エジプトにもある。ギリシャ人はこの近親相姦を唾棄したが、のちにアレクサンドロス大王の部将からエジプト王になったプトレマイオス王家はこの風習を採り入れ、有名なクレオパトラ7世は最初弟と結婚している。兄弟殺しも、新しいスルタンが即位する度に兄弟が誅殺されたオスマン帝国などを見れば、とりわけ異様ではない。常人には理解できないが。 またカンビュセスは紀元前525年にエジプトを征服したのだが、その際は砂漠で水を確保するためアラビア人と同盟したり、サモスなどギリシャ人と同盟して制海権の確保を心がけるなど周到な準備をしている。アンモンやエチオピア遠征の軽率さとは別人のようではある。 エジプト征服直後のアンモン遠征とエチオピア遠征は大失敗に終わっている。エジプト遠征に比べあまりに拙速な行動や、ヘロドトスが描くエチオピア人の姿があまりに空想的(皆120歳の長寿を保つ云々)なことから、この遠征噺は作り事ではないかという説もあるらしい。 ナパタ(スーダン)ではヌビア王の石碑が発見され(現在ベルリンの博物館に所蔵)、その中には「ヌビア王ナスタセンがケンバスデンのペルシア軍を破り、その船を全て奪った」という記述があり、このケンバスデンをカンビュセスと同一視し史実とする意見もあったようだが、ナスタセンは紀元前4世紀末にペルシアから独立した王らしく、時期が合わない。 ヘロドトスによれば、カンビュセス自らが率いたこのエチオピア遠征は、準備が足りず無謀だったためたちまち兵が飢え(近代の太平洋にもそんな軍隊ありましたね)、ついには兵士が10人一組で籤を引き、当たったものが他の兵士に食べられるという惨況に陥り、やむなく退却したという。 ついさっき検索で知ったのだが、藤子不二雄はこの話に基づいた短編漫画を作っているそうだ。 このときカンビュセスは、アンモン、エチオピアと同時にカルタゴに対する遠征も企てていたとヘロドトスは伝える。カンビュセスは支配下のフェニキア人に命じてその艦隊でカルタゴ遠征を企てたのだが、そもそもカルタゴはフェニキア人が紀元前9世紀に植民して建設した都市国家であり、フェニキア人のサボタージュでカルタゴは難を逃れたという。 もしこの時ペルシア帝国がカルタゴ遠征に成功していたら、その後のヨーロッパの歴史に与える影響は大きかったろう。カルタゴやフェニキアは、ギリシャやエトルリアを通じてヨーロッパに影響を与えており、ヨーロッパと西アジア(中近東)はより近くなっていたかもしれない。 さらに想像すれば、カンビュセスのアンモン遠征はエジプトの完全支配というだけでなく、強力な海軍を持つカルタゴへの将来の遠征に備えた陸路行だったと考えられないか。またエチオピア遠征に成功して紅海ルートの打通に成功していれば(実際は紅海交易はローマ時代に最盛期を迎える)、ペルシア帝国は地中海からインド洋にまたがるローマ帝国どころではない世界帝国になっていたかもしれない。 まあ騎兵に頼りすぎのペルシアの軍事力では、ギリシャも征服できなかったのだから(20年後のペルシア戦争)、いずれにせよ無理だったろうけど。 現実にはアンモン、エチオピア両遠征の惨憺たる失敗後まもなく(紀元前522年)、本国で殺したはずの弟スメルディス(バルディヤ)が反乱を起こし王を名乗った。ヘロドトスによればこのスメルディスは偽者で、カンビュセスはこの偽スメルディスを討伐すべくシリアまで引き返したところで乗馬の際事故を起こし(腰の刀の鞘が抜け、足に突き刺さった)、その怪我がもとで急死したという。享年は分からず、彼には子がなかった。 この偽スメルディスを倒したダレイオス(ダーラヤワウシュ)が王位を継ぎ、ペルシア帝国を磐石なものとするのだが、最近の研究では実はダレイオスこそが簒奪者であるというのが定説になりつつある。ダレイオスこそが、正当な後継者であったスメルディスを倒して彼を偽者扱いし、歴史を改竄してべヒストゥーン碑文に彫り付けたという訳である。あるいはカンビュセスの不自然な死も、スメルディスかダレイオスによる陰謀の結果によるものかもしれない。 ダレイオスが即位直後に相次ぐ反乱の鎮圧に回らねばならなかったこと、カンビュセスの妹と結婚して血統上の正統性を主張したことなどがその傍証となる。そもそもペルシア帝国の創業者と二代目であるキュロスとカンビュセスは、赤の他人のダレイオスによって無理やり彼のアケメネス家の一員に組み込まれ系図を改竄された、という説さえある(本来「テイスペス朝ペルシア」だったものが、アケメネス朝に易姓した)。 こうしてみると、カンビュセスが気違いじみた暴君だった、というヘロドトスの記録は、ダレイオスのプロパガンダを真に受けたものかもしれず、眉に唾してかからなくてはならない。またヘロドトスはエジプトの神官たちからエジプトの歴史を取材したのだが、カンビュセスがエジプト征服にあたり、神殿を尊重しつつもその旧来の利権を認めなかったため神官はカンビュセスを恨んでいたといい、だとすればヘロドトスは二重の悪意に影響されたカンビュセス像を書き記したことになる。 もしかしたらカンビュセスは、ダレイオス、アレクサンドロスや始皇帝、クビライ、あるいはナポレオンやヒトラー(?)のような世界戦略を備えた気宇壮大な大王だったかもしれないが、力量も運も及ばなかったというべきか。 カンビュセスの墓は故国のイランにあるとされるも長らく所在が分からなかったが(ヴァルター・ヒンツなどが推定はしていたが定説はなかった)、昨年12月イランのパサルガダエで、その廟に使われたと思われる石材が転用されているのが偶然発見されたという。
2007年01月30日
コメント(4)
-

阪神・淡路大震災から12年/地震雑記
今日は6000人あまりが犠牲になった阪神・淡路大震災から12周年である。 もうそんなに経ったのか。 あの日僕は関東地方某所にいて、地震には会っていない。その時間はなぜか起きてテレビをつけていて「めざましテレビ」を見ていたのだが、「先程関西で大きな地震があったようです」という第一報を耳にしている。まだ外は暗かった。少しずつ被害の深刻さが伝えられ始め、その番組はそのまま終日震災特番になった。 その日の午前中、僕は病院に行っていたのだが、そこの待合室のテレビで初めて凄まじい被害の様子(倒壊した高速道路など)を目の当たりにした。その日はいろいろ忙しかったので気になりながらもあちこち出かけていて、ゆっくりテレビ報道を見られたのはその日の夜からだった(筑紫哲也氏の「まるで温泉のよう」発言も聞いている)。テレビは6年前の昭和天皇崩御のときのような騒ぎだった。 僕の実家は兵庫県に隣接する県にあるのだが、夜になれば電話も通じるだろうと12時くらいになって電話を掛けてみたのだが、やはり繋がらなかった。翌日電話が通じたが、実家では揺れは強かったが仏壇の中の阿弥陀如来像がずれていたくらいで被害もない、と聞いてホっとした。それでも僕の実家のある地方としては近年例のない強い揺れだったという。地震が起きた瞬間、母はむしろ僕のいる関東地方のほうが大丈夫なのかと心配したようだ。 その年の3月に僕は実家に帰省したのだが、新幹線は新大阪と西明石間が寸断されていて、山陽本線に乗り換えた。それも途中で寸断されていて、代替バスが一駅か二駅分運行されていた。僕はあえてバスに乗らず、その区間を歩いた。既に地震から数ヶ月経っていたが、まだ残る瓦礫の山や崩れかけたビルを目の当たりにして戦慄した。 さらにその後、何度もトルコを車で走ったとき、1999年8月17日のトルコ北西部大地震(死者2万人)の被災者のために贈られた神戸の仮設住宅が立ち並んでいるのを見る度に、神戸の地震を改めて思い出した。イズミットの郊外にあったその仮設住宅村も、今はもう無くなっていると思う。・・・・・・・・ 上にちょっと触れたが、トルコも地震のある国である。イランもトルコもいくつものプレートが合わさって出来ているのだから仕方ないのだが、日本と違って地震がしょっちゅうあるわけでなく、稀に大きいのがドカンとくる。だから建物もあまり耐震設計とか考えずに建てているので、被害が拡大する訳である。1999年のトルコ大地震後は日本に倣って耐震を考えた建物も出てきたようだが、建築素材とか手抜きあるいは節約設計のため、いかにも頼りない建物が多い。 むしろ古代の建築物のほうがしっかり丁寧に作られているんじゃないかと思えるが(逆にしっかり作られたものだけが残ったともいえる)、地震によって崩れている遺跡なんてのも結構ある。有名どころだとネムルート山頂にある紀元前1世紀の古墳が挙げられるが、そこでは石像の頭部が崩れて地面から生えたようになっている(あれは倒れてたのを人間が起こしたんだろうけど)。地震で都市が被害を受けたという記録も枚挙に暇がない。 日本では発掘調査によって地震の跡が明らかになることがある。古墳が断層によってずれていたり、地層に液状化現象による噴砂・噴石が見られたりするのだが、さすが日本は地震大国というだけあって、地震考古学なんていうのもある。 あと阪神・淡路大震災の際に起きた断層がそのまま残されている資料館もある。淡路島の北淡町にある野島断層保存館がそれで、断層の上に保存館が建てられており、当時のまま残されている。淡路島方面に行く機会があれば是非見学して欲しい。 さて僕はトルコでの発掘に参加したが、そこはヒッタイト帝国時代(紀元前15世紀頃)の都市遺跡である。遺跡の中心には最大の建物(神殿)の基礎が残っているが、なぜか一部だけ壁の基礎が他の二倍の幅で作られている箇所があった。 上のトルコ大地震(1999年)のあと、発掘隊長である僕の先生ははっと気付いて「これは地震で破損した基礎部を補修した結果、幅が二倍になったのではないか」と解釈した。つまりこの建物は地震で倒壊こそしなかったが、一部が破損して不安になったヒッタイト人が、破損箇所を壁で覆って補強したというわけである(この建物はのちに戦争の焼き討ちで崩れたようだ)。日本のような柱建築と違い、トルコやヨーロッパでは屋根を支えるのは厚い壁であるから、これは妥当な推測といえる。 ところが先生はドイツ人だから、地震のことをよく知らない。そこで日本人で地震に詳しいはずの僕に地震に関する文献を集めるように頼んだのだが、これが結構見つからない。しょうがないので日本の地震考古学の本を見せたら興味深そうに見ていた。ところが先生は遺跡の中の岩の割れ目(遺跡自体が大きな岩山の上にある)とか、ずれて真っ直ぐでない壁を見ると「これは地震によるものだ」と言い始め、しばらく「地震ブーム」になってしまった。そもそも地震によるものなのか、その建物が建っているときの地割れかどうかも分からないので、もう少し慎重に判断したほうがいいと思うのだが。 地震に関する文献記録はこの時代には既に残っていると思うのだが、まとまった研究もあったと思う。 ところでウィキペディアを見ていると、日本の地震研究者による地震記録データベースを見つけた。これは素晴らしい。早速紀元前のトルコでの地震を検索すると、以下の地震が載っている。 紀元前1300年頃 イオニア地震(津波あり) 紀元前550年頃 トルコ・イラン国境地帯地震 紀元前4世紀 ディディマ(トルコ西部)が地震で崩壊 紀元前4世紀 ロードス島地震 紀元前4世紀 コルキス(グルジア)地震 紀元前303年 イオニア地震 紀元前282年 リュシマキア地震 紀元前224年 ロードス島・カリア地方地震 紀元前200年 ポエマネヌム地震 紀元前197年 ロードス島地震 紀元前148年 アンタルヤ地震 紀元前94年 サルディス地震 紀元前69年 アンティオキア地震、死者1万7千 紀元前26年 アイドゥン地震 紀元前17年 サルディス地震 この他ロードス島では紀元前227年、226年と地震が頻発したことが記録されている(世界七不思議の一つ「ロードスの巨像」を破壊)。上記のヒッタイト都市を揺さぶった地震は紀元前1300年よりも前のはずなので(紀元前1528年から1400年の間)、このデータベースには載っていないようだ。 ところでドイツって地震がほとんどないものと思ったら、このデータベースでは31件が引っかかった。きわめて稀なうえ震度は小さいし犠牲者も多くないが、主にライン地方で発生しているようだ。一番最近では2004年12月にシュツットガルトでマグニチュード5.4の地震が起きている。
2007年01月17日
コメント(2)
-

人類最古の戦争??
こんなニュースを見つけた。(引用開始)人類最古の戦争、6000年前に=独考古学者がシリアで遺跡発見1月4日21時0分配信 時事通信 【ベルリン4日時事】ドイツ考古学者の調査で、これまで確認された中で人類最古となる「戦争」が約6000年前にシリアで行われたことを示すとみられる遺跡が発見された。米シカゴ大学東洋研究所のクレメンス・ライヒェル氏が率いる調査隊が発見したもので、4日付独週刊紙ツァイトが報じた。 同氏によると、シリア北東部にある対イラク国境地帯の町ハモウカルで、紀元前4000年ごろによく乾燥させた粘土球が大量に見つかったという。同氏は、ウルクとみられる南メソポタミアの都市国家が北部にあるハモウカルを侵攻、粘土球を弾丸のような武器に用いて陥落させたと推測しており、「世界最古の侵略戦争の実例」と指摘している。 (引用終了) へえ、と思って元記事の「ツァイト(時代)」のページをを調べたら、これが見つかった。ついでに言及されているシリアのテル・ハムーカルについていろいろ検索すると、このページが見つかった。新発見というわけでもなく、既に一年以上前にマスコミ発表はしていたわけね。日本語記事に出てくる「石つぶて」の写真はこちら。 戦争の起源云々はいろいろ議論があるのだが、農耕文明の開始、あるいは都市文明の開始と共に始まったとされる。この記事は後者の説に拠っているが、日本では弥生時代から戦争が始まったという説が根強い。鏃が刺さったり刀傷のある人骨がかなり大量に発見されているからである。それ以前の縄文時代の人骨にも石鏃が刺さったものがあったと思うが、事故か個人的行為かなどかは分からない。 ドイツでは新石器時代に一つの穴から殺傷痕を伴う大量の人骨が発見された事例があり、或いは戦争の犠牲者ではないかとも言われているが、当時は武器が未発達ということもあるし、断定されているわけではない。 個人同士の殺し合いというならそれこそ人類の歴史に匹敵するくらいの長さかもしれないが、戦争の定義を「人間の集団が別の集団に殺意を持って組織化され行動する」とするならば、やはり文明の始まりと共に戦争は始まり、今に至っていると言えるのではなかろうか。 「原始人」というと弓矢を使ったイメージがあると思うが、実は弓矢は世界で普遍的に使われていた道具ではない。僕の知る限りでは、アメリカ先住民が弓矢を使うようになったのは日本でいえば奈良時代の頃からである(同じように刀も世界中に普遍的な武器でというわけではない)。 一方、実は弓矢よりも石つぶてのほうが威力も射程も大きかったりする。弓矢は知らないが石つぶては使うという民族は世界中に結構いるし(一昨年亡くなったマンフレート・コルフマン教授の博士論文に詳しい)、旧約聖書に出てくる少年ダヴィデと戦士ゴリアテの逸話や、戦国時代の武田軍では郡内衆(小山田氏)の投石部隊がその射程を生かして先駆けした事績はよく知られていると思う。他にも古代ギリシャやローマでは、鉛のつぶてが使われていた。 弓矢と違って製作する手間も省けるし、何より弓矢は熟練するのに長い訓練が必要となる。石つぶては最も原始的だが強力な武器だった。コルフマンはこれを「古代のミサイル」と呼んでいる。 というわけで(?)、以下にツァイトの元記事を訳してみる。しかし原文はかなり長いので、ハムーカルに関する部分のみの抄訳である。・・・・・・・・ 「粘土のモロク」(注・モロクは古代西アジアの神の名。ユダヤ教では邪神とされる) 6000年前に両河地方(注・メソポタミア=現在のイラク)で最初の都市が成立した。新発見は人類の進歩に関する考古学者の想像を変える。ウルリヒ・バーンゼン、トビアス・ヒュルター 攻撃軍が投石したとき、終わりが来た。数千の硬く乾き締められた粘土塊がハムーカルの守備隊を打ち倒し、その抵抗が弱まったとき、南方から来た攻撃軍は高さ3mの城壁を破って町に侵入した。ハムーカルは炎上した。 紀元前4000年、人類最初の戦争が起きた。「我々は人類最古の攻撃の痕跡を発見した」とクレメンス・ライヒェルは言う。南メソポタミアの都市国家、おそらくウルクの軍隊が北方に侵攻し、ハムーカルを落としてその周辺地域を征服した。「ここで起きたのは小競り合いなどではない。これは戦場だ」とライヒェルは言う。瓦礫、灰、そして大量の弾丸である。 シカゴ大学東洋研究所のドイツ人考古学者は2003年から、両河地方の先史時代の古戦場の発掘を指揮している。遺跡の中心にある20mx20mの広さの「B地区」だけで、ライヒェルとその同僚たちは2300もの土の弾丸を発見した。これは先史時代の大砲の弾であり、考古学者は確信する。「これは5500年前の『衝撃と畏怖』だ」(注・このキャッチフレーズは2003年のイラク戦争で使われた) これは征服活動があったことの証拠ともなった。残存する武器は、先史時代と歴史時代の間の薄闇の中に謎の山と疑問の材料を与えることになった。イラクとの国境から数キロしか離れていないシリア北東部でのライヒェルの発見は、初期の都市国家同士の抗争の証拠を示すだけではないからだ。この地域での数々の発見は、人類史の決定的瞬間について新たなイメージを与える。文明の興りは、従来考えられてきたのとは違う経緯を辿ったのだ。(残念ながら中略)最初の都市とともに権力抗争、そして戦争が発生した チャタル・ホユックをはじめ初期農耕集落遺跡の壁画にも、頭のない人物とその上を飛ぶハゲタカのモチーフに行き当たる。ギョべクリ・テペの頭のない人物像との共通性は、偶然で説明するには明白すぎる。鳥が死者をあの世に運ぶという信仰は、既にその以前の太古からあったのだ。クラウス・シュミットは「共通の精神世界があった」と考える。(訳注:チャタル・ホユックもギョべクリ・テペも、共にトルコの新石器時代遺跡) それが消えたとき、都市の興隆の機は熟した。さまざまな時期に起源を持つ建築技術、食糧生産、発明が、最初の大都市に集約された。行政、交易、産業の中心として。都市とともによりモダンなものが生まれた。国家、権力、そして戦争である。 ウルクとその姉妹都市では精神的な神々の世界(あの世)と共に、この世での飢餓感が生まれた。「ウルクの支配者は、今まで思われていたよりもヒッピーではなかった」とライヒェルはいう。実際ハムーカルを侵略した容疑者であると思われる。その理由はあった。あらゆる大国と同じく、ウルクは資源を渇望していた。ウルクは黒曜石、レバノン杉、鉱物を必要とした。それは北方で得なければならない。ウルクを中心とする交易網が整備された。「ウルクは穀物以外に何も持っていなかった」と考古学者のフォン・エスはいう。交易都市であり北方輸入路の宿駅であったハムーカルは、南方の権力者にとって有意義な獲物だった。 「南メソポタミアの北方に対する帝国主義戦争」というライヒェルの説は、一部の同業者から有力な反論と共に批判されている。なぜ町を襲ったはずの弾丸が建物の中にもあるのか?彼らは家の中で互いに戦ったとでもいうのか? しかし過去数シーズンでライヒェルは自説をより確信するようになった。弾丸の多くは粘土と藁で出来た壁に当たった痕跡がある。また炭化した柱や瓦礫の間には、戦争を生き延びた住民が調理のため火を焚いた痕跡があった。「彼らは動くものは何でも食べただろう」とライヒェルはいう。ハムーカルの近くの遺跡、例えば200km離れたテル・ブラクの発掘でも、戦後の様子が明らかになっている。遺物はまた、ハムーカルは戦争直後にその最盛期を迎えたことを示す。それはウルクの支配下でだった。 新しい支配者はその痕跡を遺している。より上層でライヒェルは紛れもないウルク様式の土器やウルク式の建築物の痕跡を発見している。ライヒェルにとっては明白だ。南方からの征服者はハムーカルの軍事的支配を引き継いだのみならず、文化的にも征服したのである。それはこんにちまで両河地方で繰り返されてきた紛争の姿である。(訳出終わり)(追記) その後「シュピーゲル」に関連記事が載ったので追記。黒曜石刃や投弾、遺骨や遺構の写真が見られる。 また天水農耕地域である北メソポタミアがウルク期には想像以上に有力だったこと、以前「ハムーカルの衰退は地震によるものであり戦争ではない」と反論していたウルク期研究の権威ギジェルモ・アルガゼ教授が、「投弾や破壊された壁を見れば、これは疑いなく戦争による破壊だ」とライヒェル教授の説を支持した発言を紹介している。
2007年01月04日
コメント(4)
-

U-864
少し前のニュースだが、昨日も関連ニュースが報じられていたので触れておく。まずは日本語版記事を貼り付け。(引用開始)日本目指した独潜水艦から水銀漏出=62年前、英軍が撃沈-ノルウェー沖12月21日15時1分配信 時事通信 【ロンドン21日時事】第二次大戦終盤の1944年12月、日本に向かう途中のノルウェー沖で撃沈されたドイツ海軍の潜水艦Uボートの残骸(ざんがい)から、荷積みの水銀が漏れ出しているのがこのほど確認され、ノルウェー政府は汚染防止対策に乗り出した。 BBCによると、このUボートは、太平洋戦争で敗色濃厚になっていた同盟国・日本を支援するため、兵器製造に使う水銀65トンを積んでドイツ北部キール軍港から出航した。しかし、英軍はこの動きを察知、同軍潜水艦が追尾し、魚雷で撃沈した。 (引用終了) 今年の夏はポーランド沖の海底でドイツの航空母艦「グラフ・ツェッペリン」(未完成)が発見されたり、アルゼンチン沖で自沈したドイツ戦艦「グラーフ・シュペー」の艦首の紋章(鉤十字つき)が引き上げられ、そのオークションにネオナチが参加するしないで物議を醸したり、昨日もイギリス沖でダイバーによって三隻のドイツ潜水艦(Uボート)が発見されたりと、こうしたニュースが多かった。沈没船探しがブームになって居るのか、海底資源調査とかも絡んでいるんだろうか? それはともかく、このニュース。「沈没船探し」というとロマンもあるだろうが、その船に積まれているのが財宝ではなく有毒な水銀となると物騒である。この潜水艦は3年前にノルウェー海軍の海底調査船が発見したが、昨年になってダイバーが鉄製の水銀の瓶1本を回収して環境への影響が問題視されるようになった。こうした瓶は1857本もあり、水銀の総計は上の記事のとおり65tに上る。平城京放棄の理由となったとされる、奈良の大仏に使われた水銀はおよそ50tというから、それとほぼ同量が150mの海底に沈んでいることになる。 上にリンクした「シュピーゲル」の記事によると、今年は4キロの水銀が水中に流出したと見られ、既に周辺海域での漁は禁止されている。ノルウェーというと日本も鮭を輸入しているが、影響はないのだろうか。 根本的対策としてはこの潜水艦の引き揚げが望ましいのだが、潜水艦だけに魚雷や砲弾を積んでおり、爆発の危険もあるため、ノルウェー政府は事故を起こしたチェルノブイリ原発のように、水銀の流出を防ぐ砂とコンクリートで出来た「石棺」で艦体を覆う計画を立てている。(ただし日本渡航という作戦の性格上、戦闘行動を取ることはないので魚雷を積んでいた可能性は低いという指摘もある) そしてその石棺は、水銀のみでなく、遥か日本へ向かう絶望的な作戦で死んだ70人の乗組員、そしてこの記事には載っていないが、この潜水艦に同乗していた日本人レーダー技師1名及び三菱商事社員2名(海軍嘱託)の永遠の棺ともなるはずである。 この潜水艦が撃沈されたのは、上の日本語の記事ではなぜか1944年12月と書かれているが、ドイツの記事によれば終戦もほど近い1945年2月9日のことである(ドイツ降伏は1945年5月)。出港地もキールではなくノルウェーのベルゲンとある。 その頃かつてヨーロッパを席巻したナチス・ドイツ軍はアメリカ・イギリス・ソヴィエトの連合軍に東西から挟み撃ちにあい、ドイツ国内に逆侵攻されようとしていた。ドイツの同盟国・日本は太平洋でアメリカと戦っていたがやはり敗色濃厚で、サイパン島を失ったことにより日本本土が空襲にさらされ、この月には米軍の硫黄島上陸を迎え撃つことになる。 ドイツの総統ヒトラーは、制空権を失って苦戦する日本に対し軍事技術を渡すことで、日本の形勢挽回を図ろうとする。これはあながち日本への親切心というばかりでなく、日本が太平洋戦線で盛り返せば、フランスからドイツに攻め込もうとするアメリカ軍が兵力の一部を太平洋に転送し、ドイツへの圧力が減るだろうというあてがあった。小手先の技術で劣勢を跳ね返せると思うのは甘いと言うほかないが(そもそもその技術を生かす工業力が日本には足りなかった)、日本が1941年に太平洋戦争に踏み切ったのも、同盟国ドイツがソ連やイギリスを降してくれるだろう、そうすればアメリカも講和に応じざるを得まいという甘い見込みがあったのだから、お互い様というべきか。 ヒトラーが渡そうとしたのは、ドイツが開発した世界最初のジェット戦闘機Me262の部品や設計図、BMWやユンカース社の航空機用エンジン、そして65tにものぼる軍需用の水銀だった。日本本土を爆撃するアメリカの爆撃機を迎撃するには強力な上昇性能を持つ戦闘機が必要だが、日本は航空機エンジンの開発に立ち遅れていた。また水銀は軍艦の艦底の塗料や爆弾の起爆剤、そして電気の整流器(鉄道などで使用)に使われるそうだが、日本では既に不足していたのだろうか(北海道に水銀鉱山があったというが)。 日本とソ連はまだ交戦していなかったが(日ソ中立条約)、ドイツは1941年以来ソ連と死闘を繰り広げており、シベリア鉄道を通るわけにはいかない。そこで潜水艦で長駆大西洋とインド洋を渡り、日本にこの軍需物資を送ることになった。独ソ戦が始まって以来既にこうした作戦は何度か行われていて(参照)、日本からは終戦までに5隻の潜水艦がドイツに派遣され、うち3隻が2~3ヶ月かけてドイツに到着している(他1隻はインド洋でドイツ潜水艦と連絡)。ドイツからも1944年までに2隻のUボートが派遣され、うち1隻(U-511)が無事日本に到着しているが、他は途中で連合軍に発見され撃沈されている。 1945年2月に新たに日本へ派遣されるUボートには、ドイツでレーダー技術を学んだ日本人技師も同乗することになった。これまたアメリカ爆撃機を迎撃する上で欠かせない技術である。 この日本派遣作戦に選ばれたのは、潜水艦U-864だった。1943年8月にブレーメンのヴェーザー造船所で進水、同年12月に就役したU-864にとっては、初の作戦行動である。艦長は就役以来その任にある当時32歳のラルフ・ライマー・ヴォルフラム中佐、乗組員総数は70人(ほとんどが20代前半)、それに帰国のため日本人3人が便乗していた。 U-864は合計243隻が建造されたUボートIX型のうちでも、特に日本と共同で行うインド洋作戦に従事するため航続距離を重視して設計されたD2型で、長さ87.5m、幅7.5m、高さ10.2m、排水量1616t、水上速度19.2ノット、潜行時6.9ノット、水上での航続距離31500海里、潜行航続距離57海里、武装は魚雷発射管6本(22発搭載)、10センチ砲、37ミリ砲、20ミリ機関砲各一門という諸元である。 BBCの報道を見るところ、上の記事の「1944年12月」というのはU-864がキールを出港した日付らしい。連合国側はドイツ軍の暗号解読などから既にこの作戦を察知しており、執拗にU-864の行方を捜していた。U-864はキールを出港した後、数日の航海と寄港を繰り返しつつ、当時ドイツ軍の占領下にあったノルウェーのベルゲンに達した。途中停泊していた軍港が連合軍の空襲を受けることもあった。 1945年2月7日、U-864は日本に向けベルゲン港を出航した。しかし翌日機関に故障が発生し、ベルゲンに戻らざるを得なくなった。敵の発見から逃れ、また追尾を逃れるため、潜望鏡深度に潜行して航路をジグザグにとり、ベルゲンのあるベルゲン・フィヨルドにさしかかろうとしていた。(この当時の潜水艦は原子力潜水艦でないため長時間潜行できず、普段は浮上しており、いわば「潜ることも出来る船」だった) ところが既にその2時間前、イギリス海軍の潜水艦「ヴェンチャラー」(ジェイムズ・ランダーズ艦長)はU-864のエンジン音を探知し、ずっと追尾していた。正午前にU-864が魚雷の射程内に入ったため、魚雷4発を発射した。当時弱冠25歳のランダーズ艦長の報告によれば、最後の一発が命中し、まず大きな爆発音が聞こえ、続いてU-864の艦載電池によるものと思しき小爆発が立て続けに聞こえた。U-864の船体は両断され沈没したものと思われた。存命している「ヴェンチャラー」乗組員の一人、ハリー・プラマーは「その瞬間ほっとしたが、同時に多くの敵乗組員が死んだと気付き、『Poor bastard(哀れなブタ)』と思った」と証言する。 時に1945年2月9日午後12時14分、フェーイェ島の沖北緯60度46分、東経4度35分、当該海域の水深は150mだった。浮上した「ヴェンチャラー」がその海域を捜索したが、厚い油膜や木材片、爆発の衝撃で死んだ魚が浮かぶのみで、生存者はなかった。 「戦争が悲惨だ」というのは分かりきったことではあるが、同じ死ぬのならば陸の上のほうがましで、こういう海の底で死ぬのだけは僕は勘弁して欲しい。おそらくU-864の乗組員(と日本の技師)にとっては、突然魚雷が迫ってきて船腹に命中し、訳も分からぬまま浸水してもがき苦しみながら死んでいったのだろうと思う。それを思うとやりきれないし、戦争が怖い、とありありと思う(戦争を終わらせるのも防ぐのもまた戦争なのかもしれないが)。 「シュピーゲル」の記事は「ナチスの潜水艦が海底で毒を撒き散らし環境を破壊している、迷惑な」と言わんばかりの口吻だが(そりゃ迷惑だろうけど)、艦内に残っているであろう遺体についてあまり考慮していない記事の書きっぷりは、冷酷な戦争のリアリズムに徹したというべきか(まあヨーロッパ人は日本人ほど遺骨とかに重きを置かないのだろうが)。上の時事通信の記事も、作戦の性格上ちょっと調べればこの潜水艦に日本人も乗っていたことが分かるのだが、それはあまり意味を持たないことなのだろうか。 かつての敵国であるイギリスBBCの報道では、当時20歳のU-864乗組員・ヴィリ・トランジアー機関兵長が出港直前に恋人エディト・ヴェッツラーに求婚の手紙を送ったこと、恋人を失ったエディトが84歳で今も存命であり、この「海の墓標」についてBBCのインタビューを受けているのとは、何やらこの発見に対する態度の違いを感じる。
2006年12月23日
コメント(2)
-

地球温暖化進行曲
「♪地球が暑くなって どこ悪(わり)ぃ 暖房いらずで いいじゃねぇか 蛇口をひねれば温泉で 牛乳搾れば粉ミルク あ それ どんどんだんだん 温暖化 どんどん だんだん 温暖化 こん~な地球~に 誰がし~た♪」 1990年に聞いたこの曲、実は最近まで「地球温暖化行進曲」だと思っていた。 それはともかく、本題。 (引用開始)欧州500年ぶりに「暖かい秋」 【パリ=山口昌子】欧州は今年、500年ぶりの暖かい秋に見舞われており、平均気温が例年より数度も高かったことが判明、地球温暖化が確実に進んでいることを印象付けている。 仏ルモンド紙が8日報じたところによると、スイスの気象研究家は「約1500年以来の欧州の気象条件」に関する直接、間接のさまざまな情報を収集・研究した結果、今秋がもっとも暖かいとの結論に達したという。 パリは8月、雨が多く、気温も朝晩が5、6度で、日中も10度前後と冷夏だったのに対し、9月、10月、11月は好天が続き、日中は気温が十数度になることも多かった。12月に入っても同様に暖かく、5日の仏南部マルセイユの気温は18度に達した。 フランス気象庁によると、9、10、11月の平均気温は例年の気温より2・9度高かったことが判明。記録が開始された1950年以来、最も高い気温になった。また05年は通年より平均1・4度高かったが、今秋は温度差がさらに広がりそうだ。 オランダや英国も今年が「3世紀以来の暖かい秋」であることを明らかにしている。(Sankei Web)(引用終了) 今年のドイツの夏は異様な暑さで(まあ僕は夏はトルコに居るのが通例だったのだが)、初めて研究室に(そして向かい側の別学科の教授の部屋にも)扇風機が導入されるほどだったが・・・・。 この記事と同じ内容の記事が「シュピーゲル」電子版にも出ていた。ドイツ気象庁(DWD)は、9月から11月の平均気温が12℃で、これは1961年から99年までの平均よりも3.2℃も高く、1901年の観測開始以来、今年の秋が最も暖かかったと報告している。 ドイツの大衆紙「ビルト」には、 「ヨーロッパの今年の12月はこの1300年間で最も暖かい」とセンセーショナルな見出しが踊ったという。シュピーゲル誌は、まだ12月始まったばかりでしょーが、とツッコんでいるが、1300年前っていうと日本だと平城京、ヨーロッパだとイスラム軍とフランク王国が戦っていた(トゥール・ポアティエ間の戦い)頃ですぜ。あ、今も戦ってるか・・・というのは悪趣味な冗談として。 DWDはこうしたセンセーショナルな発表を避けているが、実際のところどうなのだろうか。ヨーロッパはアルプス山脈の氷河があるおかげで、気候変動に関する研究が最も進んでいる地域の一つだが、果たして1300年前の気候がそんなに分かるものなのか?というのがこの「シュピーゲル」の記事に出ている。 オーストリアの気候学者ラインハルト・ベーム博士によると、「ビルト」の見出しが正しい可能性は高いが、確実にいえるのは過去250年のデータくらいで、過去250年で今年の秋が最も温暖だというのは確実に言えそうだという。一方スイス・ベルン大学のユルク・ルーターバッハー博士は、年輪の厚さや氷床コア、さらには修道院の年代記(計測されているものでは1659年が最古)などを駆使して過去500年の気候データ復元を試みているが、やはり「過去500年では最も暖かい」といえるとしている。上の産経の記事の「過去500年」という数字の出所はここだと思われる。 まあ気候変化の推定はサンプルによって大きく変わるみたいだし、簡単ではないみたいなのだが(参考)。 上の産経の記事を見つけたヤフーのサイトでは、温暖化についてページがリンクされている。そこで北半球における過去1000年の気候変化をあらわしたグラフを見つけたが、これがなかなか興味深い。このグラフでは分かりにくいが、過去1000年には中世温暖期と呼ばれる時期(10~12世紀。この時代にヴァイキングが活躍したことを留意されたし)と、小氷期と呼ばれる寒冷期(18~19世紀。ヨーロッパの産業革命期)があった。このグラフの折れ線は各年ごとの平均、曲線は5年ごとの平均を表しているのだと思う。 気候が暖かく(乾燥化)なったり、寒く(湿潤化)なったりすることはなんども繰り返されているが、気になるのはそれが急激に起きた時期である。ゆっくり変化するのなら対応する余裕もあるだろうが、急に起きるとそれまでのシステムが利かなくなり、一種のパニック状態になりうる(まあ「ぬるま湯の中のカエル」という喩えもありますが)。このグラフでいうと、曲線が急激に上下している時期がそれにあたる。気温の上下そのものの影響もさりながら、その急激さも無視しがたい。 それを書き出して、日本や西洋の歴史的な出来事と併記してみると(矢印の向きは気温の上下)、・12世紀末↑↓ 十字軍、モンゴル帝国の興隆、源平合戦(1182年は飢饉で源平両軍が軍事行動が出来なかった) ・14世紀半ば↓↑ ペストの流行、観応の擾乱・15世紀半ば↓↑ フス戦争、応仁の乱・16世紀後半↓ 戦国末期(元亀・天正)・17世紀後半↓・19世紀初頭↓ 天保の大飢饉・20世紀↑ 今起きていることといったところだろうか。20世紀のそれの甚だしさが目につくが、これが人類の活動(二酸化炭素の排出とか)に起因するものか、それとも何度も繰り返された寒冷化・温暖化の波に過ぎないのか、という評価の仕方で、京都議定書に対するヨーロッパとアメリカ(というよりブッシュ政権)の対応の違いになる。この尋常でなさを見ると、人口爆発も含め、無関係ってことはないでしょうな。 気候変化が人間社会に及ぼす影響は多岐にわたるが、まず一番大きいのは食糧生産に関わることだろう。近代以前の日本では米の不作で何度も飢饉が起きているし、1993年の大冷害(タイ米騒動)は比較的記憶に新しい。北朝鮮の冷害、アフリカの旱魃は人災の面もあるとはいえ、毎年のように繰り返されている。気候変化がもたらすのは災害ばかりでなく、温暖化すると米の二期作が可能になったりもする(ロシアでは小麦の収穫量が増えているという)。植物を食べる動物にも影響するし(特に遊牧民では深刻)、人類が(人工的な)植物群落や動物の群れに「寄生」している以上、これは仕方ない。陸地だけでなく、水中でも気候が変わって水温や海流が変わるとプランクトン量が変わり、漁獲高に影響する。 その他、気候の変化で環境が変わるので、土地利用が変わり、地政学に影響することもある。例えば戦国時代後期の越後は比較的温暖で、海水位上昇によって平野部の湿地が水没して湊になり、日本海交易(青苧)が盛んだった。当然集落や城の場所も変わる。積雪が溶けるのが比較的早いので、上杉謙信は手取川から小田原まで、広範な軍事行動が可能だったという説もある。「北越雪譜」(1837年)に描かれる江戸時代の越後とはかなり違ったらしい。時代によって集落の場所、つまり遺跡の位置が変わるのには気候の影響もあるだろう。 また生活や風俗、文化にも影響する。中世ヨーロッパはかなり温暖だったせいか、イタリアに住むローマ教皇の中にはマラリアで病死したものもいる。逆に13世紀以降は寒冷化したせいか、吉田兼好の頃は桜が咲くのは4月後半だった。気候の変化は風俗にも影響し、例えば紀元前後の漢代は相当な厚着が普通だったことが指摘される、などなど挙げればきりがない。 もちろん、歴史の出来事を全て気候変化で説明する(その方面の大家に僕もお会いしたことのあるY先生という人がいて、この方は気候変化論が「仏教思想が人類を救う」などと一種の宗教論にまでなってますが)のもあまりに粗雑というべきで、気候の変化(多くは天災として記録される)と人間の対応を丹念に拾っていくことを怠ってはならないが。 今年は世界有数の穀倉・オーストラリアが大旱魃で、世界の穀物価格に影響を及ぼしそうだという。かつてレスター・ブラウンが警告した「中国人(まああと20年もしたらインド人のほうが多くなりそうだ)が世界の穀物を食い尽くす」というのは洒落じゃなくなってきているような気もする。 冒頭に挙げた植木等の歌は「男は腹巻ステテコで、女はビキニで盆踊り」「おい暑ぃな、アイスクリーム買って来い!何ぃ売り切れ?どうせ買い占めたのは日本人だな」と、かなりブラックな内容が続くが、最後には人類はみんな焼け死んでしまうというオチになっている。今世界で目の前に起きている出来事は歴史理解の一助にはなりそうだが、クレイジーキャッツの歌みたいに「ハイそれまでよ」となってしまったら歴史もへったくれもないわい。
2006年12月10日
コメント(3)
-
新・世界七不思議
ちょっと古いニュースだが、あるスイスの財団が「我々の遺産は、君たちの未来」を合言葉に、「現代版・世界七不思議」の選出を企画し、投票を呼びかけているという。投票はこちらのページか、電話で出来るとの事。締め切りは来年7月という。 冒険家ベルナルド・ヴェーバーが設立し、前ユネスコ事務局長フェデリコ・マヨールが総裁を務めるこの財団によれば、収入の半分(どういう収入だろう?)は文化財保護活動や2001年にターリバンによって破壊されたバーミヤンの大仏の再建費用に寄付される。 このプロジェクトは2005年に始まり、200あった候補(ちなみに、世界遺産は現在までに650ほど登録されている)がネット上での2000万票に及ぶ投票により77にまで絞られ、建築の専門家7人により21の最終候補が選出されている。このうち7つが投票により「新・世界の七不思議」に選ばれる。 その21の候補はあとで紹介するとして、「世界七不思議」という言い方は結構古くからある(日本で「七つの」というと、「賎ヶ嶽の七本鑓」とか童謡「七つの子」だろうか)。驚異的な建築物については紀元前5世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスが、主に中近東のそれについてリストを書き残しており、最古の「七不思議」は紀元前2世紀にシドン(レバノン)の作家アンティパトロスによるものであるという。中沢新一じゃないが、七というのには何やら秘数的な意味もあったのだろうか。 しかし古代の「世界七不思議」という場合、普通は紀元前2世紀のビザンツ(現トルコのイスタンブル)の人フィロンが書き残した「De septem mundi miraculis」である。その内訳はというと、 1、バビロン(イラク)の女王セミラミスの空中庭園 2、ロードス島(ギリシャ)の巨像 3、ハリカルナッソス(トルコ)のマウソロス2世の廟 4、バビロン(イラク)の城壁 5、ギザ(エジプト)のピラミッド 6、エフェソス(トルコ)のアルテミス神殿 7、オリンピア(ギリシャ)のフィディアス作のゼウス像ということになっている。このうち、バビロンの城壁とピラミッドについては、紀元前5世紀の人であるヘロドトスによって記録されている(彼は「バベルの塔」は見なかったようだ)。 このうち「バビロンの空中庭園」のみは実態が分かっていないが、19世紀に発掘されたアッシリア(イラク北部)の都城ニネヴェのレリーフにはそれらしきものが描かれており(アッシリア王サンへリブが王妃のために建設したという)、また20世紀初頭に発掘されたバビロンの遺跡でも、それと思われる場所が推定されている。フィロスの時代には既に廃墟となっていたニネヴェ(612年に陥落)に関する伝聞をバビロンと混同したのであろうとも考えられている(アッシリア王妃サンムラマトが、伝説の女王セミラミスのモデルとされる)。一方で比較的時代の近いヘロドトスが空中庭園について何も書き残しておらず、また同時代のバビロニア史料にも見えないことから、「想像上の産物」という説も根強い。 作られた順番に並べると、ピラミッド(紀元前2500年頃)→空中庭園(ニネヴェだとすれば紀元前7世紀初頭)→バビロンの城壁(紀元前6世紀?)→ゼウス像(紀元前456年)→アルテミス神殿(紀元前5世紀半ば竣工)→廟(マウソレウム、紀元前4世紀半ば)→巨像(紀元前300年頃)となる。しかし形あるものはいつか壊れるのが世の常、フィロスの頃にはピラミッド以外はほぼ全て地震や戦乱で破壊されて遺跡になっていた(マウソレウムは16世紀まで土台が残っていた)。 さらに後年になると、「バビロンの城壁」は忘れられてしまい(6世紀の人トゥールの年代記作者グレゴールなど)、代わりにアレクサンドリア(エジプト)のファロス島にあった大灯台が加えられるようになった。この高さ160mともいわれる大灯台は、アレクサンドリア市の建設に伴って紀元前3世紀前半に建設されたが、1303年及び1323年の地震で倒壊、土台部分も1480年に要塞に改造されてしまい、原形を留めない。つまり現代も残っているのはピラミッドのみである。 その分布を見ると、8つのうちイラクが2、エジプトが2、トルコが2、ギリシャが2と、ほとんど中近東に限られている。これで「世界の」というのはおこがましいが、当時ギリシャ人は北はせいぜいフランス(あるいはイギリス?)やハンガリー、東は中央アジア、南はサハラ砂漠までしか知らなかっただろうから仕方がない。同時代の中国の長城や始皇帝陵、インドの仏教寺院などを見ていれば、七不思議に加えていただろう。ペルシア帝国の都ペルセポリス(イラン)もギリシャ人は知らなかったのだろうか。 時は流れ、1995年に建築家たちによって「現代の七不思議」というのが選出されていて、CNタワー(カナダ。当時世界最高のビル)、金門橋、エンパイア・ステートビル(アメリカ)、パナマ運河、ユーロトンネル、イタイプ・ダム(パラグアイ。三峡ダムが出来るまでは世界最大のダムだった)、デルタワーク(オランダのダム)がそれである。しかしその後ももっと高いビルや巨大なダムが出来ているのだから、「決定版」という感じがしないし、現代建築に偏りすぎている。 そこで冒頭の「新世界七不思議」となるわけだが、その候補となる21の建築物(自然景観は対象とならない)とその建設年代を以下に挙げる。・アテネ(ギリシャ)のアクロポリス 紀元前5世紀・コルドバ(スペイン)のアルハンブラ宮殿 主に13世紀・アンコール・ワット(カンボジア) 12世紀・チチェン・イツァ(メキシコ)のピラミッド 10世紀・リオデジャネイロ(ブラジル)、コルコバードの丘のキリスト像 1931年・ローマ(イタリア)のコロッセオ 1世紀末・イースター島(チリ)のモアイ像 10~17世紀・パリ(フランス)のエッフェル塔 1889年・万里の長城(中国) 現在のものは主に15世紀・イスタンブル(トルコ)の聖ソフィア大聖堂 537年・京都(日本)の清水寺 1633年・モスクワ(ロシア)のクレムリンと赤の広場 15~17世紀・マチュ・ピチュ(ペルー) 15世紀後半・ノイシュヴァンシュタイン城(ドイツ) 1886年・ぺトラ(ヨルダン) 紀元前1世紀・ギザ(エジプト)のピラミッド 紀元前2500年頃・ニューヨーク(アメリカ)の自由の女神像 1886年・ストーン・ヘンジ(イギリス) 紀元前2500年前後・シドニー(オーストラリア)のオペラハウス 1973年竣工・タージ・マハル(インド) 1653年竣工・トンブクトゥ(マリ) 16世紀頃? うーむ。なんじゃこりゃ?というのも入ってるなあ(ノイシュヴァンシュタイン城など)。コルコバードのキリスト像もいただけない。どっちも有数の観光スポットとはいえ。オペラハウスなんて、単に各大陸一つという数あわせでしか入ってないでしょ? それにしても日本代表?が清水寺というのはこれいかに。僕なら法隆寺か大仙古墳(いわゆる仁徳天皇陵)、あるいは姫路城を推すところだが。 この中では、万里の長城、コロッセオ、モアイ像、ピラミッド、タージ・マハル、マチュ・ピチュ、アンコール・ワットは外せんでしょうう。あれ?もう七つになってしまった(笑)。 こうしてざっと見ると、建設年代が13世紀、17世紀、1886年前後に結構集まってますな。 こういう「世界の不思議」というと連想するのは、かつて研究室の隣の席のパソコンに入っていて僕ばかりが遊んでいた(席の主、済みませぬ)、ゲームの「シヴィライゼーション」に出てくるイベントで(完成させると得点が増えたりボーナス能力で有利になったりする)、あれにはストーン・ヘンジ、ピラミッドや万里の長城、自由の女神やエッフェル塔のほか、シェイクスピアの劇場、システィナ礼拝堂、大聖堂(バッハのパイプオルガン)、フーヴァー・ダム(アメリカ)、国連ビルなんてのが入っていた。
2006年12月07日
コメント(6)
-

坩堝
いつものように「シュピーゲル」の電子版を読んでいると、考古学関連の記事があったのでメモ。 中世後期(12世紀)以降、ドイツ・ヘッセン州北部、カッセル市近郊のグロースアルメローデで生産された坩堝(るつぼ)はどんな高熱や金属、酸に触れても壊れないというので、錬金術師や陶工の需要が高かった。そこで生産された坩堝は12世紀頃に登場し、15世紀になるとドイツ国内のみならず広い範囲に輸出される。この坩堝はスカンディナヴィア半島、イギリス、スペイン、ポルトガル、さらにはイギリスによる恒久的な最初の北米植民地であるジェイムズタウン(1608年建設。疫病の頻発を理由に1699年に放棄)の遺跡でも発見されている。 この中世の坩堝がどうしてそのような類を見ない強度を誇ったのかは不明だったが、ロンドン大学とカーディフ大学の研究グループがヘッセン州や各国の出土品約50点を分析し、「Nature」誌に発表した。それによると、この坩堝には特別な土が混ぜられており、1100~1200℃という当時のヨーロッパとしては高温の窯で焼かれた結果、ムライトというアルミニウムケイ酸塩物質が形成され、この堅固さが得られたとの事。 ムライトはAl2O3-SiO2系の安定的固溶体鉱物。 通常は化学組成 3Al2O3・2SiO2を指すことが多い。 粘土質原料やシリマナイト族鉱物の焼成で生成し,Al2O3-SiO2系耐火物や陶磁器の構成鉱物として重要である。また合成ムライトを耐火物原料とする。とのことだが(何がなんだかさっぱり分かりません。泣)、現代の耐火レンガやスペースシャトル(耐熱セラミック)にも使われている物質だという。道理で優れた坩堝になるわけだ。 研究グループの代表は「当時の陶工は『ムライト』という物質の存在も知らなかっただろうが、経験によってこのハイテク物質の効果を知っていたのだろう」と述べている。このムライトはドイツではバイエルン北部や西部のアイフェル高地で産するカオリナイトの化学変化から出来るらしいが、ヘッセンの坩堝に含まれていた土はどこから来たのだろうか。 ヨーロッパでセキ(火石=火偏に石)器(日本でいうと須恵器や備前焼のような、無釉・高温で堅く焼き締めた焼物)が広く普及するのは12世紀くらいだと思うが、それと同時代に発達したパイロテクノロジー(火の技術)である。この時代の発達はどうしても十字軍など西アジアとの交流をその背景に考えてしまうんだが、あいにく肝心の西アジアでのこの時代の研究が進んでいるとは言い難い。 えーと、この記事の何が気になったかというと、この研究代表者がマルコス・マルティニョン・トレスというロンドン大学の先生(といっても僕より若そうだが)で、去年僕が参加したロンドン大学でのワークショップの世話人だった、ということなんですがね。 この人「考古学者」と紹介されていて、「考古学者は土をいじるだけではない」と付属写真のキャプションについている。こうした化学分析なくして現在の考古学は成り立たないのは事実だが、「考古学者」という言葉の響きから一般がイメージする像とは随分違うだろうなあ、と想像する。かくいう僕もロンドン大学の「考古学研究室」を訪れて地下にある巨大な何かの分析機器を見たときは、ドイツとの違いに随分と驚いたものだったが。 日本でも多くはそうだろうけど、イメージとして「考古学研究室」というと古ぼけた本が並んでいて、棚には土器片とか骨とか石造物といった怪しい物体が入った点箱(発掘現場で出土遺物を入れておくプラスチック製の浅い箱。マージャンの点棒を入れる箱の大きなもの)が並んでいる、というものだろうと思う。
2006年11月23日
コメント(4)
-

東の国と南の地、袋鼠と駱駝雀
(引用開始)オーストリーと呼んで オーストリア大使「オーストラリアと混同」 ■「定着していない」…戸惑う外務省 「オーストリアではなくオーストリーと呼んでください」。欧州の伝統国オーストリアの駐日大使館が「日本語表音表記の変更」を発表した。豪州のオーストラリアとの混同を避けるというのが理由だが、外務省も「まだ定着していない」としており、あまりに唐突な発表に戸惑いの声が上がっている。(大野正利)(中略) まず「日本ではオーストリアはオーストラリアと常に混同されており、違いを明確にするため」と変更の目的を明記。 続いて日本では19世紀から昭和20年まで「オウストリ」と表記されていた史実が列挙され、「(今後は)『オーストリー』の名が広く速やかに浸透していくことと存じます」と結ばれている。 あまりに突然な変更だが、この「オーストリー」の表記、日本人になじみ深いことも事実だ。 国内初の本格的な国際地理誌「萬國地名往来」(明治6年発行)で同国は「ヲウストリ」とされ、翌年開催されたウィーン万国博覧会も開催国「オウストリ」と宣伝された。(中略) 英語読みの「オーストリア」が主流となったのは第二次大戦後。ここから南半球の大国「オーストラリア」と混同する日本人が増え始めた。最近では、東京・元麻布の同国大使館に間違って訪問する人のために、オーストラリア大使館(東京・三田)への道順を記した地図を用意するほど。かつての大国が直面しているのは、こうした現実だった。(中略) 「オーストリア」と「オーストリー」、定着するのは果たしてどっち?(産経新聞) - 11月20日8時0分更新(引用終了) うーむ。確かにオーストリアとオーストラリアを言い間違える日本人が多いとはいえ(さすがに両国を全く混同する人はあまり居ないと思うが)、今更「オーストリー」と呼んでね、と言われてもなあ・・・。しかもあまり変わりないんじゃないだろうか。 「オーストリア」というのはあくまで英語名であって、日本語文脈の中でドイツをジャーマニー、中国をチャイナ、韓国を(サウス・)コーリアと呼んでいるのと同じことだから、オーストリア側としてもこの日本での呼び名にさほど執着がないというのは分かるのだが。ただ戦前に使われていたという、英語(あるいはフランス語)名称が訛ったものと思われる「オーストリー」も、あまり根拠はないんじゃない? 念の為書いておくと、オーストリアの公用語でもあるドイツ語ではオーストリアは「Österreich(ヱスターライヒ)」、オーストラリアは「Australien(アウストラーリエン)」で混同のしようがない。スラヴ系言語であるチェコ語やポーランド語(この両国はかつてオーストリアに支配されていた)、アラビア語などでも似ても似つかない言葉になる。 ただ例えば英語では日本語と同じ問題を抱えることになるし、トルコ語でも「アウストリヤ」と「アウストラリヤ」だから、世界中には混同する人も結構多いのかもしれない。 それにしてもオーストリア大使館って親切だねえ。オーストラリア大使館と間違えて来るような輩(まさかこれも「ゆとり教育」の産物じゃないでしょうね?)にわざわざ地図まであげるなんて。そんな不勉強(というか不用意)なやつは「おとといきやがれ」と追い返してもいいと思うんだが、やはり日本人はオーストリアにとって大事なお得意様だからむげに扱えないのだろう。 かつて性風俗産業のソープランドが「トルコ風呂」と呼ばれていた頃(韓国では今でもそう呼ばれているらしい)、「トルコ・大使館」「トルコ・大統領」というふざけた名前のソープランドが電話帳に載っていて、本物の大使館とゴッチャになって電話がかかって来たという笑うに笑えない話もあるが(在日トルコ人やトルコ大使館の努力でこの名称は改められた)、オーストリア大使館は自国の名前に無理解な日本人のほうを変えようとは思わなかったのだろうか。 僕は「オーストリア」を呼び換えるつもりはないですけどね。(追記) この報道を受けたオーストリア大使館のコメント(商務部ホームページより転載)(引用開始)現在、オーストリーへの表示変更は進めておりますが、まだ変更中の部分もございます。 新しい呼称への大きな理由はオーストラリアとの区別化にございますが、「オーストリー」の使用は、義務付けられているものではございません。 より多くの皆様のご理解を得、ご協力いただくことにより、一日も早い定着を期待いたします。 2006年 11月 (引用終了) あと今年は日本オーストラリア友好年だそうで(1976年の友好条約締結30周年記念)、オーストリア大使館を間違えて訪問する人が多いのはそのせいもあるのかもしれない。・・・・・・・・ もうあちこちのブログとかで書かれていると思うが、オーストリアとオーストラリアの語源について。 どちらも元々ラテン語の英語式発音が日本に普及したものであるが、その成り立ちと意味するところは全然違う。 まずAustriaだが、上に書いたようにこれはドイツ語で「東の国」を意味するÖsterreichの読みをラテン語で表記したものである。8世紀末、フランク王国のカール大帝が東方のアヴァール族を征討して現在のオーストリア辺りに東方辺境領を置いた。これはのちに「東の地(Osterrichi)」と呼び習わされるようになり(史料上の初出は996年)、それがÖsterreichとなる。 この地名の発音がラテン語風にAustriaと表記されるようになるのは13世紀以降である(「武蔵」「陸奥」という日本の旧国名を中国風に「武州」「奥州」と書くことがあるように、ドイツ語よりもラテン語で表記したほうが気取って見える)。実は英語云々をいう以前に700年の歴史を持つ名称であり、それなりに謂れのある名称といえる。 以下余談。 オーストリアは15世紀にはヨーロッパ随一の大国として台頭、15世紀のフリードリッヒ3世は「A.E.I.O.U.」を自国のスローガンにして紋章に副えた。これは「Austriae est imperare orbi universo(オーストリアは世界を支配すべし)」というラテン語のイニシャルを取ったものとされている。 もっともこのイニシャル、その後さまざまに改変されていて、例えば Austria erit in orbe ultima(オーストリアは永遠なり) Augustus est iustitiae optimus vindex(皇帝は最良の正義の守護者)というラテン語の別ヴァージョンもあり、また Alte Esel j(i)ubeln ohne Unterlass(老いたロバは絶え間なく叫ぶ) Aller Ehrgeiz ist Österreich unbekannt(オーストリアは大志と無縁) などといったパロディも作られている。 閑話休題。 上に出てきた「フランク王国」だが、こちらはフランス(ドイツ語でFrankreich=フランクの国)という国名の起源となっている。 フランク王国は5世紀末に成立したゲルマン系フランク族の国であるが、511年にクローヴィス(フロドヴィヒ)1世が死んだとき、王は四人の息子に領土を分け与えた。その一つがやはり「東方の国」を意味するゲルマン語をラテン語風に書いたアウストラシアAustrasiaで、これは英語読みすると「オーストラシア」になる。地域でいうと今のフランス北西部、ドイツ西部、ベネルクス三国にあたる。 ややこしいことこのうえないが、幸いこの地域名は、オーストラシアの宮宰小ピピン(カール大帝の父)が下克上を起こしてオーストラシア王となり、やがてフランク王国を再統一したため使われなくなった(フランク王国はカールの死後フランス、ドイツ、イタリアに分裂する)。 「オーストラリア」の方もそれなりに由来があって、2世紀(ローマ時代)の地理学者プトレマイオスにそもそもの起源を持つ。 世界地図を作った彼は、世界の南端には「Terra australis incognita」という大陸がある、としている。ラテン語でテラは「土地」、アウストラリスは「南の」、「インコグニタ」は「未知の」という意味。誰も見たことがなかったのでこの名がついた。プトレマイオスによると、この大陸はアフリカ大陸南岸と繋がっており、インド洋と大西洋を隔てている(「フェニキア人が船でアフリカ大陸を周航した」というヘロドトスの「歴史」にある記述は知られていなかったのだろうか?)。当時は当然オーストラリアの存在は知られておらず、全く想像の産物である。 この大陸はずっと「インコグニタ」だったが、ヴェネツィア出身のマルコ・ポーロが13世紀に中国に赴いた際、「ジャワ島の南に何やら大きな島がある」という伝聞を耳にした。そこには二本足で立ち、腹に二つめの頭を持つ動物がおり、中国皇帝に献上されていたという。おそらくカンガルーのことだろうが、カンガルーの分布を考えると、この島はオーストラリアと考えられる。 しかしヨーロッパ人が実際にその土地を見るのはさらに300年のちのことになる。1606年、オランダ人ウィレム・ヤンスがオーストラリア北岸を発見、これこそ「テラ・アウストラリス」に違いないということになったが、1642年に同じくオランダ人のアベル・タスマンの南岸航海によって、南極とこの大陸は地続きでなく、「未知の南の大陸」は存在しないことが分かった。 しかし既に慣用的にこの大陸は「テラ・アウストラリス」と呼ばれており、またマシュー・フリンダース(オーストラリアを最初に周航した人物)よる「オーストラリア」という名称の提唱もあってこの名が定着した。 どちらもそれなりに由来のある地名なのだから、易々と換えてしまうのはどうだろう。 せめてオーストリア側にはあまり根拠のない「オーストリー」や英語風の「オーストリア」ではなく、ラテン語に忠実に「アウストリア」と発音することを提案したいが、どうだろう。 ・・・・・・・・ 英語でダチョウのことを「オストリッチ」といい(ドイツ語では「シュトラウスStrauß」)、なんとなく「オーストリア」に近い音なので関係あるのかと思っていたのだが、全然関係ないらしい。 ドイツ語の「シュトラウス」は古代ギリシャ語のstrouthion(ストロウスィオン?)が訛ったもので、意味するところは「大きい雀」という意味。古代エジプト人からダチョウを知ったギリシャ人は、ダチョウを「ラクダ雀」と呼び、それが学名(ラテン語でStruthio camelus)にもなっている。 英語の「オストリッチ」はavis struthio(avisはラテン語で「鳥」。つまり「雀鳥」)がフランス語を経て、語源も分からぬまま訛ったものだようだ。ちなみにフランス語でオーストリアはAutricheで、「ダチョウautruche」と一文字違いである。 オーストラリアにはダチョウの仲間エミューが居ますね。
2006年11月20日
コメント(8)
-

ダマスカス刀の謎
ドイツの雑誌「シュピーゲル」に自分の専門にやや関係する記事を見つけたので、概略とコメントを記しておく。 11世紀末、「聖地」パレスチナに遠征したヨーロッパの十字軍兵士たちは、敵のアラブ(トルコ)軍の兵士が持つ刀の切れ味に驚嘆した。それは空中に放り投げた絹の薄布に触れるだけで切り裂くほどの切れ味でありながら、きわめて弾性に富んでいる。そして錆びにくい。 鉄というものはそれだけでは硬さが足りず(ぐにゃぐにゃの針金を連想されたし)、炭素と合わせることでより硬い鋼(刃金)となり、初めて刃物としての実用に耐えるのだが、鉄の宿命として硬くなればなるほど(=炭素含有率が高くなるほど)衝撃に弱くなる、つまり折れやすく欠けやすくなるという欠点をもつ(刀は曲がるだけで滅多に折れないが、硬い南部鉄瓶を地面に叩きつけたら割れる)。十字軍兵士たちのもつヨーロッパの刀は分厚く頑丈だが切れ味はいまいちで、言わば腕力で叩き切るようなものだった。ところがアラブ人のもつ刀は切れ味が優れている(=硬い)のに、折れにくかったのである。 アラブ人たちのもつ刀を見ると、細かい波状の模様が全面を覆っている。聞けばインドから輸入した特別な鋼で作っているのだという。ヨーロッパ人たちはこの鋼をアラブ軍の拠点となった都市の名に因んで「ダマスカス鋼」、その鋼で作った刀を「ダマスカス刀」と呼んで恐れたという・・・・ このダマスカス刀、18世紀には作られなくなり、「伝説の金属」となった。その後ヨーロッパの科学者によって研究が進み、現在では鋼と別の金属を合わせて鍛えた、波状の模様を持つ鋼が作られるようになり、現代のナイフ収集家などに愛用されているが、現代のダマスカス鋼は厳密には「本物の」ダマスカス鋼に外見(波模様)を似せて作られたものに過ぎないという。ダマスカス鋼の科学・技術的な背景などについてはこのページに詳しい。 ここで「独特な刃の模様」というと、すぐに日本刀の模様が連想されるが、ダマスカス鋼の模様が全面に細かくあるのに対して日本刀のそれは部分的に、一本の波でしかない。日本刀の刃模様は焼き入れ(鍛えて熱した鉄を水に漬けて急冷することにより鋼に硬さを与える技法)に際して硬くしたい部分(刃先)とそうでない部分(本体)を分けるために刃に土(粘土や味噌)を被せることによって生じるものだから、ダマスカス鋼とは本質的に模様の出来方が違う。日本刀も鋼と鉄(鍛鉄)を合わせ、何度も何度も曲げたり折り返したりして均一に鍛える工程によりダマスカス鋼に似た品質を持っているが、模様に関しては別物である。 ちなみに僕はダマスカス(シリアの首都)の軍事博物館でダマスカス刀の本物を見たことがあるが(軍の施設なので写真撮影は禁止)、錆びにくいというダマスカス鋼らしく、数百年もののはずなのによく光っていた。 ついでに書いておくと、よく時代劇でやたら刀がポキポキ折れるのだが、相当粗悪な刀(成分が不均一、つまり鉄に混じり物がある)でなければああはならない(幕末の勤皇の志士が使った粗悪な大量生産品である「勤皇刀」でならあったかもしれない)。もちろんチャンバラをすれば衝撃で曲がるが、鋼と鉄の精緻な組み合わせである日本刀の特性によって、少々の曲がりなら大抵は一日放っておけば元の形に戻ったそうである。 ここでようやく本題である。既に2001年にアイオワ州立大学のジョン・ヴァーホーヴェン博士が「ダマスカス鋼の歴史的製法の再現に完全に成功した」と宣言していたが、なぜダマスカス刀がしなやかでいて鋭いのかという問いには答えていなかったという。 今回ドレスデン工科大学のペーター・パウフラー教授らのグループは、このダマスカス鋼の謎に挑んでそれを解明し、雑誌「ネイチャー」に発表した。教授らは17世紀ペルシアの刀工アサド・ウッラーの作を分析、初めて高精度の電子顕微鏡で構造を観察し、また塩酸をかけるなどの実験をした。観察によれば鋼の中は細かいセメンタイト(鉄炭化物)の他に、ナノ(0.000 001mm)単位の筒状の構造が確認されたという。塩酸をかけるとセメンタイトは溶けるのに対し炭素は溶けないが、このダマスカス鋼に塩酸をかけてもセメンタイトが残り、おそらく直径がナノ単位の炭素の筒の中でセメンタイトが保護されたのだろう、と結論付けたという。これならば錆びにくいというダマスカス鋼の特性も説明できる。 さらに教授らは、セメンタイトが炭素よりも硬いことに注目する。つまり刀の使用によって炭素が先にちびてもセメンタイトの部分は残ることになる。つまり刃先は使うにつれナノ単位で見ればどんどんギザギザのノコギリ状になるのだが(言わば刀を使えば使うほど刃先が磨がれる仕組みになる)、これがダマスカス刀の伝説的な切れ味に繋がっているのではないかと推測しているという。同時に炭素によって弾性も保たれるというわけである。 ではこうした鋼がどうやって作られたかというのは未だに謎であるが、教授らは複雑な加工と温度操作(製鉄の際の炎の色で判断したのだろう)を想定している。ダマスカス鋼はインドで作られていたウーツ鋼という特別な鋼で作られていたのだが、このウーツ鋼は1.5%という高い含有率の炭素の他、クロム、マンガン、ヴァナジウム、コバルト、ニッケルなどの微量元素も含んでおり、これがナノ単位での化学変化に影響しているのではないかとのこと(ヴァナジウムは日本刀の素材となる、砂鉄から作られた玉鋼にも含まれていたと思う)。 僕は実は化学や物理にはてんで弱いのだが、この記事によれば、つまりは特定の鉄鉱石と特定の加工技術(一定温度の維持)による「中世のナノテク」であると結論している。切れ味するどい日本刀は機械工作レベルだが、ダマスカス刀の切れ味は化学・物理レベルという違いである(もちろんその原理を知っていたのではなく、多分に経験や口伝による知識の蓄積に頼っていたのだろう)。 僕としてはなぜ18世紀にダマスカス鋼が作られなくなったのかという事にも興味があるのだが、それはやはりイギリス(とフランス)のインド進出(植民地化)が大きいのではないかと思っている。ダマスカス鋼の原料となるウーツ鋼の生産には熟練した職人の伝統が不可欠だが、この時代にその伝統が失われてしまったと考えるのが妥当ではなかろうか。 イギリスはじめヨーロッパは、中国では既に紀元前に行われていた銑鉄(鋳物)の技術を15世紀に獲得し(高炉製鉄)、枯渇する森林資源に対応して18世紀にコークスによる製鉄を発明、鉄生産量を飛躍的に拡大して国力を伸ばした。その物量の前にはインドや中国の伝統的製鉄は形無しだったのではなかろうか。 時は流れ、世界の粗鉄生産は上位から順に1位中国(2億トン)、2位日本(8千万トン)、3位ロシア(5千万トン弱)、4位アメリカ、5位ブラジルとなっている(なおドイツは7位、インドは9位、フランス10位、イギリスは13位)。そして世界最大の鉄鋼会社は昨年インド人が経営するミッタル・スチールになった。品質はともかく、世界で最初に銑鉄を生んだ中国と、ウーツ鋼の故郷インドの躍進が著しい。なんだか本卦帰りしたようにも見える。(追記) 同じ内容のニュースの日本語版はこちらで読める。 一方、この記事を冷静かつ皮肉たっぷりに批判する記事(ドイツ語)も見つけた。その要点をかいつまんでおくと、1、マスコミ発表や「ネイチャー」の記事は、ダマスカス鋼・刀の定義があいまいであり、また歴史的・文化的背景(論文の最初の三分の一)の説明が「伝説」「小説」の域を出ず、的外れである。例えば実験に使われた刀は16世紀にイランで作られたものだというが、どうしてこれが「ダマスカス」刀と呼べるのか?2、この「ネイチャー」誌の論文の要点は「ダマスカス鋼」内部の「ナノチューブ」の発見だが、この刀がダマスカスは鋼の原料とされるウーツ鋼で作られたのか否か、鋼の出所や特徴の追及・比較・説明がない。この発見をもって「ダマスカス鋼」一般の秘密の説明できない。3、そもそもダマスカス鋼の高性能ぶりは多分に文学作品に依拠するもので、例えばヨーロッパ初期中世の刀を見れば、同じような文様や高度の炭素分をもつ刃がダマスカス鋼以前や他地域にもあることは明らかである(日本式にぴかぴかに研げば分かる)。つまり「ダマスカス鋼」の伝説は実体がない。これらの刀を同じ方法で調査すれば、同じ結果が出るかもしれない。 そして最後に、「マスコミのセンセーショナリズムに陥ち込んでいる」と、「中世のナノテク」などと報じる研究グループやマスコミの論調を批判している。 うーむ、読んでみると確かにこっちのほうが説得力がある。確かに僕も踊らされたというべきか。こうした資料に対する歴史的・文化的背景の大雑把な一般化は、考古遺物の化学分析では往々にあることだが、化学のことがよく分からんので僕らも引きずられるんだよな。いかんいかん。 ところでこの文を書いた人、「シュテファン・メーダー博士」とあるが、なんと所属が國學院大学とある。どういう人だろう?
2006年11月16日
コメント(7)
-

日本100名城
どうにもお城が好きである。 最初に城に興味を持ったのは、小学校3年のときに松本城に行ったときではないかと思う。その頃は歴史にも建築にもあまり興味が無かったのだが、巨大で中の薄暗い古い建物に強い印象を受けた。小学校の高学年になると父の遺した歴史の本とかを読むようになったし、行く機会の多かった岡山城や姫路城を見て城マニアになった。今思えば我ながら珍妙な趣味だが、皆がガンダムのプラモデルを集めている時分に城の天守閣のプラモデルを結構集めたものだ。 やがて関心は城という建築物そのものからその背景である歴史の方に移ったので、僕が歴史に興味を持つきっかけになったともいえる。歴史の関心も日本の近世からどんどん移っていって今では中近東の古代なんかを専門にするようになってしまったのだが、お城は今でも好きである。 関心や専門の変化を反映して、より古い時代、つまり白亜の天守閣よりも土塁とか石垣(石の加工法や積み方)といった方に関心が行くようになってしまっている。「野面積み」「犬走り」なんていう専門用語を口走って引かれたこともあるが、残念ながら城跡の発掘には参加したことが無い。いや、「神皇正統記」執筆の地である小田城(茨城県つくば市)の発掘調査に一日だけ手伝いに行ったことがあるか。 もちろん日本国内に限らず、ドイツやトルコでも城を見ると血がたぎる(笑)。 前振りはこのくらいとして、最近知ったニュース。 (財)日本城郭協会は来年の設立40周年を記念事業として、日本100名城の選出を行って今年2月に発表したという。選考委員は建築学のほか歴史学や考古学の専門家も加わっており、従来のこの手のリスト(天守閣が残っているあるいは復元された城が多いので、どうしても残りの良い近世幕藩体制期の城ばかりになる)には出ることの無かった、現存せず発掘によって初めて明らかになった古代や中世城郭も加わっている。 以下そのリストを転載。名前の前に○印が付いているのは、僕が行ったことのある城。僕は旅行先では大抵城跡を訪れるので、僕の日本国内での足跡の範囲が結構狭いことが端的に分かる。北海道根室半島チャシ跡群、五稜郭、松前城東北弘前城(青森県)、根城(青森県)、盛岡城(岩手県)、○仙台城(宮城県)、多賀城(宮城県) 、久保田城(秋田県)、山形城(山形県)、二本松城(福島県)、○会津若松城(福島県)、白河小峰城(福島県)関東○水戸城(茨城県)、○足利氏館(鑁阿寺)(栃木県)、箕輪城(群馬県)、新田金山城(群馬県)、鉢形城(埼玉県)、川越城(埼玉県)、○佐倉城(千葉県)、○江戸城(東京都)、八王子城(東京都)、○小田原城(神奈川県)甲信越新発田城(新潟県)、春日山城(新潟県)、○甲府城(山梨県)、○武田氏館(武田神社)(山梨県)、松代城(長野県)、○上田城(長野県)、○小諸城(長野県)、○松本城(長野県)、高遠城(長野県)北陸高岡城(富山県)、七尾城(石川県)、○金沢城(石川県)、丸岡城(福井県)、一乗谷城(福井県) 東海岩村城(岐阜県)、岐阜城(岐阜県)、山中城(静岡県)、駿府城(静岡県)、掛川城(静岡県)、犬山城(愛知県)、名古屋城(愛知県)、岡崎城(愛知県)、長篠城(愛知県)、伊賀上野城(三重県)、松阪城(三重県) 近畿小谷城(滋賀県)、彦根城(滋賀県)、安土城(滋賀県)、観音寺城(滋賀県)、○二条城(京都府)、○大阪城(大阪府)、千早城(大阪府)、竹田城(兵庫県)、篠山城(兵庫県)、○明石城(兵庫県)、○姫路城(兵庫県)、○赤穂城(兵庫県)、高取城(奈良県)、○和歌山城(和歌山県) 中国○鳥取城(鳥取県)、○松江城(島根県)、月山富田城(島根県)、津和野城(島根県)、○津山城(岡山県)、○備中松山城(岡山県)、○鬼ノ城(岡山県)、○岡山城(岡山県)、○福山城(広島県)、郡山城(広島県)、○広島城(広島県)、岩国城(山口県)、萩城(山口県)四国○徳島城(徳島県)、○高松城(香川県)、○丸亀城(香川県)、今治城(愛媛県)、松山城(愛媛県)、湯築城(愛媛県)、大洲城(愛媛県)、宇和島城(愛媛県)、○高知城(高知県) 九州・沖縄福岡城(福岡県)、大野城(福岡県)、名護屋城(佐賀県)、吉野ヶ里遺跡(佐賀県)、佐賀城(佐賀県)、平戸城(長崎県)、島原城(長崎県)、○熊本城(熊本県)、人吉城(熊本県)、大分城(大分県)、岡城(大分県)、飫肥城(宮崎県)、鹿児島城(鹿児島県)、今帰仁城(沖縄県)、中城城(沖縄県)、首里城(沖縄県) うーん、城マニアを自称しながら、100名城中たった32城か(泣)。しかも北海道と東海はゼロである(東海は大抵新幹線で通過してしまうため)。 僕はある方のホームページの掲示板でやはりこうした「100名城」選出の議論に参加したことがあるのだが、そのホームページは戦国時代がテーマだったので、時代限定なうえ(ほぼ16~17世紀に限る)、むしろ歴史的背景のほうが重視され、このリストとは趣がずいぶん異なる。それでも八王子城や根城、金山城、山中城といった戦国時代の城(最近の発掘でその実像が明らかになったものが多い)は重なっている。 この「100名城」リストは考古学者(千田嘉浩氏)の意見が強く反映されているなあと思わせるのは、北海道のチャシや多賀城、鬼ノ城、大野城といった古代城郭、果ては吉野ヶ里遺跡(弥生時代の大規模環濠集落)といった「城郭」と言っていいのやら難しいものまで入っている。中世代表として足利氏館跡が入っているのはなかなか新鮮である。今までの名城リストには決して入ってこなかっただろう。しかしここまで城の定義を広げるのなら、近代の要塞跡(お台場とか?)とかも一つくらい入れても良かったんじゃないかと思うのだが。 選出されている城にほぼ異論はないのだが、いくつか、え?これが入るの?というのを挙げておくと、高岡城、水戸城はなあ・・・。水戸城なんて近世城郭のくせに遺構はほとんど何も残っていないのだが(それを言ったら首里城だって戦災などで一度はほとんど跡形もなくなったのだが)、これは歴史的な重要性が重視されたんだろうか。長篠城も歴史的意義(1575年の合戦)のほうだろう。飫肥城や松坂城、湯築城もあまりこうしたリストでお目にかかることはないのだが、どの辺が評価されたのだろうか。楠木正成の籠城で有名な千早城にはどのくらい遺跡が残っているのだろうか。 僕個人としては、やはり歴史的名所として上に挙げた小田城、そして戦国時代の城をイメージさせてくれるという点で逆井城(同じく茨城県)を推したいのだが、逆井城は復元が想像の部分が大きすぎるというのがダメなんだろう。 こうしたリストを作るとき、どうしても地域ごとの「お国自慢」になりがちで喧々諤々の議論になるのだが、教育基本法改正にからむ「愛国心」(=愛郷心?)論議や、好景気という発表をよそに不景気に喘ぐ地方都市にとって、城というものは戦争や行政(まあ福井県庁や愛知県庁なんかは今も城内にありますが)という本来の目的を失った現在でも、地域おこしなどの結節点となりうるのではないかと思う。こういう感覚は、城下町に生まれた人にしか分からないかな? ドイツやトルコでは城は石壁で作られていたので(ドイツでは11世紀以降だが)、土塁に木造建築中心の日本に比べて(地上に)残る確率が高い。 人口密度の低いトルコはともかく(トルコの場合はキャラヴァンサライなども一種の城として扱えるのかな?)、ドイツなんかを車で走るとひっきりなしに車窓から城跡(多くは塔が一本立っているだけのものだが)を見ることが出来る。ドイツでは地域研究・郷土史研究の一環として、日本並みに城郭研究が盛んである。 いずれは「ドイツ100名城」「トルコ100名城」なんてのを自分で選んでみたいものだ。↓我が蔵書から
2006年11月15日
コメント(10)
-
シベリアの古墳で大発見
ドイツ考古学研究所のヘルマン・パルツィンガー所長は24日、外務省で記者会見を行い(ドイツ考古学研究所は外務省の下部組織である)、モンゴル北西部のスキタイ時代(紀元前4~3世紀)の未盗掘古墳の発掘で、ミイラ化した遺体や腐朽せずに遺存する革製品及び木製品を発見したと発表した。 1991年にオーストリア・イタリアのアルプス山中で発見された「アイスマン」(5000年前の男性のミイラ及び遺品)に並ぶ大発見と報じられている。この調査はドイツ考古学研究所、ロシア科学アカデミー・シベリア支部、モンゴル科学アカデミー考古学研究所の共同調査で行われたもので、2004年にモンゴル北西部のアルタイ山脈山麓のオイゴル・ゴル渓谷で遺跡分布調査に着手し、今年夏に最初の古墳の発掘に着手したところ、早速この発見になった。 こちらの記事に発表された写真が掲載されているが、それを見ると古墳の墳丘の下に石で密封した木郭(墓室)があり、その中に被葬者の男性が膝を曲げ斜めになった状態で横たわっている。男性は皮のマントや帽子、ブーツを身に着けており、木製や皮革製の副葬品や衣類が腐らずに残っている。男性の遺体は一部ミイラ化し、金髪などが残っているが、あまり残存状態は良くない。副葬品には木製の馬具の一部も含まれるが、それは薄い錫箔で覆われていたらしい。また死者への供え物として木製容器に入った食べ物が添えられていたが、木の皿に盛られた動物の肉も一部残っている。武器として弓矢と短剣、そして弓矢入れ(「ゴリュトス」)も残っており、武装した貴族の墓と考えられる。遺物の年代は上述の通り紀元前4もしくは3世紀のスキタイ文化に属すると考えられる。 遺物は全てウランバアトルに移送され、保存処理及びさらなる調査が行われる予定。パルツィンガー教授は来年ドイツでスキタイ文化に関する展覧会を企画しており(なんかおととしもそういう話を聞いたけど)、この遺物も陳列したいとしている。 スキタイについては以前に何度も書いたので(例えばここ)、繰り返さない。 パルツィンガー教授は以前から南シベリアでの調査を精力的に続けており、ロシア連邦トゥーバ共和国のアルジャン2号墳の調査でも、やはりスキタイ文化に属する未盗掘の古墳(ロシア語で「クルガン」と呼ぶことが多い)を発見し、数千点に及ぶ黄金製品などを発見している(まあ数千点と言っても、スパンコールのように衣服に縫い付けられた金の小さな飾り金具が大部分だが)。僕は以前フランクフルト大学で行われたパルツィンガー教授のアルジャン・クルガン発掘に関する講演を聴きに行って、そのあとの懇親会で副葬品について質問したこともあったっけな。 世界地図を広げると、アジア大陸のど真ん中にロシア、中国、モンゴル、カザフスタンの四国が接する場所があるのに気づく。現代の国境など紀元前のスキタイ人には知ったことではなく(スキタイ系の文化はポーランドから中国北部までの広い範囲に分布している)、アルタイ山脈の麓にあたるこの地域にはスキタイの古墳が点在している。ウクライナにあったスキタイの古墳は多くが盗掘されてしまったが、この地域は人もまばらなのでこうした未盗掘のクルガンがよく残っているようだ。 1947年に発見されたパジリク古墳群などはその代表格だが、ここでも木製の馬車や、模様も鮮やかな絨毯(現存する最古の絨毯だろう)、ミイラ化した人間や馬の遺体が発見され、人間の遺体には刺青がくっきりと残っていた(ちなみにこの遺体も金髪のコーカソイドだったようだ)。今回のミイラ化した遺体の発見はこのパジリク以来の発見ではないだろうか。この地域は冷涼で、丹念に密封された古墳の地下の土が凍土となって有機物がよく残るのである(昨年の愛知万博に出展されたマンモスのミイラなどを連想されたし)。 ヘロドトス「歴史」から、スキタイ(ただし現在のウクライナ辺りの話)の墓制に関する記述を抜粋(巻4の71。松平千秋訳、岩波文庫)。「・・・スキュティアの王が死ぬと、この土地に四角形の大きい穴を掘り、穴の用意が出来ると遺骸をとり上げるのであるが、遺体は全身に蝋を塗り、腹腔を裂いて臓腑を出した後、(香草を)いっぱいに詰めて再び縫い合わせてある。・・・・それから遺骸を墓の中の畳の床に安置すると、遺骸の両側に槍を突き立てて上に木をわたし、さらにむしろを被せる。墓中に広く空いている部分には、故王の側妾の一人を絞殺して葬り、さらに酌小姓、料理番、馬丁、侍従、取次役、馬、それに万般の品々から選び出した一部と黄金の盃も一緒に埋める。・・・・右のことをし終えてから、全員で巨大な塚を盛り上げるのであるが、なるべく大きな塚にしようとわれがちになって築くのである」
2006年08月25日
コメント(6)
-
ニュース雑記
気になったニュースの羅列。 まずは一応休戦の成立したレバノンから。(引用開始) <レバノン>現地ルポ 空爆の傷跡目立つ…世界遺産も被害か イスラム教シーア派民兵組織ヒズボラが82年に結成された拠点として知られ、イスラエル軍の空爆が集中したレバノン東部ベカー平原のバールベックに16日入った。(中略)世界遺産のローマ神殿跡は直撃こそ免れたものの、重さ約2トンの石灰石が崩落し砕けていた。レバノン文化省はイスラエル軍の攻撃との因果関係の調査に乗り出す意向だ。【バールベック(レバノン東部)で高橋宗男】 隣国シリアに向かうベイルート―ダマスカス街道を東に進み、国境の手前を北に約40キロ。街道の途中にはヒズボラをたたえるゲートが建ち、それを通過した途端、爆撃されたガソリンスタンドや工場など、空爆の傷跡が目立ち始めた。 バールベックの中心街にほど近い遺跡は、世界有数のローマ神殿遺跡だ。天地創造の最高神ジュピター、愛と美の女神ビーナス、酒神バッカスにささげたという三つの壮大な神殿跡から成る。13日朝、神殿の手前にある「六角形の前庭」の第2チャペル跡で石灰石が高さ約5メートルの壁から崩落しているのが発見された。 「イスラエル軍の空爆との関連を判断するのはこれからだ」。同遺跡に詰めるレバノン文化省の遺跡修復担当官、ハリド・ラフィンさん(40)は慎重に答えた。ラフィンさんによると、崩落した石灰石は壁の背後の木に押され、もともと不安定な状態だった。「今後、遺跡全体の調査を進め、文書にまとめた段階でユネスコに報告する」と語った。 イスラエル軍による遺跡自体への爆撃はなかったが、遺跡内の博物館のガラスは砕けている。「イスラエル軍は遺跡の上空を低空で飛行し、中心街など遺跡周辺を何度も爆撃した。空爆や低空飛行による間接的被害は明らかだ」。遺跡事務所に44年間、勤めるフセインさん(67)はイスラエルへの怒りを隠さなかった。(引用終了) 前にも書いたが、バールベックには以前行ったことがある。また知り合いのドイツ人がここの調査で働いていた。世界遺産にもなっているここのローマ時代神殿は本当に巨大で、おそらくローマ帝国の版図の中でも(現存する)最大の神殿ではないだろうか。なんといっても石柱の太さが人間の背よりも大きいのだからその規模が窺えるし、今でもそんな柱が立ち並んでいる保存状態も驚きである。 この記事は控えめながら、遺跡破損の責任がイスラエルの空爆にあるように書いてある。これは正直言って疑問ではある。石材の落下や博物館のガラスの破損が、イスラエル空軍機の出す、例えば轟音によるものだといいたげだが、実際そういうことは起きるんだろうか?(まあ時々うちの研究室の上を訓練中のドイツ空軍機が飛んで行くときは確かにものすごい爆音ではあるが)。そんな低空で飛んで対空砲火とかは大丈夫だったんだろうか?イラク占領軍が遺跡を破壊や盗掘しているというニュースも流れたが(バビロンに駐留するポーランド軍が盗掘した、とか装甲車のキャタピラが遺跡を破壊している、など)、この手のニュースは慎重に扱う必要があると思う。 神殿自体が壊れたのは地震や古代末期のキリスト教徒による破壊によるものだが、最近ではかつてここに本拠を構えていたヒズボラが陣地構築のため遺跡の石材を持ち去ったということがあったようだ。まあアフガニスタンのターリバンみたいに、目的を持って遺跡を爆弾で吹き飛ばすようなことをしないだけましかもしれないが。 ちなみにレバノンでは、ティール(古代のテュロス)という遺跡で日本の考古学者も遺跡保護に従事しています。まあ今年は中止だったろうけど。 そのレバノンに関連して。(引用開始)<レバノン情勢>ドイツが国連暫定軍参加で議論が迷走【ベルリン斎藤義彦】国連安保理のレバノン停戦決議でレバノン南部での増強が決まった国連レバノン暫定軍(UNIFIL)への協力についてドイツ政府が独軍派兵を決められず、議論が迷走を続けている。ドイツ軍がレバノン・イスラエル国境地帯に配備されればナチス・ドイツ以来、初めてドイツ兵がユダヤ人に銃口を向ける可能性があるためだ。16日の与党党首会談でも結論は出ず、政府内には海上警備などの役割を担う代替案が浮上している。 メルケル首相ら与党3党党首らは16日、独南部で会談し「中東の政治問題解決に貢献する」との基本姿勢を打ち出した。しかし、独軍派兵についてはシュトイバー・キリスト教社会同盟党首が「歴史的な理由からレバノン・イスラエル国境への派遣は考慮に値しない」と強硬に反対し、まとまらなかった。 国境地帯に展開すればイスラエル軍と衝突する事態も想定されるが、ナチスがユダヤ人虐殺を起こした歴史的責任があるドイツは事態に対応できない可能性がある。また、イスラエル寄りの姿勢を示せばアラブ諸国の反発を買う恐れもある。(中略) メルケル首相らは16日、「人道援助、復興支援のほか、(北部の)レバノン・シリア国境の海上からの警備」を支援方針として発表。場合によっては独海軍が地中海上から警備にあたる代替案を示唆した。首相は来週中に最終的な結論を出すことを目指している。 ドイツは現在、アフガニスタンなどに約7000人を派兵している。(毎日新聞) - 8月17日18時3分更新(引用終了) 歴史的経緯が全く違うので安易な例えは避けるべきだと承知しているが、あえて例えるなら北朝鮮で金王朝が崩壊した後に、日本の自衛隊が平和維持軍として駐留する事態を想像するといいかもしれない。そういうのはまず考えられないだろうが、10年前のドイツでもこういう事態は全く想像できなかっただろう。 しかし今のドイツは既に戦争も経験しており(1999年のコソヴォ紛争。しかもその参戦を決定したのは平和主義の社民党と「緑の党」だった)、今や9ヶ国に7000人の兵士を派遣し、既に数名の戦死者(=テロ攻撃による死者。事故死も含めれば30人を超える)も出している。ましてや当のイスラエルのオルメルト首相からも派兵を要請されたというのだから、ドイツとしては断る理由は無い。今回はいつもは勇ましい保守政党(キリスト教社会連合)の側が及び腰で、また各党内ですら意見の統一が出来ていない状況になっている。 歴史的背景を拒否の理由にしてはいるが、中立を維持しようとするあまり、例えばスレブレニツァの虐殺(ボスニア内戦)を阻止できなかったり、レバノンでヒズボラの成長を座視していた、これまでの「無力な国連軍」に加わるリスクを避けたいという意図もあるようだ。 もっとも今回の国連追加派遣軍にはヨーロッパからフランス、イタリア、スペイン、フィンランドが派兵を表明しており(フランスは指揮権行使も申し出る)、ヒズボラ・イスラエルとどう向き合っていくのか注目ではある。ヨーロッパ連合軍だと本当に「十字軍」みたいだけど。・・・・・・ ノルトライン・ヴェストファーレン州(ドイツ北西部)の考古学ニュースを二つ。 インデン(アーヘンの北東)の褐炭採掘場で、12万年前(中期旧石器時代)のネアンデルタール人の「住居」が発見された。ドイツ国内でネアンデルタール人の住居址が発見されたのは、ドイツではヘッセン州ブーレンに続いて二例目という極めて珍しい発見となる。 報道や写真を総合する限り、住居といっても円形のテントのようなもので、そのテントを立てるための柱穴やテントの周りの溝(水除け)の跡が見つかったようだ。住居の近辺ではフリント(火打石)製石器60点も見つかっている。この時代に恒久的な住居は無く、皮などを柱にかけたテント(インディアンのティピを想像するとよい)のようなものだったようで、本体は残存せず痕跡しか残らない。旧跡時代の遺物が見つかることはあっても、こうした遺構はほとんど例がない。 1960年代にブーレンで発見された住居址の場合は、水辺の住居址の位置にかなり大きな石が並んでいて、テントがめくれ上がらないように周りに並べたものらしい。ここでは石器や骨角器、さらにその製作過程で出来る屑などが大量に出土しており、狩猟の際のベースキャンプ的な役割だったと推測されている。当時の人類は狩猟採集で生計を立てており、収穫が減ったら他所へ移動する遊動生活をしていた。 今年はネアンデルタール人がドイツで発見されて150周年で、関係する博物館などでネアンデルタール人に関する特別展が開催されている。 日本でも「旧石器時代の遺構」として、「石器を埋納したピット(窪み)」なんてのが見つかったと報じられたが、のちにF氏の捏造だったと判明した。今のところ日本で旧石器時代の類似する遺構は発見されていないと思う。住居址が見つかるのは縄文時代に入ってからだったかな。(注・日本の後期旧石器時代でも住居のような遺構は見つかっているようです。訂正します) 次。 ボンはかつて西ドイツの暫定首都だった町だが、そこのかつての政府庁舎跡(国会議員宿舎跡)に新たに国連会議場を建設するための緊急発掘調査が進められ、この町の起源があるローマ時代の遺物が次々と発見されている。人面の装飾を持ったヘアピンや土器といった遺物、そして浴場などの都市生活を示す遺構などである。 ボンの起源はおよそ2000年前にさかのぼり、紀元前13年、皇帝アウグストゥスが義理の息子ドルススにライン河東岸のゲルマン人征討を命じ、防衛拠点としてライン河沿岸の50ヵ所に砦を築かせたうちの一つという(カストラ・ボネンシア)。「ボン」という名前はケルト語で「山」を意味する「ボンナ」に由来するものと考えられている。この砦(あるいは兵営)は中世以来の旧市街の下にあるという。軍隊に伴われて多くの職人や商人も移住して集落が形成され、都市生活が営まれた。今回の発掘が行われているかつての政府庁舎の辺りは、古代のボンの中では最も外れに位置している。 ちなみにこの発掘では、第二次世界大戦時のドイツ軍やアメリカ軍のヘルメット、また1957年の総選挙の際のキリスト教民主同盟の選挙チラシなども発見されている。・・・・・・・(引用開始)<訃報>A・ストロエスネルさん93歳=パラグアイ元大統領 アルフレド・ストロエスネルさん93歳(南米パラグアイ元大統領)16日、亡命先のブラジルで多臓器不全のため死去。1954年、軍事クーデターで政権を掌握。有名無実の選挙で大統領に連続8回当選。反共姿勢を貫き、反対派を弾圧。89年にクーデターで打倒されるまで、約35年にわたり恐怖政治による独裁を続けた。(毎日新聞) - 8月17日12時48分更新(引用終了) まだ生きてたのか。ストロエスネルの翌年にやはり大統領の地位を追われた、チリの独裁者アウグスト・ピノチェトはまだ生きてるのか。 ストロエスネルはその苗字から想像されるとおり、バイエルン出身のドイツ移民の息子である。16歳で陸軍に入り、41歳のときクーデターで政権を掌握した。政治姿勢は反共だが経済的には統制経済の信奉者で、南米第二位の最貧国(一位はボリヴィア)に世界最大のイタイプ・ダムを建設したが(現在は中国の三峡ダムが最大)、貧富の差は埋まらず国民の不満が高まったが、彼は徹底した警察国家体制でそれに対抗した。彼の政権下で不当に粛清されたのは公式発表で400人、実際は3000人に及ぶという。その彼自身も1989年に軍人のクーデターで国を追われている。 ちなみにストロエスネル政権は1959年に日本政府と協定を結び、8000人の移民を受け入れている。またソ連からもドイツ系移民(ヴォルガ・ドイツ人)を多数受け入れた。彼らは不毛のチャコ地方に入植している。 田中宇さんによれば、資本主義経済(あるいは経済のグローバル化)がこうした南米の軍事独裁者を一掃したということだが、今度はその反動か南米に左派政権が次々と誕生している。その最たるものがヴェネズエラのチャヴェス政権だが、北朝鮮への石油輸出を表明したり、イランのアフマディネジャド大統領と歓談したり、ロシアから武器を買ったりと、徹底的な反米姿勢で「第二のカストロ」になっている。
2006年08月17日
コメント(9)
-
Frankfurt + Speyer
レバノンにいるドイツ人数千人は既に国外に脱出したが、ベイルートにいる僕の知り合いは結局脱出せずに残っているらしい。彼はアメリカ系大学の教授をしているのだが、そこのキャンパスは彼に言わせれば「レバノンで一番安全な所」だそうだ。遠くにレバノン軍の対空砲火の音は聞こえても爆弾が近くに落ちることは無いだろうとのこと(イスラエルの攻撃はベイルート南部に集中している)。むしろ下手に陸路シリアに逃げようとして誤爆でもされるほうが恐ろしいという。 彼によるとむしろ困ったのはスーパーマーケットの商品がほとんどなくなってしまったことだそうで、これはイスラエルによる封鎖と住民が買い貯めに殺到したことによるそうだ。・・・・・・・・・・ 僕のほうはこの週末外出した。 土曜はフランクフルトの考古学博物館を見学。今はオーストリア・イタリア国境のアルプス山中の氷の中から発見された「アイスマン」に関する小さな特別展をやっている。 氷の中でミイラ化した5000年前の男(愛称オェッツィ)の遺体は現在北イタリアのボルツァノ(ドイツ語名ボーツェン)にある南チロル考古学博物館にあって門外不出になっているので、この展覧会では彼の遺体の傍で見つかった持ち物(袋や衣類)や、新たな研究の成果が紹介されている。ちなみに僕はボルツァノの考古学博物館に少なくとも二度行ったので、冷気が保たれたカプセル中で保存されているオェッツィにじかに対面したことがある。 この「アイスマン」は5000年前の人体が腐らずに残っていて、彼の既往症や刺青の習慣(リウマチをなおすためのまじないだった)などが明らかになった他、植物や皮で出来た道具や衣類、そして銅製の斧(銅器が想像以上に早く広汎に普及していたことが分かった)といった個人装備も揃っていた、センセーショナルな発見だった。 しかし謎に包まれていたのは、なぜアルプス山中の、万年雪に覆われた標高3000メートルもある現在でも登山家しか近寄らないような場所(アイスマンを発見したのも登山中の人で、発見当初は遭難した登山者の遺体と思われていた)で彼が死んでいたのか、その背景である。順当にアルプスを越える旅行中に遭難したのだろうという説も出たし、あるいは夏季にヤギの放牧中に転落し遭難した羊飼いだろうという推測もあった。 しかし2001年に新たな状況証拠がレントゲン撮影により見つかった。この男性は左肩を後ろから矢で射られていたのである。傷口には治癒痕が無く石の鏃は体内に残っていた。しかも手にも切り傷があった。彼は間違いなく誰かと争っており、逃げるところを後ろから射られて死亡したことが明らかになった。こんな山中でなぜそういう事態になったのか、賊に襲われたのか、個人的恨みによる凶行だったのか(仲間割れとか)、それとも何か別の理由があるのか、「アイスマン」をめぐる謎はますます深まっている。 ちなみにアイスマンを最初に研究したコンラート・シュピンドラー教授(インスブルック大学)が昨年病気で急死したのだが、地元では「アイスマンの呪い」と噂したという。もっともアイスマンが発見されたのは1991年だから、呪いにしては効果が出てくるのがえらく遅いのだが。・・・・・・・・・ 日曜はシュパイヤーに行く。フランクフルトから電車で二時間足らずの距離である。11世紀に建設されたここの大聖堂は世界文化遺産に指定されているので、観光客もまずまず多い。人口5万と小さいが歴史のある綺麗な町である。 シュパイヤーに行ったのは、ここの歴史博物館で行われている特別展を見るためだった。同時に三つの特別展が行われており、「ペルシアの世界帝国」「蛮族の遺宝」「ハインリッヒ4世」の三つである。予想以上に博物館が大きく、その展示を見ているだけで疲れてしまい、大聖堂以外は全く観光できなかった。 「ペルシア世界帝国」は紀元前にギリシャからパキスタンまでを支配し、アレクサンドロス大王に滅ぼされた(簒奪された)大帝国アケメネス朝ペルシアに関するもの。ドイツ各地の博物館や大英博物館に所蔵されているペルシア帝国時代の宝物が並べられている。僕にはどこかで見たことあるものばかりで特に新味は無かったのだが、貴族の衣装や玉座、そして戦車の復元などは印象的だった(ものすごく金のかかっている展覧会だ)。 そして古典ギリシャ芸術(壷絵)の題材となったペルシア人像の変遷も特集されている。ギリシャ人にとって、大軍で攻めてきてアテネを焼き払ったペルシア人は当初は恐るべき敵で、画題もペルシアに対するギリシャの勝利に徹していたが(紀元前6世紀初頭)、一世代くらい経ちペルシア人との交流が進むと人間味のある滑稽なペルシア人像が描かれるようになる。ギリシャ人の自己優越意識が背景にあることは一貫しているものの、異人(バルバロイ)に対する視線の変化はいつの時代も変わらないものらしい。 「蛮族の遺宝」は、カールスルーエ近くのノイポッツでライン河底の浚渫中に発見されたローマ時代の宝物(銀器など)を中心に、古代末期・3世紀頃のローマ帝国の金工技術や交通(船や馬車)に関する展示になっている。 3世紀というのは世界的にみても激動の時代である。ローマ帝国では軍人皇帝を輩出して内政が動揺し(キリスト教が爆発的に広まった時代でもある)、ゲルマン人による侵入や東方の新興国ササン朝ペルシア(イラン)による攻勢が激しく、ガリア(現在のフランス)やシリアのパルミラ王国はローマ帝国から自立状態になり、内憂外患の帝国は分裂の危機に瀕した。中国では黄巾の乱の混乱のち三国(魏呉蜀)鼎立時代になり、やがて華北に北方民族の跋扈する五胡十六国時代へと繋がっていく。日本でも魏志倭人伝に「倭国乱」と伝わる、卑弥呼の擁立にも関わらず戦乱が続いたのち、やがて全国に前方後円墳体制とも呼ばれる斉一的な祭祀(=政治)システムが広まっていく時代にあたる。 それはともかく、ゲルマン人はライン河を越えて度々ローマ帝国に侵入した。彼らは略奪や破壊のちライン河東岸に引き上げて行ったらしいのだが、このノイポッツ遺宝は、そのような略奪行をしたゲルマン人がその「獲物」を何らかの理由で川底に忘れてしまったもののようで、金銀鉄など金属の重量は700kgにも上り、この時代の一括遺宝としては欧州最大の規模という。おそらく積んでいた渡し舟が沈没したものらしい。遺宝はローマ式の精巧な細工が施された銀器(皿)などだが、ゲルマン人たちは美しい細工には目もくれずに、単なる銀の塊としてそれを断ち割り、山分けしようとしたことも窺える。 ローマ帝国はこの外患に対し、国境最前線の長城(リーメス)を放棄してライン河の線まで後退し、代わりにライン河水軍と騎兵による機動軍を強化し、ゲルマン人たちを取り込み懐柔した。また帝国東部で軍事力を背景とした強力な中央独裁体制が樹立されるに及び、さらに一世紀余の命脈を保つことになる。 一方こうした河に沈んだ黄金というとワーグナーの歌劇で有名な「ラインの黄金」を連想させるが、実際にゲルマン人の間に伝わった伝説の背景となっているのだろう。 「ハインリッヒ4世」は、ちょうど900年前の1106年8月6日に56歳で死去し、ここシュパイヤーの大聖堂に葬られたドイツ(神聖ローマ帝国)皇帝ハインリッヒ4世に関するものである。この博物館に来る前に大聖堂に寄ってハインリッヒの墓も見物したが、いたく感激したものだった。この大聖堂を建設したコンラート2世はハインリッヒの祖父にあたる。 ハインリッヒは神聖ローマ皇帝(≒ドイツ国王)であるザリアー家に生まれ、父の夭折により6歳で国王となり、幼少のため母アグネスが摂政となったが、帝国の実権をめぐる争いに巻き込まれて誘拐されたりした。成人すると弱体化した皇帝権力の再興に勤める。彼の権力闘争の最たるものが教皇との叙任権(司教などの任免権)闘争で、教皇に破門され窮した彼は、1077年1月にカノッサ城に滞在する教皇に許しを請うべく三日三晩雪の中城門の前に立ち尽くした(「カノッサの屈辱」)。実はこれで終わりではなく、教皇が独自にドイツ王(対立国王)を立てたりハインリッヒが教皇を幽閉して傀儡教皇を立てたりと、俗界の最高権力をめぐる闘争はその後も続いている。ハインリッヒ自身も晩年息子に幽閉されて退位させら、失意のうちに没している。遺言により祖父や父の眠るシュパイヤーの大聖堂に葬られた。 1900年、シュパイヤー大聖堂の地下に眠るハインリッヒらの墓所の蓋が開かれ、王冠などの副葬品は取り出され博物館に収められたが、遺骨は再び石棺に納められて今も大聖堂の地下に眠っている。 この展覧会の目玉は彼の墓所から出土した王冠や衣類、そして開棺時に撮影された彼の頭蓋骨から3D復元された彼の復元画像である。展示品も少なく考古学というより美術品の展覧会だが、著名な人物に関するものだけに面白かった。最新技術で復元された彼の画像は、こう言っちゃなんだがドイツによくいる公園に集まって昼間からビールを飲んでいるアル中おやじに似ていた。ロン毛でひげ面、赤ら顔のせいだろうか(目は大きい)。古い挿絵に出てくる彼の顔(「へのへのもへじ」のようなすっきり顔)とは印象が違う。 この博物館は考古学に関する常設展示も充実している(特にノヴィオマグスと呼ばれたシュパイヤーに駐屯地があったローマ時代がすごい。その他ワインや近代絵画の展示もあり)。全部見たらぐったり疲れた。
2006年07月23日
コメント(4)
-
Hannover + Hildesheim
なんだかイスラエルが激しい攻撃をレバノンに加えているので(イラクの現状と違いまさしく「戦争」である)、ドイツでの北朝鮮ミサイル関連報道がほとんどなくなってしまった。先日は珍しく、日本での先制攻撃容認論議を憂慮する社説が「フランクフルター・ルントシャウ」(リベラル紙)に出ていたというのに。レバノンに関しては安保理のイスラエル非難決議に対してアメリカが拒否権発動、と何かの裏返しのような事態が起きている。 それにしても財政の厳しいイスラエルが、おそらく1982年以来の大規模な陸海空からのレバノン(あるいはそこに根拠地を持つヒズボラ)封鎖作戦に出たのは、よほど腹に据えかねたのだろうか(1996年もそうだったが、果たして実効性はあるのだろうか)。せっかく昨年シリア軍が撤退したと思ったら今度はイスラエルというのは、レバノンにとっては災難というほか無い(ヒズボラに居座られる弱体政府だから、弱り目に祟り目である)。 ベイルートには知り合いがいるので心配である(攻撃目標は空港や、かつての内戦によってほとんど廃墟に近いベイルート南部の旧市街だが)。レバノンにはおよそ1000人のドイツ人が滞在しているが、レバノン系ドイツ人の家族が攻撃の犠牲になったという報道もある。ドイツ政府はイスラエルの行動に理解を示しつつもやりすぎと批判気味の態度で、ドイツ国内のユダヤ人協会は外相の「イスラエルはやりすぎ」発言を批判している。............. この日はレンタカーを借りてK君の運転でハノーファーに行く。複数で借りれば、電車で行くより安くなる。ここからは車までおよそ3時間の距離である。 ハノーファーにはニーダーザクセンの州立博物館があるが、昨年から僕らの知り合いがそこに嘱託で勤めているので行くことにした。ちょうど現在ハルシュタット(オーストリア)での調査に関する特別展をやっているので(今月一杯)、それを見に行くつもりでもあった。 予定より少し遅れて1時前にハノーファーに着き、早速旧市街の中心にある彼女の職場を訪ねる。一緒に昼食を食べたあと、少し外れにある本館のほうに行く。ハノーファーは第二次世界大戦の空襲で市街の85%が破壊されたので、歴史的建造物は一部が復元されているとはいえ、ほとんどない。旧市街近くには天井が落ちた教会の残骸が残されていて、姉妹都市である広島市から送られた鐘がぶら下げてあった。僕らが見学した州立博物館本館も、かつてはドーム状の屋根だったが、戦災で失われて今はない。 この博物館には以前来た事があるが、置いてあるものはいいのだが、なんとなく気の入っていない展示であると感じる。その後多少改められたようだが今も散漫な印象を受ける。しかし知り合いの案内で手際よく見ることが出来た。 ニーダーザクセン州は北は北海・バルト海から南は中央山地までのかなり広い地域をカヴァーしているので、遺跡や遺物もさまざまな性格のものがあるのだが、昔見つかった重要な遺物(ローマ時代の銀器など)はかつての帝都ベルリンにあり、最近見つかった重要な遺物は最寄の博物館に収められたりで、ここには意外とない。 地元の考古学に関する展示の他、文化人類学(インディアンやアフリカ、ポリネシアの民具など。ドイツは植民地をもっていたのでこういうコレクションがあちこちにある)、自然科学(動物の剥製や標本など)、そして絵画まで置いてある(有名なところだとホルバイン、ファン・ディック、ルーベンスなどか)。色々あってとても大きく、見ごたえのある博物館だが、どの部分もなんとなく物足りない感じがする。 そしてハルシュタットに関する特別展も案外小さいもので拍子抜けしてしまった。ハルシュタットはオーストリアの湖岸にあり、すぐ近くでの岩塩採掘を生業としていた人々の墓地群で知られる重要な遺跡で(1846年発見、およそ5000基の墓)、中央ヨーロッパにおける紀元前一千年紀前半の時代名称になっているほどである。岩塩坑からは数千年前の木材(たいまつの燃えかすや工具)や皮革(サンダルや岩塩を入れるための袋など)が腐らずに当時のまま発見されている。 墓地は豪華な副葬品を伴っているので貴族社会のように思われていたが、最近の墓地からの遺骨研究では、そのような豪華な副葬品を持っている人々も実際に岩塩採掘に従事していたことが明らかになったという。つまり一部の支配者が運営する男ばかりの鉱山町みたいな集落ではなく、女子供まで等しく岩塩採掘に従事し、共同体の全員が「白い黄金」岩塩で得られる富を享受していたらしい。 日本だと塩は海で採るイメージが強いが、大陸では専ら岩塩で、実際ドイツで消費されている塩は今もほとんど岩塩のようだ。 州立博物館の見学を終えて帰路につく。せっかく車があるのだからと、ハノーファーの南にあるヒルデスハイムという町に立ち寄る。ここにはかなり立派なエジプトのコレクションをもつ博物館があるのだが、もう閉館時間なのであきらめて、世界文化遺産に指定されている聖ミヒャエル教会を見に行く。 世界文化遺産だからどんなにすごいのだろうか、と思っていったのだが、市街に埋没している普通の教会といったたたずまいである。ただ違うのはかなり大きいことと、ロマネスク様式の異様な構造というところだろうか。 11世紀の創建にしてはえらく新しい印象を受けたがそれもそのはずで、ここも第二次世界大戦で手ひどい被害を受けて再建されているのである。内部には13世紀の素晴らしい天井画とかもあるらしいのだが、それを見ることもかなわず、いささか拍子抜けして家路についた。
2006年07月14日
コメント(13)
-
Bochum, Herne
この日は所要でボッフムBochumとヘルネHerneに日帰りで行く。マールブルクからは電車の接続が悪いので(急行しかない)、かなりの強行軍になる。 ボッフムのほうはこの日記にも度々登場したが、ドイツ鉱業博物館(鉱業に関する世界最大の専門博物館)で行われている特別展を見に行くためだった。今はトルコのウルブルン(岬)沖の地中海海底で発見された、紀元前1300年頃の交易船についての特別展をやっている(来週まで)。 副題は「3000年前の世界交易」で、古代から人類は交易を通して広く交流していたのだと実感する。こういうとロマンに溢れているように聞こえるが、帝国主義や現代のグローバリゼーションも、地球全体に広がったその延長上といえなくもない。価値観の画一化や現地経済の従属化など、こっちはどちらかというとマイナスイメージだが。・・・・・・・ そしてヘルネのほうは、新しいコンセプトで展示が行われている考古学博物館(ウェストファリア州立考古学博物館)が出来たとつい先日聞いたので、ボッフムの隣町(地下鉄で結ばれている)ということで行った。なるほど外観からして新しそうな博物館で(2003年開館)、現在は気候変動と人類の生活についての特別展が行われている。 この辺りは25万年前の石器や、ネアンデルタール人の化石人骨が発見された地域なので、それに関する展示も多い。常設展は遺跡の発掘現場をイメージした内装で(そのためか展示室も地下にある)、また展示物の多くを従来のようなガラスケースではなくて木箱に入れたりして臨場感?を出している。説明用の音声ガイドのボタンが、辺りに立ち並ぶ測量用のポールに仕込んであったり、トランシット(測量器具)のレンズを覗き込むと遺跡の風景が見えたりと(こちらは多くが既に壊れていた)、なかなか凝っている。順路に沿って進むと、25万年前から第二次世界大戦の廃墟(1945年)までの歴史を体験できるようになっている。 従来のありがたい「お宝」を並べたような展示(ドイツには多い)ではなくて、その物が使われた時代や使った人間に目が行くようなコンセプトのようだ。そのためか展示物一つ一つはちょっと見にくかったり観察がおざなりになりそうな感じもしたのだが(まあ専門家でもない限り展示物をそんなに観察することもないでしょうが)、一般向けにはより親しみやすいだろう。 そして何よりこの常設展示は従来の「並べただけ」の展示と違い、とても饒舌である。あちこちに有名な哲学者や作家が歴史について語った言葉が掲げてあったり、死、プロパガンダ、戦争、気候、時間、性など、人類が時空を超えて普遍的に共有するテーマに関する小部屋があったりと(その中にぽつんと一つだけ象徴的な展示物があったりする)、極めてメッセージ性、時に政治性の強いものとなっている。これは「お宝」を並べて「拝ませる」といった従来のハコ物としての博物館の姿勢を反省したものだろう。 また考古学の方法や協同諸学(人類学、動物学、植物学、年代測定、冶金学など)の研究法についてなるべく分かりやすく紹介した展示室も最近出来たらしい。考古学が「大発見」「貴重な発見」(あるいは「我々の偉大な祖先」)を宣伝する時代はもう過去のもので、その意義や社会還元を展示の前面に出すこうした展示がこれから増えていくのだろう。ドイツではまだまだ多いとはいえないが。・・・・・・ 夕方マールブルクに帰ってフランスとポルトガルの試合を飲み屋で観戦。雷を伴ったにわか雨のせいか、ものすごい湿気で不快なことこの上ない。 ドイツが出ていないので盛り上がりはそれほどでもない。決勝はフランスとイタリア、三位決定戦はドイツとポルトガルということになった。
2006年07月05日
コメント(2)
-
毎年が節目 2006年版
昨年2005年は第二次世界大戦終結60周年という「節目の年」ということで、それに因んだ行事がドイツでも多く行われた。日本の事はあまり聞かなかったが、ロシアや中国でもそれぞれ盛大に記念式典が行われた。 その他にも日本では日露戦争(日本海海戦)100年、イギリスではトラファルガー海戦200年、フランスではアウステルリッツ会戦200年という具合にそれぞれの「節目」を祝ったり偲んだりしている。トルコではガリポリの戦い(第一次世界大戦の中でトルコがほとんど唯一勝った戦い)90周年ということでそれに因んだ映画も作られたと聞く(見ていないのだが「アタチュルク万歳」の映画だったりしないのだろうか?)。 しかし、とひねくれ者の僕は思う。こういう節目なんて作ろうと思えばいくらでも作れる。作る側にはそれぞれの立場や思惑が働くわけだが、それなら今年はどういう節目がありうるか調べてみた。原典は手許にある「Chronologie der Weltgeschichte」(John. B. Teeple編, Dorling Kindersley刊)である。(10周年=1996年)・ターリバンがカーブルを占領しイスラム原理主義国家の樹立を宣言。・台湾最初の総統直接選挙。中国はミサイル演習でこれを脅迫し、アメリカが台湾沖に艦隊を派遣・イスラエルでリクード党のベンヤミン・ネタニヤフが首相に選出される。パレスチナとのオスロ合意が危機に・日本で最初のDVDが発売される・F.W.デ・クラークが南アフリカ副大統領を辞任・チェチェンからロシア軍が撤退し事実上の独立状態に・ボリス・イェルツィンが共産党に辛勝しロシア大統領に再選される。・フランスが再開していた南太平洋での核実験を停止・アメリカがキューバへの制裁を一部緩和・ホスト・コンピュータが1000万台に増加(25周年=1981年)・イランが在テヘラン・アメリカ大使館の人質52人を解放・インド軍治安部隊とシーク教徒の衝突が激化・イスラエルがレバノンに侵攻(注・当時の国防相はシャロン現首相)。PLOは本部をチュニスに移転・サウジアラビアなど六ヶ国が湾岸協力機構を設立・エジプトのサダト大統領が暗殺され、ムバラク現大統領が就任・「連帯」によるデモ激化を受け、ポーランドで戒厳令・イギリスのサッチャー政権が国営企業の民営化に着手・アルバニアの独裁者エンヴェル・ホッジャが自己の終身政権維持のため首相らを更迭・粛清する・ギリシャがECに加盟・ロナルド・レーガンがアメリカ大統領に就任・最初のスペースシャトル「コロンビア」が打ち上げられる・IBMがマイクロソフト社ソフトウェアによる最初のコンピュータを発売・カナダで第一回先進国首脳会議・アメリカがエル・サルヴァドルへの軍事支援を強化(50周年=1956年)・日本が国連に加盟・パキスタンがイスラム共和国の建国を宣言し英国連邦に加入・スエズ動乱:エジプトがスエズ運河を国有化したのに対抗しイギリス・フランス・イスラエルがエジプトに侵攻。国連決議により撤退・フランスがモロッコとチュニジアの独立を認める・黄金海岸と英領トーゴが統合・スーダンがイギリス・エジプト共同統治から独立・ハンガリー動乱(ソ連の軍事介入)・フルシチョフによるスターリン批判・イギリス領キプロスで、マカリオス大司教率いる反英独立闘争激化・アメリカ最高裁がバス利用における人種差別・分離を違法との判決を下す・アメリカが大平洋での核実験を再開・IBM社が金属盤へのデータ保存法を開発(100周年=1906年)・テヘランで政府の弾圧に抗して宗教反乱・英領インドでムスリム同盟が設立される(のちのパキスタンの起源)・中国(清朝)がイギリスのチベット権益を認める・日本で戦艦「薩摩」が進水・ハウザ(イスラム教徒)の支配に対するティヴの反乱を鎮圧するため、イギリス軍がナイジェリアに到着・人頭税に反対するズールー人にイギリス治安部隊が発砲、60人が死亡・トランスヴァアルとオレンジ自由国が自治国となる。白人のみが選挙権を得る・英仏伊がエチオピアの独立維持で合意・イギリスがオスマン・トルコにシナイ半島を割譲させる・セヴァストポリでのロシア軍ストライキで士官が殺害される・ドゥーマ(ロシア議会)が解散され戒厳令が布かれる・イギリスで巨大戦艦「ドレッドノート」が進水・アメリカ軍がキューバに介入・グアテマラとホンジュラス・エルサルヴァドルが和平条約・サンフランシスコ大地震・台風によりタヒチで1万人が死亡(200周年=1806年)・ワッハーブ派がメッカを占拠・ニジェール川でスコットランド人探検家パークが遭難・イギリスがケープ植民地をオランダから奪う・イギリスが南アフリカに海軍根拠地サイモンズタウンを建設・10月14日:ナポレオンがプロイセンをイェナの戦いで破る・神聖ローマ皇帝フランツ一世が退位:神聖ローマ帝国の滅亡とライン同盟の成立・ナポレオンの兄弟ジョセフとルイがナポリ王・オランダ王に即位・フランシス・ボーフォールが風速単位を定める(500周年=1506年)・ポルトガル人アルフォンソ・デ・アルブケルケがインド洋のソコトラ島(イエメン)を占拠・朝鮮の残虐な支配者ヨンサングンが廃位され、中宗が即位(~1544年)(注・中宗は「チャングムの誓い」に出てくる朝鮮王)・オランダ公フィリップ美公が死去(注:「狂女フアナ」の夫。スペイン女王イザべラの娘婿でハプスブルク家の嫡子)・ポルトガル人探検家トリスタン・デ・クンハが南大西洋で島を発見・レオナルド・ダ・ヴィンチが「モナ・リザ」を描く(1000周年=1006年) 同書に記述無し(2000周年=6年)・ユダヤ王国(ヘロデ朝)がローマ帝国の支配下に入る・ローマ帝国のティべリウス(のち第二代皇帝)によるゲルマニア(現ドイツ)遠征が、パンノニア(現ハンガリー)における反乱により中断 なんつうか結構マニアックな記述もある。この本はときどきこういう傾向があったりする。戦艦「薩摩」の進水とか中宗の即位というのはこの本の著者のイギリス人(故人)にとってそんなに目を引く出来事だったのだろうか。 その他ここでは書き出さなかったが、今年が「節目」として考えられるのは、1206年のテムジンのカン即位(チンギス・カン=モンゴル帝国の建国)800周年、1856年のクリミア戦争終結、シン・フェイン党設立、べッセマー製鋼法発明、ネアンデルタール人発見150周年、1931年の満州事変75周年、同年のエンパイアステートビル竣工くらいだろうか。 個人だとモーツアルト生誕250年とかいうのもあるが、そういうのを挙げたらキリがなさそうだ。今年の大河ドラマ山内一豊の没年は1605年で死後400年から一年ずれた、残念! 新しいところで5周年というなら、シャロン内閣の成立、ブッシュ大統領就任、アメリカ同時多発テロ、アフガニスタンでの戦争、アルゼンチンの財政破綻など、記憶に新しいこと(多くは忌々しいことだが)がたくさんある。
2006年01月26日
コメント(7)
-
アメリカの歴史(11) 終わりなき戦い?
一昨年の末からぼつぼつ書いてきたアメリカの歴史もやっと終わり。今日は80年代から現代まで。 もっと文化的なこととかを詰め込みたかったが、それは次の機会に。・・・・・・ 1980年の大統領選挙では、共和党候補のロナルド・レーガンが選挙人の9割を得る地滑り的大勝で現職のカーターを破って当選し、翌年第40代大統領に就任した。映画俳優からカリフォルニア州知事という経歴を持ち、また就任時69歳の高齢という歴代大統領でも異例尽くめのレーガンには、ヴェトナム戦争やイラン革命で打ちのめされたアメリカの国際的威信の回復と、年々増大する貿易と財政の赤字是正が期待された。 レーガンの圧勝はまた、中絶是認や離婚率の増大、同性愛やポルノ解禁などといった伝統的モラルの崩壊に対する保守層の反動という一面もあった。レーガンがカリフォルニアから出馬したことが示すように、アメリカ政治の重心は着実にリベラル層の多い北東部から「サンベルト」と呼ばれる南部や西部に移っており、それは西部の人口が1990年にニューイングランド諸州を初めて上回り、また80年代の人口増加の半分以上がカリフォルニア・テキサス・フロリダ3州に集中したことにも端的に現われている。 内政でレーガンは「レーガノミックス」と呼ばれる経済政策を行い、景気回復のため所得税を25%軽減した。しかしこれは増大する破滅的な財政赤字を助長し、ついには60年代以来続いた社会福祉制度からの400億ドル削減に追いこまれた。環境保護政策などの経済統制はほとんど放棄され市場に任されたが、経済は好転せず失業率は増大、日本からの電機製品や自動車の輸入増大で1984年には貿易赤字がついに1000億ドルを突破した。レーガノミックスの恩恵に与れたのは人口のわずか2%、貧富の格差が増大した。レーガノミックスの評価は今も定まらない。 1989年まで続くレーガン政権の期間、アメリカ国民に肥満者が増え、ジョギングや禁煙、自然食などの健康志向が大きくなる一方で、麻薬やエイズの蔓延が大きな社会問題になっていく。また一瞬にして大金を稼ぎ出す株のディーラーや経営者がもてはやされ(「ゲット・リッチ・クイック」)、婦人の6割が就業し、現代的な自己実現の姿とされたが、一方で離婚率が増大し家庭崩壊も問題になった。 かつて差別されていた黒人は今や4割がホワイトカラーに属し、45%が自分の家を持つようになったものの、三分の一は依然として貧困層に属して希望も無いまま麻薬や重犯罪に手を染めていった。またこの頃から、黒人に加えて中南米からのヒスパニック系移民が急増した(80年代だけで350万人)。こうした全くの別世界が国内で並存する中、南部や西部ではキリスト教原理主義セクトの活動も無視できないものになりつつあった。 レーガンはソヴィエト連邦を「悪の帝国」と呼び、通常兵力で勝るソ連に対抗してSDI(「スターウォーズ」)計画を発表するなど(1983年)、国防費を倍増し対決姿勢を明確にする。このアメリカが仕掛けた新たな軍拡競争の結果、既に限界に来ていたソ連の社会主義経済は最後の一撃を受けて破綻する。1983年には「アメリカの裏庭」カリブ海で、共産主義者がクーデターを起こしたグレナダに侵攻してこれを阻止している。また内戦中のレバノンに派兵(1982年)、また1980年にイラクによる侵攻で始まったイラン・イラク戦争では、イラク寄りの姿勢をとった。ソ連占領下にあるアフガニスタンでは、パキスタンを通じゲリラへの支援も行った。 アメリカを「世界の警察官」の地位に戻そうとする彼の政策は、内政上の失点にもかかわらずレーガン政権に対して国民の大きな支持を集めることになった。1984年の大統領選挙ではレーガンは59%の得票で圧勝し、73歳という史上最高齢で再選した。なおこの選挙では黒人のジェシー・ジャクソンが民主党の大統領候補指名選挙で善戦して注目を集めた。 レーガン政権の二期目は、中米ニカラグアやエルサルバドルでの内戦に絡むイランへの不正武器輸出疑惑(イラン・コントラ疑惑)で揺れた。しかしテロ活動への支援が疑われたリビアへの空爆(1986年)といった強硬姿勢、そして1987年にソ連の指導者として登場したミハイル・ゴルバチョフが東西冷戦での敗北を事実上認めて核軍縮を始めたことは、レーガン政権への国民の支持に繋がった。アメリカもヨーロッパから中距離ミサイルを撤収して世界平和への期待が高まる中の1989年始めにレーガンは退任するが(2004年没)、アメリカの威信を取り戻した偉大な大統領として評価されている。 1988年の大統領選挙で当選したのは、レーガン政権の副大統領だったジョージ・ブッシュである。彼の任期初年である1989年は世界各地で大きな変動が起きた年となった。東欧諸国では共産党政権がドミノ倒しのように崩壊しソ連の支配を脱するが、その象徴的なものは11月9日、ドイツでの「ベルリンの壁」崩壊だった(翌年東西ドイツは統一)。前年イラクと停戦したイランではイスラム革命の指導者ホメイニ師が死去、中国では学生を中心とした民主化運動が起きるが武力鎮圧された(天安門事件)。この年12月、ブッシュはマルタ島でゴルバチョフと会談し、事実上の冷戦終結が宣言された。既にアフガニスタンからも撤兵し、東欧諸国も離反して超大国としての威信を失ったソ連は1991年には崩壊に至り、アメリカとの協調に転じざるを得なくなる。アメリカは「唯一の超大国」となったのである。 激変する世界秩序の中、アメリカは再び平和・民主主義・自由貿易の守護者としての意識と自信をもっていく。その手始めは1989年末のパナマ侵攻で、同国の独裁者マヌエル・ノリエガ将軍を麻薬密売の罪で逮捕・連行し自国で裁いた。そしてさらに大規模になったのが、翌年8月のイラクによるクウェート侵攻・併合に始まる湾岸危機である。これは二極構造の下で一定の「平和」状態にしていた冷戦が終わった世界での、新たな複雑な紛争の火種を象徴するものとなった。アメリカは国連を利用しつつイラク包囲網の主力となって産油国サウジアラビアに大軍を派兵、翌年1月の空爆に始まる圧倒的勝利でクウェートを解放し、自らもヴェトナム戦争のトラウマから解放された。 こうした外交上の成果の一方で、ブッシュ政権はレーガノミックスの残した財政赤字や内政問題に有効な手が打てず、国民の湾岸戦争勝利の興奮もすぐに冷め、1992年の大統領選挙では大富豪ロス・ペローという第三の独立候補の出現(得票19%)もあって、わずか43%の得票に過ぎなかった民主党のビル(ウィリアム)・クリントン候補(アーカンソー州知事)に苦杯をなめた。 第42代クリントン大統領の政権運営は、議会での共和党優勢という中厳しいものとなり、またクリントン自らのスキャンダル(セクハラ訴訟、知事時代の不正、モニカ・ルインスキー事件)もあって議会に弾劾されるなど、度々窮地に立たされた。しかしアメリカが世界の最先端に立つIT産業(インターネットや携帯電話などの世界的普及)を中心とした折からの景気回復もあって、福祉制度改革による緊縮財政を行ったクリントン政権は、最大の課題である財政建て直しに一定の成功を収めた。メキシコやカナダと自由貿易協定を締結し、またGATTをWTO(世界貿易機構)に改編して経済のグローバリゼーションへの第一歩を踏み出し、80年代の好況から一転不景気に落ち込んだ日本やドイツなどに対しての経済的優位を決定付ける。景気回復にも後押しされて、クリントンは1996年の大統領選挙で再選を果たしている。 クリントンは就任当初、国連のブトロス・ガリ事務総長が推進する積極平和外交に協力し、イスラエルとPLOの歴史的和解(1993年)を仲介するなどしたが、同年ソマリア内戦で平和維持軍に参加していた米兵が惨殺されると慌てて撤兵した。1994年には内政が混乱するカリブ海のハイチに侵攻、翌年ボスニア内戦の停戦協定(デイトン合意)を仲介している。さらに民族紛争の続く旧ユーゴスラヴィアでは、コソヴォ紛争に際して1999年には安保理常任理事国ロシアや中国が反対する中、国連決議の無いままNATO諸国と共にセルビアに対する空爆に踏み切った。東アジアでは経済成長著しい中国に対し、天安門事件以来の制裁を解除して接近し、また核開発による瀬戸際外交を進めた北朝鮮とジュネーヴ合意を締結している(のち北朝鮮により反古にされる)。ヴェトナムとの国交回復やキューバへの制裁一部緩和の一方で、テロ支援国家としてスーダンやアフガニスタンをミサイル攻撃したり、制裁下にあるイラクを度々爆撃するなど場当たり的な外交も見られた。 クリントンは2001年に退任するが、二期8年に及んだその在任中よりもむしろ人気が上がっている。 2000年の大統領選挙には、共和党からテキサス州知事のジョージ・ウォーカー・ブッシュ候補(先々代大統領の息子)、民主党からは現職副大統領であるアルバート・ゴアが立候補したが、史上例を見ない接戦となった。両党に争点がないことも原因であるが、開票作業を巡って裁判に訴える事態になった。結局共和党候補であるブッシュの当選が認められ、翌年第43代大統領に就任した。 就任早々ブッシュ大統領は前任者の逆をいく決定を発表する。地球温暖化防止のため二酸化炭素排出削減を定めた京都議定書からの脱退、国際法廷設置協定の批准拒否、ミサイル防衛構想の発表などである。こうした一国単独主義に対する反感が各国から表明されたが、2001年9月11日にワシントンの国防省とニューヨークの世界貿易センターを標的とした同時多発テロ(死者三千人以上)が発生して状況は新たな局面に入った。 アメリカは西側同盟国と協力してこのテロの首謀者とされたイスラム原理主義者オサマ・ビン・ラディンを匿っているとされるアフガニスタンに攻撃を加え、ターリバン政権を崩壊させる。ついでブッシュ大統領は2002年の年頭教書演説でイラク・イラン・北朝鮮を「悪の枢軸」と呼んで対決を表明し、1990年以来国連の制裁下にあるイラクが大量破壊兵器を秘匿しテロ組織を支援していると主張、反対の声が多く国連決議も得られない中、2003年3月にイラクに侵攻してサダム・フセイン政権を崩壊させ、彼を逮捕した。結局疑われたイラクの大量破壊兵器保有が無かったと判明すると、ブッシュは「アフガニスタンやイラクを圧制から解放し民主主義を樹立した」として正当化した。 また「対テロ戦争」のために国土防衛省を新設すると共に、世界中に駐留する米軍を再編し機動性を高め、より武力行使が行いやすい体制の整備に努めている。ブッシュ政権は外交で民主主義と人権の拡大を目標に掲げたが、独自の大国志向をもちアメリカの一国単独主義を嫌う中国・ロシア・フランスとの関係が冷却化、そして南米の産油国ヴェネズエラや人権無視を非難されたジンバブエなどを反米化させた。内政は基本的に市場放任・自由貿易主義であり、イラクへの駐兵などによる放漫財政で財政赤字が増大している。 他国に忌み嫌われたものの国内での支持率が比較的高かったブッシュ大統領は、2004年の大統領選挙で再任され政権は二期目に入った。テロが相次ぐイラクでの米軍死者は2000人を超え、また相次ぐカリブ海でのハリケーンでの甚大な被害でアメリカの抱える社会矛盾が浮き彫りになるや、ブッシュ政権の支持率は低落しつつある。 現在、帝国としてのアメリカが一種の危機的状況にある事は否めない。しかし何もかもを呑み込んでいくその性質で、かつて何度も繰り返したような変容を遂げてそれを乗り越えていくのか(その揺れはアメリカ以外の国をも翻弄するだろうが)、それとも帝国主義の破産管財人としての役割を終え、国際舞台での影響力が低下していくのだろうか。 「次の超大国」中国やインドの台頭がいわれて久しいが、今のところその成長はあくまでアメリカを軸とするグローバリゼーションの枠組み内での話である。アメリカという単純そうで御しがたい国家の行く末は、政治・経済・環境といった全ての分野で、もはや地球上すべての人類にとって他人事ではない時代に差し掛かっている。
2006年01月25日
コメント(4)
-
米欧回覧実記(2)
先日買った岩倉使節団の視察記録である「特命全権大使 米欧回覧実記」(久米邦武編、田中彰校注、岩波文庫)をぱらぱら拾い読みしていると、僕の専門に多少関わる記述があったので拾い出してみる。 1873(明治6)年4月、使節団一行はロシアからデンマークを経てスウェーデンを訪問する。4月25日に国王オスカル2世に謁見した翌日、接待係の案内で首都ストックホルム市内を視察する。午前中に海軍のドッグや練兵を見学したのち、午後二時に「博古館」(博物館)を視察する。この博物館は王宮の川を挟んだ対岸にあり、エンタシス様式の柱を備えた三階建ての広大なものであり、けばけばしくは無いが華麗な壁画が描かれていると紹介される。 以下博物館の展示に関する記述を、ひらがな送りに直して転載。原文では一段落内だが、適宜段落を変える。「此の館は、当国の振古四千年前より用いたる物を陳列す。所謂『スカンデネビヤン』(原文ノママ)の古物なるものなり。石斧、石刀、石鋸、石鑿、石槍の類、三千品に下らず。往古草昧のとき、器械みな石を用いしときの遺物なり。 俗一変して銅器の発明あり。三千年前よりの古銅器を集む。此の時代に用いたる一種の剣あり、瑞(注・スウェーデン)、那(注・ノルウェー)、嗹(注・デンマーク)の地底よりは、往々之を掘り出す、其の形みな同じ。他国の境に入れば、此の形式の剣を掘り出すことなし。是にて此の三国の地には、久しく同種の人民、生息したることを証するものなり。 鉄器を用うることは、また是より更に後代のことなれども、銹び朽ちて今は存するものなし(以下略)」 この博物館では石器時代→青銅器時代→鉄器時代という時代変遷に従って(編年的に)展示しあったわけである。こうした利器(武器や道具)の素材による先史時代の時期区分を「三時期区分法」と呼んでいるが、こうした編年法や、この文章にも登場する型式学や分布論が発達して、近代的な考古学研究上大きな役割を果たしたのがこのスウェーデンとデンマークだった。 こうした北欧の近代的考古学研究(しかも現在進行形の時期)が日本語で紹介されたのは、この「回覧実記」が最初ではないだろうか。 考古学研究法の講義では必ず最初に出てくるこの三時期区分法を考案したのは、デンマーク人でコペンハーゲン博物館の責任者だったクリスティアン・ユルゲンセン・トムセンである。彼は雑多に並んでいた博物館の収蔵品を石器、青銅器、鉄器に分けて展示する事を思い付いたが、そこからこれを人類史上の技術進歩ととらえ、1836年の著書に書いた。この「三時期区分法」はのちにひろく受け入れられ、またさらに改良されていく(旧石器・新石器時代の区分、金石併用時代の設定など)。 実は同じ1836年に、やはり博物館に勤めるドイツ人考古学者ヨハン・フリードリッヒ・ダンネルが刊行したザルツヴェーデルにおける発掘調査報告書に同じ考え方が述べられている。のちのちデンマークとドイツの学者の間でどちらが先に考案したかで論争が起きたが(特に1864年のドイツ・デンマーク戦争の際)、発掘現場に出ていたダンネルがこの時代区分法を思い付き、同僚だったトムセンが評価したというのが真相だろうと考えられている。もっともこうした「時代の変化によって道具の素材が変わる」という思想はイランのゾロアスター教の教典や、古代ギリシアの詩人ヘシオドスの詩「仕事と日」に登場しているので、誰が最初に考えたということを詮索しても詮はなさそうだが。 さて岩倉使節団がスウェーデンを訪問した少し前の1869年、同国のウプサラ大学で博士号を取得した考古学者が居た。オスカル・モンテリウスである。彼はダーウィンの「進化論」の影響の下、北欧の考古遺物を研究して、のちに編年論・分布論・型式学など、考古学研究法の発達に大きな足跡を残した。岩倉らがストックホルムを訪問したときにこの博物館で働いて居た、となると話は面白いのだが、実際は別の場所で働いていたようだ(1888年かららしい)。 既にトムセンの三時期区分法が隣国スウェーデンにも受け入れられていたので、岩倉らが見たストックホルムの博物館の展示は三時期区分に基づいているのは上に挙げた文章を見る通りである。モンテリウスはこのうち墓などから出土する青銅器を研究し、その型式変化(組列)に基づいて北欧の青銅器時代を6つの時期に分けた。同様に新石器時代を四つの時期に区分している。彼が確立した青銅器時代の区分のほうは今も使われている。 「回覧実記」にも記されている通り、北欧三国には概ね共通する型式の青銅器が出土する(ドイツ北部にも分布)。青銅器は銅に錫を混ぜた青銅で作るが、北欧には銅は豊富に産出するが錫は産出しない。このため北欧青銅器時代の人々は錫の出る中欧(チェコ)や西欧(ブルターニュ、コーンウォール、スペイン北西部)のひとびとと交易してそれを得ていたようだ。北欧からは海岸に流れ着く宝石である琥珀やフリント(火打石=石器に使う)が輸出された。この時代、盛んに岩に壁画が彫られ、そのいくつかは世界遺産にも指定されている。その壁画からも明らかだが、のちにヴァイキングとして名を馳せるスカンディナヴィア人は、この頃から航海に習熟していたようだ。 「回覧実記」では青銅器時代の開始を紀元前1000年頃以降としているが、現在は北欧で青銅器時代が始まったのは紀元前2000年以前と考えられている。また新石器時代の開始もずっと遡って紀元前4500年頃とされている。これは放射性炭素分析など、分析法の発達によるところが大きい。なお「鉄器は錆びて出土しない」とあるが、今は多く見つかっており、鉄器時代が始まるのは紀元前600年頃で、ヨーロッパではもっとも遅い。 「回覧実記」では、北欧三国では似たような青銅器が出るので「同種の人民」が住んでいたと紹介している。こうした遺物の分布がなんらかの人間集団の分布と重なるという考え方は今も使われているが、ゲルマン人の研究で同様の立場をとったドイツの考古学者グスタフ・コッシナの説がナチス・ドイツの東方拡大の正当化に政治利用された経緯もあり、現在はより慎重になっている。 またモンテリウスは彼の確立した型式学や分布論に基づいて伝播論を唱え、すべての文明は西アジア・エジプトに発してそれが四方に伝播していったものだと唱えた。この考え方はのちに同じスウェーデンの考古学者アンダーソンに継承され、「中国の彩文土器は西アジアのそれが伝播したもの」という説が唱えられたが、現在は慎重な立場がほとんどになっている。ただモンテリウスが確立した型式学などは、今もドイツなどヨーロッパ大陸部の考古学界では強固な支持があって色褪せる事はない。 さてこの三時期区分法やモンテリウスの確立した考古学研究法だが、ヨーロッパに留学(1913~15年)してそれを学び、のちに京都大学教授となった濱田耕作によって日本にも広まった。濱田はモンテリウスの1903年の著書を日本語訳もしている(1932年「考古学研究法」)。その与えた影響は計りしれない。僕らも授業で必ずお目にかかる。 ところが日本の考古学にはこの三時期区分法はそぐわなかった。濱田の頃に認識され始めた弥生時代には青銅器も石器も存在する。そこで濱田はこの時代を「金石併用期」(石器時代から青銅器時代への過渡期)としたのだが、さらにのちになって弥生時代には鉄器も存在する事が判明した。つまり日本では石器時代のあと、青銅器と鉄器が同時に入ってきてしまったので強いていえば石器時代→鉄器時代となってしまうのである。しかも弥生の前の縄文時代は農耕を伴う明確な証拠がないのでヨーロッパ的な意味での「新石器時代」とは程遠い。日本と似たような経緯を辿った地域としてサハラ以南のアフリカやポリネシア、北米などがある。 そういうわけで、この「回覧実記」の記事が日本の考古学研究で顧みられる事はあまりないのだろう。 ちなみにこの岩倉使節団に随行してアメリカに留学した山川捨松(会津出身)は、のちに薩摩出身の軍人・大山巌(日露戦争時の満州軍総司令官)と結婚するが(大山は岩倉使節団には加わらず、砲兵研究のためスイスのジュネーヴに留学していた)、その子・大山柏は大山史前学研究所を設立した日本考古学史上の人でもある。まあこれは岩倉使節団とは関係ないか。
2006年01月12日
コメント(4)
-

米欧回覧実記
今日は本屋で「特命全権大使 米欧回覧実記」(久米邦武編、田中彰校注、岩波文庫)を買う。既にベルリンなどのプロイセン訪問の状況が記された第三巻は持っていたのだが、今日は南ドイツなどについての記述がある第四巻を買った。 これを買ったのは、直接的には僕にもなじみのあるマールブルクやカッセル、フランクフルトなどといったドイツの都市について記されているからである。特にマールブルクについて記された日本で最初の記録では無いだろうか。あとは明治維新まもない日本人のヨーロッパ観について知りたいと言う興味もあった。さらに一種の旅行記や日記としての興味もある。 簡単にこの本について説明しておく。1871(明治4)年12月、総勢46人からなる日本政府使節団が横浜港を出発した。団長は右大臣・岩倉具視、そして「維新の三傑」といわれた明治新政府の実力者のうちの二人である参議の木戸孝允と大久保利通が参加していた。のちに日本最初の首相となる伊藤博文(当時工部大輔)も参加している。政府の実力者や官僚達が自ら欧米を実地に見学し、帝国主義真只中の世界での日本の国作りに資そうとしたのである。現代の年末年始恒例の政治家・議員先生による税金を使った視察旅行とは覚悟もまるで違う。何せこの視察団が帰国したのは一年以上経った1873年に入ってからである。帰国後は大久保・木戸・伊藤ら外遊組と、西郷・江藤・板垣ら留守組との間で征韓論をめぐる政争も起きている。 一行は大平洋を渡って七ヶ月かけて日本を開国させたアメリカを視察、ついで大西洋を渡って帝国主義の列強イギリス、フランスを視察する。1873年に入ると国内統一を果たしたばかりで興隆著しいドイツ(プロイセン)を視察、ついでロシア、デンマーク、スウェーデン、イタリア、オーストリアなど、ヨーロッパ諸国を網羅的に見て帰国の途についた。その視察記録は旧佐賀藩士である久米邦武によって編修された。久米はのちに東大や早稲田大学で史学を講じ、近代的な歴史学の樹立を主張した人だが、この記録にもヨーロッパ諸国への概観的・網羅的な紹介と、文明論ともいえる考察、そしてこれからの日本の国作りをどうしていくべきかという問題意識が感じられる。 「米欧回覧実記」については岩波文庫版の校注者である田中彰氏による一連の著作などがあるのでそちらに譲る。 僕が興味があったのは、留学先であるマールブルクについての記録だった。早速見てみる。使節団一行は1873年3月末にベルリンを出発してロシア訪問に発ち、4月に北欧のデンマークとスウェーデンを視察している。ついでヨーロッパ文明淵源の地にして日本やドイツと同じく国内統一を果たしたばかりのイタリアに向かうのだが、その途上ドイツを通過している。該当する第70巻北日耳曼(ジェルマン=ドイツ)後記上を見る。5月1日にストックホルムから海路ハンブルク(旱堡)に到着、2日はハンブルク視察に当て、翌三日に鉄道でフランクフルト(フランキホルト=仏蘭克仏)に向かうのだが、その途上でマールブルクを通過している。当日の天気は晴だった。 朝6時半、ハンブルクの旅館を出発、7時15分、汽車が発車する。正午にハノーファー(ハノウヴル=哈諾威)駅に到着。ついでさらに南進して「コッチンヘン」(ゲッティンゲン)、カッセル(加塞)に至る。カッセルから「ニュースタッド」(ノイシュタット)に至り、走ること半時間、夕暮れの「『マル』堡」(マールブルク)に至った。一行がこの日の目的地であるフランクフルトに着いたのは夜の9時半、「ホテル・デ・アングリテール」に投宿した。この日の移動距離は350英里(マイル)だった。 以下マールブルクに関する記述。読みにくいので漢文調カタカナ送りの文章をやや改変する。「マールブルクは、人口八千五百余、ヘッセンカッセル国の名邑なり。駅舎すこぶる大なり。かつこの辺には庶村多く、山岳処処に突起し、烟花その麓に沸き、西に環し東に起こり、もって夕陽を開○(「門の中に盍」)し、堊壁の白き晩霞の紫なるに映ず。たちまち突兀の山あり、あるいは丘岑を削って、高屋をそばだつるあり、車中の眺め甚だ美なり。」 要するに駅舎が大きい、周りは山がちでちょうど夕暮れ時、紫の夕もやの中、旧市街の城壁が映えて車窓から眺めて美しかったということだ。カッセルからマールブルクの間には山がちなところと平野部が入れ替わり立ち代わり表れるが、カッセルから鄙びた小集落が続く中で、山上の城を囲む形で聳えるマールブルクの旧市街は印象的だっただろう。 マールブルクの駅舎はとりたてて大きいとも思えないが、それまでのノイシュタットなどの小さな駅にくらべれば大きく見えたかもしれない。ちなみに現在のマールブルク駅はホームが5つしかないが、これはターミナル駅であるフランクフルトの23(地下鉄除く)に比べてもひどく少ない。 この本ではマールブルクは「『マル』堡」と表記されている。「堡」はドイツ語で城を意味する「ブルク」を意訳したのだろうが、中途半端に意訳していてちょっと分かりにくい。ちなみにマールブルクの「マール」は国境、辺境などを意味するマルクが訛ったもののようだ。まあ外国語の表記は難しいですね。 ちなみにこの本ではドイツ人の国民性について、「其の資生周密にして渋鈍なるをもって、事業に伶俐活発を欠けども、精緻の業に堪えるは、その天良において嘉すべき所なり」としている。つまりは独創性や目先のすばしこさにはやや欠けるが、粘り強く仕事も丁寧であると言うわけである。 使節団はこうした国民性に日本のそれを重ね、やがて日本はドイツ式の富国強兵に邁進していくのだが、「勤勉で堅実、精密なドイツ人とその製品」という日本人のもつドイツのイメージは既に出来ている。久米ら視察団は当然こうした情報を自らの目耳から得るとともに、先々のヨーロッパ人から聞いてそのイメージを固めていったのだろう。 もう一つ、ドイツ人に対する評。「欧州人の性質たる、概して、財貨を私有する情欲甚ださかんに、君臣上下、互いにこの情欲を遂げんと、競争すること甚だ切なり。・・・日耳曼(ジェルマン=ドイツ)人は、其の中にも土地所有の強権に、執念深く、自己の一族を保護して、他族を阻隔するの情思、甚ださかんなる人種と称せられたり。欧州にて封建制の流行は、この人種の住する国地より煽動されて、近代の文明に従い、わずかに廃滅の勢に帰したるとも、日耳曼(ドイツ)において、なお小国分裂して、その情欲を固執しあえて失わず、人種の気習を異にする、千年を経ても化移せざるかくのごとくなるかな」 日本の幕藩体制に比せなくもないドイツの長い小邦分立状態の原因を、ドイツ人の土地所有、ひいては私有財産の保護に対する執着という性質に帰している。日本の幕藩体制は使節団が日本を出発した直前の1871年に、新政府の勅状一枚でうそのように消えてしまったが、ドイツの分裂体制はプロイセンによる戦争(七年戦争、普墺戦争、普仏戦争)や併合、革命を経た。 何か面白い記述があったらまた書き出してみる。
2006年01月04日
コメント(4)
-
アメリカの歴史(10) 揺らぐ超大国
昨年の今頃に自分の勉強のために連載を開始したアメリカの通史だが、結局あと一回を残して年を越す事になりそうだ。・・・・・・・ ケネディ暗殺によって第36代大統領に昇格した副大統領リンドン・ジョンソンは、若々しいケネディとは対照的な老練な政治家だったが、保守的な南部テキサス州出身ということもあって北東部のリベラル・インテリ層には人気が無かった。就任当初ジョンソンは前任者ケネディの政策を引き継いで、所得税引き下げや黒人公民権のための雇用機会均等法(1964年6月)などの成立に尽力した。 1964年の大統領選挙を前に、ジョンソンは「偉大な社会」をスローガンに、貧困や差別の撲滅を内政目標として掲げた。対する共和党は超保守派(公民権法反対、労働組合運動の制限、社会保障の切り捨て、ヴェトナムやキューバに対する核兵器使用を主張)のバリー・ゴールドウォーター上院議員を候補とする。ジョンソンが大差で再選を果たすが、ゴールドウォーターは予想に反して4割近い得票を得て、南部や西部での保守主義の根強さを示すこととなる。これは同じ民主主義に根差した社会ながら、社会民主主義が優勢となっていくヨーロッパとの乖離を示すものと受け取られた。アメリカ政治の中心は伝統的な北部や東部から、ラテンアメリカやアジアからの移民(全移民の8割以上)流入で人口が急増する南部や西部に移ってゆき、その反動としての保守化でもあった。これはアメリカ経済が対欧州から日本を始めとするアジア、そしてアメリカの経済支配が行われていた中南米との関係に重心を移したことと軌を一にしている。 当選したジョンソンは「偉大な社会」実現のための政策を次々に実行していく。老齢年金や社会保障制度の整備、出身国による移民制限差別法の撤廃、教育の充実、公害対策、都市住宅整備省の設置などである。都市整備省長官にはロバート・ウィーヴァーが指名されたが、彼はアメリカ史上最初の黒人の大臣となった。 しかしこうしたジョンソンによる内政上のリベラルな政策は、彼のヴェトナム介入の前に霞んでしまうこととなった。実際のところ、アメリカ政府が1966年にヴェトナム戦争に費やした費用は、上記の貧困対策費の20倍に達していた。 ヴェトナムでは南北統一を目指す社会主義国・北ヴェトナムが、親米軍事政権の支配する南ヴェトナム国内でのゲリラ活動(ヴェトコン)を支援していた。1964年8月、アメリカはトンキン湾で北ヴェトナム海軍の攻撃を受けたと主張、議会はほぼ全会一致決議で、必要な軍事的対抗措置を取る全権を大統領に付与した。のちに「北ヴェトナム軍による攻撃」はねつ造であったことが判明し、また弱腰を対立候補に攻撃されていたジョンソンがこの決議により「強い大統領」という姿勢を示す事が出来、その年末の大統領選挙に利した、と指摘されている。 ジョンソンは1965年に北ヴェトナムに対する「北爆」を開始、ヴェトナム戦争に本格的介入を始める。アメリカ軍はヴェトナムに爆弾の雨を降らせ、1968年にはヴェトナムに派遣されたアメリカ軍は55万に達した。これはもはや単にヴェトナムの内戦ではなく、共産主義の拡大(「ドミノ理論」)に対するアメリカの戦いと位置付けられた。しかしヴェトコンや北ヴェトナムは、ソ連の支援を得つつ、ジャングルに潜むゲリラ戦術によって装備で勝るアメリカ軍に対抗する。 テレビという情報媒体の普及によって、この密林での見えない敵に対する戦争は国民に克明に伝えられ、ゲリラ掃討と称してヴェトナムの村を焼き払うアメリカ軍の姿に、アメリカ国民は戦争の意味や正義に疑問を持つようになっていく。 ジョンソンの施策にも関わらず貧困や黒人に対する差別は依然として続き、以前はその九割が南部に集中していた黒人がアメリカ全土の都市部(スラム)へ移住していたこともあって、単に南部の問題では済まなかった。毎年夏になると、恒例のように大都市では人種間対立による暴動が起きた。非暴力闘争や白人との融和を掲げるキング牧師とは対照的に、マルコムXは黒人優位を説く人種主義運動である「ブラック・パワー」運動を率い、1965年に彼が暗殺されたのちには「ブラック・パンサー」団による武装闘争にまで発展する。 高等教育の充実により1960年代にアメリカの学生数は400万から800万と倍増したが、1964年にはカリフォルニア大学バークレー校でのフリー・スピーチ運動をきっかけに大学の官僚主義に対する紛争が始まり、ヴェトナム戦争拡大に伴う学生の徴兵猶予停止によって大学紛争は反戦・反人種差別運動と結びついた。1968年始めには100以上の大学で4万人以上の学生がデモに参加するまでになり、またヨーロッパや日本など全世界の大学に波及する。 ジョンソンが公約した「偉大な社会」は実現にほど遠く、また彼の始めたヴェトナム戦争の行き詰まりでその是非が問われるや、ジョンソンへの支持率も急激に低下した。1968年3月、ジョンソンは不利を悟って次期大統領選挙への不出馬を宣言、人気のあった民主党のロバート・ケネディ候補暗殺事件もあって、その年11月の大統領選挙では共和党のリチャード・ニクソン候補(元副大統領)が辛勝した。 1968年に北ヴェトナムとの交渉が始まっており、ニクソンは戦争を有利に終結することに苦慮したが、出口は見えなかった。国内では反戦運動が激化して1969年11月のワシントンにおける反戦集会には30万人が参加する。1970年4月、ヴェトコンの根拠地と目されたカンボジアにアメリカ軍が侵攻すると、いよいよ反戦運動は盛んになった。 しかしオハイオ州立ケント大学での反戦デモに州兵が出動してデモ隊に発砲、4人の学生が死亡した事件を境として、平和的な大規模反戦運動は下火になっていき、「新左翼」は少数の過激派による暴力的な地下活動、もしくは婦人解放・環境保護運動へと移っていく。また労働者階級や「サイレント・マジョリティ」は、学生を中心とする反戦運動に対して右傾化していった。 平和的運動によって戦争を終わらせることが出来ないという無力感は、ヒッピーや「フラワー・チルドレン」といった若者文化に表れた。こうした動きの背景には、1970年のポルノ禁止の完全撤廃、避妊薬の開発、堕胎禁止を憲法違反とする1973年の最高裁判決、離婚率の倍増、同性愛に対する禁忌意識の低下などに象徴される、社会通念の大きな変化があった。1969年7月21日、アメリカが人類初の月面着陸を成功させたことも、新しい時代の到来を感じさせた。 ニクソン政権では、安全保障担当補佐官であるヘンリー・キッシンジャーが外交政策を担当した。共産主義陣営では1960年代始めにスターリン批判や中国の核兵器開発をめぐってソ連と中国が対立し国境紛争まで起きていたが、中国はソ連との対抗上、1971年に朝鮮戦争以来のアメリカとの敵対関係を終結し(同時に台湾に代わり国連代表権を得る)、1972年にはニクソンが訪中する。一方1968年の「プラハの春」に象徴される共産主義の行き詰まりから、核ミサイルを大量に配備して北極圏を挟んでアメリカと睨み合っていたソ連も西側との融和に転じ、米ソ間で核軍縮協定(SALT I)が調印された。かつて反共主義者として鳴らしたニクソンはソ連をも訪問し(1972年)、現実外交を推し進める。 この緊張緩和の動きに乗ってニクソンはヴェトナム戦争の「ヴェトナム化」を進め、南ヴェトナム駐留米軍の規模を順次縮小、1972年には3万人にまで縮小した。1973年1月にはパリ和平協定が調印され、米軍はヴェトナムから完全撤退した。5万8千人の戦死者を出し、アメリカにとって史上最長の戦争だったヴェトナム戦争はここに終結した。東南アジアの小国に勝利を収められなかったアメリカは、超大国・「世界の警察官」としての威信と自信を打ち砕かれた。なおヴェトナムでは北ヴェトナム軍の侵攻により1975年に南北統一が実現する。 ニクソンの融和外交は、1973年に起きた第四次中東戦争及びアラブ諸国による対西側石油禁輸(オイル・ショック)を機に中東にも及んだ。キッシンジャーの活躍で戦争を調停し、翌年にアラブ諸国との和解が成立して石油禁輸は解除されたが、以後アメリカはイギリスに代わって中東外交を主導することになる。一方南米ではアメリカの影響力維持に意を注ぎ、チリの民主的選挙で社会主義的なサルヴァドール・アジェンデ政権が誕生すると、アウグスト・ピノチェト将軍率いる軍部のクーデター(1973年9月)を支援、アジェンデ政権を崩壊させた。 こうした外交的成果の一方、ニクソン政権の内政は安定しなかった。先鋭化する国内対立の中にあって、リベラル派からは保守的とされ、保守派からは基本的にジョンソン政権のそれを受け継いだ政策が批判された。経済的にも、日本や西ドイツなどの輸出攻勢によって貿易収支が1930年代以来の赤字に転落、1971年にはブレトン・ウッズ体制の破棄を宣言しドル為替を変動相場制に移行せざるを得なくなった。超大国アメリカの「世界の盟主」としての地位は、泥沼のヴェトナム戦争に象徴される政治的なものにとどまらず、経済的にも揺らぎ始めたのである。 1972年の大統領選挙でニクソンは60%以上の得票を得る大勝で再選を果たしたが、その選挙期間中ニクソン陣営はウォーターゲイト・ビル内にある民主党本部を盗聴していた。選挙に勝ったもののニクソン政権は二期目当初からこのウォーターゲイト疑惑に揺れていた。裁判所がこの事件へのニクソンの関与を認め、また「ワシントン・ポスト」紙のボブ・ウッドワード記者らが情報提供者の協力で事件の詳細を報じるにつれ、ニクソンの立場は苦しくなった。共和党内でもニクソンを見放す動きが出て、1974年8月9日、ニクソンは史上初めて任期半ばにして大統領職を辞し、ヘリコプターでホワイトハウスを去った。高潔たるべき大統領の疑惑と辞任という異常事態は、アメリカの価値観の崩壊と、そしてメディアという「第四の権力」の力を見せつけることとなった。 ニクソン辞任後、副大統領のジェラルド・フォードが昇格し第38代大統領に就任したが、失業問題や財政赤字問題に有効な対処も出来なかった彼はソ連との核軍縮協定以外さしたる成果もあげることなく、1976年の大統領選挙で敗れ去った。勝ったのは民主党候補でジョージア州知事、しかしほとんど無名だったジェイムズ(ジミー)・カーターだった。カーターは「ワシントンの政治風土に毒されていない、建国以来の質実なアメリカ的価値観」を売りにして辛勝した。 カーターはその特徴を外交面でも強調し、人権重視を謳った。このためカーター政権はチリやアルゼンチン、エチオピア、南アフリカでの独裁や人種差別に対して厳しく臨んだが、一方でこの姿勢は親米陣営を揺るがすこととなり、例えば独裁政権下にある韓国やフィリピン、ニカラグアでの混乱や影響力低下を招くことになった。とりわけ痛手だったのは、1979年のイラン革命である。親米的な皇帝独裁政権は、ホメイニ師率いる民衆のイスラム革命によって打倒された。 カーター外交の成功として挙げられるのは、一部のアフリカ諸国との接近、パナマとの良好な関係の樹立(アメリカが租借するパナマ運河の返還協定)、そして最大のものとしては1979年にアメリカの仲介で実現したイスラエル・エジプト和平がある。共産圏とは前政権以来の宥和外交を継続して1978年に中国との国交正常化を達成し、またソ連とは核軍縮協定(SALT II)の調印に漕ぎ付けたが、1979年末のソ連軍によるアフガニスタン侵攻で雪融けムードは一瞬にして吹き飛んでしまった。 国内でも、1979年の第2次オイル・ショックによる1930年代以来の大不況や、日本の輸出攻勢による国内産業の不振と失業率上昇によってカーターの支持率はみるみる低下した。さらにテヘラン(イラン)でイスラム原理主義者が起こしたアメリカ大使館人質事件の武力解決にも大失敗して不人気は決定的となり、1980年の大統領選挙では共和党候補のロナルド・レーガン(カリフォルニア州知事)に大敗して一期でその地位を追われることになった。 なおカーターは退任後も平和外交に活躍し、2002年にノーベル平和賞を受賞、「史上最強の『元』大統領」と呼ばれる。
2005年12月27日
コメント(0)
全131件 (131件中 1-50件目)
-
-

- ラスベガス ロサンゼルス ニューヨ…
- デルタ航空ステータス ステータス …
- (2024-11-15 03:44:22)
-
-
-

- ☆留学中☆
- これからの米国を占う11月5日
- (2024-11-06 05:33:29)
-
-
-

- ヨーロッパ旅行
- スペイン マドリード 総集編
- (2024-11-12 19:44:06)
-