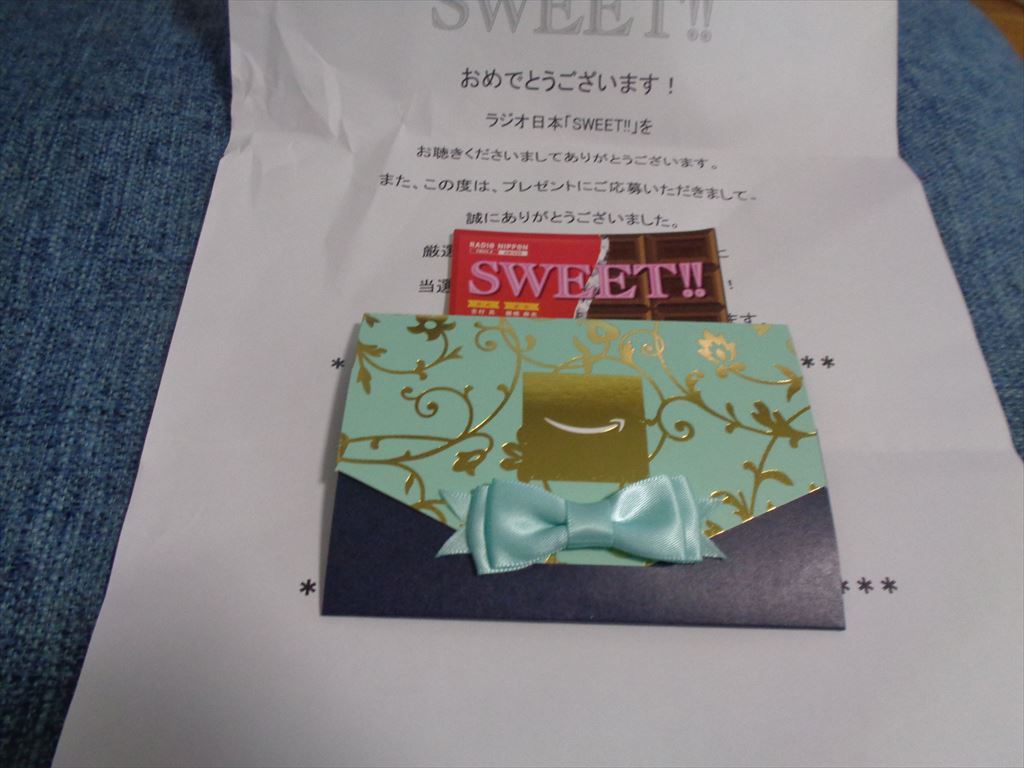全168件 (168件中 1-50件目)
-
通天閣ならぬ「チュー天閣」!キスしたカップルは入場料半額だって。
皆さん、ご無沙汰しております。幸せ大盛り中の糖尿太郎でございます。 久しぶりの日記なのに、こんな話題でごめんなさい。でも、これ、面白すぎです。バレンタインデーを前に、大阪のシンボル・通天閣で、「チュー天閣キス割」と題したキャンペーンが始まったというのです。冗談かと思いましたが、本当です。 しかもこの催しはことしで2回目!14日までの午後5時から9時に実施されているそうで、2階のチケット売り場前に設けられた特設のブースで、訪れた男女が熱い口づけを交わしているというではありませんか!!入場料は、大人2人で計1200円が600円。大学生のカップルなら計1000円が500円になるそうです。また、展望台フロアでは、大阪の夜景を眺められる2人掛けのシートも用意されているといいます。うーん。これはもう、大阪に行くしかありませんね。少なくとも、JRの辛気臭い障害者割引運賃よりは、ずっとシャレが効いています。 ということで、次の日曜はバレンタインです。いつになっても、ドキドキしますね。ま、大好きな人からチョコレートを一つだけもらえれば、私としてはそれで十分なのですけれど。 はてさて、どうなりますことやら・・?キスしたカップルは入場料半額 バレンタイン前に通天閣(共同通信)
2010.02.07
-
人生、それは優しさを分かち合う旅
それは、神様がくれたとしか思えないような偶然の出会いでした。9月のとある土曜のこと。全盲の私は、一人で慣れない駅のホームを歩いていて、迷ってしまいました。だれかに尋ねようと人を探していると、声はかわいいけれど、とても忙しそうに携帯で電話しているらしい若い女性がいました。「この人に尋ねても、きっと無視されるだろうな」、過去の経験からそう考えて、私はその女性をパスしました。ところが、その人は「ちょっと待って」と電話を中断しました。そして、「どちらに行かれますか」と尋ね、私を階段まで誘導してくれたのです。後で聞いたところ、そのまま進むとエスカレーターに突っ込んでしまうのではと、びっくりしたのだといいます。無事にホームに降りて電車を待っていると、先ほどの女性が、「さっきはごめんなさい。電話してたから、ちゃんと連れてきてあげられなくて」と、再び声をかけてくれました。途中まで一緒だということで、電車が来るまで話をしました。「目が見えなくて怖いことは何ですか?」「駅のホームは怖いですね。一度、落ちたことがあるんですよ」そうこうしているうちに電車が来て、その女性が腕を貸してくれました。その時、彼女が半端ではない荷物を持っていることに気付きました。聞けば、それは撮影機材だといいます。彼女は取材の帰りだったそうです。「私はフリーライターです。本も出しています。よかったら送りますよ」私も自分の仕事のことを話し、お互いに親近感が沸きました。そして翌日、著書『怒りの川田さん ~全盲だから見えた日本のリアル~』と、共同通信加盟の新聞各紙に昨年寄稿した「バリアフリーの裏側で」という連載記事を送りました。程なく、「すてきな本をありがとうございました」と、彼女からお礼のメールが届きました。彼女は、若いけれどものすごい努力をしていて、そしてとても優しい人でした。もしも私が健常者だったら、あんなに優しい心を持っていられたかなと、自問自答しました。目が見えない私には、辛い言葉を浴びせられたり、理不尽な差別を受けた経験が少なくありません。けれど、彼女は両手にいっぱいの荷物を持っていたのに、見ず知らずの私を助けてくれました。目になってくれました。世の中には、いい人がいっぱいいるのですよね。でも、殺伐とした社会の中で、皆の優しさが見えにくくなっているのかもしれません。見知らぬ人から優しさをもらうことの多い私ですが、私にも人に対して出来ることが沢山あるはずです。もしも誰かが持ち切れないような荷物を持っていたら、今度は私が少し持ってあげようと、出来るかどうかわからないけれど、ふとそんなことを考えました。
2009.11.15
-
神奈川県社会福祉協議会より「お詫び文」を頂きました。
皆さん、こんにちは。「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」をテーマに、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会が主催して10月23日に開かれた「障害福祉ボランティアリーダー研修」で、パネラーとして招かれた全盲の私が最寄り駅から会場までの誘導をお願いしたところ、「忙しくて手がない」と断られた問題について、11月4日付けで、神奈川県社協の林会長名の「お詫び文」を頂きました。これは、10月26日付けで私から林会長あてにお送りした手紙へのご回答で、郵送による書面のほか、電子メールに添付してワード形式の文書も頂戴しました。 なお、前回の日記でも報告しましたとおり、10月28日に、神奈川県社協の役職員の皆様にお目にかかりました。面会は10月28日午後2時40分からおよそ20分間、今回の研修会を共催したNPO法人の平塚市内の事務所で行われました。出席したのは、私を含めて計7名でした。神奈川県社協側から、常務理事、研修会を担当した県民活動推進部の部長と福祉ボランティア・シニア活動支援担当課の課長、そして直接の担当者の4名がおこしくださいました。また、共催したNPO法人の事務局長と、今回の研修会のコーディネーターで私をパネラーに推薦して頂いた大学教授も同席してくださいました。面会では、神奈川県社協の常務理事より、・川田のブログの内容はすべて事実であり、組織として全面的に謝罪すること、・林会長にも電話で経緯を伝え、謝罪するよう指示があったこと、・当たり前のことを当たり前に感じて行動するよう職員の意識改革を図ること、などをお話し頂きました。また、先に林会長あてにお送りした手紙への回答を書面で送付することも約束してくださり、それを公開することについてもご了解を頂きました。神奈川県社協の10月28日以降の極めて誠実なご対応に、心から感謝しております。 今回の出来事については、前回の日記に記しましたように、私に対する疑問やご批判を頂きました。その一方で、「同じ視覚障害者として、川田さんの行動に感謝します。だれにでも出来ることではありません」といったメッセージのほか、視覚障害児を持つご両親からは「わが子が大きくなった時に、少しでも暮らしやすい世の中になっていることを願っています。そのために、先輩の障害者として、今あなたに出来ることをしておいてください」といったご意見など、沢山の激励や応援も頂きました。今回の問題提起によって、神奈川県社会福祉協議会が、共に生きる福祉社会の推進役としての意識を確立してくださること、そして、全国の行政機関や福祉関連団体などが、催し物などでの視覚障害者の移動手段の確保について、緊張感を持って考えてくださる端緒となることと確信しています。私はこれからも、自分がおかしいと思うことについては、批判を恐れず、遠慮せず、積極的に問題提起を続けます。非力ながら、福祉のまちづくりについて考え、行動します。とかく情報発信をすると、悪意の矢面に立たされることもあります。けれど、そんなことを恐れていては、世の中は変えられません。次の世代の障害者にとって、いえ障害者だけではなくすべての人々にとって、少しでも暮らしやすい日本になるように、これからも私に出来ることを一生懸命に続けます。どうぞ、引き続きご指導・ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。 最後に、ご批判も含めて沢山のコメントやメッセージをくださった皆様、関心を寄せてくださった皆様、また、私の日記に目を留めて報道してくださったメディア各社の皆様、そして、起きたことは起きたこととして誠実に対応してくださった神奈川県社会福祉協議会の皆様に、改めて心からの感謝を申し上げます。皆様、本当にありがとうございました。 ※神奈川県社会福祉協議会のご了解を頂き、「お詫び文」全文を掲載しました。日記に画像をアップするのは初めてで、うまく出来ているか不安です。スクリーンリーダーで読んでくださっている視覚障害の方々には画像の音声化が出来ませんので、以下にテキストでも掲載します。 平成21年11月4日川田 隆一 様 社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 会長 林 英樹 本会の不適切な対応についてのお詫び 川田様におかれましては、本会が10月23日に開催いたしました『障害福祉ボランティアリーダー研修会』に際して、ご多忙の折、講師としてご協力をいただきましたことを厚く御礼申し上げます。 講師をお願い申し上げました経過の中で、研修会の当日は横浜駅でお会いし会場までご案内することを、事前にお約束したもかかわらず、直前になって『お一人で来て頂く事は可能でしょうか』とお伝えするなど、本会として著しく不適切な対応をいたしましたことを、心より反省し深くお詫び申し上げます。 本会といたしましては、この度の件を真摯に受け止め、11月2日に緊急部課長会議を開催致しました。この会議において、なぜこのようなことが起きたのかを改めて検証し、ともに生きる福祉社会づくりを推進する本会職員としての意識の徹底、風通しの良い職場づくりと職員間の協力体制の確保、管理監督者の業務の進捗状況の把握などについて、より一層の取組を図る必要があるとの結論が出され、その趣旨の徹底を図るべく、同日、職員全員を対象に研修を実施いたしました。今後も定期的に研修を実施し職員の意識改革を図るとともに、管理監督者の職員指導育成を徹底し、二度とこのようなことを起こさないための取組を進めてまいる所存でございます。 今後は、役職員一丸となって、この度の件により失いました川田様はじめ多くの県民の皆様からの信頼の回復に向け、努力してまいりますとともに、安心して生活のできる地域づくりに向け、取組を充実してまいりますので、引き続き本会事業へのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。
2009.11.05
-
神奈川県社会福祉協議会の件で応援やコメントを頂き、ありがとうございます。(その1)
皆さん、こんばんは。フリーライターの川田隆一です。「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」をテーマに、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会が主催して10月23日に開かれた「障害福祉ボランティアリーダー研修」で、パネラーとして招かれた全盲の私が最寄り駅から会場までの誘導をお願いしたところ、「忙しくて手がない」と断られた問題について、新聞に取り上げられたこともあり、インターネットの掲示板などに沢山のコメントを頂きました。 まず、コメントを頂戴した皆さんに、心からお礼を申し上げます。私は、SNSのミクシィのニュースへの日記を中心に、一部、インターネットの掲示板を読ませて頂きました。ご意見を拝読しながら、「なるほど、そういう視点もあるのだな」と気付かされることが多々ありました。私への賛否はともかく、今回の出来事をきっかけとして、多くの方々が視覚障害者の歩行環境に興味を持ってくださったこと、考えてくださったことを、とてもありがたいと思います。そして、皆さんのご意見を読んで、新聞記事では全体像が伝わりにくかった部分が多いことを痛感しました。詳細については、このブログで、3回にわたって日記を書いています。長文で申し訳ありませんが、一度お目通し頂けましたら幸いです。以下、皆さんからのご指摘が多かった事柄について、1.駅から会場までの送迎は必要か?2.「障害者は、やってもらって当たり前と思っているのか」、 「感謝の気持ちが足りない」とのご指摘について3.「社会福祉協議会からのメールは打診ではないか。 聞くだけでもいけないのか?」という疑問についての順にコメントさせて頂きます。以前の日記と重複する点がありますことをお許しください。 1.駅から会場までの送迎は必要か?ご意見の中には、「迎えに来いなんて、何様のつもりだ!」といったものがありました。一般に、視覚障害は情報障害と移動障害であるといわれています。きちんと歩行訓練を受けたり、何度か訪れて慣れた場所にならもちろん一人で行けます。しかし、初めて行くところで、道順がわからない場合には、やはり何らかのサポートが必要だと思います。健常者を出迎えるのは優遇やもてなしの要素が強いものでしょう。それに対して、視覚障害者を送迎する目的は、安全確保のためのサポートです。ゴージャスなリムジンで迎えに来てもらいたいと言うのなら、それは「何様のつもりか」でしょう。けれど、今回は、あくまでも移動の安全確保が目的でした。それは、万一の事故に対する主催者と私のリスク管理という観点からも、必要な視点だったと考えています。それでも、無理やり行こうと思えば行けるか、一人で行くことは可能か、と問われれば、可能です。しかし、それは今回の研修テーマであった「自然で気軽な移動」とは程遠く、決して安全とはいえません。研修会場は、横浜駅から歩いて15分のところにあると伺いました。一般に、視覚障害者が初めて向かう場所で、交通量の多い大きな交差点の横断を含め、徒歩15分の距離を一人で歩くことには、大きな不安があります。全盲の私にとっては、最寄りの横浜駅まで向かうよりも、横浜駅から目的地の神奈川県社会福祉会館までの路上歩行の方が、何倍も難しくて怖いのです。駅であれば、どの駅でもある程度構造が決まっており、プラットホームから落ちないようにさえ気を付けていれば、通路に自動車が来ることはありません。けれど、初めての道を15分歩くのは、かなりの危険と緊張を伴うものです。目が見える人が15分なら、私の場合にはもっと多くの時間がかかると思います。道を尋ねた相手が親切で地理に詳しい人だったら、順調に着けるかもしれません。でも、途中で迷ったら、1時間かかってもたどり着けないかもしれません。「それならタクシーで行けばいいじゃないか」というご意見も沢山ありました。しかし、慣れない駅でタクシー乗り場を見つけるのは、そんなに簡単なことではありません。うまく駅員さんや親切な通行人に助けてもらえればすぐにタクシーに乗車出来ますが、必ずしもそうとは限りません。駅員さんも常にタクシー乗り場まで誘導してくださるわけではなく、大体の方向だけを教えてくれることもあります。実際の経験として、初めて降りた駅でタクシーに乗車出来るまでに多くの時間を要したり、複数あるタクシー乗り場の選択を誤り、目的地に向かうために大回りしなければならなかったこともあります。また、どんなに運転手さんにお願いしても、目的の建物から少しずれた場所で降ろされることもあり、それだけでも迷ってしまいます。近くにあるという公園にでも入り込もうものなら、尋ねる人すらいないかもしれません。初めての場所に行く時には、途中で道に迷うことも考慮して、かなり早めに家を出るようにしています。けれども、一体何分ゆとりを持たせておけば大丈夫なのか、自分自身でも時間を読むことが出来ないのです。パネラーを仕事で引き受ける以上、こうした不確定要因のために遅刻することは絶対に許されません。遅刻してもいいから、とにかく会場に着けばよい、ということなら、どうにでもなるでしょう。しかし、目的は会場に一人で行くことではありません。パネラーとして発言することです。緊張の一人歩きに気力を費やし、会場にたどり着くころにはへとへとになっているかもしれません。それでは、目的地に無事に到着することが主目的となり、パネラーとして発言することは二の次になってしまいます。加えて、不安を押して一人で会場に向かい、万一事故にでもあえば、「何故初めての視覚障害者を一人で行かせたのか」と、主催者は強い批判を受けることでしょう。そうした点を総合的に考慮して、私は社会福祉協議会から当日の送迎を断られた直後に、パネラーとしての参加を辞退しました。そして、これは私も新聞報道で知ったことですが、神奈川県社協の職員は60人いらっしゃるそうです。60人いても、人手不足で送迎を断らなければならないような厳しい状況だったのでしょうか。それほどまでにスタッフにゆとりのない状態で障害者が集まる催し物を実施して、不慮の事故や災害が起きたら、参加者の安全は確保出来るのでしょうか。催し物の主催者としては、当然そのようなリスク管理もしなければならないと思うのですが。 いずれにしても、「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」という今回の研修テーマからして、神奈川県社協の対応は適切とはいえません。私が普段以上に障害者の送迎についての社協の姿勢にこだわったのは、テーマからしても当然と考えています。だってこんなテーマで会を開いておいて、全盲のパネラーの送迎を断るなんて、やっぱりブラックユーモアでしょう。 2.「障害者は、やってもらって当たり前と思っているのか」、 「感謝の気持ちが足りない」とのご指摘について 「障害者だから、やってもらって当たり前と思っているのか」、「感謝の気持ちが足りない」というご指摘も沢山ありました。これは、毎日新聞に掲載された「思いやり、優しさが欠けている」という私のコメントに反発が多かったためだと思います。「福祉の啓発を目的に活動するはずの社会福祉協議会なのに、その社協自身が大切な心を失っているのではないか」、という思いで申し上げました。しかし、言葉足らずだったことを、率直にお詫び致します。私は常に世の中の皆さんに感謝しています。私が一人歩き出来るのは、駅で声をかけてくださったり、道で手を貸してくださる皆さんあってこそです。一人歩きというけれど、本当は皆さんの優しさや思いやりによって歩かせて頂いています。だからこそ、私はこれまでに一度も福祉のガイドヘルパーのお世話になることなく、一人歩きを続けて来られたのです。ただ、私たちが健常者に思いやりや優しさを強要してはいけないのと同じように、健常者の皆さんから障害者に対して感謝を求められることにも、若干の違和感があります。「すみません」、「お願いします」、「ありがとうございます」障害のある私たちは、健常の皆さんの何倍も、これらの言葉を使っています。そうしなければ生きていけません。健常者の皆さんは、そんなことは言わなくても、とりあえず町を移動出来るのではありませんか?「お願いします」、「ありがとうございます」を連発しなければ、障害者が当たり前に町を歩くことすら出来ない。当たり前に生きることすら出来ない。健常者の皆さんが望んでいるのは、そんな社会のありようなのでしょうか。今回も、「自宅まで迎えに来てほしい」、と望んだのではありません。最寄りの横浜駅までは一人で行くから、その先の700メートルの移動を手伝ってもらいたい、とお願いしました。障害のある私も頑張る。頑張るから、障害のない人にも、ちょっとだけ助けてもらいたいのです。それでもやっぱり、障害者の甘えでしょうか?過剰な要求でしょうか?ただし、皆さんのコメントにあった「甘えた障害者」については、私もいやになるほど目の当たりにしています。歩行訓練も受けずに、常に福祉のガイドヘルパーに頼り切っている視覚障害の人など、決して少なくはありません。ところで、私が主宰するメーリングリストのメンバーに、ガイドヘルパーなしで、お子さんを連れてディズニーランドに遊びに行っておられる全盲のご夫婦がいらっしゃいます。ディズニーランドの係員が誘導をしてくださり、全盲のご夫婦でも、問題なくお子さんと遊園地を楽しむことが出来るといいます。「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」のテーマに対する一つの答えが、このディズニーランドにあるのではないかと思います。しかし、調べもしないで、「ディズニーランドはバリアフリーでないから」と、相変わらず福祉のガイドヘルパーとディズニーランドに出かける視覚障害者もいます。それはやっぱり、甘えだと思います。明らかに税金の無駄遣いだと思います。・ディズニーランドの誘導は、ディズニーランドの責任でやってもらう。・病院の誘導は、病院の責任でやってもらう。・社会福祉協議会の催し物の誘導は、社会福祉協議会の責任でやってもらう。 いまのうちからそのような社会的コンセンサスを作る努力をしておかないと、国の財政がもっともっと逼迫して、にっちもさっちもいかなくなった時に、ガイドヘルパーの予算が削減されて、視覚障害者の移動が大幅に制限されてしまうかもしれません。もしそうなっても、視覚障害者に基本的な歩行スキルが備わっていて、世の中の皆さんが少しずつ分散してガイドヘルプを担ってくだされば、私たちは十分に質の高い移動手段を確保出来ることになるのだと思います。そのためには、目的地の最寄り駅くらいまでは自力で歩行出来るように、視覚障害者自身が努力してスキルを身につけるべきだと考えます。けれども、怠けてそれをやっていない人が多いことも、残念ながら事実です。
2009.11.01
-
神奈川県社会福祉協議会の件で応援やコメントを頂き、ありがとうございます。(その2)
3.「社会福祉協議会からのメールは打診ではないか。 聞くだけでもいけないのか?」という疑問について> お一人で来て頂く事は可能でしょうか。との社協からのメールの一文を捕らえて、「打診しているだけではないか。障害者には聞くだけでもいけないのか?」という疑問も多くありました。前提が何もなくてこのメールが送信されたのなら、そのとおりでしょう。 社協からのメールは、文章の形式としては、確かに打診です。けれども、一般的に何かを断る時には、この程度の丁寧な文言を使用します。断りたいからこそ丁寧に書くのは、珍しいことではありません。私は、このメールが送信された前日に社協の事務所に打ち合わせにお伺いしました。その際、時間をかけて、・当日は一人でお伺いすること・会場の神奈川県社会福祉会館にはお邪魔したことがなく、道中が不安なので JR横浜駅から会場までの誘導をして頂きたいことをお願いしました。担当者は、追って待ち合わせ場所等を連絡する旨、約束してくださいました。どうして追って連絡かというと、会場に一番近い駅の出口を地図で調べたいから、ということでした。私としては、打ち合わせの日に利用したのと同じ出口で待ち合わせて頂きたいと考えましたが、その点は私が少し早めに駅に着いて出口を探せばよいことですので、先方の都合に合わせることにしました。社協からのお断りのメールは、前日にそのようなやり取りがあった上でのものです。打ち合わせから1日待っても連絡がありませんでしたので、私から確認のメールをお送りした直後に届きました。文章の形式は打診でも、実質はお断りだと判断しました。前日の打ち合わせで、移動に不安があるとあれほど伝えたにもかかわらず、「お一人で来て頂く事は可能でしょうか。」と返信されたことに、少なからず当惑しました。しかも、それまでは、私がメールを送っても返事は電話だった担当者が、この時はメールを送って来たのです。電話では言いにくいこと、つまりお断りであることを、担当者もはっきり認識していたのだと思います。 以上、不十分ではありますが、皆さんのご意見に答えさせて頂きました。 最後に、コメントの中に、「メクラは死ねばいい」、「こんなメクラは殺処分しろ」といったものもありました。殺処分って、豚の屠殺場か何かに連れて行かれるのでしょうか。鬱憤晴らしなのでしょうけれど、正直、これは悲しかったです。まぁ、障害者は鬱憤晴らし程度の役にしか立っていないと言われてしまうのかもしれませんが。障害者に対する皆さんの見方には大変厳しいものがあることを、改めて痛感しました。 いずれにしても、沢山のコメントを頂戴し、本当にありがとうございました。これからも、障害者のこと、福祉の問題を一緒に考えて頂けましたら幸いに思います。なお、報告が遅くなりましたが、この件については、10月28日に神奈川県社協の常務理事にお目にかかり、全面的に謝罪して頂いております。詳しいことは追ってお知らせします。これも、皆さんの応援のおかげです。 皆さん、本当にありがとうございました。
2009.11.01
-
社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 会長 林 英樹様
平成21年10月26日社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会 会長 林 英樹 様 川田 隆一 謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は地域福祉の増進に格別のご尽力を賜り、ありがたく御礼申し上げます。 早速でございますが、私は全盲のフリーライターで、川田隆一と申します。今般、林様にぜひともお聞き届けいただきたいことがございまして、失礼を省みず手紙を差し上げた次第です。なお、この文章は音声ワープロにて作成いたしております。誤字等の失礼がございましたら、何卒お許しください。実は先日私は、貴会の主催により神奈川県社会福祉会館で開催された「障害福祉ボランティアリーダー研修」(平成21年10月23日)に、パネラーとしてお招きいただきました。会のテーマは、「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」というものでございました。 この研修会に出席させていただくに際し、私自身が全盲で地理に不案内なため、最寄り駅から会場までの誘導をお願い致しましたところ、貴会ご担当者より、以下のようなお断りのメールをいただきました。 ※メール全文を原文のまま引用します。(引用ここから)Subject: 障害福祉ボランティアリーダー研修について Date: Wed, 21 Oct 2009 20:09:24 +0900川田隆一様遅くに失礼いたします。昨日はありがとうございました。23日の件なのですが、実はうちの課のシフトの関係で、当日のボランティアセンターにいる職員が1人しかおらず、横浜駅までお迎えにいくのが難しい状態になってしまいました。会館までお越しいただくのに大変恐縮なのですが、お一人で来て頂く事は可能でしょうか。こちらの都合で大変申し訳ありません。ご検討のほど、よろしくお願い申し上げます。************************* 社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 県民活動推進部 福祉ボランティア・シニア活動支援担当 ※以下、担当者署名(略)。*************************(引用ここまで) 以下に、経緯をご説明申し上げます。 ご担当の**様のご希望で、10月20日に、かながわ県民センター内の貴会の事務所にて、打ち合わせをさせていただきました。その際、私から、○当日は一人でお伺いすること、○会場にはお邪魔したことがなく、道中が不安なので、最寄りのJR横浜駅から誘導していただきたいことをお願いいたしました。**様は、追って待ち合わせ場所と時間を連絡する旨、約束してくださいました。 そして1日待ちましたが、ご連絡がありませんでしたので、21日夕刻に、私から確認のメールを差し上げました。それに対して**様から頂戴しましたのが、上記のメールでございます。 私といたしましては、障害者の気軽で自然な移動をテーマとした研修会で、貴会が出席を依頼した全盲のパネラーの移動の保障よりも組織の都合を優先するのは、本末転倒と考えました。また、横浜駅から徒歩15分とお聞きした会場までの単独での移動にも危険を感じました。事前に横浜在住の視覚障害者に確認いたしましたところ、会場は慣れた視覚障害者にも行きづらく、危険箇所があるとのことでございました。 そのため、22日早朝に貴会へご連絡して、研修会出席をお断り申し上げましたところ、その後、**様から何度となくお電話を頂戴し、当日の誘導がかなうことになりましたので、予定通り出席させていただきました。 その間、**様には、一度上司の方とお話しさせて頂きたい旨、再三お願い申し上げました。しかしながら、上司の方からは電話1本頂戴できませんでした。また、研修会当日に、課長の**様からごく短い謝罪の言葉を頂戴しましたが、その言葉からはお気持ちを感じ取ることは到底出来ませんでした。**様は、私にお名刺すらくださいませんでした。このことだけでも、貴会の謝罪がいかに形式的で、誠実さを欠くものかを、如実に表しているかと存じます。 最終的には誘導してくださったのだからそれでよい、ということでは断じてありません。社会福祉の専門機関である貴会職員から上記のようなメールが発信されたこと、また、上司の方が新人の担当者に責任を押し付けて誠実な謝罪をなさらなかったことこそ、大問題だと痛感いたしております。 障害者の自然で気軽な移動について考える研修会にパネラーとして出席するために、私は沢山の時間を費やし、神経をすり減らしてお願いしなければ、安心して移動する自由すら得られませんでした。今回のご対応は、私たち視覚障害者の歩行環境の実情や移動の保障について、貴会の認識が皆無であることを図らずも露呈したもので、あまりに無神経なものと言わざるを得ません。 貴会に問いたいのは、社会福祉従事者としての職員の資質や意識ではありません。それ以前の人間性の問題です。会合に招いた全盲のパネラーから、「初めてで不安なので、最寄り駅から誘導してもらいたい」と依頼を受けたら、人間としてどんな行動を取るべきなのでしょうか。貴会職員には、社会福祉従事者である以前に、人としての思いやりややさしさが欠けているのではありませんか。 林様、社会に対して障害者への理解を啓発してくださるはずの貴会職員の皆様の意識を、一刻も早く変革してください。どうか、どうか、お願いいたします。 具体的には、次の2点につきましてお願い申し上げます。 1.本状において指摘させていただいた事柄につきまして、貴会の最高責任者として事実関係を把握してください。また、把握した事実関係を、書面にてお知らせください。 2.指摘させていただいた出来事について、貴会としての正式なご見解、ならびに 再発防止への具体的な取り組みについて、林様のお考えを書面にてお聞かせください。 なお、この手紙につきましては、一部の個人情報を除いて、全文をインターネットを通じて公開させていただいております。誠に勝手ながら、ご回答は平成21年11月6日(金曜日)までに頂戴できますようお願い申し上げます。また、全盲のため活字の書面を拝読できませんので、点字または電子メールにてご返信頂けましたら幸甚でございます。 末筆ながら、貴会のますますのご発展をお祈り申し上げます。 謹 白
2009.10.27
-
人間失格。神奈川県社会福祉協議会!!
「もっと自然に、もっと気軽に!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」をテーマに、社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会が主催して一昨日開かれた「障害福祉ボランティアリーダー研修」で、パネラーとして招かれた全盲の私が最寄り駅から会場までの誘導をお願いしたところ、「忙しくて手がない」とメールで断られた問題のその後のお話です。報告が遅くなって、ごめんなさい。初めてこの日記を読んでくださった方は、前回・22日の日記これでいいのか、神奈川県社会福祉協議会!!? ~駅からの送迎を願うのは障害者の「甘え」か~から、先にお読み頂ければ、わかりやすいと思います。 実は、22日の日記をアップするのと前後して、神奈川県社会福祉協議会にはパネラー出席をお断りしました。障害者の自然で気軽な移動をテーマとしたパネルディスカッションで、全盲の私の誘導を断るような、そんな意識の低い人たちと一緒に仕事をすることに、強い疑問を感じたからです。すると、担当者から電話で、「会場まで誘導をするので、協力してもらえないか」と、連絡がありました。「いまさらなんだよ。文句を言われれば誘導出来るのなら、どうして最初から気持ちよく誘導してくれないのか」と、新たな怒りがこみ上げて来ました。しかし、そこで少し作戦を変えることにしました。予定通りパネラーとして出席して、与えられた時間をすべて使って、今回の社会福祉協議会のあまりにもお粗末な対応について会場の皆さんに聴いてもらおう、と考えたのです。 そして、いざ当日を迎えました。誘導を断るメールを送って来た本人が、けろっとした様子で横浜駅の待ち合わせ場所に現れました。前日の深刻なやり取りがあっただけに、私の方が緊張してしまいました。 駅から会場までは、歩いて15分ほどでした。初めての私にとっては、ややこしいルートでした。「社会福祉会館」というくらいだから、道中にずっと点字ブロックがあるかといえば、そんなことはありませんでした。また、大通りからわき道に入ったところにあり、曲がる道を間違える可能性も十分あります。何回か練習をすれば一人で行けると思いますが、やはり初めてでは迷ってしまうなと感じました。かといって、タクシーでは近すぎて、運転手さんにいやがられそうな距離です。 会場に着いてしばらくして、主催者側の責任者である神奈川県社会福祉協議会の県民活動推進部 福祉ボランティア・シニア活動支援担当課長が現れ、ただひとこと「この度はご迷惑をおかけしました」とおっしゃいました。「昨日、上司の方とお話ししたいとずっとお願いしていましたのに、電話1本頂けず、とても不愉快です」と応じると、「あっ、そうですか」と言ったきり、いなくなってしまいました。この人、本当に悪いことをしたとは、到底考えていないようでした。その口調からは「謝ればいいんだろ、謝れば」という気持ちを手に取るように感じました。それに、初めての私に挨拶をするのに、「事務所に忘れて来た」と言って、名刺すら出さないのです。課長がこれだから、部下があんな失礼なメールを送るのです。この課、課長が一番腐ってる。すべての責任を新人の担当者に押し付けて、電話1本かけてきませんでした。名刺忘れたのなら取りに帰れよ、ばか!ほんとはわたしたくなかったんじゃないの? 研修会が始まりました。冒頭、開会の挨拶に立ったさっきの課長が、「今回、パネラーの川田さんに、駅までお迎えに行けないとご連絡をしてしまいました。おわびします」と、10秒ほど謝罪のコメントを述べました。その言葉に、心はありませんでした。具体的なことを何も説明しませんでしたので、参加者には何のことだかわからなかったと思います。 そして、いよいよパネルディスカッションになり、私の順番が回って来ました。「本来お話ししたかった内容は、レジュメをお読みください。今日は、どうしても皆さんに聴いて頂きたいことがあります。私が昨日インターネットのブログに書いた内容を、そのまま読ませて頂きます」そう言って、22日の日記の内容のほぼ全文を、15分かけて読み上げました。「これでいいのか、神奈川県社会福祉協議会!!?」と、題名を読み上げた瞬間に、会場内が水を打ったように静かになりました。読み進むにつれ、皆「信じられない!」という表情だったそうです。例の課長はといえば、「うるさいなぁ。自分には関係ない」と、さめた様子に見えたといいます。発言を終えると、司会の障害者団体の事務局長が、「これは大変重要な問題です。きちんと話し合わなければなりません」と、フォローしてくださいました。そして、コーディネーターの大学教授が、「川田さんに起きてしまった出来事を、皆で意識を改革するためのきっかけにしなければならない」と結んでくださいました。パネラーや参加者には、私の伝えたかった思いが十分理解されたと思います。しかし、閉会の挨拶で、主催者から改めてのコメントはありませんでした。当然、閉会後の控え室で、私は例の課長からずっと無視されました。 研修会を終えて、神奈川県社会福祉協議会の意識の低さを、改めて痛感しました。会合に招いた全盲のパネラーに、「初めてなので駅から誘導してもらいたい」と頼まれたら、何をさておいてもそうするのが当たり前でしょう。それは、社会福祉協議会だからどう、ということではなく、人間としてのやさしさがあるかどうかの問題ではないでしょうか。神奈川県社会福祉協議会に問われるべきは、社会福祉従事者としての資質や意識ではありません。そもそも人間として当然の心を持っているかどうか。相手の立場に立って理解しようとしているかどうか。彼らにはそれすらないのだと思います。福祉従事者としてではない。人間として失格なのだと思います。 コーディネーターの先生がおっしゃったように、神奈川県社会福祉協議会には、この出来事を組織全体の問題として認識し、一刻も早く意識を変革してもらわなければなりません。けれど、とりわけあの課長は、問題をもみ消してしまいそうです。「研修会さえやり過ごせばいい。後は上に報告しなければ、わかりはしない」と、そう考えているように思えてなりません。それでは、社会福祉協議会の意識は何も変わりません。障害者の自然で気軽な移動について考える研修会で、私は主催者と何度もやり取りをして、やっとの思いで移動手段を手に入れることが出来ました。沢山の時間を使い、神経をすり減らしてお願いしなければ、安心して歩く自由すら得られないこと、それは自然で気軽な移動とは程遠いものです。社会の意識を変革する前に、社会を啓発してくれるはずの社会福祉協議会の意識を、一国も早く変えてもらわなければならないと思います。私は、この問題をこれで終わりには出来ません。しかるべき方法で、神奈川県社会福祉協議会の姿勢を質すつもりです。 皆さんにお願いがあります。この出来事を大勢の人たちに知って頂きたいのです。みんなで、社会福祉協議会とは何なのか、どうあるべきなのかを考えてもらいたいのです。お友達に、「神奈川県社会福祉協議会って、こんなことしたんだって」、と話題にしてくださいませんか。日記やブログに書いてくださいませんか。もちろん、私の日記に自由にリンクしてくださってOKです。そして、ぜひ、神奈川県社会福祉協議会に、あなたの言葉でメールを送ってください。大勢の声が集まれば、もっと真剣に反省し、意識を改革してくれることと思います。皆さん、どうか宜しくお願いします。神奈川県社会福祉協議会平成21年度障害福祉ボランティアリーダー研修開催(10月23日終了)
2009.10.25
-
これでいいのか、神奈川県社会福祉協議会!!? ~駅からの送迎を願うのは障害者の「甘え」か~
社会福祉協議会主催で、障害者の移動をテーマとした研修会にパネラーとして招かれました。最寄り駅から会場への送迎を依頼したところ、一度は約束しておきながら、「忙しくて手がない」と断られてしまいました。 私の仕事の多くを占めるものに、小中学校や大学、教育委員会主催の講演会の講師があります。毎回初めてのところにお伺いすることが多く、全盲の私には常に移動の不安と緊張感が付きまといます。しかし、遠い、近いにかかわらず、ほとんどの講演に、白い杖をついて一人で出かけています。大概の場合、主催者にお願いして最寄の駅から会場までの送迎をして頂いています。来週も、教育委員会主催の人権講演会で群馬県にお招き頂いています。事前に先方の担当者から「当日はどのようなサポートが必要でしょうか」とのお問い合わせがありました。遠慮がちに駅からの送迎をお願いしたところ、快く承諾してくださり、改札口で待ち合わせをして頂けることになりました。これまでに最寄り駅からの送迎を断られたことは、一度もありませんでした。ところが、なんと!地域福祉の推進を図ることを目的に税金を使って活動している社会福祉協議会から、今回初めて断られました。社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会が主催して、明日、10月23日に行われる「障害福祉ボランティアリーダー研修」のパネルディスカッションに、パネラーとして出席してもらいたいと、依頼がありました。テーマは、「もっと自然に、もっと気軽に行動したい!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」というもので、私には視覚障害者の立場から、身近な生活圏での移動の現状と課題について話してほしいということでした。 社会福祉協議会の担当者とは、先方の希望で、10月20日にかながわ県民センターにある事務所で打ち合わせをしました。当日は、横浜駅の北西口で担当者と待ち合わせをしました。私にとってそこは初めての場所でした。絶対に遅れてはいけないので、30分前に到着する電車に乗りました。そして、通りがかりの人や駅員さんに助けて頂きながら、10分前には無事に北西口に着きました。 打ち合わせの際、・当日は一人でお伺いすること・会場の神奈川県社会福祉会館にはお邪魔したことがなく、道中が不安なので JR横浜駅から会場までの誘導をして頂きたいことをお願いしました。担当者は、追って待ち合わせ場所と時間を連絡する旨、約束してくれました。 その後、1日待ちましたが、連絡がありませんでしたので、私から確認のメールを送りました。すると、程なく、こんなメールが届いたのです。> 川田隆一様> > 23日の件なのですが、実はうちの課のシフトの関係で、当日の> ボランティアセンターにいる職員が1人しかおらず、横浜駅までお迎えに> いくのが難しい状態になってしまいました。> 会館までお越しいただくのに大変恐縮なのですが、お一人で来て頂く事は> 可能でしょうか。 私としては、道中に不安があったため、長らく苦悩した末に、思い切って誘導をお願いしたのです。会場は、打ち合わせした場所とは違う場所で、横浜駅から歩いて15分のところにあり、公園の近くと聞いています。一般に、視覚障害者が初めて向かう場所で、徒歩15分の距離を一人で歩くことには、大きな不安があります。駅の中なら、プラットホームから落ちないようにさえ気を付ければ、通路に自動車が来ることはありません。しかし、初めての道路を15分歩くのは、かなりの緊張を伴うものです。目が見える人が15分なら、私の場合にはもっと多くの時間がかかると思います。道を尋ねた相手が親切で地理に詳しい人だったら、順調に着けるかもしれません。でも、途中で迷ったら、1時間かかってもたどり着けないかもしれません。先方は、「金を払うのだから、タクシーででも来ればいいじゃないか」くらいの考えだったのでしょう。しかし、「もっと自然に、もっと気軽に行動したい!~くらしの中の身近な『移動』を考える~」という研修会のテーマからして、全く本末転倒です。仮にタクシーを利用しても、目的の建物から少しずれた場所で降ろされるだけでも迷ってしまいます。近くにあるという公園にでも迷い込もうものなら、尋ねる人すらいないかもしれません。「一人で来ることは可能か?」と問われれば、それは可能です。しかし、目的は会場に一人で行くことではありません。パネラーとして発言することです。緊張の一人歩きに気力を費やし、会場にたどり着くころにはへとへとになっているかもしれません。それでは無事に到着することが主目的となり、パネラーとして発言することは二の次になってしまいそうです。自宅まで迎えに来てほしい、と言っているのではありません。最寄り駅までは一人で行くから、その後のことを少しだけ助けてもらいたいと願っているのです。障害のある私も頑張る。頑張るから、障害のない人にも、ちょっとだけ助けてもらいたいのです。今回の社会福祉協議会の対応は、視覚障害者の安全よりも先方の都合を優先するものではないでしょうか。これは、視覚障害者の歩行環境の実情や移動の保障について、社会福祉協議会の認識が皆無であることをくしくも露呈したもので、無神経過ぎる対応のように思えてなりません。学校や企業など、障害者のことを知らない人たちならまだしも、よりにもよって、私たちの税金で運営されている社会福祉の専門機関が、こんなお粗末なことをしてもよいのでしょうか。第一、障害者のことをよく知らない学校や企業だって、もっともっと誠実で人間味のある対応をしてくれています。それなのに、社会福祉協議会ともあろうものが!!?「障害者の気軽な移動」をテーマとしたシンポジウムで、主催の社会福祉協議会が、視覚障害を持つパネラーの移動の保障よりも組織の都合を優先するだなんて、正にブラックユーモアでしょう。それに、この研修会を聴いてみたいと思う視覚障害者がいても、最寄駅から会場までの移動の保障がないために、参加を断念せざるを得ない人も少なくないはずです。視覚障害関連の会合などでは、時間を決めて駅などで待ち合わせをし、みんなで会場へ移動するように配慮してくれる主催者が、いくらでもあります。また、この研修会では、視覚障害者への情報補償としての点字資料の準備なども、一切ないようです。社会福祉協議会主催の研修会なのに、障害者を軽視したこうした対応はあまりに悲しすぎます。障害者の移動について啓発活動を行う前に、まず神奈川県社会福祉協議会自体の意識を改めて頂くことが先決だと思うのです。 皆さんは、駅からの送迎を願う私の方が、障害者として甘えていると思われますか?平成21年度障害福祉ボランティアリーダー研修開催(神奈川県社会福祉協議会)
2009.10.22
-
ほかの人の目とITの技術を借りて、全盲の私にも見えた喜び! ~ついにビデオ通話実験成功~
数日前から、全盲の私には見えないもの、見たいものを、Webカメラを通してスカイプで代わりに見てくれる人を募集しています。昨夜、「サポーターやるよ。時間があるときウエブカメラ見るよ」と、メッセージがあり、早速、私にとっては初の記念すべきビデオ通話をしました。 いやぁ、よく見えるものですね!私の髪の毛が茶髪だとわかるのは当然かもしれませんが、一番驚いたのは、「後ろにあるたんすから、ブルーの服がはみ出してるよ」と言われたこと。あわてて行ってみると、確かに扉のすき間から服がはみ出していました。そして、彼女に声で指示してもらいながら、カメラを上下左右に動かし、私の顔がちゃんと映るベストポジションも覚えました。郵便物も見てもらいました。残念ながら、細かい文字はうまく映りませんでした。千円札をカメラにかざしてみましたが、それはちゃんとわかってもらえました。もしかして、カメラの操作が上達すれば、細かい文字を読んでもらえる映し方を見付けられるかもしれません。また、動画はカクカクしたものではなく、私の動作にあわせてスムーズに動いているそうです。そして、その人は、私の顔を見ながら話すことで親近感が増した、とも言ってくれました。私は一方的に見られるだけで、彼女の顔が私には見えないのが、とても残念です。でも、顔を見てもらうことで、もっと仲良しになれるのなら、私にとってもうれしいことです。いずれにしても、こんなにちゃんと映るのかと驚きました。使い方次第では、かなり有意義なこと、面白いことが出来そうな気がします。 目が見えない人の中には、「すぐにでもWebカメラを買いたいけれど、買ってもカメラの画像を見てくれる人がいない」と言う人も少なくありません。そんな悩みを解決するには、皆さんのお力を少しずつ貸して頂くのが、一番よい方法だと思います。引き続き、糖尿太郎のサポーターになってくださる方をお待ちしています。
2009.10.13
-
全盲・一人暮らしの無人島に、新しい「目」が出来た!
前回の日記、Webカメラの話の続きです。 今日、目が見える友人がうちに来てくれましたので、先日購入したWebカメラの映像を見てもらいました。スカイプのビデオ設定画面でカメラのテストが出来、相手に送信されるのと同じ画像を自分のディスプレーに映せます。画像そのものはきちんと映っていました。パソコンとカメラは前もって私が接続しておきました。「ドライバなしで一発接続」という商品説明は、本当だったようです。また、オートフォーカスタイプは、本当に自動でピントを合わせてくれるのですね!ただ、私のパソコンは窓に向かって置いてあるため、逆光で、映った顔が黒くなっているのだそうです。腹黒いという自覚はありましたが、顔まで黒いとは・・。対策として、カメラと平行にライトで照らせばいいということで、100均で小さなライトを買って来ました。(ちなみに、100均ですが、このライトは210円でした。)これできれいな画像を送ることが出来るようです。友人が活字で書かれた書類をカメラに向けて、モニターを確認していましたが、十分読める画質だといっていました。この友人がスカイプを導入してくれることになりましたので、私の無人島に強力な「目」が出来たかもしれません。いろいろ試してみて、おいおいまたご報告します。なお、画像を見て洋服のコーディネートのアドバイスや、自宅に届いた活字の郵便物などを読んで頂けるサポーターを、引き続き募集中です。お願いが一人に集中すると、その人の負担になります。サポーターは沢山いてくださる方がありがたいですから。友達が少ない糖尿太郎を助けると思って、どうぞ宜しくお願いします。メールはこちらへ
2009.10.12
-

一人暮らし全盲、ついにWebカメラで生活サポート実験開始!協力者大募集中。
皆さん、こんにちは。前回の日記について、Webカメラに関する情報をありがとうございました。ついにカメラを買いました!サンワサプライの製品で、です。200万画素のオートフォーカスタイプで、定価は13800円ですが、アウトレットサンワダイレクトで送料込み3980円でした。アウトレットですが、製品の性能に問題はなく、初期不良の場合には交換してくれると書いてあること、これまでに何度かサンワダイレクトで購入していて信頼出来ることから、これにしました。ちなみに残りあと1個だそうです。買われる場合は、自己責任でお願いします。マイク内蔵のものにするかどうか、最後まで悩みましたが、結局、内蔵ではないものにしました。専用マイクの方が音がいいかな、と思いまして。ということで、カメラは手に入れましたが、カメラを使った生活サポートの実験をお手伝いしてくれる人はまだ見付かっていません。ぜひご協力を!(詳しいことは、前回の日記をお読みください。)メールはこちらへ
2009.10.04
-
スカイプのビデオチャット、視覚障害者の生活サポートに使える可能性は?
皆さん、こんにちは。 先日、ミクシィの日記で、スカイプのビデオチャットについて書きました。スカイプは、世界中のユーザー同士が、無料で通話出来るソフトです。 パソコンにヘッドセットをつなぐだけで、電話よりも高音質の会話が 出来ます。音声ばかりでなく、Webカメラがあれば、目の見える人たちなら お互いの顔を見ながらビデオ通話も出来るという優れものです。その日記にコメントを下さった皆さんと話していて、Webカメラは 耳の不自由な人たちのコミュニケーションにとって、とても便利だと知りました。 そこではたと考え付いたのですが、このWebカメラ、私のような一人暮らしの 全盲の視覚障害者や、夫婦ともに全盲の世帯にも、便利に利用出来るのでは ないでしょうか。例えば、その日着ていく予定の背広とネクタイのコンビネーションが おかしくないか、衣服に汚れやシミがないか、カメラの画像を通じて目の見える人に確認してもらうといった利用です。自宅に届いた郵便物なども、ちょっと見てもらえたら便利です。また、女性なら(女性だけではないかもしれませんが?)、お化粧がうまく出来ているかどうか、離れて暮らしている家族などに助言してもらうようなことも出来るのでは、と期待しています。新しいもの好きの私としては、早速スカイプのビデオチャットを試してみたいのですが、それに際して、皆さんに教えて頂きたいこと、助けて頂きたいことがあります。 教えて頂きたいのは、Webカメラについてです。 ネットで検索したところ、最近の主流は130万画素、200万画素と いったもので、安い製品なら千円代からありました。 ドライバーは不要で、パソコンのUSBポートに接続すれば、すぐに 使えるというものも沢山あります。実際、この130万画素、200万画素というのは、どのくらい細かく見えるものなのでしょうか。また、全盲の私の場合、ピントや照明の調整が自分で出来ませんので、オートフォーカスのものがいいなと考えています。皆さんの中にも、Webカメラを利用中の人がいらっしゃると思います。 「この製品は画像が鮮明だよ」、「これだったら設定が簡単だから、 目が見えない人にも便利なのではないか」といった情報がありましたら、 具体的な型番なども含めて、ぜひメールで教えてくださいませんか。メールはこちらへ そして、私の壮大な実験?にお付き合いしてくださる人も大募集します。どなたか、スカイプのビデオチャットで、私の衣服や郵便物の画像を見て頂けませんか。安心してください。Hな画像を送ったりはしませんから・・。(笑)パソコンにスカイプが入っていて、ヘッドセットがある人ならどなたでも大丈夫です。カメラはいりません。私に画像を送ってくださっても、どんなに美人でも見えませんから。(苦笑) 興味を持って頂ける方は、ぜひご連絡ください。メールはこちらへ すでに、携帯電話のカメラを使って視覚障害者をサポートする活動が行われています。でも、スカイプのビデオチャットの方が、通信費も かかりませんし、ちょっと何かを見てもらいたくなるのは、一人で自宅に いる時の方が多いように思います。Webカメラによる視覚障害者の生活サポートの可能性について、情報や アイデアなども、メールでお聞かせ頂けましたらうれしいです。メールはこちらへ ご協力、宜しくお願いします。
2009.09.29
-
皆さんに、たってのお願いがあります!
こんにちは。 梅雨明けってことは、もう夏!今年も夏に取り残されそうな糖尿太郎です。 今日は皆さんにたってのお願いがあります。いえいえ、「恋人ボランティアになってください」とか、「キスしてください」とか、そんなお願いではありません。(実はそのお願いも継続中だったりしますけれど・・) 私、最近、目が不自由な人たちに呼びかけて「サクセス」というメーリングリストを作りました。現在は視覚障害者を中心に、160人ほど参加しています。目が見えなくてもストレスなく外出するにはどうすればよいか、食事をきれいに食べる方法など、主に視覚障害に関連する意見や情報交換をしています。 寄せられる投稿を読んでいて、これはぜひ目が見える皆さんにも話に参加して頂けないかなと思いました。目の見えない人が普段どんなことを考えているのか、何に困っているのか。そんなことに少しでも興味を持って頂ける方がいらっしゃいましたら、ぜひ私のメーリングリストの仲間になってくださいませんか。 もちろん、難しい話題ばかりでなく、日々の出来事など、たわいもない話も沢山あります。今は、目が見える人たちと合コンをしたい、という話で盛り上がっています。1日に30通くらい投稿されますが、適当に読み飛ばし、興味のあるテーマに返信して頂ければありがたいです。 メーリングリストの紹介文の取り寄せは、本文にinfo successと記述した題名なしのコマンドメールをMajordomo@mld.nifty.comあてに送信してください。登録方法など、わからないことがありましたら、私あてにミクシィのメッセージを頂ければお返事します。そして、参加してくださった方は、もしよければ、「川田さんのマイミクです」など、簡単な自己紹介を投稿して頂けましたらうれしく思います。 皆さん、どうぞ宜しくお願いします。 以下、長文ですが、メーリングリストを立ち上げるに際して、視覚障害者に参加を呼びかけた文章を貼り付けておきます。 皆さん、こんにちは。東京の川田隆一です。 川田隆一のメーリングリスト「サクセス」(成功)へのお誘いです。 視覚障害者がもっと自由に、あきらめていたことを、一つでも多く自力で出来るようになるための情報交換をしませんか。そして、障害者の本当の幸せとは何か。自立と自助を応援する福祉社会とはどうあるべきか。おんぶにだっこで福祉を受けるばかりでなく、私たちに出来る社会貢献はないのか。タブーを破って、本音で熱く語り合いませんか。 「本当は、障害基礎年金なんてもらいたくない。それよりも、障害者の力が正当に評価される世の中にしたい。」 「福祉に甘えてばかりの視覚障害者も、おせっかいなボランティアも、時代に取り残された運動団体も大嫌いだ。」 「そんなことはどうでもいい。私は家で有名パティシエのショートケーキが食べたいんだ。」 などなど、社会に物申したい人、視覚障害者にほとほとあきれ果てている人、生活の質を向上させたいと願う人。サクセスで一緒に考えませんか。夢をかなえませんか。 サクセスは、行動するメーリングリストを目指します。 言いっぱなしにしないで、みんなで議論した結果を、社会にきちんとフィードバックしましょう。新聞に投書をしましょう。地元の市役所に、厚生労働省や国会議員の事務所に、政策提言のメールを送りましょう。企業に、製品やサービスの改善、ホームページのアクセシビリティの実現などをお願いしましょう。一人では出来ないことも、みんなで集中的に取り組めば、広報戦略を持たない視覚障害者団体の何倍も、世の中に影響力を発揮出来ます。昨年発生したギョーザ事件の折、情報を得られない視覚障害者の実情を、共同通信にお願いして、全国の新聞で報道して頂きました。「ギョーザ事件で視覚障害者困惑 情報得られず」(神戸新聞) このように、サクセスで話し合った問題を、積極的に社会に訴えて、解決のために一歩でも前進させましょう。世の中は一度に大きくは変えられません。地道で粘り強い働きかけを続けていきましょう。大学で福祉やバリアフリーを研究している人。三療(あん摩マッサージ指圧、鍼、灸)の問題に詳しい人。法律やコンピュータに強い人。報道関係の人。点字図書館で働いている人。企業の第一線で活躍中の人。そして、私たちと共に歩んでくださるほんもののボランティアの皆さん。どうか、あなたの経験とインテリジェンスを貸してください。健常者の社会を味方につけなければ、私たちの幸せはありえません。みんなで意見を出し合って、どんどん要望や提案を発信しましょう。「口ばっかりで行動しない」、といわれる視覚障害者のイメージを刷新しましょう。 サクセスは、「何でもあり」のメーリングリストです。メル友や茶のみ友達の募集、合コンのお誘いなど、やわらかい話題も大歓迎します。一度しかない人生が楽しくなるように、あなたがやってみたいことを、何でも自由に投稿してください。みんなで知恵を出し合えば、願いがかなうかもしれません。きっとかないます。そして、政治や行政を批判するのと同じように、視覚障害者自身や視覚障害者団体の問題点も浮き彫りにしましょう。人間社会の健全な発展にとって、批判は、なくてはならない切磋琢磨です。ぬるま湯で傷をなめ合っていても、進歩は生まれません。 サクセスは、どんな人の参加も歓迎します。読んでくださるだけの人も、どうぞ気軽に登録してください。ただし、議論が白熱しても、水を差すようなことは一切しませんので、心が傷つきやすい人にはお勧め出来ません。 サクセスのルールは単純明快です。自分の意見を自由に述べる代わりに、どんな意見であろうとも、他人が意見を述べる権利を奪わないことです。視覚障害者はみんな同じではない。共通点は目が見えないことだけ。考え方も能力も努力の度合いも経済力も違うのだ。違う点の方が多いのだ、という前提に立って議論しましょう。意見の違いをうやむやにして仲良くするよりも、多少の対立は恐れずに、議論を尽くすことの方を大切に考える。それがサクセスの運営方針です。 サクセスは、私、川田隆一が管理します。いえ、ほとんど管理しません。私も一参加者として、率直に意見を述べます。もちろん、私と違う意見であっても、意見を表明する権利を最大限尊重することをお約束します。違法な内容など、よほどのことがない限り、投稿の制限や退会処分などはしません。ただし、川田隆一が一度下した決定には、絶対的に従って頂きます。判断に際しては、出来るだけ皆さんの意見も聞かせてください。尊厳ある個人の発言の機会を制限したり、いわんや退会させるような場合にこそ、悔いの残らない話し合いが必要と考えます。 サクセスは、プロバイダーの@niftyのメーリングリストシステムで運用します。メールのフッタ広告はありません。ダイレクトメールが送られることもありません。本名でも、ハンドル名でも、ご都合のよい方で参加してください。投稿も、情報の利用も、自己責任でお願いします。また、全ての法令を厳守してください。サクセスに投稿されたメールのfrom欄には、投稿者のメールアドレスが公開されます。 参加も退会も自由です。承認制ではありません。メールアドレス以外の個人情報は、お伺いしません。なお、メーリングリストを管理する私には、ご登録くださった皆さんのメールアドレスのみ通知されます。当然、プライバシーは大切に守ります。ご心配でしたら、フリーメールアドレスなどをご利用ください。 参加方法は、私への登録代行のご依頼、またはご自身での登録の2通りです。 登録代行の場合、題名に「サクセス参加希望」と記入したメールをお送りください。本文は空白で構いません。あて先はkhb15504@nifty.comです。 また、ご自身での登録は、本文にsubscribe successと記述したコマンドメールを送信してください。題名は不要です。あて先はMajordomo@mld.nifty.com です。 程なくシステムから、登録意思確認のメールが送信されますので、その指示に従って確認手続きをお願い致します。ご自身での登録は少しややこしいので、ご遠慮なく、登録代行をご利用ください。投稿用アドレスや注意事項などは、ウエルカムメールに記載してあります。 なお、メーリングリストの仕様などについての詳細は、@niftyのサイトで確認出来ます。 たとえ5人でも10人でもいい。もっと本音で語り合いたい。そんな思いで、サクセスを始めることにしました。意見は違っても、心を開いて真剣に語り合える仲間を見つけましょう。 皆さんと、有意義な情報交換や、歯に衣着せぬ議論が出来ますことを、楽しみにしております。 あなたのご参加を、心よりお待ち申し上げます。 長文、失礼致しました。
2009.07.15
-
やばい。ものすごいメールが来た!!
「あなたの視力が14日間で【0.9】回復します!」だって!!絶対だな??てことは、糖尿太郎の視力は今0だから、2週間後には0.9!!いいかもしんない。でも、いきなり目が見えるようになったら、それはそれで怖いんだろうな・・。漢字も小学1年生から勉強するのかな?うーん。見えるようになりたいような、いまさら面倒くさいのでこのままでもいいような・・?悩みは深まる!!
2009.06.09
-
薬のインターネット販売の規制。「視覚障害者が困る」と、楽天・三木谷氏は言うが・・?
風邪薬や胃薬などの一般用医薬品のインターネット販売や通信販売が規制され、原則対面販売となることについて、楽天株式会社の三木谷代表取締役名で今日発信された「国民の声を聞いてください、舛添大臣!」というメールを受け取った方が、多くいらっしゃることと思います。 この文章では、「どんなに過疎地でも、どんなに忙しくても、視覚障害の方でも、自分にあった薬を手にいれることができるようになっていたのです。」と、視覚障害者の利便性にも言及して、インターネットでの医薬品販売継続の必要性を強調しています。また、先日三木谷氏も出演してこの問題を特集したテレビ朝日の「サンデープロジェクト」でも、冒頭に「一人暮らしの私たちはどうやって薬を買えばいいのか」という視覚障害男性のインタビューが放送されました。 楽天のこうした発言を聞くたびに、私はとても腹立たしい思いにとらわれます。三木谷氏は「ネットで薬が買えなくなったら、視覚障害者が困る」と言うけれど、では、その楽天のホームページは、これまでどれほど視覚障害者のアクセシビリティに配慮してきたというのでしょうか。楽天市場のホームページは、決して視覚障害者にとって使い勝手に優れたものではありません。店舗によっては商品特性を丁寧に文章で説明しているサイトもありますが、商品画像がほとんどで、言葉による説明が皆無だったり、フレームがいくつもあり、音声ブラウザーではページの構造が複雑すぎて利用しにくいサイトも沢山あります。楽天が、ショップ運営者に対して視覚障害者のサイトへのアクセシビリティ向上の必要性を積極的に訴えているとは、到底思えません。また、以前に楽天トラベルのホームページの、フラッシュが多用された海外航空券検索について、私には利用出来なかったので改善のお願いをしました。しかし、楽天トラベルからは木で鼻をくくったような返信しかありませんでした。今、私たち視覚障害者がインターネットで買い物をしているのは、決してアクセシビリティが十分整っているからではありません。個々それぞれに工夫しながら、“取り合えず”利用しているのです。何とか物が買えるのと、安心して買えるのとは大違いです。楽天が、普段は視覚障害者のアクセシビリティに大して配慮もしないくせに、薬のインターネット販売の規制に反対する時にだけ私たちのことを持ち出すのは、あまりに身勝手です。三木谷氏は、自らの主張を裏付けるために、視覚障害者の存在を体よく利用しているだけではないのでしょうか。それを言うのなら、まずは楽天のホームページが視覚障害者にとっても使い勝手がよいように、主体的にアクセシビリティ向上を図ることの方が先決ではありませんか。都合のよい時だけ視覚障害者を持ち出して、自分たちのネットビジネス継続のために利用するのは、絶対に許せません。 それはそれとして、皆さんは風邪薬などをどのように手に入れておられますか。私個人は薬局で買っており、インターネットで風邪薬や胃薬を購入した経験は一度もありません。けれど、視覚障害者の中には、薬を買うための外出が困難だったり、薬局では十分な説明が聞けないため、成分や服用法を文章で詳しく解説しているホームページで購入しているという人も、少なくありません。アメリカで暮らしていたころ、風邪で外に出られなかった時に、近くの薬局に電話をして症状を伝えると、その日のうちに風邪薬を宅配してくれるサービスを利用したことがあります。薬を届けてくれた折に、飲み方も口頭で説明してくれました。確か宅配手数料は1ドルくらいだったと記憶しています。日本でも、そのようなサービスが普及すると便利ではないでしょうか。また、ネットで薬が買えなくなって視覚障害者が困るのなら、それは視覚障害者団体にとっては大きなビジネスチャンスのはずです。「きちんと点字や音声で使用期限や副作用の説明を付けるから、自分たちにも薬を売らせてほしい」と、厚生労働省に求めればいいのです。けれども、視覚障害者団体というものは、国からお金をせしめることばかり考えていて、自分たちで儲けようという感覚は皆無です。というか、もんくは言うけれど、ビジネスセンスはゼロです。そんな人が商売をしても、決してうまくいかないでしょう。それならば、音声パソコンや画面読み上げソフトの販売等、視覚障害者対象のビジネスに精通している民間企業が、視覚障害者に薬を販売してくれる方が、会社にとっても、また私たちにとっても、メリットが大きいのではないでしょうか。ネット規制の一方で、登録販売者がいれば、コンビニで風邪薬などを販売することは許可されました。視覚障害者を販売対象とする企業にも、登録販売者を置いてもらい、点字や音声できちんと説明しながら薬を通信販売してくれれば、今よりもずっと便利で、よほど安全になることでしょう。 なお、厚生労働省では、薬の通販やネット販売を規制する省令案について、5月18日まで、パブリックコメントを募集しているそうです。詳細は、楽天のホームページで確認出来ます。三木谷代表取締役からの反対署名の呼びかけも、ここに掲載されています。【楽天市場】医薬品の通信販売継続を求める署名にご協力を
2009.05.14
-
子宮筋腫触診で有罪になった無免許整体師、手には白い杖?
皆さん、こんばんは。相変わらず、「キス出来ない記録更新中」の糖尿太郎でございます。長らくご無沙汰してしまいました。この情けない記録中止へのご協力をお願いしつつ、今日はとても考えさせられたニュースについて。テーマは「情報格差」です。 無免許で子宮筋腫などの女性患者を触診したとして、医師法違反(無資格医業)に問われた整体師、小松忠義被告に対し、東京地裁が13日に有罪を言い渡したというニュースを、当日夕方のテレビで見た方が、大勢いらっしゃることと思います。テレビのニュースを耳だけで聴いている私には分かりませんでしたが、目の見える友人が言うには、実は、この小松被告は、視覚障害者が使う白い杖を持っていたのだそうです。アナウンサーが読み上げるニュース原稿にはありませんでしたが、画面には白い杖を手にした被告の姿が映っていたといいます。 この被告が本当に視覚障害者かどうかは分かりません。もしかしたら、今流行の障害偽装かもしれません。それはともかく、私がとても気になったのは、テレビの画面では被告が視覚障害者だと暗示する白い杖を持った映像を映しているのに、アナウンサーが読み上げた原稿では、そのことに一言も触れられていなかった、ということです。マスコミは、障害者をネガティブに報道することに対して、極めてナーバスになっていると思います。面と向かって「被告は視覚障害者」とは言えないので、「せめてもの抵抗」で、白い杖を持った映像を使ったのでしょうか。しかし、そのような伝え方では、テレビを耳だけで聴いている人には事件の全貌が分からなくなってしまいます。これは、明らかに私たち目が見えない者にとっての情報格差です。目の見えない人の多くが、ハリ灸マッサージの仕事に就いています。白い杖を持った「無免許整体師」の映像が放送されることで、視覚障害者に対する世間のイメージは、少なからず低下するのではないでしょうか。しかし、画面が見えないために、「被告は視覚障害者だ」と分からない私たちには、このニュースが目の不自由なマッサージ師などに及ぼす悪影響を懸念することも、被告の障害偽装を疑うことも出来ないのです。 判決を報道した多くの新聞も、ラジオも、被告の視覚障害については全く触れていません。障害者の犯罪を報じることについて、マスコミをナーバスにしているのは、一体誰なのでしょうか。私たち障害者の側にも、一定の責任があるのではないか。そう思えてなりません。そして、それは「情報格差」として、目の見えない私たちに帰って来ているのではないでしょうか。医師法違反:「子宮筋腫」触診、無免許被告有罪--東京地裁判決(毎日jp)
2009.04.14
-
「全盲」だからこそ、女性に「目がない」糖尿太郎です。
とても懐かしい人からメールをもらいました。大学でゼミが一緒だった女性からです。このブログや、著書も読んでくれたと聞き、ことのほかうれしくなりました。 彼女のメールに、こんな問いかけがありました。> 地域SNSに入っていて、そのメンバー間で> 「移動の足がない」とか「女性に目がない」とかいうのは> 差別用語ではないかという意見がありました。> 「川田くんは、女性に目がない」と、すぐ思い浮かんだのですが、> そういわれると、川田くん、カチンとくるものなのですか?> 「目がない」と普通に使っている私は、「バカチョンカメラ」と> 同じように、差別意識が低下しているのかな~と、> 考えてしまったものですから、ぜひ、ご意見をお聞かせ願いたいのです。 何がうれしいって、「川田くんは、女性に目がない」と、すぐに思い浮かべてもらえるなんて、私が大学生のころからずっと変わらずに、いかに信念を貫いて生きているかの証明だと思いませんか?ははははは!! それはともかく、このメールをもらうまで、「目がない」という表現が差別だなんて、考えたこともありませんでした。当然、私は全く気になりません。そんなことよりも、健常者の友人とデパートやレストランに行った時、障害のある私を無視して、私が話しかけているのに友人としかコミュニケーションをしてくれない店員さんやウエートレスさんの態度の方が、よっぽど傷つきます。私ばかりでなく、多くの視覚障害者が、あえて自ら「目がない」という表現を使うことは少ないかもしれませんが、気にならないという人が大多数ではないでしょうか。そういえば、以前に、選挙の当選祝いで達磨に目を入れる習慣について、視覚障害者の団体が「目が見えない者への差別だ」と、抗議をしたことがありました。そんなこと、私から言わせれば「運動のための運動」に思えて仕方がありませんでした。もっと急を要する障害者の解決課題は、他にいくらでもあります。世の中にある表現や習慣の中には、取り様によっては「差別」と感じるものがあります。しかし、いちいち目くじらを立てることは、ほとんど無意味ではないでしょうか。(そういえば、「目くじら」って、どんな「くじら」なのかな?)そもそも、古来の伝統や文化を相手に喧嘩をすることには、あまり意味がないように思うのです。文化としての重みも、尊重しなければなりません。 「バカチョンカメラ」には明らかに特定の人たちへの侮蔑がこめられていると感じます。けれど、「目がない」には悪意や差別性など一切感じません。あくまでも国語表現の範ちゅうでしょう。ただ、慣習的な表現であっても、それによって傷つけられる人がいるのであれば、使用を自粛しなければならないと思います。その意味で、「移動の足がない」については、私にも適否を図りかねます。おそらく大丈夫だとは思いますが、念のために下肢障害の方たちにご意見を伺ってみなければならないな、と感じました。ただし、言葉や表現の規制を求めるに当たっては、重々考えなければいけないことがあると思います。お互いに出来る限り自由な言論を保証すると、他人を傷つけたり、傷つけられたりすることが、少なからずあります。けれど、そのことにあまりに神経質になりすぎて、表現の自由をあれもこれも規制することの方が、社会全体の利益に反すると、私は考えます。 今でも、新聞の連載原稿などに「目がない」、「足がない」と書いたら、たぶん校閲部門から表現変更の依頼が出るのではないかと思います。世の中全体が、変なところで多感になっている気がします。「使っちゃいけないらしいから、うるさい人がいるから、よく分からないけれど、取りあえずやめておこうか」、みたいな。 皆が言いたいことを言う自由を保障するための副作用として他人の表現に傷つけられる危険性のある社会と、言論の自由をがんじがらめに規制され言いたいことも言えない社会とでは、どちらがいいのでしょうか。私はもちろん前者を選びます。 難しい話題はここまで。メールをくれた女性は、こんなことも書いてくれました。> 「怒りの川田さん」も読ませていただきましたし、> 「一万人とキスするぞ!」という意気込みも存じております。> 私も、川田くんにだったら、手にキス。くらいならいいかな? あのー、すみません。「一万人とキスするぞ!」ではなくて、「三千人とキスするぞ!」です。ま、どうでもいいかもしれませんけれど・・。ほんとですか。手にキス!!めちゃめちゃ嬉しい!! 皆さんも、この彼女を見習って、友達の証に、せめて手にキスくらいはして頂けると、目の前で鼻血を出して喜びます。うーん、でも、やっぱり手じゃさびしいな・・。せめて、ほっぺじゃだめでしょうか? ちなみに、引き続き「恋人ボランティア」を大真面目に募集しております。このブログを読んで、私の感性に共感してくださる方がいらっしゃいましたら、迷わず、そーっとメッセージをくださいませんか。 ☆女性に目がない糖尿太郎に、あたたかいご支援を!!
2008.11.02
-

ごめんなさい。健常者のことが憎くて憎くてたまりません。
「おい、真ん中の奴。何をだらだらやってるんだよ!!」 見知らぬ人からはき捨てられたその言葉が胸に刺さったまま、もう三日も抜けなくなってしまいました。のろまな自分を許せないのは、イライラしているのは、とりもなおさずこの私です。 それは、郵便局のATMコーナーでの出来事でした。 私はいくつかの銀行に口座を持っています。原稿料や講演料が振り込まれる口座、公共料金の引き落としなど生活費を管理する口座、また宝くじをインターネット通販で購入するための口座等、用途にあわせて使い分けています。そして、仕事用の口座から生活費へといったように、各々の口座間で現金のやり取りをしています。口座間の資金移動は、音声パソコンによるインターネットバンキングでも可能ですが、振込み手数料を倹約するために、出来るだけATMを利用して、キャッシュカードで現金を出し入れしています。 その作業にとって、ゆうちょのATMはもってこいなのです。凹凸の手がかりがないタッチパネル式ATMの操作が出来ない全盲の私には、ボタンが付いていて、操作案内や残高などを音声で確認出来るゆうちょのバリアフリー対応ATMが、何といっても便利です。最近では、ほかの銀行にも脇にある受話器から音声案内が出るATMが普及しはじめてはいますが、一つの支店にバリアフリー対応機が1台のみということが多く、沢山並んでいる中から、どのATMなら全盲の私にも使えるのかを探し出すのに一苦労ということも少なくありません。その点、ゆうちょのATMなら、機種によって差はあるものの、基本的には全ての機械が視覚障害者対応になっているのです。また、三井住友銀行など、ゆうちょATMの利用手数料を無料にしている金融機関も多く、複数の銀行をまたぐ資金移動にとって、ゆうちょのATMは魅力的です。 先週の金曜日の昼下がり。私はいつもの郵便局のATMに並んで順番を待ちました。混雑していて、私の前には20人ほどの人が待っていることが周囲の会話で分かりました。 やっと私の番になりました。その日は、仕事用の口座から現金を引き出して、生活費用など三つの口座に振り分けようと考えていました。しかし、あまりにも混雑している様子なので、郵便局では一つの口座からお金をおろして、もう一つの口座に入れるだけにしようと決めました。残りの作業は、今年2月から視覚障害者対応になった近くのセブン-イレブンのATMでも出来るからです。その郵便局に3台あるATMのうち、私は真ん中の機械でした。左側の女性は、私が並んで待っている時から、ATMの操作の手を止めてケータイで取り留めのない話を続けています。「込んでいるのだから、電話を切るかATMを空けるかすればいいのに」と気をとられていたせいか、私は引き出した札をATMの画面に落としてしまいました。慌てて拾い集めて、別のキャッシュカードを取り出して入金の操作を始めました。 そして、もう少しで終わりというその時、「おい、真ん中の奴。何をだらだらやってるんだよ!!」と、後ろに並んでいた男性がそう言ったのです。「真ん中の奴」とは、まさしくこの私でした。だらだらやっているつもりなど毛頭ないのですが、画面を一目瞭然に出来る目が見える人とは違って、「カードを入れてください」「受話器のボタンで、暗証番号を押してください」「金額は○○円ですね。宜しければシャープボタンを押してください」などと、受話器の音声案内をいちいち聞きながらの作業ですので、目が見える人よりはどうしても余分に時間がかかってしまうのです。 しかし、そのことで他の人に迷惑をかけないように、出来るだけ込んでいない早朝や夕方に利用するようにしたり、あの時のように作業を郵便局とコンビニATMに分けて時間がかかり過ぎないように工夫したりと、私なりに周囲の人たちのことを考えているつもりです。「おい、真ん中の奴。何をだらだらやってるんだよ!!」言われた次の瞬間、私は慌てて取り消しのボタンを押し、キャッシュカードと現金をポケットにねじ込んで、出口に向かって逃げました。「こっちだって好きでゆっくりやってるんじゃないよ、このボケ!」「そんなに待つのがいやなら、お前専用のATMでも買えよ」などと、小声でたんかを切りながら外に出ました。 本当はその男性に面と向かって抗議をしたかったのですが、「何をだらだらやってるんだよ!!」などと言うのは、切れやすい人に違いありません。文句を言って、いきなり刺されでもしたら、元も子もありません。 目が見えないために動作に時間がかかること。他人に迷惑をかけること。それが一番いやなのは、許せないのは、この私自身です。だらだらやりたくなくても、どうしても時間がかかってしまうこともあります。目が見える人のように、何でもさっさと出来たらどんなにいいだろうと、ATMに限らず、しょっちゅうそう思います。自分の障害にイラつき、だれよりも許せないのはこの私自身です。 そして、やむなく周囲に助けを求めると、「障害者だからって、甘えるんじゃない!」と、叱られることもあります。 私も、障害に甘えている障害者は大嫌いです。でも、助けを求めることが全て甘えだと言われるなら、私は一日足りとも生きていけません。私がいつ、白い杖を振りかざして、ATMや乗り物の行列を飛ばしましたか?立っていられるのに、いつ、シルバーシートを無理やり空けさせましたか?「甘え」とは、そういうことを言うのではないでしょうか。 全てのことが自分で出来ない。人よりも時間がかかる→だから私は障害者の認定を受けているのです。断じて、なりたくて障害者になったのではありません。 私には、したくても出来ないことが沢山あります。どんなに見たくたって、何も見えません。そんな、どんくさくて、のろまな私に一番イライラしているのは、そんな私のことを許せないのは、社会のお荷物になるのを恐れているのは、この私自身です。 けれど、どんなにいやでも、許せなくても、「早くしろ」と罵倒されても、私は、残りの人生も障害者として生きなければならないのです。いやだけれど、そうする以外にほかにないのです。 健常者の皆さんには、この気持ちが分かりますか? 「もしかして、その人は川田さんの白い杖が見えなくて、全盲だって気付かなかったのでは?」友人がそう言って慰めてくれました。そうかもしれません。次からは背中に障害者マークでも貼り付けてATMの前に立つ方がよいのでしょうか。 しかし、時間がかかるのは、待ってもらいたいのは、何も目の見えない者ばかりではないと思います。ほかに障害のある人や、お年寄りだって、そうかもしれません。それとも、待ちたくない分、障害者がガイドヘルパーをばかすか利用して、さくさく動く方が社会のためだと、みんなはそう思いますか?ガイドヘルパーのために多くの税金が使われていることを、知っていますか?社会が障害者を差別するために余分に支払っているコストがいくらくらいあるのか、差別がなくなれば倹約出来る国の予算がどのくらいあるのか、そろそろそんなことも考えてみませんか。 「おい、真ん中の奴。何をだらだらやってるんだよ!!」 こんなこと、しょっちゅう言われ慣れているはずなのに。自分が強くなるしか解決の方法はないと分かっているのに‥‥。 あれ以来、ずっと落ち込んでいます。「甘えている」と軽い気持ちで障害者を批判する人は、「早くしろ」と罵倒する人は、あなたも障害者になってください。 それでも同じように言えますか?「遅い!」と罵倒しますか? ごめんなさい。いまは健常者のことが憎くて憎くてたまりません。 ※お知らせ 糖尿太郎は本を出版しています。 障害者が社会への感謝を述べるだけでは、誰もが共に生きられる 真のノーマライゼーションは実現しません。 私自身が経験した差別や偏見、世の中への怒りを素直に伝えることも よりよい社会を目指すために必要ではないかと考え、本書を 書きました。 インターネット書店に読者の方が書いてくださったレビューをご覧頂ければ分かるように、全ての方に「さわやかな読後感」をもって頂ける本ではありません。「さわやかでない」のは、私の表現力の乏しさもさることながら、題材としている「障害者問題」そのものが、決して「さわやか」などといえるものではないからだと思います。私は、私が思う「本当のこと」を素直に書きました。さわやかではないかもしれませんが、ぜひ一度お読み頂けましたら幸いです。
2008.06.15
-

盲学校の23人が撮った!
目の不自由な児童生徒のための盲学校は全国に71校ありますが、中でも横浜市立盲特別支援学校が一際輝いているように感じます。昨年の春ごろでしたか、NHKの『ドキュメント にっぽんの現場』というテレビ番組で、「ことば あふれ出る教室~横浜市立盲学校~」と題して放送されました。点字はかな50音に対応したもので、漢字はありません。そのため、盲学校の子供たちには字の形がイメージ出来ないのです。そこで、先生が小学校で学ぶ1006字の漢字すべてに指で触れられる教材を作り、目の不自由な子供たちに漢字の成り立ちや意味、多くの熟語を語り続けている様子が紹介されたのですが、生まれた時から全盲の私もそんな教育を受けられたらどんなによかったことかと、とても感動しました。 そして、昨年夏には盲学校の23人の児童生徒が撮影した作品を展示する『キッズ フォトグラファーズ 子どもは天才!』という写真展を開いたほか、自費出版された写真集も話題になりました。写真を撮影した23人の児童生徒のうち、13人は全盲だそうです。全盲の子どもたちにもきちんと漢字を教えようとすること、写真だって撮らせてみようと考えること、そういう先生方に教育してもらえる子供たちは、本当に幸せだなと思います。そして、盲学校の教育や教師の資質にも、明らかに地域間格差があるのだなと、いやでも痛感させられたりもするわけです。教師個人の資質というより、盲学校の教師集団全体のやる気や熱意の問題かもしれません。 それはともかく、その横浜市立盲特別支援学校で、第二弾となる写真集「キッズフォトグラファーズ 盲学校の23人が撮った!」が新潮社から発売され、ゴールデンウリークの5月3日から6日まで、渋谷区広尾の広尾商店街の歩行者天国で、路上写真展も開かれているそうです。 きっかけは、昨年十二月に盲学校で行われた返還式だったといいます。この場で、夏に開かれた写真展に出品された80数点の作品が子供たちに返されたのですが、その際、写真のイロハを教えた写真家の管洋志さんが、保護者の一人から「うちの子はまだ写真を撮っているんですよ」と耳打ちをされて驚いたのだそうです。そこで、あらためて確かめると、多くの子供たちが写真に興味を持ち続け、作品を撮り続けていることがわかり、「それならまたやろう」と、今回の企画になったということです。 目が不自由な子供を持つ母親の中には、初めは全盲の子供にカメラを持たせるという発想自体がなかった人も少なくありませんでした。けれど、今は当初の戸惑いはみじんもないそうです。「視界が閉ざされていても、そのほかの感覚を研ぎ澄ませて周囲の出来事をつかみ取ろうとしていることにあらためて気付かされた」「引っ込み思案の子供の世界をカメラが広げた。背中を押してよかった」と口々に語り、シャッターを切ることで生まれた人との出会いが、わが子の可能性を広げ、成長を後押ししたと感じているといいます。 たとえ目が見えなくても、子供たちの可能性を信じて、何にでも挑戦させようとする盲学校の先生と保護者。そんな連携の中で育てられている子供たちこそ、人間が持つ最大限の可能性を引き出せるのではないでしょうか。 根拠に乏しいものさしで障害者の可能性を否定してしまったり、チャレンジするためのチャンスすら与えない理不尽な態度。社会が一番やってはいけないことはそれだと思います。 盲学校の子供たちが撮った作品を、ぜひ一度ご覧くださいませんか。 ※お知らせ もし宜しければ、この本もご一緒に読んでくださいませんか。私が初めて出版した本です。私には写真の撮影は出来ませんが、全盲の視覚障害者として生きて感じた日本の社会を、ありのままの言葉で表現したつもりです。
2008.05.03
-
聖火ってペットボトルみたいなんだ!!
こんばんは。長らくご無沙汰してしまいました。何となくブログから遠ざかってしまいましたが、極端に多忙なわけでもないのです。たぶん、大好きな(*'o'*(-' * )))))))チュッ!が足りなくて、元気が出ないだけだと思います。来週はゴールデンウイークですし、どなたかぜひ糖尿太郎を(*'o'*(-' * )))))))チュッ!付きのデートに誘ってくださいませんか。 さて、何かと心配事の多いオリンピックの聖火リレーですが、明けて明日、長野市内をリレーする80人のランナーの中に、盲導犬と一緒に走る視覚障害者がいらっしゃいます。 愛媛県四国中央市に在住の61歳の造形作家、仙波慶伸(よしのぶ)さんがその人で、ペットボトルを聖火に見立てて、パートナーの盲導犬・トレイス(雄、2歳)と練習に励んでこられたそうです。仙波さんは、5歳のころに網膜色素変性症と診断されたといい、現在は、右目が光や物の動きが分かる程度、左目は視力0.01くらいだということです。 聖火リレーへの参加は、盲導犬育成に携わるスポンサー企業のサムスンの推薦がきっかけだそうで、変更がなければ、2、3百メートルを走り、一緒に選ばれたランナー79人とともに聖火をつなぐ予定です。無縁と思っていたスポーツの世界とかかわる思わぬチャンスに、仙波さんは毎日1万歩をめどにトレーニングを重ねてこられたそうです。平和の祭典とは程遠い雰囲気になってしまいましたが、聖火リレーが何事もなく行われ、仙波さんの一生の思い出になりますようにと、心から願わずにはいられません。 それはそうと、仙波さんがペットボトルを聖火に見立てて練習をしておられるということは、聖火というのはペットボトルのような形状なのでしょうか?私の家にあるのは2リットルサイズのウーロン茶ですが、まさか聖火ってあんなに大きくはないのですよね?生まれた時から目が見えない私には、そもそも聖火を見た記憶がありませんので、イメージすることも出来ないのです。予断ですが、もしも女性の顔に触らせてもらえたとしても、全盲の私には手触りで美人かどうかを判断することは出来ません。もともと「美人とはどのような手触りなのか」のイメージがないからです。でも、一度でいいから、私もこの手で聖火に触ってみたいな・・。 「まっすぐ走れないかもしれない。でも盲導犬と楽しく走る姿を多くの人に見てほしい」と、取材に応えて、仙波さんはそう話しておられます。まっすぐ走れないのは、人生だってそうですよね。まっすぐ走れなくたって、尊い人生はいくらでもありますよね・・。盲導犬と聖火リレー 四国中央・仙波さん 26日長野へ 「楽しく走る姿見て」(愛媛新聞社ONLINE)
2008.04.25
-

僕も全盲だけど、闇の中に光を求めてさまようのは、寒いし面倒くさいなぁ・・
全盲の高校生で、17歳の清水博正さんが、「雨恋々(れんれん)」で2月27日に演歌歌手としてデビューしました。発売初週で4000枚を売り上げ、10日付けのオリコン週間ランキングで36位を記録したのだそうです。 清水さんは、生後まもなく未熟児網膜症で視力を失い、現在群馬県内の盲学校に通っています。NHKのど自慢に出場し、昨年3月に開かれたグランドチャンピオン大会で神野美伽さんの「雪簾」を歌って優勝しました。そこで審査員を務めた作詞家のたかたかしさんと、作曲家の弦哲也さんが清水さんの歌声にほれ込み、デビュー曲「雨恋々」制作の運びとなったのだそうです。たかさんは「全身から声をしぼり出すようにして歌う歌は、闇の中に光を求めてさまよい続けてきた彼の魂の叫び」と評しておられますが、世の中には、全盲の人を何が何でも闇の中に光を求めてさまよう存在に祭り上げないと納得しない人や、障害者の前には必ず厳しい試練が立ちはだかっていなければ気がすまない人が多いのでしょうか。やっぱり、障害者をネタにして泣きたいのかなぁ・・?私も清水さんの歌声を聴きましたが、全盲かどうか、闇をさまようとかさまよわないに関係なく、異彩を放っているように思えるのですが。 清水さんは紅白歌合戦の出場にも意欲を燃やしているそうです。芸能やスポーツの世界で活躍する障害者が社会に与える影響は大きく、清水さんが注目されることで、視覚障害者への理解も深まればいいなと願います。ぜひ、皆さんも清水さんを応援してくださいませんか。なお、今月11日には、NHK「歌謡コンサート」に出演するそうです。 頑張れ、清水さん!!全盲の高校生演歌歌手 デビュー曲がオリコン36位に(毎日jp) ※闇の中に3千人のお姉さんとのキスを求めてさまよい続ける盲目のフリーライター・糖尿太郎のことも、ぜひ応援して頂けませんか。これは、「不良盲人」を自負する私が、バリアフリーやノーマライゼーションについての思いを本音で語った問題作です。
2008.03.07
-
盲導犬じゃなくて、人間の「全盲」の一大ブームとか、来ないかなぁ?
吉永小百合さんが、全盲の夫を献身的に支える妻を演じる映画「まぼろしの邪馬台国」(堤幸彦監督、11月公開予定)の撮影が九州で行われているそうです。 映画は、1967年に出版された「まぼろしの邪馬台国」の著者で、さだまさしさんのヒット曲「関白宣言」のモデルにもなった視覚障害の郷土史家の宮崎康平氏さんと、妻の和子さんの古き良き夫婦像を描くものです。康平氏は邪馬台国が長崎県南部にあったと考え、和子さんが康平氏の目となって、2人で西九州を巡り歩くストーリーだといいます。 しかし、視覚障害者が出てくる作品は、全盲の夫とそれを支える妻というように、どうしていつも構図が決まっているのでしょうね。はいはいはいはい。もちろん私も「お支え希望」ですけれど! そこで、糖尿太郎は考えた。「盲導犬クイール」のときのようにこの映画が大ヒットして、盲導犬ではなく今度は人間の「全盲」の一大ブームが起きてくれないものでしょうか。 雑誌に、「一挙公開!!全盲のイケメンをゲットするための10箇条」(anan)とか、「全盲の君と恋に落ちる都内デートスポット大特集~『風がいい匂いね。私、あなたの風になりたいの』決め台詞はこれだ!!~」(女性セブン)とか、「有名人の全盲恋人自慢」(アサヒ芸能)などなど、とにかく全盲の人の一大ブームって、来てくれないものですかねぇ・・?マスコミにうまく乗れば、何だってブームになりそうな気がしないでもないのですけれど・・。 そうですよね、糖尿太郎はイケメンじゃないから、たとえ全盲ブームが到来しても、おいてけぼりにされること間違いなしですよね・・。でも、人間、夢をあきらめないことも大切ですからね・・。(苦笑)全盲の夫支える妻役熱演!竹中と初共演 小百合(東京中日スポーツ)
2008.03.04
-
盲学校・聾学校の給食に異物。小バエやナメクジまで! ~それでもあなたは、「障害は個性だ。不便だけれど不幸ではない」と、言い続けますか?~
皆さんは、この話を聞いても、「障害は個性だ。目が見えないことは不便だけれど、決して不幸ではないのだから」と、全盲の私を慰め続けてくださるでしょうか? 鳥取県立の盲学校と聾学校の給食に、昨年4月から、異物の混入が28件相次いでいたというのです。異物には、布きれや髪の毛などのほか、小バエやナメクジ、生焼けの豚肉などもあったといいます。布きれや髪の毛ならまだいいけれど、もしも私が小バエやナメクジを口に入れてしまったら、ショックで1週間は立ち直れないと思います。そして、自分に目をくれなかった神様を、改めて恨むことでしょう。県は、両校の給食の調理、配送業務を受託している仕出し店を立ち入り調査し、昨日(19日)、衛生管理体制に不備があるとして、食品衛生法に基づき文書で改善を指導したということです。目が見えれば前もって異物を見付けて、食べるのを避けられるかもしれませんが、見えない私たちの場合には、臭いなどで異変に気付かない限り、口に入れるまで分かりません。それだけに、このニュースにはドキッとさせられました。幸い体調不良を訴えた生徒はいないそうですが、それにしても28件も事故が起きるまで事態を放置した、危機管理能力のあまりにも低い学校と行政に対して、強い憤りを感じました。特別支援学校だからどう、ということはないかもしれませんが、特に目が見えないと、食べ物に異物が混ざっていても、自分では気付けない場合が多いのですから、衛生管理にはもっと注意を払って欲しいものです。県立聾・盲学校 給食に異物混入28件(読売新聞)★3月1日追記 この問題に進展がありました。鳥取盲学校が2月29日に、「両校の給食の調理、配送業務の委託先を別の業者に変更する」と発表しました。 これまで委託していた業者が、「児童や保護者の不安を取り除く」として、契約の辞退を申し入れたためだそうですが、業者の辞退ではなく、学校や教育委員会が、もっと毅然とした態度で臨み、行政主導で契約を解除すべきではなかったのでしょうか。 再発防止策として、県の教育委員会は、「厚生労働省の大量調理マニュアルに沿った衛生管理が出来ている業者を選び、入札前に調理場を確認することを学校側に徹底する」としていますが、そんなこと、これまでだって、きちんとやっておいて当然だと思います。 ともかく、解決して、ほっとしました。盲、聾学校異物混入 給食委託先を変更(読売新聞)
2008.02.20
-
全盲の私に「パンツが黄色いんですけど」と教えてくれるやさしさ、トイレに積もった埃を見なかったことにしてくれるやさしさ
これは、全盲で一人暮らしの私の苦い思い出です。 不良障害者の私が、ひょんなきっかけで知り合った女性と気があって、いざ勝負!ということになった時に、「あのー、こんなこと言ってもいいかどうか分からないけれど、あなたのパンツ黄色いんですけど」と言われました。ちゃんと洗濯をしてあったのに、それは本当にショックでしたし、相手の人に不快な思いをさせたことが、申し訳なくて仕方がありませんでした。それ以来、勝負しそうな時には、必ず新しい下着を下ろすようにしています。しかし、何回空振りに終わったことか。(涙)けれど、私は、躊躇しながらも「パンツ黄色いんですけど」と教えてくれたその人に、心から感謝しています。彼女にとって、障害のある者と接するのは、その時が初めてだったそうです。「目が見えなくて下着の黄ばみに気付いていないのなら、教えてあげる方がいいのではないかと思って」と、後で話してくれました。いい人だなと、しみじみ思いました。 一方、以前の日記に関連して、とある知人が、「一人暮らしの全盲の人(私ではありません)の部屋に行った時に、トイレに埃が数センチ積もっているのを見て愕然とした。けれど、『目が見えないとはこういうことか』と思って、何も見なかったことにした」と、話してくれました。「何も見なかったことにした」のは、彼女のやさしさだったと思います。けれど、もしも私だったら、トイレに埃が積もっていたら、ぜひ「トイレが埃だらけだよ」と、はっきり教えてもらいたいと、切に願います。「目が見えないから仕方がない。見えないから掃除は無理」などと思われるのは、悔しくてたまらないからです。しかし、そのような場合にはっきりと教えてもらいたいかどうかは人によっても違うもので、教えたばかりに立ち直れなくなってしまう人だっているかもしれません。 「パンツ黄色いんですけど」と言ってくれた人も、トイレの埃を見なかったことにしてくれた知人も、それぞれのやり方で、目が見えない人に対して精一杯のやさしさをくれたのだと思います。 さて、私たち障害者は、どちらのやさしさに対しても、感謝をしながら受け止められるだけの度量と自立心を、ちゃんと持ち合わせているでしょうか。
2008.02.04
-

全盲・一人暮らしは苦悩する ~冷凍庫にギョーザはあるけれど?~
皆さん、ご無沙汰してしまいました。 これが今年初めての日記です。いつも沢山の皆様にお読み頂きながら、なかなか更新が出来ないことを、大変心苦しく思っております。不束者の私ですが、失礼を顧みず、今年もどうぞ宜しくお願い致します。ちなみに、あまりにも寒いので、ただいま「他人以上、恋人同然」になって頂ける方を、緊急募集中です。これまでの日記を読んで、「気があいそうだな」と直感してくださる方がいらっしゃいましたら、ぜひメッセージを送って頂けませんか。まずは、ご一緒に回転寿司でもいかがですか。もちろん、キスが大好きな女性が条件ですけれど。 さて、1月30日の夕方に勃発した中国産ギョーザの食中毒問題で、食品の自主回収がはじまりましたが、全盲で一人暮らしの私は更なる困難にさいなまれています。それというのも、テレビのニュースで伝えられる回収対象リストは字幕のみで、音声ではすべての品目を読み上げてくれないことが多いのです。品目が多すぎて、限られた時間内では紹介し切れないという放送局側の事情も理解出来ますが、視覚障害者にも、身近な情報源として、ラジオよりもテレビの声を頼りにしている者が大勢いることを、ぜひ知って頂きたいのです。インターネットにも回収リストが掲載されてはいますが、音声パソコンが利用出来る人の数はまだまだわずかですし、Webサイトのアクセシビリティ保障は、決して十分とはいえないのです。 そんな中、1月31日に放送されたテレビ朝日の「報道ステーション」では、業務用も含め自主回収リスト59品目のすべてを、画面にあわせ、アナウンサーの河野明子さんが、時間をかけて読み上げてくださいました。目が見えない者への配慮だったかどうかは分かりませんが、これには感動しました。一人の視覚障害者として、感謝の気持ちでいっぱいです。テレビ朝日さん、本当にありがとうございます! しかし、回収対象リストが分かっても、私の家の冷凍庫にあるギョーザがそれに含まれるかどうかを知るのは、並大抵ではありません。私が買い物をする時には、広いスーパーマーケットのどこに何が売られているかが覚え切れず、しょっちゅう店の中の配置も変わるため、「ギョーザがほしいのですが」などと店の人に頼んで棚から商品を取ってもらうことが多く、特にお気に入りの商品でない限り、どこのメーカーの何というギョーザを選ぶかは、店員さんにお任せなのです。メーカーや品名などをいちいち確認したり、確認出来たとしても、買った物全部の詳細情報を記憶して帰ることは、私の能力を超えています。現在、缶ビールのほか、一部のジャムやドレッシングの便には、品名を示す点字が付いていますが、冷凍食品の点字表示にはお目にかかったことがありません。ましてや、賞味期限や消費期限までを点字で表示した物はありませんし、そこまでやるとなると、技術的ハードルも高いと思います。そんなわけで、私には、私の冷凍庫にギョーザがあることは分かっていても、それがどこのメーカーの何という商品名かは、もともと知らないのです。たとえ自主回収される食品名がわかったとしても、それが自宅にある食品と一致するのかどうかを自力で知ることは、極めて困難です。 食品への点字表示が皆無の状況下、目が見えない私には、メーカーを信頼して口にする以外に、ほかに有効な手段がありません。回収するといわれても、視覚障害者ばかりでなく、お年寄りなど社会的弱者には、特に困難が付きまといます。 月並みではありますが、だからこそ、危険な食品を流通させるようなことをしてもらっては、絶対に困るのです。一度出回ってしまったら、回収などイレギュラーな事態への対応に苦慮する者がいるのです。食品メーカーには、改めて責任の重さをかみ締めてもらいたいと願うばかりです。★2月27日追記 このことについて、新聞で取り上げて頂きました。 これは、共同通信の配信記事で、今後、神戸新聞以外の加盟新聞社の紙面にも掲載されるものと思います。 実は、私自信、この問題についてブログを書きましたが、それだけでは視覚障害者への食の安全対策は実現出来ず、広く社会に問題を提起し、協力をお願いする必要があると考えました。そこで、共同通信文化部で生活家庭欄を担当している記者の方にお目にかかって、視覚障害者の実情をお話ししたところ、興味を持って取材してくださいました。 記事の末尾に、「社会がパニックになったとき、障害者は置き去りにされてしまうのではないか。命や安全にかかわる問題であり、告知方法のガイドラインなどを早急に整備すべきだ」と、私のコメントも掲載して頂きました。今後も、私の問題意識を、必要に応じて社会に対してフィードバックするような活動をしていきたいと、個人的に考えております。特にこの日記をご覧くださっているメディア関係の皆様、ぜひお力を貸して頂けましたら幸いです。ギョーザ事件で視覚障害者困惑 情報得られず(神戸新聞) ※お知らせ糖尿太郎は本を出版しています。 障害のある人とない人が共に生きる本当のノーマライゼーションとは何なのか、真のバリアフリーを実現するためにはどうすればよいのか、私と一緒にお考え頂けましたら、うれしく思います。
2008.01.31
-
「赤信号、みんなで渡れば怖くない」の裏側で
それは、決して珍しい経験ではありません。私のように、全盲で一人歩きをする者であれば、日常的に遭遇することです。 昨夜もそうでした。 白い杖の私は、とある横断歩道に差し掛かりました。 そこには、目が見えない私に「ピヨピヨ」や「カッコー」の声で青であることを教えてくれる音響信号はありません。そんな時、私たちは車のエンジン音や人の足音に神経を集中して、今渡ってよいかどうかを判断します。 昨夜は、大勢の人や自転車が、慌てる様子でもなく歩道を渡っていて、信号は「青」でした。 そこで、私が何のためらいもなく横断を始めると、 「信号、まだ赤ですよ!」と、見知らぬ女性が駆け寄り、慌てたような口調とともに、私の体を手で抑えてくれました。 「ありがとうございます」 お礼を言って待っている間も、沢山の足音が、「赤」と判明した信号を渡って行きました。 「信号は赤でも安全だから」と、それこそ自己責任なのでしょう。 あの女性が静止してくれなければ、私もそうしていたでしょう。 ただし、他の人と違うところは、私だけは青信号だと信じているところでしょう。 その結果、もしも私一人が車にひかれたとしても、それはやはり私の自己責任なのです。 昨夜の女性は一緒に青に変わるのを待ってくれましたが、時には信号を無視して無効から渡って来た人から、「赤ですよ」と注意して頂き、教えてくださったことには感謝しつつも、何とも複雑な思いに捕らわれることも少なくありません。 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」 の「みんな」に、私は含まれていません。私にとって赤信号は大いに怖いものですし、赤信号を無視して渡り、私を迷わせてくれる人は、輪をかけて恐怖です。 ルールを逸脱した「青信号」なのか、本当の青信号なのか、全盲の私には、どのような判断材料が残されているでしょうか。 「青になりましたよ」 さっきの女性がそう声をかけてくださり、今度は安心して渡り始めるまで、ふとそんなことを考えました。 どこにでもある、それはいつもの光景です。
2007.12.07
-
病院が全盲の入院患者を公園に放置 ~障害者に刷り込まれた「甘えのDNA」も問題では~
大阪の病院の職員が、63歳の全盲の入院患者を「引き取り手がいないから」と公園に置き去りにしていた、というニュースに、激しい憤りと驚きを禁じ得ません。全盲であろうがなかろうが、またどんな理由であれ、医療機関が患者を講演に放置するなど、絶対にあってはならないことだからです。 その点を確認したうえで、・患者は2年半も入院費を支払っていない・看護師に大声を上げるなど、病院とのトラブルを抱えていた等の関連報道が事実であるならば、本人や家族にも大いに問題があったのではないかと感じました。 この事件には、医療難民問題など、さまざまな背景があることと思います。しかし、理由はどうであれ、2年半も医療費を支払わないのは反社会的な行為だし、支払えない理由があったのなら、医療ソーシャルワーカーや行政に相談する等、打つべき手はあったはずです。また、看護師に大声を上げるなどは、トラブルの解決手段として、大人が取るべき方法ではないと思います。 憂うべきことに、世の中には、何でもかんでもすぐに格差社会や障害者の人権問題にすり替えて、無条件に政治や社会を批判しようとする人がいます。しかし、どんな世の中にも、法律や約束を守ろうとする精神に乏しい人、人に迷惑をかけてはいけないという規範意識の希薄な人がいます。「あれもこれも、格差社会のせいにすれば許される」、とでも考えているのでしょうか。このままでは、日本はとんでもなく困った国になってしまうのではないかと危惧します。電車にただ乗りしても、万引きをしても、「格差社会のせいなのだから、自分は悪くない」と、盗人猛々しい自己主張をする人が現れないとも限りません。いや、既に現れているのでしょうか。 そして、障害者の中には、心と体に「甘えのDNA」を刷り込まれ、「障害者なのだから特別扱いされて当たり前」と、自らの障害をまるで水戸黄門の印籠か何かと勘違いしている人、また、自分に都合がよい扱いは「福祉」で、そうでないことは全部「差別」なのだと、信じて疑わない人が少なくありません。何でも政治や社会、障害のせいにすれば許されると思ったら、大間違いです。 先天性の全盲である私がかつて学んだ盲学校の校長先生の口癖は「愛される盲人になりなさい。人から好かれる障害者になりなさい」でした。幼いころの私は、その言葉に強い抵抗を感じたものでした。 けれど、今になって、「それも生きるための一つの方法かな」と考えるようになりました。卑屈だと批判されるかもしれませんが、特に障害者の場合、人から好かれる方がずっと生きやすいというのは、紛れもない真実ではないでしょうか。この全盲患者も、日ごろの態度次第では、病院との協力の下に適切な解決策を見出せていたのではないかと、そう思えてならないのです。全盲患者を公園に放置=「引き取り手ない」と119番-入院先の病院職員・堺(時事通信)
2007.11.13
-

落語家・夢之助さん:「手話通訳気が散る」
島根県安来市が主催して開かれた敬老会で、独演会をしていた落語家の三笑亭夢之助さんが、舞台に立つ手話通訳者に「気が散る」などと退場を求める発言をしていたことが分かったのだそうです。 夢之助さんは、「落語は話し言葉でするもので、手話に変えられるものではない」「この会場は聞こえる方が大半ですよね。手話の方がおられると気が散りますし、皆さんも散りますよね」などと話し、会場からは笑い声が聞こえたといいます。 その後も手話通訳は舞台の下で続けられましたが、島根県のろうあ連盟は「聞こえない人に対する侮辱」と、夢之助さんと市に抗議し、両者がそれぞれ謝罪したということです。 全盲の私は、障害こそ違え、同じ情報障害を持つ者の一人として、また著述を生業とする者として、さまざまな思いが脳裏を巡りました。 話芸であっても、落語を楽しむ権利は、当然聴覚障害者に対しても保障されなければなりません。ろうあ連盟の抗議は当然です。それに、どんな催し物にも手話通訳が付くのが当たり前の世の中になれば、「気が散る」こともなくなるでしょう。 一方、表現者の一人として、「落語は話し言葉でするもので、手話に変えられるものではない」という夢之助さんの話芸への思いには、私にも共感出来るところがあります。 しかし、乱暴な言い方かもしれませんが、手話に変えられようが変えられまいが、何としても変えなければならないのです。話芸故の微妙なニュアンスを完全に伝えることは難しいかもしれませんが、それでも聴覚障害者への情報保障として、ベストを尽くすしかないのです。それは、目が見えない人のために、テレビや映画の情景を音声で解説するのと同じことです。100パーセントは無理でも、可能な限り伝える努力こそ、「情報のバリアフリー」への第一歩に他なりません。 しかし、主催者側にも、表現者への配慮は必要だったと思います。今回の場合、市は事前に夢之助さん側に手話通訳者のことを伝えていませんでした。私も、自分の講演に手話通訳が付く場合には、ぜひ前もって知らせてもらいたいと思います。そうでなければ、普段よりも心持ちゆっくり話す等、手話通訳をしやすくするための配慮が出来ないからです。 そして、表現者が気が散ることのないように、手話通訳者の立ち位置を考慮したり、落語という話芸をニュアンスまで含めて出来るだけ正確に伝えられるよう、経験豊富で優秀な手話通訳者を起用する等の努力を主催者側が惜しまないことは、表現者への礼儀ではないでしょうか。 これは、視覚障害者向けの録音図書の制作についても同様で、書き言葉の活字図書を、どのように朗読(音声訳)されるのかは、視覚障害者への情報保障について真剣に考えている著者であればあるほど、少なからず気になる点だと思います。朗読(音声訳)については、手話通訳士のように資格制度が整備されていないため、ボランティアのスキルはまちまちです。中には、とんでもなくへたくそな人まで、堂々とボランティアを名乗っています。ボランティアは決して気持ちだけでは勤まりません。活動に必要な能力やスキルがないのに、ろくな仕事も出来ないくせに、ボランティア風だけは立派に吹かせている人の、なんと多いことでしょう。学生時代に本を読むのが上手だった、というくらいでは、朗読(音声訳)のボランティアは出来ません。力を伴わず、自らの偽善に酔いしれるだけのボランティアなど、福祉目的で著作権を制限されている著者にとっても、へたくそな読みの作品を「これしかないのだから」と押し付けられる視覚障害者にとっても、迷惑旋盤以外の何者でもありません。そして、実力を伴わないのに、「ただ働きしてくれるから」と、利用者そっちのけでボランティアを甘やかし続ける点字図書館や福祉施設の御都合主義には、虫唾が走ります。 著者にとって、自分の作品は分身のようなものです。それを聞くに堪えない読み方をされたら許せないし、視覚障害者福祉のために、法律で著作権を制限するのなら、著作権法20条1項の同一性保持権(著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するための制度)を尊重し、著者の意に沿わない朗読(音声訳)を排除し、そもそも技術のない「自称・ボランティア」に対して、「だめ出し」をする権利くらいは、著者に認めてくれてもよいのではないでしょうか。 世の中、何事も一方の立場だけを主張しても、うまくはいきません。「情報のバリアフリー」の実現には、表現者の立場に最大限配慮しようとする姿勢が欠かせないのではないでしょうか。 今回のことについても、表現者としての夢之助さんへの配慮が決して十分ではなかったように思えてならないのです。落語家・夢之助さん:「手話通訳気が散る」島根の敬老会で(毎日新聞) ※糖尿太郎は本を出版しています。 『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル』 です。この日記との関連では、・受信料半額、情報半分の公共放送・くたばれ! ざーますボランティアなどの項目があります。あなたにも、ぜひお読み頂けましたら嬉しく思います。
2007.11.01
-
「さりげなく振舞う」というバリアフリー
皆さん、またまたご無沙汰してしまいました。お元気でしたか? それにしても、急に寒くなりましたね。熱いキスが心に染み入る季節です。(って、してないんですけれど・・) さて、東京の西新宿にある京王プラザホテルが、盲導犬や介助犬などの補助犬専用のトイレ施設を、ホテル業界として初めて設置したのだそうです。 従来はホテル2階の屋外にある植栽エリアの奥を盲導犬用トイレのスペースとしていましたが、雨の時に利用しにくいことなどから、新たな設置場所を検討し、平らな床面をもつ南館ロビーの外側にある公開空地のスペースに新設しました。 施設の設計、施工新設にあたっては、財団法人日本盲導犬協会をはじめ、三つの専門団体の指導を受けたといいます。 ところで、京王プラザホテルでは、以前から様々なバリアフリーへの取組みを、業界に先駆けて積極的に行っており、私自身も、数年前に、そのテーマでラジオ番組を制作し、マネージャーにインタビューをさせて頂いたことがあります。 当時は、目が見えない人が一人で宿泊しても困らないように、赤外線センサーを用いた館内の案内や、食事やワインなどのルームサービスの音声メニューなどが完備されていました。 「視覚障害のお客様に、安全で快適にご滞在頂ける様に、スタッフ一同で最大限の努力を払っています。でも、お客様の中には、プライベートなホテルライフを楽しみたい方もいらっしゃいます。ホテル側があまりに気にしていると感じて、お客様がかえって負担に思われるようなことになってもいけません。その辺りの兼ね合いがとても難しいのです」と、マネージャーがおっしゃっておられたことを思い出しました。 確かに、自称全盲のプレイボーイ・糖尿太郎も、「そっと事を成し遂げたい、さりげなくしたい」と願っているのに、白い杖が目だってしまい、周囲に過剰な印象を与えたり、いらぬ気遣いをさせてしまうことがあります。そーっと悪いこと(って犯罪じゃないですよ!)をしたくても、自らの障害に邪魔をされて、なかなか大変だったりもします。全盲のプレイボーイには、苦労が絶えないわけです。 「さりげなく思い遣ること」「知らないふりをして気遣うこと」「時には見ないふりをしてあげること」バリアフリーに限らず、全ての人間関係でそうありたいけれど、言うほどに簡単ではないかもしれませんね。ホテル業界初、補助犬専用トイレ施設を新設(PETWALKERニュース)
2007.10.16
-
障害者は罪を犯した人を更正させるためのモルモットではないのだけれど・・
皆さん、お久しぶりです。 長い間日記を書けなくて、すみませんでした。 さて、島根県浜田市に来年開設される民営刑務所で、受刑者が盲導犬育成の一端を担う矯正プログラムが導入される見通しになったのだそうです。 生命を慈しむ気持ちを育て、社会に貢献出来る喜びを体験してもらうのが狙いで、財団法人日本盲導犬協会と連携し、受刑者が、盲導犬の候補となる子犬に社会性を身につけさせる養育者として、散歩やしつけなどにあたることになる、といいます。 外国では、罪を犯した芸能人やスポーツ選手などに一定期間の社会奉仕活動が命じられた、というニュースが時々ありますね。 実は、もうずいぶん前のことになりますが、日本でも、交通違反者に、社会奉仕活動として、道路などで視覚障害者を誘導するボランティアをしてもらうことを検討している、というニュースがありましたが、あれはその後どうなったのでしょうか? 社会奉仕そのものは良いことだと思いますが、その案が実現すると、全盲の私は、道で交通違反者に誘導してもらう可能性もあるのです。 交通違反を犯す人には粗暴な人もいる訳で、そうした人に視覚障害者の命を託して誘導してもらおうなんて、行政の発想も少し粗暴ではないか、障害者は罪を犯した人を更正させるためのモルモットではないのだけれど・・、などと考え込んでしまったことを思い出しました。 今回の盲導犬育成プログラムにしても、「子犬に社会性を身につけさせる」というのですが、そもそも罪を犯した人の中には、社会性に欠けている人が少なからずいるはずです。 果たして、社会性に欠ける人が、犬に社会性を身につけさせるための養育者と成りうるのでしょうか。 このプログラムの実施に際しては、罪種や犯歴なども考慮して対象者の条件を詰めるとのことです。受刑者の更正を促すために障害者福祉が活用されることそれ自体に疑義を唱えるものではありませんが、その先にいる人、そこで育成された盲導犬を使用する視覚障害者のこともよく考えて、犬の訓練の質が決して下がることのないよう、慎重を期してすすめられるようにと、切に願わずにはいられません。受刑者が盲導犬育成、来年開設の民営刑務所で導入へ(読売新聞)
2007.09.22
-
障害者がプールでウンコ--利用者から悲鳴
※この日記には、人によっては「不快」と感じるかもしれない内容が含まれています。閲覧に際しては、その点にご注意ください。 新横浜駅の近くに、「横浜ラポール」という障害者のためのスポーツ文化センターがあります。 私も、会議のために何度か訪れましたが、そこには全盲の人も伴走者なしで走れる誘導ランニングマシンや、点字で得点を確認できるボウリング場などがあって、スポーツ好きの視覚障害者にも単独で利用出来る、数少ない施設です。 ところが!!このスポーツセンターにある屋内温水プールで、知的障害者など一部の利用者が排便するため、他の利用者から「不衛生なので止めてほしい」と、悲鳴が上がっているというのです。 更衣室のシャワールームで、介助者が水着に着いた汚物などを洗い流すために、悪臭が充満することがあったのだそうです。しかし、このセンターのプール利用規定では、オムツの取れていない乳幼児の利用は禁止しているものの、障害によるオムツ着用者は除かれているのだといいます。 障害のある人にも、もちろんプールで水泳を楽しむ自由があります。しかし、それは人に多大な迷惑を及ぼさない、という一定の制限の中での自由であり、権利ではないでしょうか。 もしも、障害のない人がプールで排便をしたら、その人は以後その施設に出入り禁止になっても仕方がありません。 障害のない人に対して許されないことなら、たとえどんな障害を持つ人にでも、障害者だからといって大目に見るべきではないと、私はそう考えます。 水泳中に排便の危険がある障害者は、そこが障害者用施設だとしても、他人の迷惑を考えて、当然プールの利用を遠慮すべきではないのでしょうか。 全盲の私は、汚れていることに気付かずに駅のトイレに入り、白い杖の先に汚物が付いてしまったことを知らないまま、目が見える友人との待ち合わせ場所に行って、はじめて杖に付いた汚物のことを知らされたり、電車の床に誰かが吐いた物に足を取られて転んでしまったことなど、おぞましい経験を重ねて来ました。その度に、「目が見えないって、どうしてこんなに辛いのだろう」と、必死で涙をこらえて来ました。 それだけに、プールで排便、などという話を耳にすると、「もう二度と横浜ラポールのプールには行けない」と、無条件にそう考えてしまうのです。 しかし、知的障害のある人やそのご両親は、「たとえ排便をする危険があるとしても、自分にも、うちの子にも水泳を楽しむ権利があるはず。そのためにこそ障害者スポーツセンターがあるのではないか」と考える人がいるかもしれません。 私はそのような意見には賛同出来ませんが、しかし、もしかしたら、それは視覚障害者である私の身勝手なのかもしれません。「他人には『歩道の黄色い点字ブロックの上に自転車を置くな』と強いるくせに、他の障害者がプールで排便することを我慢しないのは、視覚障害者のエゴイズムではないのか」と、批判を受けてしまうのかもしれません。 「障害のある人も、ない人も、皆同じ人間だ」と、口先でノーマライゼーションのお題目を唱えるのは簡単です。しかし、いざその理念を実現させようとなると、出来れば目を背けたいようなことを、いくつも乗り越えなければならないのです。どんなにいやなことからも決して目を背けず、絶対に逃げ出してはいけないのだと思います。タブーをなくして正面から話し合い、皆の理解を深めながらコンセンサスを得て、ひとつひとつ解決していくしかないのだと思います。知的障害者がプールでウンコ--利用者から悲鳴(毎日新聞)
2007.08.31
-

全盲の男性が酔って車を運転、1週間前に続き2度目!
取りあえず、ご安心ください。日本の出来事ではありません。 バルト海のエストニア南部の町の警察署は、20歳の全盲の男性が酒に酔って車の運転を試みているところを見付けて、逮捕したのだそうです。しかも、1週間前にも同じ行動を取っていたとのことで、今度は刑事立件される見通しだというのですが、そもそも1週間前にも同じことをしていたのであれば、どうしてその時に立憲しなかったのでしょうか。 日本でもありがちなことですが、相手が全盲だからといって、警察が処罰をちゅうちょしていたのだとすれば、障害者に遠慮して住民の安全を犠牲にした、取り返しの付かない逆差別以外の何者でもないでしょう。「障害は個性」「目が見えなくたって何でも出来る。心の目がある」とは、障害者を叱咤激励するためのスローガンのようなものです。しかし、実際には、車の運転ばかりでなく、目が見えないから出来ないこと、やってはならないことが、山ほどあるのです。心の目でよく見えるのは、人の心の中だけです。美しい心も見えますが、憎しみやねたみもよく見えます。 障害者と健常者の間に、決して超えられない大きなハードルがあることは、紛れもない事実です。だからこそ、乗り越えられないからこそ障害であり、福祉の恩恵が与えられているのではありませんか。第一、全盲の人が心の目で運転している車に、白い杖で歩いている全盲の私がはねられでもしたら、これはもう、しゃれになりません。 前回の日記で、目が見えないからといって、すぐに諦めてはならないことを教えてくれた、盲学校の田島先生のことを書きました。それと同じように、自らの障害を客観的に理解すること、どうしても出来ないことを、出来ないこととして受け入れる態度を養わせるのも、障害児教育の重要な使命だと考えます。出来ないからといって決して後ろ向きになる必要はない、人に助けてもらう勇気を持つことだって立派な自立なのだということをきちんと教えるのは、あきらめないことを教えるよりも難しいかもしれません。でも、逃げてはいけないのです。 学校も、両親も、障害者の可能性を教えるばかりでなく、障害故の限界や、障害があるからこそ絶対にしてはならないことを伝える教育にも、もっと積極的になって欲しいと願います。それも、障害者を強くするための、大切な視点だと思うからです。 さてさて、そうなると、「生きているうちに3000人の女性とキスをしたい!」という糖尿太郎の夢は、果たして追い続けても良いものか、諦めるべきか? うーん・・、謎は深まる!!全盲の男性が酔って車を運転、1週間前に続き2度目(CNN Japan) **糖尿太郎は本を出版しています。 あつかましいお願いですが、どうか応援してください。
2007.08.15
-
田島先生からもらったもの~目が見えなくても諦めない心~(長文です。ごめんなさい)
最近の学校給食はすごい!! リザーブ給食といって、前もって注文しておけば、好きなおかずを選べるというのです。しかも、選択肢は「うなぎのかば焼き」か「トンカツ」!!これはどう見ても、私、糖尿太郎よりもいいものを食べています。子どもの頃からそんなものばかり食べてると、それこそ糖尿になっちゃうぞー!! それはともかく、三重県内の公立小学校で、4年生の担任の男の先生が、おかずの数を間違えて注文してしまい、希望に反して「うなぎのかば焼き」を食べることになった児童のうち、給食に手をつけなかった7人を後で呼び、「誰にも言わないように」と、口止め料100円を渡したというのです。 そのことがニュースになっていて、記事には、「不適切な指導で、子どもや保護者に迷惑をかけ申し訳ない。教諭の処分は早急に検討する」と、教育委員会のコメントまで掲載されています。 確かに、子どもに口止め料を支払うなんて、褒められることではないかもしれませんが、大人の社会のしきたりを少し早めに教えただけ、あるいは、「仕事上のエラーにはペナルティが発生する」という現実社会の厳しさを、先生が身をもって実践して見せた、という意味で、教育的効果があったのではないか、とも思うのですが。 それにしても、そもそもこんなことがニュースになったり、こんなことで教諭が処分されるというのは、平和の証か、はたまた息苦しい社会の成れの果てと見るべきか、一体どちらなのでしょうね? ところで、私が子ども時代を過ごしたのは、地元の香川県立盲学校でした。盲学校は県内に1校しかなく、家が遠い子どもたちは、小学1年生から寮生活をしていました。私は母の送り迎えで自宅から通学していましたが、ほかの同級生は寮に入っていました。同級生が家に帰れるのは、毎週土曜と日曜だけ。お母さんに車で送ってもらい、週末まで家族に会えなくなるのが悲しくて、同級生の友達は、月曜の朝はいつも泣きじゃくっていたのでした。 ある朝、すごいニュースが盲学校を駆け巡っていました。何でも、前の晩遅くに、寮の小学生が、宿直の先生と一緒に屋台のラーメンを食べに行ったというのです。七夕の夜に、寮生の一人が「一度でいいから、屋台のラーメンを食べてみたい」と点字で書いた短冊を目にした先生が、門限を破って、願い事をかなえてくれたのでした。おそらく、同じ敷地内の寮と学校を往復するだけの子どもたちを、たまには世の中の風に当ててあげようと考えた先生が、夜遅くにそっと連れ出してくれたのでしょう。盲学校の児童の家庭には、経済的に困窮している世帯も多く、外食の経験はその時が初めてだと、はしゃいでいた友達も少なくありませんでした。今だったら、そんなことでも、規則違反で教諭が処分されたり、最悪、新聞記事になってしまうかもしれません。 思い返せば、あの頃の盲学校には、良い意味での自由がありました。 総勢3名の私たちのクラスを、小学1年から4年まで担任してくださったのは、盲学校での経験の長い田島先生というベテランの女性教諭でした。田島先生は、徹底して私の好奇心に応えてくれました。幼い頃から落ち着きがなかった私は、たえずそこら中をがさごそして、何かを見付け出しては「これなぁに?」と、尋ねるような子どもでした。 ある日、先生の机の引出しから栓抜きを見付けた時のことです。例によって「これなぁに?」と尋ねる私に、「それは栓抜きだよ。ジュースの便の栓を抜くものだよ」と言うが早いか、どこからかジュースの瓶を持って来て、「ほら、やってごらん」と渡してくれました。しかし、当時の私は栓抜きを使った経験がなく、どうしても栓が抜けないのです。すると、先生は、「ほかのお勉強はしなくていいから、栓が抜けるようになるまでずっと練習をしなさい」と言って、自分で栓抜きを使えるようになるまで、指導してくれたのでした。栓抜きの時は、確か3日くらいかかったのではなかったかと記憶しています。半泣きになりながらやっと栓が抜けた時、それはそれはうれしかった!!「お母さん、僕ね、栓抜きが使えるようになったよ。ジュース持って来て」と、得意げに抜いて見せたことを、今でもはっきりと覚えています。 田島先生の「出来るまでやりなさい」のおかげで習得したことは、ほかにも沢山あります。硬貨を触って識別すること、靴紐のチョウ結び、点字のトランプでの馬場抜き、そして、ワープロが普及した今ではもう使わなくなりましたが、カナタイプラリターも、田島先生が作ってくれたテープの教材を聴きながら、必死で練習をして、両親にカタカナの手紙を書きました。目が見える人との意思疎通がどんなに楽しいかを教えてくれたのも、田島先生でした。そして、「そんなこと、自分で出来なきゃ困るやろ。いつも人に頼んで換えてもらうつもり?誰もいなかったらどうするの?」と先生に発破をかけられ、指を真っ黒にしながら、カナタイプライターの印字用リボンの交換も、自分で出来るようになりました。珍しいところでは、当時流行っていたフラフープ、なんていうのもありましたっけ。 こうして、出来なかったことが一つ出来るようになる度に、「ほら、出来たやろ。隆ちゃん、目が見えなくたって、頑張ったら何でも出来るようになるんやで。諦めたらいかんのやで」と、激励し続けてくれた田島先生こそ、私の原点です。 けれど、どうしても出来ないこともありました。包丁を使ってのりんごの皮むきは、怖くてものになりませんでした。「僕、りんご嫌いやから、みかんしか食べん」負けず嫌いな私は、その言葉通り、今でもりんごが好きではありません。箸を使う練習も、途中で投げ出してしまいました。もちろん、りんごの皮むきも、箸を上手に使うのも、たまたま私には出来ないだけで、全盲の人でも、うまくこなせる人はいくらでもいます。 いずれにしても、子どもの関心に即して目標を決め、達成出来るまで続けさせるという田島先生の指導法は、私に自信を与え、何でも簡単に諦めてはならないことを、身をもって体験させてくれたのでした。 文科省の指導要領に照らして、この教育法が適切なのかどうか、私には分かりません。しかし、それは少人数の盲学校だからこそ出来ること、個々の子どもを大切に育てるための貴重なノウハウではなかったかと、今でも感謝しています。 残念なことに、最近の盲学校では、数年に一度は行われるという教員の人事異動のため、視覚障害児教育のたたき上げのような先生が、ほとんどいなくなってしまったようです。 統合教育の進展が目覚しい今だからこそ、視覚障害児の専門教育機関として、盲学校(視覚特別支援学校)が担うべき役割は、ますます大きくなっているのではないでしょうか。
2007.08.12
-

全盲のカップルがギネスに挑戦?キスの世界記録を樹立!?
以前に、出会い系チャットで、音声パソコンを使って話した 女性に、私の目が見えないことを打ち明けた時、 「大変ね。全盲じゃ、キスもしたことないんでしょ?」 と大真面目に言われて、ぶっ飛んだことがありました。 だって、私はお好み焼きの次にキスが大好きで、3千人の女性と キスをするまでは絶対に死なないと、心に固く 誓っているのですから。 (ちなみに、現在11人!!) しかし、世の中には 「全盲の人にはキスが出来ない。 何故なら、相手の口がどこにあるかが見えないからだ」 そんなことを言う人がいたとしても、疑わない人の方が 多いのでしょうか? こうなったら、視覚障害者でもキスが出来ることを 証明するために、相手の口がどこにあるかが見えない同士の 全盲のカップルにギネスブックに挑戦してもらって、 キスの連続世界記録、13日と16時間27分6秒を 樹立してもらうしかありませんね。 そして、健常者がそんなことをしても、単なる暇人扱いなのに、 全盲のカップルだったら、 「全盲なのにギネスに挑戦なさるなんて、なんて ご立派なのでしょう!!」 「無心にキスを続けるお二人のお顔が明るく前向きで、 思わず涙があふれました。素晴らしい勇気をくれて、 ありがとう!!」 と、人々から賛美され、新聞は新聞で、 「目不自由のハンディを超えて、キスの世界記録を樹立 ~実家の母、感涙~」 とか、書いてくれるのかな・・。 そんな極端なことにはならないにしても、障害者が何かをすると、 普通に考えれば大したことではないことでも、 「偉い!」 「立派!」 「障害のある人から勇気をもらった!」 になることが多いと思いませんか? それって、障害者はよっぽど何も出来ないと思われているのか、 はたまた、この世の中は、需要の多さに比較して、感動や 美談の供給が著しく不足しているか、ですよね。 案外、こんなことも起きるかもしれませんね。 <偽のキス募金で全盲の容疑者逮捕> 警視庁新宿署は、JR新宿駅西口などで、視覚障害者に キスを普及させるなどと偽って支援を呼びかけ、 実体のない寄付金をだまし取ったとして、町田市の著述業、 川田隆一容疑者(46)を、3日までに詐欺罪で逮捕した。 調べによると、川田容疑者は、先ごろキスの世界記録を樹立した 全盲カップルへの社会的関心の高まりに着目し、 「日本障害者キス普及協会」という架空のNPO法人を名乗って 街頭に立ち、 「死ぬまでに一度でよいから、目が見えない人にも キスの感動を味わわせて欲しい」 などと呼びかけ、2週間で延べ5千人から、計6873000円余りを 詐取した疑い。 川田容疑者自身も全盲の視覚障害者で、同署では、詐取した 金は主に豊島区内のフェチシズム専門の風俗店で、 容疑者自身が女性従業員との濃厚なキスに興じるために 使ったものとみて追求している。 社会福祉法人 日本盲人連合会の話。 「全盲カップルによるキスの世界記録樹立への感動を 逆手に取った犯罪で、同じ視覚障害者として断じて許せない。 当会としては、今後も視覚障害者にキスを普及させるため、 広く社会の理解を得ながら、健全な活動を続けていきたい。」 (社会部・神田真紀子) ※この日記を「面白い!」と感じてくださった方には、私が書いた本『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル』が、もっと面白いこと請け合いです。ぜひ、お目通しください。**本書の収益金の一部は、日本障害者キス普及協会には寄付されません。
2007.08.03
-

犯罪こそ障害者を差別しない、むしろ真っ先に狙う!
昨日(7月31日)のことでした。 夜の9時すぎに、神戸市中央区のマンションで、52歳になる全盲でマッサージ師をしている男性が、エレベーターに乗ろうとしたところ、後ろから来た犯人に首を絞められ、肩から提げたかばんを奪われそうになったのだそうです。 しかし、全盲の男性が大声を上げたため、犯人は何も取らずに逃走し、マッサージ師はあごに軽いけがをした、といいます。 事件を報じた新聞記事には、男性の声を聞いて現場にかけつけた人の、「目の見えない人を襲うなんてひどい」との談話が掲載されています。 この記事を読んで、以前にアメリカの視覚障害者団体の全国大会を取材した折に、視覚障害者がどうやって犯罪から身を守ればよいか、理論と護身術の実践を教える、「セルフディフェンス」という有料の講習が行われていたことを思い出しました。 アメリカの目が見えない人たちは、お金を払ってまで、犯罪から身を守る方法を習得しているのです。「まさか、犯罪者が視覚障害者を狙うなんて」私が感想を漏らすと、「どうしてそう思うんだい。犯罪者は弱い者から順に狙うのが当たり前じゃないか。残念ながら、視覚障害者は健常者よりも弱いと思われている。健常者よりも先に狙われるとしても、何の不思議もない。だから僕たちは、自分で身を守る手段を学ぶんじゃないか」と、アメリカの視覚障害の友人から、そう反論されました。 事実、私がアメリカで生活した1年間でも、路上やバス停で、「小銭をくれ」と声をかけられた経験は数知れません。 また、渡米直後の私は、外出の際に牛革のショルダーバッグを携帯していたのですが、それを見た研修先の職員から、「高級そうな牛革のバッグを持ち歩くのは、犯罪のターゲットにされる危険度を上げることになりかねないので、やめなさい」と注意を受け、近くのショッピングセンターで、いかにも安そうに見える布製のバッグを買って来てくれたことがありました。この経験を通じて、アメリカの人たちが、犯罪のターゲットになる危険因子を取り除こうと、日常的に神経を遣っていることを痛感しました。 アメリカでは、全盲の人でも、犯罪歴がなければ銃の購入が許可されます。私がアメリカの妹のようにかわいがっている全盲の女の子は、常に護身用にナイフを携帯しているといいます。(日本においては、ナイフを携帯すると、銃刀法に抵触する場合があります。) 日本でも、「水と安全はただ」というのは、既に古きよき時代の思い出です。 先日、インターネットのブログを閲覧している折に、電車で見かけたという全盲の若い女性に対して、「あんなに美人で盲目の彼女は、一体何回強姦されるのだろう」と、書いたものがありました。同じ障害を持つ者として、心無い書き込みが悔しくて、涙が出ました。しかし、不謹慎だと怒ることは簡単ですが、「全盲の女性であれば強姦してもばれないだろう」と考える、心が腐り切ったやからが、この日本に少なからず存在することは、残念ながら事実でしょう。「強姦は犯罪です。ましてや全盲の女性を狙うなんて人間じゃない!」と訴えても、壊れた心の持ち主には何の効果もありません。 強姦に限らず、「全盲の障害者なら、顔を見られなくて済むから捕まりにくいだろう」と考える大ばか者がいても、何ら不思議ではないし、実際、相手の特徴を把握しにくい全盲の者に対する犯罪の謙虚が困難を極めるであろうことは、想像に硬くありません。現に、全盲の人をターゲットにした犯罪は、これまでにも多数発生しているのですから。 わが国においても、「今後、障害者をターゲットとした犯罪が確実に増加する。犯人は弱い者から順に狙うのだ」という前提に立って、障害者がどのようにして犯罪から身を守ればよいかを系統的に訓練するカリキュラムの実施について、警察当局や障害者福祉の専門機関が連携して、真剣に検討しなければならない段階を迎えているのではないでしょうか。 もちろん、人通りの少ない危険な場所に行かないことは、健常者にも必須の基本的な対策です。 ただ、障害者が犯罪被害を受ける危険が増しているといって、「それなら、とにかく障害者を外に出さなければよいではないか」と、私たちを社会から排除しかねないような対策だけが幅を利かせることも、決してあってはならないと思います。若い男?全盲男性襲う かばん奪えず逃走 神戸(神戸新聞) ※この日記を読んで、私のことをもっと知りたいと感じて くださった方は、ぜひ私の著書『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル』 にもお目通し頂けましたら幸いです。
2007.08.01
-
失言報道が偏見の増幅になっていないか? ~全盲の私の体験から~
安倍内閣の閣僚の失言が止まりません。 かつて、森喜朗元首相が、衆院選の演説で「無党派層は寝ていてくれればいい」と発言して、ひんしゅくを買ったことがありましたが、安倍内閣の閣僚の場合、次に何を言い出すか分からないので、遊説を中止して、参院選が終わるまで、全員夢の島で魚釣りでもしていてもらう方が、与党にとって有利なのではないかと、そんないやみのひとつも言いたくなりました。 そして、先週は、失言の矛先が、病気と闘っている人にまで向けられました。 皆さんも、既にご存知のことと思いますが、麻生外相が、日本のコメの中国への輸出再開に関連して、「アルツハイマーでも分かる」と述べた一件です。 外相の発言が的確さを欠いていたことに、議論の余地はないでしょう。 私が気がかりなのは、閣僚の失言を報じる過程で、「アルツハイマーでも分かる」という発言が、マスコミによって増幅され、結果として、この病気の人に対する偏見を、全国にばら撒いてしまうことになったのではないか、という危ぐなのです。 失言報道を通じて繰り返し流される「アルツハイマーでも分かる」という言葉に、病気と闘っている人やそのご家族は、少なからず傷付けられたのではないでしょうか。そして、病気の知識を持ち合わせない人の心に、新たな偏見を植え付けることになってはいないでしょうか。 これは、今回のこととは多少異なる私の経験です。全盲の私が中学生のころ、ラジオのニュース解説者の一言に心をえぐられました。「毛沢東の経済政策は○○同然だった」と、視覚障害者に対する3文字の差別語を使ったのです。 この場合、「○○」は、目が見えないという身体の特性ではなく、“能力がない”ことのひゆとして使われていました。これに限らず、身体機能の一部を失っている障害者のことを、能力や判断力にも劣っている、と誤解している人が、決して少なくありません。私は、中学生にして初めて、ラジオ局に抗議の電話をかけました。「無能な経済政策を、視覚障害者に例えるのは、やめてください」と、お願いしました。今回の一件でも、マスコミも野党も、実は外相の失言を喜んでいるだけ、攻撃の道具にしているだけで、病気で苦しんでいる人やその家族の心情など、これっぽっちも慮っていないのではないでしょうか。 民主党の鳩山幹事長が、「あまりにも軽はずみで、人の気持ち、特に病に侵されている方々の気持ちをまったく理解していない。とても許されないことだ」と批判する談話がテレビで流れていましたが、その言葉には、病気の人に対する思いやりなど、何も感じられませんでした。「外相も悪いけれど、鳩山さん、あなただって病気の人の心情なんてまったく理解していないのではありませんか。病気の人に名を借りて、与党を批判したいだけではないのですか。本当に言いたかったのは、あなたの次の発言『安倍首相の任命責任も含めて断固抗議したい』だけではないのですか」と、テレビに向かってツッコミを入れたくなりました。 閣僚の失言も、有権者の選択にとっての大切な情報です。だから、メディアが具体的な発言内容を伝えるのは必要なことでしょう。 しかし、それだけでなく、この機会に、アルツハイマーとはどのような病気で、最新の治療研究はどこまで進んでいるのか、といった報道を加えるなど、社会啓発にも紙面を割くことは出来ないものでしょうか。そして、野党も、ただただ批判に終始するだけでなく、例えば、民主党は、アルツハイマー病の対策として、どのような制作を提案しているのか等、病に侵されている人への思いやりを政治に活かすための党としての取り組みを示すべきではないでしょうか。 発言を批判するだけでいいなら、私にだって出来ます。 政治家なら、民主党に本当に病気の人を思いやる気持ちがあるのなら、感情論だけでごまかさず、具体的な施策を示して当然だと考えます。■麻生外相「アルツハイマー」発言、民主・鳩山氏が批判(読売新聞)
2007.07.23
-

「ナルちゃんのお部屋」は、障害者がお相手する風俗店です! ~自己満足なあなたを偽善の快楽へとご案内~
前回の日記「全盲の僕をネタに喧嘩をしないで。優先席の“立て立て攻撃”は、独りよがりの善意だ!」に寄せられたこんなメッセージに、カチンと来ました。(引用は原文通りではありません) 「座席を譲ろうとしたおじいさんから『わしはそんな歳じゃない!』と言われたら、『お元気そうで何よりですね』と話をしながら、いつのまにかその人が席に座るように仕向けます。言ってしまった言葉の自尊心を傷付けないようにしながら。」 一見、優しさにあふれているようですが、席を譲ろうとしたおじいさんは「わしはそんな歳じゃない!」と、辞退しているのです。 いや、おじいさんが遠慮しているだけかもしれない、と言われるかもしれませんが、それを考え始めたらきりがありません。ここは、相手の言葉を信じるしかないのです。 それなのに、> 『お元気そうで何よりですね』> と話をしながら、いつのまにかその人が席に座るように> 仕向けます。 なんて、まるで子どもをあやしてでもいるかのようですね。 それとも、催眠術でしょうか? 相手を傷付けなければ、上手に言いくるめさえすれば、その人の意思や自己決定権を犯しても構わない、とでも言うのでしょうか。 > 言ってしまった言葉の自尊心を傷つけないようにしながら。 こういうのって、人を上から見下ろしているようではありませんか? 自分が人として当たり前だと思っても、相手が望まないことを 無理やり押し付けるのは、迷惑以外の何者でもないと思います。「わしはそんな歳じゃない!」そう言って辞退しているのなら、「そうですか」と、自分が席に戻るか、一度立った席に戻りにくいなら、場所を移動すればよいだけのことです。 それなのに、しつこく座ることを共用するのは、一体だれの自尊心を守ろうとしているのでしょうか。 守りたいのは、席を譲ろうとした自分自身の自尊心以外の何者でもありません。 怒らせなければ、喧嘩をしなければ、自分の思い通りにしても構わない、と言わんばかりに振舞うことこそ、偽善者ではないでしょうか。 世の中には、障害者や高齢者を相手に“善行を押し付けて”自己満足したい人、自己陶酔に浸りたい人の、何と多いことでしょう。 いっそのこと、障害者が従業員として働く風俗店でも開店しましょうか。 店の名前は、「ナルちゃんのお部屋」! ナルちゃんのナルは、もちろんナルシストのナルです。 何をされても、どんなことを言われても、 「ありがとうございます。あなたのおかげで、私は救われました。 あなたにとっては人として当たり前のことでしょうが、 私はあなたから勇気と生きる希望を頂きました。ははー!!」 と、障害者のコンパニオンが、嘘涙を流しながら床にひれ伏して、ひたすら感謝をし続けるお店です。 そして、お相手をする従業員の座る椅子は、決して後ろには回転しません。「障害者は明るく前向きに生きている」と、健常者には明るく前向きでない人が山ほどいるのに、障害者にだけ、そんな幻想を押し付けるお客様の夢を裏切らないよう、お相手をする障害者の椅子は決して後ろに回転しないように固定してあるのです。 更に、「ナルちゃんのお部屋」には、シチュエーション別にいくつかの部屋があります。例えば・・。○「幸せのお部屋」 健常者の方々のブログを読んでいると、障害者を主題としたドキュメンタリーや映画を見て、「あんな大変な人たちだって、頑張って生きているのだ。それに比べれば、自分は五体満足で幸せだ!」と、障害者を通して、自らの幸せを再確認しているという人が少なくないようです。 そこで、「幸せのお部屋」では、当店の色々な障害を持つコンパニオンが、あなたを取り囲み、「盲目の私に比べれば、あなたはとても幸せです。目がお見えになるなんて、なんと素晴らしいことでしょう!恋人やお母さんの顔を見られるなんて、あなたは夢のように幸せな方です!」「音が聞こえるなんて、あなたのことが羨ましくて仕方がありません」と、口々に自らの障害を悲しみ、障害を持たずに生まれて来られたあなたのことを、障害者が心をこめてお癒しするお部屋です。○「ボランティアのお部屋」 世の中には、仕事や人生に行き詰ると、「ボランティアでもやってみようか」と、現実逃避の先に、ボランティアを選ぶ人が大勢います。 しかし、ボランティアとてリアルの世の中と同じで、技能やスキルがなければ、気持ちだけでは出来ないものがほとんどです。 けれど、ご安心ください!このお部屋は違います。 たとえ、朗読ボランティアなのに難しい漢字を読めなくても、パソコンボランティアとは名ばかりで、特別な勉強もせず、障害者のパソコンをぼこぼこに壊してへらへらしていても、コンパニオンは決して文句など申しません。 ただただ、「私がこうして生きていられるのは、ボランティア様閣下のおかげです」と、床にひれ伏してお礼を申し上げるだけです。 そうそう、このお部屋には、現実世界を模した仕掛けもございます。 それは、ボランティア役のお客様には、真ん中のソファーでふんぞり返って頂き、障害のあるコンパニオンは、隅の方でお客様のお顔色を恐る恐る見上げながら、お気を悪くさせないように、手をすりすりしながらお相手致します。 障害者の就職は依然厳しい状況が続いていますので、雇用創出も兼ねて、「ナルちゃんのお部屋」を、歌舞伎町の一角にでも立ち上げてみるというのは、いかがでしょうか。 なお、「ナルちゃんのお部屋」では、サービスの企画を募集しています。 こんなシチュエーションの部屋を作ってみてはどうか、自分はこんな風に健常者を癒して差し上げたいのでぜひ雇って欲しい、私はこうやって癒されたい、というアイデアやご希望を、聞かせて頂けませんか。 但し、「ナルちゃんのお部屋」は健全な風俗店で、女性のお客様も大歓迎ですので、性的な書き込みは厳禁です。 ※この日記を読んで、私のことをもっと知りたいと感じてくださった方は、ぜひ私の本『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル』にもお目通し頂けましたら幸いです。
2007.07.18
-
全盲の僕をネタに喧嘩をしないで。優先席の“立て立て攻撃”は、独りよがりの善意だ!
全盲の私は、電車に乗る時には、極力優先席に近寄らないようにしています。けれど、それがどこにあるのかが分からず、図らずも優先席の前に立ってしまうこともしばしばです。私は目が見えないだけで、足腰が不自由な訳ではありません。たまたま席が空いていれば座りたいけれど、全盲というのは人を押し退けてまで座らなければならない障害ではないのです。 「目が見えないと、乗り物の中でバランスを崩しやすい」と言う人もいますが、だからといって座席に座る必要はない、手すりかつり革につかまっていればよいだけのことです。 そもそも、絶対に座らなければ安全を確保出来ないと言うのであれば、その人は、ラッシュ時の乗り物を利用することを避けるべきです。何故なら、優先席が設けられているとはいえ、席を譲るかどうかは座っている人の自発性に委ねられており、優先席とはいえ、それを必要とする人の着席を100パーセント保証するものではないからです。 そして、私が何故優先席を避けたいかというと、白い杖を持って優先席の前に立ってしまうと、それだけで目の前に座っている人に対して、席を譲れという無言の圧力になりかねないからです。 もちろん、どなたかが立ってくださろうとした時には、「大丈夫ですから」と辞退し、それでも譲ってくださる場合には、感謝しつつ座らせて頂くようにしています。 それよりももっと困るのは、私の近くに立っている見知らぬ人が、優先席に座っている人に向かって、この私に席を譲るようにと騒ぎ出すことなのです。 「おい、お兄さん。目の前の白い杖が見えないのか。かわいそうだろう、立ってやれよ」 「なに聞こえないふりをしてるんだよ。立ってやれって言ってるんだよ」 こんなやり取りが始まる時、全盲の私のために席を譲れと促す人は、そもそも私が本当に座りたいのかどうか、聞いてくれたためしはありません。 私の頭越しに、「目が見えない人に席を譲ってやれ」、「いや、自分だって疲れているのだから」と、乗客同士の言い争いが始まると、それを聞かされている私は、とても悲しくなってしまうのです。 「僕は目が見えないだけだから、座らなくても大丈夫ですから、そんなことで喧嘩をするのはやめてください」 居たたまれなくなって私がそう言うと、後に残るのは何とも言いようのない気まずさだけです。多くの障害者が、自分のために旅客同士が言い争うことなど、決して望んではいないでしょう。それは、喧嘩のネタになっている障害者には、とても惨めで、悲しいことだからです。 優先席について、先日、日記の読者の方から、こんなコメントを頂戴しました。(文章は加筆してあります。) 「この前、バスの中で盲導犬を連れている人を見ました。びっくりしたんです。優先席ってのに若者が座って、その前に盲導犬を連れている人が立っているのに、よけもせず、3人ぐらいで周りを囲んで話をしていたんです。誰も声をかけていませんでした。それで、私が言ったんです。『あなたたち。ここはどんな席なのか分かってるの?目の前の盲導犬を連れている人を見て、席を譲らないとはどうゆうことなの。席を立ちなさい』と言うと、若者は『あ?優先席って書いてあるだけで、座ってはいけないとはどこにも書いてないぞ、どこに書いてある?』『あなたたちは学校で何を習ってるの?ただ学校に行ってるだけじゃないでしょうね?常識を知りなさい。犬が人に踏まれているでしょう』『うるせえよ。こっちだって疲れているんだよ、学校行っててよ』『そんな問題ではないでしょう』って私がそう言ったら、運転手さんが放送で『学生のお客様、席をお譲りください。でなければ、降りて頂きます』って行ってくれて、周りの人も『そうだ、そうだ』と言いはじめたんです。言う勇気、声をかける勇気が必要なのかもしれないけど、見て見ぬふりだけはしたくないと思います。障害者の方には、『同情でしょ?』って言う人が多いかもしれません。でも、それは同情ではない、当たり前のこと、自然のことなんです」 このコメントのどこにも、当の盲導犬同伴の目が見えない人の気持ちはどうだったか、ということは出て来ません。自分が元で客同士が言い争うことを、席を譲らない人に「譲らないなら降ろすぞ」と脅してまで、目が見えない人は本当に座席に座りたかったのでしょうか。 もしも私がその立場だったら、「自分は立っているから、お願いだから僕をネタに喧嘩をするのはやめて!お願いだから、僕をそっとしておいて!」と、心の中でそう懇願したことでしょう。 それに、席を譲らないからといって降車を強制することは、いくらなんでも行き過ぎた処置だと思います。これでは、まるで人民裁判ではありませんか。席を譲らないことは犯罪ではないし、譲らない人にも、当然基本的人権があるはずです。 たとえ善意であれ、バスの乗客が、同じ立場の乗客に、「席を立ちなさい」と、“命令”する権利はないでしょう。若者が言うとおり、優先席は席を譲ることを法律で義務付けているのではありません。あくまでも自発的なボランティア精神に期待しているのです。 それに、世の中には外見では分からない障害を持っている人が大勢います。心臓ペースメーカーを使っている人や内臓疾患の人など、見た目は元気な健常者と変わりなくても、重篤な障害を持っている人も少なくありません。 また、妊娠している女性の中にも、お腹が目立ちにくいために妊婦さんと気付いてもらえず、優先席に座っていると、いつも白い目で見られてしまう人もいます。 このままでは、そんな人たちまでもが、正義の味方気取りの乗客から「席を立ちなさい」と迫られ、下手をしたらバスからつまみ出されてしまうのです。 「そんな時には、『自分も障害者です。妊娠しています』と言えばよいだけのことではないか」と言われるかもしれませんが、自身の障害を見知らぬ人に打ち明けることには、概して心理的な抵抗を伴うもので、「障害のことを言わずに済ませられるものならそうしたい」、と考える人を、一概に責めることは出来ません。 上に紹介したバスの中の若者だって、何らかの障害を持っているため、座席に座っていたかったけれど、自らの障害については言えなかったのかもしれません。 「そんなことはない。私が見れば分かる」 善意の乗客はそうおっしゃるかもしれませんが、専門的な医学知識がなければ、その人の障害の有無を見極めるのは、極めて困難でしょう。 バスの若者に何らかの障害がある確立は低かったかもしれませんが、だからといってその可能性を無視しても構わない、ということにはなりません。何故なら、そもそも障害者に対する思い遣りというのは、とりもなおさず、少数者を大切にすることだからです。若者が障害者である可能性が低いからといって切り捨ててしまったら、それ自体が矛盾になるからです。 また、障害がない人でも、とても疲れていたりして、どうしても座っていたいという人のことも、それがその人の判断であれば、尊重すべきではないでしょうか。 優先席に座っている人に対して 「席を立ちなさい」と言っていいのは、その人の身体的特性や健康状態を十分把握している両親や親族のみで、通りすがりの人が軽々に強制すべきことではありません。 私がアメリカで生活をしていた時、バスには特別な優先席などはなかったけれど、必ず誰かが席を譲ってくださいました。それは決して、他人に促されたり、脅されたりして、しぶしぶ立つのではなく、当然、自分の意思で、自発的な気持ちに基づいて譲ってくれるのです。 日本の乗り物の優先席も、あくまでも自らのボランティア精神で座席を譲るものであり、決して人から強制されたり、逆に人に立つことを強要すべきものではないと思います。 だって、電車やバスは、教育の場ではありません。 子どもに思い遣りを教えるのは、家庭教育の責務ではないでしょうか。
2007.07.02
-
全盲の男性が橋から転落死~同じ全盲の私には決して他人事とは思えません~
またも、悲しすぎる事故が起きてしまいました。 京都市右京区にある橋から、近所に住む全盲で66歳の 鍼灸マッサージ師の男性がおよそ4.6メートル下の川に転落し、 病院に運ばれましたが、残念ながら間もなく死亡されたのだそうです。 警察は、全盲の男性が、誤って高さおよそ56センチの 欄干を越えて落ちたとみて調べているといいます。 死因は虚血性心不全で、全盲の男性が、橋の欄干近くで心臓発作を起こし、 そのまま川に落ちたのではないかとみているようです。 また、男性は、仕事の行き帰りなどの慣れた道では、 目の不自由な人が使う白い杖ではなく、短めの杖を使っていたともいいます。 全盲の私には、この事故を決して他人事とは思えません。 男性が心臓発作を起こしたことや、短めの杖の使用と 事故との因果関係について、私には それを知るすべがありません。 しかし、日ごろから歩き慣れた道であればあるほど、 ついつい気が緩んでしまうものです。 それに、56センチの欄干は低すぎて、勘違いをして またいでしまう危険性もあります。 同じような状況になれば、私だって 転落してしまうかもしれないのです。 第一、56センチという低い欄干では、子どもだって 落ちてしまう危険はないでしょうか。 目が見える人でも、心臓発作を起こしてしまったら、 歩行が不安定になり、低い欄干を踏み越えてしまって、 そのまま川に落ちてしまわないでしょうか。 では、こうした事故を二度と繰り返さないために、 どのような対策が必要なのでしょうか。 全国の橋の欄干を一定の高さにして、落ちにくく するように、関係法令の改正を求める運動でしょうか、 それとも、欄干の手前に点字ブロック等で危険を知らせること、 もしくは、もっと別の安全対策が必要なのでしょうか。 いずれにしても、視覚障害者の全国団体は、早急に 意見を集約し、社会や行政に対して強力なアピールを すべきであると考えます。 行政が、当事者不在の的外れな安全設備を導入して しまうことは、決して珍しくはありません。 視覚障害者のために、押しボタン式の音響信号が 出来たのはいいけれど、肝心の押しボタンがどこに あるのか、目が見えない人には分からないことが あります。実際、少し前に、私の住まいの近くにも 新しい音響信号機が設置されましたが、私はつい最近まで、 そこに音の出る信号が出来たことにすら気付いて いませんでした。私のためにボタンを押してくれる人は 誰もいなかったし、市の点字広報で音響信号の 新設について読んだ訳でもなかったからです。 また、街のところどころにある点字表示についても、 そもそも目が見えない人には、そこに点字表示があることが分からない、 という笑い話のような現実があります。 当事者不在のまま、ちぐはぐな安全対策が 講じられてしまうのは、何も行政だけの問題ではありません。 積極的に行政に働きかけようとしない視覚障害者団体、 普段の移動には秘書や奥さんなどに介助してもらえる 恵まれた視覚障害者を役員に祭り上げている運動団体の 実にやる気のない体質にこそ、大きな矛盾があるように 思えてなりません。 安全対策を行政に任せっ切りにしておいて、 意味を成さない施設や設備が出来てしまってから文句を 言い募るのではなく、私たち視覚障害者自信は 歩行の安全のためにどうしてもらいたいのか、 何をして欲しいのか、その点をはっきりと社会に 意思表示することこそ急務であると考えます。 しかし、法律や設備の改善には、予想以上の 時間がかかるのです。 今日からでもすぐに出来る対策は、ひとりひとりの 視覚障害者が、これまで以上に注意を払いながら 歩くことしかないのかもしれません。 私的には、たとえ普段から歩き慣れた場所であっても、 短めの杖ではなく、きちんとした白い杖を 正しく使うべきだと思います。 結局のところ、自分の安全は自分で守るしかないのですから。 やっぱり、目が見えないって辛いですね。 障害って悲しいですね。 だからこそ、痛ましい事故を繰り返さないように、障害者自信が、 世の中に向けて、もっと大きな声を上げなければ ならないのです。 そして、その声は、広く健常者の賛同を得られる ものでなくてはいけないし、健常者が私たちの声に 耳を傾けてくれなければ、理解と応援を得られなければ、 障害者の安全な生活の実現は有り得ないことだと思うのです。 末筆ながら、亡くなられた方のご冥福を、心より お祈り申し上げます。 鍼灸マッサージ師が転落死 右京区 帰宅途中の橋で(京都新聞電子版)
2007.06.24
-
女子プロレスラーを目指す盲学校の高校生!
宮城県立盲学校の高等部普通科に、 なんと!将来はプロレスラーになりたいと願う 弱視の女子生徒がいるのだそうです。 そして、盲学校の担任の先生が、その気持ちを応援してあげようと、 友人の同級生とともに女子プロレス団体 「センダイガールズプロレスリング」の道場に 連れて行ったというのです。 盲学校の卒業生の進路といえば、90パーセント以上の人が 鍼灸按摩マッサージ師の道に進みます。 全ての生徒が、好きでその道を選ぶ訳ではありません。 日本の視覚障害者の職業は、一部の例外を除いて、 極めて限られた選択をせざるを得ないのです。 そんな中、 「プロレスラーなんて、視覚障害者には無理に決まっている」 と言わずに、生徒の夢を膨らませてあげようとした 盲学校の担任の先生の心配りに感服しました。 たとえレスラーは無理でも、鍼灸按摩マッサージの資格を取得して、 プロレスラーのトレーナーとして働く道だってあるのですから。 道場では、「リングに上がりたい人はいる?」との呼びかけに応えて、 生徒が選手と一緒にストレッチをしたり、 リングやロープの感触を確かめたりもしたのだそうです。 盲学校には、生徒の自活を後押しするための 自主的な授業があり、その時間を活用して、 生徒をプロレスの道場に連れて行ったのだといいます。 さて、全国の盲学校の先生方は、時として突拍子もない 生徒の夢と真っ向勝負をしてくださっているのでしょうか。 残念ながら、ただただ 「そんなこと、目が見えない人に出来っこない」 と、生徒の夢を叩き壊すことだけに奔走している 教師の方が多いと思います。 障害者の夢をつぶしているのは教師だけではありません。 大学を卒業する時に マスコミへの就職を望んでいた私に、 ハローワークの障害者援助の担当者は、 「マスコミなんて、健常者にだって難関なんだよ。 視覚障害者なんか無理に決まってるじゃない」 と言い放ちました。大学で同じゼミだった学生からも、 「私たちだって就活に苦労しているのに」 と同情されたものです。 どうやら健常な人たちは、 「障害者は常に自分たちよりも劣る存在。 自分たちに出来ないことを、障害者に出来ようはずもない」と、 本気で信じているようです。 大学を卒業して早20年。 しかし、同じゼミだった学生の全てが、 私よりも豊かな人生を送っているとは思えません。 仕事の成功や人生の潤いを左右するのは、 決して障害の有無ではないことを、 時の流れが証明しています。 だからこそ、障害を持つ若い生徒の夢を壊さないで欲しいのです。 たとえ無理でも、はじめから聴く耳を持たない 教師によって無造作にあしらわれるのと、 自ら経験して「やっぱりこれは無理かな」と思うのとでは、 生徒の情操への影響が大きく異なるのではないでしょうか。 困難な現実を目の当たりにして、 「なにくそっ、負けるもんか!!」と思えば、 ひょんなことから道が開けることだってあるのです。 盲学校の先生には、「簡単にはあきらめない。 すぐに弱音を吐かない」という人生の鉄則を、 ぜひ生徒に教えて頂きたいと願うものです。 けれど、よくよく考えてみれば、その盲学校にこそ、 すぐにあきらめたり、何事も障害のせいにして、 ひたすら弱音を吐きまくる、温室育ちの目の不自由な教師や、 図らずも盲学校に配属されたけれども、 次の人事移動で普通校に戻れることだけを夢見て、 点字の勉強などやる気なし、という健常の教師が なんと多いことでしょう。 自らが人生を投げているような大人に教育されるほど 不幸なことはありません。 せめて、障害児の両親だけは、 いつまでもわが子の可能性を信じ、 夢の味方でいてあげて欲しいのです。 仙女に勇気もらった 宮城県盲学校女子生徒が道場見学(河北新報)
2007.06.20
-
目が見えないから、夏合宿で女子学生と混浴!?
時々この話を思い出すと、いつも複雑な思いがよみがえります。 全盲の私が初めて目が見える生徒と共に学んだのは、 一浪した時に通った大学受験のための 予備校でのことでした。 それ以前に、高校卒業までの12年間を 過ごした盲学校では、中学1年までの同級生が3人、 その後転校した東京の盲学校でも14人が最高でした。 それが予備校に変わると、いきなり200人以上の生徒と共に、 大教室に放り込まれたのです。 講師がマイクを使って授業をすることからして、私にとっては 少なからずカルチャーショックでした。 しかも、そこは通常の教育の場ではありません。 生徒同士が食うか食われるかの受験競争を強いられ、 目が見えない私はさぞや苦労をするだろうと、 覚悟して飛び込んだのでした。 しかし、それは取り越し苦労でした。 初日のオリエンテーションで出席カードが配られると、 隣の席の女性が、 「代わりに書きますから、名前を教えてください」 と声をかけてくれました。 そして、 「同じクラスだから、よかったらこれからずっと 私が隣の席に座りましょうか。 お手伝い出来ることがあったら、何でも言ってくださいね」 とまで。 戦場だと思ってあきらめていた予備校にも、人の温もりがありました。 私を遠巻きにして見詰めていた他の生徒の中にも、 講師が板書する内容を読み上げてくれる人、 通学の道中でさりげなく手を貸してくれる人、 中には、予備校のテキストの 朗読をしてくれる人まで現れたのです。 私が予備校をずる休みした時など、 通学途上で事故にあったのではないかと心配して、 予備校の職員を巻き込んでの大騒ぎになり、 下宿まで探しに来てくれたことがありました。 さすがにあの時は、予備校のチューターから 「君がいないと、みんなが心配するから、 休む時には必ず友達に連絡してください」 と、散々叱られたものでした。 もちろん、最後まで遠巻きに見詰めるだけの生徒も 大勢いましたが、あたたかい仲間のおかげで、 私は健常者と共に生きる心地よさを知り、 その後の大学生活に対する不安を 払拭することが出来たのでした。 翌年、無事に大学に進学した私を待ち受けていたのは、 授業のテキストを点訳してくれるボランティアを探すための 綱渡りのような生活でした。 日本語のテキストの点訳はまだしも、 必須科目の第2外国語として履修した ドイツ語のテキストの点訳者を見付けることは、 並大抵ではありませんでした。 しかも、私はこのドイツ語の単位を落としてしまったのです。 不幸なことに、再履修した翌年は テキストの内容が変わってしまったため、またまたドイツ語テキストの 点訳者を探す羽目になってしまったのでした。 そんな私の教科書の点訳の多くを担ってくれていたのは、 学内の「点訳会」というサークルの 学生ボランティアのみんなでした。 私自身も在学中はずっと点訳会に所属し、 目の見える学生に点字を教えたり、 点字図書館や盲導犬訓練施設の見学に出かけるなど、 視覚障害者福祉についても共に学びました。 もちろん、学内の他のサークルと同様に、春や夏になると 泊りがけの合宿にも行っていました。 その事件は、夏合宿の準備をしている時に起こりました。 4年生の目が見える女子学生が、その年に入部した 1年の女子を集めて、ちょっとしたいたずら心で こんなことを言ったのだそうです。 「点訳会の活動は、実際にうちの大学に在学中の 目が見えない学生も一緒に参加しているのが とても有意義なの。 特に合宿は、視覚障害者と共に生活をすることで、 彼らの日常生活の苦労を知るのが大きな目的なの。 それでね、視覚障害者にとって、 初めて泊まる場所で一人でお風呂に入るのは、 とても大変なことなの。 うちのサークルには、全盲の男子学生がいるのに、 目が見える男子が少ないでしょ。 それで、点訳会では、伝統的に 全盲の部員がお風呂に入る時には、家族風呂を借りて 新入生の女子に介助してもらう慣わしになっているの。 嫌だと思うかもしれないけれど、私も1年生の時には 全盲の男子学生と一緒にお風呂に入ったのよ。 あなたたちにもそうしてもらいたいのだけれど、 これは強制出来ることではないから、 どうするか、明日までに考えておいてくれるかな・・」 と。 確かに、視覚障害者にとって、初めて訪れる場所で 一人で行動するのは、苦手なことの一つです。 特に大浴場などの場合には、白い杖を持つことがためらわれ、 空間認識がうまく出来ずに、困ってしまいます。 私は温泉が大好きです。 けれど、一人では大浴場での移動が困難で、 足元も滑りやすいため、男性の同行者がいなければ、 かえってストレスになってしまいます。 それはそうなのですが・・、 だからといって、「新入生の女子が介助する 慣わしになっている」、というのは、 あまりにぶっ飛んだ発想です。 少なくとも、それまでの点訳会の合宿で、 そのようなことは一度もありませんでした。 これは、先輩一流の冗談だったのですが、 「明日までに考えておいて」と言われた新入生の女子にとっては、 人生の一大事だったようです。 翌日皆で部室にやって来て、こう言ったのだそうです。 「あのー・・、昨日のお話ですけれど・・、 みんなで相談したんですけれど・・、 視覚障害者のお力になれることなら やってみようということになりまして・・」 と、思い詰めたような表情で そう答えてくれたのだといいます。 この話を聞いて、当時の私は、 非常に複雑な思いにとらわれました。 単純に、「面白いことを考えたな」と、 くすっと笑いたいような気持ちと、 「いくらなんでも、視覚障害者をねたに そんな冗談を言うのは酷いじゃないか」 という二つの思いでした。 それと同時に、悩みに悩み抜いた末に 「視覚障害者のお力になれるのなら、やってみます」 と答えてくれたという1年の女子に対する 感謝の思いがこみ上げて来ました。 「なんていい子たちなのだろう」と、涙が出そうでした。 もちろん、実際にはありえないし、あってはならないことですが、 それでも、そう応えてくれた1年生に、胸が熱くなりました。 障害者には何が出来て何が出来ないか、そしてどんな手助けが必要か、 個人差が大きいこともあって、世の中の多くの人たちは その答えを知りません。 そして、知らないのをいいことに、必要以上の援助を求めたり、 セクハラ紛いのことをする障害者がいないとも限りません。 また、障害者にとっては真に不可欠な援助であったとしても、 性別や考え方によって、依頼された人が その援助を拒否する自由も担保されるべきだと思います。 障害者への理解が希薄であるからこそ、 もっと沢山の情報を社会に発信しなければならないし、 理解不足を悪用して過度な要求をすることのないよう 障害者同士の自浄作用も不可欠でしょう。 そして、障害者の尊厳が尊ばれなければならないのと 同様に、援助に当たる人たちの尊厳も、最大限に守られなければなりません。 障害のある人とない人が、こうした前提に立って、 問題を解決しなければならないのだと思います。 それにしても、私は本当に幸せ物です。 予備校で、大学で、あんなに優しい仲間たちに 勉学を支えてもらったのですから。 「入浴介助事件」も、今となっては 懐かしい青春の思い出です。
2007.06.10
-
「目の不自由な女好き」って、全盲の僕のこと!!?
いつものように音声パソコンでインターネットのニュースを読んでいると、 「目の不自由な女好き」 という見出しが、耳に飛び込んで来ました。 「えーっ、ついに視覚障害者が女性専用車両で 痴漢でもして捕まっちゃったかな!?」 と、慌てて本文を開いてみると、何のことはない SMAPの草なぎ剛さんが主演する 『山のあなた~徳市の恋~』という映画で、 草なぎさんが、目の不自由なマッサージ師の徳市を演じることになった、 という内容でした。 なんでも、徳市は目が不自由で、勘が鋭く女好き、 負けず嫌いでプライドが高い、という設定のようです。 この映画が封切られる直後には、 本物の視覚障害者に対しても、 女好きで、負けず嫌いでプライドが高いと 思い込む人が増えるかもしれませんね。 何しろ 「盲導犬というものは全て『クイール』という名前だ」 と、信じて疑わない人もいるそうですから。 草なぎさん主演の作品ばかりでなく、 最近、視覚障害者が主役として登場する映画は、 わりと沢山ありますよね。 『暗いところで待ち合わせ』という作品では、 田中麗奈さんが演じる目が不自由な女の子が 一人暮らしをしている家に殺人犯が忍び込む、 という内容でしたね。 フィクションですからどんな設定にしようと自由でしょうが、 「いくら目が見えなくたって、家に人が忍び込んだら分かるよ。 これは、視覚障害者に対して失礼じゃないか!」と、 一人で憤慨した糖尿太郎ではありました。 どうも、ドラマや映画に出て来る視覚障害者は、 めちゃめちゃ前向きで何でも出来るスーパーマンか、 失明して絶望のどん底を這いずる不幸の象徴のように描かれるかの 両極端が多いようです。 事実、悲劇の主人公は、よく失明させられています。 『冬のソナタ』のヨン様も最後には失明しましたし、 古典的名作の『赤い疑惑』でも、 ヒロインの幸子は一時的に目が見えなくなってしまいました。 このほかにも、不幸を演出するために視覚障害者が 駆り出されるドラマは、いくらでもあります。 そこで、私の本『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル~』では、 ●悲しみの演出、ドラマで失明なら一人500万円 という項で、 「テレビ局は役柄を一人失明させる度に、 障害者団体に番組協力費として500万円ずつ支払うとかしてもらわないと、 感動のネタに使われている障害者としてはたまったものではない」 と書いたのですが、これはまんざら冗談ではありません。 そして、当たり前のことですが、障害者にも、 明るい性格の人、そうでない人、 女好きの人、あまり興味のない人と、色々な人がいます。 困ったことに、障害者のイメージを一定の方向に誇張するのは、 何も映画やドラマばかりではありません。 現実の社会でも、障害者対象のボランティアをしているという人の中には、 「障害者は皆明るくて前向きだ」 と言ってはばからない人が大勢います。 しかし、本当にそうでしょうか? 本当にそうだと思いますか? 考えてもみてください。 たとえば目の病気で少しずつ視力が低下している人が、 いつまでも明るく前向きな気持ちのままでいられるでしょうか。 もちろん、根っから明るくて、前向きな障害者も沢山います。 しかし、それと同じように、無理をして明るく前向きな 自分を演じ続けている障害者も少なくないはずです。 そうしなければ、健常者から親切にしてもらえないから、 暗い性格では社会に受け入れてもらえないから、 本当は不安で不安でたまらないのに、世の中の人たちが期待する 偽りの障害者像を演じ続けている人も 多いのではないでしょうか。 世の中には「障害は個性だ」と言う人がいます。 そして、その口の端が乾かないうちに、 「障害者はみんな前向きで明るい」 と続ける人もいます。 しかし、障害が本当に個性なら、後ろ向きで暗い性格だって 個性のはずです。健常者には暗い人、後ろ向きな人がいくらでもいるのに、 障害者にだけは明るく前向きであることを強いる風潮が、 日本の社会に蔓延しているように感じるのは、 そして、それを助長しているのは 一部の心無いボランティアではないかと疑っているのは、 私一人でしょうか。 草なぎ剛 70年前の名作に挑む(デイリースポーツ)
2007.06.06
-
少女漫画家の田中美菜子さんって?
こんばんは。 少女漫画家の田中美菜子さんという方が、ご自身のブログ「書いてますよ田中の日記」の5月27日の日記で、「怒っておられます」と題して拙著『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル~』を紹介してくださいました。寝る前に、私の本を読んでくださっているのだそうです!田中さんは、集英社の『マーガレット』などに連載しておられるようです。目が見えなくても漫画が大好きな人が沢山いて、漫画を朗読してくださるボランティアグループもあるのですが、私は漫画について何も知りません。どなたか、田中美菜子さんはどんな感じの漫画家さんなのか、ぜひ教えてくださいませんか。
2007.05.28
-
命を無駄にする閣僚の任命責任は?
不明朗な事務所光熱費問題で追求を受けていた松岡利勝農相が、辞任ではなく自殺を選んでしまいました。そこまでして守りたかったものとは、一体何だったのでしょうか。 昨年10月に施行された自殺対策基本法では、 国と自治体、事業主などに対して、自殺対策を講じる責任を明確にしており、政府の現職閣僚として、松岡農相にも自殺防止に努力する義務があったはずです。そんな立場にある人自身が自殺などして、一体どうするというのでしょうか。これでは、最後まで自分のことしか考えない政治家だった、と批判されても仕方がありません。 もちろん、人の命の重さに違いはないけれど、教育者や政治家の自殺は、子どもたちの心にも暗い陰を落とすことでしょう。安倍首相は、自らの命すら大切に出来ない閣僚を任命したことの結果責任について、国民に対して率直に謝罪すべきではないでしょうか。 松岡農相のご冥福を心からお祈り申し上げます。
2007.05.28
-
究極の選択!午前3時ニ吠える犬か、全盲の障害者の一人暮らしか?
隣の家で飼っている犬の鳴き声が うるさいからといって、殺してしまった長野県内の男が、 動物愛護法違反と器物損壊の疑いで、 書類送検されたのだそうです。 いくら泣き声がうるさいからといっても犬に罪はない、 我慢出来ないなら飼い主に文句を言いに行くべきだ、と思うのですが、 実はこの話、決して他人事ではないのです。 何を隠そう、私こと糖尿太郎のマンションの 隣の部屋にも飼い犬がいて、困ったことに、 毎日午前3時になると、決まってワンワン!と吠えるのです。 飼い主の若いご夫婦が引っ越して来られたのは、 ちょうど1年前の今頃でした。 夜、私の部屋のチャイムが鳴ったので出てみると、 お隣の奥さんが、お菓子を持って 引越しの挨拶に来てくださっていました。 短いご挨拶の後、 「私は目が全く見えません。 ご迷惑をおかけすることは何もないとは思いますが・・」 と言うと、奥さんは何のことだか分からない様子でしたので、 玄関の脇に立てかけてあった白い杖を取って見せながら、 「目が全然見えないんです」 と繰り返しました。 夜で暗かったせいか、お隣の奥さんは、 私の目のことには気付いていなかったようでしたが、 努めて冷静な様子で 「じゃ、今日は奥さんはお留守なんですか?」 と尋ねられました。 どうやら、全盲の私と、健常者の妻が 一緒に暮らしていると思ったようです。 そこで私が 「いいえ、一人暮らしです」 ときっぱり応えると、今度ばかりはよっぽど驚いたのか、 お菓子を押し付けるように渡して、すたこらさっさと 部屋に戻ってしまったのです。 私にとって、奥さんの逃げるような態度は、かなりショックだったのですが、 マンションを管理する不動産屋さんは、隣に住んでいる私が 全盲の一人暮らしであることを、このご夫婦に 一言も伝えていなかったようです。 そりゃあそうでしょう、もしも伝えたら、 このマンションは、私の部屋以外 がら空きになってしまうかもしれませんからね。 引っ越し先の隣の住人が、全盲の 中年男性の一人暮らしだと知ったときの 二人の悲しみは、いかばかりだったでしょうか。 せっかく新天地に引っ越して来たのに、お隣のご夫婦にとっては 人生が真っ暗になってしまったでしょうか。 全盲で火は大丈夫か、 もしかして毎回ごみ出しを手伝わされてしまうのではないか、 目が見えないから、間違えて自分たちの部屋に入ろうとしたりしないか・・、 と、不安が心を駆け巡っていたかもしれません。 実際、単身の視覚障害者が部屋を借りようとすると、 大家さんや不動産屋さんから、障害を理由に 入居を拒否されることは珍しくなく、私も過去に 何度か辛い経験をしています。 やはり火のことが気になるようですが、 それを最も心配しているのは、とりもなおさず視覚障害者本人です。 私の部屋には、音声付ガス漏れ警報機と 消火器を買い求めてあります。 といっても、私の場合には セブン-イレブンに食料品を預けてありますので、 コンビニから買って来た弁当を暖めるために、 電子レンジを使っており、ガスを使うのは、 レトルトの糖尿病食をお湯で暖める時くらいです。 実際、視覚障害者の世帯で 火災発生率が高いという統計データは、 私の知る限りどこにもないようで、 火災保険の加入を断られたことは一度もありません。 とはいっても、視覚障害者のことを知らないお隣さんにとっては、 さぞや不安なのではないかと想像した次第です。 私の生活に異変が起きたのは、 それからしばらく経ってからのことでした。 どこからともなく、犬の鳴き声が聞こえてくるのです。 それも、何故か毎日午前3時頃になると、 決まってワンワンと吠えるのです。 最初は、近くの一戸建て住宅の人が 犬を飼い始めたのかなと思っていましたが、 泣き声があまりに近いので、 おそるおそる壁に耳を当ててみました。 悪い予感が的中しました。 泣き声は、明らかに隣の部屋のものでした!! 壁を隔てて、私の2メートル以内で吠えているようです。 しかし、ここは、マンションといっても、 壁は薄く、どう見ても犬を飼えるような部屋ではないのです。 こんな所で犬を飼うなんて、一体何を考えているのだろう、 そう思って、すぐに大家さんに文句を言おうと思ったのですが、 二つの理由で思い直しました。 一つは、私にとって隣の部屋の犬が 毎日午前3時に吠えることは愉快ではないけれど、 隣のご夫婦にとっては、隣室に全盲の障害者が 一人で暮らしていることの方が、私が感じる不愉快の 何倍も不安なのではないか、と思い至ったのです。 犬の鳴き声がうるさいと文句を言ったら、 「そんなことを言っても、隣に全盲のあなたが 一人暮らしをしていることの私たちの不安よりは、ずっとましでしょう」 と、逆に言い返されてしまうのではないかと、 心配になったのです。 自分の気持ちをうまく表現出来ないのですが、 「隣に住んでいるのが、全盲の私でごめんなさい。 不安を感じさせて、ごめんなさい」 と、隣室のご夫婦への後ろめたさのような 感情があるのです。 そして、もう一つの理由は、私の部屋にはいませんが、 目が見えない知人の中には、盲導犬と一緒に暮らしている人がいます。 特に都会のマンションでは、盲導犬に排便をさせるための 苦労が絶えず、近隣住民から文句が出て、 しょっちゅう引越しをよぎなくされている人もいます。 世の中の人たちに盲導犬を理解してもらいたいなら、 同じ視覚障害者として、お隣の犬の泣き声についても 我慢すべきではないのか、 盲導犬なら部屋で飼ってもいいけれど、ペットはだめだ、 と言うのは、視覚障害者のエゴではないか、 そう考えたのです。 あれから1年。 隣の部屋にいる犬は、相変わらず 午前3時になると、ワンワンと元気に吠えてくれます。 私は夜中に原稿を書きながら起きていることが多いので、 泣き声で起こされてしまうこともなく、すっかり慣れっこになりました。 そして、この1年間で、隣の奥さんとは もう一度だけお話しをする機会がありました。 その犬は雄の子犬で、とても気が荒いのだといいます。 奥さんも泣き声のことを気にしているようで、 入居前に大家さんから許可をもらったのだと話してくれました。 「いいですよ。僕、犬が大好きですから」 と、ここは物分りの良い隣人を演じているのですが、 そんな私の心に、前述した後ろめたさのような気持ちが ないといえば嘘になります。 突然ですが、ここで究極の選択です。 あなただったら、どちらを選びますか? 隣の犬が毎日午前3時に吠える居住環境と、 隣の住人が、365日・24時間、 全盲の一人暮らしという部屋? さてさて、今夜もそろそろ あの犬がお出ましになるころあいです。 <隣家の飼い犬>「鳴き声うるさい」と殺す 長野で書類送検(毎日新聞)
2007.05.24
-
弱者に弱い“人権国家”
「拳銃は置いて来てくれたんだよね、ありがとう」 愛知県長久手町の立てこもり事件で、容疑者逮捕の瞬間、猫なで声のネゴシエーターは、拡声器でそう言いました。これが、こんな腰抜けが、自分が生まれ育った国の警察の姿かと思うと、情けなくて涙と怒りがこみ上げて来ました。将来ある若い警察官が、その男の拳銃で撃ち殺されているのに、新婚の妻と生まれたばかりの子どもを残して、仲間の命が奪われたのに、当の容疑者に向かって、「拳銃は置いて来てくれたんだよね、ありがとう」は、いくらなんでも、言ってはならない言葉ではなかったでしょうか。 警察は、「容疑者との心理戦のために、寛容な態度を示さざるをえなかった」、と言うかもしれません。しかし、テレビの生中継を通して、日本中の人々があの屈辱的なシーンを見せられたのです。「日本という国は、人を撃とうが、警察官を射殺しようが、容疑者を“安全に保護”してくれる国なのだ」との印象を社会全体に与え、新たな凶悪犯罪を誘発しないと、だれが保証出来るというのでしょうか。 無論、国民の人権を守ることは、政治の使命でしょう。しかし、批判を覚悟であえて言います。拳銃で4人も撃った容疑者の人権よりも、もっと守らなければならないものが、他に沢山あります。 被害者よりも加害者の人権が重んじられる国、凶悪犯でも、精神鑑定の結果次第では罪に問わない国、こんなでたらめな国のどこが“人権国家”なのでしょうか。 そして、この国の間違った人権意識は、何も犯罪の加害者に対してだけではありません。私たちの社会に、「泣く子と障害者には勝てない」といった風潮はないでしょうか。社会的弱者の人権を尊重することと、弱者であることを悪用した行き過ぎた要求までも「ご無理ごもっとも」で通してしまうことを、時として混同してはいないでしょうか。 私自信、一人の人間として、一人の障害者として、本当に守るべきものは何なのか、これからも真剣に考えていくつもりです。 最後に、殉職された林警部のご冥福を、心よりお祈り申し上げます。
2007.05.20
-
僕を生んでくれて、育ててくれて、本当にありがとう!
「ごめんなさい。お母さんが一生あなたの両目になります。 だから、許してください」 それは私が生後3か月の時のことでした。 いないいないばーをしても全く笑わない私を見て、 両親が目の障害を疑い、眼科に連れて行きました。 そして、私には先天性白内障という目の病気があり、 目が見えないままにしておくと知能が遅れてしまう、 という眼科医の言葉を鵜呑みにして、すぐに手術を受けさせる 決心をしたのだそうです。 しかし、生後3か月の赤ちゃんに術後の安静を守れるはずもなく、 手術は失敗に終わり、私は今の今まで、 目が見えるということがどういうことなのかが分からずにきてしまいました。 冒頭の言葉は、当時母が書いた育児日記の一節です。 私が大人になってから、母が読み聞かせてくれました。 母は妊娠中に風疹にかかり、 そのせいで私の目が見えなくなったと思い込んで、 ずっと自分を責めていたようで、育児日記は 自責と当惑にあふれていました。 「おかん、ありがとう。 目のことは、もういいよ。 おかんが謝ることじゃないよ。 僕を生んでくれて、育ててくれて、本当にありがとう!」 母を思いきり抱きしめて、心からの感謝の気持ちを伝えたいのですが、 なんだか照れてしまって未だに出来ないままでいます。 「私ね、神様から宝物を預かったと思って、 あんたのこと育ててきたんよ。 私にだったら育てられると思って、 神様が私を選んであんたをくれたんだと思って、 ずっと育ててきたんよ。 もしも彼女のご両親が、 『障害者にはお嫁にあげられない』と言うんなら、 そんなのこっちからお断りよ」 27歳になった私が、職場で知り合った健常者の彼女との 結婚を考えている時、母はそう言ってくれました。 幸い彼女のご両親は、私たちの結婚を 心から祝福してくれました。 けれど、いろいろなことがあって、その後私たちは離婚しました。 人生、ドラマのようにうまくはいかないものです。 けれど、私は、私の父と母の元に 生まれて来ることが出来て本当によかったと、 心から感謝しています。 熊本の病院の「赤ちゃんポスト」に、 3歳とみられる男の子が預けられていたことが 分かったのだそうです。 その子は、自分の名前と年齢を答え、 「新幹線に乗って、お父さんと来た」 と話しているといいます。 この子が大人になっても、赤ちゃんポストに預けられた 3歳の日の記憶が消えることはないでしょう。 両親の責任を問う声に、私も同感です。 しかし、預けられた子どもには何の罪もありません。 どんな形であれ、とにかく、かけがえのない 命が救われたことに、まずは胸をなでおろしたい思いです。 世の中に、自ら進んでわが子を手放したい親など いるはずがない、私はそう信じたいのです。 「赤ちゃんポスト」のニュースは、 自分自身の幼い日の記憶を呼び起こします。 今は愛しいわが子を預けてしまったけれど、 この子のご両親にはいつの日か必ず迎えに行ってあげて欲しい、 「お父さん、お母さん、僕を生んでくれてありがとう」 この子にもそう言わせてあげて欲しいと、心から願わずにはいられません。 関係者の皆さん、どうか大切に育ててあげてください。 赤ちゃんポスト:初日に「3歳」男児が預けられる 熊本(毎日新聞)
2007.05.15
-
子守歌なら歌えるけれど、私は全盲だから目を見詰めてあげられない
全盲の私が、大学を卒業して 初めて就職したのは、電話相談をビジネスに変えた ベンチャー企業でした。 驚いたことに、500人程の社員や相談員は全て女性で、 私はその会社にとって初の男性社員として 迎えて頂いたのです。 また、視覚障害者の採用も初の試みだったのですが、 現場のスタッフの間には、目が不自由な人に対する シンパシーのような感情が流れていました。 それというのも、この会社の主力商品である育児電話相談には、 活字の育児書を読むことの出来ない目の不自由な母親からの 相談が、私が入社するよりもずっと以前から多数寄せられており、 保健師や看護師である相談員の中には、視覚障害者の生活実感を 理解しているスタッフが大勢いたのです。 例えば、子どもが病気かもしれないと言う母親に、 「顔色はどうですか?便はどんな色ですか?」 と問いかけても、目が不自由な人には意味をなしません。替わりに 「泣き声はいつもと同じですか? 便に触ってみてください。 普段より柔らかいですか?どんなにおいがしますか?」 と、視覚障害者の立場を理解して相談に応じて来たため、 その会社の電話相談を頼りに子育てに励む 視覚障害を持つ両親が少なくなかったのです。 ところで、政府の教育再生会議は、 親に向けた子育て指針として、11日に発表する予定だった 「『親学』に関する緊急提言」の発表を、 「国民への教育観の押し付け」、 「政策的な裏付けがない」などの 反発や批判に配慮して、先送りすることに 決めたそうです。 この提言には、保護者に子守歌を励行することや、 「おっぱいをあげ、赤ちゃんの瞳をのぞく」などが 要請されているようです。 しかし、耳や言葉の不自由な人の中には、 子守歌を歌えない人もいます。 全盲の私が父親になっても、 赤ちゃんの瞳をのぞいてあげることは困難です。 提言では、母乳を与えられない母親の立場に考慮し、 「母乳が十分出なくても、抱きしめるだけでいい」との 記述を加えていますが、障害を持つ両親に対しては どのような配慮がなされているのか、報道からは読み取れませんでした。 しかし、何をするにしても、さまざまな立場の人の境遇を気にし過ぎて、 結局何も出来なくなってしまう、ということが往々にしてあります。 だから、「赤ちゃんの瞳をのぞく」といった項目についても、 視覚障害者の立場をことさらに主張しない方が良い、 という考えもあります。 その一方で、子守歌を歌えなくたって、 瞳をのぞけなくたって、それに勝るとも劣らない わが子への愛がありさえすれば良い子に育つはずだ、 国は障害のある人やさまざまな立場の人に もう少し配慮しても良いのではないか、 という考えもあります。 今、この相対する二つの思いが、私の脳裏を よぎっているのです。 さて、皆さんは、どのようにお考えになりますでしょうか。 [ご参考] 育児電話相談「森永乳業エンゼル110番」教育再生会議 「親学」提言見送り 「押し付け」反発で(毎日新聞)
2007.05.12
-
視覚障害者への情報保障と、著者の生きる権利
最近、視覚障害者の読書環境が大きく変化しています。以前は、点字図書館から点字図書や録音図書を郵送してもらうのが一般的でしたが、最近では、パソコンが利用出来る視覚障害者であれば、自宅のパソコンをインターネットに接続し、点字データをダウンロードして読めるようになっています。 全国視覚障害者情報提供施設協会が運営している視覚障害者情報ネットワーク“ないーぶネット”には、およそ8万タイトル分の点字データが登録されており、視覚障害者が会員登録をすれば、無料でダウンロードして利用することが出来ます。 実は、数日前、私の本『怒りの川田さん~全盲だから見えた日本のリアル~』を読んでくださったという健常者の方からメールを頂きました。「全盲の友人から、川田さんの本を“ないーぶネット”の点字データで送ってもらって読みました。感銘を受けました」という内容でした。 メールをくださったのは目が見える人で、私の本の内容を全盲の友人から点字データで受け取り、点訳ソフトを使ってそのデータをカナに変換して、目で読まれたそうです。“ないーぶネット”に登録されているデータは、点字データといっても、点訳ソフトによってカナに変換出来るのです。一般的な点字には漢字がありませんし、点字表記では、ひとつひとつの単語や助詞の後などでますをあけますので、目の見える人にとってはかなり読みにくいとは思うのですが、それでもカナで書いてある訳ですから、読んで読めないことはありません。 もちろん、私の本をどのような方法で読んでくださっても、感動したと言って頂けるのは、著者として大変ありがたいことです。しかし、“ないーぶネット”の点字データを、目が見える人がわざわざカナに変換して読むというのは、明らかに、視覚障害者への情報保障という“ないーぶネット”の目的を逸脱し、私たち著作権者の権利を侵害しているのではないでしょうか。 私の書籍は定価が1400円ですが、私は今回が初めての作品となった新人ライターですので、著作権印税は定価の5パーセントという条件で、出版社と契約しています。つまり、1400円の本が1冊売れれば、私には70円の収入がもたらされることになります。売れっ子作家さんの場合にはこの印税率が高くなりますが、それでも15パーセント程度かと思います。私は、この1冊70円の著作権印税と、地方紙のコラムの原稿料、そして、講演をして頂く講師謝礼などで生活しており、決して裕福ではありません。それでも、自身の大きな夢に向かって始めたことですから、弱音を吐くつもりなどありません。 皆さんに分かって頂きたいのは、書籍の著者は1冊数十円から、よくて百数十円の印税の積み重ねで生きているということです。しかも、大半の著者は売れっ子ではありません。 本の点訳については法律で著作権フリーとされており、だれでも自由に点訳することが許されています。著者には印税が入って来ません。それどころか、自分が書いた本が点訳されたことすら知らせてくれないのです。それは法律がそうなっているのだからやむを得ないことですが、しかし、よりにもよって、点字データを健常者がわざわざカナに変換して読むなんて、厳密な意味で法律違反かどうか私には分かりませんが、下世話な言い方ながら、あまりにせこすぎるのではありませんか。視覚障害者の情報保障も大切ですが、著者の生きる権利も守って頂きたいと、切にお願いしたいのです。 また、無料でダウンロードした点字データを健常者の友人に提供するような非常識このうえない行為は、視覚障害者自身が視覚障害者の首を絞めることにもなりかねません。“ないーぶネット”の運営団体は、視覚障害者の常識に訴えるだけでは著作権者を守れないのだから、点字データをカナに変換出来ないように、システム上の対策を講じるべきではありませんか! とかく、福祉関係者やボランティアは、「自分たちは障害者のために良いことをしているのだから、そんなことは我慢しろ」と言わんばかりの態度をとります。 いいえ!私は絶対に許しません。障害者もボランティアも、自らの権利ばかりを主張するのではなく、薄っぺらな偽善を押し付けるのでもなく、他人の権利を守ることについて、出版文化を支え育てることについて、少しは考えるべきではないでしょうか。 これは、私の生活がかかった怒りであり、お願いでもあります。
2007.05.10
-
人は見かけだ!障害者も見かけは大事。
先日、あるメディア関係者と、視覚障害者のテレビ写りについての話題になりました。その人は、「視覚障害者の場合、姿勢に問題があって、話しながら体が前後に動いてしまう人が多く、せっかく良いことを言っていても、映像の点で損をしている。NHKの福祉番組や、民放でも障害者を題材としたドキュメンタリーならともかく、エンターテイメント性の強い番組に視覚障害者を出演させようとすると、当然不自然な姿勢のことが気になるのではないか」と言うのです。 福祉番組やドキュメンタリーならともかく、というのは、それらは障害者を題材に(ときにはお涙頂戴的に)描く番組だけれど、放送局の営業成績を左右しかねないエンターテイメント性の強いコンテンツではそうはいかない、という意味なのかなと、私なりに理解しました。 目が見える皆さんは、外出前には鏡に向かって化粧や身だしなみの点検をします。外出中も、洗面所やショウウィンドーなどで、自分の姿をチェックしますね。しかし、視覚障害者、特に全盲となると、これが出来ません。従って、不自然な姿勢以外にも、知らず知らずに我流の癖が付きやすいのです。しかも、本人は気付かないので、家族や友達、そしてリハビリテーション施設の訓練士などから、かなり頻繁に修正してもらわなければなりません。けれど、他人はアドバイスをしたいと思っても、そんなことを言っては失礼ではないかとちゅうちょして、なかなか指摘してくれません。 「人は見かけや形ではない」とは、よく言われますが、それは他人に対するある種の思いやりではあっても、社会の原則ではないと思います。その証拠に、タレントや俳優ばかりでなく、世の中の多くの人たちが、自分を少しでもよく見せるために涙ぐましいほどの努力をしています。しかし、視覚障害者に対して、社会はそれを強く求めてはいません。求めない理由の一つは、社会が、視覚障害者を対等な存在として認めていないからではないでしょうか。 ところで、アメリカの視覚障害者の団体では、目が見える職員が管部候補の視覚障害者と食事をして、その人のテーブルマナーの良し悪しを、理事会に報告するのだと聞きました。理事会はその情報も参考に、次期役員を選出するのだそうです。何故そんなことをするのかというと、アメリカでも、食事をしながらのコミュニケーションは大切な交渉手段となっており、視覚障害者団体の交渉相手は、政府関係者等、健常者であることが圧倒的に多いため、テーブルマナーに優れない代表を選出することは、団体の不利益につながる、と考えるからだといいます。 翻って、日本の視覚障害者団体はどうかというと、どんぶりに顔を突っ込んで、いわゆる「犬食い」をしている役員が、珍しくはないようです。この話を聞いて、決して食事をするのが上手ではない私は本当にドキッとさせられました。けれど、アメリカの視覚障害者団体の考え方が間違っているとは思えません。 テレビ写りをよくすることも、テーブルマナーを直すことも、努力をすれば視覚障害者にも必ず出来ることだと思います。目が見える人と同じようには出来なくても、今よりはずっと良いというレベルまで改善することは可能なはずです。 しかし、日本の視覚障害者の間で、こうしたことについて語られることはほとんどありません。努力すれば出来ることをタブーにしてしまうのは、怠慢か傷のなめあい以外の何者でもないと思います。視覚障害者が慰め、励ましあうということは、健常者が遠慮して言えないようなことでも、怖がらずに堂々と指摘しあうこと、直せることは皆で直すことではないでしょうか。遠慮のある健常者はなかなか言ってはくれないし、言わなくても健常者には何の不利益もないのですから。 視覚障害者に限らず、人が慰めあうということは、互いに甘やかすことではなく、切磋琢磨しあうことであるべきだと、私はそう考えています。
2007.05.07
全168件 (168件中 1-50件目)