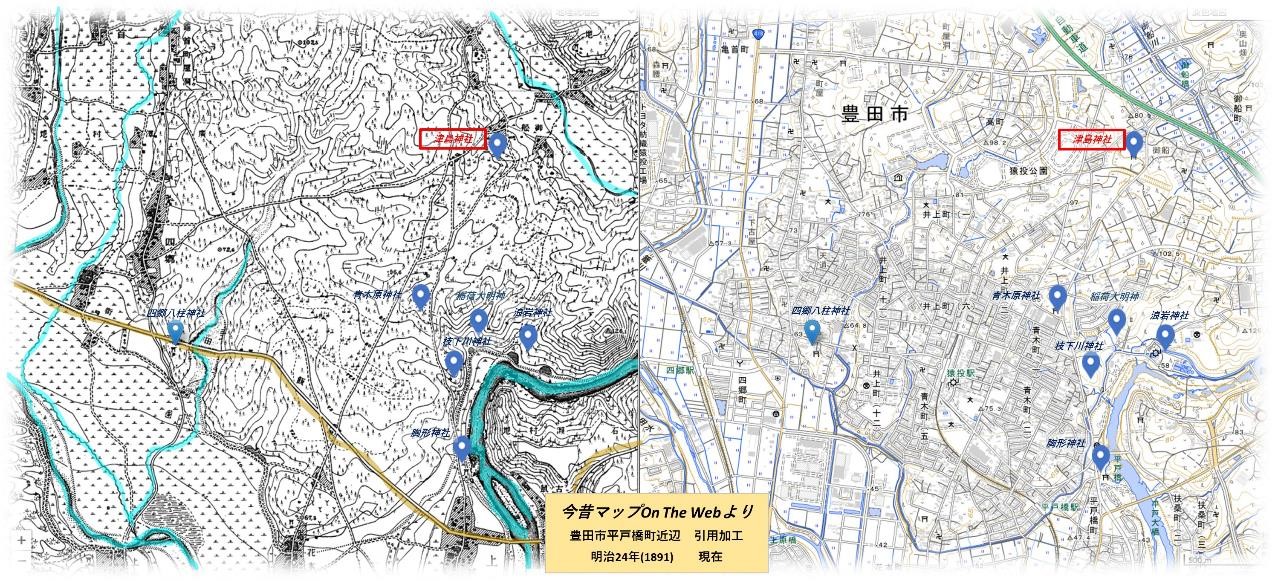トルコの旅――金の星と銀の月のしたで7

―― ギリシアで飲んだくれて、トルコで二日酔い ――

イスタンブールでは(トルコの他のどの町でも同じことだが)、嫌でも朝5時前には目覚める。
いや、正確には目覚めてしまう、のである。
町じゅういたるところからモスクのミナレットのスピーカーから流れるアッザーン(礼拝の呼びかけ)のおかげである。
ギリシアから渡って、クンカプの港で魚料理に舌鼓を打つなどして一夜を過ごした後、イスタンブールではじめて迎える朝。
まだ日が昇らない闇のなか、町のあちこちからけたたましい音に、―すわ戦争か?!―
トルコはサダム・フセインらイラクのひとびとから同胞とされながらも、西欧社会とりわけNATOに属し、対イラク空爆のための戦闘機を配備する空港を提供した複雑なお国事情がある。
ホテルのベッドから慌てふためいて飛び起きたのは、その後数々のアラブ世界を旅してきた今の私にしてみれば滑稽な話である。
カーテンを開け窓に眼を凝らし、耳を澄ます。
薄闇の空、鳩の群れがあちこちでたたわしく飛び回っている。
眠気マナコもバッチリするくらい耳につんざくサイレンと何かの叫び声。
「アッラーアクイバル、アッラーアクイバル――」
あちこちのスピーカーから流れているのは、唯一神アラーの審判がくだり、世界の終末を呼びかけているのではないか?
嗚呼、神様・・・・・神様?――この際、いずこの神でもよい、わが身に平穏と安全を――。
私は臨時ニュースを放映していないかテレビをつけ画面に食い入る。
ちょうど画面には日本のアニメ「忍者ハットリ君」が映し出されていた・・・・・・。
ハットリ君はトルコ語で喋っている。「ニンニン」だけは吹き替えられれていない。
チャンネルを切り替えるが、アタチュルクが青年将校たちに空を指さす銅像の静止画像や、「今朝のトラブゾンほか黒海沿岸地方の空模様は――」などとニュースキャスターがのんびり天気予報を伝えていたり、白地に赤く、ならぬ赤地に白の新月と星のトルコ国旗がたなびく画像だったりした。
どうやら、非常事態宣言は発令されておらず、私のアッザーン初体験は私が慌てふためいただけだったのでごじゃる、ニンニン―――。
しばらくして落ち着きも戻り、ホテル最上階のレストランへ向かう。
レストランはまだ照明を灯しておらず薄暗かった。
「ギュナイドゥン(おはよう)」マネージャーらしきひとが招き入れてくれた。
レストラン全体が紫色の壁だと思っていたのは、三方の大きな窓に映し出された日の出前のイスタンブールの空の色だった。
パンとコーヒーの朝食をとりながら、空の色が変化する刻印を見守っていた。
レストランの大きな窓の外はテラス席ンいなっており、外に出て朝もやのなか新鮮な空気を吸い込んだ。
アッザーンはやんだようで、もちろんスカッドミサイルなど飛んでこない、いつもの朝だ。
テラスから見渡す限り住宅の赤茶色の屋根が連なり、鳩があちこちで羽を休めたり飛び回ったりしていた。
先ほど部屋の窓から見たおぞましいヒッチコック映画「鳥」さながらの大群は解散していた。
鳩たちは旅人である私と違い、毎朝定期的にアッザーンに驚かされているに違いない。
屋根が連なる向こうは海が開けており、昨夜でかけたクンカプの港も見える。
沖には無数の巨大なタンカーや漁船が停泊していた。
さわやかな風にあたりながら、私は昨晩のできごとを想った。
魚屋のプロレスラーや、炭焼き魚食堂の老人や、ギリシア彫刻の少年や、ナザールボンジューの店主やトウモロコシ屋台の主人たちのことを想った―――。
彼ら、すべてのひとびとにも平等に朝はやってくる。
西の空は紫色から桃色に変わり、もうすぐ朝日が顔をだすだろう。
東の空には方角からおそらくブルーモスクであろうモスクのドームやミナレットが空を背景に黒く映えていた。
昨日、体と頭がボロボロながらブルーモスクやアヤソフィアを慌しく観光したことを思い出す―――。
イスタンブールの土を踏んだのは最悪の状態だった。
アテネ最後の夜にプラカ地区にあるレストランでついつい調子に乗って飲みすぎたワインをすべて吐き出しても、まだ胃の中が逆流しそうだった。
それもそのはずである。
その日は、朝から途切れることなく一日中、いや次ぎの日まで飲んだくれでいたのだから―――。
アテネのホテルを通して観光会社に申し込み、「エーゲ海一日クルーズ」なるオプションに参加した。
早朝ピレウス港を出航し、エギナ、ポロス、イドラという3つの島を巡り、夕刻ピレウスに戻るミニクルージングである。
私が乗った「ヘルメス2世号」はイタリア人の大観光客団、北欧から各々バカンスにやってきたひとびと、韓国、日本の観光客で満杯だった。
ピレウスの港をでて、2時間あまりでエギナ島に着く。
エギナ島は古代ギリシアのポリス国家時代、アテネと覇権を争ったこともあるが、いまは静かな保養の島だ。
エギナの港からバスに分乗して、山を越えてエギナの神殿跡を見学した。
その後、約2時間航海しては2時間くらい島見学をしていった。
私は船上ではずっとデッキで日焼けというより火傷状態の肌をさらしながら、北欧のおばさんたちには無視を決め込み、イタリアのビキニ姿のお姉ちゃん方を眺めつつ、ビールビールワインワインを繰り返していたのだ。
そして停泊した島でもムサカなどをつまみながらワインフルボトル、ビール大瓶を鯨飲していた。
帰りの船でも定位置のデッキで知り合ったジャルパックのS氏やスウェーデン人家族たちと仲良くなり、彼らとピレウスまで談笑しながらビールやワインを飲みつづけていた。
そして、夜の街プラカ地区である。
今回のギリシア・トルコ旅行で最も特筆しておかなくてはならない事件があった。
なんと、ピレウス到着直前のデッキでふるさとの同級生と出会ったのだ。
しかも私の家と彼女の実家は500メートルも離れていない同地域の、とも付け加えておこう。
こんな奇跡もあるのだ。
生憎、彼女は私の恋心をそそるようなタイプではなかったが(笑)、高校を卒業して服飾専門学校を卒業し東京のアパレルメーカーで勤める彼女は同僚と旅行中とのこと。その同伴者が可愛いかったのだ。
「アテネで夕食一緒にしようか?」とすかさず、私は豆男だ。
そして、プラカのいかにも観光客相手風なショーレストランで、ついつい調子に乗りここでもワインを飲みすぎてしまったのだ―――。
翌日、私はひどい二日酔い状態でエリニコン空港からアタチュルク空港へと飛び立った。
わずか1時間足らずのフライトで頭痛が完治するわけもなく、低空に入り、イスタンブール郊外の住宅街は画一的で自ら招いた結果に非があるのに、あまり第一印象をよくせぬままのイスタンブールの第一歩であった。
アタチュルク空港は倦怠感が漂っていた。
なぜかというと、これまで旅してきたヨーロッパの国々と違い明らかに態度が尊大な入国審査官の印象であったり、銀行でドルをトルコリラに換金しようと紙幣を出したとたん窓口が閉まったり、どこからともなく聞こえてくる赤ちゃんの泣きやまない声だったりした。
すべてが私を拒絶するかのように、憂鬱な空気が漂っていたのだ。
空港の外に出た。
真夏のイスタンブールは、澱んだ厚い雲が垂れていた。それだけでもう、げんなりしてしまう。
厚い雲は、先の湾岸戦争での度重なる製油油田の破壊のおかげで、イラクと国境を挟むトルコあたりの気候体系が変わりつつあるという噂も聞いていた。
観光するには影響がないとはされながらも、今回のトルコの旅は氷上の旅でもあったのだ。
空港バスはマルマラ海に沿って走り、ビザンチン皇帝テオドシウスが築いたテオドシウスの城壁を巡りながらイスタンブール新市街の広場へ向かっている。
テオドシウスの城壁跡には住む場所がないジプシーたちが多く住んでいた。
―― 白い歯 ――

新市街の中心地アタチュルク広場からそのまま旧市街地の観光に向かう。
怠惰な体をひきずるようにして、6本のミナレットがそびえたつ大きなモスクにいる。
このモスクはブルーモスクの愛称でしられ、1616年、スルタン、アフメット2世が建てさせた。
スルタンが「アルトゥン(黄金)のミナレットを」と命じたところ、「アルトゥ(6本)のミナレット」と聞き間違えて建てられた、という逸話でも有名である。
モスクのドームは高く、広く、ステドグラスやドーム内の装飾はブルーを基調にした美しいモスクだ。
モスク内の見学は自由に行え、観光客は多いが信者は閑散としていた。
絵を描いたような、オスマントルコ風のフェズ帽を被った信者たちが一心不乱に祈りを捧げる、という図はこのときは幻に終わった。
胃が重く、頭が痛いまま体を鞭打ち隣のアヤ・ソフィア聖堂へ移る。
537年、ユスティアヌス帝が6年もの歳月をかけてギリシア正教の大本山として建立させた。
時は移ろい1453年、コンスタンティノープルを陥落したメフメット2世がただちにモスクとして改修した。
メフメットはキリスト象などを破壊し、偶像崇拝につながる聖母ほかモザイク壁画はすべて漆喰で塗りこんだ。
現在では、その漆喰は落とされ、モザイク画が再び世の光を浴びている。
破損をかろうじて免れた聖母マリアの微笑みに笑みを返す気力もなく、旧市街観光3点セットの残るひとつであるドプカプ宮殿に向かう。
ソフィア聖堂の裏手から宮殿の総門をくぐる。
門にはスルタンの衛兵ならぬ現代の兵士が立っていた。
門を写真に収めようとしたら、通りがかりのおじさんに「ダメダメ」と注意された。
トルコでは警官、兵隊、軍事施設の撮影は禁じられている。
ドプカプ宮殿の宝石類にはあまり関心をもてず、宮殿内の見学もそこそこに私は第3庭園のテラスでボスポラス海峡を眺めながら、トルコではじめてのチャイを飲んでいた。
ようやく英気がみなぎりそうだった。
続いて、すぐ近くにあるユスティアヌス帝の地下宮殿(イエバタンサライ)へ行く。
ここは有料で1万トルコリラ(約300円)払わなくてはならない。
民家のような入口から階段を降りると、地下貯水場だった。
366本の円柱が支えている。
一番奥にライトアップされたメドゥーサの首の像がなぜか逆さに円柱の土台になっていた。
場内は常にムソグルスキーの展覧会の絵~プロムナード~が流れており荘厳な雰囲気を醸し出そうとしているようだが、ここは宮殿ではなくやはり貯水場である。
観光というものはいつもどこでも、かくも退屈なのかどうかはさておき、私は体調不良に悩まされながら歩きつづけた。
私にとって救いようのない印象のトルコを近づけてくれたのは、やはりひとである。
「ちょっとちょっと馬場さん」
スルタンアフメットジャミィから出た広場の階段に腰掛け、正面に建つアヤソフィア聖堂をぼんやり眺めていたときのことだった―――。
「馬場さん」といきなり私は袖を引かれ、顔を見やると絵葉書を掲げた白い歯をこぼさんばかりの少年の笑顔だった。
私をなぜか馬場さんと呼ぶ少年はどうみたって7才か8才くらいの年頃だ。
「ぜーんぶで10ドル」と日本語でその葉書を売りつけようとする。
「10ドル?!」
「ノーノー!1ドル」と少年は慌てて訂正した。
少年は私に脈があると読み取ったのか、チョコンと私の隣に座り、私に絵葉書を渡した。
少年は満足そうにまた一段と白い歯をみせ笑いながら、彼の楓のように小さな手のひらを二つ差し出した。
「なんだ、やっぱり10ドル?」絵葉書5枚が10ドル(笑)。
トルコならずとも観光地でこうした怪しげな物を売ろうとする商売人はいずこも同じだが、まだ年端もいかない少年の物売りとは恐れ入る。
白い歯をこれみよがしにみせつける笑顔にだまされそうな愛くるしさだが、彼を相手にするには今日の私はあまりにも体調が悪すぎる。機嫌もそのうち悪くなり、相手にしないことにした。
それに、午後からでかける予定のグランドバザールではこの少年以上にひっきりなしに襲いかかってくるであろう魑魅魍魎たる商売人攻勢を思えば、いまこんなところで気を許してはならぬ。
少年ごときに足元をすくわれてはならぬのだ。
しかし、白い歯に心を少なからず奪われた私が愚かだった。
彼らにとって組しやすいカモと見られたのか、私はこの少年―仮に少年Aとしておこうか―のみならず、駒のようなものを持った少年B、音が鳴ると踊りだすトルコの兵隊をもつ少年Cなど、その他大勢の土産物少年たちに瞬く間に包囲されてしまったのだ。
私は彼らの輪をほどいてアヤソフィアへ向かおうとするが、私を取り囲む一団そのままの大移動となってしまったのである。
さすがはオスマントルコの末裔たち、少年たちも「敵を包囲する」戦法が得意だ。
いや、関心している場合ではない。アヤソフィアへ通じるローマ競馬場跡地広場のオベリスクの袂では、善良そうなドイツ人老夫婦が別の少年グループに包囲されているではないか。
私は小心で謙虚で思慮深い島国のひと、を演じつづけた。いや演じずとも小心だけは本性だが。
私はなおも無視を決め込み、途中ベンチに座る余裕も見せた。
少年たちはベンチを取り囲み、私を見て何か言い合いっこしては、歓声をあげて笑っていた。
私をからかっているのは一目瞭然だ。
私は少年たちが去るのをあきらめて、アヤソフィアへ向かった。
どんどん早足になるのが自分でも滑稽だった。
しかし、あそこに入場してしまえば、もうタカリは去るしかないだろう。
トルコの観光地には軍人や警官がわんさかといる。
今しがたも薄茶の制服を着た警官が通り過ぎていった。
少年たちは身のこなしのすばやさに感心するくらい、いつのまにか私から離れて歩いていた。
少年たちはトルコも学校が夏休みに入ったからなのか、家計の助勢のため必死に働いているのは理解できる。もしくは、彼らは助勢どころか家計の柱であるのかもしれない。
ふと、今朝空港から通ってきたテオドシウス城壁のジプシーたちのことを思い起こした。
しかし、哀れみで絵葉書5枚を10ドルはさすがに躊躇する。
少年のなかには離れ別の上客を求めて私からだす者もおり、ひとりまたひとり脱落していった。
アヤソフィアの入口はすぐそこだ。
見学は有料で、入場口には検問らしき軍人や警官が大勢暇そうにたむろしているではないか。
私の「沈黙は金なり」という完全勝利は間近だ。
しかし、最初の絵葉書少年Aだけはなおも私に食い下がった。
すでに彼から白い歯は消え、目の光までも失っているように感じて恐怖すら覚えた。
私は彼がジプシーであると、正しいかどうかはともかく、その目をみて直感した。
私の額や腋の下から流れ落ちる汗は決してしだいに速まった歩き方やうだるような暑さのせいばかりではあるまい。
ようやくアヤソフィアの入場口にたどり着いた。
少年は私から紙幣を奪い取ることをあきらめ戦略を劇的に変えてきた。
「馬場さん、タバコをくれ」
元の白い歯の笑顔が戻る。
あとで知ったことだが、「馬場さん」は私の思い違いで、「ババ」とはトルコ語で「父」のことである。
親しみと尊敬を含む敬称でもあるらしい。
私はヤレヤレという、安堵感から彼の胸ポケットにマルボロを一本さしこみこう言った。
「君にじゃないよ。君のお父さんの分!だよ」
「兄も3人いる!」
私は呆れて顔を横に振った。
そのやり取りを遠めにしてみていたのであおう、ひとりの警官が何やら怒鳴って少年を追い払った。
「このトルコの恥さらしめ!」などと罵っていたに違いない。
私はようやく解放されたが、その別れ方に一抹の寂しさを感じるものがあった。
入場料を払い、アヤソフィアへ入るとき呼び止められた。
「ちょっとちょっと馬場さん。落ちましたよ」
私はびっくりして、慌てて足元を振り返った。
足元には何も落ちてなく、顔をあげると、警官たちの無数の白い歯があった――。
―― 旅のそぞろ心 その一 ――

とにかくトルコへ行こうと駆り立てられていたが、この国に関する知識はほとんど何もなかった。
しかし、旅には地理的、文化的、あるいは感覚的いかんによらず、―旅の漫ろ心―を駆り立てられ、それを求める場所=トポスがあるはずだ。
私にとってそれがたまたまトルコという―記号―であっただけのことだ。
旅の漫ろ――それは、自らのとるに足らない人生と、悠久の歴史的なものが持ち合わせる空気のようなものと波長が合わさったとき、その場所が旅の移動祝祭として選択される。
「真実は旅にある」というキャッチフレーズを当時創刊された旅行雑誌ガリバーが掲げていた。
たしかに真実は旅にある。
しかし、そうとばかりはいってられないことも旅は諭してくれる―――。
この愛すべきイスタンブールとアナトリアの大地にお別れを告げなければならない日がやってきた。
私がイスタンブールにて旅の拠点にしていたPホテル。
グランドバザールへは大通りのイェニチェリレル通りを隔てて300メートルにも満たない距離にある坂の上に建つホテルだ。
チャルシュカ地区というさして変哲もない住宅街にある、さらに特筆すべきものが見当たらない近代的ホテルだ。
このホテルの最上階にあるダイニングのテラスから旧市街が一望できる。
この景観だけでもこのホテルに五つ星を与えてもよいと思える。
チャイを飲みながらこの町の思索に耽ったトプカプ宮殿、土産物を手に執拗な物売りの少年たちの縄張りであるアヤフメット寺院、それら思い出の地が一望でき、モスクの背に朝日を拝めることができる。
新市街のガタラ塔からではない、ボスフォラス大橋からでもない、旧市街東サラチハネ地区にあるヴァレンス水道橋からでもない、他の何処でもない、此処から見渡すイスタンブールの町並みこそが、私にとってのイスタンブールであった。
南に目を移せばマルマラ海だ。
相変わらず沖合いにはタンカーや漁船が停泊している。
月を眺めながら焼き魚に舌鼓を打ち少年を困らせたクンカプの港、あの少年は今時分はどうしているのだろうか。
朝靄に包まれて、やけに感傷的になることが自分でもよくわかる。
感傷はよそう―――。
西の空を白みなじめ、いつものように鳩たちが飛び回っている。
もうすぐ礼拝の時を告げるアッザーンが町じゅうにこだまするはずだ。
ようやくザッザーンが心地よい朝の-悦びの詩-に聞こえなくもないようになったのに、もうイスタンブールとお別れを告げなければならない。
如何ともしがたいこの離別の心情を、的確にまた情緒たっぷりに伝えてくれる名文を引用させていただき、手助けを願おう。
「――古都の氷雨降るなかを花嫁は白いウェディングドレスに包まれて去って行った。
折りしも数多くのミナレットからはコーランの夕べの祈りの一節が流れ始めた。
―――そして私はそれら美しいジャミィ(寺院)に別れを告げなければならない。
いかに愛惜の情切々たるものがあっても、私はやはり異邦人なのだ。
私はやはり日本人であって、この国の人間になり切る能力はなく、たとえ社会の異分子としてでも日本という「場」に生きていく以外に道はない。
旅の間にいろいろな国々のさまざまな人間に出会ったが、「世界は一つだ!」とか「国境と肌の色を超越して、人間はすべて心底まで理解し合えるのだ!」などという大向こうの喝采を浴びるような台詞を吐く自信はついに生まれなかった。
もちろんこのトルコという国において、心の友を持つという奇跡が実現したことは、これからの私を一生支配するだろう。だが、個々と全体とは別の次元に属する。
「人間」というものについて、私はやはり「人間というものは如何によく互いに似ていて、同時に何とよく異なっていることか!」と嘆じたはるかな昔の天才の言葉以上のものを知らぬ。
人間にとって一番未知なものは、宇宙空間の彼方にあるものではなくて人間自身に内在するものではあるまいか―――。
トルコを去る日は小雪が舞っていた。なれ親しんだ寺院や街々が薄化粧していた。
親しい人々に囲まれ、友と互いに両頬と眼に口けし合う別離の挨拶をすると、初めて自分がこの国を去っていくのだという感慨に胸がいっぱいになり、眼頭が熱くなった。
地球が狭くなったとはいえ、やはりトルコは遠い国である。心の中ではどんなに近い存在になろうとも。
もつれがちの舌でせいいっぱい努力して友にこう叫ぶのが私にできるすべてであった。
「シンシャラー!ヤクンダレクラル!(もし神が許し給うなら、再び!)」――――。『遠くて近い国トルコ』大島直政著 中央公論社刊 ) 」
トルコを去る心情を、ともすれば私と同様に感傷過多になりすぎがちだが、披露を迎えなお心を打つ文章だと思う。
そして、これはトルコを旅したひとにだけ通じる話ではない。
トルコをフィジーでもブタペストでもグリーンランドでも熱海でも登別でも、どこにでも置き換えられる話なのだ。
あらゆる旅人に、いや、むしろあらゆるひとびとに通じることなのだ。
あらゆるひとの―出会いと別れ―に。
私がトルコを去る日は雪、ならぬ鳩が舞っていた。
日の出前に放たれる光のプリズムがさざ波をたてる海にきらめきながら落ちていく。
無窮の憧憬をこの時この地に刻まんとばかりにあてどもなく飛翔しつづける鳩の群れは、紫からやがて茜色に変わりつつある夕焼けのような荘厳な朝日のなかに溶け込んでいった。
海がざわつきはじめたような気がした。
一瞬ではあるが空気の匂いも変わった。
遠くどこかで汽笛が鳴った―――。
つづく
旅行写真満載w
旅行blogランキング
まるくん禁煙ブログ
© Rakuten Group, Inc.