全691件 (691件中 1-50件目)
-
●●●スターシップ・トゥルーパース
敵は虫である。昆虫型宇宙生物、アラクニド・バグズ。地面を埋め尽くしてやってくる大量のバグスに、地球連邦軍の兵士など一溜まりもない。巨大な蟷螂の刃に蟻のようで蜘蛛のような造詣、有機体というよりは無機物なデザインには、敵と認識した者をただただ殺しまくる残虐性を見る。バグズの尖った刃に、人間は次から次へと串差し状態。ロバート・A・ハインライン原作のSFを、ポール・バーホーベン監督が映像化。エロスとバイオレンスで定評ある監督は、名作SFの原作も眼中の外のようである。映像化する場合、原作の意図も勿論大事であろうが、バーホーベン監督は映像化することによって、全く違う意図を与えてくれている。人種、男女差別はないが、軍歴のある者だけが市民権を得る近未来。大した戦争が勃発していなければ、軍歴は免許のようなものであっただろうが、銀河全体に殖民をはじめていた人類は、先住民にバグスのいるクレンダス星という地雷を踏んだ。全面戦争への突入はバグズの奇襲攻撃から。戦争を始めるのは兵士ではない。だが戦争をするのは兵士なのである。主人公のジョニー・リコも高卒の青年である。りりしい女性陣もまた串刺しにされるには若すぎる。国のために命をかけて戦う姿が、どうのこうのと言うお涙頂戴な演出はない。主義主張を語れるようなテーマ性はないし、B級の誉れ高い戦闘シーンは見せ場にはならない。だが、ウジャウジャやってくる敵が気持ち悪く、残虐で命という概念が全くない。だからこそ、戦争というのはそういう敵の中に、若い命が放りこまれるものだとわかる映像になっているのである。しかも兵士は立派に戦っている。登場人物たちが、幼く等身大の若者だからこそ、まるで、ブラックジョークに見えるのだ。映像化によって描きだされたのは、戦争という、ブラック・ジョーク。話は映画から少しそれるが、映画のレビューをまとめる中で、司馬遼太郎「坂の上の雲」の原作で、203高地の描写をかぶるような気がした。詳しいことを書く力量はないが、旅順攻略の軍の方針と言えば、兵士が機関銃に向かって進んでいくというもの。死体の上に死体が折り重ねるような戦闘だと、書かれていたように記憶している。同作を参考にしたと言われる映画「二百三高地」では、兵士の葛藤もしっかり描かれている。バーホーベン監督が描いた本作品の戦場と、重なるところがあるのではと思うのは穿ちすぎだろうか。バグズとの戦闘に、若者たちは熱を帯びたように進んでいく。国家もまた英雄志願の若者を過大な宣伝で募集する。アメリカ国旗がたなびく場面はブラック・ジョーク的名シーンである。ストーリーはともあれ、バグズに関する造詣や設定は見事である。アメリカ公開は1997年。「2」に続き「3」公開の話も伝わってくる。「エイリアン」「プレデター」などと一線を画し、鮮烈な印象を与える宇宙生命体であろう。そして、希有な反戦映画のひとつ。
2007.08.13
コメント(74)
-

●●●恋するブラジャー大作戦(仮)
さあ、身体を前倒しにして、ブラの中にオッパイをしっかり入れて・・男二人が恥じらいながら装着するのはブラジャー。日本の大手下着メーカー「シス」の香港支社ではじめて男性デザイナーが採用された。ブリーフのデザイナーだったのジョニーは、オッパイの代わりに水の入った袋を赤いブラに入れている。工業デザイナーだったウェインは、人工乳房をどんな感触でブルーのブラの中に入れているのか。指導する女性チーフデザイナーのレナの声は二人の様子に笑いをこらえている。あ、人工乳房がはみ出ている。女性だらけの「シス」の香港支社に男性デザイナーが配属されたのは新ブランドを立ち上げて売り上げをあげるため。日本側の命令に香港支部長のサマンサは動揺を隠せないが受け入れるしかない。チーフデザイナーのレナと同じ待遇で、迎え入れたジョニーとウェインだが、まだブラジャーへの理解が少なかった。勝手に作ってきた試作品ブラジャーもつけ心地が悪く、モデルの評判も悪かった。ジョニーもウェインも、毎日職場で美しい女性に囲まれて、悦びに満たされているようでもあるが、仕事に対しては真剣である。レナに指示されて街中を駆けずり回り、いろんなブラジャーを買い集めているときも、またまたレナにふっかけられて、女性用の下着を装着させられる羽目になっても、取り組んでいるときは手を抜かない。女性たちもまた必死である。香港支部長のサマンサは社を代表してプレゼン。レナはファッションショーで自分のイメージを表現したいが制約がありままならない。プライベートでも恋愛は上手くいかず、仕事に対するプライドの高さもあいまって一人キリキリ悩んでいる。そんなときサマンサにはジョニーが、レナはウェインが何気なくフォローする。男性陣は底抜けに明るく前向きである。2001年の香港の作品だが、日本公開は2006年のようである。ややこしい邦題名だが「絶世好Bra」がタイトル。登場人物たちが作ろうした究極のブラがこの映画のタイトルである。そして男性デザイナーが出した結論は、「愛する男性の抱かれている感触」の再現。だが物語はサマンサとジョニー、レナとウェインの恋愛が成就して大団円となる。ラブコメなのである。華やかで美しい女性たちの間で、底抜けに前向きな男二人がジタバタしている。キャストが魅力的だから、物語に大きなクライマックスはいらない。サマンサには演技派カリーナ・ラウ、ブラジャーの理論を語る彼女は美しく気高い。ジジ・リョンの演じるレナは、ヘンな声をだして威張っているが、ショートカットが似合う本当に愛らしい女性である。ラウ・チンワン、ルイス・クー、数々の幅広い作品をこなしている男優は、コメディのタイミングをよく知っているようだ。ブラジャー姿の女性たちに囲まれても、嫌みがなく軽やかである。観ているだけで楽しく小さなエピソードに顔が弛む。誰も彼もが真剣だから仕事の成功にも、恋の成就にも好感度がもてる作品になっている。1997年の香港返還後から、若い女優たちが飛躍的に活躍するようになったそうである。ジジ・リョンもそうだが、『墨攻』でアンディ・ラウの相手役だったファン・ビンビンの名も上がる。香港における歴史的な変革は映画にも大きな変化を与えたのは想像に難くない。この作品にしても日本人女優も出演している上、ラウ・チンワン、カリーナ・ラウは東京でラストシーンを撮っている。アジアだけのテイストに留まらない演出だがアメリカ映画とは違うベクトルで登場人物たちが真面目で一途である。コミカルなシーンでも役者たちは真剣そのもの。男のブラジャー装着や学生服姿のコスプレ、演技派女優も下着姿を見せてくれている。ハチャメチャだが真剣なラブコメなのである。香港映画ではお馴染みの俳優もカメオ出演、そう言えばジャッキーチェンも香港映画にカメオが多い。ジャッキーもアクションも魅力的だがコミカルな姿も楽しいのが彼の持ち味ではある。「恋するブラジャー大作戦(仮)」この作品の楽しさが味わえたことで、映画を観る幅が広がったような気がした。
2007.08.12
コメント(4)
-

●●●アドルフの画集
瞳は自信に満ち溢れ、しっかりと聴衆を見つめながら、力強く連呼するのは、単純で短絡的な結果のみ。理屈はいらない。力強く同じ言葉を連呼することで聴衆はやがて、妄信的にその言葉に飲み込まれていくのである。アドルフ・ヒットラーは猛烈に敵に挑みかかる獣のように熱弁を振るい聴衆を沸き立たせるが、なんのことはない、同じ言葉の連続である。ただ、力強く声だけに連呼することで、聴衆は次第にその言葉に飲み込まれ洗脳され、自らの意志を彼に重ねてゆくのである。まずは若者たちから精神が犯されていく。やがて、独裁者アドルフ・ヒットラーの名のもと、ナチスドイツという帝国が生まれる。その独裁者アドルフ・ヒットラーがまだ、ただのアドルフ・ヒットラーであった頃の物語。1918年、ドイツミュンヘン。彼は画家志望の冴えない貧乏な軍人だった。ボロボロの画集を抱えたアドルフは、鉄工所画廊のオーナー、マックス・ロスマンに出会う。ロスマンは戦争で右手を亡くしたユダヤ人の画商。画商は既存の芸術で商売をするが、若い才能を発掘することで莫大な利益を得ようと考えているもの。ボロボロの軍服を着ていようが、画集を持った青年を放っておくはずはない。だが、アドルフの絵は技術はあり上手いが、何かを惹きつける才能を見いだせなかった。芸術の輝きは技量だけでは生まれない。それでもロスマンがアドルフを放っておけなかったのは、あまねく絵を描く者への愛情のように見えた。ロスマンがアドルフにもった愛情は彼が家族や妻、他の絵画やアーティストに対してより、はるかに少ないものであっただろうに。アドルフはそのわずかな愛情に、必死にしがみつき拡大解釈をはじめていた。自分の絵をわすかでも認めてくれる人は、興味さえもたない人々よりもずっと重要人物になる。わずかな興味も大いなる愛情にさえ思えてくるようだ。アドルフは鉄工所画廊に入り浸るが、ロスマンは本気で相手にしなかった。ロスマンがこの後、アドルフに見いだすものは才能である。ジャンルに縛られた絵画ではなく、独創的な未来社会が、ファッション、シンボル、道路、町なみさまざまな側面から多層的に描きだされたスケッチに、大いなる時代の息吹を感じることになる。だが、ロスマンが彼を見いだすまでに時代はアドルフの特技を必要としていた。宣伝。瞳は自信に満ち溢れ、しっかりと聴衆を見つめながら、力強く連呼するのは、単純で短絡的な結果のみ。理屈はいらない。力強く同じ言葉を連呼することで聴衆はやがて、妄信的にその言葉に飲み込まれていくのである。アドルフ・ヒットラーを演じるのは、ノア・タイラー、アクの強い名優である。彼の能力を充分に発揮できる役に恵まれない中、稀代の独裁者の若き日々は俳優としてのワザを存分に見せられる役柄だったろう。同じくマックス・ロスマンもまたある意味、アクの強い俳優が演じている。ジョン・キューザック、彼の場合は、どんな役柄を演じようがたくさんの人々にも愛されている魅力を放つ。役にのめり込むというよりも、どんな役にでも自分の個性を見せる俳優。ノア・タイラーとジョン・キューザック、タイプの違う役者が演じることで、二人が結局、重なることなく終わる悲劇がリアリティを持つように思える。アドルフ・ヒットラーは、才能ではなく特技を歴史に愛された。そして彼が独裁者として達成した帝国は、既に画集の中で描かれていたのである。才能は特技の前に道具として使われ、一人の人間を魔物に変え悲劇へと誘っていく。ユダヤ人のロスマン、彼もまた時代によって命を奪われるのだ。時代に愛された者は幸福になるとは限らない。翻弄され魔物に魂を売り渡し、哀れな末路へと、まっすぐに突き進むアドルフを止めることが出来たのは、まぎれもなくマックス・ロスマンだったのに。人間だけが人間を救えたはずなのに。はがゆくも哀れを感じる物語。この後の戦争に一体何人の命が奪われただろうか。誰もがアドルフになり得るのである。誰もがマックスになり得る。誰もが一つの出会いに運命を変えられていく。
2007.07.30
コメント(1)
-

●●●ダイ・ハード4.0
高架道路を疾走するトレーラー。お馴染み、ジョン・マクレーンが爆走している。追いかけるのは戦闘機。敵の策略に嵌って彼を抹殺しようとしている。ロック・オン!この絶体絶命の危機でも勿論、マクレーンは死なない。アクションの伏線が秀逸に上手い。可愛らしいマクレーンの娘ルーシーも活躍するが、全く別の場所で彼女は敵の捕らえられ羽交い締めにされてお父さんと同じ反撃をするのだ。敵の腰にある銃をそのまま撃って相手の足にダメージを食らわす。いつだって彼女は、泣き言を言わない。お父さんから受けついた気性は、ジョン・マクレーンという男を明確にした。ジョン・マクレーン。マット・ファレルという若いハッカーを、FBIに連れて行く任務の途中で、目の前で車が衝突する。全く進まなくなった道路上の車。彼は自分の車のルーフに乗り周囲を見渡す。四方八方、信号は全部青になっていた。自分の目で確認する男である。だが、今度の敵はサイバー・テロ。マクレーンにとっては正反対の敵が登場する。セクシーな女性の声に導かれ、何人かのハッカーが協力して準備された計画。だが、首謀者のガブリエルは協力者の抹殺を殺し屋に指示していた。マットもあわや抹殺寸前、彼を連行しにきたのがマクレーンでなければ、殺されていた可能性は大。そして、マクレーンとの出会いで、彼もまた生死を賭けたギリギリの戦いの巻き込まれる。マット・ファレルの自宅。そこでマクレーンとマットが出会い、最初のアクションシーンが始まる。パソコンとフィギュアに囲まれた部屋で彼はPCのエンターキーを押すことで爆死するはずだった。そこへ現れたのはジョン・マクレーン、これなんだ?とフィギュアを壊しまくっている。パソコンよりもそっちに気がいっている間に、彼を狙って殺し屋の弾はマットをかすめていた。性格設定のない殺し屋たちでさえ、敏捷で正確な動きをするマッチョマンが登場。執拗な攻撃でマクレーンとマットを攻撃してくる。冒頭から絶対絶命、そんな彼らを救ったのはマットのフィギュアがPCのエンターキーを押し、ドカンと殺し屋の方を吹き飛ばしたことによる。こうして、そうやって、こうなる。一つのエピソードは次のアクションシーンに確実につながる。出来すぎとも言えるアクションシーンの連続でとことんマクレーンを絶対絶命に。だが、観る側はどこかでマクレーンが助かることを知っているから、絶対絶命が愉しめるのである。そうくるか。そうなるか。ファイアーセール、投げ売りと訳されたサイバー・テロは、国のインフラを徹底的に壊滅させることを意味する。多くのシステムはコンピュータ制御されている。FBIなどのコンピュータだけでなく、電気、水道、電話は使用不可、株式市場も大混乱、テレビジャック、病院も混乱。ただ、アメリカも対策を練ってはいた。サイバー・テロが起こった場合、国の財産、システムは一つの場所に集まる仕組みを。だが、そのシステムを作ったのは、このテロの首謀者、ガブリエルだったのだ。美しい女性テロリスト、マイとの激闘もまた、絶対絶命の中、偶然がマクレーンを救う。マクレーンとマットのコンビがお互いを長所で補い、ガブリエルに近づいていく。ブルース・ウィリスの存在感は不思議だ。年齢を重ねることで、不思議な味わいを増している。この渋面の親父の行動に目が離せない。しかもスクリーンをドーンと占拠して作品そのものに確実な魅力を与えてくれる。マクレーンに振り回される役のマットを演じるのは、ジャスティン・ロングである。ヘタレなパソコンオタク姿も上手いが、ラストシーンでは人間的な成長も表現してみせる。驚異的な行動をするマクレーンとの間合いも自然。ジョン・マクレーンとともに、ダイ・ハードシリーズは見せたのは貫くこと。自分の意志とは無関係に巻き込まれ、いつのまにか逃げずに立ち向かっていたら、もう止まらないのである。絶対絶命の連続でつなぐアクションシーンも止まらない。確かに悪役はアメリカ社会の風刺でもあるが絶対絶命のアクションシーンこそが必要不可欠な作品であると思う。とにかく、絶体絶命の連続でもマクレーンは死なないのである。なんだか、絶対絶命が、愉快になってくるのである。
2007.07.29
コメント(4)
-

●●●吉祥天女
男を幸福にする女も、男を不幸に追い落とす女も一人の「女」の中にある。吉祥天女。1983年から1985年に吉田秋生によって世に出た名作である。漫画としての魅力だけでなく、作品が持つテーマから時代を超えても色あせない、唯一無二の作品だと言えるだろう。2007年、映画化された吉祥天女は、昭和45年の金沢を舞台にしている。漫画というよりは、小説の映画化のように、足に地がついた設定がされていた。たくさんの少女や佇まいも柔らかく穏やかな風情を見せる。約30年後の少女たちよりもずっと、彼女たちは内なる女をしっかりと抱えている、そんな風に、見えた。叶 小夜子。内なる女性を抱えた少女たちの前に降り立った天女。麻井由以子が彼女に抱いた憧れは、歴史の中で女性が歩んできた運命への反論。天女神社で同級生の男どもに襲われた時、小夜子は何人もの男を見事に薙ぎ倒した。力の強い男に囲まれたら、女性に自由はない、為すがまま。女の根底にはどこか、力に屈服する心が潜んでいる。だからこそ由以子は、小夜子の強さに強い憧れを抱いていた。だが天女の羽衣に触れた男には祟りがあるという。天女神社をはじめ、この辺りの土地の地主である叶家。小夜子は遠野建設の息子、暁といわば政略結婚をさせられようとしていた。遠野家当主の一郎や叶家の浮子たちが、巨額の財産を自分たちで管理でしようとしたがための策略。だが小夜子は大人が決めた運命など気にもせず、暁よりも遠野家の養子、涼が気になるようだ。お披露目のお茶会で並んだ高校生の三人、小夜子、暁、涼。「暁くんより、涼くんの方がいいわ」何気ない一言は、彼女が見せた明らかな意志である。男たちが観る小夜子への目線。美しい女性への目線。愛情という側面もあれば、鑑賞という側面もあれば、征服したいという欲望もあるのだろう。だが、男を幸福にする女も、男を不幸に追い落とす女も一人の「女」の中にある。女の根底にはどこか、力に屈服する心が潜んでいる。だが、小夜子は屈服しなかった。小夜子を屈服させようとした者たちは次々と彼女の手によって死を与えられていく。幼い幼児の頃から小夜子は、義理の父親の魔手さえも逃れていた過去を持つ。彼女は征服される女ではない。と、同時に守られる女でもない。涼に小夜子は魔性。それは、涼のみ、彼のみ、女を個性として観る感性を持っていた証拠。だから、小夜子を畏れ、小夜子を愛した。遠野涼は小夜子を守ろうとした。天女を愛する資格を持つ、ただ一人の男だったろうに。麻井由以子が、そして他の少女たちが観た小夜子は憧れ。だが、小夜子には由以子が憧れ。自分が愛した男に愛され、守られ、自分も彼を守ることが出来る関係など小夜子のとっては夢のまた夢。小夜子は鈴木杏、難役に大胆に挑んだ彼女はまさしく女優。勝地涼の遠野涼は、適役だろう。深水元基は暁は原作とは違う存在感である。及川中監督作品、年代や舞台設定を限定したことにより、原作のもつテーマは和らいでいる。真実の語り手である麻井鷹志が女性になり、女性にとっての小夜子と男性にとっての小夜子の差異がぼやけてしまった。だが監督が原作のテーマを充分理解し、おさえた照明と素朴なカメラワークで、二次元から三次元に降り立った吉祥天女に、しっかりとした存在感を与えている。原作とは違う演出に悪い印象は感じないですんだ。唯一無二の作品を映画にするのは難しい。寧ろ、映像となった吉祥天女が、形となったことが嬉しくさえ思えてくる。男であるとか、女であることかで、境界線を感じる必要はない。小夜子に憧れる由以子、小夜子が憧れる由以子。全ては表裏一体。自分の運命に自分の中にある。男以上に女はそうであると思わせてくれる作品である。「吉祥天女」公式サイト
2007.07.28
コメント(4)
-

●●●トンマッコルへようこそ
ようこそ、ようこそ。誰かを拒む理由などこの村にはないのだ。だからようこそ、トンマッコルへ。みなさん、ようこそ。時は1950年代、朝鮮戦争の真っ只中。朝鮮半島は南北に別れて戦っていて、そこに連合軍と名乗るアメリカ軍も混じって、戦争をしていたのである。みんな同じ一個の命を持っている人間同士が、似ているけれども微妙に違う服を着て、相手を憎み拒み殺し合う理由は何だというのだ。一体、何なんなんだ?「空から人が降ってきたよ」落ちてきた飛行機に乗っていたのはアメリカ人。スミス大尉は目を白黒させていた。トンマッコルの人々も興味津々で彼と接する。ようこそ、トンマッコルへ。人民軍も決死の行軍を続けていた。なんとか生き残ったのは、中隊長のリ・スファと、年長の下士官チャン・ヨンヒ、少年兵のソ・テッキ。迷える彼らをトンマッコルへ案内したのは、邪気のない笑顔を満面に讃える、目の大きな愛らしい少女。彼女はヨンヒ、ヘビが危険なのは知っているが、兵士にとって敵が危険な存在なのを知らない。そもそも、敵とは何なのか知らないのだろう。もう一組、トンマッコルにやってきてしまったのは、韓国軍は二人、ピョ・ヒョンチョルと衛生兵のムン・サンサン、彼もまた年が若い。兵士は敵を認識すると途端に殺し合いを始めようとする。人民軍VS韓国軍。手榴弾なんか、持ち出したりしている。爆発したら、みんな死ぬのに。ずっと睨みあってる5人の兵士たちトンマッコルの人々は首を捻っている。なんだありゃあ?と言わんばかりに。パク・クァンヒョン監督作品。長くCM監督として活躍した彼の映像は、ストーリーに先行して独自の世界観を持つ。不発弾だと思われた手榴弾が、食料貯蔵庫を爆発させてしまう。そして中にあったとうもろこしがはじけて、ポップコーンの雪が夜の闇に降り注ぐ。幻想的な美しい映像であり、なおかつ、村の暮らしも伝えてくれる。そしてもう一つ大切なこと。この場面から兵士たちは村人と同じ時間を共有することになる。兵士たちはそれぞれの思惑を持ちながらも、村人と同じようにこの不思議な雪を眺めていた。頭に洗面器(ヘルメット)をかぶっていた兵士は、いつのまにか一緒に働き、一緒に酒を飲み、一緒に眠ることになる。村の食べ物を食い荒らす巨大なイノシシに対しては、敵味方入り乱れ奮闘していた。アメリカ人のスミス大尉も参加。それぞれの能力を生かし、機知にとみ勇気にあふれる行動に、トンマッコルの村人たちも拍手喝采である。みんないい人である。この村には、誰かを拒む理由はどこにもないのだ。誰かを拒む理由なんて、よっぽどじゃないと生まれない。たくさん働いて、たくさん食べていたら、誰かを拒む理由なんて生まれようがない。ましてや、殺したいと思う理由も。ようこそ、ようこそ、ようこそ。それでも時代は朝鮮戦争の真っ只中。さりがたいほど村への愛着がわく兵士たちと彼らに親しみと持った村人たちは現実という濁流へ飲み込まれようとしていた。連合軍がスミス大尉救出作戦を決行。ようこそトンマッコルへ。村の入り口にある人形たちがそう囁いているのが彼らのは聞こえない。戦争中の土地はすべからく戦地でしかない。いっしょになればわかるのに、人民軍の兵士、韓国軍の兵士、いつしかお互いの名前を知り人柄を知り、親しみが深まり仲間となり共に戦うことになる彼らは、トンマッコルの人と一緒に花火を観ることになる。最期の花火を。もし戦争がなかったら、人柄の高潔なリ・スファと正義感の強いヒョンチョル、二人は、得難い親友になれたかも知れないのだ。しっかりとした良識を持つヨンヒに出会い、サンサンの人生は良きものになっただろう。ソ・テッキだって、ヨンヒと恋人になれたか知れない。お互いを知らない癖に、つまらない理由で殺し合う戦争というものが、5人の死によって描きだされる。トンマッコルを守るため、偽の攻撃目標になるようにたった5人で、連合軍の飛行編隊へ攻撃を仕掛けたのだ。一緒に食べる、一緒に眠る。一緒に働き、一緒に遊び、一緒に笑う。トンマッコルはそんなところ。殺し合いなんてここで生まれるはずはなかった。村人たちは、誰も拒まない。ようこそトンマッコルへ。トンマッコルへようこそ。
2007.07.24
コメント(0)
-
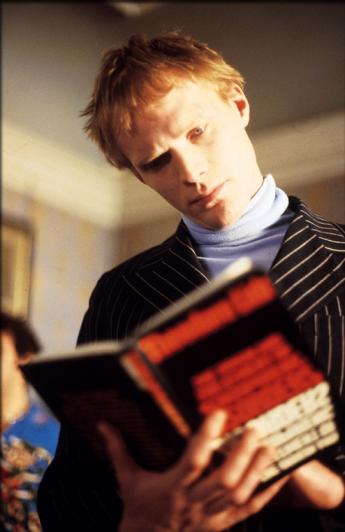
●●●デッドベイビーズ
さあ、パーティだ。とことん、ブッとぼう。イッちまおう、イカれよう、そして。殺しちまおうぜ、カンタンさロンドン郊外の静かで大きな屋敷。そこに6人の男女が住んでいた。毎日、毎日、イカれて住んでいた。毎日、毎日、ブッとんで生きていた。毎日、毎日、イカれてブッ飛んでいたら、週末くらいは、もっと、もっと!もっと!もっと!イカれて、ブッ飛びたいと思うはあたりまえ。さあ、パーティだ、最高のドラッグが彼らを待っていた。そんな連中の中に、ポール・ベタニーがいる。彼が演じるのはクエンティン。あんまり自分で何も決めないくせに、自己主張ばかりする6人の中心にいて、さも愉快そうに歪んだ自説を吹聴するリーダー格。白い面差しに細い手足、紳士のように振る舞うときもあるが、中身は誰よりもイカれていると言う役柄である。ラストシーンを含めて、彼の演技を骨の髄まで愉しめる設定だろう。さあ、パーティだ。屋敷のお坊ちゃんはジャイルズ、ボロボロの歯が抜け落ちないか心配ばかりしているアル中。口だけの暴君アンディの妻ダイアナは、セックスレスの毎日に悶々としている。クエンティンの妻シリアは彼にベタ惚れだがヒステリー。もう一人、全くの道化役なのはキース。容姿からアソコから性格まで彼は、他の5人にバカにされるために存在していた。この6人にプラスして、週末やってきたのは4人。その中には、究極のドラッグを持ってきた男と、誰とでも寝るルーシーが混じっている。火種は充分。ドラッグは人間の欲望と、隠された性格とが相関してハイになるらしい。しかしコイツらはそれをパーティにする。パーティにすることで、自分もラリってラリっている相手を笑って、蔑んでいるのに、愉しんでいるという趣向がまる見え。悪趣味全開なのはボインの姉ちゃんとウンチだけじゃない。殺人予告まで舞い込むがこいつらはもう、イッちまってる。ヤク中だらけの中のミステリ的展開。殺人予告はWEBで話題の【殺人論者.COM】殺人論者の称号をもらうには、殺戮の現場に排泄物で「G」の文字と血で「ジョニー」の署名を書き残し、それを写真にとってインターネットにアップすればいい。10人の中に犯人がいるのだが、イッちまってる奴らに犯人を捜せるはずはない。悩める若者が手を出したドラッグではなくイイオトナが手を出したドラッグである。毎日、毎日、イカれて住んでいた。毎日、毎日、ブッとんで生きていた。だからこそ、もっと刺激を。だからこそ、もっと強烈なドラッグパーティを。だからこそ、もっとエクスタシーを。欲望が欲望を肥大させ、さらなる刺激を追い求めた結果、10人の中の一人は、殺人論者の称号を得ることになる。一人を残し、誰もいなくなってしまった。犯人探しはするだけヤボ。オチは映像で確認すればいい。デッドベイビーズ、彼らは既に、死んでいたも同然だったのだ。まさに、典型的なポール・ベタニーがいる。この作品のイカれ具合とポール・ベタニーが程良いのだ。2000年のイギリス映画のようなアメリカ映画。Japan:R-18 / UK:18 / USA:R / Finland:K-18既製品になる寸前の作品である。
2007.07.23
コメント(4)
-
●●●SAW3
ゲームが続いている。私たちは麻痺してしまっている。麻痺していることを、確認させられる日が、いつか、来る。アマンダのように。ジグゾウのゲームは続いていた。ローレンス・ゴードン医師に死の宣告をされてジグゾウは気がついた。気がつき、実行したのは、死のゲームである。だが、彼が招待するゲームには、たった一つだけ針の目のように小さな小さな、小さな小さな小さな生きる望みが残されている。コンマ以下に近い、わずかな、望みが。ゲームが続いている。エリック・マシューズ刑事の同僚ケリーもまた、ジグゾウに遭遇することになる。何も出来なかった者は、何もしなかった者として裁かれるように。死の床にいながら、ジグゾウは有能な医者をゲームに招待する。医者の名前はリン、彼女はジグゾウのカルテを手に、そのゲームがどれだけ無謀かを説明していたが、受け入れる彼ではない。「末期脳腫瘍:手術不可能」ある男のゲームが終わるまでジグゾウを延命させられないと、彼女の首に巻かれた円状の爆弾が爆発するのである。傍らにはいつもアマンダがいる。アマンダはかつてジグゾウのゲームの招待され生き残り、やがて彼の手足となり働くようになっていた。ゲーム続行。自動車に息子をひき逃げされたジェフ。何者かに拉致され、再び目覚めた場所は食肉工場。「さあ、ゲームをしよう」息子が死んでから復讐心だけを糧に生きてきた男は、ジグゾウの装置に拘束された事故の目撃者や判事、そして犯人に対面する。彼らのわずかな生きる望みは、ジェフの「許し」のみである。殺してもいいと思えるほど憎い相手の命を救うことが出来るのか。ここで一つ考えてみた。もし、簡単に、ジェフが彼らを許してしまったら。ジグゾウの装置は発動せず、残虐な場面は描かれない。そうなればこの作品は、意味をなくしてしまうではないか。残虐な場面を私たちが観ることが出来たのは、ジェフが彼らを完全に許すことができなかったということ。人間の身体はどこまで回転するのか。手、足、首、身体!!ジグゾウのゲームは変質していている。かつてのゲームは、招待された本人が装置に拘束されていた。本人が痛みを享受し、命というものに対面させられていた。だが今度のゲームは計画した者も執行した者も、維持する役目を負った者も、そして、何よりも観客も参加させられている。私たちは映画であること充分に知りながら、ジェフが許さないことを期待し、残虐な映像を期待しなければならなくなってしまった。しかも人間はそういうものだと、思ってしまっているからこの映画のラストシーンは成立してしまっている。そういうものではないかもしれないのに。わずかな救いがあるはずなのに。アマンダ、アマンダアマンダ。彼女は麻痺してしまっていたようだ。彼女はわずかな救いを手にすることが出来なかった。今回の登場人物たちの関係性は、ラストシーンになるまで分断されていた。そのことがこの作品の物足りなさになってはいる。だが、このシリーズは、前作の流れを汲みながら続いている。今回の作品もプロローグなのだ。ジグゾウの装置は、まだたくさん残っている。ゲームが続いている。私たちは麻痺してしまっている。麻痺していることを、確認させられる日が、いつか、来る。いつか、きっと、来る。
2007.07.20
コメント(4)
-
●●●理想の恋人.com
まあ、なんていうか。やっぱり、こういうもんなのだ。うん。そう。歯切れが悪くなるけれども、そのへん・・・どのへん?ってそのへん。一人ひとり、みんな違う。恋愛。女性は、サラ・ノーラン。幼稚園の先生。8ヶ月前に離婚したばかりの30代。男性は、ジェイク・アンダーソン。彼も最近離婚している。30代後半くらい。スカルという手漕ぎの船を作る職人さんのようだ。『ドクトル・ジバコ』の映画が好き。二人が出会ったのは、出会い系サイト“perfectmatch.com”参加したのは本人の意志ではない。周囲の人間に申し込まれてしまったのだ。恋愛が成就するのはゴールじゃない。恋愛映画ならゴールに見えるけれども。Must Love Dogs 最初は犬が必要だった。星空を好み、犬が好きな人、が、サラのデートの条件だったのである。犬好きの人に悪い人はいない。ヘンな犬が2匹と、かみ合わない会話をするサラとジェイク。どうみても、いいオトナである。最初のデートは最悪。避妊具を探し回るデートもあった。とにかく、いろいろかみ合わない。なんか、かみ合わない。うん。そう、でも。かみ合っていなかったとしても、だ。少しずつ、なんとなく、この人なんだ、といつのまにか思えてくると、いう「感じ」が生まれてくることがある。何も恋愛に限ったことじゃない。友情もそうだ、仕事もそうだ。いろいろ、いろいろあって全てが違うのだ。サラがジェイクに出会うまで、“perfectmatch.com”で知り合った相手と何人も一回だけで終わったデートをしている。実に失礼な奴もいれば自己中な奴もいる。現実にサラは、幼稚園での教え子の父親とも良い関係を気づきそうになる。いろんなことがある。犬好きだから、恋愛がうまくいくとは限らない。犬好きだからうまくいった恋愛も当然あるだろうけど。出会い系サイトの情報は、多くは真実である必要はない。だが、会って、最初はイイ感じでも付き合ううちにいろんなことがわかってくることで、いい方にも悪い方にも転んでいくのだろう。ただし、サラもジェイクも、悪い方に転ぶ可能性を考えられる年齢ではあった。ダイアン・レインはそこそこの経験値を持つ女性の、魅力と一緒に生態までも演じてくれる。ジョン・キューザックという役者は男性の中にある男の子の部分を上手く表現してくれる。この二人の役者だからこそ、わかる、感じがある。こういう、もんだ、という感じ。二人の恋愛は実ったかも知れないが、まだ、これから、いろいろあるのだ、きっと。ゴールじゃないのだ。なにせ、サラのお父さんは、“perfectmatch.com”に登録してたりする。サラともデートの約束をとりつけていた。男やもめさんである。けれども、たくさんの女性に囲まれていようとする。困ったもんである。ネットで知り合う恋愛がスタート。ほとんどが上手くいかなかったという成功率が可笑しい。現実にはアブナイ状況もあるのである。けれども最初は誰も、お互いのことなんてわかってるはずがない。Must Love Dogs 確かにそうかも知れないが。けど、そう。なんていうか。みんな違うのである。
2007.07.18
コメント(0)
-
●●●尋秦記 タイムコップB.C.250 その2~歴史には誤差の範囲内ってのがあるような気がしてきた。
紀元前250年に、タイムスリップ!中世や近世なんてもんじゃない。古代も古代、おおいに古代である。そんな時代に2000年後を生きていた男が現れた。項少龍(ホン・シウロン)。この男は優秀な刑事であるが、中国の古代史に詳しいという設定である。なんとかして現代に戻りたいから、歴史を変えてはいけないという大原則を守ろうとする。守ろうとするのだけど、守りきれるはずもない。タイムスリップっていうネタは、いつだって作品を面白くしてくれるのだ。まず、主人公は帰れるのか。ドキドキハラハラするとこだもんね。それから、時間の歪みをどう説明するか。実はココのところがキモで、時間の歪みの説明を蔑ろにすると、作品は一気に降格して駄作になる。「尋秦記」に関して言えば、コメディの要素も多く、ツッコミながらも楽しく観れてしまうのだろうけど。それは私たちが外国人で、中国史を知らないっていう大前提があったりなんかしたりして。出来うる限り中国の歴史を見直し、「尋秦記」という作品に織り込まれた中国史を考えてみる。(かなり無謀なことしてます。お許しを)まず最初に項少龍がぶつかる歴史は「和氏の壁(かしのべき)」である。完璧、という単語の語源となるエピソードにもちろん、項少龍が絡むはずはないのだが、おもいっきり絡んでくるのである。なにせ、「和氏の璧(かしのベき)」という宝物は、趙になくては歴史はつながらないのに、楚に持っていかれようとしていた。戦国の七雄を復習しておく。秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓「和氏の璧」と完璧をつなげる故事は、趙の藺相如(りんしょうじょ)という人が、活躍する。問題の発端は秦。自分とこの15の城と「和氏の璧」を交換しませんか、と秦が言ってきた。だが当時の情勢ではそんなこと信じられるはずはない。けど、断れば秦が攻めてきて、趙は一巻の終わり。そこで項少龍は藺相如のしたことを断片的に真似て、楚に持っていかれそな「和氏の璧」を趙にあることにした。「和氏の璧」のエピソード。これは、もう既に項少龍の登場によって歴史が変わってきていることを指している。その変化を項少龍自身で戻しているのである。「和氏の璧」までに項少龍はこの時代にチョコレートとカタコト英語を持ち込んでいる。もう一度確認しておくと、項少龍は中国の古代史に詳しいという設定。なんとかして現代に戻りたいから、歴史を変えてはいけないという大原則を守ろうとする。だが彼の思想そのものがこの時代とは異質。権力に近い場所にいるのにも関わらず、性格的に権力志向が全くない。(縛られたくない性格。だから恋人との結婚さえ避けていた)刑事という職業からか、正義感が強い。しかしこの時代、義はあっても正義感はない。そして一番大きいのは女性への対応。項少龍は出会う女性に対し、個性を観て対応する。勝ち気な女性には楽しく明るく、重い責任を背負った女性には尊敬の念を持ち、強がりだが気のいい女性には信頼の顔を見せる。この時代の女性たちは現代よりもずっと、個性が認められないでいるという表現が随所にある。主人公が女性にモテる行動をするのは差し引いても彼と出会うことで女性が自らの生き方を貫こうとすることで、歴史はどんどん変わっていく。ただし、ここでいう歴史は、項少龍が学んだ中国の古代史であって、真実の古代史かどうかは定かではない。実際、そんなことはどうでもよくなるのだが。少し横道にそれるが。「龍陽の寵」という言葉もある龍陽は魏の家臣「龍陽君」を指すらしい。中国最初の男色家、とあったが、演じる俳優は女性だった。興味深いもんである。項少龍はシェイクハンドで挨拶していたというオマケつき。龍陽君、「尋秦記」一のワザを見せる連晉(りんちょん★)に負けないくらいの剣さばきである。その連晉、(ろうあい)という剣客に化けるのだが、この(ろうあい)は始皇帝の母の愛人として名を残している。※漢字で表記しきれない、または化ける文字があります。 その場合は()にひらがなを入れてます。★(りんじょん)とも聞こえました。。歴史が変わっていく。そして大問題が巻き起こる。人質だった後の始皇帝、?政(えいせい)が実は偽物でしかも死んでしまう。その上に農村で暮らしていた本物も実は既に亡くなっていたという事実発覚。このピンチもまた項少龍はなんとかしてしまう。そのことで趙盤(ちゅうぶん)という少年の運命がどんどん変わっていってしまう。つまり趙盤が始皇帝になるのが後半のストーリー。その時、項少龍は大将軍だったりする。おもしろいのは、項少龍が自ら歴史を修正出来たのは、趙盤が権力を本格的に得るまで、であったこと。項少龍と趙盤が歴史の表舞台にでてしまったとき、ふたりの姿は一時、鏡に映らなくなる。(よくある演出であるが、ドキドキした)現代まで残っている歴史というのは、勝者の歴史だろうし、真実かどうかわからない。その歴史の表舞台に立ってしまったとき、自由気ままに動けていた項少龍に消滅の危機が訪れる。それまでの彼は誤差の範囲内、なんとか歴史という縦糸に戻れたものを、名を残すほどの権力を持ってしまった時点で、人間というのは身動きがとれなくなるのだろうか。小さな歴史のズレをも飲み込む大きな歴史という時間。そういうもんを描いたのが「戦国自衛隊」なのかも、と一応映画も原作も読んだので書いておいてもいいだろう。もひとつ言えば、個人的に私は歴史が嫌いじゃない。寧ろ好きだったりする。ここまで、きた。現代につながっている過去。通史が全てだとは思っていないが。実は項少龍、現代に戻らない。その経緯は語るものでもないので止しておこう。ただ、彼は歴史の表舞台から消える。このことは「焚書坑儒」ということと絡む。秦の始皇帝が行った施策の一つは、項少龍という名を記録から抹殺する意味もあったのだ。とまあ、項少龍は古代に家庭を持ち、幸せに暮らしましたとさ、では「尋秦記」らしくない。項少龍。この作品の主人公の名は「項」でなくてはならなかったのだ。歴史に詳しい方ならすぐ気がつく仕掛けである。けれど、知らない方がビックリできるエンディングである。参考文献(wikiの関連ページにリンクできません。なぜ?)■「始皇帝」について。一番のキモです。http://ja.wikipedia.org/wiki/■始皇帝のお母さんの愛人について。「ろうあい」http://ja.wikipedia.org/wiki/■なぜか、「十二国記」になる「龍陽の寵」http://homepage3.nifty.com/tamatebako/novels/omake/hyakuninisshu/100-65a.html■和氏の璧の「璧」の璧は「完璧」の璧で壁じゃない。http://www.c-able.ne.jp/~s-town/gyoku.htm■焚書坑儒。紙のない時代だから木と布の書物を焼いてました。http://ja.wikipedia.org/wiki/※辞書より転載前213年、秦の始皇帝が行った、主として儒家に対する思想言論弾圧。民間にあった医薬・卜筮(ぼくぜい)・農事などの実用書以外の書物を焼き捨て、翌年、始皇帝に批判的な学者約460人を坑(あな)に埋めて殺したといわれる。転じて、学問や思想に対する弾圧をいう。
2007.07.17
コメント(3)
-

●●●尋秦記 タイムコップB.C.250 その1~紀元前まで遡るタイムスリップもんってかなりレアかも。
A STEP INTO THE PAST 香港で年間視聴率1位を記録した、2001年のテレビ番組である。香港の特別警察G4に所属していた項少龍(ホン・シウロン)がタイムスリップしたのは紀元前250年だった。時は中国の戦国時代、秦・楚・斉・燕・趙・魏・韓まだ秦の始皇帝が即位する前の時代。キリスト生誕の物語が始まるよりも、まだ200年以上過去の物語である。「この兵馬俑、おまえにそっくりだな」兵馬俑展の警備にあたっていた、特別警察の仲間にそんな指摘をされる項小龍。物語は現代の香港から始まる。優秀な刑事である項少龍、若き実業家、李を助ける功績を上がるが、心の中は7年間付き合っていた青という女性が気になって仕方がないようである。彼女は結婚するためにプラハに旅立っていた。いつまでも彼が結婚話をはぐらかし続けた結果である。取り返したくても取り返せない時間そんな項少龍に実業家の李は、とんでもない話を彼に持ち込んだ。タイムスリップ。紀元前247年に飛び始皇帝の即位式の写真を撮ってくるという実験の被験者になった欲しい。もし、成功したら、恋人、青との仲も修復できる時間が得られるかも知れない。古代史に詳しいことも手伝って項少龍は古代の服に身を包みタイムマシンに乗った。ところが。彼の飛ばされたのは3年前の紀元前250年。しかも場所も秦ではなく趙であった。持ち込んだ発信器も作動しない。簡単に帰れないことを覚った項少龍はまず、秦の都、咸陽を目指すことにしたのだが、そうは上手く話は運ばない。最初の古代での彼の舞台は趙の邯鄲。彼が現代に戻るためのキーパーソン、始皇帝は母親の朱姫と一緒に趙の人質となっていた。秦の宰相、呂不韋の密命を受けた烏家と一緒に、後の始皇帝、?政救出が最初の関門となった。原作のあるテレビドラマのようである。おそらく秦の始皇帝の師匠となる項少龍は、まさにヒーローでもあっただろうが、この作品の彼は現代にいる等身大の青という女性に恋する男性でしかない。しかもチョコレートは持ち込んでいるし、古代の服の下はTシャツにトランクス、go!、Thank you、oh my godなど英語を連発する。それでも人なつこい明るい性格と、持ち前の正義感や機知に富んだ考え方で、たくさんの人に支えられながらも次々と巻き起こる問題に立ち向かい解決してゆく。刑事であるから、戦う術は心得てはいるが強くないのである。最初に身につけたのも墨子剣法、つまりは攻撃ではなくて守る剣法である。そこに独自のアレンジで自己流に戦ってはいるが、常に敵味方関わらず彼よりは強いようである。剣なら最強の登場人物、連晉にも勝利するのも、お互いの命は奪わないという約束してから決闘し、項少龍は連晉の右腕を斬りつけ、連晉は彼の腹に剣をつきつける。普通なら死んでるはずが項少龍は腹にお手製の防護服をつけていたから問題ない。それよりも約束を破った連晉が非難を浴び、腕も未熟な項少龍が勝者になってしまった。項少龍VS連晉の決闘にも、さまざまなサイドストーリーがあるがまたのお話。少しばかり項少龍を演じる古天楽(ルイス・クー)のことを触れておこう。香港の俳優さんの事情に詳しくないが、1970年生まれ、金庸の作品の主人公も演じているから武侠的な作品にも実績もある方のようだ。中国ペプシのCMも長くされている。モデル出身。と、ここまでは容姿端麗で片づけられるが、実に役柄の幅が広いことでも有名らしい。精悍な顔つきから刑事や裏社会の男の役が多いというが、ラブストーリーの出演作もある。2004年製作の「Mr.BOO」のリメイク版、『新世紀Mr.BOO!ホイさまカミさまホトケさま』では3バカ大将の一人を演じている始末。日本公開作も増えているとのこと。ジャッキーチェン主演の『プロジェクトBB』では、ポスターに大きく姿が載っている。見慣れぬ香港のトップスターに最初は戸惑ったの正直な話なのだが、古天楽は動きだすほどに観る側を惹きつける。役柄の幅の広さがあってこそ、魅力的な「項少龍」が出来上がったのだろう。時代による文化の違いからタイムスリップによる歴史観まで、興味深い内容が詰め込まれた作品である。男尊女卑の時代で項少龍は現代の女性像を持ち込んできたりするのである。それに、武侠作品的な側面も多いと思うのだ。ハリウッドなら見慣れたテーマでも紀元前250年まで遡ってくれちゃってるから、ツッコミどころ無視しても楽しい。全40話の作品。全く、個人的な(遊び的な?)考察も加え、続きはまたでございまする。
2007.07.16
コメント(0)
-
●●●ダーウィンの悪夢
「ダーウィンの箱庭」ヴィクトリア湖がそう呼ばれていた頃、きっとさまざまな種類の魚であふれていたことだろう。その湖を地上とだぶらせてみれば、この湖のどれだけ異常が見えてくる。半世紀ほど前、ナイルパーチという大きな魚が、ヴィクトリアの湖の魚たちを駆逐してしまった。「大きな」人間が「小さな」人間を「駆逐」してしまったとしたら、そこはもう、異常な世界だ。アフリカ、タンザニア。ヴィクトリア湖畔の街、ムワンザでは、ナイルパーチによって一大産業が築かれていた。湖から魚を引き揚げる人々、工場で加工する人々、加工品を輸送する人々。やがて店頭に並び、私たちの食卓へ。単純にも見える流通ルートである。だが、そのルートの脇には、エイズで死んでいった若い女性が立っている。あるいは、粗悪なドラッグを嗅ぐストリートチルドレン。アンモニアガスによって、眼球が落ちてしまった女性もいる。そんなに遠くない場所に、戦争で命を落とした人々の顔が見える。みんな、ナイルパーチの流通ルートとつながっている。グローバリゼーション。国や地域という境界を越えたつながりが強まることは、一見、素晴らしいことのように見える。素晴らしい部分も確かにある。そして、私たちは素晴らしい部分しか観ようとしないところがある。何事にも闇があるのだ。ナイルパーチを引き揚げるのにもボートがいる。しかし、誰もが持っているわけではないのだ。大きなナイルパーチの加工工場。しかし、誰もが勤められたわけでもないのだ。ナイルパーチ、食用にもなる巨大な魚。しかし、値段が高すぎて現地では食べることが出来ない。何もかも、すべてに行き渡るはずがないから、行き渡らなかった者たちの選択は限られてくる。フーベルト・ザウパー監督は、街の生の姿を拾いそのまま映像にした。夜、建物の片隅で、二人の子供たちが心を落ち着かせるように吸うドラッグは、ナイルパーチの梱包材を溶かしてつくったものである。二人はそれを吸引してやっと、自分たちの中の不安を落ち着かせているように見えた。「大きな」人間が「小さな」人間を「駆逐」していく。ヨーロッパへとナイルパーチを運ぶ飛行機から、大量の武器が見つかったという。本当ならナイルパーチを積むために、からっぽであるはずの飛行機なのだが。いまなお続くアフリカの紛争、使われている武器が受け入れる入り口になれるのは、社会のシステムが崩壊している場所のみ。大都市の空港で行われる厳しいチェックが、行われないのなら武器もまた流通して当然。アフリカがアフリカを壊している。得をしているのは戦争で儲けている人たちだけ。さて、ナイルパーチである。主にヨーロッパで流通している魚であるが、日本でも「白スズキ」として食用されていたという。お弁当、給食、レストランの白身魚として使われている場合も多い。流通ルートをめぐって日本にやってきたナイルパーチ。だが、そのルートの脇には、エイズで死んでいった若い女性が、粗悪なドラッグを嗅ぐストリートチルドレンがアンモニアガスによって、眼球が落ちてしまった女性がいる。そんなに遠くない場所に、戦争で命を落とした人々の顔が見える。この映画を観たあとに、何も言えなくなった。グローバリゼーション。ナイルパーチだけじゃないのである。「ダーウィンの悪夢」公式サイト
2007.07.12
コメント(4)
-
●●●キサラギ
自殺したD級アイドルのファンだった5人の喪服の男が密室で繰り広げる絶妙な掛け合いの傑作コントである。あれえ?そうじゃなかったなあ。自殺したD級アイドル、如月ミキの一周忌、ネットで知り合った5人の男が解き明かすのは、彼女の自殺の原因。次第に解き明かされるのは、5人の男の如月ミキとの関係、だった。ミステリの要素たっぷりの密室会話劇。って。合っているけど合ってない。ミステリのドキドキ感はすべて笑いに変わっていた。笑った!笑った!古びた小さな部屋で、如月ミキ一周忌の手製の垂れ幕を張り、秘蔵の如月ミキ写真集をテーブルに立てかけて準備しているのは、このオフ会の主催者「家元」である。最初にやってきたのは「安男」、自分で焼いたりんごパイ持参でやってきた。「スネーク」「オダ・ユージ」「イチゴ娘」と、招待客は自分のキャラ全開で登場する。ハイテンションのスネークはすぐに場に溶け込んでいるが、オダ・ユージはムッツリしかめっ面。イチゴ娘を名乗る中年の親父は、喪服に着替えてイチゴのカチューシャを頭に。彼曰く、如月ミキの私物だと言う。如月ミキ。一年前、部屋ごと焼けてしまったグラドル。歌も下手でダンスも下手で、素人っぽさが抜けないまま死んでいった。何故、死んだのか。犯人は、おまえだ!!!と、自分の推理を披露するのはオダ・ユージ。名指しされたのは、イチゴ娘。だが、犯人を見つけて誰かが悪い!と決めつけるのは、この映画の趣旨じゃない。誰でも笑える定番のギャグもなく、コメディアンのアドリブ連発があるわけでもない。天然ボケキャラが天然を出すタイミングもない。笑わせる演技とは、泣かせる演技よりも難しいと聞く。計算された脚本と演出と演技と間合いで、引きづり回されて笑わされるのである。家元には、小栗旬、人気者には必ず華がある。モヒカン姿も披露したスネーク小出恵介は、芸達者でもある。二人の旬の役者に絡むのは彼しか出来ないオダ・ユージ役、ユースケ・サンタマリア、とにかくヘンなパワーだ。本格的な芸達者、香川照之のイチゴ娘は出過ぎす、やりすぎず、けれどもオイシイ。安男役は、塚地武雄、ただ一人本職のコメディアン。前半はボケ役に徹していた。ツッコミにボケにオイシイ役と、誰が誰かと言い切れないがそれでも、キャラクターは全てコントの役割を担っている。間違いなくこの作品は、計算されたコントなのである。笑って笑って気持ち良く笑って、そのうち彼らのことがわかってくると、彼らが何故、如月ミキを愛したかわかってくる。たいした取り柄のないD級アイドルだ、容姿や才能を愛したわけでもない。けれども、彼らは誰もが、周囲の誰かを愛するように如月ミキを愛していたのである。・・・一人だけ状況の違う奴もいたのだが、彼だって、そう、変わらない。愛された者は、愛した者にとっては、もう、スターだ。隣の誰か、むこうの誰か、あそこの誰か。遠い場所にいる誰か、写真の誰か。容姿や才能や、血縁のあるなしも関係ない。ましてやお金とか地位とかでもない。愛された者はもう、スターだ。しかし、まあ、笑った。たくさんの笑いが最近は氾濫しているが、計算された笑いは、また格別なのである。「キサラギ」公式ブログ
2007.07.11
コメント(2)
-

●●●ホテル・ルワンダ
1994年、4月6日、ハビャリマナ大統領死亡のニュースがルワンダに駆けめぐる。その時、国内にいた多くの人の人生が瞬時に変わってしまった。一瞬で変わった運命。血沸き立つ想いで銃をとったフツ族の民兵グループ。息を潜めて暗闇に身を広めるしかなかった、ツチ族のひとびと。地に染まるルワンダの大地。後に赤十字が算出した死者の数は100万人。日本の政令指定都市の人口の基準が100万人。野球のスタジアムを埋め尽くす満員の観衆の数は3万人だっただろうか、5万人だったか。累々と死体がルワンダを埋め尽くす。ツチ族というだけで、殺された人々の屍が。ルワンダの首都、キガリ。ベルギー系のホテル、『ミル・コリン』で支配人を勤めるのはポール・ルセサバギナ。フツ族である彼は、傲慢な白人の客を上手くあしらい、彼を格下にみるホテル側にも耐えながら天性の才能か有能なホテルマンとして働いていた。この男ならきっと、世界中のどこで働いても、有能なホテルマンになれただろう。だが、彼には愛する妻と子供がいた。タチアナ・ルセサバギナ、彼女はツチ族だった。ポールがホテルに1200人のツチ族を匿い、ギリギリのボーダーラインをすり抜けていく。有能なホテルマンは、客の好みを確実に把握し、的確に提供する能力を持つようだ。ポールの戦う力は、その能力に他ならない。銃や他の武器ではなく、機知と行動力、そして原動力となるのは家族への愛情からだった。ルワンダに滞在していた外国人は、次から次へと脱出してゆく。志あるカメラマンが虐殺の現場をおさめていたが、ジャーナリズムにルワンダを救えない。「我々は平和維持軍だ。仲裁はしない」空色のベレー帽をかぶった国連軍を率いる大佐は、葛藤を続けてはいるが、ルワンダを救えない。ルワンダは、政治や金でも風評では救えない。それらは、一つの力になるまでに時間がかかりすぎる。その間にも失われていく命がある。無差別に、闇の時間は訪れるもの。どの場所にどんな闇が訪れるか予測はできない。巻き込まれてしまった人に逃げる術はない。ポールは物資を補給した帰り道、策略にあい、怖ろしい道を車で通る羽目になる。その道を必ず通らなければならないのに、その道は死体で埋め尽くされていた。運転して進むことは、タイヤで死体を踏んでいくことに他ならない。志の高い映画に出会った。この映画の作品性は、事実を語るという目的を持っている。映像的な衝撃を抑えながらも、観る側にしっかりと憤りを感じさせる演出は可能な限り、偏りをなくした所以だろう。ドン・チードルは主人公のポールを演じてはいるが、その前にポール・ルセサバギナであろうとしている。最初は家族のことしか考えていなかったし、家族への愛はずっと変わらなかったが、ホテルマンであり続けたし、いつも彼らしい選択をし続けていた。観る側の視点を体現していたのがニック・ノルディやホアキン・フェニックスという、強い個性を放つ俳優であある。良識を持ちながら何もできなかった外国人を演じた二人も、ひとつの事実を明確に物語っている。これは全くの私見だが、たくさんの命を救った主人公の映画は、立派な大義名分よりも家族や友人のため、身近な愛情から行動していることが多いように思う。それは、少なからず「事実」だと思うのである。「ホテル・ルワンダ」公式サイト
2007.07.09
コメント(2)
-

●●●コントロール
この作品のトラップはまぎれもなく役者の演技だろう。レイ・リオッタ×ウィレム・デフォー。登場するだけで怪しいと感じさせる役者の共演である。「アナグレス」その新薬は、人間の性格や行動を修正する効果があるという。被験者として選ばれたのは、凶悪犯、リー・レイ・オリバー。死刑が執行され、死んだはずの彼は息を吹き返し死体袋の中で選択を迫られる。被験者になるか、そのまま、死体となるか。「アナグレス」を開発したのは高名なる神経薬理学者コープランド博士。既に他の薬でも製薬会社に貢献している。潤沢なる資金の元に始まった新薬の実験にコープランド博士は高い志を持ち取り組んでいた。リー・レイ・オリバーをレイ・リオッタがコープランド博士をウィレム・デフォーが演じる。凶悪犯のリー・レイ、大きな目を見開いて周囲を睨み付け、実験に反抗し暴れ、逃走を試みる。何度も実験は中止しかかるが、コープランド博士の熱意が通じたかのように、リー・レイに変化が表れていた。涙を流したのである。自分の犯した罪の意識から。実験は第二段階へ。リー・レイは街に部屋を与えられ、仕事を見つけ働き始めた。ただ、部屋には監視カメラがあり、6時間づつ「アナグレス」投与は続けられていた。彼はその生活の中で、テレサという女性とも知り合い惹かれあう。だが、犯した罪の重さは消えない。彼はまっすぐ悲劇へと向かっていた。「アナグレス」喪失などのミス・リードを感じさせるエピソードが観る者を微妙に困惑させる。レイ・リオッタ×ウィレム・デフォー。しかも、役者の存在感がストーリーをかき回してくれている。だが、結末に向かう伏線は丁寧にはられていた。複雑ではなく真っ直ぐなストーリー。しかも暖かな人の心を描いているのだ。たくさんは語れない。驚くようなドンデン返しなんて、この作品には必要ないように思う。演じるというのは、多くは架空の物語の登場人物にすぎないが、それでも「人間」が演じているのである。この役者しかできない、またはこの役者とあの役者の共演で、映画が面白くなるのは、人間の力だと思う。
2007.07.08
コメント(2)
-

●●●必殺仕事人2007
■藤田まことは嘘をつかないとある雑誌のインタビューで、藤田まことは新しいキャストについて評した。東山紀之はもうベテランで言うことなし、後継者に指名済みのようである。松岡昌宏の動きに、彼はアドバイスをしたそうだが、演じ終わったあとには思わず拍手としたという。若い大倉忠義には将来性を感じたらしい。ああ、その通り、だと思う。■あの歌この歌トランペットアレンジテレビでどの作品を観たか、というのは、ジェネレーションを測る物差しなわけでして、必殺の場合は広い年代に愛されているせいか、どの歌を知っているかがポイントとなるだろう。ってわけで、三田村邦彦が歌っていたあの歌がどうしても耳に入るけど、やっぱり、ラスボス対決のあの音楽はなくてはならないと、改めて思ってしまったぞ。■松岡昌宏のコマーシャル?松岡昌宏が自室にいるシーンはどうみてもなんかのコマーションのようである。「ポン酢」「和風だし」「みそ」「しょうゆ」食い道楽の涼次に似合いそうである。■南町奉行所のあの若者は?やたら渡辺小五郎に絡む働き者の若い同心は、今回物語に絡んでなかったような気がするが、なんか、賢そうである。気になる・・・。■南町奉行所にさわやかな男が同心を演じる俳優さんたちの中で、東山紀之はどうしてもどうしてもさわやかに見えた。■年の差カップル源太と薫のカップルはどうして相思相愛になったのか。妄想はできるが、真実は知らない。■シリーズを見込んだ作品づくりどう考えても、そうとしか思えない。今回の作品の作り方は海外ドラマで言うパイロット版、人物の紹介をしている節がある。■マジメにストーリーについてストーリーについては、あんまり考えたくないのである。考えるほどのもんはなかったのような。悲劇の要素が少なかったのは仕方ないのだから。■女優陣が作品にはまってた和久井映見、水川あさみ、原沙知絵男子優先だから、目立たないのであるが、みなさん、拍手なのである。特に和久井さんブラボー!■藤田まことは嘘をつかない2必殺は、中村主水と「せんとりつ」は一体もん、というようなことをおっしゃっていた。■殺しのテクニック妄想は出来るけど、現実はわからない。とくにからくり屋の源太くんのはね。経師屋の涼次さんは忍者さんなのであの殺し方は妄想全開にできるけどやっぱ謎が。何にしろ毒をもられたガイシャの顔の絵ヅラがよくないのがツライねえ。だから、隠してるんだろうけど。■光とカゲとうなじのゲージツ必殺はやっぱり、光とカゲの出し方なのだ。今回は充分じゃないけれどもテキドにあったので満足石原興監督、ありがとうなのである。それと、実は女性が美しいのもこの作品の特徴で、若い人はともかくもベテランや大ベテランさんも美しいバランスで画面に収まっていた。「必殺」である。やっぱり、愉しかったのである。
2007.07.07
コメント(6)
-

●●●ハードキャンディ
『小さな女の子は優しそうな狼を信じてしまい、やがて食べられてしまいました。』カシャカシャカシャ。キーボードをタイプする音。ソング・ガール14とレンズマン319は3週間チャットで会話してきた。ネット上の会話が盛り上がれば、次の段階は・・「会おう。」14才のヘイリーと32才のフォトグラファーのジェフはカフェで待ち合わせをした。その男は、仕事もちゃんと持っているからチャットで知り合った女の子に、悪い考えは持っていないと理路整然という。悪いことをすれば自分の生活が何もかも崩壊するであろうことをわきまえているという気をつけて、気をつけて。頼りがいがあって優しくて、親切な大人の男だという「服」を来て、狼は今まで何人の赤ずきんを食べてきたのか。母親の教えで、知らない人の飲み物を飲まなかったヘイリー。だがヘイリーの作ったスクリュー・ドライバーを彼は何も疑うことなく飲んでしまった。目覚めれば椅子に縛られていたジェフ。ヘイリーは家捜しを始めていた。必ず、証拠があるはずなのだ。必ず、どこかに、彼が狼であるという証拠が。しかし、部屋にあるのは、普通の服を着た少女の写真ばかり。ジェフは必死で説明する。自分はそんな人間じゃない、絶対に。逆にヘイリーの心配をする。男を騙して縛り付けるようなことをする少女の心の闇を支えようとしている口ぶりで。それが陳腐な優しいであることは、もう、ヘイリーには充分わかっていた。次は、キッチンデーブルの上に縛られているジェフ。下半身は裸で、イチモツは氷で冷やされていた。医学博士の父の医学書というのを横におき、ヘイリーは簡単な手術を始めようとしていた。他の外科手術より簡単ではるが、ジェフの一生を左右する手術である。ヘイリーがどれだけ周到に準備を進めてきたのか、ジェフの女性観がどういうものであるか、台詞の端々だけで表現している脚本が素晴らしい。固定されたシチュエーションの中で、静けさと激しさ、虚々実々の駆け引きをデイヴィッド・スレイド監督は多彩に繰り広げている。まるですべてが折り重なるように深まっていく。パトリック・ウィルソン、エレン・ペイジ。二人の俳優は演じているだけでなく、シンボルになっていた。狼と、赤ずきん。ハードキャンディ。自分のイチモツが小さなガラスのコップに入れられディスポーザーで潰されてやっと、ジェフは自分の犯した罪を思い知っただろう。狼は猟師によって腹を割かれたときに、食べてはいけないものを食べたことを知る。悪いことはしているときにはわからなくて、ばれない場合もわからなくて、思い知らされたときに、やっと、認識する。ジェフは悪いことをすれば自分の生活が何もかも崩壊するであろうことをわきまえていた。最後の最後まで自分は狼でないと弁明していたけれど。弱い者が常に食べられてばかりとは限らない。小さな女の子は物語から抜け出し、逆襲した。そして物語の中へ帰っていったのである。
2007.07.06
コメント(5)
-
●●●オールド・ボーイ
人は何のために生きているのか。15年。催眠ガスで眠っては髪を切られて中華料理を食べて健康診断もしてもらって。オ・デスは監禁されつづけていた。生きていたのではなく何かに生かされていたようだ。何かと言うよりは、誰か、なのだが。監禁を生業にするパグの7.5階のビル。機能的な監禁システムはオ・デスを生かし続ける。ただ生かし続けてはいるが、人は決して誰に生かされているだけじゃない。自分でも、生きているのだ。肉体を鍛錬し続け、テレビ世間の情報を得た。鉄の箸で抜け穴を掘り続けていた。生き続けられたのは、復讐のため。オ・デスは復讐のために生きていた。やがて、解放される。その解放は自分の力ではなく誰かに開放されたからだった。彼を監禁した誰かは、今度は彼を解放した。オ・デス、彼は自分を「獣」以下だと本気で思っていただろう。ミドに出会うまでは。寿司屋で板前をしていた若いミドは、やがてオ・デスを慕うようになる。彼の復讐を自ら手伝ようにみえるが、実際は彼女も、最初から巻き込まれていたのだ。オ・デス、疾走する。戦うオ・デス、走るオ・デス、詰め寄るオ・デス。吼えるオ・デスがいて、もがくオ・デスがいる。「15年間、お前を見守っていた」ユジンに辿りつくまでの道のりもまた、オ・デスが自ら行き着いたようだが、周到に準備されていたようでもある。自分の死さえどうでもいいユジンという男は、心臓のペースメーカーをいつでも本気で切るつもりだっただろう。そうやって最後の最後まで監禁の真相をオ・デスに教えないでおくことも彼にはさぞ、愉快な代物だろう。全く。オ・デスを監禁していたこの男は、オ・デスがいたから生きていたように見える。何のために生きていたか。生かされているのか、生きているのか。バク・チャヌク監督作品。主人公の疾走はこの監督の表現そのものだろう。観るものを絶えず釘付けにしなければ、疾走感が生まれることはありえない。目を背ける暇もなく次から次へと展開するのは、ストーリー×エピソード×映像。監禁の秘密は、抜かれた歯と左手と手鏡に映った制服の彼女の下着の中で増幅され、照明の効果が主人公の心象風景を映し出す。冷たく鋭利な刃物のようにユジンを演じるユ・ジテとオ・デスを演じるチェ・ミンシクが物語の核となっている。特にチェ・ミンスクは、オ・デスの「何もかも」を演じきっている。生かされているオ・デスも生きているオ・デスも、そして、どちらでもなくなったオ・デスも。妻がいて、娘がいて15年の歳月があればオ・デスは、生かされていただろうし、生きていただろうに。何のために、彼は自ら切り取ってしまったのか。何かのために彼が行った決断だろうが、必要のないものを切り取った気もしてくる。もう、語る必要のない物語。語れる人も語りたい人もいない物語。オ・デスの中に封印された物語。
2007.07.05
コメント(2)
-
●●●ナチョ・リブレ 覆面の神様
「新鮮なサラダが食べたいな・・」修道院の料理番をしていたナチョはついに決心する。そうだ、ルチャ・リブレでお金を稼ごう。メキシコのプロレス、ルチャ・リブレ、自由への戦いという意味をもつという。なんだか・・どうも可笑しい。ジャック・ブラックが演じればダメ男が、ヒロイックな活躍をして、感動させてくれるはずなのに。そこは「バス男」のジャレット・ヘス監督。感動なんて力強い展開はしてくれない。ユルユルのストーリーとクスクス笑いの連続。憧れのルチャのスターラムセスのように、有名になってお金持ちになって、子供たちにオイシイ食事をさせようとしたのは、映画の主人公に相応しいヒロイックな動機。街で食材も貰いにきた時に、大事なチップスを盗んだすばこしい男ヤセとタッグを組みルチャに参戦、初戦で勝てるはずもなく、惨敗と言える結果。だが思わぬメリットを二人にもたらした。ファイト・マネー。観客が彼らのファイトに大受けしていた。負けても二人はルチャの世界に受け入れられていた。負けても負けても、ナチョとヤセはお金を得た。リングでの衣裳も良くなっていったし修道院の子供たちに食べさせる料理もグレードアップ。でも、なんか可笑しい。彼は負け続けファイトマネーだけをゲットする。勝たないのだ。勝ち組にはならないのである。そして、もひとつ可笑しいことがある。修道院に新しいセンセイとしてやってきた美しいシスター・エンカルナシオンはルチャを罪という。修道院では試合をテレビで観るのも禁止されていた。ナチョは彼女に憧れていたが、彼女は彼の勇姿を応援してくれない。だから恋が成就するプロセスは存在しないし、ルチャに出ていることがバレれば、修道院からも追い出されてしまうのである。勝ち組にならない、ヒーローにもなれず、恋も成就しそうにない。ナチョがルチャに出ていることがバレるのは、時間の問題だからドキドキもしない。映画として面白くなりそな要素があんまりにも見あたらない。それでもこの男はまことに愛すべき男である。子供たちのためにがんばるが子供のようにがんばっている。立派な大人の姿をしているが男をあげようとして必死にもがいて長文のラブレターをシスター・エンカルナシオンにしたためるあたりもまるで思春期の青年のようでもある。ジャレッド・ヘス監督。ユルユルのストーリーは「バス男」と変わらない。だがクライマックスは熱いのだ。ナチョはラムセスに猛然と立ち向かっていく。子供たちとシスター・エンカルナシオンの応援がナチョの底力を引き出していた。なんだか幸せになるラストシーンは、ナチョの夢が実現した子供たちとのバス旅行。「バス男」で観た覚えのあるバスがジャック・ブラックたちを乗せて遠足である。ナチョはルチャでヒーローになってはいない。ある男性がずっと彼を応援していた。初戦より欠かさずナチョの試合を見続けたいた。ナチョを慕う修道院の子供もたった一人だったし、ナチョの相棒、ヤセも一人である。努力と才能が開花して成功するのは感動するが、そんな話ばかりが製作されればパターンになりかねない。熱く盛り上がるというよりも、まるで友人が幸せになったのを喜ぶ人の温かさがジャレッド・ヘス監督の作品にはあるように思える。ジャック・ブラックというハリウッドスターが、メキシコにもまれ生き生きとしていた。ヤセ役のヘクター・ヒネメスとのコンビも愉しい。ナチョーーーーーーーオ!!!!ジャック・ブラックの覆面レスラー姿が強烈に焼き付く映画である。そして何もしない登場人物を真っ正面から全身撮ってしまうジャレッド監督のユルユル加減が嫌いじゃないと宣言しておこう。
2007.07.04
コメント(4)
-

●●●ミラーズ・クロッシング
帽子から覗く憂いを秘めた目線の角度、完璧に背広を着こなす背中。銃を振り回し恫喝と脅迫を繰り返すギャングの中で彼はただ一人、正論を述べていた。街を牛耳る自分のボス、レオに対しても。格好いい男である。ガブリエル・バーン演じるトムという男。アイルランド系のギャング、レオの片腕である。この男が格好良さは、外見だけではない。イタリア系のギャングのボス、キャスパーが、レオの元に乗り込んできていた。彼の要求はバーニーという男を消せということだった。その男はキャスパーの仕組んだ八百長試合を、滅茶苦茶にして利益を台無しにしたという。これはギャングの世界では裏切り行為、至極当然の要求であった。だがレオはその要求を拒否する。バーニーはレオの持つ高級クラブで働くヴァーナの弟でしかも彼女をレオは愛していた。舞台は1929年のアメリカ東部、男たちは女と銃と酒を嗜み、市長も警察署長も暗黒街のボスの言いなりである。トムは女を理由にバーニーを守るレオを見限り、キャスパーに味方した。バーニーの居所を探し出し、仲間になる通過儀礼として彼の殺害を命じられる。ミラーズ・クロッシング枯れた細い木が続く落ち葉の敷き詰められた森、ギャングはそこで処刑を行う。みっともなく命乞いをするバーニーは、死を与えられるに等しい裏切りを犯した。トムは彼に向かって引き金を引いた。ヴァーナは弟のためにレオに与え、トムへは愛と打算を同時に抱きながら近づく。彼は女の思惑を知りながら自分のボスの気持ちも知りながら、唇を重ね、ベッドを共にしていた。帽子から覗く憂いを秘めた目線の角度、完璧に背広を着こなす背中。情に溺れる者や権力を追い求める者の中で、トムだけが冷静な判断をしていた。愛情のための選択をし、正論のための選択をする。そして義のために最後の選択をした。この男は最後の最後まで揺るがなかった。だから格好いいのだ。ヴァーナの弟、バーニーという男は、根性が真底腐っていた。キャスパーを裏切って自分を救ったことをネタにトムを脅しに彼の前に現れていた。ヴァーナのためにもと救った命は、全く価値のないものだったのである。コーエン兄弟のフィルムノワール、絶妙の間合いと褪せた色合い、淡々としたカメラワークが独特の雰囲気を作り出す。ガブリエル・バーンのボスを演じるアルバート・フィニーの存在感が世界を引き締める。救いようのない小悪党バーニーは、ジョン・タトゥーロが上手く演じている。情けない命乞いをしながらも命の恩人を脅しのし上がろうとする身の程知らず、全く同情の余地のないバーニーを作り上げた。トムの選択。顔色ひとつ変えずに暗黒街の男を騙し抜き、愛する女への情を残しながらも最後に選択したのは、最も信頼するボスへの忠義。彼は冷静に正論を全うした。決して揺るがず。トムはヴァーナと結婚するレオに別れを告げる。愛も権力も得ることなく、一人、舞台から去っていく。何から何まで格好いい男。だが、トムには欠点がある。バクチにはからきり弱かったのである。
2007.07.03
コメント(2)
-

●●●アルファヴィル
元気です。ありがとう。どうぞ。登録は必ず。ポエジーのない街。α都市、アルファヴィル。辞書から毎日のように言葉が削除される。永遠の夜、北圏と南圏、どちらを回って目的地まで行きましょうか、お客様。外部の国からこの都市に到着したのは、左利きの探偵、レミー・コーション。1965年が描き出した1984年の未来は、表情のない人々で満たされていた。ジャン・リュック・ゴダール監督は当時の都市風景に微妙なズレを演出し別世界を作り出した。裸体の女性のオブジェ、言葉を売る自動販売機、点滅するライト、絶えず聞こえる機械音。tititititititi・・titi・・tititititittiアルファヴィルここはα60というコンピュータの制御する都市。論理的であるべき。論理的でない者は排除する。登録は必ず。レミーが星雲を走りここに到着したのは、フォン・ブラウン教授を探しだし、この都市を破壊することだった。第3級誘惑婦が迎えた赤い星のホテルで、早速レミーは、見知らぬ男に襲われる。登録は必要。身体のどこかに番号が印された女性たち。詩のない都市、愛情はどこに。妻の死に涙した男はプールで処刑されていた。“涙を流す者を救え”笑うこともまた罪である。論理的でないことは罪なのである。その論理に吸収されればここで生きていける、レミーは知り合ったブラウン教授の娘に問う。「君はどこで生まれた?」「アルファヴィル」「いや、君が生まれたのは東京かも知れない」「フィレンツエかも知れない」「ニューヨークかも知れない」アルファヴィルを維持するために必要なのは論理的であること。論理的な挨拶は、元気です。ありがとう。どうぞ。tititititititi・・titi・・tititititittiモノクロームの映像の中でトレンチコートの似合う探偵と、憂いを秘めた長い睫の女性が引かれあっていく。演出によって醸し出されるSCI-FIの世界。それは驚異的な技術を駆使した映像よりも現代社会とリンクさせやすいと思うのだ。フランス語の音と、翻訳された言葉の意味が交錯し重なりずれてはまた重なる。ストーリーを追うのではなく読み進めながら鑑賞しているような気持ちになった。あいさつは重要。あいさつは共通の意味をもつ。意味が理解できればコミュニケーション成立。道徳的な観念もまた記号化される。愛もまた記号なのか。嗚呼、何と言えばいい。美しいモノクロームの挿絵を観ながら、見知らぬ文字を読んでいた。
2007.07.02
コメント(5)
-
●●●トランスアメリカ
女性の愛情と母親の愛情と父親の愛情と男の愛情、いろんな「○○」の愛情がある。LAに住む彼女ブリーが抱いた息子トビーへの愛情は、それのどれでもあり、どれでもない。もうすぐ肉体的にも女性になる手術を控えたブリーは、いつも化粧と胸の位置をを気にしていた。だがまだ、排泄は男のそれで、毎日のホルモン摂取は絶対に欠かせられない。だが、スタンリーだった時に出会った女性がNYで息子を産んでいたことを知ることになる。しかも彼はストリート・ボーイ、甘いルックスを活かして男に抱かれていた。窃盗の罪で捕まった息子を引き取った費用は、ブリーが手術に使うはずのお金である。NYからLAへ車での二人旅出会う人は二人を「母と息子」と勘違いする。何も知らせず養父の元へトビーを送り届けようとしたが、小さな違和感が積み重なり、トビーは彼を男だと知ってしまう。別の作品では美しい女性の姿を見せるフェリシティ・ハフマンのブリーには舌を巻く。風呂や排泄のシーンも自然にこなして、衣裳や小道具以上に仕草や表情でトランスセクシャルの人物を演じきっている。口悪く、歪んで育ったトビーだが、ナイーブな内面をケヴィン・ゼガーズが魅力的に演じる。いくども「母と息子」に間違われ、お金を取られ、ホルモン剤もなくなって、トラブル続きの連続だが、そのトラブルも小さな笑いにつながる演出である。トラブルを乗り切るごとに少しづつ、ブリーとトビーの間に愛情が育まれていく。ブリーは時には手厳しくトビーを真っ直ぐ叱る。トビーもまたブリーをどこかで受け入れている。ブリーとトビーの愛情。他人の目に自然にうつった「母と息子」なのだろう。トビーは女性としてブリーに魅力を感じていたようだし、実際には「父と息子」なのだが。だがまぎれもないのは、ブリーの「愛情」、トビーの「愛情」であるということ。ブリーは困りに困って実家に逃げ込むが、彼女の外見はスタンリーという息子の女装でしかない。彼女の両親は父親と母親の愛情に加え、孫への愛情をトビーにも与えようとするが、その愛情はブリーがトビーへ示すものとは違っていた。女性が、男性が、女性らしく、男性らしく示す愛情と、個人がそれぞれに抱く愛情は決してイコールではない。その人の感情はその人だけのもので、人それぞれに形が違うだけのものだから、上手くつながれば上手くいくのだし、食い違えば離れていくのだ、きっと。ブリーがトビーの探す父親だったと知ったとき彼は悔しくてたまらなかっただろう。彼のこれまでの人生は父親の不在が影響している。ブリーが真実を隠していたことが、この旅で生まれた彼女への愛情を裏切ったのだ。嘘は愛情を裏切る。だが、愛情というものは実に不思議で、時間をおけば再び蘇える場合がある。一度断たれた絆が再び始まる場合もある。だから、この映画のラストシーンは再び始まるのである。「父と息子」ではあるが「母と息子」かも知れない。一つの部屋にいる二人は家族なのである。「トランスアメリカ」公式サイト
2007.06.30
コメント(4)
-
●●●ダメジン
「インドに行けば一生働かなくてもいい」インド、インド、インドに行くには一人だいたい、いくらくらい必要だあ?猫だらけの家に住む猫じじいの猫を焼いて食べてるようなリョウスケ、カホル、ヒラジの三人組、全く働いてないから、金銭感覚、まるでナシ。(猫を食べていると申し上げましたが猫を焼いているという残虐シーンはございません)(ただし猫じじいの家の猫が一匹行方不明)佐藤隆太が演じるリョウスケはいいとして、緑のジャージ上下を小汚く着こなす、温水洋一のカホルは25才であると言いだす。二人の兄貴分のヒラジは知る人ぞ知る初代ビシバシステムの緋田康人。監督三木聡と温水、緋田の三人が原作のようなこの作品、上映までは長い道のりであったという。インドである、インド。かといってリョウスケ、カホル、ヒラジが目的をもってビッグビジネスに精を出すはずはない。円筒型の郵便ボスト壊し、郵便物の切手をはがして郵便局で換金。そんなもんで稼げる金額は微々たるもんである。胡散臭い神の啓示もあってインドに行こうと盛り上がったように見えて盛り上がってやる気になるような三人でもなく、多彩な登場人物が絡んでも起承転結もなく物語は進んでいく。トルエン中毒のチエミには鍾乳洞が好きなヤクザな恋人ササキがいるけれど、なんとなく同世代のリョウスケが気になってる。リョウスケは花沢というまともなサラリーマンの友人に、働けよと促されたりするけれども、ハンバーガーショップのバイトは上手くいかなかった。ちょっとボテトをオススメしたりできないのた。インバさん。インバさんは街の中に流れる、汚い川にいつも裸でつかっていてニコニコしている。インバさんの足はもう二本足ではなくて、魚みたいになっていそうである。インバさん、インバさん。インバさんは昔、働いていたそうだ。廃工場にある飛べないロケット。リョウスケは秘密のスイッチをチエミに教える。チエミは飛ばすにはトルエンと燃料タンクにぶちこむ。ササキはそのロケットで飛ぼうとした。小さなサンダル工場は借金まみれになっていて社長も従業員も起死回生を狙って新デザインサンダルを考案しようとしているけど、うまくいきそうな感じ0%。働いていてもお金は貯まらない。チエミにはタンクという友人がいる。いつもタンクの上にいるセーラー服の美女である。タンクはトルエン中毒で、それで死んでしまった妖精のような女性。いくら若くてもそやって命を落とす場合もあるんだな。三木聡監督の世界のコネタを演じるのは、なんとも豪華な俳優陣である。あんなところにもこんなところにも、有名どころから通好みの方々まで百花繚乱。主人公三人組と実のある絡みかたはロクにしない。なあんか一応インドには行くつもりの三人組。伝説の男になるんだと息巻くゲシル先輩の便乗して、銀行の金を強奪するのに参加する。一応、そこんとこ、クライマックス。なにせ、街の人(エキストラ?)も参加して、登場人物も何人か参加して、ヘン顔のイラストの紙袋をそれぞれカブリ、ダダダダと金を手づかみで強奪して街中逃げ回るんだからヘンな感じ。目的意識、責任感、そういうもんのないところにいる三人組。なんのために生きてるのか、とか、人生の意義をどうのこうの考えない作品である。そのまんま、その場を生きている。天然。インドに行っても行かなくても、結果がどうあれ、夜露をしのげる布団があればラッキーなのだ。飛べないロケット。廃工場にうち捨てられた飛べないロケット。みんなそれまでの人生があって、ジレンマを抱えているんだろうけど、そういうストーリーは一切語られないのである。猫を焼いてる場面がなかったように。それにしても、日本という国は、食べ物も生活必需品も結構捨てられているからリョウスケたちの生活にリアリティがある。インドに行こうとした三人組。いつか行くかも知れないし、一生行けないかも知れない。もしくは一生行かないかも知れないのである。「ダメジン」公式サイト
2007.06.30
コメント(6)
-
●●●300<スリーハンドレット>
芸術とはここまでやることでもあるのだ。芸術の定義は難しい。だが広義の意味でなら専門外の人間も論ずることは可能だろう。空も雲もそして屹立した岩山も風そよぐ穂先、またはスパルタの町並み、何よりも堂々たる存在感も持つレオニダス王が現れた瞬間、スクリーンは一枚の絵画となる。風景と人物の絶妙の配置。飛び散る血の流れさえも全体と調和し、遠近が世界を無限に広げる。はためくスパルタ戦士の赤いマントといとも簡単に胴体から離れる人の頭。その戦いの向こうでも剣は人間の肉を切り裂き、顔も見分けられぬ程のペルシャ帝国の大軍が彼方からも絶えず押し寄せてくる。芸術には奥行きがある。敵と味方善と悪、そして、生と死。紀元前480年、現代と重なる過去の時間、芸術とは時を超越し、人を未知の場所へ飛ばす。だが現代は決して消え去ることはない。古の芸術作品を鑑賞するのは、まぎれもなく現代を生きる者たちである。アメリカで作られたこの作品は、敵であるペルシャ帝国に痛烈な姿で表現する。実際に台詞の端々には煽動ともとれる言葉が存在する。芸術とは暖かく強く優しいものばかりではない。無神経で傍若無人、節度の欠けたものでもある。だからこそ芸術とは金や権力といった世俗とは無縁で無垢にもなりえるし感動を呼び覚ます。時に、血腥く辛辣でもあり、憎悪や皮肉の対象にもなりうるだろうが。スパルタ戦士300人は、まさにこの作品そのものを凝縮している。敵の命を省みず、自分の命を省みず、ただ国の未来と愛する者のためだけに戦う戦士たち。最初の戦いには勝利しても、圧倒的な大軍を前に抜け道を知られては生きて国へ戻ることなど考えられない。彼らには未来はないのである。だが、最後まで己れの信念を貫き通した。ザック・スナイダー監督作品。フランク・ミラーの原作を忠実に再現しようとしたという。何もかも完全に再現するのは不可能だろうが、完全に近づけれようした信念ははっきりと感じた。この作品の映像はその信念の結集だろう。戦士を顕在化した役者たちもまたこの作品の重要な存在である。彼らなしに「300」という絵画はありえない。レオニダス王の存在感を肉体と声で表現したジェラルド・バトラーは確実に代表作を一つ増やしたことになるだろう。テルモピュライでの決戦、そこに至るまでのレオニダス王の葛藤も、彼はしっかりと演じきっている。信念は政治と金にひれ伏す。だが貫き通した信念には後悔がない。血にまみれ見返りもなく弾圧の対象にもなるが、愛され記憶となり語り継がれることもある。芸術とは信念を貫いた故の結果なのかも知れない。貫くことは簡単ではない。どこまでもどこまでも続く終わりのない道。だがそれを求め、高みを目指す気概のあふれる作品には自然と価値というものが生まれると思うのだ。
2007.06.29
コメント(4)
-
●●●パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド・エンド
キャプテン・ジャック・スパロウ。ジャックは平凡な名前に雀がひっついて、酔っぱらったようにだがいつも踊っているように歩く男が踏みしめる地面は、しっかりとした大地だった試しがない。そこでも、ここでも、そしてあそこでもだ、死の世界、デイヴィ・ジョーンズ・ロッカーの中にいても彼はまるで踊っているように歩いていた。海賊を知るものに与えられるのは死のみ。凄惨な処刑のシーンが冒頭から続く。だが、一人の少年の歌が始まるとその死の意味は全く正反対の意味をもつものとなる。有無をいわさず老若男女問わず、振りかざされた権力によって奪われていく悲惨な命だが、それでも魂の「自由」だけは誰にも奪えないのだと言っているようである。そう、自由。自由だ、自由と言う言葉がこの作品にはとても良く似合う。FREEDOM、拘束されないこと、そして自由という文字は、全てが「自」から始まることを現している。「自」すなわち、自分、おのれ、一人称。キャプテン・ジャック・スパロウ。いつも船上で颯爽と皆の前に姿を現す時の彼は、仲間に囲まれていた試しがない。多くは一人で決断し、一人で行動し、いつのまにか周囲が巻き込まれてしまっている。ウィル・ターナー、エリザベス・スワン、彼と出会わなければ違う人生を歩むはずだった二人は、彼と出会ったから愛し合うことになり、思いもかけぬ運命に放りだされてしまうのだ。自由だ、自由。海の上で波と戯れるように歩くのはキャプテン・ジャック・スパロウという男。彼にとって誰が敵で誰が味方かということはもうどうでもよく、もちろん、金や権力も彼を縛る力になるうるわけはない。ただ行く手に何があるかわからないような宝の地図だったり、隠された黄金だったり、得体が知れなくともが胸躍らせるものを彼の目の前にぶら下げればもうそれで一巻の終わり、キャプテン・ジャック・スパロウは航海に出てしまうのだ。たったひとりでも。何にも拘束されずに。だから、自由だ。自由とは「自」から始まることを現している。たくさんのジャック・スパロウが度々現れて、時には正反対の意見の言ったりしている。ひとりの人間の中にはたくさんの「自分」がいるものだ。その「自分」たちが一つの結論を出す。誰にも頼らずに、誰かの責任にすることもなく、自分で決めて、自分で行動してどんな結果も甘んじて受ける覚悟を持つこと、「自由」にはそんな厳しさもある。だから自由を好まない人間がいる。自由になれない人間もいる。しかしどこかで「自由」に憧れるのだ。合理性と権力を求めたベケット卿。自分の地位をなかなか捨てきれなかったノリントン。サオ・フェンやバルバロッサのしがらみ、心臓をとられたデイヴィ・ジョーンズは不自由である。ゴア・ヴァービンスキー監督作品。活劇としての見せ場の多かった「1」やクラーケンとの戦いなど派手な映像の多かった「2」に比べエピソードを詰め込みすぎた「ワールド・エンド」はスケールが小さくなっている。だがこの作品の登場人物には息吹がある。ウィルやエリザベスはゆうに及ばず、ブラックパール号のクルーたちでさえも物語の中で割り当てられた役柄を演じているのではなく、それぞれが自分らしく生きているように見える。ハリウッド娯楽大作の看板以上に、しっかりとした中身を持っていると思えるのだ。キャプテン・ジャック・スパロウ。彼は父親に「人間が小粒になった」と漏らしていた。世界は広がりはしないのだ。怯えることはない、世界へと駆け出すのも自由。だが、自由には厳しい結果も待ち受けている。だが、何かに囚われることは悪ではない。大地に足をつけてしっかり生きる人生は悪ではない。そこから動かないと決めたのなら、それもまた「自由」から決めたことに変わりない。そうすると決めたのが自分である限り。エンドロール後の映像にある恋人たちのあふれんばかりの幸せが全てを物語っているだろう。キャプテン・ジャック・スパロウ。彼は「自由」である。だから私たちは愛してやまないのだと思うのだ。
2007.06.28
コメント(6)
-
●●●ガタカ
生まれ落ちた時に押された刻印は、簡単には消えやしないだろう。ヴィンセント・フリーマン、自然分娩で生まれた彼に押された刻印は遺伝子的に劣った「不適正者」しかも30才まで生きられないだろうと宣告されていた。近未来、近未来という、現代よりそんなに遠くない未来を描いた作品の中で、人種や民族とは違う境界線が引かれていた。「適性者」「不適正者」遺伝子というレベルでかけられる篩いには個人の力というものが全く通用しない。空高く舞い上がるロケット。ヴィンセントはそのロケットに乗りたかった。だが彼は「不適正者」、劣性遺伝子を排除されずに生まれてきた。はるか彼方、空の彼方宇宙へと夢を飛ばすヴィンセント・フリーマン。彼は今、宇宙開発を手がける「ガタカ社」にいる。もちろん「不適正者」の彼が就職試験に受かるはずもない。しかも宇宙飛行士になれるはずもない。だが、彼は諦めなかった。生まれ落ちた時に押された刻印。だが、ヴィンセントが抗った。DNAのブローカーから最高級の遺伝子を持つジェローム・ユージーン・モローを紹介されその血液で「ガタカ社」のDNAチェックをやり過ごしまさに宇宙飛行士に選ばれようとしていた。まっすぐに宇宙を目指すヴィンセントと、超エリートの水泳選手だったが自殺により下半身不随となったユージーン。「適性者」「不適正者」だが運命は遺伝子ではじき出される結果ではなく、もっと曖昧で不確実な結果を彼らに与えようとしていた。空と、地。ヴィンセントのロケットの炎とユージーンを焼く炎。アンドリュー・W・ニコル監督。1998年の作品になるがその映像はもう一つの様式美だ。無機質にも見えるが登場人物の強い感情は明確すぎるほどに画面にあふれている。しかも殺人事件とヴィンセントの弟が絡み、ヴィンセントの秘密もあいまって、エンターテイメント性も豊富に含まれている。ヴィンセントを演じるイーサン・ホーク、ユージーンを好演するジュード・ロウをはじめとする魅力的な俳優陣の演技は、映像の持つ世界観のシンボルとなり物語のメッセージを伝えてくれている。生まれ落ちた時に押された刻印。その刻印から逃れられない、と、諦めたときから決まる運命があるのだ。諦めなかったから決まる運命もあるのだ。ただ。結果が必ずしも幸運をもたらすとは限らないが。そう、人の運命は何も、刻印だけで決まるものではなく、もっと曖昧で不確実な要素が絡まった故に、一つの結果が生まれるのだと思えてくる。宇宙に行くために受けた最後の検査で、ヴィンセントの正体はばれてしまう。だが、検査技師は穏やかな表情で彼を助ける。その時に技師の心の声が聞こえた気がした。「がんばれ」ヴィンセントの血の滲むような努力が報われるようにと願う人の温かい感情。ヴィンセントのロケットの炎とユージーンを焼く炎。静かな様式美のある映像。だがこの物語は熱いのだ。篤いのた。
2007.06.27
コメント(4)
-
●●●リチャード・ニクソン暗殺を企てた男
何もかも社会のせいである。何もかも国家のせいである。何もかも、何もかも、何もかも、だ。責任を全て自分以外になすりつけていった果てに、サム・ビックという男が考えついたのは悪いものを取り除くとことだった。1974年、リチャード・ニクソンが、まだ任期中にも関わらずアメリカ合衆国大統領を辞任することになる、少し前に事件は起こった。事件ではあったし人命は失われたが、サム・ビックの行為がニクソンを辞任に追い込んだ一因ではなく、ましてや社会や国家を変えたというわけでもない。ただ民間機をハイジャックしてワシントンへ向かい、ホワイトハウスめがけて撃墜しようとした、その行為があの痛ましいテロと酷似していることのみが、特異性と言ったところだろう。ただ、この作品はサム・ビックが、どのような経緯で事件を起こしたかが描かれ、同時に社会が持つ一つの病理を浮かび上がらせている。そもそもサム・ビックはセールスマンだった。事務機具で埋め尽くされた倉庫のような場所で、懸命に客に商品の説明をするが、販売に結びつかず上司が横やりを入れてくる始末。真の商品の価格や品質よりも、セールスマンは売り上げを上げることが大事。サム・ビックはそれがが受け入れられない。売り上げは確かに必要、商品の売買は経済、強いては社会を動かしている。その社会と言えばテレビでは、アメリカ合衆国大統領の不正を報道している。その社会と言えば黒人を差別している。社会は確かに正しくはない。サム・ピックは社会に憤っていた。社会は確かに、正しくはないけれども。しかしそれは、妻マリーと別居することになり、週一回しか子供たちの面会できないことも、彼女がサムと再びよりを戻す気が全くないこととは無関係。マリーが生活のためにカクテルバーで、男たちの視線を浴びながらミニスカートで働いているのが、気に入らないけれどもだからといってどうなるわけでもない。車の機械工をしている黒人のポニーが白人に何を言われても丁重に対応する姿にいらつくが、だからといってどうなるわけでもない。だからといってどうなるわけでもない。だからといってどうなるわけでもないのだけれども。苛立たしいほどに何もできないこの作品のサム・ピックは、本来、映画の主人公としての魅力は皆無だろう。だがショーン・ペンが演じれば、サム・ピックは時代の闇の象徴となる。社会は確かに、正しくはないけれども。マリーが生活のために働くことを受け入れている。マリーはロクな働きのないサムにうんざりしている。サムの上司は、サムのために、口ひげを剃って好感度をアップさせようとアドバイスした。現在の政治を批判するブラック・パンサー党に、サムは共感して事務所を訪れるが、いきなり訪れた白人に戸惑うしかない。新しい事業を起こそうと中小企業庁に相談にいくが、融資の許可の通知には時間がかかるし、挙げ句の果てに許可は下りずに、しかも友人で黒人のポニーが刑務所に入れられる。そもそもはサムは詐欺まがいの取引をして、トバッチリがポニーに来ただけ、なのだが。何もかもうまく、いかない。何もかも、何もかも、何もかも。地元で兄の下でタイヤのセールスをしていたサム。だが兄はうまくいったが、彼はうまくいかなかった。結婚も、仕事もうまくいかなったか。うまくいかないたびに、サムは苛立たしく首をひねっているような顔をしていた。一体、どうしてだ?何が悪い?責任はどこにあるのだ?何もかも社会のせいである。何もかも国家のせいである。「自分は、悪くない。」だから悪いものを断ち切ろうとした。ただ民間機をハイジャックしてワシントンへ向かい、ホワイトハウスめがけて撃墜しようとした、しかしだからといってどうなるわけでもない。尊い人命を数人奪ったが、離陸することなく機内で射殺されてしまっただけ。そう、だからといって社会も国家も、どうなるわけでもない。サム・ピックは全く自分を見失っていた。何もかも、そう、何もかも、社会や国家の責任にして、自分の責任を全くと言っても追及していない。自分の責任を追及したからとって、どうなるわけでもないのではある、が。選挙における一票の重みは確実にあるのである。もしかしてサム・ピックはそんなに特別な存在ではないかも知れないと思うのだ。責任の所在はつねに取引される。経済もそう、政治も、戦争もそうだろう。だが、全てが片側だけが悪いわけではない。責任の所在がわかったところで、どうなるわけでもないのだけれども。
2006.06.18
コメント(4)
-
●●●かもめ食堂
たいしたものじゃないですけど。どうか、おかまいなく。何かお手伝いしましょうか。遠慮しないで、召し上がれ。若い頃のようにチヤホヤされなくなって、もともとチヤホヤされるような美貌もなかったりして。天賦の才も権力もなかったりする。でも、それなりに自分の人生があって、それなりに経験もある女性たちがこの作品の中に集う。こういう女性たちを私はとても良く知っている。かもめ食堂の店主はサチエさん。ガッチャマンの歌詞を完璧に知ってるミドリさん。自分の荷物が行方不明のマサコさん。こういう女性たちはスゴイ能力を持っている。「人をもてなす能力」「人を気遣う能力」個人差はもちろんあるのだけどもね、ただその二つの能力は人生によって培われるのだ。たぶん。きっと。ruokale lokkiかもめ食堂、フィンランドのヘンシンキにある、おにぎりがメインメニューの小さな食堂である。店主のサチエさんは小さな女性で、お客のこない店でセッセとガラスコップを磨いている。「いらっしゃい」お客さんをもてなすその言葉を、しばらくは彼女、一度も言えないでいた。最初のお客は、ニャロメのTシャツを着た日本かぶれ、なヘンな青年である。漢字で書くと「豚身・昼斗念」最も、その当て字はミドリさんによる即興で、カタカナならトンミ・ヒルトネンにこやかで可愛らしいが友達がいないようある。ご近所らしきフィンランド女性三人が、焼きたてシナモン・ロールに引かれてやってきた。コピ・ルアック、コーヒーがおいしくなるおまじない、とコーヒーがおいしくなる方法を教えてくれたのは、以前その場所にコーヒー店を出していた、中年の男性である。夫が帰ってこないと憤る中年女性は、コワイ顔をしてかもめ食堂を睨んでいたが、それは彼女のワンちゃんとサチエさんが、とても似ているから、ということだったらしい。ガッチャマンの歌詞を知っている人に、悪い人はいないとミドリさんを世話するサチエさん。ミドリさんは少々乱暴だが一生懸命かもめ食堂のテーブルを吹いている。マサコさんはとても介抱が上手くて、行方不明の荷物の中に、本物の「自分」の荷物を探そうとしている。サチエさんはサチエさんの信念を持って、かもめ食堂を日々キリモリしていて、マジメにマジメにがんばっていたりして、それでも上手くいかない可能性はあるんだろうけど、そしたらそれで止めればいい。大丈夫、大丈夫、そこのところはきっとミドリさんもマサコさんも同じだろう。そんな彼女たちが道を開いていくのは、彼女たちが持つ二つのスゴイ能力なのだ、きっと。「人をもてなす能力」「人を気遣う能力」若い頃はあんまり必要なかったけれど、それなりに経験値が高くなると必要になって自然と備わっていく能力なのだ、きっと。エプロンをして水をトレーに置いてお客さんのテーブルへ。最初は馴染みが薄かった「おにぎり」も少しずつお客さんのテーブルにのるようになったきた。彼女たち手のひらに乗せて握ったおにぎり。おにぎりは、コーヒーと一緒で、人ににぎってもらった方がおいしい。「人をもてなし」「人を気遣う」そんな心が込められているおにぎりは確かにおいしい。小林聡美、片桐はいり、もたいまさこ、息のあった女優陣が醸し出す空気感が素晴らしい。フィンランドの方々の好演も見逃せない。特に料理をする小林聡美の姿は秀逸。荻上直子監督が撮るのは、凛と人生と生きる登場人物とその場所その場所にある自然な空気感。時折ジンとくる台詞が心にしみる。「いらっしゃいませ」お客さんを迎える言葉がかもめ食堂に飛び交っている。サチエさん、ミドリさん、マサコさん、それぞれの「いらっしゃいませ」がある。かもめ食堂の店主はサチエさん。彼女は太った人がおいしそうに食べる姿に弱いらしい。
2006.06.12
コメント(15)
-

●●●ウィンブルドン
いつのまにか、黄色いボールを追っていた。あっちへ、こっちへ。手前から、向こうへ、また、その逆。ウィンブルドンイギリスにある「テニスの聖地」。この地で毎年6月の最終週から7月の第1週にかけてグランドスラムの一つである全英オープンが開催されるという。そのグランドスラムの中で唯一、芝生のグリーンが美しいグラスコートで開催されることが歴史と伝統あるウィンブルドンが多くの人に愛される理由になっているようである。だからこそ、Woking Title Firmがいつものキレのいいラブコメを作ってくれたことに、思わず快哉を叫びたくなるのである。それも、キャストが嬉しい。ポール・ベタニー&キルスティン・ダンスト第二の人生を考えていたベテラン選手ピーターが優勝候補として注目の若手リジーに出会うのは、「ホテルのフロントがルームナンバーを間違えたから」という、なんともベタな設定だったりする。二人の俳優はWoking Title Firmの他の映画のように、たちまち恋に落ちてしまうのである。ポールはずっと弱気に呟いている。ワイルドカードで出場できたウィンブルドンだが、マスコミの注目も優勝もほど遠いところにいて、この試合が終わったら引退して、テニスクラブでマダムたちのお相手をすることになっている。オレの人生これでいいのかよ、的な気持ちがアリアリと顔に出ているのにとてもじゃないが、華やかな一流のテニス選手に慣れる年齢じゃなくなっている。ずっと、ポールは呟いている。若い選手がマスコミの注目を浴びるのを見たり、試合中だって、道を歩いていたってずっと。リジーと出会うまで彼はたぶん、そこそこの才能で記録は残せただろうが、一流にはなれなかった負け犬だと思っているように見えた。リジーはずっと、獣のように吼えている。プレイスタイルもまた荒々しくて攻撃的で、自信たっぷりで勝つことしか考えていない。父親と二人三脚でウィンブルドンにやってきた優勝候補上だけを見てズンズン昇ってきたしなやかな獣。だが少しばかり何かが欠けているようにも見えた。ポールとリジー、二人は恋に落ちている。だがスポーツ選手であることが二人の障害になっている。リジーの父親は恋は集中力が落ちるからと、娘に男を近づけないようにしている。試合のためにポールと距離をおこうとするリジー、リジーと出会ったことで試合に勝ち進むポール、だが顔を合わせば二人はやはり恋に落ちているのだけれども。試合が二人を引き裂く。緑の美しいグリーンコートに黄色いボール。俳優たちは見事なプレイスタイルで一流の選手を演じる。ポール・ベタニーのピーターは、自らの心の内を語るナレーションとピッタリあった、迷いながら自分を見つけていくような動きをする。キルスティン・ダンストのリジーは、勝てば全身で歓び、負ければ全身で落胆する。俳優がスポーツ選手を演じればそのプレイスタイルまでもが演技になるようだ。行ったり来たりするボール。ポールもリジーも勝ち進んでいくが、二人ともそれぞれに試合と恋愛のバランスがとれなくなってくる。リジーは試合に敗退し、イギリス人の決勝進出者としてポールはマスコミの注目を浴び始めている。だがリジーは彼が試合のために自分を利用したのでは、と思い始めていた。ポール・ベタニー&キルスティン・ダンスト二人の俳優は人間の欠点を上手く表現する。弱気なポールと強引なリジー、欠点のある人間が出会い恋をすることで変わっていく。スポーツ、しかも舞台はウィンブルドンである、主演二人の妙味とラブコメのWoking Title Firmそれに、最高の舞台と三拍子そろい、スポーツ作品の醍醐味も十分味わえる。ギャラの高い俳優や多額な制作費、大規模なセットもいいが、(この作品も試合のシーンなどに時間も費用もかかっているだろうが)映画はアンサンブルなのである、だからこそ要素の詰まったこの作品は十分、豪華だ。いつのまにか、黄色いボールを追っている。いつのまにか、ポールとリジーを追っている。どんな結末なのかなんとなくわかっても、映画はアンサンブルなのである、いつのまにかストーリーを追いキャストを追い、上映時間を楽しむことが出来れば十分な満足が得られる。「映画を観て満足をする」それは、とても楽しいことだと思うのである。
2006.06.11
コメント(10)
-

●●●ジーザス・クライスト・スーパースター
スーパースター!スーパースター!砂漠に響き渡る歌声は待ち望んだ神を讃えているのか。救いを求める者たちが彼の回りを取り囲む。ジーザス・クライスト・スーパースターいつだってそうだ、いつの時代も。スーパースターの出現を待ち望んでいる。しかし彼は本当に「神」なんていう代物だったのか。舞台としてあまりにも有名なこの作品は、1973年に映画として世に出た。その後幾つかの作品が物議を醸し出したように、人間キリストを描いたこの作品も大変な話題だったと聞く。描かれたのはキリスト最期の7日間。砂漠にロケバスが到着し、若者たちによって鉄骨が組まれている。壮大なロックオペラはそうやって始まった。そうだ、舞台なのだ。砂漠という広大な舞台で始まるキリスト最期の7日間。スーパースター!スーパースター!細面で繊細な顔をしたジーザス・クライスト、まだ若い。だが彼の回りにはいつも人が溢れている。神の愛をとく優しげな青年の回りにはいつも人が溢れている。人が動くというのは人の心が動くということだ。ユダヤ教の長老たちや政治家はいらだたしげだ。だが、ジーザス・クライスト、細面で繊細な顔だちの青年は、自分の気持ちと民衆の熱狂の温度差にただ苦しんでいる。それを、彼だけが知っているに見える。イスカリオテのユダ、裏切り者のユダ、ユダ、あのユダだ。素晴らしい歌声が砂漠に轟く。カール・アンダーソンのユダはなんと言ったらいいだろう、痛々しく切なく、哀しい愛に溢れている。彼はキリストを思っている。民衆と同じ視点ではなく、そうきっと、側にいなくても一番のキリストの親友は彼なのだ、心の友、魂の友、彼だけがキリストの苦悩を理解している。最高に難しい役だろう、と思う。最高に難しい役を歌い上げるカールアンダーソンは、心から賛辞を送りたくなる。そしてもう一人。マグダラのマリアの美しい祈りの歌声。彼女にとってキリストは愛しい愛しいたた一人の人。スーパースター!スーパースター!スーパースター!スーパースター!「神」となる青年は苦悩していた。迷うのが人なのだ、苦しむのが人なのだ。極上のロックオペラは禁断の領域を猛々しく進む。聖書という原作とどれだけ差があるかどうか、わからぬままでも圧倒されるのだ、そのエネルギッシュな躍動感に。わからないからこそ無意識に「熱さ」を感じて引っ張られる。神、神。神となる青年は外の神とどこか違うのか。受難が彼を襲う。磔刑。神とはそのようなものなのか。愛しい女性と引き裂かれたっぷりの苦痛とともに死を強制され、その死の姿に祈りを捧げられる存在となる。彼は外の誰とも変わらぬ、一人の男性なのに。(そう解釈されることが物議を醸し出すのだろうが)砂漠という広大な舞台で終わるキリスト最期の7日間。
2006.06.05
コメント(8)
-
●●●ダ・ヴィンチ・コード【黒】
キャスティングと監督を聞いたとき、このベストセラーの映画化に期待はふくらみまくったのである。しかし、期待はふくらみすぎると良くなくて、悪い評判を聞きながらハードルを下げて見に行く。作品のテーマは原作を読む方が考えが深まる。だからこそ映画のお話は枝葉末節で書かせてもらおう。あれやこれやと思いは巡る。■極上のミステリはルーブルで幕を開ける逃げるジャック・ソニエール。不気味な影を走らせ彼を追う殺し屋はボール・ベタニー演じる修道僧シラスである。全てを見届けるのは、歴史に名を残した画家たちの静かで奥深い瞳を持つ美術品の数々。本当にルーブル美術館で撮影されたというシーンは、役者たちの好演と映画関係者の熱意や美術館側の寛容さとあらゆる好ましい要素の詰まった名シーンに思えてならない。この映画はこのシーンのために価値あるものとなる。■トム・ハンクスとジャン・レノの一期一会この作品でトム・ハンクスはジャン・レノと共演する。同じことがジャン・レノにとってもあてはまる。しかも舞台はルーブル美術館である。映画俳優はたくさんいるけれども、誰もに巡り来るチャンスだとは思えない。もし彼らが再び共演することになるとしても、そこはおそらくルーブル美術館ではないだろう。この映画はその点でも大いに価値あるものだと思うのだ。※惜しむらくはもう少し彼らのシーンが多ければ良かったが 原作でもそう多くないので仕方ないのである。■子供も気持ちになって考えてみれば球体球体、五文字の球体、ニュートン関係だってばさ。子供の時「伝記」で見たことあるニュートンのビックリ顔。なんだか「蛙飛び込む水の音」芭蕉さんの閃きにも似て。(いや、似てないです、失礼しました)まあ、そんなことはどうでもいいとしまして、冒頭のイチバン退屈なシーンにラングトンの講演会がある。そことつながってくるのだけれども、との話は次です。■で、ラングトンの講演会は何を言っていたか学生たちにスライドを見せる。何のスライドか、聞く。その答えはラングトンの予想通りことごとく違っているし、観る側も裏切られて「えー」と思うと同時に、である。ラングトンが象徴(シンボル)の学者だと知らせる重要なシーン。そして「思いこみ」で真実が見えなくなっている、というサジェスチョンがここにあったりして、例の「教皇」問題へ発展していったりするのだわ、この脚本。忘れてはいけないのは、「思いこみ」で、ニュートン関係の赤い球体を見つけられなかったりする。そう思わされているのはやはり「思いこみ」のせいである。■「何か重大な秘密があるような」感じ観る側の思いこみとは「何か重大な秘密があるような」感じである。そして「なかなか解き明かせない」って言う感じ。だからこそ、面白いんだけどさ。ダン・ブラウン、スゲー。■イギリスの大富豪はすべてを知っているのに金にまかせてサー・リー・ティービングは全てを知っていたりする。「最後の晩餐」とか「聖杯」とかキリストの系譜とか、なんだかスゴイことになっているから、もっとスゴイことが隠されているような気になってくるのね。金にまかせてなんでも手に入るから、もっともっとスゴイことが欲しかったんだけれども。ネタは子供の「伝記」に載っているようなことだったりして。だからニュートンさんの球体が解けなかったのかな。原作も作品もこのイチバンスゴイ輩に対して今ひとつ不親切である。■では何故、ラングトンだったのか原作を読んでいてイチバンしっかり抑えたかったのこはココ。ラングトンは常に思い違いを続けて物語りをミスリードする。「思いこみ」を教えるセンセイのはずが、である。だが「思い違い」を重ねることが探求というのである。彼は最後の最後まで、「思いこみ」の可能性を探していた。■この物語は「思いこみ」で出来ている(その1)モナリザが微笑むこの作品のポスターなのだけれども、キーになるのは「最後の晩餐」なのである、マグダラのマリア。イエスの系譜の問題をともに、この物語の危険な構造は、マグダラのマリアの中にあるのである。エンターテイメントであるはずが社会問題に発展したのは、ヌヴー捜査官が目を閉じたまま見た「最後の晩餐」の中に、グラスがある、と「思い込んで」いたのと同じだろう。■この物語は「思いこみ」で出来ている(その2)かといってこの物語もフィクションである、当然のこととして。■最大の難関は登場人物の個性ルーブル美術館での撮影を実現させたこの作品の関係者たち。しかしながら大きな問題点が転がっていた。この作品はラングトンを犯人と断定(思い込み)する、ベズ・ファーシュが象徴であるのに、アリガンローサに振り回されているだけの存在に。オプス・デイの代表の司教である彼も、その宗教が語られる暇が映画にないため意味を失いかけている。ラングトンに至ってはミッキーマウスの時計もなし、閉所恐怖症には触れるだけ触れてソソクサと次の展開へ。名優トム・ハンクスがもったいないのである。登場人物の弱い部分が際だつことは映画に深みを与えてくれる。そんなこんなでソフィーさんとソニエール館長の深い愛情も薄くなっているからこそあのラストシーンなのかも、と思うのある原作はもっと、家族の物語でもあったから。■政治が宗教と女性を別のものにしたというはなし大ベストセラーや大ヒットとなる作品で、そのことに触れるのは良くも悪くも大いに意味のあることだと思うのだ、うん。■秘密を守る必要性原作と映画ではちょっと違うのである。というか、原作にははっきりあるけど映画にはあんまりなかったような気がする。気のせい?※ちょっと触れてた、っていうか、 映画はすべてがちょっと触れてる感じかな?■ポール・ベタニー!!!!!!!!ロン・ハワード監督はポール・ベタニーを知り尽くしている。そんな気がするキャスティング、オイシイ役だけれども、原作にあるシラスの物語を出番以上に過剰に表現していた。アップもないし、顔も見えにくいし、後ろ姿や影も多いのに。原作にあるシラスの物語がもういっぱい思い浮かぶのである。その点ではトム・ハンクスもジャン・レノも背後にある物語が見えにくくなっていた気がするのである。ああ、もったいないけど、ベタさん万歳!(笑)ところで、よくよく考えるとよく出来た映画で、ロン・ハワード監督はさすが、と思うのだけれども、それがあんまりわかりにくい映画に仕上がっていると思うのだ。私たちはもしかしてサー・リー・ティービングになっているのかも知れない。「何かもっとスゴイことがあるかも」と。「もっと、スゴイものを」と。
2006.06.04
コメント(10)
-

●●●エターナル・サンシャイン
ジョエルとクレメンタインが、氷の上に寝ころんで手をつないで星を見ている。映画の中で描かれる恋は、現実の恋よりもずっと美しいような気がする。映画の中の恋も時には愛憎渦巻くドロドロになるけど、それでもきっと忘れるよりはずっといい。恋を忘れれば、恋をしていたときの記憶も消える。恋をしていた相手も存在しなくなるのだ。純粋な恋の物語、恋だけの物語、恋が始まり、恋が終わり、再び恋が始まる物語。内向的でしゃべるのが下手で、ジョエルはいつもクレメンタインに振り回されていた。赤い髪のクレメンタイン、青い髪のクレメンタイン。奔放できまぐれな彼女に、ジョエルはどこかイライラしていた。自分の我をを通さないジョエルに、クレメンタインもイライラしていた。ケンカが絶えなくなり不安ばかりが募り、猜疑心が生まれついに彼女は彼の元から去ってしまう。恋に破れた辛さを消すために、ラクーナ社の手術を受けるクレメンタイン。「クレメンタインはジョエルの記憶を全て消し去りました今後、彼女の過去について絶対触れないようにお願いします。ラクーナ社」バレンタイン直前にジョエルが受け取った手紙。愕然と、打ちひしがれる彼がとった行動は、自分のクレメンタインの記憶も消し去ってしまうことだった。ハワードミュージワック博士の開発した手術は一晩のうちに特定の記憶を消し去ってしまうというもの。手術の夜、ジョエルの家にラクーナ社の技術者が現れ、彼のクレメンタインとの記憶が逆回転で浮かんでは消えていく。赤い髪のクレメンタイン、青い髪のクレメンタイン、消えていく記憶に彼は待ったをかけた。愛しいクレメンタイン、ジョエルはまだ彼女を愛していた。恋は美しいばかりではない。ジョエルとクレメンタインも例外ではなく、ケンカが増えれば、お互いの嫌なところが思わず口をついて出てくるし、それは、お互いを知っているから当を得てしまっていたりする。否定の出来ない罵倒は辛辣で、しかもそれは愛する人の口から出るから、当然、辛くなるのである。秀逸な脚本は、記憶を消す側に、報われぬ恋を描き、主役の物語を際だたせている。ラクーナの技師パトリックは、クレメンタインを好きになってしまう。しかし彼がとった行動は、ジョエルの資料をただ真似ただけ。彼女の好きになった男と同じ男を演じたが、やはり彼女に振り向いてもらえない。ハワードミュージワック博士は、結婚していたが、技師のメアリとできていた。だがメアリの気持ちは一方通行。博士と彼女は肉体関係はあっても、デートはもちろん、ケンカも出来ない。ジョエルとクレメンタインは。デートをした、買い物もした、散歩もした。愛し合ったけれどもケンカもいっぱいいっぱいした。お互いを知っているから痛烈な罵倒を浴びせあった。映画の中の恋は現実よりもずっと美しい気がする。けれどもジョエルとクレメンタインの恋は、現実の恋と中身は同じ。愛も憎しみも、恋の中には全部入ってる。どちらかだけを消すことなんか出来ないのだ。育むために必要なのは、お互いをさらけ出すこと。秀逸な脚本はメアリの存在を使って、ジェエルとクレメンタインを真っ裸にする。消すのではなく「全てを相手に伝える」という手段をとる。チャーリー・カウフマン見事である。美しい映像はミシェル・ゴンドリー監督。ただ演じるのではなく内面を滲ませる役柄を、ジム・キャリーもケイト・ウィンスレットも好演している。都合良く記憶の「パーツ」だけを消せしない。あれも、これも、全部、彼女、であり彼。そして、私であり貴方、なのだ。
2006.05.31
コメント(4)
-

●●●魁!クロマティ高校THE☆MOVIE
とりあえず引き算が出来れば、都立クロマティ高校には入れるそうである。引き算ってとこがミソでありまして。インターナショナル的に考えると、引き算的発想で計算できない方がいらっしゃるとか。あはは、いい加減なクソ知識で申し訳ない、ご容赦を。池上遼一大先生の劇画タッチで、ギャグマンガってのが「都立クロマティ高校」公開に先立ち、大問題が起こってしまった。その昔、Gのユニフォームを着ていた、クロマティと言う名の選手がいたもんだからさ。ギャグマンガに使われるとはケシラカラン!と思ったのかどうだかいい加減な情報しか知らなくて、ただ、公開も危ぶまれたといういわく付きの作品。とととと、都立である。舞台は高校なので、青春モンであるけれども、しかも66年生まれ高山善廣が演じる竹ノ内豊(16)は高校一年生らしいけど、あ、カッコジュウロクって書いてしまってるな私。いい加減で申し訳ない。主要キャストに10代の俳優は皆無。どうも実年齢が問題ではなくて、クロマティマインド(造語)があるかどうかかなあ、と思ってしまうほど俳優たちははまっている。スカッとするくらいに。クロマティ高校には恐るべき歴史がある。過去、ことあるたびに、暴徒と化した生徒たちが校舎を破損させるのは聞いたことある話だけれども、その度に、校舎はなななな、んと。「全壊」してしまったいるようである。(クロ高全壊の歴史はオープニングのナレでどうぞ)そして、この年、7度目の校舎全壊の年になろうとは、誰も知るよしがなかった。・・・・っていうのは、公式HPのコピーのバクリ。ま、その通りなんだけど。主人公は神山隆志(16)中学時代、カツアゲされた彼を助けてくれた、山本一郎くんと同じ高校に入りたくてクロ高を受けた奴。クロ高なら、貧乏な上に頭も悪い山本くんでも受かるだろうと深い考えだったはずが。山本くんは「引き算」が出来なかったのである。クロ高にしか入れなかった高校生たちの中で、はっきり言って神山くんは浮いているようには見える。タバコ吸いまくり、遅刻しまくり、鉛筆まで食べてしまう生徒たちの中に混じって、学校を良くしよう!と決意する神山くんは間違ってない、寧ろ、素晴らしい奴なんだろう、きっと。ただ、間違ってなくても、方向性がズレてる場合だってあるのである。勿論、一緒に学校改革するような仲間はいないし。ツレはなんとか出来たけれど。カラカラカラカラ空回り。メカ沢くんや、覆面の竹ノ内、褐色の肌したフレディに、本人役で、阿藤快さんまで、ご登場。ご存じの方ならとっても嬉しいという、「ゴリ」と「ラー」さんが地球征服にもやってくる。小林清志さんの吹き替えに主題歌も流れたりして、本当に嬉しい方はとっても嬉しくなる企画まであったりする。クロ高には先生はいないようである。授業だってやってないようである。何故か修学旅行はあるようだけれども、も一回、確認すると、都立だったりするのだ、このガッコ。けど、それらの設定はスグにカンタンにどうでもよくなってくる。力強い展開と、そこら中に漂っているバカバカシさが混じり合い、ほどよいスカッと感があったりする。しかもこのスカッと感には、「青春」って奴がよく似合う気がする。今ここでしか味わえないかけがえのない時間。まぎれもなく都立クロマティ高校は青春しているのである。クロマティマインド(造語)ってのは、年齢とかじゃなくて。校舎が何度全壊しようとも、次の日にはまた学校にやってきて、自分たちのしたいように一日を過ごせるような、なんつーか、そういう感じというか。ま、そういう感じなわけで。主役の須賀貴匡や金子昇、そして渡辺裕之と、地球の危機やらなんやらを乗り越えて、前向きに生きる姿を演じた特撮の経験者である。特撮の前向きさとクロマティマインド(造語)が、ビミョーに重なるかもと暴論をブチカマシテ見たくなる。7回、校舎が全壊したと言う。しかし、全壊、ナッシング!の状態からクロ高は、しっかりよみがえっているのである、壊すよりもずっと、やり直す方が難しいというのに。また、よみがえるから、壊れたっていいんじゃないか!と思えてくる。って、これもまた暴論だけれども。また校舎が全壊している。スカッと全壊。それでも再び日常がやってくる。挫折とかしないのである、またいつか壊れる日のため・・・に?魁!クロマティ高校THE☆MOVIE
2006.05.30
コメント(2)
-

●●●プライマー
この作品は、怒濤のようにもつれあってく。しかし「もつれあっている」とわからせる演出はないのだ。登場人物は後から後から状況を把握し、観る側はその後から状況の変化を知らされるハメに。そうなるともう、遅い。目前に広がるのは、入り乱れた配線図。最初は重力をコントロールする研究をしていたはず。物理や化学、理系の用語が飛び交っている。登場人物たちはもがいる。会社勤めの技術者で20代後半か30代前半、空いた時間を地道な研究で得た技術でベンチャービジネスを始めているようです。けれども個人の客ばかりで、お金がいるのに、成果はちっとも上がらない。新しい着想を思いついても、お金がないから車や冷蔵庫の部品で、なんとか組み立てて研究を重ねています。そうやって出来上がった「箱」が、思わぬ現象を引き起こし、アーロンとエイブという二人の若い技術者の青年が、収拾のつかない時間のスパイラルに巻き込まれていきます。タイムトラベル。時間を扱った作品には、矛盾を説明するための仕掛けが必要となるものだ。登場人物が過去を変えることにより、現在と未来が少しづつ変容していく、という感じで。けれども、この作品はその変容が主軸ではなく、、タイムトラベルは単なる装置に過ぎない。時間を遡る。注意して過去の自分と、未来の自分が出会わないようにする。現在の株価の変動を知るエイブとアーロンが、過去に遡り、株価を購入に現在に戻ってくる。6時間のタイムトラベル。同じ時間軸に存在する過去と未来の自分。彼らは「彼ら」をダブル、と名付けていた。タイムトラベルを重ねるアーロンとエイブ。最初は二人一緒に行動していたと思っていたが、それぞれが別行動をとっていたこともわかる。二人だけの秘密だったはずが、思わぬ人物が秘密を知っていたこともわかる。登場人物たちは後から後から状況を把握していき、観る側はその後から状況の変化を知らされるハメになる。だからこそビデオなら巻き戻しをしたくなるように、もう一度、確かめたくなる。わかりやすい作品ならば、ご丁寧な回想シーンを入れて理解させてくれるが、この作品は回想シーンでさえ、混乱の材料にしてしまう。しかし、考えてみれば、アーロンはこんなことを言っていた。彼には殴りたい男がいる。時間を遡って一度は殴ってやりたいと考えている。しかし、もう一度同じ時間に戻っても、おそらく、殴りたいとは思わないだろうと言った。それはつまり。一度でも殴ったという事実があればそれでいいのだ。男をなぐったアーロン。男をなぐらなかったアーロン。一度は男をなぐったが二度目はなぐらなかったアーロン。三度同じ時間を経験することで、三通りのアーロンが出現するのだ。アーロンアーロンダブル。アーロンダブルダッシュ。この作品のタイムトラベルは装置なのだ。一人のアーロン、一人の自己。自分で自分は観れないはずが、自分で自分を観るハメになるアーロンとエイブ。自分で観る自分。どの自分は果たして自分か、そうでないか。思索が余儀なくされるだろう。答えのでない、思索。しかしその思索は、誰もがどこかで、さまざまな形で行っている「自分探し」という行動の具現化に似ている気がする。果たして今語っているアーロンは、一度でも男を殴ったアーロンなのかどうか。一度は殴ったことを知っているアーロンなのかどうか。どのアーロンが最初のアーロンなのか。どれが本当の自分なのか。77分の濃密な思索の旅。2004年のサンダンス映画祭で高い評価を得たという。確かめるためにもう一度みたいと思わせる難解さ。どの時間軸のアーロンが今どこにいるのか、まるで、探しものだ。増殖するダブル、どれが、最初のダブルか。なんて、考えても結論はきっとどこにもない。本来自分は、自分を観ることは出来ない。観ていると思っていても遠くから別の自分に観られているかも知れない。だが、観てみたいと、思っているのかも知れないが、その気持ちを確かめる「自分」はどこにもいない。あの「箱」に入ったりしない限りは。
2006.05.29
コメント(4)
-

●●●輝ける青春
カラーティ家の二人の兄弟ニコラとマッテオはまだ大学にいて将来を決めかめていた。1960年代、イタリア、ローマ。ニコラを担当する教授は彼に、他の国へ行くがいいと言っていた。これからこの国は混迷の時代に入っていく。6時間6分にも及ぶ物語の中時代は大きなうねりをあげるように登場人物たちを飲み込んでいく。作品の話の前に少しばかり映画館のお話をさせてもらおう。長時間な作品が故に、上映劇場も上映期間も限られていた作品。大阪から電車に乗り、滋賀まで足を運ぶ。全国で順次上映され評判を呼んでいるだけあって、思いの外劇場の座席は埋まっていた。休憩時間をはさみ同じ観客と時間を共有する。良き感動と楽しい興奮。もちろん、席を立つ人は誰もいない。誰しも生活があり仕事もある、だが良作を堪能する機会に恵まれれば、手放すのは愚の骨頂だ。二人の兄弟を通して37年の月日が流れていく。テレビドラマとして製作されたというが、マルコ・トゥリオ・ジョルダーナ監督の演出は、わかりやすく親しみやすい。本作を牽引するニコラ役ルイジ・ロ・カーショのにこやかな笑顔を大らかな演技が魅力的である。苦悩の一生を終えるマッテオ役は、アレッシオ・ボーニ、彫像のような体格、整った美形で劇中でも「ハンサム」と評されている。女優陣も生き生きとした美しさに加え、脇を固める年配の俳優たちもしっかり好演している。この作品は間違いなくキャストの魅力で、観客の心をグッと掴むことに成功しているように思える。1960年代から始まる物語。ニコラ、マッテオをはじめとして、登場人物たちが飲み込まれるイタリア現代史のうねり。ニコラには大学で仲のいい二人の友人がいた。だがこの時代大学を出ても成功といえる生活を掴むのは三人のうち二人。案の定、ニコラの友人ヴィターレはフィアットの労働者だったが解雇される。経済の破綻はその国に暮らす人の不満にもつながる。労働組合の支援組織だったというイタリア民兵組織「赤い旅団」はやがて、数多く誘拐や殺人事件を起こしイタリアを震撼させていく。長い混迷の時代が続く。後にニコラの妻となるジュリアも「赤い旅団」の組織に参加することになる。ストーリーを追っていけば、時代が大きく登場人物たちに影響して、社会性ばかりが強調されそうになるが、常に視点は「家族」や「愛」にしっかり固定されている。ニコラとマッテオの兄弟は、一人の女性との出会いで自分の道を定める。ジョルジア、精神を病んだ少女とまず最初に出会ったのはマッテオの方である。忌むべき悪習である「電気ショック治療」を受ける彼女を病院から脱走させ、兄ニコラを巻き込み彼女の故郷へ向かう。ろくに意志の疎通もできず諍いもあるが、イタリアの輝くような自然の中でわかわかしい三人が時折笑顔を見せている。だがジョルジアの父は新しい家族を持ち、手のかかる娘を受け入れることは出来ない。しかもこの時代精神病院は患者への対応は極めて悪かった。若いニコラとマッテオの兄弟は何もできないままジョルジアとはぐれることになる。何も出来ない、自分の力が及ばぬことを知って、ニコラとマッテオは真逆の人生を選ぶ。何とかしようと精神科医の道を志すニコラと、ままならぬ苛立ちを律しようとして軍隊に入るマッテオ。常に多くの人々に囲まれるニコラと、いつも一人で書物だけと友とするマッテオ。ニコラは大切な二人の人間を失うことになる。1966年、フィレンツェの大洪水で知り合った、金髪の女性ジュリアが「赤い旅団」に参加するのを止められず、最後の別れの挨拶にきたマッテオの様子を誰よりも気遣っていたはずなのに、彼の苦悩を受け止めてやることは出来なかった。ニコラは精神科医として実績を積み、たくさんの人の話を聞きいろんな心を受け止めたはずだった。そして自立の手助けをし、一人で生きていく手助けをしようとしていた。だが、人で生きていこうとする妻と弟を失う。僕の「愛」で彼らをしばりつけられなかった。妻と弟を失い、玄関の戸口で二人を見送ってしまった自分を呪い、ニコラは自分の生き方そのものが彼らが破滅に向かうのを止められなかったことを知る。愛する者を束縛しないで自由に生きることを望むのも愛情。だが、愛する者のために束縛することも愛情。テロリストとなった妻ジュリアと再会したニコラは、悩んだ末に一つの決断をすることになる。語ることはあまりにも多い。悩み苦しみ、愛する者を失い誕生を目の当たりにする。親から子へ、子から親へ、たくさんの想いが生まれ消え受け継がれる。物語は幸せな結末でも哀しい悲劇でも終わらなかった。ニコラとマッテオと軸とした時代の物語、愛情と家族がしっかり描かれている。そしてそれらの全てが思い出すわけでもなく最後によみがえるのは、物語の全てがよみがえるのは美しい風景故である。最後に、マッテオの子供がニコラとマッテオが行き着けなかった場所へ行き着く。美しいのである。美しいのである。物語の全てとその景色が重なり。世界が美しいことを思い出せてくれるのである。「輝ける青春」公式Webサイト
2006.05.28
コメント(2)
-

●●●飛ぶ教室
ここなら、やっていけそうな気がする、と6つも寄宿学校を変わっていたヨナタンの表情がほんの少しづつだけど和らいでいるような気がしました。ドイツ、ライプチヒ、少年合唱団で有名な聖トーマス校。ヨナタンのルームメイトは4人。リーダーシップをとるのは判断力があり精悍な感じのするマルティン、華奢なウリーはいつも少し怯えているように見えます。実験が大好きで校長の息子でもあるヨナタン。いつもお腹をすかしている力自慢のマッツ、彼らは自分たちの部屋にやってきた転校生に対して、何一つ気取らずマイペースで接しています。ヨナタンはどこか斜に構えた少年ですが、いつのまにか彼らのペースに巻き込まれて意気投合してました。ドイツの作家、児童文学の巨匠、エーリヒ・ケストナーの「飛ぶ教室」の映画化。2003年の作品なので設定は原作と少し違いますが、かつて原作を読んだときの印象が、再現されているような気がしました。子供たちにとって大人は、自分たちの未来を想像させる存在なのでしょう。現実と直面する大人は厳しく苦しそうで、子供たちは自分の未来に不安を抱いているようです。「ベルリンの壁」の悲劇がこの作品にも盛り込まれています。それでも優しく頬を撫でてくれるような優しさと、ワクワクする楽しさがこの作品には確かにありました。子供のころは「未知」をいっぱい持っているんですね。だからこそ、不安で。だからこそ、ドキドキワクワクして。ヨナタンも他の子供たちも、家族に対してそれぞれの想いを抱えていました。しかも彼らは寄宿舎にいるから、家族に思ったことをすぐ伝えられません。作品の中でも寄宿生のヨナタンたちと、通学生の子供たちが対立していたりします。でも、逆にヨナタンたちは、ルームメイトの仲間たちとの生活の中で、自分らしさを見つけていきます。合唱団のベク先生との交流、ベク先生の友達だったローベルトとの交流で、自分たちがどうありたいか、おぼろげ、ながらもつかみかけているようです。そうなんですね。ドキドキワクワクと不安が入り混じった未来。どう歩いていくかは誰も教えられない。でもいつのまにか子供たちは学んでいる、大人だって学んでいる、自分はどうしたいのか、どうありたいのか。飛ぶ教室。ステキなこのタイトルの意味を私なりに想像したりします。その教室ではきっと、自分はどうしたいのか、どうありたいのかを学ぶことが出来るのかも知れない、なんて。子役たちが本当に愛らしいです。生き生きと演技する彼らを先生役の俳優は、包み込むようでありながらもしっかり「らしさ」をアピール。大人と子供がバランス良く調和した作品に思えました。「ベルリンの壁」で別れ別れになったベグ先生とローベルト。若い頃の友情は現実に阻まれ別れが来ます。しかし子供たちはその別れとともに、再会し変わらぬ友情を確認する大人の姿を見ます。現実には確かに、悲劇は存在します。けれども乗り越えられることを示唆するかのように。
2006.05.23
コメント(4)
-

●●●ヒストリー・オブ・バイオレンス
10代の頃の彼を知らない。妻は愛する夫ともっと早く出会いたかったと言う。ハイスクール、これからの未来に、不安を抱きながらも希望はあふれんばかりの時代。若さは愛し合うカップルに楽しい日々をもたらしただろうに。彼を知らない、彼女を知らない。結婚する前の彼を知らない、彼女を知らない。生まれてきた子供たちも、お父さんとお母さんの10代の頃を知らない。小さなサラ・ストールが悪夢に怯えていた。真っ先に飛んできたのはトム・ストール、彼女の父親。兄のジャックも彼女の傍らに寄り添ってくれている。弁護士の母親のエディも忙しいながらも、娘へのいたわりのまなざしをなげかけている。いい、家族だ。いい、家族なのだ、彼らは。家族のために集まれる家族、なのだ。でも、彼女は知らない。10代の頃の、トム・ストールを。エプロンをしてカウンターの中で、自らの名を冠した“STALL'S DINER”で働くトム。従業員も客も皆、顔見知りのようだ。そこへ、見知らぬ男が二人。昨晩止まったモーテルで主人たちを殺し、殺すことで自分の要求を実現してきたような男たち。そんな二人が田舎町の“STALL'S DINER”を、新たな獲物にしようとした。殺すことで。欲しいものを無償で手に入れようと。だが、二人はトムに殺されることになる。ジョーイ。ジョーイ・キューザック。彼女の、エディ・ストールの知らない夫が出現した瞬間。10代の頃に知り合いたかった、と彼女は言った。エディ・ストールはきっと、青春ドラマのような幸せな日々を想像していただろう。だがトムは、夫、トムは、ジョーイ・キューザックとして、お金のために、自らの楽しみのために、人の命を奪い続けていた。登場人物たちが交錯するたびに、一人ひとりの人物像の輪郭が明確になっていく。トムの息子のジャックも、一度は仕掛けられたケンカを上手く拒むが、恋人の名誉を守るために相手を簡単に打ちのめしてしまう。トムも全く同じ。ジョーイであることを一度は隠しながら、彼もまた妻や家族を守るために、兄リーチー・キューザックと対面することに。トムではなく、ジョーイ・キューザック、として。妻のエディ・ストールは、自分たちを守るためにジョーイとなる夫を間近に見る。簡単に人を殺す夫を。ジョーイをつけ狙うカール・フォガティ、固めが義眼の不気味な男が、ジョーイ・キューザックという男を明確にする。カールの目をくりぬいたのはジョーイなのだ。ジョーイ・キューザック。家族は夫の、父親がジョーイであった頃を知らない。エド・ハリス、ウィリアム・ハートという他の作品ならば簡単に死なない存在感ある俳優をヴィゴ・モーテンセンが簡単に殺してゆく、という構図がある。相手が大物であり、大物を殺す姿がトム・ストールの中にジョーイ・キューザックを浮かび上がらせる。キャスティングの妙味、狂おしい表情で家族に許されようとするトム、ジョーイとは全く違う表情を見せるヴィゴ・モーテンセン対極にいるマリア・ベロと子供たちが気高く見える。家族としての暖かい光景、短いが場面だが、激しさの伝わるSEXシーン、トムを殺そうとする男たちが、簡単に次々と殺されていくアクション。そして何気なく緻密に作られた殺される側の死体。愛情と残虐さが交錯する。登場人物たちが交錯する。浮かびあがるのは明確な作品のテーマ。愛と暴力の対立に他ならない。クローネンバーグ監督の指し示すのは、相反するものは相容れないまま同時に存在する姿。知っているのは何で、知らないのは何なにか。トムはジョーイ・キューザックにならないために、ジョーイ・キューザックとして自らの手を血に止めた。その血を洗い流して家族のもとへ急ぐ彼。狂おしいほどの表情で許されようとする彼。知ってからの驚きや憤懣、苦悩知らなかった時の幸せな家族の姿は同時に存在する。だが、家族でいるかいないか、は、別の問題。家族は、家族になる前の姿を知らないまま家族になる。
2006.05.08
コメント(5)
-

●●●バス男
ああ切ないかな、この邦題。たぶん、というか、おそらく、っていうか。日本未公開の作品で話題集めするには、二番煎じ的邦題をつけなしゃーなかっただろうけど。まあ、いいんですけど。キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !! ってジャケットには書いてあるけど、全然キテナイとかなんとか、言うのはどうでも良くて。早く本題の作品について、話させてもらった方がいいかなあ、と思うんだけど、まあ、思ってはいるんだけどね。まあ、ボチボチいきます。オープニングはそのへんに売ってそうな、ハンバーガーとかのワンプレートの料理とかに、出演者やスタッフの名前が書いてあったり、文房具とかに手紙で書いてあったり、オシャレといっちゃあオシャレ。低予算映画らしい工夫が素晴らしい、なんて、褒め言葉を言う気力は、主人公くんの顔を見ると失せてしまうのだ。Napoleon Dynamiteアイダホ州の田舎町の高校生ナポレオン・ダイナマイト。皇帝と爆発物をかけ合わせた彼の風貌は、ガリガリガリの細身に長身、爆発頭にウザそうな虚ろな目をして、いつも口は半開きでハキハキしゃべらない。Tシャツのバリエは豊富なようだけど、センスの欠片もございません。一緒に住んでいるのはチャット中毒の兄キップは、半ズボン姿で無職の30代(独身)彼らのためにやってきた叔父さんリコは、どうみても鬘で胸がデカクなるハーブを売ってる。へんな奴ら。そのへんな奴らが巻き起こす、ドタバタコメディだったらわかりやすいんだけど、ドタバタはしないわけでありまして。もちろん、オシャレでもないわけで。ナポレオンくんは高校生で、女の子が気になる年頃なので、恋の話もあるにはあるのだけれども、盛り上がるほどの展開はあるわけでもなく。そんなことはどうでもよくて。メキシコ産の転校生ペドロとなあんとなく友人になったりするけど、学校の階段で二人、微妙な距離を保って座ってる。かと言って。何気ない少年の一日を淡々と描く。なあんて高尚な構成のになってるわけもなく。女の子がナポレオン宅に押し売りにやってくる。キップのチャット相手が彼の家にやってくる。ペドロが何を思ったか生徒会長に立候補。相手はダイナマイトでセクシーな金髪の女の子。リコ叔父さんは「キミの悩みはわかるよ」と胸の大きくなるハーブを売りつけようとしている。「がんばれ、オレ」リコ叔父さんは自己愛の固まり。ナポレオン家にいるのは馬でもなくロバでもなく、もしかしてリャマかしらん、と思う動物を確認した。ぬるいぞ、ぬるいぞ、この映画。ぬる~~い、温度、ぬる~~い雰囲気。まあ、どうでもいいんだけど。ぬるい料理は好きになるほどの魅力はないけど、イイ味だしていたら、食は進むのである、そんな感じで。そう物語の最初の方で、バズにまつわる名場面があったりしたな。黄色いバスに乗り込むナポレオン。隣の子供が「何するの?」と聞く。「なんでもいいだろ」」的にぞんざいな彼。それでもなにやら男のフィギュア(裸?)の足にヒモつけて、窓から放りだしてたりしてる。シチュウヒキマワシの刑のようである。延々と引き回される映像が続く。低予算映画の大らかさが詰まった、自由気ままな編集の中に映画の純粋さを観る。作りたい映像と観る側を愉しませる工夫、俳優たちも肩の力を抜いて演じている。観る側が肩の力を入れたくても入れさせてくれず、それでもイイ味だから食は進むのである。もう、どうでもいいのだ。ナポレオン、イイ奴なのだ。オシャレな会話やファッションのセンスや、知的なウィットもオベンチャラも言えないけど、友達のために、ヘンな絵を描いてあげられる。気になる女の子の似顔絵をヘンな顔で描いてあげられるのである。そして一生懸命汗を書いてビデオでダンスレッスンして、友達のためにカッコイイダンスを踊ってあげられる。かといって、褒められも自慢もせず、相変わらず、口は半開きで、目は虚ろで、ハキハキしゃべったりせず、好きな女の子にだってイイ顔できないけれども、彼女はできたようで、めでたしめでたし。ま、どうでもいいけど、イイ感じ。エンドロールの後もイイ感じ。ナポレオンが少し、格好良くなっていた。Napoleon Dynamite(英語HP、でも楽しいっす)
2006.05.01
コメント(4)
-
●●●Vフォー・ヴェンデッタ
私たちの近未来、そう遠くなく、すぐ間近にあるわけでもないくらいの近未来。さまざまな可能性を秘めている、それはきっと、わずかなピースが加わるだけで、どうにでも、変わっていくものなのだろう。何かの要因が重なり、独裁国家となった未来のイギリスが舞台。一人の女性が戒厳令の引かれた夜に急いで外へ飛び出していく。小柄で強い瞳をもつイヴィー、しかし、彼女は自警団に見つかってしまった。街を守っているはずが街を支配する権力をもった男たちは、赤い縦線に二本の横線の引かれた紋章を見せ、嫌らしい視線でイヴィーをなめ回していた。そこに現れいでたる仮面の男、V、そう名乗る黒づくめの男の反射神経は並ではない。三人の男たちを鮮やかに殺害し、彼女をある音楽会に招待した。11月5日、0:00夜空に花火が舞い上がる。審判の天秤を持つ女神が屋根にから落ちる。裁判所が崩壊した。よみがえる1605年11月5日Vの仮面はある男の顔と同じだった。国会議事堂を爆破しようとして捕まり、絞首刑に処せられたガイ・フォークスの顔と。この作品は近未来の物語ではなく、近未来の仕組みを解き明かすドラマに思えたのは、そう考えたのは地道な捜査を続けるフィンチ警視の閃きが「きっかけ」だった。すべては、ピースに過ぎないと。フィンチにはすべてが見えたのだ。Vも、イヴィーも誰も彼も。独裁国家に君臨する終身議長サトラー。秘密警察を仕切るクリーディー、そしてVを誕生させたラークフィル収容所、そこに存在したさまざまな人々。権力を得た者も、過去を悔いる者もすべてピース、欠片。だがそれらの欠片が積み重なり流れとなっていく。歴史、という名の流れ、年表に書き込まれた様々な項目、過去から未来へ、すべてがピース。偶然も必然となり連なって歴史となる。何が始まりだろう。イギリスの独裁国家はどうして産まれたか。世界の指導者を気取っていたはずの「アメリカガス臭国」カオスの象徴はその国の崩壊にある。カオスを統率するのは「恐怖」ウィルスの蔓延とワクチンの普及と、強烈なカリスマ性を持つ政治家の出現。ヒトラーと重なるサトラーはエーリッヒ・フロム「自由からの逃走」を連想させる。架空の世界を題材に、世界の仕組みを解き明かす展開、政治であり経済であり、歴史学、社会学の側面もこの作品には見え隠れする。比較的わかりやすいが、世界の仕組みはそもそもそう簡単ではない。物語ならばさまざまな解釈を選択できるが、物語からはみだせば「明解さ」がどうしても減ってしまう。しかし、娯楽作品しては申し分ない。権力側の人間たちの嫌らしさ、権力に命を落とした者たちの悲哀、心動かすエピソードは十二分にある。ヒューゴ・ヴィービング演じるVは魅力的で、終始仮面でありながら魅力的な存在であり続ける。ナタリー・ポートマンは、幾重にも重なる複雑な心情を演じるには、適切すぎるキャスティングだろう。1605年11月5日、ガイ・フォークスが望んだ議事堂の爆破。Vは長い時間をかけて、地下鉄の電車に爆薬を準備していた。そしてそのスイッチとなるレバーは、イヴィーの手に委ねられる。議事堂の爆破、その行為が何につながるのか。その結果は誰も知らない。だが、イヴィーの決断が未来を変えていく。街を埋め尽くす、仮面のV、彼らの決断が、彼らの決断が未来を変えていく。
2006.04.30
コメント(6)
-

●●●モンスーン・ウェディング
幸せにおなり。家族よ、そして娘たちよ。インド・パンジャブ地方の中流家庭、パルマ家の長女アディティの結婚式が4日後だ。だが愛らしい大きな目をした娘は、少しばかり思い悩んでいるようである。続々と集まってくる親戚たち。アメリカやオーストラリアからもやってきた。庭には原色の色鮮やかなテントがしつらえられ、オレンジ色のマリーゴールドの門が出来つつあった。娘のために、娘のために。愛する娘のためにと、アディティの父、ラリットは忙しい。何しろ、結婚式はお金が湯水のように出ていく。それにブライダル・コーディネーターのデュベイは金、金、金と何かをすれば追加料金を請求してくる。彼自らが、伝票整理に追われているしそれでもお金が足りなくてゴルフのときには友達に頭を下げ、借金もしなくちゃいけない。それでも、娘のために、愛する娘のためにと、必死である。花嫁の母のピミも娘のために22年間ためたサリーを観ては感慨深げだ。にぎやかになっていくパルマ家、次第に形になっていく色鮮やかな庭のテント。幸せにおなり。ラリットは奮闘してがんばっているが、アディティはピグラムと不倫していた。親が決めた結婚相手を承諾したのは、ピグラムに結婚の意思がないため。従姉のリアはそんな彼女を責めるが、リアはリアで、心に深い傷を背負っていた。幸せを願う父親がいて、母親がいて、だが、誰もがみな、簡単には幸せには行き着けない。ブライダル・コーディネーターのデュベイは100件以上の結婚式を手がけながらも、何故、自分に伴侶がいないのか悩んでいた。パルマ家のお手伝いのアリスは、自分とは無関係な場所の結婚式を心のどこかで憧れているようにも見える。久しぶりに集まった若者たちは意識しているが、知り合うにはまだ時間が必要である。インドを出て外国で暮らす親戚も多い。映画大国として知られるこの国は昨今、優秀なソフトウェア産業の人材が揃っておりアメリカとの交流が盛んになっているという。たくさんの人が行き交う街並、サリー売り場での賑わい、儀式に彩られた伝統的な結婚式。変わらぬインドとダイナミックに変わりゆくインド、ミラ・ナイール監督は、人間とともに時代や町並みをも描きだす。色鮮やかに生き生きと。幸せにおなり。父親のラリットの切なる願い。だがアディティは花婿となるヘマントに全てを話す。しかもラリットの姉の夫、テージが、幼いアリアに性的な興味を示していることがわかる。「大人のキスは嫌い」アリアの一言が家族の絆を揺り動かす。ラリットはテージに世話になっていた。しかしテージは幼い頃のリアにも、同じ悪戯を行っていたという。リアが男嫌いなのもそのことがトラウマになっていた。愛しい愛しい娘のために、ラリットは決断し、姉夫婦と決別する。愛する者を守るために父親は、自らが剣となり盾となり災いに静かに立ち向かう。それは決して大きな事件ではないけれど、彼の想いの積み重ねが娘たちの幸せにつながっていく。彼だけではなく、いろんな人の想いの積み重ねが、誰かの幸せにつながっていくようである。ヘマントはアディティを受け入れた。デュベイとアリスのささやかで愛らしい恋。リアはやっと結婚式に間に合ったウマントという青年に、新しい恋の予感を感じている。誰かを愛するいろんな人の想いが誰かの幸せにつながっている。
2006.04.29
コメント(0)
-
●●●エレファント
無秩序のように見えて、世界は明解に分類されているうようで、だからといって誰が、どういう理由でそうしているかわからず、殺す側人間と殺される人間が仕分けられていく。アメリカ、コロバイン高校で、高校生の少年二人による銃乱射事件が起きた。1999年4月20日、エリックとディランは12名の生徒および1名の教師を射殺して自らも自殺。そこでも殺された人間と殺されなかった人間がいる。何故そんな事件が起こったが、社会の歪みを論じるのはここでは避けよう。ガス・ヴァン・ハント監督は、時間をシャッフルしながらさまざまな生徒の個性を描きだし、その個性の善し悪しに関わらず、殺される人間と殺されなかった人間を仕分けていた。黄色いシャツを着た白髪の少年ジョンは、迷彩服を着て武装したアレックスとエリックと校舎を出たところですれ違う。「中に入るなよ、地獄になる」彼らにそう警告されたジョンは、驚いていたがすぐにその本質に気づく。本質だけ気づいた彼は校舎に入ろうとるする生徒に向かい必死で叫んでいた。「なんだかわからないけど、中に入るな!」この時彼は分類された。アレックスとエリックはもう、決してジョンには銃を向けない。この映画の中で彼の「生」だけが確定した。図書室で殺された地味な少女。カフェテリアで無作為に殺された生徒たち。ダイエットに夢中な三人組の少女たち。写真部の少年はアレックスとエリックを撮ろうとして、撮れないままに銃弾に倒れてしまった。恋人同士で逃げていた二人も、追いつめられて殺されてしまう。だがジョンの彼女らしき少女は逃げることが出来て、その手助けをした黒人の少年は、おそらく本質に気づけなかったのだろう、様子を見に行ってそのまま殺されてしまったようだ。無秩序のように見えて、確実に殺される人間と助かった人間がいる。そして、ナチスに傾倒し、ベートーヴェンの「月光」の調べを背負い、アレックスとエリック、銃を持ち、銃を撃ち、殺していく。ジョンがもし、校舎の中に居れば、アレックスとジョンもおそらく彼を殺していた。だから警告したのだ「中に入るな」と。すれ違う、ジョンとアレックス、エリック。すれ違う、三人の少女の人気者の青年。すれ違う、写真部の青年。さまざまなすれ違いさまざまな交差点。だが生き残るや否やの分岐点はどこにもない。友情や愛情も考慮されない。家庭の事情も勉強が出来るかどうかも、輝かしい未来があるかどうかも考慮されない。校舎の中にいて、アレックスとエリックに見つかれば、銃口がその命を狙う。この作品の中で、ジョンの「生」だけが確定した。だがジョンだから、という理由は明確には見あたらない。そもそもアレックスとエリックが事件を起こすに至った顛末も描かれず、ただその事件だけが描かれている。青空の下。この作品は、ガス・ヴァン・ハント監督が分類した。殺す側と殺される側。同じ青空の下に、たくさんの人間が生きている。そして殺す側と殺される側が存在する。アレックスとエリックの銃口はどこにでもある。
2006.04.27
コメント(6)
-
●●●告発
Murder in the firstヘンリー・ヤングは刑務所で、殺人を犯した。手に握ったスプーンで殺したのは、かつてその刑務所の脱獄を試みたとき、彼を裏切った男である。1941年、アルカトラズ刑務所、ヘンリー・ヤングは25年の重刑だった。その上に脱獄囚としての罪が加わり、「地下牢」と呼ばれる独居房に、3年間閉じこめられることになるのだが、それは法で決められた最大19日間を超えた人権を無視した刑務副所長の個人の判断だった。そもそもヘンリー・ヤングがアルカトラズに来たのは、わずかなお金を盗んだ罪である。ヘンリー・ヤングの物語は、殺人の罪を負った彼を弁護することとなるjジェームズ・スタンフィル弁護士の言葉で綴られる。まだ24歳の若い弁護士の初仕事なのだが、サルでも出来る仕事と上司に言われもした。だがジェームズは気づいてしまった。幼い頃に両親を亡くして、妹を食べさせるためにわずかなお金を盗んだが、そこが郵便局だったために罪が加算されたのである。その上に、時代背景が重なる。アル・カポネを収監したアルカトラズ刑務所、だが、大物の犯罪者がそういるわけもない。空き部屋にはヘンリー・ヤングのような男も収監されるような羽目になったのである。そう、刑務所が殺人者を作った、のだと。ヘンリー・ヤングもまだ28歳だった。彼の居る鉄格子の中に入ってきた若い弁護士は、弁護士であるとわかっているようだが、それ以上に話し相手であって欲しかった。なにせ、3年間薄汚い「地下牢」にいて、蜘蛛を見つけた時はやっと友達が出来た、と思ったほどだ。野球の話をしようとした。トランプをしようと誘った。弁護士は彼を救おうと必死に証言を求めるが、そんなことよりもジェームズの上着の女性の香水の匂いの方が気になるようだった。もちろんだ、彼は女性を知らない。ずっとアルカトラズ刑務所の中にいて、3年間も「地下牢」にいてそのまま「殺人者」となってしまった。冒頭から力強い映像がながれる。「地下牢」にいるヘンリー・ヤング、真っ裸の彼を真上から見下ろすショット。副刑務所長の陰湿な苛めと為すがままのヘンリー。フィクションの力強さもさることながら、マーク・ロッコ監督の映像は本当に力強い。いままで観た幾つかの名作の持つ力強さが重なり、しかも軽妙なエピソードも交えて暗さを取り除く。ジェームズはヘンリーのために、記者を偽り、女性を金で買って連れてきた。猶予はたったの4分間。だが初めてのヘンリーは上手くいかない。問題作であるはずが、ヘンリーの人柄を丁寧に描きだし、悲劇であるはずが清々しい感動を与えてくれる。ヘンリーとジェームズの友情の物語でありながら、後半はスリリングな法廷劇の様相を呈する。ジェームズは刑務所を告発し、ヘンリーを勝利へ導びこうとしていた。だがヘンリーが勝利を受け入れない。裁判が終われば、ジェームズとは別れることになる。有罪ならガス室だが、無罪なら刑務所へ逆戻り。あの刑務副所長は健在である。しかし最後の最後にヘンリーは自ら戦うことを選択した。戦って勝利することを選択した。その選択が悲劇をもたらすのだけれども。1995年の作品。ケビン・ベーコンは見事な演技である。クリスチャン・スレーターも若々しく魅力的だ。刑務副所長にゲーリー・オールドマン、短い出番だが憎々しいまでの存在感である。ヘンリー・ヤング、彼は、3年もの間、閉じこめられても正気を失わず、強くあり続けた。ヘンリー・ヤング、彼は、刑務所という権力と戦い、勝利した。罪は罪である、償うべきものであり消えやしない。だが戦って勝利したことは誰も奪えない。戦わず負けもせず、何も残らない人生ではなく、誰も奪えない勝利を手にして彼はアルカトラズで没した。そして彼の戦いがきっかけで、アルカトラズが閉鎖に追い込まれたとされる。ヘンリーはわずかなお金を盗んで捕まった。ヘンリーは、戦って勝利してアルカトラズを閉鎖に追い込んだ。何かをすれば、何かの反動がある。何かをすれば、何かの反動があるのだ。
2006.04.26
コメント(4)
-
●●●寝ずの番
ようここまで足運んでくださいました。さ、さささ、さあ、おざぶ、出しますさかい、どうぞどうぞ。なんか食べはりますか?と言うてるうちに熱燗もやってきた、ま、一杯。亡くなりはりましたんは、笑満亭橋鶴師匠、落語会の重鎮。一門の方々がもう皆、席についてはります。・・・下手な関西弁ですいません。一応私も関西人やねんけど、なんせ、プロの方々の粋な言葉使いは出来ません。せやけど『寝ずの番』と言う映画は、こういう感じやないと喋りにくいんですわ。なんせ、「おそそ」やさかいに。そうそう、アレ、ですわ、あれのこと。橋鶴師匠が最期に見たいと言い張ったアレ。橋太はんの嫁はんの茂子さんが、ババ~ンとスカートまくりあげてくれはったけど、師匠は「アホウ!」とか細く一喝しはった。一番弟子の橋次はんが聞き間違えたんや、何と聞き間違えたかなんてどうでもエエ。そんなアホな思い出話が何よりも、故人を偲ぶにはイチバンええこっちゃ。なんせ、下半身のユルい師匠やったさかい。あ、エッチの方とちゃいまっせ。ものごっつ~長い落語のネタを超早口でしゃべりまくってはったんも、ただただトイレに行きたかったからやもんな。人はみいんな、死ぬんやなあ。橋鶴師匠の次は橋次はんの葬式や。その次は、師匠の奥さん、志津子さんも逝ってもた。さあ、寝ずの番やと集まった一門の方々。昔話に話しが咲くんやけれども、下ネタとエロネタが咲き乱れてました。せやけどな、頼むさかいに、誤解だけはせんといてくださいな。女の人に「おそそ」があって、それがエエ言う男の人がいるんは普通やないか。師匠を愛する一門の方々が、師匠のネタをリアルに再現して、死んでる師匠担ぎだして踊りだすんも、普通のことやと思うんや。ヤラシイとかフキンシンとか大きなお世話。ほら、「らくだのカンカン踊り」師匠も楽しそや。なあなあ、橋太はん、初体験のお魚(エイ)はどないでした?茂子さんには言わん方がええで。ポルターガイスト、何が飛んでくるかわからんし。マキノ雅彦監督作品。俳優でも有名な監督の作品に集まったのは、中井貴一や木村佳乃を中心として、凸が凹にはまるようなはまり役の役者陣。なかでも橋次はんを演じる笹野高史の跳ね具合。やんちゃで愛される芸人を軽妙に演じてはった。監督の実兄、長門裕之の橋鶴師匠はあ、映画というのは家族がいるんやなあ、などと、彼を見ながら思ったりなんかしたんやな。そうそう、この作品な、チラシや紹介記事はイッパイあるやろけど、アレとかコレとか、大きい声で言えんネタがいっぱいあるんでとにかく観てもらわなアカンのや。せやけどヤラシイとかフキンシンとかそんなこと思いはるんやったら止めといたほうがエエ。あんな、例えば蛭子能和演じる田所はんは、師匠の奥さんの遠い親戚らしいけど、いっつもお通夜の席に座ってはって。「みなさんの話がおもしろくて」と聞いてはった。そんでエエンやと思うんや。この席に座らせてもらう、ってことは。人はみいんな、死ぬんや、なあ。ご飯も食べるし笑うし怒るし、泣くしなあ。もちろん、うんこもおしっこもするし、初体験もあるやろし、不幸も重なることがある。まあイーデス・ハンソンさんに会えるとは限らんけど。いきなり、何言うねん、って。自分にツッコミしときますわ。ようここまで足運んでくださいました。サミシイことに志津子さんまで亡くなってしもた。一門の方々がまた集まってはる。またみんなで、艶っぽい唄、唄ってはるで。当たり前やなあ、死んでしもた人にも、いろんな色恋話があったんや。♪汽車汽車シュポシュポシュポシュポシュポポ♪絶頂だ!絶頂だ!楽しいな~。
2006.04.25
コメント(8)
-
●●●ブロークバックマウンテン
心とはどこかが渇いているのだろう。充たしながら潤しながら毎日を続けている。毎日、毎日。こうなるだろう、という未来、こうであるべきだ、という未来、だがそれだけでは、充たされぬ心がある。渇く、心。アメリカ、ワイオミングのブロークバックマウンテン。雲広がる空、広大な空、だが、渇いた空。荒涼たる大地に聳える山々。イニスとジャックは仕事を求めてやってきた。そして出会った、そして仕事を得た。季節労働ではあったけれども、羊の放牧を管理する仕事は、決して楽なものではなく単調な食事に過酷な自然条件、毎日、毎日、羊の数が減るのを気遣いながら、まだ二十歳の青年二人は自分の未来に溜息をついているようでもある。貧しい、先の見えない未来に。こうなるだろう、という未来、こうであるべきだ、という未来。凍えるような寒さがきっかけで、一人で寝る寂しさがきっかけで、ブロークバックマウンテンの山に抱かれて、イニスとジャック、二人はお互いの肌を求めた。明るい青年のジャックの上に寡黙なイニスが乗り、無我夢中のイニスに恍惚の表情のジャック。だがそれは、一夜限りのはず。そう二人は言い聞かせていたかも知れない。が。こうあるべきの未来。ジャックもイニスも結婚をし、子供を持った。二人の青年は連れ合いの女性に愛されていた、と思う。ジャックもイニスも、女性たちに愛されていた、と思う。だが彼女たちの愛は彼らを潤すことは出来なかった。たったそれだけのこと。それが、全ての物語。アン・リー監督は二人の青年の物語を描いた。時代背景に、その土地の文化を重ねて、ただ、渇いた心を潤そうとした青年二人が、深い闇に似た亀裂に落ち込んでいる様を綴っていく。イニスとジャック、会うたび触れるたびに溢れる幸福と、反動のように訪れる渇きの苦しさは、砂漠の地で水を求めるようにお互いを求める。心は、そのままだと渇くのだ。当たり前でない題材で当たり前のことを描く、アン・リー監督は観る者の視野を広げようとする。ヒース・レジャーとジェイク・ギレンホール、魅力的な俳優の引力は強く、この曰く付きの作品を見事に自分たちの勲章の一つにしているように見えた。そして男優の映画でありながらも、女性たちの心も丁寧に描かれている。渇く、心。その渇きを潤すために、私たちは何をしているのか。イニスとジャック、彼らの心はお互いの存在で癒された。ブロークバックマウンテン、寒さに震え人肌を求め、渇いた心を潤すためにお互いを求めた。それだけなのだ、ただ、それだけ。
2006.04.24
コメント(6)
-
「Dream Live 2006」~響き渡る音楽、夢の時間
「Dream Live 2006」2006年2月2日、出演は、呉汝俊(ウー・ルーチン)/倖田來未/小柳ゆき/ピーボ・ブライソン阪急三番街オリジナルライブに抽選で当たって、汗をかきながら猛ダッシュで仕事場から梅田芸術劇場 シアター・ドラマシティへ。100分が予定だったコンサートは、ゆうに120分を越えていた。4回公演のラストステージ。ピーボ・ブライソンが牽引して出演者一同が何度も手をつなぎ、観客に挨拶する。「 WHOLE NEW WORLD」「BEAUTY AND THE BEAST」ディズニー映画で日本にも名を轟かせたピーボは、全くもって観客を喜ばせるエンタテイナーだ。R&B、口説きのソウル、シルキーな声、彼を評する全ての形容詞を生で聞く。デュエットする小柳ゆき、が緊張している。彼との最後のステージに、倖田來未が泣き出していた。別所哲也が司会するイベント。派手なエンジのスーツがしっくり似合う。大げさで演出過多な紹介も彼なら納得する。ミュージカル俳優でもある、披露してくれたオリジナルソングは、なかなか、ドラマティックでもあった。今回、客席がイチバン沸いたのは倖田來未。披露してくれた曲はどれもバラード。生で観た彼女の衣裳には感心する。どのドレスも、手足胸元の露出が計算されている。顔よりも目線が他へ追いやられる。「こんばんわ、倖田來未です」と、しゃべり始めれば澱みがまるでないMC。オーケストラを前にして歌う楽しさ、音楽に対する愛情をしっかりと話してくれた。歌う前の小柳ゆきは、本当に愛らしい。MCでは言葉が出ず、「あれ」「これ」など、代名詞の連続で観客もずっと苦笑い。それでもいざ、歌いだせば、声は劇場内に響き、感情が溢れている。歌に聴き惚れる。京胡の第一人者、呉汝俊(ウー・ルーチン)100年を越える楽器を手に、オーケストラと対等の音色を聞かせてくれた。白い衣裳が似合う、華やかな笑顔の彼は、京劇の第一人者のようでもあり、楊貴妃を演じたという記事をネットで見つけた。激しさと優しさと大きさを兼ね備えた「Bridge」という曲の中に、私が気持ちを寄せる中国の姿を見る。何に憧れてという言葉は出ないが、最初に行きたいと思った外国は中国だった。実際、始めて行った時の中国はただ大きく、踏ん張っていないと吹き飛ばされそうな国で、きりりと気持ちが引きしめった印象があったのだ。そんなことを彼を観て思い出した。観客の中にずんずん入っていくピーボ・ブライソン。カーペンターズの「Superstar」を歌っている。意味を全て解せなくて、これは心にズンとくるラブソングだ。今回の楽曲の中で、この歌が一番彼らしいかもと思った。自在に歌いこなす、「Amazing Grace」これは他の出演者も参加して合唱となる。本田美奈子さんを追悼しての選曲のようだ。音楽に深く造詣があるわけでもないのに、多彩な声色、吐息、シャウトが織り交ぜられると、表現力というものをやはり見せつけられる。それはきっと映画にも通じるのだろう。カーテンコールは何度も。赤い薔薇が観客に配られていた。オーケストラをバックに歌うアーティストたち。舞台照明というのは不思議なもので、別世界のような空間を演出してくれる。たっぷり、気持ちのいい時間にひたれた。
2006.02.02
コメント(3)
-
●●●愛より強い旅
激情のメロディが男の背中を撫でる。そう、熱く熱く熱く、背中を迸る声はまるで彼の想いの熱さのようで、窓辺からパリの街を見渡していた彼はやっと、ベッドの彼女に声をかけた。昨夜の情事を表すかのように、二人とも真っ裸。旅が、始まる。ザノは恋人のナイマを旅に誘った。彼の両親が捨てざるを得なかった故郷、遠く、7000キロ離れた、アルジェリアへの旅。徒歩と無賃乗車、時には金を稼ぐため農園で働くことも。通りすがりにさまざま人と出会う。その土地で暮らす人、その土地から離れていく人、パリからアンダルシア、船の乗り間違いでモロッコへ。さまざまな場所で彼らの前に、見えない「国境」が立ちはだかる。パスポートの提示、抜け道、まっすぐに目的地へ辿りつけはしない。若い二人だからこそ、時には、旅先で別の愛を見つけケンカもする。やっと到着したアルジェリアはまだ地震の被害の傷跡が消えないままだ。彼らがアルジェリア入ろうとすれば、アルジェリアから去っていく人々の流れに出会う。どこに境界があるというのか。一つの国に入っていく者と、去りゆく者がいるのである。ザノとナイマ。戯れあい、愛し合いながら確認するようにお互いの傷の所以を話す。男の暴力の傷、幼い頃の事故の傷、誰にも本当のことが言えない深い傷もある。入っていく、去っていく、その度に人は何かをどこかに刻むように。トニー・ガトリフ監督脚本作品。奔流のような熱さが、メロディのうねりとなり画面からも溢れている。「音楽が宗教」ザノがそんなことを言っていた。迸るようなのだ、ザノとナイマ、二人の胸の中、探し求めるものの想いの熱さが。ロマン・デュリスが魅力的にザノを演じ、ルフナ・アザバルが奔放にナイマを演じている。激情のメロディ。故郷に出会うザノと故郷を自分の傷に隠すナイマ。一つの国に入っていく者と去りゆく者がいる。それでも生まれた場所は刻まれている。そして、まだザノとナイマの旅は続いている。
2006.02.01
コメント(1)
-
●●●おかしなおかしなおかしな世界
ドタドタドタドタ、スラップスティック。3時間にも及ぶ、フィジカル・コメディ!It's a mad mad mad mad world1963年の製作、当時のコメディアンが総動員だと言う。老いも若きも、身体を使ってドタドタドタドタ、その「間」の良さは名人芸!ベタさ加減呆れながらも、飽きることなく、見続ける。思わず笑い、思わずニヤッとしてしまうのである。「ロジタ公園に35万ドルが埋まってる!」ハイウェイで事故にあった男は、救出に来た男女にそう言い残して死んでしまった。どうしようどうしよう、躊躇しているのはカタチだけ、迷うことなく皆、ロジタ公園に向かうことに。ドタドタドタドタ、お宝争奪戦である。社長に歯科医にギャグ・ライター、その妻に相棒に、夫と妻と通りすがり、キャラクターも増えていく、しかしながら警察も黙っていない。定年近いカルペパー警部も参戦である。スタンリー・クレイマー監督は、社会派監督ということである、この作品も、人間の際限ない欲というものにテーマがある。だが、それはさておき、そんなこと、どうでもいいくらい、ドタドタドタドタ、スラップスティック。例えば、日本で製作されたなら、吉本新喜劇の出演者に加えて、関東のボードヴィル系劇団員も総動員。ドリフターズにクライジー・キャッツ、コントに強いジャニーズたちも交えながら、コメディアン、コメディエンヌな俳優も織り交ぜて、若手芸人にはチョイ役+エキストラ、我争いオイシイ笑いを追求して、追いかけて追いつめて、はたまた、出会い頭ではじけ飛び、爆発が起きれば、髪も爆発、ベタベタシーンが次々を起きる。3時間という長丁場を飽きさせない笑いは、名人芸の連続である。つい、笑っている、笑わせてくれる登場人物はオモシロ顔。オンナを捨てた役者はパンツ姿になってくれる。アホキャラは道に迷うマザコンで、気取ってても、やはり金を追っかけてる。その「間」の良さは名人芸で、笑いは名人芸から生み出されるのだと知る。今や古くなった演出もあるにはあるが、ドタドタドタドタ、スラップスティック。つい笑ってしまうのだ。It's a mad mad mad mad world洒落たオープニングに、ホオとため息をついてからは、乾いたハイウェイで転落事故が起きるも、すぐに巻き込まれるスラップスティック!往年のバスター・キートン、ジェリー・ルイス、驚くほど若いピーター・フォークは、チョイ役ながら、なかなかイイ男である。その辺の知識があるならば、もっと愉しみも多かっただろう役者陣。ドタドタドタドタ、スラップスティック。その後もたくさんの映画が、この映画の影響を受けたようである。
2006.01.31
コメント(1)
-
●●●ある子供
人という種が生まれて、すこしづつ姿形が変化して、文明という「進化」はあったかも知れない。進化と呼んでも言い部分は幾つかはあるだろう、けれども、「進化」ばかりではなく、「退化」した部分も必ずある。若い父親が自分の子供を売った。少し気は咎めているようだが、大金を得ることの方が重要に見える。それを聞いて母親はショックで気を失ってしまった。父親の名前はブリュノ、20歳。定職につかず、街ゆく人に小銭をせがんだり、盗みで得た商品を金に変えてのその日暮らしである。赤ん坊のジミーを抱いて退院したのは、ソニア、彼女は18歳で母親になった。だが若さなど関係なく、息子を抱きかかえる彼女はもはや母親である。しかし20歳の青年は息子を抱くのさえ怖がっていた。ソニアにせき立てられ認知はしたが、定職について働く気は毛頭なさそうだ。20歳と18歳、まだ若い二人には、生活よりも愛し合う方が大事なのである。それでも、彼女は母親だった。ブリュノはまるで盗みで得た商品を売るように、ブローカーを通じ、ジミーを売った。冷酷さや小狡さなどは微塵もない。彼は彼女に「二人の金」だと札束を見せ、「また産めばいい」とさえ言ったのだ。確かに間違いではないが、間違いでなかったら正しいとは限らない。愛する女性が倒れてしまって、ブリュノはやり直しをしようとした。間違いを犯したならやり直しをすればいい。「金」を渡し、ジミーを取り戻して、全てを丸く収めようとしたのである、が。ソニアは彼を許さなかった。そしてブリュノは転落し始める。赤ん坊を売り損ない儲けをなくしたブローカーが、ブリュノから儲けを回収しようとしたのだ。その日暮らしの青年には、途方もない金額である。何が正しいとか、何が間違っているとか、そういうことで割り切れないものがある。ブリュノとソニアの二人は愛し合っていたのだ、その愛情の間に赤ん坊が現れても、二人は何も変わらなかったのである。彼は父親になったことがわからなかったし、彼女は彼と話し合うことが出来なかった。幸せになるはずの愛し合う二人だったのに、再び二人が会うのは、刑務所の中になる。そうして二人は、自分たちの愚かさを知る。感じなかったのだ、その心が。彼は赤ん坊の命を。彼女の赤ん坊への愛情を。彼女は、彼の苦しみを。二人は現在の自分以外を、感じ、想像し、考えることが出来なかった。間違っててもいいのだ。通じなくてもいいのだ。感じることが出来れば変わっていたものを、感じることが出来ないままだった。この作品は若い男女の物語だが、誰にでもあてはまりうる物語でもある。感じることが出来ずに、しぼんでしまった人という種の「心」。ベルギー・フランス合作、ダルデンヌ兄弟の脚本監督作品。「ある子供」公式サイト
2006.01.30
コメント(8)
-
●●●THE有頂天ホテル
仕事も夢も愛情もなんだって、やりたいようにやってみればいいのだ。やりたいようにすることと、上手くやれることは全く別物だけど。ほら、ホテルアバンティの筆耕係の筆が、新しい年を祝っている。サンタクロース人形のヒゲが筆だったけど。カウントダウンパーティ、民謡を歌うはずだった歌手は艶っぽい声で自分らしい歌を聴かせてくれた。夢を諦めかけたベル・ボーイはまだもう少しがんばろうと決意したばかりで、その顔は晴れ晴れとしている。陽気に踊っている客席係の女性は、元は議員の愛人でシングルマザーだが、ちっとも辛そうな顔はしていない。大体、客室にあった客の衣裳を着て、客になりすまして、誰かの愛人のフリをして、言いたいことを言ってしまえる女性なのである。三谷幸喜監督脚本の作品。ホテルのカウントダウンパーティが始まる、2時間16分前から物語は始まる。ホテル側・客側が入り混じって、本当に入り混じってシャッフルして、それでも舞台はホテル・アバンティ、新年は誰の元へ近づいてきている。申し分のない副支配人には、若き日の夢を諦めた過去がある。そのときのゴタゴタで妻とも別れたが、元妻が別の男性の妻としてホテルに現れた。この男、ホテルマンとしては優秀だが、別れた妻にはやたら見栄を張る、滑稽なほどに。どこか、その場しのぎなのだが。どこか、その場しのぎ。見えない未来よりも、その場しのぎ。副支配人だけでなく、誰も彼もがその場しのぎのようである。例えばベル・ボーイの幼なじみの女性は、盗んだ制服を着て彼の前に現れた。ホテルスタッフに追い出されたはずの、コールガールの女性もまた、熟知の裏口を通って舞い戻ってきた。その場しのぎ、その場しのぎである。カウントダウンパーティの芸人たちのマネージャーはいなくなった出演者の代わりに、強烈な髪型のまま女装している。白塗り好きの支配人は、白塗りをしたままホテルを駆け回り、人気者の演歌歌手はいつも、ステージの前は自殺したがるようだ。それでも、なんとかなるのである。汚職で窮地にある議員もまた、なげやりな態度でクロスワードを解き、自分の人生の選択肢を選びそこねていた。先のことを考えるか、スキッとさせるかどうか。例えば、自殺とか。その場しのぎかも知れないけれど、やりたいことなら納得できるのだ、スキッとするのだ、スキッとするというのは、そこに「私」がいると感じることのようである。それが「私」であると、申し分のない支配人は申し分のない仕事をしている。さまざまな登場人物たちも同じである。やりたいようにすることと、上手くやれることは全く別物だけど、「その場」という「現在」は、「その場しのぎ」で成り立っている。だったら、自分らしく。とにかくいろいろあるだろうけど。ホテルのカウントダウンパーティ、新しい年がやってくる、新しい明日が。とにかくだ、とにかくだけど。仕事も夢も愛情もなんだって、やりたいようにやってみるしかない。とにかく、その場しのぎでも!!
2006.01.29
コメント(11)
-
●●●功名が辻~いつまでもロマンティック!
愛しいと思う気持ちのぬくもり、心に宿った感情の温度は、どんな時代も暖めてくれる。どんなに荒んだ時代であっても。時は戦国時代、織田信長は稲葉山城を道三入道から譲られたが悪戯に月日重ねども、まだおちない。道三の孫、龍興は無能なれど、美濃には若き軍師、竹中半兵衛がいる。その彼がやっと動いたのは、まるで妹のように側にいた千代のためである。不破市之丞の姪の感情は、敵地にいる山内一豊に向けられていた。愛しいと思う気持ちは、戦場にあっても抑えられない。しかしどんな時代であっても、好きあっているだけで結ばれるものではない。山内一豊もまた千代が愛しい、だが、仕える主君がいて、家臣もいて、何よりも彼の誠実さが誰かを裏切ってまで幸せを得ようとしない。自分だけの幸せなど彼は欲する男ではないのである。愛しいと思えども。竹中半兵衛は愛しい女性の幸せを願った。時は戦国時代、命のやりとりが常、だがこんな時代だからこそ、好きあった者が結ばれもいいだろうと、千代と一豊を添わせようとする。秀吉の求めに応じ、織田側につき、難攻不落の稲葉山城の抜け道を教え、城にいる千代を救えと一豊に言った。命がけで救え、と彼は言った、そう言いながら彼の目には気持ちが溢れている。自分ではなく、他の男に、愛しい女性を託しているのだ。僧であり、兵の姿にもなり、千代の幼なじみの六平太もまた、愛しい女性を見守り続けている。自分ではなく他の男が、愛しい女性の思い人である切なさよ、それでも、幸せであれと彼の目も、物言わぬまでも物語っている。炎に包まれる稲葉山城。千代を探す一豊と長刀を持ち戦う千代、敵味方に別れているはずの二人は素直なまでに自分の気持ちに正直である。戦いの最中、炎に包まれる城の中、敵味方のはずの秀吉と、不破市之丞たちもまた、二人の温度に包まれていた。誰かを思う気持ちは誰にでもある。どんな時代であったも。結ばれないと思っていたのに、結ばれると知った千代と一豊の抱擁。姪の幸せ願う、不破市之丞ときぬの夫婦。焼け跡から探し得た十両は有名な逸話を生み出した。主、一豊の嫁取りを心配する五藤吉兵衛と祖父江新右衛門も、懸命な愛情に溢れているのが窺い知れる。そしてただ千代と一豊を見つめる、六平太の視線の切なさと、咳き込み血を吐く竹中半兵衛の静けさの裏側は、愛しい女性への想いに満ちあふれている。愛しいと想う気持ちのぬくもり。それでも叶わぬ願い、散る命もあっただろう。だが、千代と一豊は結ばれる。激動の時代を二人で乗り越えていく。時は戦後時代。なんとロマンティックなのだろう。
2006.01.29
コメント(3)
全691件 (691件中 1-50件目)
-
-

- 宝塚好きな人いませんか?
- 月城かなと1st Concert 「de ja Vu」
- (2024-11-25 23:50:54)
-
-
-

- NHKおはよう日本 まちかど情報室
- 【 中学・高校生用 】お弁当の作り方…
- (2024-05-07 10:19:14)
-
-
-

- 今日見た連ドラ。
- カムカムエヴリイバディ NHKドラマ…
- (2022-01-28 23:32:16)
-








