PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Comments
コメントに書き込みはありません。
カテゴリ: 劇評
現在形の批評 #55(舞台)
楽天ブログ★アクセスランキング
・ 流山児★事務所
2月10日 精華小劇場 マチネ
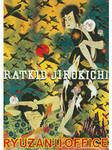
肉体顕現への執拗さ
佐藤信の戯曲『鼠小僧次郎吉』の連作が上演されたのは1970年から71年であった。かつて演劇状況を一変させんとするルネサンスが我が国で仇花的に勃興した。それが今日までに至る現代小劇場演劇史に与えた集団・俳優/身体・戯曲などの各論へ与えた影響は、もはや生きる歴史と呼ぶに相応しい佐藤信を含めた演劇ルネサンス当事者達による作品や理論、あるいはそれ以後にも頻出した演劇内外の言説によって今や周知の通りである。作り手と受け手双方による、生血が迸るかのごとく応酬する丁丁発止の緊張感こそ、当時の劇状況を支えた要であり、それはまさに両者が「共犯関係」を取り結んだ紛れもない「運動」行為だったのである。
「運動」とはまさしく何事かを変革することを不断に邁進し続ける漸進的意志を孕んだ行為のことに他ならず、そこには明確な思想を基にした全方位的な射程を備えたパースペクティブがある。演劇ルネサンスの場合の「運動」とは上記のような演劇それ自体を巡る作り手と受け手の邂逅を発端とする劇理論の再考はもとより、それを土台に据えた社会変革を目論む壮大な「格闘」を意味した。「運動」=「格闘」を<革命の演劇>という理念として最も明確に打ち出したのが佐藤信率いる演劇センター68/71であった。連作『鼠小僧次郎吉』は<コミュニケーション計画>と題された具体的事項(拠点劇場・移動劇場・壁面劇場・教育・出版)で以っていくつかの集団と移動公演を始めた時期に相当する。こういった背景を持つ作品が二十一世紀の今、蘇った。青い流れ星に引き寄せられるままに変化した五匹の鼠小僧が起こす「時(とき)」への果敢な抵抗という革命を、天野天街は上質なエンターテイメントへと仕上げた。
スピード感溢れる展開構成、映像トリックを用いた幻惑、均整のとれた機械仕掛けのダンスを執拗なまでに反復するなど、独特な天野スタイルがふんだんに盛り込まれている。アングラテイストを独自の方法論によって味付けするこの演出家らしく、自身のフィールドへ引き込んで主題を仰々しく提示したり感情移入させることなく、「目の欲望」を満たすことに重点を置いた仕上がりである。それは翻って言えば「上質なエンターテイメント」の枠を越えることがなかったとも言えるし、楽しみながらも、あの時代が志向した革命を今の時代の革命に置換させて何がしかの意味を持たせられなかっただろうかと思わされた点は残念であった。
当時刊行された連作を収めた戯曲集『嗚呼鼠小僧次郎吉』(晶文社 1971)を読むといくつかの改変点が散見される。まず舞台空間の作りであるが、戯曲が指定しているような蝋燭だけの空間ではなく、舞台両側にドアがあり、タイル張りの銭湯風呂のセットを組んで額縁の中に劇行為が収斂されるように設えている。そして、流山児祥演じる門番が背負う大きな時計はハンドバックのような小道具になっている。「あさぼらけの王」と名付けられた、門番が常に所有する紫の布にくるまれた玉は今回の上演では門番(2)とされ、少年王者館の夕沈が演じた。「あさぼらけの王」が白装束姿で自由気侭に動き回る生命体になったことで、この作品は門番(2)が仕掛けた束の間の夢という印象が強調された。このあたりは天野世界のエッセンスの表出だと言えよう。だが、この門番が倒れる直前に発する以下の台詞
それは「「人材育成」公演」(当日パンフレット)と据えられていたように、若手・中堅俳優の演技である。カブを拾った鼠の一番(イワヲ)が鼠の二番(里美和彦)、鼠の三番(甲津拓平)に与えるために半分ずつ分けるシーンで、執拗なまでそのやり取りを反復させた。天野による反復の演出は、劇を過去に戻らせたり芝居であることを前景化させるためにカットインのように盛り込まれるのが通常だが、この時はただ単純に反復されたのである。ざっと20回は続いただろうか。観客がそろそろ終わるだろうとの予想を凌駕する執拗さがあまりに滑稽で笑わせられた。目まぐるしく場面展開させて幻惑する天野トリックの中でも、ここだけが特別に浮き上がっていた。呂律が不確かになるまで疲れ果てながらも、それを突き抜けていく果てしない執念さだけが支えとなる反復には、紛れもない肉体の血肉が暴発した先の生身のリアルが露呈する。演出と俳優修行ががっちり合わさったこの場面の存在によって、この作品は観るべき価値を有した。
戯曲世界の代弁・再現による俳優の魅力とは異なった、むき出しの俳優自身の核の顕れが、観るものにほんの一時だが、裸のコミュニケーションという「共犯関係」を切り結ばせたのだ。
楽天ブログ★アクセスランキング
・ 流山児★事務所
2月10日 精華小劇場 マチネ
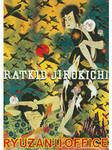
佐藤信の戯曲『鼠小僧次郎吉』の連作が上演されたのは1970年から71年であった。かつて演劇状況を一変させんとするルネサンスが我が国で仇花的に勃興した。それが今日までに至る現代小劇場演劇史に与えた集団・俳優/身体・戯曲などの各論へ与えた影響は、もはや生きる歴史と呼ぶに相応しい佐藤信を含めた演劇ルネサンス当事者達による作品や理論、あるいはそれ以後にも頻出した演劇内外の言説によって今や周知の通りである。作り手と受け手双方による、生血が迸るかのごとく応酬する丁丁発止の緊張感こそ、当時の劇状況を支えた要であり、それはまさに両者が「共犯関係」を取り結んだ紛れもない「運動」行為だったのである。
「運動」とはまさしく何事かを変革することを不断に邁進し続ける漸進的意志を孕んだ行為のことに他ならず、そこには明確な思想を基にした全方位的な射程を備えたパースペクティブがある。演劇ルネサンスの場合の「運動」とは上記のような演劇それ自体を巡る作り手と受け手の邂逅を発端とする劇理論の再考はもとより、それを土台に据えた社会変革を目論む壮大な「格闘」を意味した。「運動」=「格闘」を<革命の演劇>という理念として最も明確に打ち出したのが佐藤信率いる演劇センター68/71であった。連作『鼠小僧次郎吉』は<コミュニケーション計画>と題された具体的事項(拠点劇場・移動劇場・壁面劇場・教育・出版)で以っていくつかの集団と移動公演を始めた時期に相当する。こういった背景を持つ作品が二十一世紀の今、蘇った。青い流れ星に引き寄せられるままに変化した五匹の鼠小僧が起こす「時(とき)」への果敢な抵抗という革命を、天野天街は上質なエンターテイメントへと仕上げた。
スピード感溢れる展開構成、映像トリックを用いた幻惑、均整のとれた機械仕掛けのダンスを執拗なまでに反復するなど、独特な天野スタイルがふんだんに盛り込まれている。アングラテイストを独自の方法論によって味付けするこの演出家らしく、自身のフィールドへ引き込んで主題を仰々しく提示したり感情移入させることなく、「目の欲望」を満たすことに重点を置いた仕上がりである。それは翻って言えば「上質なエンターテイメント」の枠を越えることがなかったとも言えるし、楽しみながらも、あの時代が志向した革命を今の時代の革命に置換させて何がしかの意味を持たせられなかっただろうかと思わされた点は残念であった。
当時刊行された連作を収めた戯曲集『嗚呼鼠小僧次郎吉』(晶文社 1971)を読むといくつかの改変点が散見される。まず舞台空間の作りであるが、戯曲が指定しているような蝋燭だけの空間ではなく、舞台両側にドアがあり、タイル張りの銭湯風呂のセットを組んで額縁の中に劇行為が収斂されるように設えている。そして、流山児祥演じる門番が背負う大きな時計はハンドバックのような小道具になっている。「あさぼらけの王」と名付けられた、門番が常に所有する紫の布にくるまれた玉は今回の上演では門番(2)とされ、少年王者館の夕沈が演じた。「あさぼらけの王」が白装束姿で自由気侭に動き回る生命体になったことで、この作品は門番(2)が仕掛けた束の間の夢という印象が強調された。このあたりは天野世界のエッセンスの表出だと言えよう。だが、この門番が倒れる直前に発する以下の台詞
「おろしてくれ-背中の時計。全てが焼きついちまってるんだ。時計が重いんだよ-ねえ、おっ母さん、おろしとくれ。おろしとくれ。おっ、おっ母さあん。このままじゃ、永久に、もう永久に子の刻-おっ母さん!」という、先の戦争の悲痛な枷=責任を背負ったかのような人物の最期の口上が実にあっさりとしたものになっていた。またそれに関連して、その後、鼠小僧達が頬かむりを取った顔にはケロイド痕がなかった。最も抒情的というか、この作品の革命性を主張する仇討ち場面の天野演出の処理は不満が残った。かつての再現を行ったところで、それこそ「再現」以上の何物をも生み出さないのは明らかである。だが、戯曲という素材をいかに調理して今という時代に手触り確かなものに仕立てあげるかという点で言えば、十分に達成されていたとは言えない。とは言え、その代わりと言えば難だが、別の視点にこの舞台の白眉さが認められるのは確かだ。
それは「「人材育成」公演」(当日パンフレット)と据えられていたように、若手・中堅俳優の演技である。カブを拾った鼠の一番(イワヲ)が鼠の二番(里美和彦)、鼠の三番(甲津拓平)に与えるために半分ずつ分けるシーンで、執拗なまでそのやり取りを反復させた。天野による反復の演出は、劇を過去に戻らせたり芝居であることを前景化させるためにカットインのように盛り込まれるのが通常だが、この時はただ単純に反復されたのである。ざっと20回は続いただろうか。観客がそろそろ終わるだろうとの予想を凌駕する執拗さがあまりに滑稽で笑わせられた。目まぐるしく場面展開させて幻惑する天野トリックの中でも、ここだけが特別に浮き上がっていた。呂律が不確かになるまで疲れ果てながらも、それを突き抜けていく果てしない執念さだけが支えとなる反復には、紛れもない肉体の血肉が暴発した先の生身のリアルが露呈する。演出と俳優修行ががっちり合わさったこの場面の存在によって、この作品は観るべき価値を有した。
戯曲世界の代弁・再現による俳優の魅力とは異なった、むき出しの俳優自身の核の顕れが、観るものにほんの一時だが、裸のコミュニケーションという「共犯関係」を切り結ばせたのだ。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Aug 11, 2009 06:39:35 PM
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.










