テーマ: 旅行するならやっぱり京都(649)
カテゴリ: 京都のニュース
2016年
「第4回内国勧業博覧会」 を2年後に控えた1893(明治26)年、京都市左京区岡崎で行われた博覧会場建設のための地鎮祭で、祇園祭の山鉾が並ぶ様子を撮影した鮮明な写真が見つかった。写真を購入、分析した穎川(えがわ)美術館(兵庫県西宮市)の八反裕太郎学芸員(43)によると、この地鎮祭に山鉾が出た写真は初めての確認であり、“知られざる山鉾巡行”の一面と言える。山鉾の近代史を捉える上でも注目される。
同志社女子大で6月に開催された「藝(げい)能史研究会」の第53回大会において、八反学芸員が発表した。写真は2枚あり、それぞれ縦18センチ、横20・8センチ、当時主流だった鶏卵紙を使用していた。縦23・5センチ横28・3センチの台紙には「明治廿(にじゅう)六年岡崎大極殿四回大博覧會(かい)地鎮祭の時地かための為め引出せしの時の寫眞(しゃしん)」との書き付けがあった。
写っていた山鉾は、後方から南観音山と八幡山、鯉山、浄妙山、北観音山、黒主山で、この年の祇園祭のくじ順とは異なる。判別できないが、鉾の特徴である真木(しんぎ)が4本立つ。後祭の山鉾に真木を持つ鉾はなく、前祭の鉾も出ていたことが分かる。鯉山には現在はない屋根が付き、南観音山2階に羽織はかま姿の囃子(はやし)方が乗る。ガス灯も確認できる。また、山鉾の進行方向に瓦屋根の建物が写り、八反学芸員は金戒光明寺(左京区黒谷)だとみる。
1890(明治23)年4月8日、岡崎地区で行われた 琵琶湖疏水完成記念式典 に月鉾、鶏鉾、郭巨(かっきょ)山、油天神山の4基が出る絵図は残るが、鴨川を越えた場所で山鉾が写真に写るのは、地鎮祭の2枚だけという。八反学芸員は「山鉾町には大量の資料が眠っている。祇園祭の近代に目を向けるきっかけになってほしい」と話している。
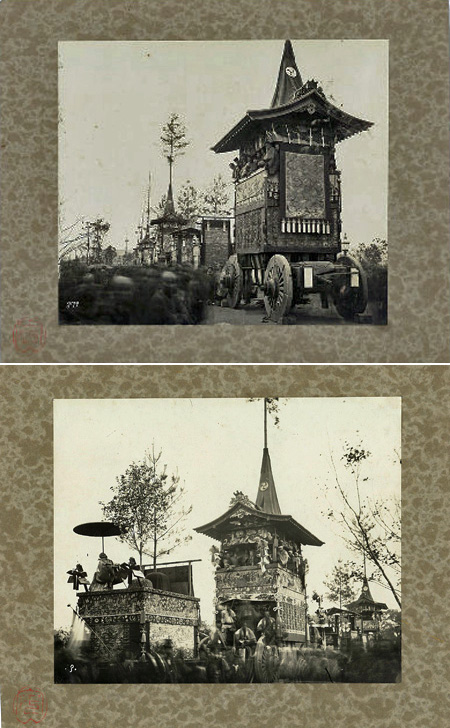
よろしかったらぽちっとお願いします。

にほんブログ村
「京都のニュース」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=20
「京都の行事・お祭り案内」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=32
「京都検定過去問」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28
「第4回内国勧業博覧会」 を2年後に控えた1893(明治26)年、京都市左京区岡崎で行われた博覧会場建設のための地鎮祭で、祇園祭の山鉾が並ぶ様子を撮影した鮮明な写真が見つかった。写真を購入、分析した穎川(えがわ)美術館(兵庫県西宮市)の八反裕太郎学芸員(43)によると、この地鎮祭に山鉾が出た写真は初めての確認であり、“知られざる山鉾巡行”の一面と言える。山鉾の近代史を捉える上でも注目される。
同志社女子大で6月に開催された「藝(げい)能史研究会」の第53回大会において、八反学芸員が発表した。写真は2枚あり、それぞれ縦18センチ、横20・8センチ、当時主流だった鶏卵紙を使用していた。縦23・5センチ横28・3センチの台紙には「明治廿(にじゅう)六年岡崎大極殿四回大博覧會(かい)地鎮祭の時地かための為め引出せしの時の寫眞(しゃしん)」との書き付けがあった。
写っていた山鉾は、後方から南観音山と八幡山、鯉山、浄妙山、北観音山、黒主山で、この年の祇園祭のくじ順とは異なる。判別できないが、鉾の特徴である真木(しんぎ)が4本立つ。後祭の山鉾に真木を持つ鉾はなく、前祭の鉾も出ていたことが分かる。鯉山には現在はない屋根が付き、南観音山2階に羽織はかま姿の囃子(はやし)方が乗る。ガス灯も確認できる。また、山鉾の進行方向に瓦屋根の建物が写り、八反学芸員は金戒光明寺(左京区黒谷)だとみる。
1890(明治23)年4月8日、岡崎地区で行われた 琵琶湖疏水完成記念式典 に月鉾、鶏鉾、郭巨(かっきょ)山、油天神山の4基が出る絵図は残るが、鴨川を越えた場所で山鉾が写真に写るのは、地鎮祭の2枚だけという。八反学芸員は「山鉾町には大量の資料が眠っている。祇園祭の近代に目を向けるきっかけになってほしい」と話している。
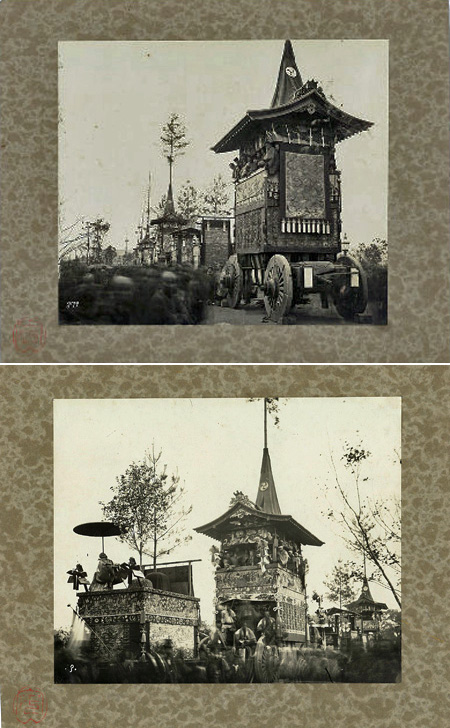
よろしかったらぽちっとお願いします。
にほんブログ村
「京都のニュース」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=20
「京都の行事・お祭り案内」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=32
「京都検定過去問」カテゴリー
http://plaza.rakuten.co.jp/saaikuzo/diary/ctgylist/?ctgy=28
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[京都のニュース] カテゴリの最新記事
-
【京都のニュース】修学旅行減は8割だけ 2021/07/16 コメント(2)
-
【京都のニュース】京都タワーの大浴場閉鎖 2021/06/13 コメント(2)
-
【京都のニュース】桂離宮 御殿かさ上げ… 2020/08/18
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
カテゴリ未分類
(6)常駐ガイド
(132)同行ガイド
(13)修学旅行ガイド
(51)修学旅行昼食処
(66)研修会
(9)京都ガイド諸活動
(53)私的ガイド
(4)京都研究
(45)京都市内全寺社巡り
(197)京都歩き
(194)美術・博物館
(50)講演会
(21)国内旅行
(6)旧東海道
(65)京都検定1級受検勉強
(239)京都検定1級過去問
(180)京都検定1級問題分析
(9)京都のニュース
(1888)京都のイベント・お祭り案内
(140)京都本
(27)津軽三味線
(31)日本でのゴルフ
(41)懇親会
(61)就職・退職など手続き
(55)吾唯足知~断捨離と必要最低限の買い物
(19)散歩・草花記
(630)健康管理
(24)この本読みました
(35)映画
(33)観劇・観戦
(9)私の十大ニュース
(99)気になったニュース・CM
(317)お天気・気候の話
(12)今日のこと
(170)仕事のこと
(0)癌闘病記
(485)癌治療振り返り
(87)癌治療情報
(593)ドイツの想い出
(209)スイス横断サイクリング
(31)ゴルフとアメリカ生活
(132)アメリカ出張
(36)ワルディ流日米国情比較
(16)母の備忘録
(0)商品レビュー
(3)ブログ記録
(10)食事処、飲み処
(13)京都案内
(218)若冲と応挙
(55)カレンダー
© Rakuten Group, Inc.












