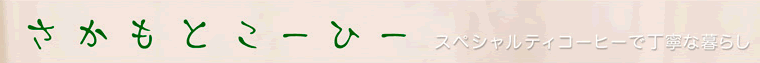カテゴリ: コーヒーの焙煎を考える
梅雨入りとかで、嫌な季節になってきましたが…昨日今日とシナモンのキャンブリックティーを淹れて、ついつい自分で飲んでしまいます。お客さんよりも自分の為の紅茶ですね。
さて、「コーヒーの焙煎を考える(14)」ですが…悩ましい「水分抜き」の続きです。
考え方次第なんで、分かってしまえば簡単なんですが…「水分抜き工程」を決めて、そのスタートからゴールまでの時間で管理するだけです。
まぁ、では、そのスタートをどこにして、ゴールをどこにするか、これが的確で無かったら何の意味も無いので、そこをどう決めるかで、その焙煎のレベルがひとつ決まってしまうと思います。
うちの場合、スタートからゴールまで50℃あります。その50℃を一定の時間で上昇するようにコントロールしています。その誤差はプラスマイナス0.2分です。ほとんどプラスマイナス0.1分でコントロールしています。0.3分ぶれると、お客さんには分かりづらい位ですが、カッピングすると明らかに分かる位味にも香りにも出ますので、そうならないようキッチリコントロールします。
ロースティング工程でも同じですので…焙煎は朝6時過ぎから出来るだけ開店前に終了するようにしています。忙しいと開店後にずれ込んだり、足らなくなって午後焙くこともたまにありますが、その時は接客しなくても良いように、スタッフに接客をお願いしてます。
ゴールは、香りを嗅いでいれば水分抜けのタイミングが見えるので、決めやすいと思います。スタートをどこからにするかは、その人が焙煎をどう捉えているかが良くでると思ってます。まぁ、最初はだいたいで決めて、焙煎、記録、カッピングの繰り返しで、より効果的なポイントを決めていくしかないでしょう。
とにかく、このスピードが早くても遅くても水分抜けが甘くなって、香りにも味わいにも悪影響すると思ってます。一番厄介なのは、だいたい抜けているケースですね。なんとなく悪く無いので、もっと魅力的になるポイントを分かっていないと、それでOKだと判断しがちですね。
特に、素材が良いと一見クリーンカップなので、何年やっても香りやマウスフィール、甘さ、爽やかさがでないと思ってます。そうそう、ペーパードリップだとその辺の微妙な感覚が分かりづらいとも思ってます。
でも、自分の物差しが決まったら、あとは繰り返しですので、快適だと思います。
さて、「コーヒーの焙煎を考える(14)」ですが…悩ましい「水分抜き」の続きです。
考え方次第なんで、分かってしまえば簡単なんですが…「水分抜き工程」を決めて、そのスタートからゴールまでの時間で管理するだけです。
まぁ、では、そのスタートをどこにして、ゴールをどこにするか、これが的確で無かったら何の意味も無いので、そこをどう決めるかで、その焙煎のレベルがひとつ決まってしまうと思います。
うちの場合、スタートからゴールまで50℃あります。その50℃を一定の時間で上昇するようにコントロールしています。その誤差はプラスマイナス0.2分です。ほとんどプラスマイナス0.1分でコントロールしています。0.3分ぶれると、お客さんには分かりづらい位ですが、カッピングすると明らかに分かる位味にも香りにも出ますので、そうならないようキッチリコントロールします。
ロースティング工程でも同じですので…焙煎は朝6時過ぎから出来るだけ開店前に終了するようにしています。忙しいと開店後にずれ込んだり、足らなくなって午後焙くこともたまにありますが、その時は接客しなくても良いように、スタッフに接客をお願いしてます。
ゴールは、香りを嗅いでいれば水分抜けのタイミングが見えるので、決めやすいと思います。スタートをどこからにするかは、その人が焙煎をどう捉えているかが良くでると思ってます。まぁ、最初はだいたいで決めて、焙煎、記録、カッピングの繰り返しで、より効果的なポイントを決めていくしかないでしょう。
とにかく、このスピードが早くても遅くても水分抜けが甘くなって、香りにも味わいにも悪影響すると思ってます。一番厄介なのは、だいたい抜けているケースですね。なんとなく悪く無いので、もっと魅力的になるポイントを分かっていないと、それでOKだと判断しがちですね。
特に、素材が良いと一見クリーンカップなので、何年やっても香りやマウスフィール、甘さ、爽やかさがでないと思ってます。そうそう、ペーパードリップだとその辺の微妙な感覚が分かりづらいとも思ってます。
でも、自分の物差しが決まったら、あとは繰り返しですので、快適だと思います。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[コーヒーの焙煎を考える] カテゴリの最新記事
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(127)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments
© Rakuten Group, Inc.