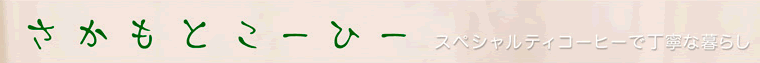カテゴリ: コーヒーの焙煎を考える
蒸し暑さが増してきましたが、立秋だそうですね。店が広くなったので焙煎の熱さが去年迄よりだいぶ楽になりました。このところ、続けてメロンがやってきて、店のみんなで頂いています。メロン食べると涼やかな気分になります。その後、アイスクリームを食べたくなると言ったら…女性陣から、疑問の声が上がりました。
そんなこんなで…「コーヒーの焙煎を考える(23)」です。今日は「味のしくみ」から、乾熱調理の続きです。
*香りをつくる物質(香りの正体)
-糖類のカラメル化
砂糖を強く熱するとあめ状となり、やがてきれいなきつね色に変わります。それとともに、とてもこうばしい香りがでてきます。
さらに加熱してこれを焦がすと、炭化して黒くなり、よい香りがなくなってしまいます。
このきつね色の状態のものがカラメルで、プディングのソースなどに使われたりします。
砂糖やその他の糖類は、100℃以上に加熱されると徐々に分子の形態が変化していきます。そして、カラメルの状態になると、分子は大きな変化をおこします。
その変化とはきつね色になることと、よい香りが生まれることです。
カラメル化は、砂糖や糖類が180℃くらいで加熱されるとおこります。
しかし、200℃以上になると炭化してしまいます。
大部分の食品には糖類が多少は含まれています。たとえば肉のようにタンパク質が主成分であると思われているものでも、グリコーゲンなどの糖類が必ず含まれています。また、肉料理などでタレを用いる場合、そのタレのなかには必ず糖類が加えられますし、しかもその材料中にもいくらかの糖類が含まれています。したがって、食品の多くは焼くことによって、カラメルの香りが当然あるわけです。
と、言った内容です。
僕にとってのカラメルは、最初に修行に入ったフルーツパーラーで、毎日毎日プリンの仕込みをしていました。プリンやプリンアラモードがとっても人気でした。
上白糖を乾いたフライパンに入れ、火にかけて、バースプーンでかき混ぜながら熱していきます。だんだん水分が出てきて、泡立ち、色づき、きつね色…ここからが一秒単位の勝負です。どこまで焦がすか、色と香りと煙と見つめながら…ここだ!ってところで少量の水を注ぎ入れ、火から降ろし、用意しておいてプリンカップに入れて行きます。
焙煎と似たところがありますね。
で、プリンを試食しては、カラメルとのバランスを考え…次の仕込みに生かしていました。
そんななんで…ケーキ屋さんの手抜きカラメルのプリンやしらっちゃけた気の抜けたようなカラメルのプリンを食べると…プリンへの愛情のなさにがっくりします。
焦がしちゃいけないけど、しっかりカラメル化しないと、プリンの魅力は半減です。
焙煎のカラメル化は色々と考えられますね。
カラメルとは分からない程の焙き具合から、カラメルの魅力が生きているもの、かなり焦げに近くなっているもの…。
素材のポテンシャルやキャラクター、お客さんのお好み…色々な要素が関わってきます。
残念なのは…焦げを恐れるあまり、カロリー不足でデベロップしていない焙煎…焙煎はあくまでも乾熱調理なんですから、しっかりかけるところではカロリーかけないと焙煎いよる魅力ができません。
「焦げ」と言っても、一人一人考え方が違いますので…「焦げ」をどう捉え、どう考え、どうコントロールするかが大切になってきます。そして、その「焦げ」は自分本位の考えでは無く…お客様本位、カスタマーオリエンテッドの視点で考えることが、より魅力につながっていくと思ってます。
乾熱調理は一瞬のスピードが必要なので、コントロールが難しいですから、どうコントロールするかが必要になってきますね。
次回は、脂肪の加熱と香りです。
そんなこんなで…「コーヒーの焙煎を考える(23)」です。今日は「味のしくみ」から、乾熱調理の続きです。
*香りをつくる物質(香りの正体)
-糖類のカラメル化
砂糖を強く熱するとあめ状となり、やがてきれいなきつね色に変わります。それとともに、とてもこうばしい香りがでてきます。
さらに加熱してこれを焦がすと、炭化して黒くなり、よい香りがなくなってしまいます。
このきつね色の状態のものがカラメルで、プディングのソースなどに使われたりします。
砂糖やその他の糖類は、100℃以上に加熱されると徐々に分子の形態が変化していきます。そして、カラメルの状態になると、分子は大きな変化をおこします。
その変化とはきつね色になることと、よい香りが生まれることです。
カラメル化は、砂糖や糖類が180℃くらいで加熱されるとおこります。
しかし、200℃以上になると炭化してしまいます。
大部分の食品には糖類が多少は含まれています。たとえば肉のようにタンパク質が主成分であると思われているものでも、グリコーゲンなどの糖類が必ず含まれています。また、肉料理などでタレを用いる場合、そのタレのなかには必ず糖類が加えられますし、しかもその材料中にもいくらかの糖類が含まれています。したがって、食品の多くは焼くことによって、カラメルの香りが当然あるわけです。
と、言った内容です。
僕にとってのカラメルは、最初に修行に入ったフルーツパーラーで、毎日毎日プリンの仕込みをしていました。プリンやプリンアラモードがとっても人気でした。
上白糖を乾いたフライパンに入れ、火にかけて、バースプーンでかき混ぜながら熱していきます。だんだん水分が出てきて、泡立ち、色づき、きつね色…ここからが一秒単位の勝負です。どこまで焦がすか、色と香りと煙と見つめながら…ここだ!ってところで少量の水を注ぎ入れ、火から降ろし、用意しておいてプリンカップに入れて行きます。
焙煎と似たところがありますね。
で、プリンを試食しては、カラメルとのバランスを考え…次の仕込みに生かしていました。
そんななんで…ケーキ屋さんの手抜きカラメルのプリンやしらっちゃけた気の抜けたようなカラメルのプリンを食べると…プリンへの愛情のなさにがっくりします。
焦がしちゃいけないけど、しっかりカラメル化しないと、プリンの魅力は半減です。
焙煎のカラメル化は色々と考えられますね。
カラメルとは分からない程の焙き具合から、カラメルの魅力が生きているもの、かなり焦げに近くなっているもの…。
素材のポテンシャルやキャラクター、お客さんのお好み…色々な要素が関わってきます。
残念なのは…焦げを恐れるあまり、カロリー不足でデベロップしていない焙煎…焙煎はあくまでも乾熱調理なんですから、しっかりかけるところではカロリーかけないと焙煎いよる魅力ができません。
「焦げ」と言っても、一人一人考え方が違いますので…「焦げ」をどう捉え、どう考え、どうコントロールするかが大切になってきます。そして、その「焦げ」は自分本位の考えでは無く…お客様本位、カスタマーオリエンテッドの視点で考えることが、より魅力につながっていくと思ってます。
乾熱調理は一瞬のスピードが必要なので、コントロールが難しいですから、どうコントロールするかが必要になってきますね。
次回は、脂肪の加熱と香りです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[コーヒーの焙煎を考える] カテゴリの最新記事
-
プロのつぶやき1105「さかもとこーひーの… 2021.05.02
-
プロのつぶやき1104「スペシャルティコー… 2021.04.25
-
プロのつぶやき1076「さかもとこーひーの… 2020.10.11
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
Category
カテゴリ未分類
(126)スペシャルティコーヒー
(1414)ニカラグア・エルサルバドル産地巡り
(9)美味しい暮らし
(279)コーヒーのコク研究
(49)コーヒーの焙煎を考える
(61)さかもとこーひー、5つのこだわり
(11)フードペアリングの方程式
(56)僕の好きな紅茶
(34)サンプリング倶楽部21
(23)コーヒービジネスを考える
(77)Comments
© Rakuten Group, Inc.