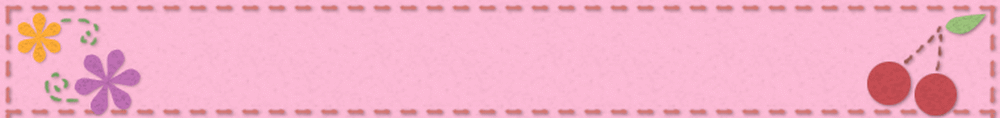PR
X
カテゴリ: ★小説「CALLING・神々の追憶」★
神社の長い階段を上りきると、眼下には大都会を望むことができた。といってもここより高い建造物はいくらでもある。ささやかな眺望だ。ここではいつも大腿筋を鍛えるために、レッグエクステンション代わりに使うタイヤを茂みから取り出して、六種類を三セットすます。タイヤはいつも、草木のなかに隠してあった。上腕三頭筋を鍛えるために、ベンチプレスをしたいが、ないものは仕方がない。
神社の林の木に勝手につけた、タイヤを蹴る。サンドバッグ代わりに蹴や拳をいれる。こうして拳や足を鍛えるのだ。本当はスパーリングなどもしたいが、相手がいない。毎日のように道場に通っていた頃がなつかしい。いずれ神主に怒鳴られるだろうが、六年たってもまだ無事だ。
選手権で優勝するなど極められなかったのは、柔道や剣道、古武道など手を広げすぎたせいだろう。一つの武道だけでは安心できなかった。いつも二人の女を守るために、急いでいた。
七時をすぎて思い出した。今日は特別の日だった。初出社の日だったのだ。慌てて階段をかけおり、アパートに戻った。シャワーを浴びて、支度を整える。バブル時代に無理矢理付け足した浴そうなので、五右衛門風呂のように狭かった。加納が発達した長身を入れると、まるで子供の行水だ。
変色し曇った鏡に映った半身は、すでに傷だらけだった。修業でついたものもあるが、ほとんどが十年前のものだ。それは刻印のように、加納の体に刻まれていた。加納への呪いの言葉として、いつまでもそこにあった。
新聞記者になろうとして、通学しながらのジャーナリスト養成学校の夜間部に通っていた。何社か受けて、やっと地方紙の一社に内定をもらった。新聞社はそれなりに競争率が高く、志望者の学歴が高い。どうしても早く決めたくて先輩を回り、教授の推薦をうけたが苦しかった。いつも金欠だったが、ジャーナリスト受験講座にも通った。どこもダメだった悪友たちに言わせると、潜り込んだことになるらしい。もちろんアルバイトで入り込みコネを作っていたことも、功を奏した。どこもダメなら、関連職種で入り込もうと思っていた。就職浪人をしないために、ありとあらゆる手段をとっておいた。アピールできることを数多く作っておいたのが、よかったのだろう。これも努力の結果だ。粘り強い作戦が、勝利をもたらす。
大学を休学して、留学したこともよかったのかもしれない。一年間たっぷりと学んだ。外国人が多い店でもバイトをしていたことがあった。日本人の多い場所だが、ネイティブと数多く話したことはいい経験になった。もともとクニの者たちは留学するものが多い。これは内定に、もっとも強いアピール材料になったはずだ。
そうして勝ち取った新聞社への初出社が、今日だった。アルバイトで金をコツコツと貯め、成人式に買ったスーツを着る。タイは苦しいが、大人になったような気がした。新聞社には初めて出入りをするわけではないが、こうして改めて社会人として自覚すると身が引き締まった。カバンを抱きしめて、ダッシュした。
大学とは反対の方向の通勤ラッシュに飲み込まれながら、東党新聞東京本社へと向かった。窓越しに東京の街を眺めていると、六年前に捨てるように出てきた、故郷のことが脳裏に浮かぶ。東京に来て誰にも故郷のことを話したことがなかった。(あの場所)には残してきたものがたくさんありすぎた。だからこそ、戻ることができない。戻る勇気が必要だった。しかしこうして社会で、独りで生きてゆくために就職をしてみると、時間に追われ、勇気を取り戻すこともおろそかになる。もしかしたら、もう戻ることはないのかもしれない。何もかも捨てて、この淀んだ大気に霞む大都市に、骨を埋めることもいいだろう。
東京でも、空はエレクトリックブルーだ。だが加納が追われるように出てきた故郷は、もっと青く美しい。目を閉じるといつでも記憶から呼び出して、あの空を見ることができる。
懐かしくて、胸が痛い。
「今度、わが東党新聞社会部に配属されてきた加納くんだ」
「加納リュウです。まだまだ若輩者ですが、よろしくご指導のほどお願いいたします」
緊張していた。ありきたりのあいさつだが、これで精一杯だ。
加納は追加合格だったので、入社が遅れていた。たった独りだけ、社会部の隅で行なわれたミーティングで紹介された。他の新人たちは三人いて、すでに馴染んでいた。バイトの待遇とは違うし、先輩記者たちの見る目も違っている。こいつはつかえるのか、それともつかえないのか。骨のある奴なのか、ただのボッチャンなのかと品定めしているようだ。
自分自身でも、どこまでプロのジャーナリストたちに食いついていけるかわからない。それでも、ここを目指してきた者たちも数多くいて、彼らの屍の上に自分の入社があるのだから、肝に命じて立派なジャーナリストにならなければならない。加納には、他にも報道を目指す理由があった。
ミーティングが終わって、それぞれが仕事に戻り始めた。部長に手招きされてついてゆく。
「しばらくは先輩記者について、イロハを教えてもらえ」
「さえ、オマエ助手がほしいといっていただろう」
「彼はカメラもできるぞ。新聞社の報道年間大賞を何度も受賞している。君ももう先輩だ。加納を一人前にしてやってくれ」
上川冴子は入社三年目だった。そろそろ一人前として紙面を任されることもある。時期外れの新入社員の入社にも、目を向けず記事の文章構成を練っていた。
「写真が好きでも、いまどき写真だけじゃ使えないわよ。今はデジカメでバカでもいい写真がとれちゃうのよ。すぐに送れるしね。書くほうに専念したほうがいいわよ。ま、頑丈そうだから荷物持ちにはぴったりね」と言った。
「まあ、そういうな」「加納です。よろしくお願いします」
「上川冴子です。よろしく。ほんと。大きいわね。荷物持ちがんばってね」
加納はラガーマンのように背が高くて、座っている冴子をはるか上から見下ろしていた。それが気に食わないらしく、彼女は荷物持ちを強調した。
「あたしは助手がほしいのであって、男がほしいっていったおぼえはありません」
「おう、よければ恋人にしてもいいぞ。年上が好みだそうだ。ちょうどいいぞ」
「冗談はやめてください。あたしは年下は嫌いなの」
神社の林の木に勝手につけた、タイヤを蹴る。サンドバッグ代わりに蹴や拳をいれる。こうして拳や足を鍛えるのだ。本当はスパーリングなどもしたいが、相手がいない。毎日のように道場に通っていた頃がなつかしい。いずれ神主に怒鳴られるだろうが、六年たってもまだ無事だ。
選手権で優勝するなど極められなかったのは、柔道や剣道、古武道など手を広げすぎたせいだろう。一つの武道だけでは安心できなかった。いつも二人の女を守るために、急いでいた。
七時をすぎて思い出した。今日は特別の日だった。初出社の日だったのだ。慌てて階段をかけおり、アパートに戻った。シャワーを浴びて、支度を整える。バブル時代に無理矢理付け足した浴そうなので、五右衛門風呂のように狭かった。加納が発達した長身を入れると、まるで子供の行水だ。
変色し曇った鏡に映った半身は、すでに傷だらけだった。修業でついたものもあるが、ほとんどが十年前のものだ。それは刻印のように、加納の体に刻まれていた。加納への呪いの言葉として、いつまでもそこにあった。
新聞記者になろうとして、通学しながらのジャーナリスト養成学校の夜間部に通っていた。何社か受けて、やっと地方紙の一社に内定をもらった。新聞社はそれなりに競争率が高く、志望者の学歴が高い。どうしても早く決めたくて先輩を回り、教授の推薦をうけたが苦しかった。いつも金欠だったが、ジャーナリスト受験講座にも通った。どこもダメだった悪友たちに言わせると、潜り込んだことになるらしい。もちろんアルバイトで入り込みコネを作っていたことも、功を奏した。どこもダメなら、関連職種で入り込もうと思っていた。就職浪人をしないために、ありとあらゆる手段をとっておいた。アピールできることを数多く作っておいたのが、よかったのだろう。これも努力の結果だ。粘り強い作戦が、勝利をもたらす。
大学を休学して、留学したこともよかったのかもしれない。一年間たっぷりと学んだ。外国人が多い店でもバイトをしていたことがあった。日本人の多い場所だが、ネイティブと数多く話したことはいい経験になった。もともとクニの者たちは留学するものが多い。これは内定に、もっとも強いアピール材料になったはずだ。
そうして勝ち取った新聞社への初出社が、今日だった。アルバイトで金をコツコツと貯め、成人式に買ったスーツを着る。タイは苦しいが、大人になったような気がした。新聞社には初めて出入りをするわけではないが、こうして改めて社会人として自覚すると身が引き締まった。カバンを抱きしめて、ダッシュした。
大学とは反対の方向の通勤ラッシュに飲み込まれながら、東党新聞東京本社へと向かった。窓越しに東京の街を眺めていると、六年前に捨てるように出てきた、故郷のことが脳裏に浮かぶ。東京に来て誰にも故郷のことを話したことがなかった。(あの場所)には残してきたものがたくさんありすぎた。だからこそ、戻ることができない。戻る勇気が必要だった。しかしこうして社会で、独りで生きてゆくために就職をしてみると、時間に追われ、勇気を取り戻すこともおろそかになる。もしかしたら、もう戻ることはないのかもしれない。何もかも捨てて、この淀んだ大気に霞む大都市に、骨を埋めることもいいだろう。
東京でも、空はエレクトリックブルーだ。だが加納が追われるように出てきた故郷は、もっと青く美しい。目を閉じるといつでも記憶から呼び出して、あの空を見ることができる。
懐かしくて、胸が痛い。
「今度、わが東党新聞社会部に配属されてきた加納くんだ」
「加納リュウです。まだまだ若輩者ですが、よろしくご指導のほどお願いいたします」
緊張していた。ありきたりのあいさつだが、これで精一杯だ。
加納は追加合格だったので、入社が遅れていた。たった独りだけ、社会部の隅で行なわれたミーティングで紹介された。他の新人たちは三人いて、すでに馴染んでいた。バイトの待遇とは違うし、先輩記者たちの見る目も違っている。こいつはつかえるのか、それともつかえないのか。骨のある奴なのか、ただのボッチャンなのかと品定めしているようだ。
自分自身でも、どこまでプロのジャーナリストたちに食いついていけるかわからない。それでも、ここを目指してきた者たちも数多くいて、彼らの屍の上に自分の入社があるのだから、肝に命じて立派なジャーナリストにならなければならない。加納には、他にも報道を目指す理由があった。
ミーティングが終わって、それぞれが仕事に戻り始めた。部長に手招きされてついてゆく。
「しばらくは先輩記者について、イロハを教えてもらえ」
「さえ、オマエ助手がほしいといっていただろう」
「彼はカメラもできるぞ。新聞社の報道年間大賞を何度も受賞している。君ももう先輩だ。加納を一人前にしてやってくれ」
上川冴子は入社三年目だった。そろそろ一人前として紙面を任されることもある。時期外れの新入社員の入社にも、目を向けず記事の文章構成を練っていた。
「写真が好きでも、いまどき写真だけじゃ使えないわよ。今はデジカメでバカでもいい写真がとれちゃうのよ。すぐに送れるしね。書くほうに専念したほうがいいわよ。ま、頑丈そうだから荷物持ちにはぴったりね」と言った。
「まあ、そういうな」「加納です。よろしくお願いします」
「上川冴子です。よろしく。ほんと。大きいわね。荷物持ちがんばってね」
加納はラガーマンのように背が高くて、座っている冴子をはるか上から見下ろしていた。それが気に食わないらしく、彼女は荷物持ちを強調した。
「あたしは助手がほしいのであって、男がほしいっていったおぼえはありません」
「おう、よければ恋人にしてもいいぞ。年上が好みだそうだ。ちょうどいいぞ」
「冗談はやめてください。あたしは年下は嫌いなの」
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[★小説「CALLING・神々の追憶」★] カテゴリの最新記事
-
★小説「神々の追憶」★ 12 2011年10月13日
-
★小説「神々の追憶」★ 11 2011年10月13日
-
★小説「神々の追憶」★ 10 2011年10月13日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.