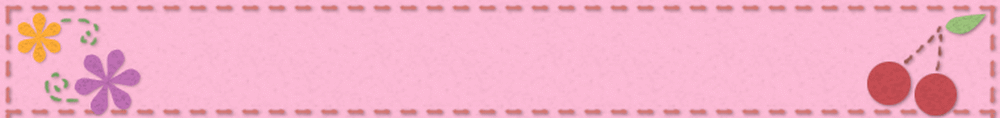PR
X
カテゴリ: ★小説「CALLING・神々の追憶」★
彼女はもうここに十年住んでいると聞いたことがある。加納が上京してから五年以上住んでいるから、かなりの年齢のはずだ。女性に年齢は聞けないので、今でも年齢不詳だった。出勤はもちろん夜なので、昼間はノーメイクだ。それなりの年なのでさすがにスッピンは見るに絶えないが、いったん彼女がメイクをしたらプロの女の本領を発揮する。出勤時には二時間もかけたメイクと、派手な衣裳で出かけてゆく。
加納が、女の魔力を思い知るのはこんなときだ。派手なメイクの女とつきあったことのない加納には、「魔女のご出勤」に思えた。
加納の予感どおり、彼の顔を見るなり肘をつかんだ。
「どうしてうちの店に来てくれないの」「金がなくて」
「加納くんなら、あたしもちでいいわよ。でも就職できたらしいって、大家さんがいってたわよ。だったら一度くらい来られるでしょ」
「まだ仕事を覚えるのが精一杯で、酒を飲むほどの余裕がないんです」
南川の髪には、カーラーがまだついていた。夜の仕事なので、ゴミを出したらまた寝るらしい。いぜん夜の間にゴミ出しをして、大家に怒鳴り込まれたという。しかし贅沢な世の中にあって古家は借り手が少ないので、大家もそれほどうるさくなくなったらしいが、水商売の女はと言われたくないから、やめたと言った。そういうことをいちいち隣の加納に話してくる。よほど気を許せる相手がいないのだろうかと、加納は思った。パトロンも恋人も、彼女にとっては油断のならないものなのだろうか。
ここにいると、そんな人間観察も趣味になってしまう。同じアパートには、大学を出ていつまでも作家になる夢を見ていた男がいて、とうとう半年前に餓死した。就職後であれば、助けてやったのにと思うが、交際はなかった。東京ではこんな住人もめずらしくはない。
このホステスも最初の頃は羽振りもよく、毛皮を自慢げに着ていたが、最近は売れっ子ではなくなったのか、安物のスーツを着て出てゆくようになった。彼女が勝手に話しだしたのだが、他にソープにもいっているらしい。この先クラブをクビになったら、ストリップ行きかもしれないと言っていた。ソープならおばさんでもいいかしらときかれたので、さあといった。
風俗は友人たちほど詳しくはなかった。ホテトルとかキャバクラとか、そんなカタカナ語くらいは知っている。ジャーナリストとなれば、くらい経験していなくてはならないのだろうか。取材に行くのは勇気がいる。週刊誌のライターでないのだから、関わりたくはない。
「一度でいいから、上司や同僚の皆さんと来てよ。同じ屋根の下の住人として」
確かにアパートであっても、同じ屋根の下に住んでいた。それでも義務はないだろうと思った。
南川さくらは、過剰にエロスを吐き出す突き出た下唇を、しきりに動かしている。色気のありすぎる商売女は苦手だ。差別ではない、女の強引さが、男として苦手なだけだった。
みつかるたびに抱きつかれ、彼女はなかなか離れない。ただああいう場所が苦手なだけだ。女性を相手に酒を飲まなくても、ストレスは発散できる。早朝に近くの神社まで走ることで、十分だ。それに女に関わる悪夢は、これ以上増やしたくはなかった。
「すいません。遅刻しますから」といって振りはらう。
勇気がいったが、強引な誘いには強引さで返す方がいい。どうせ彼女は、男のあしらいにも慣れているだろうと思った。電話番号も教えてくれと言われたが、電話はないといって逃げてきた。今は携帯を持っているが、教えたくない。きっと電話での誘いに、夜ごと悩まされることになるだろうから。
五十をすぎた大家の小林俊子も出てきていた。彼女も大仏ヘアを維持するために、古いタイプのカーラーをまいている。たぶん数十年愛用しているものだろう。
小林俊子は足が不自由で、いつも杖をついている。それなのにひったくりを捕まえて、虎の子を奪い返したことがあると自慢していた。不自由な足のコンプレックスを補うためか、口はだれよりもよりもかしましい。土曜にでもつかまれば、一時間は武勇伝を聞かされるのだ。一週間の出来事や留学中の子供のこと、夕食の献立までどうしようかと尋ねられるから、加納は世界で一番会いたくない女性だと思っていた。
彼女は、ホステスともめている加納の声を聞いて出てきた。毎日きちんと出勤しているのか確かめているようだ。プー太郎では家賃が心配なのだ。両肩に二つのバッグをさげた加納を、つま先から頭の先まで観察している。
「最近ずっとカジュアルなのね。本当に就職したの? 背広来てたの入社の日だけじゃない」
いつもこんな調子で加納を問い詰めるのだから、たまったものではない。
加納はいつも笑ってごまかす。年配の女はしつこいので、相手をするのは辛いのだ。
スーパーで買った安価なシャツと、小物がいくつでもしまえるベストに、ジーンズという学生のような格好だ。靴でさえ、スーパーの出店で買ったものだから安っぽい。どこかのブランドに似たマークがついている。
靴の強盗でさえあったほどだから、中学生でもブランドもののスポーツシューズを持っている時代だ。それほど彼の持ち物は、一目で安物とわかるものばかりだ。もしかするといまどきの大学生の方が、いいものを着ているのかもしれない。
本当は新聞記者とは、いつも背広で正装していなければならないのかもしれないが、一着しか持っていないし誰も何も言わないので、加納はしばらくこのままで通すつもりだった。
「新聞社に就職できました。毎日出社しています。家賃もちゃんと毎月払えますから、大丈夫ですよ」
そういうとカーラーをつけた頭を揺すって、未亡人の大家は安心したよといった顔をした。
「ま、そういうことなら。希望のところに、就職が決まって本当によかったわね」
これは本音半分だった。大家の小林俊子は夫の残してくれた唯一の財産であるアパートを、生活費として頼っている。無職なので、あとは少ない国民年金だけらしい。死亡保険金も借金の返済と子供の教育費に、使ってしまったと言っていた。遺族年金もないので、アパートの家賃と障害者年金だけが彼女の生活を支えていた。だから、加納の安定した収入によって借り手が減らないという事実の方が、彼の就職よりも本当は嬉しい事なのだ。
そんなことを、なんとなく加納は察していて、月々の家賃を口座振替に切り替えた。今まではバイトを理由にして、なんとか引き伸ばしてきた。月末になれば家賃が振込まれた通帳の数字を見て、俊子は安堵することだろう。あとは新聞社をクビにならないように、冴子について行って頑張るだけだ。
加納は、取材用の器材と最低限の着替えだけを持って、羽田に向かった。
死神たちはやってきた。
遥か彼方の大陸から、十二時間もかけ、乗り継ぎをしながらやってきた。もちろん遊びに来たわけではない。使命を持ってやってきたのだ。高額の報酬がかかった仕事だ。失敗は許されない。もちろん失敗などするわけがない。彼らは一流の刺客だ。暗殺、誘拐なんでもやる。そうしてすでに大金持ちだ。銀行の秘密口座には財産がたっぷりとあるが、仕事をやり遂げた後の達成感が、彼らの引退を引き止めていた。猟犬のようにターゲットを仕留めたとき、彼らの至福がやってくる。
依頼人の男も、いずれ来ると言っていた。
俺たちの仕事を見届けるためらしい。よほど、あの男が生きていると困るのだろう。確実に、すばやく処理することを望んでいる。こっちがあいつのターゲットにならなくてよかった。あいつは、手段を選ばない冷酷な男だ。
殺しのワケは聞いていない。殺し屋はつまらないことは聞かないものだ。プロはプロとして、金で動く。
かわいそうなのはあの男。おれたちが殺しにくるとも知らずに、のん気に生きているのだろうか。一杯やって、陽気に歌ってるのだろうか。
依頼人は東京で殺せといっていたが、急きょ変更になった。
ターゲットを追いかけろと司令が来た。
死神たちは、目的地へ着くと昔の仲間に連絡を取った。蛇の道は蛇。世界には金のためなら、何でもする男たちがいる。案内されてそこへゆくと、頼んでいたものが用意されていた。
場所は怪しげな倉庫だった。倉庫の奥は洞窟になっている。
そこには、ホコリをかぶった箱が置いてあり、仲間は箱を開けた。
中をのぞくと、鈍く光るものがたっぷりとあった。依頼どおりのものだった。依頼人が用意してきたが、素人相手に大げさだ。プロが本気になれば、すぐに片付く。自殺、事故死、何にでも見せかけることができる。
死神は手に取ると、ひさしぶりの感触を味わった。ずっしりとした重み、愛しいまでの手応え。まるで愛人だ。
これでいい。これで。必要なものは手に入った。早くこれを思いっきりぶっ放したい。
もちろんそれは最終手段だ。それまでに片づけば使うことはない。
待っていろ。俺たちがいくまで、夢を見ているがいい。
男たちは静かにヘッドフォンを耳にあてた。(愛人)を奥の洞窟に向ける。人々が教会でひざまずくように、彼らにはこれがおごそかな儀式なのだ。だからたとえクライアントであろうと、この儀式を邪魔することは許さない。
そこには、即席で作られたマトがあった。あうんの呼吸で、誰かれともなく撃ち始めた。
大爆音が、響き渡る。数秒でマトは蜂の巣のようになった。
今度は最新式のマシンガンを取り出した。相手はただの日本人だ。これほどのものは必要ないだろう。警察や自衛隊を相手にするわけではない。しかし(愛人)を撃ちまくりたいという衝動が、彼らを突き動かしていた。
「マシンガンはやりすぎだぞ」
「ウージーだ。久しぶりにぶっ放したいのさ。傭兵時代の血がうずく」
GOOOOOOONN!
みごとな穴が空いた。人工の鍾乳洞の出来上がりだ。巨大な悪魔の口だ。ブラックホールだ。一気に飲み込まれてしまいそうだ。だがこの男たちは、こんなことでは震えはしない。彼らはプロフェッショナルだった。人をこの世から消すことで糧を得てきた。殺しには快感を覚える。人殺しは最高だ。一人消すたびに、脳内に快楽物質が分泌される。それが彼らだった。
「フィリピンで合宿して以来の快感だ。最高だ」
マシンガンを撃つのは半年ぶりだが、腕は落ちてはいない。完璧だ。あとはターゲットを追うだけだ。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[★小説「CALLING・神々の追憶」★] カテゴリの最新記事
-
★小説「神々の追憶」★ 12 2011年10月13日
-
★小説「神々の追憶」★ 11 2011年10月13日
-
★小説「神々の追憶」★ 10 2011年10月13日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.