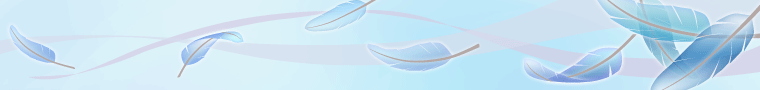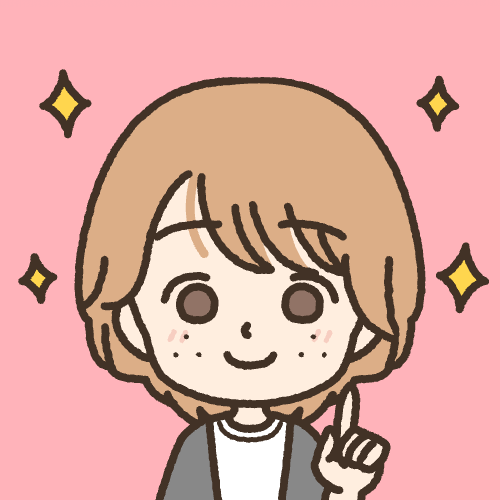フリーページ
全て
| 家計管理:家計ダイエットな日々
| 本 か行
| 映画 か行
| 映画 た行
| 映画 ら行
| 映画 さ行
| 映画 あ行
| 本 さ行
| 映画 は行
| 本 な行
| 本 あ行
| 本 た行
| 本 は行
| 本 ま行
| 本 ら行
| 本 や行
| 本 わ行
| 映画 わ行
| 映画 な行
| 映画 ま行
| 映画 や行
| 楽天ROOM
| ダイエット
テーマ: 読書(8214)
カテゴリ: 本 あ行
今日の読書は、2020年度137冊目
❤何に答えを出すべきなのかについてブレることなく活動に取り組むことがカギ。
❤知的な生産活動の目的地となるものがイシュー
❤悩む=答えが出ないという前提のもとに、考えるフリをすること
考える=答えが出るという前提のもとに、建設的に考えを組み立てること
❤10分以上真剣に考えて埒が明かないのであれば、そのことについて考えることは一度やめたほうがいい。
❤イシュー度の低い問題にどれだけたくさん取り組んで必死に解を出したところで、最終的なバリューは上がらす、疲弊していくだけだ
❤イシューを見極める:何に答えを出す必要があるのか、そのためには何を明らかにする必要があるのか、という流れで分析を設計する
❤相談相手をもつ:この人は、という人を論文、記事、書籍らあるいはブログなどで見つけたら思い切って面会や相談を申し込む。研究所やシンクタンクのような機関にも話を聞ける専門家は多いりこういう知恵袋的な人をもてるかどうかが、突出した人とそう出ない人の顕著な差を生む
❤仮説を立てる
1.どうなっているか?ではなく、縮小に入りつつあるのではないか?と仮説を立てることで、答えをだし得るイシューになる
2.必要な情報、分析すべきことがわかる
3.分析結果の解釈が明確になる。仮説を立てて仕事を与えられれば、仕事を振られた人も自分が何をどこまて調べるべきなのかが明確になる。答えを出すべきイシューを仮説を含めて明確にすることで、ムダな作業が大きく減る。つまり生産性が上がる
❤言葉にする:イシューを言葉で表現することで、自分がそのイシューをどのようにとらえているのか、何と何についての分岐点をはっきりさせようとしているのか、が明確になる。言葉で表現しないと、自分だけでなくチームのなかでと誤解が生まれ、それが結果として大きなズレやムダを生む
❤イシューと仮説は紙や電子ファイルに言葉として表現する。言葉に出来ないのは、イシューの見極めと仮説の立て方が甘いから。言葉にするときに詰まる部分こそイシューとしても詰まっていない部分。
❤言葉で表現するときのポイント
▶️主語と動詞を入れる
▶️WHERE:どちらか?どこを目指すべきか?
What:何を行うべきか?何を避けるべきか?
How:どう行うべきか?どう進めるべきか?
▶️AではなくむしろBと、比較表現を入れる
❤よいイシューの3条件
1.本質的な選択肢である
2.深い仮説がある
3答えを出せる
❤考えるための材料を入手する(可能なら2.3日で終える)
1.一次情報に触れる
2.基本情報をスキャンする(調べる)
数字、問題意識、フレームワーク
3.集め過ぎない、知り過ぎない
❤イシューが見つからないときのアプローチ
1.変数を削る:いくつかの要素を固定して、考えるべき変数を削り、見極めのポイントを整理する
2.視覚化する:問題の構造を視覚化、図示化し、答えを出すべきポイントを整理する
3.最終形からたどる:すべての課題が解決したときを想定し、現在見えている姿からギャップを整理する
・現在の事業の状況(市場視点、競合視点)
・事業はどのような姿を目指すべきか
・3~5年後の目的関数をどう置くか(相対的地位を守るか、市場を活性化するかなど)
・そのときの強み、自社らしい勝ちパターンをどう考えるか
・それは数値的にどう表現できるか
4.so What?を繰り返す:だから何?という問いかけを繰り返し、仮説を深める
5.極端な事例を考える:極端な事例をいくつか考えることでカギとなるイシューを探る
❤事業コンセプトの枠組み
事業コンセプト:何について考えると、事業機会について考えたことになるか=事業の核となるコンセプトに必要なものは何か
⇩
狙うべき市場ニーズWHERE:(どのような市場の固まり、ニーズを狙うか。どのようなセグメントに分かれ、どのような動きがあるか、時代的に留意すべきことはあるか、具体的にどの市場ニーズを狙うべきか)
×
事業モデルWhat&How(どのような事業のしくみで価値提供を行い、事業を継続的に成り立たせるか、バリューチェーンの立ち位置はどこに置くか、どこで顧客を引き寄せるか、どこで儲けるか(収益の源泉))
❤3C:顧客、競合、自社
❤神経質系の特徴
1.閾値を超えない入力は意味を生まない。ある強さを超えると急に感じはれるようになり、あるレベルを割り込むと急に感じられなくなる
2.不連続な差しか認知出来ない。
3.理解するとは情報をつなぐこと
4.情報をつなぎ続けることが記憶に変わる
❤ひとつ、聞き手は完全に無知だと思え、ひとつ、聞き手は高度の知性をもつと想定せよ
❤ストーリーラインを磨く3つのプロセス
1.論理構造を確認する:すっきりとした基本構造で整理できているか、前提が崩れていないか
2.流れを磨く:流れが悪いところはないか、締まりの悪いところはないか、補強が足りないところなないか
3.エレベータテストに備える:結論を端的に説明できるか、特定の部分について速やかに説明できるか
❤優れたチャートの3条件
1.1チャート・1メッセージを徹底する:何を言うかとともに、何を言わないかも大切。人がチャートを見て、わかる、意味があると判断するまでの時間は、15秒。どんな説明もこれ以上できないほど簡単にしろ。それでも人はわからないと言うものだ。そして自分が理解できなければ、それを作った人間のことをバカだと思うものだ。人は決して自分の頭が悪いなんて思わない
2.タテとヨコの比較軸を磨く
3.メッセージと分析表現を揃える
❤毎日の仕事、研究の中で、この作業って本当に意味があるのか?と思ったら立ち止まってみよう、そして、それは本当にイシューなのか?と問いかけることから始めよう

イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」 [ 安宅和人 ]
❤何に答えを出すべきなのかについてブレることなく活動に取り組むことがカギ。
❤知的な生産活動の目的地となるものがイシュー
❤悩む=答えが出ないという前提のもとに、考えるフリをすること
考える=答えが出るという前提のもとに、建設的に考えを組み立てること
❤10分以上真剣に考えて埒が明かないのであれば、そのことについて考えることは一度やめたほうがいい。
❤イシュー度の低い問題にどれだけたくさん取り組んで必死に解を出したところで、最終的なバリューは上がらす、疲弊していくだけだ
❤イシューを見極める:何に答えを出す必要があるのか、そのためには何を明らかにする必要があるのか、という流れで分析を設計する
❤相談相手をもつ:この人は、という人を論文、記事、書籍らあるいはブログなどで見つけたら思い切って面会や相談を申し込む。研究所やシンクタンクのような機関にも話を聞ける専門家は多いりこういう知恵袋的な人をもてるかどうかが、突出した人とそう出ない人の顕著な差を生む
❤仮説を立てる
1.どうなっているか?ではなく、縮小に入りつつあるのではないか?と仮説を立てることで、答えをだし得るイシューになる
2.必要な情報、分析すべきことがわかる
3.分析結果の解釈が明確になる。仮説を立てて仕事を与えられれば、仕事を振られた人も自分が何をどこまて調べるべきなのかが明確になる。答えを出すべきイシューを仮説を含めて明確にすることで、ムダな作業が大きく減る。つまり生産性が上がる
❤言葉にする:イシューを言葉で表現することで、自分がそのイシューをどのようにとらえているのか、何と何についての分岐点をはっきりさせようとしているのか、が明確になる。言葉で表現しないと、自分だけでなくチームのなかでと誤解が生まれ、それが結果として大きなズレやムダを生む
❤イシューと仮説は紙や電子ファイルに言葉として表現する。言葉に出来ないのは、イシューの見極めと仮説の立て方が甘いから。言葉にするときに詰まる部分こそイシューとしても詰まっていない部分。
❤言葉で表現するときのポイント
▶️主語と動詞を入れる
▶️WHERE:どちらか?どこを目指すべきか?
What:何を行うべきか?何を避けるべきか?
How:どう行うべきか?どう進めるべきか?
▶️AではなくむしろBと、比較表現を入れる
❤よいイシューの3条件
1.本質的な選択肢である
2.深い仮説がある
3答えを出せる
❤考えるための材料を入手する(可能なら2.3日で終える)
1.一次情報に触れる
2.基本情報をスキャンする(調べる)
数字、問題意識、フレームワーク
3.集め過ぎない、知り過ぎない
❤イシューが見つからないときのアプローチ
1.変数を削る:いくつかの要素を固定して、考えるべき変数を削り、見極めのポイントを整理する
2.視覚化する:問題の構造を視覚化、図示化し、答えを出すべきポイントを整理する
3.最終形からたどる:すべての課題が解決したときを想定し、現在見えている姿からギャップを整理する
・現在の事業の状況(市場視点、競合視点)
・事業はどのような姿を目指すべきか
・3~5年後の目的関数をどう置くか(相対的地位を守るか、市場を活性化するかなど)
・そのときの強み、自社らしい勝ちパターンをどう考えるか
・それは数値的にどう表現できるか
4.so What?を繰り返す:だから何?という問いかけを繰り返し、仮説を深める
5.極端な事例を考える:極端な事例をいくつか考えることでカギとなるイシューを探る
❤事業コンセプトの枠組み
事業コンセプト:何について考えると、事業機会について考えたことになるか=事業の核となるコンセプトに必要なものは何か
⇩
狙うべき市場ニーズWHERE:(どのような市場の固まり、ニーズを狙うか。どのようなセグメントに分かれ、どのような動きがあるか、時代的に留意すべきことはあるか、具体的にどの市場ニーズを狙うべきか)
×
事業モデルWhat&How(どのような事業のしくみで価値提供を行い、事業を継続的に成り立たせるか、バリューチェーンの立ち位置はどこに置くか、どこで顧客を引き寄せるか、どこで儲けるか(収益の源泉))
❤3C:顧客、競合、自社
❤神経質系の特徴
1.閾値を超えない入力は意味を生まない。ある強さを超えると急に感じはれるようになり、あるレベルを割り込むと急に感じられなくなる
2.不連続な差しか認知出来ない。
3.理解するとは情報をつなぐこと
4.情報をつなぎ続けることが記憶に変わる
❤ひとつ、聞き手は完全に無知だと思え、ひとつ、聞き手は高度の知性をもつと想定せよ
❤ストーリーラインを磨く3つのプロセス
1.論理構造を確認する:すっきりとした基本構造で整理できているか、前提が崩れていないか
2.流れを磨く:流れが悪いところはないか、締まりの悪いところはないか、補強が足りないところなないか
3.エレベータテストに備える:結論を端的に説明できるか、特定の部分について速やかに説明できるか
❤優れたチャートの3条件
1.1チャート・1メッセージを徹底する:何を言うかとともに、何を言わないかも大切。人がチャートを見て、わかる、意味があると判断するまでの時間は、15秒。どんな説明もこれ以上できないほど簡単にしろ。それでも人はわからないと言うものだ。そして自分が理解できなければ、それを作った人間のことをバカだと思うものだ。人は決して自分の頭が悪いなんて思わない
2.タテとヨコの比較軸を磨く
3.メッセージと分析表現を揃える
❤毎日の仕事、研究の中で、この作業って本当に意味があるのか?と思ったら立ち止まってみよう、そして、それは本当にイシューなのか?と問いかけることから始めよう

イシューからはじめよ 知的生産の「シンプルな本質」 [ 安宅和人 ]
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[本 あ行] カテゴリの最新記事
-
お金持ちになれる黄金の羽根の拾い方 2024年03月24日
-
穏やかに生きる術 2024年03月03日
-
インナーゲーム 2024年02月28日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.