砂漠の果て(第17部「霊感」)

アルブラートは、マーディのジープの助手席に乗り込んだ。マーディは、興味深そうに、黒いスーツを着た彼を眺めた。
「あんたは街の人間かい。俺はリビア出身でな、10年前からこの仕事をしている。だがあんたみたいな若僧が、そんな結構な身なりをして、砂漠のオアシスまで行くたぁ、初めてのこった。大抵の客は、もっとラフな格好で、物珍しい冒険を楽しみたくって、サハラ横断をしたがるんだ」
「俺は冒険や探検のためじゃない。人を探しに行くだけだ」
「へへぇ、そうかい。ますます奇妙な話だな。俺は昔はカイロでトラックの運転手をしてたがな、そういや、あんたの言葉は訛りがあるな。立派な旅行客なのに、ホテルのフロントで軒並み相手にされていなかったじゃねぇか」
アルブラートは、ムカールの幻の言葉を信じ、アイシャに会いたい一心で、他のアラブ人には自分のパレスチナ方言で話しかけまいとしてきたことを、すっかり忘れていたのだった。
「マルサー・マトルーフのホテルには、毎日サハラ案内のジープを尋ねる客が必ずいるんでな、するとフロント係の連中は、『サハラに行くならマーディに頼め』って教えるんだ。変なこった。あんたはもしかして、パレスチナ人かい」
「......ああ―そうさ。その通りだ」
マーディは、ジープを発車させると、すぐに街から郊外へと抜け、しばらく舗装されていない道をガタガタと走り続けた。15分もすると、急に左にカーブし、高い岩壁に挟まれた細い道に入っていった。
「そうか、パレスチナ人か。俺ぁ、パレスチナ人をサハラ案内するなんて初めてだぜ。大抵のパレスチナ人の若僧は、マルサー・マトルーフから、エジプト軍基地に向かって、ゲリラ部隊に入る奴ばかりだ。そら、こないだのカイロでのテロ事件も、パレスチナ人が主犯だったもんな」
アルブラートはマーディの日焼けした黒い横顔を眺めていたが、視線を道路に落とすと、呟くように答えた。
「―パレスチナ人が皆ゲリラ部隊に入るわけじゃない......
俺はそんな奴らと違う。俺は―そのテロ事件で、妻を亡くしたんだ」
マーディはびっくりしたように、アルブラートを見た。
「へっ!冗談はよせやぃ。あんた、まだ17かそこらだろ?」
「17じゃない。この間、21歳になったんだ。生後半年の息子もいる―妻は、幼なじみで―17で息子を産んで......17歳で死んだんだ」
「そうかい、そんな若くして結婚して、奥さんは死んじまったのかい―気の毒なこったな。でもまあ、あんたは実際の年より若く見えるから、ついてるぜ。そのうち、また奥さんになる娘っ子がいるさ、あんたはいい男ぶりだからな」
アルブラートは、そう言われても、もう二度と結婚などしないと思った。アイシャ以上に愛せる女性がいるわけがない、どんなに美しい人でも、もう一生涯、女性を愛することはないだろう―そう確信してやまなかった。
気がつくと、ジープはもう砂漠の中を走っていた。砂埃が辺りに立ち込める中で、彼は地平線の彼方に眼を凝らした。朝日が眩しく、無限に広がる荒野一帯を光で満たしていた。走り続けるジープ以外、何もない光景に、アルブラートは人生が無であり、苦しみと死以外は有り得ないと感じた。
「どうだ、砂漠を走っていると、どうして神様ってのは、こんなものを造ったんだって思わないかい。こりゃ、この世の景色じゃねえってな―天国も地獄もねえって気分さ、なあ。まあ、あんたはこう言っちゃ何だがな、砂漠を全く知らねえわけじゃないんだろ?」
アルブラートはマーディをちらりと見やると、しばらく黙っていた。彼の脳裏に、死海を前にした崩れかけた掘っ立て小屋、ユダ砂漠の風をオリーブの香りと共に吸い込んだアシュザフィーラでの生活、12歳の時の辛かった砂漠越えや、砂漠に囲まれたアルジュブラ難民キャンプのオアシスの緑と美しい神殿の遺跡などが次々と浮かんでは、漂うように消えていった。
「......俺はずっと難民だったんだ―物心ついた時には、もう難民だった―いつも貧しくて、腹ぺこで、裸足で―ずっと砂漠のそばのキャンプで育ったんだ......でも、裕福な暮らしなど知らなかったから、それが当たり前だと思ってたんだ―」
「そうか。じゃあ、砂漠をもう見たくないんじゃねえのかい。今は金持ちで、いい生活してるんだろ。シーワ・オアシスに人探しって、一体誰を探してるんだ?」
「......アイシャだよ―死んだ妻を探しているんだ―彼女は赤い服を着たまま焼死したんだ......遊牧民の『青い男』たちが、サハラの蜃気楼に赤い服の女の幻が現われると噂している―そう街で聞いたんだ」
マーディは不思議そうにアルブラートを見つめると、頭を振りながら、溜息をついた。時刻はもう10時を回っていた。彼は、一旦ジープを止めると、ポケットから水筒を取り出し、アルブラートに飲めと勧めた。マトルーフを出発した時は涼しかったが、今では太陽が照りつけ、相当な暑さだった。喉の渇きを覚えていたアルブラートには、水筒の水が最高においしかった。
マーディは、煙草をふかしながら、ここで10分休憩すると言った。
「あんたは面白い人だな。死んだ奥さんを探しに、こんな砂漠まで来たってのかい。そりゃ、最近『青い男』どもは、そんな噂をしている。まぁ、実際に見たから噂になるんだ。でもその女の幻が、あんたの奥さんだなんて証拠はないんだろ?」
「......そりゃ証拠はないさ―でも―2年前に亡くなった俺の友人が、昨夜部屋に姿を現わして......『蜃気楼に現われる赤い服の女はアイシャだ』と言うのを確かに聞いたんだ......」
「ははぁ、あんたはますます変わった人だぜ。夢や幻のようなことばかり信じるんだな。でもまあな、死んだ奥さんにもう一度会いたいってぇ気持ちは、分からんでもないな」
マーディは、気の毒そうな顔で若い客を眺めていたが、再び煙草をふかしながら、地平線を見やった。彼は、ジープからやや離れた所の地面を指差した。
「ほらな、ありゃあ、駱駝の足跡だ。ずうっと向こうまで続いているのが見える。あそこは、トゥアレグ族の隊商路だ。ジープがあの上を走ったりしたら、ブルキナ族の襲撃を受ける」
「ブルキナ?」
「トゥアレグ族の中で一番凶悪な奴らさ。でも俺がいつもサハラ案内の許可をもらうのは、サヘール族の連中だ。サヘール族のシェリフは、なかなかの知識人でな、温厚な人だ。もうすぐ、サヘールのル・ラフがあそこの井戸にやってくる。俺は毎日、ル・ラフから許可をもらうんだ―そら、来た来た」
地平線の彼方から、青いターバンと衣服に身を包んだ男が、駱駝に乗って、だんだんこちらの方に近づいてきた。男は、井戸の前で駱駝を止めると、皮製の長く大きな水筒に、水をたっぷり汲んだ。水をぐっと口にふくみ、飲み干すと、男はマーディの方をちらりと見て、手を上げた。
マーディは青い男の方にジープを走らせ、すぐに停車すると、親しそうに何か話し始めた。その言葉は、アルブラートには全く理解できなかった。
だが、男は駱駝を降りると、今度はアルブラートの方に近づいてきた。アルブラートはその遊牧民の男の肌までもが、青いのを見て驚いた。男は、ちゃんとしたアラビア語で、アルブラートに話しかけてきた。
「俺はル・ラフだ。蜃気楼の中の女の幻をお前は見たいそうだな。太陽が空の中央に昇った時、砂漠は一番暑くなる。オアシスに着いたら、その蜃気楼が立つ所に、俺が連れてってやってもいい。だが、女の幻を見ても、絶対に話しかけないことだ。なぜか、分かるか」
アルブラートは、黙って首を振った。
「その女は、冥界からこの砂漠にさ迷いこんで来た。冥界の者が、蜃気楼の中に立つと、その周辺に流砂が発生する。蜃気楼の幻は、きっとお前に近寄ったり、遠ざかったりするだろう。するとますます流砂が拡がっていく。女の霊は、その流砂にお前を引きずり込んで、あの世に連れて行こうとする。危険な女だ。いいか、絶対にその幻に近づくな」
ル・ラフはそう言ったかと思うと、駱駝にひらりと飛び乗り、駱駝の横腹を足で蹴り、オアシスへと先に向かって行った。マーディは、ル・ラフからサハラ横断の許可を得たし、後はもう1時間弱でシーワに着くと笑い、ホッとした様子だった。
「シーワは案外大きな町だ。ホテルは2軒しかないがな。1泊1ポンドで済むぜ。まずホテルに俺が案内するから、あんたは食事をしたら、そのお堅いスーツをガラベーヤ* に着替えるこった。着替えたら、俺の部屋まで来てくれ。ル・ラフがホテルの外で待ってるから、そいつに蜃気楼の場所まで連れてってもらいな」
2人を乗せたジープは、ガタガタと揺れながら、岩石や砂丘の間を走り始めた。シーワに着いたのは、もう11時半を過ぎていた。マーディは、石や泥で固めた茶色の家々が建ち並ぶ町へと入り、あるホテルの前で止まった。
「こっちのホテルの方が、あんたには向いてるな。でも、まぁ、カイロのホテルのような立派な設備を期待するなよ」
アルブラートは、チェックインすると、マーディの隣の部屋に入った。粗末な土壁でできたこじんまりした部屋であり、古ぼけたベッドと小さな木製のテーブルしかなかった。
彼は、あらかじめフロントで頼んだ食事を部屋に運ばせた。ベルベル人の中年の女性が、ケバーブとシャーイ(茶)を運んできた。メイドは、ベッドの片隅にある壁にかかっている、ガラベーヤを指差し、サンダルも下にあると言って出て行った。
* ガラベーヤ:イスラム圏で男性が身につける長衣。
空腹だったアルブラートは、その羊の串刺しにむしゃぶりつき、お茶をゆっくりすすった。裕福な暮らしに慣れていた彼だったが、砂漠を4時間近くジープに揺られてきた身には、このケバーブがおいしくてたまらなかった。
食事が済むと、彼はガラベーヤに着替え、サンダルをはいた。ベッドの上には、日除け用の白いターバンが折り畳んであった。彼は、ターバンを巻き、余った部分は首から肩にかけた。マーディの部屋に入ると、案内人はアルブラートの変身ぶりに感嘆した様子だった。
「ははぁ、あんたは都会暮らしに慣れた、しゃれた風采をしてたが、その格好を見ると、やっぱりアラブだな―あんたは一見、外国育ちの金持ちの若旦那に見えるが、こうやって見たら、あんたの目はやっぱり違うな。野生的で砂漠にピッタリの顔立ちじゃねえかい―それだったら、ル・ラフはあんたを心底信用するし、きっと後で、イブン・アブドゥルカリームのテントに招待されるぜ。楽しみにしてな」
「アブドゥルカリーム?」
「サヘール族のシェリフさ。あんたに負けず劣らず、立派な男前の奴だ。女房を3人抱えているし、子供は10人いる。でも一番可愛がっている女房は、一番若いラティカって踊り子だ。その女の踊りもきっと見せてもらえるぜ」
二人はホテルの外に出た。町の入り口まで行くと、座らせた駱駝に寄りかかって、ル・ラフが水煙草を吸っていた。男は、アルブラートを指差すと、駱駝に乗るよう合図した。ル・ラフの手は、指先までもが青かった。
「マーディはホテルで待っていろ。駱駝に乗せるのはこいつ一人だ。お前は駱駝に乗ったことがあるか」
「いいや、ない」
するとル・ラフは笑い、駱駝の瘤につかまって跨れと教えた。アルブラートが言われた通りにすると、男は鋭い眼を細めて、やや親しげに言った。
「お前はその格好だと、俺たちと同じバダウィ* に見える。しかも部族の中では一等級の若者みたいだな。サヘール族は一番貴い血筋を2千年前から守ってきた。お前はその血筋を受け継いだ貴人の中の貴人のようだな」
アルブラートは、アラブのことを忘れたいと願っていたのにも関わらず、街の噂とムカールの言葉に導かれて、こうして砂漠のオアシスまで来てしまい、しかも遊牧民と同じ格好をしている自分が信じ難かった。だが、その格好をして砂漠で駱駝に乗ることに、全く抵抗感はなかった。
アルブラートの乗った駱駝がゆっくり立ち上がると、ル・ラフはもう1頭の駱駝に乗った。2頭の駱駝は縄で結ばれていた。ル・ラフは自分の駱駝を歩かせながら、アルブラートを誘導して行った。
町から砂漠へと20分ほど歩いた頃、ル・ラフは駱駝の歩を止めた。太陽はちょうど頭上で凄まじい熱を放っていた。
「肩に垂らしたターバンで口を覆うんだ。少しは熱さがしのげるだろう。ほら、あっちを見ろ―蜃気楼が立ち始めている」
男の指差す方向を見ると、地平線の辺りに、ゆらゆらと蜃気楼が揺れているのが見えた。アルブラートがじっと視線を注いでいると、どこからか美しい歌声が聞こえて来た。それは懐かしい、アイシャの歌声だった。歌声は、蜃気楼から1キロ離れた場所に立つ、彼の所まで朗々と響いてきた。
徐々に、蜃気楼の中に、人の姿らしき形が現われ始めた。それは間もなく、赤い服を着た女性の姿となって、宙に浮かび上がった。
アイシャ......!あれはやっぱりアイシャじゃないか......!ああアイシャ......もはや人間ではない―この世をさ迷う魂になってしまったのか......
アルブラートが心の中で、彼女に呼びかけていると、急に蜃気楼の幻は、彼の方へと急接近してきた。アルブラートはその女性の顔を見た。間違いなく、ハネムーンの時に着た赤い服を身につけたアイシャだった。
彼女は悲しそうな表情で、彼を見つめた。二人の視線がぴったり合った。すると、周囲の砂が鈍い音を立て、渦を巻き始めた。彼の乗った駱駝は、突然起きた流砂に怯え、その場を離れようとしたが、もう既に、前足が両方とも流砂の中にぐいぐいと引き込まれていた。
ル・ラフは急いで2頭を繋いでいた縄を引きちぎると、自分の駱駝から飛び降り、駱駝と共に流砂に落ち込みかかっていたアルブラートに縄を投げて、捕まれと叫んだ。男は物凄い力でアルブラートを引っ張り上げ、流砂から数メートル離れた所に彼を放り投げた。
アルブラートは、自分の目の前で、1頭の駱駝が流砂に飲み込まれて行く恐ろしさに震え上がった。駱駝はとうとう、地面の底に姿を消した。彼は尚も震えていたが、最後にアイシャの声を聞いた。
「私を忘れたいのね、ムラート......
あなたが苦しいのなら、もう私を忘れていいわ......どうか忘れて......
私の心はアリの中に生き続けるのだから......」
* バダウィ(Badawi): アラブ系遊牧民ベドウィン(Bedowin) のアラビア語読み。

アイシャの幻は、蜃気楼に包まれたまま、その言葉を最後に、再び地平線の彼方へと去って行った。同時に、流砂も消え去り、元の砂丘に戻った。ル・ラフはアルブラートに近寄り、自分の駱駝に乗せようと彼の腕を掴んだ。だがアルブラートは、腰を抜かしたまま、立ち上がれなかった。
「お前は俺の言いつけ通り、あの女に話しかけなかったな。それなのに、あの幻は流砂を起こして、お前を地中に引きずり込もうとした。お前は、心の中であの霊魂に話しかけたのか」
アルブラートはかすかにうなずくと、怖れと哀しみに満ちた眼で、ル・ラフを見上げた。ル・ラフはしばらく黙って、砂にまみれた若者を見下ろしていた。
「お前の眼は、俺が見たこともない素晴らしい眼だ。純粋で透明な湖のように透き通った表情をしている―まさに幻を呼び寄せる眼だ。だが、あの女は誰なんだ―お前は、あの女を知っていたのか」
「......彼女は俺の妻なんだ―俺は彼女が2歳の時から、難民キャンプで一緒に育ったんだ......4歳年下で―2年前の6月に、俺たちは結婚したんだ―子供も生まれた......なのに、彼女は去年の末、カイロの爆破テロに巻き込まれて......焼死してしまったんだ......」
「なるほどな。死んだ妻か。それなら、お前に会いたがっていたんだろう。だが彼女は、死後もお前に会うという目的を、これで遂げた。もうあの女の幻は二度と現われないだろう」
アルブラートは、やっと立ち上がると、ル・ラフの駱駝の後ろに乗った。男は、シェリフのテントに案内すると彼に言った。
「あの女は、今年になってから、7回蜃気楼と共に姿を見せた。最初は、必ず美しい歌声が聞こえてくる。それで、俺たちはサイレーン* がまた出たと噂していた。その歌声と姿に惹きつけられて、これまでに3人の観光客と、3人のバダウィが流砂に飲み込まれた」
「彼女は小さい時から歌が得意だった......とてもよく響く天使のような声で、いつも歌っていた―カイロでは、オペラ座の歌手だったんだ......」
アルブラートは、流砂に落ちた恐ろしさが薄らいでくると、今度は何ともいいようのない哀しみが胸を突き上げてきた。
あのアイシャが今では冥界の住人に......今でもあのほがらかで元気な笑顔や笑い声を覚えているのに......なぜなんだ......
なぜ俺の周りからは、愛すべき人たちがいなくなってしまうんだ......父さんも―母さんも―ムカールも......今度はアイシャまで......
「お前は難民キャンプで育ったと言ったな。アラブで難民といえば、パレスチナ人か。国を奪われて、相当苦労して育ったんだろう。それにしては、全体に品が良い面立ちをしている。サウジアラビアの王子と言っても通るぐらいだ―俺たちは、もともと国がない。このサハラ全体が俺たちの庭だ。お前も、国を持たない砂漠の部族に生まれていれば、苦労しないで済んだだろうな」
ル・ラフの言葉を聞いて、アルブラートは、真の自由はこの砂漠で得られるのではないかと、ふと考えた。
そうだ―砂漠の民であれば、自分の国がなくても苦しまずに済むんだ......元からあったものを剥奪されたからこそ、「難民」の生活を強いられ、失ったものを奪回しようと苦しむんだ......ムカールも、「無国籍者」と蔑まれて育ったからこそ、国を必要としない砂漠に憧れて......
ベルベル人のアデルは、彼にとっては夢の砂漠の象徴だったんだ......
アルブラートは、それでも、自分の故郷はベツレヘムであり、パレスチナ以外に有り得ないという強い感情が沸き起こってきた。
馬鹿な......!何を考えているんだ......俺は、もうパレスチナなど忘れたいと思っているんじゃないか......アラブ人などではなく、別の人種に生まれ変わりたいほど―アラブを忌み嫌っているんじゃないか......!
「お前は無口な奴だな。さっきから黙りこくっている。俺がパレスチナ人かと言ったのが、気に障ったのか」
「いや、そうじゃない......無口なのは生まれつきだから、仕方ない」
「さっき流砂に落ちたり、死んだ女房の亡霊を見たりしたから、よけいに無口になったのか。まあこの世には、女は腐るほどいるから、もう死んだ者のことばかり考え込むな。お前はまだ若くていい男ぶりだから、またいい女が見つかる」
ル・ラフも、マーディと同じように自分を誉め、慰めてくれていることに、アルブラートは感謝したかったが、再婚の話に必ずなるのが嫌だった。
「......俺はもう絶対に結婚なんてしない。愛する女性を失うのは、もう二度と嫌なんだ」
ル・ラフはそれを聞いて、おかしそうに笑った。
「人の心には、『絶対に』なんて言葉は存在しない。特に男女関係になると、そうだ。お前の人生はまだ先が長い。それに、男は愛する女性がいないと生きていけない。お前はまだ若いから、『絶対に』なんて青臭いことを言ってられるんだ」
アルブラートは、複雑な気持ちになり、ますます黙りこんだ。ル・ラフはそんな彼を振り返り、面白そうに含み笑いをしていた。
「喉が渇いただろう。もうすぐシェリフのテントが見えてくる。シェリフは賢明で、穏やかないい人だ。必ずお前を歓待する―そら、あれだ。あの黒い天幕だ」
二人を乗せた駱駝は、間もなくシェリフのテントの前で止まった。アルブラートは、その天幕の規模に驚いた。横に連なる黒い天幕は、彼がキャンプで育ったテントの10倍ほどの大きさだった。3歳から5歳ほどの小さな子供たちが、テントからはしゃぎながら飛び出してきた。子供たちは、アルブラートを珍しそうに眺めては、何かを言ったり、笑ったりしていた。
ル・ラフは、駱駝から降りると、胸元から皮製の鞭を取り出し、地面を激しく叩いた。すると、子供たちは、いっせいに静まり返り、再びテントの中に走りこんで行った。
アルブラートは、鞭がしなる鋭い音に、ぞっとした。昔、サイダのホテルでムカールがよく鞭打たれていたことを思い出したからだった。
「なぜ―あんな小さい子供たちに向かって、鞭をふるったりするんだ」
「俺はこの鞭で、子供らを打ったりはしない。ただのしつけだ。お客に対して、じろじろ見たりするのは失礼だ。それを小さい連中に言葉で教えても、なかなか言うことを聞かない。この鞭は、礼儀をわきまえろという印だ」
ル・ラフは、アルブラートを連れて、天幕の中に入った。中は、幾つもの細かい部屋に分かれているらしく、美しい模様で織り上げられた薄い絨毯を上から垂らし、それらが各部屋を仕切っている様子だった。
「お客人か、ル・ラフ」
落ち着いた男の声が右側の垂れ幕の奥から聞こえた。ル・ラフは静かに垂れ幕を上げると、部屋の奥にいる男に、恭しく頭を下げた。ル・ラフが男に近寄り、その手に接吻しているのを見て、アルブラートは、この男がシェリフなのだと思った。
シェリフは、医師のザキリスとほぼ同じ年配に見えた。ル・ラフと同じように、肌の色は青いが、マーディが言っていたように、立派な気品ある容貌の持ち主だった。
シェリフは、青地に金糸で豪奢な模様が縫いこまれた、最上等のガラベーヤを着ていた。黄金に縁取られた、堂々とした黒い椅子に座ったまま、シェリフは、そばに来るようにと、アルブラートに手招きした。
「私はイブン・アブドゥルカリーム・アル・ドバイだ。よく来たな、アル・ハシム」
アルブラートは、いきなり自分の名を初めて会った相手から言われて、戸惑った。彼は、シェリフの前で片膝を立て、胸に手を当てて、静かに頭を垂れていたが、黙って、鹿が虎を警戒するように、そっとシェリフの顔を見た。
「アルブラート・アル・ハシム。お前の名前と顔は知っている。私は去年の夏、商用でアレクサンドリアの郊外に出かけ、1ヶ月ほど滞在した。街に行くと、カイロで流行っている若手のウード演奏家の曲が、よくラジオから聴こえていた。我々は羊の毛皮や絨毯を売りさばいた。それを気に入った客が、ラジオの演奏家のレコードを私にくれた―そのレコードの写真が、アル・ハシム、お前だった」
アルブラートは、ウードを演奏していた頃を思い浮かべた。アイシャが亡くなってからは、ぴたりと演奏を止めた。彼女が亡くなって、まだ3週間も経っていなかったが、彼には、もう三年が過ぎたように思えた。
「ハダリ* は、我々のようなバダウィが、ラジオやレコードなどを意味も分からず珍重し、有り難がると思っているらしい。だが我々サヘール族は、ハダリの連中が考えているような、未開な野蛮人ではない。私はちょうどお前の年の頃、カイロ大学に通っていた。だからハダリの文化や学問は充分学んで、知っている」
アルブラートは、自分はパレスチナ人であるがために、都会では無視され、危険視されてきたというのに、砂漠の遊牧民が大学に入学できたということに、驚きと羨望を隠せなかった。
「サヘール族は、古代から『砂漠の王』と呼ばれるほど、貴い血筋を受け継いで維持してきたのだ。コーランでも『アラブ』と言えば、まずバダウィを指す。そのバダウィの中でも、王族に近い血が、我々の中に流れている」
シェリフは、ル・ラフにコーヒーを入れさせ、アルブラートに勧めると、自分も飲み、話を続けた。
「だが、大学の中にはユダヤ人も多かった。彼らのヘブライ語で、バダウィを意味する語から、『アラブ』という呼び名が誕生したとユダヤ人たちは主張していた。彼らにとって、要するに『アラブ』とは、野蛮で原始的な未開人を意味している。彼らの我々に対するイメージは、砂漠を放浪する、薄汚い遊牧民の姿なのだ」
このイブン・アブドゥルカリームの話を聞いて、アルブラートは、なぜユダヤ人が、イスラエル軍が、自分たちパレスチナ人を、「野蛮なアラブ人」と蔑み、迫害し、虐殺してきたのかが理解できた。
大人しく話を聞いているアルブラートを、シェリフは好ましそうに見つめ、優しそうに微笑んだ。
「トゥアレグ族は、成人すると、藍で染めた青い服で全身を覆う。そこで肌の色も、徐々に青くなる。我々はこれを誇りに思っているが、ユダヤ人や、西洋人から見ると、ますます『アラブは野蛮で奇妙な人種だ』となるらしい。連中には、アラブにも固有の文化があることを理解する、寛大な心が無い。だから、私は、アラブ音楽を立派に演奏し、アラブ文化を西洋人に認識させているお前を誇りに思っているのだ」
* サイレーン(Seiren): ギリシャ神話中の半人半鳥の姿をした、美声の海の魔女。舟人を魅惑し、死に至らしめると言われる。後に美化され、音楽家の代表者をこのように呼ぶようになった。
* ハダリ(hadari):アラビア語で「町に暮らす人々」の意。
シェリフが、手をパンパンと打ち鳴らすと、天幕を仕切っている垂れ幕がそっと開いて、黒いヴェールを口まで覆った女性が、次々と料理を差し出した。ル・ラフはそれらを受け取り、シェリフと、アルブラートの前に運んできた。料理は金や銀の皿に盛られた豪勢なもので、羊の頭を丸焼きにしたものや、ひな鳥を調理したハマーム、他にコシャリ、ガムバリ* などが盛り沢山だった。
アルブラートは、アブドゥルカリームから、やや下がった客用の長椅子に腰掛けていたが、その長椅子も、金糸に縁取られた、赤地の、座り心地の良い高級なものだった。彼は、砂漠の遊牧民でも、階級制度があり、サヘール族のような最も優れた血筋の者たちは、街の住人など、考えにも及ばない、豪奢な暮らしができるのだと知った。
シェリフは、彼に酒を勧めながら、語りかけた。
「このル・ラフは、私の最も年長の甥で、娘婿でもある。彼は教育機関で学んではいないが、私の買い集めた書物はすべて読破し、頭に入っている。私が一番信頼している者だ。そうだな、ナフル・ラファージ・アル・ドバイ」
ル・ラフは笑みを浮かべると、アルブラートに食事を取れと勧めた。シェリフは酒を飲むと、ますます機嫌が良くなり、全部食べろと言ったが、アルブラートは、とても食べきれないと思い、ただただその食事の量に圧倒されていた。
「アルブラート・アル・ハシム。お前は立派なアラブ音楽演奏家だ。お前にこれをやろう。私が街で買った、ヨルダン製のカーヌーンだ」
シェリフから差し出されたカーヌーンは、ちょうど、キャンプの占領後に失われた、父のカーヌーンによく似ていた。アルブラートは有り難く受け取ったが、西洋音楽を学ぼうと思っていた矢先に、この楽器はとても弾けないと思った。
「私の妻に、モロッコから流れてきた女で、我々と同じアマーズィーグ* の高貴な血を引くラティカという者がいる。ラティカは優れた踊り子だ。マグレブ* のスーフィズム* の舞踊テクニックを身に付けている。アル・ハシム。お前に彼女の踊りを見せてやろう。その代わりに、このカーヌーンで伴奏をしてくれないか」
アルブラートは、アイシャとの共演の思い出が嫌でも付きまとう、カーヌーンに触れることが辛かった。彼はじっと考えこんでいたが、ル・ラフは、タールと呼ばれる太鼓を用意し、彼にカーヌーンを持たせると、天幕の外に連れ出した。シェリフも、まだ陽射しのきつい外に出て、地面に座り込んだ。
ル・ラフは、いきなり太鼓を連打し始めた。すると、その音に誘われたように、20歳ほどの、若い女性が天幕から顔を出した。彼女は、ゆったりとした白地に、華やかな金糸の刺繍が施された美しい衣装を身につけ、首には珊瑚や瑪瑙やヴェネチア製の真珠でできたネックレスを幾重にもかけていた。
アルブラートは、そのラティカという女性を見た途端、アデルのことを思い出した。ラティカは、アデルに雰囲気がよく似ていたが、アデルよりも野生的で、明るく華やかな顔立ちをしていた。彼は、アデルの神秘的で寂しそうな表情を思い浮かべた。
アデル......アデルはあれから、一体どこに行方をくらましたんだろう......故郷のアルジェに帰ったのか......それともモロッコに行ってしまったんだろうか......
彼は、ムカールが、死ぬ1週間前の、アデルとの挙式の際に、彼女に「アルジェの独立は来年の3月に達成される」と言っていたことを思い出した。ムカールの言葉通り、アルジェリアは1962年の3月にフランスからの独立を果たしたのだった。
アルジェが独立を勝ち取るまで―彼女はどこかの街のホテルで、またメイドをしていたんだろうか......アザゼルはアルメニアに引き取られて......なぜ皆こんなに散り散りになってしまったんだ......
アルブラートは、ぼんやりとアデルやムカールのことを考えていたが、ル・ラフの張りのある歌声と、太鼓を連打する音で、はっと我に返った。ル・ラフの使う言葉は、部族特有の言葉なのか、彼には理解できなかったが、そのよく響く歌声を合図に、ラティカはゆっくりと旋回し始めた。
彼女は、白いヴェールで顔を多い、目の部分だけを覗かせていた。太鼓の音と、ル・ラフの伸びやかな歌声に、彼女は徐々に恍惚の頂点を昇り詰めていった。旋回のスピードも徐々に速くなり、衣装は舞踏の渦に巻き込まれながらも、時折何回もふわりと大きく広がった。
ラティカは、とうとう白いヴェールを払いのけると、黒く輝く長い髪を露わにし、踊りながら、何回も、その髪を地面に叩きつけた。その後、彼女の旋回は驚くほどのスピードに変わった。もう踊り子の姿も目に止まらないほどだった。
アルブラートは、こんな踊りを見るのは初めてだった。
シェリフに伴奏を促されたが、カーヌーンに手を触れるのをためらい、なかなか弾けなかった。だが、女の踊りと、リズミカルなル・ラフの太鼓と歌声を見聞きするうちに、抑えようにも抑えられない衝動が、彼の全身を貫いた。彼は、ついにカーヌーンを手に取り、ラティカの強烈なリズムから生れる恍惚感が指先に宿ったかのように、いきなり激しいスピードで、カーヌーンを奏で始めた。
* コシャリ: 香辛料を多く使った、白米の上にマカロニスープをかけた料理。
* ガムバリ:エビ料理。
* アマーズィーグ: 「ベルベル人」はギリシャ語の「バルバロイ(言葉が分からない者)」を指す語から発生したため、ベルベル人は自ずから「高貴な自 由人」の意の「アマーズィーク」と呼ぶ。トゥアレグ族はサハラのベルベル 系遊牧民。
* マグレブ(Maghreb):リビア、チュニジア、アルジェリア、モロッコなど北西アフリカ諸国の総称。
* スーフィズム(Sufism):イスラム神秘主義教団。布状の服を身につけて一心不乱に回る、回旋舞踊と呼ばれるものを行い、神との一体化を求める。
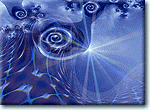
アルブラートの伴奏は、広大な砂丘の遥か遠くにまで流れていった。ラティカの凄まじい回転の速さと、ル・ラフの太鼓と歌声とに、見事に調子が合っていた。そのうち、ル・ラフは自分の演奏と歌を止めてしまった。とてもアルブラートとラティカのスピードについていけなくなったのだった。
今では、ラティカとアルブラート二人だけが、その速度を競い合っているかのようだった。踊り子は、何回も何回も黒髪を地面に打ちつけたかと思うと、その度に、爪先だけでくるくるといつまでも旋回し続けた。
アルブラートの伴奏を聴きつけて、天幕から数人の男たちや子供たちが顔を出した。彼らには、この若者の指先が、なぜあんなにまで素早く激しく動くのか、また、なぜ、それらがこんなにまで美しく、悲哀感を帯びた旋律を生み出すのか、不思議でならなかった。
演奏の間中、アルブラートは不思議な恍惚感にとらわれていた。ラティカの旋回舞踊から発するエネルギーが、彼の指先を動かしていた。彼は、事実、神が自分を支配している感覚を味わっていた。
この砂漠にこそ神が居る―この砂漠を造ったのは神自身だ―神が君臨し給う聖なる空間が砂漠なんだ―
シェリフも、ル・ラフも、部族の他の男たちも、皆、アルブラートの超越した演奏技法に度肝を抜かれた様子だった。アルブラートはラティカが踊りを止めない限り、永遠にカーヌーンを奏で続けるかと思われた。
やがて、アルブラートの額が汗でぐっしょり濡れているのに気づいたシェリフは、手を叩き、ラティカの踊りを止めさせた。アルブラートと踊り子は、互いに見つめ合ったまま、息を切らしていたが、胸の鼓動がややおさまると、ラティカは地面に放ったままの白いヴェールを拾い、顔を隠した。
彼女は、目で、彼に笑みを送ると、外に飛び出してきた自分の子供たちを優しく促し、天幕の中に、何事もなかったように姿を消した。
アルブラートは、まだ激しい疲れが取れず、肩で息をしていた。ル・ラフが思わず拍手をし、シェリフをはじめ、部族の男たちも拍手喝采した。男たちは何かを叫びながら、カーヌーンの演奏に、驚嘆の意を表していた。
「やはり思った通りだった。アルブラート・アル・ハシム―お前は当代髄一の音楽家だ」
シェリフは彼に近づき、彼の肩を親しげに軽く叩いた。
「あの声は......?」
「ああ、あれはトゥアレグ語だ。男たちはお前のことを『神の使者よ』と叫んでいる。まさにその通りだ。カイロでレコードが売れるわけだな」
アルブラートはこの時、ついにアラブ音楽を吹っ切ることができた、と感じた。
ここまでカーヌーンを弾けば、もう思い残すことなどない―アラブは固有の文化を持っている―その文化を、ただ心の引き出しの奥深くに封じ込めて、鍵をかけるんだ―そうすれば、パリに、お祖父さんと同じヴァイオリンの修業に出かけることができるじゃないか......!
ル・ラフは彼に天幕に入って休むよう勧めながら、こう言った。
「わざわざこんな砂漠の奥地まで来たお客が、こんなに凄い演奏家とは恐れ入ったな。お前は、流砂に飲み込まれなくて良かったな。まあ、若手の演奏家がこのオアシスに来るとは、シェリフの話で聞いてはいたんだが、それがお前だったとは驚いたな。俺も、お前をここまで案内した甲斐があった」
「シェリフが、俺が来ることを知っていた......?」
「ああ、そうだ。お前にシェリフが珍しい物を見せてくれる。早くテントに入るがいい」
汗を拭いながら、アルブラートが天幕に戻ると、シェリフはもう先ほどの黒い椅子に腰掛けていた。
「さあ、そこのコーヒーを飲むが良い。アル・ハシム、私はお前をレコードで知ったと言ったが、お前が今日この日、ここに来ることは分かっていたのだ。この碧水晶に、お前の姿が映ったのでな」
彼は、差し出された、透き通ったガラス玉を見つめた。何の変哲もない、ただのガラスに見えた。アルブラートが不思議そうにシェリフを見つめると、シェリフは笑った。
「今の演奏のお礼に、この碧水晶もお前に贈ろう。これは、アレクサンドリアに来ていたトルコの商人から買ったものだ。この水晶は、夜になると、碧く輝く光を放つ。その時を逃さず、水晶に目を凝らすと、自分の未来が見える。自分の身内や、友人や、自分に近寄ってくる者の姿が見えるのだ。ただし、これは15歳以下の子供が見ると、不思議とその子供とお前の過去が見える。まあ、土産と思って受け取るが良い」
シェリフは、真面目な口調で付け加えた。
「自分の未来といっても、見えるのは、その水晶を見た時から、ほんの半年間の出来事が映るだけだ。だから、また自分の未来を見たかったら、それから半年待つことだな」
アルブラートは、半年後の未来と聞いて、漠然と、パリ音楽院入学のことを思い浮かべた。
「お前にもし、子供がいて、過去を見せたくないのなら、子供が分からぬ所にしまっておけば良い―私は大学で学問を学んだが、人間に必要なのは、科学的知識ばかりでもあるまい。このような、非科学的なものにも、人間は魅了されるものだ―西洋文明は、こういった謎めいたものを排除し、それを信じる者を異端者扱いするが、お前がこの水晶に映ったということで、私は、人間には魂というものが存在する証を立てることができたのだ」
アルブラートは、カーヌーンを演奏している時、神との一体化を真に具現化していた自分の心を思い起こした。シェリフは静かに話を聞いている若い演奏家をじっと見つめた。
「あの舞踊の舞い手はスーフィと呼ばれる。ラティカは踊りながら、彼女の魂を、神が神自身を知るに至った、この世の創造の原点に辿り着かせ、なお且つ、その魂を、神的中心に到達せしめようとしていたのだ。だが、アルブラート、お前も彼女の恍惚感と一体化し、一心に神との合一の悟りの境地に到達しようとし、それが見事に成功していたな」
「......私は、演奏している時は、何も考えていませんでした―ただ、ラティカの驚くべき回旋のスピードに合わせていただけです―神との合一など、感じてはいませんでした......ただ、この砂漠に神が君臨し給うのだと―その感覚を維持しながら、カーヌーンの弦をはじいていたのです」
「神との一体化の境地を目指す者は、何も考えたりしない。踊りや、演奏の中で、その境地に知らず知らず至るのだ。ラティカは既にその境地に、いつでも辿り着くことができる。だが、お前もファナー* にいつしか至ったのだ。だから、男たちは『神の使者』とお前を崇めたのだ」
「でも私は......もうカーヌーンは―しばらく弾きません―この砂漠にやって来たのも、蜃気楼に現われる、死んだ妻の幻を見たいだけだったのです......彼女は年末のカイロでのテロ事件に巻き込まれて亡くなりました......2年前に死んだ友人が、昨夜、部屋に現われて、『サハラに行って彼女に会えば、アラブを捨て去ることができる』と言ったんです......」
「そうか。お前が蜃気楼の幻に会いに来ることは、この碧水晶にすべて映っていた。流砂に落ち込むこともだ。アル・ハシム。お前は幻を呼び寄せる魂の持ち主なのだな―お前の眼を見れば、すぐ私には分かる。芸術家は皆そうしたものだ。だが、なぜアラブを捨てたいと思うのか、話してくれないか」
「......私はパレスチナ人です―幼い頃から難民として育ち、イスラエル軍にキャンプを占領され、捕虜になりました。キャンプの女性や子供たちは、皆虐殺されました―シリア軍のおかげで、やっと収容所から救出され、死んだと思っていた少女とも再会でき、2年前に挙式しました......
でも、難民がゲリラ化してからは、パレスチナ人は他のアラブから『テロリスト』と見なされ、私もレバノンで、治安部隊に右足を撃たれて、足が不自由になりました......そして、イスラエルに報復を誓ったパレスチナ・ゲリラのために、カイロのシナゴーグ爆破が起きて、妻を失いました......
この様々な過去の不幸は、すべてイスラエルとアラブとが対立し合う社会が作り出したものです―それに、私の祖父にはアルメニア人とジプシーの血が流れている―祖父は立派なヴァイオリニストとして、ヨーロッパに住んでいるんです。だから、私は......アラブを捨てて、ヨーロッパに行くことに決めたんです―」
アブドゥルカリームは、ル・ラフと共にこの話を黙って聞いていた。シェリフは、うつむいているアルブラートを、穏やかな眼差しで見つめると、彼の手を優しく握った。
「誰でも、辛い目に遭えば、自分の生きてきた社会を否定したくなる。お前はあれだけの才能を持った、優れた芸術家だ。多分、お前の決心した道は、間違ってはいないだろう―ただ、お前がすべきことは、アラブであることを、意識の底に封じておくことだ。いつかまた、アラブ音楽を演奏したい時が必ず来る。その時に、意識の底の鍵を持つ唯一の者であるお前が、鍵を開け、再び自由な空間を手に入れれば良いことだ」
アルブラートは、絹の布で包まれた碧水晶とカーヌーンを受け取り、シェリフに厚く感謝の意を表すると、ル・ラフと共に天幕を出た。もう午後の4時を過ぎていたが、アルブラートはこのサヘール族のシェリフに出会って、まる1日を過ごしていたように感じた。
ル・ラフは、彼を、自分の駱駝の後ろに乗せると、シーワの町に向かって出発した。
「俺は、あのタール* を12歳の時から、20年間やってきた。でも、お前は違うな。あれだけの腕前で、あの賢明なシェリフからも一目置かれるほどの音楽家だ。小さい時から、あの楽器を弾いていたのか」
「はっきりとは覚えていない......4歳か5歳の時から―気がついたら、いつも楽器がそばにあったんだ」
「誰にも教わらなかったのか。何か血筋でもあるのか」
「......父が、ベツレヘムの音楽院を出て、演奏活動をしていたんだ―でも父は、俺が楽器に初めて触れた頃にはもう病気になっていて......
5歳の時に、亡くなったんだ―だから、特に何も教わることができなかった」
「それでも、お前はこの砂漠に来て、あんな見事な演奏をした。本当にもう弾かないのか。お前はこの砂漠で、自分の居場所は見つからなかったのだな―お前は、アラブ世界に、もはや居場所を見出せない。だからヨーロッパに行くというのだな」
ル・ラフからこのように言われて、アルブラートは、自分は何か勘違いをしていることに気がついた。
アラブ音楽を心の底に封じ込めて、鍵をかける―それで終わりじゃない―俺がアラブを捨てるということは、単に音楽だけの問題じゃない―アラブの血そのものを......忘却の暗闇に捨て去る......
そうだ―アラブであることと決別するために、こんな砂漠の奥地まで来たんじゃないか......
* ファナー:神との融合の境地。
* タール(Tar):木の枠に皮を張った太鼓で、自然の四要素「風・水・土・火」を表現する。
「よくヨーロッパやアメリカなどの観光客などが、俺たちの集落まで来て、俺たちの姿を写真に撮っていく。彼らは、珍しい民族の写真を手に入れて、喜んでいる。俺たちは、見世物じゃない。だから、あんなことはごめんだ。だがマーディがどうしてもと頼むから、断らないだけだ。どうあっても、自分自身の外見は、今更変えることができないからだ」
ル・ラフは、シェリフによく似た物静かな口調で、話し続けた。
「お前も、その外見は一生変えることはできない。お前は、どこから見てもアラブ人だ。しかも王子のような立派な容貌だ。でも、お前はアラブを捨てると言う。いいか―真実アラブを捨てるには、外見よりも大事なことがある。どうすればいいか、教えてやろうか」
彼は、アルブラートをちらりと振り返った。アルブラートは顔を上げ、戸惑ったように、この青い男を見た。
「自分の生きてきた社会や、その中で育まれた物の中で、最も重要なのは、言葉だ。自分が親から教わり、今まで使ってきた言葉だ。アラブがアラブであるためには、アラビア語が一番大事な要素だ。まず言葉が文化を形成しているんだ。お前は、そのアラビア語を、すべて忘れることで、アラブであることを止めることができる―お前は、ヨーロッパの言語を知っているか」
「......英語とフランス語は知っている......」
ル・ラフは、真剣な表情で、若者をじっと見つめていたが、少し笑うと、再び前を向いた。
「それなら、条件は充分に整っている。お前がヨーロッパのどこに行くのか知らないが、西洋人の社会の中で暮らし、己の民族性すべてを捨て去るには、アラビア語は二度と使わないことだ。考える時も、独り言を言う時も、寝言を言う時も、すべて、西洋人の言葉を使うことだ。そうしないと、お前はアラブ人であることが、いつまでも意識の底に残ってしまうぞ」
ル・ラフからこのように言われるまで、アルブラートは、「アラブを捨てる」という自分の言葉の意味を、具体的に把握していなかったことに気づいた。彼は、生まれてから21年間、絶えず使ってきた言語を忘れ去ることまでは考えていなかった。
アラビア語を忘れ去る―母語を記憶から消滅させる―そのことを考えると、大海に浮かぶ小舟のように、よるべない寂しさと共に、恐怖をも感じた。
「シェリフは、お前に、『アラブであることを意識の底に封じておけばよい』と言った。だがそうすることが、何を意味するのか、具体的に言わなかった。シェリフは、俺と違って優しいからだ。俺の言うことは、お前には厳しいことかも知れない。だが、単にアラブ音楽の演奏を止めたからといって、それでアラブ人であり得ることまで捨て去ることは不可能だ」
その後、しばらく二人は無言だった。夕方の5時近くになった頃、辺りは沈みかける夕陽に照らされ、深く美しい金色の光に包まれた。どこからか、涼しい風が吹いてきた。壮大な黄金の砂漠の中で、動いているのは、二人の乗った1頭の駱駝だけだった。
井戸が見えてくると、ル・ラフは駱駝を止め、井戸の水を皮袋に汲み上げた。アルブラートにまず水を飲ませた後、彼は自分の喉を潤した。
「あと半時ほどで、町に着く。お前はホテルに行って、マーディを俺の所に連れてこい。俺もお前を集落まで案内して、また町まで送っていくという仕事をしたんだ。マーディから50ポンドは受け取る」
彼は、無言でいるアルブラートを静かに見つめた。
「俺がお前に話したことが、ショックだったか―俺はお前のためを思って、アドバイスしただけだ。お前の体にも、意識にも、深く沁みこんでいるアラブというものを、お前が『捨てる』と決意しているからだ。曖昧な決意のまま、西洋に行っても、お前は自分を見失うだけだ―だが、お前がアラブ世界に留まるというのなら、俺のアドバイスは無用だ」
二人は再び駱駝に乗った。ほどなく、シーワ・オアシスの町が見えてきた。ル・ラフは町の入り口で駱駝を止めると、ここで待つと言った。アルブラートは、ホテルに向かうと、彼に言われた通りに、マーディを呼び出した。
マーディがそばに来ると、ル・ラフは50ポンドを受け取り、懐にしまい込んだ。青い男は、駱駝に飛び乗ると、笑いながら二人に話しかけた。
「アル・ハシム。お前ともう二度と会えないのは残念だな。おい、マーディ。このお客はただの若造と違うぞ。カイロでも、アレクサンドリアでも名の通った、一流の音楽家だ。明日は丁重にマルサ・マトルーフまでお送りしろ」
●Back to the Top of Part 17
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 読書日記
- 「諸君、狂いたまえ」
- (2024-11-26 18:05:11)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- duta89 link daftar terbaik dengan …
- (2024-09-11 01:49:11)
-
-
-

- 私の好きな声優さん
- 声優の篠原恵美さん、病気療養中に死…
- (2024-09-12 00:00:14)
-
© Rakuten Group, Inc.



