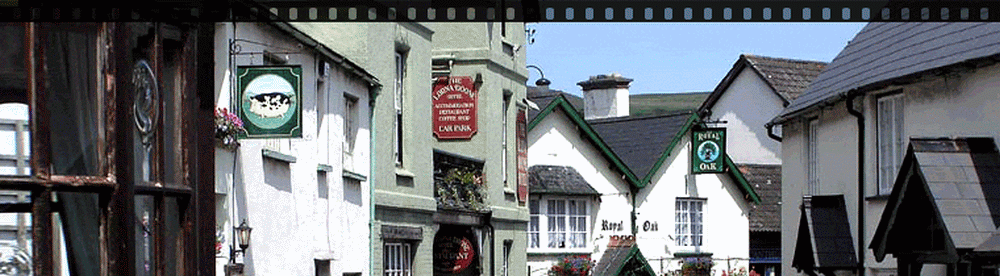-
1

滑稽な悲劇・・・「レヴェルゲ(死んだ鼓手)」~『子供の不思議な角笛』から~
マーラーの歌曲集『子供の不思議な角笛』といえば、 いわゆる「角笛交響曲群」を生んだマーラーの世界の原点であり、彼が造った「王国」でもあります。 代表的なところでは、 「魚に説教するパドヴァのアントニオ」「原光」は 彼の交響曲第2番「復活」において、ほぼ原曲のまま登場します。 若書きの第1番を除き、第3番、第4番まではこの歌曲集の「王国」の支配下にあると言っていいでしょう。 ところで、 標題のレヴェルゲ(死んだ鼓手)。 「僕は死ぬまで行進せねばならぬ!」 という歌詞に象徴されるように、 課せられた使命の到達点が「死」や「敗北」だとわかっていても、 どうしてもそれに逆らうことができず、 「行進」を止めることができない、そんな「滑稽な悲劇」を歌う哀しい唄。 これが後の大曲 交響曲第6番「悲劇的」 の原点であり、 この小品にその双葉の芽吹きをはっきりと感じることができます。 「厭々ながらの行進」と「滑稽な悲劇」は、彼の半生をかけたテーマだったようです。 僕はこの曲を聴くと、個人的な情景として「二百三高地」を思い浮かべてしまいます。 しかしこのレヴェルゲに漂う独特の哀愁は、 古代の防人のようでもあり、 現代の官僚やサラリーマンのようでもあり、 不思議な共有性・共時性で僕たちの共感を誘います。 ♪ 「ああ、兄弟よ、僕は撃たれた。 弾が僕に当たったのだ。 僕を兵舎に運んでくれ」 トライラリ・トライラライ・トライラレ(行進の歩調) 「ああ、兄弟よ、僕はお前を運べない。 敵軍が僕らを打ち負かしたのだ。 神様だけがお前を助ける」 トライラリ・トライラライ・トライラレ 「ああ、兄弟よ、君たちは通り過ぎるのか、 まるで僕がもうおしまいであるかのように」 トライラリ・トライラライ・トライラレ 「僕は太鼓を打ち鳴らさねばならぬ。 でないと僕はひとりになってしまう」 トライラリ・トライラライ・トライラレ 「兄弟たちは刈られた草のように いっぱいに大地に横たわっている」 でもその鼓手は、最初からもうすでに死んでいるのだ。 それは出だしの歌詞を聞けばわかる。 「朝の3時から4時までの間、 あの小道を行ったり来たり。 僕たち兵士は行進せねばならぬ・・・」 トライラリ・トライラライ・トライラレ・・・ 僕の恋人が見下ろしている。 トライラリ・トライラライ・トライラレ・・・
2007年03月19日
閲覧総数 979
-
2
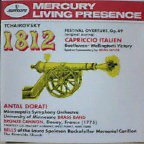
アームストロング砲
幕末のむかし,佐賀藩に秀島藤之助という色白の藩士がいた。 薩長土肥で有名な鍋島閑叟の時代である。 精神的な「攘夷」ではなく現実的な「国防」を考えていた英明の君主鍋島閑叟は,その股肱の臣であり佐賀藩きっての秀才である秀島藤之助に対し,世界最新鋭の大砲である アームストロング砲 の製造を命じた。 秀島藤之助は,絵が好きだった。 好きなだけでなく,卓抜した画才があったといわれる。 しかし,「絵など書いてなんになるか」 という主君閑叟の言葉に,自らの画才を封じた。 そういう閑叟でさえ,大変な詩文の才の持ち主ではあったが,そのようなそぶりを見せることなく,佐賀藩の近代化に生涯その心血を注いだ。 二人とも,身体は丈夫なほうではなかった。 藤之助は,主命により,アメリカ南北戦争で使われたばかりの新式大砲の製造に取り掛かった。 ところでアームストロング砲とは,いままでの大砲の常識を覆す画期的な兵器だった。 まず,弾は筒先からごろごろと入れるのではなく,後ろから入れる後装式。 弾は球型の弾丸でなく椎の実のような炸薬入りの尖頭弾。 砲身は銅でも鋳物でもなく,鋼鉄製。 さらに砲内に多数の溝が掘られることにより弾丸に回転力を与え命中率が格段にアップ。 射程距離は既存の大砲の約2倍。 きわめつけが,連射可能回数は約10倍の性能。 しかし,安全性に保障はなく,常に破裂する危険性があり,南北戦争では発射と同時に何人もの味方の砲手を一瞬で木っ端微塵にしてしまった危険な武器である。 藤之助は,寝食を忘れてその製造に打ち込むが,専門のお抱え技師などいるはずもなく,設計図をはじめ材料の見立てから一人で試行錯誤を繰り返すという文字通り手探りの孤独な作業だった。 藤之助は,蘭学の知識はあったが,肝心の製鉄についてはまったくの専門外。 たまらず,同僚で鉄に明るい田中儀右衛門に教えを乞うた。 しかし田中も田中で閑叟から「自前の蒸気船を作れ」という無理難題とも言うべき命令を受けており,常に多忙だった。 ついつい,藤之助を邪険に扱い,その知識不足を嘲弄するようになった。 藤之助は,苦悩した。 孤独な戦いの中で,ついには発狂した。 しかも英国船を視察中に発狂し,雷雨の夜,外国船の室内で田中を斬った。 藤之助は,雷が苦手だった。 すぐに取り押さえられ,その後蟄居され,維新後に死んだ。 発狂後,彼の口から出る言葉はすべて,アームストロング砲のことばかりであったという。 閑叟は,藤之助と田中の件については,刃傷沙汰扱いせず,減知・改易なし,戦死と同じように名誉の死として扱った。 閑叟が近代化を急ぐ余りの過酷な命令による,今でいう過労死だった。 ・・・・・・・・・ その後,アームストロング砲についての藤之助の研究は,他の藩士に引き継がれ,ついに,二門,試作に成功した。 砲手は,藤之助の遺臣弁蔵。 弁蔵はその主藤之助に心底惚れこみ,主君の死後もこの新式砲の傍を離れることができなかった。 時代は流れ,薩長による倒幕は半ば成ったが,西郷隆盛と勝海舟による江戸城無血開城のあと,これを不満とする旧幕臣たちが多数上野に集結し,「彰義隊」と称して新政府軍に対抗した。 新政府軍総司令官大村益次郎は,彰義隊を討伐すべく上野に向かった。 世にいう彰義隊戦争である。 しかし,上野を包囲すべき新政府軍と彰義隊の兵力差はほとんどなく,彰義隊は旧幕臣とはいえ,大砲も数門そろえた手強い軍団だった。 これでは包囲戦どころではなく,市街戦となると上野の街に多数の被害が出るおそれがあった。 新政府軍の中に,薩長土肥の「肥」である肥後の佐賀藩から二門のアームストロング砲があった。 総司令官大村益次郎の緻密な作戦のもと,戦いの火蓋は切って落とされた。 戦闘は一進一退かに見えたが,ほどなく,藤之助の遺臣弁蔵に対し大村総司令官から,隊長を経由して「撃たれよ」と発射命令がくだされた。 アームストロング砲が火を吹いた。 二門,六発ずつ。合わせて十二発。 不忍池を飛び越え,彰義隊に炸裂した。 そのたった十二発で,彰義隊は壊滅した。 (司馬遼太郎著「アームストロング砲」より) まるでプロジェクトXの幕末版みたいな話であるが,僕はこの秀島藤之助という繊細な感覚をもった武士に深い共感を覚える。自分の身を折り重ねるような,といったらさすがにおこがましいし,言い過ぎだけど,気分としてはそれに近いものがある。 「男の人って,どうして『1812年』が好きなのかしら」 やれやれ,なんであんな乱暴で品のない音楽を,信じられないわ,と,学生時代に同い年の女の子にため息まじりに言われたことがある。 けれど, それはたぶん,男というのは,大なり小なり秀島藤之助みたいなもんなんじゃないの, と僕は思うのだが。 チャイコフスキー作曲 大序曲「1812年」 ドラティ指揮ミネアポリス交響楽団 同曲は,ロシアにおけるナポレオン戦争を描いたもの。 ラ・マルセイエーズの旋律がフランス軍として描かれ,それをロシアの大砲が粉砕する。 この録音は,大砲の録音が秀逸で「オーディオ史上の一大事件」と言われた。 まさに「アームストロング砲」級の名録音。 ちなみに,彰義隊戦争は1868年。 1812年にはアームストロング砲は存在しない。
2006年02月21日
閲覧総数 15296
-
3

ピアノ・ソナタ〈清掃〉~「のだめ」再び~
明日,ヨメさんがはるばる九州からやってくる。 あれ,ブラームス,先週あなた九州帰ったばっかりでしょ。ずいぶんリッチな遠距離じゃないの~,って言われりゃまあそうなんだけど。 先週帰ったのは式関係もろもろの打ち合わせのためで,今回ヨメさんがいらっしゃるのは,とある資格試験をお受けになるためです。 ヨメさんはなんにもできない僕と違って,立派な専門知識と技能を持ったスタッフ職・専門職の人で,今回受ける試験に通ればうちの行政内部だけじゃなくて,民間に出ても食うには困らないらしい。 まったく,えらいものである(大きな声では言えないが,僕よりお給料がよい。僕,本気で主夫になろうかな・・・)。 で,まあ今回宿を貸さねばいけないわけだが, 困ったことに, 僕の普段の部屋は,とっても散らかっている。 よく, 「ブラームスの部屋はきれいに片付いてそうだよね。」 と言われるのだが,酔いつぶれた僕を部屋まで送った人はいつも吃驚仰天し,そして次の日決まってこうのたまわれる。 「ブラームスの部屋はもっときれいかと思ってた(失望)。」 そうである。 僕の普段の部屋はキタナイ。 いや,正確に言うと,散らかっている。 しかも,散らかっているのは,大量の聞き散らかしたCDと読み散らかした本が大半。あと,洗濯して干した(部屋干し)はいいが,たたんで収納していない服(←とりこんだもの以外は物干しがハンガー代わりとなっている)。 駄菓子菓子(←懐かしい),掃除といえば,そこらじゅうに散らばったモノを元のしかるべき場所に納めればこと足りる。 (でも,もとのしかるべき場所にはいつの間にか収納のキャパがなくなってたりする・・・あれ,おかしいな。) しかし,これだけは言っておくが,別に汚いもの(例えば食べ物のゴミとか)があるわけではない。 そのへんは「のだめ」と違うところだ。 そうそう, のだめの第1巻で出てきたピアノ・ソナタ〈清掃〉(←ネーミングに笑った)。 千秋がのだめの部屋のあまりの汚さを見るに見かねて掃除をしてしまい,そのあとでのだめが即興で弾いた曲だけど, 気になる。 どんな曲だー! 楽しそうだー!! 千秋真一指揮のR☆Sオケよりもこっちの方が聞きたいー!!! と思う。 その点,二次元のマンガで3次元の音楽を描くやり方はずるい。 けど,そこは読み手の「想像力まかせ」ということで,二ノ宮知子サンはうまいことやってると思う(←やっぱりズルイ)。 でも,モーニングで連載中の「ピアノの森」は,あれは酷いと思う。 あんなの,よく臆面もなく毎週毎週書けるよな。 設定もストーリーもキャラクターも表現手法もマンガチックすぎてマンガにすらなっていないのに。 まあ,クラシックのマンガならばマンガのクラシックと言えば言えなくもないが(←毒)。 でもそんだけ,「のだめ」はすごいってことか。 小うるさいクラシック・マニアを黙らせて,しかもCDまで出しているんだもんな(←これはすごいことだと思う。僕の経験則上,うるさ加減においてはクラシック・マニアほどタチの悪い人種はいないからだ。)。 のだめカンタービレ。 まだまだキャラは育っていくはず。 まだまだネタはあるはず。 まだまだがんばって続けて欲しいものである。 でも,個人的には,単行本の表紙でのだめが弾いている楽器がそろそろ尽きてきているのではないのか・・・とそれだけがちょっと不安。(←これが本当の老婆心) ずいぶん遅い時間になりましたが,今まで掃除をしておりました。 掃除と言ってもその辺に散乱したものをしかるべき場所に戻しただけですが。 たまに地層と化しているからおおごとである。 夜中に窓を開けるわけにもいかない(1階なので)ので,仕上げは明日。 今日のところはこの辺でよかろう。 CDも本も服も,なんとかしかるべき場所に収まってくれたし。 やれやれだ。 でも,片付いた部屋というのはいいものだ。 自分の気持ちまですっきりしたような気がする。 これからはオフィシャル・イメージどおり,部屋はいつも片付けておくとするか。 そうすりゃヨメさん来る前に夜中まで掃除しなくて済むしね。
2005年10月14日
閲覧総数 901
-
4

戒壇堂の広目天
連休を利用して大阪・京都・奈良に行ってきました。 これは東大寺戒壇堂(戒壇院ともいう。)。 GWだというのに、大仏殿の喧噪をよそに、参拝客もまばらで、ひっそりしていました。 大きいだけで美しさにかける大仏さま(大仏殿の建造物は好きだけど)などは横目に、僕が奈良で一番にお会いしたかったのがこの方。 広目天。 戒壇堂の四天王の中で、甲冑や武具などの面では最もひかえめな存在であるにもかかわらず、彼こそが、この日本史上最高の彫像である四天王の4体の中の、白眉なのであります。 そしてその所以は、この眼差しの鋭さです。 実際に拝顔した印象は、こんなに厳ついものではなくて、ごくごく自然に、昔からそこにいらしたのだな、と感じさせる佇まいでした。 ライトアップもされておらず、さして広くもない薄暗いお堂の中に、4人の方がそれぞれの方位を、今も静かに守っておられました。 ごくごく自然に、まったくの日常として。 四天王とは、北の多聞天、東の持国天、南の増長天、そして西の広目天の4人の天部である、仏の守護神のことをいいます。 戒壇堂の四天王は、それぞれが優れた彫像であるだけでなく、それぞれの武具・甲冑・姿勢・手足の動き・表情あるいは足元の餓鬼に至るまで、前後・左右又は対角のコントラスト・シンメトリー、若しくは四方の円のグラデーションをなしており、4楽章の交響曲のような統一感と安定感を持った傑作です(それについて詳細に述べようとするならば、拙い私の見識でも一つの論文が書けるかもしれない。)。 それぞれ、世俗的なご利益があります。 多聞天:知恵、財宝授与 持国天:国家安康、家内安全 増長天:商売繁盛 広目天:知恵、無病息災 多聞天と広目天とでは、「知恵」というキーワードで似ているようですが、多聞天には多くの知恵を得て共に利するという側面がある一方、広目天においては、広く世間を見、大らかな心で視野を広げて、正しい知恵を得ることが、結果的には無量の寿命を得るという意味があるということです。 それはさておき、私が広目天に魅かれるのは、そのドスのきいた目力、ではなくて、その表情の奥に感じさせる豊饒な知識と強靭な精神です。 それでいて、実際に会ってみると、好戦的な雰囲気などまったくなく、泰然自若としていて、むしろ、献身的なひた向きさがあり、指先と腰回りには、ハッとするような繊細さを感じました。 そういう人に、私はなりたいと思います。
2012年05月05日
閲覧総数 11739
-
5

ピン・ポン・パン ~トゥーランドット(荒川静香をたたえて)~
トゥーランドット第2幕第1場面。 ピン・ポン・パンが婚礼と葬儀の打ち合わせをしている。 と言ってもこのオペラの筋を知らない人にとってはなんのことかわからない。 説明しよう。 最初に言っておくが,ピンポンパンと言っても,例の子供向けテレビ番組のことではない。 ピンは宰相,ポンは料理頭,パンは大膳職,架空の中国王朝の大臣たちである。 その国には,トゥーランドットという氷の心を持つ皇女がいた。 彼女はまさしく絶世の美女であったが,求婚する王子たちに3つの謎を出し,それに答えられなかった場合はその王子たちをことごとく刑場に送り込み殺してしまうという,恐ろしい所業を重ねていた。 今回,またひとり放浪の王子がやってきて,トゥーランドットに求婚するしるしである鐘を三度鳴らした。 やれやれ,とピン・ポン・パンの3大臣は嘆く。 事務方としては,あの愚かな若者のために,また婚礼と葬式の準備を同時にしなければならないではないか!どうせまた葬式だろうが。今回で20人目だ。やれやれ。 この第二幕のピン・ポン・パンの場面は,このオペラの中での劇中劇,いわば間奏曲のような役割を果たす。 コミカルだけどシニカルな,官僚又はサラリーマンの哀愁漂う,ちょっと大人向けの「見せる・聴かせる」場面である。 最初に言っておくけど,この第二幕の第一場面,この「ブラームスがお好き」は結構好き。 さて,ここは宮殿の大臣たちの部屋。 ポンは婚礼の準備,パンは葬式の準備。 しかし三人とも,実はこの仕事にうんざりしている。 私たちはとうとう刑吏の大臣に成り下がってしまったのか! ああ,故郷に帰れば,美しい山や竹林や庭や池があるというのに,こんなくだらない儀式のために,私たちは細かいシキタリが書かれた経典を枕に一生を終えてしまうのか・・・ ああ,あの皇女トゥーランドットが生れてからというもの,これではお世継ぎも望めないし,終わりだ,この王朝はもはや終わりだ・・・ 3人は郷愁に浸りながらもこの国の行く末を憂えている。 彼らは止めようとした,トゥーランドットに挑もうとするあの無謀な若者を。 女など捨てろ!それができないなら百人めとれ! 気高きトゥーランドットも, しょせんは顔はひとつ,腕は二本,足も二本,胸は二つ。 たしかに美しく,高貴な血筋だが,足は足,ただの足には変わらぬさ! 百人の女を持てば,馬鹿め,溺れるほど足が持てるのだぞ, 二百本の腕に,二百のやさしい胸だ,どうだ,胸が二百だぞ! 百のしとねだ!百のしとねだぞ! あっはっはっは!あっはっはっは! 一人の女のために命を捨てようとするやつはキチガイだ,行ってしまえ!若者よ! ここはうちのキチガイだけで墓穴は一杯なんだ,よそ者のキチガイに付き合ってる暇はない! それでもあの若者はきかなかった。 やれやれ,どうせまた首がひとつ落ちるだけさ。 姫の謎を解けた者はいない。 ああ,と3人は嘆く。 さらば,愛よ,さらば,わが民族よ! さらば神聖なる血統よ! この王朝は終わりだ! おお,どうか待ちに待った晴れやかな夜が, 姫の幸福な降伏の夜がやってこないものか!(ピン)わしは姫に新床をのべてやりたい!(ポン)わしはやわらかい羽根ぶとんをふかふかにしてあげよう!(パン)わしは寝室に香水を振り撒こう!(3人で)そしてわしら三人で,庭に出て歌おうではないか!(ピン)明け方まで愛の歌を!(ポン)こんな風に!(パン)こんな風に!(ピン・ポン・パン) この中国には,愛を拒むような女はいない! かつてはひとりいたが, その氷のような女も今は火となり燃えている! 姫よ,あなたの帝國ははるか長江を越え広大無辺! だがあの薄いカーテンの向うには, あなたを支配する花婿がおれらるのだ! あなたはすでに口づけのかぐわしさを知り すでに全身の力が抜けてしまわれた, いまや奇跡が起こる,このひめやかな夜に栄えあれ! 栄えあれ,この絹のふとんに栄えあれ! 甘い吐息の証人よ,庭ではすべてがささやき 金の釣鐘草がリンリンと鳴いている, 二人は睦言をささやきあい,花は露の真珠でちりばめられている 帯を解いて未知のひめごとをいまや知る, 美しい五体に栄光あれ! 再び王朝に平和をもたらす, 愛に,陶酔に,栄光あれ!栄光あれ! かなりあけすけな歌であるが,彼らもトゥーランドットの氷の心が溶けるのを心の中では願っているのだ。(「栄光あれ!」は,「グロリア!」と歌われます。) この3人の三重唱はなかなか聞かせる。 が,いいところで邪魔が入り,3人は「仕事」に戻る。 無謀な若者とトゥーランドットの闘いの儀式が始まるのだ。 はたして「謎が三つで死がひとつ」か。 それとも「謎は三つでひとつの命」か! 希望,血潮,そしてトゥーランドット! もちろんトゥーランドットは,ハッピー・エンドで終わる。 「誰も寝てはならぬ」(ネッスン・ダルマ)は僕が最も好きなアリアのひとつです。(そしてこのオペラは僕のツボ中のツボです) 壮大なフィナーレは,この「誰も寝てはならぬ」の旋律に乗って, アモーレ! 永遠の命なる太陽よ! 世界の光たる愛よ! わたしたちの限りない喜びは 陽光の中で微笑み歌う! アモーレ! 汝に栄光あれ!愛に栄光あれ! と大オーケストラと大合唱で感動的に歌われます。 しかしいま,トゥーランドットと言えば, ビバ! 荒川静香 である。 昨夜の彼女は本当に小指の先までしなやかで美しかった。 「人間の身体とは,女性とは,こんなにも美しいものなのか」 と思ったのは久しぶりだ。 鳥肌が立ち,不覚にも涙が出そうになった。 ため息がでるほど見事に日本女性の美しさを表現してくれました・・・ 荒川静香よ,おめでとう! トゥーランドットとともに,汝に栄光あれ!
2006年02月24日
閲覧総数 5431
-
-

- 楽器について♪
- Gibson | ギブソン 楽器 SG STANDARD…
- (2025-04-26 06:58:00)
-
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- 4月20日 石川県加賀市×OCHA NORMA …
- (2025-04-23 08:56:20)
-