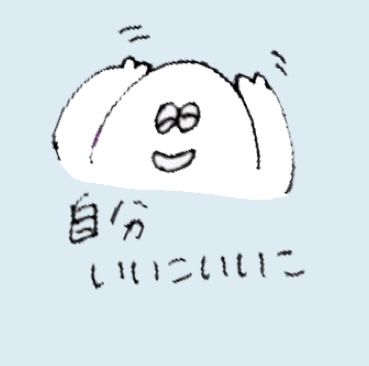全597件 (597件中 1-50件目)
-
ありがとうございます。
昨日は色々な方からお祝いのメッセージを頂きました。本当にありがとうございます。また、日頃からこのページを読んでくださっている皆様方にも心から感謝したいと思います。このページを通じて、私は、自分の気持ちや考えを整理したり、自分の思いのようなものを1つの形にすることができました。拙い文章にもかかわらず、それを読んでくださる方がいることに感謝したいと思います。>blueskyandさん一番乗りのお祝いコメント、本当にありがとうございます(^^)。周りの人が心から喜んでくれると、ようよう実感が出てきます。期待に沿えるよう、無理しない範囲で頑張りたいと思います。>runa♪さんありがとうございます。大学を卒業してから数年、本当にこれからだなあ、と思います。頑張りたいと思います。>allison77さんありがとうございます。希望する進路に無事進めるというのは本当にありがたいことだと思います。立派な裁判官になれるかどうかは分かりませんが、とりあえずきちんと仕事と人に向き合って、頑張りたいと思います。>ヴィヴィさんありがとうございます。本当に神経を使う仕事だと思うので、体の健康も心の健康も気を付けつつ、頑張りたいと思います。本当にありがとうございます。>剣竜さんありがとうございます。一夜明けて、ようやくほっとして、少しずつ実感が湧いてきたところです。あまり冷静でも論理的でもないので(汗)、これからもきちんと勉強しないと、と思っています。いつか法廷でお会いしたときには、どうぞお手柔らかにお願いしますね。ガンガン異議とか忌避とか出さないでくださいね(^^;;)>☆☆HIRO☆☆さんありがとうございます。一裁判官として何をどこまでできるか分かりませんが、きちんと誠意を持って、頑張りたいと思います。HIROさんも、環境が変わって何かと大変だとは思いますが、頑張ってください。応援しています。>ぼのやんさんありがとうございます。本当に、柿8年ではないですが、一人前になるのに時間のかかる仕事だと思います。やはり、最初の数年でかなり柿のおいしさも変わってくるようなので、日々鍛錬と思って頑張りたいと思います。>Johnniyさんありがとうございます。どこに転勤になっても、やはり体が資本だと思うので、体調には本当に気を付けつつ、頑張りたいと思います。>たかむーさんありがとうございます & おめでとうございます!同期の裁判官同士、長いお付き合いになるかと思いますが、これからもよろしくお願いします。>yjochiさん初めまして、どろっぴーです。お祝いの言葉を頂き、ありがたく思っています。また、先日もブログの方で取り上げて頂き、ありがとうございました。裁判官に対する期待や思いというのを、まだまだ自分のものとしては掴めておらず、環境が変化することについて正直心配も多いのですが、目の前の人、目の前の1つ1つの事件にきちんと向き合いつつ、なんとか頑張りたいと思っています。>やむやむ1101さんありがとうございます。周りの状況にも恵まれ、自分の行きたい方向に進めたことをありがたく思っています。日本の重要な役割を担うという実感は正直まだ湧きませんが、目の前の人、事件にきちんと向き合うことから始めたいと思っています。今後も、うまく言葉が見つかったら是非書き込みしていってくださいね(^^)。ありがとうございました。>パンドラの箱6949さんありがとうございます。公正であること、そして、人からも公正であると信頼されることは、とても難しいことだと思いますが、頑張りたいと思います。>kaomayaさんありがとうございます。忙しさに潰れず、クールブレインにホットハートで頑張って行けたらいいなと思います。いや、ホットブレインもやはり必要かもしれません。なんにしても頑張りたいと思います。>8はちさんありがとうございます。周りの状況と幸運に恵まれて、こういう段階を迎えられたことを感謝したいと思っています。熱い弁護士さんになられた8はちさんと法廷でお会いできる日を楽しみにしています。>なびさんありがとうございます。心身共に健康に留意して頑張りたいと思います。>有香3315さんありがとうございます。どこまでできるか分かりませんが、頑張っていきたいと思います。>岡村善郎さんありがとうございます。岡村先生のように、誇り高く、理念があり、かつ、気骨ある法律家になりたいと思ってます。>takataka5150さん ありがとうございます。本当にこれからが本番ですので、なんとか頑張っていきたいと思います。
2004年10月07日
-
ご報告
さきほど採用内定通知を受け取りました。判事補として某地方裁判所に採用されることが内定しました。今までこのページを通して、色々な方に応援して頂きました。本当にありがとうございました。まだまだ実感は湧かないのですが、家族や周囲の人が非常に喜んでいてくれて、そのことがとてもありがたいなあと思っています。これからも健康に気を付けて頑張りたいと思います。まずはご報告まで。
2004年10月06日
-
祝1000日目
おかげさまでホームページ開設1000日目を迎えることができました。皆様ありがとうございます。明日、10月6日に裁判官の採用内定通知あるいは不採用通知が来ます。受験生の時から、ホームページをやり始めたときからそれこそ1000日くらいかかって、こういう段階を迎えるというのは、なにか不思議な気分です。1001日目に、今後の職業が決まるというのも妙な気がします。まあ、単なる偶然といえば偶然かもしれないですが。振り返ってみると、司法試験に最終合格してからの時間の流れが、非常に早かったように感じます。受験生の時は、基本的には答練、そしてその前提になる試験のスケジュールに対応した季節の流れを感じていたので、生活のリズム自体は余り変わらないイメージがあったように思います。合格後は、修習に入るまでに色々やっておこうとして免許の取得なり旅行なりと、環境の変化がありますし、また、それらの資金源としてバイトを日常的にやるようになるので、そこら辺で徐々に日常生活の中でも時間の区切りが出てきます。修習に入ると、基本的には3か月単位での環境の変化があり(前期修習3か月、実務修習1年、内訳として、検察3か月、弁護3か月、民事裁判3か月、刑事裁判3か月、後期修習3か月。私の期は修習期間が1年半です)、特に一年間の実務修習期間は大きな変動ですし、その期間中も法曹三者それぞれの立場を見ると言うことで、かなり気持ちの変化があります。それぞれの立場になりきって、色々思考を巡らせ思いを馳せるというのが実務修習の醍醐味だからだと思います。また、後期は2回試験に向けて怒濤の起案ラッシュでして、非常に時間の経つのが早いです。矢継ぎ早にやってきます。また、この期間を通じて、朝起きて夕方まで仕事をするというごくごく当たり前の社会人生活を体験し、多くの、そして様々な大人、社会人に会うことで、自分自身もかなり社会化が進みます。社会は非常に速いスピードで動いているような気がします。本当にみんな忙しそうです。それに合わせている間に時の流れを早く感じるようになるのだと思います。とりあえず1つの区切りと言うことで、振り返ってみました。
2004年10月05日
-
悩ましいですね
57期修習生のホームページを見ますと、多くのページが2回試験の合格発表や検事任官をもって、閉鎖なり停止なりという形を採っています。最果ての地で修習された方のページも最近は見ることができなくなってしまい、また、検事に任官された3人の方のページも更新停止という形になりました。寂しい余りです。この業界、守秘義務という重い義務があり、また、検事や裁判官については、公務員の中でも、司法関係と言うことで、表現の自由については特に重い制約が課されています。また、検事については組織体としての要請も大きく、一検察官が自由にホームページ上で意見を言うというのもなかなか難しいようです。裁判官についても、一時期ほどではないにせよ、上からの縛り、というのはやはり結構あるのではないかと思います。出すぎた杭は打たれないかもしれませんが、出る杭はやはり打たれるでしょう。ただ、私が今思うのは、法曹界、とりわけ裁判官については、ごく普通に生活している人にとって余りにも縁遠い、かつ、イメージが掴みにくい職種であるということです。裁判官という仕事に就いている人も、事件の真相がどういうものなのか普通に悩んでいることや、判決を出した後も本当にその判決が正しかったのかどうか、時にくよくよしているところもあることなども、分かって頂きたい気もするわけで、もちろん、それでもきちんと仕事に向き合って頑張っているわけで、そう言う意味で、もうちょっと裁判官という仕事について具体的な良いイメージを持って頂けたら、とも思います。まだ私は裁判官でもなく採用待ちの人間に過ぎないのですが、実務修習地での裁判官の様子や、研修所の教官の様子を見るにつれ、多くの裁判官がそうしたイメージをより広く持って頂きたいと思っているように見受けられます。より広い意味では、裁判というものに対して、また、裁判という場で前提となる法律というものに対して、もっと広い関心を持って頂けたら、と思っているように見受けられます。基本的に裁判所はあんまり行きたくない場所かもしれません。しかし、やっていることはごくごくまともなことです。法廷が近くなると言うことは、訴訟などの揉め事が表沙汰になりやすいと言うことでもありますが、同時に、やくざさんなり怖い人なりをそれなりに静かにさせつつ、交渉させることもできますし、うやむやにされて誤魔化されていたことをそれなりに明るみに出すこともできるわけで、社会的に見て、結構、というか、かなり健全なことをやっていたりします。あるいは、裁判官を批判する論説や出版物もありますが、それらは確かに存在するかもしれませんが、それはやはりごく一部だと言うことを分かって欲しいというのもあるかと思います。(ここから先は任官希望者の採用待ちの心理状態というのを踏まえた上でお読みください。)そう言う意味で、私がこのページを続けることの意味はあると思います。ただまあ、走狗と見られて、誰かから利用されるのも嫌ですし、組織内で変な目で見られるのも嫌です。なんらかのプレッシャーを受けることもあるのではないかと、今更ながら萎縮的効果を感じることもあります。例えば、このHPが不利益評価されて、裁判官の公正らしさに欠ける、と判断されて、採用試験で落ちていることもあるかもしれません。実際にそういう事実があるかどうか、というのも問題ですが、同時に、任官希望者が何らかの形でそう言うプレッシャーを感じていると言うこと自体がこれがまた結構な問題なわけです。立場上、発言に気を付けないと行けないのはもちろんなのですが(あんまり好き勝手なことを行っていると信頼を失いますしね)、社会生活の範囲、要は色々と遊びに行ったり、社会勉強したり、新しい友達付き合い、人間関係ということについても、どうにもこうにも億劫になってしまいがちにならないか、ということです。基本的にはたぶん考え過ぎなのですが、要はそれだけのプレッシャーを感じてしまうというのが問題なのだと思います。もちろん、最初に述べたとおり、採用待ちの不安定な状態だからここまで感じるだけなのかもしれませんが。そう言うわけで、今後のこのページの行方については未だ悩み中です。難しいですねえ・・・。
2004年10月04日
-
昏々と+口述関連
眠っております。やけに眠いです。疲れがどっと出ている感じです。そうは言いつつ、以前に買った「野中広務 差別と権力」魚住昭著を読みました。シビアな話でした。影の総理とまで言われるまでに至った経緯、特に中央政界に打って出るところ辺りまでは非常に読み応えがありました。その後、政争に敗れ、引退するに至った辺りは、読んでいて寂しい気もしました。人には旬というものがあるのかもしれないなあ、と思います。法曹界の先輩方には、「細く長く」でいい、とおっしゃる方が多いですが、それだけ弁護士にしても、検察官、裁判官にしても、身を滅ぼす人が多いようです。懲戒しかり、左遷、辞職、罷免しかり、と言った感じでしょうか。明日、実務庁にご挨拶に行く予定です。任官はまだ決まっていないのですが、無事修習を終了したということのご報告とお礼と思って行く予定です。6日に、採用内定通知が来たら、またご報告することになります。その際は、お手紙という形になりそうです(電話というわけにはやはりいかんのだろうなぁ・・・。)。はてさて、いわゆる社会人としての生活を送っていなかったせいか、今後は、礼儀という部分でかなり気を遣わないといけなさそうです。やはり転勤族ですので、遠隔地間でのご挨拶となると手紙などが必須となりますし、そういうのをやらないと何かと苦労するみたいです。そこら辺は、おそらく色々な形で目上の方から教えて頂く形になるのでしょうが、ん~、個人的にちょいと苦労しそうです。手紙は苦手ですねぇ・・・。そうそう、そろそろ論文試験の合格発表が近づいている様子ですね。なかなか落ち着かなくて、勉強が手に付かないと言う人も多いかと思いますが、そう言う人も、発表後、合格していた場合、どのような動きをするのか、勉強のスケジュール、口述模試の受験の申し込み、スーツの持ち合わせがないのであればスーツの購入、そのためのお金がないのなら誰かから借りる算段を付けるとか、色々あるかと思います。スリッパとかそう言うのについては、前の方の日記で書きましたが、余り華美に至らないものであれば良いと思います。基本的には、お堅い職種(銀行とか、お客様の信頼が大切な職種)の就職面接だと思って、服装を考えれば問題ないと思います。あと、関東圏の人は、口述会場の下見に行かれるのも良いかと思います。浦安の方で、駅からバスを使うことになると思いますので、またバスも本数が少ない直通と、途中までバスで、5分くらい歩いて会場に行くルートと(全部歩くと結構かかる)ありますので、チェックしておくと良いでしょう。レックかどこかの予備校が直通バスを出してくれますが、アンケートなどに答えないとバスに乗せてくれないはずですので、そこら辺も鑑みて、試験時間に遅れないようにしておくと良いかと思います。で、具体的な勉強のスケジュールについてですが、たぶんろくに準備していない方が多いと思うのですが、発表までの期間、全部勉強に集中していられるかというと、上述の通り口述模試やスーツの購入などで、結構時間を食われます。なので、よくよく気を付けましょう。口述模試も丸一日かかりますので(なぜなら、刑事系民事系各40分+憲法20分で、計1時間40分に加え、かなりの待ち時間が生じるから。)、注意した方が良いでしょう。私は口述模試については、確かレックは抽選で外れて、辰巳で一回受けたきりだと思います。基本的に、口述模試は、できるだけ早い時期に受けると良いでしょう。雰囲気を掴めば、その後の勉強もしやすいからです。で、信頼の置けるテキストなり基本書の通読と、条文素読とがメインとなると思います。基本的には論文直前記の勉強と同じで十分ですが、条文の番号については必ず、規則についてはなるべく引いて覚えるようにしましょう。試験官が聞くのは、まず定義、条文です。事例問題の場合は結論です。定義条文で躓くと心理的ダメージが大きいので、よくよく注意して、テキストを読み込み、条文を引き引き、定義を覚えてください。
2004年10月03日
-
久々の無職生活
というわけで、昨日無事に修習を終了して、無職と相成りました。カテゴリーも、「前期・後期修習」というカテゴリーを付けるわけにも行かなくなり、環境は変わったなあと言う感じです。ちなみに、検察官になられた人については、10月2日付けだったかで辞令が出ているようで、無職になる間もなく、みなし公務員(修習生)から、本物の公務員へと身分が継続している様子です。また、弁護士になられた人も、日弁連の検索ページから既に名前を探せるようになっており、職業は弁護士です、と宣言できるようになっています。私も知り合いの名前を検索してみて、おおっ、なんか格好良いな、とちょっとうらやましかったです。検察官は、この日から寮に入って研修生活です。弁護士さんも、この週末のどちらか一方はいわゆる日弁連(日本弁護士連合会)で研修があるそうです。さて、裁判官の方は、10月6日に採用内定乃至不採用通知が来て、同月12日に説明会、同月18日くらいに辞令交付だったかと思います。また、採用選考の方は、下級裁判所裁判官指名諮問委員会という最高裁判所の諮問機関が行います。この委員会は、10月4日に開かれる予定で、作業部会というのがこの10月2日から開かれる予定だそうです(それぞれ最高裁のHP、司法制度改革コーナー、下級裁判所裁判官指名諮問委員会、開催状況第8回議事録から)。なお、開催状況第1回には、参考資料として、12 現在の裁判官指名手続の実情に関する資料 というのがあります。なお、志望調査カードについては、おそらく去年か一昨年のものだと思います。既に57期である私が書いたものとは内容・書式共に異なっています。私自身は、新しいものに変わって良かった、と心底思っております。なお、参考資料については、実務修習中の成績報告書もあり、興味深いかと思います。そうそう、司法修習という制度自体については、一般向けのものとして、同最高裁のHPの中のindex 裁判所の案内、司法研修所というコーナーがあります。こちらの方がより分かりやすいと思います。また、同じく司法制度改革コーナーの司法修習委員会のページの方も見てみますと、修習成績の付け方についても色々と参考資料があり、興味深いかと思います。第6回の配付資料などが、そこら辺について書いてあります。なお、法科大学院生の方には、この司法修習委員会の議事録は結構参考になると思います。実務修習のあり方や研修所・2回試験のあり方についても記述がありますので、暇なときに(あんまりないかもしれませんが)読んでみると面白いかもしれません。最近情報公開の波は結構進んでおり、委員会の資料や議事録というのを見てみるのも、今後の流れの予測としては面白いかもしれませんね。修習生活、1年半ほどありましたが、本当に楽しかったですね。2度目の高校生活と言われるのも分かる気がします。クラス制というのも良いものだと思います。同期同クラスは一生の付き合いになると言いますが、これは本当だなあと思います。何かと頼りになる人ばかりだと思いますしね。司法研修所は、いずれ廃止になるのが今のところの流れのようですが、やはりとても楽しいところでもありますし、切磋琢磨の場としても優れている点もあり、ノスタルジーかもしれませんが、ぜひとも残して欲しいと思います。2回試験については、落合先生のブログでもご指摘がなされていましたが、もう少し改善の余地があるかと思います。司法修習生に関する規則では、いわゆる2回試験(司法修習生考試)の、合格不合格は、日頃の修習成績をも参考に判断されますが(先の司法修習委員会第6回議事録 配付資料24-1 司法修習における成績評価の実情より。司法修習生に関する規則第16条。制度的担保として同第13条、10条)、実際の試験結果としては、合格・不合格の他に、合格留保というものがあります。そして、今回は43名が合格留保という形になっています。この合格留保の根拠については定かではないのですが、2回試験の成績がまずかった場合の救済措置として追試をするということになっています。なお、試験官に対しては、氏名をブラインドにして、起案の答案用紙だけを基に、合格、合格留保・不合格を判断するようになっている様ですので(噂ですが)、とりあえず何らかの形で、合格留保乃至不合格としよう、という暫定的な結論を出した後、日頃の修習成績を考えて、留保と不合格とを分けるという形にしているのではないかと思います(推測です。)。確かに合格留保という形は、不合格ではなく、救済措置なのではありますが、やはり一発試験の要素が強すぎるのではないかと思います。もちろん、身近な人が一次的とはいえ残念な結果になってしまったことによる、身びいきなのかもしれませんが、もう少し改善の余地があるのではないかと思います。今回の2回試験で、結構きつい結果が十分にあり得ることが周知されました。これにより、楽勝と思って修習生活を送ってきた人の中にも、修習に真剣に取り組む人が増えると思います。それ自体は良いことだと思います。でもですね~、どうも、交通事故のような合格留保が多いのではないかと思うのです。こればかりはなんともし難いのでしょうか。まあ、一回目の試験の司法試験では、そんな甘っちょろいことが許されないことからすれば、やむをえないのかもしれないですが、ん~、合格留保があるだけましと考える方が良いのかもしれませんが・・・。年末に追試がありますが、それまでの約2か月半、留保の方は相当勉強されると思います。このことで、より優れた法律家が現れることは確実です。実際、2か月半後には法律知識等で大差をつけられている可能性も十分あります。いずれにしろ、ぺいぺいの法律家である私が(法律家と自分で言うのも、まだ危なっかしいですが)、勉強をサボれる理由にはなりませんので、しばしの休養の後は、きちんと勉学に励みたいと思います。ではではまた。
2004年10月02日
-
卒業です
10月1日、無事司法修習を終了しました。各教官からの講義の後、全体での修了式があり、その後、クラスの一人一人に対して終了証書の授与がありました。昨日の日記に書いたとおり、今年は多数の合格留保者が出ました。そして、非常に残念なことに、我がクラスからも、3か月後に卒業を迎えることになる人が出てしまいました。普段の勉強態度や成績を見る限り、「えっ、どうしてこの人が」という人が留保となっており、まさしく想定外な結果でした。日頃からこの人大丈夫かなあ、と言う人が落ちたと言うよりは、何でこの人を落とすんだ?という印象が非常に強かったです。そもそも、2回試験というのは、修習を終了するに当たって、すなわち実務法曹として旅立つに当たって、法曹としての最低限の知識や技能を身に付けているかどうかをチェックする試験と言われています。しかし、その最低限の知識や技能をチェックするための方法として、今現在行われている試験というものが適しているものなのかどうか、その点についてはかなり疑わしいと言えるのではないでしょうか。確かに、試験は試験ですから、成績の良い悪いや順位というものは明確に出るわけで、その成績の悪いこと自体はやむを得ないのですが、2回試験の成績が悪いことと、法曹としての適格がないこと、というのは、全くリンクしていないように思います。物差しを変えない限り、不合理な結果を蒙る人が出てくるのは避けられないわけで、非常に残念です。ただ、我がクラスの留保者は、逞しく次のステップに向けて心の準備をしているようで、何よりだと思います。おそらく留保というレッテルは、今後も付いて回ることになるかと思いますが、人生万事塞翁が馬ではないですが、きっと大物の弁護士、あるいは人の心に近い弁護士になるのではないかと思います。3か月にもう一度卒業式をやれることを心から楽しみにしたいと思っています。にしても、試験の公平性の維持や参考文献やパソコンを1000人分以上そろえることの難しさから、法律家にあるまじく、六法と白表紙しか見ないで、準備書面や判決書を手書きで書かなければならないというのは、やはり疑問な気がします。準備書面を書くときにろくに文献を参考にしない(もちろん、時間的にきちんと見ることができないときはかなりあると思いますが)こともないでしょうし、もう少し何とかして欲しいものだと思います。かなり衝撃が大きかったので、お礼が遅れてしまいましたが、応援頂いた皆様方、本当にありがとうございました。裁判官任官の採否は10月6日のこととなりますので、まだもう少し時間はかかりますが、とりあえずご報告とお礼をさせていただきます。それではまた。10月1日、研修所での修了式を終えた後、謝恩会二次会と続きました。用意周到に巧みに準備された進行で、非常に楽しいひとときを過ごすことができました。幹事の方々には本当に感謝したいと思います。また、教官やクラスにも恵まれて、楽しい修習生活を送ることができました。実務修習中も、指導担当や同僚に恵まれ、充実した一年を過ごすことができました。ある教官がおっしゃられていましたが、君らがここにいることは、もちろん君らの努力に依るところも大きいのだが、ただしかし、環境が幸運にも君らにそれを許したというのに過ぎないと言う面もある。環境ゆえに、君らより能力がありながら、ここに来れなかった人たちもいる。君らは、そう言う人たちの思いも背負っているのだ。権限と地位を持つに至ったものには、それ相応の責任と義務を果たすべきということでしょう。公費での研修という司法修習制度が終焉を迎えつつあり、個人が私費で法律家になる時代が近づいてきました。弁護士は、当事者の利益を代弁し、擁護するものであるという以上に、法の支配を現実に及ぼす担い手としての一面を有しています。より分かりやすく言うと、やくざがバックにいる闇金は、違法な金利で、債務者の生活を圧迫し、それこそ身ぐるみはがして売り飛ばしたり、というようなこともしかねません。しかし、弁護士が入り、そこまでの金利は取れませんよ、もう返済は不可能ですから破産手続に入りますよ、と闇金の横暴、人格を無視した取立、生活破壊を阻止し、債務者をそれなりの方法で、更生させます。そうすることで、やくざに騙されて借金まみれになってしまった人でも人間らしい生活を送ることができます。ところで、借金まみれになっている人がどれだけの弁護報酬を支払えるでしょうか。例えば、事件を起こしてしまった被告人は、やはり厳しい生活環境を持っています。家族との関係が切れてやけになって犯罪を起こしてしまった被告人を、例えば、再び家族の元に返らせることができたなら、その被告人は、二度と犯罪を犯さないかもしれません。ただ、そう言う被告人は、しばしお金がありません。国選弁護という決して弁護費用としては高くない金額で弁護士が動くのは、やはりその被告人のためであり、そして、その被告人が更生することによって、再び犯罪が起こらないと言う意味で、社会のためでもあります。そういった公益的な活動を担う弁護士という職業を、公費で育てるというのは、きわめて政策的に有意なことであるにもかかわらず、今後は公費での教育をやめることになります。ロースクールの学費に加え、司法修習時代の給与は貸与制となり、公費はかなり削減されることとなります。国から給与をもらったから、弁護士は公益的な業務に就く、というのでは、志が低すぎる、と批判する人もいます。弁護士は社会生活上の医師に喩えられます。医者については国からの給与制が導入されたそうです。医師は、国からの給与をもらわないと、公益的な業務に就かないのでしょうか。およそ医療制度を国全体に普及されるのと同じくらい、法の支配、より分かりやすく言えば、殴られたり、名誉を傷付けられたら法廷でその損害を回復することができる、無実なのに逮捕されたら、釈放を求めることができる、やくざに絡まれて因縁を付けて脅されたり、総会屋に取り込まれそうになっても、法律のプロである弁護士に助けを求めることで、その難を逃れることができる、という社会にすることは大切なことです。そのために、今まで修習生について給与制が取られていたのでしょう。公費での教育を受けた最後の世代として、果たすべき役割を果たしていこうと思います。
2004年10月01日
-
不合格3名・留保43名
タイトル通りの結果となってしまったようです。10月30日時点では、私は伝聞情報としてしか知りませんでしたので、日記自体は特に編集はせず、原文のママ残しておきます。伝聞なので、正確なところは分かりませんが、不合格者が3名、合格留保者が43名出た模様です。不合格者3名については、おそらくは欠席の方と思われます。合格留保者については、実際に試験は受けたが、3か月後の追試を受けるに至った方となります。かなり衝撃です。一昨年くらいに初めて19名という合格留保者が出て、騒ぎになったのですが、今年はいきなりその倍以上と言うことで、かなり騒然としているようです。なお、私自身ですが、私は発表を見ずに帰ってしまったため、どちらか分かりません。まさかここまでの人数になるとは思っていなかったので、いまさらながらちょっとびくびくしています。たぶん大丈夫だとは思いますが・・・。なお、合格留保者については、発表後一カ所に集められ、今後の予定について説明があったそうです。しかし、かなりの激震が走っています。噂では確かに数十名という噂が流れていましたが、いざ実際にそうなってみるとかなりの衝撃です。私自身は大丈夫かとは思いますが、明日きちんと確認を取るまで、レス等が遅れてしまうことをお詫びします。しかし衝撃でした。今日はこの辺で失礼します。<追加>さきほど番号を確認してもらいました。私は無事合格した模様です。ただ、他の人のこともあり、正直に言って余り喜べる状況ではありません。今日はこの辺で。
2004年09月30日
-
あと2日
明日、明後日で、司法修習も終わります。明日は、外部講師による講演が3連続であり、夕刻には2回試験の合否が発表になります。明後日は、刑事弁護、民事弁護、検察、民事裁判、刑事裁判の5科目それぞれの最終授業があり、最後に修了式があります。その後、クラスごとに謝恩会なりの催しが自主的に行われます。
2004年09月29日
-
口述試験順位開示への動き
口述試験の総合順位については、合格者も知ることができるようになりそうです。なお、論文試験の科目別順位については開示を認めなかったそうです。私は聞いてみたいような聞いてみたくないような、という感じです。ttp://www.asahi.com/national/update/0929/036.html
2004年09月28日
-
外部講師による講演
商事仮処分租税事件と立証方法企業法務と弁護士それぞれ外部講師による講演でした。裁判官、検察官志望の人は、明日、明後日に面接を控えているため、色々な噂が飛び交っております。しかし、実際のところ、2回試験の成績に関する情報は、教官のところには行っていないようで(従前がどうだったかは不明です。)、余り信憑性がないようなあるような、という感じです。結局、合否ラインというのは毎年採用人数と募集人数との関係で変動するようで(裁判官の場合)、また、そうは言っても、やばいだろうと言われていても受かる人もいるようで、これは何とも言えないようです。検察官の場合は、あんまりそう言う意味での変動は少なそうです。よっぽど成績が悪いときは何かあるかもしれませんが。ん~、なんとも言えませんが、2回試験の成績については、少なくとも現在の時点では教官には行っていないと言う印象を持ちます。後日どうなるかは分かりませんが。なお、司法試験の成績については、教官は知らないと言う建前になっていますし、実際教官もそのようにおっしゃっていますが、本当のところは分かりません。裁判官の採用面接では、局長クラスが6,7人(結構な重鎮クラスだと思われます。)、一人の受験者を面接するそうです。で、2回試験の成績、実務修習、後期での成績、さらに、この面接の結果、願書等々を基に、第三者機関である下級裁判所裁判官指名諮問委員会が採用の是非を判断することになるそうです。ん~、やっぱり緊張しますねえ。まあでも、今日会った任検希望者や任官希望者の様子を見る限り、今更落ちないだろうけど、まだ面接もあるし、落ち着かない感じ、というのが実情でしょうか。帰り際にあった人が随分と機嫌が良さそうだったのが印象的でした。そうそう、先日、再びクラスの人に、このページを発見されました。いやー、なんか照れますね。自分がページを持っているらしい、というのは何人かは知っているようで、ちょっと意外でした。まあでも、しばらくは内緒にしていたいので、私のことを直接知っておられる方は私だけにこそっとお話ししてくださいね。他の人には内緒にしておいてくださいね。クッキー情報楽天も結構有効期限の長いクッキー情報を設定しているようですね。一番長いのは3年くらいの長期のものでした。まあ、便利は便利ですけどね。ちょいと長すぎる気がしました。まあ、クッキーとかネットの仕組みはあんまりよく分かってませんが、自衛手段としてちょっとは理解しておかないと、と思います。
2004年09月27日
-
編集中
過去日記を編集中のため、昔のページが表に出ているかと思いますが、内容的には変わっていません。一応、司法試験関連(受験生時代)、合格から修習開始まで、前期・後期修習(司法研修所での集合研修)、実務修習期というカテゴリーで分けています。また、新しいカテゴリーも実務に就き次第、作ろうかと思います。とはいえ、内容についてはまだまだ悩み中です。sweet プチという雑誌を、オール読みきり傑作ラブコミックをコンビニで買ってしまいました。おもいっきりcute&H!シゲキ的恋愛マガジンらしいです。一通り読んでみたのですが(たいしてH!シゲキ的ではありませんでしたが)、やはり女の子の感じ方というのは、随分男性と違うのだなあ、というのが感想です。私にはなかなか感情移入が難しいですね。ではではまた。
2004年09月26日
-
クラス旅行続き+あと6日
宴会、温泉、各部屋での2次会、翌日は野外プログラムと言った感じでした。前期のクラス旅行と比べて、それぞれの距離感の取り方もお互い分かっているところが大きく、個人的には非常に過ごしやすい旅行でした。また、クラスの人の、普段とは違う面を発見したり、透明度の高いきれいな心情に触れることもできて、しみじみと快い気持ちを抱いたりもしました。魅力的な人を見ているのはそれだけで心地よいものだなと思います。クラスの行事としては、このクラス旅行が終わると、修習修了後の謝恩会というか打ち上げを残すのみとなります。いずれにしても、こういう企画ものの幹事をやって頂ける方には、頭が下がります。とりわけ2回試験直前の時期から色々と準備もあったことも考えると、本当に恐縮しますし、感謝したいです。また、何らかの形で企画段階から関わろうという気持ちを持つ余裕が私にはなかったのだな、と今振り返ってみると気が付きます。しかし、仲の良い修習生同士で、どうでもいいことをだらだらと語れるこの時間がもうすぐ終わってしまうと思うと、時の流れは本当に速いと感じます。修習生で居られるのもあと6日です。「57期修習生の○○です」から、「弁護士の○○です。」、「裁判官の○○です。」、「検察官の○○です。」、にそれぞれ変わります。初めて着る、着慣れない服を着るときのように、新鮮さと緊張感、そして不安が入り交じる物事の始まりが、いよいよ近づいています。
2004年09月25日
-
講義+クラス旅行
この日は、外部講師を招いての講演が3本立てであり、講義終了後、その足で一泊二日のクラス旅行に行きました。他のクラスでは、土曜日からの一泊二日旅行も多いようです。ところで従前は、2回試験終了後一週間くらいは丸々休みがあったようで、この時期は結婚式ラッシュだったそうです。その足で新婚旅行という感じみたいですね。外部講師を招いての講演の方は、医療過誤訴訟(医療側) 児玉 安司否認事件弁護のすすめ 升味 佐江子弁護士業法と税務 永島 正春 (敬称略)の3つを受けました。医療過誤訴訟では、医療側はとかく悪く言われ勝ちですが、医療ミスというものの事実的背景や、組織法としての医師法が極めて貧弱であること、医療過誤保険の脆弱性、などなどを考えると、マスコミが言うことを鵜呑みにすることがいかに危険なことか、というのがよく分かりました。うーん、ちょっと上手くまとめ損なってますが、株式会社に関する法制度が商法の改正で逐次バージョンアップされているのに対し、病院という組織体においては、上場企業レベルの病院においても、ろくに組織の自治や権力分立、会計面の明朗化などの措置が採られていないことを、書き残しておきたいと思います。否認事件弁護のすすめは、99,7%の有罪立の中で、否認事件弁護をする弁護人の悲哀を感じさせるものでした。講師の修習生時代の刑事弁護教官がおっしゃった言葉が印象に残りました。「刑事裁判において被告人の権利を守るものは誰ですか。検察官ですか。(いいえ。)裁判官ですか。(いいえ。)じゃあ、誰ですか。(弁護人です。)それなら、全てをやってみなさい。被告人のためなら、違法でないことは全てやるんです。弁護人の対面なんて問題になりません。」土台無茶なことをやろうとしているのが刑事弁護人というのが実情ですが、だからこそ、下手な対面にこだわらず、やれることを最後までやるその根性こそが刑事弁護人の本質なのかもしれません。っていうか、弁護士にしても検察官にしても裁判官にしても、どれもそれがスマートに見えるとしたらたぶん幻想です。どれもこれも泥臭いです。少なくとも自分がきれいにスマートでいられるなんてことはないと思います。泥まみれになって恥をかいて、それでようやく仕事になるんだと思います。恥をかくのが嫌だからと通り一遍の仕事をしていたら、自分がなりたい法律家にはなれないだろうし、いずれきつい形で、しっぺかえしを食らうと思います。それでも恥をかきたくなかったら、日頃から勉強すればいいし、手を抜かないできちんと向き合えばいいと思います。そうは言っても、もちろん恥をかかないと成長しないのですが。恥をかくのが嫌だからと何もせずにいたら、自分のせいで一人の人間の人生が決定的に変わってしまうこともある、その恐ろしさにどれだけ自覚的でいられるかはとても大切なことだと思います。おっかない仕事だと思います。クラス旅行ホント楽しかったですね。最初は2日目すぐに帰ろうかなとか色々考えていたのですが、最後まで居て良かったなと思います。クラスの人たちと一緒にいる機会もあとわずかと思うととても寂しかったですね。これから皆それぞれの人生を色々な形で歩むのだろうし、10年後、20年後にはどうなってるか本当にわからないなあ、と思います。今はまだまだ対岸の火事ですが、弁護士会から懲戒を食らったりすることもあるかもしれないし、事実上罷免されることもあるかもしれないし、誰かが刑務所に入ることになることもあるかもしれません。修習生になり、いよいよ実務に就くというこの時期になると、それぞれの人生の軌跡というものに思いを馳せたくなるのかもしれませんね。
2004年09月24日
-
今日の購入書籍関係
リーガルマインド会社法 第8版 弥永真生野中広務 差別と権力 魚住昭法学教室10月号(今更ですが)週間STanan落差が激しいですが、最後のはとりあえず米倉涼子の写真は見てみたいと言うことで、買ってしまいました。中吊り広告の威力を見た気がしますね。ではではまた。法学教室10月号には新司法試験のことが結構詳しく書かれているようですね。ぱらっと見た感じですが、それなりに枠ができてきているようで驚きました。新司法試験のプレテストというのも来年の夏に予定されているそうですね。どんな問題になるのか早く見せて欲しいと思います。
2004年09月23日
-
目的意識論 +お勧めHP
受験生へのお薦めページ(それ以外の方にも十分お勧めですが)ヒーリング司法試験私が尊敬する人の一人です。私が受験生の頃には、もう合格されていて、いまは京都で独立開業されている弁護士の先生です。このページの中でなにより参考になるのは、やはり「学習方法考察のページ」の「目的意識論」だと思います。私が受験生の頃はPART5までの未完でしたが、今は完成しています。この目的意識論のスピリットを自分なりにであれ、捉えられたこそ、私も合格できたのではないかと思います。「なんのため」に自分は今この勉強をしているのか、それを明確に意識した勉強の重要性、そしてそういう勉強をするための方法論について詳細に書かれています。また、癒し系のページは、答練でささくれ立った私の気持ちを慰めてくれました。ヒーリングコラムは、それぞれが興味深いです。このページ全体に、目的意識論とその考え方の柱が行き渡っていますので、ぜひお時間のあるときに読まれると良いかと思います。っていうか、本当にお勧めです。常に目的を意識して勉強すること。すごく難しいですが、これが出来れば、かなり結果に近くなると思います。予備校答練や授業でも、結構こういった目的意識論は有形無形に出てきているのですが、どうも受験生の立場だとその場限りのものになってしまいがちです。あるいは、そういった目的意識論を理解させないで、カリキュラムに乗って行けば全部大丈夫みたいなノリになってしまい、結局大金を予備校に入れる形になってしまったりします。ただ、目的意識論を十分に踏まえながら、授業や答練を受けることは、有益だと私は考えます。LECの柴田先生は私は凄いと思うのですが、あの先生が凄いのは、明確な目的意識を持たれて、講座設定をしていることです。その講座設定の趣旨を受験生が理解できているかどうかは別にして、きちんと理解できれば、その受験生は自発的に目的意識論を余り意識しないでも、柴田先生の意図を理解して勉強すること=目的意識を持って勉強することという構図になり、勉強を進めることが出来るようになります。もっとも、最初から相性が合うかどうかは分かりませんし、当初に述べたとおり柴田先生の意図をどれだけ理解できるかというのも重要な問題です。表層の方法論だけ学んでも効果は上がりにくいからです。どちらにしても、マスプロ授業を基本とした予備校の授業や答練においては、自分にとって欠けている部分を補う個人個人、人それぞれの目的意識論が不可欠です。その目的意識論を身に付けるために、ヒーリング司法試験をお勧めする次第です。<お勧めページ>今日は、目的意識論という点で、ヒーリング司法試験のページをお薦めしましたが、私が受験生時代によく参考にさせて頂いたページとして、・リーガル・ホームページ K.Otomoさんのページ(56期)勉強法や対談コーナーが特に参考になります。・むうくんの部屋 むうくんのページ(54期)メールマガジンがメイン。過去のものが見れます。答案の書き方や添削についてのメルマガが特に参考になると思います。両方のページとも、司法試験最強リンクsumeruから実務家のページというところから飛べます。参考にしてみてください。しかし、今、楽天のページを色々と編集してみてはいるのですが、どうも日記の片付け方というか、上手な仕分け方ができないですね。昔の日記とか、受験勉強の仕方の話とかそういうカテゴリーとかでうまくまとめられたらいいのにな、というか、あんまり手間をかけずにまとめられたらいいのになあ、と思います。以前も重いので編集してくれたら嬉しい、という趣旨のカキコがあったので、編集しようとしたのですが、なかなか手こずってます。しばらく昔の記事が編集されてアップされているかもしれませんが、お気にならさずにお願いします。ではではまた。
2004年09月22日
-
2回試験口述考試刑事系
(編集されていますので、コメントとの若干のズレが生じているかもしれません。)主査は刑事裁判。検察、刑事弁護はそれぞれ副査。時間は、7分,3分,3分程度。覚せい剤の営利目的譲渡事件で、譲渡自体は認めているが、営利目的を否認。乙1号証、立証趣旨は、身上・経歴等。ただし、暴力団構成員であることが書かれており、その暴力団が覚せい剤の営利譲渡に絡んでいることが分かっている。この場合、乙1号証を営利目的の認定に使って良いか。立証趣旨の拘束力と不意打ち認定。実務では、立証趣旨に拘束力がないのが通説。にもかかわらず~♪、思わず、認定に使ってはいけないと言ってしまった。いや、使ってはいけないと言う結論は良いのだけれど、同意されているのが立証趣旨の範囲内だから、と言う意味で、同意の効力の問題にしました。実際のところは、不意打ち認定を避けるため、というのが答えらしいです。おそらくこれは、同意の効力について、特にその立証趣旨に限り同意したという明示のものがある場合には、同意の効力はそこに限定されるが、明示のものがない場合には立証趣旨に拘束力はない以上、緩やかに認定できるという立場を前提としていると思われます。ただ、それでも不意打ちになるような認定はできないと適正手続の観点からしているようにも見えます。立証趣旨の拘束力と言うことですか?と聞かれて、はいと言ったはいいものの、その瞬間、左右の副査が首を傾げる有様、ああ、やってられないさ、とやさぐれたくなりました。あれ~、どっちだったけな~?立証趣旨に拘束力はないはずだし、同意の場合はどうだったけな???みたいな感じでした。「まあ、弁護人がその立証趣旨に限って同意したわけですから、」とかそんなようなニュアンスのことを言うと、「同意の効力と言うことですか。」「はい、そうです。」「ふむ(軽く頷いて)まあ良いでしょう。」と一区切り尽きました。実務と違うことを言うと質問がつっかえますので、あんまりよくないかもしれません。特に主査が裁判官だからというのもあるかと思います。続いて、乙2号証で、本件で問題になっている甲に対する譲渡ではない、乙に対する譲渡の事実を書かれた書面が同意されたとして、これを営利目的の立証に使えるか、ということを聞かれました。いわゆる前科に基づく認定、ですが、今回では余罪に基づく認定ということになります。「なぜ良いのか」、と聞かれます。「いや、手口が似ているとか、え~っと。」「そりゃ、詐欺とかはそうだろうけれど、営利目的上の場合は?」「ええっと、譲り渡し場所とか方法とか」「まあ、いいでしょう。」(正解はおそらく入手先とかもあると思います。)では、次に、単純譲渡の事案で、甲に対する譲り渡しを認めている場合、乙に対する譲り渡しの事実を立証するため、乙の検察官面前調書を検察官が請求しました。弁護人はこれに不同意としたため、検察官が乙に対する証人尋問請求をしました。裁判官としてはどうしますか。「えっと、採用できないと思います。余罪を実質的に処罰することになりかねないからです。」「余罪を考慮することは一切行けないのですか」「いや、情状として考慮することはできますが・・・」「では、情状として考慮する場合と実質的に処罰する場合とではどう違うのですか。」「えーっと、量刑とか・・・。後は事実認定をどこまでするかの問題かと」「まあいいでしょう。刑事裁判は以上です。」刑事裁判はこれで終了。単純譲渡を否認している場合の、他人に対する譲渡の事実を立証に使えるか、というのも聞かれたような気がします。これは余罪に基づく認定ばりばりになりそうなので、無理というのが結論になるかと。検察業務上過失致死事件。三車線道路の真ん中で、トラックが被害者をひいてしまった場合。どんな過失が考えられますか。「えーっと、前方不注意と、スピード違反と・・・。あとは酒酔いか、あ~でも、これは同じですね。」「うん、まあそれくらいかな(本当はブレーキを踏まなかった過失もあり得る)。じゃあ、その事件を捜査するときどんなことをするかな」「まずは現場を見に行く。あとは実況見分でしょうか」「そうだな。まずは実況見分だな。で、その時はどんなことに気を付けてすればいいか」「夜間とのことですので、同じ時間帯にやることや、死角や視野、あとは、車通り、人通りの多さなどでしょうか」(あとは、ブレーキ痕とか)「じゃね、最後に聞くけど、被害者が死んじゃっているんだけどね、被疑者の方は、被害者がいきなり出てきたんだ、って言っていて、結局左から出てきたのか、右から出てきたのか、被疑者の話だけじゃ分からないんだ。どっちからか認定したいんだけど、どういう風に調べる?」「えーっと、まずそうですね・・・。被害者の自宅を調べて、その方向と、あと同居人がいれば、どこに行くと言っていたか聞いたりして、それで調べます。あとは、そうですね、持ち物、あーっと、コンビニの袋とかを持っていたら分かりやすいですね。」「(微笑しながら)検察からは以上です」刑事弁護「外国人が逮捕・勾留されたとのことで、あなたは弁護人として初めての接見に行きました。被疑事実の確認はするとして、他に何を確認しますか。」「確認ですか・・・。こちらから言うというよりか、相手方から聞き出すという意味でですか。」「はい」「えーっと、名前と、」「外国人ですよ。」「ビザとか、ですね。」「後は何か?」「第一言語を聞いておきます。」「次に、接見した外国人被疑者が、どうも通訳が信用できないので、署名捺印したくないと言っていますが、どうしますか。」「しなくて良いよ、と言います。後でひっくり返せないから一切しなくて良いと言います。」「しなくてよいということですね。」「はい」「では、他に何かすることはありませんか。」「そうですね。通訳文を調書に書かせるよう勧めて、原文での文章を書かなかったら、署名捺印しないぞ、と言うようにいいます。」「検察官に対しては何か言いますか。」「はい、通訳に不信感を持っている旨、伝えます。あと、裁判所の通訳を使うよう言います。」(検察副査、首を傾げる)「まあいいでしょう。刑事弁護からは以上です。」<感想>初っぱなの立証趣旨の拘束力で転んだのは結構ダメージが大きく、きつかった。両隣の副査が思いっきり首を傾げたものの、意見を撤回するほど頭が回らず、そのままくるくるとした頭のまま、突入して、質問も最後まで行かなかった気がします。あーぁ、立証趣旨の拘束力の話とかなんでここであるとか言っているのかな、と非常に不思議に思います。っていうか、より正確に言うと、同意の効力の問題で、ぐちゃぐちゃと頭が混乱してしまいました。っていうかな~、あ~あ、という感じです。何より司法試験の刑訴の勉強と、前期後期の授業の復習がもっとも効果的だと思います。とやかく情報に振り回されるより、まめに復習しましょう。っていうか、私はこの連休中遊んでいたので、偉そうなことは全く言えませんが・・・。基本的に裁判教官はあんまり助けてくれませんし、まあもちろんそれなりに誘導してくれますが、リアクション的には刑事弁護や検察担当に期待した方がよいかと思います。で、初日の誘導具合に比べると、2日目はかなり誘導が減るようで、余裕だと思っていると、結構痛い目に遭います。まあ、そんなもんでしょうか。あ~ぁ、なんで立証趣旨の拘束力認めてしまうような話に持っていってしまったのかなあ、思わず言ってしまって、そのまま修正できませんでした。まあもういいんですけどね・・・。せっかく2回試験が終了したのに、まったくもってすっきりしない気分です。解放感もないですし、喜びがこみ上げてくるようなこともないです。はぁ・・・、溜め息ばかりです。もっとも、裁判官になれるかどうかは分かりませんが、2回試験自体に落第することはないと思います。なので、食いっぱぐれることもないだろうと、ちょっと安心はしています。2回試験に向けて応援してくださった皆様方、本当にありがとうございました。とりあえず10月から、職種はともかく法律実務家にはなれそうです。これからも頑張ります。とりあえず合格発表は確か、29日か30日だと思ったので、そこでまた報告させて頂きたいと思います。なお、裁判官の合否の方は10月に入ってからです。ではではまた。
2004年09月21日
-
保険
クラスによってあったりなかったりするのですが、2回試験に落ちた人のために、クラス単位で保険をかけたりします。なお、2回試験とは、司法試験合格後修習修了に当たって十分な知識なり経験なりを有しているかどうか、をチェックする試験、要は、これに受からないと、弁護士や検事、裁判官になれないと言う試験です。聞いた話だと、2回試験には、合格と合格留保と不合格というのがあり、不合格だと来年の58期と一緒に再び2回試験を受けないといけないらしく、合格留保だと、3か月後くらいに再試験があり、これに受かると晴れて法曹資格(上に述べた法曹三者のいずれかになるための資格)を得ることが出来ます。で、合格留保の場合は、とりあえず3ヶ月間給料は出ないので(当然弁護士として働くことも出来ない)、その間の生活費について、クラスのみんなで助け合おうという話が、最初に述べた保険の話です。大体1クラス75人なので、一人一万づつ掛け金を入れて、誰か落ちた人のためにそのお金、合計70万程度を融資する、という感じらしいです。まあ、自分が落ちたときには保険金が入ってくるので、助かると言えば助かります。まあでも、誰も落ちないのが一番ですが、なんとなく保険がある上で試験を受けられる、というのは良い話ですね。クラスの発起人の方々には、忙しい中ありがたい、と思います。もちろん、こういう話もクラスによって様々ですし、実際に落ちた人がいると判明した時点で、クラス内でカンパという話になるところもあるらしいです。まさかの時のための保険ですが、いざ落ちていたら本気で有り難いに違いないと思います。ちなみに、保険の対象は合格留保や不合格の場合のみらしく、J志望がJになれなかった場合、P志望がPになれなかった場合には保険は下りないようです。まあ、就職先を捜せばすぐに働けるので当たり前と言えば当たり前かもしれませんね。明日は最後の口述、刑事系です。なんか筆記が終わって3連休で、もうやる気がしません。筆記の途中で3連休とか、筆記の前に3連休とかにすればいいのに、と思います。ただ、やる気ないとか言って、余裕なふりをしていると、いざ本番や本番の直前で相当慌てるので、ろくなことはない気がします。論文発表待ちの受験生の皆さん、よくよく肝に銘じておきましょう。ではではまた。
2004年09月20日
-
2回試験口述考試民事系
2回試験中休み中です。口述試験は民事系が17日にありました。土地を建物所有目的で賃貸に出したが、賃借人が建物に抵当権を付けた。その後、競落した第三者に対する建物収去土地明け渡し請求。第三者の方は賃貸人が賃借人に抵当権競落の場合の土地賃借権譲渡を承諾したではないかと主張。賃借人の方で、承諾は強迫によるものだと主張。取消の意思表示の相手方とか、行方不明の場合の意思表示を伝える方法とか、入札手続の概要とか、保全の方法とか、だいたいそんな感じのことが聞かれました。ああーっと、要件事実の話ももちろん聞かれました。占有権限とか、承諾の有無とか、建物買い取り請求が権利抗弁としての主張となる場合と、買い取り請求だけで建物収去に対しては一部抗弁となることなど、が聞かれました。かなり誘導してくれるので、筆記の勉強をそれなりにでもしていたのであれば、まず心配する必要はないと思います。ではではまた。大阪弁護士会のHP。読みやすくて分かりやすいです。http://www.osakaben.or.jp/main/index.php
2004年09月19日
-
最近のアクセス数
2回試験が始まったのが、確か9月7日だったと思うのですが、それ以降以下の通りのアクセス数です。楽天のアクセスランキング、「そのほか」カテゴリーで久しぶりにランクインしました。30番台後半位に入ったようです。本当にお祭りみたいな感じでした。9/08 : 1144 (一般教養)9/09 : 848 (民事裁判)9/10 : 1115 (民事弁護)9/11 : 932 (休み)9/12 : 605 (休み)9/13 : 829 (検察)9/14 : 801 (刑事弁護)9/15 : 695 (刑事裁判) 明日9月17日と、21日、22日のそれぞれ午前コマ午後コマ、合計6コマのうちで、2コマ、口述試験があります。とりあえず私は明日に民事系、21日に刑事系です。しかしなあ・・・・、任官できなかったら、何になるか考えておかないと。弁護士やると思うけれど、どこでやるか、どんなタイプの弁護をやるか、う~ん。悩みどころだ。実務修習地に行くのも良いけれど、やっぱりこっちを離れるのもなんだしなあ・・・。東京は弁護士多すぎだから、東京近郊の隙間のように弁護士がいない地域に町弁みたいな感じで入るのがいいかなあ、とか思います。ま、とりあえずよく寝て、明日以降に備えたいと思います。ではではまた。
2004年09月16日
-
2回試験刑事裁判起案報告
有印私文書偽造、同行使、偽造公文書行使、詐欺未遂懲役3年未決30日算入私文書、公文書のそれぞれ偽造部分没収。偽造私文書の行使と偽造公文書の行使は一括行使で観念的競合私文書偽造と行使と詐欺未遂は順次手段結果の関係偽造公文書行使と詐欺未遂は手段結果の関係結局一罪として重い偽造公文書行使一罪罪となるべき事実では、共謀の成立過程とその内容を詳細に。偽造の具体的態様、行使及び詐欺の具体的態様を詳細に書いた。で、やりすぎて、時間配分をミス。事実認定に入れたのが4時頃。事実認定上の問題点争点:共謀の有無共犯者の自白を直接証拠として検討した。但し、刑事事実認定では共犯は殺意と同様、特殊な間接証拠型の事実認定をしており、本件が直接証拠型に当たるかは謎。共謀って主観的要件と言うけれど、謀議行為そのものが認定できる場合は、共謀を否認されても、なんというか謀議行為が認定できれば、それで良いのかと思う。まあ、謀議行為らしきものの存在自体は否認していないことからすると、やっぱり間接事実で認定していくのかもしれないけれど、結局共犯者の自白で認定していくことになるから、実質直接証拠っぽい感じになる。いずれ総括するときもあるかもしれないけれど、今年の二回試験は後期の起案よりもどれもこれも難しかった。今年の研修所は落とす気まんまんなのかもしれない、とちょっと思った。あんまり難しい難しい言うと、来年が簡単になるかもしれないので、なんなんだけれど、どうせなら後期でももっと難しいのを出して欲しい気がする。ついでに、時間が普段の起案より40分くらい増えるのは、あんまりメリットにならない気がする。今日の起案は、2回試験5科目目にしてページ数を記入できなかった。まあいいか。たぶん本問の方で、30枚強くらいだと思うが、今までやってきた刑裁起案の中で一番少ない枚数になってしまったのが残念。にしても、疲れた・・・。
2004年09月15日
-
2回試験刑事弁護速報
道路交通法違反 無免許運転下命1,証言は信用性なし2,自白に任意性なし 証拠排除すべき3,自白に信用性なし4,その他の不利な間接事実には全て理由がある(Aの弁解)教科書的にはよく見かけることだが、取調官が任意性を飛ぶような取り調べやっていると本気でむかつく。お前は、誰のために、何のために取り調べをやれる権限をもらってるのか、一生かかって考え直せ、と言いたくなる。それにしても書くことありすぎ。任意性で膨らみすぎて、やばかったっぽい。半分割ったかもね。昨日の検察と合わせて、合わせ技一本!っという感じかも。やばいですね。それはともかく、明日は刑事裁判です。そして、最後の筆記考試です。試験祭りも、そしてみんなで騒げるのも、もうそろそろ終わりですね。さびしいもんだ。
2004年09月14日
-
2回試験検察起案速報
今日は、年を取ってからの恋愛は時に身を滅ぼしますね、という事件でした。ブランドものばかり買ってしまって、会社のお金を使い込んじゃったのさ~、という事件です。詳細はネタバレが多すぎるので何なんですが、とりあえず送致罪名は詐欺でした。ぱっと意見を聞いた限り、罪名の構成は、3パターンほど。さらに目的物の種類でもうちょっと増えたようです。実際、事実関係に即した罪名の構成及び被害金品の特定が悩ましい気がしました。しかも、最後の方でわざわざ補充捜査で微妙な検面調書を取っているところが怪しかったです。ところで、今年の検察教官室は、後期起案及び2回試験を通じて、財産犯における占有についてよくよく問いたかったようにも思います。あと、事件性と犯人性がごっちゃに成るような事件について、それでも犯人性を書かせる、というのがテーマとしてあったような気もします。実務的には非常に大切なことなのかもしれません。先週の民裁、民弁では、起案終了後悲鳴が聞こえてくるようでしたが、今日の検察起案ではそんな気配はありませんでした。早出しの人も多かったですしね。でも、そうは言っても、そんなに甘くなさそうな検察教官室にびくびくです。明日は刑事弁護です。明後日は刑事裁判です。そして筆記考試は終わります。中日を終えましたが、まだまだ続きます。とりあえず頑張ります。レスはまた落ち着いたらさせて頂きますね。ではではまた。
2004年09月13日
-
司法試験口述体験記
とある方の司法試験(2回試験ではなく)口述式試験体験談です。メールで頂いたので、適宜編集して掲載します。<私の民事系での体験談> まず,2,3問民法を答え始めたところで,条文がすぐに出てこずしどろもどろになってしまいました。(注1)条文が答えられず話が進まないことにいらいらしたらしい民法副査(民訴主査。一見して大学教授;注2)が体を揺すり室内をじろじろ観察しだした。(→うわー,落ち着いて考えられないからきょろきょろしないでくれ~と腹の中で懇願する。思わず手を合わせてしまう。注3) さらに,冷蔵庫が気になったらしく,その扉を一旦開けてすぐに閉め,再び開けて「ないな~」(→えっ!?何?何が?何がないの?っていうか,何を見てるんだっ、おまえは~!?俺の試験は終わったのか!?とパニック 注4)。 そして,念を押すように,「ないな?」(→だから誰に言っているんだ?俺か?俺が答えていいのか?そりゃーないっすよ~,試験会場に生ものがあったら困るじゃないですかっ、あっはっは、と頭の中で会話していたため,意識は専ら副査に。民法で何を聞かれているか集中できず。) その後,民訴で信義則と答えた時に,「君はさっきから信義則信義則って,一般条項だってわかってんのか!」と指さされる。(→指を指されたことにうぉっ、と思わず飛び上がり,怒らせることを言ったのか?という疑問と,おいおいあんた聞いてたのかよというつっこみが頭の中をぐるぐるっと回った。注5) 最後,「参加的効力」と答えると,ずっと下を向いてだるそうにしていた先生は「は?あ,そう。」と驚いたように顔をあげた。(→何だ知ってるんだ,という顔に書いてあった。その後どこぞの大学の先生は,参加的効力が答えられなかったら落とすつもりだったと聞いた。あれは俺のことだったに違いない。) まあ,こんなことがあっても受かるんですね。 教訓。 まず,条文は答えられないと後が辛い(→私はこれで民訴担当になめられた)。きちんと読み込んでおくべき。 次,最後までとりあえず黙らなければ何とかなる。何とか食い下がる。 人を動揺させておいて,思考回路止まらせておいて(困った時の信義則頼みをした私も悪いが),それを責めるあたり大学教授らしいです。 なお余談ですが、私の聞いた話では,過去,京大生が茶髪,Tシャツ,ジーンズで来て,「君は来る場所を間違えたようだ」といわれて試験を打ち切られ,翌年はスーツで髪の毛もダークにしてきて受かったという話も聞いたので,ある程度の常識は求められていると思います。 ご参考までに。以上、本文終わり。以下、どろっぴー注釈注1:一通り問題状況を説明された後、Yes、Noで答えられる質問をされ、次に大体条文の条数を聞かれます。注2:口述試験では、二人の試験官が一人の受験生と口述で問答をします。一応主査と副査となっており、概ね、片方は大学教授、もう片方は実務家で、現役の弁護士、裁判官、検察官だったりします。民事系は、民法と民事訴訟法、各20分ずつくらいで計40分弱、刑事系は刑法と刑事訴訟法、これも各20分で計40分、憲法も、20分くらいです。なお、憲法は一科目だけですが、試験官は二人です。注3:普通に受け答え出来ている受験生に対しては、概ね優しい試験官の方が多いです。主査の質問に対して、ちょっと迷っても、正しい答えを言うと、副査の先生が「うんうん」と頷いてくれたり、あるいは、はっきりとこちらからでも分かるように力強く頷いてくれることがあります。反面、間違った答えを言うと、ん~~~???というような怪訝な顔をしてくれたりもします。ただ、この方のように、あんまり試験官の顔色を窺いすぎると自分のペースを乱す結果になるので、自力で切り抜けることをまず第1に考えましょう。注4:試験官の方も忙しいですし、朝から一人40分近くの口述試験を14,5人やりますので、午後にもなれば、かんなり飽きています。なので、退屈そうに何か不審な行動を取られても、あんまり動揺しないようにしましょう。注5:論文試験と一緒で、いきなり信義則とか使って、最後まで信義則と言い続けようとするのは、かなり印象が悪いです。もっとも、試験会場でパニックになると、1つの言葉がぐるぐると頭の中で回ってしまうことは良くあることなので、そう言うときは、すいません、ちょっと深呼吸させて頂けませんか、などと一言合間を置くのも良いかと思います。コメントとりあえず、条文は大切です。で、基本的なところさえ間違っていなければ、そうそう落ちません。この方の場合も、参加的効力、という言葉を普通に話しておけば良かったのですが、信義則や試験官の言動にかき回されて、頭が混乱した結果なかなか腹の中でも分かっていても、言葉に出すことが出来なかったようです。基本的には、論文試験を受けるときの勉強をやっておけば、満点解答とは行かないにしても、落ちるような成績は取らないので、安心してください。普通に受けてくれば大丈夫ですので、あんまり心配しないで行くと良いと思います。論文発表まで後一月ですね。そろそろ下三法や苦手科目は一回しすることを考えても良い頃です。口述でぱにくらないためにも準備してください。それではまた。
2004年09月11日
-
2回試験民事弁護速報
売買代金等請求事件と言いつつ、実際は、売却委任契約の締結、代金の弁済委任の法律構成。金くれって言っているけれれど、その請求原因事実をどこから引っ張ってくるのか、一瞬では分からないのが今までと違う。有権代理的構成がまず一本、問題文自体に主張整理された法律構成として出されており、後はいかなる法律構成をしても良いですよ、という自分で考えろ起案でした。今までの起案だと、相手方の準備書面とかを見れたので、それなりにこっちも構成がしやすかったのですが、今回はほぼ完全にブラインド。訴状と答弁書だけしか見れず、後は書証と長めの証人尋問とで、問題用紙に簡単な法律構成(しかも、無理筋な構成)しか出ておらず、なにをせいっちゅうんだあああああ、という感じでした。証人尋問の、尋問1つ1つの意味から逆算して、どう構成を作っていったらいいのか、という感じで、2時を回る頃になんとか法律構成がいくつか出来てきて、それからは恐ろしいほど時間がなくて、という感じでした。大雑把に言うと、営業担当者が適当なことをやって、お客さんから預かったものをどうにかしてしまったという事案でした。で、お客の側の代理人に立って頑張れ、という問題です。なお、小問は2つ、1,起案用紙一枚以内で答えよ。(1)第三者の所にある証拠書類について、本件では弁護士照会により、証拠収集したが、訴訟提起後受訴裁判所を通じて、証拠収集するための手段は何があるか。(2)弁護士照会の方法に依るのと、(1)の方法に依るのとどういう違いがあるのか。理由を付けて述べよ(みたいな感じだったような気がする。)2,起案用紙一枚以内で答えよ。(1)原告は本件訴訟に勝訴して、判決が確定した。被告は取引先に対する売掛代金の他見るべき財産がないようである。原告訴訟代理人としてどのような申し立てをすれば良いか。申し立ての内容、必要書類、付随して行うと良い申し立ては何があるか、述べよ。丙銀行に対する預金債権であればいかなる申し立てをするべきか。(2)全面敗訴の判決(仮執行宣言付き)を受けた被告は、控訴を考えているが、差し当たって、原告からの執行を受けたくないと考えている。被告訴訟代理人として取るべき手段は何か。小問はともかく、本体は難しかったです。昨日の民裁も時間もないし、入り組んでいるしで、難しかったですが、今日のはまた違う難しさでした。基本的には間接事実をどれだけ拾えて、どれだけきちんと評価したか、あるいは認定の過程を示せたか、らしいので、書く場所はどうであれ(どこの法律構成で間接事実として拾っていくか、ということ)、なんとかなったかな、とも思います。っていうか、みんなかなり混乱したようなので、相対的に落ち着くところに落ち着くかと思います。っていうか、2回試験であんなに難しいのを出すのであれば、普段の起案からもっと難しいのを出してくれ、と本気で思います。月曜からは、鬼の刑事系3連発です。検察、刑事弁護、刑事裁判です。とりあえず土日は体力回復に勤めつつ、勉強したいと思います。ではではまた。
2004年09月10日
-
2回試験民裁速報
来年のこともあるので、昨日最初に書いたときよりも大雑把にしました。一応問題は回収されるので、その関係上、編集させて頂きました。建物明け渡し等請求事件請求原因所有権に基づく返還請求抗弁転貸借再抗弁債務不履行解除 期間満了系再々抗弁(1)承諾(2)正当事由の評価根拠事実なお、ネタバレなので、大事なところは書いていません。大ブロックで間違えました。結構ブルーです。まあでも、いや、やっぱり・・・。事実認定で頑張ったので、まあフォローできているかと期待しつつ。明日も頑張りたいと思います。町村教授にトラックバックして頂きました。ありがとうございます。というか、勝手にリンクして失礼しました。これからもお邪魔させて頂きます。カキコ頂いた方へ。ちょっと時間不足のためお返事できませんが、いずれレスさせて頂きます。ではではまた。昨日は一日でアクセス数が1000件を突破した模様です。す、すごい・・・。
2004年09月09日
-
2回試験教養科目速報
次の2題のうちから1つ選び解答してください。1,近時、なぜ人を殺すことがいけないことなのか理解できない子どもが増加していると言われる。このことについてあなたはどう考えるか。2,現代の日本社会において、「1つの職業を生涯全うすること」についてあなたはどう考えるか。語尾等は不正確かもしれませんが、こんな感じです。とりあえずもう過去問なので、ネット上に載せても何の問題もないでしょう。去年の過去問について、教官から一応の説明があるくらいですから。ではでは、今日はこの辺で。レス等しばらく出来ませんがよろしくお願いします。そうそう、HIROさんがカキコしてくれたように、試験官のアルバイトで大学生っぽい子が結構な数来ていました。予測も外れてしまいましたね。試験直前に教育問題、学級崩壊とかはありうるかもね~とは話していましたが、こんなにストレートに「なぜ人を殺してはいけないか」の議論が出てくるとは思いませんでした。なお、昨日コメントしたサマータイム制については、53期か54期だそうです。ではではまた。
2004年09月08日
-
明日から2回試験
明日午後4時頃から、2回試験の教養科目の試験が始まります。2時間ほどで、ある論題について起案するとのことです。ちなみに去年は、サマータイム制について論ぜよ、だったというような噂を聞いています。ついでにこの論題について、「僕の夏休み」という題名で書いた人がいて、見事に追試を食らったとか(噂ですよ^^)。今年は、少子高齢化だとか、ジェンダーだとか、個人情報だとかが今のところ噂になっています。スケジュールは以下の通りです。9月8日(水) 教養 9日 木 民事裁判 10日 金 民事弁護 13日 月 検察 14日 火 刑事弁護 15日 水 刑事裁判 17日 21日 この3日の間に、2コマ口述試験 22日 民事系、刑事系の2科目 試験形式は、問題文を15分ほど読む時間与えられ、その際メモなどを取ることができ、その後待合室で15分程度待つ。試験室に入り、2乃至3人の面接官から10~15分程度一問一答で考試が行われる。これから試験期間中は、速報みたいな形で日記は付けようと思いますが、あんまりその余裕もないかもしれません。レスも後れるかもしれませんがよろしくお願いします。とりあえず頑張ります。ではではまた。重要判例http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004090700096&genre=D1&area=O10
2004年09月07日
-
刑裁起案検察起案返却
どちらも無難な成績を取れました。検察起案は、1回目でう~ん,2回目で、げっ、とへこんでいたので、3回目で持ち直せて良かったです。最近ようやく書き方が分かってきたような。1,Vは~~~と供述している。2,かかるVの供述の信用性について検討する。 利害関係、証拠との一致、供述内容の自然性合理性等3,よって、信用できるV供述に依れば、~~~~と認められる。例えばこんな感じ。刑裁起案は、やはり起案の手引きは確実に。あそこで間違えるようだと減点は大きい模様。判決書の部分は間違えないことがなにより大切。今日はこの辺で。疲れのためレスできずにすいません。
2004年09月06日
-
民法改正案 ロー生のブログと研修所でやること
南山法科大学院町村教授のブログ民法改正案についての説明が加えられています。この教授のブログは面白いので、たまにお邪魔させて貰っています。新司法試験の合格率が人数の関係で徐々に厳しくなることが明らかになるにつれ、また、もともと未修者の場合1年前後で現行の択一レベルが要求されていることから、ロー生はかなり激しい勉強をしている様子。ちょっとうらやましい・・・。新司法試験で三振博士は絶対に避けたい、一発で合格するぞ、という強制の契機がかなり働くので、バリバリ勉強するところもあるのでしょうが、私もロースクールで、六法に関しては、もう一度一通りの知識を勉強できたら良いだろうなあ、と思います。試験前に高めた知識レベルは基本的には下がっていく方向ですので(もちろん、あれはそういうことだったのか、という理解は相当程度深まっています)、もう一回勉強できたらいいな、とも思います。あと、現行試験以外の科目、行政法、労働法、知的財産権法破産法、などの科目も勉強したいですね。あと、商法とかちょっと弱めの所も勉強したいですね。司法研修所の前期、後期では(実務修習期間ではなく、集合研修のこと)基本の5科目としては、民事裁判、民事弁護、刑事裁判、検察、刑事弁護があります。民事裁判では主として、実体法上の法律要件について、主張立証責任を当事者間に配分するという「要件事実」の勉強をします(かなり大雑把な説明です)。もちろん、実務的な民事訴訟法上の手続についても勉強します。民訴の実際を勉強すると言った感じですね。民事弁護では、当事者の側に立って、上記の要件事実、自分と相手とそれぞれが負う主張立証責任を当然の念頭に置きつつ、いかに有利な事実を広い、不利な事実を弾劾するか、などを勉強します。もちろん、模擬法律相談や、執行、保全、破産などの実務上の手続についても相当程度勉強します。あと、立証活動として、具体的にどうやって証拠を集めるか、などについても勉強します。結構訴訟外についての勉強も多いです。刑事裁判では、判決書の書き方などから、被告人と真犯人の結びつきについて(被告人が本当に犯人なのかそれとも別に犯人が居るのか、とか)や、刑法の各構成要件の例えば、殺意の有無や犯行抑圧に至る程度の立証について、証拠に基づく認定を勉強します。もちろん実務的な刑訴の手続も勉強します。検察では、起訴前の段階での起訴の是非、犯人性の検討、構成要件の検討(主観・客観)、法律上の問題点などを検討します。大きな目で見ると、刑事裁判科目とやっていることは変わらないように見えるのですが、やはり一方当事者の観点からどう考えるか、また、補充捜査として何をやるのか、検察官としての合理的な疑いを超える立証は何か、という視点は、刑事裁判官のそれと違います。何がどう違うかと言われるとこれを正確に表現するにはまだきちんと考えたことがないので、難しいのですが、主張する人と判断する人との違いがよくよく分かれるところなのだろうと思います。刑事弁護についてはこれはまったく検察と逆、弁護人の立場からの構成になります。供述証拠の任意性、特信性等の証拠能力の叩き方、信用性の叩き方、などを学びます。刑事訴訟法の証拠法について結構学ぶことも多いです。あと、捜査段階での身柄関連、違法収集証拠とか、そこら辺については、刑訴で学ぶようにかなり争いのあるところですので、刑事弁護のサイドからどう叩くか、というのを勉強します。で、大雑把に言うとこんな感じで、あとは、特別科目として労働法などをやることはあります。民訴刑訴の手続法、実体法としての民法、刑法、あと商法総則などは既に体系的な勉強は一応は終えている上、前期後期の修習を通じて、アップデートしたり、使う機会があるのでまあまあ良いのですが、それ以外の科目については結構微妙です。民事執行・保全法などは実務的には必須ですので、体系的な勉強とまでは行かないものの、基本的なことは結構勉強します。さしあたって実務で困らないようにという配慮からです。破産法についても、基礎的な部分だけ教わります。もっとも、大きな難しい破産事件は、小さな事務所の新人がいきなりやることは少ないので、基本的な部分でまあ、良いのかと思われます。にしても、要は研修所に入ってしまうと、体系的な勉強がもう徐々に出来なくなるのでして、それはもちろん実務家であればなおのこと当然でして、今この時に体系的な勉強が出来るロー生がとてもうらやましい、とそういうことです。合格率が平均20%程度になって、なかなかそんなのんびり勉強も出来ず、試験対策バージョンになっているかと思いますが、体系的な理解がないと試験なんて到底受からないでしょうから、やることをやっているのは結構うらやましいです。俺もロースクール入れないかな、と思ったのですが、司法修習が終わった人はもう入れないらしいです。まさか、今から2回試験を受けないと言う訳にはいかないしなあ・・・。ということで、ロー生のブログを回りつつ思ったことの雑感と、修習所での勉強内容を本当に大雑把に紹介、という感じでした。
2004年09月05日
-
歯医者さん + 問題研究要件事実
歯石を取ってもらいました。虫歯の治療よりは痛くないけれど、やっぱり痛いです。歯科衛生士さんに、歯の磨き方も教えてもらいました。歯並びが悪いので、結構丁寧にやらないとダメみたいです。歯茎も腫れやすいタイプとのことでした。ちょっと前に痛かったのは収まったので、とりあえず良かったです。今日は疲れたので、この辺で。問題研究要件事実市販されていますが、修習前に要件事実に関して読む資料として渡されています(なお、私の時はまだできていませんで、実務修習の半ばくらいに渡されました。)。今日、基本からという意味でざーっと読んでいるのですが、非常に分かりやすく書いてある、と思います。かつての裁判教官の方からすると、簡単すぎてあんなもんを出すのは問題だ、との噂を聞いたことがありますが、基礎的なことがきちんと書いてあるのは非常にありがたいです。もちろん自分が修習前に読んで良く理解できるとは思いませんが、後期が終わるこの段になっても、ざっと読み返すには非常に良い本だと思います。一読了解の部分が多く、復習には最適な気がします。類型別の方は、必ずしも一読了解でない部分も相当あり、結構読むのがつらかった覚えがあります。まあ、何度か読めば、それなりに理解できるようにはなるのですが・・・。ロースクール生もおそらくやっているのでしょうが、ああいうのがきちんと頭に入っていること、理解できるだけでなく、きちんと文章としてその場で表現できることが求められていることをしっかりと覚えておいてください。類型別にしても、あんなもんは後期の起案の際には当然見ることが出来ません。でも、新司法試験だとどうなるのかちょっと興味深いですね。ただ、試験の実際問題として、自前の資料を持ってこさせるわけには行かないでしょうし(書き込みの点)、かといって貸与するためには、受験者全員の数の分の資料を試験当局が持っている必要があり、その場合は受験料にかなり跳ね返ってくる畏れがありそうです。さて、それはともかく、要件事実自体は、きちんとやればそれなりに理解できると思いますが、要件事実がもっとも効果を上げるのは、認否、書証調べを経て、実質的争点が絞られた後、その事実に関して、どういう間接事実を集めればいいのか、というのを考える場面です。その意味で、要件事実論は基本的には道具に過ぎませんし、その道具を良く理解することが、効率的かつ効果的な立証活動を促します。もちろん、実務的な経験や社会経験によって、何が重要な間接事実かというのは、自ずから導き出されるとは思います。反面、学問的知識、ここで言えば、要件事実というのは、その知識自体から派生的に何が重要な間接事実かを考えさせるきっかけとなり、また、整理された理解をもたらします。何が立証事項か分かっていないで、立証活動するほど非効率的なことはないですし、また、立証責任を勘違いしていると結構恥ずかしい思いをする上、弁護過誤にもなるので要注意だと思います。ということで、私ももっと勉強します。ではではまた。
2004年09月04日
-
2回試験受験票配布
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040903AT1G0300E03092004.html東大生も大麻所持?先日中大生の大麻所持が報じられていましたが、今度は東大生が吉祥寺駅で逮捕されたそうです。大麻ってそんなに流通してるんですかね。覚せい剤より安全だと思っているから大学生が手を出すのでしょうか。ところで、法律マメ知識ですが、覚せい剤は所持していること自体も、自己使用も犯罪になりますが、大麻は所持は犯罪ですが、自己使用は犯罪となっていません。より正確に言うと、大麻を所持することが出来る者(大麻栽培者(繊維・種子を採取する目的)、大麻研究者)以外の者が、研究目的で使用することを禁止しています。言い換えると、大麻取扱者以外の者が、研究目的以外で使用することは、反対解釈から禁止行為となっていない、ということです。ちなみに、大麻取扱者が、目的外の使用をすることは禁じられています。言い換えると、大麻取扱者が自己使用することは禁止行為になる、ということです。以上は、大麻取締法2~4条、24条~24条の3辺りに書いてあります。ところで、2回試験の受験票が配布されました。2回試験とは、司法修習生が、修習終了後に受ける国家試験で、これに受からないと法曹資格が得られないと言う試験です。普段のクラスとは違うクラス乃至中教室でテストを受けます。受験番号及び席番号が与えられる形になり、試験の座席に着席後は隣の人と話しても速攻で不正行為らしいです。2回試験は、研修所とは独立の第三者機関がテストを行うと言うことで、まあ、国家試験なので当たり前と言えば当たり前なのかもしれませんが、立ち入り禁止区域とか色々制限が厳しいようです。口述考試については、三日間の間に、民事系と刑事系の2科目をやります。司法試験の口述試験のように、午前コマ午後コマがあり、3日あるうち、1日は遊びの日になります。私は、1日目の午後コマと2日目の午前コマでした。間に土日の休みが入るのですが、まあ、早く終わるのが良いのか、時間があるのが良いのか、ちょっと良く分からないですね。なお、筆記考試の方は、普段の起案と違い、10:20~5:50の時間帯で行われるそうです。また、普段のようにホッチキスで起案用紙をまとめるのではなく、パンチで穴を開けて、黒いヒモで通してまとめる形になるそうです。細かいことは考試応試心得というのが配られます。今見たところ、先ほどの第三者機関とは、司法修習生考試委員会だそうです。とりあえずそんな感じでしょうか。この土日は勉強します。ではではまた。あぁ、いかん。勉強するはずがついつい・・・。ところで、私ら修習生というのは、研修所に雇われているというのではなくて、最高裁判所採用で、勤務地(配属というのかな)が各実務修習地の裁判所となります。そういった関係で、東京と埼玉以外の修習生は、一応各地方裁判所から研修所へ出張している、という形を取っています。なお、給料については、最近問題になった物価調整手当というのがあります(東京だと基本給に13%だかそれくらいつく。東北の方とかだと0%。つまりつかない。だが、寒い時期には寒冷地手当というのが付く。田舎の方は、調整手当がないこともある)。そして、東京埼玉の人は、出張ではなく通勤という形になるので、定期代が多少出たりします(全額かどうかは知りません)。その結果、同じ様に和光の研修所に行っているのに、ある人は16万円台、ある人は22,3万円台というのがあったりします。しかししかし、ここら辺でさすが公務員というか、いわゆる出張費が入るのです。出張費は一日1000円強、後期修習約60~70日位だと思いますが入ったわけです。そして、東京に来るまでの旅費も出ましたので、+1万円ちょっと。むふっ♪で、研修所の帰りに、刑事訴訟法講義 池田修・前田雅英伊藤眞実務法曹基礎講座 労働法 伊藤塾と、マンガをいっぱい。イエスタディをうたって 冬目景出るとこ出ましょ 稲光伸二その他を買ってしまいました。これから、2回試験で、その後実務家になろうという人が今更法学部生、ロー生向けの刑事訴訟法講義で良いのか、また、そもそも予備校本買ってる場合か、問題なのですが、とりあえず、今日の刑事弁護講義で刑事証拠法の基本的知識が結構怪しかったので、ざっと読んで回復したいと思ったので、買いました。伝聞供述の証拠能力についての条文とかすっかり忘れてました。あうぅうぅぅう。っていうか、司法試験って・・・。労働法については門外漢なので、ざっと読むために買いました。基本書買って読むっていうのはちょいきついですしね。とりあえずざらっと通そうかと。人付き合いにどん欲と自ら認める人のHPを見て、むむぅ、すごい、と思った。幅広く人と付き合えるというのはやはり1つの長所だろうと思う(しかし、「ちょうしょ」と打って、まず最初に「調書」が来るのは問題だろう。)。見習えないけど、もうちっと気を付けるようにしてみよう。ではではまた。
2004年09月03日
-
民裁起案3講評
今日は丸一日民裁起案3の講評。明日も午前中は講評。かなり多くの論点が出ていたので、2回試験対応とも言えそう。自分も含めてみんなレベルが相当上がっているような気がした。ところで、後期の刑事弁護起案に向けて勉強しておいた方が良い論点は、物的証拠の検討第三者の供述調書の証拠能力(特信性)第三者供述の信用性(目撃供述、犯人識別供述の信用性、共犯者供述の信用性)自白調書の任意性、信用性、アリバイ供述の信用性物的証拠の検討は、「情況証拠から見た事実認定」法曹会特信性の話は、「刑事実務証拠法」石井一正自白の任意性も上に同じ。アリバイ供述は、自白の信用性・法曹会第三者供述、目撃供述も上に同じ。犯人識別供述については法曹会の「犯人識別供述の信用性」ごちゃごちゃ書いてますが、自白調書の証拠能力の叩き方、第三者供述の証拠能力、特信性の叩き方はきちんと押さえておくことだと思います。新実例もその範囲でとりあえずやっておくと良いと思います。今日は疲れ気味なのでこの辺でレス付けられずすいません。
2004年09月02日
-
神山弁護士+口述関連
書くのを忘れていましたが、今日は非常に有益な講演を聞くことが出来ました。神山弁護士のプロフェッショナルとしての刑事弁護です。有罪率99.98%の日本において、刑事弁護をすることの意味。とりわけ、無実を争う場合の、新人弁護士が持つ葛藤、というか、素朴な正義感とのせめぎ合いや、ある種の諦め、すべての行動に、1つ1つきちんとした理由を持ち、行動し、判断することの大切さを教えられました。えん罪事件、再審事件などで大弁護団を組む場合には、捜査段階、一審段階からの弁護活動を1つ1つを解体し、分析して、このときこのときどうすべきであったのか、というのを逐一検討するそうです。この世界には、正解はないこと。神ならぬ身であれば、真実そこで何があったのかは正解は分からないこと。自分たちに出来るのは、事実の痕跡として残された証拠から推測することしかできないこと。証拠として、事件現場で見つかった2本の陰毛が提出された。DNA鑑定すると一本は被告人の、一本は被害者のものだった。もうこれは覆しようのない証拠かもしれない。ところが、さらに事故現場に何か残っていなかったか、証拠請求すると、もう2本、陰毛が出てきた。それは、DNA鑑定してみると、被告人のものでも、被害者のものでもなかった。こうなると、事実は随分と違ってくるのではないだろうか。素朴な正義感について一人のえん罪を防止するために、10人の人間を有罪にしてもかまわない。このテーゼをどこまで信じられるか。やっぱり、疑わしい、怪しいやつを野放しにしては行けないのではないだろうか。との素朴な正義感について。神山弁護士のコメントの趣旨としては、確実な証拠があって、どうにもこうにもこいつ以外あり得ないのであれば、それはまあやむを得ないかもしれない。でも、ただ怪しい、ろくな証拠もないのに、ただ怪しい、というだけで、無実の人間がなんの根拠もなく、一生刑務所に入ったり、生命を奪われることがそれがまともな社会なのか、と。突然あなたが逮捕されて、訳の分からない間に裁判にかけられて、死刑になる。それが本当にまともな社会なのか、と。神山弁護士の話は実践的で非常に有益なので、機会があるときは是非聞きに言った方が良いと思います。民弁ラストの起案が返却されました。証拠上2段の推定は崩れまくりだろうと主観的に思っても、あくまできちんと客観的な盗取可能性、接近可能性、その上で、具体的な方法、さらに主観面としての動機を書くのは必須のようです。代理人としては、そんなん当たり前だろう、と思っても、代理人は代理人、裁判官は裁判官で、自分がそう思っても、裁判官がそう思ってくれるとは限らない、そう思って書くのは非常に大切なようです。成績的にはとりあえず上3分の1には入っているようなので、後は油断せず、きちんとやりたいと思います。論証の仕方、論調、重要な間接事実の拾い上げ、なぜそうなのか(理由)、だからどうなのか(評価)、をきちんとやっていきたいと思います。掲示板に書き込みがあったので、そのお返事です。質問の趣旨は、口述の時に履くスリッパはどんなものがいいのか、スーツは黒か紺が多いようだが、グレーでも大丈夫か。の2点です。私が見た限り、ごく普通のスリッパが多かったように思います。カラフルなピンクや赤とか、くまさんがプリントされてるとか、そういうことはなかったように思います(^^)。なので、あんまり目立たない色のスリッパを選べばよいのではないでしょうか。で、スーツについてですが、多いのはやはりリクルートスーツで、黒や紺が多いようです。グレーの人も結構いたように思います。ただまあ、そんなことは誰も気にしてません。サラリーマンがグレーのスーツを着ていたところで誰も文句を言わないように、まっとうな格好をしていれば十分です。スーツであれば、なんの問題もないと思いますよ。そういえば、ひとりだけ私服、ジーパンで来ていた方がいらっしゃった覚えがありますが、彼も無事に受かったそうです。情報が不足していたのかもしれませんが、ちょっと驚くにしても、そういうことで判断するようなものでもないので、安心して良いと思います。ついでにネクタイについてですが、これもたいして見られていないと思うので、もんのすごい派手なやつでなければ、なんでも良いと思いますよ。ではではこの辺で。
2004年09月01日
-
刑事模擬裁判終了
112の合議体中約2割が無罪。事案はスリの犯人性、とだけ言っておきます。おそらく58期の実務修習中の模擬裁判の素材になると思うので。もっとも、私たちが使った事案には多少変化が加わると思います。ネタバレを防ぐのと、検察弁護間のバランスを取るためかと思われます。ところで、司法試験の試験委員もやっていらっしゃる先生とお話しする機会があったのですが、やはり司法試験の答案で要求されるのは論理性のようです。答案の前半で、ある理屈を取ったのに、後半でその理屈を取ると不都合になるからと言って、違う論理を持ってきたりする答案はやっぱりダメみたいです。ここからは私の意見ですが、不都合になるなら、なることを認めた上で、その上でどうするか、というのが問われているんだと思います。ご都合主義な答案はやはりダメなようです。あと、人によっては、論点ごとに問題文ごとに学説を変える人もいるようですが、やはりそれは法律家としては不適切だと思います。そう言う人は口述でも叩かれやすいので、どうかお気を付けください。というか、一貫した論理を取ることをお勧めします。しかし、あと一月で実務だというのに、自分自身を振り返ると、こんなんではあぶなっかしいなあ、と本当に思います。他方で、弁護士になる大部分のクラスメイトに思うのは、やはりみんな相当逞しくなっているな、ということです。もともと精神的にタフな人が多いのでしょうが、私なんぞから見ると、芯も強いし、結構きついのに、社交性もあるし、と言った感じで、みんなそれぞれすごいな、と思いますね。ではではまた。一週間後に2回試験だというのに、まったくその気がしない自分の暢気さにあきれてますが、とりあえず体調には気を付けたいと思います。皆様もどうぞご自愛ください。
2004年08月31日
-
争点の明確化 +
今年の刑事模擬裁判は、窃盗被告事件。主な争点は犯人性。事案は、電車内でのスリ。罪状認否では、とりあえず同じ電車に乗っていたことくらいしか分かっていないので、どこら辺の間接事実で勝負になるのかが良く分からない。特に本件では、盗んだときそのものは見ていないようなニュアンスだからである。冒頭陳述に対する認否の形でも良いから、裁判所がなんとなくここら辺が問題になるのかとか、そういうのを明らかに出来たらよいと思う。あと、思うのだが、刑事裁判に置いては立証責任は検察官にあり、合理的な疑いを超えない証明が必要と良く言われれる。しかし、それはあくまで理屈であって、犯人性が疑われるような事案であれば、基本的にはアナザーストーリーを立てないと結構厳しい気がする。抽象的に立証不十分だと言ってもあまり説得力はないわけで、どうも有罪にすると整合性の付かない証拠がある場合には、それを一定のアナザーストーリーの中に位置づけて、説得的に話を立てないと厳しいのではないだろうか。その意味で、否認事件に置いて、弁護側の冒頭陳述というのは有効だと思う。手の内を晒すと良く言うが、晒される程度で崩れる証拠なら厳しい気がします。というのは、甘いのかもしれませんが・・・。以下は独り言なので、あまりお気になさらぬよう。私が合格したときに比べ、受験生はもちろん、修習生のホームページも増え、最近ではより専門的な分野について知識のある弁護士の先生方がブログを持ったりもしている(昔からあったのかもしれないが、私はあんまり知らなかった。)。司法試験リンクsumeruがそこら辺を徐々に上手く取り込んでくれて、結構色々なページを見られるようになった。受験生の頃は、自分の勉強なり、状況について気楽に色々書くのは、結構楽しく、どうも籠もりがちな生活からすると、良い気分転換になった。合格後も、なんとなく、というか、それまで毎日日記を書いていたせいか、結局続けてしまった。修習生活というのが、どうもピンと来ないまま修習に入ってしまったせいもあるし、新生活がなんとなく不安だったから、腹に溜めないようにするためだったのかもしれない。また、受験に関する情報ももう少し伝えたかったという気持ちもあった。それに、当時はまだ修習生のページも、かの有名なヒーリング司法試験のページくらいしかなく(色々とお世話になりました。すいません、修習ものとしては、K.Otomoのリーガルホームページでした。ヒーリングの方は受験時代に専らお世話になりました。)、余りお目に掛かることが出来なかったので、書いても良いかな、というイメージがあった。守秘義務に関しても、書き方さえ気を付ければ、また日時をずらしたり、手続的な面とかについて触れたり、あるいは、実務庁で見聞きした事件にしても、個別具体的な事件の内容には触れず、ある程度抽象化した形でコメントすれば、個人的には平気な気がした。あとなにより大切なのは、所詮は修習生であって、決定権限はないし、私が誰かが分からないと事件自体なかなか特定できないところもあるかと思ったからである。今後、私が色々と意見を述べる場合、それは一応は一人の裁判官としてのコメントと取られるわけであるし、単なる若造の意見とかという訳にはいかないこともあるかもしれない。実質的な権限や識見、能力はともかく、外部から批判するに際して、十分目標足り得るものだと思う。国の一機関であると言うことはそういうことなのかもしれない。世間的に見ればぺーぺーも良いところなので、たいしたことないはずなのだが、こういう萎縮的効果はいまさらながらに大きいと思う。ところで、57期の修習生も、その多くがホームページをやめそうな勢いである。あるいは、形を変えて、今のページをやめて、他のページを新しく作り直すなど、同一人のページと特定されない方法を採る様子である。ある方のページを見ると、一応本名は隠した方が良いのだけれど、個人的な意見を好きに述べようと思うと、つい法律の話になってしまい、そうすると、自分の意見を述べる際にもなんとなく自分の立場を明らかにした方が良い感じになり、みたいなことが書いてあった。これもまた一理あるような気がする。んー、あと問題なのは、コンテンツのレベルの話で、先に述べた弁護士の先生方のような専門分野での話をするには、私自身の能力が不足していること。身の回りの話をするには、あんまりに特定されそうな気がして怖いこと。今までは修習生は1200人くらい居るし調べないとなかなか分からないところもあるけれど、裁判官になると人数も同期では100人程度だろうし、調べる手だても結構ある。あと、気になるのは、やはり表現の自由の制約とか、守秘義務の関係。表現の自由に関する萎縮的効果というのはこれほど大きいとは思わなかった。なにをしてはいけないという具体的な実体がないから、また、ラインがはっきりしないから、それが不安につながり、表現を差し支えるように成るというのは非常に説得的な流れだと思う。政治的意見というのは、どこまでのものなのか。例えば、ロースクールとか、例えば、訴訟手続の具体的流れに関しても、意見と言えば意見であるし、検察寄り、弁護寄り、なんていうのもなくはないと思う。ん~、例えば、新制度について説明しても、どこかからかとやかく言われるのではないかと、ちょっと不安になったりもするわけで・・・。どうすっかな~。1つの居場所ではあると思うので、なんらかの形では残したいと思うのですが・・・。
2004年08月29日
-
いわゆる民暴、民事介入暴力
午前中は、民事介入暴力について弁護士の先生から講演。非常に実践的で、ためになる講義でした。民事介入暴力とは、暴力団が、フロント企業や交通事故をきっかけに暴力を背景に、不当に過大な金銭を要求してきたり、エセ右翼、エセ同和などの形で、街宣活動をかけたり、あるいは、企業に貸したと思っていたオフィス賃貸物件が、実は組事務所になっていたりとか(他のテナントが逃げて、誰も入ってくれなくなる上、組系の賃借人が増える可能性もある。この場合は賃貸借契約の用法違反で解除する形になる。)、そういう事態のことを言います。講義では、弁護士の先生が実際に体験した実話のみならず、脅しすかしの様子を録音したテープや、事務所に動産執行をかけた際のビデオなどを見せて頂き、非常に興味深かったです。やくざというのは、こちらのほんの少しの弱みに付け込んで、それはお前が悪いんだろ、あ、悪いと思うならこっちへ来い、といった風に1を10にして、がんがん攻め込んできますので、そういう時の対応の仕方などについて説明がありました。基本的には、こちらはいつも淡々とすること、間違ったことやお前が悪いんだろうと言った悟道をしてきたとき、あるいは無理にどこかへ連れ去ろうとか、これにサインしろ、とか言われても、いや、それとこれとは違いますから、と淡々と断ること。怯んだり、怯えたりする様子を見せると、かさになってかかってきますから、内心ではびくびくしていても、それを表には出さないこと。さらにガンガン突っ込まれて、脅されても、あくまで冷静に、相手の言うことを遮らず、言わせること。ただ、不当な点には一切従わず、事実と違うことについてはそれは違うと思います、と一言だけいうこと。そうして、1時間も2時間も話し続けさせれば、段々落ち着いてくるそうです。この、1時間も2時間も話させれば落ち着くだろう、という予測可能性があれば、結構頑張れると思うので、あくまで落ち着いてその時間を耐え、可能であれば、早めに警察に連絡し、その間をあくまで淡々と冷静にいけると良いようです。あと、彼らは正業に就いていない分コンプレックスが非常に強いと言うことなので、その反面メンツを大事にします。なので、特に若い弁護士が、ニヤニヤと馬鹿にしたような目で見るのは禁物のようです。余計に加熱させて、ややこしいことになりがちです。淡々と、怯まず、怯えず、従わず、と行くべし、とのことでした。まあ、いざ現場ではかなり怖いと思いますが、速攻で拉致られるとかそういう事態さえさければ、あるいは暴力を当初から振るわれるとか、そういう事態を避けること、警察との連絡を早めに取ることで、大事に至ることは防げるとのことでした。また、個人で対応するのは無理ですから、弁護士を立てることで、心理的にかなりラクになることは確かです。弁護士さんの知り合いがいない場合でも、各弁護士会で、民事介入暴力委員会が必ずありますので、それに所属する先生を、と弁護士会に電話した際、お話しすると良いと思います。午後は刑事模擬裁判。傍聴席裁判官でしたが、ろくに争点が分かりません。冒頭陳述に対する認否とかせめてして欲しい気もするけれど・・・。まあ、弁護方針も色々あるでしょうし、冒頭陳述も事前に書面を渡してくれるわけでもないので、仕方がないかな、と思います。来週の月曜日が証人尋問で、火曜日には判決です。むむぅ、忙しくなりそうです。
2004年08月27日
-
10万ヒット突破
今日、めでたく10万ヒットを突破しました。このページを始めて2年8か月余りで、のべ10万人。本当にありがとうございます。今日の17時37,8分辺りに訪問してくださった方が10万人目の方でした。ありがとうございました。きっと幸運がが舞い込むに違いないと思います。皆様、これからもどうぞよろしくお願いします。さて、昨日は検察起案で、今日は民事共通演習、要は民事模擬裁判の和解、判決、及び証人尋問等の講評でした。まずは検察起案から。今年の3月作成の記録だったので、もしかすると58期の前期修習で使われた素材かもしれません。事案はタクシー強盗。主たる争点は、強盗の故意、特に財物奪取に向けられた暴行乃至脅迫の故意があるかないか、でした。犯人性については自白もあり、あまり争いはないが、犯人識別供述や多少の物証を書く必要がある程度でした。構成要件該当性については、暴行が財物奪取に向けられたものであることや、犯行抑圧に至る程度のものか、被害者は畏怖していたか、あとは先ほど述べた暴行乃至脅迫の故意が問題になります。色々と弁解を述べているので、その弁解を排斥する一方、当初の自白について信用性を検討する必要があると思います。なお、私は信用性をきちんと検討していなかったように思うので、反省しています。法律上の問題点としては、1項強盗と2項強盗とが同一の機械に行われた場合にどうなるか、という問題があります。とりあえず、検察起案については、受験時代の刑法各論、財産犯の所だけきちんとやっておくのがかなり重要です。ここら辺がしっかりしていると、結構きちんと点数を取れるようになると思います。ま、今まであんまり検察起案の良くない私が言うのもなんですし、今回私が取れたかどうかも謎ですが・・・。民事模擬裁判のことはまたどこかで書きます。明日は刑事模擬裁判です。検察官チーム、弁護人チームはそれぞれかなり大変そうです。民事模擬裁判と刑事模擬裁判の準備がかなり重なって、負担が想像以上に重くなるので、気を付けた方が良いと思います。ではではまた。
2004年08月26日
-
後期はストレスフル
暑い、起案が連続するプレッシャー、模擬裁判、民事刑事それぞれにおけるチームでの行動、相手方当事者との関係、そして2週間後の2回試験。結構ストレスフルです。心の健康と体の健康を大切にして、周りへの配慮を忘れたくはないものです。
2004年08月24日
-
そろそろ10万ヒット
今週中にもしかすると10万ヒットに行くかもしれません。キリ番ゲッターな方はどうぞ書き込みをしていってくださいね。今日は、刑裁起案3でした。平成14年度の2回試験問題をアレンジしたものかと思われます。内容としては、強盗未遂でバリバリ犯人性。犯人識別供述は一応あるが、たいした認定力がなく、実質は間接証拠型と思われる事案でした。今回は、小問もあったせいか、時間はないはずなのですが、あんまりやる気がなかったため、適当に気を抜いてやっていたら、時間内に収まりました。大事なことを落としていたら問題ですけどね。どうなっていることやら。ちなみに、小問は、新実例刑訴そのままですので、早い内に読んでおくとラクだと思います。とりあえず疲れが溜まっていて、あんまり体調は良くありません。ではではまた。盗品の近接所持ならぬ、犯行車両及び凶器の近接所持みたいな事案でした。犯行車両及び凶器とおぼしきものを犯行直前と直後には所持していたのですが、犯行日時においてはそれらが盗まれており、犯行後に放置してあったという主張です。そりゃ無理だろ、と第一感で思うにしても、そのままはねるのではなくて、とりあえず裏付けがあるかどうか、盗まれたにふさわしい行動を被告人が取っているかどうか、などなどを検討する必要があります。いかに不合理な弁解と思われていても、裏付けがあったりするとひっくり返りますし、裏付けがなくても、あれ、これはありうるかも、と具体的なレベルで成立してしまうと、結論が変わるので、とりあえずそれらの可能性を真摯に検討する必要はあります。刑事弁護的には、これらの主張をもっともらしく立てないと行けませんし、刑事裁判的には、少なくともこれらの主張もきちんと検討しているよ、という姿勢を示す必要があります。なお、これらは起案としての態度であって、実際の場でどうなるかはそれこそ事件次第でしょう。弁護人にしても自分が納得しないで無罪主張しているようでは役立たずですしね。その程度で裁判所を説得できるはずがないですから。
2004年08月23日
-
後期終盤戦の気分
結局あんまり勉強してないですね。明日は刑事裁判の起案ですが、そして、小問が出るのにもかかわらず、ろくに新実例刑訴も読んでいません。あー、やる気ねー。張りつめたやる気というのがどうも出ないようです。この暑さのせいか、疲れが溜まっているのか、はたまた歯の具合が相変わらず悪いせいか(どうもあごが疲れやすいのです)、しっくりと休めていません。昼寝も昨日に続けてしております。今日はたまには半身浴でもして、疲れを取ろうかと思います。体力付けないと厳しいですなあ、何事にも。まあ、体力がないので、かえって体調を気にして無理しないと言うメリットもあるのですが、まあ、なんともかんともと言う感じです。しかし、この微熱はなんとかならないものかと思います。しかし、2chとかでは、裁判官の採用では2回試験だけでなく司法試験の成績も考慮されるとかいう噂も聞くけど、本当かな???、と思います。そんなんじゃたまらんわなぁ。実務中に成ろうと思った人はどうするんじゃという気がします。ちなみに昔は教官も確実に修習生の司法試験の成績は知っていたそうですが、今は少なくとも公式見解では知らないとのことらしいです。まあ、噂は噂のレベルかなあ、とも思います。そんなんでどうこうされてたら、裁判教官もさすがに信用を無くすだろうと思うからです。50何期かの任官拒否は、それ自体の当否は私自身には良く分かりませんが、それがその後の採用方針に影響を与えたことは確かなようで、公明正大な方向に進んでいる気がします。とりあえずそう言う点では私は今のところ結構信用しています。もっとも、人によっては、私がそんなに嫌われていないからだよ、といったニュアンスのことも聞きますが・・・。なんにしても実務修習中は楽しかったですね。前期中も解放感があって、人間関係自体はなんかしんどかったけれど、まあ良かったです。後期は起案起案講評講評又起案みたいな感じで、しんどいです。人間関係については、結構グループとか出来ていたりして、特に無理矢理仲良くしようと思わなくても平気なので、それほどしんどくないです。あとまあ、一応はみんな顔見知りなんで、そんなに緊張もしないですし、気楽に過ごせます。ああっと、民裁起案3は若干ですが詳しく書き直しました。代物弁済の形で債権譲渡がなされた場合で、債権取得原因として代物弁済を書く場合、債権譲渡通知は不要であるが、但し、その債権で相殺などする場合は、履行強制のために債務者対抗要件として債権譲渡通知が必要となること。売買型の契約において、履行遅滞解除をする場合、履行期限の経過の摘示は不要なこと。なぜなら、確定期限であれば、確定期限が未到来のことは抗弁ですし、催告が確定期限到来前になされたことも抗弁のような気がしてくるからです。不確定期限だと、期限の到来+債務者の悪意が履行遅滞の要件ですが、この場合はどうなのか。催告により当然に悪意になるわけですし、催告が確定期限前になされた場合には、それを抗弁として相手方に主張させれば足りるのは、上記と同じ気がします。期限の定めがない場合であれば、なお一層あてはまるでしょう。次に、解除のためには、相手方の同時履行の抗弁を奪っておく必要があります。履行遅滞が違法でないこと、の要件かと思われます。ここらへんどうも今一翼分かってないような気がしますので、もうちょっと要件事実とか読まないとな、という感じです。とりあえず言えるのは、研修所に入っても、民法の解除とか債務不履行とかあそこら辺の所は非常に大切ですし、大事なところなのできちんとやっておくと良いと思います。私はダットサンとか読みながら復習をしています。しかし、どこまでいっても、我妻先生すごすぎ、という感じです。
2004年08月22日
-
健康診断
先日、採用試験のための健康診断がありました。尿検査、血液検査(赤沈検査)、血圧、脈拍、身長、体重、問診くらいでした。正味1時間弱と言ったところでした。この健康診断、最高裁の建物の中で行われました。この最高裁の建物は、私は入り口を間違えて入った関係で正門の方も見れたのですが、コの字形の入り口で、なかなか威圧感のある、また防御しやすそうな構造でした。中は大理石の階段が正面にあって、非常にきれいな感じでした。もっとも、健康診断をやったのは、普通の建物と同じ感じでして、最高裁の法廷とかは見ることが出来ませんでした。予約していかないと行けない感じみたいですね。民裁起案3ですが、基本的にはやはり類型別をきちんと読み込むこと。それこそ本当に読み込んで、どうもわかりにくいところは、要件事実の1巻2巻を適宜参照すること、大ブロック単位で予備的抗弁とかa+bとかについては、1巻、2巻の逐条でないところをきちんと読んでおくことが大切かと思います。ではではまた。
2004年08月21日
-
民裁起案3
所有権に基づく妨害排除請求権 1個X原告 Y被告 B Yの子息 C 建設会社請求原因1 商事代理 XB売買 X 株式会社(商事代理→顕名不要に) YB先立つ代理権授与 <なお、私は商事代理は書きませんでした。先立つ代理権授与を被告が争っているのに、具体的な日時まで指定できないのは主張自体失当と考えたからです。類型別などでは争っていない場合には先立つ代理権授与で足りる、とされていますが、争っている場合については微妙な気がします。>2 追認 YB本件土地売買 600万円 Y 株式会社 Y→X 追認抗弁1 通謀虚偽表示 XB売買が通謀虚偽表示であること2 履行遅滞解除 XY登記手続に必要な書類を提供(履行の提供) YX 催告 相当期間の経過 YX 解除の意思表示 <売買型の契約では、履行遅滞解除に履行期の徒過は不要とのこと。期限未到来は抗弁事項、期限の定め無しの場合は遅滞のための催告と解除の前提としての催告とを兼ねられるから? 履行の提供は、解除の前提として、履行が違法でないこと、同時履行の抗弁権を奪うために必要。 もっとも、相手方の債務不履行は相手方に反対事実主張させれば足りる。履行はつまり、600万円の弁済は相手方が主張立証。本件では、600万円の不払いによる履行遅滞解除。> 再抗弁抗弁2に対して相殺 YC請負契約 YC 催告 Y履行遅滞中途で解除 出来形は3270万円であること 出来形と残部分が可分であること 出来形部分の引き渡し 注文者において出来形部分の引き渡しを受けることに利益のあること XC消費貸借 500万円 XC代物弁済 XC消費貸借債務に代えて、CのYに対する請負代金請求権670万円を譲り受ける CY債権譲渡の通知(債務者対抗要件として)相殺の意思表示再々抗弁弁済と相殺の再々抗弁 YC弁済 1600万円 YC弁済 1000万円 CY消費貸借 150万円 Y→C 相殺の意思表示再抗弁段階で、3270万円のC→Yの債権が発生して、その内670万円分をXは譲り受けました。そこで、Xは、Yに対して、抗弁で主張されていた600万円の土地売買代金の債務と、この譲り受け債権と対等額で相殺しました。これによって、履行遅滞ではなくなります。これに対して、再抗弁で、YC間3270万円の債権が、1000万円、1600万円の弁済を受け、更に150万円分の相殺により、520万円の債権額しかのこっていないことを主張します。 こうなると、XがCから譲り受けたのもせいぜい520万円の範囲でしか対抗できませんから、600万円の売買代金債務と相殺により消滅するのは、520万円に留まり、Xが支払わないと行けない600万円の債権の内、80万円が未払いとして残っていることになります。そうすると依然として履行遅滞は残っており、解除は有効。ということになります。むむぅ、あんまりきちんと書く気力が残ってないですね。ただ、起案的には事例って限られているのかなとも思いました。→多少詳しく書き換えました。しかし、柔道強かった。すげー。
2004年08月20日
-
交互尋問
今日は昨日に引き続いて交互尋問でした。私は最終準備書面作成グループだったため、今日の尋問や講評の後最終準備書面の骨子作成に入りました。尋問中も記録が出来上がるわけではないので、集中する必要があり、その後に書き始めたため、結構遅くになってしまいました。ということで、今日は疲れました。争点整理や尋問チームは準備が大変ですが、その場で終わるところ、最終準備書面グループは尋問は基本的に全て集中して聞いた上で、みんなが終わっているのにもかかわらず、そこから始めるという点で結構面倒くさいです。って、これは裁判官グループもさりげなく同じですね。今日は疲れたのでこの辺で。ではではまた。
2004年08月18日
-
おそるべきは +袴田事件再審へ
ロースクールか。法科大学院において学部の成績もかなり重視されることが明らかになりました。その結果、大学レベルで実体法の勉強に力を注ぐようになり、ローでも相当程度のプレッシャーの下で勉強するようになるわけですから、結構な力が付くと思います。現行司法試験においては、正確かつかなり詳細な知識が択一レベルでは少なくとも問われてきました。論文レベルでも基礎的な知識について確実な理解と表現が問われてきました。今のロースクールでは、かなりきちんと勉強はしていると思います。あとはどれだけトレーニングをするかだと思います。はっきりと言いますが、別に講義受けているだけで賢くなるわけでは全くありません。あと、講義を受け、自分で疑問を持って資料を調べて、理解しても、別にそれをすぐに使えるようになるほど法律は簡単ではないですし、新しい問題に遭遇したときにどう考えるかという発想が身に付くわけでもありません。現行の受験生というか、今までの合格者がそれなりに評価されるのは、私は答練などのアウトプットのトレーニングを異常に積んでいるからだと思います。アウトプットするには、かなりの理解と記憶の定着を必要としますし、あーっと、論点ブロック暗記しただけで司法試験受かると思っている人がいたら、たぶん一生受からないのでよくよく思い違いを直すと良いと思います。理解と記憶の定着があるから、新しい問題や今まで自分が考えたことがない問題でも、基礎となる知識と理解と整合性を持ちつつ、解決策なり対応策なりを見出せるのだと思います。整合性を持つと言うことは、論理的に矛盾なく、納得のいく説明があると言うことです。自然科学ではないので、価値観に基づく論理性というところはありますが、理屈が通っていることは前提として必要です。なんで択一が難しいかというと、おそろしく正確な知識と理解が問われるからです。一見些末とも見える法律知識でも、その知識は条文とその趣旨、価値観との関連で出てくるものであって、単体としてのつまらない知識ではなく(単体として覚えるような頭の使い方をしていると、基本的に受験は長期化しますし、応用力がなくなります。)、総体としての科目ごとの理解がバックにあり、それでいてその論理性なり整合性なりを緻密に問うてくるというところがあります。択一レベルの知識を1つ1つ理解するのは、多少時間はかかるにせよ、きちんと勉強して説明を受ければ誰だって出来るようになると思います。これから出てくる新しい知識を1つ1つ理解していくことはもちろんいつまで経っても変わらないのですが、理解の基礎となるベースの知識というのは確固足るものである必要があるし、確実なものでないときちんとした法律的な発想が出来ないと言う点がもっとも問題です。憲法は価値観のレベルで、民法は実体法の基礎、解釈学のベースであるという点で、刑法は罪刑法定主義との関連で、両訴訟法は手続法のベースという点で欠かせないもので、それについて何らかの方法で基礎的な知識を確実なものにして欲しいと思います。ロー生はたぶん時間はないかと思いますが、一学期で成績が悪かった科目については、きちんと答案を書き直すことをお勧めします。追試を受けてそれで良かったからいいや、というのではなく、知識を確実なものにすること、誰かに説明できるくらいに丁寧に答案を書き直すくらいの勢いでやることが非常に大切になってくると思います。たとえあなたが優秀な人間でも、あなた程度に優秀な人間はいくらでもいます。その中でおごらず、確実に基礎を固めていくことで、あなたは一歩抜きんでます。正直に言って、ローで講義を受け、中途半端に分かった気になっている人に負けるほど現行の合格者連中は甘くありません。ただ、多くの科目を早い段階で広く学ぶことの出来る時間と教育的環境があるロー生は、しかも実務家教官まで巻き込んで授業を受けられるロー生は、油断することなく基礎的な知識を確実にしていけば(そのためにはアウトプットの練習、すくなくとも試験問題の復習など)、相当に力を付けられる状況にあります。是非とも頑張ってほしいと思います。そうしたロー生が実務に出てくれば、現行試験で受かってきた人間にも良い刺激を与えるでしょうし、法曹界のレベルアップにつながるのではないかと思います。あとは、あんまり商業ベースに、というかお金勘定に走らないで欲しいということくらいでしょうか。公設事務所に行く人が全くいなかったり、都会で職にあぶれたから地方に行くなんて言う傲慢な考え方は持って欲しくないです。現行受験生の人へ。正直言って教育的な環境ではロー生に負けていると思います。ただ、ロー生はまだまだ宝の山を使いこなせていないと思います。自分に甘えず、基礎的なことをきちんとこなし、トレーニングを重ねてください。弱点を把握し、弱点を克服すること。日々の勉強だけしか出来ることはありませんが、それでも頑張ってほしいと思います。ではではまた。http://www.asahi.com/national/update/0817/002.html袴田事件が再審にかかるようです。前期の白表紙でお目にかかった覚えがあります。基本的に刑事弁護の白表紙では、無罪事件なり再審になるような事件の記録をもらうので読み物としても結構面白いと思います。先日の宇和島事件、元交際相手の通帳から預金を出したとか出さないとか言う事案ですが、後に流しの窃盗で真犯人が捕まり、既に弁論終結後で、一審判決直前の段階になっていたのにもかかわらず、期日の延期、弁論再開となり、論告段階で検察官が無罪求刑をするという異例の事態になったという事案です。著名な無罪事件やえん罪とおぼしき事案は、判決文自体は判例タイムズや判例時報などでも見ることが出来ますし、あるいは、そういった本を探してきて、物語として読むのでも良いですし、その本の判決日をチェックしておいて、判決集などに当たってみるのも面白いと思います。あと、論文試験が終わった方や時間に余裕のある方は、もうそろそろ裁判所の休廷機関も終わるでしょうから、裁判所に行って刑事事件を傍聴するのもよろしいかと思います。手続の流れや証人尋問の際の手続、事案によっては遮蔽措置やビデオリンクなども見ることが出来ると思います。法廷ごとに予定表が出ていますし、大きな裁判所であれば、受付の所に期日簿があるので、それを見ながら、あるいは受付の人に色々聞いてみるのも良いと思います。とりあえず傍聴に行って、自分はどういう法律家になりたいのか、思いを馳せてみるのはいかがでしょうか。モチベーションも上がるのではないでしょうか。ではではまた。
2004年08月17日
-
講義講義講義
ADRについて 一橋大 山本和彦教授裁判員制度 市民の司法参加について 日弁連嘱託の弁護士刑事弁護講義 少年事件の弁護ADRについては、概括的な話として結構面白かったです。海外では、営利型の仲裁機関が発達していること、逆に日本では司法型の仲裁機関、いわゆる調停ですね、が発達していることから始まって、先日出来た仲裁法について簡単に説明がありました。消費者と労働者に関しては、事業者の側のみ仲裁について確定判決と同様の効力を認める片面的な構成を現時点では取っていること(附則で適用について例外を定めている)などは興味深かったです。悪徳業者が仲裁機関とグルになって不公正な利益をむさぼるのを防止するためらしいです。二コマ目は裁判員制度についての講義。公判前証拠調べ手続など起訴状一本主義を大幅に変えるシステムが来年中には導入になること、裁判員制度の下で、精密司法は完全に変わりそうであることなどが伺われ、なかなか興味深い、というか、大丈夫なのかこんなんで、今までの証拠から経験則に基づいて事実を認定し、という事実の認定が本当に大雑把になりそうでちょっと心配です。裁判員制度の下での判決書きはどの程度の認定になるのか、事実認定の補足説明なんてどこまで出来るのか、結構謎です。なお、起訴状一本主義の点ですが、基本的には裁判官は余談なんぞ抱きませんので、あんまり心配要らないかと思います。起訴状一本主義が採用されていたのは、戦前の裁判官がバリバリ検察官寄りできちんと立場が分かれていなかったからだと思います。現職の裁判官はそこらへんのトレーニングは受けているので、そんなんで予断は抱かないと思います。少年事件については、基本的に審判は儀式なので、それまでにどれだけ出来るかが勝負と言うことでした。一般の刑事事件と同じように、公判の場で証拠調べ、という訳にはなかなかいかないこと(争っている事件は別ですが)、伝聞証拠の適用がないので、弁護側も結構好きな証拠を出せることなどがポイントかと思います。ではではまた。オリンピックで寝不足の人が多いようですが、体調を崩さないよう気を付けたいですね。<弁護士職務経験法について>ttp://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20040623AT1G2302723062004.html判事補・検察官の弁護士経験、初年度は各10人前後 最高裁と法務省、日本弁護士連合会は23日、裁判官や検察官が本職を離れて弁護士になり、多様な経験を積んで資質や能力の向上を図ることを目的とした「弁護士職務経験法」が成立したことを受け、運用の概要をまとめた。最高裁からは任官後2年半から5年半の判事補が、法務省からは同3年半から5年半の検察官がそれぞれ弁護士事務所に“出向”する。 裁判官、検察官とも弁護士になる期間は原則2年間で、いずれも国家公務員の身分は残したまま弁護士事務所が雇用する。事務所からは、本職の時とほぼ同額の給与が支払われる。制度が始まる2005年度は、それぞれ10人前後が弁護士になる見通し。
2004年08月16日
-
柔道部物語
小林まことの柔道部物語は私は好きでした。三五十五の成長物語は面白かったです。しかし、野村選手強いですね。渋くてすごく格好が良いですね。谷選手も、相当な怪我のはずなのに、それを感じさせない根性というか、本当にすごいと思います。柔道は見ていて楽しいですね。本当に一瞬で勝負が決まるので、スリリングですし、技が決まったときは見ている方も興奮します。さて、また明日から修習です。週末に起案があるので、それに備えたいと思います。ではではまた。
2004年08月15日
-
任官希望者の採用関係スケジュール
裁判官に任官を希望する場合ですが、公式スケジュールとしては、 7月上旬 願書配布 7月中旬 願書提出期限 8月中旬 健康診断 9月中旬 2回試験 9月下旬 採用面接10月頭 修習終了式10月上旬 採用内定通知等10月中旬 内定者への説明会10月中旬 正式採用、辞令交付10月下旬 研修11月 各任地へ通常は2年半の勤務。その後は転勤で、3年間別の土地で勤務。という流れがオーソドックスらしいです。検察官の場合は、私もあんまり詳しくないのですが、10月の頭には浦安の口述試験会場になる場所で2週間ほど研修があり、その後東京地検で半年勤務。その後、1年間は東京以外の部制庁で(要は東京以外の大規模庁)勤務(新任という)、ついで2年間は非部制庁で勤務(新任明けという)。ついで、大規模庁に戻ります(たしかA庁というらしい。)という感じらしいです。で、以下は、裁判官、検事双方に共通なのですが、先日弁護士職務経験法(正式名称は覚えてませんが)が成立したので、裁判官も検事も約2年間、弁護士として働くことになります。現状としては、裁判官は採用後2年半と5年半の時期に、つまり最初の任地か次の任地が終わった後に2年間、検察官は、3年半と5年半の時期に、つまり新任明け終了時か、A庁終了時に行くらしいです。なお、留学する人もいますので、これは適当にずれるのかもしれません。えーっと、検事の採用スケジュールというか、願書とかの配布、提出期限は、概ね裁判官と同じですが、大体一週間くらい早い様子でした。なので、後期にかえったら任官希望者は色々な書類が必要となるので、気を付けておいてください。ではではまた。あ、ちなみに弁護士の場合も、弁護士登録の関係で、弁護士の先生の推薦とか、会費の納入とかが必要になります。いろいろ書類関係が配布されるので(これは大体7月下旬ころだったと思います)、お気を付けください。とりあえずお金がいっぱい必要になるので、きちんと貯めておきましょう。修習生の安月給にはちょっと大きな負担が一気にかかる模様です。登録費用については各弁護士会によって違ったりしますので(日弁連分はもちろん同じですが)早い時期に額を聞いておいて、頭に入れておいた方が良いかと思います(大阪が一番高いらしい)。もっとも、今の状況だと、弁護士さんになればすぐに返せそうな額でもあるので(そういえば、56期の弁護士になり立ての先生は、10月11月はぴーぴー言っていました。すぐにそんなことはなくなりましたが)、事務所の先生の感覚からするとあんまり大きな問題にはなっていないのかもしれません。また、実際のところ、みんな適当に融通を付けていますし、弁護士会で貸してくれるところもあるので、なんとかなります。あんまり問題視しすぎないようにしたほうが良いと思います。もう色々と情報はあると思いますが、給料の月額とボーナスが何ヶ月分か、個人事件の受任の有無、許可の要否、実際の受任の難易(周りの視線等も含めて)は結構重要事項です。あとは、やっぱりボスの性格とか、事務員さんとの関係、雰囲気、兄弁(護士)の様子など、色々見ておくと良いと思います。その他一般的なことは就職活動と一緒だと思います。法廷での訴訟活動も参考になるかと思います。まめに飲みに連れて行って貰ったり出来るのは、修習生の内ですので、就職活動も兼ねて色々行かれると面白いと思います。修習担当の先生を通じて連れて行って貰うのも良いでしょうし、同期と連れ立って色々行ってみるのも良いと思います。臆せず、ずうずうしく、それでいて礼儀に反しない程度にお邪魔してくるのがベストかと思われます。ではではまた。
2004年08月14日
-
民弁起案2(一部訂正) +追加
所有権移転登記抹消登記手続等請求事件。最終準備書面の起案。売買の事実を否認。包括的代理権を潰す。94条2項の悪意乃至重過失と帰責性がないことを主張。小問は、土地の移転登記抹消登記手続請求権を被保全債権として、処分禁止の仮登記、及び占有移転禁止の仮処分をする場合の、民事保全手続、及び保全執行の方法。ついで、第三者が訴訟係属中に現れた場合の訴訟承継の要否、並びにその後の執行の方法。処分禁止の仮登記は、書記官が登記所に登記を嘱託(53条3項、47条2項、3項)。占有移転禁止の仮処分は、仮処分命令を債務名義として、執行文付与を受け、というのは間違い。執行文の付与は保全手続では迅速性の観点から原則不要。あぁ、間違えてしまった。仮処分命令を債務名義にして、執行官に不動産を保管して貰い、かつ公示をして貰う。訴訟承継は不要。処分禁止の仮登記は、後れる登記は抹消できるし、占有の移転については当事者恒定効あるから。判決が確定後は登記に関しては、債務名義としての確定判決で足りる。執行文も不要。意思表示は判決時に擬制されるから、現実的な意味での執行が観念できず、執行開始の要件としての執行文は不要だから。他方で、占有移転に関しては、占有が第三者に移転している場合には、現実の明け渡しという執行が観念しうるから、承継執行文とその送達が必要。その上で、執行開始とあいなる。よって、登記に関しては抹消登記の通知が必要。占有移転に関しては、承継執行文とその送達が必要。小問は、結構積極ミスがぽろぽろありました。ちょいとまずったかもです。で、今思ったのですが、本案では登記に関してのみ争っていて、明け渡しについてはなんら書いていないことに気が付きました。ということで、明け渡し関係は基本的に余事記載かも、という感じです。うぅ、まずいかも・・・。最終準備書面としては、構成自体はシンプルでした。それゆえに、間接事実の拾い上げ、評価、証拠からの事実の認定それぞれの段階で、きちんとできているかどうかで差が付きそうな事案でした。あー、結構まずいかも。みんな出来ていそうだし。なお、今年のやつは去年の2回試験の問題ではないかとのもっぱらの噂です。ではではまた。追加・・・謙虚にならないといけないな、と思います。実務修習でちょっとした自信を付け、後期に入って色々と知識を得たりすると、自分がまあまあ出来るような気がしてきますし、また、実際に2か月後には、というかもう一月半後ですが、実務家になっていることを考えると、既にいっぱしの実務家気取りで調子に乗ってしまいがちです。修習生同士で話すときもついつい調子に乗ってしまっているような来もするので、そろそろ気を付けないとなあと思います。あとなんだかせっかちになっているのも、とても問題な気がします。もう少し穏やかな言葉を選べたら良いなと(イライラしているときや疲れているときでも)、思います。とりあえずそんな感じでしょうか。でもまあ、今日は起案後にクラスの友人とがつんと食べて、飲んだのでとても良い気分です。週末はゆっくり過ごそうと思います。にしても、修習生の日記やロースクール生のブログなどすんごいたくさんありますね。スメールさんのところから、色々遊んでみたりすると楽しいです。それに加えて、最近はロースクールの教授のページもたくさんあるので、これもまた興味深いです。研修所の教官もブログとかやればいいのに、ってもうやってる人とかいるのかな???どなたか見つけたらカキコお願いします。ではではまた。
2004年08月13日
-
刑弁起案2
覚せい剤取締法違反被告事件。覚せい剤譲渡の罪で起訴。共犯者(譲受人)の自白と被告人のアリバイ供述。典型事例と言えば典型事例でした。山は当たりました。が、しかし、法曹会の本はとても読み切れず、あまり活かせませんでした。しかし、いかにもアリバイ工作しました、という時に弁護人としてアリバイ工作したことについて、どう弁解すればよいのかがどうもはっきりしませんでした。アリバイ工作と検察官は言うが、どこにそんな証拠があると開き直る態度で良いのではないか、という意見を聞きましたが、ん~、難しいところですね。
2004年08月12日
全597件 (597件中 1-50件目)