テーマ: 日記を短歌で綴ろう(3392)
カテゴリ: 近所のこと
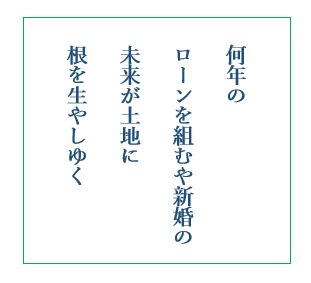
♪ 何年のローンを組むや新婚の未来が土地に根を生やしゆく
南側の家の新築工事が始まった。一昨日、床板を設置する工事をしていた。アッと今に家が建っていく。空き家バンクがどうのという議会の一般質問を聞いてきたばかりに・・。

基礎パッキン工法でコンクリートの基礎の上にパッキンを噛まし、土台や大引を乗せていく。そこに根太を使わない「構造用合板」を用いる剛床(根太レス工法)とか言うらしい工法で床板を張っていた(もちろん断熱材は入れてある)。その床板を釘で打ち付けていたようだ。前に建てていたときも同じことをしていたのだろうが、今回の2人でやっているそのトンカチの音がやたらに喧しかった。釘の数が多い?

この家の時は1人で、補助的にくぎを打っている感じだった
今回はパネルの四方全体に細かく打ってあるようだ。数が数だけに必死になって打っている姿がいかにも素人っぽく、印象的に残っている。今は大工というより組立工で、カンナも金槌もあまり使うことがないのだろう。

この日は早朝までかなりの雨が降った。それが止むのを待っていて、10時過ぎに工事が始まった。その最初のとっかかりにアルバイトらしき私服の若者が何人か働いていた。アルバイトにも務まるのかと、意外な感じがした。

この画面の中だけでも6人いる。
こじんまりした家だが、今日中に建ち上げてしまうため、雨の遅れをカバーするバイトが必要だったのだろう。プレカットした材木を所定の場所に運ぶだけでもバイトがいればずいぶん違う。
若い夫婦らしい施主も見学に来ていた。上棟式みたいなものはしないものの、家が建ちあがる様子を見るのは楽しいことだろう。

組み建てていくだけなのでどんどん出来上がっていく。
「いつ引っ越しですか?」と訊いてみた。9月の後半とのこと。3カ月後にはも入居できるわけか。昔なら半年以上、場合によっては1年がかりだった。今はもう、3カ月で即席ラーメンみたいに出来てしまう。有難味が少ないというか、味気ないというか・・。

12時40分
1日が一番長い季節なので、作業も落ち着いてできるだろう。陽が短い秋ともなると、あっという間に暗くなってしまうからねぇ。

日進市から知多市へ移住して来るらしい。理由を聞くと知多市の方が安いからと。確かに日進市は発展している最中で人気があって、不動産も高い。
この地の利があって角地で、南向きの一番いい場所が売れ残っていたなんて、運が良いとしか思えない。

もう一軒の方も基礎のコンクリートが打ち終わり、型枠を外してしまえば後はもう棟上げを待つばかり。こちらもほぼ同時に完成して、今年中に2所帯が隣保班に加わることになりそうだ。


基礎パッキン工法でコンクリートの基礎の上にパッキンを噛まし、土台や大引を乗せていく。そこに根太を使わない「構造用合板」を用いる剛床(根太レス工法)とか言うらしい工法で床板を張っていた(もちろん断熱材は入れてある)。その床板を釘で打ち付けていたようだ。前に建てていたときも同じことをしていたのだろうが、今回の2人でやっているそのトンカチの音がやたらに喧しかった。釘の数が多い?

この家の時は1人で、補助的にくぎを打っている感じだった
今回はパネルの四方全体に細かく打ってあるようだ。数が数だけに必死になって打っている姿がいかにも素人っぽく、印象的に残っている。今は大工というより組立工で、カンナも金槌もあまり使うことがないのだろう。

この日は早朝までかなりの雨が降った。それが止むのを待っていて、10時過ぎに工事が始まった。その最初のとっかかりにアルバイトらしき私服の若者が何人か働いていた。アルバイトにも務まるのかと、意外な感じがした。

この画面の中だけでも6人いる。
こじんまりした家だが、今日中に建ち上げてしまうため、雨の遅れをカバーするバイトが必要だったのだろう。プレカットした材木を所定の場所に運ぶだけでもバイトがいればずいぶん違う。
若い夫婦らしい施主も見学に来ていた。上棟式みたいなものはしないものの、家が建ちあがる様子を見るのは楽しいことだろう。

組み建てていくだけなのでどんどん出来上がっていく。
「いつ引っ越しですか?」と訊いてみた。9月の後半とのこと。3カ月後にはも入居できるわけか。昔なら半年以上、場合によっては1年がかりだった。今はもう、3カ月で即席ラーメンみたいに出来てしまう。有難味が少ないというか、味気ないというか・・。

12時40分
1日が一番長い季節なので、作業も落ち着いてできるだろう。陽が短い秋ともなると、あっという間に暗くなってしまうからねぇ。




この地の利があって角地で、南向きの一番いい場所が売れ残っていたなんて、運が良いとしか思えない。

 最後の追い込み。6人がかりでやっつけていく。
最後の追い込み。6人がかりでやっつけていく。
もう一軒の方も基礎のコンクリートが打ち終わり、型枠を外してしまえば後はもう棟上げを待つばかり。こちらもほぼ同時に完成して、今年中に2所帯が隣保班に加わることになりそうだ。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[近所のこと] カテゴリの最新記事
-
★ コミュニケーション・モンスターがブチ… 2024.01.19
-
〇〇 若返りゆくを楽しむ春の宵 2023.04.22
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
サイド自由欄
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
◎たまに見るページ
◆ 一減一増。捨てネコを保護 2011年9月19日
◆ 胸は男女の象徴としてあり 2015年2月12日
◆ 好きこそ何とか、ものを創るとは好きを極める事 2015年4月22日
◆ 文字の持つ多様な姿 2015年7月27日
◆ 他人を寄せ付けるか、あるいは自分が寄っていくか 2015年10月8日
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
◎たまに見るページ
◆ 一減一増。捨てネコを保護 2011年9月19日
◆ 胸は男女の象徴としてあり 2015年2月12日
◆ 好きこそ何とか、ものを創るとは好きを極める事 2015年4月22日
◆ 文字の持つ多様な姿 2015年7月27日
◆ 他人を寄せ付けるか、あるいは自分が寄っていくか 2015年10月8日
フリーページ
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.












