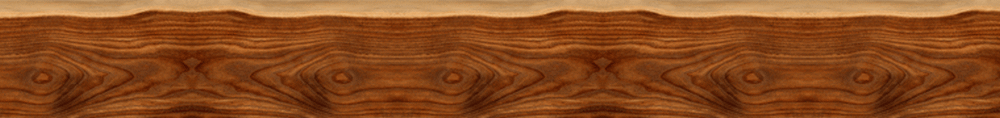プロローグ
~遠い日の欠片~
はちがつ ふつか はれ
ぼくは、きょうふしぎなおんなのひとにであいました。
ぼくは、おつかいをおかあさんにたのまれて、おさかなやさんにいきました。
おさかなやさんには、いっぱいのおさかなさんがいて、ぼくはたのしくなりました。
でも、ぼくはいいこだからよりみちせずに、さんまをさんびき、おとうさんとおかあさんとぼくのぶんをかいました。
ぼくだって、おかあさんのやくにたつんだぞ。えっへん。
かえりみち、こうえんできれいなおんなのひとが、だれかをさがしているのをみつけました。
ぼくは、おかあさんとおとうさんに、いつも「困ってる人がいたら助けてあげなさい」と言われていたので、おんなのひとをたすけてあげようとおもいました。
そのおんなのひとは、ぶどうみたいなかみのいろで、なんだかめがするどかったので、おっかないひとにみえました。
でも、こえをかけてみるとおかあさんみたいに、とってもあたたかいかおで、こっちをみてわらいかけてくれました。
としはおかあさんとおなじくらいかなぁ?
ぼくは、おんなのひとのとしをきいてみようかとおもいましたが、まさゆきおにいちゃんといつもいっしょにいるおねえさんが、いつもいつも
「れでぃーにとしをきくのは、さいていよ!」
といって、まさゆきおにいちゃんがおこられているのをみているので、としをきくのはいけないことだとおもい、ききませんでした。
おんなのひとに、「さがしものですか?」と、ぼくがきくと
「ええ。そうなんだけど。もう見つかったわ。ぼくのおかげよ。」
と、とてもうれしそうにわらいました。
ぼくは、なにもしてないので、へんだなーとおもって、そのおんなのひとにきいてみました。
「なにをさがしていたんですか?」
おんなのひとは、ぼくをみてにこりとわらうと
「ふふふ。内緒。」
といって、ゆびをくちびるにあてました。ぼくはふしぎなひとだなぁとおもいながら、とてもきれいなわらいかたをするひとだなぁとおもいました。
ぼくが、なんだかよくわからずぼーっとしていると、おんなのひとはぼくのおでこにおでこをあわせて、
「いい?僕?これから貴方は、様々な困難に出会うわ。大切な人を失うことももちろんあるでしょう。出会いの数だけ、別れは訪れる。それは必然。
でも、別れが多いということは、それだけ多くに出会えたことの証明でもあるの。
そして大切なものを失った時、絶対負けちゃダメ。そして憎んでもいけない。誰でも許せることって、とても大事なことなの。相手の事も、もちろん自分の事もね。
誰にだって『物語』はある。それが喜劇になるか悲劇になるかは、努力と捉え方次第。
もう逢えないことよりも、出会えたことを喜べる大人になってね。おねえさんとの約束!」
なんだかむずかしくて、よくわからかいことをいうと、おんなのひと・・・ううん、おねえさんは、こゆびをだしました。つられてぼくもこゆびをだしました。
「はい!ゆびきーりげんまん!うそついたらはりせんぼんのーますっ!!」
おねえさんはげんきいっぱいに、たのしそうにぼくとゆびきりしました。
ぼくは、もうひとりでおつかいできるおとななので、はずかしくてしたをむきました。
でも、このおねえさんをとてもすきになったので、なまえをきこうとかおをあげました。
あれ?
さっきまで、ゆびきりしていたおねえさんは、どこにもいませんでした。
でも、ゆめなんかじゃないとおもいます。そのしょうこにおねえさんのいいにおいと、ゆびきりしたときのあったかさ。
そしてなにより、わすれられないとびっきりのえがおが、ぼくのこころにのこっていたからです。
あの、おねえさんはだれだったんだろう?
おかあさんにもおとうさんにきいても、まさゆきおにいちゃんにきいてもわかりませんでした。
おわり
「・・・そうか、あれは、お前だったんだな。」
月明かりの下、その淡い光に照らされて輪郭が曖昧な、まるで幻影とよんでもさしつかえないような男が一人ぽつりとつぶやいた。
「すまないな。俺は、あのときの約束は果たせなかった。そして、これからも果たせそうにない。」
誰に言うでもなく、続ける。その台詞には、何の感情も含まれていない。聴衆はさしずめ月と虫たちくらいのものだろう。
「思えば・・・・」
男は、さもめんどうくさそうに立ち上がる。
「おまえに出会った時から、俺の人生は狂い始めたんだよなぁ。」
ククッとくぐもった笑い。だが、懐かしむような暖かい笑い。
男にしては、珍しく自嘲も嘲笑でもない、純粋な微笑みであった。
男は、ふっと、感慨に耽る。
「あぁ・・・そういえばお前のところに行かなくなったのは、いつからか・・。今となっては、思い出せるはずもない・・・な。」
男は、彼女に花を手向けようと思い立つ。浮かぶは彼女との穏やかな記憶。
「はははっ・・お前は、花なんかよりも食い物の方が喜ぶようなヤツだったよな。」
男は、彼女の好物であった苺のババロアを思い出し、一人嗤う。
本気で、パティシエなんかを目指していた秋の日を想いながら。
「死者に花を手向けて救われるのは、死者ではなく手向けた人間。即ち、遺された方ってヤツさ。死者は黙して語らず。要するにただの自己満足って事さな。
・・・どのみち、ババロアの作り方なんて記憶の遠い彼方に消えちまったさ。」
悪態をつきながらも男は笑い続ける。
それは、男に残った最後の想い出。唯一の日だまりのような追憶。
「日記か・・・・感傷に捕らわれるなんてらしくないな。」
男は、漏れ出すような含み笑いを続けながら、日記帳を遠くへ投げ捨てようとした。
―――だが、思い出を紡いだそれは男の手を離れることは無かった。無意識にひしっと掴んで離れない。
「やれやれ・・・。俺もまだまだ甘いな。深層意識レベルで未練でも残ってるんだろうな。
まぁ、持っていても邪魔になるような事はないだろう。」
そう独りごちると、マントと呼んでも間違いでは無いくらいの幅広なコートに、遠い夏の欠片をしまいこんだ。口調では辟易しているように聞こえるが、正の感情は隠しきれない。過去をゆっくり反芻しているかの表情。
そこには、男のかつての人格が見え隠れしている。
「だが、お前はもういない。温もりと思い出だけを残して消え去っちまった。」
男はスッと、顔から喜の感情を消す。
「あの日から、俺の存在する意味は変わった・・・」
静けさが周囲を支配するなか、男の足音と声なき声だけが木霊する。その口調は弾むようで、何の悪びれた様子もなく、唄うように呟いた。
「―――世界の敵であることに。」
Act1 赤ずきんへ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 『眠らない大陸クロノス』について語…
- チケット系の意見 個人的なまとめ
- (2024-10-24 04:28:14)
-
-
-

- フィギュア好き集まれ~
- とある科学の超電磁砲 佐天涙子 レー…
- (2024-12-01 19:46:52)
-
-
-

- アニメ・特撮・ゲーム
- 【11/25限定 1等最大100%ポイントバ…
- (2024-11-25 15:39:02)
-
© Rakuten Group, Inc.