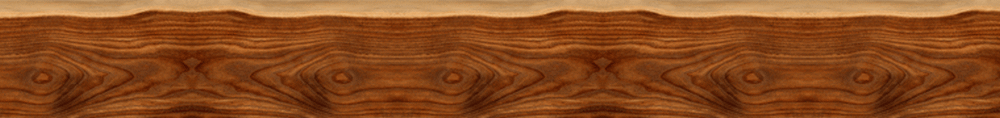Act 2 続き
樹は料理が出来ない社会不適合者なので、未来が作ったのであろう。
今まで、帰ってきてご飯が用意されている、という経験がほとんどない瞬にとっては新鮮な出来事だ。
加えて、身体が冷え切っていたので、てっとりばやい暖でもある。ありがたみが増すというものだ。
だが、一人分しか用意されてない。何故かと未来に問うと、樹があまりにも急かすので先に食べてしまったのだそうだ。実にあいつらしいな、と瞬は苦笑する。
席に着くとおいしそうに湯気を立てているピザトーストに齧り付いた。
「ぬっ・・・これはピザ・・・なのか?」
口に入れるなり違和感が瞬を襲う。
味は確かにピザであった。だが、未来の料理は食感が異質なのだ。
昨夜が綿ならば、今夜は紙だ。一体どんな調理法と食材を用いればこうなるのであろうか?
少なくとも冷蔵庫に入っていたものは普通の食感の食物であった。
そんな重要事項を失念するとは俺は相当な迂闊者であるな、と、瞬は心底落ち込み、肩を落とした。
再び、ガッカリな結果となった食事を終えると、風呂へと向かう。
先程、風呂上がりの樹に会ったので、どうやら空いているようだ。
芯から冷え切っていたせいか、やはり食事だけでは十分に暖まれなかったようである。
脱衣所に入り、がらりと浴室の扉を開いた瞬は
「ふぇ・・?」
呆然としている未来と目が合い、そのまま無言でぴしゃりと閉めた。
「お、おおおおおおお風呂にはいきなり入ってくるなんてさいてーだよっ!もうっ!」
脱衣する前で良かったと瞬は心の底から思う。
ダボダボのパーカーや、恐らく包帯を隠すためであろう、少し大きめの制服などで、中々気付けなかったが、未来の身体は、存外に整ったプロポーションであったからだ。
もしも、全裸の状態であったならば、きっと身体の一部の生理反応を誤魔化すことができなかったであろう。
未来は、胸囲こそ無いが、丸みを帯びていて、きちんとした女性の体つきであった。
幼児体型というワケでは無かったのだ。
幼く見えるのは身長の低さと、その童顔、無邪気な性格によるものと言えるであろう。
「安心するがいい。湯気が多くて見えてはいない。もっとも見るべき所も無いがな。」
磨りガラス越しに、コホン、と一つ咳払いをした後、取り繕う。
無論、嘘八百である。しっかりと脳と双眸にその姿を焼き付けている。
「な、なななんだとーーー!!見るべきところが無いかどうか、きちんと見ろっ!ほらっ!ほらっ!」
勢い良く扉を開ける未来。
間近にその肢体が突きつけられ、慌てて目線を下に向ける瞬。直視は心臓に悪すぎるというものだ。
「・・・・・・・・・・・あ。」
勢い余ってやってしまった自らの行いに、未来は、少し冷静になると、わーー!という絶叫を上げながら浴室の扉を壊れそうなくらい激しく閉めた。
「ぅぅうううう・・・ぐすっ。」
扉越しには未来が鼻を啜る音をたてながら、考えるよりも先に行動してしまう自らの性格を悔やんでいる。
「その・・・ところで未来。・・・主の腹の傷はなんなのだ?少し大きいぞ?」
そんな未来の様子を見かねた瞬は、口火を切る。話のとっかかりを作ろうと模索した故の結果である。
空気の読めなさもここまで絶望的だと犯罪モノというものではあるが。
「うぐっ・・ひっく・・・うん?なんか物心ついた時にはあったんだよー。けっこう大きい傷だから、記憶に残ってそうなものなんだけど、さっぱりなんだ。
・・・って、やっぱり見てたんじゃんかー!!!ばか!ばか!ばかぁ・・・」
案の定、藪をつついてアナコンダと邂逅する羽目となった。
これ以上は藪から八岐大蛇が出てくる可能性も否めないな、そう判断した瞬は、すごすごと部屋に戻る事にした。
自室のソファーに座り込みと、暖を取るためストーブを付ける。
「・・・あの傷には何故か見覚えがある。デジャビュというヤツであろうか?」
呟くように、一人考え込む瞬は、部屋が暖まってくると同時に深い眠りへと誘われていた。
~~~~~
「ラグ爺。僕も、クリスマスやってみたい。」
冬の寒空の下、かじかむ両手を自らの吐息で温めながら、共に歩む老人に何の気無しに呟く少年。日も昇り始める時間帯であるが、曇天の為か気温は上がらない。
どうやら今夜はいつにもまして冷え込みそうである。
だが、色めき立つ町並みはその寒気を忘れてしまいそうなほど活気に溢れ、騒がしい。
少年の年齢は10にも満たないであろうが、落ち着いた印象である。
その童顔も相まって実年齢よりずっと幼く見える。外見との齟齬を感じるが故に、余計にそう印象付けられる利発な雰囲気を湛えた少年である。
対照的に、シルクハットを目深に被る紳士然とした老人は、隠居してもおかしくない年齢ではあるが、腰が曲がっているワケでも無く、血色も良く、老いてますます盛ん、と言った様子の快活な印象を受ける。
少年にとって、クリスマスという行事で浮かれている町全体は今まで体験したことのない世界。
だからだろう、なんとなく興味を惹かれてしまったのは。
老人は、少年の控えめな声色の頼み事に、印象通りの豪快な笑い声を上げると得意げに胸を叩く。肯定の意である。
だが、その勢いが強すぎた為か激しく噎せる。
その仕草に頼りなさを覚えつつも、老人の咳き込む姿が何だか可笑しくて少年はクスクス笑う。
「お!初めて笑ったのう!そうじゃ。・・・それでいいんじゃ。子供はそうして笑っているのが一番自然なんじゃ。笑えなくなるって事はとても悲しい事じゃからな。」
見た目の印象とは裏腹に、アイスブルーの、まるで深淵を見通す様な思慮深さを湛えた瞳が、少年の漆黒の双眸を慈しむように覗き込む。とても暖かい、それでいて澄んだ眼差しである
「・・・ラグ爺はみんなと違って何で僕に親切にしてくださるのですか?」
少年は小首を傾げながら老人へと問いかける。
―――少年は所謂孤児であった。
両親に捨てられたか死んだのかは定かでは無いが、物心ついたときには、その異能とも言うべき才能を見いだされ、現在の位置にいる。
本来、親から向けられて然るべき愛情や、笑い方を知らず成長してきた少年にとって、他人からの無償の愛は初めての経験。故に、その意図が理解できない、といった様子である。
「なぁに。血よりも確かな絆ってのはあるってことじゃよ。・・この答えじゃ不服かな?」
と、少年の頭をわしゃわしゃと、その傷だらけの大きな手が髪を乱すくらいの荒っぽさで撫でる。老人の言葉は、まだ幼い少年には理解できなかったが、その感触に心地よさを感じた少年は、ただ目を細めて受け入れた。
少年にとって、老人は実の家族では無い。
だが、実の孫・・いや、それ以上に接してくれる老人は、少年にとって紛れもない“家族”であった。
「のぅ、儂らに子供達の未来を奪う権利は無いと思うんじゃ。生を謳歌する義務があると言っても良い。汚い仕事は儂らだけでいい。瞬ちゃ・・・いや、『月読命』はまだ幼い。今ならまだ日の光を浴びれる世界に戻れるはずじゃ。」
少年の願いを聞き届けた老人は、スーツ姿の顎髭を生やした短髪の男に提案する。
おそらくは所属している組織の、首魁とおぼしき人物であろう。
そしてそれは、提案というよりは、懇願に近い泡沫の想い。傍らに佇む少年は、不安そうに双方を交互見る。
「ほぅ。戦場では『神風』と謳われた、軍神『ウルスラグナ』ほどの男が、そのような世迷い言を吐くのか?
言ってる事があめぇよ。それにてめぇは一つ勘違いをしているな。
そのガキが既に何人殺していると思ってる?十分、闇に魅入られてるさ。あいつは立派にこちら側の人間だ。」
額に手を当てて、堪えきれない、といった具合に笑みが零れるスーツの男。
たまらず、老人の袖をギュッと掴む少年。
何故だろう?今まで、標的の存在、生きてきた証そのものを刈り取る行為自体には何も感じなかった少年であるが、そのことを老人に知られた事がたまらなく怖かった。
それはきっと、少年の心の底にこびり付いていた良心の残滓。合わせて、老人に嫌われてしまうかもしれないという、僅かばかりの依存心がさせたのだろう。
少年はそのまま俯き、微動だにしない。
老人も、その事実に薄々感づいていたのか、歯ぎしりをする音が少年の耳に届く。
少年は大切な何かを失ってしまいそうで、その姿を直視できない。
老人の顔は今、きっと怒り、悲しみ、憎しみなどがないまぜになった表情をしている事だろう。
「ん?なんだ?その面は?そのガキから聞いてなかったのか?まぁ、そんな事はどうでもいい。
・・・要するに、だ。こいつは成長すれば立派な兵隊となる。それこそ戦場で英雄と謳われたてめぇよりな。」
スーツの男は、老人を一瞥すると、懐から煙草を取り出し、火をつける。
そして、幾ばくかの紫煙をその口から燻らし
「まぁ、この際だ。はっきりと言っておこう。てめぇらは、ホイホイ黙って俺様の言うこと聞いてりゃ良かったんだよ。何か目的を持って物事を押し進めるとき、情ほど邪魔なモノは無いって事だ。一旦、情が芽生えたらそれはなかなか取り去れない。全く厄介なこって。」
そう、静かに言い放つと
「お前らはもういらねぇ。『月読命』を失うのは惜しいが、空位を作った方が効率的だ。新しい兵隊がはずれの能力なら、また処分すれば良い。・・・・やれ、エスター。」
まるでトランプゲームでパスをするかの様な気軽さで言い放った。
言葉を言い終えるか終えないウチに、年は十代半ばといった所であろうか、何の覇気も感じられない少年が影より出でると、老人と少年へと僅かばかりの逡巡も無く、手にしたリボルバーの引き金を引く。
両手からは計12発。それは全て二人の急所を狙って撃たれたモノで、まさに瞬く間に発射される。
老人は咄嗟に少年の前に盾になるよう仁王立ちをし、放たれし12の鉛塊を手にした棒状のモノで弾き落とす。
銃弾が当たる瞬間、得物を微細に動かし運動エネルギーを逃がす事による防御である。
それは、まさに流水のごとき技術。老人が累々たる死線をくぐり抜けてきた証でもある。
「ほぅ。腐っても軍神なだけはあるな?達人武器を選ばずというヤツか?よもや孫の手ごときで高速の飛び道具を防ぎきるとはな。」
「儂をやりこめようならば、戦車の一台でも持ってくる事じゃな。」
賞賛の言葉に軽口を叩く老人ではあるが、旗色は悪い。
エスターと呼ばれたガンスリンガーは、弾切れと共に懐から別の銃を取り出し、トリガーハッピーのごとき怒濤の弾幕を張る。
それは、薄れる気配が無く、老人は防戦一方と呈していた。
#19はここからです=========
「な?すげぇだろ?こんな風に何の躊躇いも無く殺しができるんだ。因みにこいつは月読命に施したカリキュラムのサンプルだったガキだ。
・・・ガキだから。ガキだからこそだ!こいつらは、自分の命、他人の命を超越した世界で生きてんだよ。心が出来上がってから施した教育じゃ、こうはいかねぇ。
月読命のような優れたポテンシャルを持たない、何の異能も無いタダのガキでさえ、この戦闘力。全く笑いが止まらねぇ!」
仰ぐように、両手を広げ、自慢のコレクションを披露するコレクターの様に朗々たる声をあげるスーツの男。
少年はそのブギーマン然とした様子に身震いし、動けない。
エスターの様に人としての感情を待たなかったのなら、こうはならなかっただろう。
人の、老人の優しさに触れ、自我が芽生えてしまった故の、相手の力量を推し量れるからこその畏怖。なんとも皮肉な話である。
「このままでは、ジリ貧じゃな。ならば活路を開くまでっ!」
ひたすら受け身に回り、後手後手になっていた老人は、言うなり、手にした孫の手を、特殊警棒のように延長し、折りたたみ傘を開くように展開する。
その先には、爪状の鋭い刃物が五振り。老人の愛用する武器の真の姿。
対象を引き裂き、中身を掻き出す事に特化した凶器、元来の意味「馬子の手」を体現する暗器である。
それを構えると、無表情な銃使いへと突進する老人。
吹き荒ぶ嵐と比喩しても大袈裟ではない銃弾の五月雨は、老人に、時には裂かれ、時には易々と躱される。
イノシシのごとき猛襲をかけるその姿は、まさに戦の神ウルスラグナ。
戦争の勝利を司り、障害を打ち破るモノを意味する字(あざな)。それが宣言通り血路を開く。
―――「逃げろ」と老人の背中が語っていた気がした。
少年は、それを見てたまらず逃げた。暗殺者として育てられていたからだろう。勝算が五分以下ならば、撤退。最早、本能レベルで身体に染みこんでいる思考。
それが「逃げろ」と告げていた。
故に、少年は逃げた。脇目もふらず。振り返りもせず。脱兎のごとく。ただひたすらに。命が惜しくて。自分可愛さのあまりに。
それが、少年の見た老人の最後の姿。その後どうなったのかは知らない。
のちにエスターというキリングマシーンが追いすがって来たという事は、おそらく無事ではいないだろう。
幾千もの過酷な夜を越えた老人は、誰よりも強く。―――そして、誰よりも優しかった。
どれくらい走ったのか最早定かでは無い。日は既に落ちて久しい。
今では、薄ぼんやりと下弦の月が儚く嗤う。天候の悪さも相まって雪が降り出し始め、それがまた少年の体力を無慈悲に奪っていく。体力的にも精神的にも臨界点に達している。
加えて、少年の特殊な体質は体力の消耗が人よりも何倍も激しい。
いつもはそれを補う為に、常人よりも過多な睡眠時間、無駄の無い動き、呼吸法を使用しているが、まさしく命からがらの状況である今は、そんな事にかまけている余裕もない。
疲労が蓄積されていたからか、少年の足は痙攣し、もつれ、転げる。
俯せの視界には子供が遊ぶ小さな滑り台が映る。どうやらどこかの公園の様だ。詳しくは解らないが。
降り積もる雪が徐々に少年を覆っていく。このままでは、凍死は確実だ。頭では解っていても身体は動かない。それぞれが別々の生き物になってしまったかのようだ。
自分が気紛れにした発言でこのような事態になってしまった情けなさや悔しさが少年の中では渦巻いていた。
そして、もう傍にいない、自分に初めて温もりをくれた老人。初めて心を許した“家族”。その喪失感。
でも、何故か涙は出なかった。
情けなさ過ぎて、結局誰も救われない現実を嘲笑したい心境であったからかも知れない。ただただ、嗤いが止まらなかった。
世界は、少年を大悟させるには十分過ぎるほど、どうしようもなく理不尽で、
―――そう、まるで、この降り積もる氷の結晶の様に冷たかった。
「ねぇ、ここはベットさんじゃないよ?」
その、命の灯火が今、まさに消えようとしていたとき、少年の上に何かが陰る。
少年が、さも面倒くさそうに顔を上げると、少年と同じ年齢ぐらいで在ろう少女が、かがみ込み、キョトンとした、何とも愛らしい顔で見つめていた。
「僕に干渉するなっ!」
先程まで自嘲気味に、この世の全てが馬鹿らしくて、嘲嗤っていた少年であったが、不意にいきりたつ。
少女のあどけなさに無性に腹が立った。なんで、こんなにもこいつは自分と違い平和そうな顔をしているのだ、と。
ただ、ここにいる少女と同じように、クリスマスというお祭りをやってみたかっただけなのに、何故、自分だけがこんな目に遭うのだ、と。
「うるさいっ!」
叱咤とともに、少年の腹に少女の拳が入る。
その容赦の無い一撃に、藻掻く気力、体力すら失われていた少年は受け身をとる事すら叶わず、直撃を食らう。
今の少年にとっては、少女の一撃ですら致命傷に近い。少年は息も絶え絶え、喘息患者の発作の様に喘ぎ声を上げる。
「なんでもいいから黙ってね。私の家に連れて行くから。」
一方、少女は悪びれた様子もなく満面の笑みでそう言い放つと、ちょっと重いから自分でも歩いてね、と一言。少年の肩を自分の肩に掛ける。
それによって、少年は少女に体重のほとんどを預ける形となり、無理矢理立ち上がらせられる結果となった。
「なんで・・?放って置いてくれって、言ったじゃないか。僕の事なんか助けたって何の得にもならない。むしろ災いだ。ラグ爺みたいにきっと不幸になる。」
先程の一撃から、幾分か呼吸を正すと、少女に抗議する。
少年にとって少女の行動は理解の範疇を越えていたからだ。
少年の生きていた世界は、生き馬の目を抜く世界だ。他者を蹴落とし、ときには屠り、甘さは自らの破滅を招く、そんな世界。
「だからうるさい!」
「がっっ・・!」
少女の肘が少年の腹に再び入る。今度は呼吸が一度止まるくらいのクリーンヒットだ。
視界が0コンマ1秒ほど暗転し、意識がブラックアウトしかける。
「ん~・・『なんで?』って言われても、そんな大した理由じゃ無いよ。私が昔ピンチさんだったときね、
『助けられるなら、見捨てるなんて真似出来ない。人が誰かを助けるのに理由はいらない。』って、私の初恋の人、私のヒーローさんはそう言ってたんだよー!
だからね、私は今度ヒーローさんに会った時に胸を張れるようになりたいんだっ!
つまりね、君の為じゃなくて、私の為!私の我が儘っ!だから君に文句なんて言わせないよ!」
少年にとっては似ているのかどうなのかの判別はつかないが、少女が声色を変えて話す様から察するに、そのヒーローとやらは、どうやら男の子なのだろう。
嬉しそうに、それでいて得意気に、クスクス笑う少女は、外見こそ自分とそう変わらない年齢であるが、少年の目にはとても大人びて見えた。
「ただいまー!」
元気一杯、勢いよく玄関のドアを開ける少女。
公園からここまでそれなりの距離があり、加えて少年を支えてきたので、疲れの一つでも見せておかしくは無いが、そういったものは見られない。まさに天真爛漫といった様子だ。
対照的に少年の体力は、リザーブタンクの底すら既に尽き、エンスト状態といったくらい疲労の色が強い。
少女の無意味なくらいの快活さは、少年を鼓舞、励起させる為も在るのだろう。
おかえり、と出迎えたのは白衣姿の女性であった。
少女が年齢を重ねれば、このような美女になるだろう。瓜二つである。少女の態度、様子から察するに、どうやら少女の母親のようだ。
「遅かったわねー。今日はクリスマスだから早く帰るように、って言ったでしょ?マツリも光子ちゃんが帰ってくるの待ってたみたいなんだから。光子ちゃんにばっかり懐いちゃって、もう。私が呼んでも全然反応しないんだもん。」
童顔なのか、単純に若いのか、少女の姉と言っても何の違和感もない、白衣姿の女性は、困っちゃうわねー、と溜息を吐く。
「あれ?そこの男の子は?お友達?」
白衣の女性は、嘆息から顔を上げ、改めて少女に目を向けると、見慣れない少年が少女に寄り掛かるようにして傍にいる事に気付く。
「うん!なんか凄く疲れてるみたいだから、連れて来ちゃった。」
えへへ、と舌を出しイタズラに笑う少女、光子。
白衣の女性もそれを見て、もう、なんて言いながら柔らかく微笑む。
子供を愛する心を持つ親にしか出来ない、全てを包み込むような、穏やかな海を想わせる母性を湛えた笑みである。
「僕のお名前は?」
少年の目線に合わせるようにしゃがみ込むと、同じように微笑し、穏やかに語りかける白衣の女性。
「・・・つくよみの・・いや、瞬。・・・神風瞬。」
――
―――
――――
「・・・今、何時だ?」
ソファーから転落し、目が覚める。
魘され、身体は妙に汗だくだ。少し前まで嫌な夢を見ていたからであろう、現実に戻った今となっても、何十キロも奔ったような疲労感が残る。
外を見ると未だ暗い。どうやら、まだ夜は明けていないらしい。
一度寝たら、起こされない限り、途中で目覚める事の無い瞬にとって、これは異常であると言える。
どうもここ最近様子がおかしい。頻繁に昔の夢を見る。
―――おそらくは未来の影響であろう。
彼女を見ているとその容姿の所為か過去の出来事が甦ってくる。
過去を思い出す事が無いのは、忘れた事が無いからだとは思っていたが、自分の記憶のピースが所々抜け落ちている事に改めて気付く。
「・・・懐かしいな。そうだ。あの日から俺は『神風瞬』となったのであったな。」
一人呟く。ラグ爺の生きた証だけは失いたく無い。あの日、そんな想いから気付いたら、そう口にしていた。
―――「瞬」。本当の名前すらも知らない自分に、老人がくれた名前。
―――そして、「神風」。老人が戦場にて謳われていた通り名。「月読命」というコードの少年が死んで、「神風瞬」という人間が産まれた日。
「そうだ。俺は、あのときラグ爺を見捨てて逃げたのだ。
・・・ヒカリ、ラグ爺。俺はいつもそうだ。大切なモノほど、この両手から滑るように零れ落としてしまう。もっとも、守る努力すらせずに逃げ出すような下衆が何かを掴みとろう、などとは些か虫が良過ぎる、か・・・。」
手を翳し、己の、何も守ることが出来なかった手のひらを眺める瞬。いくら優れた力を持とうとも、扱う人間次第でその価値は変わる。
それで何も掴み取れないのなら、それは無いに等しいのだ。瞬の中に、虚しさと苛立ちだけが募っていく。
そんな事を、思案していると、ふと、頬に何か暖かいモノが伝う。それが、口に入り、妙に塩辛い。
「・・・俺は、泣いているのか?」
何年か越しに、流された涙。あの日公園で流すハズであったそれが、堰を切ったように溢れ出す。
そして、同時に零れる笑み。己に人間らしい感情があった事が、ただ嬉しい。それ故の笑み。
あの日の自嘲じみた歪な嗤いでは無く、真っ直ぐな、それでいて純粋な感情、喜怒哀楽による笑みが、―――あの日の少年、瞬の表情を象る。
「わーー!瞬君が泣きながら笑ってるっ!こ、こわいっ!頭がおかしくなっちゃったのっ?!ミラージュさーん!瞬君が壊れちゃったよぅ!」
少し大きめな声で笑っていたからであろう、たまたま部屋の前を通りかかった未来に見られる羽目となってしまった。激しく狼狽した様子で階段を駆け下りる未来。
「うるさい。馬鹿者・・・。」
言葉とは裏腹に、慈しむような表情で、未来が去るのを見届ける瞬。
賑やかで、常に前向き、己と正反対の性格であるが、どこか似た境遇を持つ少女、未来。
――彼女を守ることが、先の二人への償いになるだろうか?
それは誰にも解らないし、ただの自己満足と言えるだろう。
だが、瞬は、未来を守ることを決意した。誰でもない自分自身の為に。あの日の少女と同じ自身の我が儘の為に。
#20はここからです=========
翌日、未来は終始、にやけ顔を湛え、ご機嫌であった。
昨晩、瞬の弱みを握れたからだ。
18にもなる男性にとって、泣き顔を見られるという行為は面子に関わる拷問である。
特に、少女に見間違われる程の童顔から、ネタにされたり(主に三河に、であるが)、子供扱いされたりする事が多い瞬にとっては人一倍、矜持や沽券に関わる。
未来は、瞬がいつものように、皮肉混じりにからかおうとする度、総一や三河、果ては朋香にまで、話す素振りを見せ、牽制する。
「なになに?なんか面白い話でもあんの?」
面白そうな話には必ずと言っても良い程、興味を示す三河は、野次馬根性全開だ。まさに、入れ食いである。
「いいや、大した話題では無い。主から毎度繰り出される、身を削ったギャグには負ける。」
瞬は、未来の方をチラチラ気にしながら、話題を逸らそうと必至である。
この心境は、テロリストに占拠された現場の人質と酷似している、と言っても過言では無い。又は、そのネゴシエーターと言った所か。
「また、去年みたいに樹がイタズラでもしたのか?いやーあの女モノのカツラの似合い具合は見事だったなよなぁ・・。三河じゃ無いけど、けっこうグッときたぜ?」
くくく、と忍び笑いする総一。
きっと現在、彼の脳内では過去の映像が投影されているのだろう。漏れ出す様な笑いである。
「わわっ!それ、なんか面白そうな話かもっ!詳しく聞きたいんだよっ!」
目を爛々と輝かせる未来は身を乗り出すと共に、口元を猫のように緩める。もっとも、瞬にとって、その姿は憎めないイタズラ子猫のような可愛らしいモノではなく、チェシャ猫の様にいやらしいものであるが。
総一の言霊じみた一言は、瞬の努力を間髪入れずに水の泡にした。
「何でもない!総一!主も黙るのだ!」
いつになく狼狽し、まくし立てる瞬。
己の消し去りたい恥ずかしい過去に、流石に平静を保つ事が出来なかったようだ。
一方、総一は、へいへい、と飄々とした笑いを浮かべ、肩を竦める。
「あ、あの・・その・・えっと・・神風君のお話だったら私、聞きたい・・です。」
先日に続き、朋香らしからぬ発言に瞬を始め、一同は困惑する。
今のように自ら話に入ってくることは皆無で、消極的で内気な少女。
それが、皆の、黒崎朋香という少女の認識である。
これも未来の影響によるモノなのだろうか?
普段ならば、その正のベクトルへの変化に手放しで喜ぶところであるが、今はそうも言っていられない。
まさに、朋香の発言は爆弾に衝撃を加える、火に油を注ぐ、と形容できる代物である。己の事で精一杯だ。
「そぉ?じゃあ、朋香ちゃんだけには特別教えちゃおうかな~?」
案の定、未来は待ってましたとばかりに、朋香の耳に顔を近づける。
朋香は照れて顔を、熟れたさくらんぼみたいにしながらも、期待に胸を躍らせ待ちきれないといった様子でそわそわしている。
事態に、精神的大ダメージを被る危険性を感じた瞬は、脳内で発令されたエマージェンシーコールに従い、未来を射殺す様な目付きで睨み付ける。
半端なチンピラなら尻込みしてしまいそうな、ナイフのように鋭い視線である。
「べー、だ!睨んだって無駄なんだからねっ!このくらい当然っ!人のお風呂覗いた罰だよ!」
だが、虚しくも、その必至の抵抗は、頭の中が年がら年中快晴の、お天気少女には通用しないようである。
さらには、この衝撃発言により、誘蛾灯に集まる虫のように、未来に事の詳細を確かめるべく、クラスの皆が殺到する。
幸か不幸か、より大きなスキャンダルによって、元の話題が覆い隠されるように、有耶無耶になってしまった。
「未来さん。神風君にお風呂覗かれたんだ。・・・良いなぁ。」
朋香の問題発言じみた呟きは、例のごとく騒音の中心となっている、大暴走した三河の轟音、爆音にかき消され、誰の耳にも届くことは無かった。
騒がしいスタートを切った一日であったが、それ以外のこれといった事件は無く過ぎ去る。
そして、放課後を迎えると、下校の鐘が鳴ると共に、帰り支度を始める一同。
今日と言う日は、瞬にとっては、散々な一日であった。
よっぽど身近に話題にするネタが無いのか、他のクラスからも、今朝のトピックの真偽を確かめに来る者がやってきた。
それへの弁明で一日が終わったと言ってもいいほどに。
貴重な睡眠時間が削られた事もあり、瞬はいつにも増して疲労の色が濃い。
「さ、帰ろうぜ。」
その騒ぎっぷりにより、噂が広まる原因の一端を背負った三河は、瞬の苦悩なぞ露とも知れず、さりげなく未来と腕を組もうとする。
その様子を見た瞬は、この世に「ベスト・オブ・空気が読めないで賞」、略してBOAなるモノが存在するのであれば、三河の受賞は盤石であるな、と思った。
「わひゃっ!」
だが、三河が未来に触れるか触れないかの瞬間、未来は飛び上がるようにして、微かな悲鳴と共に三河から離れた。
三河的思考回路では、予想だにしなかった、拒絶全開の避けられ方に、珍しく本気で落ち込み項垂れる。
その様子を見て、腹を抱え笑い転げながら三河を指差す総一。
尋常ではない笑いっぷりである。どうやら彼のツボだったようだ。
「違うんだよ。別に祥君が嫌いってワケじゃ無いんだー。何て言うか、祥君に触られたとき、なんかビビッと来たんだよー。そろそろ乾燥してきたのかなぁ・・・?」
顎に人差し指を当て、小首を傾げる未来。
漫画であるならば、その頭上には大きなクエスチョンマークが在ることであろう。小動物のような可愛らしい仕草である。
「そ・れ・は、きっと電気が走ったような衝撃を俺に感じたって事さねっ!もしかして運命っ?!いやーそうやってストレートに告白されちゃうと、グランドシャイボーイな俺は照れちまうねぇ、どうも。」
落ち込み一転、得意の勘違いっぷりを盛大にお披露目する三河。
静電気という単語は、どうやら彼の辞書には無いらしい。ナポレオンも仰天である。
辞書から抜かす言葉を変えるだけで、かくもこう間抜けな格言になるモノなのか。
一同は、またか、と三河という存在自体をスルーする。
顔をリンゴ病のように赤らめているのは、三河という特殊な人間に慣れていない未来だけであった。
「俺はそこの大食らいに、手製の苺ババロアをご馳走する約束してるんだ。」
最早、夕暮れの校門の付属品と化している優衣と合流すると、一同は自然とこの後どうするかと言う話題になる。
例のごとく、総一が口火を切ると同時に、優衣の肘鉄が腰に入る。
地に膝を着き、悶える羽目となった総一の様子に、つくづく懲りないヤツであるな、と瞬は思う。
「年配の方だけに、『婆ロア』が好物ってな。どうだ?みんなも来るか?」
呻きながらも、軽口を欠かさない総一。
当然の如く、その側頭部に駄目押しとばかりに、優衣の膝蹴りが鈍い音を伴い、めり込む。
痛みを堪えながらも、精一杯頑張った総一であったが、健闘虚しく、その一撃を持って完全に沈黙した。
「ぅ・・二つの意味で酷いかも。」
「うむ。ギャグセンス。想い人に対する態度。どちらも及第点以下であるな。当然の報いである。」
その様子を、あちゃー、と心配そうに見つめる未来と瞬。
三河は一人、「優衣様のパンツ見られなかったっ!」と、頭を抱えて自らの失態を嘆き、大後悔していた。
「でもさ、総一君雰囲気変わったよね。それとも私の早とちりだったのかな?なんかもっとおっかない人だと思ってたんだけど。
やっぱり、第一印象ってアテにならないもんだねー。勝手に人の性格を想像で決めつけちゃダメだよね、うん!
・・・祥君はそのまんまだったけど。」
思い返せば、今日の総一の態度はいつも通りであった。
親友との誤解が氷解した事をしみじみと感じ、瞬の口元から人知れず笑みが零れる。
それに大切な友人、仲間である総一の本当の姿を、未来にちゃんと知ってもらったことも純粋に嬉しい。
「なぁ!ミクたん!俺の第一印象はっ?!」
そんな穏やかな表情の瞬とは一転、三河は未来の口から、自分の名前が出たことに一人興奮して、身を乗り出すようにして、食いつく。
「バカ」
「え?そんだけ?他には?」
「なんかオイル臭い。」
「終わり?」
「うん」
言葉という名の刃に、一刀の元に斬り捨てられた三河は、再び全力で落ち込む事となった。
「え?廃材置き場なんかに行くの?」
三河のこれからの行き先に、素っ頓狂な声を上げる未来。
ババロア食事会のホストであると共に作り手である総一が、ちょっとアレな状況になってしまった今、本日はこの場で強制的にお開きとなったのである。
「うむ。主はホントに機械が好きなのであるな。」
三河のアフター5と言えば、ナンパか流鏑馬、バイクのメンテナンス、廃品物色と、パターン化されている行動に馴染みのある瞬は、その奇行に動ずる様子もなく頷く。
一方、未来は目を白黒させ、だからオイルの臭いがいつもするのかー、と呟きながら、その珍妙なライフスタイルの理解に苦しんでいる様子だ。
「あたぼうよ!
・・・それにな、俺にはあいつらの訴えっていうか、慟哭が聞こえるのさ。『俺たちはまだ使える!使ってくれっ!』てな。
それもそうさね。機械ってのは、人間に使われるために産まれて来たんだ。少し故障したくらいで、『ハイ、おしまい』じゃあ、浮かばれねぇだろ?
人間だってそうだ。役に立たなくなったからって、切り捨てる。そんなの俺は絶対に許せねぇよ。」
ぎりっ、と拳を握り、眉をひそめ顔をしかめる三河。いつもの陽気な彼らしからぬ反応である。
これには、未来だけでなく、彼を良く知る瞬や優衣すらも目を瞬かせる。
「俺は常にそう思ってる。解ってくれとは言わない。ただ、俺の話を聞いて欲しかった。それだけだ。」
「うん。解る気がするよ。祥君の気持ち。世の中には必要ないモノなんて無いよね。何かしら意味があるって事だよね。」
未来は瞠目しながらも三河の言葉に真剣に耳を傾ける。
瞬も同様に動揺しながらも静かに頷く。二人とも三河の考え方に、何処か思うところがあるようだ。
「ねぇ、三河君が珍しく真面目な話してるわよ?何か悪いもんでも食べたんじゃない?」
前者二人とは対照的に、傍にいる、意識を取り戻し始めた総一へと耳打ちする優衣。
「優衣じゃあるまいし、いくらあいつでも拾い食いはしないだろう。それに、優衣。声がでかい。内緒話をするなら。もう少しボリューム落とせ。大阪のおばちゃんか、お前は。」
何とか、三途の川から生還を果たした総一であったが、言い終えるか終えない内に、優衣の飛び後ろ回し蹴りが後頭部に浴びせられる。俗に言うソバットである。
今度はパキッと何かが砕ける音と共に、糸の切れたマリオネットの様に崩れ落ちる総一。
「しっかし懲りずにショートコントするよなぁ、お前等。ま、でも、その通りだ。らしくないよな。久しぶりにマジになっちまったねぇ、どうも。」
にひひ、といつも通りの何も考えていない様な、お気楽な様子へと戻る三河であるが、その目に何処か憂いの様なモノがある事に気付く者はいなかった。
そんなこんなで皆と別れ、未来と共に帰路に着く瞬。
学校というコミュニティは、人当たりが良く、且つ人見知りしない未来にとって快適な空間の様だ。
一緒のクラスな上、終日共に過ごしていた瞬であるにも関わらず、今日の出来事を延々と、時にはジェスチャーを交えながら楽しそうに語る未来。
どんな一日であったか知っている瞬に話すと言うことはよっぽど楽しかったのだろう。
だが、瞬は今、何よりも眠気が勝っている。そんな未来の話の8割を瞬は聞き流していた。
それでも、未来は続ける。今の彼女にとって、相手が話を聞いているか否かは些末な問題のようだ。
未来は周りが見えない程浮かれていて、瞬は、周りが見えないほど疲労していた。
―――だからだろう。互いに、それの接近に気付けなかったのは。
そんな噛み合っているようで噛み合っていない会話が続き、一方的にまくし立てる未来が、今まさに自動車に轢かれてしまうという事態に気付いたのは、それから発せられるクラクションと周囲の人間の悲鳴からであった。
横断歩道の信号は青。所謂自動車の信号無視である。
大型ダンプカーである事から、睡眠不足によるうたた寝か何かをしていたのだろう。未来は小柄な少女である、それにより発見が遅れたのも原因の一つなのかも知れない。
いずれにせよ、運転手が今からハンドルを切った所で間に合わないという事実に変わりは無い。
―――油断していた。瞬は己の失態に歯噛みしながらも、駆け出す。
状況は最悪だ。眠気と疲労、加えて大衆の目、瞬にとってのマイナスファクターが多すぎる。全力の10分の1の力が出せれば良い方であろう。
もっとも、万全のコンディションであったとしても、同じく耳を劈く様な警報機の爆音によって、事に気付いた彼は、現場に間に合うハズも無いが。
「危ないっ!」
今まさに、超質量の鉄塊が、死に神の鎌の様に少女の儚い命を刈り取ろうとしていた瞬間、叫びと共に未来を包み込むように青年が覆い被さる。
帽子を被り、大きめのダウンジャケットを着込んだ切れ長の目の青年である。
ダンプカーはそのまま未来とそれに被さる青年の直ぐ真横をまるで滑るようにして避けると、そのまま走り去り、停止する様子も見せず、民家の壁にぶつかり大破。爆破炎上した。
辺りは炎に包まれ、どこから湧いてきたのか、まるで屍肉にたかる蠅、蛆のように野次馬が集まり出す。
―――おかしい。何かが変だ。瞬は未来の無事を安堵すると同時に、疑念が湧いた。
自動車の進行方向的に、いくら青年が助けに入ろうと衝突を免れるハズは無いのだ。そんな事ができるのならば、未来に助けなどいらない。自ら回避すれば良い。
加えて、通過後のダンプカーへ感じる違和感。
良識を持った人間ならば、幸いにも事故に至らなかった今回のようなケースでは、停車し被害者の元へと駆け寄るのが一般的な行動であろう。
このまま轢き逃げしようとしていた悪質なドライバーであったとしても、自分が事故に遭っては元も子も無い。いくらこの場から一刻も早く去ろうとしていたとしても、あの様な無謀な運転はするだろうか?
感じた限りでは、減速すらせず激突した様に見える。
慣性の法則に従う、滑っているかのような等速直線運動である。
―――そう、まるで氷上にいたかのようだ。
「大丈夫ですか?」
細目な所為もあるだろう。その柔和な顔に見合った、丁寧な口調で未来に安否を問う青年。
「あ、ありがとうございます。」
未来は借りてきた猫の様に、しおらしくなる。どちらかというと、突然の出来事に頭がついていけず、放心状態に近いのではあるが。
瞬は、思案しながらも、すぐさま未来の元に駆け寄る。
「・・・なんか、凄い騒ぎになっちゃいましたね。私が無事で、反対に運転手の人があんなになっちゃうなんて。」
呆然と、自らのガソリンへの引火によって燃え盛るダンプカーを見つめる未来。
火の勢いは収まる気配すら無く、焦熱地獄を思わせるような業火を産み出す。
最早、元の大型自動車の原型は留めておらず、黒い骨組みだけが残り、化石標本の様だ。
「さあ?ブレーキでも効かなくなったんじゃあないでしょうか?」
未来の呟きに、くく、と、くぐもった笑いを浮かべながら返答する青年。
だが、それは青年の穏やかな顔に似合わない、卑しい笑み。そのギャップ、齟齬が、違和感を際だたせる。
「どちらにせよ、交通ルールすら守れないヤツは死んで当然ですよ。これは報いだ。」
瞬は、青年の口元が、いびつに歪むのと同時に、その頬に回し蹴りを叩き込む。
その軌跡はまさに稲妻。
雷鳴じみた轟音を伴う一撃である。遠慮というモノを一切欠いた、容赦無き蹴りに青年の身体は、宙に浮く。・・・ハズであったが、青年の頬に触れたにも関わらず手応えは皆無、空振りとなる。
「未来から離れろっ!!」
瞬は、その奇妙奇天烈な現象に逡巡しながらも、怒声と共に、素早く身体全体を反転。
回し蹴りを放った逆側の脚を胸の位置まで上げ、重心を移動させると同時に真横に突き出す。
蹴込みと呼ばれる、体重を乗せ、相手を押し出す様にして蹴りを入れる、足の裏の「面」による攻撃である。
その鐘を突く様な一撃に、たまらず青年は吹き飛ばされる。
だが、瞬には、手応えはおろか、空を切った様に、触れた感触すら無い。
恐らく青年が自ら退いただけであろう。
「ちょっと!いきなり、何するんだよぅっ!」
突然の、瞬による一連の敵意に、状況を良く理解していない未来は、抗議の声を上げる。
瞬は未来の声が聞こえていないのか、はたまた無視しているのか、未来の方を見向きもせず、じっ、と青年を見据える。
「いや、僕が悪かったよ。軽率でした。大切な彼女に馴れ馴れしく触れてしまったら、彼氏も面子が立たないだろうからね。断じて彼女に対して下心は無いよ。信用してください。」
しらじらしく瞬の蹴り込んだ腹部辺りを、痛がるようにして撫でながら、あはは、と遠慮じみた笑いを浮かべ、謝罪する青年。
その場面だけを写真のように切り取って観賞するのであれば、平社員が、取引先に笑顔を取り繕う様に見えるだろう。
気が弱く、人の良さそうな人物印象を受ける、そんな笑み。
「見損なったよ!そんな理由で私の恩人さんを突き飛ばすなんてさ!」
そんな青年を見て、未来の瞬に対する怒りのボルテージは上がっていく。
やかんが頭に乗っていたのであれば一気に沸騰してしまいそうな位の憤慨、激昂である。
「未来、少し黙れ。」
一括する瞬。熱量全てを冷ましてしまうような、その冷涼な気迫に黙らずを得ない未来。
付き合いこそ短いが、いつもの瞬からは考えられないほどの威圧感。殺気が滲み出ている。
以前、自分と相対していた時ですら、ここまでのプレッシャーは醸し出していなかった。
「・・・こう見えても、荒事には慣れっこでな。経験上、目を見て喋らない人間は信用できない。自身を「信用できる」という人間に心を許すな。という自己哲学があるのだ。主はその二つを見事なまでに満たしておるな。それに、瘴気のように全身から立ち上る、その腐った気配はそう易々と隠せるモノでも無い。猿芝居は止めたらどうなのだ?」
依然、片時も青年から目を離さず、睨み付ける瞬。
拳を何度か握り、膝は少し曲げ、身体は少し前傾姿勢をとる。いつでも飛びかかれるような臨戦態勢だ。
「・・・やれやれ。同じく泥の底で生きるような人間である貴方には解ってしまいますか。これでも、演技には、多少なりとも自信があったのですがねぇ。
・・・できれば、油断した所を一気に叩きたかったのですけれど、上手く行かないもので残念です。腐った気配ですか。ご挨拶ですねぇ。だが、貴方も僕と同類の人間であるハズですよ。違いますか?元『十戒の同族殺し』さん?」
もったいぶったような仕草で、からかうように、にやける青年。先程までの人の良さそうな雰囲気は霧散しており、代わりにいやらしいほどまでに、狂気を連想させる。
「僕はシヴァ。ヒンドゥーの破壊神にして、『消し去るモノ』を意味する名前だ。」
青年は、元々細い目を、さらに糸のように細め、謳う様に慇懃無礼といった様子で名乗ると、腕を腹に宛がうように執事然としたお辞儀をし、瞬と未来の前に立ちはだかった。
Act2 続きの続きへ
ジャンル別一覧
人気のクチコミテーマ
-
-

- 『眠らない大陸クロノス』について語…
- チケット系の意見 個人的なまとめ
- (2024-10-24 04:28:14)
-
-
-

- フォトライフ
- 源氏物語〔12帖 須磨 12〕
- (2024-12-02 10:20:08)
-
-
-

- 動物園&水族館大好き!
- 多摩動物公園 今日のデコポン
- (2024-12-02 00:00:17)
-
© Rakuten Group, Inc.