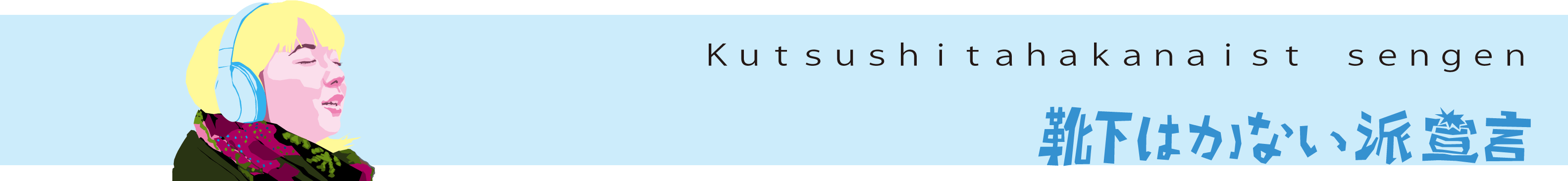走れよ、メロス!第2話

走れよ、メロス! 第2話
さく utty
[第一話のあらすじ]オッス、俺、メロス。セイント(聖闘士)と呼ばれる軍人だ。今日は、親友で蝋人形職人のイカロスとアテネの町に来たんだけど、財布を忘れちまって、俺が取に行くことになっちまった。ところが、家に着いてみると変な奴がいたんだよな。困ったよ・・・
「・・・邪道だ・・・」
メロスは小さく呟いた。
「えっ、メロスさん、今何と?」
「下着をつけないYシャツなど、邪道以外の何物でもぬわぃ!!」
と、言いながらメロスは立ち上がった。その表情は先程の激怒のものに戻っていた。
「兄さん!」
「メロスさん・・・」
「貴様のような奴にメロスとは呼ばれたくない!」
「だって・・・さっき・・・」
アキレスはメロスの豹変ぶりにまたもや混乱していた。
「いいから、とっととでていけ!!」
ついにメロスはアキレスを追い出してしまった。
「そんな!メロスさん!!」
アキレスはしばらくドアの前で叫び続けた。すると、今一度ドアが開いた・・・かと思うと、メロスが顔を出し、メロスの妹が着ていたYシャツを丸めてぶつけられ、
「貴様のYシャツだったのか、いいか、もう二度と俺や、妹の前に現れるな」
という一言も浴びせられ、以来、メロス達はもちろん、メロス達の住む町内にも近付かなくなったという。
そして、メロスと妹の間には気まずい空気が漂っていた。
きり出したのは妹のほうだった。
「追い出すことなかったじゃない」
妹はいつものパジャマ姿に替わっていた。
「あいつはやめとけ」
メロスはぼそりと呟いた。すると妹は目を閉じ、軽く首を振ってこう言った。
「わかったわ。この話はもうやめましょう」
「・・・」
メロスは黙ったままだ。
「ところで、兄さん、アテネは楽しかったの?」
妹は明るい話題に変えたくてこの質問をした。だが、それは明るい話になる訳なかった。
「あぁ、楽しかったさ・・・」
メロスは、ボソリ、ボソリと話し始めた。
「まずな、アテネの超有名なレストランに行ったのよう。そしたらよ、何だかわからんけど、すごいもんがじゃんじゃん出て来て、うまいやら珍しいやらでよ、喰うのも大変だったなぁ・・・」
いい調子になってきた。と、妹は思った。
「・・・で、次はどこ行ったの?」
「どこ行ったって、お前・・・そこでよ、金忘れてきたことに気づいてよ・・・」
メロスはやっと自分がなぜ泊まる予定を取やめて帰ってきているのか思い出した。
「ええっ!お金忘れて行ったの?」
誰でもびっくりするはずである。
「あっ、ああ、そういや俺、あれだ、財布もってもう一回アテネまで行かないとならないんだった。イカロスが待ってるんだった!」
そう言うとメロスは洗面所へ駆け出した。あった。財布だ。中身もちゃんと入ってる。
メロスは、財布を上着のポケットに入れると、変な男はもう入れるなよ。それから、今日は鍵掛けて、もう寝るんだぞ。と、言い残して、再び家を飛び出した。
妹は、寝てるところをたたき起こして、しかも、あれだけ騒いでおいて、もう寝ろ。とはいい気なもんだ。とも思いながら、両親亡き後、自分をここまで育ててくれた、どこかおっちょこちょいだが妹思いの兄に頼もしさを感じるのだった。
メロスが行ってしまって3時間が経った。今頃はまだ走っているのだろう。
メロスの大変さとは裏腹に、イカロスのほうは退屈で仕方がなかった。
イカロスは、レストランに地下の物置き部屋のような所にいた。水道がひとつと、テーブルクロスや白衣などの洗濯物、紙ナプキンやろうそくなどの消耗品、また、その消耗したものが雑然とおいてある、よくある物置部屋だった。
これまで、何度かあの嫌な感じの店主が顔を出していた。用件は決まっていた。皿洗いを1ヶ月もしたら帰してやる。というものだ。イカロスも、最初のうちは、断固として断っていた。それは親友であるメロスを裏切る行為にあたる気がしたからだ。しかし、3時間経って、その考えも変わってきた。忙しいときの3時間なんて早いものだ。ところが何もしてないとき、特に何かを待っている時の3時間は長いなんてもんじゃない。我ながら、よく3時間も我慢できたなと思うほどだ。そういうわけで、今度店主が来たら皿洗いでも何でもやってやろうかとも思うようになっていた。
だが、その次に店主が来た時のセリフはさっきまでのものとは少し違っていた。
「今日はもう店じまいだから・・・どうする?」
イカロスは今日、初めてこの店主にあった。知り合ってたったの1日でここまで他人を嫌いになったことはなかった。特に「どうする?」の部分は背筋が寒くなるほどだった。
「まあ、どうするって言っても、金のないやつを泊める宿なんかないわな・・・毛布を用意したから、今日はここに泊まるがいい」
「はあ?」
イカロスは店主の言葉に耳を疑った。てっきり、外にでも放り出すくらいのことはされると思っていたのだ。
「ここじゃ嫌なのか?」
「・・・いや・・・」
「嫌なのか?」
「いや、嫌じゃないです」
さっきまでは、嫌な奴だと思っていた店主の、思いもよらぬ人間味のある言葉に、イカロスも心動かされた。
「ははぁん・・・私を嫌な奴だと思っていたんだろう」
図星だった。
「・・・だけど、わりと優しいことも言うから好きになった、と・・・」
そこまでは思っちゃいなかった。
「私もね、仕事中はついピリピリしてしまうんだ。よく言われるんだ。だけど、一代でこの店をここまで大きくすることができたのも、はたから見ると怒っているように見えるほどの熱意って言うか・・・真剣さのたまものなんじゃないかなぁ・・・」
店主はこの後も苦労話を30分ほど熱く語って、帰宅する。
話は長かったものの、店主の人柄のよさを垣間見たイカロスは、この物置部屋の清掃を店主に申し出た。もちろん、報酬を期待しての事でも、メロスを裏切っての事でもなかった。ただ、今晩一晩泊めてもらうことと、毛布のお礼の意を込めての行為だった。
店主は大層有り難がっていた。このところ、忙しくて物置部屋はほとんど掃除していなかったのだという。
未使用のもの、洗濯が必要なもの、処分するものに分けてくれということだった。
最後に、イカロスは店主に尋ねて言った。
「このろうそくの残ったものは捨てるんですか?」
「ああ、処分するものに入れてくれ。もし、欲しいのならばあげるけど」
イカロスの質問に店主は、少し勘違いが入ってたようだが、イカロスにしてみればいい答えだった。
やがて、時は過ぎ、翌朝。店主は物置部屋の様子を見て大変喜んだという。だが、彼をもっと喜ばせることになるものがそこにあったことには、まだ気付いてはいなかった。
同じころ、メロスは朝靄のアテネの街の入口付近まで来ていた。このペースなら、余裕で正午までに間に合うはずである。
それにしても、親友のためとは言え、我ながらよくこんなにも走れるものだとも思っていたが、気が付くと、足は皮が擦り切れて血まみれで、靴ももう大きな穴が開いていた。
「これじゃ、もう雨の日には履けないな・・・」
こういうことは、気が付かないうちは大したことはないのだが、一度気になり出したら止まらないもので、とりあえず、水場があったら足を冷やすことにした。
すると、ちょうど良いことに、老人が泉で野菜を洗っているところに出くわした。
泉はきらきらと朝日を反射させて輝いていた。。また、そのせせらぎは、メロスの乾ききった体に一時の清涼感を与えていた。
メロスは早速、老人に声を掛けた。
「あのう・・・」
「なんじゃ」
老人はメロスに目も会わせず、今朝採ったばかりだと思われる、泥だらけの大根を泉の水で丹念に洗いながら答えた。
「じつは・・・」
メロスはこの泉を、足を冷やす為に使いたい。と、いう旨のことを老人に話した。
「だめじゃ」
メロスは老人の返答にしばらく絶句した。
「ひとが食うもんを洗っとる所で、おまいさんのこ汚い足を洗うわけにはいかんじゃろ。まあ、こういうことはモラルの問題だから、お前さんのような若造にはわからんかもしれんのう」
老人の言うことはもっともだった。メロスも思わず納得してしまった。
だが、老人はメロスのぼろぼろの足の様子を見て一言呟いた。
「・・・桶なら貸してやらんこともない・・・」
「ありがてぇ!」
メロスは思わず叫んだ。冷静になって考えると、それは少し間抜けな言葉だったが、今のメロスがそんなことに気づくわけがなかった。
「・・・じゃが!!」
メロスは老人の一言に思わず何事かと思った。
「あの、じゃが、何ですか?ジャガイモなんて言わないでしょうね」
先程も述べた通り、今のメロスは間抜けなことを平気で行ってしまう。それほど疲労してたと言うこと!
「つまんねーよ。・・・条件じゃよ。条件。タダで貸すほどひとが良い訳ないじゃろ」
老人は、メロスのボケに突っ込みを入れることもなく軽くあしらい、条件を言ってきた。
「なに、大した条件じゃないさ。この大根と人参をそのまま食って見せてもらおうか」
老人はまだ洗ってない、泥の付いたままの大根と人参を差し出した。
「そ、そんなことでいいんですか」
メロスは、本当に大した条件じゃなかったので、逆に驚いた。
「なに?条件が足りないとでも言うのかい?」
「いえいえ、そんなことないです。じゃあ、いただきます!」
そう言うと、メロスは泥のついた大根と人参に次々とかじり付いた。しかも、泥などもろともせず、あっという間に食べてしまった。
「こりゃたまげた・・・土とかジャリジャリして気にならんのかい?」
老人は驚きのあまりメロスに尋ねた。
「全然。おいしかったですよ」
メロスの言葉に、老人はあきれてこういった。
「なんだ面白くない奴だ。ホレ、桶は貸してやる。使い終わったらあそこの家まで持ってきておくれ」
老人はそう言うと、洗い終わったばかりの野菜をザルに入れて、その家へと向って去って行った。
メロスは老人を見送ることもなく、早速、桶に水を汲み入れ、足を浸した。
© Rakuten Group, Inc.