カテゴリ: 日本史全般
~籠(この)神社の謎 その2~

<橿原市 檜原神社神籬>
山の辺の道を歩いた時に遭遇したのがこの神社。滅多に見られない3連の鳥居に目を奪われた。ここに「元伊勢」の説明があった。不思議な籬(まがき)の内側で天照大神が一休みされた由。帰宅後ネットで調べると、第10代崇神天皇が「同床共殿」を避けるため、皇女豊鍬入姫命に天照大神の神霊を託された由。つまり大神を祀るため、適当な場所を探しに同皇女が最初に訪れた場所がここと言う訳。

<籠神社本殿=ネットから借用>
次に皇女が訪れたのが丹後の宮津にあった吉佐宮。つまり籠(この)神社の前身だ。皇女はこの後も6度土地を変遷し、24か所の地を訪ねた由。さらに第11代垂仁天皇の第4皇女倭姫命がそれを引き継ぎ、さらに6度変遷して24か所の地を巡った由。そして最終的に落ち着いたのが現在の伊勢神宮(正式名は神宮)と言う訳だ。合計12度変遷し、45か所で適地を探したことになる。(ウィキペディアより)


その中に奈良県明日香村の飛鳥坐(あすかにいます)神社の名がある。その小社にも私は偶然訪れている。つい最近、そこに男女のシンボルが祀られていることを知った。一時的にせよ皇祖である天照大神が休んだ場所に、道祖神が立つとは。だがそれは生命とエネルギーの起源として自然とも思える。実は道祖伸は、国つ神である猿田彦が天孫族を道案内した証とされているのだ。

<籠神社奥宮の眞名井神社>
内宮遷宮後食事を司る神が必要との天照大神の神託により、丹波の国から呼ばれたのが豊受大御神。この神を伊勢に祀ったのが外宮だ。約300年もの間、天照大神はずっと腹を空かせていたのだろう。籠神社の奥宮である眞名井神社の主神が豊受大御神。私たちが天橋立を見降ろした山の奥に、そのお宮があることを知っていたが、私は籠神社参拝を優先したのだ。
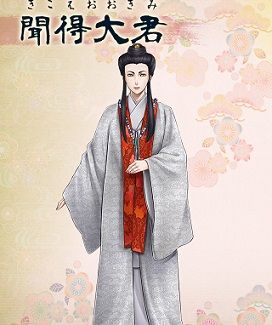
<琉球王国祝女(のろ)の頂点だった聞得大君(きこえおおぎみ)>
卑弥呼の時代、祭政は別れていた。祭(まつりごと)は巫女である卑弥呼の仕事で、政(まつりごと)は男弟の仕事。大和朝廷発足後はそれを一緒にした。だが崇神天皇は神託によって皇祖の意思を尊重し、皇女に天照大神を祀る宮の適地を探させたのだろう。天皇に代わる神宮の世話役が斎宮。現代においても旧皇族の黒田清子さんがその務めを果たしている。
なお、琉球王朝でも祭政が別れていた。政治は琉球王が、神事は王の親族である聞得大君が司った。古代日本と同様の二重構造だ。日本の古い形が琉球王国に残存していたことに、大多数の沖縄人が気づいていないだろうが。
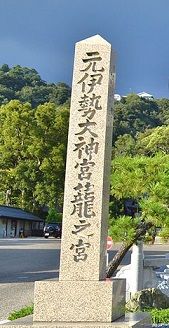
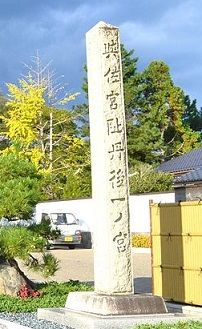
<籠神社前に立つ2本の石標>
これで籠神社の重要性が分かったはず。だからこそ「丹後国一之宮」の名誉を与えられたのだろう。もう一つの疑問は丹波と丹後の関係。名前も位置も近いことから、丹波から分国したのが丹後と考えていたのだが、今回調べたらその通りだった。こんな風にして、歴史の謎がまた一つ解けて行く。

籠神社の宮司は代々海部氏が務めて来た由。同氏は天孫族とする考えもあるが、縁起にある通り海神を祀る海人族のはず。それでもう一つ謎が解ける。それが目の前の海。宮津は天然の良港で、古来日本海を通じた交流があった。九州の宗像氏や出雲族、安曇氏などが想定されよう。そしてそれは北陸出身の第26代継体天皇ともつながるはず。江戸時代には北前船がこの宮津に寄港していた。<この項完 続く>

<橿原市 檜原神社神籬>
山の辺の道を歩いた時に遭遇したのがこの神社。滅多に見られない3連の鳥居に目を奪われた。ここに「元伊勢」の説明があった。不思議な籬(まがき)の内側で天照大神が一休みされた由。帰宅後ネットで調べると、第10代崇神天皇が「同床共殿」を避けるため、皇女豊鍬入姫命に天照大神の神霊を託された由。つまり大神を祀るため、適当な場所を探しに同皇女が最初に訪れた場所がここと言う訳。

<籠神社本殿=ネットから借用>
次に皇女が訪れたのが丹後の宮津にあった吉佐宮。つまり籠(この)神社の前身だ。皇女はこの後も6度土地を変遷し、24か所の地を訪ねた由。さらに第11代垂仁天皇の第4皇女倭姫命がそれを引き継ぎ、さらに6度変遷して24か所の地を巡った由。そして最終的に落ち着いたのが現在の伊勢神宮(正式名は神宮)と言う訳だ。合計12度変遷し、45か所で適地を探したことになる。(ウィキペディアより)


その中に奈良県明日香村の飛鳥坐(あすかにいます)神社の名がある。その小社にも私は偶然訪れている。つい最近、そこに男女のシンボルが祀られていることを知った。一時的にせよ皇祖である天照大神が休んだ場所に、道祖神が立つとは。だがそれは生命とエネルギーの起源として自然とも思える。実は道祖伸は、国つ神である猿田彦が天孫族を道案内した証とされているのだ。

<籠神社奥宮の眞名井神社>
内宮遷宮後食事を司る神が必要との天照大神の神託により、丹波の国から呼ばれたのが豊受大御神。この神を伊勢に祀ったのが外宮だ。約300年もの間、天照大神はずっと腹を空かせていたのだろう。籠神社の奥宮である眞名井神社の主神が豊受大御神。私たちが天橋立を見降ろした山の奥に、そのお宮があることを知っていたが、私は籠神社参拝を優先したのだ。
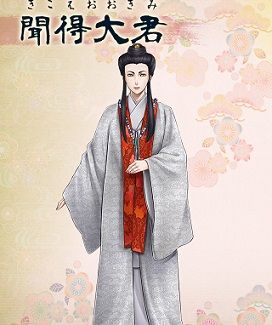
<琉球王国祝女(のろ)の頂点だった聞得大君(きこえおおぎみ)>
卑弥呼の時代、祭政は別れていた。祭(まつりごと)は巫女である卑弥呼の仕事で、政(まつりごと)は男弟の仕事。大和朝廷発足後はそれを一緒にした。だが崇神天皇は神託によって皇祖の意思を尊重し、皇女に天照大神を祀る宮の適地を探させたのだろう。天皇に代わる神宮の世話役が斎宮。現代においても旧皇族の黒田清子さんがその務めを果たしている。
なお、琉球王朝でも祭政が別れていた。政治は琉球王が、神事は王の親族である聞得大君が司った。古代日本と同様の二重構造だ。日本の古い形が琉球王国に残存していたことに、大多数の沖縄人が気づいていないだろうが。
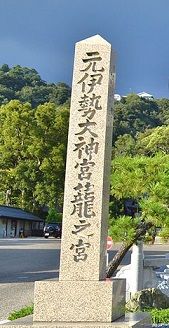
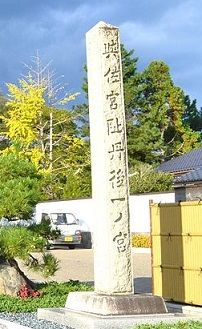
<籠神社前に立つ2本の石標>
これで籠神社の重要性が分かったはず。だからこそ「丹後国一之宮」の名誉を与えられたのだろう。もう一つの疑問は丹波と丹後の関係。名前も位置も近いことから、丹波から分国したのが丹後と考えていたのだが、今回調べたらその通りだった。こんな風にして、歴史の謎がまた一つ解けて行く。

籠神社の宮司は代々海部氏が務めて来た由。同氏は天孫族とする考えもあるが、縁起にある通り海神を祀る海人族のはず。それでもう一つ謎が解ける。それが目の前の海。宮津は天然の良港で、古来日本海を通じた交流があった。九州の宗像氏や出雲族、安曇氏などが想定されよう。そしてそれは北陸出身の第26代継体天皇ともつながるはず。江戸時代には北前船がこの宮津に寄港していた。<この項完 続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[日本史全般] カテゴリの最新記事
-
遥かなる南の島々 追補版(8) 2021.05.22 コメント(2)
-
アイヌの話(9) 2021.03.09
-
旅・歴史と美を訪ねて(28) 2019.12.16 コメント(13)
Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
ローズコーン
さん
おはようございます。
こうして歴史ものはやはりこれまでの学習における知識の許に、先ずは推測を盾イマージネーションを広げそしてそれが事実かどうか検索する、そしてそこで自分の推測と考えがぴったり歴史の事実とあうと、どんなにか喜びの大きなきなことでしょうね。
いつもその推測はあってっておいでですね。さすがです。
勉強してない者には、はあ~~~と感心するばかりですが。 (2019.12.12 06:18:04)
こうして歴史ものはやはりこれまでの学習における知識の許に、先ずは推測を盾イマージネーションを広げそしてそれが事実かどうか検索する、そしてそこで自分の推測と考えがぴったり歴史の事実とあうと、どんなにか喜びの大きなきなことでしょうね。
いつもその推測はあってっておいでですね。さすがです。
勉強してない者には、はあ~~~と感心するばかりですが。 (2019.12.12 06:18:04)
Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
マックス爺
さん
ローズコーンさんへ
お早うございます!!
いつもコメントをありがとうございます。
早朝からこんな面倒くさい文章を丁寧にお読み
いただき、ありがとうございます。
私は歴史や考古学を組織的に学んだ者ではありません。
でも長期間それなりに本を読んでいると、一定の
法則が分かって来ます。分国の際の名前の付け方などです。
私の場合、現地を訪れて疑問を抱く。それを帰宅後
ネットで調べて専門家の意見を確認する。その繰り返しです。
基礎的な知識がないと疑問すら起きませんが。
推論とその確認。そんなことを繰り返しつつ自分なりの
学習を進めています。遠い遠い道のりですよ。(;^_^A
孤独ではありますが、楽しい学習ですね。🌸(^^)v
(2019.12.12 06:50:56)
お早うございます!!
いつもコメントをありがとうございます。
早朝からこんな面倒くさい文章を丁寧にお読み
いただき、ありがとうございます。
私は歴史や考古学を組織的に学んだ者ではありません。
でも長期間それなりに本を読んでいると、一定の
法則が分かって来ます。分国の際の名前の付け方などです。
私の場合、現地を訪れて疑問を抱く。それを帰宅後
ネットで調べて専門家の意見を確認する。その繰り返しです。
基礎的な知識がないと疑問すら起きませんが。
推論とその確認。そんなことを繰り返しつつ自分なりの
学習を進めています。遠い遠い道のりですよ。(;^_^A
孤独ではありますが、楽しい学習ですね。🌸(^^)v
(2019.12.12 06:50:56)
Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
Kazu さん
Aさん,こんにちは~
本日のテーマ,興味深く読ませていただきました。伊勢に落ち着くまで90年も要したのですね。
今でこそパソコンがあり,検索すれば瞬時にデータが手に入り,真
贋を見極めれば知識となりますが,数年前までは図書館の専門書等
でなければ難しかった。しかし,Aさんの知識はその後者の積み重
ねですよね。よっぽど根気よく,また綿密に整理されたのでしょ
う。
でも,それらの努力の結果を,発するこどが可能なブログというツ
ールに出会えたことは,ほんとに良かったかと思います。
陳腐な一言ですみません。 (2019.12.12 10:22:36)
本日のテーマ,興味深く読ませていただきました。伊勢に落ち着くまで90年も要したのですね。
今でこそパソコンがあり,検索すれば瞬時にデータが手に入り,真
贋を見極めれば知識となりますが,数年前までは図書館の専門書等
でなければ難しかった。しかし,Aさんの知識はその後者の積み重
ねですよね。よっぽど根気よく,また綿密に整理されたのでしょ
う。
でも,それらの努力の結果を,発するこどが可能なブログというツ
ールに出会えたことは,ほんとに良かったかと思います。
陳腐な一言ですみません。 (2019.12.12 10:22:36)
Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
yorosiku!
さん
Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
マックス爺
さん
Kazuさんへ
今日は~!!
いつもコメントをありがとうございます。
伊勢神宮の候補地探し。それもまた神話に近い
のだと思っています。
その理由は第11代天皇までは架空の人物とする
説があるからです。初代の神武天皇などはなにせ
300歳まで生きたと言うのですから。(;^_^A
仰る通り、昔は専門書を紐解くしかありませんでしたね。
この分野は「霊感」みたいなもので、勝手なことを
書く人が結構いるのですよ。特に邪馬台国などは。(^_-)-☆
だから誰がどんな書店から出した本か。そして著者の
経歴はどうかなどを基準にして読む本を選らんで来たのです。
その点今は楽ですね。ウィキペディアなどがある程度
信頼できる学説やらその分野の定説を載せていますので。😊
1)基礎的な知識に加え 2)現地で受けた印象や疑問
3)ネットでの確認や最新情報の入手 の繰り返しです。
そんな素人ののろい歩みでも、苦労したことが報われる
のは楽しいですよ。疑問が10年後、20年後に解けることが
実際にあるのですから。
明日からはKazuさんお待ちかねの出雲大社です。
じっくりお読みいただけたら嬉しいです。ではね。(@^^)/~~~
(2019.12.12 11:23:18)
今日は~!!
いつもコメントをありがとうございます。
伊勢神宮の候補地探し。それもまた神話に近い
のだと思っています。
その理由は第11代天皇までは架空の人物とする
説があるからです。初代の神武天皇などはなにせ
300歳まで生きたと言うのですから。(;^_^A
仰る通り、昔は専門書を紐解くしかありませんでしたね。
この分野は「霊感」みたいなもので、勝手なことを
書く人が結構いるのですよ。特に邪馬台国などは。(^_-)-☆
だから誰がどんな書店から出した本か。そして著者の
経歴はどうかなどを基準にして読む本を選らんで来たのです。
その点今は楽ですね。ウィキペディアなどがある程度
信頼できる学説やらその分野の定説を載せていますので。😊
1)基礎的な知識に加え 2)現地で受けた印象や疑問
3)ネットでの確認や最新情報の入手 の繰り返しです。
そんな素人ののろい歩みでも、苦労したことが報われる
のは楽しいですよ。疑問が10年後、20年後に解けることが
実際にあるのですから。
明日からはKazuさんお待ちかねの出雲大社です。
じっくりお読みいただけたら嬉しいです。ではね。(@^^)/~~~
(2019.12.12 11:23:18)
Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
マックス爺
さん
yorosiku!さんへ
こんにちは。
ご来訪とコメント、ありがとうございます。
いえいえ、海に面した神社よりも奥まったところに
ある神社の方が何百倍も多いのでしょうね。
でもYorosiku!さんが行かれた鵜戸神宮
などは海辺の神社の典型的な見本。その意味では
大変良い経験をされたと思いますよ。(^_-)-☆
海辺にある神社も全くなくはないと言ったところ
でしょうか。
神社の立地はご祭神の性質にもよるし、祀る
側の事情にもよるのだと思います。
浅草寺も創建時は小さな島にあったようですものね。
その問題は明日以降の出雲大社シリーズで
詳細に記しています。どうぞお楽しみに。😊
(2019.12.12 11:51:54)
こんにちは。
ご来訪とコメント、ありがとうございます。
いえいえ、海に面した神社よりも奥まったところに
ある神社の方が何百倍も多いのでしょうね。
でもYorosiku!さんが行かれた鵜戸神宮
などは海辺の神社の典型的な見本。その意味では
大変良い経験をされたと思いますよ。(^_-)-☆
海辺にある神社も全くなくはないと言ったところ
でしょうか。
神社の立地はご祭神の性質にもよるし、祀る
側の事情にもよるのだと思います。
浅草寺も創建時は小さな島にあったようですものね。
その問題は明日以降の出雲大社シリーズで
詳細に記しています。どうぞお楽しみに。😊
(2019.12.12 11:51:54)
Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
クマタツ1847
さん
正直言って、私は古代史は全然勉強していません。
むしろ連れ合いの方が古代史はよく勉強しています。
私は、学校の日本史に興味を持ったのがそもそも始まりでですが、今では薩摩の歴史、とりわけ島津氏と明治維新の二つに絞っています。しかしそこから日本全体の歴史を知る必要に迫られて、少しづつですが、調べるようになった段階です。元々、歴史を特別勉強もしていませんので、全くの付け焼刃です。 (2019.12.12 16:33:57)
むしろ連れ合いの方が古代史はよく勉強しています。
私は、学校の日本史に興味を持ったのがそもそも始まりでですが、今では薩摩の歴史、とりわけ島津氏と明治維新の二つに絞っています。しかしそこから日本全体の歴史を知る必要に迫られて、少しづつですが、調べるようになった段階です。元々、歴史を特別勉強もしていませんので、全くの付け焼刃です。 (2019.12.12 16:33:57)
Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
マックス爺
さん
クマタツ1847さんへ
今晩は~!!
いつもコメントをありがとうございます。
歴史の学び方、楽しみ方は人それぞれでしょうね。
奥様が古代史をねえ。それは嬉しいなあ。😊
私が歴史に興味を持ったのは、小学校時代に
貝塚らしいものを見つけたことと、高校生の時に
古墳付近で遺物を拾ったことからでした。
それから考えたら、ずいぶん長い間興味を抱き続けて
来たと感無量ですね。
私もただただ素人の独学。本を読んでの勝手な解釈ですよ。
それでも現地に立って見ると何かを感じ、何か
得るものがありますね。そして今はネットで何でも
調べられるので、超らくちんです。
自分が何を知り、何を知らないか。先ずはそれが
分かってないと調べられませんがね。
これからも大いに旅をし、歴史を学びたいものです。(^^)v (2019.12.12 16:57:14)
今晩は~!!
いつもコメントをありがとうございます。
歴史の学び方、楽しみ方は人それぞれでしょうね。
奥様が古代史をねえ。それは嬉しいなあ。😊
私が歴史に興味を持ったのは、小学校時代に
貝塚らしいものを見つけたことと、高校生の時に
古墳付近で遺物を拾ったことからでした。
それから考えたら、ずいぶん長い間興味を抱き続けて
来たと感無量ですね。
私もただただ素人の独学。本を読んでの勝手な解釈ですよ。
それでも現地に立って見ると何かを感じ、何か
得るものがありますね。そして今はネットで何でも
調べられるので、超らくちんです。
自分が何を知り、何を知らないか。先ずはそれが
分かってないと調べられませんがね。
これからも大いに旅をし、歴史を学びたいものです。(^^)v (2019.12.12 16:57:14)
Re:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
こ う
さん
こんばんは
3連の鳥居ですか
初めて見るかもしれません
祭(まつりごと)に政(まつりごと)
文字でなんとなくわかったような気になりますが
歴史が得意でない私は・・・ですね(^^ゞ (2019.12.12 23:25:47)
3連の鳥居ですか
初めて見るかもしれません
祭(まつりごと)に政(まつりごと)
文字でなんとなくわかったような気になりますが
歴史が得意でない私は・・・ですね(^^ゞ (2019.12.12 23:25:47)
Re[1]:旅・歴史と美を訪ねて(24)(12/12)
マックス爺
さん
こ うさんへ
お早うございます!!
いつもコメントをありがとうございます。
3つ連続した鳥居、他では見たことないですね。
祭は神事、政は政治。今の天皇は政治は行わずに、
宮中の神事だけを行っていますよね。
2つを一緒にやっていた時代があったと言うことです。
(2019.12.13 08:30:40)
お早うございます!!
いつもコメントをありがとうございます。
3つ連続した鳥居、他では見たことないですね。
祭は神事、政は政治。今の天皇は政治は行わずに、
宮中の神事だけを行っていますよね。
2つを一緒にやっていた時代があったと言うことです。
(2019.12.13 08:30:40)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









