テーマ: 写真俳句ブログ(36783)
カテゴリ: 俳句
<俳句教室にもコロナの騒動の影響が>
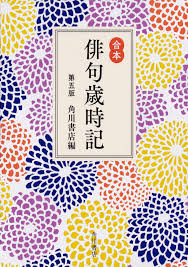
2月の俳句教室はKちゃんが集金に来る日だったので慌てた。 彼女がギリギリで来たこともあって、眼鏡を家に忘れて困った。手元は見えるが黒板に書かれた字が見えない。それで隣のKさんに聞いて、何とか最後まで頑張った。

次の試練は句友の作品の講評を講師に指名されたこと。
太古よりウイルスが降り春の雪
この句友は講師が嫌いな「現代俳句」を詠み、講師が嫌いなカタカナも平気で使う。こんな時は力量が試されていると考えて、思ったことを言った方が良いのだ。「この句は時間軸と空間軸が雄大で、到底凡人には評価不可能な表現能力を有しています」。それで逃げ切った。

次は自分の句の自評。私の提出句がこの日の「トリ」になった。
春風を拒みて立つや屏風岳
春が近づいて海からの春風(しゅんぷう)が吹いて来る季節だが、南蔵王に聳え立つ屏風岳は、文字通りその南風・春風を拒むかのように屹立している。今蔵王連峰では、春と冬がせめぎ合ってる真っ最中。春風は「はるかぜ」ではなく虚子が詠んだ「春風や闘志抱きて丘に立つ」のとおり、ここは「しゅんぷう」と読ませたい。それで講師はグーの音も出なかったようだ。

次は兼題(宿題)の「立春」を詠んだ句の出番。 私は 春立ちて吾妹の声も若やぎぬ を出した。
吾妹は「わぎも」と読み、妻を意味する古語。古代の皇族や貴族の場合、腹違いの妹を妻とすることが公式に許されていた。それで「わがいもうと」が短絡して「わぎも」となった。古語の使用も講師の心証を良くしたようだが、彼は兼題の「立春」を用いず 菜の花や吾妹の声の若やぎて
とした方がより文学的と言いたかったのだろう。それ以上抗う必要はなく、「ああそうですか」と引き下がった。だが本心は立春が兼題なのになあと。
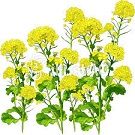

私がこの日提出した3番目の句は 愛憎を八つ裂きにして風光る
「風光る」が春の季語。長らく生活を共にした夫婦の愛憎劇をテーマにした。どんなに夫婦の仲が悪かろうが、季節はお構いなしに訪れる。そんな心境だ。<続く>
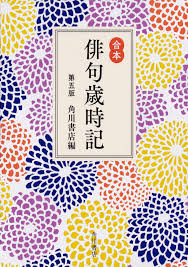
2月の俳句教室はKちゃんが集金に来る日だったので慌てた。 彼女がギリギリで来たこともあって、眼鏡を家に忘れて困った。手元は見えるが黒板に書かれた字が見えない。それで隣のKさんに聞いて、何とか最後まで頑張った。

次の試練は句友の作品の講評を講師に指名されたこと。
太古よりウイルスが降り春の雪
この句友は講師が嫌いな「現代俳句」を詠み、講師が嫌いなカタカナも平気で使う。こんな時は力量が試されていると考えて、思ったことを言った方が良いのだ。「この句は時間軸と空間軸が雄大で、到底凡人には評価不可能な表現能力を有しています」。それで逃げ切った。

次は自分の句の自評。私の提出句がこの日の「トリ」になった。
春風を拒みて立つや屏風岳
春が近づいて海からの春風(しゅんぷう)が吹いて来る季節だが、南蔵王に聳え立つ屏風岳は、文字通りその南風・春風を拒むかのように屹立している。今蔵王連峰では、春と冬がせめぎ合ってる真っ最中。春風は「はるかぜ」ではなく虚子が詠んだ「春風や闘志抱きて丘に立つ」のとおり、ここは「しゅんぷう」と読ませたい。それで講師はグーの音も出なかったようだ。

次は兼題(宿題)の「立春」を詠んだ句の出番。 私は 春立ちて吾妹の声も若やぎぬ を出した。
吾妹は「わぎも」と読み、妻を意味する古語。古代の皇族や貴族の場合、腹違いの妹を妻とすることが公式に許されていた。それで「わがいもうと」が短絡して「わぎも」となった。古語の使用も講師の心証を良くしたようだが、彼は兼題の「立春」を用いず 菜の花や吾妹の声の若やぎて
とした方がより文学的と言いたかったのだろう。それ以上抗う必要はなく、「ああそうですか」と引き下がった。だが本心は立春が兼題なのになあと。
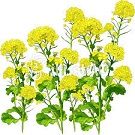

私がこの日提出した3番目の句は 愛憎を八つ裂きにして風光る
「風光る」が春の季語。長らく生活を共にした夫婦の愛憎劇をテーマにした。どんなに夫婦の仲が悪かろうが、季節はお構いなしに訪れる。そんな心境だ。<続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









